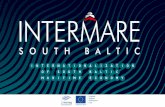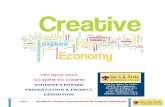Exhibition of Genesis-5
Transcript of Exhibition of Genesis-5
3
2014 年 Genesis-5 は、今までの展覧会にいくつかの要素が加わった。一つは熊本県の新規文化事業「アーティストイン阿蘇」の始まりである。本企画は阿蘇の5市町村に海外のアーティストを招聘し滞在制作を行うというもので、高森町ではフランス人のパスカル・ブラトー氏の滞在制作があった。また、県の新たな芸術文化発掘事業「ヌーヴェル・ヴァーグくまもと」による助成を受け「阿蘇アースアートミュージアム構想」を発足した。一環としてアースアートアーカイブを立ち上げ、関連するアーティストの取材・記録を行った。アースアートの提唱者でもある池田一氏の協力により、環境アートの研究者・清水裕子氏による基調講演も「世界の環境アートその多様な活動について」と題し行われ、アートの可能性を展望し充実したものとなった。私も10 月にポーランド・ポズナニ市で開催された、メディエーションズ・ビエンナーレの関連会議「ポストグローバルフューチャー」では招聘 30 団体・個人の展覧会開催者の一つとして参加発表を行った。内容は以上のような阿蘇における
アート活動の動向・展望である。 地質学的・環境的なアートの可能性とは、何なのかどこにあるのか、起源展に於いては根源的な問であるが、改めて「人間の前に自然がある」という自明性に気づかなければならない。また、人間は自然や天体の運行に抗えない媒体(メディア)であること、知性(科学)で宇宙を、分断し単位・系列・構造化することが真理を実現する唯一の道では無い。人は観測する時、自らもまた観測されている。アートによって人は想像し、創造する世界で真理に近づく。自然からのメッセージを、受信・共振・発信する起源展を基盤として、今後の活動を進めたい。 今、阿蘇は火山活動を活発化させているが、カルデラ内の地元住民はもとより新住民としての移住者も、阿蘇という悠久の時を共に生きている。阿蘇は、大あくびをしているのか、怒りに打ち震えているのか、それとも人間たちとの遊戯を渇望しているのか。その答えは人間である我々が知る由もない。ただ、感じることができるだけである。
はじめに三枝泰之(Genesis-5 起源展実行委員/崇城大学三枝研究室)
4
「起源」とは物事のはじまりであり、それがすべての源泉となり、ひろがってゆく状態だといえる。水の滴がひとつ生まれ、それが水紋のようにゆっくりとまた時には激しく円を描きながら伝わってゆく。そこには何かがはじまる、生まれ出るエネルギーに満ちた時空がある。そのエネルギーは自然と人間、場所と人、人と人とのインタラクティブ(相互作用的)な関係性から生まれるものだ。 今日、その関係性は希薄化して、20 世紀における共同体の崩壊ということが言われて久しい。特に 2011 年の東日本大震災後、社会的なひずみが露呈し、私たちは根源的な疑問に直面してきたといえるだろう。我 は々今まで何をしてきたのか?そしてどこに向かおうとしているのか?4 年近くの時を経て、この問いかけも少しずつ色あせてきている。しかし、想像を絶する犠牲を通して、コミュニティの絆や自然に対する畏敬の念をもつことが、未来への期待をかろうじてつなぎ止める縁(よすが)になろうことは、私たちの心の奥底に確実に刻まれたといえるだろう。 世界ジオパークにも認定された阿蘇は世界有数のカルデラであり、地球の熱いマグマのエネルギーにあふれ、古来より自然と人間を結びつける神話が伝えられてきた。このスピリチュアルな場所は強力な磁力を発し、古代から多くの人 を々魅了し、今では約 5 万人もの人びとが生活している。特に、大震災後、より自然に近い健康的な場所で、自然と
共生するコミュニティの新たなモデルを求めて、東京をはじめ都市部から移住してきた人びとがいる。 かれらが中心となって、起源展の舞台でもある阿蘇フォークスクールが運営されている。峨々たる根子岳のふもとに抱かれ、周囲を田園や草原の風景に囲まれた、なつかしい木造校舎、2003 年に閉校になった旧上色見小学校。その運営は NPO 化され、その大きな目的のひとつは「先人達の暮らしの知恵や文化を学ぶ場を提供する」ということだ。そのことばの通り、NPO には地域で永く農畜産業などを担ってきた代表の方々や卒業生、工芸家、有機農法の実践者、別荘を建てて新たに住み始めた人びと、そして震災後の移住者たちと、枠組みを超えた多様な人びとが参加している。その構成は阿蘇に住む多様な住民の状況を体現し、実際に話をうかがってみると、かれらの年齢、目的、および関心、利害が多様化していると感じる。このような多様化は国内、特に都市部以外の地域では希なことだ。その多様性は時にコミュニケーションのギャップを生じさせるが、同時に協働の過程でダイナミックなエネルギーを生み出す可能性を秘めている。このような地域でアートにはなにができ、求められるのだろうか?20 世紀後半よりアートは自らの領域を飛び出し、場所、地域、社会と確実に近づいてきたといえるだろう。場所と関わるサイト・スペシフィック(その場所に限定された)な作品から、地域や社会の状況を表現し、再認識させるシン
起源展 Genesis 5 に寄せて清水裕子(環境アート研究者)
5
ボリックな作品、さらには現実の課題に向き合い、具体的な変化をもたらそうとする活動(ソーシャリー・エンゲイジド・アート:Socially Engaged Art)へと拡張している。
起源展も、アートを通して地域独自の環境について共に考える貴重な機会になっている。実際に地域共同体の重要な基盤となってきた学校という場所を中心とする人間の営み、さらには自然や地球、宇宙とのつながりを意識する作品が生み出された。それらは学校という場の記憶を喚起させる作品(東耕平、下條賢一、川嶋久美、松本和子など)やその周辺に広がる田園風景(山本てつお)とサイト・スペシフィックな対話を試みる作品、また地域で見つけた廃材を素材とした楽器で演奏するサウンド・リノベーション・バンドなど、さまざま興味深い作品が制作された。
なかでも、池田一は、雄大な根子岳を借景にして、地元の葦を使った巨大な本を制作した。折りたたまれ、今まさにひらかれようとしているページに、まだ物語は書かれていない。訪問者は本のページに各自の物語を書くことをうながされる。それぞれが心のなかで自らのヒストリーを紡ぐ行為が集積して、一冊の巨大な本が完成される。それは住民が作品への参加=本の制作を通じて、地域社会の新たな歴史
を創造するための共同作業を象徴している。すなわち、この作品は仕事も関心も価値観も多様化している住民があらためて対話し、議論するための時間と空間を提供しているのだ。 加えて、今回から始まったアーティスト· イン· 阿蘇(熊本県)は、海外からの 7人のアーティストを阿蘇の 5 自治体に招聘し滞在制作してもらうプログラムである。かれらの多彩な作品やその制作過程は、異なる関心や背景を持つ人びとの刺激となり、新たな相互作用をもたらしている。また起源展やアーティストインレジデンスの活動はすべて阿蘇アースアートミュージアムと呼ばれるアーカイブ・サイト(http://aso-art.net/)に記録され、地域の文化資源として共有されると同時に、世界に発信、ネットワーク化するためのプラットフォームづくりが進められている。 将来的には、起源展やアーティスト· イン· 阿蘇が環境とアートを考える拠点となり、さらに枠組みを超える参加 / 対話型アートプロジェクトやグローバルな視点から地域の課題について議論する学際的なコラボレーションが実現されることを期待したい。これらのアプローチを通じて、阿蘇における起源展をはじめとする活動は環境アートのユニークな実践を世界的に発信する拠点となるだろう。
Message for the Genesis Exhibition
Hiroko Shimizu
The Aso is a world leading caldera where ca. 50,000
people are living. This spiritual place, with full of energy
of the earth and myths related to the nature and man,
has attracted people since ancient period.
Now, in addition to the traditional farmers, especially
after East Japan Great Earthquake Disaster in 2011,
new comers emigrated away from cities, seeking for a
new model of a community deeply related to nature.
Consequently, age, purpose, and interests of the old and
new residents are diversified.
In this circumstance, the Genesis exhibition seems a
precious opportunity to think together about thier own
environment through art. It can provide time and space
for dialogue and discussion for all the residents.
Ichi Ikeda, using local reeds, created a huge folded
book on which the story is not yet written. Visitors are
encouraged to write each story to the book imaginarily.
This act ivity symbolizes that the residents can
collaborate to create a new history of the community
through the participation.
In addition, Artist-in-Residence program is initiated
by Kumamoto Prefecture this year simultaneously,
inviting seven artists from abroad. Diverse artistic
interventions will open up interaction between people
with different interests and backgrounds. I hope that
the Genesis exhibition in the future will develop into
further participatory art projects and interdisciplinary
collaboration for local issues concretely from a global
perspective. These approaches will make the exhibition
more unique one in the environmental art scene.
6
2014 年のパネリストは、アーティストイン阿蘇の高森町
招聘作家パスカル・ブラトーも加わり、代替的な農業の実践
者であるピリオ・ドニー&假野祥子、阿蘇フォークスクール
からは阿蘇神話街道の著者でもある山村将護、また世界的に
活躍する環境アーティスト・池田一、そして司会の福山洋に
より「阿蘇の自然とアートの展望」というテーマで行われた。
事前のパスカル・ブラトーの紹介では「家」をテーマにし
た作品づくりが、室内の展覧会場に限らず地域の屋外生活環
境の中に設置されていく事で、作品から社会やコミュニティ
自体を捉え返していくという活動が見えた。
清水裕子の「環境とアート」を語る基調講演が、まさにベー
スとなりパスカルの紹介、本ディスカッションへと繋がった。
山村将護の日常の生活はまさに阿蘇の自然と共存するもので
あり、池田一の活動もまた本来の意味でのアースアートを標
榜するものである。今、あらためてアートの可能性を語る時、
人間の文化活動を支える自然を抜きには考えられないことを、
再認識した。とりわけ阿蘇地域は、世界的にも象徴的な火山
の麓というサイトであ
り、今回、池田一がイ
メージした「今日もわ
くわく、水わく、火わ
く、雲がわく」のキャッ
チコピーにふさわしい
場といえるだろう。
「世界の環境アートその多様な活動について」と題した講演は、
本活動の意義を裏打ちすると同時に、今後の展望を暗示させ
られる内容であったといえるだろう。アートと環境、社会、
関係性の変化を近代以前から近代、現代へと歴史の流れを背
景に解説頂いた。アートの役割が一部のパトロンや貴族のも
のからアートのためのアートへ、そして今社会や環境に関わ
るものの登場。それらの流れを 1960 年代のカウンターカル
チャーや環境問題、アート業界などと関連付け読み解き、環
境アートの社会的な役割や活動のテーマへと導いた。現代の
地域文化政策などでアートの可能性が見えてくる。対話、参
加、協働のプロセスから批評的、先験的、感覚的、統合的な
視点で対話の媒体となり得る。a. カウンターアクション b. 土
地の再生 c. コミュニティ活動 d. 場づくり e. 大きなビジョン
の提示これらをいくつかの事例・活動を紹介頂きながら、アー
ト活動を統合的な環境を支える共生モデルの可能性としてま
とめられた。
清水 裕子◆ Profile
環境アートの多様な活動について研究している。持続可能性についてグローバル、ローカルに考え行動するアート、その学際的なあり方やコミュニ
ティとの協働のプロセスについて事例を紹介し現状を分析する。大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員、南カリフォルニア大学芸術建築科パブ
リックアート研究科修士修了。環境アート研究、アート・ディレクター。「エコロ ジカル・アート 環境との対話」、「日本のパブリックアート」展、
Stadtkunst Kunststadt(Berlin,2010)、ユネスコ、パブリックアート会議報告 (Paris,2011)、ECO-ART (Finland Pori Museum, 2012)、Earth Art
Catalogue(Zinio, 2014) などに執筆。三島市せせらぎ事業デザイン委員 ( 元 )、静岡県景観賞審査員、静岡県三島市在住。
左から “ぽっこわぱ” 假野祥子 & ピリオ・ドニー(バイオダイナミック農法)/ Pascal Brateau(アーティスト/フランス)/山村将護(阿蘇フォークスクール)/池田一(アースアーティスト)/司会:福山洋(崇城大学)
Keynote Speech.基調講演【世界の環境アート その多様な活動について】8 月 30 日 1:00pm 〜
Panel discussion【阿蘇の自然とアートの展望】8 月 30 日 3:00pm 〜
7
左から松本和子、荒牧弘幸、Katarzyna Szeszycka、Pascal Brateau、Arabella Murray-Nag、Sitthiphonh Jonathan、Uliana Apatina
参加者:左から池田一、清水裕子、荒牧弘幸、奥に下城賢一
Performance
■光永誠(サウンド・リノベーション・バンド)
廃材楽器によるサウンドパフォーマンス
■山内桂(sax)による即興演奏・インプロビゼーション
左から池田一、福山洋、右から山村将護、山本幸一
右 山田良典による開会のあいさつ
Opening Party 8 月 30 日 6 : 00pm 〜
8
大地のジャバラ本 <人湧く国:最初の晩餐>◎池田一 ICHI IKEDA
制作年:2014
素材:竹、藁 他
作品説明:
「人湧く」には、人がワクワクする、人心が湧く、人から起源
する等の、想いが込められています。「人湧く国」とは、里と
か村と言うと巨大な機構の中の従属的な部分という感じがす
るので、他との従属関係にとらわれない、自立した場所を指
す意味で、国としました。
「最初の晩餐」とは、なにもなくても、人々が集まって祝う晩
餐で、それは「人湧く国」の事始めの寄り合いといったイメー
ジ。湧水だけでなく、自然の食材(野菜や果物)などを持ち寄り、
いつもの食事会といった趣きでいい。
プロフィール:
2011 ECO-ART, Pori Art Museum( ポリ、フィンランド )
2010 木口家集落<地球の家>アートプロジェクト(枕崎、
鹿児島、日本)
2010 錦江自然美術ビエンナーレ(招待)(韓国忠清南道公
州市)
2009 Earth Art, ロイヤル植物園(バーリントン、カナダ)
2009 48℃ Public. Art. Ecology, チャンディ・チョーク公
園(デリー、インド)
2009 にいがた水と土の芸術祭、大通川/矢川(新潟、日本)
2008 Unlearning Intolerance, 国連本部(ニューヨーク、米
国)
2008 水箱アートミュージアム展、川口市立アートギャラ
リー・アトリア(日本)
2007 〜 Envisioning Change、ノーベル平和センター(オ
スロ、ノルウエー)、ブリュッセル、モナコ、シカゴ巡回
2007 Show Me Thai、東京都現代美術館(東京、日本)
2006 〜 11 The Missing Peace: Artists Consider Dalai
Lama、世界巡回展
2006 〜 8 花渡川アートプロジェクト Moving Water Days
(枕崎、鹿児島、日本)
2006 サラエボ・ウインター、トルコ文化センター(ボスニア・
ヘルテェゴビナ)
2006 〜 7 空間に生きる - 日本のパブリックアート展、世田
谷美術館 他巡回
2005 GROUNDWORKS、カーネギーメロン大学(ピッツバー
グ、米国)
2002 台北公共芸術節、大湖公園(台北、台湾)
2002 Water’s-Eye, ジョグジャカルタ、バンドン、ジャカ
ルタ(インドネシア)
2001 高雄国際コンテナ芸術節(高雄、台湾) 2003、2007
10
制作年:2014
作品説明:
「新くまもと百景」の1位に選ばれている月廻り公園に設置
された、インスタレーションのタイトルは、“the other side
of the world” 地球の裏側。とにかくパスカルの作品を貫い
ているモチーフは家、家、家、ナンシーでもベルリンでも阿
蘇でも家がテーマである。パスカルの家は様々に表現を変え、
ある時は金属のフレームで、ある時は雑誌の山で、ある時は
言葉で、材木で、シリコンで、テープでという具合である。
元々建築家である彼はコミュニティの最小単位は家族が集ま
る「家」ということで、家をテーマに作品を作り続けている
が、今回の作品は 1960 〜 70 年代アメリカミニマルアート
のカール・アンドレやソル・ルウィットに影響を受けた、コ
ンセプチュアルな作品。組み上げられた材木を角度を変えて
見てみるとそこに逆さまの家の形象が現れる。ヨーロッパか
ら見ればそれが正しい位置、つまりタイトルの地球の裏側を
表象している。この幾何学的でスクエアな透過式の立体物は、
雄大な阿蘇五岳を背景に孤立することで風景に絶対的な力を
呼び戻している。対峙することで「自然と人間」の関係を表
現したアートといえるだろう。(文責:三枝)
the other side of the world ◎パスカル・ブラトー Pascal Brateau
montain houses inside/out looking for volume
11
阿蘇の田畑に原始人◎山本てつお Tetsuo Yamamoto
制作年:2014
素材:竹、水性塗料
作品説明:根子岳を望む 14 体の呼び交し
プロフィール:
1959 年生まれ。熊本県荒尾市在住。九州産業大学
美術学科卒。
1987 年 あらお造形展 ( 熊本県立美術館 )
1900 年アートドキュメント展 ( 北海道立美術館 )
1992 年第 6 回釜山青年ビエンナーレ ( 韓国・釜山文化会館 )
1993 年九州現代美術展 ( 福岡市美術館 )
1997 年手で触れて見る作品展 ( 佐賀県立美術館 )
12
制作年:2014
素材:廃材
作品説明: 上色見に眠る廃材を用いて楽器を制作した。今回
は、築 100 年以上の納屋の破片とフォークスクール周辺の
金属廃材を使用。長いあいだ風雨にさらされた独特の質感か
ら生まれる響きには、堆積した土地の記憶が織り込まれてい
る。廃材に残された過去の記憶に耳を傾け、楽器として新た
な生命を吹き込んでいく。
プロフィール:
2010 年春、九州大学大学院の杉山、渡辺、岡崎、光永によっ
て結成。廃材特有の質感やその多様性の中から音を見出し、
楽器の制作・演奏を行っている。これまで、リノベーション
ミュージアム冷泉荘(福岡市博多区)、旧上色見小学校(南阿
蘇)、臨海 3R ステーション(福岡市東区)、雲仙岳災害記念
館(島原市)などで作品を制作・展示。2014 年 1 月、九州
大学大橋キャンパスにて開催のコンサート「廃材が響く:ジョ
ン・ケージ&ルー・ハリソン」に出演。
サウンド・リノベーション in ASO 2014 ◎サウンド・リノベーション・バンドSound renovation band 岡崎峻/光永誠/杉山紘一郎/渡辺融/松岡涼子/小野村頼子/石田耕太郎
13
大地の尻尾 草木の背中 The tail of earth The back of trees and plants◎井上 玲 Rei Inoue
阿蘇で拾ったものを作品の「種」にして
阿蘇の赤土と柿渋で絵を描き「枝」とします
阿蘇の大地と草木の色と形を探します
阿蘇の赤土 協力 吉田工芸舎
http://www.yoshidakougeisha.com/
What I gathered in Aso will be my seeds of drawings.
And using Aso akatsuchi red clay and Kakishibu
the Japanese traditional paint which matured with a
persimmon the seeds will spread its branches.
This is a quest for the colors and the forms of earth,trees
and plants in Aso.
A s o A k a t s u c h i r e d c l a y : C o o p e r a t i o n b y
Yoshidakougeisha
http://www.yoshidakougeisha.com/
1997-99 tokyo Musashino art school pringting couse
Graduated
2008-10 China Central Academy of Fine Arts pringting
couse Graduated
solo exhibition
2001 tokyo gallery yamaguchi
2003 tokyo MAKIIMASARU FINEARTS
2010 beijing Today Art Museum printing center
2011 aso folk school Genesis Ⅱ
2013 aso folk school Genesis Ⅳ
14
制作年:2014
素材:チョーク
作品説明:在りし日の教室で、大地に風が吹く様子を窓ごし
に見ていたかもしれないチョークが、自分もそうなりたいと
思い、描いた夢。
プロフィール:
1983 福岡県出身、熊本市在住。
2007 九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻 修了
2011 「DEMADO CONTEMPORARY ART PROJECT
Vol.4 《たまてばこ堂》」 HRD FINE ART (京都)
2013 「ART PROJECT OITA2013 循環」フンド―キンマ
ンション(大分)
チョークのみる夢◎川嶋 久美 Kumi Kawashima
15
制作年:2014
素材:ビニール傘、キャンディ
作品説明:子供は子供だったころ 腕をブラブラさせながら
思った、小川は川になれ川は河になれ 水たまりは海になれ
と。子供は子供だったころ 知らなかった。
すべてに魂があって ずべての魂はひとつだった。 子供は
子供だったころ 考えなんて持たなかった
癖だってなにひとつ。 あぐらをかいたり 両足を揃えて
跳んだり。
プロフィール:
1972 熊本生まれ
1997 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程壁画専攻 入学
1999 同大学院修士課程 修了
1999 ドイツ学術交流会(DAAD)スカラシッププログラ
ムにより、デュッセルドルフ美術アカデミー マグダレナ・
イエテロヴァ教授クラス入学 2004 年まで同クラスに在籍
2006 帰国 熊本在住
2013 崇城大学 芸術学部 非常勤講師
主にインスタレーション作品を国内外に発表
「子供の情景」〜眠りに入るこども〜◎下城賢一 Kenichi Shimojo
制作年: 2014
素材:貝、ガラス、紙
作品説明:巻貝を裏返しにすることによって、顕わになるも
のがある。入口から渦巻き状入り込む形状に私たちは神秘を
深め、宇宙や性を見出し、自分の存在を再確認する。情報化
社会の中で私たちはいかに自分を取り戻すのか、リアリティ
の追求の先にリアリティはもはやない。巻貝という自然物に
落とす私たちの眼差しは、より一層強くなり Life Research
(生命の調査)は続く
プロフィール:
熊本県八代市生まれ、多摩美術大学卒業後、渡米。
主にインスタレーションの作品を国内・国外に発表
Life Research/ 生命の調査◎松本和子 Kazuko Matsumoto
16
制作年:1. 2013 2. 2014
素材:1.FRP 2. ホウ、カツラ
作品説明:
1. 私が今勤務している幼稚園に設置して、子供が乗って遊べ
るような作品を作るという発想でつくりました。 子どもの
像を乗せたのは、先に楽しそうに乗っている姿を見ることで
抵抗なく作品に乗れるように、また座ったときにしがみつけ
るように。はだかにしたのも、ちょっとした遊びです。
2. 人も木のように長生きできるのかなと思ったとき、できる
という考えに達しました。そのときの気持ちと、数年前に作っ
た作品を復習するような気持ちで作りました。種をまく人に
なろうと決めた自分の第一歩的な作品です。
プロフィール:
2010 ビエンナーレ KUMAMOTO ファイナル 入選
Genesis 起源展 Genesis2
2012 HIGASHI BAZAAR(ギャラリー楓)
Genesis 起源展 Genesis3
Geo Genesis2012 新しい地球を探して
メディエーションズ • ビエンナーレ「The Unknown」(ポー
ランド ポズナン)
制作年:2014
素材:FRP
作品説明:命の公平性、平等性について考えました。
プロフィール:
1986 年生まれ
崇城大学大学院芸術研究科博士後期課程在籍
東京、九州を中心に展示
1.こども心 2. 群生◎東 耕平 Kohei Higashi
AAA ◎カナ Kana
▲ 2▼ 1
17
制作年:2014
素材:安山岩(写真作品)
作品説明:
美しい砂浜の広がる海辺に、生命感あふれる安山岩の彫刻を
置きました。それにより、普段見慣れてしまった風景が新鮮
な輝きを放ちながらよみがえります。風 景と一体になった彫
刻は潮の満ちひき、天候の移り変わりによって、千変万化の
表情を見せます。満潮のときに彫刻は水没し、見る人はその
残像を感じながら、 また美しい海辺の風景を楽しむのです。
プロフィール:
1993 カナダ フランスを遊学
1994 カナダ ケベック州 Sant.Jean.Port.Jol において
アーテイスト インレジデンスに参加 3ヶ月間彫刻を制
作する
1995 アメリカ カリフォルニア州に移住 オークラン
ド市に移住
2000 島原市に移住
制作年:2014
素材:植物で草木染めをした手漉きの和紙
作品説明:ここにある「色」を「見る」ための装置。
校庭内で採取した植物で草木染めをした手漉きの和紙を繋ぎ
あわせた。
色はオシロイバナ、キバナコスモス、桜の枝、メドウセージ
など。
プロフィール:
2010 東京藝術大学美術研究科絵画科油画専攻 修了
小豆島アーティスト・イン・レジデンス 2010/spring 招聘
作家
2010 東京藝術大学修了制作展 ( 上野 / 東京 )
2010 「Story of the Island」展 ( 小豆島 / 香川 )
「The Story of Plants 2010 ivy,olive」 (musee-f 表参道 /
東京 )
2012 熊本県立第二高等学校 50 周年記念展(早川倉庫 /
熊本) 「gatto」設立
2012 個展「私のものづくり」(画廊喫茶ジェイ / 熊本)
和紙、インスタレーション、アクセサリー制作
The Story of Plants/ 色を見る◎宮川 有紀 Youki Miyagawa
宝島◎野島泉里 Senri Nojima
18
アーティストイン阿蘇・小品賛助参加 ◆Katarzyna Szeszycka, Arabella Murray-Nag, Nana Heim -Kwon
Closing BBQ Party ◆
Katarzyna Szeszycka
展示教室
Trans Continental Duo
Arabella Murray-Nag
Nana Heim -Kwon
19
【参加アーティスト】
(海外4名*賛助作家含)1 pascal brateau パスカル・ブラトウ – French 2 Katarzyna Szeszycka カタリナ・シャゼツカ - Polish
3 Nana Heim -Kwon ナナ・ヘイムコン - Germany 4 Arabella Murray-Nag アラベラ・マリーナグ - British
(国内作家 11 名)
(国内)1 池田一(神奈川) 2 山本てつお(荒尾・熊本)3 サウンド・リノベーション・バンド(福岡)4 井上 玲(福岡)5 川嶋久美(熊本)6下城賢一 ( 阿
蘇・熊本 ) 7松本 和子(熊本)8東 耕平 ( 熊本 ) 9 KANA(熊本)10宮川 有紀(熊本)11野島泉里(島原・長崎)
【教育関連】1 崇城大学 三枝研究室 1 名 2 九州大学大学院 藤枝研究室 廃材楽器 (7 名 )
【Performance】8 月 30 日 6:00pm 〜
1 光永誠(サウンド・リノベーション・バンド)廃材楽器によるサウンドパフォーマンス
2 山内桂(sax)による即興演奏・インプロビゼーション
【ドキュメント内写真】 児玉龍郎/三枝泰之/山口次郎/浅川浩二
【日時】 2014 年 8 月 30 日[土]〜 9 月 21 日[日]
《基調講演》………「世界の環境アート その多様な活動について」8 月 30 日 1:00pm 〜
《パネルディスカッション》………「阿蘇の自然とアートの展望」8 月 30 日 3:00pm 〜
【会場】 阿蘇フォークスクール 阿蘇郡高森町上色見 1390-1 ☎ 0967-62-0027
火・水曜休校(祝祭日開校)/ 10:00am 〜 5:00pm(最終日 3:00pm 迄)
【問合せ】 ☎ 0967-62-0027(阿蘇フォークスクール http://asofolkschool.eco.to/)
【主催】 Genesis 起源展実行委員会
【共催】 NPO 法人阿蘇フォークスクール/崇城大学三枝研究室
【協力】 紅蘭亭/里の駅「たにやま」/浅川浩二
【助成】 アースアートミュージアム:ヌーヴェル・ヴァーグくまもと補助事業
起源展:高森町
Specification 明細事項