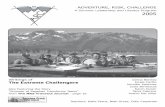A study of PLCs development process in a U.S. middle school : Change and challenge of DeFour's...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of A study of PLCs development process in a U.S. middle school : Change and challenge of DeFour's...
米国における「専門職の学習共同体(Professional Learning Communities:PLCs)」
の発展段階の検討-ミドルスクールにおけるデュフォーのモデルの受容と課題
新谷龍太朗(関西国際大学 非常勤)
2015年6月21日(日)
1
日本教育経営学会第55回大会 於:東京大学
本発表の問題関心
2
• 学校内で新たな教育実践を生み出すための、教員の協働の在り方や条件、プロセスとはどのようなものであるかを、デュフォーモデルの受容と課題から明らかにする
• 「学習する組織としての学校」(OECD2001 第3章 シナリオ4)
「教師の専門性の再定義」「学び合い」
• 学校教育法改正(2007年) 「確かな学力」
「基礎的な知識及び技能」「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の能力」「主体的に学習に取り組む態度」
→言語活動の充実
• 2014年12月22日中央教育審議会 大学教育や選抜の課題
アクティブラーニング、問題解決力(PISA2012)、探究学習
→新たな教育実践、授業スタイルが求められている
日本の学習指導要領(2002 告示1998)では生徒の自発性を高めることを目的に教科横断的・総合的な学習の在り方が提示された。米国では問題解決力や高い思考力をつけることを目的に教科横断的なリテラシーを高めようとするナショナル・カリキュラム構築の動き(2008~)が生じている。
先行研究
3
• 「学校の廊下までは新学力観は入ってきているが、教室の中までは入ってきていない」(別惣2000)
• 「新学力観の定着過程を、組織文化や小集団によるマネジメントなどの視点から検討する必要がある」(福本2000)
• 「同僚的相互作用が見られる学校ほど、新学力の定着が見られる」(諏訪2000)
→教育政策がどのように教育実践に影響を与えているかを、分散型リーダーシップや同僚性に着目してみる必要がある
• 「総合的な学習は教員文化の変容を企図したものであったが、実際には、成果を挙げつつも、それは従来の授業スタイルに基づく」(川村光・紅林伸幸・越智康詞2012)
「探究的な学習」への消極的姿勢、時間的制約の中での合理的選択
→授業スタイルに変容を及ぼすとすれば、何が必要だったのか
PISA2003を用いた分析では、階層下位の生徒に対して、定着確認は有効だが、応用させる方略は負の影響がでる(須藤2010)
米国のカリキュラム改革の流れ
1957年のスプートニック・ショックを契機とする「新カリキュラム」 1964年公民権法以降の補償教育プログラムの開発
1960年代~70年代 学習の個性化を目指したオープン・エデュケーション
1980年代 新保守主義の立場からの基礎教養の強調
1990年代 スタンダードに基づく改革→各州でテストが増える
2000年代 NCLB法により強いアカウンタビリティと狭い学力観
2010年代 共通コア州スタンダーズで、PISAを意識し、学習過程やコミュニケーション、思考力、教科横断的なリテラシーを求める方向へ
→日本と似た状況にある
4
【共通コア州スタンダーズ】
2010年6月に基準が公表され、2013年12月には45州が受け入れる。PISA報告書を踏まえ、生活と結びついた「高次の思考力」をつけることが意識される。数学では「領域の焦点化」「一貫性」「より高い水準」がキーワードとされ、基礎力を固めると共に、四則演算を教える際に概念やスキル、問題解決との関連付けるなど、思考過程や応用力、答えを導き出す過程でのコミュニケーションに焦点が当てられた。言語技術では、全米学力テストの8年生の結果が停滞していることを根拠として、アカデミックかつ学問横断的な読み書きが重視された
米国における「専門職の学習共同体」
リチャード・デュフォー(DuFour. R. et. al 2008) 「生徒のためによりよい結果が出るように集団的な審議を重ね、アクションリサーチを行うプロセスに
おいて協働することに教育者たちが貢献することである。専門職の学習共同体は生徒のための学習の向上には継続的で仕事に埋め込まれた教育者にとっての学習が鍵であるという仮定のもとで運営される。」
週に一度、時間を取って取り組むものでなく(they do not do PLC)、そのようにある(they are a PLC)という文化
実践志向・結果志向
討議の手順 4つの質問
何を学ぶか:「正しい教材で教えられているか」
どう測るか:「生徒は教えた内容を学んでいるか」(形成的評価)
どうするか:「学んでいない/学んでいるとしたらどうすべきか」
5
デュフォーは、教員や校長、教育長として34年間に渡り公立学校に関わり、校長を務めた高校が、学力格差縮小の功績で連邦政府から受賞した実績がそのモデルの浸透の背景にある。デュフォーのモデルに対しては、「新自由主義的教育改革の求める学力観を無批判に受け入れている。」という指摘もある。
強いアカウンタビリティ、共通コア州スタンダーズに対応する教育実践が模索される中で、教師の協働が求められる cf)「企図された協働」「ソフトな統制手段としての協働」
デュフォーとホード(S.M.Hord)の比較 デュフォー ホード
構成要素
共有されたビジョン
協働的な文化
集合的な審問
行動志向
結果志向
共有されたビジョン
支援・共有リーダーシップ
集合的な創造性
共有された個人の実践
支援的な条件
重視事項
生徒の学習、日常からの学び、形成的評価
常に探索し改善するコミュニティ
研究展開
協働的チームとなる為の質問、好実践の収集
構成要素の枠組みに基づく比較、解釈、指標化
ホードの定義「学校における教育者たちがより効果的になるために共に学ぶようになることで、生徒がさらにうまく学ぶようになる」 教師の専門性や学校の成長プロセスの解明が求められる(織田2015)
新谷(2012, p.8)を一部抜粋
研究対象及び方法
「専門職の学習共同体」に取り組む米国の公立ミドルスクール
南東部、2013年10月17日・18日、2014年9月15日から26日のフィールドワーク、2008年から2013年にかけて毎年校長に対してインタビュー
生徒数675人(6年生~8年生)、教員42人(10年未満50%) 比較的貧困層が多い
2008年から「専門職の学習共同体」に取り組み学力向上
教員に対する意識調査では、協働しやすい環境、意思決定への参加意識、学び合う環境の面で向上
学区の指導主事は、校長の積極的な姿勢もあり、「専門職の学習共同体」の取り組みが定着してきたと評価
7
ノースカロライナ州
教員の協働の重視や、省察的実践家としての教師育成に力を入れてきた(全米教職専門職委員会の認定教員の割合が1割台で、全米トップクラス)
「専門職の学習共同体」に参画しリーダーシップを発揮することが、教員評価の項目に含まれている。
ブルンズウィック郡
「専門職の学習共同体」の取り組みで改善した高校が全国的に評価される。
教育長が率先して「専門職の学習共同体」を実践し多くの学校が改善。校長会でも。
教員評価の基準1「リーダーシップの発揮」の一項目として、「出席」(attende)「参加」(participate)「リーダーを引き受ける」(assume a leadership role)」「学習の質の改善に向けた協働」(collaborate)の段階がある
リランドミドルの様子
教科指導
全教員で共通
週に1度の「専門職の学習共同体」の時間に「4つの質問」で討議
授業を復習クイズから始める展開
チームごとに共有
8年生社会チーム:同じ週でステーションワーク形態による授業
8年生理科チーム:同じスライドを使い、一部同じタイミングで同じ話し
7年生若手教員(高校・大学の同級生):ペア学習をとりいれる
机の配置は、スクール形式、E字型、コの字型、島型がほぼ同じ割合であった。
リテラシー教育
いじめを題材とした本を用いた朝読(1コマ)が、全教員が関わりクラスサイズを小さくして行われていたが、授業の展開は教員により様々であった。
2014年10月から「7つの習慣」や、ペア学習・グループ学習を埋め込んだ教科共通の進め方でリテラシー授業を全面展開しようとしていた。
8
リランドミドルでの「専門職の学習共同体」
10
【共通の週間授業計画】
毎週2コマを使い、共通の週間授業計画を策定する 2コマ続き→データと計画の回
●目的/アジェンダ:今日、生徒は何を学ぶ予定か 重要な問いは何か
例:8.NS.2(州の学習指導要領の番号)、有理数と無理数の比較、無理数を小数点で置き換えたり、数直線上に示すことができるか?
●活動、戦略:どのような授業をするか。それは生徒にとってどのような違い(意味)があるか →
ノートや議論、演習に向けて直接的な指導やワークシートのレビュー
無理数がおよそどの程度の大きさになるかについてペアでのポエムづくり
よくできる生徒や、発達に問題のある生徒に対しての指導方法
AVIDや用いる予定の書き方指導としてコーネルノートが計画されている
●朗読:どの教科書を読むか
●テクノロジー:電子黒板や書画カメラ
●査定、生徒の学びをどのように知るか:ワークシートや議論のモニタリング、グループでの発表
【共通の形成的評価に基づくデータ分析】
縦に、発達上の問題がある子ども、よく出来る子ども、性別、人種が、横に教師が並び、小テストの出来具合が記録される→計画した授業によりどのような学びが生じたのかを検証
議題:データは自分の指導方法についてどのようなことを伝えているか/何が成功で、何がうまくいかなかったのか、何を変えなければならないか/次週は生徒の学びを図るために、どのような査定方法(小テスト)を用いるか/クラスを量的・質的データから分析した評価/生徒の理解度を高・中・低で分けたとき、それぞれどのような点がうまくできていたか、またはできていなかったか
リランドミドルでの「専門職の学習共同体」
11
毎週2コマを使い、共通の週間授業計画を策定する 2コマ続き→データと計画の回
目的/アジェンダ:今日、生徒は何を学ぶ予定か 重要な問いは何か
例:8.NS.2(州の学習指導要領の番号)、有理数と無理数の比較、無理数を小数点で置き換えたり、数直線上に示すことができるか?
13
活動、戦略:どのような授業をするか。それは生徒にとってどのような違い(意味)があるか →ノートや議論、演習に向けて直接的な指導やワークシートのレビュー、無
理数がおよそどの程度の大きさになるかについてペアでのポエムづくり、よくできる生徒や、発達に問題のある生徒に対しての指導方法が考えられている。
AVIDや用いる予定の書き方指導としてコーネルノートが計画されている
リランドミドルでの「専門職の学習共同体」
17
先行研究(Servage2009)をもとに、「ケア」「社会的正義」「スコアマネージャー」「リサーチャー」などの言葉で教員の専門性を定義するとしたら、と質問
ミドルリーダー
MK先生(8年生ELA、40代女性)「ビジネスや医者を考えると、彼らはデータを用いる。新
しい技術やアイディアを使うことも専門性のひとつ」「ケアは、それ以外の要素とは一線を画す」
KJ先生(6年生理科、30代女性)「ここ3,4年はリサーチャーの部分が大きい。データ主導
で、データを集め、エビデンスを集めるという感じで。ケアについて時間を割く必要もある。アカデミックでない部分での対応も必要だから。」
新しく加わった教員
HD先生(7年生数学、20代女性)「スコアマネージャー」
BS先生(8年生数学、20代女性)「すべて。ケアを行うが、社会的な規範も教える必要がある」
PJ先生(8年生理科、20代女性)「ケアが最初に来るが、教えていることを実際の生活と結び付けて考えて欲しいと思っている。」
「専門職の学習共同体」における専門性の定義
学校で共有されているビジョンについて問うという文脈であるが、WR先生(7年生ELA、20代女性)は「一番大事なのは子どもとの関係。それがこの学校のしていること。」「ケアされていないと感じたら、ケアレス」と話していた。
→定義の仕方にばらつきは見られるが、ケアの価値観は共通して言及される。
18
比較的うまく行っている8年生社会科チーム
チームがうまく行っている背景に共通の専門知、それぞれの異なる経験に対する尊敬
自分のやり方にこだわりすぎないこと、共通コア州スタンダーズの影響
40代・50代の意見
教育改革に翻弄されることに辟易している
協働や教育実践のシェアを成果と捉える
ミドルスクールのチーム文化が土台となっているが、学習面にシフトしている
20代・30代の意見
責任のシェア・リソースや経験の共有が取り組みを意義づける
単なる進捗確認から、データに基づく分析へと移行したことをチームの成長と捉える
→協働と教育実践の共有が価値づけられ、「4つの質問」が「善いもの」とされる
「専門職の学習共同体」に対する意見(8年生社会)
学区の押し付ける「形」から、校長の支援的リーダーシップにより、自校の状況にあった修正ができたことで、オーナーシップ感覚が生まれていた。
19
オープンマインドの難しさ
同僚性や協働の価値づけを認めていたベテラン教員が、翌年に学校を去る
「エゴを捨てることが大事」(8年生ELA・40代女性)
協働という名の強制力
「コラボレーションという名の下で、これをしろと暗に言われていると感じる部分もある。」
→校長の観察頻度や支援的態度が葛藤を和らげる
中堅教員が自分のやり方を崩さず、取り組みが形骸化する、若手が取り組みに意義を見出せなくなる
学区の要求と学校の現状の間で齟齬が生じる
「専門職の学習共同体」に伴う葛藤
20
「専門職の学習共同体」の3段階モデル
第一のステージ 「集まる」
個々人が専門家として実践するが、チームになっていない
学校全体で設定したテーマや生徒の様子について話し合うことで一定の情報交換はされるが、自分の授業のやり方は崩れない
第二のステージ 「データを用い、課題や知見を発見する」
共通の形成的評価(小テスト)を開発し、生徒の学びをサブグループごとに分析し、その課題と解決に向けた取り組みについて話し合い、次週の授業に活かす
協働しているという実感や、データを通じて成果を実感することで、「良いチーム」という実感が高まり、人間関係の良化が考え方や行動の変化を促す
第三のステージ 「新たなペダゴジーを開発・試行する」
生徒の学びの過程を解釈しようとする対話
チームで協力して、新たな教育実践を開発・試行し、省察する
メンターと若手教員という威光模倣が生じる関係や、経験豊富な教員たちの会話に周辺的に参画することで、新たな授業のやり方に向けた学習が生じる
考察
第一ステージ:6年数学、6年ELA、7年理科、7年数学、7年ELA 第二ステージ:6年社会、6年理科、8年数学、8年ELA、7年数学+コーチ、7年ELA+コーチ、第三ステージ:8年生社会、8年生理科、欄外:7年生社会(集まらない)、
What else should we do for the beginning stage?
Beginning stage of PLCs Gather Talk about at least one common subject of whole school Talk about a student to understand them more
What else should we do for the 2nd stage?
2nd stage of PLCs Using data Find out at least one topic to talk about, or new idea We can feel sometimes, “we are good team” because we create new, we try hard . . .
Master stage of PLCs would help Understanding the reality of students learning Creating new knowledge and good CFA Reflecting our practice and change continuously
考察
協働に伴う葛藤(感情コンフリクト) 「メタ認知(ビジョンの共有)とオープンマインドが足がかりとなる
「協働の難しさを乗り越えるには、なぜそれをするのかと言う共通の目標を持つことが必要」「安心して自分の失敗も話せるような、オープンマインドになることが必要」(8年生ELA)
校長の支援的な働きかけ(状況理解や共感を示す)が、年配教員を巻き込む際に必要
「監視ではなく支援されている」「私達の大変さや、何に悩んでいるかを理解してくれている」(7年生ELA)
チームの成熟度(メンバーの関係性)と、授業のやり方の共有度は比例する
メンターと若手教員の間での威光模倣(8年生社会) 専門知を有するメンバーと、そのコミュニティへの正統的周辺参加(8年生理科)
個人学習と組織学習のつながり
「データ」と「シェア」をキーワードとし、個人の実践を、データの解釈と共通の目標と計画づくりの場で共有し、新たな実践を考え試行する研究開発のサイクル
フォーマルな取り組みだけでは授業のやり方の共有に至らない。インフォーマルな同僚関係や威光模倣を伴うメンターと若手教員の関係や、専門知を持つ教員たちの良好なパートナーシップ関係に基づく実践共同体への参画を通じて授業のやり方が共有される。
24
結論
学校内で新たな教育実践を生み出すための、教員の協働の在り方や条件、プロセスとはどのようなものであるかをデュフォーモデルの実態と課題から考察
デュフォーモデルの受容は、チームの成熟度により、「集まる」「データを用い課題や知見を発見する」「新たなペダゴジーを開発・試行する」という三段階で発展する。
場の発展のためには、学区や校長が時間を確保するなどの物理的条件を整備すると共に、協働に伴うコンフリクトを克服するための、学校ビジョンの共有と、校長の支援的リーダーシップが必要とされる。
フォーマルに討議の場を設定するだけでは、教員の授業のやり方は変わらない。
授業のやり方の変容や共有には、インフォーマルな教員の同僚関係や、授業を実際に見て討議する場の有無が影響する。
したがって、教育政策が要求する新たな教育実践を実現させるためには、教員の同僚関係にも目を向けた支援が必要である。
日本への示唆:学校経営と授業研究を、特に階層的不利益を被る子どもたちに着目してデータに基づく分析を行い、<アクティブ・ラーニング>や新テストにより格差が広がらないように注視するとともに、有効な授業方略をチームで研究する。
25
今後の研究課題
今回の調査では、学校内でのチームの成熟度の分散を明らかにしたが、同じチームがどのように成熟していくのかというプロセスも明らかにする。
チームの様子が、メンバーの入れ替わりにより大きく変化することは明らかにしたが、入れ替わりのある中でどのようにチームの経験と暗黙知を継承・発展させていくかも捉える。
共通コア州スタンダーズの要求する、対話と思考力を重視するカリキュラム改革に応答する授業改善として取り組み始めた、全教員共通のリテラシー授業が、それぞれの授業にどのような影響を及ぼすのかを明らかにする。
学区全体で同じデュフォーモデルのPLCに取り組んでいることから、同じ学区の、他の学校での取り組みとの比較により、成功要因を明らかにする。
また、学区の派遣するPLCコーチがどのようなチームとして機能しているのか、校長会や教育長のスタッフチームがどのような運営をしているのかも、学区全体の改善を視野にいれる。
26
参考文献
27
DuFour, R., et al., 2008, Revisiting Professional Learning Communities at Work, Solution Tree.
DuFour, R., et al., 2010, Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at
Work second edition, Solution Tree.
Servage, L.,Who is the “professional” in a professional learning community? An exploration of teacher
professionalism in collaborative professional development settings, Canadian journal of education
32(1) , pp.149-171,2009, p.151.
織田泰幸,2015,「「専門職の学習共同体」としての学校に関する基礎的研究(4) : Shirley M. Hord &
Edward Tobiaの研究に着目して」『三重大学教育学部研究紀要, 自然科学・人文科学・社会科学・教育科
学』66, p. 343-358.
川村光・紅林伸幸・越智康詞, 2012, 「小・中学校における「総合的な学習の時間」の実践の変容」『関西国際大学研究紀要』第13号, pp.1-14.
新谷龍太朗, 2012, 「新自由主義教育改革における教師の協働の可能性と課題-アメリカにおけるプロフェッショナル・ラーニング・コミュニティの考察から」『アメリカ教育学会紀要』第23号, pp.3-14.
新谷龍太朗, 2014a, 「共通コア州スタンダーズの開発プロセス及び内容-中学校学習指導要領との比較を踏まえて」『アメリカ教育学会紀要』第25号, pp.15-27.
新谷龍太朗, 2014b, 「米国における「専門職の学習共同体(Professional Learning Communities: PLCs)の検討-デュフォーのモデルを発展させた中学校の事例を通して」『日本教育経営学会紀要』第56号,
pp.68-81.
参考文献
28
須藤康介,2010,「学習方略がPISA型学力に与える影響 : 階層による方略の違いに着目して」『教育社会学研究』第86集, pp. 139-158.
諏訪英広, 2000, 「第Ⅵ章 組織文化としての指導体制と学校改善」岡東壽隆・福本昌之編著『学校の組織文化とリーダーシップ』多賀出版、pp.165-204.
福本昌之, 2000, 「第Ⅴ章 学習指導要領の改変が教育実践に定着する過程」岡東壽隆・福本昌之編著『学校の組織文化とリーダーシップ』多賀出版、pp.165-204.
別惣淳二, 2000, 「第Ⅳ章 学習指導要領の教育観、学力観、評価観が教職員に及ぼす影響」岡東壽隆・福本昌之編著『学校の組織文化とリーダーシップ』多賀出版、pp.107-164.