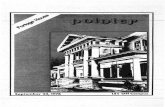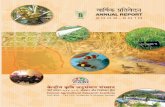F ICT F ICT F 1 ( 2552 ) F F F 80 5 2550 F ( 6) F F F 10210 F(02 ...
2008 G/1 7n 24 F
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2008 G/1 7n 24 F
卒業研究概要
卒研題目:倫理観がもたらす環境財の持続可能性: 非厚生主義的消費者行動分析
学籍番号:200612355 主専攻:社会経済システム 氏名:川瀬翔平
指導教員:石川 竜一郎先生
1. 目的
環境問題が顕在化し、社会的に危機感が持たれている現状では、環境財の消費において、消費者は
たびたび効用最大化行動では説明のつかない意思決定をしているように見える。本研究の目的は、こ
うした意思決定を、消費者の環境に対する共感やコミットメントによって自然環境の非利用価値を認
めたことの帰結として考え、倫理観による価値判断が持続可能な消費を導くことを示すことである。
2. 特色
消費者選択の対象として消費される環境財を持続可能財と非持続可能財とに分類した。これによれ
ば、持続可能な消費を、環境財の致命的な集中消費が行われる前に代替的利用価値を持つ持続可能財
の消費へ転換させる消費行動と定義できる。また、非持続可能財はその定義から、代替的利用価値を
持つ持続可能財との比較において非利用価値が大きい。したがって、消費者の環境に対する共感やコ
ミットメントは、非持続可能財の非利用価値を選択判断に組み込む役割を持つと言えることになる。
3. 結論
環境財の非利用価値を認識する倫理観は、利己的厚生主義的倫理観と非厚生主義的倫理観とに分け
ることができ、どちらも合理的消費者の正当な選好判断である。環境財の非利用価値を認識すること
が持続可能な消費につながるために、環境に対する倫理観は、それが何であろうと非持続可能財の消
費を食い止め、環境財全体の消費持続可能性を維持する役割を持つ。この結論は Paavola [7]の主張
とは矛盾はなく、かつ厚生主義的消費者も環境に優しい消費選択が可能であることも示唆している。
3
謝辞
この論文を執筆するにあたり、大変多くの方々に支えていただきました。どんなに参考図書や先行
研究を呼んでも前に進まない苦しい時期もありましたが、多くの友人の心の支えがあったからこそ書
き上げることができました。特に、指導教員である石川竜一郎先生には、論文での議論を集約させる
際には一緒になって考えていただきました。ここに深くお礼申しあげます。
石川研究室の堀由布子さん、杉本雅介くん、横田哲也くん、研究室は違いますが山田邦明くん、相
川洋平くん、長谷川浩司くんには、何度も話を聞いていただき、多くの示唆もいただきました。大変
感謝致します。
また、奥島真一郎先生、谷口綾子先生には、石川竜一郎先生を通して、重要な図書の紹介など大変
ためになる助言をいただきました。深く感謝致します。
最後に、両親には時間を割いて書きかけの論文を読んでいただき、さらに助言を与えていただきま
した。ここにあらためて感謝いたします。
4
目 次
第 1章 序章 7
1.1 問題意識 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 厚生経済学の基礎概念 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 厚生経済学の発展 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.2 規範的経済学の情報的基礎 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3 厚生主義的帰結主義の問題点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 環境問題への適応 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.1 環境財 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.2 利用価値と非利用価値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第 2章 持続可能な消費の提言 21
2.1 先行研究の問題意識 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.1 独立な状況での消費選択モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.2 相互依存的状況での消費選択モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3 先行研究の結論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
第 3章 持続可能な消費の実現 37
3.1 非厚生主義的アプローチ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.1 持続可能財と非持続可能財 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
3.1.2 共感とコミットメント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.1 環境財の消費を伴う消費者選択 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2.2 独立な状況での消費者選択モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.2.3 相互依存的状況での消費者選択モデル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3 結論 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
第 4章 まとめ 61
6
第1章 序章
1.1 問題意識
昨年、2007年のノーベル平和賞では、初めて環境問題を人類の平和に重大に関わるとして認め、
人々に対する環境への関心を呼び起こすために寄与したとして、IPCC気候変動に関する政府間パネ
ルとアル・ゴア氏に対しノーベル平和賞が与えられた。日本でも消費者の環境に対する関心は年々高
まるばかりであり、企業もその企業活動に環境活動を取り入れ、環境に優しい商品の開発も活発にな
りつつある。企業は、消費者が環境保全の価値を認める行動をとり始めているために、環境に優しい
商品の開発に投資を行い、コストをかけて商品を供給している。
環境問題が人類の平和に重大なかかわりがあると認められてきたのは、経済学の一つの転機では
なかろうか。これまで、世界は経済学の恩恵を十分に受け発展してきた。しかし、その発展もまった
く害がなかったわけではない。世界が持てる者、持たざる者に分離され、経済学が発展する依然には
なかった類の脅威が平和を脅かしている。そして、同様に、大量生産・大量消費が社会生活で必然的
に生じる現代では、これまで考えられなかった類の環境問題も生じている。資源配分の達成方法を研
究してきた経済学はここへ来て、更なる深化が必要になっている。環境問題に関して言えば、問題を
踏まえたより深い議論が必要かつ、パラダイムの転換が必要なのではないかと考えるのである。
伝統的な経済学の視点から地球温暖化などの環境問題を考えても、市場での個人的利益追求が環
境問題をも解決できると考えることもできる。しかしながら、この考えには少なくとも環境改善によ
るメリットを消費者が認識し、何かしらの情報的基礎に基づく環境への関心が消費者に芽生えること
を前提としている。では、この情報的基礎とはどのようなものだろうか。消費者が環境問題に配慮す
7
るような消費選択肢をとったとき、伝統的経済学の顕示選好理論においては、消費者はその選択肢を
取ることによって自身の効用を最大化していると考える。つまり、上でも述べたように、環境改善に
よるメリットを享受することを消費者は認識していると考えるのである。しかしながら、このよう
に消費者の行動から考えると一つの疑問が生じる。果たして、環境に配慮する消費を行う消費者は、
常に自身が環境改善による十分なメリットが得られると考えているのかという疑問である。この疑問
の答えは残念ながら否であろう。環境問題に直面した消費者は、往々にして効用最大化行動では説明
がつかないような、環境に配慮した行動をとるだろう。そして、環境問題に直面した消費者が効用最
大化行動では説明できない行動をとるとき、そのような消費者はまさしく自身が持つ倫理観もしく
は道徳心に突き動かされてると考えられるのではないだろうか。
このような問題意識の下、本論分での主要な目的は、こうした意思決定が、消費者の環境に対する
異なる倫理観によって自然資源を利用しないことに価値を認めたことの帰結であると考え、倫理観に
よる価値判断が持続可能な消費を導くことを示すことである。第 1章では、本論分での主要な問いに
答えるために、まず、これまでの伝統的な規範経済学の問題点を示す。これによって、消費者の選択
になぜ倫理観が影響していると考える必要があるのか明らかにする。次に、伝統的な規範経済学の
問題点と改善案は、環境問題にどのように適応できるか示す。第 2章では、本論分の主要な問いを
分析するための先行研究を概観する。ここでは、環境に対して倫理的関心を持つ個人の消費行動が、
持続可能な消費を行ううえで、どのような影響を持つのかの分析を示す。第 3章では、第 1章におけ
る目的のための予備的考察を基として、先行研究の問題点を克服しながら、倫理観による価値判断が
持続可能な消費を導くことを示す。
1.2 厚生経済学の基礎概念
私の関心は、環境への倫理的関心が消費行動にどのような影響を与えているかであり、そのよう
な動機が効用・厚生もしくは消費者の選択判断にどのように影響するかにある。したがって、はじ
8
めに、消費者選択において最大化の対象となる効用・厚生という選択判断の情報的基礎が、これま
での経済学でどのように取り扱われてきたのか明らかにすることは重要である。この節では、主に
鈴村興太郎氏の著作を基に、これまでの厚生経済学発展の沿革を示すとともに、経済学の情報的基
礎には何があるか、それに対してどのような批判があるのか明らかにする。さらに、Diamond and
Hausman [4]を基に、環境財の消費を伴う消費者選択においては、環境への倫理的関心が選択判断に
おいて非厚生情報を取り入れることの可能性を明らかにする。
1.2.1 厚生経済学の発展
厚生経済学 (welfare economics)とは、ある経済における分配の効率と、その結果としての所得分
配を分析する経済学の一分野である。厚生経済学は経済政策のあるべき姿を理論的に設計する課題
と密接なかかわりを持っており、それだけに、歴史的起源は非常に古い。しかし、この分野に対して
厚生経済学という名前が与えられたのは、アーサー・セシル・ピグーの記念碑的著作 (Pigou [8])に
よってである。
経済学の重要な位置づけを担うミクロ経済学は、経済の資源配分にかかわる諸問題を主として理
論的に研究する学問分野である。異なる社会は、異なる経済制度を用いてその経済問題に対応してい
る。したがって、資源配分の問題の理論的な研究を課題とするミクロ経済学は、ある経済メカニズム
がさまざまな資源配分の問題を解決するうえで、どのような性能を示すのか理論的に解明しようと
する「事実解明的アプローチ (positive approach)」と、ある資源配分の問題はいかにして解かれる
べきか、ある資源配分の問題はいかなる経済メカニズムで対処すべきか、という問題を取り扱う「規
範的アプローチ (normative approach)」とに、ごく自然に分けることができるのである。
そして、後者の規範的アプローチの研究を推進する分野を一般に厚生経済学という。その際には、
経済のあるべき制度的仕組みを設計するにあたり、現存の、あるいは歴史上の経済メカニズムに限定
すべき必要性はない。したがって、厚生経済学が担う課題は、経済のあるべき制度的仕組みを理論的
に、公理主義的に設計するという壮大な課題も含むことになる。
9
1.2.2 規範的経済学の情報的基礎
厚生経済学がミクロ経済学における規範的アプローチを担当する分野であることは明らかになっ
た。そして、これまでの厚生経済学においては、開発された特定の判断方法に依拠しながら、社会シ
ステムの妥当性を判断してきたのである。では、規範的アプローチのなかで、ある経済の社会的な
妥当性の評価はどのような情報的基礎をもとに、つまり、どのような判断方法によって行われている
のだろうか。この項では、あとで行われる分析の理解を助けるために、規範的経済学における社会
的評価形成の情報的基礎を分類し、伝統的な厚生経済学がこれまで共通して「厚生主義的帰結主義
(welfarist-consequentialism)」を保持してきたことを明らかにする。
ある社会システムもしくは政策の妥当性を評価する上での情報的基礎という概念を理解するため、
それらを種類ごとに分類する必要がある。まず、社会的評価の判断基準を、政策やシステムの帰結の
みの情報に関心を絞るのか、それとも帰結だけでなく、そこに至るプロセス自体にも注目するのかに
分けることが理解を助ける。
これらは帰結的観点と非帰結的観点といわれる。詳しく述べると、帰結主義 (consequentialism)」
とは、あるシステムないし政策の是非を判断する際に、社会評価の対象となる経済システムや経済政
策の帰結に関する情報にもっぱら関心を絞り込んで、帰結の是非からその帰結がもたらす経済シス
テムや経済政策の是非を判断する立場を指す。これに対して、「非帰結主義 (non-consequentialism)」
とは、行動や政策の帰結の是非もさりながら、その帰結の背後にある非帰結的な情報――実際の帰結
以外に選択可能であった機会集合 (opportunity set)自体の価値や、帰結の実現を媒介した選択手続
きないし選択メカニズム (choice procedure or choice mechanism)など――にも配慮して、行動や政
策の是非を広範な情報的基礎に立脚して評価する立場を指す。当然のことだが、非帰結的な判定方法
といえども、一般的には帰結の是非をまったく考慮の外に放置するわけではない。非帰結的観点に立
ちながらも帰結の是非を考慮しない立場は、特に「義務論的 (deontological)」な評価方法と呼ばれて
区別される。
帰結主義的な観点に立つ判定方法それ自体の内部にも、ひとつの重要な分岐点がある。行動や政策
10
図 1.1: 規範的経済学の情報的基礎の概略
がもたらす帰結を評価する際に、その帰結から人々が得る厚生にもっぱら注目して、このものさしに
反映されない帰結の特徴はおしなべて無視する立場は、特に「厚生主義的帰結主義」ないし「厚生
主義 (welfarism)」と呼ばれている。これに対して、帰結主義の立場に依拠しつつも、ある帰結から
人々が得る厚生に関する情報に加えて帰結に関する非厚生的な情報も考慮に入れて、行動や政策の
是非を広い観点から評価する立場は「非厚生主義的帰結主義」ないし「非厚生主義 (non-welfarism)」
と呼ばれている。
厚生主義的帰結主義の内部でも、厚生を基数的に解釈するか、序数的に解釈するか、また、個人間
比較の可能性を認めるか、認めないかによって一層の細分化を行うことが可能である。非厚生主義的
帰結主義も、厚生情報に追加あるいは代替して考慮されるべき非厚生情報として何を採用するかに
応じて、さまざまな立場が区別される。システムや政策に関する規範的評価の情報的基礎についての
以上の議論を簡潔に表すのが図 1.1であるである。ここで示しているように、功利主義は厚生主義的
帰結主義に属し、その厚生は基数的かつ個人間比較が可能であるとして分類される。また、パレート
原理に代表される規範的な評価は厚生主義的帰結主義に属し、その厚生は序数的かつ個人間比較不
可能であるとする効用理論である。ピグーによって創始された初期の厚生経済学は功利主義的考えに
よって規範的評価を行ってきたが、対する新しい厚生経済学においても、その厚生が基数的か序数的
かまた、個人間比較可能か不可能かの違いはいるにせよ、厚生主義に依拠して規範的評価を形成して
いるのである。
11
1.2.3 厚生主義的帰結主義の問題点
本稿の主要な目的は、環境問題を引き起こす消費選択において、環境に対する倫理観が消費者選
択行動に与える影響を分析することである。ここには、環境問題に対応した持続可能な消費選択を
分析するために、厚生主義に立脚した分析で十分なのかという議論も含む。正統派の規範経済学に
おいて、つまり、厚生主義的帰結主義に基づくパレート原理や補償原理による資源配分には、消費の
持続可能性の論脈でどのような問題があるのだろうか。公害問題や地球温暖化のような環境問題は、
環境財の公共財的性質によって社会的ジレンマのような状況によって、社会システム内の人々の厚生
が失われたという側面が強いが、生物多様性の危機などの問題をどうだろうか。これは、社会的ジレ
ンマのような状況によって、社会システムの外の主体の厚生が失われたという側面が大きいのではな
いだろうか。もし、社会システム内の人々の厚生が最大化されていたとしても、社会システム内の
人々は、通常このような状態を最適な資源配分の結果とは思わないのではないか。これは環境問題の
文脈では、厚生情報のみを基礎とした資源配分の結果は、人々は妥当だとは思わないことを示唆して
いるとともに、環境問題を引き起こす消費者選択では、消費者を厚生主義に立脚させた上での分析で
は不十分である可能性も示唆している。
ここで述べたような正統派の規範的経済理論の問題点は、この理論が個人の選好に対して過酷な重
荷を負わせてしまっているという Sen [9]の指摘を示すことで明らかになるだろう。以下では、Sen [9]、
鈴村・後藤 [12]、Harsanyi [5]を参照して、厚生主義的帰結主義的規範理論が人間行動の多様性を捨
象してしまっているという問題点を明らかにする。また、人々の行動動機が多様であれば、個人が選
択肢の厚生情報のみを判断基準とする必要がないことも示す。
正統派理論においては、個人が持つ選好を唯一の道具として、次のようなまったく異なる種類の
問題に対処しようとしている。第一に、個人の私的利益追求の問題である。つまり、正統派の理論で
は、個人の利害関心は主体が表明する選好にそのまま反映されると仮定される。第二に、個人の厚生
の評価の問題である。正統派の理論では、個人の厚生は主体の選好と直接的な対応関係にあると仮定
される。第三に、個人の選択行動の合理化の問題である。個人の選択行動は主体の選好が合理的に最
12
適化された行動であると仮定されている。このように正統派理論では、個人の選好に対して過剰な重
荷を課してしまっており、同時に選好、利害、厚生、選択という異なる意味を持つ概念を必然的に連
結してしまっているのである。ここでは、人間の行動動機の多様性を全て捨象して、人間をたった一
つの選好に隷属する《合理的な愚か者》として処遇してしまっているのである。
加えて、まずHarsanyi [5]によって導入された《倫理的選好 (ethical preference)》と《主観的選好
(subjective preference)》という選好の概念的区別により、正統派理論が選好概念の多義性を無視し
ているという具体的な異論を述べることが可能である。倫理的選好は、主体が自分の主観的な立場や
個人的な利害から意識的に離れて、客観的な衡平性や正義など没個性的 (impersonal)な社会的配慮
に基づいて表明する規範的な選好判断である。主観的選好は、主体が自身の人格と個人的立場にあく
までも固執して、主観的に表明する個性的 (personal)な選好判断である。このどちらもが、当該個
人が持ちうる選好判断と呼ばれるに相応しい資格を備えている。にもかかわらず、正統派理論では個
人の選好と個人の主観的利害を直結させてしまっているのである。ここでは、人々の倫理的選好に正
当な位置を与えない極端な立場となっており、人々がそれぞれ異なる倫理観から、道徳的判断を行う
社会的存在であることを、意識的に無視する過ちに陥っているのである。
次に、Sen [9]によって導入された《コミットメント (commitment)》という人々の行為形態の概念
により、正統派理論では人間行動の動機に関して視野が狭い特殊なアプローチであるという具体的な
批判も述べることができる。コミットメントは、正義感や他人の窮状に対する義務感から、自分の
(主観的)選好の観点からは最善でない選択肢を敢えて自覚的に選択するような行為形態である。明
らかにコミットメントは人々の倫理観と密接な関係があると考えられる。しかしながら、正統派理論
は、主体の倫理観に動機付けられた主観的選好に反するような行為に対して理論的な位置を認めな
いという極端な立場なのである。
簡潔に言えば、正統派の規範経済学において厚生主義的帰結主義に基づく情報的基礎しか用いな
いとは、消費者を以上で示したような過剰な重荷を課された選好を基に合理的行動を行う者として
扱うということを表している。しかしながら、本稿では、選択を行う特定の消費者とは厚生的結びつ
13
きが考えにくい、もしくは、個人の主観的な選好に反する行動を取っていると考えられるような環境
問題を巡る消費選択を考える。ここでは人々が往々にして多様な異なる倫理観を行動動機として行動
していると考えられる。したがって、正統派経済学での厚生主義的帰結主義に基づく分析では不十分
である。人々が多様な倫理観を行動原理とする行動を取るとき、人々の選好を厚生情報に直結するも
のとして捉えるのではなく、非厚生的な情報も取り入れなければ消費の持続可能性を考慮した資源配
分の妥当性は判断できないのである。
1.3 環境問題への適応
現在自然環境保護の問題には多くの人々が関心を抱くようになっている。大量の炭酸ガス放出が主
な原因とされる地球温暖化、フロンガスによるオゾン層の破壊などは、全地球的に影響が懸念され解
決が急がれているし、ヨーロッパでは酸性雨による森林破壊や湖泥の酸性化など局地的な公害問題も
増加している。また、人間に明確な直接的影響はないものの絶滅危惧種の増加や、生物多様性に対す
る人々の懸念も年々大きくなっている。
これらの環境問題は、自然環境が通常の公共財のように消費の非排除性と消費の集合性という性
質をもつことに起因すると考えることもできる。自然環境の供給を望む人々は、自然環境が消費の
非排除性を持つために、自身が本当に考えるその対価よりも過少にしか費用を負担しようとしない
だろう。人々が大気などの自然資源を消費するとき、その私的費用は社会的費用を大きく下回るだろ
う。それによって、自然資源が過剰に消費されたり、過少にしか保全されないのである。
経済理論では市場が完全であれば資源は効率的に配分されるが、外部経済・不経済が存在する場
合、公共財の場合などは資源は効率的に配分されない。自然環境はそれ自体が公共財の性質を持つも
のがほとんどであり、その消費に伴い外部経済・不経済も発生するためにこのような環境問題が生じ
る。このように考えるとき、自然環境の最適な資源配分は政府が課税や規制といった介入をすること
によって問題を解決に導くことができる。しかし現実的には、政府がほかの公共財を供給するように
14
地球温暖化や生物多様性に対応すれば、現実の環境問題を解決できると考えるのは楽観的過ぎるの
である (細田 [6])。
自然環境という財は公共道路や公共施設といった通常の公共財とは明らかに異なる性質を持つ。そ
れは自然環境が自然によってのみ供給されるということである。伝統的経済学で考えるように消費
者がその主観的選好にのみ依存した消費者選択を行うとき、特定の自然資源が社会で消費されつく
されようとしていても、そこに利用価値がある限りその価値は消費者に配分されるべき価値である
と考えられてしまう。そこでは、自然環境が自然のみによって供給されているということへの配慮が
まったくなされていないのである。特定の環境問題を考えるとき、自然環境を保全することに対する
なにかしら価値を認める必要が生じている。しかしながら、このような価値は、通常の財がそうする
ようには人々の厚生には影響しないために、規範的評価の情報的基礎として正当に評価されていない
のである。にもかかわらず、人々は往々にそういった価値を自身の判断基準として用いる。実際に、
Paavola [7]によれば、そのような自然環境を使用しないことといった、消費者の環境資源への消極
的な働きかけの価値は、多くの消費者選択において観察されるのである。
環境に対する倫理観は、環境を保全する価値という、直接的には厚生に関わる情報とはいえない価
値を、消費者選択分析で認識する上で重要である。したがって、持続可能な消費の論脈での資源配分
の妥当性判断には、人々が環境に対する倫理観によって、そういった非厚生情報を考慮している状況
を考える必要が生じる。以下では、消費可能な自然環境として環境財を公共財に対して定義すること
によって、環境に対する倫理観を消費者分析に取り入れる必要性を明らかにする。また、消費者は環
境財に対してどのような価値を認めるのか示し、第 3章での分析に必要な基礎的情報を提示する。
1.3.1 環境財
本論文では、細田 [6]を引用して環境財を次のように定義する。環境財は消費の排除不可能性と消
費の集合性という公共財と同じ性質を持ち、おもに自然によって供給される。人間はこの財を利用し
て経済価値を生み出すが、この財自体は生産できない。したがって、一旦この財が破壊されたり、不
15
完全な形でしたか保全されない場合、その財を復元することは困難である。例としては、自然景観、
野生動植物はもちろん、均衡した自然な状態としての空気や、未開の原生林なども含まれる。
通常の公共財との大きな違いは、人間は環境財を生産することができないということである。した
がって、人々が環境財を利用することを望むに任せて、環境財を消費していけば、それは枯渇してし
まうか、人間が価値を見出せないほど質が低下していまうかして、破壊されてしまい二度とその環境
財を消費することができなくなってしまうのである。通常の公共財であれば、人々が利用を望めば、
その対価を徴収すればその公共財はさらに生産することができるのに対してである。
ここから容易に導かれるのは、環境財の消費を巡る選択状況では、環境財を消費・利用する価値の
みでなく、環境財を消費・利用しない価値も消費者行動に影響を与えていなければならないというこ
とである。そして、このような環境財を消費・利用しない価値は、ほかの公共財や私的財の持つ価値
のようには、選択行動に影響を与えない。この環境財の非利用価値は、人々の倫理観を媒介として選
択判断に影響を与える。そして、環境財の非利用価値は、直接的に厚生に関する情報とはいえない
ために、伝統的経済学での厚生主義に基づく枠組みのなかでは、正当に位置づけることができない。
したがって、環境財の資源配分の正当性を判断するため、情報基礎を厚生情報に限定せず、それ以外
のあらゆる情報に基づいて判断する必要が生じるのである。
以下では、環境財の利用のされ方を分類し、それぞれの利用形態は人々が環境財に対してどのよう
な価値を認めるために行われるのか明らかにする。同時に、環境財の価値を分類して、厚生情報以外
の情報的基礎を、消費者選択における価値判断に位置づけることとする。
1.3.2 利用価値と非利用価値
環境財は自然によって供給され利用されるが、その利用形態はいくつかに分類できる。人々は環境
財の所有権を持つか、自由に使う権利を与えられるかすると、その環境財を利用して経済価値を生
み出そうとする。そこで、その利用方法として第一に考えられるのは、環境財の直接的利用である。
森林を伐採したり、水産資源を利用したりする場合は環境財を直接的に消費して経済価値を生み出し
16
ていると考えられる。対して、環境財の間接的利用も考えられる。レクリエーションとしての森林浴
や、山や森の水源浄化機能は、消費はできないものの間接的に利用して経済価値が見出されていると
考えられる。人が環境になにかしらの影響を与えるとき、ここで挙げたように人は環境財を直接的も
しくは間接的に利用することで影響を与えるのである。
とは言っても、通常の経済活動は地球上で行われる限り、多かれ少なかれ環境財を直接的もしくは
間接的に利用するものであるということは容易に認識できる。しかし、忘れてはならないのは、環境
財がすがたをかえて市場で取引されるとしても、環境財自体は自然によってしか供給されないという
ことである。伝統的な経済学では、たとえ市場で取引される財が環境財を直接的もしくは間接的に
使用するものであっても、それを利用する価値にのみ経済的価値を見出して分析してきた。しかし、
Housman [4]によると、近代の大量消費社会が到来して以来、グランドキャニオンや絶滅危惧種のよ
うに貴重な生態系に対しても、人々は関心を払うべきだという認識が生まれてきたということが述べ
られている。
人々が財を消費するとき、一定の費用を支払う。その財が市場で取引される財であれば、消費者は
その財を消費するために市場で決められる価格を支払う。このように市場で観察される消費者の行動
は、消費者にとってその財が少なくとも価格以上の価値を認めているということを示している。も
し、その財がある事故で破壊されたなら、市場で支払った価格がその消費者にとっての被害額と考え
ることができる。このように、伝統的な経済学では、このような費用効果分析もしくは被害補償原理
の考えかたで、その財の価値を評価する。通常の市場財や公共財の場合にはこのような考え方はもっ
ともらしい。それは通常の財や公共財は、それを利用する経済主体がその主観的な利用価値のみを考
えれば十分だからである。
では、環境財においてはどうだろうか。自然にしか供給されないという環境財の特徴から導かれる
ことは、環境財に対して評価される価値が消費者の主観的な利用価値のみだけでは、望ましい社会的
帰結が得られないということである。環境経済学においては、消費者の環境の直接的・間接的利用に
対しての評価を、なんらかの方法で測定する試みが行われてきた。それは伝統的経済理論である顕示
17
選好の理論がベースになっていると考えられる。たとえば消費者にとっての、環境財の間接的利用
の価値(例えば、娯楽としての釣り)は、通常市場で取引されることはないが、その価値の評価は、
市場財の評価と類似している。つまり、環境財の価値は直接的には計測できないが、消費者の行動を
観察することで間接的に評価できると考えるのである。その方法として初期に発達してきたのは、代
替的な環境財の利用に行動を変化させることの費用を測定する方法である。このような方法はトラ
ベルコスト法として知られている。しかしながら、こういった基本的枠組みにおいても、消費者の観
察可能な行動に依存した環境財の評価が行われている。ここで生じる疑問は、こうした消費者の行動
から導かれる環境財の価値は、やはり消費者の主観的利用に基づく価値としてすべてその消費者の
厚生に結びつくのだろうか。それとも、行動から導かれる環境財の価値は環境財そのものの総価値を
反映しているのだろうか、ということである。
環境財の非利用価値は、その環境財を保全することの総価値を考慮して、利用価値を補完するため
の概念である1。伝統的経済学では、環境財を直接的・間接的に利用する主体は、その行動が自身の
効用の上昇に寄与し、選好を満足するためにその行動をとると考える。それはまさに、Harsanyi [5]
が言及した主観的選好(subjective preference)を満足する環境財の価値に重きを置いた解釈である。
利用価値は、まさしくこの主観的選好を満足する価値と考えられる。そして、同様に考えれば、環境
財を保全することの総価値を考慮する非利用価値は倫理的選好 (ethical preference)を満足する価値
なのである。ただし、Harsanyiの用いた《倫理的選好》と《主観的選好》の概念は、経済主体の消
費選択行動のもととなる個人の選好を、客観的な衡平性や正義など没個性的(impersonal)な社会的
配慮に基づいて表明する規範的な選好判断と、個人が主観的に表明する個性的(personal)な選好判
断とに区別するために用いられている。したがって、それは環境の客観的価値を区別しようとしてい
る、利用価値と非利用価値とに完全に対応可能とは思えず、このような単純な二分法は完全には成り
立たない。なぜなら、人々は環境財の非利用価値を認めることに対して喜びを感じたり、社会的評価
1利用価値には、自身の将来利用の期待価値も含まれる。しかし、この利用価値は将来の不確実性のために、正確にはわからない。そこで、将来の確実な価値のための権利の価値として、オプション価値が存在する。非利用価値であるオプション価値はあくまでも、将来利用の現在価値を補完する概念である。このように、非利用価値はその他にも多様な個人的関心に基づくものとして記述され分類される。一つの分類として Housman [4] は、非利用価値を(1)主体自身と関連した非利用価値、(2)主体以外の他者と関連した価値、(3)人間の利用には関連しない非利用価値とに分類している。
18
を得ることを目的に、その価値を認めるかも知れないのである。
そのような場合を考える場合には、A.Senが導入した《共感》と《コミットメント》を用いること
は理解を助ける。共感は、他者への関心が直接に自身の厚生に影響する場合に対応している。もし、
他者の苦悩を知ることが自身の具合を悪くするのであれば、それは共感である。対して、他者が苦悩
するのを知り、自身の具合は悪くないが、それは不正なことだとしてそれをやめさせる場合は、それ
はコミットメントに対応するものである。実は、共感はまさしく上で述べた、非利用価値を認めるこ
とで自身の効用増加を期待するという意味で、主観的選好の一部に含められる可能性があるのであ
る(Sen [9])。
正統派理論の慣行では個人の関心は主観的な利害に直結しており、それは主体が主観的選好に基
づく行動をとる場合と対応している、と上で述べた。ここでは人が、公平で没個性的な判断を行わな
いものとして扱われる。しかし、共感は自分以外の被害に対しての物理的でない、間接的な反応であ
る。環境財の利用価値に対しては、その定義から人々が共感を感じる余地はほとんどないのである。
対するに、環境財の非利用価値は環境財を保全することの総価値を反映したものであり、自然環境側
からみた価値と考えられる。したがって、人々が自然環境側に対して共感を感じる余地はあるのであ
る。そのように考えれば、正統派理論の慣行で想定している経済主体も、自身の厚生に影響する限り
において、倫理観がその消費者選択に影響していると考えられる。
人々は、環境財に関する消費者選択において非利用価値を評価する際、共感とともに、コミットメ
ントによっても影響されている。共感が自分以外の被害に対して厚生の減少をもたらすために選択に
影響するのに対して、コミットメントはそうではない。厚生主義の仮定のもとでは、コミットメント
に対して正当な位置を与えていないのである。したがって、環境財を巡る議論では、その非利用価値
に対して、その十分な位置を与えてはいないといえる。環境財の資源配分の妥当性を判断するには、
環境に対する厚生主義的倫理観に対応する共感と非厚生主義的倫理観に対応するコミットメントが、
消費者選択における非利用価値の認識に密接に関わっていることを認める必要がある。
繰り返すが、環境財を巡る議論では、そこに、直接的に主体の厚生に関係しないが、資源配分にお
19
いて考慮される資格を十分にもった非厚生情報である非利用価値が存在するために、消費者選択にお
ける共感とコミットメントの影響も考慮しなければ十分ではない。非利用価値は個人のそれぞれ異な
る倫理観によって、消費者選択で影響を与えるのである。したがって、消費者が環境財の利用価値と
非利用価値とを個人の多様な倫理観のもとに認識して選択行動を行うとすれば、倫理観が環境財の
消費選択行動に与える影響と、環境財の持続可能性についての議論が可能になるのである。
20
第2章 持続可能な消費の提言
第 2章では、環境に対して倫理的関心を持つ個人の消費行動が持続可能な消費を行う上でどのよう
な役割を持つのか分析する、Paavola [7]の先行研究を概観する。先行研究がはじめに行うのは、環
境への倫理的関心は人々の異なる倫理的信念に基づいて存在し、異なる行動原理により消費者選択に
影響を与えるという仮定である。そして同時に、利己的厚生主義者は、自身の厚生を犠牲にして環境
保護を行うことはできないが、非厚生主義的帰結主義者はそれができるとする主張も行う。これらの
仮定を基に、まずは独立な状況における消費者選択モデルを用いて分析を行う。次に簡単なゲーム
理論の枠組みにおいて、消費者が社会的依存関係にある場合を想定した補足的議論も行う。最後に、
社会が環境に対し非厚生主義的倫理観を持つ消費者で満たされている場合には、持続可能な消費が
行われることが示される。
2.1 先行研究の問題意識
企業が環境活動に取り込み、そのコストを商品に転嫁させるとき、その商品を選択する消費者に
とって、財に付随する環境に対する貢献は少なくともその上乗せたコスト分以上の価値があると考え
られる。つまり、通常のように環境財の市場がなく、その市場価格が存在しないとき、その環境財に
対してどの程度支払う意思があるのかは、個人の環境に対する関心に大きく依存することになる。
客観的に個人がその環境財の水準に対して支払おうとする額が観測可能であった場合、伝統的な
規範経済学の枠組みの中では、その支払い意思額が個人がその環境水準から受ける便益であり、効用
または厚生の上昇であると考える。しかしながら、公園や公共施設のような通常の公共財においてそ
21
の対応が妥当であったとしても、こと環境問題に対してそのような見方が妥当であるとは限らない。
なぜなら、個人の環境財に対する支払い意思額は、個人の倫理的関心に負う部分が大きいし、環境財
に関する情報が完全であっても、倫理的関心による厚生の上昇と結論付けるのは、早計であるという
ほかない。
よって、Paavola [7]は、消費選択における、消費者の環境財に対する支払い意思額が環境への関
心とどのようなかかわりがあるのか明らかにすることを試みている。つまり、環境保護的消費行動を
とる動機には様々なものがあることを明らかにし、主体の厚生には直接影響しないような動機も含
むようにしすることで、より広い範囲で行い経済分析に適応することを試み、新たな政策的含意を
引き出そうとしているのである。具体的には、規範的分析のなかで非厚生主義的なアプローチを採
用して、その情報的基礎に厚生以外のものとして環境への倫理的関心を考慮するのである。そして、
合理的消費選択に関するミクロ経済学的アプローチによる分析の中で、環境に対し倫理的関心を持
つ個人の行動が持続可能な消費を形作る上で果たす役割を考察しているのである。
2.2 モデル
Paavola [7]では、持続可能な消費について次のような定義を行った。持続可能な消費は、単に環
境に有害な影響を減少させる消費を意味する、というものである。また、個人の消費へ言及する際に
は、彼らの倫理的信念によって、環境を悪化させないように奉仕的かつ自主的に消費行動を修正する
動機を持つことの可能性を認める。そして、このような動機は、功利主義、非功利主義的帰結主義、
義務至上主義など形式的に異なる倫理的信念が根底にあると考えるのである。さらに、消費者が直面
する選択肢の組は、社会的道徳から派生する協調行動によって、または、そのような行動によって後
押しされる公的機関によって制限されて提供されるものであると主張する。
22
2.2.1 独立な状況での消費選択モデル
持続可能な消費を行ううえで、個人の行動がどのような役割を果たすのか分析するための手始め
としては、単純な合理的選択モデルを用いることは有用である。通常の合理的選択モデルでは、それ
ぞれの消費者は、自分自身の厚生にのみ興味を持ち、自身が直面している選択肢と予算制約のもとで
効用の最大化を図る。そして、消費者は直面している消費選択に関する情報を得る完全な能力を持っ
ているいう、完全情報の仮定も取り入れる。この分析では、消費者選択の分析のはじめの一歩として
独立な消費者の消費行動を分析するために、外部性の存在は無視されることになる。
しかしながら、このように通常用いられる合理的選択モデルでは、効用または厚生のとり扱いに
おいて重大な問題点が存在する。初期の厚生経済学における経済分析で用いられる効用概念は喜び
(pleasure)や有用性(usefulness)として理解されていた。それゆえに、効用は個人の厚生や選好と
強く結び付けられていた。20世紀に入ってから効用は、それが何であろうと、個人の選好の満足度
として再定義されることとなった。しかしながら、この再定義は、選好をどの程度満足させられたか
と効用を定義することで、個人の厚生関心からすべての物質的要素を排除する結果となっているので
ある。
言い換えれば、伝統的な規範経済学において、個人の選択行動は個人の選好に直結しており、そし
て、その選好は個人の利害とも直結している。したがって、この考え方の中では、個人の多様な倫理
的信念に基づく行動でさえも、ただその選好判断によって行われる結果だと考えてこられたのであ
る。しかし、このように選好判断を万能として考える見方には問題がある。個人の多様な倫理的信念
は確かに、いくつかに分類しうるし、するべきであり、それによって、倫理的信念の多様性を分析の
中に取り入れることができるのである1。
そこで Paavolaはこの分析の中で、それが何であろうが、その選好の満足度が効用であると認め
る広い定義を手放し、より狭い意味での効用を、個人の経済的厚生に関連付けられた喜びや実用性と
して定義しなおしている。これは概念的に、Harsanyi [5] によって導入された倫理的選好と主観的選
1詳しくは、第 1 章 2 節 3 項、もしくは鈴村・後藤 [12]
23
好を用いて考えることができる。
Paavolaのこの効用の再定義は、個人の倫理的選好にその正当な位置を承認しない、正統派理論の
慣行をより際立たせる役目を負うのである。したがって、消費者の選好の基礎にある倫理的信念を選
好判断に導入したときと比較することで、選択行動におけるそれらの含意を分析することが可能に
なるというものである。
はじめに行っているのは、通常の合理的選択モデルにおける経済主体は、上で述べた狭い意味での効
用最大化を追求する、主観的選好に基づく行動をとる、功利主義的信念(利己的厚生主義 self-centered
welfarism)を持ち、また、そのような信念しかもっていない場合についての分析である。これは伝
統的経済学における消費分析と同様である。このような合理的選択モデルにおいて消費者はある選
択肢に直面する。消費対象の財は、直接消費者に厚生を与えるか、もしくは、家庭で最終財に変換さ
れた後、間接的にそうするような特徴を持つ。消費者は、予算制約のなかで与えられた選択肢から、
選択を行い、制約のなかで最も利己的厚生を満足するように行動する。これはある時点での消費を先
延ばしにしたりすることも含むし、借金により先に消費を行うことも含む。彼らがどんな選択を行う
場合でも、選択肢のリストは市場によって形作られ、彼らが取得可能な財集合や貯蓄機会集合を制御
することはない。つまり、消費者は与えられた選択肢から自由に選択できるが、彼らが直面する選択
肢自体を選ぶことはできないし、選択から逃れられるわけでもない。
もし世界が利己的厚生主義の消費者、つまり、主観的選好にのみ依拠した行動しかとらない消費者
のみから成り立っていると仮定するならば、個人の独立な行動をより持続可能な方向へ移行させるよ
うな興味深い戦略は示すことはできない。利己的厚生主義の消費者の選好がどんなものであろうと、
現在消費するか未来に消費するかにかかわらず、消費者は予算制約いっぱいの消費を行えばよりよい
厚生を得ることができる。またそれはその消費が他人や環境に対してなにか影響を与える場合でも
同様であるだからである。
このような選択行動を行う消費者においても、人の厚生や環境保護はいくつかの消費選択において
両立できることが示されている。Paavolaはその例として、第一に、ジェットスキーに行かずに美術
24
館に行くというように、物質的消費を伴う行動ではなく、非物質的な行動を選ぶ場合をあげる。そし
て第二に、消費者がその選択によって厚生を改善すると信じるならば有機栽培による野菜を選択する
ような場合をあげている。しかし、ここでももちろん、利己的厚生主義の消費者は個人の厚生を犠牲
にするような環境保護は行わないのである。さらにいえば、このような利己的厚生主義の消費者も、
環境への選好は持ちうる。環境に利己的関心を持つ消費者が、ある環境財のために提示する支払い意
思額を考えると、その消費者にとっての環境財の価値は、主観的選好を満足させる、直接的または間
接的な厚生の上昇そのものなのである。しかしながら、このように厚生主義に立脚した分析よって
は、環境の貨幣価値を認める消費者の実際の行動を分析することは困難となる。Paavola [7]は、環
境の貨幣価値を認める個人は、環境保護を行うモチベイションを持ちながらもそのモチベイションを
自身の厚生向上のために使うことができていないということを指摘し、厚生主義に立脚した分析で
は倫理的選好判断を行う消費者の分析は行えないと主張するのである。
上で行った分析では、幾分制約的で非現実的な仮定を用いている。つまり、個人の選好判断と呼ば
れるにふさわしいはずの倫理的選好についての分析が抜け落ちているのである。社会に存在する個
人は、主観的選好や利己的厚生主義的判断にばかり基づいて行動しないだろう。自分の倫理的信念を
もっとも満足させるように、より意図的に行動することも十分に考えられるのである。Paavolaは、
倫理学や経済学の文献を引用して、合理的選択モデルのなかで異なる倫理的基礎から派生するよう
な環境への選好を理解する方法を示している。それは、個人の合理性の概念を、帰結重視または意
図的な行動として広く捕らえることにより、より一般化する方法である。これは個人の消費者選択
の是非を判断するときの、情報的基礎として、厚生主義的帰結主義の情報のみに注目するのでなく、
より広い情報を判断の基準として取り入れる方法であると解釈できる。以下、経済主体が主観的選好
にのみ依拠せず、倫理的信念を反映する倫理的選好にも依拠した消費者選択を行う場合について分析
するために、多元的価値を許すようにモデルを拡張することになる。
多元的価値の存在を理解するためには、個人が複数の異なる倫理的信念を持つこと (intrapersonal
value pluralism )、そして、各個人がそれぞれ異なる倫理的信念を持つこと (interpersonal value
25
pluralism)を示せばわかりやすい。個人が複数の異なる倫理的信念を持つとは、個人が自身の直面す
る選択肢において、その選択に影響しうる倫理的信念を複数持つことをあらわしている。個人は自身
が直面する選択状況において異なる選択を導く倫理的信念を持つと、熟考してどちらの信念を優先
させるか決定しなければならない。各個人がそれぞれ異なる倫理的信念を持つとは、異なる個人は同
様な選択状況において異なる倫理的信念を元に選択するかもしれないし、異なる倫理的信念から同
じ選択肢を選ぶこともあることを表している。
では、代表的な倫理的信念にはどのような特徴があるのだろうか。まず利己的厚生主義であるが、
この信念のもとでは自身の厚生を減少させるような選択は行わない。もしかしたら、そのような消費
者たちも、それぞれが車を使うよりもバスを利用することに価値を見出すかもしれない、同様に菜食
主義的消費を行うような異なった価値を持つかもしれない。だとしても、彼らの選択はただ、彼らの
厚生に一番寄与するようなものを表しているに過ぎないのである。次に非厚生主義的帰結主義であ
る。このような信念のもとでは、その選択肢がどのぐらい厚生の向上に寄与するかどうかは関係な
い。その結果に本能的に価値を認めるかどうかで判断するのである。たとえば、結果として大量にご
みが発生し、環境を悪化をさせるような選択肢は本能的に認められないだろう。最後に非帰結主義
である。消費者はなにも結果のみを気にして行動するわけではないだろう。同じ結果をもたらすが、
より小さな選択可能集合とより大きな選択可能集合では、多くの人がより大きな選択可能集合に価
値を見出すだろう。帰結主義的観点から言えば、この価値は同様とみなされるはずなのにである。非
帰結主義の特殊ケースとして、義務論的信念がある。義務論的信念に基づく選択においては、選択肢
の一部は、ただ間違っている、もしくは宗教で禁止されているからとして、排除されうる。その選択
は厚生の大小や結果の善悪には関係ないのである。ここで言及したような倫理的信念に基づく選択
を行う消費者も、広い意味での合理性の枠内で合理的に振舞っているのである。
環境への選好は、このように利己的厚生主義、非厚生主義的帰結主義、義務論的信念を基礎として
存在し、消費者の選好を別々に構成することになる。繰り返し述べるが、利己的厚生主義の環境へ
の関心は、その消費者に自身の厚生を減少させるような方法をとるようにすることはない。非厚生
26
主義的帰結主義や義務主義についていえるような非厚生主義的な環境への関心は、反対にそうさせ
ることができるのである。非厚生主義的信念において自身の厚生を減少させる選択を行う場合をよ
くあらわしているのは、国家の制度上の選択問題に直面している個人の行動である。多くの個人は、
自身の厚生が損失を被るとしても、政府に対して、活動の自由や政府からの自由を追求する。このよ
うに表明された態度は、このような自由が手段としての価値ではなく、本質的なものとして感じられ
ていることを暗に意味していると捉えることができるだろう。
価値多元性の認識は、経済分析における多くの重要な含意をもつ。Paavolaが指摘するのは、利己
的厚生主義以外の信念を基礎とする選択においては、消費者が自身の厚生を減少させるかもしれな
い選択肢を望み、実際に取りうるということの重要性である。環境に何かしら関心を持つ多くの消
費者の選択行動においても、このような状況はよく見られる。たとえば、機能的には同様であるが
より費用のかかる環境に優しい商品を選ぶ消費者は、現在では多く見られる。このような選択では、
消費者の中で、利己的厚生主義的信念による選好と非厚生主義的信念による選好の葛藤があり、結果
として、非厚生主義的信念に基づく選好を優先したと考えるべきだろう。
消費者が非厚生主義的信念を基礎とする環境への選好を持ち合わせていれば、個人の独立な行動
は持続可能な方向に変化させやすいことは明白である。そのような消費者は、ほとんどの消費選択に
おいて、利己的厚生主義的倫理的信念に基づいて行動する消費者よりも、環境に優しい選択をとる
と考えられるからである。また、そのような消費者は、利己的厚生を犠牲にした選択を行うことで、
消費能力を実質的に減少させてしまうのである。しかしながら、実際にそのような選好を示す人々ば
かりでないことは確かであり、未だ問題は残る。
非厚生主義的信念に基づく環境への選好を持つ人々ばかりではない通常の社会では、個人の行動
に任せた配分の結果には、社会的価値を認められない。持続可能な消費へのなにかしらの寄与も、社
会においてもっとも環境に関心2 を持つ消費者によってなされる。消費者が環境に優しい行動をとる
2厚生主義的信念に基づく関心と非厚生主義的信念に基づく関心の双方。利己的厚生主義であっても、その消費者の環境に対する選好の強さは異なると考えられるので、環境に強い共感を持ってしまった消費者は、それほど強い共感を持たない消費者よりも、環境保護に対して予算を割かないだろう。また、非厚生主義の消費者同士においても、そのコミットメントの強さによって、環境保護に対して割く予算には違いが生じるだろう。
27
ことで、効用の上昇を得ることができるとしても、やはり、それではそのような消費者に費用を押し
付けることの理由にはならない。利己的厚生主義的信念に基づく環境への選好しか持たない消費者
は、非厚生主義的信念に基づく環境への選好を持つ消費者や、利己的厚生主義的信念に基づくが強い
環境への選好を持つ消費者の、環境へ配慮した行動にただ乗りすることになるのである。このよう
な状況においては、社会的団結の結果としての消費税や所得税は、個人の行動に任せるだけよりも、
よりよい環境改善を実現できるのである。
加えて、選択肢の制限について次のように考えることができる。その倫理的信念がなにであろう
と、環境への選好を持つ人々の数が十分であれば、市場を通して、消費者が直面する選択肢それ自
体を変化させることができる。消費者の環境に優しい財への需要が増加し、環境に優しくない財へ
の需要が減少すれば、結果として企業は環境に優しくない財を供給することをやめるだろう。だと
しても、環境のために自身の厚生を犠牲にしたくはないと考える消費者が多数いる場合には、選択
可能集合に与える影響は制限されることになる。ここでやはり社会的共同行動の必要性が浮上する。
利己的厚生主義の消費者も多数いる場合には、たばこや麻薬といった、福祉(well-being)は悪化さ
せるが厚生は向上させると考えられる選択肢は、政府や自治体の介入による協調行動でしか排除で
きないのである。
合理的選択モデルにおいて、より多くの消費者が環境に対して非厚生主義的信念の下で選好を持
つ場合には、個人行動戦略は持続可能な消費行動をもたらすより大きな見込みを持つ。だとしても、
やはり社会的協調行動は社会的に妥当であるという帰結が生まれる。非厚生主義的環境への関心が
広く持たれていなければいないほど、協調行動はより少ない費用で社会的に望ましい状態をもたら
すことができる。また、非厚生主義的関心が広く持たれていたとしても、個人がたびたび道徳的ジレ
ンマに陥ることをなくすことができるのである。
次の項では、実際の状況において多くの消費選択が相互依存的であるという認識が、この節で行っ
た合理的モデルの評価をどのように補完するのかを考察することになる。
28
2.2.2 相互依存的状況での消費選択モデル
ある消費者の選択や厚生が、ほかの消費者と影響しあう状況とはどんなものであろうか。ある個
人の消費がほかの個人の厚生に影響を与えるような効果は、消費の外部性や地位に関する外部性
(consumption or positional externality)と呼ばれる。Paavolaは、はじめに、消費に関する相互依
存的状況は、これまでにどのように捕らえられてきたのかを明らかにしている。第一にバンドワゴン
効果について述べる。流行に多く作用されるような財にバンドワゴン効果がよく観察される。そのよ
うな財においては、他者がそれを選ぶことによって付加的な価値が与えられ、自分がその財を選ぶ追
加的な理由となる。第二にスノッブ効果である。消費者はある選択肢の組に直面したとき、ほかの消
費者がある特定の財を選んだことによって、その財に対する評価を減少させる場合がある。第三は
ヴェブレン効果である。この効果は、ある特定の財においては、その価格がそれを消費した消費者
の地位や消費能力に関する情報を他者に伝えるという点に注目した外部性の考え方である。加えて、
相互依存的な消費者選択の存在理由を、経済主体がその効用関数に他者の決定に関する情報を含む
ためとする見方もある。これは Becker(1976)によって用いられたものである。しかし、このように
消費者選択の相互依存性を捉えれば、その個人対個人の関係は、各個人による他者の決定に関する情
報の評価によって捉えられることになってしまう。これでは、各個人が他者に影響されながら選択を
行う説明になったとしても、消費の社会的側面を捉えたことにはならないだろう。
Paavolaは、消費の社会的側面を捉えることに重点を置いている。そのために、Becker [1] の、経
済主体の効用関数が所得、富、福祉やほかの経済主体の決定を含むからこそ消費は相互依存的であ
る、という主張は受け入れられないと述べる。
そこで Paavolaが行う重要な指摘は、社会的相互依存関係は消費した・財・の・外・部・性 によってもたら
されるというものである。この指摘は、相互依存的消費選択は、たびたび、選択の対象となる財の特
定の特徴によってもたらされるという考察による。つまり、その特定の特徴を持つ財が、その財を消
費した消費者のステータスや富についての情報を伝達することによって、他者の選択や厚生に影響
を与えるのである。したがって、選択の対象となる財を特定の特徴ごとに分類する必要が生じるこ
29
ととなる。ここで Paavolaが用いるのは、”positional goods”と”nonpositional goods”という概念
である3。”positional goods”は、消費者のステータスについての情報を他者に伝達する能力を持つ
財であり、”nonpositional goods”は利己的厚生主義的信念に基づく選好のみを満たす財である。私
は、ここではこれらをそれぞれ地位財と非地位財と呼ぶことにする。
地位財と非地位財という概念を用いるときその扱いは十分注意する必要がある。なぜなら、特定の
消費の社会的側面を考察するとき、その富やステータスについて、その消費の結果生じる状態とどの
ように関連付けるかで、導かれる結論が異なる可能性があるからである。たとえば、必需品のように
実際に生活に必要不可欠な財 (genuine needs)を非地位財とし、個人の福祉にあまり関係がなく、他
人と区別できるという意味において価値をもつ余分な財を地位財と考える。すると、地位財を消費
することは、非物質的な価値に対して予算を割くのであるから、より物質的である非地位財を消費
する場合よりも、その環境負荷は小さくなるだろう。具体的な例としては、高い付加価値を持つ財、
装飾品などが当てはまるだろう。もちろんこれは限定的な解釈であって、ここでは、同様の道具的価
値をもちながら、より環境に悪影響を与えるか、そうでないかを考察したいのであるから、違った解
釈が必要であろう。
Paavolaは、より現実的に、地位財を消費しようとするとき (status-seeking)、その行動は非地位
財を消費する場合よりも、環境に対しより悪い影響を与えるという仮定を取り入れた。つまり、消費
者が自身の消費能力をより高く見せようとするとき、物質的財をより多く消費すると仮定するので
ある。よって、Paavola [7]では単純化のため、ステータスのための消費はその道具的価値に対する
消費よりも、環境に対しより悪い影響をもたらすとする。
利己的厚生主義な合理的消費者が利得最大化行動を行う相互依存的消費者選択は、非協力ゲームに
よればよく分析できる。二人消費ゲームにおいて、利己的厚生主義の消費者が得る利得表を表 2.1に
表す。括弧の左側の数字は消費者 Aが得る利得であり、右が消費者 Bの得る利得である。このゲー
ムのナッシュ均衡は、それぞれが地位追求行動により、相手と自分を区別しようとすることである。
3Frank(1985) によってより詳細な定義がなされている。
30
表 2.1: 囚人のジレンマ
A/B Do not signaling Signaling
Do not signaling (3 , 3) (1 , 4)Signaling (4 , 1) (2 , 2)
二人ともが地位追求行動をとるこの均衡では、社会全体の利得はもっとも少なく、社会的厚生は最低
である。この結果は、地位追求行動とる場合がそうしない場合よりも環境に悪影響を与えるという仮
定から、環境の観点からももっとも望ましくない状態である。囚人のジレンマで仮定している双方が
コミュニケーションできない状態では、利己的厚生主義の消費者は、この状態を変えることはできな
い。この結果は社会に複数の経済主体の存在を許した場合でも変わらない。
利己的厚生主義の消費者の組は、互いに地位追求行動をとってしまうジレンマを解決するために
は、なにかしら協力して行動するしかないのである。とは言っても、協力して地位追求行動を制限す
る方法は次の意味で重要である。すなわち、たとえば地位財に対する課税は、他者と区別する行動を
望む消費者にとってその財をその意味でさらに価値あるものにしてしまい、結果、その消費を増加さ
せてしまうかもしれない。所得に対する税にあっては、消費者の消費能力は制限できるが、地位追求
行動を制限できるとは限らない。所得課税政策における消費者の厚生と環境への影響は、政府が課税
による収入をどのように使ったかに依存するのである。ここでの議論によって、消費者選択が相互依
存的であるという認識を取り入れれば、皆が協力する社会的協調行動に頼るべきだという追加的な
根拠が生まれることが示された。
以上では、合理的選択モデルにおいて、社会に存在する人々が環境に対して関心を持っていたとし
ても、利己的厚生主義的信念しか持たないという仮定に基づいて分析した。では、人々の中に利己的
厚生主義以外の倫理的信念に基づく環境への選好を持っている人が存在する場合、または社会構成員
の全員がそうである場合はどうであろう。Paavolaは非協力二人ゲームを用いて、二つのケースにつ
いて分析し、さらに、N人ゲームを応用してその考察を行っている。二人ゲームの考察は N人ゲー
ムに含まれるため、ここでは N人ゲームを用いて、非厚生主義的倫理的信念に基づく環境への選好
31
図 2.1: N人ゲームの利得関数
がどのような含意を持つのか分析することとする。
何人かの消費者が厚生主義的倫理的信念に基づく環境への選好を持ち、また何人かが非厚生主義
的倫理的信念に基づく環境への選好を持つといった現実的な社会は、N人ゲームを応用することで
描写できる。通常行われる N人ゲームは、消費者が利己的厚生主義であるとした場合の分析である。
まず、その仮定によって社会的ジレンマと呼ばれる状況を描写する。社会的ジレンマは、二つの単純
な特徴を持つ。第一には、それぞれの経済主体は、ほかの主体がどのような行動をとっていようと
も、社会的に望ましくない行動をとることにより、協力的な行動をとる場合よりもさらに高い利得を
得る。第二には、すべての経済主体が協力する場合、すべてがそれをしない場合よりも、社会の全員
にとってよりよい状態となる (Dawes [2])4。これを表したものが図 2.1である。
社会の構成員すべてが、利己的厚生主義である場合には、すべての消費者にとって地位追求行動が
支配的な戦略となる。図 2.1で仮定している状況においては、地位追求行動をとらないための決定的
4N 人ジレンマゲームの数学的構造は、以下社会的ジレンマの不等式
D(m) > C(m + 1) (2.1)
D(0) < C(N) (2.2)
(m = [0, N − 1])
D(m) : m人の消費者が地位追求行動をとらない場合の、地位追求行動をとった人の利得C(m) : 自身を含むm人の消費者が地位追求行動をとらない場合の、地位追求行動をとらない消費者の利得ゲーム理論の文脈では、2.1で表される選択状況において、非協力行動つまり地位追求行動が支配戦略(dominating strategy)
である。
32
な結託が、消費者がk人以上でなされていない場合には、地位追求行動をとらない消費者の私的利
得がマイナスになってしまう。そして、そのような結託が消費者k人以上でなされている場合には、
それぞれが得る私的利得はプラスとなる。また、消費者の全員が地位追求行動をとらないとき、社会
にとってもっとも望ましい状態となるのである。では、消費者が利己的厚生主義でなく、非厚生主義
的信念に基づいて行動するときどのようなことが言えるだろうか。ある消費者が非厚生主義的信念
に基づく環境への選好を持つならば、その経済主体は、ほかの主体がどのような行動をとっていよう
とも、環境に優しい行動をとる(協力行動)をとることを選ぶ。なぜならば、環境に対する非厚生主
義的選好を持っている消費者は、自身の厚生または効用を減少させても、環境に優しい行動を選ぶこ
とができるからである。よって、社会的ジレンマの一つ目に挙げた条件は、非厚生主義的環境への関
心を持っている消費者に関しては当てはまらない。利己的厚生主義の消費者には協力行動をとる動機
がないのに対して、非厚生主義的倫理的信念を持つ消費者はその動機があるのである。
しかし、図 2.1で仮定している状況において、地位を追求しない行動が社会的厚生の観点から存続
可能であるためには、協力行動を取る人k人以上いなければならない。先進的な環境保護活動家は、
十分な協力者のいない状況において、致命的な損失を被らなければならないかもしれないのである。
これは明らかに持続可能な状態とはいえないだろう。環境に対して厚生主義的信念に基づく関心しか
保有していない消費者は、自身の厚生をマイナスにするような選択をとることはないために、先進的
環境保護活動家にはなれないし、k人以上の連合を作ることはできない。非厚生主義的信念を持つ消
費者は、反対にそうすることができるし、自身の厚生を犠牲にしてでさえも、環境に対するコミット
メントを形成することを望むのである。
ここでの重要な問題は、環境に対しコミットする非厚生主義の消費者は、地位を追求しない行動が
厚生主義的消費者にとってもある程度好ましいほどに多いのかということである。k人以上の環境に
対しコミットする非厚生主義の消費者いれば、利己的厚生主義の消費者にとって、地位を追及する
行動をとらなくても正の利得を得ることができる。したがって、その利己的厚生主義者も環境への
関心があれば、地位を追求しないかもしれない。しかしながら、環境に対しコミットする N(N <k
33
)人が地位を追求しない行動をとり、厚生主義の消費者 N(N > n− k)人が地位追求行動をとった場
合の社会状態は、全ての利己的厚生主義者が地位追求行動をとるために、社会のすべての構成員が地
位追求行動をとる場合の社会状態とは、環境の観点からさしたる違いがないといえるだろう。
以上の相互依存的状況における消費者選択分析からの Paavolaの考察は次のようなものである。持
続的消費選択には、環境にコミットメントを行う一定の大きさの消費者の集合が必要であり、そのよ
うな協調行動は環境の観点から社会的に重要である。であれば、社会で決定的な協調行動が行える
かどうか、また、行うかどうかを個人の行動に任せておいてよいのかという問題が生じるのである。
例としては、消費者による環境に悪影響を与える財の不買活動と政府によるそのような財の供給を
禁止する法律との対比が挙げられる。個々の消費者が道徳的に行動することは、その道徳的消費者を
満足するだろうが、社会的に行われる協調行動によって防げることのできる望ましくない結果のすべ
ては防ぐことはできないのである。
2.3 先行研究の結論
独立な消費者の合理的選択モデルでの分析によれば、環境に対する非厚生主義的倫理信念が社会
に普遍的に広がれば、私たちの消費はより持続的なものとなることが示された。しかしながら、実際
の社会のように人々が厚生主義的、非厚生主義的、非帰結主義的倫理的信念に基づく環境への関心を
持つ場合には、個人の行動に任せるよりも、協調的行動を構築すれば多くのメリットを享受できる。
それは主に、環境への関心が少ない人やまったく持たない人の、他者の環境保護的行動へのただ乗り
排除すること、そして、消費の選択肢の制限や消費能力を制限できるということある。さらに、より
低コストで消費構造や消費量を修正できるし、それによる費用と便益をより衡平に配分できること
も大きなメリットである。最後に、そういった社会的協調行動によれば、消費者はどのような道徳的
ジレンマにどのような頻度で直面しなければならないのか選ぶこともできるのである。
相互依存的状況での消費選択の分析によれば、社会の構成員すべてが非厚生主義的信念に基づく
34
環境への関心を保有していれば、私たちの消費がより持続的なものになるという追加的な根拠が得
られる。ここでの分析は、地位追求行動をとれば実際には消費者の厚生を減少させるという認識に
よって、社会的厚生と環境保護への関心は同様に扱うことができることを示している。そして重要な
ことは、環境の観点から望ましい結果を得るには、ある一定の大きさの地位を追求しない消費者の集
合が必要だということである。これを達成するには、規制や課税といった社会的協調行動がもっとも
望ましい。
環境に対して倫理的関心を保有する消費者の個人的行動に依存した状態は、非常に危険なもので
ある。これは、エリート主義の環境のサブマーケットや生活スタイルを生み出す危険性を内在する。
環境保護に対して深いコミットメントを示した消費者は、自身の厚生を犠牲にした消費行動を行うこ
とになる。地位追求を巡る議論においては、そういった消費者は狭義に理解される経済厚生を犠牲に
して、生活様式においてより高い価値を実現できうる。しかしながら、そのような消費行動は、自
身の厚生もしくは福祉を心配しなければならない人々とって実現可能なものではない。したがって、
一部の人々による環境保護的生活スタイルは、社会全体の消費構造を変革するほどには至らない。エ
リート主義を作り出すのでなく、より協力的な行動によって環境に優しい消費の選択肢が社会に広が
れば、そのコストは低減するし、利己的厚生主義的な消費者でさえ消費構造を変化させるようになり
うるのである。
この論文の中で Paavolaは、消費をより持続的な方向に変化させる潜在的戦略として、政府や自
治体による規制や課税といった社会的協調行動を主張している。社会の選択肢に対する公共的介入と
しての共同行動は、たしかに魅力的な特徴を持つ。しかし、それを潜在的として言及しているのは、
そのような介入は消費者の個人的行動に任せて、自動的には達成できないからなのである。そして、
最後に指摘するのは、このような問題は厚生主義的倫理的信念以外の信念を経済主体に許した場合
に、より複雑な問題となるということである。
35
第3章 持続可能な消費の実現
第 2章では、環境に対する倫理的関心が消費者選択に与える影響を考察した先行研究 [7]を概観した。
その主要な論点は次のようなものであろう。第一に、環境への倫理的関心は、人々の異なる行動原理
によって消費行動に反映されることである。具体的には、そのような関心は人々の異なる倫理的信
念、利己的厚生主義、非厚生主義的帰結主義、非帰結主義などを基礎として存在するという洞察であ
る。第二に、利己的厚生主義者以外の人々は、自身の経済的厚生を犠牲にして環境に優しい消費行動
を行うことができるということである。つまり、利己的厚生主義者は自身の利害に密接に関わる選好
に基づく選択行動しかとらないないのに対して、それ以外の消費者はそうではなく、個人の倫理観を
反映して広い意味での合理的な行動をとるのである。そして、第三に、消費の社会的側面を捉える
試みである。つまり、財の物質的外部性を無視して、財自身が持つ物質的でない、社会的側面からの
影響によって消費者の相互依存的状況が生じる状況の分析である。本章では、Paavola [7]の上述の
いくつかの重要な示唆を受け入れるとともに、批判的考察を行う。その上で、その理論的補強ととも
に、環境に対する倫理観が消費者選択に果たす役割の新しい含意を示すことを目的とする。
本稿では、消費選択の結果として環境財の消費が行われる状況を仮定する。そこで、環境問題を
引き起こす引き金は特定の環境財の集中的消費であると捉えて、消費者が消費選択可能な環境財を
持続可能財と非持続可能財に分類する。この分類によれば、非持続可能財は、持続可能財と比べて、
環境財の非利用価値は相対的に大きくなる。また、非利用価値を選択判断に組み込むメカニズムとし
て、A.Senが導入した共感とコミットメントを用いて、厚生情報にしか反応しない厚生主義的消費者
と非厚生情報にも反応する非厚生主義的消費者を区別する。この区別によれば、環境に対する異な
る倫理観が環境財評価に与える影響を考察することができる。そして、上記の予備的考察のもとで、
37
まず、独立な合理的消費者モデルにおいて、独立な消費者の環境財の持続可能性に関する行動を分析
する。次に、Paavolaが用いた、相互依存的状況での合理的消費者モデルにおいて、社会相互依存関
係の中にある消費者の環境財の持続可能性に関する行動を分析する。また、これらの分析のなかで、
倫理観を消費者選択に導入した場合の持続可能な消費を明確に示す。
3.1 非厚生主義的アプローチ
本稿の主要な目的は、消費者の環境に対する倫理観が持続可能性に果たす役割を考察するととも
に、消費者が環境財を巡る選択状況におかれたときの、その選択の結果の持続可能性を示すことであ
る。Paavola [7]は、環境への関心を持つ利己的厚生主義者と非厚生主義者を定義し、非厚生主義者
は選択行動から得られる自身の厚生上昇を犠牲にして環境保全を行うことができるために、より持
続可能な消費を選択可能であるとした。これによれば、環境に対する異なる倫理的関心が、持続的な
消費に与える影響は示すことはできる。しかしながら、これでは倫理観の持続可能性への影響は示せ
ても、倫理観の果たす役割は未だ不明確なままである。つまり、人々が環境問題につながる消費で問
題となる財を選択する状況に直面したとき、倫理観がその財の価値の認識に与える影響を分析する
ことはできないし、消費選択の帰結と倫理観のつながりを示すこともできない。消費選択の結果の持
続可能性を論じるには、持続可能性で問題となる選択の対象を特定することが必要である。つまり、
財の特徴の定義である。これにより、その財の消費において倫理観の果たす役割を明確に示すことが
できるし、選択の結果の持続可能性をより具体的に示して説得力を高めることもできる。
3.1.1 持続可能財と非持続可能財
Paavola [7]は、利己的厚生主義者と非利己的厚生主義者では、環境に対する倫理的関心が選択行
動に与える影響が異なる、また、非利己的厚生主義者は持続可能な消費を行う選択をすることができ
ることを示した。ただし、実はここでの持続可能な消費とは、ただ環境に優しい消費1 を行うという1environmentally friendly consumption or consumption which has less adverse environmental effects
38
意味での持続可能性を述べており、実はそれ以上の意味はないのである。これは、消費選択の対象と
なる消費行動、つまりは、消費される財が定義されていないことから生じる問題である。そこでま
ず、持続可能な消費とは何か再考する必要が生じる。
地球温暖化、自然資源の浪費や生物多様性の危機などの環境問題は、一般に環境財の過剰消費に
よって生じる。つまり、特定の環境財が過剰に消費されていることが認識され、それによって、人々
がなんらかの被害を受けるようになったときに、その状態を環境問題が生じているというのである2。
特定の環境財が過剰に消費されていることが人々に認識されたなら、消費者はどのような行動をとる
だろうか。消費者は、類似の利用価値を見出せる代替的な環境財の利用へとシフトするだろう。例え
ば、発電方法を石油・石炭火力発電から原子力発電に切り替えるのは、自然にあるべき状態を二酸化
炭素によって消費する状態から、放射性物質の廃棄によって消費する状態へ移行したと考えること
ができる。このような選択は持続可能な消費のための選択と言えるのではないだろうか。私たちは、
その環境財が再生可能資源であれば、その再生可能な量を超える消費を行いたいとき同様の利用価
値のある代替的な環境財を用いるし、その環境財が枯渇性資源であれば、その財が枯渇に近づいたと
き同様の利用価値のある代替的な環境財の利用に移行する。つまり、環境問題を引き起こす引き金と
は、特定の環境財の集中的な消費であり、持続可能な消費とは、特定の環境財を集中的に消費しない
ことを究極的に意味しているのである。
ここで、消費者が特定の環境財の選択状況に直面したときの代替的な選択肢をつぎのように定義
することが、消費の持続可能性を表す上で有用であろう。一つ目の選択肢は、非持続可能財の消費で
ある。非持続可能財とは、その環境財が枯渇しかけている、もしくは、地理的条件や生態系の条件か
ら、その存在自体に価値を認めることが社会的に認知されているような環境財である。二つ目の選択
肢は、持続可能財の消費である。人間の使用量に対して自然に存在する量が豊富であり、その環境財
が枯渇することをほとんど、またはまったく誰も認知していないような環境財を持続可能財と呼ぶ。
非持続可能財と持続可能財の概念図を表したものが図 3.1である。より非持続可能な財とは、ほかの
2自然環境の存在量とその自然に備わった浄化能力に比べて、人間の生産、消費活動における環境資源利用の量が微少であったときは認識されなかった自然本来の有用性(つまり本来の利用価値)が、利用量の増加とともに交換価値として自己主張し始めた状態。これを環境問題と認識する [10]。
39
図 3.1: 非持続可能財と持続可能財の概念図
より持続可能な財との対比において、非利用価値に対する利用価値が小さい環境財である。より持続
可能な財とは、より非持続可能な財との対比において、非利用価値に対して利用価値が大きい環境財
である。消費者は、同種の利用価値をもつ環境財消費の伴う選択状況において、ある予算制約の下で
二つの選択肢のうち一つを選択するのである。このような仮定を前提とすれば、ある消費者が非持続
可能財に対して持続可能財を選べば、その消費者はより持続可能な消費を行っていると言えるので
ある。
持続可能財と非持続可能財は同種の利用価値を持つというここでの仮定は、消費者が特定の目的
のために環境財を消費するとき、いくつかの代替案の中から持続可能な消費の選択肢をとるのかど
うかを明らかにするためである。選択の結果として持続可能財を消費する場合、持続可能財は定義に
より、枯渇することを誰もが認識してはいない。つまり、自由財のような状態である。したがって、
この財を消費することの価値は、その持続可能財の利用価値のみを反映するのである。対して、非
持続可能財は、枯渇もしくは失われつつあることが社会的に認知されているような環境財であるた
めに、この財を消費することの価値は、その非持続可能財の利用価値のみでなく、非利用価値も反映
するのである。ここで、上の仮定によって環境財の利用価値は同種である。これが想定する状況は、
これまで特定の環境財を消費してきた社会において、より非持続可能な消費を行ってきた消費者がい
つの時点で代替的な持続可能財に消費を変更するかといった状況である。環境財の非利用価値が市場
40
での価格に反映されないときには、消費者はそれが持続可能財であろうと非持続可能財であろうと、
その利用価値からどれだけの経済的利益をえられるかを問題にする。このとき代替的な持続可能財
の利用価値から得られる厚生の上昇が、これまで集中的に消費してきた環境財の利用価値から得ら
れる厚生の上昇よりも大きくならない限り、代替的な持続可能財の消費には切り替えない。つまり、
これまで集中的に消費されてきた環境財と代替的な持続可能財の利用価値から期待される厚生上昇
が同値になるとき、代替的な持続可能財の消費に切り替わりはじめるのである。しかしながら、この
ように利用価値のみが市場で認識されて行われる資源配分の結果、上で述べたように、自然によって
のみ供給されないという環境財の特性が反映されないために、環境財が過剰に消費され、持続的でな
い消費が行われるのである。
環境財を持続可能財と非持続可能財とに分類したことで、持続的な消費をもたらす資源配分には、
環境財の非利用価値が認識される必要があることの可能性が明らかになった。伝統的経済学の枠組
みでは、人々はより自身の選好の満足度の高い財を選択する。それによれば、選択判断では人々の
倫理観は問題でなく、人々が環境財の非利用価値を何らかの形で認識した上で消費選択を行っても、
それは単に消費者の選好を満足するからであると説明される。しかしながら、これでは環境財の消費
を伴う消費選択で、持続的な消費をもたらす資源配分が実現されるために、環境に対する倫理観が果
たす役割は分析できない。そこで、環境に対する倫理観は、利用価値には影響せず、非利用価値の価
値判断で一定の役割を果たすとする考え方をとり、ある選択状況において環境財の非利用価値が選択
判断に組み込まれるメカニズムとして、共感とコミットメントを挙げることにする。これらが選択判
断に影響することを仮定すれば、伝統的経済学のように、消費者の倫理観の役割を捨象する必要はな
いし、むしろ、持続可能性を論じるこの論脈での、倫理観の役割を明らかにすることができるので
ある。
41
3.1.2 共感とコミットメント
先行研究 (Paavola [7])では、利己的厚生主義とそれ以外の倫理的信念を保有する個人を定義する
ことで、環境への倫理的関心の消費者選択への影響を分析する。ここでは、利己的厚生主義者の環境
への関心は、経済主体のもともとの選好の一部であると考えている。つまり、利己的厚生主義者が環
境に優しい製品を購入するのは、ただ、その人の効用が上昇するからという理由であって、それは、
ほかの倫理的信念を持つ消費者が、環境に優しい製品を購入する場合とは異なると考えているので
ある。しかし、この枠組みでは、厚生主義者が自然環境、もしくは、無差別な将来の世代に対する共
感3のために環境を害する消費をしないことに価値を認めることの可能性については論じていない。
したがって、環境を利用しないことの価値が消費者選択に組み込まれることを把握するためには不十
分である。
環境財を巡る消費選択行動においては、消費者は、提供される財を利用することによる自身の利益
もさることながら、環境財を利用しないことの価値を考慮して、どのような消費を行うか選択するこ
とになる。つまり、消費者が判断する選択肢ごとの価値は、その選択の結果環境財が消費されるので
あれば、消費される環境財の利用価値と非利用価値に必然的に対応するのである。そして、この非利
用価値は、利用価値がそうするようには人々の行動に影響を与えることができない (Hausman [4])。
なぜなら、非利用価値は、その環境財を保存することの総価値を考慮した利用価値を補う概念であっ
て、その環境財を利用しないように消費者の行動を抑制する働きをするからである。つまり、利己的
厚生主義者は、環境財の利用価値をそれが自身の厚生上昇に寄与するがゆえに評価するが、環境財の
非利用価値はその人が利己的であるがゆえに評価しない。しかし、社会の構成員が利己的でなく、環
境に対する倫理観を持っている場合、環境財の利用価値は人々の厚生に寄与するがゆえに評価される
としても、非利用価値はその人が倫理観を持つゆえに評価されるのである。非利用価値はまさしく、
多様な倫理観を通して消費者の選択行動に影響を与えるのである4。
そこで、消費者の選択判断に環境財の非利用価値が組み込まれるメカニズムとして、共感とコミッ
3つまりそうすることによる効用の上昇を期待していること4補足として、第 1 章 3 項を参照
42
トメントを考えるのである。これは、非利用価値を消費者選択に影響を与えるための、多様な倫理観
を大きく二つに分けることを意味する。一つは、厚生主義的倫理観であり、この場合には非利用価値
が共感を通して、消費者の厚生に影響を与えるために消費者選択に影響を与える場合である。もう
一つは、非厚生主義的倫理観であり、この場合には自身の厚生が上昇するからという理由ではなく、
環境へ影響を与えるのが望ましくないから、といった非厚生情報に基づくコミットメントによって、
消費者選択に影響を与える場合である。このように、環境に対する倫理観は、厚生主義的倫理観と非
厚生主義的倫理観とに分けることができ、それぞれの倫理観が環境財の消費に与える影響が分析可
能になる。
3.2 モデル
ここでは、ミクロ経済学の枠組みにおける、合理的消費者モデルを用いて、その消費行動を分析す
る。ここでの合理的消費者とは、異なる倫理的信念によって認める消費者自身の価値を常に最大にす
る消費者である。この消費者は一定の予算制約の下で、環境財の消費を伴う行動を選択することがで
きる。消費者の行動によって環境財は消費されるが、その環境財は、持続可能財もしくは非持続可能
財である。また、人々の環境に対する倫理観を、厚生主義的倫理観と非厚生主義的倫理観の二つに分
類する。人々は、環境財の消費に関わる消費者選択において、環境財を消費することによって生じる
価値 (利用価値)と環境財を消費しないことの価値 (非利用価値)を考慮する。そして、非利用価値が
消費選択行動の動機となるには、消費者が環境に対して何らかの倫理観を保持していなければなら
ない。
3.2.1 環境財の消費を伴う消費者選択
資源配分について言及するとき、それらは市場機構を用いる方法に大きく影響されている。それは
すまわち、ミクロ経済学で伝統的に重視されてきた競争的価格メカニズムであり、重大な経済的問
43
題に取り組む上で重視されてきた。つまり、消費者選択においても、競争的価格メカニズムが消費者
同士の資源配分を調整して、最適な資源配分を達成できる。対して、公共財が問題になる場合には、
公共財が持つ消費の排除不可能性と消費の集合性という特性のために、自由な競争に任せていては
消費者にとっての最適な資源配分は達成されない。公共財は、多数の人々に同量の外部効果を同時に
引き起こすと考えられるからである。しかし、その場合には政府や自治体などの公共部門が課税や規
制といった介入により、外部効果に対する個別的費用を調整することで、消費者にとっての資源配分
がある程度望ましい形では達成される。
では、地球温暖化やそれに伴う気候変動、資源の浪費、そして生物多様性の危機など様々な環境問
題に関する議論においてはどうであろうか。上述の環境問題は、主に環境財と言われる財を消費する
ことの帰結として生じるものである。環境財をただ公共財の性質を持つ財として捉えれば、消費者に
とっての環境財の最適な資源配分は、公共部門の役割によってある程度解決されるか、環境問題と
して問題視されて少なくとも現在のような喫緊の課題となる以前に解決されるのでないだろうか (細
田 [6])。それは、環境財の市場が実際には存在しないから、もしくは市場を作り出すことが困難であ
るからという理由があったとしても、主張できるはずである。
しかしながら、環境財には公共財としての性質のほかに、自然によってしか供給されないという特
別な性質を有している。これが示唆するのは、環境財を巡る資源配分で考慮しなくてはいけないこと
は、消費者にとっての資源配分だけではなく消費者と自然環境の資源配分だということではなかろう
か。つまり、消費者は環境財を消費する消費選択において、自身の主観的・経済的利害を反映する選
好のみを満たす行動をとるべきでなく、自然環境の価値を反映する社会的観点からの選好をも反映す
るべきなのである。
一部の人々が消費者選択もしくは環境財を巡る価値評価において、自然環境側からみた環境の価値
を自身の行動に影響を与える判断基準として評価していることは、環境経済学の分野での環境評価の
実証分析等で明らかにされている (Hausman [4])。環境経済学の分野で著名な仮想評価(contingent
valuation)の手法(CVM)では、ある環境財の存在についての価値評価が問題となる場合がある。
44
その環境財とは、消費者にとって直接的な使用価値を持つものでなく、ただ、その環境財がなくなる
もしくは消費されるよりも、保存されることが好ましいからという理由で価値を持つものである。環
境経済学では、このような環境財の価値を非利用価値と呼んで、環境財の利用価値と区別する5。そ
して、この非利用価値こそが、社会が認める自然環境側からみた環境の価値であり、消費者の主観的
選好と密接なつながりが予測される環境の利用価値を補完する価値なのである。CVMでは、仮想的
状況における人々の環境財への価値判断を推定するために、実際の消費者選択において、人々がどの
程度環境財の非利用価値を評価しているのか測定することは困難である。しかしながら、消費者が環
境財の非利用価値をその選択判断基準として用いることについては、異論は少ないだろう。
消費者が環境財の消費を伴う選択を行うとき、消費者は環境財を消費することによって得られる
価値 (利用価値)と失われる価値 (非利用価値)を考慮して価値判断を行う。持続可能財が消費される
選択肢においては、その非利用価値は認識されないか、相対的に小さい。したがって、利用価値の
非利用価値に対する比率は大きい。対して、非持続可能財が消費されるような選択肢の価値は、そ
の非利用価値は大きいく、認識される。したがって、利用価値の非利用価値に対する比率は小さい。
ここで、消費者が非持続可能財の消費を伴う選択肢に対して利用価値しか認めていない場合、その消
費者にとって持続可能財の利用価値から得られる厚生上昇が、非持続可能財のそれと同じか、より大
きくなるときに、消費者は持続可能財の消費を選択することになる。しかしながら、この状態では、
すでに環境財の非利用価値は過少にしか保存されず、持続的な消費を行っているとはいえない。
人々が各々の倫理観によって共感もしくはコミットメントを用いる選択判断を行うときはどうであ
ろうか。このとき、人々は非利用価値を厚生情報もしくは非厚生情報として、共感かコミットメン
トによって選択判断に影響を与えることができる。その消費者にとって、持続可能財の利用価値に
認める価値が、非持続可能財の利用価値に認める価値から非利用価値の共感・コミットメントによっ
て認める価値を引いた価値と同じか、より大きくなるときに消費者は持続可能財の消費を選択する。
ここでは、環境財の非利用価値が消費者選択に反映されていると言うことができ、非利用価値が反映
5第一章三項参照。
45
されていない場合に比べて持続的な消費が行われていると言えるのである。
3.2.2 独立な状況での消費者選択モデル
個人の倫理観が、環境財の持続可能な消費にどのような役割を果たすのか示すために、まず、個人
が独立な状況であり、消費に伴う外部性が存在しないという、単純な合理的消費者のモデルを用いて
分析する。通常の合理的選択のモデルでは、消費者は自身の効用に注目して、直面する選択肢と予算
制約の下で、効用最大化行動をとる。また、ここでは、消費者は直面する選択肢に関する完全な情報
を持つことを仮定する。
伝統的経済学における効用とは、第 1章、第 2章で述べたように、それがなにであろうと個人の選
好の満足度を表すものとして、取り扱われている。このように効用を取り扱うことは、人々が異なる
倫理観によって行動した結果でも、それはただ個人の選好判断によって行われる結果であるとして考
えることと同じである。ある消費者が倫理観から環境問題に対応した商品を購入するとき、それは効
用最大化行動の結果である。そして、ほかの消費者が環境問題を認識しているが、自身がほかの人よ
りも費用を負担するのを嫌がって、環境負荷のある商品を購入するとき、それは効用最大化行動の結
果である。さらに、一部の消費者が環境問題を認識しており、社会的な立場から環境に対応した商品
を購入することで社会的な立場を守ることができるとき、それも効用最大化行動の結果なのである。
このような正統派理論の慣行は、個人の異なる倫理観にその正当な位置を承認しない極端の立場で
あり、倫理観が人々の経済活動において果たす役割についての分析を意識的に行わない過ちに陥って
いるのである6。
私は、環境財の消費を伴う消費者行動において、ひとびとの異なる倫理観の役割を考察したい。し
たがって、人々が上で述べたような定義の効用を最大化するという前提では、十分な議論はできな
い。この問題に対応するための Paavola [7]の提案は、利己的厚生主義者が最大化の対象とする効用
として、経済的利害に直結した狭義の効用を定義して、その他の非厚生主義的倫理観を持つ消費者の
6詳細は鈴村・後藤 [12]、Harsanyi [5]
46
最大化の対象と区別することである。Paavolaが言う利己的厚生主義者も、環境への関心を持つこと
ができる。そのような消費者はそれぞれ自家用車を利用するよりも公共交通機関を利用することを
望むこともあるのである。しかし、それはその消費者が、その選択肢を選ぶことによって厚生を改善
すると信じるからである。ここでの消費者は自身の厚生を犠牲にするような環境保護は行わないの
である。このように効用を再定義することによっては、利己的厚生主義者が自然環境に対して共感す
るために環境保護を行う場合も、ただ自身の主観的選好を満足する選択として判断される。しかしな
がら、自然環境への共感は人々の環境に対する倫理観をから生じるものである。したがって、このよ
うな定義では利己的厚生主義者が持つ環境への倫理観の役割は考察できない。そこでまず、環境に
対して一切の倫理観を持たない消費者が選択状況において最大化の対象とするのは、個人の主観的・
経済的利害に直結した利己的な効用であるとして分析を行う。
環境に対して一切の倫理的関心を持たない利己的厚生主義者は、主観的かつ利己的な選好に基づ
いて選択判断を行う。このような消費者は、消費選択において環境財の利用価値のみしかその選択判
断の基準としない。また、このような消費者が持続可能財もしくは非持続可能財が消費される選択肢
のどちらかを選択しなければならない状況を考える。
ここでの独立な消費者の消費選択の対象において、全てが持続可能財である場合は、利己的消費者
に環境に対する倫理観があるかないかは関係がないために、伝統的経済学が想定する消費者分析と
同等である。しかし、これではその消費が持続可能であるかどうか論じることはできない。さらに、
社会においては、環境財からより効率よく、高い厚生の改善を得るために、特定の環境財に消費が集
中することは十分考えられる。このように、特定の持続可能財もその集中的消費によって、非持続可
能財となり、環境問題として顕在化するのである。しかしながら、環境に対し一切の倫理的関心を持
たない利己的厚生主義者は、環境財が持続可能財から非持続可能財へと変わってしまったときでも、
その非利用価値を判断基準としないためにその非持続可能財を消費し続ける。非持続可能財の消費
は、その消費者にとって持続可能財の利用価値から得られる厚生上昇が、非持続可能財のそれと同じ
か、より大きくなるときまで続くのである。このようなとき、消費選択において、環境財の非利用価
47
値が一切反映されていないために、実際には非利用価値が存在する環境財について、結果として人々
は環境問題が生じていると判断するのである。
しかしながら第 3章 2節 1項で述べたように、実際には人々は全ての選択状況において非利用価
値を考慮しないということはない。それは、人々が環境保護に対して支払う、もしくは受け入れる意
思のある価格を CVMで評価した場合でも明らかだし (Hausman [4])、人々は生態系を保護する配慮
をおこなった商品や、環境対応自動車など、人々は環境に優しい選択肢を自発的な費用搬出のもとで
選択することもあるのである。そこでは、なんらかの環境への倫理観によって、環境財の非利用価値
が人々の選択判断に影響を与えているのである。
そこで次に、消費者が環境財の消費を伴う選択肢において、環境財の非利用価値を選択判断に組み
込む倫理観を持つ場合を仮定する。Paavola [7]での、環境への関心を持つ利己的厚生主義者におい
ては、環境財の非利用価値は、共感を通して個人の厚生に影響する限り、その選択肢の価値判断に影
響する。ここでは、消費者は環境財の非利用価値を自身に関する厚生情報として認識している。対し
て、非利用価値を非厚生情報として認識して、自身の選択判断に影響させる場合もある。このような
環境に対する倫理観を持つ消費者は非厚生主義者である。つまり、環境に対する倫理観は、厚生主義
的倫理観と非厚生主義的倫理観として存在し、それぞれ共感とコミットメントという形で環境財の非
利用価値を選択判断に組み込ませる役割をもつとするのである。
環境に対する倫理観を持つ独立な利己的厚生主義者が、持続可能財と非持続可能財の消費を巡る
消費者選択に直面したとき、そのような消費者はどのような消費を行うだろうか。消費選択の対象が
全て持続可能財であるときは、環境への倫理観は選択判断において影響しない。持続可能財であった
特定の環境財が、代替的な持続可能財との比較において非持続可能財へと変化するとき、消費者は共
感によって、環境財の非利用価値を認識するようになるのである。このときにも、確かに人々は特定
の環境財の集中的消費を行う。しかし特定の環境財の消費は、その消費者にとって持続可能財の利用
価値に認める価値が、非持続可能財の利用価値に認める価値から非利用価値の共感によって認める
価値を引いた価値と同じか、より大きくなるときまでである。結果として利己的厚生主義者が持続
48
可能財を選択したとき、その消費者は、持続可能財の利用価値と非持続可能財の利用価値と非利用
価値の厚生情報を考慮し、持続可能財の消費が、もっとも自身の厚生上昇に寄与すると考えている。
しかしながら、ここでは環境財の非利用価値が消費者選択に反映されていると言うことができ、非利
用価値が反映されていない場合に比べて、持続的な消費が行われているといえるのである。
共感によって、環境財の非利用価値が選択判断に組み込まれる場合を考えると、人々の厚生は最大
化され、その意味で資源配分は最適である。また、このときには環境財の持続可能性もある程度担保
されるのである。伝統的経済学で考える合理的な消費者が環境への倫理的な関心を持つとは、そのよ
うな個人が環境に対して共感することの可能性を含めて考えて、また、それ以外の可能性を排除して
考えている状況を指すのである。しかしながら、環境への倫理的な関心はそのような利己的厚生主義
者のみが持ちうるものではない。上で言及したように、コミットメントは利己的厚生主義者の選択判
断にはなりえない。なぜなら、コミットメントの定義から7、それは環境財の非利用価値を非厚生情
報として認識した場合に対応するからである。
したがって、次に環境に対する倫理観を持つ非厚生主義者が、持続可能財と非持続可能財の消費を
巡る消費者選択に直面した状況を分析する。上の議論と同様に、消費選択の対象が全て持続可能財で
あるときは、環境への倫理観は選択判断において影響しない。持続可能財であった特定の環境財が、
代替的持続可能財との比較において非持続可能財へと変化するとき、消費者は共感とコミットメント
によって環境財の非利用価値を認識するようになるのである。共感によっても非利用価値を認識する
のは、非厚生主義者が非利用価値の非厚生情報のみを判断基準とするのでなく、厚生情報も判断基
準とする可能性を考慮してのものである。このような消費者が、環境に対しての倫理観から、持続
的でない消費行動をしないという強いコミットメントを持つならば、特定の環境財の集中的消費は
行われないか、集中的消費による環境問題が生じる前に、持続可能財の消費へと消費行動を変化さ
せる。代替的な持続可能財の非利用価値に比べて非持続可能財の非利用価値少しでも大きくなると、
そのような人々は瞬時にこれまでの消費を改め、代替的な持続可能財の消費に切り替えるのである。
7詳細は第 1 章 3 節 2 項と、第 3 章 1 節 2 項を参照
49
このように、環境に対する倫理観を持つ非厚生主義者は、環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義
者よりも、持続的な消費を行えるのである。
利己的厚生主義者が環境に対して共感を持つことで、共感を持たない場合に比べて持続可能財の
消費に多くの予算を割くとき、それはその消費者の厚生に寄与することであるために、問題はない。
環境への共感の度合いが異なる多数の利己的厚生主義者が存在したとしても、彼らが合理的選択を
行うとき、社会の厚生は最大化されるためにその意味では問題はないのである。しかしながら、利己
的厚生主義者と非厚生主義者を比較した場合はどうだろうか。非厚生主義者は、利己的厚生主義者が
するようには厚生を最大化させているとはいえない。非厚生主義者が最大化するのは、環境財の利用
価値と非利用価値の厚生情報と非厚生情報を考慮したものなのである。
環境の非利用価値は、利己的厚生主義者よりも非利己的厚生主義者において、より正しく認識され
ているというべきである。利己的厚生主義者は自身の厚生に関係する範囲でのみ非利用価値を認識
するのに対して、非厚生主義者は厚生情報に限定されない。環境に対する倫理観を持つ非厚生主義者
が社会に多数存在すれば、その社会では持続的な消費が行われる可能性が高い。しかし、環境に一切
の倫理観を持たない利己的厚生主義者よりは、環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義者のほう
が、持続的な消費を行うことができるのである。
通常の社会では、人々がいろいろな価値観・倫理観を持ち、利己的厚生主義者でも非厚生主義者も
存在するだろう。そのような社会で環境問題を生じさせる消費者選択において、個人に任せた行動に
頼るのは厚生の配分の意味で、社会的に望ましくない。なぜなら、利己的厚生主義者は非厚生主義者
の持続的な消費にただ乗りすることになるからである。非厚生主義者は、その倫理観から環境の非利
用価値に対して大きな価値を認めるが、利己的厚生主義者は、その分非利用価値に対して価値を認め
る必要がなくなるのである。このような状況では、政府、自治体、NPOなど、消費行動を行う主体
以外が社会に認められている環境財の非利用価値を代弁し、消費税や所得税、規制など経済的手法を
駆使することで、個人の行動に任せるよりも、社会的に低いコストでより持続可能な消費を実現で
きる。
50
Paavola [7]は、利己的厚生主義者が多数いる場合には、タバコや麻薬といった福祉は減少させるが
厚生は増加させると考えられる選択肢を排除するには、社会的協調行動を用いるしかないと述べる。
これに加えて、環境財の消費者選択での議論では、持続可能性を損なうが厚生は増加させると考えら
れる選択肢である非持続可能財の消費を排除するにも、社会的協調行動を用いるしかないのである。
これまでは、合理的消費者が独立に消費選択を行う状況を分析してきた。その分析では、環境財の
非利用価値が非排除性と集合性という性質を持つことから、政府、自治体や NPOなどを媒介とした
社会的協調行動が必要とされるという考察も行った。以下では、環境財の非利用価値が非排除性と集
合性を持つことに起因する相互依存的状況とは少し性格のことなる状況を仮定して、合理的消費者
が社会的相互依存関係にあるとき、これまでの議論をどのように補完することができるかを考察す
ることとする。
3.2.3 相互依存的状況での消費者選択モデル
合理的消費者が社会的相互依存関係にあるとはどのような状況をさすのだろうか。この節では、
Paavola [7]が紹介した相互依存関係の捉え方を簡単に概観し、環境財の非利用価値が非排除性と集
合性を持つことに起因する相互依存的状況とは性格の異なる状況を分析することの必要性を明らか
にする。そして、Paavolaの分析方法によれば、消費者の社会的相互依存関係が持続可能財と非持続
可能財の消費の選択状況がどのように分析されるのかを示して考察を行う。
消費者の選択や厚生が、ほかの消費者と影響しあう状況は、普通、バンドワゴン効果、スノッブ効
果、ヴェブレン効果によって説明できる。このように、ある人の消費がほかの個人の厚生に影響を与
えるような効果は、消費の外部性や地位に関する外部性と呼ばれる。この外部性が生じている状態で
ある相互依存的な消費者選択は、Becker [1]によれば、経済主体がその効用関数に他者の決定に関す
る情報をふくむためである。しかしながら、このように相互依存性を捉えれば、そこでの個人対個人
の関係は、各個人が他者の選択をどのように評価するかで捉えられることになる。それによれば、各
個人が他者に影響されながら選択を行うことの説明をすることはできる。これはまさに、各個人が環
51
境財の非利用価値に関する他者の決定に影響されながら選択を行う場合と対応し、これによって各消
費者が他者の影響の下でどのような行動をとるのか説明できるのである。しかしながら、Paavola [7]
は、これでは消費者選択の社会的側面を捉えたことにはならないと述べるのである。ここで言う社会
的側面とは、第 3章 2節 2項の最後で言及したような、各消費者が他者の決定に関する情報を評価
することから生じる相互依存関係とは異なるのである。そこで次に、それを補完する社会的相互依存
関係にある状況での消費者分析を行う。以下ではまず、分析のための概念を示すこととする。
Paavola [7]によれば、社会的相互依存関係はある特定の財が持つ特性によって生じる。つまり、消
費した財そのものが外部性を持つと考えるのである。ある特定の財は、その財を消費した消費者のス
テータスや富についての情報を社会に放つために、他者の選択や厚生に影響を与えるのである。この
ように考えれば、各消費者が他者の決定に関する情報を評価するといった状況を考える必要はなく、
各消費者は、消費者選択の社会的側面によって、相互依存的な状況にあると考えることができる。ま
た、これは各個人が環境財の非利用価値に関する他者の決定に影響されながら選択を行う場合とは
矛盾しない。社会的相互依存関係がある特定の財の特性によって生じるとする状況は、各個人が他者
決定の情報を評価して、それに影響される状況を補完するものと考えることができるのである。
この社会的相互依存関係を分析するためにまず、選択の対象となる財を、特定の性質ごとに分類す
る必要がある。ここでは対象となる財を二つに分類できる。一つは、地位財 (positional goods)であ
り、この財は、消費者のステータスについての情報を他者に伝達する能力を持つ。つまり、選択に関
する情報を消費者選択肢に反映させ、選択肢を巡る社会的状況を変化させるのである。もう一つは、
非地位財 (nonpositional goods)であり、消費者がこの財を消費しても、ステータスについての情報
は他者に伝達されないか、その情報は他者にとって意味のないものである。
ここで環境財も地位財か非地位財のどちらに分類することができる。社会的側面を無視した独立
な消費者選択であれば、その分類に関係なく第 3章 2節 2項の議論は成り立つ。環境財消費の社会
的側面を捉えるときに、消費される環境財を地位財、非地位財に分類することが有用なのである。環
境財のうち、自然環境に存在する量が希少であるような希少金属や絶滅が危惧される動植物、もしく
52
はグランドキャニオンのように自然に唯一なものは、社会的側面を持つと考えられる。それらの社会
的側面とは、そのような希少で珍しい環境財は、現実の利用価値や非利用価値とは別に、社会的な価
値が与えられていると考えることができるのである。それは、そのような環境財を消費・利用するこ
とが、自身の社会的ステータスを表すからである。利己的厚生主義的観点から言えば、それらの利用
価値から得られる厚生は、分離は難しいが、地位財の利用価値から得られる厚生よりも大きいので
ある。このように社会的側面を持つ環境財の多くは持続可能財であると考えられるが、その影響は
正と負のどちらもとり得る。これまでの集中的な消費により、ほかの代替的な持続可能財よりも効
率的な利用が実現されているような非持続可能財においては、その社会的側面から代替的な持続可
能財への転換を促されるかもしれない。例えば、火力発電と原子力発電を対比させると、それらは
それぞれ、正常な環境を二酸化炭素か核廃棄物で消費している。このときに火力発電による正常な
環境の消費は、社会的に負の側面を持つだろう。ある消費者が火力発電による電力供給を望むとき、
その消費者はその消費選択によって、自身のステータスが低いことが社会に露見してしまうかもしれ
ないのである8。
ここでは、環境財の消費において、社会的側面が持続可能性に与える影響を分析する。そして、環
境問題を論じる上で重要なのは、消費者が社会的相互依存関係にあるとき、消費者が持続的でない消
費をとってしまう特定の消費者選択である。したがって、以下の社会的依存関係の分析では、消費者
は非地位財である持続可能財を消費するか、地位財であって選択者に社会的な正の影響を与えるよう
な非持続可能財を消費するかを選択する状況を仮定する。また、ここで仮定する状況では、社会的相
互依存関係が消費者選択に与える影響を分析したい。したがって、社会的相互依存関係を考えない
ときの、環境に関心のない利己的厚生主義者が代替的選択肢から得られる厚生改善は同値であると
する。
環境に対して一切の倫理的関心を持たない利己的厚生主義者が、相互依存的状況のなかで効用最
大化行動を行う場合には、非協力二人ゲームが有用である。このような二人消費ゲームにおいて、消
8もしかしたら、人々が特定の環境財を集中的に消費したことでそれが非持続可能財となった場合には、その非持続可能財は選択者に負の影響を与える地位財となり、もともと希少である環境財の場合には、選択者に正の影響を与える地位財となるのかも知れないが、その議論は私の主要な目的ではないので、深くは議論しない
53
表 3.1: 囚人のジレンマ
A/B 非地位財の消費 地位財の消費
非地位財の消費 (3 , 3) (1 , 4)地位財の消費 (4 , 1) (2 , 2)
費者が得る利得表を表 3.1に示す。括弧の左側の数字は消費者Aが得る利得であり、右側の数字が消
費者 Bの得る利得である。このゲームのナッシュ均衡は、Aと B共に地位財の消費を行うことであ
る。このような消費者の組は、社会的相互依存関係がないとする仮定での合理的消費者選択でさえ、
環境財の非利用価値を反映した消費をせずに持続可能でない消費を行う。それに加えて、社会的相互
依存関係にある消費者は、自身のステータスや消費能力を他者に見せつけ、他者と自分を区別しよ
うとするのである。ここで、非持続可能財は自然環境において特別な希少性を持つことから地位財
としての性質を帯びるという仮定をおけば、ジレンマの結果として非持続可能財は社会的な正の影
響がさらに大きくなる可能性がある。これが意味することは、環境財の持続可能性のさらなる悪化
である。また、ここでのゲームで仮定しているように消費者同士が協力し合うことができないとき、
利己的厚生主義者はこの状態を変えることはできないのである。利己的厚生主義者は、より持続可能
でない消費を行ってしまう状況を改善するためには、なんらかの社会的協調行動がなければならない
ことが示されるのである。
以上では、合理的選択モデルの非協力二人ゲームにおいて、社会において環境に関心を持たない利
己的消費者しか存在しない場合について分析した。しかし、実際の社会には、環境に対する倫理観を
持つ消費者も存在する。そして、環境財の非利用価値は、利己的厚生主義者によっては共感で認識さ
れ、非厚生主義者によっては共感とコミットメントで認識されるのである。以下では、環境への倫理
観を持つ消費者が社会的相互依存関係にある状況において、共感によって環境財の非利用価値を認識
する場合と、コミットメントによって環境財への非利用価値を認識する場合について分析する。
環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義の消費者の分析においても、上で行ったように社会的
相互依存関係が消費者選択に与える影響のみを分析したい。そのために、始めに次の仮定をおく。社
54
表 3.2: 価値の実現値
A/B 非地位財の消費 地位財の消費
非地位財の消費 (3 , 3) (1 , 2)地位財の消費 (2 , 1) (0 , 0)
会的相互依存関係を考えないときの、環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義者が二つの代替的
選択肢から得られる厚生改善は同値である。この仮定の下で、社会的相互依存関係にある消費者の二
人非協力ゲームにおける利得を考えると、環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義者がそれぞれ
の選択をとったときの利得は、環境に対する倫理観を持たない利己的消費者における利得と同じであ
る。したがって、環境に対する倫理観を持つ利己的厚生主義者も、社会的依存関係がないときに比べ
て、より持続的でない消費を行うジレンマに陥る。しかしながら、利己的厚生主義者が持つ環境に対
する倫理観は、それがない場合に比べて持続的な消費を行うための役割を担っている。独立な消費者
分析での議論と同じだが、そのような消費者は、共感により環境財の非利用価値から厚生情報を受け
取る。地位財と非地位財から得られる利得を比べたとき、社会的相互依存関係から生じる非地位財の
正の影響を相殺するだけの厚生情報を、環境財の非利用価値から受け取るならば、ジレンマ的状況は
解消されるのである。だとしても、社会的相互依存関係がないときと比べて、より持続的でない消費
を行うジレンマ自体は解消できない。このジレンマを解決するためには、やはり社会的協調行動が必
要となるのである。
では、環境に対する倫理観を持つ非厚生主義の消費者の行動はどのようなものになるだろうか。こ
のような消費者は、持続的な消費を行うことにコミットすることが考えられる。このような消費者が
それぞれの選択肢から得られる価値の実現値は、表 3.2で表される。環境に対してコミットする消費
者は、他者がどのような選択肢をとろうとも、非持続可能財を選ぶのである。したがって、ここで仮
定したように環境財消費の社会的相互依存関係が存在する場合もジレンマ的状況に陥ることはない。
環境に対する非厚生主義的倫理観が人々に持たれているときには、社会は常に持続可能な消費を行う
ことができるのである。
55
以上のように、環境に対する倫理観は、それが厚生主義的なものであろうと、非厚生主義的なも
のであろうと、持続的な消費に寄与する。重要なことは、それが厚生主義的なものあったとしても、
消費者が環境に対して十分大きな共感を持っていれば、一定の持続的な消費が行われるということで
ある。それが非厚生主義的な場合は、消費者が環境に対してコミットメントを持つことで、常に持続
的な消費が行われるのである。このように考えると、環境への厚生主義的、非厚生主義的倫理観は、
持続可能な消費行動の達成のために同じような役割を果たしているのである。
しかしながら、現実の社会においては、厚生主義的な倫理観を持つ人もいれば非厚生主義的な倫理
観を持つ人々もいるのである。このように多元的な倫理観を社会に認めるとき、厚生主義的な倫理観
を持つ消費者は、非厚生主義的な倫理観を持つ消費者の地位財の社会的影響を犠牲にした行動にた
だ乗りすることになる。社会で非地位財を消費する人々が多くなれば、地位財を消費するひとが一層
少なくなるために地位財の社会的影響は大きくなるからである。非厚生主義者が非地位財を消費す
れば、厚生主義者にとって地位財を消費したときの社会的影響が大きくなるのである。
以上では、独立な消費者選択を補完する、社会的相互依存関係にある状況の分析を行った。社会の
全ての構成員が利己的厚生主義者であると仮定したとき、人々が環境に対する倫理観を持っていた
としても、社会はジレンマ的状況に陥り、より持続可能でない消費を行うことになる。したがって、
人々が社会的協調行動に頼るべき追加的理由が得られた。また、社会には利己的厚生主義者と非厚
生主義者が存在すると仮定したときも、人々が環境に対する倫理観を持っていたとしても、社会は
ジレンマ的状況に陥り、より持続的でない消費を行うことになる。加えて、利己的厚生主義者にとっ
ては、非厚生主義者の地位財を消費しない選択に対してただ乗りする追加的動機も生じる。したがっ
て、これによっても、人々が社会的協調行動に追加的理由が生じる。最後に、倫理的な消費者は確か
に、道徳的な行動をとることで、満足感を得る。しかしながら、そのように個人の行動に依存するよ
りも、社会的協調行動によって社会的費用をより小さく、そしてより多くの望ましい結果を得ること
ができるのである。
56
3.3 結論
第 3章では、消費者選択の結果として環境財の消費が行われる状況を想定し、そのような状況にお
いて、消費者の環境に対する倫理観はどのように持続可能性に影響を与えるのか分析した。はじめ
に、消費される環境財を持続可能財と非持続可能財とに分類した上で、消費選択肢の定義を行った。
同時に、非持続可能財の非利用価値が消費者選択で考慮されるためのメカニズムとして、共感とコ
ミットメントを導入した。次に、これらの分析の予備的考察を下に、合理的消費者モデルを用いての
分析を行った。ここでは、第一に、通常の財と環境財の消費選択における帰結の違いを環境財の定義
にしたがって分析した。第二に、独立な合理的消費者選択モデルを用いて、消費者が厚生主義的倫理
観しか持たない場合と非厚生主義的倫理観も持つ多元的倫理観を導入した場合を分析した。そして、
第三に、社会的相互依存関係にある合理的消費者のモデルを用いて、同様に厚生主義的倫理観しか持
たない場合と、多元的倫理観を導入した場合を分析した。
環境財の定義によって生じる特徴的な帰結についての分析では、環境財の消費を伴う消費者選択に
おいて、その非利用価値を考慮しなければ、持続可能な消費を行うことができないことが示された。
人々はたびたび、この非利用価値を認識した選択行動を行うが、非利用価値は利己的厚生主義もしく
は非厚生主義的倫理観によって、選択判断に影響を与えることができる。非厚生主義的倫理観を持
ち、環境に対して強いコミットメントを持つ消費者は、代替的な選択肢を比較して非利用価値より大
きい非持続可能財の消費を伴う選択肢をとらないために、持続可能な消費行動をとることができる。
環境に対して利己的厚生主義的な倫理観を持つ消費者は、代替的持続可能財から得られる厚生情報
と非持続可能財から得られる共感によるものも含めた厚生情報を比較し、自身の厚生を最大化され
る選択肢をとる。環境に対して一定の強い共感を感じるならば、非厚生主義的倫理観を持つ消費者と
同程度の持続可能な消費を行うこともできる。
独立な消費者選択モデルでの分析では、環境に対する非厚生主義的倫理観を持つ消費者のみから
なる社会では、個人の厚生は最大化されていないかもしれないが、持続可能性の観点から最も望まし
い帰結を得ることができることが示された。ただし、社会における消費者が、環境に対して利己的厚
57
生主義的な倫理観しか持たない場合には、個人の厚生は最大化されているし、持続可能性の観点から
望ましい消費が行われている可能性もある。さらに、社会において環境に対する利己的厚生主義的倫
理観と非厚生主義的倫理観を持つ消費者が存在する現実的な状況では、政府や自治体、NPOなどに
よる社会的協調行動が多くの利点を有する。これは主に、非厚生主義者の持続的な消費選択にただ乗
りする利己的厚生主義者を排除したり、環境財を消費する能力自体を制限する場合に必要性が高い。
協調行動の経済的手法として、非持続可能財に税金をかけたり、直接的規制を行う場合が考えられ
る。税収は、人々が環境への倫理観を持つための教育や福祉に使われるべきであるし、協調行動自体
が人々の消費行動を見直させるきっかけともなるだろう。
社会的相互依存関係にある消費者の合理的選択モデルでは、環境に対する非厚生主義的倫理観を
持つ消費者のみからなる社会において、持続可能性の観点から最も望ましい帰結を得ることができ
ることが示された。ただし、ここでも利己的厚生主義者のみからなる社会では、同程度の持続可能な
消費を行う可能性もある。対して、社会には環境に対する利己的厚生主義的倫理観と非厚生主義的倫
理観を持つ消費者が存在する現実的な状況では、利己的厚生主義者にとって、非厚生主義者の厚生負
担にただ乗りすることが望ましい。これは独立な消費者選択に補完的に言うことができる。したがっ
て、社会的相互依存的状況も考えれば、社会的協調行動に頼るべき追加的理由が生じることになる。
独立な状況においても、社会的相互依存関係がある状況においても、社会が利己的厚生主義者の
み、もしくは非厚生主義者のみで成り立っている場合には、消費者の環境に対する共感とコミットメ
ントの役割は同じである。また、共感が大きければ、コミットメントと同程度に持続可能な消費に
寄与することができる可能性がある。しかしながら、通常のように社会に多元的な倫理観が存在す
る場合は、共感とコミットメントの役割は異なる。非厚生主義者が環境に対して強いコミットメン
ト示す持つとき、そのような消費者にとっては利己的厚生主義者がどの程度ただ乗りするかすら関
係がないかもしれない。対して、利己的厚生主義者は環境に対して強い共感を持っていたとしても、
利己的厚生主義者が、持続的な消費を行う限りただ乗りの誘引は生じるため、より持続的でない消費
で満足してしまう可能性がある。つまり、社会において倫理観が一種類しかないという仮定を取った
58
ときよりも、社会での多元的倫理観を許容した仮定を取ったときのほうが、社会的協調行動に頼る必
要性は大きいのである。
環境問題に対応するためには、環境に対する倫理観を持つ個人の行動に任せておけばよいという
考えには、社会的厚生の観点からも問題がある。環境に対して高い倫理観は全てのひとに持つことは
できない。自分自身の福祉や厚生が高くない消費者は、環境に対して余計な費用を支払うことがで
きないことも考えられる。環境を保全することから得られる道徳心の満足感は、所得の高い一部の
消費者に限られるかも知れないのである。また、このような一部の人が道徳心を満足させるために
行う持続可能な消費は、社会的な消費の持続可能性にはほとんど影響を与えないだろう。ここでも、
社会的協調行動の必要性が説かれるのである。政府や自治体、NPOなどによる課税、規制、エコ製
品への認証などは、消費者に広く浅く負担を求めるが、これによって、潜在的には環境に対して倫理
的関心を持っていた人々の実際の行動にも影響を与えることができるのである。
59
第4章 まとめ
近年における、人々の環境問題に対する意識の高まりは急激なものである。このような環境問題は大
きなもので地球温暖化、自然資源の浪費や生物多様性の危機などが挙げられる。そのような認識され
てきた環境問題とは、経済が発展して大量生産、大量消費の結果として、環境財の自然によってしか
供給されないという性質が社会的に認知されてきた結果なのである。
伝統的な経済学では、消費者は自身の効用を最大化する行動を取ると考えられてきた。しかしなが
ら、環境問題が認識されてきている近年では、環境財のの消費において消費者は効用最大化行動で
は、説明のつかない意思決定をする場合がよく見られるようになった。例えば、消費者のエコ商品を
購入や、変わったもので電気のグリーン購入なども挙げられる。
本研究の目的は、こうした意思決定が、消費者の環境に対する共感やコミットメントによって自然
資源の非利用価値を認めたことの帰結と考え、倫理観による価値判断が持続可能な消費を導くこと
を示すことである。そのため、はじめに、消費者の選択になぜ共感やコミットメントが影響してい
ると考える必要があるのか明らかにするために、これまでの伝統的な規範経済学の問題点を示した。
しかし、共感やコミットメントが消費者の選択に影響を与えると考えるとしても、それらはどのよう
な行動規範が基となっているのだろうか、また、それらは消費選択肢のどのような情報に対して価値
判断を行っていると考えられるのだろうか。したがって、次に、公共財に対して環境財を定義するこ
とで、環境に対する倫理観を持つ消費者は環境財の非利用価値の非厚生情報もしくは、厚生情報に対
して価値判断を行うことを示した。また、Paavola [7]を基に、利己的厚生主義的行動規範に従う消
費者は共感によって非利用価値の厚生情報を評価し、非厚生主義的行動規範に従う消費者は共感とコ
ミットメントによって非利用価値の厚生情報と非厚生情報を評価することを示した。
61
先行研究 (Paavola [7])は、環境に対して倫理的関心を持つ個人の消費行動が、持続可能な消費を
行ううえでどのような役割を持つのか分析を行う。その結論は、利己的厚生主義以外の行動原理に
基づいて行動する、環境に対して倫理的な関心を持つ消費者が社会に多数存在すればより持続可能
な消費を行うことができるというものである。ここで、持続可能な消費とは、消費者選択における
選択肢を比較しより環境負荷の小さい消費選択を行う場合を指す。しかしながら、これはあまりに
も単純すぎる仮定であり、持続可能な消費が行われている状況は明確に定義されていない。また、先
行研究においては、消費される環境財を明確に定義していないために、利己的厚生主義者が共感に
よって環境財の非利用価値を評価する場合については考えておらず、利己的厚生主義者の倫理観は、
分析の対象としていない。
第 3章では、本研究の目的を果たすため、第 1章での予備的考察とも言える準備を前提として、先
行研究が用いた分析方法に従い、その問題点の補強をしながら倫理観による価値判断が持続可能な
消費を導くことを示した。先行研究の一つ目の問題点を克服するため、消費者選択で消費の対象とな
る環境財を持続可能財と非持続可能財とに分類して定義した。これによれば、持続可能な消費とは、
環境財の致命的な集中的消費が行われる前に、代替的利用価値を持つ持続可能財の消費へ消費行動
を転換させるような消費行動と定義することができる。先行研究の二つ目の問題点は、環境に関心を
持たない利己的厚生主義者は、それが非持続可能財であっても環境財の利用価値のみしか評価しない
ことを考えれば克服できる。非持続可能財はその定義により、代替的利用価値を持つ持続可能財との
対比において非利用価値が大きい。環境に対して関心を持たない消費者が、非利用価値を評価しない
のに対して、環境に対する倫理観を持つ消費者は、この非利用価値を共感かコミットメントによって
評価することができる。環境に対する利己的厚生主義的な倫理観を持つ消費者は、共感によって非利
用価値を評価することができるのである。
独立な合理的消費者モデルでの分析では、社会の全ての消費者が環境に対する利己的厚生主義的
な倫理観を持つ場合、それらの消費者が環境に対して持つ共感が強ければ強いほど、持続的な消費が
行われる。しかし、環境に対する非厚生主義的倫理観を持つ消費者のみからなる社会では、持続可能
62
性の観点から最も望ましい帰結を得ることができる。さらに、社会において環境に対する利己的厚生
主義的倫理観と非厚生主義的倫理観を持つ消費者が存在する現実的な状況では、利己的厚生主義者
には非厚生主義者の持続的な消費行動にただ乗りする誘引があり、政府や自治体、NPOなどによる
社会的協調行動が多くの利点を有する。
社会的相互依存関係にある消費者の合理的選択モデルでは、環境に対する非厚生主義的倫理観を
持つ消費者のみからなる社会において、持続可能性の観点から最も望ましい帰結を得ることができ
る。ただし、利己的厚生主義者のみからなる社会において、彼らが環境に対して感じる共感が十分に
強ければ、同程度の持続可能な消費を行う可能性もある。対して、社会には環境に対する利己的厚生
主義的倫理観と非厚生主義的倫理観を持つ消費者が存在する現実的な状況では、利己的厚生主義者
にとって、非厚生主義者の厚生負担にただ乗りすることが望ましい。これは独立な消費者選択に補完
的に言うことができる。したがって、社会的相互依存的状況も考えれば、社会的協調行動に頼るべき
追加的理由が生じることになる。
環境財の消費を伴う消費者選択では、人々は倫理観によって環境財の非利用価値を価値判断する。
環境財の非利用価値を認識する倫理観は、利己的厚生主義的倫理観と非厚生主義的倫理観とに分け
ることができる。環境財の非利用価値を認識することが持続可能な消費につながるために、環境に対
する倫理観はそれが何であろうと、非持続可能財の消費を食い止め、環境財全体の消費持続可能性を
維持する役割を持つ。この結論は Paavola [7]の主張とは矛盾はなく、かつ厚生主義的消費者も環境
に優しい消費選択が可能であることも示唆している。
63
関連図書
[1] Becker, Gary S. (1976) The Economic Approach to Human Behavior, Chicago and London:
The University of Chicago Press.
[2] Dawes, R.M. (1980) “Social Dilemma,” Annual Review of Psychology 31: 169-193
[3] Frank, Robert H. (1985) “The Demand for Unobservable and Other Nonpositional Goods,”
American Economic Review 75(1): 101-116.
[4] Hausman, Jerry A. ed. (1993) Contingent Valuation: A Critical Assessment, Amsterdam:
North-Holland.
[5] Harsanyi, J.C. (1955) “Cardinal welfare, individualistic ethics and interpersonal comparisons
of utility,” Journal of Political Economy 63: 309-321
[6] 細田衛士 (1991) “非営利団体の活動と環境保全-企業財団の新しい役割を求めて-,” フィナン
シャル・レビュー, 大蔵省財政金融研究所, November 1991.
[7] Paavola, Jouni (2001) “Towards Sustainable Consumption: Economics and Ethical Concerns
for the Environment in Consumer Choices,” Review of Social Economy, vol. lix, no. 2, June
2001.
[8] Pigou, A.C. (1920) The Economics of Welfare, London: Macmillan. 4th ed., 1952
65
[9] Sen, Amartya K. (1977) “Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Eco-
nomic Theory,” Philosophy and Public Affairs 6: 317-344. (大庭健 ·川本隆史 (1989) 『合理的
な愚か者,経済学=倫理学的探求』, 勁草書房.)
[10] 柴田弘文 (2002) 『環境経済学』, 東洋経済新報社.
[11] 鈴村興太郎 (2006) 『世代間衡平性の論理と倫理』, 東洋経済新報社.
[12] 鈴村興太郎 ·後藤玲子 (2001) 『アマルティア ·セン-経済学と倫理学-』, 実教出版株式会社.
66