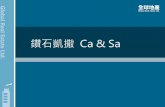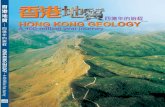細石刃核をどう持つか_旧石器研究第10号
-
Upload
tohoku-gakuin -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of 細石刃核をどう持つか_旧石器研究第10号
細石刃核をどう持つか―北海道奥白滝Ⅰ遺跡と上白滝 8 遺跡の細石刃資料の
動作連鎖概念に基づく技術学的分析―
大場 正善
日本旧石器学会『旧石器研究』 第 10 号 (2014 年 5 月) 41−66 頁 抜刷
41
2014 年旧石器研究 (Palaeolithic Research)10 pp.41 - 66
要 旨
本稿は、動作連鎖の概念に基づく石器技術学により、痕跡が残り易い黒耀石で、かつ豊富な接合資料が得られている北海道奥白滝Ⅰ遺跡出土の紅葉山メトードと上白滝 8 遺跡の峠下メトードに用いられたテクニークの復原を目的とする。テクニークの復原にあたって、まず両遺跡の細石刃に関する痕跡と、直接打撃、間接打撃、押圧による実験資料に残る痕跡と比較を行った。その結果、当該資料が押圧によって剥離された可能性が高いことが判明した。さらに、細石刃が直線的で、規則的であることから、何らかの固定具が用いられている可能性が高い。そこで、固定具を用いた民族事例やさまざまな実験事例について、製作実験を交えて細石刃剥離の合理性を検証した。そのなかでも、J. ペルグラン氏が考古資料に残る痕跡と氏の豊富な経験的知識により復原したL字状固定具を用いた押圧テクニークは、細石刃剥離でもっとも合理的なテクニークであることが判明した。 そのうえで、奥白滝Ⅰ遺跡の紅葉山メトード関連資料に残る痕跡について技術学分析を行い、紅葉山メトードには、ペルグラン氏のL字状固定具を用いた押圧が用いられた可能性が高いことが判った。一方で、峠下メトードでは、細石刃核の作業面と下縁のなす角度がL字状固定具には対応しないために、L字状固定具を用いることが困難であった。そこで、細石刃核の形態に合わせた「く」字状固定具を新たに考案。「く」字状固定具を用いた製作実験を行ったところ、考古資料と類似した形態と痕跡を有する実験資料を得ることができた。また実験からは、峠下型細石刃核の断面形より製作者の細石刃核を装着した持つ手が明らかとなり、その反対に押圧具を持つ手、すなわち利き手が推定できることが判明した。上白滝 8 遺跡、および北海道出土の峠下型細石刃核を検討したところ、細石刃核の 9 割以上は右利き用であったと考えられる。 9 割以上が右利きであったとすると、現在よりも割合が多いため、当時の製作者は、「左手で細石刃核を持ち、右手で押圧具を持たなくてはならない」とする強い社会的な慣習があったことが推定される。
キーワード:動作連鎖、石器技術学、実験考古学、メトード、テクニーク、紅葉山メトード、峠下メトード、押圧、L字状固定具、「く」字状固定具、利き手
細石刃核をどう持つか―北海道奥白滝Ⅰ遺跡と上白滝 8 遺跡の細石刃資料の動作連鎖概念に基づく技術学的分析―
大 場 正 善 1
1 .はじめに
1−1 テクニーク復原の問題 2008年時点で、 遺跡数は1000か所を超える(大竹2008)。これまでの日本の細石刃技術研究では、細石刃の製作工程について、各地で資料が増加して盛んに議論されさまざまな「技法」が復原され、提唱されてきた。その一方で、細石刃を製作する際の製作道具や製作時のジェスチャー、すなわち実際に細石刃をどう剥離するのかについては、等閑にされてきたきらいがあった。徐々にではあるが、近年、細石刃技術の始まりとその細石
刃をもたらした後述する“テクニーク”について、関心が集まりつつある(仲田2010;芝2013;高倉2013;堤2013など)。しかし、製作道具が有機質の素材であれば、有機質がほとんど残存しない日本では、それを知ることが難しい。ましてや、すでに消えてしまっている細石刃を製作しているヒトの姿を見ることは、当然ながら不可能である。細石刃が実際にどのように製作されたのかを知るには、何も手掛かりがないかのように思えてしまいがちである。 しかし、手掛かりは、細石刃技術関連に残された“痕跡”にある。痕跡、自然の営為によるものも含まれるが、そ
2013 年 11 月 29 日受付。2014 年 4 月 11 日受理。1 (公財)山形県埋蔵文化財センター 〒 999-3246 山形県上山市中山字壁屋敷 [email protected]
論 文
42
細石刃核をどう持つか(大場正善)
れはヒトの何らかの具体的な行為を行った結果生じる形跡である。つまり、痕跡を生じさせた原因である行為を突き止めれば、実際に細石刃をどのようにして作っていいたのかを明らかにさせることが出来よう。
1−2 対象資料 そこで本稿では、痕跡が残りやすい黒耀石を石器石材とし、かつ接合資料が豊富に得られている、北海道白滝遺跡群(図 1 )・奥白滝 1 遺跡Sb 7 〜10の紅葉山メトード(北海道埋文2002)、上白滝 8 遺跡のSb14〜19の峠下メトード(北海道埋文2004)にかんする資料について、動作連鎖の概念に基づく技術学分析を行い、復原した細石刃製作に用いられた製作道具と、 製作時のジェスチャーについて考察する。観察した資料は、奥白滝Ⅰ遺跡が接合資料13点、細石刃核10点、石刃核 1 点、細石刃多数、上白滝 8 遺跡が接合資料15点、細石刃核31点、細石刃多数となる。また、補足的に旧白滝 5 遺跡Sb 1〜13出土資料などについても観察を行っている。実験で用いた石材については、北海道白滝赤井山山頂部西アトリエ産の漆黒の黒耀石と同山頂部東アトリエ 2 産の黒に茶や赤が混じる黒耀石を用いた。したがって、ここで示す技術的知見は、これらの黒耀石のものとなる1 )。
2 .技術学の方法
まず、本章は実際のテクニーク同定にかんする諸概念とその手順の概要について解説する。
2−1 動作連鎖 技術学の中心的概念である“動作連鎖”とは、フランスの民族学者であり、先史学者でもあるA.ルロワ=グーラ
ンが考古学に応用した、“ヒトの技術的行為を民族誌学的に記録化するための概念”である(図 2 :ルロワ=グーラン1973;山中2007,2009a)。たとえば、いま目前にするヒトの技術的行為であれば、連続写真や動画撮影をすれば、その動作連鎖を容易に記録することができる。しかし、わたしたちが扱う先史時代の石器資料は、すでにヒトの姿が消えてしまっている。さらに、遺跡から出土してくるのは、動作連鎖の結果であり、連鎖の終点でもある。そのため、残された遺物と遺構に残された痕跡を基に復原して認識するほかはない。復原は、犯人追跡的に行うのであり、その意味において、動作連鎖とは「いつ、
図1 白滝遺跡群の位置(北海道埋文2008に加筆)
図2 エチオル遺跡復原の石刃に絡んだ動作連鎖(Karlin et al. 1992)
※吹き出し、あるいは四角枠の中に描かれている石器を作る過程が“メトード”で、そのメトードに沿って描かれているヒトの姿が“テクニーク”である。このメトードとテクニークの両方が復原されてはじめて、動作連鎖が浮かび上がってくる。
43
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
誰が、どこから、何をもって、その地にやってきて、そこで何をして、そしてどのように、どこへ去っていったか」を認識する資料認識の概念である。あくまでも、型式認識のような「集団」や「社会」、「文化」を解釈するための概念ではない(山中2009a)。個々の動作連鎖分析の蓄積があってはじめて、社会や文化、歴史的な議論が組み立てられるものである。 そして、動作連鎖の概念で資料を認識することの重要性については、つぎのことも挙げられる。上述したように、遺跡から出土した遺構・遺物は、すなわち現在すでに動きを失った静態の状態でしかない。しかし、考古学は、本来あったはずの動態の状態を復原し、認識することが目的の一つであると言えよう。ところが、その静態から動態を解釈することは、過去を見ることができないのだから、現在と過去の間に横たわる「大きな溝」に阻まれている(Binford and Binford 1968;阿子島1983)。その
「溝」の架け橋、すなわち「ミドルレンジ」は、民族学、実験考古学、歴史考古学に求められた。考古資料と同じ石器を作るには、考古資料と同じメトードとテクニーク、すなわち当時と同じ動作連鎖を想定し、演じなければならない。つまり、過去においても現在においても、同じメトードを想定・実行し、同じテクニークを演じなくてはならないのである。とくに、製作の難しい行為ほど、想定された動作連鎖のとおりに「テクニーク」の実演が同じであることを求める固定度が強い(山中2010)。したがって、動作連鎖の概念で資料を認識することこそが、現在と過去をつなぐ「ミドルレンジ」となっていると言えよう(山中 同上)。
2−2 石器技術学 石器に絡んだ動作連鎖研究、すなわち石器技術学は、J.チキシエにより旗揚げられ(Tixies 1967)、J.ペルグランが製作実験を論理に組み込むことによって飛躍的に発展している(山中2012)。ペルグランは「先史時代人よりも石器作りが上手いのではないのか」との評価もさることながら、「動作連鎖の概念」が石器研究に有効に働くことを、方法論的に提唱した研究者でもある(山中2011)。2006年以降、山中一郎・京都大学名誉教授が橋渡しとなって、ペルグランより直接指導を受けることができた筆者らも、そのフランスの石器技術学の流れをくむ(大場2007;会田2011;山中2011)。
2−3 復原の手順 テクニークを同定する手順としては、まず主目的となったトゥールの形態を仔細に観察した上で、個々の資料を動作連鎖の順、つまり原石から製作、使用、廃棄の順に置き分け、段階ごとでどのような剥片が剥離され、あるいは石核やトゥールなどがどの順番に残されたのか
を把握する。接合資料があれば有利だが、剥片やトゥール素材剥片の背面構成や剥離方向、それぞれの大きさ、石核の形状と剥離位置と剥離方向を観察し、石器群の中でトゥールがどのような製作工程で作られたのかを検討する。そして、剥離事故や石材の質の影響といった製作時の変異を切り捨て、石器群中における基本的な製作工程、すなわち製作者の頭の中で思い描かれた“メトード” を抽出する。なお、目的となったトゥールの形態、あるいは主目的剥片とそれを割り出すための石核のイメージが“コンセプト” であり、そのコンセプトに沿うようにメトードが組み立てられる(ペルグラン氏よりご教示)。石器作りでは、コンセプトとメトードが明確に描けなければ、石器を作ることができないと言っても過言でない。 テクニーク、すなわち石器製作者の姿は、実際に見ることができない。したがって、テクニークの同定は、参照すべき実験データからの“類推” によっている。具体的には、製作工程の段階ごとに個々の資料を選り分け、残された痕跡を仔細に観察し、それぞれの工程ごとに残された打点形状やバルブ、フィッシャーやリングの発達の状態、剥離面の形状、末端形状、剥片の大きさや厚さ、擦痕や縁辺の潰れなどの状態を把握する。そのうえで、それらの痕跡をなしたと考えられるテクニークを、自身のもつ経験的知識と照らし合わせて直観的に推定(仮説)を行う。一方で、経験にないテクニークを考察する際には、“アブダクション(米盛2007)”、すなわち仮説形成の推論が用いられる。推定では、 1 例だけでなく、それではできないものを含めて推定され得る限りの例を挙げることになる。 つぎに、メトードを復原し、テクニークを推定したうえで、考古資料と同じ石材を使い、復原したメトードにしたがって、推定したテクニークを用いた製作実験を行う。実験は、推定したテクニークをほぼ確証するために行うようなものであるが、あくまでも実験資料と考古資料を対比して、推定したテクニークにたいする検証を必ず行う。仮に、実験資料が考古資料と異なる痕跡であっ
図3 技術学分析の手順
44
細石刃核をどう持つか(大場正善)
たならば、実験で用いたテクニークを再検討して、再実験し、さらに対比を繰り返す。この実験と対比の繰り返しは、同じ痕跡となるまで行われる。同じ痕跡が生じたときに初めて推定したテクニークが検証されることになるが、同時に、復原した技術は過去の技術により近づくことにもなろう。しかし、消えてしまった過去の姿であるため、100%の検証は不可能である。そのため、数多くの証拠を挙げることで、仮説にたいする蓋然性をより高める必要がある。逆に、残されたわずかな可能性から、他のテクニークの可能性について、絶えず考え続けることも重要となる。 このテクニークの同定は、些細ない痕跡をも見分けて、その痕跡を生じさせた過去のヒトの行為を診断的に判断することを要する(山中2009a)。対比は、痕跡を「属性」として計測して、数量化してなんらかのまとまりを導き出す、いわゆる属性分析でなく、あくまでも実資料同士の直接対比となる。対比の際には、いくつかのテクニークで製作した実験資料をそろえておくとよい。 テクニークの同定は、「観察→仮説→実験→検証」といった、科学的方法の過程を踏む(図 3 )。緻密な観察によって同定の根拠となる証拠(痕跡)を数多く拾い上げる。そして、集められた証拠をもとに立てられる仮説をいくつか挙げ、その上で仮説をもとに実験を行い、実験資料と考古資料を比較して検証を行うのである。この過程は、世に科学的医学を問い、「実験医学」を確立したフランスのC. ベルナールの方法に拠っている(ベルナール1970,2008)。また、この同定の過程については、法科学における「工具痕鑑定」や、物理学における「破損解析」などでも、同様の過程で分析が進められている(メイヤーズ2005;吉田2005)。 なお、分析、および対比に際して、いわゆる「属性分析」を用いることの問題については、山中2004,2005,2009bで鋭く指摘し、大場2013でも詳述したので参照されたい。
本稿では、とくに細石刃剥離のテクニーク復原に焦点を絞って分析を行う。
3 .直接打撃と間接打撃の可能性
本章では、はじめに分析対象資料に用いられたテクニークについて大まかに絞るために、直接打撃、間接打撃、押圧のうち、どのテクニークの可能性があるかを検討する。
3−1 直接打撃と間接打撃 まず、細石刃は、直接打撃と間接打撃で剥離するができる。たとえば直接打撃の場合は、細石刃核に頭部調整を顕著に施した上で、細石刃剥離作業面を人差し指から小指で覆うように保持し、小形の鹿角製ハンマーや軟石製ハンマーで打面縁辺を軽く打撃する(図 4 − 1 )。直接打撃で剥離された細石刃は、両側縁の規則性と、個々の剥片の外形や厚さにたいする規格性に欠けている(図 4− 2 )。その規則性の欠如が、直接打撃で剥離した細石刃の大きな特徴である。また、剥離開始部の形態については、鹿角製ハンマーの場合は基本的にリップを呈することが多い。軟石製ハンマーを用いた場合は、やや不明瞭な剥離開始部を呈している、あるいはその部分が砕けているなど、変異幅が広い。 間接打撃の場合は、細石刃核の保持の仕方が一番の問題となる。椅子などに腰かけた姿勢で、細石刃核を左右の太腿の間に挟んで保持した場合は、たとえば細石刃核の断面形が 3 ㎝四方のような小形のものであれば、大腿骨が若干内反っているために、細石刃核をしっかり挟むことができない(図 5 )。左手で細石刃核とパンチをともに保持する場合(図 6:Clark 1980;大沼・久保田1992)は、細石刃核が親指と人差し指で輪を作った範囲よりも小さければ、細石刃核とパンチを同時に持つことがより難しくなる。そもそも、峠下型細石刃核や広郷型細石刃核は、
図4 直接打撃による細石刃剥離
1 直接打撃による細石刃剥離の様子 2 直接打撃で製作した細石刃(左)と細石刃核(右)
45
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
図5 細石刃核を太腿で挟んで間接打撃をするテクニーク(左)と、細石刃核を太腿で挟んだ様子(右)
図6 片手で高さ約5 ㎝の細石刃核とパンチを同時に保持した様子(左・中)と、高さ約3 ㎝の細石刃核とパンチを同時に保持した様子(右)
1 紅葉山型細石刃核 2 峠下型細石刃核 3 実験資料 図7 細石刃核作業面に残る細石刃剥離痕に観る“血瘤状のバルブ(S=1/2)
1 固定具なしでの押圧 2 1 の直後 3 実験資料 図8 固定具を使わないで細石刃を剥離するテクニーク
46
細石刃核をどう持つか(大場正善)
1 作業面を上に向けた保持の様子 2 「多面体彫刻刀形石器」から細石刃剥離の様子図9 固定具なしの押圧テクニーク(左:Flenniken and Hirth 2003、右:Pelegrin 2012)
図10 鹿角製L字状固定具と細石刃核打面との接触部分に生じた小剥離(関口2003に加筆)※打面が平坦打面の場合は識別が容易であるが、調整打面の場合は識別が難しい。
図11 両足の内側で挟むだけで保持する「胸圧剥離」(左:Holmes 1919に加筆、中:ボルド1971に加筆、右:大場2008)
47
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
その形状から、太腿で挟んで保持するテクニークでも、片手でパンチと細石刃核を同時に保持するテクニークでも保持することが相当に難しい。
3−2 対象資料に用いられたテクニーク 今回対象とする資料に用いられたテクニークは、剥離された細石刃の剥離開始部の形状と直進的な全体形状、そして規格性、細石刃核の大きさや形状から判断して、直接打撃と間接打撃の可能性は低い。もっとも、当該資料すべてに、押圧2 )で特徴的に現れる、砕けの少ない、あるいはない剥離開始部、そして“血瘤状のバルブ”が認められることと、後述する諸痕跡が認められることから、細石刃剥離には、押圧が用いられた可能性が高いことが考えられる(図 7 )。 そもそも、押圧で細石刃を剥離するには、掌に皮布を敷いてその上に細石刃核を載せて握るだけの保持でも可能である。しかし、そのように剥離された細石刃は、両側縁が蛇行し、規格に欠け、かつ大半が掌に細石刃の末端が当たって折れてしまう(図 8 :ペルグラン・山中2007)。ほかにも、イスなどに腰かけた姿勢で、細石刃核の作業面を天井に向け、打面を身体の正面と対向させた状態で、利き手の反対の手で握り持ち、さらにその手を両腿の間に挟み持って固定を強化し、棒状押圧具を用いて押し上げるようにして細石刃を剥離するテクニークがある(図 9 − 1 :Flenniken and Hirth 2003;ペルグラン・山中2007)。そして、地面に腰を下ろし、開脚した上で、掌中で保持した多面体彫刻刀形石器状の細石刃核を片腿(利き手と反対の方の足)の上面に置いて固定するテクニークもある(図 9 − 2 :Pelegrin 2012)。 しかし、これらのテクニークでも、細石刃核の安定性が得られないので、上述のような細石刃、あるいは側面観の湾曲が大きい細石刃になってしまう。当該資料は、より直線的な細石刃が剥離されていること、折れていない細石刃が出土していることから、細石刃核を安定させ、かつ剥離した細石刃を折れないように保護するような固定具を用いた固定法であったことが想定される。なお、大形の楔形細石刃核となるが、ペルグランは、座った姿勢で、楔形細石刃核を両足の裏で挟むテクニークを考案し、長さ 6 〜 8 ㎝程度の規則的な細石刃剥離に成功している(ペルグラン・山中2007;大場2007;Pelegrin 2012)。 ところで、日本でよく知られる細石刃を剥離するテクニークで、概説書や博物館の展示パネルなどで頻繁に引用される、細石刃核・石刃核を両足の内側に挟んで保持し、T字状の押圧具を用いて胸で押圧するテクニーク、すなわちいわゆる「胸圧剥離」がある(図11左・中:ボルド1971;芹沢1986など)。しかし、足で挟むだけでは、剥離の際の加圧による数十㎏に及ぶ荷重に耐えられないし、ましてや加圧したときに、細石刃核が前転する
(図11右)。仮に、イラストのように裸足の場合は、両足の内側を酷く傷付けてしまいかねない。靴を履いたとしても、加圧による細石刃核の前転を防ぐことが相当に難しい。つまり、このテクニークで細石刃を剥離することは、まずできないといっても過言でない。したがって、先史時代にこのテクニークがあった可能性は、極めて疑わしいと言わざるを得ない(Clark 1982;ペルグラン・高橋2007;大場2008)。 このテクニークにかんしては、J. E.クラークが絵画資料の検討と製作実験によって、切れ込みを入れた板を地面に埋めて、これを石刃核底部の支えとし、地面に腰を下ろした姿勢で両足の裏で石刃核打面を押して足の裏と地面に埋め込んだ板で石刃核をはさみ込み、十手状の押圧具を用いて、テコを応用して押し上げるように石刃を剥離する、新たな復原案を提示している(図12:Clark 1982;Timus and Clark 2003)。
4 .細石刃剥離と固定具
分析対象資料は、何らかの固定具を用いて細石刃が剥離された可能性が高い。固定具を用いて細石刃を押圧で剥離するテクニークをどのように考えてきたのかについて、何らかの固定具を用いて細石刃を剥離するテクニークについて概観する。
4−1 万力状固定具 細石刃核を固定するために万力状固定具を用いたのが、D. E. クラブトリーである(図13− 1 ・ 2 :Crabtree 1967,1968)。この固定法は、細石刃核・石刃核の両サイドを角材で強固に挟み込むテクニークである。これによって一定程度の安定が得られるので、直線的な細石刃・
図12 クラークが復原したメキシコ式石刃核固定法 (Timus and Clark2003に加筆)
48
細石刃核をどう持つか(大場正善)
1 万力状固定具 2 万力状固定具のテクニーク 3 製作時の支え木と支える人図13 クラブトリーが用いた万力状固定具とそのテクニーク
( 1 :Whittaker 1994、 2 ・ 3 :ビデオ“The Hunter’s Edge”より抜粋)
1 小型万力状固定具 2 小型万力状固定具のテクニーク 3 K. アッカーマンのテクニーク図14 小型万力状固定具とそのテクニーク
( 1 ・ 2 :Tabarev 1997、 3 :2005年10月に西村誠治氏が撮影)
※作業面の正面観が直線的な逆三角形、あるいは左右対称形の円筒形を呈している場合は、両側縁の上端が固定具の鉤状の内角に当たる。そして、底部を押さえる板に挟まれるので、上下左右に挟まれた状態になるので、固定が安定する。しかし、峠下型細石刃核のような、作業面の正面観が左右非対称の場合は、右側面上下端部が固定具鉤状の内角に接触し固定されるが、左側面上下端部は固定具鉤状の内角に当たらないので、左側の固定が甘くなる。結果的に、細石刃核の固定は安定しない。
図15 V字切れ込み入り固定具とそのテクニーク、および臼状固定具
1 . V字切れ込み固定具とそのテクニーク、2. 1 で剥離した細石刃、 3 . 幹上固定具とそのテクニーク、4・5. 臼状固定具とそのテクニーク
49
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
石刃の剥離が可能となり、クラブトリーは、固定具が重要な役割を果たすことをはじめて指摘したのである(ペルグラン・山中2007)。 しかし、この固定具でも、数十kgにもおよぶ荷重に耐えられないこと、細石刃核の両側面が規則的でないと挟むのが難しいこと、強力に挟む込むことで生じる、打面縁辺などの潰れや小剥離が分析対象資料において観察されないこと、細石刃剥離進行にともない剥離位置を変えるときに行う、細石刃核の固定具への再設置にいちいち手間がかかること、打面と作業面のなす角度(以下、前面角)が60°よりも浅い角度の細石刃核の固定が難しいこと、装置が大掛かりであることなどの問題がある(ペルグラン・高橋2007)。また、クラブトリーの固定具とは異なった打面と底部を挟み込む「縦型万力」にしても、傾斜した打面や非常に小さい打面の細石刃核を固定することができない問題がある(ペルグラン・高橋 同上)。さらに、この固定具で使用するT字杖状押圧具の使い方についても、横木を胸に当てて、前を向いている作業面にたいして、前に押し出すジェスチャーであり、これは運動学的に無理なジェスチャーであると言える(図13−3 :ペルグラン・高橋2007)。以上のことからすれば、万力状固定具は、非合理的なテクニークであり、先史時代に用いられたとする可能性は、低いと言える。一方で、装置が大掛かりであることを改善した固定具として、A. V. ターバレフやK. アッカーマンが使用した 2 枚、ないし 3 枚の小型の板で挟む込む小形の楔形細石刃核用の固定法を考案している(図14:Tabarev 1997、2005年10月の第 9 回考古学コロキウムより)。しかし、固定具の軽量化以外の問題は、改善されていない(大場の経験による)。
4−2 その他の固定具 日本において考古資料の細石刃核に残る痕跡を基に想定される細石刃核の固定法については、以前から指摘されている(安蒜1979;橘1981;宮田1998)。しかし、実際に実験を行って、細石刃核などに残された痕跡について追究した例は、ごくわずかに過ぎない(図10:関口2003)。以下に、日本における実験・製作例について概観する。 岩本圭輔は、 厚さ 3 ㎝程度に輪切りした丸太材に、細石刃核を入れるためのV字状の切り込みを設けた固定具を考案している(図15− 1 :佐々木編1991)。これは、作業面を外側に向けて細石刃核を切り込みの中に入れて、足で踏んで固定するテクニークであるが、円錐形細石刃核などの小形の細石刃核の固定が難しいこと、剥離した細石刃の逃げ場がないために、細石刃が床と挟まれてしまって折れるなどの問題がある(図15− 2 )。 大沼克彦は太さ70〜80㎝、高さ40〜50㎝の丸太材の
木口の一端に、V字状の切れ込みを入れ、切れ込みの下に剥がれ落ちた細石刃を逃がすための溝を設けた、大型固定具を考案している(図15− 3 :大沼1998)。さらに石刃核を固定した例であるが、テコを応用して押圧し、剥離した石刃を逃がす空間を設けた、大きな丸太材の中心をくり抜いた臼状の大型固定具も考案している(図15− 4 ・ 5 大沼2002)。ただし、問題は、この固定具の製作と移動にかかる困難さである。 大沼克彦・久保田正寿は、自然の中で容易に準備できる固定具や固定法を考案している(大沼・久保田1992)。一つは、小形のY字状の小枝を固定具とするテクニークである。この固定法は、小枝のV字に開いた部分に合わせるように、逆三角形を呈した作業面を入れ、二股に分かれた枝で作業面の両サイドを支えるように固定する固定法である(図16− 1 ・ 2 )。しかし、この固定法は、細石刃核の底部が支えられていないので、安定性に欠ける。したがって、より直線的な細石刃が得難いこと、後述する細石刃剥離面の末端に認められるごく薄いヒンジが見られず、ウットルパセの出現率が高い特徴が挙げられる
(図16− 3 )。 もう一つは、大きな礫、あるいは凸字状固定具に楔形細石刃核を立てかけて、上から全体重を掛けるようにして固定するテクニークである(図17− 1 )。このテクニークでは、細石刃核の支えを補助する礫の接触している部分、すなわち打面の片縁辺と細石刃核の下縁に、石に当たった際に生じる潰れや擦れが生じる。また、中腰の状態で、左手掌で打面を覆いかぶせるようにして細石刃核を保持し、長手の鹿角製棒状押圧具を右手で支えながら右胸で押すジェスチャーは、運動学的に若干無理のあるジェスチャーと言える(図17− 2 )。
4−3 L字状固定具 石器技術学の第一人者であるJ. ペルグランは、動作連鎖の概念に基づく石器技術学分析によって、押圧にかんするいくつかのテクニークを復原している。ペルグランは、フリント、あるいは黒耀石製細石刃核・石刃核に残る痕跡、すなわち加圧した際に固定具と接触した部分に生じた細石刃核底部の潰れや、押圧時に固定具との接触部分から発生する反動で生じる細石刃剥離面の末端のごく薄いヒンジ、打面が固定具と接触したことで生じた小さな剥離面などを参考にして、細石刃核を作業面の両サイドと底部の 3 点で容易に固定することができ、剥離した細石刃を受ける溝と浅い孔をもつ、側面観がL字状を呈した固定具の構造を考案している(図18:ペルグラン・山中2007)。また、この固定具の構造は、押し出す力よりも、より強い力を生じさせ、かつ無理のないジェスチャーである引く力が利用できるように、細石刃核・石刃核の作業面と身体の正面が対面するようになってい
50
細石刃核をどう持つか(大場正善)
る。 ペルグランは、この固定具の構造を基に、石核の大きさ、剥離する細石刃・石刃の大きさ、およびそれに応じて大きくなる圧力に合わせて、木製、あるいは骨製の大小の手持ちする固定具と地上置き固定具、そして大形の丸太材を用いた固定具と、それぞれの固定具に応じた、短い棒状押圧具と肩当て杖状押圧具、小形T字杖状押圧具と大形T字杖状押圧具、テコを応用した大形押圧具といった製作道具、そしてそれらを使うジェスチャーを復原している(図19:ペルグラン・山中2007)。これらのテクニークで製作された実験資料には、考古資料に残る痕跡と矛盾がないことから、ペルグランは、先史時代においても復原したテクニークが用いられた可能性が高いと結論づけている。 このように、これまで復原されてきた押圧テクニークの中で、考古資料と実験資料に残された痕跡との共通性と細石刃製作の合理性の点から、ペルグランが復原したテクニークは、上述してきたペルグラン復原以外のテクニークに比べて、分析対象資料に用いられたテクニークとして妥当なものであると思われる。しかし、これは、ヨーロッパを中心にした地域の資料で復原されたテクニークであるので、分析対象資料にこのテクニークが用いられていたのかについては、さらなる検討を要する。
そこで、次章において、白滝遺跡群発見の紅葉山メトードと峠下メトードの例について、ペルグラン復原のテクニークが適用できるかを中心に検討を行う。
5 .紅葉山メトードと峠下メトードのテクニークの復原
5−1 紅葉山メトードに用いられたテクニーク5−1−1 紅葉山型細石刃核に残る痕跡 奥白滝 1 遺跡Sb 7 〜10で出土している紅葉山型細石刃核は、高さが2.5〜5.5㎝、幅が1.8〜2.7㎝で、円錐形、あるいは砲弾形を呈する。細石刃核に残る最後に剥離された細石刃剥離痕から、目的とされた細石刃の形態は、幅が 5 ㎜程度で、長さが細石刃核の高さに準ずるもの、あるいは打面再生が行われていることから、残核である細石刃核の高さよりも若干長いものが考えられる。 細石刃核404(図21− 2 :母岩28・接合1026)のように、細石刃核の一部には、底部に下方向からの小剥離と、その剥離面の縁辺に潰れが観察される(図21− 1 )。また、ほとんどの細石刃核の細石刃剥離面の末端には、触ると引っ掛かりを感じる程度の、 1 ㎜に満たないような薄
1 礫立てかけ固定法 2 凸字状固定具とそのテクニーク 図17 立てかけ固定法とそのテクニーク
( 1 :大沼・久保田 1992、 2 :2002年 2 月、筆者撮影)* 2 の右は、作業をやり易くするために、多数の板を積み上げて固定具の底上げを行っている。
1 Y字状固定具のテクニーク 2 細石刃を剥離した直後 3 製作した細石刃と細石刃核 図16 Y字状固定具を用いたテクニークと製作した細石刃と細石刃核
51
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
いヒンジが認められる(図21− 3 )。 底部に観られる小剥離と潰れからは、加圧時に細石刃核の下にある程度硬い物があって、それに接触したことが考えられる。細石刃剥離痕末端に観るごく薄いヒンジは、同じく加圧時に下からの反動を受けて、細石刃剥離の進行に影響を及ぼした結果生じたものであると考えら
れる(図21− 4 ・ 5 ・ 6 )。なお、これらの痕跡は、直接打撃や間接打撃で剥離した細石刃核には、ほとんど生じることがない。また、万力状固定具に挟み込んだ際に生じるような、細石刃核の側面の擦れや潰れなどの痕跡は、観察されなかった。5−1−2 細石刃剥離に用いられた固定具の推定
図19 押圧による細石刃・石刃剥離の5つのモード(ペルグラン・山中2007、MOME 1 〜 4 :2006年京都大学総合博物館にて、筆者が撮影。MODE 5 :ペルグラン・山中2007)。
図18 ペルグランが復原した固定具の構造*写真の固定具は、ペルグラン氏の固定具を参考にして、大場が製作したもの。
52
細石刃核をどう持つか(大場正善)
上述の痕跡と、より直線的な細石刃が剥離されていること、折れていない細石刃があることを考慮すれば、ペルグランが復原した剥離した細石刃を保護するための溝を有するL字状固定具が用いられた可能性が考えられる。なお、細石刃核打面が平坦打面である場合は、打面縁辺と固定具との接触点に薄い小さな剥離が生じる(図10・20:関口2003)が、対象資料は、打面調整が顕著に施されるので、この固定具溝との接触で生じる痕跡を判断することが難しい。 細石刃の長さが 5 ㎝以下であれば、手持ちの固定具で剥離することが可能である。したがって、当該ブロックで出土している細石刃核の高さからは、この手持ち固定具が用いられたことが考えられる。 ただし、固定具は、目的とする細石刃の大きさ、すなわち細石刃核の大きさに合わせたものが必要である。たとえば、固定具の溝が細石刃核の高さよりも 1 ㎝以上長ければ、溝が邪魔になって押圧が難しくなり、逆に溝が 1 ㎝以上短かけば、剥離した細石刃が溝の縁に当たって折れ、掌に細石刃が刺さってしまう恐れがある(図22− 3 )。したがって、遺跡で出土した細石刃核の大きさを考慮すれば、 3 種類程度の溝の長さの固定具の存在が想定される(図22− 1 )。 一方で、石刃核に分類されている420には、最終剥離面から数えて 3 枚目に当たる、幅が1.1㎝で長さが 6 ㎝の、両サイドの稜線が直線的で、かつ並行、側面観も直線的な剥離面がある(図24− 1 )。細石刃核と同様の、剥離面末端のヒンジ(図24− 2 )と石刃核底部に小剥離と潰れ(図24− 3 )が観察されることから、この面の石刃は、押圧で剥離された可能性が考えられる3 )(図24− 4 )。石刃、あるいは 5 ㎝以上の長さの細石刃を押圧で剥離するためには、相当に強い力が必要であり、手持ち固定具のテクニークでは、強い押圧が難しいし、保持側がそのような強い力に耐えることができない。したがって、打面調整される以前の元々の高さも考慮すれば、この剥離面では、手持ち固定具よりも強い力を生み出すことができる細石刃核を地上に設置し、座位でT字杖状押圧具を使う地上置き固定具が用いられたことが想定される。 手持ち固定具の溝の長さは、細石刃核と石刃核の高さを考慮すれば、3 ㎝、4 ㎝、5 ㎝の 3 種類が考えられる。固定具の溝の幅は、細石刃核の幅と細石刃の幅を考慮すれば、細石刃核の幅よりも狭く、細石刃の幅よりも若干広いものとなる4 )(図22− 2 )。実験で用いた手持ち固定具の溝幅は、溝の長さが 3 ㎝のものが 8 ㎜、 4 ㎝と 5㎝のものが12㎜に設定した(図22− 4 )。また、地上置き固定具は、溝幅が15㎜で、溝の長さが 5 〜10㎝に調整できるものを用いた(図24− 1 )。いまのところ、当該遺跡の細石刃と同様の幅の細石刃が剥離できることから、今回実験で設定した固定具溝の幅は、妥当であると
考えられる。5−1−3 紅葉山メトード細石刃剥離のテクニーク 押圧具は、細石刃核の大きさや力の加え方で、いくつかの形態が想定される。たとえば、手持ち固定具で長さが 3 〜 4 ㎝の細石刃を剥離しようとすれば、鹿角の主幹部から削り出した長さが10〜20㎝で尖頭状の鹿角製棒状押圧具(図23− 1 )、長さが 5 ㎝の細石刃を剥離しようとすれば、肩当て杖状押圧具(図23− 2 )、地上置き固定具で剥離するのであれば、T字杖状押圧具や40㎝程度の長さの鹿角製棒状押圧具が想定される(図24− 2・3 )。もちろん、上述した押圧具のほか、牙歯を使用したものや、鹿角の枝角、木製グリップの付いた鹿角製の棒状の小片をはめた押圧具、より長い杖状押圧具など、異なる形態のものの可能性も想定され得る。 手持ち固定具の場合は、利き腕で押圧具を持ち、もう一方の手で細石刃核をはめた固定具を持つ(図25− 1 )。固定具の基本的な持ち方は、固定具に細石刃核を装着し、利き手の反対の手で固定具溝の背部を人差し指から小指に当て、親指と親指の根元で握り持つか、または同じく利き手の反対の手で逆手の状態で固定具溝の背部を掌に当て、人差し指や中指の根元で固定具の底部を支え、そして中指や薬指の中間や指先で細石刃核の背部や打面を押さえる、といった 2 つとなる。さらに、固定具を持つ手の甲を太腿の内側に当てると、保持の補助となるし、太腿を閉じるジェスチャーを加えることで押圧の助力となる。押圧は、押圧具を作業面上の稜線と同じ方向に据えて、押し掻くようなジェスチャーで行う。肩当て杖状押圧具を使う場合は、押圧具の基部を脇に入れて押圧具の上部を利き手でつかみ、脇腹を支点にして捻りを入れながら押すジェスチャーとなる(図25− 2 )。 地上置き固定具の場合は、作業面と対面するように細石刃核を設置し、T字杖状押圧具の基部の横木、あるいは鹿角製肩当て杖状押圧具の基部を腹部に当て、両手、
図20 打面縁辺と固定具溝との接触で生じる薄い剥離
55
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
図25 紅葉山型細石刃核で復原される細石刃剥離のテクニーク
図26 手持ち固定具と鹿角製棒状押圧具で製作した細石刃と細石刃核※写真右側は細石刃剥離の前半段階で剥離した細石刃で、左側が後半段階で剥離した細石刃。
図27 地上置き固定具とT字杖状押圧具で製作した細石刃と細石刃核※写真右側は細石刃剥離の前半段階で剥離した細石刃で、左側が後半段階で剥離した細石刃。
56
細石刃核をどう持つか(大場正善)
あるいは片手で押圧具の前半部分を押し込んで、押圧具全体を撓らせるようにするジェスチャーである(図25−3 )。このジェスチャーは、無理なく大きく加圧することができる。押圧具の材質には、硬さと弾力性が求められるし、押圧具の柄の部分は、少し湾曲させる必要がある。今回は、ツゲ製のものを用いた。 なお、この地上置き固定具を用いた押圧では、腹で押圧具を押し込むようなことは、まったくしないし、「胸圧」でもない。あくまでも、押圧具の腹部に当てた部分は、押圧の際の支点である。
以上、当該ブロックにおける、奥白滝Ⅰ遺跡における紅葉山メトードの細石刃剥離に用いられたテクニークは、考古資料と実験資料に残る痕跡との対比に矛盾はなく、基本的にペルグラン復原のL字状固定具の押圧テクニークが用いられた可能性が高いと考えられる(図26・27)。
5−2 峠下メトードに用いられたテクニーク5−2−1 峠下型細石刃核に残る痕跡 上白滝 8 遺跡Sb14〜19で出土している峠下型細石刃核は、石刃や剥片を素材とし、片面加工、あるいは半両面加工で、作業面からみた断面形がおもに逆D字状であり、一端にスポール剥離を施して細石刃剥離打面にした形態である。とくに注目されるのは、細石刃核の作業面と下縁のなす角度が120°前後に開き、前面角が60°前後になるものが多いこと、下縁が細石刃核の後端まで数㎝、長いものでは10㎝程度伸びていることである(図28− 1 )。 上述のL字状固定具は、細石刃核の底部が円錐形、あるいは作業面と底部が90°以下で交わっていれば、固定具の細石刃核を設置する部分にうまくはまるので、固定具溝と作業面を並行にして据えることができる(図21−5 を参照)。また、L字状固定具を用いた場合は、基本的に細石刃核の前面角が約90°となる。ただし、作業面と下縁のなす角度が90°以下の場合は、前面角が90°以下であってもL字状固定具に装着することができ、細石刃剥離が可能である。しかし、峠下型細石刃核の作業面と下縁の形態は、L字状固定具の細石刃核を設置する部分の形態と大きく異なっている(図28− 2 )。峠下型細石刃核は、作業面と下縁のなす角度が120°程度開いており、L字状固定具に細石刃核を固定することが難しく、したがって120°の角度に対応した異なる形態の固定具を想定しなくてはならない。 なお、上述したが、固定具なしや万力状固定具、 2 ・3 枚の板で挟む固定具、Y字状小枝固定具での場合は、そもそも峠下型細石刃核の形態のものを固定することができないし、またこれらの固定具での固定の場合、細石
刃核の前面角が約90°でないと押圧が難しい。 資料に残る痕跡を確認すると、細石刃核の上縁縁辺と下縁に微細剥離痕や擦痕が観察されることは、以前から指摘がある(安蒜1979)。細石刃核116には、下縁の作業面付近の 1 ㎝程度の範囲、しかも両面において、複数のステップを呈した微細剥離痕と縁辺の潰れが観察される(図29− 1 )。一方で、作業面の右側にあたる右上縁縁辺には、縁辺が鈍くなるような潰れが観察され、さらに潰れの前段階に施された、素材の腹面側に規則に並ぶ小剥離面が観察される(図30− 1 )。 下縁に観るステップを起こすような微細剥離痕は、並び方が不規則であるので、意図的に打撃した剥離痕であるとは考え難い。むしろ、下縁になにかある程度硬い物に当たって生じる潰れ(ステップは、力の方向が細石刃核の内側に向かっていたために起こった)であると考えられる。また細石刃剥離面の末端には、ごく薄いヒンジ
(図29− 2 )が観察されることからも、L字状固定具を用いたことで生じたように、細石刃剥離の際に固定具の一部が細石刃核の底部と接触していたことが考えられる
(図29− 3 ・ 4 )。 上縁縁辺の連続する小剥離面と潰れは、剥離の連続性から、固定具とは関連しない痕跡であり、むしろ意図的に縁辺を鈍くさせたことが考えられる(図30− 1 ・ 2 )。上縁縁辺を仔細に観察すると、縁辺に観る潰れは、ステップを起こした平坦な微細剥離面の集積であることが確認されるので、この潰れを生じさせた原因は、鹿角製ハンマーなどでの擦りが考えられる5 )(図30− 3 )。5−2−2 峠下メトードに用いられた固定具 そこで想定される固定具の形態は、固定具溝と底部支えが120°に交わり、底部支えの長さが 1 ㎝以上ある「く」字状を呈している(固定具①:図31− 1 )。固定具溝と底部支えのなす角度が120°であることから、作業面と固定具溝とが並行に据えることができ、かつ細石刃剥離後の細石刃核の前面角が60°前後になる。固定具溝の幅は、細石刃や最終細石刃剥離痕の幅が 4 ㎜前後であること、作業面の幅が 1 〜 2 ㎝であることから、 4 ㎜以上 1 ㎝未満であることが考えられる。したがって、今回の実験で使用した固定具は、溝の幅を細石刃の幅よりも余裕を持たせた 7 ㎜に設定した。また、溝の長さは作業面の長さを考慮して、2.5㎝に設定した。底部支えの長さは、下縁が潰れている範囲が 1 〜 2 ㎝であることから、2.5㎝に設定した。 右利きの場合、細石刃核と「く」字状固定具は、左手で保持することになる。持ち方は、L字状固定具と異なって、固定具溝の背部を人差し指以下の 4 本の指で覆うようにしてつかみ、上縁縁辺を親指の付け根付近に密着させて作業面を溝に押し込むようにし、親指で打面を押さえ付けるような持ち方となる(図34− 1 )。この持ち方は、
57
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
図28 峠下型細石刃核の形態と、L字状固定具の関係
図29 峠下型細石刃核の下縁と細石刃剥離痕末端に残る接触痕跡(縮尺は任意)
図30 峠下型細石刃核の上縁の調整痕と縁辺部の擦痕
58
細石刃核をどう持つか(大場正善)
細石刃核の細石刃剥離作業面からみた断面形が逆D字状の場合である。押圧は、地面に腰を下ろした姿勢、あるいは椅子などに座った姿勢で、股間付近の窪んだところに細石刃核を保持する手を、細石刃核が横になるようにして置き、短い鹿角製棒状押圧具の先端を右から押し込むようにするジェスチャーとなる(図34− 2 )。このとき、細石刃核を保持する手を太腿の内側で押してやれば、細石刃剥離の際の助力となる。 ただし、上記の固定具の場合、作業面の素材腹面、あるいは平坦面に接する部分を細石刃剥離するときに問題が生じる。同遺跡群旧白滝 5 遺跡Sb 1 〜13出土の資料になるが、平坦面と作業面が接する部分の細石刃剥離痕を観察すると、剥離の進行にブレは認められず、直線的な細石刃が剥離されている(図32− 1 :北海道埋文2008)。つまり、この部分を固定具溝に設置したときには、打面からみた細石刃核の長軸と固定具底部支えの長軸が交差してしまい、かつ底部支えから細石刃核がはみ出して、保持し辛くなってしまう(図33− 2 )。そのため、問題の部分から細石刃を剥離するときには、細石刃核を安定的に固定することができず、うまく細石刃が剥離できなくなってしまうことがある。考古資料には、細石刃核の平坦面の奥まで、細石刃剥離が進行しているものがあり、問題部分の剥離を可能にするための何らかの工夫があったことが窺われる。 この問題の改善策としては、この平坦面に接する部分を剥離するときに使う、別種の固定具を用意することである。その固定具とは、固定具を上から見たときに、溝の縁が底部支えの長軸に対して斜めに交差する、すなわち平坦面に接する部分を固定具溝に設置しても、細石刃核の長軸と底部支えの長軸が並行的になるように、「く」字状固定具の右側の固定具溝の高さを 5 ㎜程度減らしたものである(固定具②:図33− 1 の右・ 3 )。つまり、問題の部分を溝に設置したときに、打面からみて作業面が右肩上がりになり、その突出する右側に併せて固定具の右側の溝を低く設定している。したがって、この固定具を用いることによって、そして細石刃核の長軸と底部支えを同時に並行的に、細石刃剥離が細石刃核平坦面側に進行することが容易となる(図32− 2 )。5−2−3 峠下メトード細石刃剥離のテクニーク もし、断面形がD字状の細石刃核を左手で保持する場合は、断面形のトップ、すなわち細石刃核上縁縁辺が親指の付け根に密着しないために、細石刃核を安定的に固定することができなくなる(図35− 1 )。逆に、これを右手で保持するならば、右手掌に細石刃核の平坦面が密着し、親指の付け根付近に上縁縁辺が当たるので、安定した保持が可能となる(図35− 2 )。つまり、このことから、細石刃核の保持の仕方は、図34− 1 のような持ち方に限られていくし、峠下型細石刃核が逆D字状の断面形態を
呈している理由は、固定具と親指で細石刃核を挟んで持つのに適した形態をしていることが指摘される。なお、L字状固定具と同じ持ち方をした場合は、固定具の底部支えが斜めになっていることから、押圧の際に細石刃核が下にずり下がってしまうし、それに断面形の形態が、持ち方とあまり関係しなくなってしまう(図35− 3 )。 ところで、もし細石刃核の上縁縁辺が鋭い状態であった場合、押圧を加えたときに密着する親指の付け根付近を傷付けてしまう恐れがある。そのため、上縁縁辺をあらかじめ擦るなどして鈍くする必要がある。そのことから、考古資料に認められる上縁縁辺の小剥離面や潰れは、そのような理由であった可能性が考えられる。なお、手袋をしても、手袋の生地が邪魔をして作業が難しくなる。 したがって、峠下型細石刃核の形態と「く」字状固定具の形態、およびその持ち方は、相互に関連することが指摘できる。とくに、細石刃核の断面形は、製作者の細石刃を剥離する際の保持する手に対応すると考えられるのであり、逆に保持する手のもう一方の剥離具を持つ手も推定できることになる。押圧具を持つ手、すなわち利き手であり、つまりこの細石刃核の断面形を手がかりにすれば、細石刃を製作したヒトの利き手について推定することが可能となろう。上白滝 8 遺跡Sb14〜19で出土している峠下型細石刃核の断面形が、確実に判断できるもので、逆D字状が28点、D字状が 3 点であることから、当該ブロックで細石刃を製作したヒトびとは、右利きが優勢であった可能性が考えられる(図36)。 なお、以前より固定具痕であろうと指摘されてきた、平坦面側の打面と下縁から対向するようなかたちで入る小剥離や潰れ、あるいは 1 枚程度の平坦剥離といった、2 か所の痕跡から想定されている、上下に挟む固定具・固定法(安蒜1979)は、以下の理由から否定される。①上下で挟んだとしても、 2 点でしか支えられていないので、固定が安定しないこと。②平坦面上下にある痕跡が固定痕だとしても、固定のためには痕跡の剥離方向が一致しなくてはならないのであるが、互い違いになるものが多いこと。③そもそも、大きな剥離が生じるくらいの固定は、細石刃核の形態を変形させてしまうおそれがあるので、固定の仕方に問題があることである。今回の復原によって、下縁からの痕跡が固定具との接触痕、そして打面側の小剥離と潰れが、保持するときのケガ防止のための調整であると指摘できるが、打面からの 1 枚程度の平坦剥離については、技術的な理由については不明である。いまのところ、作業面形の修正などの理由が想定されるが、具体的な理由については、今後の課題としたい。 また、第32− 1 のように、峠下型細石刃核の中には、下縁に浅いノッチが入るものが散見される。実際に、「く」字状固定具を使用して下縁にノッチを施した細石刃核か
59
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
図31 峠下型細石刃核を固定する「く」字状固定具①
図32 細石刃剥離が平坦面にまで及んでいる峠下型細石刃核(左:北海道埋文2008に加筆)
図33 細石刃剥離の進行に対応した2種類の固定具
60
細石刃核をどう持つか(大場正善)
図34 「く」字状固定具を用いた細石刃剥離のテクニーク
図35 「く」字状固定具を用いる際の持ち方の検討
図36 上白滝8遺跡Sb-14~19出土の細石刃核の断面形(S=1/2:北海道埋文2004に加筆)
61
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
ら細石刃を剥離する際には、ノッチの作業面側の突出部が底部支えに引っかかることで、押圧時の細石刃核のズレを防ぐことができる。このノッチと 3 〜 4 章で挙げたテクニークとの関連性が認められないことからも、細石刃核の下縁に施されたノッチは、いまのところ「く」字状固定具を用いた押圧の際のズレ防止の役割であった可能性が考えられる。
6 .考 察
6−1 復原した固定具 以上、今回の復原において、紅葉山メトードによる細石刃剥離では、ペルグランが復原した手持ちL字状固定具と手持ち鹿角製棒状押圧具や杖状肩当て押圧具などが用いられたことが考えられる。そして、地上置きL字状固定具とT字杖状押圧具や鹿角製杖状押圧具も用いられた可能性が指摘される。復原したこれらの固定具は、考古資料と実験資料に現れている痕跡と矛盾がないのはもちろんのこと、製作のしやすさ、携帯するのに不便でないこと、そして復原した以外の固定具やほかの固定法について、いまのところ想定され難いことから、過去においても用いられていた蓋然性が高いと言えよう。 復原した固定具は、木製以外でも、管状骨の髄腔を利用すれば、簡単に製作することができる(ペルグラン・高橋2007)。ただし、骨製固定具は、保持した際に溝の中に細石刃核がめり込み、繊維に沿って縦に割れてしまい易いことが言える。現段階において復原研究が進んでいるフランス、そして有機質資料が豊富に発見されているシベリアと中国において、確認されていないことを鑑みれば、固定具の素材には、骨ではなく、加工しやすく、また細石刃剥離時に固定の際の握力に耐えられる、ある
程度硬さのある木が選択されていたことを示唆しているのかもしれない。復原した固定具の構造は比較的に単純な構造をしており、木を素材にして石器で十分に製作可能である。7,000〜9,000年前の段階の遺跡になるが、極北のジョホフスカヤ遺跡の資料(木村1999)のような細石刃石器群とともに木製資料が豊富に見つかっている遺跡から、今後、木製固定具が見つかる可能性があろう。
6−2 従来の細石刃剥離にかんする実験研究の問題とその改善策6−2−1 モノ作りの合理性 これまで民族事例やいくつかの細石刃剥離の実験研究を基に、押圧による細石刃剥離の多様なテクニークが想定されてきた。しかしその一方で、分析対象とする資料をモデルにした場合に、それらのテクニークを用いて、実際に細石刃を製作してみると、考古資料と矛盾した痕跡が生じるテクニークが多い。そして、無理なジェスチャーを用いたり、細石刃核が固定具に設置し辛かったり、設置に手間がかかったりと、石器を製作する上での合理性に問題がある、すなわち“作り難い”テクニークが多いことが判明した。 つまり、従来の実験研究では、“作り易さ”について十分に検討されてこなかったことが考えられる。一般的に、モノ作りでは、“作り易さ”を考慮し工夫するという、作る上での合理性が働く。この合理性が過去の石器作りでも同様に働いていたことを前提にすれば、復原するテクニークについても“作り易さ”に配慮する必要があったであろう(阿部2007)。また、合理性だけではなく、大沼・久保田(1992)が自然界で容易に入手することができる材料から、固定具・固定法を考案したように、当時の自然環境や生業といった、当時のコンテキストにも配慮する必要もある。したがって復原では、当時のコンテキス
図37 「く」字状固定具を用いて実験製作した実験資料
62
細石刃核をどう持つか(大場正善)
トでも手に入れることができる素材を用いて固定具や押圧具を作り、製作した固定具や押圧具の“使い易さ”を求め、かつ石器を作る“作り易さ”を追究していかなくてはならない。6−2−2 考古資料の把握と経験的知識の必要性 考古資料と矛盾する痕跡が実験資料に生じてしまうのは、実験する際に、モデルとなるべき考古資料の分析が十分でなかったこと、場合によっては、モデルとなる考古資料がないことが挙げられる。石材の種類によって硬さや脆さが違うために、力の加え方や力の強弱が異なるのは当然のこと、細石刃核の形状、とくに細石刃剥離作業面の前面角部分の形状の違いによっても、力の加え方や力の強弱が異なり、生じる痕跡にも違いが表れてしまう。つまり、考古資料に用いられたテクニークを復原するには、考古資料と同じ石材を用いて、同じメトードに従って実験をすることが必須である。したがって、復原実験を行うためには、考古資料のメトード復原が欠かせないのである。さらに、実験では、メトードに従うことはもちろんのこと、各工程に残された打点やバルブ、リング、フィッシャー、剥離面表面の形状、波打ち方、上縁の潰れなどといった痕跡にも注意したテクニークを用いなければならない。つまり、痕跡から道具とジェスチャーを想定するために、痕跡にたいする経験的な知識が必要となるのである。 実験に用いるテクニークについては、想定され得る限りの実験を行う必要がある。しかし、直接打撃で剥離した細石刃が対象とする考古資料と全く矛盾した、あるいは間接打撃をするのに細石刃核を保持するのに多々問題があったように、考古資料に残る痕跡を仔細に検討することで、数ある細石刃を剥離するテクニークの中から絞ることが可能である。逆に言えば、実験で用いるテクニークは、痕跡から想定されるいくつかのテクニークである。研究の経済性からすれば、想定され得ないテクニークでの実験は、対照実験として数例行うとしても、行うことに大きな意味はない。6−2−3 考古資料に即した復原 白滝遺跡群では、ペルグランが復原したL字状固定具だけでなく、「く」字状固定具が存在していた可能性が高い。本遺跡群にみる多様性からは、細石刃剥離メトードごとに特有の固定具があった可能性が考えられる。つまり、L字状固定具が合理的であるからといって、すべての資料にたいして安直に当てはめることは、誤った復原になりかねないのである。復原を行う上では、個々の細石刃の形態、そして細石刃核などに残る痕跡について検討し、実験研究で得られた痕跡にかんするデータとの照合を経た上で、対象とする資料に用いられた固定具が、どのような固定具であったのかを十分に検討しなくてはならない。そして、石器製作技術の復原を行っていくた
めには、検討に耐えうる実験データの蓄積が、課題として残される。
6−3 保持を復原することの意義 峠下型細石刃核は、固定具に合わせ、かつ“持つ”ことを工夫してかたち作られていたと考えられる。作業面と細石刃核下縁のなす角度が120°付近に開いていること、掌の切傷防止のために細石刃核上縁を潰していること、保持を効果的にするために、右利きなら保持する左手掌側に平坦面を、そして上縁を親指の付け根付近に密着するように設定していることといった、実際の製作に基づいたこれらの指摘は、従来の型式学や「技法」研究では、指摘されてこなかった。むしろ、型式学的な研究では、峠下型細石刃核が“持つ手”を意識してかたち作られていることを知ることができなかったのではないだろうか。テクニークを復原することの意義の一つとしては、石核のかたちや調整剥離について、製作時に持ち易くするための工夫といった、石核や石器素材を“保持する”ことの視点から、剥離面や形態自体の意味を見出すことにある
(大場ほか2006)。 また、“持つ”ことを意図して細石刃核が製作されているということは、メトードの中に保持することを意図した工程が組み込まれているということである。逆にメトードの中に保持を意図した工程が組み込まれているということは、剥離具や剥離具を持つ手のこともメトードの中に考慮されていることが、当然ながら考えられ得る。つまりこの場合、メトードとテクニークは、切り離せな
表1 北海道内出土峠下型細石刃核の断面形の集計
63
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
い関係であると言える。したがってこのことは、技術の伝承や技術の伝播を考える際に、メトードとテクニークの両者がセットになって伝わらない限り、意味がないことを意味している。メトードと固定具、押圧具、製作時のジェスチャーのうち、どれか一つでも欠けると、考古資料と同じ細石刃・細石刃核は出来上がらない、と言っても過言ではない。ここに動作連鎖の概念で考古資料を観て、そのデータを次の段階の議論に組み込んでいく意義が生じるのである。もちろん、「細石刃」が直接打撃でも間接打撃でも押圧でも剥離できるように、ア・プリオリにメトードとテクニークを固定的に捉えるのではなく、分析する上ではメトードとテクニークを分けて考えなくてはならない。 峠下型細石刃核の断面形は、製作者の利き手が判断できる良好な資料である。過去に、ホロカ型彫刻刀形石器の刃部に残る擦痕(加藤ほか1969)、荒屋型彫刻刀形石器の彫刻刀面作出際の保持(山中1982)、同石器の刃部の傾き(桜井1986)、磨製石斧に残る擦痕の傾き(阿部1988)、断面が扁平な長楕円形のハンマーに残る敲打痕
(竹岡1991)などから、石器製作者、あるいは石器使用者の利き手が指摘されてきた。しかし、この峠下型細石刃核の断面形からの利き手推定は、細石刃を製作したヒトに限られるとは言え、今回復原したテクニーク以外の方法が想定され難いという実験結果が示すように、より蓋然性ある推定方法であると言える。 上白滝 8 遺跡峠Sb14〜19に峠下型細石刃核は、 9 割近くが右利き用の細石刃核であり、当該地点に細石刃核を残したヒトびとは、右利きが優勢であった。また、北海道内における18遺跡から出土した170点の峠下型細石刃核の断面形の比率は、逆D字状が約93%、D字状が約7 %となる(表 1 :日本考古学協会1999年度釧路大会実行委員会編1999を基に作成)。したがって北海道内において峠下メトードにより細石刃を製作していたヒトびとは、右利きが主体であったことが想定される。ただし、峠下メトードにおける左利きの比率は、現代の左利きの人が10〜20%いるのにたいして若干低い傾向にある。しかしこれについては、このメトード、およびテクニークの点において、比較的にシステマティックな製作技術(動作連鎖)であることを考慮すれば、製作者は「左手に固定具と細石刃核を、右手に押圧具を持たなくてはならない」とするといった、当時としての社会的な慣習が強かったことが考えられる。つまり、今を生きるわたしたちの80〜90%に達するとも言われる右利き優勢の社会は、少なくとも北海道の峠下メトードで細石刃を作っていたときにまで、さかのぼれる可能性があるのである。 今後、ほかの石器製作技術や、トゥールに残る使用痕から判断される操作方法などの分析を行い、このブロックに石器を残していったヒトびとが右利き優勢であった
ことの蓋然性を詰めていきたい。
[付 記] 2009年、J.ペルグラン氏が2009年度日本考古学協会山形大会に招聘されたおりに、峠下メトードの「く」字状固定具を用いた押圧テクニークについてご意見を伺ったところ、ペルグラン氏より厳しいご指摘を受けた(山中2011)。以来、このことを真摯に受け止め、「解釈認識」を避けるべく検討を重ねてきた。しかし、いまのところ峠下メトードでは、「く」字状固定具を用いた押圧でなければ、細石刃を剥離することが難しい。少なくとも、L字状固定具では、峠山型細石刃核の作業面と下縁のなす角度の問題を解決しない限り、細石刃を剥離することができない。したがって、本稿で示したテクニークがもっとも蓋然性のある復原案として提示し、今後も対案について検討するとともに、大方の批判を受けたい。
謝 辞 本稿を執筆するにあたり、東北学院大学文学部教授・佐川正敏先生には、ご支援とご指導をいただき、また日々ご教示をいただいております。また、フランス国立科学研究所教授・J. ペルグラン先生、京都大学名誉教授・山中一郎先生、郡山女子短期大学准教授・會田容弘先生、粟田薫氏、冨井眞氏、高橋章司氏には、動作連鎖、及び石器技術学についてご指導とご意見をいただきました。遠軽町教育委員会の松村愉文氏、瀬下直人氏、熊谷誠氏、北海道埋蔵文化財センターの直江康雄氏、坂本尚史氏、鈴木宏行氏からは、白滝遺跡群の資料閲覧のご配慮、ならびに本稿にかんするご意見とご教示をいただきました。八ヶ岳旧石器研究グループ・堤隆氏からは、2013年 9 月『シンポジウム 日本列島の細石刃石器群の起源』において製作実演と誌上発表の機会をいただきました。西村誠治氏からは、K. アッカーマン氏の製作の様子の写真と動画を提供していただきました。山田しょう氏からは、英文タイトル、および英文要旨の添削をしていただきました。末筆ながら、記して感謝申し上げます。 本稿は、2009年『日本旧石器学会 第 7 回講演・研究発表シンポジウム予稿集 南九州の旧石器時代石器群―「南」の地域性と文化の交錯―』「押圧による細石刃剥離のための押圧具と固定具の復原―北海道白滝遺跡群の細石刃技術にかんする技術学的分析―」、および2009年度提出博士課程学位『東北アジアの石刃技術、細石刃技術、両面加工技術の総合研究―石器製作技術における新しい研究法・石器技術学の構築―』「第Ⅳ章細石刃技術の復原 第 1 節 北海道白滝遺跡群の細石刃技術」、および2013年『シンポジウム 日本列島の細石刃石器群の
64
細石刃核をどう持つか(大場正善)
起源』「動作連鎖の概念に基づく技術学における石器製作実験―意義と必要性とその方法について―」を基に、加筆・修正を行って構成している。また、筆者が受給した平成20年度日本科学協会笹川科学研究助成「東北アジアの先史時代における石器製作技術に関する技術学研究―石器製作実験を応用し、ヒトのジェスチャー(動作連鎖)の復原を目指す細石刃技術の研究―」(研究番号20−139)、および文部科学省・大学院教育改革支援プログラム『遺跡・遺物資料処理技能開発の日中間共同推進』の援助による研究成果の一部が含まれている。
註
1 )両者とも、硬さや粘りについて大きな差異はない。しかし、割れの進み方は、若干異なる。西アトリエ産の漆黒の黒耀石は、質的に均一に近いので、割れの進み方が思う通りにコントロールし易い。一方で、東アトリエ 2 産の黒耀石は、黒や赤、茶の部分が混在しているために不均質であり、そして節理も発達しているので、割れのコントロールが難しい。それぞれの産地は距離的にあまり離れていないが、同じ「黒耀石」であっても剥離性が異なっていることには、注意しなくてはならない。
2 )また、本稿では、押圧具を用いて押し込む圧力で石片を割るテクニークを、“押圧”と表記している。従来は、この種のテクニークを「押圧剥離」と表記することが多い。しかし、「直接打撃」や「間接打撃」がジェスチャーのみを表しているのにたいして、「押圧剥離」は、ジェスチャーを指す「押圧」のあとに、剥がれる現象と剥がす行為を示す「剥離」が続く。仮に、上記のテクニークを指す用語をジェスチャーと「剥離」を組み合わせた用語に統一するならば、「直接打撃剥離」、「間接打撃剥離」となる。しかし、「剥離」と表記しなくても、テクニークを指す用語として十分であり、現象と行為を示す「剥離」は必要ない。そもそも、行為としての
「剥離」は曖昧であり、具体的なジェスチャーを意味していない。それに、いちいち「〜剥離」と表記するには、煩わしさを感じる。したがって本稿では、「押圧剥離」ではなく、ジェスチャーのみを示す“押圧”をこの種のテクニークを指す用語として用いることとする。
3 ) 細石刃核作業面に凹凸があった場合には、作業面を一気に整えるために、厚手の細石刃、あるいは石刃を剥離することがある。その場合は、押圧だけでなく、ほかのテクニークを用いることがある。
4 ) 固定具の溝の幅よりも、幅広い細石刃は剥離できないので、この固定具の溝の幅は、細石刃の幅を規定することになる。
5 )遠軽町教育委員会の松村愉文氏と瀬下直人氏のご教示に拠れば、赤井石山付近では、ハンマーに適した円礫があまり採取できないと言う。このことは、テクニークが周辺環境に規定されてしまうこともあり得ることを示している。
引用・参考文献
阿部朝衛 1988「縄文人のきき手と二分原理」『法政考古学』13:1 −13
阿部朝衛 2007「旧石器時代人の利き手研究法」『日本考古学』23:1 −18
会田容弘 2011「日本旧石器研究の新たな展望へ向けて―㈳日本考古学協会2009年度大会(山形大会)分科会Ⅰの記録」『山形考古』
9( 3 ): 8 −15 阿子島香 1983「ミドルレンジセオリー」『考古学論叢』1 :171−
197安蒜政雄 1979「 2 石器の形態と機能」『日本考古学を学ぶ( 2 )
―原始・古代の生産と生活』大塚初重・戸沢充則・佐原 真編、17−39頁、東京、有斐閣選書
ベルナール,クロード 1970『実験医学序説』(三浦岱栄訳)、395頁、東京、岩波文庫
ベルナール,クロード 2008『実験医学の原理』(山口知子・御子柴克彦訳)、460頁、東京、丸善プラネット
Binford, S. R. and Binford, L. R. (editor.) 1968 New Perspectives in Archaeology, 373p., Aldine, Chicago.
ボルド, フランソワ 1971『旧石器時代』(芹沢長介・林謙作訳)、303頁、東京、平凡社
Clark, J. E. 1980 Obsidian in Mesoamerica [ Announcement and Invitation], Flintknapper’s Exchange 3 (3): 3
Clark, J.E. 1982 Manufacture of Mesoamerican Prismatic Blades: An Alternative Technique, American Antiquity 42 (2): 355−376
Crabtree, D. E. 1967 Notes on Experiments in Flintknapping: 4 –Tools Used for Making Flaked Stone artifacts, Tebiwa 10 (1): 60−73
Crabtree, D. E. 1968 Mesoamerican Polyhedral Cores and Prismatic Blades, American Antiquity 33 (4): 446−478
Flenniken, Jefflrey. j. and Firth, Kenneth, G. 2003 Handheld Prismatic Blade Manufacture in Mesoamerica, Mesoamerican Lithic Technology ―Experimentation and Interpretation, pp. 98−107, edited by Kenneth G. Hirth, The University of Utah Press, Salt Lake
北海道埋蔵文化財センター 2002『白滝遺跡群Ⅲ』、543頁、江別北海道埋蔵文化財センター 2004 白滝遺跡群Ⅳ』、485頁、江別北海道埋蔵文化財センター 2008『白滝遺跡群Ⅸ』、427頁、江別Holmes, W. H. 1919 Handbook of Aboriginal American―Part 1
Introductory the Lithic Industries―, 372p., Ohio Historical Societyイニザン, マリー, ルイーズ 1995「後期旧石器のアジアに起源を
もつ押圧石刃剥離技術」『東京都埋蔵文化財センター研究紀要』14: 111−123
イニザン, マリー, ルイーズ・ロッシュ, ヘレン・ティキシエ, ジャック 1998『石器研究入門』(大沼克彦ほか訳)、146頁、東京、クバプロ
加藤晋平・桑原 護 1969『中本遺跡―北海道先土器遺跡の発掘報告―』、60頁、東京、永立出版社
Kaelin, C. and Pigeot, N. , Ploux, S. 1992 L’ethnologie Préhistoreque, La Recherche 23: 1106−1116
木村英明 1999『シベリアの細石刃石器群( 2 )』平成10年度科学研究費補助金重点領域研究( 1 )成果報告書、48頁、佐倉
ルロワ=グーラン 1973『身ぶりと言葉』(荒木 亨訳)、413頁、東京、新潮社
メイヤーズ, チャールズ 2005「付録 銃器及び工具痕鑑定(異同識別)入門」『隠れた証拠―法科学事件ファイルから―』(内山常雄訳)、195−210頁、東京、立花書房
宮田栄二 1998「細石刃の製作技法」『九州の細石刃文化―九州島における細石刃文化の石器と技術―』、35−40頁、福岡、九州旧石器文化研究会
仲田大人 2010「関東地方の細石刃石器群」『旧石器考古学』73:13−24
日本考古学協会1999年度釧路大会実行委員会編 1999『海峡と北の考古学―シンポジウム・テーマ 1 資料集Ⅰ』、364頁、釧路、
65
旧石器研究 第 10 号(2014 年 5 月)
釧路市埋蔵文化財調査センター大場正善 2007「<紹介>ペルグラン石器製作教室に参加して―フ
ランス技術学研究にふれて―」『古代文化』58( 4 ):152−159 大場正善 2008「日本では「石器作り」をどのようにイメージしてき
たか―図版や展示における石器作りのあるべき姿―」『アジア文化史研究』8 : 1 −19
大場正善 2009「押圧による細石刃剥離のための押圧具と固定具の復原―北海道白滝遺跡群の細石刃技術にかんする技術学的分析―」『日本旧石器学会 第 7 回講演・研究発表シンポジウム予稿集 南九州の旧石器時代石器群―「南」の地域性と文化の交錯―』、23−28頁、東京、日本旧石器学会
大場正善 2012「動作連鎖の概念に基づく技術学のおけるテクニークの同定法―山形県高瀬山遺跡出土杉久保型ナイフ形石器群の石刃剥離のテクニーク同定を例に―」『第26回東北日本の旧石器文化を語る会予稿集』、59−68頁、仙台、東北日本旧石器文化を語る会
大場正善 2013「動作連鎖の概念に基づく技術学における石器製作実験―意義と必要性とその方法について―」『シンポジウム 日本列島の細石刃石器群の起源』、74−80頁、長野、八ヶ岳旧石器研究グループ
大場正善・小野章太郎・安倍奈々子 2006「宮城・福島の石刃石器群」『第20回東北日本の旧石器文化を語る会 東北日本の石刃石器群』92−121頁、山形、東北日本の旧石器文化を語る会
大竹憲昭 2008「日本列島尾における旧石器時代遺跡数」『日本旧石器学会 第 6 回講演・研究発表シンポジウム予稿集 日本列島の旧石器時代遺跡―その分布・年代・環境―』、32−35頁、東京、日本旧石器学会
大沼克彦 1998「日本旧石器時代の細石刃製作作用岩石加熱処理に関する研究」『日本旧石器時代の細石刃製作作用岩石加熱処理に関する研究』平成 8 年度〜平成 9 年度科学研究費補助金(萌芽的研究)研究成果報告書、 5 −32頁、大沼克彦編、町田
大沼克彦 2002『文化としての石器づくり』、181頁、東京、学生社
大沼克彦・久保田正寿 1992「石器製作技術の復元的研究―細石刃剥離方法の同定―」『ラフィダーン』13: 1 −26
Pelegrin, J. 1994 Lithic technology in Harappan times, South Asian Archaeology 2: 585−598
ペルグラン,ジャック・高橋章司 2007「旧世界の石刃製作技術―中米の黒曜石製石器製作技術への見通しと適用―」『古代文化』58( 4 ):110−130
ペルグラン,ジャック・山中一郎 2007「押圧剥片剥離の実験研究―最少から最大へ―」『古代文化』58( 4 ): 1 −16
Pelegrin, J. 2012 New Experimental Observations for the Characterization of Pressure Blade Production Techniques, in The Emergence of Pressure Blade Making: From Origin to Modern Experimentation, edited by P. M Desrosiers, pp. 465−500, New York, Springer
桜井準也 1986「旧石器時代人の利き腕」『慶応義塾大学考古学研究会報告』3 :13−20
佐々木高明編 1991「細石刃作り」『日本の歴史① 日本史誕生』、58頁、東京、集英社
関口昌和 2003 石器mode 〜旧石器時代の実験考古学http://members2.jcom.home.ne.jp/s−mode/、2013年11月20日引用
芹沢長介 1986『旧石器の知識』、180頁、東京美術、東京芝 康次郎 2013「九州における初期細石刃石器群の形成過程」」『シンポジウム 日本列島の細石刃石器群の起源』、38−43頁、
長野、八ヶ岳旧石器研究グループTabarev, A. V. 1997 Paleolithic Wedge−shaped Microcores and Experiments
with Pocket Devices, Lithic Technology 22 (2): 139−149橘 昌信 1981『大分県上下田遺跡発掘報告書』、43頁、別府、別
府大学付属博物館高倉 純 2013「北海道における押圧細石刃剥離技術の出現」『シ
ンポジウム 日本列島の細石刃石器群の起源』、47−56頁、長野、八ヶ岳旧石器研究グループ
高倉 純・中沢祐一 1999「北海道―旧石器時代石器群研究の課題―」『石器文化研究―岩宿発掘50周年記念 日本旧石器時代研究50年と今後の展望―』7 : 1 −10
竹岡俊樹 1991「旧石器時代の石器分析からみた左右差の起源と発展」『左右差の起源と脳』久保田競編、117−142頁、東京、朝倉書房
Titmus, G. L. and Clark, J. E. 2003 Mexica Blade Making with Wooden Tools −Recent Experimental Insights−, Mesoamerican Lithic Technology ―Experimentation and Interpretation, edited by Kenneth G. Hirth, pp. 72−77, The University of Utah Press, Salt Lake
Tixier, J. 1967 Procédés d’anaiyse et questions de terminologie concernant l’Etude des ensembles industriels du paléolithique récent et de l’ épipaléolithique dans l’Afrique du Nord−Ouest’, Background to Evolution in Africa, edited by W.W. Bishop and J.D. Clark, pp. 771−820, Chicago
鶴丸俊昭 1981「先土器文化の遺跡」『北見市史 上巻』北見市史編さん委員会編、347−446頁、北見、北見市役所
堤 隆 2013「石器群の小形化・細石器化と細石刃石器群成立へのイノベーション」『シンポジウム 日本列島の細石刃石器群の起源』、70−73頁、長野、八ヶ岳旧石器研究グループ
山中一郎 2001「石器研究法に革新を」『季刊考古学―前期旧石器文化の諸問題―』74:70−71
山中一郎 1982「荒屋遺跡出土の彫器―型式学的彫器研究の試み―」『考古学論考 小林行雄博士古希記念論文集』小林行雄博士古稀記念論文集刊行委員会編、 5 −40頁、東京、平凡社
山中一郎 2004「考古学における方法の問題」『郵政考古紀要』35:1 −37
山中一郎 2005「新堂廃寺出土瓦の技術学的検討」『新堂廃寺・オガンジ池瓦窯出土瓦の研究』、 5 −15頁、京都、京都大学総合博物館
山中一郎 2006「石器技術学から見る「石刃」」『第20回東北日本の旧石器文化を語る会 東北日本の石刃石器群』、13−25頁、山形、東北日本の旧石器文化を語る会
山中一郎 2007「<研究ノート>「動作連鎖」の概念で観る考古資料」『古代文化』58( 4 ):30−36
山中一郎 2009a「動作連鎖の概念を巡って」『日本考古学協会2009年度山形大会研究発表資料集』、 3 −16頁、山形、日本考古学協会
山中一郎 2009b「第Ⅰ部 瓦研究の新方法」『瓦研究の新方法―富田林・新堂廃寺瓦塼類資料の研究から―』、 3 −14頁、京都、京都大学総合博物館
山中一郎 2010「「ミドルレンジ」そして「動作連鎖」」『遠古登攀―遠山昭登君追悼考古学論集―』、453−460頁、京都、遠古登攀刊行会編
山中一郎 2011「ジャック・ペルグラン先生 山形再訪 要請・同行記」『山形考古』9( 3 ):217−221
山中一郎 2012「型式学から技術学へ」『郵政考古紀要』54: 1 −41
66
細石刃核をどう持つか(大場正善)
How to Hold a Microblade Core: Technological Analysis of Microblade Assemblages at the Oku-Shirataki I and Kami-Shirataki 8 Sites
Based on the Concept of Chaînes Opératoires
Masayoshi OBA
Based on the concept of chaînes opératoires, this report aims at replicating Late Paleolithic microblade production techniques used in the Momijiyama Méthode at the Oku-shirataki I Site and the Tohgeshita Méthode at the Kami-shirataki 8 Site (Engaru Town, Hokkaido). The assemblages are rich in conjoined materials made of obsidian that allow for clear identification of surface traces left by the microblade production.
First, surface traces and morphological features produced on microblades by direct percussion, indirect percussion and pressure flaking were examined in detail through experiments, which suggested that the pressure flaking was probably used in the two méthodes. In addition, the straightness and the regularity in shape of the microblades suggests a use of some kind of device-like holder for a microblade core.
In the next stage, eight series of experiments were conducted to test the practicality of the use of a holding device, and a technique using a L-shaped grooved device, invented by Jacques Pelegrin, turned out to be the most reasonable.
Detailed analysis of materials produced by the Momijiyama Méthode at Oku-shirataki I confirmed the use of an L-shaped device was highly likely. On the other hand, for the Tougeshita Méthode at Kamishirataki 8, the use of an L-shaped device was found to be difficult, as the angle between the working surface and the bottom edge of an archaeological microblade core does not match that of L-shaped device.
Therefore, I invented a wide open 120 degree V-shaped device, which led to the successful reproduction of the miroblades and traces of the device found on the archaeological materials.
The inferred use of a V-shaped device combined with the cross sectional shape of a Tougeshita type microblade cores can reveal with which hand the kapper held the device, and accordingly, which hand was the knapper’s dominant hand that held a pressure tool.
The analysis of 170 Tougeshita type cores including those from Kami-shirataki 8 indicated that over 90% were right-handed, which goes beyond the modern average. This suggests a presence of a social tradition for the dominant use of right hand.
Keywords: Chaînes opératoires, Lithic technology, Experimental archaeology, Méthode , Technique, Pressure flaking, Momijiyama Méthode, Tougeshita Méthode, L-shaped grooved device, V-shaped grooved device, Dominant hand
米盛裕二 2007『アブダクションー仮説と発見の論理』、260頁、東京、勁草書房
吉田 亨 2005『破断面の見方―破面観察と破損解析―』、230頁、東京、日刊工業新聞社
Whittaker, J.C. 1994 Flintknapping−Making &Understanding Stone Tools−,341p., Texas, University of Texas