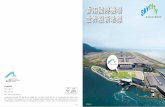(Ogura 2015a) 中世後期・近世カシミールにおける...
Transcript of (Ogura 2015a) 中世後期・近世カシミールにおける...
73
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
中世後期・近世カシミールにおける
支配の正統性と宗教アイデンティティ
小倉 智史*
Political Legitimacies and Religious Identities
in Late Medieval and Early Modern Kashmir
OGURA Satoshi
Abstract
Before the annexation of Kashmir to the Muġal Empire in 1586, two Muslim dynasties, the Šāhmīrid (1339–1561) and the Čakid (1561–1586) ruled the region. Under the rule of these two dynasties, Sanskrit was used as the languages of cultural activities—in addition to Persian. As is well known, the eighth sultan of the Šāhmīrid Zayn al-‘Ābidīn (r. 1418/1420–1470) promoted the translation of Sanskrit classics into Persian and revived the tradition of Sanskrit historiography. Surely the Šāhmīri court had both some Pandits who were skilled in Persian and some Muslim intellectuals who had knowledge of Sanskrit. Moreover, the presence of a bilingual document and bilingual inscriptions of tombstones suggests that such multilingual literacy came to be spread among the public to a certain extent.
In the linguistic cosmopolitanism of Kashmir of the period, Muslim rulers of Šāhmīri sultanate proclaimed multiple political legitimacies depending on languages. The Sanskrit inscriptions and texts narrate their Indic legitimacy, while the numismatic sources which have Arabic and Persian phrases attest that they were orthodox Sunni rulers.
As long as the author perused utilizable sources, it seems that both Muslims and non-Muslims who had multilingual literacy were aware of the difference of religions. A Muslim chronicler, on the one hand, notwithstanding his use of Sanskrit text as primary sources, clearly did not accept non-Islamic religions. A Brahman who was skilled in Persian, on the other hand, regarded Islām as a true religion and recognized the importance of Qur’ān and Ḥadīṯ. His view seems to represent a sort of “Religious Pluralism.”
* 日本学術振興会特別研究員
74
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
神よ!希望の蕾を咲かせ給え。
永遠の楽園にある一輪の花を示し給え。
その蕾という唇の微笑みと花の飾りによって我が庭園を[飾り給え]。
[その花の]芳香によって我が鼻を[満たし給え]。
―――『ユースフとズライハー』[YZ: 578]1)
神よ!恩寵という蜜を備えた希望の蕾を咲かせ給え。
その蕾から生じた望ましく美しい果実を私に与え給え。
今日まさにその花によって私の心という庭を美しく飾り給え。
その[花の]高潔なる芳香によって、私の体を満たし給え。
―――『カターカウトゥカ』[KK: 1. 4–5]2)
はじめに
本稿で扱うのは中世後期から近世、すなわち 14 世紀から 17 世紀前半にかけてのカシミー
ル地方である。カシミールはベンガル・パンジャーブ・スィンドと並ぶムスリム多住地域で
あり、1891 年にイギリスが行ったセンサスによれば、域内人口の実に 93%をムスリムが占
めていた[Lawrence 1895: 302; 井狩 1993: 246–247]。20 世紀後半にはムスリムの割合が更に
増加しており、95%を超えているという[Sanderson 2009]。域内に数%残る非ムスリムの構
成も南アジアの他の地域とは大きく異なり、ほぼバラモンのジャーティに属する人々によっ
て占められている。すなわち今日のカシミールの社会は、大多数のムスリムとごく少数のバ
ラモンによって成り立っている。
ムガル朝にカシミールが併合される前に、同地にはシャーミール朝(1339–1561)、チャク
朝(1561–1586)という 2つのムスリム地方王朝が興った。この両王朝の支配下において、住
民のイスラーム化が進んでいったと考えられている。
ある社会の「イスラーム化」の歴史を考えるにあたって気をつけなければならないのは、
その過程がムスリムを支配者とする王朝が立ったことによって、被支配者である住民がイ
スラームに改宗する、というような単線的なものではないということである。真下裕之は
中世・近世の南アジア史において、(1)テュルク人の政治的覇権、(2)ペルシア語文語文化
の進展、(3)社会のイスラーム化の 3つのプロセスを混同せぬよう注意を促している[真下
2007a: 103]。例えば一人の人間が複数の宗教を別個のものと認識しつつ同時に信仰すること
はそう簡単ではないが、複数の言語を習得し、運用することはそれより遥かに容易である。
75
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
そのため、ムスリムによってもたらされた言語であるペルシア語を習得しつつも、イスラー
ムには改宗せずに旧来の信仰を維持する人々が現れる余地を残すことになる。カーヤスタと
呼ばれる書記ジャーティの人々がその一例である。そして中世後期のカシミールにおいては
その逆の例、ムスリムが本来的には異教徒の言語であるサンスクリットを習得した例も見ら
れる。ペルシア語を習得した非ムスリム、サンスクリットを習得したムスリムが共生した当
時のカシミール社会状況を、ここで Linguistic Cosmopolitanismと呼んでおこう。そのような
社会にあって、支配者たるムスリムの君主たちはどのように自らの支配の正統性を主張した
のだろうか。また多言語を操った人々は、自らの宗教のアイデンティティを、そして異教徒
の信仰をどのように理解していたのだろうか。本稿はこの問題について筆者がこれまでに得
た知見をまとめたものである。まず第 1節でムスリム王朝成立以前のカシミールにおける文
化・宗教の状況を見て、続く第 2節ではシャーミール朝、チャク朝史を概説する。そして第
3節ではシャーミール朝時代の Linguistic Cosmopolitanismの実相、4節では支配の正統性の
主張、5節では多言語運用者の宗教アイデンティティの諸相を論じる。
1. ムスリム王朝成立以前のカシミール
1-1. 地域アイデンティティと超域文化への帰属意識
南アジアの北西端に位置するカシミール地方は、ヒマラヤ・カラコルムという 2つの山
脈に囲まれたその地勢ゆえに、北インド平野部の諸政体からの強い政治的独立性を保って
いた。7、8 世紀に同地を訪れた玄奘や悟空は、カシミール盆地へと至る諸道の峠に関所が
設置されていたことを伝えている[大唐西域記 : 125]。この峠において交通を監視する機構
は、19 世紀の終わりまで実に 1000 年以上にわたって維持されていた[Slaje 2012a: 11]。カ
シミール地方が北インド平野部に興った王朝の版図の一部になったのは、1586 年のムガル
朝への併合が歴史上初めてのことであり、それまではカシミール盆地内、主として現在の
スリナガル周辺に主邑を置いた地方王朝がいくつも興亡し、同地を支配してきた。他方カ
シミールは古代から中世前期にかけて、ヴァーラーナスィーと並ぶ伝統的学問の中心とし
ての地位を保ち[Alberuni: 1, 173; 井狩 1993: 248]、南アジアの他地域との学術的な交流が
盛んであった。例えば中世前期を代表するシヴァ教の学匠アビナヴァグプタ(ca. 975–1025)
の許には、その教えを請わんと南インドからも弟子たちが訪れていた。このことは彼の著
作の写本が遥かタンジャーヴールやティルヴァナンタプラムで発見されていることからも
76
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
裏付けられる[川尻 2009]。
そのような地理的・政治的・文化的環境にあって、同地に住む人々の間に「カシミール」
という地域アイデンティティが現れたのは存外に早い。8世紀頃に成立したと見られるプ
ラーナ文献『ニーラマタ・プラーナ』がそのような地域アイデンティティを表明する一つの
作品である。この作品はカシミールの風土記とでもいうべきものであり、その内容はカシ
ミール盆地やその中を流れる河川の縁起譚や、シヴァ教、ヴィシュヌ教、竜神信仰にまつわ
る諸聖地の賞賛、儀軌の説明からなる。『ニーラマタ・プラーナ』はカシミールの地域性が
色濃く現れた作品であるが、興味深いのはその冒頭部である。複数の伝承が入れ子になって
いる同作の冒頭において、無名の著者はカシミールの王が何故バーラタ戦争に参加しなかっ
たのか、その理由を語っている。つとに知られているように、『マハーバーラタ』において
カシミールの王がバーラタ戦争に参加したことは一切言及されていない。『マハーバーラタ』
はいわゆるヒンドゥー教において最大の聖典とでも言うべき作品であり、その中にカシミー
ルの王が登場しないことは、インド古典文化の中核たるマディヤデーシャと同地との繋がり
の弱さを意識させる。そのため、地理的には孤立した辺境にありつつ、高い文化水準を誇っ
た地であるカシミールの人々は、このようないささか屈折した形でインドの大伝統との繋が
りを主張しなければならなかったのである[井狩 1993: 251–253]。
『ニーラマタ・プラーナ』において語られる「インド」という超域伝統への帰属意識は、第
二ローハラ朝(1101–1320)のジャヤシンハ(r. 1128–1155)治下である 1148 年に編纂された、
カシミールの王統叙事詩『ラージャタランギニー』にも継承されている。同作品の著者カル
ハナは、カシミール最初の王であるゴーナンダ 1世をバーラタ戦争の時代に在世したとす
ることで、カシミールの歴史の古さを『マハーバーラタ』と同程度のものとし、カシミール
の伝統文化をインドの大伝統に結びつけようとしている[永田 1998]。『ラージャタランギ
ニー』という歴史文献がカシミールで編纂された背景の一つには、同地の地域伝統をインド
の大伝統と関連付けたり、カシミール文化がその始原において超域的文化と同程度の古さを
有していると主張したりすることで、「ここはインドである」ということを主張する必要が
あったことも考えられるだろう。
1-2. 多宗教の併存と異教観
次に、ムスリム王朝成立以前のカシミールの宗教状況について概観しよう。カシミールに
おける最も古い信仰は、同地に豊富にある水に由来する竜神信仰と思われるが、仏教やヒン
77
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
ドゥーの神々を奉じる宗教が到来してからも、諸宗教は特に排除しあうことなく共存して
きた[桑山(編)1992: 102]。例えばウトパラ朝(855/6–939)の君主アヴァンティヴァルマン(r.
855/6–883)は自身敬虔なヴィシュヌ教徒であり、アヴァンティプラ3)にヴィシュヌ寺院を建
立したが、シヴァ教を奉じる大臣のために、その隣にシヴァ寺院をも建立している。
アレクシス・サンダーソンらによって近年研究が大きく進展したカシミール・シヴァ教に
ついて言うと、11 世紀の時点でタントラ的な儀礼を実践するスヴァッチャンダバイラヴァ
崇拝の一派が主流をなし、その両翼に二元論的なシャイヴァ・シッダーンタと一元論的なト
リカ4)やクラマ 5)などの諸派があったとされている[川尻 2009: 332–334]。特に一元論的な
シヴァ教では 10 世紀頃から「万物は一者(シヴァ)の意識の顕現である」という思想が発達
し、先に述べたアビナヴァグプタの例から分かるように、その思想はカシミールのみならず
南アジアの広域に伝わっていた。14 世紀に南インドのヴィジャヤナガル王国で編纂された
諸学派の学説綱要集『サルヴァダルシャナサングラハ』には、カシミール・シヴァ教の項で
その一元論的な思想が紹介されている。またシヴァ教以外にもヴィシュヌ教、仏教の有部や
唯識、ニヤーヤを中心とするバラモン教、文法学の伝統もカシミールに根付いており、ヴィ
シュヌ教においてはヴァーマナダッタ6)(ca. 1025–1075)、仏教においてはダルモーッタラ(ca.
740–800)などの学匠が活躍した[川尻 ibid.]。
そのような多信仰・他宗教が併存する環境において、バラモン教の立場から語られた一種
の宗教多元主義とでも言うべき思想を取り上げておきたい。ウトパラ朝のシャンカラヴァル
マン(r. 883–902)の時代に活躍したニヤーヤの学匠ジャヤンタは、認識論・論理学の大著で
ある『ニヤーヤマンジャリー』の中で、ヴェーダに敵対しないシヴァ教やヴィシュヌ教、敵
対する仏教やジャイナ教、順世派の正統性を論じ、最終的に「全ての聖典は正しい」という
考えを表明するに至る[片岡 2007: 39–45]。彼によって著された、聖典を巡る騒動を主題と
する戯曲『アーガマダンバラ』においても、同じような考えが表明されている。片岡啓は当
時のカシミールにおける反社会的な黒衣派の流行、およびシャンカラヴァルマンによる黒衣
派の禁教が、ジャヤンタに「正しい宗教とは何か」という命題を追究させるきっかけとなっ
たことを推測している[片岡 ibid.]7)。
最後に、ムスリム王朝成立以前のカシミールにおける、ムスリムの動向について触れてお
こう。カルハナは『ラージャタランギニー』の中で、ローハラ朝のビクシャーチャラがトゥ
ルシュカと呼ばれる人々を頼ったことを伝えている[KRT: 8. 885, 886, 919, 923]。先行研究
はこの記録を 12 世紀のカシミールにいたムスリムの存在を裏付けるものと評価しているが
78
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
[Rafiqi 1976: 3]、この評価は原文のトゥルシュカという語を半ば機械的にMuhammadanと
したオーレル・スタインの解釈に基づくものである。実際のところカルハナは明らかにムス
リムではない人物、あるいはテュルクではない人物に対してもトゥルシュカという語を用い
ており、ビクシャーチャラが頼った人々が本当にイスラームを奉じていたのかは明らかでは
ない。もう一つの情報はかのマルコ・ポーロによるもので、13 世紀後半のカシミールにお
いて偶像教徒が多数をしめる中、イスラーム教徒も雑居して屠殺を生業としていたことを伝
えている[東方見聞録 : 1. 103–104]。
2. ムスリム地方王朝 シャーミール朝(1339‒1561)、チャク朝(1561‒1586)
前節でカシミールが 16 世紀末に至るまで政治的な独立性を保っていたことを述べたが、
本節で取り上げるカシミール最初のムスリム王朝、シャーミール朝についても事情は同様
である。真下が指摘しているように、デカンやベンガルなどのムスリム地方王朝がデリー
政権の成立に由来するテュルク人ムスリムの動向との関わりによって成立したのに対して、
シャーミール朝はデリー政権の動向とは関係なく、まったく独自に成立した[真下 2007b:
133]。
カシミール最初のムスリム王朝を創設することになるシャーミールという名前の人物は、
1313 年に第二ローハラ最後の王、スーハデーヴァ(r. 1301–1320)の宮廷を訪れた。彼の出自
については、父親の名が恐らくターヒルというムスリム名であったことが推定されるもの
の、詳細は不明である。あとで見るようにシャーミール・スルターン家の系譜は多分に伝説
化されている。1320 年のモンゴル軍侵入による第二ローハラ朝の滅亡、ラダック王族の生
まれであるリンチェンの統治(r. 1320–1323)、ヒンドゥー王族による統治の復活といった出
来事を経た中で、シャーミールは域内の在地有力氏族との積極的な婚姻政策によって次第に
権力基盤を確立し、ついに 1339 年にスルターン・シャムスッディーンという称号のもとに
王朝を開いた。
王朝初期には第 2代スルターン、ジャムシード(r. 1342–1344)と第 3代スルターン、アラー
ウッディーン(r. 1344–1355)の間に内訌が発生したが、アラーウッディーンの即位以降は目
立った在地有力氏族の反乱はなく、スルターンの権力は概ね安定していたようである。続く
第 4代スルターン、シハーブッディーン(r. 1355–1373)は、爵位をもった有力者たち(ḍāmara)
を率いてガンダーラ[JRT: 342]、スィンド[JRT: 374]、ガズナ[JRT: 377]、ペシャーワル
79
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
[JRT: 379]に遠征を行っている。
第 5代スルターン、クトゥブッディーン(r. 1373–1389)の時代までは、スルターンが積極
的にカシミールのイスラーム化を進めたことを証明する形跡はみられず、史料に現れる人名
もスルターンを除いてほぼサンスクリットの名前であることから、多数の非ムスリムによっ
て構成される被支配者層の上に、スルターンを中心とする少数のムスリム支配者層が立つと
いう社会構造が維持されていたものと考えられる。
状況が大きく変化するのは第 6代スルターン、スィカンダルの治世(1389–1413)のことで
ある。クブラウィー教団のスーフィー、ムハンマド・ハマダーニーを筆頭とするムスリムの
集団がスィカンダル宮廷に到来したのと前後して、イスラームに改宗したスィカンダル宮廷
の軍隊長スーハバッタは、偶像寺院の破壊8)、非ムスリムに対するジズヤの課税9)などの政
策を推し進めた[JRT: 596; JRT: 606; Slaje 2007b: 332–333]。1413 年にスィカンダルが没して
彼の長男アリーシャー(r. 1413–1418/1419)が即位すると、スーハバッタは宰相となり[JRT:
616; Hasan 1959: 98; Slaje 2007b: 333]、1417 年に没するまでの間、バラモンに対する弾圧策
を一層推し進めた。ジョーナラージャはアリーシャーの治世に多くのバラモンがカシミール
を離れたり、あるいは自ら命を絶ったことを伝えている[JRT: 655–659]。またサンダーソン
はカシミールにおける二元論的シャイヴァ・シッダーンタの伝統がこの頃に急速に消滅した
ことを指摘しており、その理由を同派の学匠たちがムスリム政権下においてパトロネージュ
を失ったことに求めている[Sanderson 2007: 431]。
1420 年10)にアリーシャーに代わってザイヌルアービディーンが即位すると、彼は一転し
て非ムスリムに対する融和策を採り、他地域に移住したバラモンたちの招来や失われたサン
スクリット文献の再移入を行い、ムスリム・非ムスリムそれぞれの学芸を保護した[Slaje:
2007b; Hasan 1959: 131–140]。1470 年までの半世紀にわたるザイヌルアービディーンの治世
は開放的な文化状況が現出しており、またスルターンの権力も安定していた時代であった。
しかし一方で王朝後期の混乱の原因もこの頃に芽生えつつあった。
ザイヌルアービディーンの長男アーダムハーンと次男ハージーハーンの間で後継者争いが
起こり、ザイヌルアービディーンは遂に 2人の争いを収拾できなかった。またザイヌルアー
ビディーンはイラン東部のバイハクからサイイド・ナースィルを統領とするサイイド家を招
来し、姻戚関係を結ぶとともに11)、盆地内の一地域の統治権12)を与えている。アーダムハー
ンとハージーハーンに由来する 2王統の並立と、バイハクのサイイド家と在地有力氏族との
政治的な対立が、王朝後期を通じて続いた政権内の党派争いの主要因となった。
80
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
1470 年にザイヌルアービディーンが没すると、次男ハージーハーンが第 9代スルターン、
ハイダルシャー(r. 1470–1472)として即位した。この頃からサイイド家は次第に宮廷で幅を
利かせるようになったようで、続くハサンシャー(r. 1472–1484)の治世にはサイイド家の当
時の統領サイイド・ハサンは多くの所領を獲得し[ZRT: 3. 424]、宮廷からの命令を実質的
に彼が発するようになる[ZRT: 3. 434]。そして 1484 年にハサンシャーが没すると、彼とサ
イイド家の娘との間に生まれていた息子を、僅か 7歳でスルターン、ムハンマドシャーとし
て即位させた[ZRT: 4. 1]。当然ムハンマドシャーに統治能力はまだ備わっておらず、サイ
イド・ハサンが摂政として実権を握った。このようなサイイド家の専横に不満を募らせた
カシミールの在地有力氏族らは結託してサイイド・ハサンを暗殺し[ZRT: 4. 46; Hasan 1959:
168]、これをきっかけにしてサイイド家と在地有力氏族との間で約 4ヶ月間にわたる戦闘
が発生した。スリナガルの政情が不安定になる中、アーダムハーンの息子がこれを好機と
見て 1486 年にスリナガルへ進軍し、ムハンマドシャーを退位させてスルターン、ファトフ
シャーとして即位した。
ここからファトフシャーが没する 1519 年までの 33 年間は、ファトフシャーとムハンマド
シャーが互いに相手を退位させて自分が即位するという行為を繰り返す混乱期であった13)。
そのような時期を経たことで、シャーミール朝のスルターンの権力は名目的なものになっ
ていったようである。1519 年にファトフシャーが没したことで、スルターン位はムハンマ
ドシャーのもとに安定するかに見えたが、しかし 1528 年には在地有力者の中で当時最も有
力になっていた、チャク氏のカージー・チャクによってムハンマドシャーは 4度目の退位
を余儀なくされ[ŚRT:1. 246–248]、その後は対立関係にあった在地有力氏族が思い思いにス
ルターンを即位させる状態が続いた。対外的にも 1531 年にはムガル朝軍の、1532 年にはモ
グール・ウルス軍の侵入を受けたし、1540 年にカシミールに侵入したミールザー・ハイダ
ルは遂に同地を征服するに至り、1551 年に暗殺されるまで約 10 年にわたって傀儡スルター
ンのもとカシミールを実質的に統治した。彼がカシミールを統治していた時代には、フマー
ユーンの名で貨幣が打刻されていたという[Kak 1932: 137]。ミールザー・ハイダルの没後も
権力がスルターンの手に戻ることはなく、1561 年に最後のスルターン、ハビーブシャー(r.
1557–1561)がチャク氏のガーズィーハーン・チャクによって廃されたことで、シャーミール
朝は終焉を迎えた[ŚRT Appendix C: 37; ṬA_txt: vol. 3, 488; ṬA_ms: 372v; Hasan 1959: 243]。
シャーミール朝に代わって開かれたチャク朝は、25 年間の間に 8人もスルターンが代わ
るなど氏族内の争いが絶えず、政権は不安定だった。他方ムガル朝側はチャク朝の成立に前
81
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
後してアクバルが武将カラ・バハードゥルをカシミールに送るなど、1560 年代から同地を
王朝の版図に加えるべく、様子をうかがっていた[Hasan 1959: 276]。そしてカーブルにいた
アクバルの異母兄弟にして宿敵ミールザー・ムハンマド・ハキームが 1585 年に没し[ṬA_txt:
vol. 2, 395; BS: 173v]、ムガル朝の北西方面への版図拡大に対する障害がなくなったことで、
アクバルは宮廷をラホールに移すとともに、カシミール征服に本格的に乗り出し[Richards
1993: 49]、同年年末に彼は滞在中のカーブルからカシミールに軍を派遣した[ṬA_txt: vol. 3,
506; ṬA_ms: 377v; BS: 174v; Hasan 1959: 280]。当時のチャク朝スルターン、ユースフシャー
(r. 1578, 1580–1586)ははじめ抗戦の姿勢を見せたが、抵抗は不可能と見て降伏を表明し、翌
1586 年にムガル朝との間に条約を結んだ[ṬA_txt: vol. 3, 506; ṬA_ms: 377v; Hasan 1959: 281–
282]。こうしてカシミールはムガル朝に併合された14)。
3. シャーミール朝時代の Linguistic Cosmopolitanism
シャーミール朝時代の文化的特徴としてまず挙げられるのは、Linguistics Cosmopolitanism
とでも言うべき多言語の併用環境と、言語の壁を超えた知的交流である。例えばザイヌル
アービディーンは『アタルヴァ・ヴェーダ』をはじめとするスィカンダル、アリーシャー
時代に失われたサンスクリット古典の再移入に務めるとともに15)、一部の文献をペルシア
語に翻訳させた。複数の史料が伝えるところでは、ザイヌルアービディーン宮廷において
(1)『マハーバーラタ』[TSA: 21]、(2)ソーマデーヴァの『カターサリットサーガラ』、(3)
クシェーメンドラの『ダシャーヴァターラ』、(4)おそらくカルハナの『ラージャタランギ
ニー』、(5)『ハータケーシュヴァラ・サンヒター』という作品[以上、ZRT: 1. 5. 84–86]、
(6)ジャヤーナカの『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』16)がペルシア語に翻訳されたとい
う。サンスクリット古典のペルシア語への翻訳事業はムガル朝のアクバル宮廷の例がよく知
られているが、ザイヌルアービディーン宮廷での翻訳はそれに先行するものである。残念な
がらこのときに翻訳されたテキストはほぼ全てが散逸してしまっているが、ジャハーンギー
ル時代に『カターサリットサーガラ』のザイヌルアービディーン宮廷訳を改訂したアッバー
スィーの語るところでは、先行訳はアラビア語の語彙を必要以上に多用する、ペダンティッ
クな訳文であったそうである[DA: 4]。
またザイヌルアービディーン時代には、カルハナの没後断絶していたサンスクリットによ
る歴史叙述も復活している。『ラージャタランギニー』編纂以降のカシミール諸王の歴史を
82
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
知りたいというザイヌルアービディーンの意向を受けて、ジョーナラージャというバラモン
が同じ『ラージャタランギニー』という名の作品を編纂し、12 世紀半ばから同時代までの出
来事を綴ったのである。ペルシア語文化圏のムスリム王朝において王朝史がペルシア語では
なくサンスクリットで編纂されたことは極めて異例のことである。後で見るように、歴史叙
述という行為を通じてサンスクリット読者層に対してシャーミール朝の支配の正統性を主張
する意図があったと思われるが、ジョーナラージャが他にマンカの『シュリーカンタチャリ
タ』や『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』といったカルハナと同時代、すなわちジャヤシ
ンハの時代に活躍した文人たちによる作品の注釈を残していることを考えると、ザイヌル
アービディーン宮廷の文芸活動は、中世前期カシミールにおいて文芸活動の隆盛期と言える
ジャヤシンハ時代を範とする面もあったのかもしれない。ジョーナラージャはザイヌルアー
ビディーン治世中の 1459 年に急死するが、その後も彼の弟子シュリーヴァラらの手によっ
て、カシミールがムガル朝に併合されるまでサンスクリットによる歴史叙述の伝統は連綿と
続いた。それらの作品にはいずれも『ラージャタランギニー』か、それに類する作品名が与
えられている。
それら『ラージャタランギニー』作品群の中で、特にペルシア語文献の影響が色濃く見ら
れる一断片を紹介しよう。以下に引用するのは、16 世紀前半に活躍したシュカの『ラージャ
タランギニー』の中に付録のような形で組み込まれている、僅か 9詩節からなる断片である。
その内容から一つの完結した作品の序文にあたる部分が残存したものと推測される。また作
品編纂時のカシミールの支配者に対する賞賛をしている箇所で、ミールザー・ハイダルの名
が挙がっていることから、彼がカシミールを実質的に統治していた 1540 年代に編纂された
可能性が高いと考えられる。邦訳は次の通りである。
まだ見ぬ形を備えたるものの支配者17)たる創造主によって、世界を創造するために、
自らの意志を持つ人形が如き、バーバー・アーダムという名前の者が創造された[1]
女性と連れ立っている彼が前にいるのを[神が]見て、神の難しい遊びによって
一万八千世界(ālama < ‘ālam)が顕現した[2]
七つの天、三十六の大地によって占められる「アルシャコールシャ
(arśakorśa < ‘arš wa farš)」という広大な世界を[神が]見て、
聖仙(ṛṣi)の姿をした預言者たち(pigambarāḥ < payġambar)が創造された[3]
神の家を拠り所とする、尊敬すべき使徒(rasola < rasūl)、すなわち預言者は18)、
83
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
空衣(digambara)の望みによって、世界の人々を憐れ慈しむ男として栄えよう[4]
神(khadaiva < ḫadīw)が創造した大地の中心に、最も高い山ヒマラヤがあり
そこに大地という最良の女性の首飾りたるカシュガル国がある[5]
[それは]善き人々の善行の集積であり、全ての弓使いたちの家であり
様々な木々の蔓草を備えたる、全ての繁栄する女性たちが[愉しむ]庭園である[6]
知識を持つ者、バララーマ19)の両腕の力という名声備えたる者、良い馬を持つ者、
幸運を持つ者、大地の王、軍事力によって高められし自らの名誉と
名前の音によって飾られた、この国で生まれた広大な土地を獲得した、
傑出したる太陽の化身、カシミールの人々を様々な政策によって闇を打倒し、
論理を知るようにした者に勝利あれ[7]
サティーサラ20)において長い間失われてしまっていた
アヌーシルヴァーン21)に等しき、かつての大地の王の振る舞いをなすべく
まさに王国に降り立った、言葉の権威たる
ミールザー・ハイダル・ムハンマドに末永く勝利あれ[8]
悪しき振る舞いという森の火事で燃えてしまった、その預言者の庭園22)に
良い行為という雨を降らせることで養育させるため
全ての優れた預言者たちの集まりによって、神の祝福が投げられよう[9]23)
一目見て分かるように、この詩節はイスラームの創造論・預言者論に基づくものである。
世界創造の過程においてまず唯一の創造者はアーダムを創造し、ついでハワー(イヴ)、多
なる世界、預言者の創造へと続いていく。そしてイスラームの概念を説明するにあたって、
「アーラム(世界)」「アルシュ・ワ・ファルシュ(天地)」「ペイガンバル(預言者)」「ラスー
ル(使徒)」といったアラビア語・ペルシア語の語彙が借用されている。更にミールザー・ハ
イダルを賞賛するにあたって引き合いに出された人物は、インドラやクリシュナといったイ
ンドの神や英雄ではなく、フィルダウスィーの『王書』など数多のペルシア語文献において
公正な王の象徴とされている、アヌーシルヴァーンである。この断片の著者は不明だが、ペ
ルシア語文献にかなりの程度通じていたことは間違いない。また 15 世紀後半、ペルシア語
に通じたバラモンの学匠や、サンスクリットの知識を持ったムスリムがシャーミール朝宮廷
にいたことをシュリーヴァラが伝えている。ザイヌルアービディーン自身もまたサンスク
リットに通じており、シュリーヴァラから思想文献『モークショーパーヤ』の講義を受けて
84
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
いた[Obrock 2013: 231–233]。
サンスクリットとペルシア語の両言語は、シャーミール朝の宮廷内だけで併用されていた
わけではない。16 世紀のカシミールで活躍したスフラワルディーヤのスーフィー、シャイフ・
ハムザの廟がスリナガル中央に聳えるハリ・パルバト山の中腹にあるが、この廟に関連した、
984 年ジュマーダー第 1月/1579 年 7‒8 月の日付を持つ文書は、ペルシア語とシャーラダー文
字サンスクリットが併記されている。また当時のムスリムの墓で、ペルシア語とシャーラダー
文字サンスクリットの墓碑銘が併記されているものがスリナガルの随所に見られる。一例を
上げると、Mazari Qalan地区に残る或る墓石には、下半分にペルシア語で「終末が良いもので
ありますように(‘āqibat ba-ḫayr bād)」と刻まれており、上半分にはシャーラダー文字サンスク
リットで敬礼をしているかのような文言が刻まれている[Ahmad 2013a: 附図]。サンスクリッ
トとペルシア語を併用する環境は、宮廷の外側にも広がりを見せていたのである。
4. スルターンたちによる支配の正統性の主張
上述したような言語使用環境において、支配者たるシャーミール朝のスルターンたちはど
のようにして支配の正統性を主張したのであろうか。この問題に取り組むために我々に残さ
れた史料は必ずしも多くはないが、それでも史料から得られる情報は示唆に富んでいる。
まずは王朝によって刻石されたサンスクリット碑文史料を見てみよう。シハーブッディー
ン治世のサプタルシ暦 4445 年ヴァイシャーカ月白半月 12 日/1369 年 4 月 19 日の日付を持
つ、カシミール盆地南部のコーティハール24)に建地されたシャーラダー文字サンスクリッ
ト碑文には、その 9行目から 10 行目にかけて次のような一節がある。
幸福なこの地に、幸運なるカシミールの王国に、シハーブッディーン、月が如き王、
パーンダヴァの血族の者あり[Deambi 1982: 113–118; Deambi 2008: 150]25)
パーンダヴァが『マハーバーラタ』に登場する一族であることは言うまでもない。重要な
のは、ムスリムのスルターンであるシハーブッディーンが、この一族の後裔たることを主張
していたということである。シャーミール朝スルターンによるパーンダヴァ裔の主張は、先
に紹介したジョーナラージャの『ラージャタランギニー』からも窺える。スルターン家の系
譜は多分に伝説的であると前述したが、ジョーナラージャはその起源をパーンダヴァの第
85
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
3 王子アルジュナの異名パールタと同じ名を持つ、パールタという人物としている。『タバ
カーティ・アクバリー』をはじめとするムガル朝時代のペルシア語史書にはしばしばシャー
ミール・スルターン家の起源をアルジュナ本人に同定しているものがあるが[ṬA_txt: 3. 424;
ṬA_ms: 355r]、これはジョーナラージャの記述に基づいたものである可能性が高い。また、
ザイヌルアービディーン治世の 1428 年に刻石された碑文の冒頭部には、次のような文章が
刻まれている。
オーム。[ラウキカ暦]4年マールガ月白半月 5日金曜日/1428 年 12 月 3 日金曜日
非実体にして森羅万象の実体たるもの、無属性にして属性を備えたるもの
存在、非存在という定義付けから免れている全実体に敬礼。
カリユガが始まってから 4530 年が過ぎた[今年]、
吉祥なるスィカンダルの息子、サティーサラにおいて大地の王たる
ザイヌルアービディーン王は
コーナモーシャの領主カゲーンドラのアグラハーラにおいて……[Deambi 1982: 122–
123; Deambi 2008: 151]26)
このように、碑石に刻まれた文章はまずインド思想における一元論的な梵のごとき存在に
対する敬礼から始まっている。先に紹介した『ラージャタランギニー』の一断片とは異なり、
これらの碑文にはイスラーム的な神概念や王権論などは一切語られていない。インド思想に
基づく支配の正統性の主張は、ジョーナラージャの『ラージャタランギニー』の中にも見え
る。彼の語るところでは、シャーミールはカシミールに到来する前に見た夢の中で、シヴァ
の妻であるパールヴァティーから「あなたとあなたの子孫はカシミールの支配者となる」と
いう予言を伝えられ、彼女の灌頂儀礼を受けたという[JRT: 138]。またシャーミール朝の
スルターンをシヴァの部分的化身とする記述もある。ジョーナラージャが『ラージャタラン
ギニー』の編纂を開始した理由がザイヌルアービディーンからの要請であったことを考える
と、このようなインド思想に基づいた支配の正統性の主張も、王朝の意向を反映したものと
言えるだろう。
このような事例を見ると、シャーミール朝のスルターンたちは本当にムスリムという自覚
があったのか、イスラーム的な称号を名乗っていただけに過ぎないのではないかと思われ
るかも知れない。しかしことはそう単純ではない。同時代に鋳造、打刻された貨幣資料に
86
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
は、つとめてイスラーム的な支配の正統性が主張されている。同じザイヌルアービディー
ン治世のヒジュラ暦 851/1447‒48 年に鋳造された銅貨にはアラビア語とペルシア語のアマ
ルガムの文章が打刻されており、その中には「信徒の長の副官(nā’ib al-amīr al-mu’minīn)と
いう表現が見られる[Rodgers 1876: 277–285]。またハイダルシャー治世の 874/1470 年に鋳
造された銀貨には「慈悲遍き者のカリフの副官(nā’ib-i ḫalīfa al-raḥmān)」と打刻されている
[Rodgers 1896: 223]。すなわちムスリム共同体の指導者としてアッバース家カリフの権限を
認め、シャーミール朝のスルターンはカリフの代理者としてカシミールを統治するという主
張がなされている。ザイヌルアービディーン時代に「エジプトの支配者」との使節のやりと
りがあったことが同時代史料に記録されているが[ZRT: 1. 6. 26]、これは当時マムルーク朝
の庇護下にあったアッバース家カリフとバイアを行い、認証状を受け取るための外交手続き
であったと考えられる。貨幣において主張されるシャーミール朝の支配の正統性はつとめて
スンナ派イスラーム的であり、碑文史料や『ラージャタランギニー』とは対照をなしている。
スルターンたち自身の宗教アイデンティティに関しては、ザイヌルアービディーンを含む全
てのスルターンが土葬されており、彼らの墓はいずれも遺体がメッカの方向を向くように配
置されていることから、少なくとも来世観においてはイスラームのものを受容していたと言
える。そのため、サンスクリットで記録された史料に見られるインド思想に基づいた支配の
正統性は、スルターンたち自身の宗教観を反映したものではなく、あくまで政治的な手段と
して主張されたものと理解されるべきだろう。
現在我々が利用しうる史料をみる限りでは、シャーミール朝の君主たちはサンスクリット
ではインド思想的な、アラビア語・ペルシア語ではイスラーム的な支配の正統性を主張して
いたと考えられる。すなわち言語と宗教を一致させた形である。このような主張の方法は、
サンスクリットのみを解する非ムスリムや、アラビア語・ペルシア語のみを解するムスリム
を対象とした場合、有効であっただろう。しかし先に述べたように、当時のカシミールの社
会にはペルシア語を解する非ムスリムやサンスクリットを解するムスリムも一定数いた。こ
のような二元的な正統性の主張は彼らの目にはどのように映ったのであろうか。この点は今
後検討されるべき課題である。
5. 多言語使用者たちの宗教アイデンティティの諸相
本節では多言語を使用するムスリム、非ムスリムがどのような宗教アイデンティティや異
87
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
教観を有していたのかを見ていく。
5-1. サンスクリットのリテラシーを持つムスリムの異教観
現在利用可能なペルシア語文献がカシミールで書かれ始めたのは、16 世紀半ばごろのこ
とである。ミールザー・ハイダルが歴史書『ターリーヒ・ラシーディー』を同地で執筆した
ほか、著名なスーフィーたちの事績をまとめた聖者伝がいくつか編纂された。しかしこれら
聖者伝の著者たちが先行するサンスクリット文献を参照していたのかどうか、未だ確定的な
ことは言えない。確実にサンスクリット文献を参照しているムスリムの例は、カシミールが
ムガル朝の版図となった 17 世紀第一四半期にまで下ることになる。取り上げるのは、1614
年に執筆されたペルシア語史書『バハーリスターニ・シャーヒー』とその著者である。
本書は先史時代から同時代までのカシミールの歴史が綴られたもので、著者の名前ははっ
きりしない。『バハーリスターニ・シャーヒー』において著者が自ら語るところでは、著者
の先祖はスィカンダルの治世に一人のスーフィーの随行者として、ガズナからカシミールに
移住したのだという。本文中の記録から推察しうるのは、著者がシャーラダー文字で書かれ
たサンスクリットの読解能力を有していたこと、『ラージャタランギニー』で用いられてい
るサプタルシ暦の知識があり、4桁の年数のうち 10 の位、1の位のみを記す叙述法も理解し
ていたこと、敬虔なムスリムであり、非ムスリムに対して批判的な感情を持っていたこと程
度である。まず、『バハーリスターニ・シャーヒー』の冒頭において、著者はムハンマドや
当代の君主への賛美も経ずに、次のような言葉で叙述を始める。
諸王やハーキムたちの全ての状況や出来事、高貴な人々の諸行状といった、カシミー
ルの諸王国のスルターンたちの情報を、歴史家たちはカシミールの筆で記した。より信
頼性があり、[過去の]事跡に関する[ことがら]については、以下のように記録されて
いる。[BS: 1v]
この「カシミールの筆」という言葉はフォリオ 19v、62vにも登場し、それぞれシハーブッ
ディーンの遠征活動、ムハンマドシャー 1度目の治世(1484–1486)に生じたサイイド・ハサ
ンの暗殺に関する叙述の中で言及されている。中でも 19vの記述は、著者が『ラージャタラ
ンギニー』を参照していたことを裏付ける根拠となる。
88
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
カシミールの筆で書かれている…(Bā下点なし、Ḥ、Y)の史書においてこのこと
(Šihāb al-Dīnの遠征活動)が記されている。また彼は次のように語っている「私がたと
えあらゆる彼(Šihāb al-Dīn)の勇敢さを詳細に記し、あらゆる彼の勇ましさの叙述に勤
しんだとしても、人々は詩的表現の誇張に帰して否定してしまうだろう。また正しいと
は思わぬであろう」。[BS: 19v]
著者が引用する判読不能な人物の言葉は明らかに JRT: 391においてジョーナラージャ
が語っている、「たまたま話の流れで[なされた]我 (々私)によるこの超人(シハーブッ
ディーン)の英雄的行為の叙述は、お世辞を言っているようなものだと未来の人々に理解
されよう」27)という詩句と綺麗に対応する。そしてこの判読不能な人物の綴りは ĞNYと復
元しうると筆者は考える。すなわち、ここで言及されている「彼」とはジョーナラージャの
ことであり、rājaが王を意味する一般名詞と見做され、前半の Jonaのみがアラビア文字で
転写された28)。しかし書写を経るうちに綴りが崩れてしまった、と解釈されよう。ここか
ら、BSの著者が JRTを参照していたことが明らかとなる。そして「カシミールの筆」とい
う言葉も、カシミールでサンスクリットを書写する際に用いられていた、シャーラダー文字
のことを指すと考えられるのである。
このようにサンスクリットのリテラシーを有し、『ラージャタランギニー』から得られる
情報をソースとして活用している一方で、『バハーリスターニ・シャーヒー』の著者は異教
徒たちの信仰には批判的である。例えば、ザイヌルアービディーンの治世に関して、彼は次
のようなコメントを残している。
彼のまったき欠点、完全なる汚点とは次のようなものである。不信仰や不信仰者、偶
像崇拝や偶像彫刻は亡きスィカンダルの治世に根絶やしにされ、カシミールの王国にお
いてその如何なる痕跡も残っていなかったのであるが、ザイヌルアービディーンは再び
不信仰と偶像崇拝の諸基礎を確立し、他宗教徒たち、邪教徒たちの諸慣習に対する新た
な繁栄、新たな浸透を明らかなものとした。[BS: 57r]
このように、『バハーリスターニ・シャーヒー』の著者は異教徒の信仰を弾圧したスィカ
ンダルの政策を賞賛するかのような態度を示す一方で、ザイヌルアービディーンが彼らに対
して融和的であったことを、彼の汚点と明言している。他の箇所でも異教徒を改宗に導いた
89
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
スーフィーの事績が賞賛されている[BS: 14v–15v]。同書を読む限り、著者はイスラームが
最も優れた宗教であること、そしてその普遍性を確信している。彼にとって異教徒の信仰は
到底受容されざるものであり、彼らが残したサンスクリットの文献はあくまで情報源として
価値を有するものであった。なお、異教徒たちの信仰の仔細や、それに基づいた儀礼などの
記述は同書にはほとんどない。そのような情報は著者の関心の埒外であったのだろう。
5-2. ペルシア語リテラシーを持つバラモンのイスラーム観
では、ペルシア語を知る非ムスリムはイスラームとムスリムのことをどのように捉えてい
たのだろうか。この問いを考えるにあたってもっとも興味深い例を提供してくれるのが、15
世紀後半にシャーミール朝宮廷で活躍したバラモン、シュリーヴァラである。
彼はほぼ確実にザイヌルアービディーンの治世に生まれた人物で、ジョーナラージャを師
として教導を受けた。自身の宗教的な帰属は一元論的なシヴァ教である。シャーミール朝宮
廷とは良好な関係を保ち、ザイヌルアービディーンのサンスクリットやインド思想の教師
となっていたほか[ZRT: 1. 7. 100–102, 131–133; Obrock 2013: 231–233]、ハサンシャーの治世
には宮廷の音楽部門の長(gītāṅgādhipati)を務めている[ZRT: 3. 242–243]。また彼はペルシ
ア語に堪能で、カシミーリー語で話された会話を即座にペルシア語に翻訳できたほか[ZRT:
3. 238]、フィルダウスィーの『王書』にも言及している[ZRT: 1. 4. 39]。彼の『ラージャタ
ランギニー』の中に見られる面白い記述では、酒に入り浸っていたハイダルシャーをペルシ
ア語詩(pārasībhāṣākāvya)における酩酊者のモチーフになぞらえたものがある[ZRT: 2. 133]。
彼は急死したジョーナラージャの後を次いで『ラージャタランギニー』の編纂を続けたほか
にいくつかの著作を残したが、特に興味深い作品は『カターカウトゥカ』である。この作品
はティムール朝時代の著名な神秘主義者にして詩人、アブドゥッラフマーン・ジャーミー
(1414–1492)の代表的な作品『ユースフとズライハー』のサンスクリット訳で、ジャーミーが
『ユースフとズライハー』を上梓してからわずか 22 年後の 1505 年に編纂された。本稿の冒
頭で引用したのは『ユースフとズライハー』と『カターカウトゥカ』それぞれの冒頭で綴られ
る神への呼びかけである。シュリーヴァラが原典を見事に翻訳していることが分かるだろう。
『カターカウトゥカ』の中でシュリーヴァラは『ユースフとズライハー』のことを「ムスリ
ムの聖典と結びついた物語」であること[KK: 1. 2]、その物語が「神より語られたる言葉」で
あることを語っている[KK: 1. 39]。知ってのとおり『ユースフとズライハー』の主題である
2人の恋物語は『クルアーン』のユースフ章を基とするものであるが、シュリーヴァラは明
90
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
確にそのことを理解していた。『クルアーン』自体について彼は「ムスリムのヴェーダ」「彼
ら自身のヴェーダ」などと呼んでいる[ZRT: 2. 206; 3. 509]。そしてイスラームの預言者ムハ
ンマドについては、「このムハンマドという名の最も優れたる預言者は、ハディーヴ(神)と
会話をなし、清浄なる心を持ちながら(すぐにでも天界に昇れるというのに)、神の命令を
受けて、[イスラームの]ダルマという橋を築いた偉大なる者である」と語っている[KK: 1.
16–17]。『バハーリスターニ・シャーヒー』の著者が異教徒たちの信仰にさしたる関心を示
さなかったのとは対照的に、シュリーヴァラはイスラームについてある程度の正確な知識を
持っていた。『ユースフとズライハー』と『カターカウトゥカ』の対応箇所をみる限りでは、
彼はアッラーとシヴァは一元論的な文脈において同一の存在であると考えていたものと思わ
れる。
但し、イスラームとシヴァ教それぞれの神が同一であるという認識は、それぞれの信仰と
それに基づいた実践や慣習、すなわち「宗教」も融和・統合されるべきであるという考えを
必ずしも導くわけではない。たとえ一なる神から語られた言葉に共に基づくものであったと
しても、シュリーヴァラにとって彼が信じるものとイスラームは全く別のものであった。彼
はイスラームやそれ以外の信仰を語る際に、「ダルシャナ」という言葉を用いている。「ダ
ルシャナ」とは「見る」を意味するサンスクリットの語根√d─ṛśから派生した語で、「ものの
見方」「世界観」「哲学」「哲学派」「救済論的思弁」などの意味を持つ。この「ダルシャナ」
という言葉に実践や慣習を意味する単語が限定複合語の形でコンパウンドする用例が彼の
『ラージャタランギニー』の中に見られることから、ものの見方や世界観に基づいてそれぞ
れの宗教的実践や慣習があると彼が考えていたことが分かる。特に興味深いのは、シュリー
ヴァラが『ラージャタランギニー』の中でイスラームの葬送儀礼について自説を述べる以下
の一節である。ここで彼は当時のムスリムの間で奢侈な墓を築く風習が広まっていたことを
批判している。
ムスリムの人々は彼らの墓[を築くこと]に熱心であり、いつも[墓に装飾を施す]多
くの職人たちに金を払っている。そして彼らは「私がいつどのように死ぬのだろう?」
[という問いを事前に]唯最高神を除いて誰も知り得ないということを考えようともし
ない[89]
身体の中にある自らの命の限界を知る者に対しては、死神は従順かつ友好的である。
そういった者こそ生前に墓を築くに相応しい。私が思うにムレーッチャたちには単にこ
91
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
れ(墓の建造)に対する悪しき没頭があるだけである[90]
ヴァイシュラヴァナ・バッタ29)やその他の者たちは[生前に]自らの墓を築いていた
が、最終的に彼らは村で死に、その地に横たえられた[91]
一般民衆とて一人ひとり百尋の土地を囲い込むことに熱心に専念しており、他のもの
をそこに入らせようとはしない。どうして彼らは恥じ入らないのか[92]
シャーストラによれば、遺体[を埋めた]地面の上に小さな石ころが置かれてさえい
るならば、死者は来世に向かうときに幸福になると言われている[93]
嗚呼、死んでいるというのに墓を口実としてまるで生きているかのように大地を覆う、
人々の欲望のなんと大きなことか[94]
嗚呼、高位にある者たちはせいぜい墓を築くことに精を出すがいい。それを築くこと
によってどれほどの腹を空かせた貧者たちを生き永らえさせられるというのか[95]
もう一方のダルシャナの慣習が賞賛される。というのも何千万人もの人がいつも僅か
一尋の土地の中で火葬をしてきたからだ。その点で[葬送をするにあたり]まだ余裕が
ある。[96]
この文脈で相応しくない批判を語り始めたことについて、ムスリムたちは私を許すべ
きである。というのも詩人の言葉というのは節度を欠いたものであるから[97]30)
引用の 93 頌においてシュリーヴァラは、奢侈な墓を築く風習が「シャーストラ」におい
て推奨されない行為であることを指摘している。詳細な検討は別の機会に譲るが[Ogura
Forthcoming]、ここで挙げられている「シャーストラ」とは、奢侈な墓を築いたり墓の上に
モスクを築いたりすることを禁じるスンナ派のハディースを指している。すなわち彼はムス
リムの法源でもって当時のムスリムの慣習を批判しているのである。彼はまた「もう一方の
ダルシャナ」の習わしである火葬の有用性も説いているが、それは信仰面での優位に基づく
ものではなく、単に場所を取らないからという実利的な根拠によるものである。信仰にお
いて優劣はないという彼の公平な態度が窺えるだろう。『カターカウトゥカ』『ラージャタラ
ンギニー』の記述を見る限り、シュリーヴァラは一なる神に由来する複数のダルシャナがあ
り、それぞれのダルシャナの信徒はそのダルシャナが持つ聖典・経典の内容に忠実な実践を
行うべきであると考えていたと推測されよう。このようなシュリーヴァラの思想の背景を考
えるにあたって、ヴァルター・スラーイェは興味深い指摘をしている。彼によれば、シュ
リーヴァラの『ラージャタランギニー』の中には、ジャヤンタの『ニヤーヤマンジャリー』
92
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
とのパラレルがあるという[NM: 1. 8. 4ff; ZRT: 1. 5. 79; Slaje 2007b: 333, n. 21]。シュリーヴァ
ラがニヤーヤの学統を継承していたかどうか筆者は確証を持たないが、『ニヤーヤマンジャ
リー』が広く読まれた作品であることを顧みれば、彼が同書を読んでいたことは十分に考
えられる。仮定に仮定を重ねることになるが、シュリーヴァラが『ニヤーヤマンジャリー』
を通じてジャヤンタの「全ての聖典は正しい」という思想を学んでいたならば、それをイス
ラームにも適用して、「イスラームの聖典もまた正しい」と考えるに至ったこともあり得る
話ではある。シュリーヴァラがジャヤンタの宗教多元主義を継承したのかどうかという問題
も、今後検討されるべき課題である。
むすび
以上見てきたように、ムスリム地方王朝時代のカシミールでは、サンスクリット、ペルシ
ア語が共に使用され、両言語を理解するムスリム、非ムスリムもいた。シャーミール朝のス
ルターンたちはサンスクリットではインド思想に基づいた、ペルシア語ではスンナ派イス
ラームに基づいた支配の正統性を主張していた。両言語を操る人々はムスリム、非ムスリム
ともに宗教の違いを意識していた。
カシミールはデリーを除く南アジアの諸地方の中で比較的史料に恵まれていることもあ
り、当時の言語・文化・宗教の諸状況をこのように論じることができた。筆者がまだ十分に
利用できていない史料もまだまだ残されており、本稿の内容はあくまでこれまでの知見をま
とめたものであるが、前近代南アジアにおけるイスラームと異教徒たちの社会との関係を考
察する上で本稿が幾らかの貢献ができるのであれば、筆者にとって幸甚である。
註
1) Ilāhī ġunčah-yi umīd ba-gušā’ī gulī az rawḍah-yi jāwīd ba-namā’ī ba-ḫandān az lab-i ān ġunčah bāġam wa zayn-i gul ‘atr parwar kun damāġam
2) prabodhayāśākalikām prasādamadhunā prabhā tadutpannepsitaphalaṃ dātum arhasi me śubham śobhitaṃ kuru tenaiva mānasodyānam adya me tatsaugandhyena śuddhena śarīraṃ paripūraya
3) スリナガルの南東約 25kmにあるまち。
4) 西暦 800 年以前の初期段階において三対の女神の能力を獲得せんと儀礼を行っていたことから、「トリ
93
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
カ」と呼ばれていた一派。後に超越的性格を持つ女神としてカーリー崇拝を取り込み、更に 10 世紀には森羅万象は絶対的一者たるシヴァの意識の顕現であるとする教義体系が現れ、それに結びついた儀礼を発展させていった[川尻 2009: 332–334]。
5) カーリー崇拝の伝統と結びついた一派で、起源は 9世紀以前のウッディヤーナとカシミールとされる。概念的構想を段階的に浄化することで解脱を得られるという解釈と、それぞれの段階の神格を崇拝することに特徴がある[川尻 ibid.]。
6) クラマに属する同名のヴァーマナダッタもいた[Torella 1994]。
7) 同時に片岡は、クマーリラ以来のインド思想史における聖典権威をめぐる議論の中に、ジャヤンタの宗教観・聖典観を位置づけてもいる[片岡 2007: 47]。
8) 但し、1540 年代のカシミールになお多数の偶像寺院が残っていることをミールザー・ハイダルが伝えていることからも分かるように、このときの寺院破壊は必ずしも徹底したものではなかった[TR: 621–622; Hasan 1959: 96–97]。
9) jātidhvaṃse mariṣyāmo dvijeṣv iti vadatsv atha | jātirakṣānimittaṃ sa tān durdaṇḍam ajigrahat || [606]「ジャーティが破壊されるとき、私たちは死ぬだろう」とバラモンたちが語るとき、ジャーティを維持しているという理由で、彼(Sūha Bhaṭṭa)は彼らに重税を課した。
10) なお、ザイヌルアービディーンは 1418 年にもアリーシャーがハッジに向かったために、彼に代わって短期間スルターンになっている。1418 年から 1420 年までのアリーシャーとザイヌルアービディーンの関係については[Slaje 2007b]を参照せよ。
11) ZRTによれば、ザイヌルアービディーンはサイイド家の娘を妻にし[ZRT: 1. 7. 47]、また自身の娘をサイイド・ナースィルに与えていた[ZRT: 3. 153–154]。
12) バフルーパはカシミール盆地西部、スリナガルのほぼ真西にあった地域で、同じバフルーパの名を持つ聖泉が北緯 34 度 0 分 37 秒、東経 74 度 35 分 48 秒にある[Slaje 2014: 311]。
13) 1517 年までにファトフシャーとムハンマドシャーはともに 3回即位しており、ムハンマドシャーはその後更に 2回(1517–1528, 1530–1538)スルターンになっている。この間サイイド家や在地有力氏族の成員は、2人のうちのどちらかを支持する勢力にまわり、複雑な合従連衡を繰り返した。
14) ムガル朝に併合された後、ユースフシャーはマンサブ 500 を与えられて、ビハールに転封されたという[Hasan 1959: 283]。また併合後も 1589 年 6 月のアクバルのスリナガル行幸まで、ユースフシャーの息子ヤアクーブシャーらが抵抗を続けていた。
15) 『アタルヴァ・ヴェーダ』のカルナータカからの再移入については、スラーイェの詳細な研究がある[Slaje 2007b]。
16) Lms2の ZRT 1. 5. 84–86に対応する箇所で、『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』(PRTHY RAĞ BĞYと転写されている)もペルシア語に翻訳されたことが記されている[Lms2: 81r]。ZRT原文で『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』の名が挙がっておらず、『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』のペルシア語訳の写本も今日まで知られていないため些か如何わしい情報ではあるが、固有の作品名が言及されていることから、翻訳者が『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』の ペルシア語訳の写本を入手していた可能性はある。ひょっとすると ジョーナラージャの『プリトヴィーラージャヴィジャヤ』注釈もまた、ザイヌルアービディーン宮廷における文芸活動の一環だったのかもしれない。
17) 造形者 al-Muṣawwir(Q: 59/24)の訳であろうか?
18) ここでは使徒、預言者ともに単数形なので、ムハンマドのことを指していると思われる。
19) クリシュナの兄。
94
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
20) 「サティー(シヴァの妻)の湖」という、カシミールの異名。
21) ササン朝君主ホスロウ 1世(r. 531–579)の異名で「不滅なる魂を持つ者」という意味。近世ペルシア語文献において、ホスロウ 1世は公正な君主の模範としてモチーフにされる。
22) 恐らく、ペルシア語史書に現れるカシミールの異名の一つ、「ソロモンの庭園 Bāġ-i Sulaymān」をサンスクリットに訳したもの。イスラーム側のカシミール縁起譚として、ソロモンが 2体のジンを遣わして、湖を干拓させたというものがある[TḤM: 6–7]。
23) adṛṣṭavigraheśena svecchākrīḍanaka iva | Dhātrā vinirmitaḥ sraṣtuṃ jagad bābādhamābhidhaḥ || [1] dṛṣṭvainaṃ strīyutaṃ cāgre prādurāsan daśāṣṭa ca | sahasrāṇyālamān yasya vibhor durgaṭalīlayā || [2] arśakorśaṃ divaḥ sapta bhuvaḥ ṣaṭtriṃśadāvṛtam | jagat sphāram avekṣyarṣirūpāḥ sṛṣṭāḥ pigambarāḥ || [3] vibhudhāmāśrayī śrīmān rasolo ’dya pigambaraḥ | digambarecchayā lokakṛpālur mānavo jayet || [4] khadaivasṛṣṭibhūmadhye himavān girir uttamaḥ | tatrāsti deśaḥ kāskāro hāro bhūmivarastriyaḥ || [5] satāṃ sukṛtasambhāro ’gāraḥ sarvadhanuṣmatām | nānādrumalatākāro vihāraḥ sarvasaṃpadām || [6] medhāvī revatīśaprathitabhujabalaḥ saddhayaḥ śrīdharaś ca | bhūpālendraḥ pratāorjitanijayaśasā bhūsito nāmavarṇaiḥ || jīyāt taddeśajanmārjitabahuvasudhaḥ prodgato bhānumūrtiḥ | kāśmīrān yo hi nānānayatimirahatān nyāyavijn᷈ān vyadatta || [7] merejahaidhara mahammadavākpramāṇo | jīyāc ciraṃ vasumatīm avatīrṇa eva || kartuṃ satīsarasi nauśaravānatulyaṃ | pūrvorvarīśacaritaṃ cirakālanaṣṭam || [8] sarvaiḥ pigambaravarair militaiḥ khadaiva- | syāśāsyate iha pigambaravāṭīkām tām || etāṃ kukṛtyacaritākhyadavāgnidagdhāṃ | satkarmavṛṣṭinivahaiḥ paripoṣanāya || [9]
24) カシミール盆地南部のアナントナーグから南に約 16kmの場所。
25) asti sukhasthale puṇyakaśmīramaṇḍale | śāhābhadeno rājenduś śrīmatpāṇḍavavaṃśajaḥ || [Deambi 1982]において本頌の末尾は Pāṇḍavaṃśajaḥと転写されており、サンスクリットとして意味を
成さない。しかし[Deambi 2008]に収録されている碑文の写真から、当該箇所が Pāṇḍavavaṃśajaḥと読めることが確認できるので、写真に従って[Deambi 1982]の転写に修正を加えてある。
26) oṃ saṃ 4 mārge śuti 5 śukre anātmā viśvabhūtātmā nirguṇas saguṇaś ca yaḥ sadasadvyaktirahitas tasmai sarvātmane namaḥ triṃśādhike ca śatabhūtayute kalasya kaleḥ yāte sahasracature śaradā babhūva śrīmatsakandarasuto dharaṇīdharendra- skhatīkhare (<satīsare) ha jayanolabadenaśāhaḥ agrahāre khagendrasya khonamośe ha bhūpateḥ …
27) tasya varṇayatāṃ śauryaṃ prasaṅgād atimānuṣam | asmākaṃ cāṭukāritvaṃ jñāsyate bhāvibhir janaiḥ
95
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
28) 3 文字めの Yは元の名をムスリム名のニスバのような形に変形させたものと考えられる。このような転写は Lms2、Mmsにも見られ、ジョーナラージャはそれぞれ ĞWNY、ĞWLYと転写されている[Lms2: 20r; Mms: 43v]。
29) この箇所で Dharは原文の vaiśravaṇaを「裕福なムスリムの」と訳しているが、筆者はシャーハーバーディーによる『ラージャタランギニー』のペルシア語訳に依拠して個人名と解釈する。ペルシア語訳の文章は以下の通りである。WŠRWN BHT-i wazīr-i sulṭān Zayn al-‘Ābidīn bā mardumān-i dīgar gurīḫtand. mardumān-i sulṭān ta‘āqib namūdah īšān rā ba-qatl āwardand. gūrḫānah’hā ba-takalluf banā kardah būdand. mu‘aṭṭal mānd. wa qālib’hā-yi īšān dar mawāḍi‘-i qatl-i īšān uftādah mānd. wa ḫāk gašt.「Sulṭān Zayn al-‘Ābidīnのワズィールであったヴァイシュラヴァナ・バッタは他の人々と共に逃亡した。スルターンの[手勢の]者たちは追跡して彼らを殺害した。彼らは奢侈な墓を[生前に]作っていたのだが、無駄になってしまった。そして彼らの遺体は殺された場所に横たえられ、そこは土饅頭になった」[Lms2: 97v]。いずれにせよ、ヴァイシュラヴァナ・バッタはイスラームに改宗したものの、以前の名前を使い続けていた人物と解釈するのが妥当であろう。
30) kurvanti mausulajanāḥ svaśavājirārthaṃ | yatnaṃ sadaiva bahukāruṣu dattavittāḥ | no cintayanti parameśvaram antareṇa | jānāti ko mama kadā maraṇaṃ kathaṃ syāt || [89] yaḥ svāyuṣo ’vadhim avaiti svadehaniṣṭhaṃ | yasyāntako bhavati mitratayātivaśyaḥ | yujyeta taṃ prati śavājirakarma kartuṃ | mleccheṣu durvyasanamātram idaṃ mataṃ me || [90] te vaiśravaṇabhaṭṭādyāḥ kṛtvāpi svaśavājiraṃ | ante yatra mṛtā grāme bhuvi tatraiva śāyitāḥ || [91] eka eko bhuvo hastaśatamātravṛttau rataḥ | parāpraveśado yatnāt prākṛto lajjate na kim || [92] śrutaṃ yac chāstrataḥ sūkṣmaśilāś cec chavabhūtale | sthāpyante tat sukhaṃ tasmin paralokagate bhavet || [93] aho lobhasya māhātmyaṃ jīvadvad yan mṛtā api | śavājirāpadeśena kurvanty āvaraṇaṃ bhuvaḥ || [94] mahānto hanta kurvantu kṛtayatnāḥ śavājiraṃ | tannirmāṇena jīvanti kiyanto api bubhukṣitāḥ || [95] vandyo ’nyadarśanācāro hastamātre bhuvastale | dagdhā yat koṭiśo nityaṃ sāvakāśaṃ tathaiva tat || [96] ityādyanucitā nindā prastāvād vihitātra yat | kṣantavyā mausulair yasmāt kavivāco nirargalāḥ || [97]
参考文献
ĀḌ: Jayanta Bhaṭṭa, 2005. Āgamaḍambara. Csaba Dezsȍ (ed.), New York.
Alberuni: Abū Rayḥān al-Bīrūnī, 1910. Alberuni’s India, 2 vols. Edward C. Sachau (tr. into English),
Trübner.
ĀP: Anonymous, 1994. Ādi Purāṇa. Ikari Y. and Hayashi T. (eds.), In: A study of the Nīlamata:
96
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir, Kyoto, pp. 83–136.
BS: Anonymous, n.d. Bahāristān-i Šāhī. British Library, India Office Islamic, No. 943.
DA: Musṭafá Ḫāliqdād ‘Abbāsī, 1375s. Daryā-yi Asmār. T. Chand and S, A, Ḥ, ‘Ābidī (eds.), New Delhi.
JRT: Jonarāja, 1967. Rājataraṅgiṇī, S. Kaul (ed.), Hoshiarpur.
KK: Śrīvara, 1898. Kathākautuka, R. Schmidt (ed. and tr. into Germany), Kiel.
KRT: Kalhaṇa, 1900. Rājataraṅgiṇī, 2 vols. M. A. Stein (ed.), Westminster.
KRT_P: Muḥammad Šāhābādī, 1974. Rāj tarangīnī tarǧuma-yi Fārsī. Ṣ. Āfāqī (ed.), Rāwalpindī.
Lms2: Muḥammad Šāhābādī, n.d. Rāj Tarangīnī. British Library, Add. 24, 032.
Mms: Anonymous, n.d. Intiḫāb-i tārīḫ-i Kašmīr. Die Bayerische Staatbibliothek, Cod. Pers. 267.
NM: Jayanta Bhaṭṭa, 1969. Nyāyaman ͂jalī. K. S. Vardhacharya (ed.), Mysore.
NP: Anonymous, 1936. Nīlamata Purāṇa. K. de Vreese (ed.), Leiden.
ŚRT: Śuka, 1966. Rājataraṅgiṇī, in S. Kaul (ed.), Rājataraṅgiṇī of Śrīvara and Śuka. Hoshiarpur.
ṬA_ms: Nizām al-Dīn Aḥmad Harawī (dated AH 1003/1594–5). Ṭabaqāt-i Akbarī. Aligarh Muslim
University, Maulana Azad Library, Subhan Allah Collection, 954/3.
ṬA_txt: Nizām al-Dīn Aḥmad Harawī, 1913–41. Ṭabaqāt-i Akbarī. 3 vols. B. De and M. H. Husain
(eds.), Calcutta.
TḤM: Ḥaydar Malik Čādūrah, 2013. Tārīḫ-i Kašmīr. R. Bano (ed. and tr.), Srinagar.
TR: Mīrzā Muḥammad Ḥaydar Duġlāt, 2004. Tārīḫ-i Rašīdī. ‘A. Ġ. Fard (ed.), Tehran.
TSA: Sayyid ‘Alī, 2009. Tārīḫ-i Kašmīr. Z. Jan (ed. and tr. into English), Srinagar.
YZ: ‘Abd al-Raḥmān Jāmī, 1959. Maṯnawī-i Haft Awrang. M. M. Gīlānī (ed.), Tehran.
ZRT: Śrīvara, 1966. Zaynataraṅgiṇī and Rājataraṅgiṇī, in Rājataraṅgiṇī of Śrīvara and Śuka. S. Kaul
(ed.), Hoshiarpur.
大東西域記:玄奘 1971『大唐西域記』水谷真成(訳注), 平凡社.
東方見聞録 : マルコ・ポーロ 1981『東方見聞録』愛宕松男(訳注), 平凡社.
Ahmad, Iqbal. 2013a. Kashmir Inscriptions. Srinagar.
―――. 2013b. Kashmir Coins: Ancient Coins of Jammu, Kashmir, Ladakh and its Frontier Districts.
New Delhi.
Deambi, Bhushan Kumar Kaul. 1982. Corpus of Śāradā Inscriptions of Kashmir. Delhi.
―――. 2008. Śāradā and Ṭākarī Alphabets: Origin and Development. New Delhi.
97
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
Fujii, Masato. 1994. “On the Textual Formation of the Nīlamatapurāṇa,” in Ikari Yasuke (ed.), A Study
of Nīlamata: Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir, Kyoto.
Halbfass, Wilhelm. 1981. India and Europe. New York.
Hangloo, Rattan Lal. 2000. The state in Medieval Kashmir. New Delhi.
Hasan, Mohibbul. 1959. Kashmir under the Sultans. New Delhi, 2002.
Holzwarth, Wolfgang. 1997. “Islam in Baltistan: Problems of Research on the Formative Period,”
in Irmstraud Stellrecht (ed.), The Past in the Present: Horizons of Remembering in the Pakistan
Himalaya, Köln.
Ikari, Yasuke. 1994. “Maps of Ancient Tīrthas in Kashmir Valley,” in Ikari Yasuke (ed.), A Study of
Nīlamata: Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir. Kyoto.
Kak, Ram Chandra. 1932 [2009]. Handbook of the Archaeological and Numismatic in Kashmir.
Srinagar.
Kumari, Ved. 1968. The Nīlamata Purāṇa, vol. 1, Srinagar-Jammu.
Lawrence, Walter R. 1895. TheValley of Kashmir. New Delhi, 1991 (rep.).
Losensky, Paul. 2008. “Jāmi,” EIr.
Majumdar, Rani. 1998. “The Kathakautuka – A Persian Love Poem in Sanskrit Garb,” Journal of the
Oriental Institute 47(3–4), pp. 283–287.
Obrock, Luther. 2013. “History at the end of History: Śrīvara’s Jainataraṅgiṇī,” Indian Economic and
Social History Review 50(2), pp. 221–236.
Ogura, Satoshi. 2011. “Transmission lines of historical information on Kašmīr: From Rājataraṅgiṇīs to
the Persian chronicles in the early Muġal period,” Journal of Indological Studies 22–23, pp. 23–59.
―――. (Forthcoming) “Incompatible Outsiders or Believers of a Darśana?: Representations of
Muslims by Three Brahmans of Šāhmīrid Kašmīr,” Rivista degli Studi Orientali 88.
Pandit, Kashi Nath. 1991. Bahāristān-i-Shāhī: A Chronicle of Medievel Kashmir. Calcutta.
―――. 2009. A Muslim Missionary in Medieval Kashmir. New Delhi.
Parmu. 1969. A History of Muslim Rule in Kashmir (1320–1819). Srinagar.
Rafiqi, Abdul Qayyum. 1976. Sufism in Kashmir. Srinagar. 2009 (Rep.).
Richards, John. F. 1993. The New Cambridge history of India I-5: The Mughal Empire. New Delhi,
2008.
Rodgers, Charles James. 1876. “The Copper Coins of the Sultans of Kashmir,” JASB 48(1), pp. 277–285.
98
前近代南アジアにおけるイスラームの諸相
―――. 1896. “Rare Kashmir Coins,” JASB 65/1, pp. 223–225.
Sanderson, Alexis. 2007. “The Śaiva Exegesis of Kashmir,” in Dominic Goodall and André Padoux
(eds.), Mélanges tantriques à la mémoire d’Hélène Brunner, Pondicherry, 231–442, 551–582
(bibliography).
―――. 2009. Kashmir, BEH.
Slaje, Walter. 2004. Medieval Kashmir and the Science of History. Austin.
―――. 2005a. “A Note on the Genesis and Character of Śrīvara’s So-Called ‘Jaina-Rājataraṅgiṇī’,”
JAOS 125/3, pp. 379–388.
―――. 2005b. “Kaschmir im Mittelalter und die Quellen der Geschichtewissenschaft,” IIJ 48/1, pp.
1–70.
―――. “2007a. The Last Buddhist of Kashmir as Recorded by Jonarāja,” Sanskrit Studies 2, pp. 185–
193.
―――. 2007b. “Three Bhaṭṭas, two Sulṭāns, and the Kashmirian Atharvaveda,” in Arlo Griffith and
Annette Schmiedchen (eds.), The Atharvaveda and Paippalādaśākhā, Aachen.
―――. 2008. “Geschichte schreiben: Vier historiographische Prologue aus Kaschmir,” ZDMG 158/2,
pp. 317–351.
―――. 2012a. “Kashmir Minimundus: India’s sacred geography en miniature,” in Roland Steiner
(ed.), Highland Philology, Halle, pp. 9–32.
―――. 2012b. “Inter alia, realia: An Apparition of Halley’s Comet in Kashmir Observed by Śrīvara
in AD 1456,” in Roland Steiner (ed.), Highland Philology, Halle, pp. 33–48.
―――. 2014. Kingship in Kaśmīr (AD 1148–1459): From the Pen of Jonarāja, Court Paṇḍit to
Sulṭān Zayn al-‘Ābidīn. Halle.
Stein, Marcus Aurel. 1900. Kalhaṇa’s Rājataraṅgiṇī: a chronicle of the kings of Kaśmīr, 2 vols.
Westminster.
Torella, Raffaele. 1994. “On Vāmanadatta,” in P. S. Filliozat et al. (eds.), Pandit N. R. Bhatt
Felicitation Volume, Delhi, pp. 481–498.
Witzel, Michael. 1994a. “Kashmiri Manuscripts and Pronunciation,” in Ikari Yasuke (ed.), A Study of
Nīlamata: Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir, Kyoto.
―――. 1994b. “Brahmins of Kashmir,” in Ikari Yasuke (ed.), A Study of Nīlamata: Aspects of
Hinduism in Ancient Kashmir, Kyoto.
99
中世後期・近世カシミールにおける支配の正統性と宗教アイデンティティ
Wilson, Horace Hayman. 1825. “An Essay on the Hindu History of Cashmir,” Asiatic Researches, 15.
井狩彌介 1993「ヒンドゥー教文献の構造と展開――カシミールのプラーナ文献から」長野
泰彦・井狩彌介(編)『インド=複合文化の構造』法藏館.
井上あえか 2010「カシュミール問題の現在」山根聡(編)『南アジア・イスラームの多角的解明
にむけて――歴史・思想・文学・政治』京都大学イスラーム地域研究センター, pp. 48–65.
小倉智史 2010「カシミールのペルシア語年代記におけるスーフィー伝――在地有力者との
関係を中心に」『イスラム世界』74.
片岡啓 2004「バッタ・ジャヤンタ作『聖典騒動』序幕・第一幕(和訳)」『人文知の新たな総
合に向けて』(京都大学文学部 21 世紀 COEプログラム「グローバル化時代の多元的人文
学の拠点形成」)第二回報告書 V〔文学篇 2 翻訳・注釈〕, pp. 5–29.
――― 2007「正しい宗教とは何か――Bhaṭṭa Jayanta作 Niyāyaman᷈jarī「聖典権威章」和訳」
『哲学年報』66, pp. 39–84.
川尻洋平 2009「カシミールシャイヴァ研究の現状と課題」『南アジア古典学』4, pp. 331–358.
桑山正進(編)1992『慧超往五天竺國傳研究』京都大学人文科学研究所.
サンダーソン, アレクシス 1995「カシミールのバラモンにおける浄と力」マイクル・カリザ
ス他(編)『人というカテゴリー』紀伊國屋書店, pp. 345–391.
竹中千春 2001「カシミール――辺境から国境へ」『アジア研究』47/4, pp. 23–38.
永田啓介 1998「Rājataraṅgiṇī(chapters I–III)と Nīlamatapurāṇa」『インド思想史研究』10.
真下裕之 2007a「デリー・スルターン朝の時代」小谷汪之(編)『世界歴史大系 南アジア 2』
山川出版社, pp. 102–118.
――― 2007b「地方王朝の分立」小谷汪之(編)『世界歴史大系 南アジア 2』山川出版社, pp.
119–134.
松本耿郎 2011「ジャーミーの『ユースフとゾレイハー』における愛の人間完成学」『聖トマス
大学論叢』45, pp. 80–98.




























![On “Explosion of Litigation” in Early Modern England [Chinese 近代早期英国“诉讼爆炸”探析]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631b4c42a906b217b90664fa/on-explosion-of-litigation-in-early-modern-england-chinese-.jpg)



![穿梭在現代塵世裡的古老三輪車 [The survival of trishaws in a modern Chinese city]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c322b3e8acd997705cb8f/-the-survival-of-trishaws-in-a-modern.jpg)