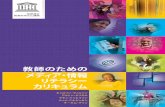『百科全書』を読む――本文研究の概観と展望 2005年3月,...
Transcript of 『百科全書』を読む――本文研究の概観と展望 2005年3月,...
『百科全書』を読む
―本文研究の概観と展望( )1 ―
逸見龍生
I. はじめに
II. 『百科全書』の言説生産
III. 先駆的研究
IV. 『百科全書』校訂研究の基礎的方法論
V.シュワッブ『百科全書目録』(1971~1972, 1984)
VI. 1980 年代以後~『百科全書』基礎研究の方向性
VII.日本の『百科全書』研究
VIII.『百科全書』のデジタル化における問題
IX. おわりに
参考資料:各国版『百科全書』
参考文献表
I. はじめに
ディドロの『百科全書』(1751-1772、補遺 1776-1777)はフランス啓蒙主義思潮のなかで生まれた代表的著作と
してあまりにも名高いにもかかわらず、その全貌がまだ十分に知られているとはいいがたい。このテクストに関し
ほぼ 初のモノグラフを著わした文学史家ルイ・デュクロは「これほど語られていながら、これほど知られていな
い著作はない」と二〇世紀初頭に述べた( )2 。デュクロが一世紀前に記したこの言明は、ジャック・プルースト(モン
ペリエ大学)やジョン・ラフ(ダーラム大学)などの古典的研究を始め、本稿で以下に概観する 1960 年代以後欧
米の百科全書研究の飛躍的な発展を経た現在となっては、むろんそのまま受け取るわけにはいくまい。しかし
日本の研究状況を振り返ってみると、第二次世界大戦後すぐに桑原武夫京都大学教授を中心に組織された京
都大学人文研の共同研究斑による『フランス百科全書の研究』(1954 年、岩波書店)の刊行後は、いくつかの例
外を除けば残念ながら顕著な寄与はみられなかった。
2004 年度より文部科学省の科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成プログラム」に採択され設立した慶應
(1)本稿は平成 17 年 1 月 28 日に慶應大学三田キャンパスで開催されたシンポジウム「『百科全書』問題の今」(慶應大学デジタルメ
ディア統合機構コンテンツデザイン・応用研究ユニット主催)でおこなった口頭発表「『百科全書』研究の概観と展望──慶應義塾
大学 DMC『百科全書』プロジェクト構築に向けて」をもとに書き下ろしたものである。同シンポジウムについては以下の URL を参照
のこと。http://www.dmc.keio.ac.jp/topics/topics2005.html#SYMPO050129
(2)Ducros, Louis, Les Encyclopédistes, Slatkine Reprints, Genève, 1967 (1902), p.iv.
49
大学デジタルメディアコンテンツ統合機構(DMC)において、鷲見洋一慶應大学教授を中心に「『百科全書』デ
ジタル化プロジェクト」が国内外の研究者を集めて発足した。同プロジェクトはこれまでの本国の研究の立ち後れ
を埋め、『百科全書』パリ・オリジナル版を筆頭とする慶應大学所蔵の百科全書関連貴重書コレクションを 新の
研究成果を踏まえ、先端的デジタルアーカイブ技術を用いてハイパーデータベース化し、百科全書研究の国際
的進展に寄与しようとする試みである。
本稿は、同プロジェクトの発足に際して、これまでの『百科全書』研究の成果を特に本文批評校訂、すなわち
情報論的データ化の基盤となるテクストの〈物質的位相〉の観点から整理し、これまで何が明らかにされてきた
か、どこまで研究が進んできたか、いまだ何が解明されないままになっているかを概観したい。
II. 『百科全書』の言説生産――テクストの動態性・物質性
それにしても何がこれまで包括的な『百科全書』本文研究を困難にしてきたのか。まず実際的問題、次に理論
的な観点からいくつかの点を指摘しておく。
(1)実際的な問題としては、量の問題がまずあろう。図版 11 巻と補遺(本文 4 巻・図版 1 巻)を除いて、ディドロ
たちが執筆した本文 17 巻だけを取っても刊本の総頁数は大部のフォリオ版で優に一万六千頁を超える。項目
が扱う主題も、政治経済や歴史地理、哲学や文学など人文学から、数学や力学、化学、天文学、医学など自然
科学全般、同時代を中心とした工芸技術、世界各地の文化・習俗、衣装や料理法、工芸品など日常のごく細部
にいたる膨大な広がりをもつ。『百科全書』の執筆者にしても、身元が実際にわかっている者だけで百数十余名
におよぶ。研究者にとって、個々の項目内容の検討の必要に加え、執筆者が誰か、いつ、いかなる目的をもっ
て項目を書いたかという問題がつねに残り続ける。
(2)さらに、研究者がアクセスできる信頼に足る刊本がきわめて希少であることも挙げられるだろう。現段階では
日本国内で少なくとも十数から二十セットの原本の存在が確認されているが、実際に『百科全書』刊本をつねに
手にとって頁をめくることのできる環境にある幸運な研究者の数はごく一握りの少数に限られている。またあとで
述べるとおり十八世紀書物史、ことに『百科全書』刊行史に特有のきわめて複雑な書物出版事情が介在し、国
内図書館に所蔵の各刊本が真にパリ・オリジナル版なのかどうか、あるいはジュネーヴ偽本なのかいまだ厳密に
は確認されていない。1969 年に刊行され現在比較的流布している 5 巻のコンパクト版があるが、マイクロフィルム
から転写したその本文テクストの欠陥は知られている。フランス内外の『百科全書』抄録版、さらに邦訳(岩波文
庫版)も含め諸国語翻訳に再録されている項目数は、『百科全書』の総項目数からみたとき、あまりにも瑣細であ
る。1990 年代以後米仏でそれぞれ『百科全書』デジタル版がインターネット(シカゴ大学 ARTFL プロジェクト)と
CD-ROM(および DVD)版(ルドン社)で登場した。今回の本邦のプロジェクトのいわば前駆である。しかし、以下
に取り上げるとおり、本文校訂面でいずれも少なからぬ問題点を抱えている。
(3)パリ・オリジナル版刊本の希少さ、刊行当時に出現した偽本の介在、そして書籍からインターネットや
CD-ROM にいたる現代のメディア媒体の進展にあわせたかたちで様々に出現した今日の『百科全書』刊本の本
文再現の拙劣さなどの悪条件に加え、これも後述するとおりパリ版刊行完結前後にイタリアとスイスで刊行が開
始され始めた諸国版にかんしていえば、刊本を閲読するだけでも絶望的な困難さがつきまとう。
50
この点では欧米図書館すら日本の状況とそう変わりがない。たとえばイタリアで刊行された注釈つきのルッカ版
『百科全書』はパリ国立図書館を筆頭にフランス国内図書館での所蔵が確認されていない。むしろ同じく注釈つ
きのリヴォルノ版『百科全書』、スイス・イヴェルドン版『百科全書』、さらにパリ版『百科全書』がモデルとしたチェ
ンバースによる英国百科事典『サイクロピーディア』などを始め同時代西欧の著名な辞書・辞典コレクションが慶
應大学メディアセンターに多数収蔵されており、この一点に限ればフランスよりも国内の研究環境のほうがむしろ
例外的に整備されているといっていいだろう。
だがこうした実際的な問題だけが『百科全書』研究に障害を生み出す主因となったわけではない。問題をさら
に複雑にしているのは、近代以後規範化された文学史や思想史の枠組みそのもののなかに、『百科全書』という
テクストへ注がれようとする視線を周縁的なもの、二義的なものと抑圧してこざるをえなかった事情が伏在してい
ることである。後世における『百科全書』の運命ともいうべきこの受容の問題はそれ自体数多くの議論を含んでお
り、近代化された学問的知や言説の生産の類型学と階層化という理論的な問題一般とも深く関わっているが、こ
こではごく簡潔に要点だけ列挙しよう。ここでもネガティブな「~ない」というかたちで示さなければならない。
(1)執筆者の位階をめぐる複数の水準でのさまざまな困難。いわゆる「百科全書派」と呼ばれる一群の執筆者
集団として同定されてきたテクストの書く主体は、はたしてしばしばそう指摘されてきたように政治的・社会的・イ
デオロギー的な均質性をもつ強固で一貫した啓蒙的意志の結集なのか、それとも複数的で多様な方向性をも
つ相互に異質な個の結節点が形成した、偶発的でゆるやかなネットワークと考えるべきなのか。集合的主体とエ
クリチュールという関係をいかに考察するべきか。十八世紀のように〈個人全集〉という言説装置を成立させ、書
かれたものと書くひと、散乱するテクストとそれを有機的に統合する個としての「作者」に定位させていく欲望が一
方できわめて顕著となった時代に、匿名的な言葉が圧倒的に多数を占め、「個」をいわば隠蔽し、消去しながら
みずからを定立させていこうとする『百科全書』のようなテクストをいかに考えていけばいいのか。
(2)上記の(1)とも関連して、そもそも本文の範囲、位階、境界をいかに確定すべきか。文学や思想という領域で
の「作者」という近代的主体(ミシェル・フーコー)が自律的な閉じた「作品」という神話を論理的に要請したのだと
すれば、そのような眼で『百科全書』のテクストを読んでいこうとする近代以後の人間はある種の違和感を覚えざ
るをえない。
アルファベット順に配列された辞典は直線的な本文テクストの読解を求めない。しかもテクストの 小単位とな
る「項目」(article)はかならずしも個々に完結し閉じられているわけではない。本文途中や末尾などに配置された
参照符号(renvoi)を経由して他の項目へと開かれ、しばしば矛盾しあい、しばしば補完的な両者の関係性のダイ
ナミクスのなかでテクストを統べている隠された意味の層が明らかにされる――項目「百科全書」(『百科全書』パ
リ版第五巻所収)においてディドロ自身が示した参照符号のネットワーク(クロスレフェランス・システム)の意識的
で戦略的な使用法は、『百科全書』の言説生産の本質的な特性としてよく知られるようになった( )3 。
表面的には相互に無関係にみえる項目間を有機的に結びつけあう参照符号の機能のほかに、これまで注目
されることの少なかったものの、近年その重要性がとみに問われるようになったもう一つの隠された機能がある。
項目本文冒頭におかれた分類符号(désignant)である。『百科全書』第一巻冒頭にはベーコンの分類にならって
(3)cf. Starobinski, Jean , «Remarques sur l'Encyclopédie», Revue de Métaphysique et de Morale, 3, 1970, pp.284-291.
51
知のシステムを理性と記憶、想像力の三つに分割して体系化した「人間知識の体系」の分類表がある。「百科全
書序言」(第一巻)でダランベールは、読者が読む項目がこの分類表のどの部分に位置づけられるか示すため
に便宜的に分類符号を各項目冒頭に付したと書いている。すなわちひとつひとつの項目は分類符号を通じて
他の項目と関連づけられ、まとまりをもったひとつないし複数のゆるやかな集合体を形成している。『百科全書』
をひとつの宇宙に見立てるならば、分類符号によって連関されるテクスト群はいわば大小さまざまの星雲ともい
えるかもしれない( )4 。
『百科全書』内部のテクスト間の連関だけではない。ダランベールによる第一巻「序論」が明言する以上に、先行
する同時代の様々な書物――チェンバース『サイクロピーディア』を始めとするフランス内外の様々な既成のテク
スト――を読み、「翻訳」し、書き換えるという間テクスト的な実践をとおして『百科全書』本文の多くが書かれたこ
とも近年ますます明らかとなりつつある。つまり『百科全書』とは、本文の〈外部〉へと向けて、いわば暴力的に開
かれたテクストなのである。『百科全書』を読む読者はテクストの後ろに別の声、別の手の介在をつねに疑ってか
かるほかない。こうした『百科全書』の言語のすぐれて〈外部的〉な位相を無視してしまえば、『百科全書』は中世
的な知の円環という伝統へのノスタルジーにたやすく回収されてしまう。
『百科全書』のテクストが呈する上述の困難にもかかわらず、実は近年活性化されつつある文学史・思想史研
究の新たな動きに呼応して、『百科全書』はエクリチュールやテクストの理論の再構築を促すきわめて興味深い
事例となりつつあるのかもしれないと考えている。その意味でも特に注目したいのは十八世紀地下文書研究の
近年の急激な進展である( )5 。十八世紀フランスにおける文化空間の編成にあってきわめて重要な役割をはたし
た地下文書(littérature clandestine)には、少なからぬ面で『百科全書』の言説生産の特性と重なりあう共通性があ
る。作者の同定がままならず、生産されるテクストはくっきりとした明確な輪郭を欠いたまま、写稿から写稿へと人
の手を介してたえず書き換えられ、削られ、別な言葉と置き換えられ、張り合わされるという産出プロセスを辿るこ
とによって、地下文書は通常の印刷メディアとは異なる独自の流通の力学と、独特な言説生産の技術的位相を
もっていた。
地下文書研究の権威オリヴィエ・ブロック(パリ第四・ソルボンヌ大学)は、論文「マテリアリズムと地下文学性―
―伝承・エクリチュール・レクチュール」においてこうした地下文書独特のエクリチュールの生成の様態を指して、
「書かれたものの成形化」(formation des écrits)と呼んでいる( )6 。生産・流通・受容の過程で多くは匿名の筆者に
(4)分類符号の重要性については、のちに取り上げる次の文献を参照のこと。Leca-Tsiomis, Marie. 1999. Écrire l’Encyclopédie.
Diderot : de l’usage des dictionnaires à la grammaire philosophique, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 375, xii/528 p.
また、2004 年 11 月に『百科全書』における分類符号の機能を主題とする国際コロックがパリ第十・ナンテール大学で開催されてい
る。Colloque international " Les branches du savoir dans l'Encyclopédie ", Université Paris X Nanterre, jeudi 18 et vendredi 19
novembre 2004.
(5)『思想』(岩波書店)2002 年第七号にまとまった形で十八世紀地下文書研究の現状が紹介されている。特に地下文書の研究史
については三井吉俊「地下の水脈へ――ヨーロッパ意識の危機と地下文書」(『思想』前掲書、pp.27-50)の導入部に詳しい。なお
日本で初の地下文書原典の翻訳(野沢協監訳、全二巻)も法政大学出版局から刊行が予定されている。
(6)Bloch, Olivier, «Matérialisme et clandestinité: tradition, écriture, lecture», dans Matière à Histoire, Paris, Vrin, 1997, pp. 272-286.
52
よって加筆や削除、コメントや注釈、議論の修正、論述の方向の転換、議論の再構成がくりかえされ、オリジナル
とその複写、正典と偽書、本文とその注釈の位階がたえず反転するような、本質的に動的で匿名的なエクリチュ
ールの位相のことである。ブロックが指摘した十八世紀地下文書のテクストのダイナミックな生産と流通、受容の
場の生成のありかたは、『百科全書』の本質的に多層的で集合的なエクリチュールの動態性を考える場合にも有
効ではないか( )7 。古典主義時代から啓蒙の世紀へと流れこむ唯物論の思想史的水脈を言語=メディアの物質
的生産と交換という次元に着目して辿る必要を説くブロックの指摘は、『百科全書』という特異な言説の生成の場
における言語のポリティクスを歴史的文脈に引き寄せてあらためて捉え直そうとするときに、光を投げかけてくれ
るのではないか。先行するテクストや言説とのポリフォニックで複数的な声の交叉する場として、作家の個の内部
に完結する代わりに本質的に外部性と他者性を刻み込まれた〈社会的〉なテクストが産出される匿名のプロセス
として、ブロックは「アンシャンレジーム」固有の歴史的・批評的知(ブロックはピエール・ベールの『歴史批評事
典』の意味だと言っている)の実践の場を捉えているが、「作家」としての個をたえず脱=人称化させ、多方向に
向けてそのテクストを開いていくこうした批評的知の契機は『百科全書』の言説がエクリチュールとして形成化さ
れていくその背後にもやはり同様に貫徹しているのではないか。つきつめて言えば、百科全書経験と呼べるよう
な何かが深く十八世紀後半の作家たちに共有されているとすればそれはいかにしてか、また何を指し示すもの
なのか。たとえばディドロという作家と思想家の誕生において、それはどのような意味を担うのだろうか。
ディドロやドルバックといった百科全書派を代表する二人の思想家がともに十八世紀後半の哲学的地下文書
の刊行に深く関わった事実を見ても、地下文書研究と『百科全書』研究は相互に浸透しあう共通の核をもってい
る。そればかりではなく、はたして偶然かどうか二十世紀後半にその研究が質・量ともに飛躍的に拡大した点で
も両者は共通している。両研究の進展においてつねに障害として立ちはだかっていたのが、〈本文〉の位相や書
き手の認定を始めとするテクストの歴史をめぐるきわめて困難な諸事情だった。こうした水準をテクストのマテリア
ルな次元と呼ぶとしたら、『百科全書』研究の場合にせよ、地下文書研究にせよ、好むと好まざるとこのマテリア
ルな次元とたえずつき合ってこざるをえなかったことになる。解釈者はテクストの生成の場、書かれたものの成形
化という本質的に時間的な位相に属するテクストの系譜学的な形成プロセスをたえず問題にしなければならな
いのである。だがそれがブロックの言うように実は十八世紀という時代の言説生産、エクリチュールの産出の深層
を規定するきわめて固有の力学だったとしたらどうか。十九世紀以後の文学史と思想史の制度化された視線か
ら消失していく固有の歴史的な律動を刻み込むものだったとしたら。
以下にプルースト、ジョン・ラフらを筆頭に 1960 年代後半における百科全書本文研究の歴史的な転回点を中
心に概観していく研究小史は、こうした理論的位相とも密接に関わっていくことになるだろう。
III. 先駆的研究
まずプルーストやラフの研究が登場する以前の重要な研究を振り返っておこう。特筆すべきなのはフランス人
研究者ルイ=フィリップ・メイによる「『百科全書』の歴史と典拠」(1938), 次にアメリカ人研究者ダグラス・H・ゴード
ンによる『ディドロの『百科全書』検閲と本文再校訂』(1947)、そして 50 年代に同じくアメリカ人研究者ジョージ・B・
(7)ブロックの同指摘に関してはすでに論じたことがある。逸見龍生「ポリプとしてのメディア」『文学』(岩波書店、2001 年 1・2 月号、
pp.167-169)を参照のこと。
53
ワッツが行なった一連の各国版『百科全書』刊本研究である。
①ルイ=フィリップ・メイ「『百科全書』の歴史と典拠」(1938)( )8
メイの本論文は、百科全書の企画・出版を一貫して支えたル・ブルトンら四書店のうちのひとつであるブリアソ
ン書店が百科全書刊行事業会計担当として残した詳細な会計収支記録を仏国立古文書館で著者が偶然発見
し、revue de synthèse誌にこれを公開したものである。ディドロやダランベールに書店側が毎月支払った編集料、
会合のための食費、編纂や項目執筆のためディドロが書店側に依頼して購入した書籍の細目などを網羅し、百
科全書生成事情を考察するための第一級の史料である。購入書籍細目については後にジャック・プルーストが
La Bibliothèque de Diderotと題して初期から中期にかけてのディドロの思想的発展や文学の受容史を書いたと
きの原資料となった( )9 。会計収支の記載は、ディドロとダランベールが『百科全書』刊行に参加する以前の 1745
年から始まっており、いまだ不明な部分が多い『百科全書』 初期の状況が伺い知れる。その点でも今日もなお
きわめて貴重な資料のひとつでもある。この 初期についてはこれまで殆ど研究がなかったが、鷲見洋一教授
が 1745 年版趣意書を入手、チェンバースとの関連など近年積極的に調査している。
ただし、国立古文書館所蔵の原資料を実際に検討したラフによれば、メイによる転記には抜けや誤記が少なく
ないと言う( )10 。メイが発見した資料そのものの重要性からみてラフの指摘は看過されるべきではないが、しかし
1963 年のラフの指摘以後具体的な調査は私の知る限りまだされていない。この点は今後の研究の進展を待ち
たい。
②ダグラス・H・ゴードンによる『ディドロの『百科全書』検閲と本文再校訂』(1947)( )11
他方、ダグラス・H・ゴードン(ヴァージニア大学)論文の概要とその意義はよく知られている。ゴードンは、通常
の『百科全書』全 32 巻の他に「百科全書関連書類」(略称「extra volume」)と呼ばれる別巻一巻が挿入された
『百科全書』パリ版セットをパリの古書店から購入、この別巻に 1745 年版趣意書(現存するものとしてはこの趣意
書が世界でただ一部のみしかないと長い間考えられていたが、2000 年に鷲見洋一教授がもう一部の趣意書の
存在を古書店カタログに発見、現在では慶應大学メディアセンターがこれを購入所蔵している)や 317 頁 49 項
目に及ぶ『百科全書』本文校正刷が含まれていることを発見した。ゴードンはこのセットが書店側の中心人物ル・
ブルトンの私蔵書であった可能性がきわめて高いことを同論文で実証、『百科全書』本文編集プロセスを明らか
(8)1.MAY, Louis-Philippe, «Histoire et sources de l'Encyclopédie d'après le registre des délibérations et de comptes des éditeurs et
un mémoire inédit», Revue de synthèse, février 1938, no.XV, 109 p.
(9)Proust, Jacques, «La bibliothèque de Diderot», Revue des Sciences Humaines, 23, 1958, Avril-Juin, pp. 257-273.
(10)Lough, John, «Two Unsolved Problems», dans The Encyclopédie in Eighteenth-Century England and other studies, Newcastle
upon Tyne, Oriel Press, 1971, pp. 71-89. 初出は French Studies, 1963, pp.121-135.
(11)2.GORDON, Douglas H., TORREY, Norman L., The Censoring of Diderot's Encyclopédie and the Re-established text, New
York, Columbia University press, 1947.
54
にする決定的資料として提示した。同資料は現在ヴァージニア大学ゴードン・ライブラリーに所収されている( )12 。
ゴードンはこれら校正刷に記載された 49 項目中刊本で完全に破棄された項目「Constitution」を除く 48 項目に
ついて、校正刷と刊本との異同を照合し、編者(大部分はディドロの手になる)や著者が校正刷へ加えた加筆や
修正、当局による処分をおそれたル・ブルトンがディドロら著者に無断でテクストの内容の削除や改変をおこなっ
たいわゆる「検閲」の模様などをつぶさに指摘した。『百科全書』のテクストの具体的な生成のさまを初めて現実
に示したまさに画期的な研究であった。
なおゴードンは同論文で 49 項目の大部分をディドロが執筆したものとみなし、残りをジョクールら他の執筆協
力者に割り振っているが、現在まで進展した執筆者研究によると、ディドロ執筆項目と思われるものは 13 項目、
その中の 9 項目はゴードンの同書の指摘とともに DPV 版に再録されている。
③ジョージ・B・ワッツによる各国版『百科全書』刊本研究( )13
ジョージ・B・ワッツが 50 年代に発表した一連の『百科全書』各国諸版の比較研究は、後にジョン・ラフがその研
究の重要性を指摘し、さらにロバート・ダーントン(シカゴ大学)やフランク・A・カフカー(シンシナティ大学)がそ
の後再び問題を大規模に取り上げたが、それまでの間長く忘却されてきた、いわば「知られざる名著」であった。
いわゆるオリジナルの『百科全書』パリ版だけではなく、概ねオリジナルよりも廉価で、版型が徐々に小型化さ
れてより閲覧しやすくなった多数の『百科全書』後続版がスイスやイタリアなどヨーロッパ各地で 1770 年代に刊行
されている。ワッツはこれに初めて着目し、主にアメリカ国内の大学図書館を調査し、パリ版と発行年、発行所ま
で同一に模してつくられたジュネーブ・フォリオ・リプリント版(1772-1776)の出版経過を辿り、パリ版との主な異同
を指摘した「『百科全書』の忘れられたフォリオ版諸版」(1953)、スイス各地で 1770 年から 1782 年にかけて立て続
けに発刊された四つの諸版を取り上げた「百科全書スイス諸版」(1955)などの論文において、これら各国版『百
科全書』刊本研究の重要性を説いた。十八世紀においてどれだけの規模で『百科全書』が流通し、それがどの
ような社会階層によって、いかに読まれていたか、フランス国内のみならずヨーロッパ諸国でいかに啓蒙思想は
拡大していったかなど、書物の社会史、思想の受容史の観点からも、パリ版以外のこれら後続版『百科全書』の
詳細な研究が今日盛んになってきている。ワッツの一連の研究はそうした流れの先駆的役割を果たすものであ
る。後述するようにロバート・ダーントンは特にヌーシャテル印刷協会による四折版を中心に取り上げて、これらス
イス諸版の出版と普及について精査したが、基本的な事項を押さえるにはワッツのこれらの研究が今なお も優
れているといえる。
なお各国版『百科全書』については、ワッツの研究に加え、レーヴィ・マルヴァーノによるイタリアの諸版(ルッカ
(12)The Douglas H. Gordon Collection of French Books, University of Virginia,
http://www.lib.virginia.edu/small/collections/gordon.html
(13)Watts, George B., «The "Encyclopédie" and the "Description des arts et métiers"», The French Review, XXV, no. 6, 1952, pp.
444-454.; «Forgotten Folio Editions of the Encyclopédie», The French Review, XXVII, no. 1, 1953, pp. 22-29, Addenda 243-244.;
«The Supplément and the Table analytique et raisonnée of the Encyclopédie», French Review, 1954-55, no. XXVIII, 1954-55, pp.
4-19.; «The Swiss Editions of the Encyclopédie», Harvard Library Bulletin, IX, no. 2, 1955, pp. 213-235.
55
版、リヴォルノ版)『百科全書』に関する研究もまた重要である。この分野に関してはまだ現在に至るまで後で紹
介する数点を除いてはほとんど研究がされていない。しかしこれら二種のイタリア版には『百科全書』本文復刻の
頁下にイタリア人編集者による脚注があり、『百科全書』を同時代の人間がいかに受容したのかを伺える一級の
資料である。ともに現在ではきわめて入手が困難なため研究もまだほとんど進まず、今日の研究者にとってはな
おマルヴァーノの論文「『百科全書』トスカーナ版」(1923)( )14 がきわめて有益な情報を与えてくれる。
④ このほか『百科全書』典拠研究として、ルネ・ユベール『百科全書における社会科学』(1923)( )15 を挙げる必要
があろう。古い本であるが、「国際ディドロ学会」の機関誌RDE創刊号にジョン・ラフが『百科全書』研究史を総括
して寄せた論文中の表現によれば、「いまなお有益に読める」著作である( )16 。桑原武夫編『フランス百科全書の
研究』における「政治思想」「経済思想」「歴史」の章はこのユベールの研究に多くを負っている。時代的な制約
もあるものの、現在の眼から振り返ってみると、この研究はその後の『百科全書』研究の流れを導く決定的な寄与
を二点において果たしたと言える。
まず一点は、十九世紀を通じて流布していた伝統的な『百科全書』観、すなわち、『百科全書』はなるほど十八
世紀の論壇に投げかけた「論争的書物」ではあるものの、辞典記述の根幹は新味のない先行記述の寄せ集め
にすぎないとするゲーテにまで遡る従来の見解を批判し、『百科全書』の内部に複雑ではあるが一貫した特異な
知のありかたが認められると指摘した点。哲学者・文化人類学者レヴィ・ブリュルの弟子であったルネ・ユベール
は、『百科全書』に一種の近代的な「社会理論」(社会の起源、社会集団の伸長と歴史、社会的結合関係の契機
の重要性)の萌芽がみられるとし、この「社会理論」には一社会の道徳や心性は社会集団の機構によって差異
が生じるという見解が一貫していており、百科全書派の社会観は現代の比較社会学・比較人類学にも通じてい
ると論じたのである。
第二に、『百科全書』項目本文の典拠となる同時代文献をきわめて詳細に比較調査することによって、ユベー
ルは『百科全書』の著者たちが同時代、そして前世紀までの知的伝統を広く渉猟し、その内容を深く取り入れな
がら、同時にその伝統を乗り越える視点を産み出していたことを、かなりの程度実証しえた。『百科全書』が全体
として形成する言説の特異性を体系的に捉えようとした点と、この言説が先行する言説に対してもっている内在
的連続性と差異の抽出という視点を『百科全書』研究史におそらく初めて導入した点において、ユベールの研
究はまさに先駆的であった。
⑤ 後に、トリーノ大学教授フランコ・ヴェントゥーリによる『百科全書の起源』(1946)( )17 もやはり挙げておかねば
(14)Levi-Malvano, Ettore, «Les éditions toscanes de l'Encyclopédie», Revue de littérature comparée, no. 3, 1923, pp. 213-256.
(15)Hubert, René, Les Sciences sociales dans l'Encyclopédie, «Bibliothèque de philosophie contemporaine», Paris, Félix Alcan,
1923.
(16)Lough, John, «Connaissance de l'Encyclopédie: les progrès accomplis et ce qui reste à faire», Recherches sur Diderot et
l'Encyclopédie, 1, 1986, p. 18.
(17)Venturi, Franco, Le origini dell'Enciclopedia, «Piccola biblioteca Einaudi: 26», Einaudi, 1977 (première édition, 1946)(『百科全
書の起源』大津真作訳、法政大学出版局、1979 年)
56
ならないだろう。『百科全書』出版事業が企画され、ディドロとダランベールの参画を経て若き無名の著作家たち
の集団が『百科全書』刊行に着手していくまでの 初期の状況を厳密な史料分析に基づいて活写した名著であ
る。若きディドロやダランベール、ルソーの交友関係や同時代の政治史、社会史、アンシャンレジーム期の知識
人の社会的機能などを論じて集団的な創造としての『百科全書』の位相にきわめて具体的な輪郭を与えた名著
である。また十九世紀に編まれた近代的ディドロ個人全集であるアセザ=トゥルヌーAssézat-Tourneux版『ディド
ロ全集』(1875-1877)に採録された、ディドロによる『百科全書』執筆項目の選定基準を初めて批判し、少なくとも
その4項目についてはディドロではなく、イヴォン師によるものであることも指摘し、『百科全書』本文研究に新た
な途を拓いた点でも、続くプルーストやラフ、シュワッブの世代にヴェントゥーリ史学はきわめて大きな影響を与え
た。
IV. 『百科全書』校訂研究の基礎的方法論
ジャック・プルースト、ジョン・ラフ、そしてリチャード・N・シュワッブの研究が短期間に一斉に登場した 1960年代
から 70 年代前半にかけて、『百科全書』研究は疑いなく決定的に新たな段階に入った。彼ら三人の研究は、い
ずれも『百科全書』のエディシオンの問題をその研究の根底に据え、詳細な資料調査に基づくきわめて緻密で
体系的な本文研究の方法論を構築したことにその特徴がある。
①ジャック・プルースト『ディドロと百科全書』(1962)( )18
ジャック・プルースト(1926-)の博士論文『ディドロと百科全書』(1962 年、1968 年に第二版、初版への追加・修正
表を付す)は、ディドロ研究のみならず、『百科全書』研究においても今なお 重要の規範的な意味をもつ研究
の巨峰であるといえよう。ヴェントゥーリが 25 歳で執筆したディドロ研究の名著『ディドロの青年時代』(1939)が若
きディドロの知的形成を追って『百科全書』にディドロが参加したところで終わっているのを承け、プルーストは
『百科全書』時代のディドロの思想進展に焦点を当てて、網羅的にディドロと『百科全書』の関係を探っていっ
た。その過程でプルーストは初めて『百科全書』のエディシオンに関する統合的な問題を打ち立て、執筆者の同
定、典拠、renvoi などの内的組成、図版、出版や具体的な『百科全書』編纂作業のプロセスなどに関する研究の
方法論を築いた。これらの研究の成果は補論として巻末に付された「『百科全書』執筆協力者」「ディドロ執筆項
目」、ディドロの執筆した「哲学史」本文と弟子ネージョンが編纂したテクストの異同を比較した「『哲学史』項目の
修正本文」「ディドロ執筆項目およびその典拠文献照合表」の四点にまとめられている。ここでは 初の二点と
後の一点について簡単に内容を紹介する。
a)執筆協力者
「『百科全書』執筆協力者」は各巻序言に記載された執筆協力者 142 名[紛らわしいが、情報提供だけで執筆、
(18)PROUST, Jacques, Diderot et l'Encyclopédie, Paris, Albin Michel, 1996 (1962, première éd.).
57
図版や文字装飾(オーナメント)など実際の作業に加わっていない者も含む]、および序言には記載されないも
のの本文中で項目執筆者として挙げられたり推測の容易な者 18 名、計 160 名についてその人物を可能な限り
厳密に同定し、これをリスト化したものである。同補論 I の冒頭には桑原武夫編・京都大学人文研による『フラン
ス百科全書の研究』も先行研究として挙げられ、かなり強い調子で批判されている(鶴見俊輔らが中心となって
おこなった同研究については後でまた述べる)。この執筆協力者研究については、その後ラフ、カフカーがプル
ーストの調査を更に発展させた論考を発表しているので、後で細説する。
b)ディドロの執筆項目研究
「ディドロ執筆項目」はヴェントゥーリに続き、アセザ=トゥルヌー版『ディドロ全集』に収録されたディドロ執筆項
目の選定方法を批判し、ディドロの書簡や同時代の資料などを参照して新たにディドロが確実に執筆したと思わ
れる項目をリストにしたものである。アセザ=トゥルヌー版『全集』の選定方針は、編集に関する『百科全書』第1
巻緒言の記述に従って、項目(あるいはその一部)に記号などで筆者の記載がないもの、およびアステリクスが
付せられたテクストへの追加・編集補遺についてはすべてディドロによるものとし、うち分量的にも内容的にも重
要とみなされる 969 項目について収録している。しかしアステリクスについては当初の編集方針がしばらく維持さ
れていく(但しこの点についてはラフ( )19 が指摘するように、第十巻の唯一のアステリクスが付された項目
«Marbreur de papier»以後、アステリクスは完全に消える)ものの、無署名項目については、すでに第二巻以後の
諸言ではっきりと言明されているように、巻を追う毎に弾圧を懼れて匿名を希望する執筆者が増え、特に百科全
書事業が八年間の長い刊行中断後、1765 年に一度に 終巻十七巻までの九巻が出版された本文第八巻以後
では、無署名項目の数はそれまでに比べ圧倒的に増えている。
プルーストはアセザ=トゥルヌー版がこうした事情を無視して無署名項目をすべてディドロのものと見誤ったこと
を批判し、アセザ=トゥルヌー版の選定方針に代えてより確実な方法を採り、ディドロの執筆項目としては、1)デ
ィドロのものとしてアステリクスが付された編集補遺項目にまず限定し、無署名項目については 2)テクストにディド
ロの名が明示されているもの、3)ディドロの弟子ネージョンによる証言、すなわち①パンクークによる『方法論的
百科全書』のための「古代・近代哲学」(3 巻、1792-1797[1791 年とのプルーストの指摘をラフにより訂正])、②ネ
ージョン編纂による『ディドロ著作集』(1798)、③『ディドロの生涯と著作に関する歴史的・哲学的回想』(1821、死
後出版)の3点を基準にしてそこに挙げられた項目に限定すべきであるとした。
この結果、アセザ=トゥルヌー版に収録された無署名項目全 414 項目のうち 48 項目のみが確実にディドロのも
のとして取り上げられ、結局アステリクスのついた 555 項目とこの 48 項目を合わせた 603 項目をディドロによる執
筆が確実視される項目と決定した。アセザ=トゥルヌー版に収録された項目数のおよそ半分である(なおこれら
の数は 1965 年のラフの指摘を受けて後に数え間違いなど誤記が訂正され、結局アステリクスのついた項目が一
つ減り 554 項目、無署名項目が 13 項目増え 61 項目、総数でアセザ=トゥルヌー版に収録されたもののうち 615
項目がディドロによるものとされている)。アステリクスのついた項目はディドロによるものとみなし、無署名項目に
(19)Lough, John, «The Problem of the unsigned articles in the Encyclopédie», dans The Encyclopédie in Eighteenth-Century England
and other studies, op.cit., p. 164.
58
ついてはネージョンの記録に基づき確実にディドロのものと証言がある場合のみこれをディドロの執筆項目とし
て選定するという、プルーストが確立したこの方法は、今なお も確実性の高い方法として現行のエルマン社の
『ディドロ全集(DPV 版)』においてもそのまま踏襲されている。
但しこの点は重要なので強調しておくが、いうまでもなくネージョンはすべてのディドロの執筆項目について証
言しているわけではないし、ネージョンのディドロ評価そのものも革命の急転期(いわゆる「バブーフの陰謀」の
挫折後)に、該博な知識をもつ正統な哲学史家としてのディドロをオーサライズするために、ある特定のディドロ
の側面を後代に向けてより強調する傾向があったことは否めない。この点でプルーストの禁欲的な選定方法に
は実は難もあることも認めなくてはならない。事実、無署名項目数が増え、アステリクス付きの項目が激減する八
巻以後の巻になると、プルーストの方法に従うとディドロが執筆したとみなせる項目はごく一握りの少数なものに
限定されてしまう。DPV 版全集でも、『百科全書』のディドロのテクストを集めた四冊のうち、『百科全書』第八巻
以後の全項目はたった一巻(『全集』第8巻)にまとめられているにすぎない。ディドロの執筆量が八巻以後急激
に4分の1以下にまで減ってしまったとは考えにくいのではないか。この問題点を鋭く突いたのが後に見るラフで
ある。
c) 典拠研究
「ディドロ執筆項目およびその典拠文献照合表」は、ディドロ執筆による『百科全書』本文と彼が典拠とした文献
との照合を 145 項目、およそ全体の二割強について指摘した。前半はプルーストが発見したディドロの重要な典
拠、ヤコブ・ブルッカー(1696-1770)『批評的哲学史』(1742-1744)との異同を「哲学史」の 54 項目について取り上
げ、後半は特に 初の数巻でディドロが担当した「同義語」に関する項目 91 項目について同時代の辞書・辞典
との典拠関係を調査したもの。『百科全書』項目が典拠とした文献を項目本文と精密に付きあわせ、異同を確認
するという作業は、ここでもプルーストの本書をもってその嚆矢とする。後述するが、特にこの言語辞書とディドロ
執筆項目との関係は、90 年代に至ってレカ=ツィオミによってさらに詳しく調査された。
以上見てきたように、プルーストの提示した『百科全書』の諸問題とその解決のための方法は、それまでほとん
ど誰も着手することのできなかった『百科全書』時代のディドロの思想の内的進展をテクストの基礎的な水位にま
で降りたって鮮明に説き、『百科全書』本文研究を画期的な新しい水準にまで引き上げた。古めかしい膨大な過
去のデータのコーパス、鬱蒼と暗い過去の言葉の堆積として『百科全書』を観るのではなく、その生成の時間に
まで遡り、執筆、編集、印刷、執筆者間の協力、ディドロら執筆者による既成のテクストの変形や改変、またその
プロセスで現れる様々なヴァリアン
異文の問題など、『百科全書』の産出を可能とする様々な技術的位相を初めて組織的・
体系的に描き出した。その後プルーストは、医学・生理学関係で多くの寄稿者を生んだモンペリエを中心とする
「百科全書派」の社会集団研究『十八世紀バ・ラングドック地方における百科全書思想』(1968)( )20 を刊行し、『百
科全書』の執筆者研究をさらに広げていく。
(20)Proust, Jacques, L'Encyclopédisme dans le Bas-Languedoc au XVIIIIme siècle, Le centre des études du XVIIIme siècle et le
centre d'études occitanes, Montpellier, Faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier, 1968.
59
しかしその一方でプルーストは、七十年代になると詩学(poétique)の領域にも強い関心を示すようになる。哲学
や文学など言説の境界をたえず越境し、同時代の規範的思考に対してたえまないずれや差異を産み出してい
く。後期ディドロのそうしたエクリチュールの形式の特異性を、『百科全書』を媒介にして緻密に読み解く視点を
打ち出していくのである。多方面に及ぶ夥しい文献を読みこなし、他の寄稿者の膨大な原稿にも目を通しながら
大量の項目を執筆した『百科全書』時代のディドロの知の経験は、同時に巨大なエクリチュールの集合的な生成
の場に身を置き、他者の言説(=doxa)の近傍/対抗(=para)としてペンを握る姿勢を持続させること、他者の
〈声〉との対話的かつ「逆説的」(paradoxal)な関係のうちで自己の思惟をたえず重層化・複数化させる戦略を徹
底して学び、身体に沈澱していくことを意味した。『ディドロと百科全書』におけるプルーストの研究をたんにラン
ソン流の実証主義的な姿勢に還元させないでおきたい。プルーストの『百科全書』研究は「作家」ディドロの動態
的な対話の詩学のこうした独自な解読と解きがたく結びついているのである。
②ジョン・ラフ『ディドロ=ダランベール百科全書に関する諸試論』(1968)、『十八世紀英国における百科全書、な
らびにその他の研究』(1971)
イギリス・ダーラム大学の研究者ジョン・ラフ(1913-)による二冊の論文集『ディドロ=ダランベール百科全書に関
する諸試論』(1968)、および『十八世紀英国における百科全書、ならびにその他の研究』(1971)は、『百科全書』
パリ版の研究、およびディドロの果たした役割をあくまで中心に据えたジャック・プルーストの研究を相対化し、デ
ィドロの他の重要な執筆協力者や、フランス以外の他国版の『百科全書』にまで視野を広げて考える機会をえよ
うとする者にとっては、プルーストと同等かそれ以上の重要性をもつ画期的な研究である。
『諸試論』にはまず前述のワッツの各国版『百科全書』諸版に関する先駆的研究を取り上げ、その重要性を再
評価し、特にパリ・オリジナル版とそれと混同されやすい書店主パンクークによるそのリプリント版であるジュネー
ヴ(フォリオ)版とを比較照合した研究(この点についてはシュワッブの『目録』を紹介する際に細説する)( )21 、およ
びやはりパンクークに焦点をあて、彼が 初に企画したものの失敗に終わった幻の『百科全書』新版についての
経緯を整理した研究( )22 (『百科全書』補遺 4 巻と『百科全書』イヴェルドン版の出版もこれに関わっている――こ
の点についても後で述べる)がある。ワッツ以後長い間中断され、停滞していた観のある研究のこの方向は、ラフ
によって再びその重要性に光があてられ、ヨーロッパ規模での『百科全書』受容の拡がりが重視され始めた近年
の『百科全書』研究に新しい潮流を引き起こしたといえるだろう。
だが決定的なラフの研究の意義は、ドルバックとダランベールそれぞれの『百科全書』執筆項目に関してまとま
ったモノグラフを書き、また『百科全書』執筆項目数としては 大の寄与を果たしながら、その伝記事実について
は長くほぼ闇に包まれていたド・ジョクールの人となりをかなりの程度明らかにしたこと( )23 、そして何よりも『百科全
(21)Lough, John, «The Different Editions », dans Essays on the Encyclopédie of Diderot and D'Alembert, London, New York,
Toronto, Oxford University Press, 1968, pp. 1-51.
(22)Lough, John, «The Panckoucke-Cramer Edition », dans Essays...., op.cit., pp. 52-110.
(23)Lough, John, «Louis, Chevalier de Jaucourt (1704-1780). A biographical Sketch», dans The Encyclopédie in Eighteenth-Century
England..., op.cit., pp. 25-70.
60
書』 大の問題点である夥しい「無署名項目」に関して、プルーストを承けてさらにより柔軟な基礎的方法論を確
立した点にあるだろう。このうち特にドルバックの『百科全書』執筆項目の特定に関しては、「無署名項目」に関す
る調査をもとにしたラフの寄与が今なお決定的である。
a) ドルバック執筆項目研究( )24
『百科全書』第二巻緒言で新しい寄稿者としてドルバックが紹介され、以後本文には執筆協力者(-)の記号で
427 項目に渡ってドルバックの執筆項目が明示されていくが、第八巻以後ドルバックの記号を付された項目は著
しく減る。ラフはこの点に注目し、八巻以後激増する無署名項目の中にドルバックが執筆した項目も相当程度含
まれているのではないかと推理していく。
ラフがこれら無署名項目からドルバック項目を選定するために採った方法は、プルーストのそれとはかなり異な
るものの、同様にきわめて独創的である。ラフは、ドルバックの手になることが明示的な 427 項目を精査し、各項
目の末尾に掲げられた他の項目への参照指示(クロスレフェランス)が、かなりの数に渡ってドルバック自身の執
筆項目に対して行われていることに着目すると、今度は参照先のうち特に第八巻以後の無署名項目を調査して
いった。
その結果、ドルバックの名が明示された 427 項目以外に科学・技術関連(450 項目)、ドイツ史(15 項目)、「代表
者」「神権政治」など長くディドロの執筆項目とされてきた政治哲学関連(5 項目)、そして北欧(14 項目)、シベリア
(8 項目)、メキシコ(13 項目)、北米(8 項目)、南米(7 項目)、アフリカ(32 項目)、日本(22 項目)、中国(15 項目)、
インド(59 項目、うち 1 項目は科学・技術関連項目で既出)、イスラム(11 項目)の歴史・習俗・制度・社会を取り
上げた項目など全 13 グループ総計 659 項目について、(1)相互に参照指示が行なわれ、また(2)それぞれ共通
のコアとなる典拠文献が本文中に引用されており、(3)ドルバックがこれらの文献を蔵書として所有していたことが
ドルバック没後の蔵書売却リストから確実視できる点から、ドルバックの執筆項目と見なされる可能性がきわめて
高いことを明らかにした。
特に政治哲学や世界各地域の社会・習俗等にあてられた項目数が新たに 200 点以上発見できるとしたラフの
指摘は、ドルバックの『百科全書』への寄与は主に鉱物学や冶金学など技術系の領域に限られるとしてきた従来
の観点を覆し、『自然の体系』や地下出版された後期ドルバックの反宗教思想とも関わる『百科全書』の隠された
水脈を具体的に探りあてたという意味でもその功績は大きい。ただし、なぜ八巻以後に特定の項目に署名が残
され、他の項目には署名が付されなかったのかの疑問はいまだ解かれていない。この点はプルーストが調査し
たディドロについても同じことが言えるのだが。
b)「無署名項目」研究( )25
ドルバックの執筆項目選定と並ぶ重要さをもつもうひとつのラフの研究は、プルーストの研究成果を承けて
(24)Lough, John, «D'Holbach's contribution», dans Essays..., op.cit., pp. 111-229.
(25)Lough, John, «The Problem of the unsigned articles in the Encyclopédie», op.cit.
61
1965 年に発表した「無署名項目」に関するモノグラフである。ラフはプルーストの研究の重要性を充分に認め、
プルーストの誤記や数え間違いを指摘した上で、問題の無署名項目のうち、1)アセザ=トゥルヌー版には採録さ
れないながらネージョンの資料からディドロのものと確実視できる 32 項目、2)逆に、ネージョンの証言はないけれ
どもアセザ=トゥルヌー版には採録されたディドロの執筆項目と高い確率で認められる 249 項目、3)ネージョンの
証言もなければアセザ=トゥルヌー版に採録されてもいないにもかかわらず、ディドロ執筆項目である可能性の
高い 349 項目、すなわち 630 項目を新たにプルーストのリストに追加した。ディドロが執筆したと思われる無署名
項目数は、したがって、プルーストとラフを単純に足すと 691 項目になる。
1)はネージョンの証言からもディドロの執筆項目なのは確実であり、DPV 版全集にも採用されている。いっぽう
ネージョンによる確実な証言がない2)と3)については、DPV版全集では「ディドロの執筆とみなすことが可能かも
しれないが、この版には収録しなかった項目リスト」(V, pp.211-220)としてタイトルのみ挙げられている。この 2)と
3)に属する 598 項目の割り出しに当たってラフが利用した方法が、ドルバックのときと同じく、項目間のクロスレフ
ェランス・システムの採用(ディドロ自身の執筆項目にレフェランスしているかどうか)と、項目で用いられた典拠資
料の特定による項目のグループ化の手法である。
ここでは主にチェンバースの『サイクロピーディア』を始めとして、ディドロが参照したことの確実な文献が典拠と
して採用されているかどうか検討することが鍵であった。ラフが挙げる項目の3分の2以上は「文法」に分類された
「同義語」に関するものであり、「哲学史」と並んで「同義語」項目がディドロの執筆項目において大きな比重を占
めるというプルースト『ディドロと百科全書』の指摘を裏書きする結果となっている。
いずれにしても、ラフの新規追加分を含めても、8巻以後のディドロ執筆項目として認められる数は、1巻・2巻
だけでおよそ 3500 項目を数えた初期の頃に比較すると、やはりきわめて少ない。初期の項目には地名の説明
など数行程度しか記述のないごく短いテクストが大多数であった点を差し引いても、ディドロの執筆が巻を重ね
るに連れて少なくなったというプルースト、ラフの指摘は誤ってはいないだろう。ただし同じく当のプルースト、ラフ
らも指摘しているように、8巻以後の無署名項目の激増という事情のなかで、いまだ多くのディドロの執筆項目が
特定されないまま残っている可能性もきわめて高い。
同じ論文でディドロ以外の無署名項目の特定についてもラフは新たに試みている。アセザ=トゥルヌー版にデ
ィドロ執筆項目として採録された無署名項目 414 点のうち、ディドロのものでないことが同時代史料などから明ら
かな 102 項目を特定し、また無署名項目全体のうちディドロ以外の執筆者によることが他の文献資料を通じてほ
ぼ確実に特定できる 34 項目を挙げるなどをしている。このように、ラフによって無署名項目の執筆者特定は大き
く前進した。とはいうものの『百科全書』における無署名項目の総数は、数え方にもよるがおそらく 4 万項目はく
だらないはずである。無署名項目研究の領域はいまだ未知の部分がきわめて多い。
V.シュワッブ『百科全書目録』(1971~1972, 1984)( )26
(26)Schwab, Richard N. With the Collaboration of Walter E. Rex, Inventory of Diderot's Encyclopédie, Vol. 6, «Studies on Voltaire
and the eighteenth century (80, 83, 85, 91-93)», Oxford, The Voltaire Foundation, 1971-72; Schwab, Richard N., Inventory of
Diderot's Encyclopédie. VII. Inventory of the Plates, with a study of the contributors to the Encyclopédie by John Lough, «Studies on
Voltaire and the eighteenth century (223)», Oxford, The Voltaire Foundation, 1984.
62
カリフォルニア大学デービス校教授リチャード・N・シュワッブが、ワルター・E・レックスと協力して 1971 年から刊
行を開始した『ディドロ百科全書目録』は、エディシオンとしての『百科全書』総体を初めて厳密に体系的な書誌
学的手法で分析し、本文編6巻・図版編1巻計7巻におよぶ長大な目録を作成した著作である。全体は序論(第
1巻、1971)、本文項目(entry)総目録(第2巻~第5巻、1971-72)、執筆者別総索引(第6巻、1972)、そして図版
総目録およびラフによる「『百科全書』協力者」リストと解説を付した 終巻(第7巻、1984)からなっている。
この『目録』によって以下の点が初めて明らかにされた。
①項目数
『百科全書』各巻毎の項目数の内訳を示すと、以下のようになる。
本文 総ページ数 16,142p
第 1 巻: 1751 A = Azy (914p:5234 項目、5247 事項)
第 2 巻: 1752 B = Cez (871p:6628 項目、6635 事項)
第 3 巻: 1753 Ch = Cons (905p:3758 項目、3765 事項)
第 4 巻: 1754 Cons = Diz (1098p:5022 項目、5027 事項)
第 5 巻: 1755 Do = Esy (1011p:3492 項目、3500 事項)
第 6 巻: 1756 Et = Fn (928p:2419 項目、2427 事項)
第 7 巻: 1757 Fo = Gy (1030p:3131 項目、3137 事項)
第 8 巻: 1765 H = It (936p:3765 項目、3766 事項)
第 9 巻: 1765 Iu = Ma (956p:4240 項目、事項同数)
第 10 巻:1765 Mam = My (927p:3776 項目、事項同数)
第 11 巻:1765 N = Par (936p:4476 項目、4477 事項)
第 12 巻:1765 Parl = Pol (965p:4056 項目、事項同数)
第 13 巻:1765 Pom = Regg (914p:4318 項目、事項同数)
第 14 巻:1765 Reggi = Sem (949p:5065 項目、事項同数)
第 15 巻:1765 Sen = Tch (950p:4583 項目、事項同数)
第 16 巻: 1765 Te = Venerie (962p:4650 項目、事項同数)
第 17 巻:1765 Venerien = Zhéné (890p:3141 項目、事項同数)
合計すると総 71709 項目(うち7巻までに 29684 項目、第8巻以後 42025 項目)あることになる。
これにさらに『補遺』全4巻の内訳を示すと、
63
第 1 巻: 1776 (926p:2752 項目、2759 事項)
第 2 巻: 1776 (933p:2262 項目、2263 事項)
第 3 巻: 1777 (984p:2158 項目、事項同数)
第 4 巻: 1777 (1004p:1680 項目、事項同数)
すなわち総項目数 8852 項目が『補遺』には含まれている。
②図版点数
さらに図版点数も以下のように明確になった。
図版 総数 2885 枚
第 1 巻: 269 点 1762
第 2 巻: 233 点 1763
第 3 巻: 201 点 1763
第 4 巻: 298 点 1765
第 5 巻: 248 点 1767
第 6 巻: 294 点 1768
第 7 巻: 259 点 1769
第 8 巻: 254 点 1771
第 9 巻: 253 点 1771
第 10 巻:337 点 1772
第 11 巻:239 点 1772
『補遺』
全 1 巻:244 点 1777
③執筆者総数
プルーストが『ディドロと百科全書』「『百科全書』執筆協力者」リストに挙げた 160 名は、ディドロが関与していな
い別の版と考えるべき『補遺』は除き、項目執筆に現実に携わった者も、図版作成や情報提供をしたに留まった
者もすべて一様に区別なく挙げている。それに対しシュワッブの『目録』は、無署名項目を除く全17巻すべての
署名入り項目を網羅的に調査し、その中から 139 名の項目執筆者の名前を特定し、さらに 3 名の異なる匿名の
項目執筆者を割り出した。すなわち『百科全書』本文の執筆者としては総数で 142 名、およびそれぞれの執筆者
の執筆項目が具体的に判明したことになる(執筆者別総索引にこれらのシュワッブらの調査の結果は反映され
ている)。後に紹介する『百科全書派人名辞典』でカフカーがフランス「百科全書派」たちの伝記的事実の詳細
64
な調査をした際に、カフカーが対象としたのはシュワッブが明らかにした匿名以外のこれら本文執筆者 139 名で
ある。また、シュワッブの作成した索引は、先ほど挙げたプルーストとラフの無署名項目に関する重要な先行研
究の成果が織り込まれられているという点でも、学術的な信頼度のきわめて高いものとなっていることを付け加え
ておく。補遺4巻については 88 名の執筆者別索引が挙げられている。不明者の多くは第7巻が十年後に出版さ
れた際に、補足情報としてかなりの程度明らかにされた。
ここまで見てきたことからも明らかなように、プルースト、ラフ、シュワッブのまさに巨大なと言うべき研究によっ
て、『百科全書』パリ版に関する大きな研究史の転回が 60 年代から 70 年代にかけて進んだ。もう一度それをまと
めて見よう。
まずそれは特に『百科全書』を生産する側、特に執筆者の研究を中心に進められたものであったことに留意し
よう。『百科全書』に特に関係の深い作家の執筆項目の確定がディドロを中心としてかなりの程度進んだ。その
研究の過程で、特にラフが先鞭をつけたように、クロスレフェランス・システムが膨大な無署名項目の海から執筆
者を個別に割り出すために重要な意義をもつものとして特に重視されることになった(その点で、これは付け加
えなければならないが、シュワッブが項目総索引を作成するに当たって参照指示記号を省いたことはきわめて
残念である)。直接にテクスト(本文)の産出に関わる執筆者の総数、その執筆項目の全体像が特にシュワッブの
研究によってかなり明確化された。こうした研究の方向は集団的・匿名的な『百科全書』の全体像をまずは各執
筆者という個のプリズムを通して解析してみせたところにその 大の意義があったと言ってもよいだろう。その方
向の延長線上に、フランク・A・カフカーの『百科全書派人名辞典』(個人編)(1988)( )27 があると言ってよい。カフカ
ーの研究はシュワッブの『目録』から明らかとなった『百科全書』本文項目執筆者 138 名について詳細な伝記的
事実をおさえ、個々の執筆者に関する 新の研究成果を文献リストに網羅した労作であり、同辞典続編( )28 ととも
に『百科全書』研究に必須のものものとなった。研究が立ち後れていた『補遺』については、キャスリーン・ハーデ
スティが 1977 年に発表した研究『百科全書補遺』( )29 によってかなり進み、『補遺』の執筆者 46 名、『百科全書』イ
ヴェルドン版からの参加執筆者 16 名、『補遺』が典拠として挙げて引用した著者 16 名、匿名著者 9 名、すなわ
ち総計 87 名のうち、78 名までは執筆者を特定している。ディドロやドルバック以外、これもラフが先鞭をつけたジ
ョクールとダランベールの二人の「百科全書派」の巨頭について、その『百科全書』への具体的寄与の研究もか
なり進んできている。特に 14000 項目と独力で『百科全書』の4分の1弱の項目を書き上げたジョクールについて
は、マドレーヌ・F・モリス( )30 などによる再評価の作業が進みつつあることは注目すべきである。『百科全書』の底
流を流れるプロテスタンティズム思想の驚くべき重要性については近年ジャック・プルーストも指摘するようになっ
(27)Kafker, Frank-A (in Collaboration with Serena L. Kafker), The Encyclopedists as individuals: a biographical dictionary of the
authors of the Encyclopédie, Vol. 257, «SVEC», Oxford, The Voltaire Foundation, 1988.
(28)Kafker, Frank-A, The Encyclopedists as a group: a collective biography of the authors of the Encyclopédie, Vol. 345, «SVEC»,
Oxford, The Voltaire Foundation, 1996.
(29)Hardesty, Kathleen, The Supplément to the Encyclopédie, «Archives internationales d'Histoire des idées», Hague, Martinus
Nijhoff, 1977.
(30)Morris, Madeleine F, Le chevalier de Jaucourt. Un ami de la terre (1704-1780), Genève, Droz, 1979.
65
たが、スイス・プロテスタントの家系の出身であり、ディドロやドルバックとは異なり無神論を奉じなかったジョクー
ルは、今後の『百科全書』研究の鍵となるかも知れない。その点で、モリスの研究はジョクールの『百科全書』との
関連をプルーストやラフの方法論を継承しつつかなり明確化した重要な研究である。ダランベールについては、
マルティーヌ・グルー、ヴェロニク・ル・リュの諸研究が重要であるが、ここでは触れる余裕はない。プルーストが
調査したモンペリエと百科全書思想に関しては、ロズリーン・レイの十八世紀生気論の研究(2000)が『百科全書』
との関連で重要であろう。特にレイの研究はいまだ未整理の部分がきわめて多い第八巻以後の『百科全書』に
ついて大きな示唆を与えている( )31 。
④異本、異文との比較照合
だがしかし、『百科全書』研究の基礎領域を見事な形で拡充させたシュワッブの『目録』の意義はこれだけにと
どまらない。『目録』を別の意味で際立たせているのは、おそらく『百科全書』研究史上初めてパリ・オリジナル版
の様々な異本の比較照合をし、印刷や製本、植字工や製本、活字デザインなど印刷工程を中心とする『百科全
書』のいわば物質的な位相をきわめて具体的で詳細なかたちで明確に浮かび上がらせたことにあるだろう。
シュワッブは、総目録のための底本となる版を探索するなかで、カリフォルニア大学デービス校、同大学リヴァ
ーサイド図書館、ヴァージニア大学(ゴードン・セット)、オックスフォード大学クイーン校、同テイラー校など英米
の大学図書館所蔵の『百科全書』6セットを中心に、仏国立図書館、マザリーヌ図書館、仏国立古文書館、ロンド
ン大学、ウォーバーグ研究所など世界各地図書館で総計26種の百科全書パリ・オリジナル版の比較調査を行
なった。その過程で彼は、いわゆるパリ版『百科全書』にも、1751 年以後順次発行されたオリジナル版のほか、
①1752 年下半期に改版出版された第2フォリオ版(第1巻と第2巻の改版)、②1754 年に改版された第3フォリオ
版(第1巻、第2巻、第3巻の改版)、③第1巻から第7巻までの偽造本(カリフォルニア大学リヴァーサイド図書館
所蔵、いわゆるリヴァーサイド版)、④パリ版を忠実にパンクークらが模したと言われるジュネーヴ・フォリオ版の4
種類の版が少なくともあることを発見した。これらの4種類の版は区別されずにすべてオリジナル版とみなされて
各国図書館で購入されており、シュワッブの調査によると、オリジナル版に一部第2・第3フォリオ版が混入してい
たり、あるいはパリ版とみなされたセットの半数は実はジュネーヴ・フォリオ版が入っていることがしばしば見られ
ることが明らかとなった。例えば、現行で も流布していると思われる『百科全書』のファクシミリ版(シュツッツガ
ルド版)は典型的な混合版である( )32 。本文の六巻、八巻、十二巻、図版の一巻、十巻、十一巻はジュネーヴ版
(31)Groult, Martine, D'Alembert et la mécanique de la vérité dans l'Encyclopédie, Paris, Champion, 1999; Le Ru, Véronique, Jean Le
Rond d'Alembert philosophe, Paris, Vrin, 1994.; Rey, Roselyne, Naissance et développement du vitalisme en France, de la deuxième
moitié du 18e siècle à la fin du Première Empire, Préface par François Duchesneau, Oxford, Voltaire Foundation, 2000.
(32) «Unfortunately the recent photographic facsimile of the Encyclopédie published by Frommann Verlag, Stuttgart, is a mixed set.
Vols. vi, viii, and xii of the text and vols. i, x, and xi of the plates are reproduced from the Geneva edition. In other respects as well,
this edition is not all that one might wish : the colophons for all the volumes through vii, except that of vol. iii, are missing. Much of
the mispagination throughout the volumes of text has been corrected and a substantial number of signature designations are missing.
A few pages of the texte are simply blanks. The asterisk is absent on *CHA, III.I, *D, IV.609 and *Fraude, VII.291. Many of these
peculiarities may be the result of failures in the photographic processes», Inventory, t.1, op.cit., pp.61-62.
66
のものとなっている。
このことが著しく問題となるのは、4つの版すべてに違いがあることが判明したからである。例えばオリジナル・
第1フォリオ版に見られた誤記(Errata として巻末にまとめてリストにされている場合が多い)が第2フォリオ版、第3
フォリオ版では訂正されて本文で組み直されている箇所が見つかったり、逆にオリジナル版に見られる執筆者記
号や参照記号が第2フォリオ版以後で消失していたりなどする箇所が少なからずあった。こうした異本、異文の
存在は『百科全書』のような大部の書物が問題となる場合、きわめて大きな困難をもたらさざるをえない。本文だ
けでも1セット1万6千頁を超える『百科全書』では、たとえ同じ版でも印刷途中で活字の摩耗などによって版の
組み替えが行われざるをえないような場合には、本文の改変が生じるため、完全に同じひと揃いはひとつも存在
しないということになる。とはいえ、あらゆるセットすべての本文を逐一検討することは量的に不可能である。そこ
で、この問題の解決のためにシュワッブは、基準となる特徴的な印刷上の細部のみに着目してそれらを各版に
ついて比較していくという手法を取った。
1)パリ版の三版の間の異同については も詳しく調査し、タイトル頁のテクスト(表題、献辞、出版社名など)およ
び図版、奥付などの分割線の数、各巻冒頭におかれた木彫職人パピヨンによる活字装飾(オーナメント)、頁番
号の記載の誤記、そして項目の「見出し」および「執筆者記号」を比較する。この結果、特に第3フォリオ版には
数多くの改変が「執筆者記号」の部分で見つかった(はたしてこれは植字工のミスなのだろうか、それとも修正な
のだろうか。シュワッブは迷わず前者を採っているものの、ここは一考の余地がある)。
2)リヴァーサイド版、ジュネーヴ版については、明らかに他の印刷業者による異本であることが明瞭なため、本文
項目は検討せず、タイトル頁、奥付、頁番号の記載などのみ。この場合はオリジナル版と区別ができればよいか
らである。
以下に示すのはシュワッブの『目録』の示す上記の方法論を使って行なった、慶應大学所蔵の『百科全書』パ
リオリジナル・フォリオ版本文十七巻の照合調査結果である。
□慶応大学図書館所蔵『百科全書』パリ=ヌーシャテル版
○パリ版各版、ジュネーヴ・フォリオ版、リヴァーサイド版との照合結果(参照 Schwab, Inventory, vol.1., p.114)
シュワッブの掲げた各版の比較照合リストのうち、慶應蔵書がパリ版と一致した項目には○を付した。
■扉絵、序文、その他
67
vol.1
Dedication ○
i, top ○
i, L ○
xlv, bottom,○
xlvi, Double ○
xlvii, Double○
xlvii, *Ex ○
li, Double ○
li, *Ob ○
li, Double ○
lii, Two Double ○
facing I, × facing
xlvii Taylor と同じ
(Schwab, 68,
misnumbering ○)
vol.2
i, triple ○
i plain 'L' ○
iii, Correction ○
[]○
1, Rect ○
1, B, pas. ○
473 C, Pap ○
871, De l'Impri ○
Unnumbered
*asple × [Scwab
69, note71 のどの版
とも適合しない]
(Schwab, 69,
misnumbering 134
as 334 ○)
vol.3
i, top ○
i, L ○
xiv, Double ○
xv, Double ○
xv, ERRATA ○
[] ○
[] ○
xvi, bottom ○
1, C, pap ○
905, Double ○
905, De l'impri ○
[906]ERRATA ○
(misnumbering 59
as 65 ○
636 as 536 ○
819 as 619 ○)
vol, 4.
i, top ○
i, N ○
iii, triple ○
iii, Errata ○
iv, Errata ○
iv, Ornament ○
1, top ○
1, C, pap ○
608, bottom, Or ○
609, D, pap ○
1098, Double ○
[]○
1098, De l'Imprim
○
(misnumbering 223
as 233 ○
269 as 196 ○
892 as 92 ○)
vol5. (傷み多し)
i, top ○
i, S ○
ii, bottom ○
iii, L ○
xviii, ornament ○
1, ornament ○
1, D ○
182, ornament ○
183, E ○
1011, ERRATA ○
1011, ERRATA ○
1011, ERRATA ○
[] ○
[1012], ERRATA
○
[1012], Double ○
[1012], De
l'Imprim ○
(misnumbering 859
as 759 ○)
vol. 6 [全体的に折
れ目あり]
i, top ○
i, P ○
vi, Double ○
viii, Ornament ○
[時の老人]
1, top ○
1, E ○
340, bottom ○
341, F ○
926, Double ○
926, De l'imprim
○
[927-928],
ERRATA [Schwab
の誤植か。 III-V ま
68
である]
(misnumbering 450
as 350 ○
856 as 848 ○]
857 as 849 ○
859 as 851 ○
904 as 490 ○)
vol. 7 [後半にかな
り皺あり]
i, top ○
i, L ○
xiii, Double ○
1, top ○
1,, F ○
406, Ornament ○
407, G ○
[] ○
1025, Double ○
1025, De l'impri
○
1026, Single ○
1026-1030,
ERRATA ○
(misnumbering 922
as 622 ○)
vol. 8
i, Double ○
1, H ○
423, I ○
Tableau des
Mesures... は
924-925 の 間 に 挿
入 (934-935 ではな
く)
(misnumbering 366
as 386 ○
422 as 224 ○
486 as 436 ○)
vol. 9
1, J ○
105, Double ○
(misnumbering 770
as 670 ○
104 and 782 not
numbered ○ )
vol. 10
1, M ○
(misnumbering 226
as 126 ○
329 as 331 ○
335 as 337 ○
336 as 338 ○
585 as 595 ○
710 as 610) ○
vol. 11
1, N ×
[geometric; O と P
に つ い て は Large
Plain で OK だが]
295, Double ○
733, Double ○
vol. 12
1, P ○
124, Ornament ○
(misnumbering 257
as 277 × 修正済
み
278 as 280 ○
563 as 463 ○
573 as 357 × 修
正済み
883 as 873 ○)
vol.13
1, P ○
635, Double ○
635, Q ○
731, Double ○
731, R ○
misnumbering 594
as 584 ○
636 as 638 × 修
正 済 み [Schwab,
Ibid., 77, note 86 を
参照]
730 not numbered
○
vol.14
1, R ○
451, Double ○
451, S ○
misnumbering 255
as 257 ○
273-280 as
373-380 ○
678 as 778 ○
vol.15
1, S ○
783, T ○
misnumbering 408
as 418 ○
813 as 713 ○
69
vol. 16
1, Triple ○
1, T ○
789, U ○
misnumbering 205
as 105 ○
206 as 106 ○
627 as 527 ○
628 as 528 ○
vol. 17
1, V ○
583, W ○
647, X ○
661, Y ○
685, Z ○
not numbered
582 ○
660 ○
854 ○
887 ○
■本文
1, A pap ○ 914 以後 ○
○パリ版初版、1752 年二版、1754 年三版との照合結果(参照、Schwab, Ibid., pp.85
et suiv.)
シュワッブの掲げた本文と異本の比較照合リストのうち、慶應蔵書がパリ版初版と一致
した項目には○を付した。
vol 1
i Discours ○
5a ○
5b ○
6a ○
8a ○
10a ○
11b ○
11b ○
17b ○
25a ○
25a ○
25b ○
32a ○
33b ○
34a ○
34a ○
38b ○
39b ○
40a ○
58a ○
59b ○
63a ○
68a ○
68b ○
69b ○
73b ○
81a ○
85b ○
85b ○
93b ○
93b ○
94a ○
94a ○
94b ○
94b ○
94b ○
94b ○
108a ○
110b ○
112a ○
114a ○
114a ○
115a ○
132b ○
138a ○
141a ○
141b ○
146a ○
161b ○
164a ○
173a ○
70
178b ○
179a ○
181a ○
181a ○
181b ○
182b ○
182b ○
192a ○
192b ○
192b ○
192b ○
192b ○
198a ○
207b ○
210a ○
213b ○
214a ○
225a○
240a ○
240a ○
242b ○
245a ○
245a ○
247a ○
256a ○
262b ○
264a ○
289a ○
307b ○
313b ○
316a ○
317b ○
318a ○
322b ○
322b ○
326b ○
326b ○
355b ○
358a ○
365b ○
384b ○
386b ○
393b ○
395a ○
397a ○
407b ○
445a ○
468a ○
487a ○
488a ○
488b ○
495b ○
496b ○
502a ○
521a ○
525a ○
533b ○
542a ○
546a ○
561b ○
563a ○
565a ○
600b ○
603a ○
604b ○ Schwab
判に誤植。Arcanée
で は な く 、
Arcannée]
610b ○
615a ○
615b ○
621b ○
635b ○
636a ○
636a ○
636a ○
636a ○
643b ○
697b ○
698b ○
700a ○
701a ○
705b ○
718a ○
718a ○
720b ○
745a ○
746a ○
746a ○
747b ○
757b ○
761b ○
776a ○
783b ○
817b ○
822b ○
839b ○
857a ○
857b ○
861b ○
863a ○
865b ○
879a ○
880b ○
886b ○
892b ○
895a ○
903a ○
906b ○
906b ○
909b ○
909b ○
vol.2
4b ○
15b ○
71
16b ○
23a ○
23b ○
23b ○
24a ○
29a ○
56b ○
57b ○ [Blason,
ではなく en terme
de Blason とイタ]
63a ○
63b ○
74b ○
74b ○
74b ○
92b ○
96b ○
97a ○
97b ○
98a ○
98a ○
131a ○
139a ○
142b ○
145a ○
146a ○
161a ○
162a ○
222a ○
226a ○
255b ○ [Blason,
ではなく en terme
de Blason とイタ]
347a ○
347b ○
362b ○
371a ○
372a-b ○
372b ○
379b ○
383a ○
388a ○
390a ○
410a ○
420b ○
443a ○
446a ○
448a ○
454b ○
455b ○
456b ○
466b ○
470b ○
527a ○
539a ○
541a ○
568b ○
584b ○
600b ○
619a ○
624a ○
629a ○
798b ○ [Blason,
ではなく en terme
de Blason とイタ]
831a○
844a ○
vol 3
19a ○
116a ○
116b ○
127b ○
140b ○
144a ○
160b ○
254a ○
308b ○
338b ○
402a ○
457a ○
602a ○
700a ○
709b ○
781a ○
899a-b ○
■ censored texts and the cancels ( 参 照 Schwab, Ibid., pp.127 et suiv. ) A
(cancellanda)か B(cancellant, final version)かを調査
t.1
91 A
t.2
34a B
35a B
35b B
[arrête-toi のあとの
ヴィルギュルなし]
398a B
398b B[griève
のあとのヴィルギュ
72
ル な し 、 イ タ の
Diction.n はひとつ]
t.3
357b B
782a B
782a B
782b B
783a B
783b B
784a B
784a B
784b B
784b B
784b B
785a B
785a B
785b B
786a B
786a B
786b B
788a B
t.4
19a B
19a B
19a B
19a B
19a B
19a B
19b B
19b B
19b B
19b B
19b B [Schwab
版 lont-temps → 慶
応版 long-tems]
20a B
20a
B[Autrefoi
s des → Autrefois
les]
63 [マニュスク
リとの対照が指摘さ
れ て い る
Constitution
unigenitus について
はここでは除 く。削
除 を示 すアステリク
ス 63b 欄外下部に
あり]
155a B[avouoit
→ avoit, Enfin 、
Seychelles の 後 の
ヴィルギュルなし。]
295a B
295b B
296a B
296a B
296b B
296b B
296b B
296b B
296b B
296b B
523a B
523a B
523b B
524a B
529b B
530b B
t.6
533a B
533a B
534a B
534a B
534a B
534a B
534a B
534a B
534a B
534a B
534b B
534b B
534b B
534b B
534b B
535a B
535a B
535a B
535a B
535a B
535a B
535a B[soutenir
→soûtenir]
535a ! [terre,
lui fournit
d'ailleurs quelques
autres bestiaux]
535b B
536a B
536a B
536b B
536b B
536b B
536b B
536b B
536b B
537a B
537b B
537b B
537b B
537b B
541a B
73
541a B
542b B
542b B
582a B[sans
s'amollir のあとにヴ
ィルギュル]
t.7
574b B
t.11
735a B
736b B
736b B
736b B
737a B
74
おおむね『目録』の記述にほぼ完全に一致している。この結果からみても、慶應大学
所蔵『百科全書』が少なくとも本文については間違いなくオリジナル・エディションの第
一フォリオ版であることがわかる。さらに、リストに見られる cancellanda/cancellant のとこ
ろは、前述のゴードン研究で明らかになった編者による修正前のテクスト(cancellanda,
A)および修正後のテキスト(cancellant B)のどちらであるか照合した部分であるが、ここ
で興味深いのは、慶應所蔵版第一巻にAすなわち編者による修正以前のテクストが見
つかることである。このことは、慶應所蔵版第一巻が、『百科全書』刊行が始まってその
直後、第一フォリオ版刊本の中でもきわめて 初期に印刷された貴重な刊本の一冊で
あることを示す根拠となるだろう。
さて、印刷上の細部の特徴からこうして各版それぞれの違いを洗い出していったシュ
ワッブの発見は、『百科全書』研究にいくつかの新たな問題を拓くことになった。一言で
言うならば、それはメディア媒体としての『百科全書』の技術的位相の重視である。文学
や思想研究者はしばしばテクストの内容、テクストの情報にのみ関心を寄せ、この情報
を載せ運ぶ情報媒体の物理的・物質的層――支持体(シュポール)――に特別の注
意を払うことはほとんどない。しかしながら、その出版・刊行・流通・伝播のプロセスその
ものが言説の生産と緊密に結びついていた『百科全書』のような書物の場合、問題は
大きく異なってくる。どういうことか。たとえばシュワッブが重視した弁別要素の一つであ
る活字装飾(オーナメント)は、ジャン=ピエール・ペレのアンシャンレジーム期の印刷技
術に関する記念碑的研究(ジャン=ピエール・ペレ『十七世紀・十八世紀におけるイヴ
ェルドンの印刷所』1945) ( )33 や、シルヴィオ・コルシニによる地下思想とその流通・伝播
の拠点である印刷所との関連に関する近年の研究 ( )34 が明らかにしているように、印刷
(33)Perret, Jean-Pierre, Les Imprimeries d'Yverdon au XVIIe et XVIIIe siècle, Lausanne, 1945.
(34)Corsini, Silvio, «Imprimeurs, libraires et éditeurs à Lausanne au siècle des Lumières», dans
Le livre à Lausanne. Cinq siècles d'édition et d'imprimerie 1493-1993, sous la direction de Silvio
Corsini, Lausanne, Payot Lausanne, 1993, pp. 49-69.; La preuve par les fleurons? Analyse
comparée du matériel ornemental des imprimeurs suisses romands 1775-1785, Ferney-Voltaire,
75
工房の抱える装飾活字職人がそれぞれ個性を発揮して独自の様式に練り上げたもの
である。周知のように、十八世紀には禁書を逃れて多くの反宗教的・体制批判的書物
がカムフラージュのため匿名や偽名、あるいはいわゆるfausse adresseで出版された結
果、特定のテクストの真の出所を同定することは必ずしも容易ではないが、オーナメント
の様式がその同定のための唯一の手がかりとなっている場合も少なくない。シュワッブ
によるオーナメントの着目は、『百科全書』の背後に拡がるほとんど注目されないもうひ
とつの文化的場(ブルデュー)、印刷工や植字工、活字装飾職人、書店主や印刷工房
といった複雑なエージェントからなる十八世紀印刷技術の歴史的厚みについて研究者
の目をあらためて開かせることになった。アメリカの歴史学者ロバート・ダーントンの一連
の『百科全書』刊行史研究はまさにここ関わってくる。
『百科全書』研究に様々な画期的な地平を切り開いたシュワッブの記念碑的研究で
あるが、その精緻な目録にたった一点だけ不満があるとすれば、それは「本文項目総
目録」の中に、各項目内の参照先項目のリストが加えられかった点につきるだろう。項
目目録には見出し、分類符号、執筆者、項目の長さまでも記載されているものの、他
項目の参照指示まではリスト化されていない。
また『百科全書』本文中に明示的に引用された文献の表題や著者名等二次的書誌
情報をシュワッブが割愛した点も悔やまれる。これらの点まで考慮されていたら、まさに
この「目録」は完璧と言えた。後に見るように、デジタル化された現行の『百科全書』
CD-ROM 版やインターネット版は、こうした問題を一顧だにしていない。
V. 1980 年代以後~『百科全書』基礎研究の方向性
①ダーントン~百科全書刊行史研究
ワッツやマルヴァーノの業績を紹介した第 III節ですでに述べたように、八十年代以後
現在までの『百科全書』研究において主流となりつつある研究動向は、スイス版、イタリ
Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 1999; «La contrefaçon du livre sous l'Ancien
Régime», dans Les presses grises. La contrefaçon du livre (XVIe-XIXe siècle), texte réunis par
François Mourreau, Paris, Aux amateurs de livres, 1988, pp. 22-37.
76
ア版など『百科全書』後続版を研究の主眼に据え、パリ版中心の研究に傾いてきた観
のある従来の研究をよりヨーロッパ規模の啓蒙の受容研究へと関心を広げていこうとす
るものである。この動きを決定的なものとしたのが、ロバート・ダーントンによる『「百科全
書」のビジネス』(1979)など一連の百科全書刊行史研究 ( )35 である。ダーントンは、主に
スイス諸版、特に『猫の大虐殺』( )36 以来彼の書物の社会史研究のなじみのフィールド
ワークの対象であるヌーシャテル印刷協会が刊行した『百科全書』四折版を中心に、後
続の書店主たちがいかに『百科全書』再版刊行事業を企画し、それを実現させ、廉価
版・普及版の形でパリ版の読者たちより更に広汎な社会階層にまで広げ、ヨーロッパ各
地域にまで浸透させていったかを克明な資料とともに明らかにしていった。ダーントンに
よれば、ヌーシャテル印刷協会の資料は、ヨーロッパに現存する印刷史史料としてはパ
リや他の主要都市など比較にならないほどの理想的なかたちでアーカイブ化されてい
るらしい。じっさい、印刷計画の詳細、紙の原価、印刷費、運送費、価格、売上、純利
益、スイス版予約販売者の分布、職種割合など『百科全書』研究としてはこれまで類の
なかった様々な事実がダーントンの研究によって初めて実証された( )37 。
②『百科全書』パリ版の〈前〉と〈後〉
カフカー編纂による『十七世紀および十八世紀における百科全書~『百科全書』の9
つの先駆』(1981)、『十八世紀後期の百科全書~『百科全書』の 11 の継承』(1994)もま
た、同様の関心から生まれた研究論文集である( )38 。カフカーの関心は、ダーントンと重
(35) Darnton, Robert, L'Aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800. Un best-seller au siècle des
Lumières, Paris, Librairie Académique Perrin, 1982 (original version, 1979); «Un imbroglio
bibliographique. Les éditions de l'Encyclopédie», dans Gens de lettres, gens du livres, Odile
Jacob, 1992, pp. 245-270.
(36) Robert Darnton, The Great Cat Massacre : And Other Episodes in French Cultural History,
Vintage, 1985(邦訳『猫の大虐殺』 海保 眞夫 ・ 鷲見 洋一 訳、岩波書店、1990 年)
(37)ダーントンのこれらの研究を日本で初めて体系的に紹介した本格的な百科全書研究として、寺
田元一『「編集知」の世紀――一八世紀フランスにおける「市民的公共圏」と『百科全書』――』(日
本評論社、2003 年)がある。
(38)Kafker, Frank A., ed., Notable Encyclopedias of the Seventeenth and Eighteenth Centuries:
77
なりつつもむしろ、『百科全書』パリ版は従来の解釈が強調しすぎてきたきらいのあるよ
うな孤立した突発的な歴史的事件などではなく、実際には十七世紀から続くより大きな
知の地殻変動、知をめぐる文化的な転換(世界像の急激な拡大と産業革命という近代
の知的空間に結節する時代の変容)のなかで形成された新たな百科全書思想/百科
全書主義(encyclopédisme)の有機的でダイナミックなネットワークの網の目の中に置か
れた文化的表象であるととらえようとしているように思える。先行する辞書・辞典類と『百
科全書』パリ版との関連にあらためて光をあてられたほか、ダーントンが主に受容史の
観点から取り上げたスイス版や、ダーントンはほとんど取り上げなかったイタリア版とパリ
版との内容上の差異や連続性、対立やずれといった問題が立てられている。中でもす
でに述べたように『百科全書』パリ版に豊富な注釈をつけたイタリアの二版や、スイス・プ
ロテスタンティズムの立場からパリ版の内容に相当に手を入れて書き換えたことがわか
っているイヴェルドン版、そして『百科全書』パリ版を質量ともに凌駕すべくパンクークに
よって企てられた『体系的百科全書』はパリ版とどのような異同があるのか、具体的に明
らかにしようとする研究が本格化している( )39 。イヴェルドン版『百科全書』に関するシン
ポジウム記録が「バンジャマン・コンスタン年報」(第 14 号、1993 年)に掲載されたのもこ
の時期である( )40 。
Nine Predecessors of the Encyclopédie, Frank A. Kafker, Oxford, SVEC, 1981; Notable
encyclopaedias of the late eighteenth century: eleven successors of the Encyclopédie, Vol. 315,
«SVEC», Oxford, Voltaire Foundation, 1994.
(39 )例 えばカフカーの『十 八 世 紀 後 期 の百 科 全 書 ~『百 科 全 書 』の 11 の継 承 』に収 録 された
Morris, Madeleine F., «The Tuscan editions of the Encyclopédie» (pp. 51-84)、Hardesty-Doig,
Kathleen, «The Yverdon Encyclopédie» (pp. 85-116)、Hardesty-Doig, Kathleen, «The quarto and
octavo editions of the Encyclopédie» (pp. 117-142) な ど の 論 文 、 お よ び Donato, Clorinda,
L'Encyclopédie d'Yverdon et l'Encyclopédie de Diderot et de D'Alembert: éléments pour une
comparaison, Annales Benjamin Constant, no 14, 1993 などを参照のこと。
(40)cf. Annales Benjamin Constant, op.cit. なおこのシンポジウムに関して Hofmann, Anne, «Table
ronde sur l'Encyclopédie d'Yverdon», Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 1993, no. 14,
1993, pp.177-179.が簡潔に内容を報告している。
78
③典拠研究
こうした動向に呼応するように、『百科全書』パリ版も従来とは異なる視点で読まれ始
めている。プルーストが発見したブルッカー『批評的哲学史』以外にも、新たな様々な
典拠研究――むしろ『百科全書』による先行テクストの言表戦略的な〈変形〉と〈翻訳〉
というテクスチュアルな次元でのアプロプリエーションのプロセスを重視し強調するという
意味で、起源を求めて過去へと遡行していった従来の文学史的「典拠」探求とは逆の
ベクトルを志向するというべきだろうが――があらたに重要な研究領域となりつつある。
a)「第一趣意書」
そもそもパリ版が英国のエブラヒム・チェンバーズ『サイクロピーディア』の仏訳プロジェ
クトとして企画されたことは周知の事実であり、ディドロとダランベールが編集の中核に
就いた『百科全書』にもかなりの頻度でチェンバースからの引用が残存していることは、
すでにラフが 1980 年に指摘したとおりである( )41 。だがにもかかわらず両者の連関の具
体的な様態についてはまだほとんど研究は進んでいない。この点で、ディドロらの参画
以前、ドイツ人ゼリウス・英国人ミルズらとル・ブルトンが『百科全書』出版計画を立てた
1745 年に配付された「第一趣意書」を取り上げた鷲見洋一教授による研究は大きな重
要性をもつ ( )42 。この「第一趣意書」のデジタルアーカイブ化は今回の慶應大学DMC
『百科全書』プロジェクトの初年度事業として予定されている。
b)「トレヴー辞典」
パリ第十・ナンテール大学のマリ・レカ=ツィオミの浩瀚な博士論文『ディドロを書く―
―ディドロ、辞書の利用から哲学的文法へ』(1999)は、こうした流れを一挙に加速させ
(41)Lough, John, «The Encyclopédie and Chamber's Cyclopaedia», Studies on Voltaire and the
Eighteenth Century, 185, 1980, pp.
(42 )Sumi, Yoichi, «Atmosphere» et «Atmosphère». Essai sur la Cyclopaedia et le premier
Prospectus de l'Encyclopédie», dans Vérité et littérature au XVIIIe siècle. Mélanges rassemblés
en l'honneur de Raymond Trousson, Paul et al Aron, Paris, Honoré Champion, 2001, pp. 271-284.
79
た本格的な研究である。レカ=ツィオミは、『百科全書』ディドロ執筆項目のうちきわめて
重要な部分をなす「文法」項目群を対象に、ディドロの哲学的・作家的実践の本質に
おいて『百科全書』における同項目群の執筆がいかに重要な意味をもっていたかを、
項目執筆に当たってディドロがつねに依拠した様々な同時代の辞書――その中核は
十八世紀 大のフランス語辞典、イエズス会「トレヴー辞典」である――と精緻な比較
照合をおこなうという形で提示して見せた( )43 。
c)「パリ科学アカデミー」
錚々たる名前のなかに自分の研究を連ねるのは面はゆいが、『百科全書』パリ版第一
巻ディドロ執筆項目の一部と、パリ科学アカデミー「概要と論文集」の関係について筆
者が論じたものを挙げておく( )44 。筆者がフランス留学を終えて帰国する直前に国立図
書館で発見したいくつかの史料をもとに、主に医学・生理学関連のディドロ執筆項目の
典拠としてこのコーパスが一貫して参照されていることを論証しようとしたものである。
DPV版全集に収録された執筆項目のみに限定されている点に難があるが、ディドロの
唯物論思想の一傾向を示すテクストとして挙げられる項目「霊魂 Âme」(イヴォン執筆)
への編集補遺の本文が、アカデミーの文書のまさにモザイクといってよい貼り合わせで
あることを具体的な典拠資料とともに示せたのは幸いであった。
④現状の課題
現状の『百科全書』研究の課題としては、特に次の四点を挙げなければならない。
a)イタリア版研究の手薄さ
b)後続諸版『目録』の必要性
(43 )Leca-Tsiomis, Marie, Ecrire l'Encyclopédie. Diderot: de l'usage des dictionnaires à la
grammaire philosophique, «Studies on Voltaire and the Eighteenth Century», Vol. 375, Oxford,
Voltaire Foundation, 1999.
(44)逸見龍生「『百科全書』第一巻ディドロ寄稿項目における『王立科学アカデミー概要および論文
集』典拠」『人文科学研究』(新潟大学)第九十二輯、平成八年、pp.49-70.
80
c)パリ版と各国版との本文比較照合の困難
d)無署名項目研究の停滞
いずれについてもその内容の概略は説明済みであるが、なかでも各国版研究に関し
ては入手困難な稀覯書を参照する必要がどうしてもあり、現段階ではなかなか具体的
な解決策がない。慶應大学『百科全書』プロジェクトではリヴォルノ版およびイヴェルド
ン版『百科全書』のデジタル化およびパリ版との本文比較を可能とするデータベースの
開発も予定している。
VI.日本の『百科全書』研究
①『百科全書』国内所蔵図書館
学術情報システムデータベース(Webcat)を見ると『百科全書』パリ版所蔵図書館とし
て、青山学院、熊本県立大、筑波図書館情報大、九州大、小樽商科大が挙げられて
いる。そのほか同データベースに記載はないものの、慶應大、東京大、京都大、早稲
田大、一橋大、名古屋大など他の大学図書館にも所在は確認されている(複数セット
を所有する大学もあり)。公立図書館では大阪府立中央図書館大原文庫貴重書コレ
クションにパリ版刊本があり、同館Webサイト「フランス百科全書図版集」でデジタル画
像として閲覧できる。マイクロフィルム、光ディスクでの提供もおこなっている( )45 。ただし
これら国内各図書館の諸版について、前述のシュワッブの書誌学的方法論を用いて
国内所蔵刊本を網羅的に調査した研究はいまだ存在しない。すでに指摘したような印
刷史・書物史的観点からの『百科全書』刊本研究の重要さをかんがみても、早急に着
手すべき領域といえるであろう。
②鶴見俊輔他「『百科全書』における人間関係」(桑原武夫編『フランス百科全書の研
究』1954)
( 45 ) 大 阪 府 立 中 央 図 書 館 「 百 科 全 書 図 版 集 」
http://www2.library.pref.osaka.jp/France/France.html を参照。
81
桑原武夫編『フランス百科全書の研究』(1954 年、岩波書店)は、京都大学人文研が
戦後初のきわめて大規模な共同プロジェクトであった「ルソー研究」に続いて行なった、
日本の『百科全書』研究の嚆矢であった。日本でのその後の『百科全書』のイメージを
決定的に確定したという意味で、この研究書の重要性は大きい。だが今日の眼から見
れば、社会科学領域の主題論研究では先に挙げたルネ・ユベールの影響がどれも色
濃くみえすぎるなど、残念ながら総じてオリジナリティに欠けている。何よりも記述が概括
的にすぎるのは遺憾である。しかし今西錦司らが参加した「医学・生理学」の項など着
想がさすがに卓抜で面白く読める箇所もある。
『百科全書』本文研究の観点から特に注目すべきなのは、鶴見俊輔他「『百科全書』
における人間関係」である( )46 。『百科全書』成立の状況を解説し、具体的に執筆者や
協力者の名をリスト化して協力の類型を分類し、執筆者・協力者を「実践家」と「理論
家」と二分し、その世代、職業、身分などの観点から網羅的に論じた、きわめて野心的
な論文であった。百科全書派の具体的研究としてもおそらく 初期に属する。
だがプルーストはすでに挙げた『ディドロと百科全書』巻末補論「『百科全書』執筆協
力者」においてこの鶴見論文を手厳しく批判し、1932 年に仏国立図書館で開催された
『百科全書』回顧展カタログやルイ=フィリップ・メイなどによる先行研究をいっさい使用
しておらず、夥しい欠落や事実認定の誤りがあって、いったい何を根拠に執筆者たち
のリストを作成したかまったく不明だと強い調子で論難した。その上で世代による分類
は無意味、身分による機械的な分類では役に立たない、さらに実践家と理論家という
区分にいたっては、何を言わんとしているか、理解しがたいなどと駁論している( )47 。
プルーストの批判を受けて同論文は『フランス百科全書の研究』の第二版(1971)刊行
を機に執筆者リストの部分を小西嘉幸、中原新吾、早水洋太郎の協力により全面的に
改稿している( )48 。52 年初版にあった多くの誤りは、第二版時点ですでに刊行されてい
たシュワッブの『目録』など初版以後の欧米の研究成果を活用して相当程度修正され
(46)桑原武夫 , 鶴見俊輔 , 樋口謹一 「百科全書における人間関係」桑原武夫編『フランス百科全
書の研究』(岩波書店、1954 年)、17-71 頁。
(47)Proust, Jacques, Diderot et l'Encyclopédie, op.cit., p.513.
(48)本稿では『鶴見俊輔著作集』所収の第二版「百科全書における人間関係」(『鶴見俊輔著作集
I 哲学』、筑摩書房、1975 年)185-236 頁を参照した。
82
た。その結果執筆協力者として同論文は本巻 200 名、『補遺』に 51 名を挙げる。しかし
キャスリーン・ハースディ『百科全書補遺』が『補遺』執筆者について 78 名まで具体的
に特定している現在、『補遺』については資料として古い感が残るのは否めない。
また第二版では概ね修正がなされたものの、校正ミスの可能性もあるとはいえ、まだな
お執筆者の特定に誤り等が残っているという印象も抱かされないわけではない。例えば
プルーストが批判した執筆者の「協力のタイプ」(a-編集、b-執筆、c-寄稿、d-図版作
成、e-資料協力)についてみると、b について本巻 32 名、補遺で 15 名の数が挙げられ
ており、合計 47 名の筈であるが、212 頁にある「数字の要約」を見ると b)執筆として 64
名とあり、計算が合わない。
もっとも、プルーストの批判にもかかわらず、同論文には鶴見俊輔らしい卓見も随所に
みられることはやはり指摘しておかねばならない。鶴見はさまざまな人物たちの協力によ
って長い時間をかけて形成されていった『百科全書』の集合的性格の特性を、大中小
の数々の自律的な「ウズ」の比喩を用いて説明し、「さまざまの勢力があるいは対立的
に、あるいは相補的にからみあって参加」しあうダイナミックな様態、「執筆者が文筆業
者としてもつ 低限度の誇り、自主的運動の意識」の側面を強調している( )49 。こうした
鶴見の視点には一種の魅力も感じられないわけではない。その議論の抽象性はやはり
否めず、そして鶴見には『百科全書』における言説生産の歴史的層への眼差しが決定
的に欠落しているのではないかと疑いをもちつつも。
VII.『百科全書』のデジタル化における問題
①現行版(ARTFL 版、Redon 版)の問題点
1990 年代以後、情報技術の革新にともない現在ではインターネット(American and
French Research on the Treasury of the French Language、略称ARTFL版)およびルド
ン社CD-ROM(マッキントッシュ、ウィンドウズ用)・DVD(ウィンドウズ用)で『百科全書』パ
リ版本文および図版のデジタルデータを入手することができる ( )50 。第三のデジタル化
(49)同書、213-214 頁。
(50)http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/encyc/
83
『百科全書』もシャンピオン社が予告している。これらのデジタルデータの登場によっ
て、『百科全書』本文研究も新たな段階を迎えることになった。しかしながら、現行のデ
ジタル版にはともに以下のような根本的な欠陥が知られている。ピエール・シャルチエ
(パリ第七・ドゥニ・ディドロ大学)の指摘に即して問題点を整理しておく( )51 。
まず非常に多くの箇所にテクストレベルでの欠損がある。テクストをスキャンする過程
で誤認識したと思われる、誤植、文字化け、文字の混同が多く、非ラテン語系言語、ギ
リシア語やヘブライ語などについてはほとんど信頼性がない。本文中の数式、図表もし
ばしば欠落しており、『百科全書』第一巻序文に掲げられた「人間知識の系統図」もデ
ジタル版にはない。
デジタル化の制作者側が百科全書の印刷技法面の複雑な特徴を知らぬままに機械
的な操作をほどこしていった結果生じた問題があまりにも多い。
1) 十八世紀における綴字表記がまだ固定せず、特に固有名詞に表記のばらつきがあ
ること。たとえば十七世紀思想家スピノザの綴りはときに Spinoza ないし Spinosa が用い
たが、現行表記の Spinoza で検索しても Spinosa 表記の本文は検索結果に反映されな
い。
2) 『百科全書』における小カピタルの使用はきわめて多様であり、時には項目の見出し
に使われ、時には項目末尾や中におかれた参照指示にも用いられることがあるし、参
照指示でも小カピタルで印刷されていない場合もある。こうした区別を無視してデジタ
ル化した結果、著者の名前の引用が、項目執筆者の名前との混同や、註を導入する
「*」の記号と、ディドロの執筆項目を示す「*」の記号が混同などがある。
3)参照記号が大カピタル体の場合のみ現行版においては認識されている模様で、一
つの項目から多数の参照指示が大カピタル体以外の活字で印刷されている場合には
認識されない。
4)執筆者の情報についてプルーストやラフ、シュワッブを筆頭とするこれまでの学術的
な研究成果がまったく反映されておらず、著者名による検索に関して信頼度が残念な
がら低い。
および http://www.dictionnaires-france.com を参照
(51)Chartier, Pierre. 2001. «Présentation», Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 30,
avril, p. 5-16.
84
シャルチエと同様、レカ=ツィオミも現行デジタル版について強い不満を抱いており、
現段階では本文レベルで原文との径庭があまりにも大きく、『百科全書』研究者が憂慮
なく用いるには残念ながらあまりにもほど遠い状況であると結論している( )52 。
IX おわりに
以上、『百科全書』本文研究の観点から、プルースト、ラフ、シュワッブらによって急速
に研究に進捗がみられた 1960 年代から 70 年代初頭にかけての時期を中心に、戦前
から今日のデジタル化の問題まで概観してきた。1950 年代までの先駆的研究、本文校
訂研究の基礎的方法論が確立した 70 年代初頭、その後受容史や書物史の興隆やヨ
ーロッパ規模の視野での研究体制の確立を受けて現在進みつつある各国版『百科全
書』研究の進展、本文テクストの生産・生成・受容に関するより精緻な研究の方向な
ど、現在にまでいたる百科全書研究史の大きな流れは少なくとも提示できたと思われ
る。
慶應大学『百科全書』プロジェクトは、グーテンベルグ聖書をはじめ国内外の貴重書
を対象としたデジタル・リサーチ・ライブラリーを同大学で構築してきた実績を生かし、有
機的な相互連関・参照システムからなる『百科全書』筆頭とする十八世紀の諸辞典・辞
書の電子出版を目指している。しかも問題点を多く抱えた現行の『百科全書』デジタル
版にくらべ、より精度の高い信頼の置ける本文の厳密なデジタルテキスト化を図るのは
当然であるが、それだけにはとどまらない。上に述べてきたシュワッブ以後の書誌学的
研究の成果を十分に生かし、十八世紀の原書印刷製本情報をごく細部まで可能な限
り精緻に記録することによって、『百科全書』を産み出した印刷工房の技術的位相にま
で下りていくことを可能とするデータベースの構築も目的としている。
『百科全書』の世界の全体像が思いがけないかたちでその時不意に初めて姿を現わ
すかもしれないのである。
(52)Leca-Tsiomis, Marie. 2002. «Numérisations et exactitude du texte encyclopédique : quelques
propositions pour l’avenir», Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 31-32, avril, p.
293-302.
85
参考資料:主要『百科全書』各国版
1 パリ版(フォリオ版)
[趣意書]
第1趣意書(1745)
第2趣意書(1751 : 1750 年秋頃)
本文 17 巻(1751-1765)
図版 11 巻(1762-1772)
補遺 5 巻(1776-1777)
2 ジュネーヴ版(フォリオ版)
本文 17 巻(1771-74)
図版 11 巻(1770-76)
3 ルッカ版(フォリオ版)
本文 17 巻(1758-71)
図版 11 巻(1765-76)
4 リヴォルノ版(フォリオ版)
本文 11 巻(1770-75)
図版 11 巻(1771-78)
補遺 5 巻(1778-79)
5 スイス四折版
本文 36 巻
図版 3 巻
「新版」、「第3版」とタイトル頁に書かれた3つの版あり。
ニューシャテルで刊行された模様。
86
参考文献(本文中に取り上げた順に)
1) MAY, Louis-Philippe, «Histoire et sources de l'Encyclopédie d'après le registre
des délibérations et de comptes des éditeurs et un mémoire inédit», Revue de
synthèse, février 1938, no.XV, 109 p.
2) GORDON, Douglas H., TORREY, Norman L., The censoring of Diderot's
Encyclopédie and the Re-established text, New York, Columbia University press,
1947.
3) The Douglas H. Gordon Collection of French Books, University of Virginia,
http://www.lib.virginia.edu/small/collections/gordon.html
4) WATTS, George B., «The "Encyclopédie" and the "Description des arts et
métiers"», The French Review, XXV, no. 6, 1952, pp. 444-454.
5)———, «Forgotten Folio Editions of the Encyclopédie», The French Review,
XXVII, no. 1, 1953, pp. 22-29, Addenda 243-244.
6)———, «The Supplément and the Table analytique et raisonnée of the
Encyclopédie», French Review, 1954-55, no. XXVIII, 1954-55, pp. 4-19.
7)———, «The Swiss Editions of the Encyclopédie», Harvard Library Bulletin, IX,
no. 2, 1955, pp. 213-235.
8)———, «The Encyclopédie méthodique», PMLA (Publications of the Modern
Language Association of America), LXXIII, no. 4, 1958, pp. 348-366.
9) LEVI-MALVANO, Ettore, «Les éditions toscanes de l'Encyclopédie», Revue de
littérature comparée, no. 3, 1923, pp. 213-256.
10) HUBERT, René, Les Sciences sociales dans l'Encyclopédie, «Bibliothèque de
philosophie contemporaine», Paris, Félix Alcan, 1923.
11) VENTURI, Franco, Le origini dell'Enciclopedia, «Piccola biblioteca Einaudi:
26», Einaudi, 1977 (première édition, 1946)
12) PROUST, Jacques, Diderot et l'Encyclopédie, Paris, Albin Michel, 1996 (1962,
première éd.).
13) LOUGH, John, Essays on the Encyclopédie of Diderot and D'Alembert, London,
88
New York, Toronto, Oxford University Press, 1968.
14)———, The Encyclopédie in Eighteenth-Century England and other studies,
Newcastle upon Tyne, Oriel Press, 1971.
15) SCHWAB, Richard N. With the Collaboration of Walter E. REX, Inventory of
Diderot's Encyclopédie, Vol. 6, «Studies on Voltaire and the eighteenth century (80,
83, 85, 91-93)», Oxford, The Voltaire Foundation, 1971-72.
16)———, Inventory of Diderot's Encyclopédie. VII. Inventory of the Plates, with a
study of the contributors to the Encyclopédie by John LOUGH, «Studies on Voltaire
and the eighteenth century (223)», Oxford, The Voltaire Foundation, 1984.
17) KAFKER, Frank-A, (in Collaboration with Serena L. Kafker), The encyclopedists
as individuals: a biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, Vol.
257, «Studies on Voltaire and the eighteenth century», Oxford, The Voltaire
Foundation, 1988.
18)———, The encyclopedists as a group: a collective biography of the authors of
the Encyclopédie, Vol. 345, «Studies on Voltaire and the eighteenth century»,
Oxford, The Voltaire Foundation, 1996.
19) MORRIS, Madeleine F, Le chevalier de Jaucourt. Un ami de la terre
(1704-1780), Genève, Droz, 1979.
20) PERRET, Jean-Pierre, Les Imprimeries d'Yverdon au XVIIe et XVIIIe siècle,
Lausanne, 1945.
21)CORSINI, Silvio, «Imprimeurs, libraires et éditeurs à Lausanne au siècle des
Lumières», dans Le livre à Lausanne. Cinq siècles d'édition et d'imprimerie
1493-1993, sous la direction de Silvio CORSINI, Lausanne, Payot Lausanne, 1993,
pp. 49-69.
22)———, La preuve par les fleurons? Analyse comparée du matériel ornemental
des imprimeurs suisses romands 1775-1785, Ferney-Voltaire, Centre international
d'étude du XVIIIe siècle, 1999.
23)———, «La contrefaçon du livre sous l'Ancien Régime», dans Les presses grises.
La contrefaçon du livre (XVIe-XIXe siècle), texte réunis par François Mourreau,
89
Paris, Aux amateurs de livres, 1988, pp. 22-37.
24)DARNTON, Robert, L'Aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800. Un best-seller au
siècle des Lumières, Paris, Librairie Académique Perrin, 1982 (original version,
1979).
25)———, «Un imbroglio bibliographique. Les éditions de l'Encyclopédie», dans
Gens de lettres, gens du livres, Odile Jacob, 1992, pp. 245-270.
26) Kafker, Frank A., ed., Notable Encyclopedias of the Seventeenth and Eighteenth
Centuries: Nine Predecessors of the Encyclopédie, Frank A. Kafker, Oxford, Studies
on Voltaire and the eighteenth century, 1981.
27)———. Notable encyclopaedias of the late eighteenth century: eleven successors
of the Encyclopédie, Vol. 315, «Studies on Voltaire and the eighteenth century»,
Oxford, Voltaire Foundation, 1994.
28) MORRIS, Madeleine F., «The Tuscan editions of the Encyclopédie», dans
Notable encyclopaedias of the late eighteenth century: eleven successors of the
Encyclopédie, Frank A. Kafker, Oxford, Voltaire Foundation, 1994, pp. 51-84.
29)HARDESTY-DOIG, Kathleen, «The Yverdon Encyclopédie», dans Notable
encyclopaedias of the late eighteenth century: eleven successors of the Encyclopédie,
Frank A. Kafker, Oxford, Voltaire Foundation, 1994, pp. 85-116.
30)HARDESTY-DOIG, Kathleen, «The quarto and octavo editions of the
Encyclopédie», dans Notable encyclopaedias of the late eighteenth century: eleven
successors of the Encyclopédie, Frank A. Kafker, Oxford, Voltaire Foundation, 1994,
pp. 117-142.
31) HOFMANN, Anne, «Table ronde sur l'Encyclopédie d'Yverdon», Recherches sur
Diderot et sur l'Encyclopédie, 1993, no. 14, 1993, pp.
32) LOUGH, John, «The Encyclopédie and Chamber's Cyclopaedia», Studies on
Voltaire and the Eighteenth Century, 185, 1980, pp.
33) SUMI, Yoichi, «Atmosphere» et «Atmosphère». Essai sur la Cyclopaedia et le
premier Prospectus de l'Encyclopédie», dans Vérité et littérature au XVIIIe siècle.
Mélanges rassemblés en l'honneur de Raymond Trousson, Paul et al Aron, Paris,
90
Honoré Champion, 2001, pp. 271-284.
34) LECA-TSIOMIS, Marie, Ecrire l'Encyclopédie. Diderot: de l'usage des
dictionnaires à la grammaire philosophique, Vol. 375, «Studies on Voltaire and the
eighteenth century», Oxford, Voltaire Foundation, 1999.
35) 逸見龍生「『百科全書』第一巻ディドロ寄稿項目における『王立科学アカデミー概
要および論文集』典拠」『新潟大学人文科学研究』第九十二輯、平成八年、pp.49-70.
36)鶴見俊輔他「『百科全書』における人間関係」(『フランス百科全書の研究』岩波書
店、1952、pp 17-71)
37)同(第二版)『鶴見俊輔著作集 I 哲学』(筑摩書房、1975)所収、pp.185-236
38) CHARTIER, Pierre, «Présentation», Recherches sur Diderot et sur
l'Encyclopédie, 30, no. avril, 2001, pp. 5-16.
39) LECA-TSIOMIS, Marie, «Numérisations et exactitude du texte encyclopédique :
quelques propositions pour l'avenir», Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie,
31-32, avril, 2002, pp. 293-302.
91