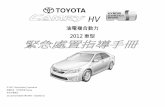社会科と価値教育の重複領域について (The Overlapping Domains of Social Studies and...
-
Upload
philippines -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of 社会科と価値教育の重複領域について (The Overlapping Domains of Social Studies and...
社会科と価値教育の重複領域について
1Czarina Baraquiel Agcaoili ,2Susumu Oshihara 1フィリピン大学と愛媛大学、2愛媛大学
要旨: 本研究はフィリピンにおける社会科と価値教育(Values Education)の重複する領域について述べている。幼稚園から 12年生までを対象にしたカリキュラムを実施するにあたり,/を目前に?,大きな挑戦の一つには社会科を価値教育から区別することは非常に困難な
ことがあった。価値教育は,すべての学習領域に統合されたものである。実施においては,
社会科における知識とスキルよりも,知識と公民的価値の保持により重点が置かれている。
このことは,2つの科目の関係性を明確に打ち出していると言えるだろう。 本研究では,社会科における価値教育の統合と,幼稚園から 12 年生までを対象にしたカリキュラム編成における社会科カリキュラムの重大な変容を紹介し分析してゆく。 キーワード: シティズンシップ教育・社会科・価値教育
はじめに: 民主的な社会では,子どもたちを知的に可能だというだけではなく,社会・国家・世界
に対して責任を負うことのできる市民でもある倫理的な大人になるよう仕向けなければ
ならない。民主主義の繁栄のためには,社会は自らの権利と義務を知り,社会や政界につ
いての知識もあり,公共の善に関心を持ち,プロアクティヴで責任感のある市民が必要な
のである。学校はそのシティズンシップ教育の過程において重要や役割を果たしている。 フィリピンにおいて,シティズンシップ教育は,生徒たちが国家の歴史・政治・文化・
経済・社会問題を学ぶ社会科と強く結び付いている。これらの概念は知識基盤社会におい
て有益なものである。しかし,民主的社会を強化するためには,常識や倫理 morals and ethicsが知性と同様に重要である。これこそが本論の要となる。社会科は,どのように価値教育と関連するのだろうか? 本研究では,価値教育と社会科が,その目的・内容・教育方法・アウトプットといった
点で,シティズンシップ教育の推進のためにどのように相互寄与しているかに着目する。 図1.分析の枠組み
基礎教育カリキュラム
(BEC):
全学習領域に統合され
ている
幼-12年生向けカリキュラム:
個別の科目
目的
内容とキースタンダード
教授法
基礎教育カリキュラム
(BEC):
全学習領域に統合され
ている
幼-12年生向けカリキュラム:
個別の科目
目的
内容とキースタンダード
教授法
価値教育
目的
内容とキースタンダード
教授法
期待される
アウトプット
社会科教育
図1は本研究の分析枠組みである。まず、社会科の目的・内容・教育方法が 2002年版基礎教育カリキュラム(BEC)の下にあることを表し、価値教育との統合ならびにその効果について端的に展開・分析する。次に、幼稚園から 12 年生を対象としたカリキュラムの下で行われた、社会科における重要なカリキュラム改革について説明を行う。さらに、社
会科と価値教育の関係性を、目的・内容・教育方法の点ならびに強力なシティズンシップ
教育の推進のため互いにどのように貢献しあっているか分析する。終盤にかけて、価値教
育と社会科を統合する教育学的アプローチを、カリキュラムにみられる様式・パターン?
に基づいて開発してゆくこととする。 2002 年版基礎教育カリキュラム 2002 年版基礎教育カリキュラム(BEC)は 2002 年 6 月、フィリピン全土の公立小学校ならびに中等学校で実施された。BEC の哲学ならびにデザインは、以下の 3 つを推進することを目指していた。(1)より高度で複雑な学習コンピタンスをフィリピンの学習者が獲得すること。(2)カリキュラムの一本化と学習領域の統合。(3)創造的で革新的な教授法アプローチの導入(Bernardo & Mendoza, 2006)。BECは単なる知識の獲得のいならず、生徒らを生涯にわたる学びに備え、愛国的(makabayan)で人間味にあふれ(makatao)、自然を大切にし(makakalikasan)、敬虔な(maka-Diyos)フィリピン市民を形成することを目指していた。このカリキュラムでは英語・数学・科学・フィリピン学・マ
カバヤンといった 5つの学習領域が設定されている。最初の 4つの学習領域はツールとしての学習領域であるが、一番最後のマカバヤンは体験的学習領域もしくは人生・生活?の
実習機会である。 表 1. 初等・中等教育における社会科
初等教育 中等教育 1年次 市民生活と文化 1年次 フィリピンの歴史と
政府 2年次 市民生活と文化 2年次 アジアの歴史 3年次 市民生活と文化 3年次 世界の歴史 4年次 *地理・歴史・市民生
活 4年次 経済
5年次 地理・*歴史・市民生活
6年次 地理・歴史・*市民生活
*特にフォーカスされる 社会科は、マカバヤンの科目でも家庭科・音楽・保健・価値教育に次いで主な構成要素
である。表 1にみるように、初等教育において社会科は市民生活・歴史・地理といった 3領域に標準をあわせている。その一方で、中等教育における社会科はより専門化している
のである(DepEd, 2002) マカバヤンは人間形成を通じて社会のニーズを提示することを目指しており、知識と専
門的スキルを持つ市民を形成しようとしているだけではない。この学習領域は、構成要素
に込められ、横断してみられるコンピタンスと価値、ならびに4つのツール学習領域との
強固な融合を特徴としている。マカバヤンの構成は、フィリピン社会を強化する基本的な
要因が価値観であると認識されていることを示している。たとえば、初等教育では特に社
会科に融合されている価値観として、真実を明らかにする意志・神への信仰・お互いの尊
重と心配り・平和維持・勤労への意欲・正直さ・協力・国家への感謝と愛・環境へのケア・
多数の幸福のための助け合い・外国文化への気づきがある(Miranda & Echano, 2004; Mendoza & Nakayama, 2003; DepEd, 2002; Bacani, 2002)。マカバヤンのビジョンを達成するためには、教員らが統合的な教授法と相互交流のある学習手法を用いてこの学習領
域を教えなければならないのである(DepEd, 2002)。 BEC の理想的目標にもかかわらず、教員らはマカバヤンの枠組みと実践に困惑していた。Cruz (2005)によると、この学習領域の目的は、フィリピン人生とにどのように人間になるかを教えることであった (Cruz, 2005)。フィリピンのアイデンティティと価値観という問題に根差した窮状といえる、人々はフィリピン人になるとはどういうことかと日々
混乱しているのである。そのために、解決策のない難題への回答としてのマカバヤンの取
り組みは、この科目がどうあるべきかの混乱の基本的な理由になるのである(Cruz, 2005)。Cruz (2005)にとって、人々を人に成らしめるための教育は、ひとえに価値教育のタスクである。ゆえに、マクバヤンは価値教育の同義語に過ぎないのである。 教育方法に関していうと、Diokno(2009)は、知識と市民的価値の保持が過度に強調された結果として、社会科のスキル、とくに歴史的思考スキルが妥協をされざるを得なかった
としている。生徒たちは時間列思考・出来事の文脈的理解・分析・解釈・歴史的書記スキ
ルを伸ばせなかった。初等・中等レベルが用いる社会科教科書は、この問題を深化させた。
フィリピンでは、教員は情報と学習活動の源として教科書を見做し、ひどく依存している。
Diokno(2009)によると、教科書は概念的な間違いや事実誤認を含んでおり、事実やデータの妥当性、信憑性といった歴史学習の基礎信条を侵害するものである。これに加え、
文章には学習者のフィリピン史や社会への理解に悪影響をひきおこす人種的バイアス・植
民地的バイアス・ジェンダー差別が含まれているのである(Macaraegにて Diokno, 2010)。 表 2:6 年生全国達成度テスト結果
学年度 達成率
2008-2009 67.84% 2009-2010 70.88% 2010-2011 70.40% 2011-2012 65.97%
生徒たちの学びに関して、2008年から 2012年の全国達成度テスト(NAT)の結果を見ると、小学生が HEKASI(地理・歴史・市民生活)もしくは社会科の習得を達成日損ねていることがわかる。表 2 にあるように、2012 年では 6 年生の達成率は 65.97%に過ぎない(DepEd, 2013年 9月)。達成度別の受験者分布の割合をみると、科目を習得しているのは 0.55%に限られており、32.04%は平均レベル、9.58%は低レベル、そして 0.29%は非常に低いレベル、さらに 0.03%は全く習得できていないという結果であった(DepEd NETRC, n.d.)。これらの結果は基礎教育における社会科教授の非有効性のせいであると考えられる。 幼稚園から 12 年生を対象としたカリキュラム (以下 K to12 カリキュラム )における社会科 2012年 6月、政府は K to 12基礎教育プログラムの実施を開始した。これはフィリピンの基礎教育において行われた改革の中で最も包括的なもののひとつである。K to 12カリキュラムでは、社会科のカリキュラムならびに教育方法が飛躍的に進化した。 K to 12カリキュラムでは、社会科は個人とグループ・コミュニティと社会・過去どのように生きてきたかと、今をどのように生きているか・お互いならびに環境との関係と相
互補助・信仰と文化を学ぶものであると定義されている。この科目では、学習者は歴史的
な思考スキルやその他の社会科的スキルを身につけていくことが求められている。さらに、
批判的・内省的・責任感のある・生産的な・愛国的な・人類と自然に対し気配りのこまや
かな・歴史や社会問題に関心のある市民になることが望まれている。社会科は、ローカル
とグローバル両方を視野に入れた市民の育成を目指している。これらのゴールはこれまで
のカリキュラムでもフィリピン人の根幹にある価値観とされていた信心深さ
(maka-Diyos)、人類への心配り (makatao)、愛国心 (makabayan)、自然への敬意(maka-kalikasan)を反映している。それに加えて、社会科が育成を目指す知識とスキルは、
生涯学習を支える 4本の柱、知り方を学ぶ・やり方を学ぶ・共生を学ぶ・なり方を学ぶことにもつながるのである(DepEd, 2013; SEAMEO INOTECH, 2012)。これらのゴールを達成するために、構築主義や協働学習、体験型学習や文脈づけといった異なる教育理論を
追随している。また、テーマ時系列学習・概念学習・探求型学習や、統合型・分野間交流・
分野融合型アプローチなどの様々な方略も用いている(DepEd, 2013)。 新しい社会科の重要な特徴について K to 12社会科カリキュラムの特徴は、マカバヤンとはかなりかけ離れたものである。まず、新しい社会科は歴史・地理・市民生活に限られたものではない。1 年生から 12 年次まで、各ユニットの内容スタンダードと成果スタンダードは、アメリカの National Council for Social Studiesによって作成された 10の社会科テーマ別スタンダードから採用された 7テーマに基づくものとなっている。カリキュラム開発者らは各学年レベルにふさわしいテーマのみを利用すると明言していた。とはいえ、K to 12カリキュラムを制覇することで全テーマを学ぶことになる。 表 3: K to 12 カリキュラム社会科における 7 つのテーマ
テーマ 内容詳細 期待される学習成果 1 人々・社会・環境 コミュニティや環境の一部
としてのみならず、より広い
社会や環境の一部としての
人間に着目
地図や図、単純な技術機器を
使って地理の基本概念を理解
する。自分と、所属するコミ
ュニティの位置がわかる。 2 時間・継続性・変化 人間についての学習の中心
となる、社会と環境とは時間
概念のことである。個人の生
活や社会・環境の変化を理解
するための基本的な文脈と
礎になる。
現在と過去・信仰の継続性・ 構成やその他・歴史的重要
性・過去と現在における出来
事の文脈・近代と過去の完全
な理解を進めるに必要な様々
なスキルの違いを理解する。 自身と国家を理解し、個人・
社会や国家、世界の成員とし
てのアイデンティティを育て
る。 3 文化・アイデンティ
ティ・国家 文化は個人・グループ・国家
アイデンティティに影響を
若者・個人・フィリピン人と
しての個人的なアイデンティ
及ぼす。文化とはダイナミッ
クなものである。このような
文化の特徴は、フィリピンな
らびに世界における幅広い
アイデンティティの形成に
影響を与えている。
ティを発達させ、フィリピン
の中に存在する様々な文化に
ついて理解し重んじる。これ
が地方/国家的視野の基礎と
して、世界に対するより幅広
い視野を育てるためである。 4 権利・義務・シティ
ズンシップ 市民的コンピタンスは全市
民の権利と義務の理解に基
づいている。全市民は信仰や
政治観・文化・ジェンダー・
民族・人種・個人の傾向にか
かわらず、他者の権利を尊重
することが義務付けられて
いる。
コミュニティや国家・世界の
出来事に、意味のある積極的
な参加をすることができる。
5 権力・権威・統治 市民性の一部は権力という
概念の理解・民主的統治の意
義と重要性・フィリピンにお
ける政治の種類の理解であ
る。本テーマには、憲法・権
威の概念・各レベルでのリー
ダーシップ・政府についてが
含まれる。
権力・権威・統治の概念を理
解すること
6 生産・流通・消費 選択・必要性・出費・コスト・
ベネフィットといった概念
は経済学だけではなくフィ
リピン・アジア社会・世界の
歴史を学ぶ際にも使用され
る。
経済学的概念を日常生活で用
い、日用品の値段決定や経済
発展に関する政府施策など、
消費者・会社らの決断が社会
に影響を及ぼしていることを
数学的プロセスを用いて理解
できる。 7 地域とグローバル
なつながり ほかの国々に関する知識は、
フィリピンのアジア地域や
世界における位置と役割の
理解を進めてくれる。そして
フィリピン人が世界コミュ
ニティのメンバーとして世
界が直面している問題を解
地域・国家・世界的視野と気
づきをはぐくみ、社会と世界
の基礎的事象への感謝を持
つ。
決する貢献ができる 社会科が、より今日的で、分野融合的かつ多分野的な科目になったことは新しい特徴と
言える。例えば、表 3にあるように、社会科の授業は(1) 人間・社会と環境、(2)時間・連続性と変革、(3)文化・アイデンティティと国家、(4)権利・責任とシティズンシップ、(5)権力・権威と統治、(6)生産・分配と消費、(7)地域ならびに世界とのつながりといった 7つのテーマに根を下ろしている。これらのテーマは人類学・経済学・地理学・歴史・政治
科学・心理学・社会学やその他の分野から導かれたものである。これらの分野の知識やス
キルは、地理学における機具の使用や、日常生活における経済学的概念の応用といった形
で、社会科において養われるのである。 第二として、新しい社会科はらせん型カリキュラムという考え方に準拠している。生徒
らにもともと備わっているスキルを、社会科が育成を目指しているより複雑なスキルの基
礎として用いようとするのである(DepEd, 2013)。カリキュラムの横糸の役割を果たす以下の 6 つのコンピタンスが、社会科らせん型カリキュラムの出発点となっている。(1)問いかけ、(2)データ分析と解釈、(3)情報の分析と解釈、(4)リサーチ、(5)コミュニケイション、(6)社会規準の応用である。これらは(1)誰もに機能的リテラシーを、(2)機能的に読み書きができ、進んだフィリピン人の育成、(3)生涯教育といった基礎教育 3 つのゴールに基づいている。6つのコンピタンスは、それぞれの学年レベルの発達段階にふさわしいアプローチとスキャフォールディング(足場作り)のプロセスを用いて形作られてゆく。K-12カリキュラムの修了時には、生徒らは社会科学に関する概念と、歴史・地理・文化・経済・政治・公民・社会的問題に関する理解を示すことができるべきである。また、グロ
ーバルな知見を獲得し、リサーチ・探求・批判的思考・理知的な判断・創造性・社会科・
ふさわしいリソースの利用・コミュニケイションといったスキルを使いこなすことができ
るべきである。これらに加え、批判的・内省的・責任感のある・生産的で・自然を尊重し・
愛国的・人類を思いやるようになることが期待されているのである(DepEd, 2013)。 図 2.拡大する社会的文脈
世界
国
コミュニティ
家族
自分
州・地域
社会科の内容とフォーカスについては、拡大型の社会的文脈モデルの使用が明らかにみ
られる。図 2で示すように、生徒らはまず自身について、また家族やコミュニティがどのように自身のアイデンティティに影響を及ぼすかを学ぶ。この認識的枠組みは続く学年段
階においても、フィリピン人として、また世界市民としてのアイデンティティとともに、
多様さを増す社会の在り方を理解するために用いられる。同様に、個人とコミュニティ・
国家・世界との関係性を学び、公共善を強め、推進するためにも用いられる。当然、これ
もらせん型カリキュラムの考え方に連動するものである。
表 4.幼稚園から 10 年生までの社会科 学年段
階 話題 テーマ
幼稚園 自分と他者 1-2 1年 自分と家族と学校 1-3 2年 わたしのコミュニティ・今とむかし 1-5 3年 わたしの州と地域 1-6 4年 フィリピン 1-6 5年 フィリピンの歴史①:国家としてのフィリピン
の発展 1-6
6年 フィリピンの歴史②:国家としての挑戦と対応 1-6 7年 アジアについて 1-7 8年 世界について 1-7 9年 経済学 1-7
10年 現代社会問題 1-7 幼稚園から 10年生までの話題は、社会科 7つのテーマならびに拡大する社会的文脈の相関性を示している。例に挙げると、表4では 1学年時、児童らは自分自身と家族に焦点化する。その段階で扱われるテーマは(1)人々・社会・環境、(2)時間・連続性・変化、(3)文化・アイデンティティ・国家である。 表 5.幼稚園から 10 年生における社会科のキーステージ
幼稚園―3 年次 4-6 年次 7-10 年次 自分のコミュニティとより
広い社会の一員として、自身
と物理的・社会文化的環境に
関する理解を深め、様々なス
キルを用いながら、自分と家
リサーチ・探求・批判的思
考・理知的な決断・創造的思
考・社会科・リソースの持続
的な利用・コミュニケイショ
ンといったスキルと、地理/
探求・データと様々な情報分
析・リサーチ・有効なコミュ
ニケイションのスキルと、地
理/歴史/経済/政治/文化に関する基礎的な概念理解を用
族・学校・コミュニティ・継
続と変化という概念・距離・
方角についての基本的な理
解を示し、価値づけをする。
歴史/経済/統治/公民/文化に関する基礎的な概念の理解
を用いながら、生産的で責任
感のある、愛国的なフィリピ
ン市民としての能力を発揮
する。
いて、批判的・内省的・創造
的・理知的な決断者・積極
的・環境保護的・責任感のあ
る・生産的・人類を思いや
る・愛国的かつローカルでグ
ローバルな視野を持つフィ
リピンの若い市民としての
能力を発揮する。 表 5は幼稚園から 10年次の社会科キースタンダードを示している。11・12年次には、
生徒らは地域・国家・グローバル規模の問題のディスカッションに焦点化した選択科目を
選ぶようになっている。これらのコースでは、学習者の知識を広げ、批判的思考スキルの
発達が目指されている(DepEd, 2013)。 第 3に、新しい社会科は生徒らの多様な言語背景に繊細に対応している。The Summer Institute of Linguisticsは、フィリピンで 172言語が用いられていると報告している。このうち 3つは外国語(英語・カスティーリャ地方スペイン語・閩南中国語)であり、のこりの 169言語は先住民の言葉である(Castro, 2011)。Ocampo (2006)によると、小学校段階における母国語をもちいた教授は自信をたかめ、文化的アイデンティティを保ち、よりポ
ジティヴな学習体験を推進するそうである。K to 12カリキュラムでは、幼稚園から 3年生まで、社会科は児童らの母国語で教えられる。学習教材もこれらのことばで書かれてい
る(SEAMEO INNOTECH, 2012)。 新しい社会科と価値教育 (Edukasyong Pagpapakatao) Parker (2010)によると、社会科は啓発された政治的参加と内省的市民性を目指しているという。よい性格の人々、もしくは政府や社会に関する知識はあるが公的なことに不参
加な個人というだけでは、先進的な民主主義にとって十分ではないのである。このことは、
社会科と価値教育を結び付け、また分かつパラメーターが存在することを示している。 目的 社会科と価値教育は両方とも責任感のある決断をすることができ、公共善を推進するこ
とに熱心な市民の育成をめざしている(SEAMEO INNOTECH, 2012)。これらの目標達成のために、価値教育は道徳的で倫理的な判断と行動をする能力を養うことに重点を置いて
いる。反対に、社会科では知識の伝達と社会科的スキルの養成により焦点化している。
内容・テーマ 社会科授業は、社会科学の様々な規律から求められた 7つのテーマに根差している(表 3を参照のこと)。そのうえ、幼稚園から 10年生までの話題は、拡大する社会的文脈論に基づいて設定されている(図 2を参照)。その反面、価値教育における授業は以下の 4テーマに基づいて設定されている。(1)自分と家族の責任、(2)他者を仲間の人類として扱う(pakikipagkapwa)、(3)国家の発展と世界統一への貢献、(4)神を中心とした生き方と良きことの選択(DepEd, 2013; SEAMEO INOTECH, 2013)。これらのテーマに基づくと、社会科はより社会科学的知識に執念しており、価値教育はキャラクター教育に焦点化して
いるといえる。 複数のコンピテンス 社会科は幼稚園から 12年生までをかけて(1)探求、(2)データ分析と解釈、(3)情報の分析と解釈、(4)リサーチ、(5)コミュニケイション、(6)社会的規範の応用といった 6つのコンピテンスを養成していく。その反面、価値教育では(1)理解、(2)内省、(3)相談、(4)決断、(5)行動・振る舞いといった5つのマクロスキルを包摂している(SEAMEO INOTECH, 2013)。 表 6.幼稚園から 10 年次までの価値教育におけるキーステージ 幼稚園から 3 年次 4-6 年次 7-10 年次
自分と家族の責任、またコミ
ュニティ・国・神へという概
念や、それを表す行動につい
て理解し、幸せで協調的な生
活をおくれるようになる
自分と家族の責任、またコミ
ュニティ・国・神へという概
念や、それを表す行動につい
て理解し、公共善を推進する
ことができる。
自分と家族の責任、また社会
化(pakikipagkaqwa)、社会、勤労・生産性(paggawa)と道徳的価値といった概念
を理解し、責任を持って決断
ならびに行動し、公共善を推
進するとともに幸せで協調
的な生活をおくれるように
なる。 キーステージのスタンダードという点において、社会科と価値教育には共通点と相違点
がある。双方の科目が生徒らに自身・家族・コミュニティといった概念を理解し、他者へ
の愛・人類への思いやり・愛国心・理知的かつ論理的な判断といった価値を養うことを求
めている。その一方で、社会科が知識と歴史的思考力の発達に注力し、価値教育は倫理的
な人間の育成を強調していることもまた明確である(表 5と 6を参考)。
教育方法 教育方法に関して、双方の科目の教員は、様々な方略を通じて多様な社会問題に生徒ら
を触れさせることになっている。社会科教員は、テーマ/時系列別・概念的・探求・統合
的・分野横断的・多分野的アプローチを用いる。これらの方略は、学習者の歴史的思考力
やその他の社会科的スキルを磨きつつ、課題や複数の視点を提示する。一方、価値教育の
教員らは倫理的判断と社会/感情的学習アプローチを用いる(DepEd, 2013)。これらの方略は生徒らが社会問題を道徳やコミュニティ規範に基づいて解決する助けとなる。倫理的
判断アプローチにおいて、生徒らは状況の道徳的側面に敏感になるよう、またその決断が
個人や団体に及ぼすかもしれない影響に気づくような養成をうける。感情学習アプローチ
では(1)自己への気づき、(2)自己管理、(3)社会への気づき、(4)ポジティヴな関係性の構築、(5)責任の伴う判断といった 5つのスキルを養ってゆく。 表 7.1 年次 1 学期目の社会科と価値教育
社会科 価値教育 学習規範 物理的環境を重んじ、連続性と変
化・相関性・距離と方向といった概
念を用いて、家族・学校の一員とし
ての自己の理解と気づきを持つ。
自分を大切にするということ・他者/
国/神の尊重を態度に示す方法を理解
していることを表す。
内容規範 連続性と変化の概念を用いて、自己
への気づき(pagkilala sa sarili)の重要性を理解していることを示
す。
自己への気づきの重要性・個人の健康
の維持・家族の良き一員であることの
受容性を理解していることを示す。
たとえば一年次、4学期あるうちの 1学期目において、社会科と価値教育を比べると、テーマ(自己への気づき)は同じであっても、学習規範や内容規範は異なっている(表 7を参照)。社会科では、1年生は自分の個人的な特徴や、続いているものと変わったもの、個人を特別な存在とするものについて学ぶ。まず、第 1次・2次情報源を用いて、自分たちについての情報を集める。次に、年表や図表その他の発表物をつくって、どの特徴が続いて
きたものであり、変わったものかを分析する。そして教員は、ディスカッションや分かち
合い、ストーリーテリングやその他のグループ活動を通して其々の子のアイデンティティ
とクラスメイトのアイデンティティについて内省し感謝できるような機会をつくる。 1年次 1学期目の授業では、社会科と価値教育の重なり合う領域がみられる。社会科は自己への気づきを誘いながら同時に歴史的思考力・リサーチ・探求と効果的なコミュニケ
イションスキルなどを養っている。また、児童たちの多様な背景への尊重の念を養っても
いる。反対に、価値教育でも自己への気づきを促すが、自身や個人の健康を確立すること
により重点を置いているのである。 図 3.社会科と価値教育を統合する教育的アプローチの様子 これら 2つの科目にみられる現行のパターンでは、社会科と価値教育を結びつける教育
学的アプローチが提示できる(図 3を参照)。この教育学的アプローチを用いることで、生徒らはコミュニティーの歴史的・政治的・社会文化的文脈に基づいて、道徳的判断と倫理
的決断を行うよう育成できるだろう。言い換えれば、このモデルが啓蒙された政治的参加
もしくは内省的なシティズンシップの推進となるのである。
Westheimerと Kahne (2002)によると、よき市民には個人的に責任感のある市民・参加する市民・正義に基づく市民といった、3つの概念があるという。価値教育の方略は、個人的に責任感のある市民の養成に倣っている。個人的に責任感のある市民とは、納税や
法の順守・リサイクル・災害や緊急時でのボランティアといったよき市民の責務を果たす
人のことである。一方で、新しい社会科は参加する市民を養成している。参加する市民と
は、政府やその他の機構がどのように機能しているか、団体行動における計画・参画の重
要性を理解する人のことである。このような市民は、公的な出来事に参加し、必要な時に
はリードをとることができる。手短に、このような市民は、社会の事象に参加するため必
要な知識とスキルを有している。さらにいえば、社会科は生徒らが正義に基づいた市民に
なるよう備えさせている。正義に基づいた市民は、社会の出来事や不正義に関心を持ち、
根幹にある問題を定義するために団体行動が有益であると信じている。このような市民は、
不正義を再生産する人々に対し批判と挑戦を持ちかける。
まとめ 社会科と価値教育のカリキュラムの分析において、2科目間に自然かつ健全な重なりが存在することが分かった。社会科と価値教育は、個人的に責任感のある・参画する・正義
知ること
理解すること
価値づけ
行動する
に基づいた市民の育成のため互いに貢献し、教育者やカリキュラム開発者に対しても明確
に、目的・内容・コンピテンスと教育方法を提示することができる。 図 4.社会科と価値教育の関係性
基礎教育カリキュラ
ム(BEC):
全学習領域に統合さ
れている
幼-12年生向けカリキュラム:
フィリピン人のコアとなる価値観
+道徳的で倫理的な判断と行
倫理的判断
社会・感情学習アプローチ
価値教育
基礎教育カリキュラム
(BEC):
全学習領域に統合され
ている
幼-12年生向けカリキュラム:
個別の科目
目的
内容とキースタンダード
教授法
社会科教育
目的:責任感のある判断ができ、公共善の推進に熱心な市
民を育成すること 自分・家族・コミュニティという概念を理解し、他者への
あり・人類への思いやり・愛国心・責任感・理知的で論理
的な判断といった価値観を育成する 教育方法:社会問題の分析
個人的に責任感の
ある市民 参画する市民 正義に基づく市民
図 4は 2つの科目の重なる領域を示している。分析によると、社会科と価値教育は相関しているカリキュラムである。創刊するカリキュラムとは、生徒たちのニーズに呼応する学
習体験を提供するにあたって、科目間の境界線に融通の利くことを表す。例えば、目的と
いう点では、社会科と価値教育は責任感ある判断を行い、公共善の推進に熱心な市民の育
成を目指している。この目標のために、双方の科目が学習者の概念理解と、市民参画に重
要なコアとなる価値観の育成を支援する。両方の学習領域が、学習者を様々な社会問題に
触れさせてもいるのである。 内容とコンピテンスという点において、社会科は社会科学的知識の伝授と、歴史的思考
やその他の社会科スキルの育成をより重要視している。反対に、価値教育は人格教育?キ
ャラクター教育?、また道徳的かつ倫理的な判断や行動といったスキルの育成に焦点化し
ている。これに関連して、この 2学習領域は知識の伝授と目指すスキルの育成に異なる教授方略を用いている。 社会科と価値教育は異なる種類の公民的知識を伝授し、スキルや価値観を育成している。
前者は参画し正義に基づいた市民を育成しているが、後者は個人的に責任感のある市民を
育成している。社会科と価値教育の自然で健全な相関を探るために、本研究は教育者が提
示されている教育学的方略を用いることを推奨する。これはフィリピンのみならず、啓蒙
された政治的参加に必要な知識・価値観・スキルを兼ね備えた市民を育成することを目指
す、他の民主国家においても応用が可能であろう。
目的




















![コプト語の複数定冠詞(ハンドアウト)[Coptic Plural Definite Article (handout)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321a6dc64690856e108cc3b/coptic-plural-definite-article.jpg)