知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who...
Transcript of 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who...
Shinshu University Institutional Repository SOAR-IR
Title 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い
Author(s) 飯岡, 詩朗
Citation 人文科学論集. 文化コミュニケーション学科編 47: 87-108(2013)
Issue Date 2013-03-15
URL http://hdl.handle.net/10091/16983
Rights
87
知らなすぎた男ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い
飯 岡 詩 朗
空虚さに向き合うにはかなりのガッツが必要だが、絶望に向き合うにはもっとたくさんのガッツが必要だ。
リチャード・イェイツ1
はじめに 2008年の東京で見るダグラス・サーク
2008年夏,渋谷東急を会場に開催された第30回ぴあフィルムフェスティバルでは,スペシャルプログラムとして1950年代のハリウッドを代表する映画監督ダグラス・サークの特集上映(「ダグラス・サーク特集~かなしみのハッピーエンディング~」)が組まれた。上映されたのは11作品で,1930年代のドイツ時代の3作品のうち2作品は過去に日本国内でVHSとLDが,1950年代のアメリカ時代の8作品のうち6作品は2007年12月までに日本国内でDVDが発売されてはいたが,滅多にない映画館の大きなスクリーンでの上映の機会を逃すまいと,各3回の上映は毎回多くの観客を集めていた。(わたし自身が鑑賞した回はいずれも定員300席の会場は満席だった。) 映画館の大きなスクリーンでの鑑賞は,テレビの画面でならほとんどの作品をすでに見ていたわたしにも,いくつかの「発見」があった。その一つは,作品の細部の輝きに気づけたことである。とりわけ,直前のユニヴァーサル社の火事により運良くニュープリントで見ることのできた『いつも明日がある』(There's Always Tomorrow, 1956)では,ラッセル・メティの撮影が産み出す陰影の美しさだけでなく,俳優の台詞や演技以上に主人公の感情を雄弁に表現する映像(例えば,バーバラ・スタンウィック演じるノーマの頬に差した勢い良くガラス窓をつたう雨粒の影など)の力を実感した。もう一つは,俳優の演技への印象の変化である。とりわけ,主人公が女優を職業とし,それ以外の主要な登場人物すべてにかかわる「演技/模倣」の主題を持つ『悲しみは空の彼方に』(Imitation of Life, 1959)の場合,その変化がより強く感じられた。具体的には,ラナ・ターナー演じる主人公ローラが,職業として演技をする家の外だけでなく,家の内においてすらも常に演技をしているようにどうしても見えてしまったのだ。 しかし,わたしにとってこうした「発見」以上に強く印象に残ったのは,いくつかの作品のもっとも悲痛で,哀感が最高潮に達すると思われる場面で,会場内に予想外に大きな笑いが起こったことだ。そうした大きな笑い声が起こった場面の一つは,サークによる最後のハリウッド映画であり,最後の長篇作品である『悲しみは空の彼方に』の終盤で,主人公のローラと娘のスージー(サンドラ・ディー)との口論の場面である。ローラは,自分がこれから結婚しようというスティーヴ(ジョン・ギャビン)に娘も真剣に恋をしていることを黒人の(事実上の)「メイド」であるアニー(ファニタ・ムーア)に聞かされ取り乱し,それ
88
が事実かどうかを娘に問いただそうとするが,逆に娘のスージーからいつも自分の相手をしてくれたのはアニーだったと責められ,ついには「スティーヴのことであなたともめるくらいなら,彼と別れるわ。彼には二度と会わない(If Steve is going to come between us, I'll give him up. I'll never see him again.)」と口にする。しかし,スージーは「ママ,演技は止めて!(Oh, Mama, stop acting!)」とすぐに切り返し,さらに「もういいわ。私がスティーヴをあきらめるから。だからお願い,犠牲者ぶらないで!(Don't worry, I'll get over Steve, but please, don't play the martyr!)」と続ける。この母娘の一連のやりとりのうち,スージーが「ママ,演技は止めて!」という台詞を発した瞬間に,会場内には大きな笑いが起こったのだった。 同じくわたしにとって予想外に大きな笑いが起こったのが,『いつも明日がある』のエンディングだった。玩具メーカーの経営者である父親クリフォード・グローヴズ(フレッド・マクマレー)が,かつての同僚で,いまはNYで活躍している服飾デザイナーであるノーマ・ヴェイル(バーバラ・スタンウィック)と不倫関係に陥っていると邪推した長男ヴィニー(ウィリアム・レイノルズ)と長女エレン(パット・クロウリー)。兄妹は二人を別れさせようとノーマに会いに行き,父親を「誘惑」した彼女を批難するが,逆に,仮にクリフとわたしの間に何かが起こったとしてもそれはあなたたち家族のクリフに対する愛情や思いやりが足りなすぎたからだ,ときつく叱責される。この後,ノーマから永遠の別れを告げられ途方に暮れて帰宅した父親を,これまでの自分達の態度を反省したヴィニーたちが迎えるのだが,その場面にヴィニーとクリフの間で次のようなやりとりがある。
ヴィニー:おかえり,父さん。(Hello, Dad.)クリフ:ただいま,ヴィニー。(Hello, Vinnie.)ヴィニー:気分はどう?(How're you feeling?)
それまで物語を見守って来た観客からするとあまりに無神経すぎる,このヴィニーによる「気分はどう?」という台詞が発された瞬間に,会場内に起こった大きな笑いは,上述の『悲しみは空の彼方』の場面で起こった大きな笑い以上に予想外であったし,違和感すら感じるものだった。 2008年の夏に東京で,見ず知らずの多くの観客と共にダグラス・サークの作品を見たときのわたしのこうした違和感を手がかりに,本稿は,『いつも明日がある』と笑いの関係を考察し,サーク作品の新たな読み直しの意義を探ることを目的とする。まず,次の第1節では,この2008年夏の東京でのサーク特集についてのアメリカの映画批評家による報告記事をもとにサーク作品と笑いの関係を整理する。続く第2節では,映像テクストの詳細な分析から『いつも明日がある』が他のより広く知られる1950年代のサークの代表作とは異なり,アイロニーとしての笑いを呼びにくい作品であることを明らかにする。第3節では,『いつも明日がある』を作品が製作・公開された1950年代のコンテクストに埋め直し,とりわけ同時代にテレビで放送されていたシットコムとの類似性から『いつも明日がある』をシットコムのパロディとしてとらえ直す。
89知らなすぎた男
1.ダグラス・サークを笑う
映画批評家のクリス・フジワラ(Chris Fujiwara)は,前節で言及したダグラス・サーク特集をレポートする短い記事の中で,サークの作品をアメリカと日本で見る体験を比較している。フジワラによれば,作品に対して敬意のある日本の観客とともにサークを見ることの方が,サークを笑わずには見ることができないアメリカの観客とともに見るよりもはるかに愉しいという。さらにフジワラは,アメリカでのサークの上映では避けることのできないが日本ではほとんど見られない笑いのタイプを四つに分類している。 一つ目は,キャンプ的な笑い(Pop-Trash-Camp Laughter)である。アメリカの上映では,『風と共に散る』(Written on the Wind, 1955)におけるドロシー・マローンの演技には笑いが耐えないし,とりわけ(ゲイであったことが広く知られている)ロック・ハドソンが,『天の許し給うものすべて』(All That Heaven Allows, 1955)や『風と共に散る』などで「男らしい」言動をするときには,大笑いがおこるという2。 二つ目は,強烈なイメージに対する笑い(The Laugh Against Strong Image)である。例えば,『風と共に散る』のエンディングでドロシー・マローンが,油井やぐらの模型を握りもたれかかる場面は,あらかじめ笑い声が音声トラックにおさめられていたとしても,誰も気づかないほどにアメリカでの上映では笑いがわき起こるという。同様の笑いは,『風と共に散る』で性的不能のカイル(ロバート・スタック)が玩具の馬にまたがって遊んでいる少年に目をやる場面や,『心のともしび』(Magnificent Obsession, 1954)の終盤,難しい手術を行うロック・ハドソンをオットー・クルーガーが見下ろす場面や,『天の許し給うものすべて』で,大きな窓の向こうに鹿が登場するエンディングでもおこるという。 三つ目は,情動を否認する笑い(The Emotion-Disavowing Laugh)である。例えば,『悲しみは空の彼方に』終盤のアニーの壮大な葬儀の場面や,『心のともしび』でジェーン・ワイマンがタクシーから飛び出して車にひかれる場面や,『天の許し給うものすべて』でロック・ハドソンが崖から落ちる場面など,過剰にメロドラマ的な場面で,アメリカの上映では笑いが起こるという。 四つ目は,イデオロギー的優越性を示す笑い(The Ideology Knowing Laugh)である。例えば,『悲しみは空の彼方に』のエンディングで,スティーヴ(ジョン・ギャビン)がサラ・ジェーン(スーザン・コナー)に向ける笑顔に,アメリカでの上映では笑いがおこることがあるという。つまり,家父長的に事態を収束させるかのような自信ありげな態度を示すスティーヴが,サラ・ジェーンが抱える性差別的で人種差別的な問題に対しては無力であることを認識していることを誇らしげに示すために観客は笑うのだ。 フジワラは,こうしたタイプの笑いが日本の上映では存在しなかったという。しかし,こうした笑いの不在は,日本の観客が50年以上前の外国映画のどこで笑うのが適切なのかわからなかったからという理由もあるかもしれないが,それだけではないのではないか,とフジワラは述壊し,日本の観客がユーモアに対する鋭敏さも持ち合わせていた証拠として,日本の観客がアメリカの観客と同様に笑った箇所を挙げている。それは,『天の許し給うものすべて』における,カントリー・クラブにロック・ハドソンが登場する無残な場面や,前節で
90
わたしが挙げた『悲しみは空の彼方に』の母娘の口論の場面,『いつも明日がある』における保守的な考えにとらわれた子どもたちの言動である。そして,フジワラは,日本の上映での笑いは,作品が明らかにねらっていた笑いであり,そのように適切な箇所では笑い,そうでない箇所では笑わない観客によってこそ,現代において,正当にサーク作品の真価は問われうる,と結論する。 アメリカでの上映で起こる四つのタイプの笑いと日本の上映で起こった笑いが,フジワラが言うように峻別できるものあるかは措くとしても,わたしたちがいまサークを見るときに起こる笑いが,どれも同じタイプの笑いではないというのはたしかだろう。もちろん,当時の観客を笑わそうと作品が意図していたもの/ことを笑う笑いと,作品が本来は意図していなかったであろうもの/ことを笑う笑いとを峻別することも容易ではないだろうが,1950年代のサーク作品の中では,明らかに過激さや過剰さを欠いているために,フジワラが整理したような四つのタイプの笑いが起こりづらいと考えられる『いつも明日がある』と笑いの関係を以下では考察していく。
2.『いつも明日がある』とアイロニー
1950年代,ハリウッドは,減少する観客に歯止めをかけようとさまざまな方策をとった。ワイドスクリーンや3Dなどの視覚的表現上の技術的革新がその代表的なものだが,映画が扱う題材においても大きな変化が見られ,各スタジオがこぞってより刺激的で大胆な題材を扱った「大人向け(adilt)」のドラマを製作した。そうすることで,アメリカ全土の家庭に普及した結果,家庭内で見るにふさわしい高い道徳性を要求され,自主規制により保守的な題材にしか扱うことのできなかったテレビとの差異化ができたからである。 ダグラス・サークの1950年代メロドラマもおおまかにはこうした流れの中に位置づけられ,とりわけ『風と共に散る』は,「大人向け」の刺激的で大胆な題材とサーク独自の過剰な表現スタイルが効果的に絡み合い,後に多くの批評家/研究者から高い評価を得ることとなった3。一方で,『いつも明日がある』は,『風と共に散る』と比べはるかに穏当な題材を扱った『心のともしび』や『天が許し給うすべて』よりも,題材においても表現スタイルにおいてもサークらしい大胆さや過剰さを欠いており,たとえば,『灰色の服を着た男』(The Man in the Gray Flannel Suit, 1956)など,サーク以外の「大人向け」のドラマと比べても見劣りする,刺激を欠いた作品のように見える4。 しかしながら,大胆さや過剰さを欠いた『いつも明日がある』においても,サークらしいアイロニーや,ポール・ウィルメン(Paul Willemen)の言う「距離化(distanciation)」はもちろん見てとれる。そのことは,「昔むかし,陽光あふれるカリフォルニアで……(Once upon a time, in sunny California...)」というタイトルカードに続くショットで,どしゃ降りのカリフォルニア市街地が映し出される冒頭からあきらかである5。 どしゃ降りの中を帰宅したクリフを追うカメラも,クリフから距離を取りながら,彼が家族の誰からもまともに相手をされず家の中を右往左往する様をとらえ続ける。妻マリオン(ジョーン・ベネット)の誕生日を祝おうと花束を手に帰宅し,約束の観劇と夕食へと誘うも,末娘の初めてのバレエ発表会を理由にキャンセルされ,やっとのことで入手したチケッ
91知らなすぎた男
トを無駄にしまいと,長男や長女を誘うも断られ(しかし長女から小遣いはせびられ),あげくの果てお手伝いにも相手にされないクリフの滑稽な様が観客の笑いを誘うよう演出されているのは,おそらく疑いがない。そのことは,続く場面で,一人家に残されたクリフがエプロンをしたままキッチンのテーブルでひとり食事をしている様が映し出されることで強調されている。(ただし,これらの場面で,クリフの滑稽さが過度に強調されているわけでもないことは,『理由なき反抗』(Rebel without a Cause, 1955)の父親のエプロン姿[図1]を知っているものにとっては,明らかだろう。)
物語は,クリフが食事をしている最中に家を訪れるかつての同僚ノーマの登場で動き出す。クリフはノーマを観劇へと誘い出し(後にクリフはノーマがすでに同じ舞台をニューヨークで見ていることを知る),その後,ノーマの希望で二人はクリフの会社に向かい,かつて二人で開発した玩具を手に取りながら思い出話に花を咲かせるが,その夜は近日中にクリフがノーマを自宅での夕食に招待するという約束をして二人は分かれるのみで「大人向け」のドラマらしい展開はない。 二人の関係が進展するのは,夕食会の前の思わぬ再会によってである。妻マリオンと二人きりでリゾート地のパーム渓谷で週末を過ごそうというクリフの計画は,末娘の足首の怪我が原因で御破算になる(その怪我が大騒ぎをするほど深刻なものでないことは,窓枠越しに示される娘たちの部屋のショットからもあきらかだろう)。しかし,そこで仕事上の打ち合わせの約束もあったことを知った妻マリオンは,打ち合わせのついでに息抜きもできるだろうと一人ででも計画どおり出かけるようにすすめ,渋々ながら向かったパーム渓谷で,クリフはノーマと偶然の再会を果たすのである。 パーム渓谷で再会した二人は,乗馬,水泳,夕食,ダンスを楽しむ。ダンスの最中に届いた電報によって翌日の仕事上の打ち合わせはキャンセルとなり,クリフが一泊する理由はなくなるのだが,ノーマと過ごした時間がよほど楽しかったのか,クリフはもう一泊して気分転換をすることに決め,ノーマにも一緒に過ごしてくれるように頼む。しかし,「大人向け」のドラマらしい展開がその後あるわけではない。 翌日は,長男ヴィニーと恋人のアンと友人のカップルの四人でパーム渓谷に車で向かう場
[図1]
92
面から始まる6。しかし,父親が滞在しているリゾート地に押しかけ,父親のお金で存分に楽しもうという能天気なヴィニーたちを待ち受けていたのは,思いもよらぬ父親の行動だった。ヴィニーは父親が仕事上の打ち合わせをしているはずの日に,見ず知らずの女性と仲良く過ごしている「不倫」の現場を目撃してしまうのだ。 ここまでのクリフとノーマの関係が「不倫」と呼ぶには程遠い健全な関係であることを知っている観客にとって,ヴィニーの誤解は明白なのだが,その誤解によって,クリフの家庭は軋み始める。クリフは,パーム渓谷でノーマに再会したことを一切隠し立てせず話すのだが,ヴィニーのクリフへの疑いは消えず,長女エレンへ感染してしまう。(兄妹の愚かさはヴィニーの恋人アンによるクリフの擁護によって強調されている。) 兄妹の父親に対する疑惑と不信が高まるなかで行われた夕食会の場面は,大胆さや過剰さを欠いた『いつも明日がある』においては,きわめて顕示的(expressive)な場面と言えるだろう。テーブルを飾る燭台は,家庭の裕福さとともに,その日の夕食がいつもよりも豪華で特別なものであることを示すと同時に,登場人物の関係性をはっきりと描き出してもいるからだ。この場面の一連のショットの連鎖をみてみよう。 まず,ノーマとクリフが,二つの燭台によってはさまれ,両者の親密さが示される[図2]。この後,カメラが右にパンすると,クリフとヴィニーの間に燭台が現れ,ノーマとク
[図3]
[図2]
93知らなすぎた男
リフの二人と,ヴィニーとエレンの二人を分断する[図3]。その後,父親が「招かれざる客」と何食わぬ顔で楽しげに会話しているのに耐えられなくなった兄妹は相次いで席を立つことになる。カメラは二人を追って右にパンするが,ショットが変わり,カメラがノーマとクリフをその前の同じショットスケールで再び捉え直すと,ほんの十数秒前にはフレーム内に存在していなかった燭台が画面の手前にあらわれ,ノーマとクリフをはっきりと分断するのだ[図4]。このように,夕食会の場面は,サーク作品らしく(あるいは50年代メロドラマらしく)ミザンセンが登場人物の関係性を雄弁に語っているのだ7。 同様に,ミザンセンが登場人物の関係をはっきりと描き出す場面として,夕食会の後日,マリオンが息子の恋人アンとともにノーマの店を訪れる場面が挙げられる。もちろん,マリオンの来店は,夕食会に招かれた際にノーマ自身が促したものではあるのだが,ここでの彼女の行動は,むしろ敵情視察のようなものととらえた方が良いのかもしれない。実際,この場面は,クリフをめぐる二人の女性の対決の場面として描かれるからである。ノーマに薦められるままに,マリオンはノーマがデザインしたドレスを試着するが,ノーマやアンの褒め言葉にもかかわらず,マリオンは,こんな派手なドレスは必要ない,と,まるでノーマの仕事自体を否定するかのように拒絶する。 この二人が敵対的かつ対照的な関係にあることは,こうしたやりとりに加えて,ミザンセンによって雄弁に語られる。ノーマがデザインしたドレスを脱ぎ,慎ましい母/妻が着るに
[図4]
[図5]
94
ふさわしいスーツに着替え,ノーマに礼を言う場面を見てみよう。ここでは,手前の室内装飾が,画面上を二つに分断することで,両者の敵対的関係が明確に示されている。さらに,マリオンが着替えを終えていることによって,華美なノーマとの対照性はよりいっそう強調される[図5]。 この訪問の前,夕食会の夜にマリオンが鏡台を前に口にしたノーマに対する哀れみの言葉("I think she's lonely. [...] I feel sorry for her. [...] She's missed what every woman really want.")を思い返せば,よりこの場面が二人の女性の対決の場面であることは明らかになるだろう。 哀れみの言葉をマリオンが口にする直前の場面では,ノーマを招いてのせっかくの夕食会が,子どもたちの無作法によって台無しになったことにいらだつクリフは,その怒りと悲しみを妻マリオンに理解してもらおうとするのだが,それは空しいものに終わる。妻の無理解にもいらだつクリフは,ついには自分がただお金を稼いで家に持って帰るだけのロボットのようだと感じるとまで口にする("I'm, becoming like one of my own toys? Clifford Groves the Walkie-Talkie Robot! [...] Wind me up [...] and I drive to the office and work all day to pay the bills!")が,それでもマリオンはクリフの苦悩を理解できない(しない)まま,先にベッドに入ってしまう。 この後,マリオンの無理解に悲嘆しノーマへの思いを募らせたクリフは,眠りについたマリオンの目を盗んで寝室を抜け出し,階下でノーマに電話をかける。階下に辿り着くまでのショットの連鎖を見てみよう。クリフはマリオンに気づかれまいと何度か彼女の方をうかがいながら部屋を出るのだが,その後カメラは,階下で降りて来るクリフを待ち受けるのではなく,ほんの数秒間寝室に留まり,マリオンをミディアムクロースアップで捉えつづける。すると,マリオンは,寝返りをうち,彼女の瞳が一瞬光るのを観客は目にすることになる[図6]。
マリオンの瞳の光は微かなものではあるが,この場面よりも先のいくつかの場面で,登場人物の瞳の輝き[図7]に目を引かれていた観客が,この一瞬を見落とすとは考えにくい。 もちろん,この瞳の光は,すでに見たミザンセンのようには雄弁にではないが,彼女が完全に眠りについているわけではないことを示しており,さらには,クリフのおかしな行動に気づいていないわけではない,ということをも示すだろう。もちろん,この瞳の光をカメラ
[図6]
95知らなすぎた男
が偶然とらえてしまったものだと見なすことはできない。マリオンの目を盗むことにクリフが成功したことだけを示したいのであれば,クリフが部屋を出たとたんに,カメラは階下でクリフを待ち受ければ十分なはずだからである。また,実際,『いつも明日がある』の撮影台本には,マリオンが「目を半開きのまま寝返りを打つ」とのト書きもあるのだ8。 この瞳の光を見てしまって以降,観客のマリオンに対する見方は変わらざるを得ないだろう。この場面で,彼女が寝たふりをしてクリフの行動を密かにうかがっていたとするなら,すでに見たこの場面の後のノーマの店を訪問する場面の意味はよりいっそう明白になるだろう。いずれにしても,モリー・ハスケル(Molly Haskell)の言う,「防腐処理をほどこされ平板化された」(272)主婦や「典型的な母親」(323)と見なすにことができるほど,マリオンを単純な登場人物として捉えることは困難になる。もちろん,マリオンの得体の知れなさは,ジョーン・ベネットがそれまでに演じた狡猾なファムファタル(『飾窓の女』(The Woman in the Window, 1944)『スカーレット・ストリート』(Scarlet Street, 1945))の,夫が留守の間,娘=家族を守るためなら死体遺棄すらする母親(『無謀な瞬間』(The Reckless Moment, 1949))の,また,夫/父親を差し置いて娘の結婚式を仕切る妻/母親(『花嫁の父』(Father of the Bride, 1950))のイメージ越しに観客がマリオンを見ているからにほかならない9。 マリオン以上にクリフの行動に注意を払っていたのは,長男のヴィニーである。クリフの行動の監視へとヴィニーを駆り立てたきっかけが,誤解であることはすでに述べたが,映画の終盤でノーマに叱りつけられるまで,彼はそのことに気づくことができない。エイミー・ローレンス(Amy Lawrence)が指摘するように,1950年代に流行した壁を取り払ったオープンな間取りは,そもそもは親が常に子どもに目が届くように設計されたものだが,同時にそれは,ヴィニーがそうであったように,子どもによる親の行動の監視にも役立つものでもあった(162)。そして,そうした間取りを,『いつも明日がある』はディープ・スペースとして活用している。パーム渓谷から帰った後,クリフがノーマに夕食会の誘いの電話をする場面では,画面の手前では,ヴィニーたちが,不倫への疑いを抱いたまま父親の行動を監視している[図8]。 ヴィニーによる監視行動こそがクリフをノーマへと向かわせたのだということは,前庭側から窓枠越しに父親が電話をする様子を示す場面[図9]でより強調される。
[図7]
96
ここでは,窓枠越しに父親の行動を監視するヴィニーの後ろ姿が画面の右半分近くを黒く塗りつぶす。狭められた画面の中で,父親は窓枠によってさらに小さな空間に息苦しく閉じ込められているように見え(後の場面で彼は「空気を吸いたい(I wan to get some air)」と口にすることになる),家庭を崩壊の危機から救おうとするヴィニーこそが父親を「不倫」へと追い込んでいることを仄めかす。映像が示すように,ヴィニーと父親の間には,距離があり,その間には多くの障害物があるため,父親を理解することもできないし,「怪しい」行動を「目撃」しながら,その行動を直接止めることもできない。結果,クリフはノーマに会いに行き,自分の苦悩("I felt desperate sitting in my own living room. I felt as though I were trapped in a tomb of my own making.")と彼女への思い("I had to escape because I was still alive alive and wanting you.")をついに口にし,二人はここに至って初めてキスをする。 こうしたグローヴズ家を危機から救うのは,ほかならぬマリオンである。翌日の再会を約束してノーマと別れたクリフは,帰宅するものの玄関の前で立ち止まる。すると背中から「パパ!(Daddy!)」と声が聞こえ,次女フランキーが飛びついて来る。外出していた妻と次女の二人と帰宅時間が一緒になったのだ。クリフの様子がおかしいことに気づいたマリオンは,家の中に入ろうとしないクリフの腕をとって庭の方へと歩き出す。そしてクリフとマリオンは,ヴィニーがそうしたように,窓枠越しに家の中を覗き込むことになる[図10]10。
[図8]
[図9]
97知らなすぎた男
エレンがピアノを弾く姿を二人で眺めながら,夫のいない夕食の味気なさを訴えるマリオンの言葉をうつろな顔のままクリフは聞くのだが,マリオンを呼ぶ末娘フランキーの声に促されカメラは右にパンし,マリオンは,フランキーの方にため息をつきながら走っていく。そのときカメラは,その姿を見つめるクリフの姿を捉え続ける[図11]。
この場面は,妻マリオンが,夫クリフに,自分たちの幸せとはどういうものなのかを夫クリフに理解させようとする場面だろう。マリオンの「レクチャー」を通して,自分が「幸福」であった/あること,さらには,これから自分が成そうとすることは,その「幸福」を捨てることだということを,部屋へと消えて行く妻と次女を目で追いながら,クリフはおぼろげながら理解するのだ。 クリフが,この「レクチャー」の場面での体験の意味を真に理解するのは,ノーマから別れの言葉を告げられる場面である。その場面の直前には,クリフとの面会を約束した時間より前にホテルにやって来たヴィニーとエレンをノーマが叱責する場面がある。
ヴィニー:二人を見たし,話しているのを聞いたんだ。(I saw you heard you.)ノーマ:いったい全体,何を見て,何を聞いたというの?(And just exactly what did
you see and hear?)
[図10]
[図11]
98
この場面は,子どもたちが実際のところ何一つ見ても聞いてもいないこと,父親の思いを少しも理解できていないことを子どもたちにノーマが言って聞かせる場面であり,上述のマリオンによる「レクチャー」と類似した場面だと言える。ノーマの言葉によって二人は,自分たちの父親への日頃のふるまいを反省することになるだろう。続くノーマとクリフの別れの場面も,同じように,ノーマがクリフに現実を理解できていないことを言って聞かせる場面であり,彼女の「レクチャー」を通して,クリフは,上述の場面でマリオンと共に見たものの意味を真に理解するのだ。 ノーマは現実(reality)を直視するからこそクリフのもとを去ると告げる。ノーマの言う現実とは,「夫として父親としてのクリフォード・グローヴズの20年間(twenty years of Clifford Groves as a husband and as a father)」であり,その現実から目を背けてはならない,とクリフに訴える。さらに,家族のもとをいま去れば,ヴィニーの卒業式にも,エレンの結婚式にも,フランキーのバレエのリサイタルにも行けなくなるのだ,と言い聞かせ,クリフに現実を理解させようとする。こうしたノーマの言葉によって,クリフはマリオンの「レクチャー」を思い返し,ようやく自身の置かれた状況を理解することができる。いまでは疎ましいとすら感じるようになってしまった家族ではあるが,その家族をいったん捨ててしまえば,窓の外から,あるいは遠くから,家族を眺めることしか出来なくなってしまうのだということを理解するのだ。クリフにとってノーマとの別れが受け入れ難いものであるのは,走り去る彼女を彼が追いかけたことから明らかだが,タクシーに乗り込んだ彼女を追いかけず雨の中立ち尽くしたのは,ノーマとの別れが一方では受け入れざるを得ないものだと理解していることの証しだろう。監督のサークはあるインタヴューで,「メロドラマにおいては,主人公はアンハッピーなハッピー・エンドを生き続けなければならない」と言っている。ここでクリフが辿り着いたのは,まさにそのようなハッピーともアンハッピーとも受け取りうる終わりではないのか11。 こうした地点から本稿の冒頭で取り上げた,ノーマとの別れの後,帰宅したクリフを迎える家族の言動を見直すと,無神経に聞こえたヴィニーがクリフにかける言葉も,次のようなマリオンとクリフのやりとりも,けっして白々しいだけのものではなくなるだろう。
マリオン:ここ数日心配だったわ。イライラしたりふさぎ込んだり,いつものあなたらしくなかったから。(You've worried me these last few days. It's not like you be irritable and depressed.)
クリフ:ああ。でも,もう大丈夫だ。(I know. I'm all right now.)マリオン:良かったわ。(Good.)クリフ:君は僕以上に僕のことをわかってるんだな。(You know me better than I know
myself.)マリオン:そうね。生涯そうでありたいわ。(Well, I should, after a lifetime with you.)
こうした言葉を口にするとき,マリオンもクリフも,それを白々しいと知りつつ口にしていたとしたら,観客はいったいどのような位置からこの家族を笑うことが可能になるだろうか? また,この直後,家族に迫っていた危機をおそらくは何も知らぬまま,「仲の良い」
99知らなすぎた男
両親を満足そうに眺める末娘フランキーの「なんて素敵なカップルなのかしら?」という言葉に観客が笑うならば,それはいったいどのような笑いだというのか[図12]?
3.シットコムと(しての)『いつも明日がある』
一家の大黒柱である父親が,昔の同僚と再会し不倫関係に陥りそうになるが一歩手前で踏みとどまる話とでも要約できる『いつも明日がある』は,「大人向け」のハリウッド映画よりもむしろ当時テレビで放送されていたいわゆる「ホームドラマ」によく似ている。実際,『いつも明日がある』のグローヴズ家の家族構成は,1954年10月から放送が開始された郊外に暮らすアンダーソン家を舞台とするシットコム(シチュエーション・コメディ)『パパは何でも知っている』(Father Knows Best, 1954-1960)と同じ,妻,息子1人,娘2人であるし,家族にまつわる「小さな問題」の解決によるハッピー・エンドという物語構成もよく似てはいる[図13]。また,当時の業界誌によれば,クリフ役には,『パパは何でも知っている』で父親ジムを演じたロバート・ヤングが検討されてもいたという12。 実際,『いつも明日がある』には,『パパは何でも知っている』との関係をうかがわせる具体的な場面も存在する。街をあげての中学校の職業体験週間に長男バドが裁判官として駐車違反をした父親を裁くことになるシーズン1エピソード14「生徒週間」("Boy's Week"
[図13]
[図12]
100
1955年1月2日放送)の冒頭には,約束したことをやらずにいるバド(ビリー・グレイ)にしびれを切らしたジムに,妻のマーガレットが「明日やるとパパに伝えてとジムが言ってたわ(He told me to tell you he'll do it tomorrow)」と言うと,「いつも明日だ!(Always tomorrow!)」とジムが呆れる場面がある。まさにこの場面で,ちょうど花瓶に花を生けていたマーガレットは,ジムのジャケットの左の下襟のボタン・ホール(一般にフラワー・ホールと呼ばれる)に花を一輪さすのだが[図14],この場面は,パーム渓谷のリゾート地で偶然再会したクリフとノーマによって再演されており[図15],上述のとおり,それを偶然目撃してしまったクリフの息子ヴィニーが二人の関係を邪推することから物語が展開していく。
こうした類似点から両者にことさら密接な関係があると強く主張しようというのではない。なるほど,『いつも明日がある』のグローヴズ家と比べると,『パパは何でも知っている』のアンダーソン家は,いつも明るく平和であり一見すると似てはいない。しかし,その明るく平和なアンダーソン家を演出や演技によって成り立っている家族として描くのが『パパは何でも知っている』なのだとすれば,『いつも明日がある』を『パパは何でも知っている』と共に見ること,同時代の作品として見ることは,けっして意味のないことではないと思うのだ。まずは,具体的なエピソードをもとに『パパは何でも知っている』が描く家族を見てみよう。
[図14]
[図15]
101知らなすぎた男
シーズン1エピソード12「クリスマスのお話」("The Christmas Story" 1954年12月19日放送)は,クリスマス・イヴにクリスマスの現代化――息子はクリスマスに便乗して小遣い稼ぎを目論み,娘たちはピンク色のツリーの方が素敵などと言う――を憂うジムのアイデアで,昔ながらのクリスマスを迎えるため,ツリー用のモミの木を入手しようと家族全員が郊外に車で向かうという話である。道中,息子は雪になるという天気予報をジムに伝え,早めに家に引き返そうと提案するが,息子の言葉に耳も貸さないジムは車を走らせ続ける。ジムになんら具体的な計画がなかったことがわかる頃には外は大雪で,ついには車は山のなかで立ち往生してしまうことになる。もちろん,最終的には,ハプニングを楽しむことのできる家族のおかげで,それなりに素敵なクリスマスが訪れ,ジムのミスは帳消しとなり父親としての面目は保たれる。 このエピソードにかぎらず『パパは何でも知っている』のジムは,小さな失敗をいくつも重ねるダメな父親だと言ってよい。もちろん,家の外で保険外交員として働くジムがダメだと言うのではない。家計を支える稼ぎ手として優秀(であるらしい)ジムが,家族の前では,けっして少なくない欠点を抱えた人物として描かれるのだ。(もちろん,ジムが欠点をなかなか克服できないことが,毎週放送されるシットコムの基本構造となっている。) 欠点を抱えたジムが父親としての面目を保つことができているのは,一つには上述のエピソードのように,都合の良すぎる偶然により放送時間内にハッピー・エンドがもたらされるからであり,もう一つは家族の「支え」があるからである。例えばシーズン1エピソード6「ジム爺さんの若返り」("Grandpa Jim's Rejuvenation" 1954年11月7日放送)は,子供たちが急に大人になってしまったという思いにとらわれ,自分がひどく年老いてしまった気がして落ち込むジムを家族が励まそうという話である。ここでの励まし方は,子どもたちがより「子どもらしく」演技することによって,子どもたちにはまだ父親が必要だととジムに信じ込ませるというものである。(その計画を立て,演出をしたのは母親である。) このエピソードに特徴的に見られるように,『パパはなんでも知っている』の母親は概して父親よりも賢く,父親を操っているとすら言えなくもない。そうした母親による父親の「操縦」が前景化するのが,シーズン1エピソード11「マーガレット,ダンスに行く」("Margaret Goes Dancing" 1954年12月12日放送)である。エピソードはまず,妻たちの会話から始まる。アンダーソン家の母親マーガレットは,友人のマートルから夫婦そろってダンス・レッスンに行かないかと誘われる。マーガレットは無理だと断るのだが,マートルは,子供のせい,家庭のせい,などといろいろ理由をつける彼女を非難する。続いて二人はつぎのようなやりとりをする。
マーガレット:でもジムを知ってるでしょう? 彼を説き伏せて何かをさせようなんて,絶対無理よ。ましてやダンス・レッスンなんて。
マートル:夫を説き伏せて何かさせようなんてダメよ。将軍の制服を着せてあげて,後ろから押していくの。そうすれば自分で大隊を率いていると勝手に思うわ。
マーガレット:でもジムは絶対に仕向けられたくないって考える人だし,絶対に男らしく独立独歩を保ちたいって考える人だから。
102
このようにマーガレットはあまり乗り気ではなかったのだが,ジムの承諾を得ないままにマートルに夫婦二人してダンス・レッスンに行くと約束してしまう。 次の場面で,ダンス・レッスンに夫婦揃って行く予定であることを父親よりも先に知った長女ベティは,そのロマンティックなアイデアに興奮しながら,なぜ父親にはっきりとダンス・レッスンに行きたいと伝えないのか,と問うのだが,マーガレットは,マートルが自分にしたように,「夫たちが勝手に自分で思いついたと思い込ませる」のが「賢い妻」なのだと「レクチャー」する。 ただし,このエピソードでは,「賢い」演出家としての母親/妻の姿だけが描かれるのではない。父親/夫が妻の策略に気づいていること,女性という「奇妙な種族」のやり口を理解していることがはっきりと描かれてもいる。もちろん,現代のわたしたちから見ればそこにジムの性差別的な女性観が見てとれるのは明らかだが,このエピソードで注目したいのは,夫婦間のコミュニケーションすらも演技や演出によって支えらるものだという家族の描き方である。それが明確にあらわれているのがこのエピソードのエンディングである。 そこではマーガレットの演出は先述のエピソードのようには上手くいかず,マーガレットは一人でダンス・レッスンに,ジムはメンズ・クラブに行くことになる。しかし,二人はそれぞれの場所で楽しむことができずに早々と帰宅する。そして,マーガレットよりも一足遅く帰ったジムは,反省したのかマーガレットを元気づけようと一芝居打つことにする。ジムは,学生時代にそうしたようにバンジョーを奏でて,二階の寝室にいるマーガレットをダンスに誘う。ジムの演出にうたれたマーガレットは涙を浮かべ,ジムと月夜の下でダンスを踊ろうと階段を駆け下りる。一足先にジムのもとに集まっていた子どもたちのせいでロマンティックなダンスは御破算になってしまうのだが,ここでは,ジムの一見バカバカしい演出/演技こそが夫婦の関係を修復しているのだ。 リン・スピーゲル(Lynn Spigel)は,第二次世界大戦後のアメリカにおいて,住宅がしばしば「劇場(theatre)」の比喩を用いて語られていたと指摘するが,『パパはなんでも知っている』が描く家族とは,まさに「劇場」のような住宅の中で演じられるものにほかならな い13。そして,その「劇場」で上演されるのはシットコムであり,当時,テレビで放送されるシットコムに付きものであったのがラフ・トラック(laugh track)と呼ばれる後から付加される笑い声の音声トラックだった。 スタジオでシットコムを収録した際の観覧者の笑い声を強めたり整音することからはじまったとされるラフ・トラックは,当時の製作者にとってはかならずしもはじめから歓迎されたわけではなかった。そもそもはテレビ受像機の前の視聴者にスタジオで観覧しているかのような擬似体験を味わってもらおうという意図ではじまりながら,音量を大きくしたり,あまり必要のないところに付け加えるなど,徐々にエスカレートしていく傾向に抵抗した製作者たちは,「本当らしさ」を保持するために,実際のスタジオ観覧者(がいた場合)が笑った箇所や,試写をしたときに見た人が笑った箇所だけにしか,後から笑いを付けさせないように努力したという(Leibman 61-62)。 自然なものであれ,強調されたものであれ,ラフ・トラックは,ドラマの見方を視聴者に教えてくれた。つまりラフ・トラックが番組をコメディとして見るよう方向付けたのだ。ニーナ・C・ライブマン(Nina C Leibman)はこう言っている。「笑い声の音声トラックが
103知らなすぎた男
おそらくテレビのファミリー・メロドラマに影響をあたえるもっとも有力な技術的要因だった。ラフ・トラックが,これらのシリアスな番組がまとっていた見せかけのユーモラスさを保っていたのだ」(63)。つまり,番組がはからずもふれてしまうシリアスな問題を視聴者がそのままシリアスに見てしまう可能性を,ラフ・トラックが封じていたのだ。ライブマンはラフ・トラックの特徴と機能を次のようにまとめる。
明らかに悲劇的な題材に焦点化したテレビ番組の脚本ですら,ふざけた不適切な笑い声の音声トラックによって,構造的に影響を受けた。家を失った若者や家出人(逃亡者),離婚や,青年期の不安や不信感,子どもに無関心すぎる父親や暴力を振るう父親などを扱ったストーリー これらすべてがかなりの数のテレビ番組のエピソードで問題にされていた は,こうした笑い声によって,パロディや嘲笑の対象という印象を与えた。なぜなら,視聴者は絶えずこうした題材を「ユーモア」として受け取るように促されていたからだ。テレビ番組に付加される笑い声の音声トラックは,こうして,悲しみや哀れみといった当たり前の感情を抱くことを思いとどまらせるよう仕組まれた,説得力のある「しるし」として機能していた。登場人物がそうした感情を経験するときですら,視聴者は優越者としてのシニカルなスタンスを取り,くだらない冗談としてそれをあざ笑うよう促されていた。(63)
ラフ・トラックの笑い声は,「ふざけた不適切な」ものにほかならないが,その笑い声によって「悲劇的な題材」すら「パロディや嘲笑」,「ユーモア」の対象へと変えてしまい,視聴者が「悲しみや哀れみといった当たり前の感情を抱くことを思いとどまらせ」ることができるのならば,『いつも明日がある』においてクリフがおかれた状況すら,ラフ・トラックさえあれば,「パロディや嘲笑」,「ユーモア」の対象へと変わってしまうのだろうか? 『いつも明日がある』の中でクリフは,自分のおかれた状況について,自分がお金を稼いでくるだけの玩具の「ロボット」のようであるとか,「自分で作った墓石に閉じ込められているかのよう(I were trapped in a tomb of my own making)」だと語る14。こうしたクリフの叫びがこの作品の中で悲痛なものであるのは疑いないが,この作品の外に目を向ければ,同じような言葉は,『パパは何でも知っている』のジムからも聞くことができる。 家族に縛られたジムとマーガレットの姿を描くシーズン1のエピソード9「2回めのハネムーン」("Second Honeymoon" 1954年11月28日放送)の冒頭で,そうした言葉がジムによって口にされる。ジムは,久しぶりに妻と二人きりで週末に小旅行に出かけようと思い立つ(ジムはオフィスからマーガレットに何度か電話するが繋がらない)。早々に仕事を切り上げて家に帰ったジムはその計画を話すのだが,マーガレットは子供たちを置いて出かけることは無理だろう,と提案を喜びながらも躊躇する。ジムはここで,子どもたちのせいで身動きが取れなくなるなら「牢獄(jail)」にいるようなものではないか,口にする。実際,二人がそのプランを子供たちに話そうとしても,子供たちは,はじめ,自分の都合を話すばかりで耳を傾けようとしない。(こうした展開は,『いつも明日がある』の冒頭に類似している。)けれども,あらたまって子供たちに夫婦二人きりでの小旅行のプランを話すと,存外子供たちはみな賛成で,とくに長女ベティはロマンティックなプランに感激して積極的に後押しを
104
してくれさえする。 結果,ジムとマーガレットは週末の間だけ子どもたちからの「自由」を手にするのだが,その「自由」を謳歌することはすることはできない。車で家を出て早々,二人は子供たちのことが気になり出し,なんらロマンティックな気分になることはできず,郊外のロッジに到着しても子供たちが気にかかり,リラックスすることもロマンティックな気分になることもできず,様子を訊こうと家に電話をかける。一方,家では,子どもたちがとくに寂しがるでもなくリラックスしている最中で,しつこくかかってくるボーイフレンドからの電話に嫌気がさしていた長女は電話に出ようとせず,そうした状況を知らないジムとマーガレットは急に心配が募り,慌てて家へと引き返すことになってしまう。 最終的に家族そろってロッジで週末を過ごすということでこのエピソードは「ハッピー・エンド」を迎える。ここでは,「牢獄」である家の外では生きていけない「囚人」としての親の姿が,「主人」である子どもたちなしでは生きていくことのできない「奴隷」としての親の姿が,哀れに描かれているのだが,もちろんそれは,ラフ・トラックの力も借りながら,終始コミカルに描かれることになる。 前節で見たように,『いつも明日がある』はディープ・スペースを用いたり,ミザンセンに雄弁に語らせるなど,同時代のテレビのシットコムと比較すれば明らかに映画的な表現スタイルが用いられているし,「陽光あふれるカリフォルニア」を舞台としながら影を強調した照明は,クリフの苦悩をより深刻に描き出している。しかし,先にも述べたようにこの作品は,「一家の大黒柱である父親が,昔の同僚と再会し不倫関係に陥りそうになるが一歩手前で踏みとどまるハッピー・エンドの物語」と要約できるし,より作品に即すならば,「一家の大黒柱である父親が,昔の同僚と再会し,子どもたちは二人の関係を邪推するが,最終的には二人の間には(ほとんど)何もなかったことがわかるハッピー・エンドの物語」とも要約できるだろう。こう要約すれば,『いつも明日がある』が描く世界と『パパは何でも知っている』が描く世界が非常に似通っていることが見えて来るだろう。だから,『いつも明日がある』の冒頭やエンディングにはラフ・トラックが付加されたとしてもそれほど違和感がないだろう15。言い換えるなら,『パパは何でも知っている』と同様の題材を映画で描いたのが『いつも明日がある』であり,この作品は,『パパは何でも知っている』(を代表とする郊外に暮らす家庭を舞台とする同時代のシットコム)のパロディなのだ16。 『いつも明日がある』が『パパは何でも知っている』のパロディであるならば,パロディ矛先は,つまり,そもそもの笑いの対象とされているのは,『パパは何でも知っている』の楽天性だろう。一方で,両者の類似性から,『いつも明日がある』で軽んじられる父親を見て観客が笑ってしまうのも不思議ではない。しかし,両者の関係を考慮するなら,その笑いは思いのほか真剣にとらえなおされなくてはならないのではないか。言い換えるなら,『いつも明日がある』は,ラフ・トラックが付加されたシットコムとは異なり,「悲しみや哀れみといった当たり前の感情を抱くことを思いとどまらせるよう仕組まれた」作品ではないし,「登場人物がそうした感情を経験するときですら,視聴者は優越者としてのシニカルなスタンスを取り,くだらない冗談としてそれをあざ笑うよう促されて」いる作品でもないということである。
105知らなすぎた男
おわりに
本論の冒頭で,わたしは,2008年の日本でのダグラス・サークの特集上映で,『悲しみは空の彼方に』と『いつも明日がある』の上映の際に起こった笑いへの違和感を述べた。本稿では考察できなかった前者については措くとしても,少なくとも後者の上映の際に起こった笑いについては,以上の考察からも,不適切なものだったとは必ずしも言い切れないだろう。しかし,それを見てわたしたちが「優越者としてのシニカルなスタンス」からしか笑うことができていなかったのならば,笑っているわたしたちの方がむしろ作品から笑われるかもしれない。 メロドラマにおいては,シニカルな笑いを誘うのも,涙を誘うのも,登場人物との「距離」であり,登場人物よりもより多くを知り,状況を精確に理解する観客の認識の優越性である17。しかし,すでに見たように,『いつも明日がある』で主人公のクリフは,最終的に,ノーマやマリオンの「レクチャー」を通して,自分自身が置かれた状況を精確に理解し,たとえそれが彼にとって絶望を感じさせるものだとしても,家庭を捨てないという決断をしたと言える。あるいは,クリフは自分自身が置かれた状況を精確に理解したがゆえに決定不能に陥り,現状に留まった,と言った方がより精確かもしれない。いずれにしても,『いつも明日がある』が「アンハッピーなハッピー・エンド」だということを,クリフは理解しているのだ。そのようなクリフを観客が笑うならば,それは「アンハッピーなハッピー・エンド」という「ガッツが必要」な状況18を生き続けることの意味を問うことなしに,みずからの優越性を守ることにほかならないだろう。(そして,そのような笑いの機能にあらためて着目したとき、『いつも明日がある』と同時代のシットコムの楽天性の意味すら再考を迫られることになるだろう。)作品をそれがもともと作られ見られた時代に埋め直すことを通してはじめて,優れたメロドラマ作家の作品という決まりきった評価枠から多少なりとも距離を取り,同時代には真剣に取扱われることのなかった作品が投げかける問いに,笑いと涙と共に向き合うことができるのではないだろうか。
参考文献
Basinger, Jeannie. (1977 [2005]). "The Lure of Gilded Cage: All I Desire and There's Always Tomorrow." Bright Lights Film Journal 2 [48]. <http://www.brightlightsfilm.com/48/sirklure.htm>.
Cohan, Steven. (1997). Masked Men: Masculinity and the Movies in the Fifties. Indiana University Press.Crowther, Bosley. (1956). "Screen: Domestic Tale; Palace Has 'There's Always Tomorrow'" New York
Times. January 21, 1956.Danks, Adriean. (2005). "'The Far Side of Paradise': Douglas Sirk's There's Always Tomorrow." Senses of
Cinema: Cinémathèque Annotations on Film, Issue 37 <http://sensesofcinema.com/2005/cteq/theres_always_tomorrow/>
ダイアー,リチャード.(2006).『映画スターの〈リアリティ〉 拡散する「自己」』青土社.Evans, Sara M. (1997) Born for Liberty: A History of Women in America. Free Press.Fujiwara, Chris. (2008). "Tears Without Laughter: Deciphering Audience Responses to Douglas Sirk, in the
106
U.S. and Japan" Moving Image Source. Aurust 8, 2008 <http://www.movingimagesource.us/articles/tears-without-laughter-20080818>.
Harvey, James. (2002). Movie Love in the Fifties. Da Capo.Haralovich, Mary Beth. (1990). "All that Heaven Allows: Color, Narrative Space, and Melodrama." Peter
Lehman, ed. Close Viewings: An Anthology of New Film Criticism. Florida State University PressHaskell, Molly. (1987). From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies. 2nd ed.
University of Chicago Press.Klinger, Barbara. (1994). Melodrama and Meaning: History, Culture and the Films of Douglas Sirk. Indiana
University Press.Halberstam, David. (1993). The Fifties. Fawcett.飯岡詩朗.(2007).「黒人観客とメロドラマ的想像力」小林憲二編『変容するアメリカ研究のいま
文学・表象・文化をめぐって』彩流社.ハリデイ,ジョン編.(2006).『サーク・オン・サーク』INFASパブリケーションズ.Klevan, Andrew (2005) Film Performance: From Achievement to Appreciation. Wallflower Press.Leibman, Nina C. (1995). Living Room Lectures: The Fifties Family in Film and Television. University of
Texas Press.Lawrence, Amy. (1999). "Trapped in a Tomb of Their Own Making: Max Ophuls's The Reckless Moment
and Douglas Sirk's There's Always Tomorrow." Film Criticism 23.Mercer, John, and Martin Shingler. (2004). Melodrama: Genre, Style Sesibility. Wallflower Press.Neale, Steve. (1986). "Melodrama and Tears." Screen 27.Pomerance, Murray (2005) American Cinema of the 1950s: Themes and Variations. Rutgers University
Press.シュミット,D[聞き手].(1986).「私のメロドラマはゆらぎはじめたモラリティについての映画
です ダグラス・サークは語る」『季刊 リュミエール』3Spigel, Lynn. (1997). "From Theatre to Space Ship: Metaphors of Suburban Domesticity in Post War
America." Roger Silverstone, ed. Visions of Suburbia. Routledge.Stern, Jane, and Michael Stern. (1977 [2005]) "Two Weeks in Another Town: Interview with Douglas Sirk."
Bright Lights Film Journal 2 [48]. <http://www.brightlightsfilm.com/48/sirkinterview.htm>.Wayne, Jane Ellen. (2009) The Life and Loves of Barbara Stanwyck. JR Books.Williams, Linda (1998). "Melodrama Revised." Nick Brown, ed. Refiguring American Film Genres: History
and Theory. University California Press.Wegner, Hart. (1982). "Melodrama as Tragic Rondo: Douglas Sirk's Written on the Wind." Literature/Film
Quarterly 10.Wellemen, Paul. (1971 [1991]). "Distanciation and Douglas Sirk." Lucy Fischer, ed. Imitation of Life:
Douglas Sirk, Director. Rutgers University Press.Richard Yates. (1960 [2008]). Revolutionary Road. Kindle edition. Vintage.
107知らなすぎた男
付記:本稿は日本映像学会第35回大会(2009年5月30日・日本大学芸術学部)で行った口頭発表「「家庭」にはもう明日はない ダグラス・サーク『いつも明日がある』における知らなすぎた男」を土台としている。
註1 Yates, Revolutionavy Road, Ch.5より。2 KlingerのCh.5を参照。フジワラの言うキャンプ的笑いに留まらず,サーク作品の現代の観客による受容に着いては,Klingerのマス・キャンプをめぐる議論が有益である。
3 KlingerのCh.2を参照。4 一方で,『いつも明日がある』公開時のポスターやロビーカードは,この作品が「大人向け」のドラマであることを強く臭わせるものとなっており,実際には存在しない水着姿でのクリフとノーマの抱擁が描かれていたり,二人の関係に疑いの目を向けるマリオンや,二人から目を逸らすマリオンの姿が同一の画面内に描かれていたりしている。
5 Basingerを参照。Basingerは『私の望みすべて』(All I Desire, 1953)と『いつも明日がある』を,「典型的なサーク映画」(typical Sirk film)だと述べている。
6 ヴィニー役のウィリアム・レイノルズは,『いつも明日がある』の一つ前のサーク作品『天が許し給うものすべて』で,主人公のケアリー(ジェーン・ワイマン)の心情を顧慮しない息子ネッドを演じている。
7 Basingerもこの場面での燭台の役割に言及している。8 Eurika Entertainmentが2010年に発売した『いつも明日がある』のDVDに特典として収録されたdialogue and continuity script(pdf版)を参照。
9 ダイアーを参照。もちろん同様のことが,ノーマを演じたスタンウィックにも,クリフを演じたマクマレーにも言える。また両者はロマンスのRemember the Night(1940),「フィルム・ノワール」の『深夜の告白』(Double Indemnity, 1944),西部劇のThe Moonlighter(1953)で共演している。そのため,『いつも明日がある』で二人が過去を思い返す際,観客はこれらの作品での二人を思い返すかもしれない。
10 庭から窓越しに家の中を覗くここでのクリフの行為は,作品を超え,スタンウィック主演のサーク作品『わたしの願い』(All I Desire, 1953) の冒頭でのスタンウィック演じるネオミの行為を反復している。11 Sternを参照。同じインタヴューのなかで,サークは,『いつも明日がある』でクリフが置かれた状況を「不可能な(耐え難い)状況(an impossible situation)」と述べている。『わたしの願い』の結末も同様に「アンハッピーなハッピー・エンド」と言えるだろう。原作とは異なるこの作品の「ハッピー・エンド」は,プロデューサーのロス・ハンターに求められたものだとサークは述べており,この「ハッピー・エンド」への不満を隠さないが(ハリデイ 174),ネオミが人気も衰え疲れ果てた女優業を捨て安らぎ求め家庭に留まる(帰る)というこの作品の結末が「ハッピー」か「アンハッピー」かは,容易に決定できない(Callahan 182も参照)。同様の「アンハッピーなハッピー・エンド」は,フリッツ・ラング監督によるスタンウィックの主演作『クラッシュ・バイ・ナイト』(Clash by Night, 1952) にも見られる。
12 クラシック映画の専門チャンネルTurner Classic Movieが提供する,American Film Institute編纂のデータベースにおける『いつも明日がある』のNotesの記述よれば,Hollywood Reporter誌の1954年9月号にそのような記事があったという。また,作品は異なるが,『わたしの願い』では,スタンウィック演じる主人公ネオミの末息子テッドを,「パパは何でも知っている」で長男バドを演じるビリー・グレイが演じている。 <http://www.tcm.com/tcmdb/title/92777/There-s-Always-Tomorrow/notes.html>
13 スピーゲルは,家庭生活は役割演技であり,家族の構成員がすべてパフォーマーであるという見方が,1950年代には社会学者の言説でしばしば見られることを指摘した上で,そうした見方を大衆化したのが当時のテレビで人気のあった郊外に暮らす家庭を舞台とするシットコムだと論じている。ただし,スピーゲルが挙げているのは,「パパは何でも知っている」ではなく,より家庭生活の「劇場性 (theatricality)」が前景化するセレブリティの夫婦を描く「アイ・ラブ・ルーシー」(I Love Lucy, 1951-1957) や「オジーとハリエットの冒険」(The Adventures of Ozzie and Harriet, 1952-1966) である。Halberstam の Ch. 15, Ch. 34も参照。
14 Lawrenceはこのクリフの台詞を自身の『いつも明日がある』論のタイトルに用いている。15 日本映像学会第35回大会(2009年5月30日・日本大学芸術学部)で行った口頭発表「「家庭」にはもう明
108
日はない ダグラス・サーク『いつも明日がある』における知らなすぎた男」の中で,試みに『いつも明日がある』の冒頭とエンディングにラフ・トラックを付加した映像を呈示した。発表の主旨はキャンプ的な受容を再考し,それをむしろ批判するものではあったが,その映像をキャンプ的なお遊びやサークへの冒涜として否定的に受けとめる聴衆も少なからずいたようである。
16 本稿は,『いつも明日がある』の父親役に『パパは何でも知っている』の父親役を演じたロバート・ヤングのキャスティングが検討されていたという事実と,家族構成の類似性や物語が父親に焦点化されている点に特に注目し,『いつも明日がある』と『パパは何でも知っている』との類似性や関連性を議論しているが,『いつも明日がある』の製作年よりも前に放送が始まっていた同じような設定のシットコムであるThe Adventures of Ozzie and Harriet(1952 1964)Make Room for Daddy(1953 1964)との類似性や関連性については,あらためて検討しなければならないだろう。
17 Neal, Williams, 飯岡を参照。18 スタンウィックは「ガッツのある役が好み」だと述べている。Wayne 135 を参照。
キーワード:ダグラス・サーク;『いつも明日がある』;「パパは何でも知っている」; メロドラマ; ホームドラマ; シットコム; 映画; テレビ; ハリウッド;Sirk, Douglas; There's Always Tomorrow (Film); Father Knows Best (TV program); melodrama; family sitcom; motion pictures; television; Hollywood
(2012年10月31日受理,12月4日掲載承認)
![Page 1: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: 知らなすぎた男 : ダグラス・サーク『いつも明日がある』と笑い [The Man Who Knew Too Little: Laughter Buried in Douglas Sirk’s There’s Always Tomorrow]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023042013/633336a89d8fc1106803b223/html5/thumbnails/23.jpg)


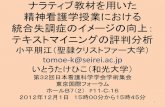
![『伽馱金剛真言』について (On the Gatuo jingang zhenyan [*Vajragāndhārī-mantra])](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63447f4303a48733920aeac1/-on-the-gatuo-jingang-zhenyan-vajragandhari-mantra.jpg)

















