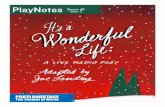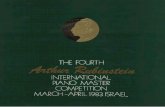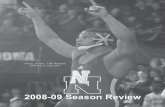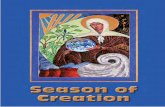Preliminary Report for the Archaeological Survey in Kayseri Province, Turkey (KAYAP), Fourth Season...
Transcript of Preliminary Report for the Archaeological Survey in Kayseri Province, Turkey (KAYAP), Fourth Season...
1Bulletin of the Okayama Orient Museum Vol. 26 pp. 15-29 2012岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 15-29 頁 2012 年
トルコ共和国カイセリ県遺跡調査プロジェクト(KAYAP)第4次調査(2011 年)概報
紺谷 亮一 1、須藤 寛史 2、山口 雄治 3、早川 裕弌 4
フィクリ・クラックオウル 5、クトゥル・エムレ 6
Preliminary Report for the Archaeological Surveyin Kayseri Province, Turkey (KAYAP), Fourth Season (2011)
Ryoichi KONTANI1, Hiroshi SUDO2, Yuji YAMAGUCHI3,Yuichi S. HAYAKAWA4, Fikri KULAKOĞLU5, and Kutlu EMRE2
KAYAP (Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi) started its archaeological survey in Kayseri province since 2008. During the third season, since August to September 2010, we visited and recorded 33 sites. Consequently, KAYAP have registered 66 archaeological sites, historical monuments, and related places in the three seasons 2008-10. Provisional analysis of the data we collected shows the clear change between Chalcolithic period and Early Bronze Age in the term of site number and location in each period. After the EBA, site number increased abruptly, and the sites tended to be located at lower and gentler-slope places. The area surveyed by KAYAP still restricted in western half of Kayseri province at the end of the third season. In the future seasons, we will survey rest of the area, and examine the provisional result above.
1 ノートルダム清心女子大学 Notre Dame Seishin University2 岡山市立オリエント美術館 Okayama Orient Museum3 同志社大学 Doshisha University4 東京大学 The University of Tokyo5 アンカラ大学 Ankara University6 元アンカラ大学 ex-Professor Ankara University
はじめに
筆者らは 2008 年度より、トルコ共和国カイセリ県における考古遺跡調査プロジェ ク ト(KAYAP, KayseriArkeolojik Yüzey Araştırması Projesi)をスタートさせ、今回報告する 2011 年度調査で4シーズン目を迎えた。本プロジェクトの目的は、カイセリ県内にある考古遺跡の網羅的かつ体系的遺跡情報の構築、整備にある。すなわち、踏査による遺跡表面調査から取得した考古資料や地理情報を、GIS(地理情報システム)を基盤と
してデータベース化することである。このような情報基盤を構築した上で、最終的には中央アナトリアにおける人類の居住史について、多角的な側面から再構築することを目指している。 調査対象地であるカイセリ県には、前期青銅器時代からローマ時代にいたるまで栄えた古代都市、キュルテペ遺跡(古代カニシュ)が位置している。前2千年期初頭には現在のイラク北部のアッシリアから多数の商人が移り住み、西アジア全域に及ぶ交易活動の拠点となったこの遺跡の調査成果は、アナトリアにおいて他の追随を許さないほどに古代西ア
2 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
ジア史の理解に大きな貢献を果たしている。しかしながら、その周辺域つまりカイセリ県下の考古遺跡の様相は、まだ十分把握されていないのが実態である。従って、本プロジェクトによるデータベースの構築は中央アナトリアという地域史的枠組みを飛び越え、キュルテペ遺跡のより深い理解と、そこから派生する古代西アジア史全体の理解に資することができると考えている。 結論への過程は未だ模索中ではあるものの、調査も4シーズン目を迎え、記録した遺跡数は 85 件(図1)にのぼる。2011 年度の調査では、先史・古代遺跡の他に、遊牧民ユルックのものと思われる夏営地跡も訪れることができた。また、新たな都市遺跡を記録することもできた。本稿では、これらの概要を報告し、いくつかの所見について述べたい。
1.2011 年度の踏査遺跡
2011 年度における KAYAPの調査では、カイセリ県東部のサルズ地域、エルジェイズ山南部のデヴェリ地域を主要調査域として設定し、8月 24日~9月9日にかけて行った。テル遺跡 13件、遺物散布地6件、トゥムルス2件の合計 21件の遺跡を調査・記録した。本節では、これらの遺跡の概要について報告する。 なお、サルズ・デヴェリ両地域を含むカイセリ県東南部では、既にS.ギュネリやS.ギルギネルによって踏査の報告がなされている(Güneri 2005; Girginer 2007)。本年度の KAYAP では、これらをトレースしつつ、新規の遺跡を発見、記録することに努めた。
KAYAP11-01 ホルギュッチル・ホユック(Hörgüçlü Höyük 図2、3) プナルバシュ郡エルマル村の北西 2.5㎞に位置する(N38°35’22.22/E36°14’60”)。谷に面した急峻な崖錐(talus)斜面において、
谷に沿った形で東西 200 m×南北 60 mの範囲に遺物が散布している状況を確認した。標高は 1,540 mを測る。崖錐にはいくつかの盗掘抗が見られ、その中の一部には石列(住居跡?)が確認された。さらに別の盗掘抗では人骨も散布していたが、その時期については不明といわざるを得ない。表採資料としては銅石器時代もしくは前期青銅器時代Ⅰ期の土器片を主体とし、少数ではあるが鉄器時代の土器片、黒曜石片が確認された。現在、この場所はクロム鉱産出地として活用されている。本遺跡は、当該期の一時的な居住痕跡である可能性が高い。KAYAP12-02 セリン・スリトゥ
(Senir Sırtı 図4、5) メリクガジィ郡ヒサルジュク地区に位置する(N38°37’55.52/E35°31’13.58”)。ヒサルジュクから東約 0.5㎞、幹線道路より比高差約 100 mの自然岩盤上において、東西100 m×南北 180 mに遺物が散布している状況と、一部住居跡ないし工房跡と考えられる矩形石列遺構を数棟確認した。標高は1,559 mを測る。確認した遺跡範囲は建設に伴って大きく撹乱されており、本遺跡がテル状であったのかについては不明である。表採資料としては前期青銅器時代の土器片が多く採集されている。 この自然岩盤は 250 万年前のエルジエス山の火砕流堆積物で形成されており、その斜面には人為的な洞窟のようなものがいくつも見られた。これら洞窟内部の外面表部には黒色の煤状を呈するヘマタイトが付着していることを、地理学者の同行のもとに確認した。ヘマタイトには、少なくとも成分上は錫の成分も含有されているため、本遺跡が当該期の青銅生産に関わっていた可能性も考えられる。これまでカイセリ近郊において錫が存在したとの報告は皆無であり、本遺跡は古代青銅生産へ大きな問題提起を発するものとなり得るものであるが、今後掘削された錫の推定
3KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
量や化学分析などを行っていく必要があるだろう。KAYAP12-03 キルキオレン・ホユック
(Kirkören Höyük 図6、7) トマルザ郡の中心から北約 3.5㎞に位置する(N38°28’53.32/E35°48’9.09”)。本遺跡は、標高 1,414 mの玄武岩溶岩台地上に立地し、東西 200 m×南北 180 m×比高8mを測る円形のテル遺跡である。テル頂上部には極めて深い盗掘抗があり、文化層は少なくとも5m以上に達していることがわかる。他に、十字架が彫られた玄武岩製の石版(●×●m)を確認した。また、テルの裾野には石組み井戸があり、周辺を酒船石のような石版が囲んでいる。村人によれば、これはアルメニア人によるものであるという情報を得た。表採資料として前期青銅器時代、アッシリア・コロニー時代、鉄器時代、ローマ、ビザンツの土器片が確認された。なお、テル南側にも規模の小さな2つのテルらしき高まりを確認しているが、これらも遺跡の可能性がある。S.ギュネリによって報告されている(Güneri 2005)。KAYAP12-04 ダルデレ・ホユック
(Darıdere Höyük 図8、9) サルズ郡ダルデレ村の南西 3.5㎞、サルズ‐マラシュ幹線道路脇に位置する(N38°26’48.52/E36°28’4.35”)。本遺跡は、標高 1,561 mを測る石灰岩の自然岩盤上(東西 160 m×南北 180 m×比高 12 m)に立地する。頂上部から小川に面した斜面にかけて遺物が散布している状況を確認した。岩盤上の遺物堆積層は非常に薄く、遺跡形状もテル状を呈さないものと考えられる。少数ではあるが、銅石器時代~前期青銅器時代、鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集した。本遺跡はS.ギルギネルによっても報告されている(Girginer 2007)。KAYAP12-05 サルズ・ホユック
(Sarız Höyük 図 10、11)
サルズ郡の中心部に位置する(N38°28’49.12/E36°29’48.8”)。本遺跡は、市街地区内に完全に没しているため、規模、形態等は不明である。しかし、遺物散布範囲は広く高まり状を呈しているため、以前はテル遺跡であったと考えられる。標高は1,580mを測る。遺跡上にある家屋の庭先にはピボット(ドア開閉用の軸石)が放置されていた。前期青銅器時代、アッシリア・コロニー時代、鉄器時代、ビザンチン時代の土器片を採集した。本遺跡はS.ギルギネルによっても報告されている(Girginer 2007)。KAYAP12-06 オレンテペ
(Örentepe 図 12、13) デヴェリ郡の中心部から南東 1.5㎞に位置する(N38°22’5.38/E35°27’36.98”)。本遺跡は標高 1,214 mを測る、周辺からも一目でわかる巨大な独立自然丘上(東西 375m×南北 375 m×比高 40m)に形成されている。遺跡南側はスルタンサズルまで続く沖積平地を広く見渡すことができる。遺物はほとんど丘陵頂部に散布していた。丘陵頂部にはテル状の高まりも認識できず、岩盤の露出が目立つため、文化層は非常に薄いと考えられる。また、表採資料としては、少数のビザンチン時代の土器片のみが採集された。従って、本遺跡はテル遺跡とはいえず、丘陵上を利用した一時的な遺跡であると考えられる。S.ギルギネルがイレンテペ(İrentepe)として報告した遺跡である(Girginer 2007)。KAYAP12-07 ビレチ・ホユック1
(Bileç Höyük 1; 図 14、15) デヴェリ郡中心部アイギョズメ地区の南西1.2㎞、デヴェリ−ヤヒヤル幹線道路の脇に位置する(N38°21’14.39/E35°28’1.29”)。標高 1,147 mを測る、西方のスルタンサズルへと続く沖積地上に立地する。本遺跡は東西 55 m×南北 45 mの円形状の立ち上がりの一部が残るのみであり、その内部は完全に破壊されていた。村人によればかつて遺丘で
4 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
あったとされ、オルタヨル(Orta yolu)と呼ばれていたらしい。現在は資材置き場として利用されており、遺物の散布は少量であった。表採資料としては、少数の鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集した。この辺り一帯を Bileçと呼ぶことから、Bileç Höyük 1として記録した。KAYAP12-08 ビレッチ・ホユック2
(Bileç Höyük 2 図 16、17) デヴェリ郡アイギョズメ地区の南西 2.3㎞に位置する(N38°20’44.85/E35°27’27.22”)。本遺跡はビレチ・ホユック1遺跡から南西に 1.2㎞進んだ、標高 1,131 mを測る地点にあり、ほぼ同様の立地を呈する。現在工場の敷地内にあり大きな破壊を受けているが、わずかなテルらしき高まりを形成している。平面規模は不明であるが、周囲との比高差は低くなだらかな印象を受ける。少数ではあるが、前期青銅器時代の土器片を採集した。現地ではアフメットアーテペシ(Ahmet Ağa Tepesi)と呼ばれているが、S.ギルギネルが本遺跡をビレッチ・ホユックとして報告していることを考え(Girginer 2007)、KAYAPではビレチ・ホユック2遺跡として記録した。KAYAP12-09 トゥズラ・タシュラル
(Tuzla Taşıları 図 18、19) サルズ郡クルデレ村の北東 0.5㎞に位置する(N38°20’26.47/E36°24’57.59”)。標高1,506 mを測る自然岩盤の頂部から斜面上にかけて、東西 135 m×南北 80 mの範囲に遺物が散布している状況を確認した。北側には小川が流れ、その比高差は約 23mを測る。この自然岩盤下部の小川付近では遺物の散布は認められない。テルの形状は呈しておらず、堆積層も薄いと考えられる。前出のホルギュッチル・ホユックと同タイプの遺跡といえるだろう。S.ギルギネルの報告によれば銅石器時代の土器片も報告されているが(Girginer2007)、前期青銅器時代の土器片
しか採集できなかった。採集土器片に大きな破片は認められず、他にチップなどを少量採集した。KAYAP12-10 ケメル・ホユック
(Kemer Höyük 図 20、21) サルズ郡ケメル村内に位置する(N38°21’15.24/E36°25’48.8”)。サルズ−マラシュ幹線道路沿いにある。本遺跡は、標高1,514 mを測る岩盤上に形成された東西230m×南北 120 mのテル遺跡である。遺跡北側面には岩盤が露出しており堆積があまり確認されないことから、テルは岩盤の斜面上に形成されている。従って、テルの南側面に主に文化層が堆積していると考えられ、テル頂部から南斜面下端までの比高は10mを測る。サルズ近郊では珍しく完全にテルと断定できる遺跡である。テルの南側面は家屋建造に伴い大きく破壊されている。この断面から判断すると3m以上の文化層の堆積が推測される。前期青銅器時代、アッシリア・コロニー時代、鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集した。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-11 チャウラ・テペシ
(Çağla Tepesi 図 22、23) サルズ郡クルデレ村の北西1㎞に位置する(N38°20’28.09/E36°24’14.62”)。トゥズラ・タシュラルと同じ谷筋にあり、両者は約1㎞しか離れていない。標高 1,503 mを測る急峻な谷の先端頂部において、約 50mの範囲に遺物の散布する状況を確認した。谷下部には小川が流れ、遺跡との比高差は約 27mを測る。同様に頂部には、直径約 30m×高さ 4.6 mを測る円形のトゥムルスも形成されている。この谷筋はタウルス山中へと続いており、かつての抜け道、もしくは移牧ルートとして適当な場所だったのかもしれない。日干しレンガ片、多くの銅石器~前期青銅器時代の土器片、少数のローマ時代の土器片を採集した。一時的なセトルメントと考えられ
5KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
る。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-12 イェシルケント(ヤラック)・ホユック
(Yeşilkent(Yalak) Höyük 図 24、25) サルズ郡イェシルケント地区内に位置する(N38°17’44.4/E36°26’7.68”)。サルズ‐マラシュ幹線道路沿いにある。本遺跡は標高1,535 mの平地部に立地し、東西 85 m×南北 95m×比高 10mを測るテル遺跡である。遺跡の1/3は破壊を受けている。前期青銅器時代、アッシリア・コロニー時代、鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集した。TAYに登録されており(http://www.tayproject.org/)、ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-13 タウラ・ホユック
(Tavla Höyük 図 26、27) サルズ郡タウラ村の北1㎞に位置する(N38°24’31.6”/E36°31’25.64”)。本遺跡は、標高 1,690 mの小盆地状を呈する平地部に立地し、東西 45 m×南北 51 m×比高7mを測る円形のテル遺跡である。テルの周囲5m程にも濃密な遺物の散布が認められるため、耕作によって一部削られているものと考えられる。大量の銅石器~前期青銅器時代の土器片を採集した。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-14 トゥズタシュ・テペ
(Tuztaşı Tepe 図 28、29) サルズ郡アルトソウト村の南東 1.5㎞に位置する(N38°26’25.31/E36°27’40.08”)。標高 1,567 mを測る急峻な谷の先端頂部において、東西 80 m×南北 65 mの範囲に遺物の散布する状況を確認した。谷下部には小川が流れ、遺跡との比高差は約 20mを測る。また、直径 35m×高さ3mを測るトゥムルスが頂部に築かれており、遺跡周辺の状況はチャウラ・テペシに酷似している。前期青銅器時代、鉄器時代の土器片や石器片を採集した。ギルギネルによっても報告されている
(Girginer2007)。KAYAP12-15 デヴェリ・ホユック
(Develi Höyük 図 30、31) サルズ郡ブユックソベチメン村の南西 2.2㎞に位置する(N38°29’30.37/E36°37’45.68”)。本遺跡は、標高 1,848 mの広い谷底平野部に立地し、東西 67 m×南北 145m×比高 11mを測るテル遺跡である。外観はテル状を呈しているが自然岩盤上に形成されており、文化層の堆積は極めて薄いものと考えられる。テル南側には小川が流れている。本遺跡の位置するコジャ・スと呼ばれる涸谷沿いには、僅かな高まりをもつ低丘陵部が連続している。これらはおそらく、テルを形成しない一時的なセトルメントの集合体と考えられる。本遺跡では、前期青銅器時代、鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集した。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-16 フユック
(Hüyük 図 32、33) サルズ郡、ブユックソベチメン村の南西1㎞に位置する(N38°30’24.51/E36°38’33.57”)。デヴェリ・ホユックと同じ谷にあり、約2㎞北東に進んだ標高 1,850 mの低丘陵上に立地する。遺跡北側には泉が湧いている。東西 175 m×南北 150 m×比高 12.5mを測る規模をもつが、テル遺跡ではなく、堆積の薄い遺物散布地として認識した方がよい。特に丘陵頂部から泉のある北側におおく遺物の散布を認めることができた。デヴェリ・ホユックと立地状況が酷似しており、一時的セトルメントの一部と考えられる。鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集したが、それらよりも石器類(主にチップ)の方が多く散布している。KAYAP12-17 アクギュベルジン・ホユック
(Akgüvercin Höyük 図 34、35) サルズ郡クチュックオルトゥル村内にある(N38°31’58.96/E36°43’56.84”)。フユ
6 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
ック遺跡から更に東へ 8.4㎞進んだ谷沿いの極めて急峻な自然岩盤上に立地する。標高は1,750 mを測る。遺跡北側の谷底には小川が流れており、比高は 42mを測る。本遺跡は、東西 45 m×南北 32 m×比高 15 mを測るテル遺跡であるが、テル中腹に自然岩盤の露出が認められることから文化層の堆積は厚くないものと考えられる。従って、これも一時的なセトルメントの可能性がある。ギルギネルはアッシャウ・クチュック・オルトゥル(AşağıKüçükÖrtülüHöyük)という遺跡名で報告しているが(Girginer2007)、KAYAPでは村人の認知する名称を採用した。前期青銅器時代、鉄器時代、ビザンチン時代の土器片を採集した。KAYAP12-18 カラプナル・ホユック
(Karapınar Höyük 図 36、37) サルズ郡カラプナル村の南1㎞に位置する(N38°36’41.36/E36°35’23.87”)。狭い谷が小盆地状に開けた地点、標高 1,764 mを測る丘陵上に立地する。本遺跡は、東西145 m×南北 272 m×比高 26 mを測るテル遺跡である。テル東側下端部には小川が流れている。テル頂部には多くのブロック状の石が散布している。これは遺跡と関連するものかどうかは不明である。テル中腹にも岩盤が露出していることから、文化層の堆積は薄いと考えられる。前期青銅器時代、鉄器時代、ローマ時代の土器片を採集したが、散布状況は極めて希薄であった。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。KAYAP12-19 サルジャ・デヴェ・テペシ
(Sarıca Deve Tepesi 図 38 〜 41) デヴェリ郡サルジャ村の南西1㎞、デヴェリ−ヤヒヤル幹線道路沿いに位置する(N38°36’41.36/E36°35’23.87”)。西方のスルタンサズルへと続く標高 1,098 mの平地端部に立地し、直径 80m×比高8mを測るテル遺跡である。遺跡は大きく撹乱を受けており、特にテル中央部にある大きな盗掘抗からは高
さ1.5m程の石壁が確認できる。銅石器時代、前期青銅器時代、アッシリア・コロニー時代、鉄器時代、フリギュア時代の土器片の他、完形に近い石皿を2点採集した。遺跡規模は小さいながら、ほとんどすべての時期を含む点は特徴的である。ギルギネルによっても報告されている(Girginer2007)。
小 結-サルズ地域の暫定的評価- 本年度の調査では、特にカイセリ県とカフラマンマラシュ県との県境にあるサルズ地域を重点的に踏査した。この地域では 13遺跡を記録できたが、明確なテル遺跡と呼べる遺跡はわずか4遺跡(KAYAP05,10,12,13)であった。他は、テル状を呈していても堆積層の薄さが目立ち、およそ長期の居住期間が想定困難な遺跡と、テルを形成しない散布地という状況であった。これら明確にテル状を呈さない遺跡群はその立地において、丘陵上などに薄い堆積ないし遺物の散布するテル様の遺跡(KAYAP04,15,16,17,18)と急峻な谷地形の尾根上に形成されるもの(KAYAP01,09,11,14)の2群に分けることが可能である。前者は前期青銅器時代を含みつつも鉄器時代やローマ時代など比較的新しい時期であるのに対し、後者は銅石器~前期青銅器時代というほとんど単一に近い時間的なまとまりをもっており、遺跡形態と立地の差異が時間的なものである可能性が高いことを示しているように思われる。 このようなテル状を呈さない遺跡は、遊牧、移牧などに伴う一時的なキャンプ・サイトであると考えるのが、現状では最も妥当な評価であると考える。アナトリアにおける遊牧民ユルックの生活パターンを参考にすれば、前者のテル様の遺跡は季節的なベース・キャンプ地として考えることができるかもしれない。鈴木瑛子の調査によれば、ユルックの冬営地はムラから離れた小高い丘(ホユックやテペと呼ばれる)にキャンプを張るようであ
7KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
り(鈴木1998)、状況としては一致する現象といえるだろう。この鈴木の調査は、より西方のアンタリヤ県の事例であり、また冬営地の状況に関するものであるため安直な比較はもとよりできないが、傾聴に値する。また後者の散布地は、季節移動に伴う一時的なキャンプ地であるかもしれない。ユルックは、キャンプ地の選定に水害、とくに鉄砲水を避けることに重きを置いているという(松原1983 など)。移動経路である谷底ではなく、一段上がった尾根上~斜面に遺物が散布する状況1)は、ユルックの季節移動におけるキャンプ・サイトの立地志向とほとんど同様である。この点は、注目に値するのではないだろうか。 今回記録できた散布地などは大変発見しづらい遺跡であり、その数は実際のところ、相当数に上るであろうことは容易に想像がつく。これは、サルズ地域における所謂典型的なテル遺跡の少なさというものが、今回示した以上に存在比率としては小さなものである可能性も同時に示すものである。この地域は北シリア−ガジィアンテプ−カイセリへと向かう交通路の峠のような役割をはたしている。また、中央アナトリアとは大きく異なり、急峻な谷、多くの緑、豊富な水、高い標高などの特徴から風景も一変する。遺跡としてテル状を呈さない現象が、このようなカイセリ県東部の地勢的条件によるものなのかどうか、現在まで踏査を行ってきた地域を再点検しながら、最終的な評価を行う必要がある。そして、民族考古学的アプローチのための情報収集も積極的に行わなくてはならないだろう。
2.遊牧民ユルックの夏営地
カイセリからサルズへの道中、狭い谷間の微高地上において 300 頭を超える家畜群に交じって建ついくつもの石積遺構を発見
した(N38°32’51.01”/E36°27’9.42”)(図42)。サルズ郡 Yedioluk 村の南 2.5㎞、プナルバシュ−サルズ幹線道路沿いの標高 1,852m付近に位置するそれらの遺構群は、一目見て周辺の村と異なることが理解された。牧夫によれば、この場所はソラクラル・ヤイラス(SolaklarıYayrası)と呼ばれているとのことであった。またコンクリートで作られた給水施設にも「14072004SOLAKLARI」と書かれていることを確認した(図 43)。ヤイラス(Yaylası)とは、トルコ語でトルコ系遊牧民ユルックの夏営地を指す言葉である2)。以上から、ここは比較的最近まで使用されていた3)ユルックの夏営地であるということが推察される。彼らの生活遺構を調査することは、KAYAP 自体の調査目的にも適うものである。また、上で述べてきた先史・古代遊牧、移牧民の活動生態を考察する上でも非常に重要であると判断された。調査期間の関係から簡易調査しかできなかったが、本節ではそれらの概略について述べたい。
(1)遺跡の概要 ソラクラル・ヤイラスは、北東−南西方向に走る構造谷の、谷底から谷壁斜面基部にかけて立地する(図 44)。谷底には谷壁斜面からの渓流に分断された微高地が存在する。石積遺構はその微高地よりも谷壁斜面側、とくに傾斜変換線付近に構築され、岩盤の露出面を遺構の壁体として利用されるものも散見された。石積遺構は現状で計 38 件確認でき、その他にかつて遺構があったと思われる整地跡や矩形を呈した一段組の石列なども複数確認できた4)。前者は(整地跡?)傾斜変換線付近に多く構築されており、後者は(一段組の石列?)微高地上に見られた。石積遺構はそのほとんどが長軸を谷筋と並行させ、遺構3~4件でひとつのまとまりを形成している様子がうかがえる。 石積遺構はすべて現地表面上に構築されて
8 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
いるが、残存状況はそれぞれ異なる。壁体が完存するものから一段だけ残った石列まで様々である。すべての遺構に上屋が確認できないこと、壁体の完存する遺構周辺に崩落石も確認できないことなどから、上屋は革製テントかもしくは植物を葺いたものであったと考えられる。建材は人頭大~拳大までの石材であり、おそらく周辺から採取したものであろう。なお、現在牧夫が使用している建物はコンクリートを使用したものである。遺構プランは矩形・正方形であり長軸5~ 20 m、短軸5~ 10m前後、単室・複室両者存在する。入口はほとんどが長軸方向に設けられていた。建物内部には炉や煙道を設けるものあり、確実に住居として利用されたものがある。遺物はほとんど確認できなかったが、ペットボトルやアルミ製のカンなど近年のものが少量散布している状況であった。
(2)遺構の分類 これらの石積遺構群は、構造、内部施設、残存状況、使用建材などからすべてが同一時期に構築、使用されたものでないことは明らかである。遺構群は、大まかには以下のように分類することができる5)。1類:石積住居をコンクリートでコーティングした上屋をもつ住居。現在、牧夫が使用しているものである(図 45)。2類:矩形プランで複室構造を呈する。石積みによる構築であるが、一部にはコンクリートが使用されている。遺構内部には壇上遺構、炉(コンクリート製)や煙道を備え、最も残存状況が良い(図 46)。3類:矩形プランで複室構造を呈するが、遺構正面、入口の両脇に壇上の施設を伴う。内部施設は見当たらない。比較的残存状態が良く、壁体が高さ1m前後残っている(図47)。4類:矩形・正方形プランで単室・複室両者存在する。内部・外部施設をもたない。残存
状況には幅がある。この遺跡でもっとも多くみられる(図 48)。5類:整地痕跡や一段組の石積みが残るのみである(図 49)。 残存状況が遺構の時期を示すわけでは決してないが、意図的な石抜き住居(図 50)も散見されることから、大局的には残存状況が時間差を示すものであると考えられる。つまり、石材(建材)の再利用による遺構の構築、使用、廃棄のサイクルを繰り返すによって、この場所には 40件以上の遺構が形成されているのである。建材にコンクリートを使用する2類の遺構は、上屋をかければすぐにでも使用できる程状態のいいものであり、現在使用されている1類を除けば、最も新しいものであると判断できよう。3類と4類の前後関係についてはわからない。それは4類にも状態の良いものがあるからである。しかし、1類にも壇上施設が認められることや、総じて3類の残存状態が良いことなどから、3類は4類よりも後出するものと考えるのが妥当であろう。そして4類はむしろ、長期間構築され続けている結果とみるべきである。5類に関しては、これが最も古い遺構であると即断することはできない。すなわち、整地跡はテントをたてた場所かもしれず、一段組の石列などは石が抜き取られた残り部分という他に、テント内への風の侵入を防ぎかつテントの耐久度を高める役割をもった遺構かもしれないからである。これについては別の観点からの検討が必要であるが、例えばテントの柱を立てるためのピットなどは認められなかった。 以上の簡単な検討から、おおよそ4類→3類→2類→1類の変遷が想定設定され、またそれぞれに4類(や5類)が伴う、という状況を考えることが許されよう。これらの数的変化の詳細については、すべての範囲を調査した後に報告することにしたいが、3類は5件前後、2類は1件、1類は2件と想定した
9KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
時期が新しくなるにつれ、減少していくことがわかる。各時期に4類と5類を加えた数が本来の数であろうが、特徴的な遺構の減少はそのまま全体数の減少を少なからず反映したものであろう。 先に想定した変遷がどの程度の時間幅で起こったのか、この遺跡がいつ頃形成されたのか、については現段階で判断できる材料を得ることができなかった。私たちの運転手であるケマル氏に依れば、10 年以上前からこの光景を目にしていたという。2004 年7月に作られたコンクリート製の給水施設の存在は、その時点では使用され、その後も使用する意志のあったことを示すものである。また、2009 年8月に撮影された衛星写真(Googleearth)(図 44)には、現在とほとんど変わらない状況を見ることができる。断片的な情報であるが、少なくともここ 10年は大きな変化が見られないものと考えてよいのかもしれない。また、本遺跡の形成時期についても、遺構内に埋土が厚く溜まっているわけでもないことから1世紀を超えるほど古いものではないと思われる。
(3)遺跡の性格 ユルックの夏営地は、多数のチャドル(山羊の皮製テント)を主体として、少数の石積みの住居や墓群、メスチットと呼ばれるイスラムの礼拝所などで構成されているのが普通である(Cribb1991;鈴木1998;松原1984,1990 など)。石積みの住居群は冬季の狩猟用の小屋であり、秋営地でのキャンプ時に時折夏営地に戻ってくる時の宿泊施設として機能している(鈴木1998)。また、礼拝所も石積みで構築されていることが記録されている(松原1990)。 1980 年に行われたアンタリヤでの松原の調査では(松原1984)、夏営地でのチャドル数は 15 件であり、1960 年以前は 50 以上あったことが報告されている。1960 年前
後という年代は、トルコ政府の遊牧民定住化政策によって多くの遊牧民が定住化した年代であり、以後急速に遊牧民の数が減少していったらしい6)。 このようにみると、本遺跡がユルックの夏営地であるとした場合、石積遺構が多く構築されているという点で他の報告例と大きく異なることがわかる。近年まで利用されていたことも考えると、本遺跡は、最初はユルックの夏営地として利用されていたものが、政府の定住化政策をへて定住化したユルック(定住化遊牧民)が使用し続けていたと考えるのが、最も妥当なものであると思われる。(定住化していない?)遊牧民の利用が続いていた(?)という可能性も考えられるが、その場合石積遺構の多さについての説明が困難になろう。鈴木によれば、定住化遊牧民も以前利用していた夏営地へ移動することが報告されている。その理由は、家畜のため(移牧)や、夏営地を懐かしむ、避暑など様々である。夏季には、ひとつの村の住人すべてが夏営地に行き、村が空になることもあったようである。また、彼らにとって遊牧民時代の夏営地は、集団の部族的結合を認識、維持する機能をもっていることが明らかにされている(鈴木1998)。ただし、その際再びテント生活を送るのか、住居を構築するのかという点についての記述はないため、この想定は推測の域を出るものではない。
以上、ソラクラル・ヤイラスの概要について述べてきた。遺跡の性格については、仮説的に示したが今後詳細な調査が望まれるものである。特に、この地が夏営地であるとすれば、周辺の村が管理しているはずであり7)、その村の特定と聞き取り調査などが必要になるだろう。遺跡の調査においては、石積遺構にのみ着目していたが、遺物の分布状況やテントを取り去った後に残る炉やピットの検出と分布などを押さえておくことも今後行わな
10 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
くてならない。 サルズ地域では、第1章で述べてきたように、テルを形成しない一時的な居住地と思われる遺跡を見つけることができた。こうした散布地に見られる生活パターンは、遊牧民ユルックから類推されることも多いであろう。その意味で、このような遺跡の調査は非常に重要なものである。また、アダナ地方のユルックの夏営地はエルジエス山系にあることが記述されている(松原1991:164)。すなわち、カイセリ県南部のヤヒヤルやデヴェリ地域にもこうした夏営地や散布地に類似した遺跡が多く存在する可能性は極めて高いと考えられる。今後、こうした遺跡の理解促進のためにも、データの充実化、民族考古学的調査を行わなくてはならない。
3.新たな交易都市か−イキテペ遺跡再訪−
イキテペとはトルコ語で「2つの丘」という意味で、実際に大小2つの遺丘が東西に並んでいる(図 52)。カイセリの南西約 40㎞、観光地で有名なカッパドキア地方(ギョレメ、アバノス)のすぐ近くにあり、エルジェイズ山の南西裾野で風光明媚な場所である。遺跡の南には数十年前まで「スルタンサズルー」という湖があり、フラミンゴなどが集まる野鳥の楽園として国立公園に指定され、またラムサール条約湿地にも登録されている。しかし近年の農業用水路などの建設によって湖は干上がり、現在は塩湖のような状態になっている(図 51)。 イキテペ遺跡は 2010 年に KAYAP で一度訪れている。採集された土器片の多くはアッシリア・コロニー時代のものであった。キュルテペ遺跡のカールムⅡ層、Ⅰb層とほぼ併行する時期と考えられる(紺谷他2011)。しかしその後、この遺跡には周壁と思われる石列があるという情報を得たため、今シーズン再度調査した。その結果、地表面に露出し
ている石列を発見した(図 53)。GPS による簡易測量を行ってみると、石列が遺丘を取り囲むように配されていることが分かった(図54)。北部と南部には門らしきものを確認できた。また四角い部屋のようになっている部分もあった。これは「箱型壁」と呼ばれるアッシリア・コロニー時代の都市にみられるものとよく似ており、都市の周壁の可能性がある。 ところでイキテペ遺跡は、2008 年から 2009 年に調査したエイリキョイ遺跡(KAYAP08-12)(紺谷他2010)とは上述のスルタンサズルーを挟んで対岸の位置関係にある。この場所は地中海方面からタウルス山脈を越えて中央アナトリアに至る交通の要所である(図 51)。KAYAP でこれまで踏査した遺跡 85件についてキュルテペ遺跡を起点とする位置関係を分析した。図 55は単純な直線距離、図 56は地表面傾斜を考慮したコスト距離による分布状況である。直線距離では概ね 30~ 60kmの間に遺跡が多く分布する。しかしエイリキョイ遺跡やイキテペ遺跡は約 80km の距離にあり、比較的遠い遺跡群に属することになる(図 55)。ところが地形(傾斜)を考慮したコスト距離に変換すると、エイリキョイ遺跡やイキテペ遺跡のキュルテペ遺跡からの相対距離は縮まり、遺跡の集中する距離帯に属することが分かった。(図56)。コスト距離はアクセスのし易さを数値化したものなので、キュルテペ遺跡からのコスト距離をもとに古代交易ルートの候補を推測することも不可能ではない(図56図矢印)。今後、遺跡の規模や内容とコスト距離の分析から、交易ルートモデルの具体化を試みることが課題である。また、コスト距離が小さいにもかかわらず遺跡がみつからない(キュルテペ遺跡南部など)のはどういうことなのか。今後の遺跡踏査によって再検証していく必要がある。 キュルテペ文書によればアナトリアには十
11KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
数カ所のカールム(アッシリア商人居留区)があったとされる。現段階で地名が確実に同定されているのはボアズキョイ遺跡(ハットゥシャ)、アジェムホユック遺跡(プルシュハンダ)、キュルテペ遺跡(カニシュ)のみである。遺跡の規模や周壁の存在から、イキテペ遺跡はアジェムホユック遺跡とキュルテペ遺跡の間に存在するカールムをもつ交易都市であった可能性がある。もしそうであれば、「アッシリア・コロニー時代の新たな交易都市」を発見したことになる。今後詳細な地形測量と GPR(地中レーダー)探査などを行いたい。
おわりに
4年間の調査により、カイセリ県のほぼ全域を踏査し、全部で 85件の遺跡・史跡を記録した。しかしこれまでの踏査方法は、既知の遺跡を再調査するか、車で移動しながら車中から目についた遺跡らしき丘を調査するというものであった。したがって今回確認したような、テルを形成せず、遺物だけが散布している遺跡や洞窟遺跡の発見は難しく、他にもまだ多数存在すると思われる。ただ、これまでの踏査によりカイセリ県内での各地域の特性が見えてきた。今後はいくつかの重点地域を選択し、徒歩による遺跡の精細な探索、統計的な分析ができるような方法での資料採集、なるべく多くの遺跡での地形測量、高解像度衛星画像や空中写真を用いたリモートセンシングによる調査などを行っていく。 現在注目している地域はキュルテペ遺跡のあるカイセリ平野、カイセリ県南部のヤヒヤル、東部のサルズ地域である。 カイセリ平野ではキュルテペ遺跡の近隣にほとんど遺跡が確認されていない。キュルテペ遺跡周辺はかつて小河川が網の目のように走り、湿地帯となっていたらしい。遺跡が見つからないのは小河川による沖積土により埋
没してしまっているのか、あるいは湿地帯ということでそもそも遺跡が形成されなかったのか。この点を綿密な踏査により確認したい。 ヤヒヤル地域はカイセリから地中海へ抜ける通路となっている。その交通路上にエイリキョイ遺跡やイキテペ遺跡など大規模なテル型遺跡が存在する。また新石器時代の遺跡が確認されるのもこの地域である。ヤヒヤル最南部についてはまだ踏査がおよんでいないので、今後更なる調査が必要な地域である。 最後に今シーズンの重点調査地であった東部のサルズ地域は、シリア方面への交通路となっている。複雑な地形の割には比較的多くの遺跡が存在している。またテルを形成しない小規模な遺跡(キャンプサイト?)も確認できた。この地域で活動する現在の遊牧民の移動パターンと古代遺跡の分布をより詳細に比較・分析できるデータを収集したい。また、シリア、ヨルダン砂漠での先史遊牧民調査の成果との相対化も興味深い点である。サルズ地域の肉(羊肉)、蜂蜜はトルコ国内でも有名である。調査中、500 頭を超える羊をたずさえた遊牧民、養蜂家の姿を度々目撃した。遊牧民が都市に毛皮、羊毛、羊肉を提供する活動が古代にもあったことは想定できる。シリア、ヨルダンのような乾燥地帯を持たないアナトリアでは、その場所は高原地帯、山岳地帯が選択的に採用された。そしてそれは村落、中規模都市、大規模都市という重層的なヒエラルキーを持つメソポタミアとは異なる都市化プロセスがアナトリアにはあったのであろう。これはアナトリアパターンと呼べるかもしれない。 なお来年以降、キュルテペ遺跡における発掘調査に日本隊が参加する計画が現実的なものとなってきた。これまでの踏査で得られたデータとキュルテペ遺跡の発掘により得られたデータを有機的に検討することにより、カイセリ地域における考古学研究に新たな知見をもたらすことができるのではないかと考え
12 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
ている。
註1)ただし、水辺付近の遺物は単に洗い流されている可能性も否定できない。
2)アナトリアに居住するトルコ系遊牧民は、オスマン朝期にはクズル・ウルマック川を堺にして、その東側に住む者はギョチェル=エヴ、トルクメンまたはアシレット、西側に住む者はユルックと総称された(アルジャンル1981)。これらの名称の差異は、東方からの移住時期や集団規模、オスマン朝中央権力との関係などの歴史的・政治的要因によるものである(永田1984)。しかし、東部の遊牧民をユルックと呼称する例も一部には存在し(アルジャンル1981)、また遊牧集団の分裂や移住により両者を厳密に区別することは難しい。例えばアンタリヤを中心に居住したサチカラル・ユルックは、その半数が 18 世紀中頃にアダナ地方に移動した際サチカラル・アシレットとも呼ばれている(松原1991:163)。従って、ここではより一般的と思われるユルックという名称を暫定的に用いることにする。サルズ地域付近を夏営地とする遊牧集団の名称については、より詳細な調査が必要である。
3)この場所を利用していた牧夫は遊牧民ではなく移牧民?であり、犠牲祭で羊を売るために家畜群を太らせに来たとのことであった。ただ、この場所に一定期間寝泊まりし、そのためのコンクリート製の住居をもっていた。その意味で、この場所は現在でも使用されていると言えるが、ユルックがこの場所を現在も使用しているのかどうかについての確たる情報を得ることはできなかった。
4)本年度の調査では、北側 2/3 しか観察、記録することができなかった。そのため、後者の整地跡などの痕跡は今後増加することが予想される。
5)なお、入口や角部の作り方も異なるが、残存状況の関係からこの分類には反映させていない。今後の課題としたい。
6)この過程で、軍警察が冬営地や秋営地のチャドルを襲い、即刻家を建てるように強要する事態も起こった。その際、「石づみの壁に葦をならべた屋根をふいて当座をのがれた」という報告もある(松原 1984(下):P176)。ただ、軍警察の去った後には石積住居ではなく住み慣れたチャドル生活に戻っていた(松原1990:246)。イレギュラーではあるが、こうした理由によって石積遺構が構築されることもあるようだ。
7)遊牧民は独自に夏営地を決め勝手に使っているわけではなく、オスマン帝国期以来国家体制に組み入れられた時より様々な税を払わなければならなくなった。夏営地では家畜群の規模に応じた
放牧税を、その土地を行政上管理する村や警察に納めなければならい(例えば松原1984;三沢1989、)。
文献Cribb,Roger 1991 Nomads in Archaeology.
CAMBIDGE.G ü n e r i , A . S e m i h 2 0 0 5 ” O r t a A n a d o l u
Höyükleri1998 Yılı Çalışmaları: Kayseri’de Arkeolojik Keşifler.” Arkeoloji, Anadolu & Avrasya 1
Girginer, K. Serda. et al. 2007 2002-2006 Yılları Kapadokya ve Kilikya Yüzey Araştırmaları: Gerel Bir Değerlendirme. Doğudan yükselen lşık Arkeoloji yazılarl Atatürk Ünıversitesi 50 kuruluş Yıldönümü Arkeoloji Bölümü Armağanl.
鈴木瑛子 1993 「トルコ共和国における遊牧民の社会集団に関する一考察」『日本中東学会年報』13日本中東学会
松原正毅 1984 『遊牧の世界(上・下)』中央公論社
松原正毅 1990 『遊牧民の肖像』角川書店永田雄三 1984 「歴史上の遊牧民−トルコの場合」永田雄三・松原正毅編『イスラム世界の人々3−牧畜民』東洋経済新報社
アルジャンル・イセンビケ(永田雄三訳) 1981 「オスマン帝国におけるアシレトとユリュクとの区別」『東洋學報』62-3・4 東洋文庫三沢伸生 1989 「オスマン朝の検地帳に見える遊牧民− 1560 年付マラティヤ県明細帳の分析−」『アジア・アフリカ言語文化研究』38』東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
紺谷亮一、クトゥル ・エムレ、フィクリ・クラックオウル、津村宏臣 2009 「トルコ共和国カイセリ県における考古的一般調査 2008(プロジェクト名:KAYAP)」『ノートルダム清心女子大学紀要 文化学編』33(1):37-46。
紺谷亮一、クトゥル・エムレ、フィクリ・クラックオウル、須藤寛史、山口雄治、津村宏臣、岸田徹、早川裕弌 2010 「エイリキョイ遺跡における考古地理学的調査−トルコ共和国カイセリ県における一般調査の一成果−」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』24:91-108。
紺谷亮一、クトゥル・エムレ、フィクリ・クラックオウル、須藤寛史、山口雄治、早川裕弌 2011 「トルコ共和国カイセリ県における一般調査(KAYAP)概報−第3次調査(2010 年)と過去3シーズンのまとめ−」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』25:15-29。
Kulakoğlu, F., R. Kontani, H. Tsumura and S. Ezer 2010 “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi (KAYAP): 2008 Yılı Çalısmaları Sonuç
13KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
Raporu.” In 27 Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, pp. 305-317.
Kulakoğlu, F., K. Emre, R. Kontani and S. Ezer 2011 “Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi (KAYAP): 2009 Yılı Çalısmaları Sonuç Raporu.” In 28 Araştırma Sonuçları Toplantısı 3. Cilt, pp. 409-428.
0 50km
HöyükTümülüsDistributionCarvingGraveyardsMonumentsArchaeological stitesothersWatershed boundary
Zamantı
Irmağı
Kültepe
Kayseri
Ercyes
Kızılırmak
11-01 Hörgüçlü Höyük
11-02 Senir Sırtı
11-03 Kirkören 11-04 Darıdere Hoyük11-05 Sarız Höyük
11-06 Örentepe11-07 Bileç Höyük 111-08 Bileç Höyük 2 11-09 Tuzla Taşıları
11-10 Kemer Höyük11-11 Çağla Tepesi
11-12 Yeşilkent (Yalak) Höyük
11-13 Tavla Höyük11-14 Tuztaşı Tepe
11-15 Develi Höyük11-16 Hüyük
11-17 Akgüvercin Höyük
11-18 Karapınar Höyük
11-19 Sarıca Deve Tepesi
10-34 Yahyabey Köyü
10-33 Kuruca
10-32 Uzunkaya Höyük
10-31
10-30 Müşevge
10-29 Kadılar Höyük
10-28 Çardakbaşı10-24-27 Soysallı 1-4
10-20-23 Ikitepe/arası10-19 Toparın Pınar
10-18 Hacafer 210-17 Hacafer 1
10-16 Soğulca Höyük10-14/15 Mahzemın Höyük/yanı
10-13 Saltepesi Hoyuk
10-12 Purağı Derindere10-11 Koyun Aptal Höyük10-10
10-09 Tumba Höyük
10-08 Ağın Çesimesi
10-07 Bünyan Tümülüs
10-06 Kurt Tepesi
10-05 Ekrek Tepe10-04 Zekaltı Höyük
10-03 Bayramın Kalesi
10-02 Çakıllı Pınar
09-19 Dededağı09-18 Çadılkaya
09-17 Çorak Tepe09-16 Taşkuyu Höyük (east)
09-15 Augun Höyük
09-14 Kara Höyük
09-13 Yemliha Höyük
09-12 Dadağı Höyük09-11 Vatan Kilisesi
09-10 Kavaklı Cami
09-09 Taşlık Cami
09-08 Küçük Höyük09-07 Özvatan Kum ocağı
09-06 Hacıbeyli
09-05 Fraktin Yazılı Kaya09-03/04 Fraktin
09-02 Beşik Tepe
09-01 Kızıl Höyük08-14 Yapı
08-13 Ziyaret Tepe
08-12 Eğriköy
08-11 Hacının Tepe08-10 Kürü Hüyük
08-09 Yığma Tepe
08-08 Aptal Ören08-07 Höyük(Çukur)08-06 Kale Höyük
08-05 Safrenti Kale
08-04 Hazarşah
08-03 Sultanhanı Höyük08-02 Yassı Dağı
08-01 Dolma Tepe
図1 KAYAP で調査した遺跡(2008〜 2011年)
20 岡山市立オリエント美術館研究紀要 第 26巻 2012 年
ホデゥル山地
デヴェリオヴァ(スルタンサズルー)
38-52D805
ニーデ方面
D805
カイセリオヴァ
エルジェイズ山
イキテペ遺跡
エイリキョイ遺跡
21KAYAP第4次調査(2011 年) 紺谷・須藤・山口・早川・クラックオウル・エムレ
Kültepe Eğriköyİkitepeİkitepe
KültepeKültepe
İkitepeİkitepe
EğriköyEğriköy
100km100km
50km50km
KızılırmakKızılırmak
EğriköyEğriköy
KızılırmakKızılırmak
İkitepeİkitepe
KültepeKültepe
AcemhöyükAcemhöyük
5
10
15
20
25
30
0500 100 150 200 250 300 350 400 450
Weighed Distance from Kültepe (km)
Num
ber
of s
ites
Kültepe İkitepeİkitepeEğriköy