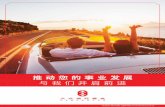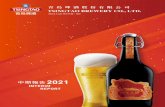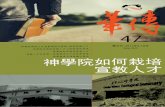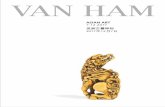Kusumi,Takeo...
Transcript of Kusumi,Takeo...
九州前方後円墳研究会 2006.06.17-18
「土師器から見た前期古墳の編年」 久住 猛雄
(福岡市教育委員会) 1.はじめに (1)土器編年と古墳編年 表1:本稿における編年案(畿内と北部九州の併行関係、前期古墳編年)
・土器編年は当該時期の考古学的編年作業の基本 ※常に資料的に検証の繰り返しが可能。古墳出土土器も例外ではない。 ・古墳出土土器の「保守性」??←都合のいい前提は疑問 (都出比呂志1974←佐原眞の応酬) ・地域出土の土器様相との対比→地域における編年的位置が基本 ・編年作業における土器群の系統的理解の重要性 ※北部九州におけるA・B・C・D系統 ※壺形土器でもB・C・D系統(C系統は精製器種B群系譜も)、山陰系、折衷融合系譜がある ・顕著な「跛行性」の存在 ※福岡平野中枢部と周辺、例えば糸島・唐津地域 ・古墳どうしのみの土器対比は危うい ・地道な併行関係の把握の必要性と方法論 ※土器の搬出・搬入関係が基本。様相対比は危うい面がある。(「布留0式拡散論」) ・墳墓供献特定器種(例えばある種の系統の二重口縁壺)は広域対比も可能 ※東四国系壺形土器など ・広域に類似する変化とその背景 ・壺形埴輪の成立 ※布留2式古相併行の「埴輪化」後、地域的様相が強くなる。 (2)古墳出土土器と古墳の時期 図1(小池香津江2003ほか) ・古墳に「伴う」土器とは? ・周溝出土土器、墳頂出土土器、主体部出土土器、、、、 (3)畿内の古式土師器編年と大和・河内の併行関係 <前提作業> 表2:畿内の古式土師器編年対応関係詳細と併行関係および古墳編年との関係 ・概略的編年 図2(柳本照男1991) ①布留0式 ※辻土壙4下層 図3 ②布留1式古相 ③布留1式中相 ④布留1式新相 ※萱振遺跡(中河内)SE03出土土器(庄内式期Ⅴ=布留1式新相)の評価 図4
⑤布留2式古相 ⑥布留2式新相 ⑦布留3式古相 ⑧布留3式新相 ・大和・河内の併行関係について ※大和型庄内甕と河内型庄内甕の搬出入の検討 図5 ・庄内Ⅲ=庄内3式~布留0式 ・庄内Ⅳ=布留1式前半 ・庄内Ⅴ(布留Ⅰ)=布留1式後半 (4)畿内と各地の併行関係 表3:各地土器編年併行関係表(案)
・山陰と畿内の併行関係 図5・42
・河内の庄内Ⅳ=山陰・草田6期新相(小谷1式) ・畿内と東海地方の併行関係 図6 ※赤塚次郎の案は誤り(豊岡卓之1999、北島大輔2000)。 ・布留0式=廻間Ⅱ- 2・3式 ・布留1式古相=廻間Ⅱ- 4~Ⅲ- 1式 図6・20 ・布留1式新相=廻間Ⅲ- 3式 ・布留2式古相=廻間Ⅲ- 4式 ※平城宮下層SD6030下層の理解(米田敏幸1990、豊岡卓之1999ほか) ※北部九州におけるS字甕の出土 図9 ・河内と吉備の併行関係 図7 ・庄内Ⅲ=Ⅹb期 ・庄内Ⅳ=Ⅹc期 ・庄内Ⅴ(布留Ⅰ)=Ⅹde期 ※「Ⅹde期」(大久保徹也2006)の下限は布留2式古相か ・畿内と北部九州の併行関係 図10 ・ⅠB期=庄内2~3式
※筑前型庄内甕の最古型式の編年的位置 図45 ・ⅡA期=庄内Ⅲ・布留0式 比恵50次/纒向辻土壙4下層・南飛塚周溝下層 ・ⅡB期=布留1式古相 ・ⅡC期=布留1式新相
・山陰地方と北部九州の併行関係 図43・42 ・ⅠB期=草田5期 ・ⅡA期=草田6期古相 ・ⅡB期=草田6期新相・小谷1式 ・ⅡC期(~ⅢA期古相?)=草田7期・小谷2式 ※この関係は確度が高い ・吉備と北部九州の併行関係 図8 ・ⅠB期=Ⅹa期 ・ⅡC期=Ⅹde期前後 ・北部九州と九州各地の併行関係
表4:九州における古式土師器編年対照表・各地併行関係表 ※福岡平野産の筑前型庄内甕・北部九州型布留甕・精製器種B群の搬出の認識(後二者は各地で
基本的に在地生産がされるが優品に搬入品がある場合あり) 2.畿内の主要前期古墳の土器編年における位置 ①箸墓古墳(布留0式) 図11・12 ・二重口縁壺の特徴 図11 ・布留0式前半に築造開始→布留0式後半に築造終了か 図12 (※ここでの「布留0式後半」は寺沢薫の「布留0式新相」ではない。) ②ホケノ山古墳(布留0式) ・加飾二重口縁壺の型式学的位置 図13・14 ※意外に新しい時期に多い ・周濠出土土器 図15 ・主体部落ち込みの小型丸底壺 (類似例 図22) ③布留0式期の他の墳墓 ・葛本弁天塚古墳 図16 ④西殿塚古墳(布留1式古相か) 図17
※二重口縁壺・朝顔型埴輪における頸部接合技法の分類と変遷(廣瀬覚2001参照)
a)壺形土器の場合 b)壺形埴輪の場合 ⑤桜井茶臼山古墳(布留1式古相) 図19 ・古い要素と新しい要素 (置田雅昭1988、野々口陽子1996、広瀬覚2001) a)口縁部 b)頸部 c)胴部~底部
※集落出土の類似二重口縁壺例 図20 ・「造営キャンプ」(城島遺跡外山下田地区)の土器 図21上 ・布留1式古相」段階の設定 図21下
※集落ほか(古墳祭祀以外)出土の二重口縁壺の型式変遷 図22
⑥中河内における墳墓出土壺型土器の変遷(布留0式~布留1式) 図23
⑦メスリ山古墳(布留1式新相) 図24 ・墳頂封土中出土二重口縁壺①の型式 (胎谷古墳 図25に類似) ・小型器種②の型式学的位置
※布留1式新相から布留2式古相の小型丸底壺の変化 図26 ・墳丘出土土器③ ⑧椿井大塚山古墳(布留1式新相) 図27
・布留1式新相から布留2式古相への二重口縁壺の変化 図28 ※山城地域でも布留1式新相段階の土器群(鴨田左京30次SX3041)に二重口縁壺の類例あり(吹田直子2003 「山城Ⅸ期」) ①口縁部端部の拡張、口縁部の回転的なヨコナデ顕著なもの存在 ②頸部が太く内湾エンタシス状に立ち上がり、かつ外傾するものの存在 ③肩部形状は頸部からナデ肩気味に下がる ④頸部接合が曲線鈍角的で鋭角的ではない(頸部接合法が新相か) ⑤胴部内面にヘラケズリがある(畿内型茶臼山式壺では新しい特徴) →桜井茶臼山古墳より明白に新しいと考える。古墳編年の見直し。
・特殊器台・特殊器台・特殊器台型埴輪の変遷と主要古墳の編年 図29・30 (豊岡卓之2000・2003) ※土器編年と一致する ・布留2式古相段階における畿内の壺型埴輪 図31 ※壺形埴輪の確立=多様化 ・東四国(阿波・讃岐)系壺型埴輪の存在 図32 (蔵本晋司2004) ※広域における分布
・円筒埴輪編年(鐘方正樹2003ほか)と土器編年の関係と問題点 図24 ※Ⅰ- 2式からⅠ―3式 図24 ※Ⅰ- 4式からⅡ- 1式・・・布留2式古相が多い(図26・31) →細分に問題か?(形態・技法と時期・系統) ⑨東殿塚古墳(布留1式中相) 図34
※東殿塚古墳と同段階の土器群(辻土壙7) 図35 ⑩西求女塚古墳(布留1式中相) 図36
※山陰系土器群はヨコナデ技法が退化し、小型器種の型式と組成からも東殿塚古墳段階。鏡群での
評価ほどは古くない ⑪元稲荷古墳(布留1式中相) 図37 ※二重口縁壺は埴輪化しはじめた様相。直口広口壺の口縁部は布留1式中相の布留甕と相似的。桜
井茶臼山古墳より新しいと考える。 ⑫東大寺山古墳(布留2式古相) 図26・37 ※石製小型坩は布留2式古相段階を忠実模倣か。直口広口壺の口縁部は布留2式古相の布留甕と相似的。
→円筒埴輪Ⅱ- 1式の一部と布留2式古相が併行。 ※Ⅰ- 4式の寺戸大塚古墳、御旅山古墳も布留2式古相の可能性大。Ⅰ- 5式の平尾城山古墳も
布留2式古相(図26)埴輪3型式段階と布留2式古相が併行??→円筒埴輪は古相と新相の系譜が併行しないのか?(疑問)
<ここまでのまとめ> ・従来の集成1期は布留0式(箸墓ほか)から布留1式新相(椿井大塚山)まで時期幅がある。 ・従来の集成2期は布留1式古相(桜井茶臼山)から布留2式古相(寺戸大塚・平尾城山)まで幅があ
り、「集成1期」と重複する。 ・従来の集成3期の一部は布留2式古相に併行するが(東大寺山)、一部は布留1式新相に位置する(メ
スリ山)。(※他の古墳は一部布留2式新相になる可能性もある。) →従来の前方後円墳集成編年(広瀬和雄 1992)は、その 1期から3期については、解体的に見直しして再編年すべきである。 ※「大賀編年」(大賀克彦2002)について 土器編年との対比では大幅に前後するものが多く、結局のところ鏡とその組成の編年をそのままスライドして基本
としており(1面出土でもそれを基準とするものさえ多い)、問題が多い。鏡以外の個々の型式学的検討を無視して、
例えば滑石製品がその「前Ⅴ期」に一斉に出現する(はずだ)とするなど、実状にあっていない(メスリ山は布留 1式新相である)。円筒埴輪の最近の研究に対しては理解が不足しており(系譜・系統関係を追求しつつある研究の現状
のはずだが)、その編年観を一切無視するなど問題がありすぎる。埴輪について「直接的な系譜関係にない資料群を「型
式学的に」操作するという方法は一般的に無効である」と言うが、その言説そのものは理想論として真であるけれど
も、果たしてそこまで型式学的に追求できる器物がどれほどあるのだろうか?そして一方では、実際には埴輪研究も
系統・系譜を追求している(鐘方正樹2003・2005、広瀬覚2005、豊岡卓之2003、筒井崇史2003など)。 なお次にあげるように、土器編年とは全く整合が無いものが多くある(九州の例)。 「前Ⅰ期」 祇園山(甕棺はⅡC期段階)、五島山(銅鏃からⅡC期以降) 「前Ⅱ期」 藤崎6号(ⅡC期)と津古生掛(ⅡA期)などが同一とされる。 「前Ⅳ期」 向野田(ⅢA期新相~ⅢB期)と異常に古く位置付けられる。 「前Ⅴ期」 卯内尺(ⅢA期古相)と沖出(ⅢB期)が同時期とされる。 同様に、他の地方でもおかしな例が少なくない(例えば先述のメスリ山や。「前Ⅲ期」に桜井茶臼山・椿井大塚山・
寺戸大塚が同時期であるなど)。土器編年が著しく間違っているのでなければ、この編年案に根本的な問題があると考
えられる。 また布留 0式段階には三角縁神獣鏡ないしその関連鏡群が実際は出土しはじめており(藤崎 32次1号墓、津古生掛古墳、権現山51号墳など)、あるいは安満宮山古墳などはその段階と評価できるだろう。「前Ⅰ期」=布留0式が三角縁神獣鏡出現以前とするその説は成立しない。
3.他地域の前期古墳の編年的位置 ①東海地方における前期古墳の編年 図38(赤塚次郎2005) ※併行関係を別にすれば(前述)、スムーズな様相変遷であり、基準となりうる。例えば、波文帯
三角縁神獣鏡が布留 1 式新相に出現など(東之宮古墳)。雪野山古墳は編年上、桜井茶臼山古墳と併行することになり(布留 1 式古相併行)、碧玉製品の出現や大型倭鏡の副葬開始という点でも重
要である。 ②権現山51号墳の編年的位置 図39・40 ※出土土器は、吉備のⅩa期とⅩc期の型式指標の交差するⅩb期の可能性が高い。よく比較され
る萱振SE03とは型式学的ヒアタスがある(口縁部・胴部~底部形態)。 ←Ⅹb期=庄内Ⅲ=布留0式 ※特殊壺からは葛本弁天塚より(図40)、文様からは箸墓より(図29)後出する要素があるが、細
分された時間変遷での比較であり、布留0式の併行幅内で問題ないと考える。 ③神原神社古墳(草田7期=ⅡC期=布留1式新相) 図41 ※集落出土土器による編年の小谷2式(草田7期)であることは動かない(図 42)。北部九州との
併行関係も動かない(=ⅡC期)(図43)。したがって布留1式新相併行である。一部の古相を示すように見える土器や紀年銘鏡という印象、および河内と大和の併行関係の誤解から古くする一部の
立場(藤田憲司 2006など)は誤りである。古墳祭祀に確実に伴う土器群の大部分の編年的位置は明白である。 ※直口広口壺は形態的に北部九州系の可能性があること、赤彩土器群であることが注意される(藤
崎7号墓と共通)。※直口広口壺は形態的に北部九州系の可能性。
4.北部九州の前期古墳の編年的位置と墳墓出土土器 (資料集「北九州- 筑前・肥前北部」も参照)
①那珂八幡古墳(ⅠB期新相) 図44 (資料集27) ・比恵・那珂遺跡群における墳墓出土土器の変遷 図44・46・47 ※比恵 36 次(資料集 26)(ⅠB期古相)よりは新しい可能性があるが、近接する那珂 62 次SX028(資料集28)(ⅡA期)よりは確実に古い。また高坏などに比恵・那珂遺跡群のⅠB期土器群に類似するものがあり(図 45)、やはりⅠB期でよい。二重口縁壺は「B系統」だが、おなじ系統の松木遺跡140街区8号住居(ⅡA期)よりも底部の特徴から古い。比恵6次1号墳(図44下段)と同じ段階の築造であろう。 ※三角縁神獣鏡は第2主体の築造である。これがⅠB期というわけではない。墳頂出土土器は、その掘り方出土のようであるが、本来は中央主体時の墳頂祭祀に伴うものであろう。なお周囲
の直前までの集落(ⅠB期井戸がある)は、在地系多数であり外来系精製土器がたまたま墳頂
に混入するとは考えがたい。 ※ⅡC期からⅢA期古相の二重口縁壺 図47 →卯内尺古墳(ⅢA期古相)の小型壺形埴輪(精製)の特徴に継承(資料集35) ②ⅡA期の初期前方後円墳 ・津古生掛古墳 (筑後の資料集参照)
※葬送祭祀を行った可能性がある近在の87号住居から推定福岡平野産布留系甕出土(図48)→二重口縁壺の型式からも、ⅡA期の築造であると言える(周囲付設墳墓群はⅡB期も含む)。
・須玖御陵古墳 図50 ※住居廃絶直後に同時期の甕棺が埋設される特異な住居の存在(御陵遺跡1号住居)。住居址も、
比恵遺跡群中枢に近い先進的組成+韓半島系含む特異なセット(図50)。津古生掛87号住居と同様に、葬送祭祀の住居か?→須玖御陵古墳はⅡA期の可能性。
③箱崎遺跡・博多遺跡群の墳墓出土土器 図51 ※精製器種B群が展開、山陰系+畿内系の折衷二重口縁壺の成立(ⅡB期)(→ⅡC期に各地に波
及) ④藤崎遺跡の墳墓出土土器 図52・53
※西新町遺跡の集落遺構出土土器相の変遷と類似 ・ⅡA期 在地系+畿内系精製土器・山陰系・畿内系その他(B系統) (※集落よりは外来系多い傾向) ※藤崎32次1号墓(ⅡA期) (資料集21) ・・・・下層に供献土器。藤崎遺跡にある集落土器相は在地系のみ。混入ではない。上層
土器群(ⅢA期新相)は墳墓造営や集落(西新町)がほとんど無い時期。選地的に
も早い時期に墳墓があったはず。 →ⅡA期=布留0式における三角縁神獣鏡の存在証明
・ⅡB期 在地系少数化+畿内系(精製+D系統)+山陰系 (※甕棺には在地系が残る傾向) ※3次7号墓(ⅡB期) ・・・・精製土器群、赤彩土器群。主体部大きく攪乱され不明だが盟主墓か。周溝に珠文
鏡あり。最も早い出土例か。 ・ⅡC期 在地系ほぼ消滅。畿内系(精製+D系統)+山陰系 ※3次6号墓(ⅡC期) (資料集22) ・・・・方形周溝墓ということで古いイメージがあるようだが、やや新しい時期。山陰系
二重口縁甕は神原神社古墳と同段階(小谷2式併行)。 ・ⅢA期古相 墳墓造営が衰退か ⑤糟屋平野の上位首長墓と福岡平野中枢産土器 図54 ・戸原王塚古墳(ⅡA期) (資料集46) ※筑前型庄内甕、初期布留系甕、山陰系壺、精製長頸壺が搬入。他の土器群も福岡平野中枢(比
恵・那珂、博多、雀居など)の「畿内系」技法を受容し在地生産。土器工人移動か。また二重
口縁壺(資料集46)は、那珂62次SX028の二重口縁壺群と類似する。 ・光正寺古墳(ⅡB期) (資料集47) ※高坏・小型器種だけでなく、墳頂に多数配されたとみられる精製二重口縁壺群も搬入の可能
性がある(、福岡平野中枢に特徴的なきれいな橙色系水漉胎土)。
⑥双水柴山2号墳 図56上段 (資料集1) ※墳頂「第 2 主体」出土の精製土器群の大半は福岡平野中枢からの搬入(一部在地品か)。な
お墳丘周囲出土の布留系甕などの他の土器を含めてもⅡB期を遡らない。 ←比恵遺跡9次15号井戸(図55)の様相に類似)
※久里双水古墳(資料集2)は、東四国系二重口縁壺の編年的位置や(図32)、墳頂の在地系小型供献土器群(唐津地域は在地系が遅く残る)が粗雑化が顕著なことからⅡC期に下るも
のである。
⑦各地に搬出された古墳供献精製土器 ・峠山1号墳(ⅡB期) 図56中段
・阿志岐B群26号墳(ⅡC期) 図56下段 ・徳瀬遺跡(日田市)(ⅡC期) 図57上段 ・角房古墳(宇佐市)東側2号方形周溝墓(ⅢA期古相) 図57下段 ※在地産とみられる他の小型器種は、形態がイレギュラーで水漉胎土の質が劣る。搬入品
と考えられる個体は福岡平野のⅢA期古相の形態に類似(図58)。 ⑧豊前石塚山古墳 図59 (豊前の資料集も参照) ※二重口縁壺のうち中型品は山陰系との折衷的様相で(口縁部ヨコナデ、内面ケズリ、頸部
屈曲)、新相を呈する(図61より新しく、図62と同じ段階)。小型精製二重口縁壺は、頸部から胴部がナデ肩状で、鋭角的ではなく、新相である(図63より新しい)。布留系甕は新し
い特徴か(長嶺正秀2005の復元は疑問)。すなわちⅡC期となる。なおイイダコ壺の供献はきわめて珍しいが、加美14号墓と那珂9次4号方形周溝墓に可能性がある。
→「九州最古」ではなくなるのは明白。副葬品に共通性が多い椿井大塚山古墳も布留 1式新相であり、従来の編年観やそれを前提とした歴史観(宇野慎敏 1989・2000など)は成立しない。2 世代後(ⅡC期)の被葬者がⅡA期の古墳の被葬者に三角縁神獣鏡を配布することは無理であろう。(なお高橋護 1988bによると備前車塚古墳はⅩd期であり、とすれば布留1式新相=ⅡC期併行となる。)
⑨豊前赤塚古墳 図64 (豊前の資料集も参照) ※一個体の口縁部のみであり、位置付けは難しいが、よく似た壺形土器は福岡の箱崎遺跡 22
次にある(図 51、高坏の型式からⅡB期か)。在地の土器様相で検証すると、赤塚の首長がいた居館の可能性がある小部遺跡の環濠上層において、円形浮文の加飾は無いが、他は類似する
ものがある(図64・小部7c区SD01上層- 202)。ⅡB期併行であろう(B系甕の型式や布留系土器群の受容から)。口縁部の端部のみ類似する二重口縁壺は小部3区SD01にある(図64右- 157)。ⅡB期である(在地系甕の型式と布留系甕)。また小部SH03住居には垂下タイプだが浮文を付ける二重口縁壺があり、ⅡB期にもその加飾があることが分かる。 =赤塚古墳はⅡB期の可能性が高い。
⑩糸島地方の前期古墳の編年的位置 ・元岡池ノ浦古墳 図65上段 ※埴輪は楕円筒の可能性が高く、Ⅰ- 5式に近似する可能性があり、とすればⅢA期古相か。
ただし、資料が少なく、ストレートに時期を当ててよいか問題がある(鋤崎古墳に新古の要
素があるなど)。丘陵下部の谷部で池ノ浦古墳に伴う可能性が高い壺形埴輪が複数検出され
ており、卯内尺古墳(ⅢA期古相)(資料集35)のうち新相の特徴の直口縁壺形埴輪に類似、または老司古墳(ⅢB期)(資料集 37)では古相の特徴を持つ直口縁壺形埴輪に類似するものがあり、ⅢA期新相に下がる可能性を考えておく。
・三雲端山古墳 図65中段 ※布留系甕の型式や、一次口縁垂下タイプの二重口縁壺から(ⅡB期出現の形式の大型化)、
ⅡC期であろう。 ・三雲築山古墳 ※端山古墳の二重口縁壺が埴輪化したような壺の形態。甕の特徴からⅢA期古相か。
⑪鋤崎古墳(ⅢB期) (資料集19) ※布留 2 式=ⅢA期よりも新しい土器しかない。高坏と小型器種はⅢB期(重藤輝行 1995
のⅢA期)であることは確実。円筒埴輪には古い属性もあるが、鰭付円筒の型式(筒井崇史
2003のA3式)や、器財埴輪(家形、靫形)の様相は新しい。 ⑫羽根戸南G2・G3号墳 (資料集24・25) ※報告では、G2号墳を「集成2期」、G3号墳を「3期」とするが、出土土器を再検討する
と、前者はⅢA期古相~新相、後者はⅢA期新相(4号主体に伴うものはⅢB期か)、築造は
それぞれ、G2号がⅢA期古相=集成3期相当、G3号がⅢA期新相=集成4期前半となる。 5.まとめ ・前期前半(~ⅢA期古相=布留2式古相併行まで)は編年をかなり見直す必要がある ・各地域の土器編年構築と併行関係の厳密化の必要性 ・先入観にとらわれない編年再構築の必要性
※実年代論について - 参考・引用文献- 青木(小池)香津江(編)1998「桜井市纒向遺跡102次(勝山古墳第1次)発掘調査概要」『奈良県遺跡調査概報(第二分冊)1997年度』奈
良県立橿原考古学研究所 青木勘時1997「天理市域の古墳出土土器について- 東殿塚古墳を中心として- 」『庄内式土器研究』ⅩⅣ 庄内式土器研究会
青木勘時ほか2000「第3章 東殿塚古墳」『西殿塚古墳・東殿塚古墳』天理市埋蔵文化財調査報告第7集 青木勘時2001「初期埴輪と土器- 天理市東殿塚古墳の埴輪列とその意義- 」『立命館大学考古学論集Ⅱ』 青木勘時2005「畿内「布留0式」土器と東国の出現期古墳」『東日本における古墳の出現』東北・関東前方後円墳研究会編 六一書房 青木勘時(編)2005『天理市埋蔵文化財調査概報(平成14・15年度・国庫補助事業)』天理市教育委員会 (マバカ西古墳) 青木勘時2006「大和地域」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 青山博樹2004「底部穿孔壺の思想」『日本考古学』第18号 日本考古学協会 赤澤秀則1992『講武地区県営圃場整備事業発掘調査報告書 5 南講武草田遺跡』島根県鹿島町教育委員会 赤塚次郎1990「廻間式土器」『廻間遺跡』愛知県埋蔵文化財センター 赤塚次郎1992「東海系のトレース」『古代文化』第44巻第6号 財団法人古代学協会 赤塚次郎1995「前期前方後円(方)墳出土の土器」『季刊考古学』第52号 前期古墳とその時代 雄山閣 赤塚次郎(編)2005『史跡東之宮古墳調査報告書』犬山市埋蔵文化財調査報告第2集 犬山市教育委員会 赤塚次郎2005「東之宮古墳の編年的位置とその特徴」『史跡東之宮古墳調査報告書』(上記文献) 秋山浩三ほか2000「近畿における吉備型甕の分布とその評価」『古代吉備』第22集 古代吉備研究会 秋山浩三2006「吉備・近畿の交流と土器」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 東 潮・関川尚功1977「東殿塚古墳」『磯城・磐余の前方後円墳』奈良県立橿原考古学研究所 安達厚三・木下正史1974「飛鳥地域の古式土師器」『考古学雑誌』第60巻第2号 市村慎太郎2005「庄内式における布留系甕・布留傾向甕についての素描」『大阪文化財研究』第28号 財団法人大阪府文化財センター 井上和人ほか(編)1980『平城宮発掘調査報告書Ⅹ』奈良国立文化財研究所 (平城宮下層SD6030・SD8520) 石野博信・関川尚功(ほか)1976『纒向』桜井市教育委員会 井上裕弘1991「北部九州における古墳出現期の土器群とその背景」『古文化論叢』児島隆人先生喜寿記念論集 今尾文昭(編)1983『大和考古資料目録 第11集- 前期古墳資料(1)- 』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 (桜井茶臼山古墳資料) 今尾文昭(編)1995「北葛城郡當麻町太田遺跡第1次発掘調査概報」『奈良県遺跡調査概報 1994年度』奈良県立橿原考古学研究所 今尾文昭2005「オオヤマト古墳群における古墳出現期の様相」『東日本における古墳の出現』東北・関東前方後円墳研究会編 六一書房 宇垣匡雅1997「特殊器台形埴輪の文様と編年- 古市秀治「特殊器台形埴輪の研究」について- 」『考古学研究』第43巻第4号 宇野慎敏2000「豊前北部・筑豊地域の墳墓について」『古墳発生期前後の社会像』九州古文化研究会 宇野慎敏1989「北部九州における前期古墳の展開とその背景」『古文化談叢』第20集(下) 九州古文化研究会 大賀克彦2002「凡例 古墳時代の時期区分」『小羽山古墳群』清水町埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ 福井県清水町教育委員会 大久保徹也2006「讃岐及び周辺地域の前方後円墳成立時期の土器様相」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 大野 薫(編)1983『萱振遺跡発掘調査概要・Ⅰ - 八尾市緑ヶ丘2丁目所在- 』大阪府教育委員会 大庭康時(編)1995『博多48- 博多遺跡群第62次調査の概要- 』福岡市埋蔵文化財調査報告書第397集 (博多62次方形周溝墓) 岡部裕俊・河村裕一郎1994「糸島地方の古墳資料集成(その1)」『福岡考古』第16号 福岡考古懇話会 置田雅昭1977「初期の朝顔形埴輪」『考古学雑誌』第63巻第3号 置田雅昭1988「古式土師器研究- 最初の布留式土器- 」『天理大学学報(学術研究会誌)』第157輯 小栗明彦2003「大和の円筒埴輪編年」『埴輪論叢』第5号 埴輪検討会 折尾 学ほか(編)1982『西新町遺跡』福岡市埋蔵文化財調査報告書第79集 柏原孝俊(編)1989『津古生掛遺跡Ⅲ』小郡市文化財調査報告書第50集 (津古生掛87号住居) 鐘方正樹1997「前期古墳の円筒埴輪」『堅田直先生古稀記念論文集』 鐘方正樹2001「古墳時代前期の円筒埴輪編年と玉手山古墳群」『玉手山古墳群の研究Ⅰ- 埴輪編- 』柏原市教育委員会 鐘方正樹2003「古墳時代前期における円筒埴輪編年の研究動向と編年」『埴輪論叢』第4号 埴輪検討会 鐘方正樹2005「玉手山古墳群の研究成果と諸問題」『玉手山古墳群の研究Ⅴ- 総括編- 』柏原市教育委員会 亀田 博(編)1982『見田・大沢古墳群』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第44冊 (古市場胎谷古墳) 蒲原宏行1989「北部九州出土の畿内系二重口縁壺」『古文化談叢』第20集(中) 九州古文化研究会 蒲原宏行1992「古墳時代初頭前後の土器編年- 佐賀平野の場合- 」『佐賀県立博物館・美術館調査研究報告書』第16集 蒲原宏行2003「佐賀平野における弥生後期の土器編年」『佐賀県立博物館・美術館調査研究報告書』第23集 河上邦彦ほか1997「小泉大塚古墳」『島の山古墳調査概報 付.小泉大塚古墳調査報告』奈良県立橿原考古学研究所 学生社 川上洋一(編)2000「桜井市纒向遺跡(第117次調査)発掘調査概要報告」『奈良県遺跡調査概報(第三分冊)1999年度』奈良県立橿原考古
学研究所 河内一浩2005「玉手山古墳群の埴輪Ⅴ- 総括『玉手山古墳群の埴輪』」『玉手山古墳群の研究Ⅴ- 総括編- 』柏原市教育委員会 北島大輔 2000「古墳出現期の広域編年- 尾張低地部編年の提示、近畿・北陸地方との併行関係を中心に- 」『S字甕を考える』第7回東海考
古学フォーラム三重大会資料集 京都大学文学部考古学研究室向日丘陵古墳群調査団1971「京都向日丘陵の前期古墳群の調査」『史林』第54号第6号
久住猛雄1999a「北部九州における庄内式併行期の土器様相」『庄内式土器研究』ⅩⅨ 庄内式土器研究会 久住猛雄 1999b「4 那珂八幡古墳の編年的位置付けと比恵・那珂遺跡群における土器祭祀の変遷について」『那珂 22』福岡市埋蔵文化財調
査報告書第623集 久住猛雄2002a「出土土器の位置付けについて」『元岡・桑原遺跡群1』福岡市埋蔵文化財調査報告書第722集 (ⅢA期の細分、X型小型器
台の分類、高坏接合法の分類) 久住猛雄2002b「3 鋤崎古墳出土の土器について」『鋤崎古墳』福岡市埋蔵文化財調査報告書第730集 久住猛雄2002c「九州における前期古墳の成立」『日本考古学協会2002年度橿原大会研究発表資料集』日本考古学協会 久住猛雄 2003「2.古式土師器の分類と編年について」『青木3- 青木遺跡群第4次調査の報告- 』福岡市埋蔵文化財調査報告書第 734 集
(高坏接合法分類補遺) 久住猛雄2004「1.周溝墓出土土器とその意義」『藤崎遺跡15- 藤崎遺跡第32次調査報告- 』福岡市埋蔵文化財調査報告書第824集 (藤
崎32次1号墓=三角縁盤龍鏡出土墳墓の時期について) 久住猛雄2005a「今山8次調査出土古式土師器について」『今山遺跡 第8次調査』福岡市埋蔵文化財調査報告書第835集 (糸島地方における古式土師器編年と指標の提示) 久住猛雄2005b「3世紀の筑紫の土器~北部九州・特に博多湾岸周辺における外来系土器の受容と展開~」『邪馬台国時代の筑紫と大和』香芝
市二上山博物館・香芝市教育委員会 (筑前型庄内甕の分類と編年、博多湾岸周辺外来系搬入土器の集成) 蔵本晋司2004「丸亀市吉岡神社古墳の再検討- 供献土器のありかたを中心として- 」『財団法人香川県埋蔵文化財センター研究紀要』ⅩⅠ 栗原和彦ほか(編)1976『今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告』第4集 福岡県教育委員会 (ⅢA期新相指標:湯納遺跡D5・11溝) 小池香津江 2002「附編 前期古墳出土の土器- 二重口縁壺をめぐって- 」『大和と東国~初期ヤマト政権を支えた力~』奈良県立橿原考古学
研究所附属博物館 小池香津江(編)2003『古墳出土土器が語るもの- オオヤマトの前期古墳資料展- 』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 小池香津江2005「古墳出土土器は何を語るか」『東日本における古墳の出現』東北・関東前方後円墳研究会編 六一書房 考古学研究会(編)1974「研究報告をめぐる討議 古墳出現前夜の集団関係(都出比呂志)」『考古学研究会』第21巻第1号 古代を考える会(編)1986『加美遺跡の検討』古代を考える43 後藤宗俊・羽田野光洋ほか1979『守岡遺跡』昭和50・51年度発掘調査概報 大分県教育委員会 (守岡遺跡19号住居) 近藤喬一(編)1990『京都府平尾城山古墳』古代学研究所研究報告第1輯 近藤義郎(編)1986『椿井大塚山古墳』京都府山城町埋蔵文化財発掘調査報告書第3集 山城町教育委員会 近藤義郎(編)1991『権現山51号墳』『権現山51号墳』刊行会 財団法人大阪府文化財センター(編)2005『シンポジウム 河内平野における古墳の出現- 久宝寺遺跡と加美遺跡- 』要旨集 財団法人大阪府文化財センター(編)2006「シンポジウム「古墳出現期の土師器と実年代」討議録」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文
化財センター 坂田邦彦(編)2004『御陵遺跡』春日市文化財調査報告書第36集 春日市教育委員会 (御陵遺跡1号住居) 佐藤良二郎・江藤和幸(編)2004『小部遺跡』宇佐地区遺跡群発掘調査報告書Ⅰ 宇佐市教育委員会 (小部遺跡「環濠」) 重藤輝行・西健一郎 1995「埋葬施設にみる古墳時代北部九州の地域性と階層性- 東部の前期・中期古墳を例として- 」『日本考古学』第 2号
日本考古学協会 重藤輝行(編)2000『西新町遺跡Ⅱ』福岡県文化財調査報告書第154集 (西新町遺跡12次) 重藤輝行(編)2001『西新町遺跡Ⅲ』福岡県文化財調査報告書第157集 (西新町遺跡12次) 渋谷忠章・牧尾義則ほか(編)1996『徳瀬遺跡』大分県文化財調査報告書第94集 大分県教育委員会 (日田市徳瀬遺跡) 清水眞一(編)1991『城島遺跡外山下田地区発掘調査報告書』桜井市教育委員会 清水眞一2000「メスリ山古墳前方部出土の土師器」『庄内式土器研究』ⅩⅩⅢ 庄内式土器研究会 吹田直子1997「椿井大塚山古墳と山城地域前期古墳出土土器について」『庄内式土器研究』ⅩⅣ 庄内式土器研究会 吹田直子 2003「山城における古墳時代初頭前後の土器様相」『古墳出現期の土師器と実年代』シンポジウム資料集 財団法人大阪府文化財セ
ンター 吹田直子2006「山城地域」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 杉本厚典 2001「河内における弥生時代中期末から古墳時代初頭にかけての土器の型式編年と様式」『大阪市文化財協会研究紀要』第 4号 財
団法人大阪市文化財協会 杉本厚典 2003「河内における布留式期の細分と各地との併行関係」『古墳出現期の土師器と実年代』シンポジウム資料集 財団法人大阪府文
化財センター 杉本厚典2006「河内地域」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 杉山富雄(編)1986『比恵遺跡 第9・10次調査報告』福岡市埋蔵文化財調査報告書第145集 (比恵9次SE15) 関川尚功1976「纒向遺跡の古式土師器」「畿内地方の古式土師器」『纒向』桜井市教育委員会 関川尚功1988「弥生式土器から土師器へ」『季刊考古学』第24号 土器からよむ古墳社会 雄山閣
高橋 徹2001「大分の弥生・古墳時代土器編年」『大分県立歴史博物館 研究紀要』2 大分県立歴史博物館 高橋 護1988a「弥生時代終末期の土器編年」『岡山県立博物館研究報告』第16集 高橋 護1988b「岡山南部地方の土器編年と庄内式」『八尾市文化財紀要』3 八尾市教育委員会文化財室 竹中克繁2004「九州壺型埴輪研究序論- 壺形埴輪の変遷とその意義- 」『熊本古墳研究』第2号 熊本古墳研究会 竹並遺跡調査会(編)1977『竹並遺跡』 田中清美1988「加美遺跡1号方形周溝墓出土庄内式土器」『八尾市文化財紀要』3 八尾市教育委員会文化財室 田中裕介2000「九州における壺形埴輪の展開と二・三の問題」『古墳発生期前後の地域相』九州古文化研究会 種浦 修(編)1989『土師本村遺跡』諸富町文化財調査報告書第7集 諸富町教育委員会 (土師本村遺跡SK9) 種浦 修(編)1990『三重櫟の木遺跡』諸富町文化財調査報告書第8集 諸富町教育委員会 (三重櫟の木遺跡SX157) 壇 佳克2004a「熊本の古式土師器- 編年的考察と時期的位置付け- 」熊本古墳研究会発表要旨(2004.03.28配布資料) 壇 佳克2004b「人吉盆地における古墳時代の土器編年について- 系統的視点からみた併行関係の再検討- 」『熊本古墳研究』第2号 熊本古
墳研究会 伊達宗泰・小島俊次ほか(編)1977『メスリ山古墳』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第35冊 千賀 久(編)2005『巨大埴輪とイワレの王墓- 桜井茶臼山・メスリ山古墳の全容- 』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 次山 淳1993「布留式土器における精製器種の製作技術」『考古学研究会』第40巻第2号 次山 淳2006「小型丸底土器の地域色- 形態からみた大和と河内- 」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 都出比呂志1974「古墳出現前夜の集団関係- 淀川水系を中心に- 」『考古学研究』第20巻第4号 都出比呂志1979「前方後円墳出現期の社会」『考古学研究』第26巻第3号 筒井崇史2003「鰭付円筒埴輪の形式分類とその変遷」『京都府埋蔵文化財情報』第90号 財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター 坪根伸也2004「豊後における古式土師器の成立と展開」『西南四国- 九州間の交流に関する考古学的研究』平成14年度~平成15年度科学研
究費補助金(基盤研究(C)(1)) 研究代表者 下條信行 寺沢 薫(編)1986『矢部遺跡』(下記に同じ) 寺沢 薫1986「畿内古式土師器の編年と二・三の問題」『矢部遺跡』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第49冊 寺沢 薫1987「布留0式土器拡散論」『考古学と地域文化』同志社大学考古学シリーズⅢ 寺沢 薫(編)2002『箸墓古墳周辺の調査』奈良県文化財調査報告書第89集 奈良県立橿原考古学研究所 寺沢 薫2002「布留0式土器の新・古相と二、三の問題」『箸墓古墳周辺の調査』(上記文献) 徳田誠志・清喜裕二2000「倭迹迹日百襲姫命大市墓被害木処理事業(復旧)箇所の調査」『書陵部紀要』第51号 宮内庁 豊岡卓之(編)1999a『纒向 第5版 補遺編』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 豊岡卓之(編)1999b『古墳のための年代学~近畿の古式土師器と初期埴輪~』奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 豊岡卓之2000「土器・埴輪と「おおやまと」の古墳」『古代「おおやまと」を探る』伊達宗泰(編) 学生社 豊岡卓之2003「特殊器台と円筒埴輪」『橿原考古学研究所紀要 考古学論攷』第26冊 奈良県立橿原考古学研究所 豊田祥三2005「朝顔形埴輪の誕生~その成立と展開の背景~」『立命館大学考古学論集』Ⅳ 中井一夫・豊岡卓之(編)1996「附篇1 葛本弁天塚古墳」『中山大塚古墳』奈良県立橿原考古学研究所調査報告第82冊 中島 正(編)1999『椿井大塚山古墳』京都府山城町埋蔵文化財発掘調査報告書第21集 山城町教育委員会 長嶺正秀(編)2000『苅田町の文化遺産- 苅田町文化財詳細分布地図- 』苅田町文化財調査報告書第34集 苅田町教育委員会 長嶺正秀2005『筑紫政権からヤマト政権へ 豊前石塚山古墳』シリーズ遺跡を学ぶ022 新泉社 中村一郎・笠野 毅1976「大市墓の出土品」『書陵部紀要』第27号 中村春寿・上田宏範(編)1961『桜井茶臼山古墳 附 櫛山古墳』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第19冊 長家 伸(編)1994『西新町遺跡3』福岡市埋蔵文化財調査報告書第375集 (西新町遺跡5次) 奈良県立橿原考古学研究所(編)2001『ホケノ山古墳 調査概報』大和の前期古墳Ⅳ 学生社 西川修一ほか(司会・編)2005「Ⅱ 総合討議 東日本における古墳出現について」『東日本における古墳の出現』東北・関東前方後円墳研究
会編 六一書房 西村 歩(編)2003『久宝寺遺跡・竜華地区発掘調査報告書Ⅴ』(財)大阪府文化財センター調査報告第103集 西村 歩2005「久宝寺1号墳の調査成果」『シンポジウム 河内平野における古墳の出現』財団法人大阪府文化財センター 野々口陽子 1996「いわゆる畿内系二重口縁壺の展開」『京都府埋蔵文化財論集』第3集 創立十五周年記念誌 財団法人京都府埋蔵文化財調
査研究センター 萩原儀征・寺沢 薫1989『纒向石塚古墳範囲確認調査概報』桜井市教育委員会 橋本輝彦2001「大和における東海系土器のひろがり」『邪馬台国時代の近江と大和』香芝市二上山博物館・香芝市教育委員会 蓮岡法暲・勝部 昭・松本岩雄ほか(編)2002『神原神社古墳』加茂町教育委員会 広瀬和雄1992「前方後円墳の畿内編年」『前方後円墳集成 近畿編』山川出版社 廣瀬 覚2001「茶臼山型二重口縁壺と前期古墳の朝顔形埴輪」『立命館大学考古学論集』Ⅱ
廣瀬 覚2005「2 壺形埴輪の大型化とその背景- 将軍山古墳出土壺形埴輪の検討から- 」(廣瀬 覚(編)2005 所収) 廣瀬 覚(編)2005「将軍山古墳群Ⅰ- 考古学資料調査報告集1- 」『新修 茨木市史 資料集8』茨木市 藤田憲司2006「神原神社古墳と山陰の前方後円墳時代初期墳丘墓」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化財センター 藤井利章(編)1979『発志院遺跡』奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第41冊 藤田三郎(編)2003『保津・宮古遺跡 第3次発掘調査報告』奈良県文化財調査報告書第100集 奈良県立橿原考古学研究所 松浦一之介(編)2004『箱崎21- 箱崎遺跡第26次調査報告(1)- 』福岡市埋蔵文化財調査報告書第815集 (箱崎26次周溝墓、壺棺) 松永幸寿 2004「日向における古式土師器の成立と展開- 宮崎平野部を中心として- 」『西南四国- 九州間の交流に関する考古学的研究』平成
14年度~平成15年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(1)) 研究代表者 下條信行 松本洋明(編)2000『西殿塚古墳・東殿塚古墳』天理市埋蔵文化財調査報告第7集 天理市教育委員会 松山智弘2000「小谷式再検討- 出雲平野における新資料から- 」『島根県考古学会誌』第17集 島根県考古学会 松山智弘2002「第4節 神原神社古墳埋納坑出土の土器について」『神原神社古墳』加茂町教育委員会 真野和夫1985「赤塚古墳とその周辺」『えとのす』29 豊(大分)の考古学 新日本教育図書株式会社 向日市文化資料館(編)2004『向日丘陵の前期古墳』 森下章司2005「前期古墳副葬品の組合せ」『考古学雑誌』第89巻第1号 日本考古学会 森岡秀人・西村 歩2006「古式土師器と古墳の出現をめぐる諸問題- 最新年代学を基礎として- 」『古式土師器の年代学』財団法人大阪府文化
財センター 安田 滋(編)2004『西求女塚古墳発掘調査報告書』神戸市教育委員会 安村俊史(編)1994『船橋遺跡』柏原市文化財概報1993- Ⅴ 柏原市教育委員会 安村俊史(編)2001『玉手山古墳群の研究Ⅰ- 埴輪編- 』柏原史教育委員会 柳田康雄1982「三・四世紀の土器と鏡」『森貞次郎博士古稀記念 古文化論集』 柳田康雄(編)1982『三雲遺蹟Ⅲ』福岡県文化財調査報告書63 福岡市教育委員会 柳田康雄1986「高三潴式と西新町式土器」『弥生文化の研究』第4巻 弥生土器Ⅱ 雄山閣 柳田康雄1991「土師器の編年 2 九州」『古墳時代の研究』第6巻 土師器と須恵器 雄山閣 柳本照男1983「布留式土器に関する一試考」『ヒストリア』第101号 大阪歴史学会 柳本照男1991「9.土師器・須恵器」『古墳時代の研究』第8巻 古墳Ⅱ 副葬品 雄山閣 柳本照男2004「ⅩⅡ.土器からみた西求女塚古墳の年代」『西求女塚古墳発掘調査報告書』神戸市教育委員会 山口譲治(編)1993『博多36- 第59次調査報告- 』福岡市埋蔵文化財調査報告書第328集 (博多59次SC48) 吉田東明(編)2002『西新町遺跡Ⅳ』福岡県文化財調査報告書第168集 福岡県教育委員会 (西新町遺跡13次) 吉留秀敏2000「筑前地域の古墳の出現」『古墳発生期前後の社会像』九州古文化研究会 米田敏幸1986「中田1丁目39番地出土土器」『八尾市文化財紀要』2 八尾市教育委員会文化財室 米田敏幸1987「中河内の庄内式と搬入土器について」『考古学論集』考古学を学ぶ会 米田敏幸1990「中河内の『布留系』土器群について」『考古学論集』第3集 考古学を学ぶ会 米田敏幸1991「土師器の編年 1 近畿」『古墳時代の研究』第6巻 土師器と須恵器 雄山閣 米田敏幸1992「畿内における前半期古墳の土器年代についての予察」『考古学論集』第4集 考古学を学ぶ会 米田敏幸1994「河内における庄内式土器の編年」『庄内式土器研究』Ⅶ 庄内式土器研究会 米田敏幸2006「土師器」『大和の古墳Ⅱ』新近畿日本叢書 大和の考古学 第3巻 近畿日本鉄道株式会社 和田晴吾1987「古墳時代の時期区分をめぐって」『考古学研究』第34巻第2号 考古学研究会 ※福岡市および周辺の集落(一部墳墓)関係の調査報告書は割愛したものがある。御寛恕を請う。また、福岡周辺地域(「筑前・肥前北部」)
の前期古墳の報告書などの文献は、本資料集の当該地域資料集成(赤坂 亨ほか作成)を参照されたい。