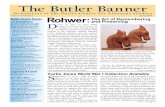Justice in the Right Banner of the Qaračin Mongols during the Qing Dynasty (in Japanese language)
Transcript of Justice in the Right Banner of the Qaračin Mongols during the Qing Dynasty (in Japanese language)
167
清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判額定其労 *
Justice in the Right Banner of the Qaračin Mongols in the Qing Period
Erdenchulu
AbstractThis paper is based on Mongolian archival materials and aims to shed light on the judicial systems of the
Qaračin Right Banner, one of the basic administrative regions of the Qing Dynasty in Mongolia. This study repre-sents new research on, and adds to our understanding of the judicial systems of this region. In the Qing period the local administrative area in this banner—which can be considered the counterpart to the ȷ̌asaγ office ( ȷ̌asaγ-un ya-mun), the central government office—was customarily organised territorially into regions, sub-regions, and villages. In these territories there were many leaders such as noblemen (tabunang), and daγamal tabunangs who were the managerial officials for these noblemen and the non-noble officials. The public procedure for bringing a suit was to present it to the ȷ̌asaγ office, or to the Čiγulγan (or Qural), the council for dealing with public affairs. As for the suits brought to the ȷ̌asaγ office, petty cases such as conflicts concerned with cultivating land were commonly transferred to the daγamal tabunangs or non-noble officials to solve, and more serious or difficult cases were settled centrally. In the latter case the officials there listened to the suits in council and then they produced a draft of the judgement which was reported to the ȷ̌asaγ, who made the final decision. In the suits involving noblemen, in principle the daγamal tabunangs were required to carry out or participate in the procedures of justice, e.g. communicating war-rants from the ȷ̌asaγ office, conveying, judging at a local level, and other legal functions. Meanwhile, as well as the justice administered by the central government office, in practice the local leaders would also unofficially settle cases. The judicial system of the entire banner therefore shows a binary structure with both central and local levels. It can be supposed that the origin of this system lie in the political structure within the banner in that the local leaders were under the rule of the ȷ̌asaγ, but at the same time they themselves ruled their local area or common people (albatu). Incidentally, some social aspects of the judicial processes can be indicated from the cases introduced in this paper: the intention of the victims was regarded as the important thing in the settlement of a murder case; for concerned parties and their relatives a suit might make them a large economic profit or could cause them a huge loss; moreover, the suits might lead to revenge activity from the defendant.
*京都大学大学院法学研究科博士課程、日本学術振興会特別研究員 DC
キーワード:モンゴル、清代、ハラチン右翼旗、政治秩序、裁判Keywords:Mongolia, Qing period, Qaračin Right Banner, political structure, justice
目次1.はじめに2.旗内の政治秩序
2.1.ザサグ衙門と地方
2.2.地方の秩序編成
2.2.1.身分と役職
2.2.2.地域と村落
168 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
2.2.3.貴族の管理体制
2.3.ノヨン ・アルバト関係3.公的裁判の手続き
3.1.訴訟の提起
3.2.裁判を行う人
3.2.1.ザサグと印務処官員
3.2.2.在地権力者
3.2.3.ダーマル・タブナン
3.3.召喚と現地検証
3.4.判決の論拠
3.5.判決の執行4.私的裁判の実態
4.1.事例一(章京ジャヤートによる人命案件)
4.2.事例二(僧侶バートルによる窃盗案件)
4.3.事例三(タブナン・バダラホの諸案件)
4.3.1.タブナン・バダラホについて
4.3.2.嘉慶 3年の公文書に見える諸案件
4.3.3.嘉慶 10年の公文書に見える諸案件5.社会における裁判の位置
5.1.裁判と政治秩序
5.2.裁判と社会6.結論
1.はじめに
本稿は清代ハラチン・モンゴルの右翼旗(qaračin baraγun γar-un qosiγu、喀喇沁右翼旗)にお
ける裁判の全体像について概観しようとするものである(注 1)。
清代のハラチン・モンゴルは、ジョスト盟におけるハラチン右翼・中・左翼の三旗及びトゥメ
ド左翼旗に分布した(注 2)。その居住地域はモンゴルの東南端に位置して中国本土に接し、『王
公表伝』巻二十三によれば、広さはおよそ東西 500里(注 3)・南北 450里であり、北京からの
距離は 760里とされる。人文地理学の知見に基づけば、当該地域では康煕期から漢人の入植が進
行し、乾隆期にはハラチン・モンゴルは既に遊牧から農耕へとその生業形態を変化させていた[珠
颯 2009 : 102]。また档案史料を見ると、本稿で取り上げるハラチン右翼旗では、雍正 10(1732)
年頃には既に漢人とモンゴル人の雑居現象が見られ[档案 505-1-35]、清末期の調査によれば、
当時はモンゴル人だけの村は極めて少ないと報告されている[町田 1905 : 145]。以上を総合すれ
169東北アジア研究 16号(2012)
ば、少なくとも清代の雍正年間以降のハラチン右翼旗(以下、右翼旗と呼ぶ)については、モン
ゴル人も定住して農業を営んでおり、また旗内にはモンゴル人だけで構成される村落も存在して
いたが、モンゴル人と漢人とが混住する村もあったと想定してほぼ間違いはないだろう(注 4)。
本稿では右翼旗における裁判並びにその背景を解明するに当たり、主に内蒙古自治区档案館に
所蔵されている清代の右翼旗のザサグ衙門と地方在住の役人とが作成したモンゴル文档案を手が
かりとする。モンゴル文档案の内容は、①裁判記録文書(注 5)、②旗内発行の命令文、③十戸
編成冊子、④理藩院への上行文に大別される。なお档案テキストの日本語訳に当たっては、人名
と地名は全て現代モンゴル語ローマ字転写で表示し、 { } 内は原語、〔 〕と( )内は筆者によ
る内容補足と補注をそれぞれ示すものとする。また日付は旧暦、年齢は数え年で表示する。
以下、まず 2で旗内の政治秩序について概観し、3でザサグ衙門による公的裁判の手続きにつ
いて叙述する。そのうえで 4において地方有力者による私的裁判の様子を具体的に確認し、これ
に基づいて 5では社会全体における裁判の位置づけを試みる。そして最後に 6において本稿の結
論を述べる。
2.旗内の政治秩序
2.1. ザサグ衙門と地方右翼旗のザサグ職は、その他のハラチン ・モンゴル旗におけると同様に、在地貴族のウリヤン
ハイ氏出身者によって世襲された(注 6)。ザサグが居住する場所は「ザサグ衙門(ȷ̌asaγ -un ya-
mun)」又は「ザサグの処( ȷ̌asaγ -un γa ȷ̌ar)」と称された。ザサグ衙門は旗の公務の中心であっ
たので、本稿では以下、ザサグ衙門以外の旗内の地を「地方」と呼ぶこととする。
ザサグ衙門にはザサグの邸宅の他に印務処が置かれ(注 7)、印務処には旗の公務を司る臣下
たち(tüsimed)が常駐した(以下、本稿では便宜的に「印務処官員」と呼ぶ)。これらの印務処官
員の人数は、裁判記録文書に現れて来る限りでは書記も含めて数名から十名程度であったと思わ
れる。
またザサグ衙門には印務処とは部屋を別にした法廷が存在し(町田 1905 : 挿絵[11枚目下方「法
庭」])、これが「tangkim, 堂」や「se, 司」[档案 505-1-487, 138b]と呼ばれたものと思われる。
なおザサグ衙門と地方との間の命令と報告は文書形式で行われるのが一般的であった。
2.2. 地方の秩序編成
2.2.1. 身分と役職後述する如く、地方の秩序編成には様々な肩書きや役職を持つ者が関係したため、まずはこれ
らの者について簡略に説明しておくことにしよう。
まず旗内における清朝の制度に基づく職位としては、ザサグの下に協理タブナン(tusalaγči
170 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
tabunang)、管旗章京(ȷ̌akiruγči ȷ̌anggi)、梅林章京(meyiren ȷ̌anggi {梅林})、扎蘭章京(ȷ̌alan ȷ̌anggi
{扎蘭})、蘇木章京(sumun ȷ̌anggi {佐領})、驍騎校(orulan kögegči {kündü})、領催(bošoγo)が
あった(注 8)。これらの職位には特定の職務が付与されており、協理タブナンはザサグを補佐し、
管旗章京や梅林章京、扎蘭章京は印務処の仕事に従事した。なかでも扎蘭章京は更に 5つずつの
蘇木(原則として 150人の箭丁から成る)を統轄管理する任を担う(注 9)。蘇木章京は各蘇木
を統轄し、また各蘇木には驍騎校 1名と領催 6名が配置されて蘇木内の公務に当たっていた。
また上記の諸職名を持つ者のうち、協理タブナンと領催以外の者には清朝による職位とは別に、
「等級(ȷ̌erge)」という単なるステイタスを示すための肩書きが与えられることがあった(注 10)。
等級はザサグによって付与されたが、清朝の職位を有しない者もそれを授かることが可能であっ
た。従って、等級を持つ者の中には特定の職務に任命されておらず、単なる等級のみを有する者
もいたと理解される。等級の名称として用いられるのは、上記の管旗章京(管旗章京等級[ȷ̌akiru-
γči yin ȷ̌erge])から驍騎校(驍騎校等級[kündü ȷ̌erge])までの職名および「金頂子(altan
ȷ̌ingsetü)」などであった。職位や等級を持つ者は制帽の上端に頂子(ジンセ)をつけていたため
に「ジンセテン( ȷ̌ ingseten)」と俗称された。なお後述する「社の長」(注 11)も等級を持つこと
があった。
一方、地方には上記の諸ジンセテン以外に等級を有しない「保正」または「ダーマル」、「村長」、
「十戸長(牌頭[payitou])」等の職名を持つ者がいた。保正とは保甲制における保長のことを指し、
ダーマルは保正の同義語と見られる(注 12)。保正やダーマル、十戸長は社の長によって任命さ
れた可能性が高いと思われるが、村長が誰によって選定されたのかについては現在のところ不明
である。
なお本稿では以下、ジンセテン及び地方在住の特定の職務を持つ者たちを、同じく地方在住の
貴族であるタブナン及び彼らの監督者であるダーマル・タブナンと対比して「在地権力者」と総
称し、また場合によって両者を併せて「地方有力者」と呼ぶことにする。
2.2.2. 地域と村落清代のハラチン ・モンゴルでは、一般に各「旗」は複数の「領域」から成り立っており、更に
各領域は幾つかの「地域」に分割されていた。また各々の地域は単一ないし複数の「村」から構
成されていた(注 13)。右翼旗には十数個の領域があったことが档案から知られている(注 14)。
各領域の規模や分布状況については未だ不明であるが、領域内部の地域と村落編成の特徴を把握
するために、ここでは一例として同治 4(1865)年 11月 4日付のザサグ衙門に提出された十戸
編成冊子の档案(注 15)を取り上げて考察する。
同档案は qayidaγaという領域に属すると思われる bayiča、naran、murui、ȷ̌anggin( ȷ̌anggi-yin)ayil、čimedという 5つの地域における「ジンセテン、アルバトの人口・名前・年齢を調べて記
録し、戸を管理するダーマル、ダルガを配置して報告する冊子」である(注 16)。この 5つの地
域は扎蘭等級 dobȷ̌aiを長とする一つの社に組織されたものであり、またその中には bayičaと
171東北アジア研究 16号(2012)
naranの 2地域(計 100戸)に liüčengというダーマルが配置され、murui、 ȷ̌anggin ayil、čimed の3地域(計 117戸)には temürと言う保正が置かれている。つまり社の中にも百戸を基本単位と
する下位組織(保)が存在したのである。同档案に記されている qayidaγa領域の 5つの地域の
村と人口構成を示すと表 1のようになる。
地域名村・寺院(戸 /人数)
在地権力者・十戸長戸数人口
蘇木章京名・所轄戸数
内 訳奴
隷
使用人
耪
青
インジ
村長数
bayiča
boyinuγ(16/109)
扎蘭等級 dobȷ̌ai 1/17 geȷ̌i 1 9
驍騎校等級 vangȷ̌inbou 1/10 geȷ̌i 1 5 1
ダーマル liüčeng 1/12 tayipingbou 1 1
十戸長 üȷ̌inbou轄 13/70 geȷ̌i 13 1
aγui寺 3/36
menggetü(23/107)
十戸長 iüšibou轄 11/51 tayipingbou 11 2
十戸長 masibatu轄 12/56 tayipingbou 12 1
tumba(33/195)
十戸長 geȷ̌i轄 12/65tayipingbou 7 / geȷ̌i 3mimiȷ̌ülgür 1 / tabartu 1
1
十戸長 quriyaγči轄 11/63 tayipingbou 10 / sirab 1 3 1 1
十戸長 yuvanbou轄 10/67 tayipingbou 9 / tabartu 1 1 1
narannaran(28/136)
蘇木章京 tayipingbou 1/3 tayipingbou 1
十戸長 sergenȷ̌ab轄 14/76 tayipingbou 13 / eblekü 1
十戸長 maγunoqai轄 13/57tayipingbou 7 / eblekü 3tabartu 2 / sirab 1
1
naran寺 6/10
murui
murui(53/337)
扎蘭等級 degȷ̌ingge 1/16 不明 1
驍騎校等級 samanda 1/17 不明 1
金頂子 γouȷ̌ing 1/10 laγsintu 1
十戸長 ȷ̌ iyoušungγa轄 14/83laγsintu 8 / sayičingγa 3gölige 2 / tayipingbou 1
十戸長 siyangtu轄 13/84laγsintu 9 / töbden 2sirab 1 / tabartu 1
1
十戸長 liüčeng轄 11/75laγsintu 5 / ögedelekü 3širab 2 / tabartu 1
十戸長 balsang轄 12/52laγsintu 5 / töbden 3 / ögedelekü 1tabartu 1 / sirab 2
1
yekeamuγulangtu
寺0/12
表 1 ハラチン右翼旗の qayidaγa 領域における 5 つの地域の村と人口構成
172 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
表 1からは次のようなことが明らかになる。
第一番目には、地域の構成についてである。表 1で示した通り、bayičaという地域には 3つの
村が存在するのに対して、その他の 4地域には 1つずつの村しかなく、また後者の場合は地域名
と村の名前が一致している。つまり 1つの地域には 1つ又はそれ以上の村落が存在したのである。
また各村の中で人口が最も多いのは murui(53戸 337人)、最も少ないのは boyinuγ(16戸 109人)
であることから、村落の人口規模は百人から数百人に及んだと推測される。
また各地域には村落以外に寺院が必ず存在した。寺院は ȷ̌anggin ayilに 3つあるのを例外として、
その他の地域には 1つのみ存在する。各地域には 1つ又はそれ以上の寺院があったことが窺える。
従って地域を宗教圏として位置づけることも可能であろう。
一家族の人数は平均 5~6人(2~3世代)であり、家族と一緒に住んでいる奴隷や使用人(küčün-ü
kümün)、耪青(佃戸)、インジ(注 17)の数は全体を通して見る限りでは極めて少数であると
言える。
第二番目には、村長の数が一つの村に 1~3名であることである。村長が 2人以上いる村はmuruiと tumbaであり、muruiの村長は badaraqu(52歳)と bomsang(32歳)の 2人、tumbaの
村長は ȷ̌ütang(51歳)と pandai(28歳)、čangli(32歳)の 3人である。
ではなぜ 1つの村に 2人以上もの村長がいたのだろうか。ȷ̌anggin ayil村(46戸 300人)は、村
長が 3人いる tumba村(33戸 195人)より人口規模が多いにも拘わらず、村長が 1人しか置か
れていない。このことから分かる通り、村長の数が村の人口規模に応じて決められてはいなかっ
注: 十戸長の管轄の中にジンセテンが含まれる特例が見られる。即ち naran村の十戸長 sergenȷ̌abの管轄戸の中に驍騎校 sebel一戸(蘇木章京 ebleküの蘇木属)、murui村の十戸長 ȷ̌ iyoušungγaの管轄戸の中に章京等級 badaraqu一戸(蘇木章京 sayičingγaの蘇木属)、同村の十戸長 siyangtuの管轄戸の中に書記 darma一戸(蘇木章京 sirabの蘇木属)がそれぞれ含まれている。
ȷ̌angginayil
ȷ̌anggin ayil(46/300)
章京等級 čoγtu 1/5 sirab 1
保正 temür 1/10 4
十戸長 edlegči轄 14/88sirab 12 / tabartu 1tayipingbou 1
1
十戸長 füsingge轄 10/71 tayipingbou 8 / laγsintu 2
十戸長 nökügesü轄 9/56 laγsintu 8 / tabartu 1
十戸長 füling轄 11/70 laγsintu 6 / tabartu 2 / sirab2 2 1 11
šaȷ̌in-ibadaraγuluγ-či寺
3/7
emüne寺 1/3
aγulan寺 1/1
čimedčimed(18/96)
村長 vangčuγ轄 9/45 laγsintu 8 / geȷ̌i 1 1
十戸長 fütiyanbou轄 9/51 laγsintu 9 1
qatun寺 4/11
173東北アジア研究 16号(2012)
たことは明白である。ただ村長が複数存在するケースでは 50歳代と 30歳前後の者が一組になっ
ているのに対して、1人しかいない場合には、その村長は全員 40歳前後であることから考えると、
各村には 30歳前後の若き村長が 50歳代の村長の下で一定年数修行するという村長養成のための
自主的な体制があったという推測が成り立つ。なお村長は村のリーダーであるが、同時に旗から
組織される十戸に組み込まれて十戸長の管轄下に置かれている(čimed村では村長 vangčuγが十
戸長を兼務)。
第三番目には、各地域(čimedを除く)に蘇木の政務を担う蘇木章京や社の長を務める扎蘭等
級の者のほか、具体的な職務を持っていない章京等級( ȷ̌anggi-yin ȷ̌erge)や驍騎校等級、金頂子
などのジンセテンが在住していることであり、これらの在地権力者は各地域を拠点にして地方の
統制に当たったものと思われる。
第四番目には、同一の村に住む箭丁が必ずしも同一の蘇木に所属するわけではないということ
である。例えば menggetü村の箭丁は全員蘇木章京 tayipingbouの蘇木に属するが(注 18)、tumba村の箭丁は tayipingbou、ge ȷ̌i等の蘇木章京が管轄する 5つの蘇木に属している。つまり箭
丁は蘇木毎に居住しているのではなく、むしろ各蘇木の箭丁が混ざって暮らすのが通例であった。
また全体に着目して見ると、bayičaと naran両地域には蘇木章京 tayipingbouの蘇木に管轄される
箭丁が圧倒的に多いのに対して、それ以外の 3地域では蘇木章京 laγsintuの蘇木に所属する箭丁
が大勢を占めていることが分かる。
第五番目には、十戸組織に管轄される戸数が実際には殆ど 10ではないことである。つまりtumba村の十戸長 yuvanbouと ȷ̌anggin ayil村の十戸長 füsingge所轄の十戸がちょうど 10戸である
のを除けば、他は全て 10戸ではない。即ち ȷ̌anggin ayil村の十戸長 nökügesüと čimed村の十戸長fütianbouが管轄する十戸はそれぞれ 9戸であるが、それ以外の十戸の戸数はいずれも 10戸を上
回っている。
2.2.3. 貴族の管理体制表 1に現れる人々はモンゴル人平民に限られており、貴族たるタブナンは含まれていない。し
かし他の档案からは各地にタブナンが暮らしていたことが知られる。例えば裁判記録文書には、
「köndelenのタブナン」[档案 505-1-41, 3b; 505-1-201, 8b]や「ničügünのタブナン」[档案 505-1-
41, 8a]、「niruγulquのタブナン」[档案 505-1-487, 27b]といった表現が度々現れているほか、乾
隆 28(1763)年 9月 18日付のザサグ命令文には、「王(注 19)の文書(vang-un bičig)。sibege
γool、köndelen、qayidaγa、ničügün、niruγulquのダーマル・タブナンたち皆に命ずる。……」[档
案 502-1-10, 38b-39a]と記されている。つまりタブナンは旗内の各領域に散らばって居住し(注20)、同族出身のダーマル・タブナンが当該領域のタブナンの統轄管理に当たっていた。一方で、
平民はタブナンの統轄管理に加わることはできなかった(注 21)。
各領域に配置されていたダーマル・タブナンについては、その人数を全体的に把握することが
不可能であるが、乾隆 28(1765)年の 5つの領域の事例を挙げるならば、sibege γool 2人、kön-
174 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
delen 5人、qayidaγa 5人、ničügün 2人、niruγulqu 7人であった[档案 502-1-10, 28b]。ではどの
ようなタブナンが如何なる方法でダーマル・タブナンになったのだろうか。ザサグ命令文には次
のような事例が示されている。
王の文書。タブナン šamba、altansangたちに命ずる。ダーマル・タブナンの dardungが報告す
るには、「ダーマル・タブナンであった ayusiが僧侶になりました。彼の代わりにダーマル・タブ
ナンを任命して頂けませんか」と。そこで、その地域のタブナンたちの中から廉潔かつ有能でダー
マルに成れそうな者についてザサグ衙門に来て報告せよ。このために命じた。二月二十日[档案502-1-171, 10a]。
即ちダーマル・タブナンに任用されるのは廉潔かつ有能と認められるタブナンであり、在地のタ
ブナンたちの推薦した候補の中からザサグが選んで任命していたことが分かる。
またダーマル・タブナンの職務については、道光 28(1848)年 6月 18日付の裁判記録文書の
中で、
……ダーマル・タブナンである buyankesigはザサグの処の命令を受けた、所轄の親族集団(qa-
riyatu töröl ayimaγ)を管理し些細なことを処理する職務を担っている者である。本来ならば所轄
の地域に訴訟や係争事件があれば、〔ザサグ衙門に〕報告して処理させるべきは報告し、取り締
まって処理して終わらせるべきは〔現地で〕終わらせてから報告すべきである。……[档案 505-
1-403, 11a]
と記されている。つまりダーマル・タブナンは自らが属する血縁分枝集団の管理に当り、集団内
に起きた「些細なこと」を処理する職権を持っていたのである。また所轄の地域内のタブナンに
関わる係争事件については、ザサグ衙門に報告したり或いは現地で処理してからその結果をザサ
グ衙門に報告したりすることができた。
更に乾隆 28(1762)年 2月 17日付のザサグ命令文によれば、ダーマル・タブナンは村落内に
村外から来た逃亡者や流民、犯罪者などが隠れているかいないかについても毎年 2月 1日と 7月1日の二回に亘ってザサグ衙門に報告しなければならなかった[档案 502-1-10, 3b-4a]。
2.3. ノヨン ・ アルバト関係伝統的なモンゴル社会では身分は血縁的に大きく貴族と平民の 2つに分かれ、平民はアルバト
として貴族に従属していた。しかしながら清代になると清朝は貴族に少数のアルバト(随丁[qa-
riyatu, qamȷ̌ilγa])のみを残し、その他の大多数のアルバトを清朝皇帝のアルバト(箭丁[sumu-u
arad, quyaγ])にし、またモンゴルのチベット仏教の活仏にも一定のアルバト(シャビナル
[šabinar])を配分した[岡 2009 : 147-148]。また以上の貴族と平民以外に、清代のモンゴルでは
175東北アジア研究 16号(2012)
僧侶(ラマ)や奴隷の身分も存在した。
上記のモンゴル一般に見られる身分は清代の右翼旗にも存在したが、箭丁(右翼旗では箭丁はdangsatu albatuと称される)については、皇帝のアルバトとして軍事組織である蘇木(注 22)に
所属して旗のアルバ(貢租賦役)を負担すると同時に、依然としてタブナンに従属し彼らにも「定
額の白いアルバ(toγtamal čaγan alba)」と呼ばれるアルバや臨時のアルバを提供した。箭丁が提
供する旗のアルバとタブナンに対する「定額の白いアルバ」はいったん蘇木単位で割り当てられ
た後、蘇木の内部において各箭丁戸に個別の額が割り当てられた。箭丁戸は経済力に応じて幾つ
かの等級に分けられ、それに即して応分のアルバを負担した。アルバトは自らが属するタブナン
のことを「ノヨン」と称した。
「定額の白いアルバ」とは年に一回だけタブナン集団に提供するアルバであり(注 23)、タブ
ナンに対して臨時に提供するアルバとは異なってその負担額が決まっていた。「定額の白いアル
バ」の総額と項目は蘇木や年によって異なることもあろうが、その中身についてはここでは乾隆56(1791)年の扎蘭 quvasingγaが管轄する蘇木章京 nayirtuの蘇木(170戸)の事例を通して見て
みよう[档案 505-1-165]。同蘇木の「定額の白いアルバ」の総額と項目を档案の記述に従ってqotaと kebüdの居住地域別に示したのが表 2である。
表 2から分かる通り「定額の白いアルバ」には家畜等の現物の他に労役も含まれている。また
蘇木章京 nayirtuの蘇木の場合は、箭丁戸は「定額の白いアルバ」を負担する際に頭等~六等の6つの等級に区分されていたことが档案から窺える[档案 505-1-65]。
「定額の白いアルバ」とは別に、アルバトはタブナンに対して不定期的な現物と労役のアルバ
をも提供しなければならなかった。従ってアルバトが提供するアルバには通常旗のアルバ、「定
額の白いアルバ」、タブナンに対する臨時アルバの三種類があった(注 24)。なおタブナンは随
丁を持ち、随丁はタブナン同士の間で売買することができた(注 25)。
一方、タブナンは所轄のアルバトからアルバを受け取ったが、その反面、皇帝に対して毎年ア
ルバを納めなければならなかった(注 26)。またタブナンにはアルバトを「大切にし、助けたり
qota kebüd軍馬飼養粟(aγtan-u amu) 百斛* 飼料(ebesü) 二千五百包粟(sira amu) 一担 薪(tülege) 百六十車豚(γaqai) 十 炭(negüresü) 三十車雁(γalaγu) 十 掃除 八ヶ月毎に女一人(γaȷ̌ar
sigürdekü naiman sara-yin eme nige)鴨(nuγusu) 十
表 2 蘇木章京 nayirtu の蘇木の乾隆 56(1791)年における「定額の白いアルバ」
灯油(deng-ün toso) 三百九十碗箒(tiyau ȷ̌u) 百八十四ヶ月間の軍馬飼養人 一人(dörben sara- yin aγtan-u borduγan-u kümün nige)*斛は 10斗に相当する。
176 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
教育したり」[档案 505-1-63, 26b]する道徳上の義務があった。タブナンは名義上蘇木に所属した
(注 27)。
なお耕地は旗(「外倉地」「官倉地」)やザサグ(「内倉地」)、寺院、個人等によって保有された
が、個人保有の耕地には更に「福分地」(祖先伝来の土地)や「生計地」(旗より分与された土地)、
「差役地」(役人の俸給の代わりに与えられた土地)、「恩賞地」(報奨として授かった土地)、「自
置地」(地価を払って獲得した土地)といった種類があり、モンゴル人は通常自らの耕地の一部
だけを自分で耕作し(「自種地」)、残りは佃戸に小作させていた(「吃租地」)(注 28)。
3.公的裁判の手続き
3.1. 訴訟の提起訴訟は口頭またはモンゴル文訴状で提起された(注 29)。訴訟が最初にどこに提起されるべき
かについては、次の乾隆 28(1763)年 9月 19日付のザサグ命令文が端的に示している。
王の文書。……一件。元より、あらゆる係争事件は訴える民がザサグ衙門とチョールガンの場
に来て訴えるのが慣例である。それにも拘わらず、係争事件をザサグ衙門とチョールガンの場に
報告せずに、こっそりとコネや面子の通ずる臣下(tüsimed)の家に行って訴える民がなおいる。
これは禁令と慣例にはとても合わないため、これ以降、係争事件について訴えることがあれば、
如何なる者でも自らザサグ衙門とチョールガンの場に行って訴えよ。係争事件は〔ザサグ衙門か
ら〕隠蔽し、知り合いと陰謀し〔地方にある〕臣下の家に行って訴えたりしてはならない。もし
この禁令に背いて捕まったり第三者に告発されたりすることがあれば、訴えた者と訴えを聴いた
者とを厳重に罰して戒める。……[档案 502-1-10, 39b-41a]
つまり下線で示した通り、訴訟は全てザサグ衙門またはチョールガン(注 30)が開催される際
にチョールガンに対して提起すべきものであり、これに反した場合は厳しく罰せられるのが原則
であった。
ただ上記の史料からは、地方では在地権力者に対して訴訟を提起することもあったことが知ら
れる。そこで後者の実態については次章において具体的に提示することとして、以下ではまず公的
裁判の一般的な手続き、つまりザサグ衙門に提起された訴訟の処理方法について明らかにする
(注 31)。
3.2. 裁判を行う人
3.2.1. ザサグと印務処官員ザサグ衙門に提起された訴訟はまずは印務処が受理し、その後に印務処官員から案件がザサグ
177東北アジア研究 16号(2012)
に上申され、当該案件を印務処において処理するか、それとも在地権力者やダーマル・タブナン
に命じて処理させるかがザサグの手によって決められた。では印務処において処理することと
なった場合、ザサグ衙門における裁判は実際にどのような流れで行われたのだろうか。次の裁判
記録を事例に見てみよう。
公(注 32)の護衛 nasunȷ̌iγの婦人(ekener)čoγȷ̌imaは次のように訴えた。「梅林だった私の父ȷ̌amiyangが息子がいないまま亡くなったことにより、父の財産や家畜、奴隷(ger-ün kümün)等
は〔私の〕従兄である扎蘭 bolodが独り占めし、私に分与してくれません。そこで追及して訴え、
〔ザサグ・ノヨンに〕道理を伺います(yoso asaγuγad)」と。扎蘭 bolodが供述するには、「私の
叔父が息子のいないまま亡くなったため、祖母は生前、叔父の一部の奴隷を売買し、叔父が生前
に持っていた財産と家畜を叔父の債務のために払い尽くしました。今残っているのは四人の奴隷
だけです」と。この案件について調べてみると、そもそも父親の保有分は近親が引き取った上で
娘に一割を与えるべきであったが、父親の保有分は祖母が生前に費やしてしまっている。そこで、
現在いる四人の奴隷から二人を娘〔čoγȷ̌ima〕に与えるよう処理して終わらせる。これについて
命令を仰ぐため、管旗章京 esenmendü、baluu、梅林章京 sü ȷ̌ügtü、典儀長 seter、扎蘭章京 sa-
dung、samtan、balȷ̌uur、erdenisang、nomonsang、čečegtüたちが王に伝達して上申した。〔ザサグの〕
命令は、「undurquを妻と一緒に bolodに与えよ。六十歳の doγdolと一人の未婚娘のうえに、bolodから更に満一五歳になった一人を取って併せて三人を čoγ ȷ̌imaに与えて処理し、言い渡し
て後で档案に記せよ」とのことであった。これを同じく〔伝達した印務処の〕臣下が〔ザサグの
邸宅から〕出て来て言い渡した。早速、書記 pongsoγがこの案件を档案に書き記した[档案 505-
1-63, 13b-14a.日付は未記載]。
この裁判は乾隆 21(1756)年に行われたものであることが同档案の表題から分かる。婦人čoγ ȷ̌imaは自分に対する父親の遺産分与をめぐり従兄である bolodをザサグ衙門に訴えた。bolod
は召喚され、案件は 10人の印務処官員によって審理された。そしてこれらの印務処官員は判決
原案(波線下線部分)を作成し、それをザサグに上申した(点線下線部分)。判決原案は、bolod
が持っている undurqu夫妻と老人 dogdol、未婚娘の 4人の奴隷の内から 2人を取って čoγ ȷ̌imaに
与えようとするものであった。しかしザサグは bolodから老人 doγdolと未婚娘 1人の上に更に
もう 1人の満 15歳になった者を取って併せて 3人の奴隷を čoγ ȷ̌imaに与えるよう命令している
(一重下線部分)。つまりザサグは判決原案の中の čoγ ȷ̌imaに与える奴隷を 2人から 3人に変更し
たのである。そしてこのザサグの命令は案件を審理した印務処官員によって両当事者に言い渡さ
れ(二重波線部分)、最後に同裁判の審理内容が書記 pongsoγによって档案に記録された(二重
下線部分)。
つまりザサグ衙門における裁判は次のような流れで行われた。まず印務処官員は合議体の形で
案件を審理し判決原案を練り上げた。次いで印務処官員たちはザサグの邸宅に行って案件と判決
178 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
原案を上申した。判決はザサグの同意又は訂正を経て案件を審理した印務処官員によって当事者
に言い渡され、最後に書記が当該裁判の審理内容を档案に書き記した。
本事例が示す如くザサグは通常は案件を直接に審理することはしなかったが、しかし重大な案
件の場合はその審理に参加したり(注 33)、或いは場合によっては案件審理の様子を監視したり
することもあった(注 34)。
また案件を審理した印務処官員の人数は通常数名から十名程度であり、その職位は管旗章京以
下、扎蘭章京以上であった(注 35)。
なお審理においては法廷記録が取られ、それが判決原案や裁判記録文書の元となったものと見
られる。
3.2.2. 在地権力者在地権力者による事案処理については、彼らに対して訴訟事案の処理を命ずるザサグ命令文 3
通を提示して考察する。
① 王の文書。扎蘭 erteiに命ずる。護衛 mandalの奴隷(注 36)である ȷ̌oriγtuが耕地のことで不
平不満を言った件については、〔以前に〕汝に命令文を送り「処理してやれ」としたのである。
それにも拘わらず、ȷ̌oriγtuは「lambouから耕地を取って下さいましたのに、なぜ arnaiの耕
している耕地を取って下さらないのでしょうか」とまたも不平不満を言っている。この文書
が到達したら直ぐに当事者双方の真実を明らかにして処理してやれ。もし〔判決を〕受け入
れそうでなかったら、当事者双方の民を村の牌頭たちと一緒に汝が自らザサグ衙門に連れて
来い。このために命じた。三月十一日[档案 505-1-171, 23a-b]。
② 王の文書。〔蘇木〕章京 ilerkeiに命ずる。汝の蘇木の sembelに対して、toloiという者が耕地
のことで不平不満を言って訴えたので、文書が到達したら直ぐに当事者双方を会わせてそれ
ぞれの言い分を聴いて処理し〔係争を〕終わらせてやれ。もし〔判決を〕受け入れそうでなかっ
たら、〔人を使って〕当事者双方の民を証人と共にザサグ衙門に送らせよ。このために命じた。
同(三)月十六日[档案 505-1-171, 31b]。
③ 王の文書。〔蘇木〕章京 möngke、牌頭 dayabögere {dayabür}、balsangたちに命ずる。dügüreng
が不平不満を言った言葉の中に、「〔蘇木章京〕vang ȷ̌uurの蘇木の bayarの未婚娘を妻にしよう
と馬二頭を渡して婚約したことがある。しかし bayarの未婚娘が死んでしまったため、bayar
と話し合い二頭の馬の換わりに三軒の家をもらうことになった。しかし bayarの親戚たるtüme ȷ̌öb、ȷ̌ in ȷ̌ub、čoγtanたちがその家を占拠して私に渡さないので不満です」とある。そこで、
文書が到達したら直ぐに当事者双方を会わせてそれぞれの言い分を聴いて真実を明らかにし、dügürengの馬を取って与えるように処理してやれ。このために命じた。三月十一日[档案
179東北アジア研究 16号(2012)
505-1-171, 23b-24a]。
この 3件の事例はザサグ衙門に訴えられた耕地争い(①②)と婚約破棄に伴う財産争い(③)に
起因する訴訟であり、地方在住の扎蘭(①)や蘇木章京(②)、或いは蘇木章京と牌頭が合同で(③)
案件を処理するよう命じられている。在地では当事者同士を会わせてからそれぞれの言い分を聴
くという審理方法が採られ、また牌頭や証人からも事情を聴取することがあった。そしてもし当
事者が判決に対して不服であれば、当事者たちは裁いた在地権力者本人(①)または別の在地権
力者(②)の手によって牌頭や証人と共にザサグ衙門に送られた。牌頭は当事者に最も身近な在
地権力者として案件審理の際に事実情報を提供したり、或いは③に見えるように蘇木章京等の在
地権力者と共同して事案処理を行ったりした。また地方で行われる事案処理では村の老人も証人
として呼ばれることがあった[档案 505-1-171, 30b]。なお①からは奴隷でも訴訟を提起すること
が可能であったことが窺える。
上記 3件の事例から分かるように、在地権力者に事案処理が委ねられるのは軽微な平民同士の
係争事件のみに限られていた。
3.2.3. ダーマル・タブナンダーマル・タブナンに訴訟事案の処理が委ねられることもあった。以下の 2通のザサグ命令文
を通してその実態を明らかにしてみよう。
① 王の文書。ダーマル・タブナン čebden、dardung、dorȷ̌obたちに命ずる。〔蘇木章京〕badarangγui
の蘇木の箭丁 bederiyeが不平不満を言った言葉の中に、「私の父 dalaiが存命であった頃、私
の二頃の耕地が協理たる sandabに奪われた件を太爺王(ザサグ)に訴えて耕地を戻して頂き
ました。しかしその耕地を〔協理は〕私に一年間耕させた後またも奪い取り、十数年になり
ました」とある。そこでおまえたちダーマル・タブナンは当事者双方を会わせ、それぞれの
言い分を聴いて処理してやれ。このために命じた。〔二月〕十九日[档案 505-1-171, 8a-b]。
② 王の文書。ダーマル・タブナン dorȷ̌ob、dardungたちに命ずる。タブナン balampilが不平不満
を言った言葉の中に、「私のアルバト booȷ̌ilと sirmaの未婚娘を私が自分の娘にインジとして
与えようとしたことについて、〔以前に私が〕ザサグの処に不平不満を言ったことがあり、〔こ
れについては〕既に『彼らの未婚娘をインジとして与えよ』と断じて下さっています。しか
し booȷ̌ilと sirmaは自らの未婚娘をインジとして出してくれないため不満です」とある。そこ
でこの文書が到達したら直ぐにおまえたちダーマル・タブナンは、以前に booȷ̌ilと sirmaの未
婚娘をインジとして行かせることに関する争いがあったかなかったかについて法の通り正し
く調べ、公正に処理してやれ。もし〔判決を〕受け入れそうでなかったら当事者双方の者た
ちをザサグ衙門に連れて来い。このために命じた。三月十一日[档案 505-1-171, 25b-26a]。
180 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
①は箭丁が耕地を奪われたとして協理タブナンを訴えた訴訟、②はタブナンが自分のアルバトが
未婚娘をインジとして出してくれないことを訴えた訴訟であるが、いずれもダーマル・タブナン
たちにその処理が命じられている。これは当事者の中にタブナンがいたためであり、双方の当事
者が全員タブナンであった場合にも当然ダーマル・タブナンが案件を処理した。
ダーマル・タブナンたちも前述の在地権力者同様、当事者たちを会わせてそれぞれの言い分を
聴くことによって案件を審理した。また②で示された通り、判決が受け入れられなかった場合は
当事者たちをザサグ衙門に連れて行かなければならなかった。またこのような場合は、在地権力
者と同様、ダーマル ・タブナンたちは他の者を使って当事者たちをザサグ衙門に送ることも可能
であったと推測される。
また在地権力者が行った事案処理との比較からも分かるように、地方に処理が命じられた訴訟の
うち、当事者が全員平民である場合は扎蘭や蘇木章京等の在地権力者によって処理されるが、当事
者の中にタブナンがいる場合にはダーマル・タブナンによって裁かれるのが原則であった。なお①
からはダーマル・タブナンは協理タブナンに関する争いも裁くことが可能であったことが窺える。
3.3. 召喚と現地検証ザサグ衙門で裁判を行う際には、被告人や証人等の召喚及び現地での検証が必要とされた。こ
れらの手続きは以下の諸事例の中に見て取れる。
① 王の文書。〔蘇木章京〕vang ȷ̌uurの蘇木の nima、erdenisangたちに命ずる。おまえたちをtoγočiが訴えているのでこの文書が到達したら直ぐにザサグ衙門へ遅滞せずに速やかに来い。
このために命じた。三月十三日[档案 505-1-171, 29a]。
② 王の文書。〔蘇木〕章京 möngke、lasȷ̌iγたちに命ずる。僧侶 namqaiyangsuの訴えに関わったnamdar、sakiya、sooȷ̌i {souȷ̌ü}たち本人と、第三者(köndelen kümün)の barbu、nomongerel、morongたちをこの文書が到達したら直ぐにおまえたち二人が集め揃えてザサグ衙門に送って
来い。一人も残してはならない。このために命じた。同〔三月十三〕日[档案 505-1-171, 29a]。
③ 王の文書。sibartaiのダーマル・タブナン dügüreng {düreng}に命じる。タブナン balaの牛を盗
んだタブナン sülȷ̌imの随丁 küsel本人を牌頭 badarangγuiとタブナン sülȷ̌imと共におまえがザ
サグ衙門に送って来い。このために命じた。〔二月〕十七日[档案 505-1-171, 5a-5b]。
④ 〔蘇木〕章京 enkeȷ̌irγalの蘇木の箭丁 čang ȷ̌ulが文書を呈し、彼の伯父である僧侶 ayuriの植え
た粟畑をタブナン ürgümbouとダーマル・タブナン ȷ̌ ig ȷ̌idが夜中に武器を構えて来て刈り取っ
たと不平不満を言った。この事件について取り調べるようダーマル・タブナンの qanabadaiと
梅林等級 sümingγaたちに命じたのである。彼らが取り調べて報告する文書の中で、「命令に従っ
181東北アジア研究 16号(2012)
て箭丁 čang ȷ̌ulが畑のことでタブナン ürgümbouたちを訴えた件について、現地に行って調べ
てみると(後略)」[档案 505-1-487, 178b-179a]。
これら 4つの事例は、①~③は召喚、④は現地検証についてである。召喚に関して①では被告人
本人にザサグ衙門に来るよう直接命じているが、②と③では蘇木章京やダーマル・タブナンが被
告人と関係者を連れて来るように命令されている。村長や牌頭が当事者や関係者をザサグ衙門に
連れて来るよう命じられることもあったが、それは②で示された如く召喚された当事者や関係者
が全員平民であった場合に限られており[档案 505-1-94, 8b-9a]、③のように召喚相手の中にタ
ブナンがいた場合はダーマル・タブナンが召喚の任に当たるのが一般的であった(注 37)。在地
権力者やダーマル ・タブナンに当事者及び関係者をザサグ衙門に連れて来させるというこのよう
な召喚の方法は、召喚相手がザサグ衙門に直ちに来なかったり或いは遅延したりすることが見込
まれた時や、召喚された人数が多かった場合等に用いられたと思われる。なお③でタブナンsülȷ̌imが窃盗を行った自らの随丁 küselと共に召喚されていることから、随丁に対して主人たる
タブナンが監督責任を負っていたことが分かる。
事例④は平民とタブナンの間で起きた争いであり、当事者の中に ȷ̌ ig ȷ̌idというダーマル・タブ
ナンがいたために、現地検証には別のダーマル・タブナン qanabadaiと梅林等級 sümingγaが命じ
られたと考えられる(注 38)。このように扎蘭や梅林、蘇木章京等の有力な在地権力者がタブナ
ンの関わる案件において召喚や現地検証を命じられることもあった。また現地検証において当事
者の中にタブナンがいた場合はダーマル ・タブナンの参加が要請された。
3.4. 判決の論拠前述の通りザサグ衙門における裁判では、判決文の内容は予め印務処官員によって起草されて
から最終的にザサグによって決定された。では判決は一体どのような論拠に基づいて決定された
のだろうか。
まずは清朝が制定したモンゴル人専用法典である蒙古例(『蒙古律例』または『理藩院則例』)
について考察してみよう。本稿で用いた諸裁判記録文書の中では蒙古例の名前が言及されたり
(注 39)、或いはその条文が書き写されたりする事例が幾つか見られる。前者については、条文
が提示されていないため法典の規定内容が裁判に適用されたか否かについて直接に確認すること
が困難である。しかし後者においてはそれが可能であるため、以下、実例を通して検証してみし
よう。まず、乾隆 14(1749)年 10月 14日付の裁判記録文書を取り上げる。
ničügün〔領域〕のタブナン erdenisangの随丁である ongγodaiの妻が、「私の娘 durdamalを〔蘇
木章京〕gönčidの蘇木の sonorが彼自分と婚約させるよう〔私に〕申し込んだのであります
(beye-du-ban süileȷ̌ü γuyuγsan bile)。私に二頭の大型家畜を〔婚約のために〕渡しましたが、今に
至るまで娘を娶っていません。娘は二十二歳になりました。道理を伺います」と不平不満を言っ
182 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
た。sonorの言葉の中に、「私は大型家畜三頭と銀六両を渡すと言って ongγodaiの娘 durdamalを
自分と婚約させるよう〔彼女の父母に〕頼み、先に馬一頭と三歳牛一頭を渡したのです。今義理
の父母は、娘が二十二歳になったと言って〔娘を〕私に嫁がせません」とある。この案件を管旗
章京 balu、梅林 süȷ̌ügtü、samtan、扎蘭 sadung、erdeni、erdenisangたちが王に伝達したところ、
次のような命令が下された。「定めた律には(toγtaγaγsan čaγaȷ̌in-dur, つまり『蒙古律例』)、未婚
娘をその実家に四頭の大型家畜と二十頭の羊を渡すことによって娶れよ。〔その〕未婚娘が二十
歳になれば、申し込まれた婚約が破棄され、父母が自分の好きなところに〔娘を〕嫁がせよ」と
なっている。この律の通り、未婚娘が二十二歳になっているため、sonorは四頭の大型家畜と
二十頭の羊を翌寅年の五月初一までに揃えて〔未婚娘の父母に〕引き渡し、女(eme)を娶れよ。
もし〔翌寅年の〕五月初一までに大型家畜と羊を引き渡さなければ、婚約は破棄され、父母が〔娘
を〕他の人と結婚させよ。」……(档案 505-1-41,13b-14a)
下線で示したように、判決では婚約を申し込んだ sonorが 4頭の大型家畜と 20頭の羊を供出し
て婚約した未婚娘の両親に渡すように命令されており、これら家畜の頭数は『蒙古律例』の規定
に則っている。しかし、上で示す「未婚娘が二十歳になれば、申し込まれた婚約が破棄され」る
という『蒙古律例』の条文は明らかに適用されていない。なぜなら、この規定内容に従うならば、22歳になった durdamalの婚約は訴えの時点ですぐに破棄されるべきであったが、そうなされて
いないからである。その理由は、訴訟を形式的によりも本質的に解決しようとする当時の裁判の
姿勢にあると思われる。上述の内容から分かるように、裁判における紛争の根本的な原因は被告sonorが約束した家畜や金銭を原告側に数通り提供することが出来なかったことにあると考えら
れるため、それさえ解決されれば紛争自体も自ずと収まるのである。そこで一定の期間を決めて
被告に未払いの家畜と金銭を原告に提供させるように判決している。また、これは同時に婚約履
行を主張する被告にも配慮した措置だと考えられる。
一方で、上記の事例と異なって蒙古例の条文を提示しつつも判決がその規定内容に明らかに不
一致する裁判が存在する。これについて、以下の同治 10(1870)年 4月 23日付の裁判記録文書
における窃盗を行った rinčinyalsan、gelegdandar、ȷ̌amiyangの三人の僧侶に対する判決内容を通し
て明らかにしよう。
……『蒙古律例』を調べてみると、「一件。盗品の額が〔銀〕百二十両以上であれば、首犯は
絞罪に処して監候し、秋審にかけよ。従となって一緒に盗みを行い、物品を分けて受け取った者
等は雲南、貴州、広東、広西の悪気候の地へ遣(流)せよ。共謀したが窃盗を行わず、ただ窃盗
の後に物品を分けて受け取った者等は山東、湖南に遣せよ;一件。凡そ死罪のモンゴル人は贖罪
金を支払って免罪となるには、九・九頭の馬(yisü yisün mori)を供出させて〔それらを〕公の
物にせよ。さらに、僧侶が窃盗の罪を犯せば、〔世俗の者と〕同じく法の通り断罪して処せよ」
となっている。rinčinyalsanと ȷ̌amiyang、gelegdandarの三人の盗んだ物の額を計算してみると、
183東北アジア研究 16号(2012)
〔銀〕数百両に達している。彼等の罪には重い刑罰が当たっていることに従って、彼等を地方衙
門(注 40)に押送し法の通り断罪して処してもらうならば、斬、絞、遣の刑罰になるのである。
しかしこのようにすると皆に負担がかかり、また宗教(burqan šasin-u üiles)のためにもよくな
いことになる。rinčinyalsanは窃盗を提案して夜中に仲間と共にそれを行い、また自分の家で隠
したり或いは分けて受け取ったりした盗品を調べ出した際に、それらは彼の僧侶であった祖父の
物であるとして抵抗し、さらに〔寺院側が取り調べに備えて〕密封した木製箱(abdara)の底を
壊して〔盗品を持ち出そうとして〕上司を騙そうとした。彼の行為は僧侶の道徳(quvaraγ-un
yoson)に深刻な恥をかけるに至っているため、このような重罪に関わった rinčinyalsanについて
は適切に処罰し( ȷ̌üilčilen abačiȷ̌u)、彼を鞭打ち百にした上で枷をかけて三ヶ月間町を回らせ
(qoruγa kerügülȷ̌ü)、期間が終了した時点でさらに所轄の寺院の庭を三年間掃除するようにする。gelegdandarはいくら rinčinyalsanの意思に従って〔夜中に〕盗みをしたと雖も、人家に入って窃
盗を行ったのは事実であり、またその盗品を自分の意思で売却し、さらに čoyidarȷ̌aiの物を盗ん
だり burqantu地域の人の物を騙し取ったりし、また逃亡して審理を避けようとした。彼の犯し
た罪は首犯のそれよりも重いため〔刑罰を〕加等し(qubi nemeȷ̌ü)、鞭打ち百にした上で枷をか
けて四ヶ月間町を回らせ、期間が終了した時点でさらに四年間寺院の庭を掃除するようにする。ȷ̌amiyangは gelegdandarと一緒に〔人家に侵入して〕窃盗を行い、また盗品の代金を分けて受け取っ
て使っている。そこで彼を鞭打ち百にした上で枷をかけて三ヶ月間町を回らせ、期間が終了した
時点でさらに寺院の庭を三年間掃除するように処理する。……[档案 505-1-487, 81a-82b]
下線部分の通り、窃盗を行った 3人の僧侶を駐防官の所に押送し上申して『蒙古律例』の規定内
容どおり断罪させるならば、彼等の刑罰は「斬、絞、遣の刑罰になるのであ」った。しかし、「こ
のようにすると皆に負担がかかり、また宗教のためにもよくないことになる」と考慮されたため、3人は鞭打ちや枷、労役に処せられている。ここで言う「負担」は主に犯人押送の人力・経費や
死刑実行後の葬儀・法会等に関わる諸費用のことを指したと想定され、また「宗教のためにもよ
くないこと」とは犯人を死刑にして殺してしまうと、すべての生命は愛しいといったチベット仏
教の教えに反することを意味するものと思われる。
そして上の 2つの事例およびその他の多くの裁判事例から明らかなように、判決は何よりも案
件の抱えている諸状況を総合的に考慮して下されるのが通例であった。ただ、かと言って判決内
容における措置は無限に流動的かつ個別的なものであったわけでもない。例えば窃盗案件では首
犯は鞭打ち百と罰三・九畜、従犯は鞭打ち八十と罰二・九畜に処罰されるというように[档案505-1-63, 6a-7a]、むしろ安定したものであった。
また別の裁判記録文書では、「……を処した法の通り(sidkegsen qauli-bar)」[档案 505-1-197,
46b]という言葉が現れる。ここで言う「法」とは明らかにその裁判において取られた措置を意
味しているので、過去に採用された措置に照らして判決が下される場合もあったことが分かる。
これが判決内容が上述のように比較的に安定する所以でもあろう。
184 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
3.5. 判決の執行判決の中では鞭打ちや枷、罰畜の刑罰が最も多く用いられた。鞭打ちに関しては裁判記録文書
上には鞭で打つ回数のみが述べられるに止まり、執行人が誰であってまたどのような鞭が使われ
たのかなどの情報は一切記されていない。
枷の刑罰は犯人が手足に鎖をかけられて領催の監視下で蘇木内の各戸を転々と回らせる形で実
行され(注 41)、また受刑者と家族の面会は禁止されていた(注 42)。
また罰畜の執行方法は以下の 2つの事例の中に見て取れる。
① 王の文書。ダーマル・タブナン erkemendü、bayansangと〔蘇木〕章京 tusatuたちに命ずる。
タブナン nomonȷ̌iγを彼のアルバト arslanが訴えた裁判において罰として取り上げた一・九畜
と五畜(注 43)を〔nomonȷ̌iγから〕取って arslanに与えてからここへ報告せよ。このために
命じた。〔三月〕初一日[档案 505-1-171, 17b]。
② 王の文書。ダーマル・タブナンの norȷ̌ob、uqaγantu、čilaγutuとタブナン čibaγaに命ずる。čoqorを罰して取り上げた三・九畜とタブナン čibaγaを罰して取り上げた二・九畜の計五・九
畜の中から三・九畜を数通りに速やかに備えておけよ。法に従って他の旗に渡す罰畜である
ため、決して怠ってはならない。このために命じた。同(三月初一)日。〔蘇木〕章京sayiȷ̌iraquに〔送達させた〕[档案 505-1-171, 19b]。
事例①では、タブナンに対する罰畜の刑罰はダーマル・タブナンと蘇木章京が共同で行うことに
なっており、またその執行結果についてはザサグ衙門に報告するようになっている。事例②はタブ
ナンと平民に対する罰畜没収の執行であり、3人のダーマル・タブナンがその任に当たっている。
この 2つの事例の中で、罰畜没収の執行にダーマル ・タブナンの参加が要請されたのは、罰せ
られた当事者の中にタブナンがいたためだと思われる。また①からは蘇木章京もダーマル ・タブ
ナンと共同でタブナンに対する罰畜没収の執行に参加し得たことが分かる。なお罰畜の対象者が
全員平民であった場合は、罰畜没収の執行は在地権力者が行ったと推測される。
4.私的裁判の実態
上記 3では旗内における公的裁判の手続きについて、ザサグ衙門に提起された訴訟の処理を中
心に明らかにした。しかし全ての事案が公的裁判によって処理されていたとは考え難く、また 3
の冒頭でも指摘したように、現実には訴訟は全てザサグ衙門(ないしチョールガン)に提起され
たのではなく、地方において在地権力者などに提起されて処理されることもあった。
では地方における私的な裁判はどのような仕方で行われていたのだろうか。その実態を明らか
にするため、本章では 3件の案件処理の実例を紹介する。その際これらの諸事例を便宜上それぞ
185東北アジア研究 16号(2012)
れ「事例一(蘇木章京ジャヤートによる人命案件)」、「事例二(僧侶バートルによる窃盗案件)」、
「事例三(タブナン・バダラホの諸案件)」と呼ぶことにする。
4.1. 事例一(蘇木章京ジャヤートによる人命案件)同案件は同治 10(1871)年 5月 19日付の裁判記録文書[档案 505-1-487, 98b-106b]に記され
ているものであり、事件の概要は次のようなものであった。同(1871)年 2月に社の長である金
頂子 γomboȷ̌iγの脱穀場で火災が起きたが、同村の漢人の協力を得て火は途中で消された。その
後 γomboȷ̌iγは火災の原因は箭丁 ögedeleküの放火によるものであるとの疑いを抱き、彼を扎蘭等
級の蘇木章京 ȷ̌ayaγatu(ジャヤート)に訴えた。そこで 4月 15日に ȷ̌ayaγatuは ögedeleküを逮捕し、
羊舎の中で吊して拷問した。ögedeleküが吊されている間に γomboȷ̌iγは彼の頬を強く捻ったりし
ていた。ところが ögedeleküはその場で死んでしまい、そこで ögedeleküの隣人たちが ȷ̌ayaγatuを
ザサグ衙門に訴えた。
案件処理の段階ではザサグ衙門と案件の関係者、調査者との間で計 8通の文書がやり取りされ
ており、これらの文書を提出順に並べると下記のようになる(なお、「→」は文書の提出先を示す)。
①訴 状 :箭丁 doγtosi、sülȷ̌im、liȷ̌ inbou、debelkü → ザサグ衙門
②報告文 :蘇木章京 ȷ̌ayaγatu → ザサグ衙門
③命令文 :ザサグ衙門 → 扎蘭 kičiyeltü
④訴 状 :僧侶 ȷ̌amiyangsirab(死者の弟)→ ザサグ衙門
⑤請願書 :タブナン danzanbalȷ̌uur(死者のノヨン)→ ザサグ衙門
⑥報告文 :扎蘭 kičiyeltü → ザサグ衙門
⑦請願書 :タブナン danzanbalȷ̌uur → ザサグ衙門
<口頭命令 :ザサグ衙門 → タブナン danzanbalȷ̌uur>
⑧請願書 :タブナン danzanbalȷ̌uur → ザサグ衙門
以下、訴訟の提起から判決が下されるまでの案件処理の全過程を上記の諸文書に基づいて叙述
しよう。ögedeleküの死について、まずは同じ村に住む箭丁 doγtosi、sülȷ̌im、liȷ̌ inbou、debelküたちがザ
サグ衙門に訴状を提出して ȷ̌ayaγatuを訴えたが(①)、それに次いで訴えられた ȷ̌ayaγatuもザサ
グ衙門に文書を提出してこの事件についての報告を行った(②)。ȷ̌ayaγatuが提出した報告文に
おいては、
……γomboȷ̌iγの脱穀場で放火したことを証言する村人 ürgümbou、ösge、urtu、bötügemȷ̌i、buyan-ölȷ̌eiたちを召喚して〔ögedeleküを〕尋問したところ、ögedeleküは放火したことを認めて
供述しました。但し彼と一緒にやった人がいるかいないかについて取り調べている途中、彼は縛
186 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
られた場所で死んでしまいました。……
と記載されており、これによると ögedeleküは死ぬ前に放火の事実を認めたことになっている。
ところが、上記①の訴状においては、ȷ̌ayaγatuは「偽の供述を作り」、死んだ ögedeleküに罪を「な
すり付けている」と述べられている。つまり、ögedeleküによる放火の事実を巡っては原告と被
告の言い分は最初から食い違っていたのである。
そこでザサグ衙門は ȷ̌ayaγatuの上官に当たる地方在住の扎蘭 kičiyeltüに文書を送り、死体を保
管して事件の真相を解明すると同時に、当事者と関係者らを召喚してザサグ衙門に送るように命
令した(③)。
しかし時を置かずして、死者の弟である僧侶 ȷ̌amiyangsirabがザサグ衙門に訴状を提出し、以
下のように訴えた。即ち 4月 15日に ȷ̌ayaγatu、γomboȷ̌iγ、γomboȷ̌iγの伯父 oyuudai、伯父の妻で
ある dingsiyangたちが共謀し、ögedeleküを呼んで血が出るまで殴打した。それを聞いた ögedele-
küの妻 tügemeが現場に駆け付けようとしたが、dingsiyangは彼女を引きずって家の中へ入れて
閉じ込め、現場に行かせなかった。tügemeが家から出られたのは ögedeleküが死んだ後のことで
あった。その後 ȷ̌amiyangsirabは死体を見に行ったが、彼らは死体を見せなかった。このような
仕打ちを受けたことに対して極めて不満である、と(④)。
また被害者のノヨンであるタブナン danzanbalȷ̌uurもザサグ衙門に文書を送り、「この事件の真
偽を弁別して処理し、ögedeleküの冤罪を晴らして頂けませんか」と請願した(⑤)。これはȷ̌amiyangsirabが danzanbalȷ̌uurにも事件を報告したためであった。danzanbalȷ̌uurが提出したこの
請願書は ȷ̌amiyangsirabの提出した訴状と共に kičiyeltüに送られた。
そうしたところ真相解明と召喚護送を命じられた kičiyeltüがザサグ衙門に文書を送り、事件の
取り調べについて以下のように報告した(⑥)。
……私 kičiyeltüは自ら事件現場に到着し、死体は少しでも動かしてはいけないと命令し、〔さ
らに〕箭丁 delgerと ikenggeの二人に死体を見張らせました。そして扎蘭等級の〔蘇木〕章京ȷ̌ayaγatu、金頂子 γomboȷ̌iγ及びその他の関係者を召喚しましたが、その間に死者の近親であるögedele、toγmid、debou、qoȷ̌igir、tüsiyeltü、僧侶 sarandaiたちが文書を呈して〔次のように〕請
いました。「ögedeleküはもともと病気があり、ȷ̌ayaγatuたちが彼を吊したところ病気が重なって
あいにく死んでしまいました。乱暴に殴られたことはないと言われています。私たち sarandaiとögedeleは死者の近親であるので、彼らの間で訴訟沙汰が起きることを平気で見ていられません。
そこで私たちは彼らを調停し、γomboȷ̌iγに死者の法会を行ってもらったうえ、死者の妻と子供
に生計を支えるための五十畝の耕地を与えて係争を終わらせようと勧めました。これに対して双
方は同意していますので、調停した通りに係争を終結させて頂けませんか」と。また死者の弟で
ある僧侶 ȷ̌amiyangsirabと死者の妻である未亡人 tügemeの二人も文書を呈し、「ögedeleküは病気
があったため、ȷ̌ayaγatuが彼を吊したところ病気のことが重なって死んでしまいました。乱暴に
187東北アジア研究 16号(2012)
殴られていないのは事実です。このため甘んじて親戚の調停した通りに係争を終わらせたいです。
今後は決して追訴したりしません」と許しを願いました。更に、死者の姉妹側と妻の実家側もが
それぞれ文書を呈し、係争を〔調停したと通り〕終わらせて頂けないかと願いました。そこで、
私 kičiyeltüは僧侶 ȷ̌amiyangsirab、未亡人 tügeme、〔蘇木〕章京 ȷ̌ayaγatu、金頂子 γomboȷ̌iγ及び調
停を行った ögedele、tüsiyeltü、僧侶 sarandai と証人 ürgümbou、doγtosi、sülȷ̌im、liȷ̌ inbou、de-
belkü、ösge、urtu、bötügemȷ̌i、領催 sampil、buyan-ölȷ̌eiたち関係者を召喚して揃え、彼らを彼ら
から受け取った画押のある〔誓約〕文書と一緒にザサグ衙門に送りました。
つまり kičiyeltüは命令された通りに死体を保管して事件当事者や関係者を召喚してザサグ衙門に
送ったものの、検死や実況見分を行ったり関係者から事情を聴取したりして事件の真実を明らか
にしようとはしなかった。それは被害者側と加害者側との間で和解が成立し、被害者側が事件の
追及を取りやめたからであった。また現地では被害者の親族および妻側の親族が和解の成立を証
明するため、今後は本案件について訴追をしない旨の誓約書を kičiyeltüに提出した。
そしてその後、ザサグ衙門では法廷が開かれ、当事者や関係者に対する尋問、および、和解と
これに関連する誓約書の内容について再度確認する作業が行われた。ところがそうして判決内容
が討議されている時点で今度は danzanbalȷ̌uurがザサグ衙門に次のような文書を提出した(⑦)。
……事件は死者の弟である僧侶 ȷ̌amiyangsirabが所轄のノヨンたる私に報告したため、私は所
轄のノヨンの立場から人を使って取り調べに行かせましたが、ザサグの処は既に扎蘭 kičiyeltüを
派遣して取り調べを行っていました。しかしその取り調べの間に死者の近親が調停を行い、死者
をザサグの処とタブナンの私に知らせずに葬ろうとしました。これについて考えてみれば、öge-
deleküの僧侶たる弟 ȷ̌amiyangsirabは以前に文書を呈して極めて不満であると言ったのにも拘わ
らず、今は何の根拠もなく人命案件を和解して終わらせようとしています。これは疑わしいです。
できれば、勝手に堂(tangkim)をつくり拷問を施して人を死なせた件と、勝手に出訴したり和
解したりした件とを区別して処理頂きたいです。
即ち、danzanbalȷ̌uurは兄の死について「極めて不満」であったはずの ȷ̌amiyangsirabが人命案件を
和解により終結させようとしたことに対し疑問を呈し、この件に関しては、勝手に法廷(注 44)を
設けて人を拷問した件とは分けて、「勝手に出訴したり和解したりした件」として改めてその原
因を追究してほしいとザサグ衙門に請願したのである。ところが上記⑦の内容から明らかなよう
に danzanbalȷ̌uurは当事者間の和解の条件につき情報を得ないままにこの請願書を提出している。
また同書をザサグ衙門に送って来た danzanbalȷ̌uurの護衛である fuȷ̌i {fugi}は ȷ̌amiyangsirabをdanzanbalȷ̌uurの処へ連れて行こうとしたが(注 45)、看守役の蘇木章京 aqalaiに拒否された。こ
れがザサグ衙門に報告されると、ザサグ衙門は danzanbalȷ̌uurに対して、「死者の弟と妻が追及し
ないことを所轄のタブナンが追及している。その本当の狙いが、ögedeleküが病気ではなくただ
188 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
殴られて死んだことを知っていて人命を追及したいのか、それとも人命は追及しないこととし、ȷ̌ayaγatuたちが勝手に堂をつくったことだけを追及したいのかのどちらにあるのかを説明して報
告せよ」と口頭で問い質して命令した(注 46)。
つまり danzanbalȷ̌uurがザサグ衙門に案件の処理を請願したにも拘わらず、ザサグ衙門で取り
調べ中の ȷ̌amiyangsirabを連れて行こうとしたことに対して、ザサグ衙門は困惑したものと見ら
れる。
そして上記の口頭命令に対して danzanbalȷ̌uurは以下のような報告文を提出して返答した(⑧)。
〔人命案件は〕ögedeleküの妻と弟および親戚が全員一同で追及しないと言いましたが、それで
も所轄のタブナンに誓約したことを聞かせて〔係争事件を〕終わらせるべきであります。事件を
未解明のまま終わらせたことにより事後は後悔し、蒸し返して再び争うことが起こらないように
と気にかかって〔以前にザサグ衙門に〕文書を呈したのであります。ȷ̌ayaγatuと γomboȷ̌iγたちが
誤って ögedeleküを殴り死なせた件は旗内のモンゴル人アルバトの間で起きた事件であるため、
どうぞザサグの処から法のとおり処理して頂けますようお願いします。皆に負担をもたらさない
ために恐れずに報告したものです。
この報告文を受けてようやく判決が下された。判決の冒頭では、
調べてみると、モンゴルの旗で強盗(qulaγai degerem)や人命に関わる案件が発生した場合、
当該地のジンセテンとダルガたち(tere γaȷ̌ar-un alban ȷ̌ingseten daruγa nar)が調査して終えると〔犯
人と関係者を〕直ぐにザサグの処に送って審理させるべきである。軽微なものは審理して結審す
るが、重大なものは地方衙門に移送して処理する。これは決まった原則(toγtaγsan yoso)である。
……
と述べられ、旗内の命盗案件処理の一般原則が引用されている。そして判決の内容は以下のよう
なものである。i 人命案件については死者の親族の意思に従って追及しないこととする。ii ögedeleküの死について、最初は拷問によって死んだと訴えられたが、後には拷問ではなく
吊したところ病気が重なって死んだと供述されており、供述の真偽は判断し難いものとなっ
ている。本来ならば彼らの和解を無効とし、審理を通じて真相を解明するべきであった。し
かし人命案件はもはや追及する者がいないのでザサグ衙門も取り調べをしないこととする。iii ȷ̌ayaγatuは犯人をザサグ衙門に移送するべきであったが、勝手に法廷を設けて人を吊して拷
問したため、彼の扎蘭等級を剥奪し、蘇木章京職を免職とする。iv γomboȷ̌iγは「些細なこと」で ögedeleküを逮捕させて拷問させ、また自らも ögedeleküの頬
を強く捻ったりした。そこで彼の金頂子の等級を剥奪し、社の長の職を免職とする。
189東北アジア研究 16号(2012)
v ȷ̌amiyangsirabと doγtosi、sülȷ̌im、liȷ̌ inbou、debelküの最初の訴えと後の供述が相互に矛盾し
ていることから、彼らは「誠実でいい人」ではないことは明らかである。本来ならば取り調
べて処罰するべきであるが、人命案件を追及しないことになったので処罰は免じる。しかし
その代わりに厳しく叱責し、今後は同じようなことが発生しないように監視する。vi danzanbalȷ̌uurは所轄のノヨンの立場から人命事件を報告したのであり、後はザサグ衙門によ
る処理を仰いでおれば良かった。しかし danzanbalȷ̌uurがその後事件の処理に関与したのは
不適切である。ザサグ衙門が公務を司る時にタブナンに許可を請うというような法(qauli)
は一切存在しない。またザサグ衙門に看守されている取り調べ中の者を、所轄のタブナンが
召喚して連れて行こうとしたことは正しくない。これらのことをタブナン danzanbalȷ̌uurに
言い聞かせる。vii fuȷ̌iがザサグ衙門で取り調べ中の ȷ̌amiyangsirabを所轄のタブナンの処に連れて行こうとした
件については、もし fuȷ̌iが自らの意思でそうしたのであれば、danzanbalȷ̌uurは自ら彼を処罰
するべきである。
4.2. 事例二(僧侶バートルによる窃盗案件)本案件は、同治 10(1871)年 2月 27日付の裁判記録文書[档案 505-1-487, 27b-46a]に記され
ている、僧侶 baγatur(バートル)による 2件の窃盗事件の処理を巡るものである。案件処理の
流れ及び判決内容を整理すると下記のようになる。
同治 9(1870)年 12月に僧侶 baγaturが僧侶 bodiの家から金銭と衣服(debel)を盗んだが(注 47)、
逃げている途中で bodiに捕らえられ、baγaturは自分の父 qaraükerの家に送られた。次の日、 qaraükerと baγaturは金銭と衣服を bodiの家に持って行って返却した。
窃盗事件は bodiによって社の長かつダーマル ・タブナンである sayičingγaと蘇木章京 lotaに報
告された。しかしその後寺院側が僧侶 möngkeölȷ̌eiを sayičingγaたちの処に送り、事件をザサグ
衙門に報告せずに現地で解決するよう請願した。またタブナン γarudiも同様な申請を行った。
そこで sayičingγaたちは「皆に迷惑になることを考慮して(olan-u čirügdel-i bodoȷ̌u)」請願を受け
入れ、事件の処理を寺院側に一任した。寺院側は baγaturを僧侶身分を剥奪して寺院から除籍し
た上で、父 qaraükerに寺院の一日分の「茶(mang ȷ̌a)」を提供させることにし、以上のことをsayičingγaたちに文書で報告した。但し寺院側は窃盗事件自体は処理できないものと見なし、baγaturを sayičingγaと lotaに引き渡そうとした。ところが baγaturが sayičingγaたちに引き渡さ
れる前に、タブナン medeltüと牌頭 ündüsüが案件の処理を行った(注 48)。即ち medeltüとündüsüは baγaturを銅銭 40,000枚で罰して案件を解決するよう sayičingγaたちに報告し、了承を
得たのである。その後、baγaturは銅銭 25,000枚を sayičingγaと lotaに渡した(注 49)。この事件
はこうしていったん解決をみた。
しかしこの事件の後、同(1870)年 6月に起きたタブナン出身の僧侶 čoγtanの家から衣服が
盗まれたという事件が出来し、これも baγaturの仕業ではないかと疑われた。そこで寺院側は再
190 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
び baγaturを捕らえて殴打しつつ尋問した。baγaturは čoγtanの衣服を盗んだことを認めたが
(注 50)、盗品である衣服の代価たる銅銭 6,000枚を čoγtanに賠償しなかったために、medeltüはqaraükerから一頭のロバを強制的に取って čogtanに与えた。これに対し、qaraükerは不満を持ち、
妻と息子の ȷ̌anaと共に čoγtanの家に赴き、罵詈雑言を投げ掛け、更に戸口に石を投げるなどした。
このようなことがあったため čoγtanはロバを medeltüに渡し、後者はこれを元の所有者であるqaraükerに返却した。čoγtanの兄であるタブナン mergenの供述によれば、彼が qaraükerたちの
かような横暴を sayičingγaに報告したにも拘わらず、sayičingγaは適切な処理を行わなかったと
いう。また mergenはこの件を蘇木章京 palȷ̌iに報告して sayičingγaと共同で qaraükerを捕まえさ
せようとしたが、sayičingγaは同様にこの請願を黙殺したとされる。
そこで翌年(同治 10〔1871〕年)の 2月 12日に社の長 vangčinbolは別の社である niruγulquの
右翼社に赴き、当社の長であるタブナン damingと驍騎校 lotaに対して baγaturと qarčaγai
(注 51)の逮捕を勧めたが、「所轄の社には社の長かつダーマル・タブナンである sayičingγaがい
るので、私たちは当社の人を逮捕しに行くべきではない」と言われて拒否された。しかし翌日vangčinbolは社から蘇木章京 palȷ̌iを呼び、彼と共に再び damingと lotaの処に赴いて、「貴方たち
に窃盗犯を告発しているのに逮捕しないと言うのは適切なのか」と言って再び犯人の逮捕を促し
たところ、damingと lotaはついに了承した。damingと lotaは人を派遣して寺院側から事情を聴
取し、baγaturの窃盗の事実を証明する文書を受領した。damingと lota、palȷ̌iは vangčinbolに案内されて qaraükerの家に到着し、彼と ȷ̌anaを逮捕した。
但し張本人の baγaturは留守中であったので彼を捕らえることはできなかった。damingと lota、palȷ̌iは baγaturの行き先を知るために qaraükerを殴打した。また vangčinbolたちは qaraükerの 2
頭のロバと 2頭の牛を銅銭 47,300枚で売り、qaraükerと ȷ̌anaの拘置に必要な費用やザサグ衙門
まで押送するための旅費とした。baγaturは、結局判決が下された時点でも逮捕されていない。
ところで、この事件は čoγtanとその弟であるタブナン buyan-ölȷ̌eiが sayičingγaと蘇木章京 lota
を訴えた際に初めてザサグ衙門の知るところとなった。čoγtanと buyan-ölȷ̌eiの訴えは、sayičingγa
と蘇木章京 lotaが案件を審理せずに baγaturを銅銭 40,000枚で罰して釈放したこと、および、baγaturが čogtanの衣服を盗んだと自ら認めたにも拘わらず、彼らの父 qaraükerは賠償を行わない
どころか、妻と息子と共に čoγtanの家の戸口と窓を損壊し悪罵したことを糾弾するものであった。
ところがザサグ衙門が訴えを受けて当事者たちを召喚しようとしていたまさにその時に、damingと驍騎校 lotaは共に文書を提出し、qaraükerと ȷ̌anaを逮捕したこと、および、qarčaγaiを
逮捕したが勾留中に逃したことを報告した。また一方で、vangčinbolと mergenも共に文書を提
出し、baγaturと qarčaγaiが窃盗を行ったと sayičingγaと蘇木章京 lotaに報告したにも拘わらず、
彼らが両名を逮捕しなかったため、damingたちに逮捕させたと報告した。
その後、上述の sayičingγaと蘇木章京 lotaがザサグ衙門に到着したことを受けて、法廷におい
て全当事者の尋問が行われた。この時、審理の途中で vangčinbolの数々の不正を告発した訴状がsayičingγaと章京 lotaにより提出されている(判決 iiiを参照)。
191東北アジア研究 16号(2012)
本案件は管旗章京 olȷ̌ibai、liyül、梅林章京 sayintai、梅林等級の蘇木扎蘭(注 52)sudnam、文書ハ
ファン(注 53)頭等護衛 uriya、文書ハファン扎蘭等級 soγtorの 6人によって審理され、その後
判決原案はザサグに報告された。ザサグは判決原案に vangčinbolを杖で 40回打つことを付け加
えた上で(判決 iiiを参照)、他は原案の通りにするよう命令した。判決の内容を整理すると以下の
ようになる。i sayičingγaと蘇木章京 lotaが窃盗案件をザサグ衙門に報告せず自身の裁量で処理し、被疑者
baγaturから罰金を徴収したことは適切とはいえない。また sayičingγaは以前に自身がvangčinbolを自分の社の長に推挙したにも拘わらず、今になって彼が「本分を守らないこと
を起こすかもしれない」と述べるなど、その行動は矛盾している。そこで sayičingγaと蘇木
章京 lotaを一・九畜で罰する。また被疑者 baγaturから徴収した銅銭 25,000枚を戻した上で
所轄の蘇木に渡して保管する。sayičingγaが賄賂を受領して被疑者 qarčaγaiを釈放したと訴
えられた件については、qarčaγaiが逮捕された時点で改めて審理することとする。ii čoγtanは baγaturに窃盗の事実を強引に認めさせた上で、baγaturの父 qaraükerからロバを徴
収し、さらに後者との間に揉め事を引き起こした。また čoγtanと buyan-ölȷ̌eiが vangčinbol、daming、mergen、驍騎校 lotaと手を組んで悪事を働いたのは不適切である。そこで 2人を厳
しく叱責する。iii vangčinbolは本案件以外にも以前に相続人のいない todorqaiの耕地を横領したことがあるの
で厳重に処罰すべきである。しかし彼は謝罪しており、また甘んじて罰を受けようとして
いる。そこで罰を減じて七畜で罰し、qaraükerのロバと牛を売って得た銅銭 47,300枚は彼とdamingと驍騎校 lotaから没収して蘇木の財産とする。また以前、彼は有印文書(tamaγatu
bičig)を送達せずに隠匿したとして sayičingγaを相手取り虚偽の訴えを提起しているが、こ
れは罪が重いため、杖(qabtaγai)で 40回打つ。なお彼が蘇木の耕地を横領したり、漢人を
受け入れて自分のところに住まわせたりしたと訴えられた件については、所轄のダーマル ・
タブナンと扎蘭に命じて取り調べさせることとする。iv damingと palȷ̌i、驍騎校 lotaが社の長である sayičingγaに報告せずに事件に関与したのは誤り
である。またその際に逮捕した被疑者を逃がしてしまったことについても責任を負わねばな
らない。一方、寺院に居住する僧侶 baγaturが盗んだのは同じ寺院の僧侶のものであるため、
本窃盗事件は baγaturの実家とは無関係である。それにも拘らず baγaturの父を逮捕したうえ、
彼の牛とロバを売却してしまったことは誠に不適切と言わざるを得ない。また damingは以
前に γarudiが彼を訴えたこと(注 54)で γarudiに恨みを抱き、γarudiの親戚である qarčaγai
を逮捕することによって γarudiを事件に巻き込もうとしたことが明白である。このような
人物は厳重に処罰しないと不徳の人が更に増えるであろう。そこで damingと palȷ̌i、驍騎校lotaを一・九畜で罰する。
v mergenはこの窃盗事件を徒におおごとにし人心を騒がすことに加担したものの、尋問され
ると当事者の誰一人についてもその事情を詳細に話すことはできなかった。このことから彼
192 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
はただ事後に物を分けてもらうこと(ed qubiyaȷ̌u asiγlaqu)を目論んでいたのであり、他に
は企みがなさそうである。そこで彼を一畜で罰する。vi qaraükerには息子 baγaturの盗んだものを隠匿した罪は認められない。但し qaraükerには平
時において自分の息子を良く教育しなかったという責任が認められるため 50回鞭打つ
(注 55)。
vii ȷ̌anaが兄 baγaturの窃盗を知らないというのは信じ難いものであり、嘘の供述をした可能性
が高い。また彼は父 qaraükerと一緒に čoγtanの家の前で喧嘩をしたため、ȷ̌anaを 30回鞭打つ。
4.3. 事例三(タブナン・バダラホの諸案件)
4.3.1. タブナン・バダラホについてタブナン badaraqu(バダラホ)が引き起こした諸案件については、嘉慶 3(1798)年と嘉慶 10
(1805)年に右翼旗が理藩院へ送った二通の公文書(注 56)に基づいて紹介する。ここではまず
嘉慶 3年の公文書に依拠しながら badaraquの人物像について触れて置こう。badaraquは右翼旗に嫁いで来た和碩端静公主(注 57)の孫であり、四等タブナンの爵位を持っ
ていた。父であるタブナン namsaiは皇室の婿(額附)であり、その妻との間に möngkeölȷ̌eiとい
う息子が生まれた。また namsaiは侍女の qai氏を妻として迎え入れているが、この qai氏との間
に生まれた息子が badaraquである。つまり möngkeölȷ̌eiは badaraquの異母兄である(注 58)。badaraquは凶暴かつ残忍な人物であったという。
乾隆 51(1786)年に理藩院による命令を受け、右翼旗にあった和碩端静公主の 11蘇木のアル
バトは孫の möngkeölȷ̌eiと badaraquが均分して相続することになり、二人にそれぞれ 5つの満蘇
木と 1つの半蘇木のアルバトが割り当てられた。
4.3.2. 嘉慶 3 年の公文書に見える諸案件badaraquは乾隆 57(1792)年から同 59(1794)年にかけて、次のような 3件の人命案件を引
き起こし、それぞれについて理藩院による処罰を受けた。1件目は、乾隆 57(1792)年 4月に自らの奴隷 engkeȷ̌abを殴り殺した案件である。badaraquは
engkeȷ̌abが彼の背後から彼を撃つような真似をしたとして、engkeȷ̌abを殴打し死亡させた。理藩
院は badaraquを三・九畜で罰し、また engkeȷ̌abの母と兄を badaraquの管轄から解放した。2件目は、同(1792)年 11月に自分の奴隷 nimaを殴って殺害した案件である。狩猟に出かけ
た badaraquは nimaの家に行ったが、小熊を捜し出せなかったため(ötege-i eriȷ̌ü oluγsan ügei-yin
učir-tu)nimaを殴り、彼を死なせてしまったという(注 59)。理藩院は、badaraquが非常に凶暴
かつ残忍な性格を持っているため、法の通り三・九畜で罰するだけでは彼を戒めることができな
いとし、彼を五・九畜で罰した。また nimaの妻と息子及び親戚のアルバトは badaraquの管轄か
ら解放された。
193東北アジア研究 16号(2012)
3件目は、乾隆 59(1794)年に自らの奴隷 tümenを殴り、彼を自殺させた案件である。この案
件は同年 8月に右翼旗から理藩院に報告された。理藩院は badaraquのタブナン身分を剥奪した
上で、駐防官とジョスト盟長に命令し案件を審理させた。彼らが審理して理藩院に報告したとこ
ろによれば、tümenは badaraquの殴打を受けたことにより自分を刺して死んだという。理藩院
は tümenの妻と息子及び親戚のアルバトを badaraquの管轄から解放し(注 60)、彼が持つ 5つ
の満蘇木と 1つの半蘇木のアルバトは没収して兄の möngkeölȷ̌eiに与えた(注 61)。また理藩院
はこの時 badaraquに以前剥奪した四等タブナンの爵位を再び与えているが、同時に右翼旗のザ
サグに対し、彼を直接に厳しく叱責した上で監視下に置くよう命令した。
4.3.3. 嘉慶 10 年の公文書に見える諸案件嘉慶 10年の公文書には、badaraquが自分をザサグに訴えた自らのアルバトに対し処罰を行っ
た諸案件の記録が存在している。即ち嘉慶 6(1801)年に badaraquの管轄下にある各蘇木は、badaraquが過度にアルバを徴収したとして彼をザサグに訴えた(注 62)。badaraquを訴えたのは3つの満蘇木と 5つの半蘇木の代表者たちであり(注 63)、訴えを先導した彼らは全員 badaraqu
によって処罰された。処罰内容は、蘇木章京 terčinの蘇木の場合以下のようなものであった。
まず、badaraquを訴えた驍騎校 sembeleは五畜、箭丁 lotaと asaraltu、gönčinはそれぞれ三畜
で罰せられ、この 4人からは一畜を銅銭 3,600枚に換算した上で、家畜の代わりに計銅銭 50,400
枚がbadaraquにより徴収された。また箭丁učaraltuは五畜で罰せられ、彼の場合は一畜が銅銭 2,000
枚で換算され、計銅銭 10,000枚が徴収された。
つまり蘇木章京 terčinの蘇木の場合は、badaraquを訴えた 5人は家畜で罰せられたが、その際
家畜は金銭に換算された。しかし一畜の換算方法は二通りあり、箭丁 učaraltuの場合は一畜が銅
銭 2,000枚で計算されたのに対し、それ以外の 4人の場合は一畜当たり銅銭 3,600枚で換算され
ている。badaraquが行った処罰が如何に恣意的であったのかがここから見て取れる。
嘉慶 10年の公文書の中には、badaraquがアルバトに対し刑罰を執行した事例がこの他にも見
出される。例えば badaraquは箭丁 dardaγが娘を無断で売ったとして、dardaγと彼を管轄する蘇
木章京 badaγの二人をそれぞれ三畜で罰して 50回ずつ鞭打ったという。
また badaraquは自分の借金を肩代わりして返済しなかったとして、典儀(qafan)sebeg ȷ̌igを嘉
慶 9(1804)年 12月 22日に 50回、28日に 120回それぞれ鞭打ったという。その結果、sebeg ȷ̌ig
は重傷を負い歩行することができなくなった。ザサグ衙門は蘇木章京 samyangに命じて sebeg ȷ̌ig
の傷跡を調べさせた。取り調べの結果によると、sebeg ȷ̌igの左右の太ももは肉が断裂し、その跡
には穴が 1つずつできあがっていたといい、またこのとき断裂した肉と言われている一握りの肉
片は家族が紙に包んで持っていたとされる。さらに、胴体の胸部より下は腫れ上がり、右の足と
太ももは骨と皮だけになっていた。このことから sebeg ȷ̌igが相当の重傷を負っていたこは明白で
ある。
このように badaraquは自分のアルバトに対し刑罰を実施することさえしていた。彼が下した
194 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
罰畜や鞭打ち等の刑罰には上述のように相当の恣意性が認められる。かかる振る舞いが継続し得
た背景として、彼の特別な政治的地位を指摘することができる。即ち上述したように、公主の孫
である badaraquはザサグと同等の政治的地位を有し、それが故にザサグや協理たちの命令を無
視することさえあったのである(注 64)。
また badaraquによる数々の悪行や過重なアルバ徴収に対して、彼のアルバトが直ちに訴え出
なかったのは、「一つにノヨン・アルバトの定め(noyan boγol-un ȷ̌irum)を考慮し、二つに罰を
受けることを極めて怖がっていた」ためであるとされる。「ノヨン・アルバトの定め」とは、ア
ルバトは自分のノヨンに服従するものであり、背いたり訴えたりしてはいけないというほどの意
味であろう。2つ目の理由については、badaraquを訴えた者は上記のように badaraqu本人によっ
て処罰される一方、他方では連座されて理藩院による処罰をも加えて受ける可能性があったと理
解することができる。例えば badaraquが以前に起こした 3人の人命案件の処理の際、理藩院はbadaraquに事件を起こさせたとして配下の扎蘭と蘇木章京等をも罰したというからである[档案505-1-236, 20a]。
5.社会における裁判の位置
5.1. 裁判と政治秩序さて上記 4で紹介した諸事例に見られる私的裁判の様子についてここで一旦まとめることとし
よう。
まず事例一は、放火の疑いが持たれた箭丁 ögedeleküが扎蘭等級の蘇木章京 ȷ̌ayaγatuと社の長
である金頂子等級の γomboȷ̌iγたちに拷問されたあげく死亡した案件がザサグ衙門に持ち込まれ
処理されたというものである。この事例については次の二点に注目すべきであろう。1つは、ögedeleküが放火したのではないかとの訴えがザサグ衙門ではなく ȷ̌ayaγatuのもとへと持ち込ま
れ、 ȷ̌ayaγatuもまた ögedeleküをザサグ衙門に引き渡さずに自ら法廷を設けて拷問したという点
であり、2二つ目は、死者の弟 ȷ̌amiyangsirabが人命案件を所轄のノヨンであるタブナンdanzanbalȷ̌uurに報告し、後者は自ら人を派遣して人命案件の取り調べを行おうとしたという点
である。この二点からは、当事者が事件を蘇木章京や所轄のタブナンに訴え、これをうけて蘇木
章京やタブナンがアルバト(箭丁)の事件をザサグ衙門に直接報告せずに自ら取り調べを行うこ
とも有り得たという当時の事案処理の実態の一面が明らかになる(注 65)。
ついで事例二は、僧侶 baγaturの窃盗事件が地方において処理しきれず、結局ザサグ衙門に訴
えられたというものであり、このことからは以下に述べるような地方における事案処理の実態が
看取される。1つ目は、baγaturが僧侶 bodiの金銭と衣服を盗んだ事件の処理の方法に関するも
のである。即ち、タブナン medeltüと牌頭 ündüsüは、被疑者から罰金として銅銭 40,000枚を徴
収することで案件を処理すべきであるとする判決原案を作成し、この判決原案は社の長かつダー
マル ・タブナンである sayičingγaと蘇木章京 lotaに承認され、事案はそれに従って最終的に処理
195東北アジア研究 16号(2012)
された。さらに baγaturは僧侶であったため、所轄の寺院は彼の僧侶身分を剥奪したうえで寺院
から除籍し、そのうえ彼の父 qaraükerに寺院の一日分の「茶」を提供させている。第二は、タ
ブナン出身の僧侶 čoγtanの物品が盗まれたことに関するものである。即ち、このケースではbaγaturは寺院で殴打された結果、窃盗を認めたため、medeltüは baγaturの父である qaraükerか
ら盗品の対価として一頭のロバを強制的に徴収し čoγtanに与えている。しかし qaraükerによる
暴力的な抵抗を受けて čoγtan がロバを返却したため、事件の処理は失敗に終わり、結局 čoγtan
がザサグ衙門に訴え出ることになったのである。つまり事例二からは、窃盗案件が地方で在地権
力者やタブナンにより如何に処理されたのかという問題について、その具体的な様子が明らかに
なるのである。
最後の事例三は、公主の孫であるタブナン badaraquによる 3件の人命事件を含めた諸案件か
ら成り立っている。このうち人命案件はいずれも理藩院に報告されたうえで処理されているが、3件目の人命案件においてわざわざ駐防官と盟長が案件の審理を命じられていることから分かる
通り、公主の孫である badaraquの案件は右翼旗のレベルで審理することが不可能であった。た
だここで注目すべきは、badaraquにより刑罰が実施されていたという事実である。即ち badaraqu
は命令違反や叛逆行為に従事したと見なした自らのアルバトや奴隷に対して鞭打ちや罰畜の刑罰
を実施したのであるが、このことから彼が自分の管轄下にあるアルバトや奴隷間の係争事件を処
理することも可能であったとの見方も生じる。
以上のことからは、訴訟はザサグ衙門やチョールガンに提起されて処理されるべきであるとい
う公的原則があるにも拘らず、地方では地方有力者による私的かつ自律的な事案処理がなされて
いたという結論が導かれる。このような裁判の構造は、旗内の政治秩序と社会編成のあり方と密
接に関係しているように思われる。即ち、在地権力者や貴族はザサグの支配下に置かれながらも、
他方では地方において「地方有力者―地域」や「貴族―アルバト」といった図式に則った領域的・
属人的な支配を行っていたのであり、彼らが自律的に行う裁判はその支配体制の一環として位置
づけることが可能となるのである。
5.2. 裁判と社会また、上述の 3つの事例を社会生活の観点から考察してみるならば、下記のような裁判の諸特
徴が抽出できるだろう。
まず、人命案件の処理には死者の親族の意思が最も重視されたという特徴が挙げられる。事例
一では、人命案件がザサグ衙門に持ち込まれるものの、取り調べの途中で死者の親族が加害者側
と和解して追及を取り止めたことにより、ザサグ衙門は本件をこれ以上追究しないとの決定を下
している。つまり、死者の親族の意思を尊重することでザサグ衙門が敢えて人命案件を追究しな
いということも有り得たのである。またこのことは、ザサグ衙門における人命案件の裁判では死
者の親族の意思が加害者に与える刑罰の軽重に影響を及ぼすこともあったことを示唆している。
次に、訴訟は当事者や関係者に少なからぬ経済的利益や損失をもたらすものであったことが指
196 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
摘されよう。事例二では、案件が現地で処理される段階で有名無実な社の長であるタブナンvangčinbolが別の社にいる在地権力者たちに被疑者 baγaturを逮捕させようとしている。しかし
その人物は baγaturを捕らえることができず、代わりに彼の弟と父 qaraükerを逮捕した。さらにvangčinbol等は押送の費用を捻出する名目で qaraükerのロバと牛を売却している。窃盗事件の被
害者でもない vangčinbolが被疑者の逮捕を先導したのは、私利目当てであった可能性が高い。ま
た裁判を通じて私的な利益を得ることが当時の社会において決して珍しくなかったことは、本事
例におけるタブナン mergenに対する判決内容から直接に窺い知ることができる(判決 v)。この
ような私的な利益の源としては、犯人の拘置や押送といった名目の費用のほか、加害者側から被
害者側に引き渡される罰と和解のための金銭や家畜、耕地等が挙げられるだろう(注 66)。
上に述べたように訴訟により利益を得る者がいる一方で、犯人の親族が訴訟の結果、大きな損
失を被ることがあった。それは、犯人に科される財産刑はその親族が連帯負担することがあった
からである。例えば事例二で社の長 damingが盗人 qarčaγaiを逮捕しようとしたのは、qarčaγaiに
対する罰を彼の親族たる γarudiにも負担させるためであったとされる(判決 iv)。また在地権力
者が現地で事件を取り調べたり判決を執行したりする際の旅費は当事者が負担するのが通例で
あった(注 67)。ザサグ衙門における訴訟のコストが高かったことは、案件の地方レベルでの終
結を促進する 1つの理由と成り得たのであろう。
また訴訟は復讐行為を生み出すものでもあった。事例二では damingは以前自分を訴えたこと
のある γarudiを恨んでいたため、彼の親戚である qarčaγaiを逮捕し処罰させることにより彼に経
済的な打撃を与えようとしている(判決 iv)。また、事例三では人命案件の処理の際に死者の家
族や親族がタブナン badaraquの管轄から解放されている。これは、裁判の結果罰せられた bada-
raquが、死者の家族と親族を復讐するのを避けるためであったと考えられる(注 68)。また犯人
を逮捕した者が、捕まえた犯人から復讐されることもあった(注 69)。
なお右翼旗では主人が自分の奴隷に対し私刑を実行したり、タブナンが侍女にそれを行ったり
することが珍しくなく、私刑が行き過ぎて人命が害されることもままあったが、その結果裁判に
かけられ有罪となった主人の側が、逆恨みして被害者の親族に復讐を行うケースさえあったこと
が史料から窺える(注 70)。
6.結 論
清代のハラチン ・モンゴルの右翼旗では、訴訟はザサグ衙門またはチョールガンに提起される
のが公的な原則であった。ザサグ衙門に持ち込まれた訴訟の殆どはザサグ衙門において処理され
たが、一方で耕地争い等の軽微な案件は地方の在地権力者やダーマル・タブナンにその処理が命
じられ、また事例三に見えるような政治的地位の高い者に関する案件は理藩院に上申されて処理
された。
ザサグ衙門で行われる裁判では、印務処官員は通常合議体の形で案件を審理してから、判決原
197東北アジア研究 16号(2012)
案を作成してザサグに上申した。判決は、判決原案に対するザサグの同意または修正を経て、印
務処官員の口から当事者に言い渡された。その後、判決内容は書記によって档案に記録された。
ザサグは通常、印務処官員が行う案件審理には参加しなかった。
ザサグ衙門の裁判における当事者及び関係者の召喚や現地検証、判決の執行等の事務は在地権
力者やダーマル・タブナンに命令して実行させるのが通例であった。当事者及び関係者のザサグ
衙門への押送は、在地権力者とダーマル ・タブナンが自分で、または、他者に命ずることでこれ
を実行した。また、現地での取り調べはその任に充てられた在地権力者とダーマル ・タブナンが
自ら執り行ったが、結果を報告するに当たっては彼等自身がザサグ衙門に赴くこともあれば、文
書を送ってその内容を伝達することもあった。更に判決を執行したのも上述の通り、在地権力者
やダーマル・タブナンであった。判決はザサグの命令という形式を採ったが、案件が抱えている
諸状況が総合的に考慮されて下されるのが通例であった。判決における法的な措置は比較的安定
したものであった。
一方、在地権力者やダーマル・タブナンがザサグ衙門の命令を受けて審理を行う場合には、当
事者と関係者を一同に召喚しそれぞれの言い分を聴くという審理方法が採られ、また解決案に不
服な当事者は、当該在地権力者やダーマル ・タブナン本人または彼らに命ぜられた別の者によっ
て関係者と共にザサグ衙門に送られた。
なおザサグ衙門の裁判における召喚や現地検証、判決の執行と、地方に命じて行う事案処理で
は、当事者や関係者が貴族であった場合はダーマル・タブナン、アルバトであった場合は在地権
力者が遣わされるのが原則であった。
以上はザサグ衙門が行う公的裁判の一般的な手続きである。しかし地方では地方有力者による
自律的な事案処理つまり彼らによる私的な裁判も行われており、右翼旗における裁判の全体はザ
サグ衙門と地方の二極構造を有していたと言える。裁判のこうした政治的構造は、ザサグ衙門と
地方という旗内の政治秩序を反映するものであると同時に、地方における在地権力者および貴族
による領域的・属人的な支配の継続に由来するものと考えられる。
また本稿で紹介した諸事例から、人命案件の処理に当たっては被害者の親族の意思が重要視さ
れたこと、訴訟は関係者に少なからぬ経済的利益や損失をもたらすこともあったこと、更に、訴
訟は復讐行為を引き起こす場合もあった等の諸点が指摘され得た。
付記本稿は日本学術振興会平成 22年度特別研究員奨励費による研究成果の一部である。原稿作成
の段階では寺田浩明氏(京都大学大学院法学研究科教授)、磯貝健一氏(追手門学院大学国際教
養学部准教授)から多くのご教示を賜った。また、本稿の大部分の内容については第 8回中央ア
ジアの法制度研究会(於:静岡大学、2010年 12月 4日)において口頭発表を行っており、その
際参加者より有益なご指摘を頂いた。更に二名の匿名の審査員から本稿の内容に関して貴重なご
指摘を頂いた。以上の方々に衷心より感謝の意を表する。
198 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
注(1) モンゴルの伝統的な裁判制度に関する先行研究としては、判決記録集や法典に基づいて裁判制度の概要を示し
た窪田(1984)、田山(2001)と、裁判関係文書に依拠して刑事裁判制度の実態を解明した萩原(2006)とがある。但し、前者については、この手法によっては現実の裁判の様子を描き出すことができないという問題が存在する。また後者は、使用する裁判関係文書の殆どが、刑事裁判を行うために旗とその上級の役所の間でやり取りされた行政文書であるために、民事的な裁判も含めた旗内の裁判の全体像を描き出していないという問題点を抱えている。そして何よりも、モンゴルの各地域に特殊性が存在することが既に広く想定されている以上、清代モンゴルの裁判制度を研究するに当たっては、まず特定の旗に焦点を当てた実態解明が必要不可欠であると筆者は考えている。本稿はまさにその作業の一環として位置づけられる。なお管見の及ぶ限りでは、ハラチン・モンゴルの裁判制度に関する研究は現在までなされていない。
(2) 本稿で扱うハラチン・モンゴルについては八旗に編成されたハラチン部のモンゴルを含めていない。ハラチン三旗の中で右翼旗は崇徳元(1636)年、左翼旗は順治 5(1648)年、そして中旗は康煕 44(1705)年に設けられ、トゥメド左翼旗は崇徳 2(1637)年に設立された。ハラチン中旗は右翼旗から分離した旗である。右翼旗の総人口は不明であるが、乾隆 55(1790)年の蘇木数は 43とされる(内蒙古自治区档案館所蔵档案[以下、档案と略す]504-5-1771)。またジョスト盟にはこれらの旗以外にトゥメド右翼旗があった。
なお上記の「档案 504-5-1771」における番号は档案館側の档案目録の登記方法に基づくものであり、順に 「全宗号」「目录号」「巻号」を指す。また他の档案番号の中に現れる葉番号は档案館のスタッフが枚数順に書き加えたものであり、引用の際には一葉の表裏を aと bで区別して記した。
(3) 清代中国の 1里はメートル法で換算すると 576メートルに相当し、また 1斗は 10.355リットル、1頃(100畝)は 614.4アール、1両(10銭)は 37.3グラムに相当した[小川・他 1973 : 1224]。以下同様。
(4) なお右翼旗に居住していた漢人は行政上同旗に管轄されていなかった。漢人は当初は理藩院の理事通判、後には建昌縣に管轄されその長官たる「縣丞」によって管理された。その変遷の詳細は次の通りである。即ち『塔子溝紀略』巻三によると、理藩院は乾隆 6(1741)年(『承徳府志』では乾隆 4[1739]年)に塔子溝というところに理事通判を配置して漢人の管理を行わせた。またその翌年には塔子溝に衙署及び市街地を建てたのであり、それが所謂塔子溝庁であったものと思われる。『承徳府志』巻三十二(職官三)によると、塔子溝庁は乾隆 43(1778)年に建昌縣に変わり、またその理事通判が「理事通判管建昌縣事」へと改称された。しかし、嘉慶 16(1811)年には建昌縣に「縣丞」という縣の長官が新たに配置された。理事通判は満洲と蒙古八旗出身者によって担われたが、「縣丞」は最初の赴任者が満洲八旗出身の者であるのを除けば全員漢人であった。なお塔子溝はハラチン左翼旗の領内に位置していた。
(5) 本稿で用いる裁判記録文書は筆者がこれまでに閲読を果たせた 7冊のみであり、それぞれ乾隆 14(1749)、乾隆 21(1756)、嘉慶 3(1798)、道光 4(1824)、道光 28(1848)、光緒 8(1882)、光緒 28(1902)年に作成されたものである。これらの裁判記録文書はおよそ 150年間をカバーするものであるため、この 7冊から清代の右翼旗における裁判制度の全体像を窺うことは可能であろうと筆者は考えている。本档案館には裁判記録文書の档案が他にも多数保管されているが、そられに対する調査は今後行う予定である。
(6) 右翼旗では 11世代の計 14人のザサグがその任に当たっており、ザサグ 1人当たりの平均在位年数は 20年弱(最短 1年最長 49年)である[金海・他 2009 : 32-33]。なおザサグの上司としては盟長や上述の理事通判等の清朝中央からの駐防官が存在した。
一方で、清朝はモンゴルの貴族に対して爵位を与えていたのであり、その爵位は高い順から和碩親王(qošui čin vang)、多羅郡王(törö-yin giyün vang)、多羅貝勒(törö-yin beyile)、固山貝子(qosiγun-u beyise)、鎮国公(ulus-un tüsiye güng)、輔国公(ulus-tur tusalaqu güng)があり、また固有の貴族であるタイジ(台吉)とタブナン(塔布囊)には更に一等から四等までの等級が付与されていた。そしてこのうち王公は典儀長(長吏、ȷ̌ iγsaγal-un daruγa)や典儀(ȷ̌ iγsaγal-un tüsimel)、護衛(kiya)といった従士を有することができた。『理藩院則例』ではその人数は、和碩親王は典儀長 1、四品典儀 1、五品典儀 1、一等護衛 6、二等護衛 6、三等護衛 8;多羅郡王は典儀長 1、五品典儀 1、六品典儀 1、一等護衛 6、二等護衛 4、三等護衛 5;多羅貝勒は五品典儀 1、二等護衛 6、三等護衛 4;固山貝子は六品典儀 1、三等護衛 6;鎮国公と輔国公は七品典儀 1、三等護衛 4と規定されている。
なお右翼旗のザサグに付与された爵位の中では多羅郡王の爵位が順治 7(1650)年から代々世襲(「世襲罔替」)となっている[『王公表伝』巻二十三]。
(7) 町田[1905 : 149]によれば、清末期の右翼旗のザサグ衙門には印務所(処)と管事所、長史所という 3つの機関が設置されていた。このうち印務処は文書、司法及び旗下の政務及び財務を掌り、長吏所は地方吏、郷長等
199東北アジア研究 16号(2012)
一般官吏の監督進退を掌り、管事所は王室の儀式、財務等王室に属する百般の事務を掌ったとされる。(8) 汪国鈞[2006 : 98]によれば、清末期、右翼旗には協理タブナンが 3名、管旗章京が 1名、梅林章京が 2名、
扎蘭章京が 8名いた。(9) 扎蘭章京のうち印務処に勤務するのは通常 2、3名程度であり、残りの扎蘭章京は地方にある実家で公務に携
わった。印務処に勤務する扎蘭章京とそれ以外の扎蘭章京とが定期的に交替していたのかどうかについては不明である。
(10) これについて一例を挙げるならば後述の「扎蘭等級の蘇木章京 ȷ̌ayaγatu」(4.1を参照)の如くであり、これは蘇木章京 ȷ̌ayaγatuが扎蘭章京の等級を持っていることを意味する。これに対して表 1に見える「蘇木章京tayipingbou」のような等級を持たないで清朝の制度による職位のみを有する場合もあった。なお協理タブナンが等級を持たないのは、協理タブナンには元から清朝の爵位が与えられているからであり、また領催はアルバの徴収や刑罰執行等の雑役を負担していたために等級が付与されなかったであろう。
(11) 「社」ないし「太平社」とは犯人捕獲に当たって「保」を超えて広範な協力を得るために設置された司法上の単位である[档案 504-9-798; 502-1-547, 38a]。「社の長」は「一切の窃盗事件を厳しく取り調べて〔犯人を〕逮捕する職務のある者」[档案 502-1-547, 41a]とされる。社の長の任命はザサグによる認可を受けねばならなかった[档案 505-1-487, 39a]。なお「保」とは保甲制における行政的単位であり、その来歴については注12を参照。
(12) なお保甲制についてハラチン中旗の档案には、「保正と甲長の制度を模倣してダーマルとダルガを設置した」という記録が存在しており[档案 505-1-1085]、恐らく右翼旗でも保甲制が同様な形で導入されたのであろう。保甲制がいつからハラチン ・モンゴルに導入されたのかについては今後調査する必要がある。
(13) なお「領域」や「地域」の語は筆者が便宜的に付した呼称であり、档案中で使用される術語ではない。一方、「旗(qosiγu)」や「村(ayil, bölög)」、また「社(še)」や「保(bou)」は実際に当時使われていた行政用語である。
(14) 例えば档案 502-1-10(tngri-yin tedkügsen-ü qorin naimaduγar on qaraγčin qonin ȷ̌il-dür qosiγun-u dotura tarqaγsan dangsa debter ene bulai[乾隆 28〔1763〕年癸未年に旗内に発給した文書])からは、sibege γool、köndelen、qayidaγa、ničügün、niruγulqu、ibegel、öb、qota、kebüd、sibartai、boltoγ、niru、quyaγ、čilaγun ongγoča、türgenなどの領域が知られる。なお档案 502-1-10は档案館の分類上はジリム盟ホルチン右翼后旗のものとされているが、内容から実際は右翼旗の档案であることが分かる。
(15) 档案 505-1-470(ȷ̌akiya daγaȷ̌u, qariyatu ȷ̌akiruγsan še doturaki murui, ȷ̌anggi-yin ayil, čimed, bayiča naran ȷ̌erge-yin ayil bölög-ün ȷ̌ingseten, albatu nar-un aman toγa nere nasu ȷ̌il-i todorqayilan bičigleȷ̌ü erüke ȷ̌akirqu daγamal daruγa talbiȷ̌u medegülügsen debter[命令に従い、所轄の社の中の murui、ȷ̌anggin ayil、ȷ̌ imed、bayiȷ̌a、naran等の村落におけるジンセテン、アルバトの人口・名前・年齢を調べて記録し、戸を管理するダーマル、ダルガを配置して報告する冊子]).なお「アルバト」とは貢租賦役の負担者を指す。「ダルガ(長)」はここでは十戸長(arban ger-ün daruγa)を指している。
(16) 同档案では qayidaγaという領域名は明示されていない。しかしながら別の档案(505-1-487, p153)には、「qa-yidaγa-yin ȷ̌anggin ayil-un süme(qayidaγaの ȷ̌anggin ayilの寺)」という表記があるので同档案は qayidaγa領域を扱うものであると推定される。なお qayidaγa領域にはモンゴル人のほか、漢人も居住していたと推測されるが、この档案には漢人の名前は記載されていない。これは、漢人が行政上旗に属していなかったためであると思われる。
(17) 「インジ(inȷ̌i)」とは新婦が嫁ぐ先に持参して行く女子や家畜を指し、それらは「インジの人(inȷ̌i-yin kü-mün)」や「インジの家畜(inȷ̌i-yin mal)」と呼ばれたりする。
(18) 各蘇木はその蘇木を管轄する蘇木章京の名前で呼ばれた。例えば「蘇木章京 tayipingbouの蘇木」とは蘇木章京である tayipingbouの管轄する蘇木の意味である。
(19) 王とは右翼旗のザサグ多羅杜稜郡王の略称であり、このうち「杜稜(dügüreng)」とは称号である。この事例では王とはザサグの radnasidiのことを指している。なお右翼旗ではザサグ職を持たない閑散王公(sula vang güng)に当たる鎮国公と輔国公の爵位があったほか、時期によっては固山貝子の爵位も存在した。『王公表伝』巻二十三を参照。また鎮国公と輔国公は「公」とも略称される。
(20) 従って村々の実際の戸数とモンゴル人口は表 1で示したよりもやや多いことが想定される。(21) 例えば「比丁」(原則三年毎に行う成人男性の調査)時のタブナンに対する調査はダーマル・タブナンが行っ
ていた[档案 502-1-10, 38b-39a]。(22) 右翼旗では全蘇木は nutuγ(29蘇木)と qota(5又は 6蘇木)・kebüd(5又は 6蘇木)という 2つの地理的空
200 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
間に区分されていた。nutuγの蘇木は qotaと kebüd以外の旗内領域に分布する各蘇木を指し、旗によるアルバ分配は qota・kebüdの蘇木よりも多かった[档案 502-1-10]。つまり逆に言えば、nutuγの蘇木に比べてqota・kebüdの蘇木は特別な集団として扱われたのである。蘇木の中には箭丁 150人を満たす満蘇木(dügüreng sumu)もあれば、その半分の箭丁で編成される半蘇木(qondoγo sumu)もあった。例えば qotaの諸蘇木を例に見れば、嘉慶 10(1805)年には 3つの満蘇木と 5つの半蘇木が存在し、併せて「5つの満蘇木・1つの半蘇木」と呼んでいる[档案 505-1-236, 21b-44a]。また qotaの蘇木は同一年において「qotaの 5蘇木」或いは「qotaの 6蘇木」と記されることがあり[档案 502-1-10, 16b, 23b]、恐らく 5つの満蘇木・1つの半蘇木の状態が 5または 6蘇木と混同して呼ばれたのであろう。なお qota・kebüdの蘇木は後述する端静公主とその夫であり後にザサグ職を免ぜられた γalsangに統轄されていた蘇木である可能性が高い。档案 505-1-201(10a-19a)によると、乾隆 51(1786)年に端静公主の 11蘇木のアルバトは 2人の孫が相続し、2人にはそれぞれ 5つの満蘇木と 1つの半蘇木が割り当てられた。
(23) ただ蘇木ごとに負担した「定額の白いアルバ」がタブナンたちにどのような仕方で分配されたのかは不明である。
(24) 右翼旗におけるアルバト 1人の負担するアルバの量は不明であるが、同じハラチン・モンゴルの左翼旗について乾隆 43(1778)年の扎蘭 sayintu所轄の蘇木章京 serengȷ̌abの蘇木のアルバ報告文の中にアルバト eldebが納めたアルバの額に関する具体的な情報が存在する。つまり「アルバト eldeb、一人。旗のアルバとして銅銭百六十四枚を納めました。自分のノヨンのアルバとして、六月に tabunの活仏のところで十日間働きました。九月には射撃手の馬丁を十日間やりました。十一月はqorqoγ山のkebüd蘇木の炭を yeke gerへ運び届けました。『定額の白いアルバ』として粟一斛を納めました。」[档案 503-1-207, 1b]。
(25) 档案 504-1-36, 52b-54b.なお随丁が旗のアルバを負担したか否かについては右翼旗の事情は未解明であるが、ハラチン左翼旗では随丁が旗のアルバを免ぜられていたことからすれば[档案 503-1-207, p1]、右翼旗でも同様であった可能性が高いと言える。
(26) 例えば嘉慶 3(1798)年には皇帝にアルバを提供するタブナンが 106名いた[档案 505-1-201, 5b-10a]。但しそのアルバの内実は不明である。
(27) 例えば档案 505-1-201(5b)には「我が旗の eldeü蘇木のダーマル todoの管轄するタブナン……」と書かれている。他に档案 505-1-236(4b)も参照。
(28) 地籍整理局[1937a : 716-718]。なおハラチン・モンゴルにおける土地関係の詳細に関しては同(1937a)と(1937b)、天海(1943)を参照されたい。
(29) 裁判記録文書には通例、口頭で訴えた場合は「……が不平不満を言った言葉の中に(……γumudaγsan ügen-dür)」[例えば档案 505-1-197, 8b]と現れ、訴状をもって訴えた場合は「……が文書を呈して[訴えるに](……bičig bariȷ̌u [ȷ̌aγalduγsan anu])」[例えば档案 505-1-323, 13a]と表現されている。なお訴状の原文は未見である。
(30) チョールガンにおける裁判の詳細は不明であるが、チョールガンそのものについては次のようなことが知られている。チョールガンは一般に「ホラル(qural)」つまり会議と呼ばれた(本注では「ホラル」を用いる)。右翼旗では毎年の 9月にザサグ衙門でホラルが開催されていたのであり、この定例のホラルは「九月のホラル(yisün sara-yin qural)」と呼称されていた[档案 505-1-10, 26a; 505-1-323, 54a]。「九月のホラル」について道光 4(1824)年の裁判記録文書に、「今年の 9月 2日にザサグの処でホラルを開いて旗内の各種の公務を調べて処理するために、扎蘭、〔蘇木〕章京と驍騎校たちに対して一人も残らず指定した日にザサグの処に集まるよう早くから文書を送って命令した。……」[档案 505-1-323, 39b]と記されている。また光緒 28(1902)年10月 1日付の裁判記録文書には、「毎年の 9月に扎蘭章京たちとジンセテンたちを集めて旗内の公務を商議して処理することは、昔より定まった制度(iȷ̌aγur-ača toγtaγsan dürim)である。……」[档案 505-1-547, 頁番号未記載]と記録されている。即ち「九月のホラル」では旗内各地からジンセテンたちが集められて公務処理のための会議が開催されたのである。その際にジンセテンたちは未解決の案件を討議したり、訴訟を報告して処理したりしたものと思われる。「九月のホラル」は通常 1日に開かれるが[档案 505-1-10, 26a]、上記の如く 2日に開催される場合もあった。「九月のホラル」における裁判は、恐らくは後述するザサグ衙門に提起された訴訟のケースと同様に、印務処官員が中心となって裁判を審理したのであろう。
一方、右翼旗ではザサグ衙門における「九月のホラル」以外にもホラルが開催されることがあった。例えば嘉慶 3年の裁判記録文書からは「aburaquのホラル」や「γanȷ̌uur寺のホラル」といった開催地の名前で呼ばれるホラルが知られており、また当該ホラルでは訴訟も処理されたという[档案 505-1-197, 47b-48b]。但しこれらのホラルの開催日時は不明である。
(31) 本稿では「裁判」を支配者が被治者の非行や紛争に対して行う一方的かつ終極的な裁断行為として捉える。
201東北アジア研究 16号(2012)
この定義に基づけば、右翼旗における裁判についてはザサグが主宰する裁判と地方有力者による自律的な裁判とに大きく 2つに区分することが可能である。前者は公的、後者は私的裁判に属し、また前者にはザサグ衙門における裁判とチョールガンにおける裁判との 2つの方式が含まれる。なお後述する在地権力者やダーマル・タブナンがザサグの命令を受けて現地で事案を処理する行為は前者に属する。
(32) ここで言う「公」とは閑散王公の輔国公 lhaȷ̌abのことを指していると思われる。lhaȷ̌abは乾隆 20(1755)年に輔国公の爵位を父 arabtanから継承し、乾隆 49(1784)年には同爵位が代々世襲となった[『王公表伝』巻二十三]。
(33) 同治 10(1871)年 7月 1日付の裁判記録文書に現れる、梅林章京と驍騎校が職務違反に関わった裁判は「王が自ら審理し(vang noyan beye-ber sigüküi-dür……)」ている[档案 505-1-547, 頁番号は未記載]。
(34) 例えば档案 505-1-487(138b)には、「王が大司を見ていた時に……(vang noyan yeke se üȷ̌eȷ̌ü bayitala……)」と記されている。
(35) 印務処官員が 1人で案件を審理することも稀に見られる。例えば乾隆 21(1756)年の裁判記録文書では梅林süȷ̌ügtüが 1人で案件を審理してザサグに上申している[档案 505-1-63, 10a-b]。また協理タブナンが案件審理に参加することもあった。例えば上記裁判記録文書では、協理タブナン ačituは 3つの案件の審理に参加している[档案 505-1-63, 3b; 5b; 7a]。
(36) 当時の「奴隷(ger-ün köbegüd {kebüd}, boγol)」の法的身分については今後検討する必要がある。但しこの命令文の内容から、「奴隷」が相当程度の自立した経済生活を送っていたことが想定される。
(37) 扎蘭がタブナンをザサグ衙門へ連行して来るよう命じられる例外もあった。例えばあるザサグ命令文によれば、扎蘭 ningbuが人命案件に関わったタブナン döndöをザサグ衙門に連行して来るよう命令されている[档案 505-1-171, 13a-b]。ただここで言う扎蘭 ningbuについて、彼がタブナンなのか或いは平民なのかを個別的に特定することはできない。
(38) 同事例で梅林等級 sümingγaがタブナンの関係する案件の現地検証に加わったのは、当事者及び現地検証者の中にダーマル・タブナンがいたことによる取り調べの不公正の発生を防止するためであった可能性もあると思われる。
(39) 例えば档案 505-1-63, 6bでは、窃盗を行った「batuは法に従って(qauli-yi daγaȷ̌u)首犯として処すべきであるが、適切に議し(ȷ̌üilčilen kelelčeȷ̌ü)、盗人 batuを鞭打ち百にし、三・九畜で罰して牛の持ち主の milaに与える。batuはこれ以前にも悪逆な窃盗の事件を多く起こし、今なお悪行を止めないので、両手に鎖をかけて所轄の蘇木の者に引き渡すことにする」と記述されており、蒙古例が言及されるのみでその条文が示されていない。なお、ここにいう「九畜」とは家畜による処罰の単位であり、例えば『理藩院則例』巻四十四によると「九畜」には馬 2頭、去勢した牡牛 2頭、牝牛 2頭、3歳牛 2頭、2歳牛 1頭が含まれる。
(40) 「地方衙門(γaȷ̌ar oron-u yamun)」とは理事司員等の駐防官のいる衙門を指していると思われる。軽微な案件は旗のレベルで終結させ、重大な案件は盟長や駐防官に上申するというのが当時の清朝側が定めた原則であると考えられるからである。
(41) 例えば嘉慶 3(1798)年 9月 27日付の裁判記録文書には、盗人 burnai、baγaturたちを「手足に鎖をかけて(γar köl-i ni qadaγad)所轄の蘇木に命じて預かった。……burnaiを蘇木の中で預かる間、彼の伯父である ȷ̌oriγtuの当番であった時に……」と記されている[档案 505-1-197, 76a]。
(42) 例えば嘉慶 3(1798)年 11月 5日付の裁判記録文書には、受刑者 γoyoqorの妻が「三人で僧侶 bayansangの家に行って『私を夫に会わせて頂けませんか』と頼んだところ、これについて bayansangは人を使って領催 sed-kiltüに聞きました。sedkiltüは『夜暗くなってから来て会え』と言いました。……」と書かれている[档案505-1-197, 81a]。
(43) 「五畜」とは前述の「九畜」に含まれる大型家畜のうち、五畜を供出させる刑罰である。例えば『理藩院則例』巻四十四によると、「五畜」には去勢した牛 1頭、牝牛 1頭、3歳牛 1頭、2歳牛 2頭が含まれる。また「五畜」の他に「七畜」や「三畜」、「一畜」の刑罰も存在し、「七畜」には馬 1頭、去勢した牛 1頭、牝牛 1頭、3歳牛 2頭、2歳牛 2頭が、「三畜」には牝牛 1頭、3歳牛 1頭、2歳牛がそれぞれ含まれる[『理藩院則例』巻四十四]。但し「一畜」の畜種については蒙古例に規定が存在しないが、恐らく上記の大型家畜の中の 1頭を指すものであろう。
(44) 原語は「堂(tangkim)」。档案においては、在地権力者がなんらかの事件の関係者を一同に集め、事件の審理を行ったり、場合によっては被疑者を拷問したりすることを「堂をつくる(tangkim ȷ̌okiyaȷ̌u)」或いは「司を設ける(se bayiγulȷ̌u)」と表現する。取り敢えず、ここではこれを「法廷」と訳しておく。
(45) 護衛 fuȷ̌iが取り調べ中の ȷ̌amiyangsirabを danzanbalȷ̌uurの処に連れて行こうとしたことについては、それが
202 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
danzanbalȷ̌uurと fuȷ̌iのどちらの意思によるものであったのかは関連文書には明確に記されていない(後述の判決 viiを参照)。しかしながら、これは danzanbalȷ̌uurの命令によるものであると筆者は考えている。というのも、danzanbalȷ̌uur が ȷ̌amiyangsirabの「勝手に出訴したり和解したりした件」を取り調べるようザサグ衙門に請願したことからも分かるように、事件を自分に報告して置きながら勝手に和解した ȷ̌amiyangsirabに対して danzanbalȷ̌uurは不満を抱くようになったと考えられるからである。danzanbalȷ̌uurは ȷ̌amiyangsirabを召喚して問い質すつもりだったのではなかろうか。
(46)この命令については fuȷ̌iが danzanbalȷ̌uurに伝えたものと見られる。(47) 後に社の長 vangčinbolとタブナン mergenがザサグ衙門に提出した文書によれば、盗んだものの中にはロバも
含まれるとされるが、ロバについては他の供述者は一切言及していない。なお社の長 vangčinbolとは、後述するもう 1人の社の長である sayičingγaが彼を社の長にするようザサグに推薦し許可された者であるが、sayičingγaの供述によれば、vangčinbolが「本分を守らないことを起こすかもしれないと気をつけて」まだ社の中で公布していないという。つまり vangčinbolはまだ正式に社の長に任命されていない者であった。
(48) タブナン medeltüと牌頭 ündüsüが当事者と如何なる関係を有するかは不明である。また、この両者はザサグ衙門に召喚されていない。
(49) この罰金は社が預かっていると sayičingγaと lotaは述べる。(50) qaraükerの供述によると、baγaturが čoγtanの衣服を盗んだと認めたのは、殴打による痛みに堪えられなかっ
たためであり、実際には盗んでいないとされている。(51) 裁判記録文書の中では、baγaturの共犯者は qarčaγaiであり、qarčaγaiはいったん捕らえたものの逃がしてまっ
たという記述が存在するが、詳細な事実関係は不明である。また vangčinbol の訴えによれば、sayičingγaが賄賂を受領して彼を釈放したとされる。
(52)蘇木扎蘭(sumun-u ȷ̌alan)については現在のところ不明である。(53) 「ハファン(qafan)」とは「官」を意味する満洲語であり、「文書ハファン(bičig-ün qafan)」とは字義通り文
書の仕事を司る印務処官員を指すと思われるが、詳細は不明である。(54) 本档案によれば、タブナン damingは自分のアルバトである γarudiの娘を連れて来て使用人としていた。こ
の娘は成人した時点で父に返すべきであったが、damingは娘を父 γarudiに返さずに勝手に売却した。これに対し γarudiは damingをザサグ衙門に訴えたという。
(55) qaraükerに対する鞭打ちについて、原文には「qaraükerは尋問する時に既に鞭打ったが、qaraükerが平時において自分の息子を良く教育しなかった誤りに対してまた 50回鞭打つ」とある。これは「尋問時にもう鞭打っているので今回は 50回に軽減する」と解釈できるだろう。
(56) この二通の公文書は次のようなものである。まず嘉慶 3年の公文書は同(1798)年 12月 8日付の文書であり、档案 505-1-201(10a-19a)に抄録されている。文書の中では、タブナン badaraquが悪行を改めたか否かについての理藩院からの問い合わせに対して返答がなされている。
一方、嘉慶 10年の公文書は档案 505-1-236(11a-51b)に抄録された、右翼旗が badaraquの悪行を理藩院に訴えるためのものであり、文末にはザサグに対して badaraquを訴えたアルバトたちの訴状がそのまま収録されている。本文書には日付がないが、その前後に抄録された公文書の日付が 6月 12日であることから、本文書も同一の日付を持つ可能性が高いと思われる。
(57) 和碩端静公主は康煕帝の五女であり、康煕 31(1692)年に右翼旗のザサグ ȷ̌aši(札什)の次男である γalsang(噶爾蔵)に嫁いで来たという[『清皇室四譜』巻四]。γalsangは康煕 43(1704)年にザサグ職を受け継いだが、同 50(1711)年にその職を免ぜられ、ザサグ職は弟の serengに与えられた[『王公表伝』巻二十三]。和碩端静公主は嘉慶 3年の公文書では「töb kičiyenggüi güngȷ̌ü」と呼ばれている。
(58) なお badaraquの母 qai氏は嘉慶 4(1799)年に死亡し、möngkeölȷ̌eiの母は嘉慶 8(1803)年に死んだとされる[档案 505-1-236, 22a]。
(59) nimaが殴られた原因についてこれ以上は不明であるが、次のような可能性も考えられる。つまり badaraquが捕まえた小熊は nimaの家の周辺で逃がしてしまい、nimaは badaraquに小熊の捜査を命じられたが、それを探し出せなかったために殴打されたという可能性である。これについて今後さらに調査する必要がある。
(60) badaraquの管轄から解放された tümenの家族と親戚は計 37戸であり、これらのアルバトは möngkeölȷ̌eiの管轄下に入ったという[档案 505-1-236, 47a]。
(61) その結果、badaraquに残されたのは箭丁アルバト 13戸と非箭丁(toγso)アルバト 58戸の計 71戸のアルバトであった。なお没収された 5つの満蘇木と 1つの半蘇木のアルバトは嘉慶 10(1805)年の時点では badaraquに戻されている。
203東北アジア研究 16号(2012)
(62) この案件がどこで審理されたのかについては档案には記載されないが、恐らくは理藩院に報告されて処理されたものと思われる。
(63) 3つの満蘇木は terčin、mangqadai、qubituの各蘇木であり、5つの半蘇木は tegülder、badai、balȷ̌id、süiketü、bayantaiの各蘇木である。
(64) 例えば badaraquが自分のアルバトや漢人から奪ったラバや白炭、地租について、理藩院が持ち主に返却するよう命令を下したが、彼はそれに従わなかった。これについて嘉慶 10年の公文書には次のように書かれている。「我々ザサグ及び協理はこれらのことに関して〔執行するようにと〕badaraquにいくら命令しても〔彼は〕我々の命令を全く気にしなかった」[档案 505-1-236, 17a-b]。
(65) なお蘇木章京が地方において拷問を行う例は他にも知られている。例えば協理タブナンによる命令文には次のような事実が記されている。uudalaが留守中に同居していた甥の bürintegüsと uudalaの妻の間で喧嘩が起こり、bürintegüsは自分の財産を残したまま家を出て行き別の親戚の家に住んだ。uudalaの妻は bürintegüsに対して自らの財産を持っていくよう催促したが、bürintegüsは聞き入れなかった。しかしその後 uudalaの家にあった bürintegüsの食糧が盗まれた。bürintegüsは uudalaの妻を疑って蘇木章京 ȷ̌üelに訴えた。ȷ̌üelは uu-dalaの妻を捕まえて漢人とモンゴル人の前で服を脱がせて拷問した[档案 505-1-94, 12b-13a]。この事例は uu-dalaの訴状による一方的な訴えであるのでその真偽に一定の疑問が残るものの、ȷ̌üelが法廷を私設して窃盗事件の審理を行ったり拷問を実施したりした事実自体は疑いのないものであろう。
(66) 例えば乾隆 21(1756)年 3月 10日付の裁判記録文書(档案 505-1-63, 6a-7a)によれば、被害者 milaは盗まれた 2頭の牛をそのまま戻してもらったばかりか、盗人を罰した三・九畜をも受領しており、結果として窃盗事件の裁判を通じて大きな経済的利益を獲得している。
(67) 例えば光緒 8(1882)年 8月 9日付の裁判記録文書における僧侶 ȷ̌alafüngγaの提出した訴状によると、案件の取り調べを行った 3人の在地権力者が彼の家に宿泊し銅銭数万枚を費やしてしまったという[档案 505-1-165, 37b]。
(68) タブナンが自分を訴えたアルバト及びその親族に対して復讐を行った事実は档案 505-1-63(25b-26b)からも確認することができる(注 70を参照)。なお、タブナンがアルバトに対して行う復讐の方法には過度にアルバを徴収することがあった。
(69) 例えば嘉慶 3(1798)年の裁判記録文書には以下のような犯人による復讐の事例が記載されている。即ち、牌頭 mandaquは人を集めて 8頭の大型家畜を盗んだ baγaturと burnaiを逮捕した。両犯人はザサグ衙門で処罰されたが、このうち burnaiは受刑中に逃亡し、mandaquの家の壁に穴を開けて侵入したり、彼の馬を盗んだりするなどの復讐を行ったという[505-1-197, 26a-27a; 76a-79b]。
(70) タブナンが侍女を殴り殺した案件として、乾隆 21(1756)年 10月 27日付の裁判記録文書には次のような事案が記されている。即ち、タブナン dondobdorȷ̌iは自分のアルバトの娘である sentergeを 7歳の時から連れて来て侍女として使っていた。しかし 31歳になった sentergeは男と駆け落ちをした。dondobdorȷ̌iは sentergeを「探し出して連れて来て、懲戒して殴ったところ」彼女は死んでしまった。裁判では dondobdorȷˇiに対し、「今回の事件を原因に恨みを抱き、〔死者の兄弟である〕šongqor、naimadaiの親族たるアルバトを搾取し」ないよう命令が下されている[档案 505-1-63, 25b-26b]。
参考文献<編纂史料>『王公表伝』
全国図書館文献縮微復製中心(2003)『清代蒙古史料合輯』所収の『欽定外藩蒙古回部王公表伝』(2003年版)『承徳府志』
承徳民族師範高等専科学校『承徳府志』点校組(2006)『承徳府志』(光緒朝重訂、木版印刷影印本、遼寧民族出版社)
『清皇室四譜』 (癸亥冬十月上海聚珍仿宋印書局排印)
204 額定其労:清代ハラチン・モンゴルの右翼旗における裁判
『塔子溝紀略』 『遼海叢書』(遼海書社、1934年)第三集所収の『塔子溝紀略』
『蒙古律例』 Баярсайхан, Б. mongγol čaγaȷ̌in-u bičig(2004)所収の『蒙古律例』(モンゴル文、乾隆 54年版、木版印刷影印本、Улаанбаатар)
『理藩院則例』 上海大学法学院 ・上海市政法管理幹部学院 ・張栄铮 ・ 金懋初 ・劉勇強 ・赵音(1998)『欽定理藩部則例』所収の『理藩院則例』(漢文、光緒 16年版、天津古籍出版社)
<その他>天海謙三郎
1943『奮熱河蒙地の開墾資料二則』満鉄・調査局。汪国鈞
2006『蒙古紀聞』(玛希、徐世明校注)呼和浩特:内蒙古人民出版社。及川三男
1914『熱河蒙旗概要』。岡洋樹
2007『清代モンゴル盟旗制度の研究』東京:東方書店。小川環樹、西田太一郎、赤塚忠
1973『新字源』東京:角川書店。金海、斉木徳道爾吉、胡日査、哈斯巴根
2009『清代蒙古志』呼和浩特 :内蒙古人民出版社。窪田新一
1984「『ウラーン =ハツァルト』にみる 18・19世紀モンゴルの裁判制度」『大正大学大学院研究論集』8 : 1-12。珠颯
2009『18-20世紀初東部蒙古農耕村落化研究』呼和浩特:内蒙古人民出版社。田山茂
2001「中世蒙古の裁判制度」田山茂『蒙古法典の研究』79-102頁、東京:大空社。地籍整理局
1937a『錦熱蒙地調査報告 中巻(喀喇沁右旗)』。1937b『錦熱蒙地調査報告 下巻(喀喇沁中左旗敖漢旗)』。
萩原守 2006『清代モンゴルの裁判と裁判文書』東京:創文社。
町田咲吉 1905『蒙古喀喇沁部農業調査報告』。