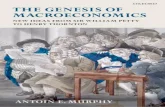Exhibition of Genesis-2
Transcript of Exhibition of Genesis-2
�
2010 年の 9 月に 1 回目の起源展を実施し、それから約半年後の 2011 年 3 月11日に宮城沖で大地震が起きた。その地震は大津波を伴って人間の科学技術の粋の象徴である原子力発電所を破壊した。一回目の展覧会を始める前の 6 月に起源展のイメージを言葉にしていた。————今大人の世界は、イメージに先立つ言葉で膠着(こうちゃく)しています。今までは印刷などによる活字によって言葉も手に取れる所にありました。でも今はモニタの上を瞬く間に現れ消えていきます。人の記憶も同様に外に保存されることで、匂いや雰囲気のような曖昧さを無くしてしまったようです。それは人間だけがこの地球を工場化し、わが物顔で名前を付け終わったかのように。…目の前に世界最大級のカルデラがありました。…あなたはこの火山から何をイメージしますか? 私たちはここに「地球の起源」をイメージします。————この広報用のコピーは、人間存在の危惧感に満ちている。やがて来る自然からの答えを予感するかのように。 2011 年の起源展は、初回の起源展の持っていた見えない自
然の脅威や畏怖をイメージで捉えたものとは結果異なった。大津波によってさらわれていった、東北太平洋沿岸の人の作った町、その歴史、法律、言葉など…瓦礫の山の風景が片時も脳裏を離れることが無かったからだ。そしてイメージが不在の「起源展 2」のポスターが作れなかった。しかし1回目の記録写真を見ているうちに実際行われた事実を告知しようと納得した。
「現実がメッセージ」だということである。 それからの起源展 2 の動きは瞬く間に進みそして、自ら考えていた内容を遥かに超えて人の共感を産んでいった。世界的な環境アーティスト・池田一の参加、若い家族たちの自然食による賄いのグループ、多ジャンル(アート、農業、ジオパークなど)のパネルディスカッションと参加者も交流できた分科会、町長も参加して頂いた盛況なオープニング、ハロとアキさんのキュレーションによるドイツのアーティストたちの環境的なパフォーマンス等 、々この起源展の運動(ムーヴメント)の始めを見た思いがする 2011 年であった。そして 2012 年の起源展 3 は自然とともに運動して行くことだろう。
はじめに 起源展2「現実がメッセージ」だった
三枝泰之(Genesis-2 起源展実行委員/崇城大学三枝研究室)
�
起源展は異なった学問分野にまたがりながら芸術、科学、哲学を通してアプローチしていくことを基に、複合媒体を介してそれらを統合します。公共の空間に着手すると共に、もう一方で自然事象から影響を受けた表現や提示を作り出します。このプロジェクトは特に自然環境に焦点をあてており、また特に熊本は、地球上でも巨大な火山地域の一つに位置しています。それが阿蘇山です。 火山活動は一般的に地球の形成の初期にあたり、地質学のプロセスに関わる全ての人 に々とりましても、もっとも視覚的で壮大な事象です。新しい土地を産み出しながらも、生存の破壊という両面性をもっています。 この点におきまして、火山は体と魂の興奮、危険、苦悩をもたらす自然の側面という関係を人間に経験させます。故に起源展は、火山活動の現象を物質的かつ非物質的解釈で展開していくことになります。 起源展1-2010 年秋に火山地域の主催者による第一回目の視察は以下の点です: 三枝泰之教授が率いる日本の異なる地域から集まった
アーティストと国際的に活躍するアーティストの仲間達がひとつの場所に集う。キュレーターのアキ・ウェンドランドと、地球科学者であり、ハノバーのアートギャラリー Faust の館長であるハロ・シュミットもその一員です。 目的は、約 10 年さかのぼり、その地域との接触を引き継ぎ、「火山地域での暮らし」の側面を彼らの雰囲気も交えて、哲学的、社会学的、科学的に芸術の力を借りながら描写します。公共の場においての展覧会や、ワークショップによる広大な社会的プログラム、パフォーマンス、講義、そしてアート・トレイルの設立によりその地域の人々が現代美術に接する機会を設け、考え、価値、認識の交換を可能にすることができます。 組織のネットワークの構造は、個人に向けても公的参加においても、高森町という小さな町(校長、市長の事務所、アーティスト・イン・レジデンンスを個人で率先)であり、持続的に地域を維持しています。
起源展:国際芸術プロジェクト―火山地域への介入Kurator, Harro Schmidt ハロ・シュミット(Genesis-2 起源展 EUキュレーター)
�
プロジェクトは異なった学問分野にまたがるアプローチに順じ、革新的で環境にやさしい技術を追求します。これは、阿蘇火山博物館の協力によるアート・トレイルの設立を確かにすることも含め、また池辺館長との最初の会話も有意義でした。ドイツ側としては、フランソア・ホルツ(ライプニッツ大学の鉱物学)の助言も受けました。他の協力的なパートナーはチューリッヒにある芸術大学の「デジタル・アート・ウィーク」の編集長、アーサー・クレイ、そしてベルリンで火のパフォーマンスをする「火山の専門家」カイン・カラワンなどです。 最近の自然災害による悲惨な事態が日本において起き、テクノロジーの危険性を垣間見ました。起源展を実現していく際に、環境への社会の認識を高めることが必要です。これは例えば、再生エネルギー(太陽、風力、水力エネルギー)を使った公共の場でのメディアアートなどの展示、熱によるエネルギー、生化学的な火山生体の利用などです。 起源展2:アジアとヨーロッパの五大要素―高森町におけ
る道のアートプロジェクト(アジア人とヨーロッパ人の五大要素―公共空間、高森町)アンナ・グルネマン、クリスティアン・オッパーマン(ハノバー)、イルカ・チューリッヒ(コペンハーゲン)そして 5人の日本人アーティスト、キュレーター :ハロ・シュミット、アキ・ウェンドランド、シチリアの火山を前に、古代ギリシャの哲学は四大要素の理論を展開しました。4 つの要素とは空気、火、水、そして地球です。後にアリストテレス(384-322BC)はエーテル(宇宙空間に存在し光を伝える働きをすると考えられていた化学物質)を第五元素として加えました。アジアでも道教と仏教という自然の観念を交えた理論が出現しました。そして「空の概念」が五大要素の第五番目としてあります。起源展においては 5人のヨーロッパ人と5人の日本人が高森町に集い、この 5 つの要素のアイディアを連動させていきたい。ハロ・シュミット 10.07.2011
Geneis2 では5人のドイツ人アーティストを召還して行われた。自然を構成する5つの要素-水、土、火、木、空気(ヨーロッパではエーテル)は主にパフォーマンスと展示で行われた。慌ただしい生活の中で、自然は風景であり通り過ぎるものでしかない。5人のアーティストはそれぞれの要素を丁寧に抽出し、生活に擦り合せることで私たちの意識を自然へと還元してくれている。もちろんそこには文化圏の違いがあるために、感覚的に擦りあわない場面に日本人は出会わす。ま
たパフォーマンスという形式は時に観客に居心地の悪さを味合わせる。日本にはそういった経験をし、好嫌からわき上がる対話や論争自体が欠けている。言霊思想をもつ日本では論争は敬遠されるが、これこそが近代化をはたしたとされている日本に取り入れるべき訓練である。観客の皆さんはこの展示とパフォーマンスに出会い、それを易 と々体現してくれたことに心から感謝したい。
ご挨拶Kurator, Aki Wendland アキ・ウェンドランド(Genesis-2 起源展 EUキュレーター)
�
Opening Performance制作年:2011
作家名:即興演奏/ヨー・コージ、創作書道/横溝幸治
ボーカリゼーション/水口麿紀
参加者:手前から山村将護、池田一、葉山耕司、堀健祐、
佐藤増夫、高森町町長・草村大成
Tape Cut右から、山村将護、ハロ、荒牧弘幸、高森町教育長・佐藤増夫、
高森町観光協会会長・堀健祐
Opening
Opening Chorusコーラス:はなしのぶコーラス
平成8年 9月、高森中学校PTA活動の一環として「ママさんコーラス」
が発足、翌年高森を代表する花「ハナシノブ」に因み、名称を「はな
しのぶコーラス」と改める。高森中学校文化祭、吹奏楽部定期演奏会、
地元イベント等に出演。県劇での「県合唱祭」にも5回出場。「無理なく、
楽しく、出来る時に……」そして、「継続は力なり」をモットーに現在
15人で活動。童謡、唱歌、日本歌曲、歌謡曲を得意とする。
指導者 工藤のぞみ 代表 堤峰子
�
▲作家紹介手前から:水口磨紀/福永祐生/ takaosuzuki /下城賢一/松本
和子/長瀬崇裕/野島泉里/川嶋久美/井上玲
上色見熊野座神社神楽保存会
▼まかない食堂「根子岳ごはん」地元食材を使った美味しくやさしい自然食ユニット。
賄いメンバー:ちひろ・まさみ・ゆん・くりを
Opening Party
ワークショップ
くんくんウォーク in 高森作家名 :井上尚子( いのうえひさこ )
WS 概要:共に食し、嗅ぎ、語らい、歩き、
日常生活の中で気づかなかったにおいを発見
する楽しい時間を育みました。
プロフィール:1974 年生まれ。女子美術大学非常勤講師。五感を刺激
する空間作品を制作し、主に香りの効用から来場者の記憶回想を促す心
地よい空間を提供している。
�
EU Artists Performance & Installations
Christiane Oppermann, Hanover –
www.mindthepark.de/christiane-oppermann/
Concept for BeijingChristianeOppermann
ras de l´eau (abovethewaterline),2010
Videoprojectioninthepublicspace
作品は時間旅行である。これは「時間の流れ」を暗喩として
示しているショートストーリーだ。Rasde l´eau は現実の
ライネ川を渡る船へと象徴を転化させている。ビデオでは女
性が河の上を飛んでいるかのように滑空してる。画面では
彼女の足は見えず、手はゆっくりとした動きで羽ばたいてい
るように動いている。自然の環境と鳥のような彼女の動きは
ビデオが写されている校舎との時差を露にする。Rasde l´
eau は過去から現在への旅であり、過去の自然と全面の建物
とを混同し、未来へと滑空する。
cajacers_Thorshavn
performance–AnnaGrunemann+ChristianeOppermann
制作年:2010_8.38min.素材 :video
�
Zigeunerschnitzel /intervention–videoinstallation
AnnaGrunemann
制作年:2000/2011_45min.
Space:MinamiASO/28.8.2011/Folkschool/29.8.2011
これは普通のドイツのダイニングキッチンと同じ状況である。
テレビ、電子レンジ、テーブル・・・・。私は 2000年にハ
ノーバーの毎日 800 食もの調理をしている大きなレストラ
ンでドキュメンタリービデオを撮影した。そのビデオ隣には
電子レンジ−これも多くの人々の食生活を支えている。私は
ビデオで流れている料理と同じ料理を用意した。ビデオでは
45分かかって調理されているものが、ここの人々の目の前
では3分で出来あがってくる。観客は私が準備している手順
とモニターに映し出されている映像との違いについて考える
だろう。ここでは料理や食事風景はそれ以上の意味を持ち始
め、観客は観客であると同時に食べている人という意識の交
錯がある。
Whale-Sea lifeHarroSchmidt-Director,Hanover,Germany
古いオーバーヘッド・プロジェクションは、テーマに従った
特殊なイメージのアウトラインと、その異なった過程の動き
を拡大し、射影する。それぞれのイメージは壁や部屋の角や
天井に状況によって映し出される。本展示は、自然を使用す
る人類へのコメント(作品 "sealif" より)の視覚化を目指し
たものである。
Visitors professionilisation in three languages
performance–AnnaGrunemann+ChristianeOppermann
/japanesetranslationAkiWendland
制作年:2011_12min
アートの理解に観客はどんな知識が必要なのだろう?まずは
絵の構成だ。二人のアーティストが観客の前に立ち、世界が
どんな手順で絵になるかを話し始める。阿蘇山の美しい情景
(と同時に切り取られた絵の構成)を前にして、正しい景色の
選び方のおかしなデモンストレーションが始まった。より良
い観客の理解のために英語、ドイツ語、日本語の3つの言語
で行われた。
�0
Fire Jump(ファイア・ジャンプ)制作年:2011
作家名:IlkaTheurich イルカ・チューリヒ
作品説明:ファイア・ジャンプは、火の要素を基に、変容の
側面を強調し、変容の効果を町の道端で公開するパフォーマ
ンスです。
五大要素の理論は Iching(易経)によく似ています。五大
要素はプロセスの段階、もしくは行動の質を表しています。
火の要素はこの場合、構成物質ではなく、ダイナミックに相
次いで起こることを暗示しています。
ファイア・ジャンプは存在する町の地域に直接的に介入し、
その町の構造やプロセスにパフォーマンスが反応していきま
す。パフォーマーは詩的なイメージを作り出し、受けての現
在住んでいる町の見え方を変えることができます。パフォー
マンスは存在する状況に応じて正確なインパクトを与えるた
めに、その場所の詳細な情報の中で発展していきます。
Before...制作年:2011
作 家 名:TomaszWendland/ パ フ ォ ー マ ン ス(byAki
Wendland)
素材 :時計、プラスチック製の箱
作品説明:
3月 11日の津波によせて。日本の東北地方には大津波を経
験した先人が崖の上に「ここより下に家を建ててはならない」
と岩に記し、警告を発していた。2010 年にMMACフェス
ティバル in 仙台で、私はいくつもの時計を燃やした。燃やさ
れた時計のうちの一つは次の日まで鳴り続けていた。私はそ
れが次の年の地震の警告であったことに、その時まだ気づい
ていなかった。熊本でのパフォーマンスは自然の力は人間に
よってコントロールさせるものではないというメッセージで
ある。自然がその力を見せる前に (before...) 私たちはそれを
敬うべきである。
��
国内作家展示「平和への、L 字線分 L-shaped Walks of Peace」制作年:2011
作家名:池田一
作品説明:「LivesonWaterPlanet 水の惑星を生きる」というイ
メージが端的に表現されていて、自然と人間の共生をシビアに提
示するだけでなく、今回の巨大津波による水との闘いを連想する人
もーーー。
日本から世界にいま発信する基本イメージが、「WalksofPeace」
です。現実には、1997以来、アジア各地で撮影してきた写真を使
用します。L字線分は、垂直の「未来に立ち上がる線分」と、水平
の「いまを切り開く線分」から
構成されます。
素材:真竹、干し草ブロック、
写真
��
「平和への、L 字線分 」フィナーレ●9月 24日 夕方6時 30分〜
池田一の「平和への、L字線分L-shapedWalksofPeace」に点火して、
「L文字焼き」をいたします。垂直の「未来に立ち上がる線
分」と、水平の「いま切り開く線分」、「L文字焼き」は、「水
と火」を結びつける重要なイベントとして、位置づけてい
ます。夕闇の中に浮かび上がる「Lの文字」さて、上手く
点火出来るか…。
皆様のご観覧お待ちしています。__告知より
��
サウンド・リノベーション in ASO 2011制作年:2011
作家名:サウンド・リノベーション・バンド(岡崎峻/光永誠
/杉山紘一郎/渡辺融/松岡涼子/小野村頼子/石田耕太郎)
作品説明:昨年のGENESIS起源展に引き続き、高森、
上色見に眠る廃材を使って楽器を創作。人の手を離れて年数
が経ち、雨風にさらされた廃材たちは、独特の形・質感と、
多様な響きの可能性を生み出す。過去の記憶として残された
廃材に注意深く耳を傾けることで、楽器としての新たな生命
が吹き込まれていく。
素材:高森、上色見の廃材
プロフィール:
2010 年春、九州大学大学院の杉山、渡辺、岡崎、光永に
よって結成。廃材特有の質感やその多様性の中から音を見
出し、楽器の制作・演奏を行っている。これまで、文化ア
パート・冷泉荘(福岡市博多区)、旧上
色見小学校(南阿蘇)、臨海3Rス
テーション(箱崎ふ頭)など
で作品を制作・展示。展示
する土地の廃材にこだわ
ることで、楽器の形や
音の響きにその土地
特有の文化・風習が
浮かび上がってくる。
��
「散策者・倫理と芸術」制作年:2011
作家名:野島泉里
作品説明:ここでいう倫理と芸術の関係は、環境倫理学など
の観点とは違って、そもそもの自然に対する感性、つまり詩
心にかかわるものである。森に入るとそこには奥深い神秘的、
もしくは精神的空間が広がっている。森に限らず、風の動き、
潮の匂い、星々への想像力、人間は自分の内面と自然との交
歓を通して限りない豊かさを手にいれることができる。ここ
であえて倫理という言葉を使ったのは、おそらく大昔に比べ
てこの詩心が、人類に不足しているために、地球の破壊が進
んでいるからだ。これは近代文明の負の遺産である。この作
品は阿蘇の森を歩き、静かなる森の精をそっと借りてきたも
のである。
「石彫連山」廊下作品
フォークスクールの廊下に石の彫刻を並べた。私の心には、
根子岳、中岳、帽子岳、杵岳、烏帽子岳といった、阿蘇連山
の悠揚たる姿が広がっていた。古来自然を模した庭園を造っ
た日本人的な感覚だろうか。
Simply制作年:2011
作家名:長瀬崇裕
素材:石
プロフィール:名古屋造形大学4年
��
「子供の領分・Childrens Corner」制作年:2011
作家名:下城賢一
作品説明:
2011 年初夏、初めて旧上色見小学校を訪れた。歴史ある
建物や校庭にはそこで学んだ子供たちの声や息使いをあり
ありと感じることができた。散策するうち教室や廊下の壁
に無数に穿たれた穴に目が止まった。虫食いの穴か?と思っ
て凝視するとそれはこれまで掲示物などを留めるために使
用された画鋲の穴の跡だった。それに気が付いた瞬間、数
多の画鋲が壁を埋め尽くしているイメージが湧いた。「過ぎ
去った時間は消えてしまったのではなく、そこに堆積し、
私にもう一度掘り起こしてもらいたがっている。」帰路に見
上げた夜空には先ほど幻視した画鋲のイメージと重なるよ
うに幾千万の美しい星たちが見えた。
プロフィール:
1972 熊本生まれ
1997 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程壁画専攻 入学
1999 同大学院修士課程 修了
1999 ドイツ学術交流会(DAAD)スカラシッププログ
ラムにより、デュッセルドルフ美術アカデミー マグダレ
ナ・イエテロヴァ教授クラス 入学 2004 年まで同クラ
スに在籍 2006 帰国 熊本在
memories制作年:2011年 8月
作家名:松本和子
素材:ガラスのコップ、土、水、クロス
作品説明:良い思い出が集まっている場所で、かつて小学
生だった彼らの心を表現してみました。現実は混沌としな
がら進み、振り返ればそれらは良くも悪くも思い出として
ゆっくりと水の底に蓄積される。身体のほとんどは水で構
成されており、グラスも体として表現されています。それ
らは物質としての水にとどまらず、記憶が介入した水とし
てです。
プロフィール:
熊本県八代市生まれ、多摩美術大学卒業後、渡米。
現在崇城大学・芸術学部・非常勤講師
主にインスタレーションの作品を国内・国外に発表
��
くうそういきもの制作年:2011
作家名:川嶋久美
作品説明:“たくさんの生き物達にまぎれて、空想の世界の生
き物達も阿蘇の大地に潜んでいるかもしれない”という想像
を元にした参加型作品。会場には風・草・影・雲をモチーフに
した網と、その側に用紙を置く。観客に、それらの網で捕まえ
られそうな生き物を空想して描いてもらい、会場に並べて展
示することで様々な空想上の生き物が集まる場を作った。
素材:虫取り網、ネット、ビニール
プロフィール:
1983福岡に生まれる
2005九州芸術工科大学芸術工学部画像設計学科 卒業
2007九州大学大学院芸術工学府芸術工学専攻 修了
2009 河原町アワード2009ミドリネコ賞・ゲスト審査賞
2010河原町アワード2010 HRD賞
2011河原町アワード 2011 BEPPUPROJECT 賞・スー
パーホテル賞
命と思い 制作年:2011(プルタブ集め10年・制作1ヶ月)
作家名:福永祐生
作品説明:「気持ち(内面)を見てほしい」今までもこれから
もそんな作品を作っていけたらと思います。
素材:プルタブ・針金
プロフィール:1991年 7月 21日誕生ペンネーム・翻輪可
御船中学卒業/御船高校普通科芸術コース卒業/崇城大学芸
術学部/みんなで創る御船舞台の会団員/劇団ゼーロンの会
団員
��
阿蘇の神々御座す処制作年:2008〜 2010
作家名:長野良市
作品説明:最近の作品制作の取り組みにピンホール写真があ
る。今回はデジタル一眼レフカメラによるゾーンプレートを
試みた。被写体は阿蘇の自然と生活風景のなかに、神々の存
在感を感じたものを選んだ。
素材・インクジェットペーパー(局紙)
プロフィール:1957年阿蘇生まれ
1981年青山学院大学卒業
1983年日本写真芸術専門学校 報道写真(樋口ゼミ)卒業
以後、阿蘇を拠点に「東アジアの中の九州」をテーマに写真
家活動 写真集「阿蘇」(時事通信社1992)など写真集多数
(社)日本写真家協会 (協)日本写真家ユニオン ピンホー
ル写真芸術学会会員 (社)日本写真協会
http://earth-aso.jp/
METROPOLIS制作年:2011
作家名:takaosuzuki
作品説明:この作品は、作者のイメージする理想の「科学」
と「心」の進化のバランスをMETROPOLIS(都市計画)に
置き換え、その繊細なバランスを極細素描画で描きます。
ロールシャッハ・ジャパン 3.11制作年:2011
作家名:石田陽介
作品説明:福岡市箱崎在住のコミュニティアーティストであ
る石田陽介は、「3.11」後の心象風景へと分け入るスクリー
ンを、自身のホームタウンである箱崎のまちへと透写してい
る。水面に映るかのような‘シンメトリーである世界’の旋
律と戦慄。まちは揺らいでいる。
素材:アルポリック
プロフィール:ソーシャル・アートセラピスト/コミュニティ
アーティスト/アト
リエHプロジェクト代表
1967年広島生まれ。多摩美術大学絵画科油画専攻卒・九州
大学大学院修士課程ユーザー感性学専攻卒。精神科病院にお
ける絵画療法士勤務を経て、九州大学子どもプロジェクトの
アドバイザーに就任。子ども未来学の実践活動に携わる。現
在はソーシャル(まちの)アートセラピストとして、福岡市
箱崎地区にて産学官民の協働によるコミュニティアートプロ
ジェクトを展開。唐津市主催のシニア未来学・女性未来学講
座を企画プロデュースしている。
��
『そら 2011-1』『そら 2011-2』制作年:2011
作家名:内田勝弘
作品説明:そら=空=空(くう)であり、空(くう)=無=有、
五大元素の一つ、“水”の位相として上空に満つる水蒸気とそ
の大気をイメージして表してみた。
プロフィール:
1955 熊本県阿蘇郡生まれ
1978 佐賀大学特設美術科卒業/故・坂本善三に師事
1990 二人展(新宿・紀伊国屋画廊)
1992 熊本県立美術館学芸課に勤務(2002年まで)
1994 第3回「英」展(田川市美術館主催)に招待出品
1998 熊本市屋内プール「アクアドーム」に立体作品
2009 九州アートコンテンポラリー出品
STAND FIRM- 赤壁 -制作年:2010
作家名:浪崎洋子
作品説明:ピンクは鉄で溶岩がそのまま固まった。上層部は
急冷粉状。噴火で上に巻き上げられ落ちたもの。約5000年
前の地層でより新しい。気の遠くなる時を越えて人が住める
大地。赤壁が複数のトルソーにも見えてくる面白さ愚かしさ
を表現した。『STANDFIRM』( スタンドファーム ) は「堅
く立って揺るぎないもの」の意。
素材:ミクストメディア
プロフィール:
1955 熊本生まれ
1974 熊本県立第二高校・美術科卒業
1976 九州造形短期大学卒業
2005 東光展・奨励賞
2006 浪崎洋子美術研究所開設
東光展・奨励賞/銀光展・銀光会賞
『illustrator 浪崎洋子展』如水館 (苓北町 )
2007 東光展・東光賞
2008 日展・入選
2010 『illustrator 浪崎洋子展』(熊本県立美術館・分館 )
��
からだのおくのことばたち the words from
soul after 3.11 制作年:2011
作家名:井上玲
作品説明:私たちは言葉に囲まれて暮らしています。言葉は
わたしたちのこころから産まれたものですが、それは形とな
り、時にはわたしたちをしばるものになってしまいます。3.11
の後、人々は恐怖を感じるとともに自分の心の言葉を発し始
めたように感じます。体から遠くなってしまったことばを取
り戻すために、多くの人が声をあげはじめました。今だから
湧き上がる気持ちを作品にしてみたい。それは遠くなってし
まったことばを取り戻す作業になるのではないか。ことばへ
のからだへの旅をはじめてみました。
素材:デジタル撮影によるプリントアウト(印画紙)
プロフィール:1974年生東京武蔵野美術学園・北京中央
美術学院版画科卒業/切り絵、版画、身体表現、俳句など表
現媒体は問わず制作発表を続ける。現在屋久島から九州を北
上する「ことばと人に出会う旅」を続けている。
聖なる源の愛と光制作年:2011
作家名:水口磨紀
作品説明:宇宙創成の源のエネルギーを表現しました
素材:水彩絵の具 ケント紙
FOREST GIRL制作年:2008
作家名:東耕平
素材:FRP
プロフィール:崇城大学芸術学部美術学科研究生
炎の生き物~小学生との合同作品~制作年:2011
作家名:岡愛美
作品説明:テラコッタ野焼き
プロフィール:崇城大学芸術学部美術学科卒業
�0
2011年とは日本人のみならず人類にとって大きな意識変
革を促された年だったと言えよう。「東日本大震災」それは
天災としての地震・津波の被害にとどまらず人災としての原
発による放射能汚染問題である。今回のパネリストは多ジャ
ンルにわたりアート部門から本展キュレータでもあるハロ・
シュミット(ドイツ)、今回招聘した環境アーティスト・池田
一、代替的な農業の実践者のピリオ・ドニー&假野祥子、阿
蘇フォークスクールからは阿蘇神話街道の著者でもある山村
将護そして雲仙普賢岳災害記念館副館長でもあり2012年の
島原世界ジオパーク大会実行委員長・杉本伸一という面々で
行われた。司会の福山洋によるナビゲートからそれぞれの立
場による「自然と人間」という古くて新しいテーマを巡って
討論があった。
本パネルディスカッションで語られた多くの内容は人間の
前に自然があるという自明性を確認するようなものだけでは
なく今後生活者としての態度を考えさせられるものだった。
また今回初めての試みで、終了後分科会という形で観客参
加型フリートーク、ワールドカフェが行われた。それぞれの
立場から阿蘇や火山に関する意見のみならずアートや地域再
生など広く有意義な意見交換が行われた。
左から AkiWendland(ポーランド/通訳)/ SchmidthHarro(ドイツ)/池田一(環境アーティスト)/杉本伸一(世界ジオパーク大会実行委員長)
/山村将護(阿蘇フォークスクール)/ピリオ・ドニー&假野祥子(バイオダイナミック農業)/福山洋(司会・崇城大学)
Panel discussion【自然と人間】8 月28日 1:00pm〜
��
World Cafe (分科会形式フリートーク)ワールドカフェでは、幾つかのテーブルごとに各パネリストを中心にそれぞれの議題を書き出し参加者のフリートークが行わ
れた。
火山のふもとで生きるということ
火砕流で焼かれ土石流で埋まったふるさと、
人々はなぜ火山のふもとに暮らすのだろうか。
火山は災いをもたらす一方で、
雄大な景色をつくり、多様な動植物をはぐくむ。
地熱で温められた地下水は温泉となり、
人々の疲れを癒す。
そんな恵みがあるからこそ、
人は火山の周りに集まるのだ。
そして豊かな自然を求めて
ひとびとがやってくる。
杉本伸一
(世界ジオパーク大会実行委員長)
��
【参加アーティスト】(国外5名)1HarroSchmidt–Germany 2ChristianeOppermann–Germany 3AnnaGrunemann–Germany
4IlkaTheurich–Germany 5AkiWendland–Poland
(国内作家9名)団体含め30名ほど
(国内)1長野良市(阿蘇・熊本)2内田勝弘(阿蘇・熊本)3川嶋久美(阿蘇・熊本)4野島千里(島原・長崎)5下城賢一( 阿蘇・熊本 )
6松本和子(阿蘇・熊本)7石田陽介 (福岡 )8浪崎洋子(阿蘇・熊本)9池田一(神奈川)
【教育関連】1崇城大学 三枝研究室1名 2九州大学大学院 藤枝研究室 廃材楽器 (6名 )
【賛同作家】 長瀬崇裕/水口磨紀/ takaosuzuki /井上玲/東耕平/岡愛美/福永祐生
【Performance】8月 27日 1:00 〜 あそ望の郷くぎの/28日 4:00 〜 フォークスクール
1ChristianeOppermann クリスティアナ・オパーマン 2AnnaGrunemann アンナ・グルンマン 3IlkaTheurich イルカ・チューリッヒ
4AkiWendland アキ・ウェンドランド 5ヨーコージ+創作書道(横溝幸治) 6高森町神楽
【ドキュメント内写真】 児玉龍郎/三枝泰之/古賀遼也/山口次郎
【日時】 2011年 8月 26日[金]〜9月 25日[日]
《パネルディスカッション》………「自然と人間」28日 1:00pm〜
【会場】 阿蘇フォークスクール 阿蘇郡高森町上色見1390-1☎0967-62-0027
火・水曜休校(祝祭日開校)/10:00am〜 5:00pm(最終日3:00pm迄)
【問合せ】☎ 0967-62-0027(阿蘇フォークスクールhttp://asofolkschool.eco.to/)
【主催】 Genesis 起源展実行委員会
【共催】 NPO法人阿蘇フォークスクール/崇城大学三枝研究室/クンストハレ・ファウスト
【協力】 紅蘭亭/里の駅「たにやま」/ Tomek&Aki /浅川浩二
【助成】 くまもと21ファンド
財)阿蘇地域振興デザインセンター
■ "GENESIS-2" 起源展音楽祭 with根子岳ごはん
【日時】 8月 27日[土]〜9月 24日[土]
【参加アーティスト】上色見熊野座神社神楽保存会&インド古典音楽OKB 「起源の融合」/正木高志 ライブ&トーク 「根子岳の麓で根っこの話」/
夜の学校はビアガーデン! TheBigSmile(jazz)Live 「星空大笑いの夕べ」重松壮一郎ピアノライブ 「musicforalllivingthings 〜生きとし生け
るもの全てに向けた音〜」/井上尚子さんと作品を嗅いでまわる「南阿蘇くんくんウォークワークショップ」/藤川潤司 川原一紗 Live「おとのわ
〜大地のおへそとつながる〜」/起源展音楽祭フィナーレ 秋本節&佐藤GWAN博九州ツアーin高森
【Food&Drink】フォークスクールまかない食堂「根子岳ごはん」「起源展」のまかないごはんをつくるべく結成。「根子岳ごはん」地元食材を使った
美味しくやさしい自然食ユニット。賄いメンバー:ちひろ・まさみ・ゆん・くりを
【報道】
TV報道 ・2011.8.26(金)4:50〜 TKU「ぴゅあぴゅあ」 ・2011.9.7(水)6:10〜 NHK「クマロク」
新聞 ・2011.8.28(日)毎日新聞21面「自然と人間の関係見直して」 ・2011.9.5(月)熊本日日新聞13面「火山テーマ作品ずらり」
Specification 明細事項