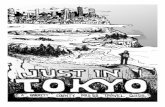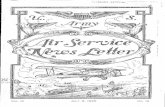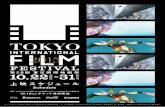[Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese
Transcript of [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
昭和戦前期精神病院の症例誌について
Case Histories of a Psychiatric Hospital in Tokyo, in Pre-war Showa鈴 木 晃 仁 Aるh o S U Z U K
要 旨
この小論は、精神病院の (症例誌)を 紹介 し、これまで日本の歴史学者 ア ーカイブズ学者によって用いられ
てこなかったジャンルの史料について、その特徴と利用の可能性に触れる。具体的に取 り上げられるのは、東京
の小峰研究所が所蔵する |:子脳病院 (1901-1945)のアーカイブズであり、その中でも個々の患者の症例誌 (casc
hiStOry)を分析の中心とする。症例誌がこれまで医学史研究において利用され、その分析がヒス トリオグラフイ
を大 きく転換 させてきたのは英米を中心 とする地域を対象としたものであるため、そこで発展 した二つの研究手
法、すなわち患者のデモグラフィーを明らかにする量的な研究と、治療 と権力の関係を分析する質的な研究を紹
介し、王子脳病lscのアーカイブズを用いて、それらの方法を用いた結果を試験的に提示する。
This articlc introduccs casc histories Of psychiatric hospitals a gcnre of resourccs that has not becn
utilizcd in Japan by histOrians Of psychiatry The■atures()f this genre of material and the pOssible、vays of its
usc win be discussed Thc archives of Oヽi Brain HOspitJ(1901-1945)now houscd at the Komine lnstitute in
TOkyO 、vill be the particularおcus Of this、vork and frOm its diverse matcrials,the case histOrics Of individual
patients、vill bc analyzed Thus Lr. case histOrics have been m」nly cxploited in Ang10-Amcrican psychiatry
history, and this new typc Of material has transformed Ang10-American histOriOgraphies ThercfOrc this
papcr presents thc rcsults of alplying the twO nc、v malor research mcthOd010gles that havc developed in
Britain and NOrth America namcly the quantitative analysis of thc dcmOgraphy of thc patients and the
qualitativc cxanlinatiOn of the power of the thcrapeutics,ven in thc hOspltal
23
7 -r.l JA+Efrx No.18 (2013.4)
は じめ に
精神病院の症例誌とはいったいどのようなものか。まずは、必ずしも歴史学の世界に定着 して
いないこのタイプの史料を紹介するのに好適な、関根真― (18941981)という精神科医の自伝
的な随筆から取った事例からはじめよう。関根は、1894年に埼玉県で生まれ、東北帝大で九井
清泰 (1886-1953)のもとで精神医学を学び、1923年に東京府立松沢病院に勤務 したのち、1940
年に精神疾患の傷疲軍人のために新設された傷痰軍人武蔵療養所の所長となった。敗戦後は、軍
事保護院の廃上によって転換された国立武蔵療養所の所長を務めている。戦後日本の精神医学の
発展に貢献 した人物であ り、『落葉かき』(1971)、F落葉かき拾遺』 (1979)などの自伝的な随筆
集が、彼が生 きた時代の形成期の精神医学のエビツー ドを多 く伝えている。その中で、彼が研修
した松沢病院について、呉秀三 (18851932)と三宅鉱― (1876-1954)の二人の院長について
の回想や、病院での多彩なエピソー ドを生き生きとした筆致で書 き記 している。
関根が呉院長の回診を回想 した部分に、患者の 「病床日誌」について詳しく記 している箇所が
ある。少 し長 くなるが引用 しよう。
[呉]院長が病棟の玄関に上ると、病棟の組長 (主任看護者)が 患者全員の病床日誌を両腕
でだきかかえて出迎えるのである。看護者は病棟の廊下に適当の間隔に不動の姿勢で、病室
に向って配置につ くのである。病床日誌は和紙を綴ったものであつて、縦罫の経過用紙に毛
筆で書いたものであつて、長期入院患者の日誌は部厚 くなるので、慢性病棟で六、七十名以
上の患者となると、全員の日誌を重ねると相当な厚 さと重さとなり、組長も日誌をだきかか
えるのに楽ではなかった。
回診の途上、息者の症状を質問されたとき、とっさに思者の氏名が思い出せないと症状 も
説明できないのでもぢもぢしていると、よくしたもので、傍の看護長が手早 く部厚い日誌の
間からその患者の日誌を引き出してそっと渡してくれるので、その急場をきりぬけられるこ
とが出来るが、突然 「あの患者さんは誰ですか」と尋ねられて、即答出来ないで窮 してしま
い頭をかかえざるを得ないこともあった。
また回診の途中、患者が何か訴えでもすると、早速とりあげて聞き入るのであつた。もし
その訴えの内容に興味ある妄想でもうかがわれると、その患者の居室に案内させて、汚れた
畳の上にきちんと端座 して診察を始めるのである。担当医師は直ちにその患者の日誌を院長
に提出するのである。傍では清水看護長が硯箱で墨をすって、墨で毛筆の先を整えて間診の
筆記に供えてくれた。医師は院長の間診の運び具合を細かに和紙日誌に縦書 きに筆を走らせ
るが、その際には机 もないので、日誌を左手にもって書 くので、余程の達筆家でないと問診
内容を洩なく書けないので、若い医師は院長の前での筆記には苦労 したものである。
松沢病院の書庫に保存されている巣鴨病院時代の古い病床日誌には、精神医学界の大先輩
が達筆を振って書 き綴 られた貴重な筆跡が保存されていることであろう。
2
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
(中略)
院長が患者を診察するときは、病床日誌を開かれて、まづ最初に家族歴に目を通すのであ
るが、もしも家族歴の記載が不備であると、その病歴記載者に対 して、皮肉たっぷ りに不備
の点を指摘されるのである。それというのも、初めて入院する患者の診察時には、日誌に家
族歴、既往症其他を詳 しく記入 して、日誌の表紙裏の医師署名fFlに診察医師の氏名をサイン
して責任を明かにしてお くことになっていたので、後 日までその責任を問われるのであっ
た。入院の際、同伴 した家族や知人が家族歴などについてあまり承知 していない場合には、
後日補足する積 りであっても、つい失念 して放置する場合はかなり多かった。たまたまその
不備のままで院長の診察に出されると暴露 してしまうのである。院長は常に息者の家族歴に
は、家族の全員の名前、年齢、健康状態、死因、死亡年齢等々をもれなく記載することが、
患者の診察や指導にあたって、重要な材料となることを注意され、とかく軽視勝ちに陥るこ
とをさとされたものである。なお診察の際は患者の挙動帖 (看護 日誌)に も目を通され、診
察の参考にされ看護者に対 しては患者の状態はありのままに平易に書 くようにと注意を与え
ていた。(『落葉かき』70-73頁)
松沢病院の精神科医にとって、患者の病床日誌というマテリアルがいかに重要であったかを良
く伝えてくれる記述である。人院したときに家族などから聞 く情報、院長の診察の際に毛筆で筆
記される問診の情報、長期入院で部厚 くなった日誌の束の重量感、医師が氏名を忘れてしまった
ときにそっと看護長がその患者の日誌を渡すことなど、精神病院における臨床のさまざまな日常
的な構造を示唆するヒントに富んでいる。
このような病床日誌 症 例誌が保存されてお り、歴史的な史料となったときに、それらを用い
てどのような研究ができるのか。戦前期東京に存在 した精神病院である王子脳病院の症例誌など
を素材にして、研究の方向性を点描するのがこの小論の目標である。
王子脳病 院のアーカイブ
「王子脳病院」は、19ol年に東京府の北豊島郡 滝 野川西ヶ原に設立され、大正 昭 和期に
繁栄するが、1945年の空襲で全焼して廃院となった精神病院である。同じ経営者が王子脳病院
に近接した地に 「小峰病院」という私立病院を1925年に設立して、両者を一つのシステムとし
て運営していたので、その精神病院システムをこの論文は 「王子脳病院」と呼ぶ。設立当初は院
長も頻繁に交代するなど、経営と運営に困難があったようだが、設立者小峰善次郎の養子の小峰
茂之 (18831942)のもと、王子脳病院は非常に繁栄して、おそらく戦前期の東京で最も成功し
た私立精神病院であった。1920年には、精神病院法 (1919)で定められた代用精神病院として
東京府に指定され、私立でありながら一定数の公費の息者を受け入れる公的な精神医療の機能を
担うようになった。それにともなって病床も拡大し、1928年には 150床であったが、1937年に
アーカイブズ学IItt No18(20134)
はほぼ2倍 の 280床 となった。さらに、先に触れたように、1925年には近隣の地に純粋に私立
の病院である 145床の 「小峰病院Jを 開設 して、「王子脳病院Jと 「小峰病院Jと いう建物 と名
目の上で二つの病院となっているものを、一つの連続 した病院コンプレックスとして運営するよ
うになった。この二つの病院を有するシステムは、合計 して 350床程度の病床を持ち、代用病院
として東京の公的な精神医療の一翼を担 うと同時に、マラリア療法、インスリンショック療法、
電撃療法などの重要な先端的な療法をいち早 く導入 し、それと並行 して東北帝大で精神分析を学
んだ若い医者たちを雇用するなど、新 しい野心的な精神医療を積極的に導入 していた。院長の小
峰茂之は、東京の精神病院の形成に重要な役割を果た していた人物であ り、精神医l■~の
領域で
は、自殺、心中、同性愛心中、浮世絵などの多様な領域にわたって論文を発表している。特に自
殺については、日本の精神病における自殺研究の開拓者であるといってよく、重量感があり多様
な側面をカバーした仕事をしている。その他に、日本医師会の理事 となったのと関連 して、医療
の総動員政策にかかわる論考も発表 している重要な人物である。
王子脳病院のアーカイブは、現在は小峰研究所が所蔵 し、そのうちのある部分を論文執筆者の
研究室に移動 して作業をしている。症例誌が膨大な数にわたって存在するため、アーカイブの全
体像はまだ確定 していないが、その全容はほぼ明らかであり、a)滝 野川健康調査 (1938)関連
の資料、b)患 者名簿、c)症 例誌、d)そ の他 に 分けて考えることができる。
a)滝 野川健康調査は、1938年に新設の厚生省が総動員体制と医療制度の根本的な改革にそな
えて、東京の滝野川区で行った傷病 受 療の.ni査でぁる。小峰茂之はこの調査の実行委員長で
あった。この調査自体は354世帯、2,215人を対象にして 1年 間行われた。それぞれの世帯に
ついての情報である 「世帯調査票」と、個人がどのような特徴を持ちどのような傷病を経験 し
どのような治療を受けたのかを記録 した 「傷病記録票Jが 主たる資料である。
b)憲 者名簿は、「王子脳病院 小 峰病院患者名簿Jと いう表紙がつけられた入院患者の名簿で、
1926年から 1940年まで存在する。1943年分は欠けている。この患者名簿は、氏名のほか、性
別、職業、年齢、入退院年月日、診断名、転帰が記録されてお り、入院患者のデモグラフイー
を再構成するのに必須の資料である。データベース化 して整理すると、1943年分を除いて、
約 7,000件の入院がこの期間にある。この数字は、個人を特定 して 「名寄せJを 行っていない
状態での計数で、同一個人が間隔を置いて 2回 入院した場合には人院が 2件 と数える方法であ
る。
c)症 例誌は、患者一人ずつについて一冊の症例誌が作 られている。それぞれの症例誌は三種類
の資料からなり、医師が記入 した病床日誌、看護人が記入した看護日誌、体温や服薬などが記
入されている体温板の三種類が一冊に綴 じあわされている。複数回入院した息者については、
複数の入院が一冊に綴 じあわされている。病床日誌、看護日誌は用紙を二つ折にして 「袋」に
なった部分に、息者からの手紙、息者自身が書いたもの、他の病院からの手紙などが入れられ
ていることがあり、患者についてのフアイルの役害」を果たすことがあつた。この症例誌は、も
3
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
ともとは、退院年度順に段ボール箱に入れられていたが、現在これを患者の五十音順に整理 し
ている。2012年 同 月の段階で、男性 「あJ行 の患者について整理 と集計がほぼ終わっている
が、この部分で 728点存在 している。この数値から全体数を推算すると、約 4,000人分の症例
誌があると考えられる。
d)「その他Jの 資料には、「不法監禁の訴J「憂国誌」「痴人の夢物語Jな ど、息者が書いた資料
が別に整理されたもの、小峰茂之が行っていた研究や執筆 した論文の資料 メ モ 原 稿などを
中心とする研究関連のもの、さまざまな理由で増築と改築を重ねたため病院建築関連の図面な
どがある。
症例 誌 と新 しい医学 史の ヒス トリオグラフ ィ
精神病院のアーカイブには症例誌以外にも多くの種類の貴重な史料が存在するが、症例誌がま
とまった数において保存されている場合には、最も重要で価l14が高い史料となる。そもそも、精
神病院において医師と患者と看護人がそれぞれ何をしたのかということを、患者の入院期間にわ
たつて最もつぶさに記録している組織的な資料が、非常に重要な一次資料であることは贅言を要
しないであろう。また、症例誌には患者の家族、生育、教育、職業、発病から入院にいたるまで
の過程などを記す欄があり、これらの精神病院の外部でおきたことについても記録されている。
つまり、患者の家庭や地域社会と連接して精神病院での医療を考察するための貴重な史料として
用いられてきた。じっさい、欧米においては、1980年代からの劇的な精神医療の歴史研究の伸
展と拡大は、病床日誌などの資料の組織的 計 量的 精 級な分析に大きく依存していたといって
よい。
症例誌が精神医療の歴史研究の主要なマテリアルになった背景は、大きく分けると、現在の医
療の位置付けにも通 じる医学史の方向転換 と、症例誌を作 り出す権力についての思想的な洞察の
二種類があるので、それぞれを簡単に説明する。
1980年代からの医学史研究の転換は、医学 と医療の位置付けが大 きな方向転換をしたことと
深 く連動 している。1960年代から70年代 くらいまでの医学史のヒス トリオグラフイは、医学の
理論的 技 術的な進歩を記述することに主眼を置いていたが、これは、19世紀以降に発展をは
じめ、20世紀に劇的な進歩をとげた近現代の医学に大きな影響を受けた態度であった。さらに、
先進国における経済発展と福lll国家の充実がもたらした、医療をうける機会の拡大と質の向上
が、この楽観的な史観を後押 ししていた。がんなどの生活習慣病の問題は大 きくなっていたが、
それまでの人類の歴史において主要な死因であ り、医者にとっても患者にとっても大 きな問題で
あった感染症については、1980年の天然痘の根絶宣言が象徴するように、医学によって克服 さ
れた、あるいは近い将来に克服されるだろうという意識が広まっていた。20世紀の前半におい
ては、医科学と医療技術の進歩の成果が、福祉社会と経済発展によって人々に行 きわたることが
善であるという枠組みの中で医学史のヒス トリオグラフイが作られていた。
7 - h'I :t z+Elfn No.ls (2013.4)
しかし、1970年代から80年代以降の医学は、そのような楽観的な方向とは反対の方向に向か
うこととなり、医学史のとストリオグラフイもそれに従つて動 くこととなった。この時期には、
医療倫理学が確立 して医者の権限について批判的な制限をかけることが確立 し、インフォーム
ド コ ンセントの概念とともに息者は医療の く受け手〉から 〈作 り手〉としての重要なエージェ
ントとなった。長期的な経済発展の停滞や高齢化にともない、医療福祉を拡大 し続けることは難
しい状況となり、医療は見直され再検討される主題となった。人類の勝利であるかのように思わ
れた感染症においても、HIv/AIDSが 世界的な流行をは じめ、199o年代には貧困国において巨
大な公衆衛生の問題として定着 して現在に至っている。2000年代にかけては、SARSや インフル
エンザの世界的な流行のリスクが大きな問題 として注 目された。即ち、20世紀の末期から21世
紀にかけての医学においては、20世紀中葉までの楽観的な考えは雲散T‐●消 したといってもよい。
たしかに、1980年代以降においても、ヒトゲノムの解析や再生医療など、医科学はめざましい
進歩を続け、診断や治療法は大 きく改善 していた。 しかし、それにもかかわらず、医療の歴史を
記述する枠組みとしての 「医学の黄金時代」は終焉 した。新 しいヒス トリオグラフイは、医科学
と医療技術の進歩ではなく、医療者と患者 と疾病 病 気の三者が作 り出す場 として医療 を提え
て、その場が文化、社会、政治、行政、環境などによって形成されるものであるという 「トータ
ルなJ医 療の歴史の捉え方を主流 としている。
このような新 しい医学史研究は、過去の医者―患者―疾病という医療を形成するコアの部分に
最 も近いのは、症例誌とそれに類似の資料であると考えた。症例誌は、ある疾病 病 気にかかっ
た患者と医師が作 り出した状況を記 した資料である。特に重要なことは、新 しい医学史の大 きな
特徴が患者を医学史のなかに取 り込んだことにあるのと対応 して、症例誌には個々の患者につい
ての情報が記され、その行為や思考や言葉が記されていることである。 もちろん、患者自身が書
いた病気の経験や受けた医療の記録のような資料 も存在 し、精神医療の歴史については、とりわ
けロイ ポ ーターの一連の仕事が「患者の視点からの精神医療の歴史Jという方向性を開拓 した。
中世後期のイギリスの女性であるマージェリー ケ ンプ、19世紀に精神病院を批判 したイギリ
スのジョン パ ーシヴァル、19世紀末に精神疾患にかか りその妄想を長大で精細な 『ある神経
症患者の回想』にまとめたダニエル シ ュレーバーをはじめとして、精神病患者が書いた手記に
あたるものは豊かな資料を提供する。また、精神医学においては、医師が執筆 した患者の症例も
数多 く、フロイ トによる 「症例 ドーラJ「少年ハンスJ「狼男Jな どの一連の症例やジャネの 『症
例マ ドレーヌ』などは、精神科医だけではなく精神医療の歴史の研究者にとっても古典的なもの
になっている。それほど有名ではなくても、精神医学の書物には多 くの症例が含まれているし、
日本では呉秀三、三宅鉱一、内村祐之、秋元波留男と四代にわたる東大教授がそれぞれの精神鑑
定例を出版 した書物群は、医者が書いた患者についての詳細な記録になっている。これらのタイ
プの史料 も積極的に探索 蒐 集されて利用 されなければならないことはもちろんである。 しか し
ながら、息者自身による手記については、患者自身の視点によって構成され語られているという
28
昭和戦前期精神病院の症,1誌について (鈴木)
メリットを持つ と同時に、その数は症例誌に較べたときに著 しく少なく、また、バイアスがか
かった資料であることは明らかである。医師が記録 して出版 した症例については、フロイトにお
いて特に顕著であるように、ある理論の正 しさを証明するために書 きとめられた症状であ り、場
合によつてはそのために引き出されてきた症状であり患者の行動である危険がつきまとう。昭和
30年 にある日本の精神科医が書いた一般向けの書物では、ある個人の症状 事 情 と別の個人の
ものを組み合わせて、仮想的な 「患者」を合成する場合すらある。
症例と権力の問題については、ミシェル フ ーコーの F監獄の誕生』における分析が古典的な
ものである。この書物でフーコーは、近世ヨーロッパのベス ト流行時における街の空間の厳重な
封鎖 「碁盤割 り」と、そこで個人が特定され評定 検 査される権力を、規律 訓 練の図式と呼
び、それ以前のハンセン病患者の追放に見られるような排除の図式と対比させた。ハンセン病息
者の追放は、一方と他方に三分する分書」を行 うが、ペス ト型の権力では、権力の対象を個人化さ
せるものであった。19世紀以降の精神医療は、二つの型の権力を接合させ、まさしくハンセン
病型の隔離収容の空間において、ある個人を 「症例Jと して定義 し形成する力をはたらかせた。
この力は近現代の社会にとって本質的なものであるというフーコーの7111察は、歴史的な妥当性は
ともか く、その深さをいまだ失ってはいない。
患者という個人の権力分析が、個々の事例の背後のダイナミクスを読み解 く質的な手法である
のに対 し、症例誌は計量的な手法の分析 も許す史料である。症例誌は、国や地域や時代を間わ
ず、精神病院のアーカイブにきわめて多数にわたって存在する史料である。症例誌が歴史学者に
よって発見された時期は、コンピューターが歴史学の研究者に個人レヴェルで利用可能になった
時期 と重なってお り、患者の諸属性や受けた治療の内容や入退院のパターンについて集合的 計
量的に分析する方向に発展させることが可能になった。ジョゼフ ・メリングらが 19世紀のエク
ゼターの精神病院群を対象にした研究は 13,000人の患者記録をデータベースに入れ、4,llK10人に
ついて重点的な分析をするという大規模な作業にもとづいている。また、情報の質においても、
収容施設に入る以前の情報については息者と生活をともにしてきた家族が提供 したものであり、
人院後のものについては患者自身の行動を間近で観察 した医者や看護人が記 したものである。こ
れらの情報が家族や医師 看 護人の意向を反映し、それぞれのlFrK略にもとづいて選択され構成さ
れた記述であることは言うまでもないが、それらの情報の背後には確実に患者についての実態が
存在 し、症例誌からその実態に光を当てることは十分に可能である。
この小論の第一の目標は、このような可能性を欧米の研究において発揮 してきた症例誌 という
史料を、日本の精神医療史研究において用いることが可能であることを示すことである。日本に
おいては、これらの患者記録への歴史資料 としてのアクセスは整備されておらず、一ilの歴史学
者にとっては不慣れな資料だろうが、ハンセン病を中心にして実際にそれらを用い始めている研
究者 も現れてきている。また、個人の歴史的な記録の取 り扱いにはプライヴァシーの保護の点で
29
7-r 1 .,/+ifrn No.l8 (2013.4)
注意を払わなければならないが、医学情報の取 り扱いに関する一定のガイドラインが存在 し、日
本医史学会は患者情報の取 り扱いについての倫理規定の概念を持っている。 しかし、史料へのア
クセスや個人情報の問題以上に日本の人文社会系の歴史研究者による症例誌の活用を妨げている
のは、理系と丈系の 「二つの文化Jに 由来する距離感のため、医学の問題とその一次資料に対 し
て文系研究者が敬遠する意識であるように見受けられる。そのため、〈医者 患 者 疾 病とそれ
をとりまく環境 社 会 文 化〉という医学と医療のコアにあたる部分の分析に対 し、人文系の研
究者が及の要になっているという印象を筆者は持っている。
スペースの制約と研究の段階という二つの理由で、この小論では、精神障害者の病院内での生
活の全体像を示すというよりも、重要なポイントが点描されるにとどまる。まず、彼 らの生活の
基本的な構造を示す指標は、人退院のパターンである。どのくらいの期間にわたって在院してい
たのか、退院の際に病気が治って退院したのか、治らないまま退院したのか、あるいは死亡 して
退院したのか。このような精神病院の患者の入退院のデモグラフイーについての情報は、精神障
害者の生活を理解する上で基本的なデータであるが、患者記録による組織的で正確な計量が可能
になるまでは、歴史研究の射程に入っていなかった。そのため、不正確なイメージが検証されな
いまま、そのイメージにもとづいて精神医療の特徴が議論されてきた。イングランドの精神医療
史研究を離陸させたアンドリュー ス カルの優れた著作でも、19世紀の精神病院 (「貧民狂人収
容院J)は 患者を長期収容する施設であるという前提にもとづいて、社会における不都合な存在
をFt」じ込める精神病院の機能が強調されていた。それに対 して、デイヴィッド ラ イトはバ ッキ
ンガムシャー州狂人収容院の患者記録の分析から、息者の在院期間の中間値は500日程度である
ことなどを明らかにして、長期収容というより、家族というもう一つのケアの空間との共同関係
の中で狂人収容院を理解すべきであることを説得的に議論 した。それと同じように、戦前の日本
の精神病院についても、患者のデモグラフイーについてのIF確な情報が共有されていないため、
少数の例にもとづいた精神病院の像が戦前の精神医療の性格付けに影響を与えてしまっている。
たとえば、兵頭晶子の 『精神病の日本近代』は優れた著作であるが、その歴史理解の根本にある
「日本の近代化にともなって、短期的な治療の対象である狐憑 きから、不治の病として長期にわ
たって監禁される精神病へと移行 した」というテーゼは、精神病院の患者の在院期間についての
無根拠な思い込みにもとづいている。この小論の一つの目標は、戦前期東京の精神病院である王
子脳病院を例に取 り、息者のデモグラフイーという精神障害者の生活の構造の一つの要素を明ら
かにし、それから当時の精神医療の特徴を捉えなおすことである。
もう一つのポイントは、精神病院において治療がどのように実施されたかということである。
精神病院はいつの時代においても収容監禁と医療の二つの側面を持ってお り、両者のバランスは
さまざまに変化 してきた。戦前の精神病院はどの程度治療的な空間であり、収容監禁の側面に比
して、治療はどこまで重要な位置を占めていたのだろうか ?「治療の歴史Jに 対する無関心 とい
うのが、長いこと精神医療であれそれ以外の分野であれ、医学史研究の重要な空自の一つであっ
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
た。医療系分野の出身の医学史研究者は、治療について、「それは効いたかどうかJと いう著 し
く貧困な問いしか持っていなかったし、人文社会系の医学史研究者の多 くは、「それは野蛮な人
権侵害か」という総 じて同程度に貧困な問いしか持っていなかった。特に、近年の人文社会系の
研究者による医学史研究の成果の多くが、過去の医学の蛮行をさばくいわゆる 「メッセージ性J
を持つた歴史研究として問われている日本では、その傾向が現在でも強い。欧米の医学史研究で
は、このような状況の反省の上にたつて、ジョン ウ ォーナーやチヤールズ ロ ーゼンバーグな
ど1980年代以降に治療という行為が持つ複雑な意味合いを明らかにしようとする新 しい治療の
歴史が現れた。精神科医療の歴史においても、ジョエル ブ ラズロウやジャック プ レスマンの
研究は、患者記録から治療が持っていた意味を再構成 した著作が 90年代に現れた。前者は、20
世紀のカリフォルニア州立病院の患者記録を素材にして、マラリア療法の導入とともに、梅毒に
起因する進行麻痺の患者に対するネガテイヴな表現が患者記録において減少 したこと、すなわ
ち、治療法が患者に 「治療の対象」という新 しいアイデンティテイを与えたことを論 じて 「治療」
の意味の広が りを示 し、後者は、20世紀アメリカのロボ トミーの歴史を取 り上げて、それを野
蛮と決めつける現代の我々の確信が強固なわりには、ロボ トミーが実施された具体的なメカニズ
ムをほとんど知らないことを歴史学者に痛切に思い知らせた。この小論は、戦前期日本の精神病
院の患者が受けていた治療のパターンと意味を明らかにして、精神病院がどの程度まで 「医療」
の性格を持ち、その医療の性格はどのように構造化されていたのかを論 じることをもう一つの目
標とする。
4.患 者 の入退院のパ ター ン
王子脳病院は精神病院法のもとでの代用精神病院であったから、私費の患者と公費の患者 (多
くは代用思者)が おり、両者はまず、生活スペースの点で異なっていた。図 1は、王子脳病院の
建築の変遷を研究している勝木祐仁が作成した、1937年近辺における王子脳病院の建物の敷地
図と建物の平面図である。王子脳病院 小 峯病院は複数
の建物が複雑に立ち並ぶコンプレックスであつた。「EJ
の形をした小峯病院が存在 し (A)、それをはさむ形で
王子脳病院の二つの建物があった。片方は 「王子脳病院
乙敷地Jに 建てられた 「SJの 字を押 しつぶ したような
不規則な形をしている建物であ り (B)、この複雑な建
物も複数回の建て増 しの産物であつた。もう片方にある
不規則な形をしている建物 (C)は 、王子脳病院 「甲敷
地Jに建てられた比較的古い建築物である。Bの 隣には、
1937年ごろに新築されたと思われる二階建ての建物(D)
が示されている。
ヽ
夢31
D、 、、、、
7 -n ( a^+ i f t 1E No18 (2011 .4 )
図 2の 平面図にはBと Dの 建物の利用
図が示されているが、そこでは、男と女の
:}:[:iな[|[『:」「i([i「 》'EI蹴iにξR晟 ∫昇曾 ま間 十 畳 間の三人部屋、十二畳の四人部 |
屋、十人畳の六人部屋が配 されている。D
の建物は男性患者専用で、Bの 建物では男
性患者と女性患者の生活スペースの間には壁が設置されている。この図から、私費患者と公費患
者の生活空間、男性患者と女性患者の生活空間は意外に近いことが分かる。
このような生活空間の静態的な区分だけでなく、公費患者と私費患者は、病院の利用の動態に
ついても違いがあった。その違いが最 も明らかになるのは、患者名簿から計算できる在院期間で
ある。表 1は、1930年、35年、40年 に入院した私費患者 公 費患者について、その在院期間の
平均値 中 間値を掲げたものである。私費患者は、男も女 もほぼ35日から45日の中間値の間で一定 してお り、一ヶ月から一ヶ月半の在院が一般的であった。一方、公費患者はそれぞれの入院
年次コホー トにより大きな変動があるが、500日から950日、一年から二年半 くらいというのが
中間値になっている。すなわち、公費患者は私費息者の 10倍から20倍の期間にわたって精神病
院を経験 したことになる。
表 1 王 子脳病院入院忠者の在院期間 入 院年コホー ト別 (1930年 、35年、40年 )
私費 19 3 0入院 1 9 3 5入院 1940入 院
男性 女性 男 性 女性 男性 女 性
患者数 216 102 189
平均 (日) 114 95 84
中間値 (日) 425 “ 46 40 43
公費 1930入院 1 9 3 5入院 1940ヌ、院
息者数 54 42
平均 (日) 558
中間値 (日) 959 770 499
04
j^
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
私費息者と公費患者は、在院期間だけでなく、在院の結果どのようになったかという 「転帰J
においても大きく違っていた。1926年から42年までに入院 退 院した私費 公 費の患者の42
年までの転帰をまとめたのが表2である。(42年で区切つたのは、1943年入退院の患者名簿を欠
くためである。)全 治退院の割合でいうと公費患者のほうがはるかに高く、私費患者は軽快 未
治の段階で退院したものが多かつたことを示す。言い換えると、公費患者は全治しないと退院で
きず、軽快 ・未治では入院が継続されたが、私費においては、家族の都合や入院の経費などの理
由で、軽快 未 治の段階でも退院となることが多かった。そして、なかなか退院せず在院期間が
長い公費の患者は精神病院内で死ぬことが多かった。私費患者の約一割が病院内で死亡している
というのもその在院期間を考えると高い数字であるが、公費患者の三分の二近くにあたるものが
病院内で死亡しているというのは非常に高い数字である。公費患者の三分の二は結果的に 「残り
の人生を精神病院で送る」ために王子脳病院に入つたのに対し、私費患者の大多数にとって精神
病院は改善を得るために短期間滞在し、そのうち四割程度が改善し、四割弱が改善せずに退院す
る場であつた。
公 費
実数
全 治
軽 1央
未 治
死 亡
公費変更
そ の 他
記入なし
129 221
34 58
40 69
367 630
1 2 2 1
1 0 2
合 計 583 1000
1942年までの公費患者の高い死亡率す ら色あせてみえる高死亡率の惨状が、表 2で 示 した
データが終わる 1942年以降、特に 19“年 45年 にやって くる。総力戦下の社会における精神
病院の患者の高い死亡率は有名であ り、第一次世界大戦中の ドイツの精神病院においても、第二
次世界大戦中の日本の精神病院においても、入院患者の死亡率の急上昇が見られた。少 し違う手
法で計算された死亡率であるが、松沢病院では患者の死亡率は 1944年に386%、 45年 には414
%、 井の頭病院ではそれぞれ 386%と 527%で ある。王子脳病院においてもこの時期に患者の
死亡率は急上昇 した。1930年代には、年頭に在院していた公費患者のうち 10%前 後が一年以内
に死亡する程度であつたが、1941年の 15%、42年の 17%と 上昇 し、1944年には年頭に在院 し
ていた公費患者 109名のうち51名 (47%)が 一年以内に死亡するという 「強滅Jと いう言葉が
ふさわしい状態となった。(同年の私費患者について同じように計算された値は、平年よりもか
表 2 王 子脳病院入院患者の転帰 19261942
387 66
2348 403
2146 369
564 97
35 06
36 06
306 53
33
7 n ( 17+6 tX Nu t8 (2 r , l l 4 )
なり上がっているが、それでも19%に とどまっている。)
王子脳病院においては、精神病院に公費で人院する患者は、生 きて退院することなく死ぬまで
病院に滞在 したものが三分の二程度であったこと、特に戦争の末期にはすさまじく高い死亡率が
見られたことが確認できる。ここで、「死ぬまで精神病院に在院 したJと いう表現には注意が必
要である。この表現から、現代の日本のような精神病院患者の高齢化や、慢性化 した患者がいつ
までも生きている空間としての精神病院を想像 してはいけない。先に見たように、死ぬまでの在
院期間はそれほど長 くはな く、院内で死亡 した公費患者 425人の平均死亡年齢は42歳程度で
あった。入院から死までの期間が短かった理由を知るためには、死因に関するより詳細で組織的
なデータ分析が必要であるが、長期入院患者をサンプリングした表 3を見れば、結核による死亡
が突出して際立ってお り、結核という感染症が、精神病院の入院患者の生存期間を短 くすること
に大きな役割を果たしたことは確実である。脳病院で結核による死亡が多かったことは昭和期に
は広 く知られてお り、1933年には鎌倉脳病院の院長の西井烈が 『読売新聞』 に 「精神病と結核J
という小文を連載寄稿 し、息者の不衛生な生活から来る体力低下が、高い割合で患者に結核の病
変が見出されることの原因であろうと書いている。また、この時期の精神病院の二大疾患は、早
発性痴呆 (精神分裂病 ―統合失調症)と 並んで、梅毒が進行 して中枢神経を侵 した結果発病する
麻痺性痴呆であったことも重要である。麻痺性痴呆はもともと予後が悪 く、発病 してから死の転
帰までの時間が短い。当時はマラリア療法も利用できるようにはなっていたが、麻痺性痴呆患者
は発病 入 院後に比較的速やかに死を迎えることが多かった。すなわち、結核 と梅毒という二つ
の感染症が王子脳病院の死因で大きな割合を占めてお り、そのため、公費患者が死ぬまでの時間
はそれほど長 くはなかったと考えるべきであろう。
表 3 長 期入院患者の年齢 ・診断 ・在院期間 ・転帰など
辱響性 年齢 公私別 人院年月日 退 院年月日 在 院期間 備考
A 女 41
B 女 22
C 男 26
D 女 42
E 女 18
F 男 29
C 女 51
H 男 51
1 男 19
J ;弓 27
K 男 37
L 男 26
M 女 35
公 早 発性痴呆
公 早 発性痴呆
公 早 発性痴呆
私 早 発1■痴呆
公 躁 鬱病
私 精 神分裂病
公 早 発性痴呆
公 進 行 ir痺
公 早 発1■痴呆
公 早 発性痴呆
公 早 発性痴呆
公 早 発性痴呆
私 精 神分裂病
1,331228 19401227
1932 219 1941 8 3
1932 423 1941 421
1933 3 14 1943 913
1938 4 1 19431016
1937 213 1943 520
1931 1013 1940 1 12
19291210 19361031
192910 2 1935 1018
1936 6 11 1944 226
1930 411 19381030
1932 712 1935 225
1933 615 1943 915
7年 死 亡 (1市結核)
,年 6ケ 月 死 亡 (llI●結核)
9年 6ヶ 月 死 亡 (肺結核 )
10年 6ケ 月 死 亡 (肺結核)
5年 6ケ 月 死 亡 (助1糸占核)
5年 3ケ 月 死 亡(栄養障害)
8年 3ケ 月 死 亡 (狭心Im)
6年 11ケ月 死 亡 0ビ因記載な し)
6年 Hヶ 月 死 亡 (脳膜出血)
7年 8ケ 月 死 亡 (肺結核)
7年 6ケ 月 死 亡 (肺結核)
2年 7ケ 月 末 治退院
10年 3ケ 月 末 治退院
19311 2 2頃 まで私費入院
19291 0 5 1 1 1 6ま で私費人院
1936H 2 1 1 2 2 1に 短期F「5・●・院
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
昭和戦前期に精神病院に入院した精神病患者 精 神障害者のデモグラフイーの輪郭をまとめる
と、王子脳病院には、1ケ 月から2ケ 月程度在院しただけで軽快 未 治のまま退院してい く私費
患者 と、2年 程度在院し、その三分の二は病院で死を迎えた公費患者がいた。また、公費患者は
現代の精神病院患者のように高齢化する以前に、結核や梅毒 という感染症で比較的若 くして死ん
でいた。戦争末期から終戦期の食糧不足と極度の栄養欠乏の状況は凄惨なものであったが、その
現象は、戦争末期に突然新 しいデモグラフイーのレジームが現れたわけではなく、精神病院で死
を迎えるという、それ以前に存在 していた構造がより急速に展開したものであつた。また、これ
は推測であるが、戦後の精神病院に5年 から10年以上にわたる長期入院者が数多 く現れるとい
う構造は、「死ぬまで精神病院に収容され続けるJという公費息者の入退院のデモグラフイーが、
結核の克服、衛生状況と栄養状況の改善、そして抗生物質の利用による梅毒性の精神病の減少と
いう精神科の疾病構造の変化にともない、入院から死までの時間が引き延ばされた結果であると
考えることもできる。そうだとしたら、戦後の精神病院における入退院の構造は、「死まで在院
し続けるJと いう戦前における公費患者の人退院の構造をもとにして、患者の量的拡大 と病院内
での寿命の伸展の結果作られたものであると考えられる。
5.薬 剤 と治 療 法
前章では、王子脳病院において、公費患者と私費患者の在院のデモグラフイーが大 きく異なる
ということを論 じた。この章では、両者は滞在の内実、特に治療の実施とその意味においても大
きく異なっていることを論 じる。
公費患者は、それが精神病院法のもとの代用患者であれば、国から六分の一の補助のもと、各
府県から息者一人 一 日あたりにつきいくらという形で定まった金額が支給される仕組みになっ
ていた。その金額は府県により異なっていたが、1921年の東京を例に取ると1円 5銭 であつた。
精神病院の建造物や人員配置については、東京府の場合は警視庁によって比較的厳密な基準が定
められてお り、敷地周囲には高さ18メ ー トル以上の塀を設けることといった治安 監 禁的な規
則、運動場 娯 楽室の設置といった患者の生活環境に関する規則、医師は患者 50人 につき一人、
看護人は患者 5人 につき一人以上といった人員の基準をクリアする必要があり、そのうえで一定
の金額のもとで代用患者をり|き受けることになっていた。その条件で、公費の息者に対 してどの
程度の生活水準を提供できたのかよく分からない。一方、ほぼ同じ時期の私費患者の入院費は食
事つきで最llt一日2円 からで、王子脳病院の特等は一日5円 、小峯病院の特等は9円 であった。
公費患者と私費患者の間に提供 された生活に差があったことは確かであった。図 2で確認 したよ
うに、王子脳病院では公費と私費の患者の生活の区切 りはゆるいものであり、両者の生活空間は
共有されていたので、代用患者と私費患者は互いに生活の違いをまざまざと見ることになってい
た。表 3症例 Gの 女性は、当初は私費扱いで入院し、2ケ 月あまり後に代用扱いとなった患者で
あるが、彼女は初めて代用扱いになったときに怒 りを表明 している。
35
表 4 患 者 Mに 与えられた治療のようす
アーカイブズ学研究 No 18(20134)
「昼の食事、前と変り、代用の法 [ママ]よ り食事が来たのに対し非常にいかり、看護婦
の言うことなんかなかなか聞入れず。食事は完全に食せしも窓を開きて 『まもる、むかいに
来てくれ』などと大声で言居られる。J(19311224)
この記述から推察するに、代用意者向けの食事と私費患者のものとは、調理や配膳の場所や仕
組、あるいは品数や内容が違っており、はっきりと目に見えて違う形で差異化されていたのだろ
う。病院内では他の患者の食事を盗む 「盗食Jは きわめて一般的であったが、この背景には同一
の生活空間で違う食事が出されていることがあったのかもしれない。
私費患者と公費患者の食事の格差は詳細には分からないが、治療の格差は症例誌から鮮明に現
れる。当然のことであるが、治療に対して支払いをする私費患者には潤沢に一場合によっては過
剰に一治療が施された。それを最も雄弁に語っているのが、表3息者Mに 与えられた治療をま
とめた表4である。この患者は、入院当時35歳の女性で、1933年6月 15日に入院して lo年あ
まり私費息者として在院し、1943年9月 15日に退院した。未治退院ではあるが、その横に 「入
院時より精軽 [快]」と記されている。lo年間私費患者として在院したことが示唆するように、
この患者は日本の富裕層 上 流階級に属しており、父親は官内庁の勅任官で、著名なミッショ
ン ス クールの女学校を卒業していた。結婚してすぐに夫と死別し、入院当時は子供一人と夫の
母親とともに暮らしていた。表4は 、鎮静 催 眠系の薬効をもつ薬剤についてはそれぞれの薬品
ごとに、それ以外の薬品については、その主たる作用によって「強心 強 壮J「栄養J「殺菌消毒J
「ホルモンJ「インシュリン」「その他 不 明」に分類して、投与された日数を一日1回として数
えたものである。薬剤の性能については、1948年に非几閣より発行された 『最新医薬品類衆』
全5巻 を参照した。
月経 浣腸 下剤ダ f tよ ダ メ Lらレ 季 :
その他
鎮静
睡眠
静計
鎮合 栄養殺菌童夕:;『果詣
剤数
葉日「レ
備考
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
16 16 90 o
9 2 0 0
67 16 20 155
29 10 0 226
86 フ 8 44 146
100 142 0 114
62 98 0 250
5 26 0 0
29 85 0 45
0 45 0 0
2 21 0 214
0 0 0
1 0 0
15 0 o
8 0 0
7 0 o
0 0 o
1 0 0
31 0 0
102 315 0
39 231 133
146 11 241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
9
90
1
190
234
19フ
114
251
31
462
424
621
178
20
74
3
1
0
0
0
10
0
5
380
155
308
393
460
388
555
217
860
5 1 9
758
90 2
0 0
1 0
3 75
0 1
0 0
80 0
12 0
63 0
25 0
3 0
4 0 0
91 0 41
0 0 27
0 0 68
17 141 25
17 32 83
3 4 119
0 0 148
0 0 240
0 0 25
0 0 108
36
昭和戦前期精神病院のFI例誌について (鈴木)
まず、同表は、彼女が王子脳病院で過ごした 10年のあいだに、複数の種類を変えて組み合わ
せなが ら鎮静剤の利用が漸増 していつたことを示 している。入院当初の 12年 は、神経系への
作用を通 じて鎮静作用 催 眠作用をもつ薬品が使われる頻度は低かつた。しか し、3年 目の 190
回をはじめとして、パピア ト、ナルコポン、ルミナール、モヒア ト、ア トロピンなどの鎮静剤は
次第に頻繁に数多 く用いられるようになった。1941 42年 にはいずれも400回 と一 日1回以上
のペースで、8か 月間滞在 した 1943年には621回 と一日25回 以上のペースで鎮静剤が用いられ
た。また、併用される薬剤の種類 も増えていつた。在院期間の前半には 1種類から3種類の併用
だったのか、後半には5種類までの薬剤が併用されるようになっていつた。滞在の最後の年の 3
月から7月 は、ナルコポン、ルミナール、モヒア トを毎日併用 している状態であつた。それぞれ
の薬剤の性格についてより詳細な調査が必要だが、常識的に判断して、鎮静剤の継続的な使用に
よってある薬剤に対 して患者が耐性をもち 「効かなくJな るために、種類を変えながら量が増え
てい く過程がここに見てとれる。この女性患者 Mは 、在院中に、神経系に作用する複数の薬剤
の薬漬け状態に移行 したといってよい。
表 4は 鎮静 催 眠の葉剤以外 もこの女性に与えられたことを示 している。これらの薬剤は、そ
れぞれの段階での症状や彼女の状態に対応 して与えられていた。入院直後にまず問題になつたの
は衰弱 と体重減少であつた。入院する 1年前の 1932年 7月 頃から、彼女は拒食 不 眠 独 語
無断外出 徘 徊の症状があり、1933年 4月 頃からは著 しい抑鬱状態であった。拒食のため、入
院時には体重が 23キ ロしかない状態であ り、入院してからも彼女の拒食は続 き、翌月は209キ
ロにまで減少 した。拒食のために衰弱症状がはげしく、樟脳から製 したビタカンファー、デギタ
リスから製 したデギタミン、カフェインを含むアンナカなどの強心剤が多 く投与 された。栄養を
補うために詳細は不明であるが 「人工栄養」が与えられ、ブ ドウ糖注射 (「ロデノン」)や 、ビタ
ミンBl剤 である照内末、肝油から製 したヤノールなどが与えられた。その後病院で食事 もとる
ようになって体重は急速に回復 し、半年で20キ ロの増加をみた。入院当初は衰弱を防いで栄養
を摂取させることが治療の中心であった。
体重の次に重要なターゲットとなったのは、生殖腺の機能である。1933年 6月 に入院してか
ら1934年 3月 まで彼女は無月経であった。一般的に言って女性の月経 と精神病を結びつける言
説は根強 く、体重を回復させた王子脳病院の医者たちが彼女の月経を回復させることを次の日標
にしたのは自然な流れである。1933年の 12月から、「メタロザール」と記 された薬 と卵巣製剤
であるオバホルモンがセットにされて3日 ごとに投与され、1934年の 1月 にはメタロザールと
卵巣製剤のベラニンの組み合わせに切 り替えられる。同時期にギナンドールという別の卵巣製剤
も投与された。「メタロザールJと いう名称の薬剤は確認できなかったが、いずれも卵巣製剤 と
セットで投与されていることから判断して、ホルモン製剤の一種であると判断される。このホル
モン剤の投与のあと、患者の月経は不規則なが ら回復 し、1934年には8回 の 1935年には6回 の
月経がみられる。体重と同様に、生殖腺機能の乱れについても、それを某物によつて矯正するこ
アーカイブズ学研究 No 18(20134)
とが行われていたのである。
それ以外にも、息者 Mに はあふれんばか りの薬 と治療が与えられた。1937年から1938年に
かけての活発なインシュリン系の薬品投与は、当時新 しい治療法として注目されていたインシュ
リンショック (昏睡)療 法の試みである。1939年から1940年末にかけては 「特薬Jと 記されて
いる内容が不明な薬剤が長期間にわたって投与されている。動物の脳から精製 した 「セレブロホ
ルモン」や、「空気イオンJ「超短波J「赤外線Jな どの少なくとも王子脳病院ではマイナーな療
法 も試された。それが妥当なものであったかどうかはさておき、私費患者 Mの 10年間の入院は
治療の試みで埋め尽 くされたものであ り、収容よりも治療に重′し、がかかったものであることは明
白である。
患者 Mは 長期滞在であるが、短期滞在の私費患者においても治療的な性格がより鮮明に現れ
る。表 5は 、1940年に退院 した患者から30件 の患者記録 (私費 27人 、公費 3人 )を サンプリ
ングしたものにおける治療法の使用を一覧表にしたものである。治療法としては、当時の新治療
法から1)マ ラリア発熱療法、2)イ ンシュリンショック療法、3)電 気痙攣療法 (ECT)、4)カ ー
ジアゾル痙攣療法、の四種類を選び、それ以外の薬品の利用を一括 して 5)他 の薬品とした。マ
ラリア発熱療法については実施 したか否かを、それ以外の治療法については、実施された日数を
記 した。
表 5が 示すことは、1940年の段階では、多 くの私費患者にとって精神病院が治療的な性格 を
持ったもの、それも最先端の治療を受ける場所 としてはっきりと位置づけられていたことであ
る。インシュリンショックは三分の一以上の27人 中 10人が、ECTは およそ半分の27人 中 13
人の患者に試みられている。27人 の患者の延べ在院日数の中でインシュリン昏睡は 125%、
ECTは 105%を 占めている。これらの治療法は、それぞれ二日から数日間の間隔をあけること
が多いので、2割 から5割程度の日数がショック療法のコースに当てられていたことになる。何
よりも、これらの最新治療法について、入院から治療が始まるまでの日数が、すべて四日以内で
あることに注 目すると、入院の目標そのものがこれらの治療法を受けることであったことが推察
できるだろう。また、これらの治療法を受けたあと、思者は長居をすることなく速やかに退院し
ている。前節で見たように、私費患者には軽快や未治で退院する割合が高いのも、治療のコース
が終わると退院するという利用のパターンと関係があるのだろう。
すなわち、王子脳病院の私費セクションでは、インシュリンショックゃ ECTな どの一定の効
果を持つ治療法が導入された 1940年の段階において、そこに治療を 「日的としてJ在 院する特
徴が現れていた。精神病院の目的を、全治させることであり、患者を通常の社会生活、特に職場
に戻すことであると狭 く捉えるとしたら、これらの私費患者が軽快 未 治で退院 したということ
は、精神病院の失敗であり不完全であることを意味する。しかし、別の見方をすると、王子脳病
院で治療を受けたあとに軽快 未 治で退院 した患者たちは、別の場所 (おそらく家庭)で ケアを
受けていたことになる。すなわち、精神病 精 神障害を持つ人々のキュアとケアの長期的なサイ
E召和戦前期精神病院の症,1誌について (鈴木)
表 5 1940年 退院の患者 (サンプリング)に おける治療法の一覧
番号 性 別 病 名 年 齢在院期間
(日)
人院から
治療が始まるまで
の日数
マラリア
発熱
インシェリ
ンショック
(日)
電気痙撃
(日)
カージアブル
痙撃 (日)
他の薬品
投与 (日)転 帰 it言己
私費患者
1 男 早 27 62 3 22 55 軽 快
2 男 麻 41 37 3 0 14 未 治
3 男 53 2 40 全 治インシュリン
失敗
4 男 ll 43 4 O 32 未 治
5 男 ll 30 1 0 13 未 治
6 男 甲 25 91 2 21 4 ll.快
7 女 うつ 11 1 1 軽1央
8 男 FF 87 軽1夫インシュリン
失敗
9 男 早 3 32 21 9 軽 快
女 (麻) O 52 軽 庚
1 1 男 早 51 3 2 未 治インシュリン
失敗
男 躁 7 6 タヒ定=
男 麻 37 1 0 14 軽 快
女 11 l 軽 快
男 麻 10 未 治
16 女 早 1 52 軽 医
17 女 早 61 1 未 治
男 痴 呆 4 17
女 早 2 26 軽1夫
20 男 早 3 5 未 治
女 42 軽 R
22 女 早 3 軽 庚
23 男 痴 呆 27 3 1 1インシュリン
失敗
24 女 早 43 1 5 軽 快
男 早 17 2 3 軽 快
26 男 早 27 119 4 14 軽1夫
27 男 酒 中 34 9 全,台
4 言ヽ| l,3
( 1 2 5 % )
162
( 1 0 5 % )
966(62.5"n )
公費患者
女 麻 0 1 死 亡
男 麻 35 78 0 13 タビt=
男 早 66 0 死 亡
」ヽ言| 1127 0 0 0
(r.e7" )病名 :早 =早 発性痴果、麻=麻 痺性痴呆 う つ=欝 病、躁=躁 病、酒中=酒 精中毒
アーカイブズ学研究 No 18(20134)
クルにおいて、精神病院はインテンシブな治療を施 し、家庭などにおいてはより長期的なケアが
担われるという役害」分担が発生 していたことになる。
一方で、公費患者のサンプル (症例 28.29,30)|こ おいては、私費患者 とは興味深い仕方で
異なった治療法のあり方がうかがえる。マラリア発熱療法は全員に施されているが、インシュリ
ンショックとECTは 用いられておらず、他の薬物はごく少ない。他の公費患者の記録を参照す
ると、ECTは まれではあるが無視できない頻度で行われているが、インシュリンショックは見
当たらない。暫定的に言えば、マラリア発熱療法はルーティンとして公費患者に行われ、ECT
も時折行われたが、インシュリンショックは行われず、他の薬品も私費患者より使用は非常に少
なかったというパターンが見える。インシュリンショックが行われなかったのは、その薬品その
ものが非常に高価であったことによるのだろう。
戦前の精神病院の公費部門は監禁施設という■1面を持っていたのは疑いえない。その入院の多
くは、徘徊 し事件を起こした患者が警察に捕らえられるという事件をきっかけにしている。警察
は多 くの公費患者の入院について間接的に関与 している。 しか し、進行麻痺の患者に対 しては、
必ずマラリア療法が施 されていたことは一定の強調をしなければならない。公費患者であって
も、マラリア療法は受けていたのである。 しかし、それと同時に、マラリア療法を精神病院内で
実施するためには、マラリア原虫を患者から患者に植え継いでいく必要があったことにも注意 し
なければならない。マラリア療法は、それを受ける患者への治療であると同時に、他の患者のた
めにマラリア原虫を培養するという意味も持っていた。症例 30の患者が、早発性痴呆の診断で
ありながら、マラリア療法を受けていることは、治療の目的と同時に原虫の培養器として用いら
れた可能性を示唆 している。
マラリア療法を除 くと、公費患者が受けていた治療は少なく、また彼らに与えられた薬剤は治
療と言うよりも管理の側面を持っていたと言える。表 6は 、長期在院した公費息者から3名 を選
び、看護日誌に書かれている記録から、その患者たちの様子を一覧表にしたものである。看護 日
誌の記述の中から 「作業 手 伝い 娯 楽室での活動J「交話」「退院請求」「(精神疾患以外の)病
気J「茫然無為」「独語空笑」「憂鬱悲嘆」「妄想J「色情行為」「不潔行為」「徘徊」「興奮J「反抗」
「不良行為」「暴行J「薬物投与Jの項目を選びだし、一ヶ月を前半 後 半の二つの期間に分けて、
それぞれの期間に、その項 目にあう記述が一度以上あった場合には、その期間にポイント1をつ
け、それを年ごとに合計 したものである。
40
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
作業
年 手 伝娯楽
表 6 長 期在院公費患者のようす
交話賽漿
病気量管 埜貢 贔麓
妄想 色情 不潔 徘徊 興奮 暴行 反抗葬量
薬物
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
3
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
3
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
17
19
9
17
2
6
19
17
22
24
24
24
1934
患者 A 1935
41歳 (女)1936
7年 滞在 1937
死亡 1938
価 溢血)1939
1940
患者 B22歳 (女)
早9年 半滞在
死亡
(肺結核)
9 8
14 20
21 18
13 9
8 2
10 3
17 0
5 1 17
3 9 22
1 11 24
4 12 23
16 22 23
9 16 23
4 7 23
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
2
0
0
0
0
0
0
18
5
4
23
23
24
21
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5
4
5
2
0
0
0
0
8
5
2
3
0
0
1
8
3
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
4
2
0
1
患者 C26歳 (男)
早9年 滞在死亡
(肺結核)
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
7
0
0
0
1
3
20
8
5
6
9
5
4
4
11
17
13
0
0
0
0
0
0
0
0
14
6
0
0
1
3
18
1 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
15
8
6
1
4
7
8
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
7
5
6
4
1
0
0
0
11
11
9
5
12
2
1 1
3 3
5 0
3 3
5 4
4 3
9 12
11 5
患者 Aは 、入院時には41歳の女性であり、診断は妄想性の早発性痴呆であつた。入院までの
経過については本人が語ったところによれば、広島生まれで東京に上京 し、髪結いや料理屋勤め
などで金を貯めるが、病気や商売の失敗が重なったうえ、内縁の夫に捨てられたという。入院後
は、医者が記 した病床日誌によれば、内縁の夫に毒殺されかかつたことや、退院させないと大地
震が来るなどの妄想を語るが、退院請求がいつさい聞き入れられないと、徹底的な 「拒診Jを す
る。昭和 10年の秋ごろから、死の二ヶ月まえの 1940年の 10月ごろまで、カルテは日付 と医師
名のゴム印にところどころ 「拒診Jと 書きいれられるだけの状態となる。そのあいだ、医者には
きわめて敵対的な態度をとり続けていた。1937年 H月 6日 には、「診察せんとすると顔色を変
えて 『馬鹿ヤロウ。ハシタ野郎、こんなところに居候にきやがつて』」と医者がのの しられ、医
者から患者から看護婦から、ぜんぶ私が食わしているんだと、妄想を交えて医者を怒 り、看護婦
41
アーカイブズ学研究 No lS(20134)
が,、とんに少しでもふれると、シラミがついたといって、シラミをとってつぶす真似をする
( 1 9 3 7 1 1 6 )。
医師側の記録からは、医師との関係が非常に険悪である様子が浮かび上がる患者 Aで あるが、
看護記録においては、むしろ模範的な患者像がうかがえる。表 6を みると、「作業 手 伝い 娯
楽」、すなわち、作業室での作業や他息者の世話の手伝い、娯楽室での他の患者 と花札をすると
いつた、精神病院の中で円滑な社会関係を営んでいるポイントが高い。「交話Jの ポイン トも高
く、他の患者 との関係もすこぶるよい。人院当初から、他の患者と身の上話などを談笑 している
のが見られる (どこまで妄想であるかは別にして、彼女の身の上話に他の女性患者が耳を傾けた
ことは容易に想像できる)。時として他の患者にあんまをしたり (193452)肩 をもんだりしてい
る。だからといって精神症状がないわけではない。「独語空笑Jと いう精神病の症状を記述する
のにしばしば用いられる言葉は、ほぼどの期間においても使われてお り、妄想も時折記録されて
いる。 しかし、これらの精神病の症状は、色情的行為、不潔行為、廊 ドの徘徊、興奮、看護人や
他の患者への暴行、あるいは不良行為などをほとんどともなっていない。その意味で、息者 A
は、精神病の症状は常に存在 してお り、医者 との関係は険悪であったが、看護人と患者との対人
関係は良好であ り、病院内での空間的時間的秩序を守 り、社会性 も高い生活を送っていた。一方で、それと対照的なのが患者 Bで ある。Bは 1932年に入院 しているが、当初の二年間の
看護 日誌は失われているため、表では 1934年からの看護日誌からのポイン トをあげている。B
は入院時 22歳 で、生まれは台湾で、母はその名前から台湾人であると推察される。高等女学校
を卒業 して結婚するが数年で離婚 し、離婚の話が持ち11がってから、脳の中や腹の中に人が入っ
たなどと騒 ぐようになる。離婚 して実家に帰 り、寡婦 となった母と、連れてきた自分の子供に暴
行 し、巣鴨の保養院に一カ月収容されたのち、代用患者 として王子脳病院に 1932年 2月 に入院
した。
患者 Bの 病床 日誌から、患者 Aと 同様に、医師との関係は悪いか不在であることが読み取れ
る。1934年には、医師に暴行 し、拒診する。1935年からは、「呆然」「不管性J「不関性Jな どの
言葉が使われることからも分かるように、医師との応答が成立 しな くなり、1935年9月 から日
付 と医師名のハ ンコだけがカルテに並ぶ ようになる。入院 して23年 で、医師 とのコミュニ
ケーションが取れないか、そのルー トが存在 しない息者になっていた。この点では、患者 Bは
患者 Aと 大きな違いはない。
しか し、患者 3が 看護婦たちと持った関係は、患者 Aの それとは全 く違ったものであった。
息者 Bの 看護 日誌は、彼女と看護婦たちのすさまじい苦闘をまざまざと見せてくれる。1934年
3月 からの看護日誌は、他の患者を打ち、他の患者の食物を盗み、食器に五本の指を入れ、着衣
やふとんを破 き、着物をまくって下腹部を出し、手や着物の綿を陰部に入れる 「色情的行為」が
毎日のように行われ、 しかもそれが数年にわたって継続 していることを示 している (193562.
19381021)。そのため、患者 Bを 表で表すと、「作業 手 伝い 娯 楽J「交話」のポイントが低
42
昭和戦前期精神病院の症例誌について (鈴木)
くな り、「不潔J「暴行J「反抗」「不良行為」などのポイントが高い。ちなみに、患者 Bの 行為
については、看護婦たちは、明確に意図された「反抗Jであ り、自分たちを困らせようとして行っ
ている 「不良行為Jで あると捉えていた。「注意するとかえって意地になるJ「なんとかして人の
困るよう、困るようにしている。注意なせばなすほど意地になってせるなり」(1938923)「本日
も相変わらず火鉢の上にあがつて看護婦が注意 しても一行[いっこう]聞き入れず、反対をなす。
強き注意をすれば反行 [反抗]を なす。注射をなせば、あだをなす。手の付けようなく、昼間髪
を乱 しておらるJ(19371214)。 看護婦たちは患者 Bの 症状の変化に比較的敏感で、さまざまな
好転の機会を捉えて記録 していた。「本日余興がありて、他患者が行ってしまうと自分 も行 くの
だと騒いでいる。つれていって差 し上げると静かに見ておられたJ(19341021)「 お正月なりと
申して新 しい衣服に取 りかえれば非常に嬉 しそうにして割合に看護婦の言 うままになりおるJ
(193711)「熱発 して後、少 しくはっきりして来たように見受けられる。時折、体の不潔を気に
して入浴が したいとか体をふいてほしい等 と申さる」(1938H9)。 しか し、このような希望は、
次々と打ち砕かれた。お正月の新 しい着物は一ケ月もたたずに破 られ、その年の春には彼女はま
た半裸で色情的行為を繰 り返 していた。だっこしてお風呂に連れて行ってと看護婦に甘えたあと
は、気に入らないことがあるといって風呂場で放便 した。希望が現れては消え、「不潔」「暴行J
「反抗J「不良行為Jが 繰 り返されるなかで、Bの 入院は9年 以上 も続いた。なお、患者 Bに 物
理的な拘束が行われたのは、少なくとも看護 日誌に記録 されている限 りにおいては、1935年 4
月 8日 と7月 1日 に手が縛られた二 日しかなく、それ以外は、居室や廊下を比較的 「自由に」う
ろついていたことを言い添えてお く。
そ して、息者 Aと 息者 Bと の対比の中にお くと、Bだ けに薬物が与えられたことの意味が明
らかになるだろう。患者 Bに は 1937年 7月 以来、ナルコポン、スコポラミン、ル ミナール、ベ
ロナールなどの神経系に作用する薬剤が投与 される。これは、明らかに問題患者を病院内で管理
するための薬剤であつた。これらが投与されたときには、暴力行為を鎮めるための注射であった
ことがはっきり分かる。1938年 2月 26日 には、「他患者を打つのでル ミナール注 [射]、施行すJ
と記されている。1933年 1月には、一ケ月に 11回のルミナール注射が行われ、これほど多 くは
ないが、1937年にも月に数回の割合でルミナール注射が行われている。また、「反抗Jが 多かっ
たBに 対 して、他の代用患者にはあまり見 られない電気痙攣療法 (ECT,「電痙J)が 行われた
ことにも注 目するべ きである (1939H21,19391224,194012,1940312)。 上でみたように
ECTは 治療を求めて短期で入院 した私費患者にも頻繁に実施されたが、患者 Bに 対 して行われ
た電気痙攣療法は、それとは意味合いが違う。早発1生痴呆 分 裂病を治療する手段であると同時
に、興奮を鎮める手段であり、問題行動と反抗に対する懲罰のニュアンスも一定程度は持ってい
たと考えられる。ちなみに、それは必ず しも強力で有効な懲罰の道具ではなかった可能性 もあ
り、1940年に行われた電気痙攣療法は、少 しは状態を改善 したのかもしれないが、息者はす ぐ
に裸体で窓にのぼって放尿するようになっていた。
43
7-h 4 ./f+nfrk No.t8 (20t3.4)
患者 Cに おいても、その薬の利用のパターンは思者 Bと よく似ている。患者 Cは 入院時 26歳
の男性で、父母はすでに没 し、福島県の農村から兄弟で東京に移住 してきた労働者であった。彼
は 「自分は子爵である」などの強固で明確な妄想を持ち、日本医科大学の臨床講義に連れて行か
れるなど、医学的な価値が高い患者であったため、医者たちの病床日誌は当初はかなり充実 して
いる。看護日誌によると 「他患とも談話 しない。頭から羽織を被 り、茫然として室隅にうず くま
り居る。看護人が何かたずねても少しく不機嫌に応答Jと ある。このような自己の世界への閉鎖
と他患者や看護人を含めた外界への無関心が彼の世界を圧倒するため、作業 娯 楽のポイントや
交話のポイントは著 しく低い。 しかし、この茫然無為の世界に、時として発作的な暴力が現れる
ため、散発的に 「興奮」「暴行」「不良行為」などを起こし、そのポイントが上がっている。
これらの散発的な暴行に対 しては、薬物による対処が試みられた。患者 Cは 、1935年の 2月
からズルフォシンの注射を受けるようになった。2月 に6回 、3月 にも6回 受けている。このあ
とも、月に数回の割合で 1940年までズルフォシンの注射が記録されている。この注射について、
そのすべてではないがかなりの件数が、興奮や暴行に対 して鎮静効果を持つことが期待されてい
たことは間違いない。例えば、1935年 6月 1日 には 「落ちつ きなく興奮。陰部露出 して平気。
午後ズルフォシン3 0cc」、1937年 8月 14日から18日にかけて、「興奮 し多動多弁あ り。硝子一
枚破 りお り。ルミナール20瓦 J「独語怒号を発す。ズルフォシン2 0cc注射」「廊下窓硝子二枚
破る」「窓硝子 1枚破る。ズルフォシン25瓦 」のような記述がある。茫然無為の生活の中で時
折興奮 し暴行 してはズルフォシン等を打たれるというパターンは、1935年から40年 まで、息者
Cの 生活の一つの要素となる。
以上の記述から、王子脳病院の患者に対する薬剤や治療法の使用は、私費患者と公費患者にお
いて明確に違っていたことが分かる。その違いは、私費患者が料金を払って治療を受けることが
多かったというトリヴイアルな違いだけではなかった。私費息者にとっては、治療の意味合いが
強い短期滞在という精神病院の利用が一般的であ り、その文脈の中の薬剤であリインシュリン療
法であり電気痙攣療法であった。一方公費患者においては、長期滞在の中で在院生活の秩序の侵
犯を減らすという意図で行われた薬剤投与であ り電気痙攣療法であった。この対比は絶対的なも
のではなく、この小論では詳細に触れなかったが、私費患者の中にも治療を目的としなかった長
期在院者はいたし、また、私費で短期であっても、精神病院への入院自体が、ある種の懲罰的な
意味合いを持っていたと思われる患者は存在 した。 しかし、大きな構造としては、治療を目的と
して精神病院の生活が構造化されていた私費患者と、入院生活に秩序をもたらすことを目的とし
て薬剤や治療法を施されていた公費患者の違いを指摘できる。
6.症 例 誌 の歴 史的 な利用 の展望
この小論は、現在進行形の研究の途中経過報告という性格を持っており、この段階で示すこと
ができるデータなどをもとに、考えている方向性を提示するものである。王子脳病院の症例誌は
44
昭和戦前期精神病院のll例誌について (鈴木)
多 くの長所を持つが、短所 も持つ史料である。特に、私費患者については診療報酬の情報がな
く、公費患者について行政的な情報が欠落 していることが短所である。 しかし、精神病院の症例
誌は、精神医療の歴史を書 くのに必要な史料のネットワークのうち、最大で最重要なものである
ことは、少なくとも欧米での精神医学の歴史研究の進みかたをみる限り、疑うことができない。
私たちは、既存の症例誌の使い方を工夫して、そこからどのような問題を問いそれに応えること
ができるかという方法論の問題を議論することが必要であろう。それと同時に、別の精神病院の
症例誌の確保や、それと関連する文書の確保、家族の文書など、精神病院の症例誌が示唆する
ネットワークを復元するようなアーカイブを作 り上げることが必要であろう。そのような歴史研
究が可能になるために、何 らかの貢献ができればと思って、この小文を寄稿 させていただいた。
【注記】この小文は、近く法政大学出版局より上梓される山下麻衣編集の 『歴史の中の障害者』
に執筆した 「脳病院と精神障害の歴史」と内容が重なる部分がある。
文献一覧
関根真― (1971)『落葉かき』私費出版。
東京精神病院協会 (1978)『東京の私立精神病院史』牧野出版。
西井烈 (1933)「精神病と結核J『読売新聞』19331110朝刊 9頁、1933 H H朝刊 9頁、1933H12朝 刊 9頁。
兵頭晶子 (211118)『精神病の日本近代―憑く心身から病む′き身へ』青弓社。
フーコー、M(1975)田 村椒訳 『狂気の歴史』新潮社。
ポーター、R(1993)日 羅公和訳 『狂気の社会史』法政大学出版局。
Prcssman,Jack(1998)Thc Last Rcsort Psychosurgcw and mC Limits of Mcdicinc,Calnb五 dgc:
Prcss
Braslow, Joel (1997) Mental Ills and Bodily Cures: Psychiatric Trcatment in the First Half of
Berkeley: University of Califomia Press.
Melling, Joseph aod Bill Forsythe (ZOOO) potitics of Madness: The State, Insanity and Society
Cambridge University
the Twentieth Century,
in England 1845-1914,London:Routlcdgc
Scull,Andrcw(1993)Thc Most Solita,of AfnictiOns:ヽ 4adncss and Socicty in Bntain 1700-1 9Klll,Ncw Havcn:Yalc
Univcrsity Prcss
Roscnbcrg,Charlcs(1992)Explalning Epidcmics and Othcr Studics in thc Histo,of MCdicinc,Camblldgc:CambHdgc
Univcrsity Prcss
Walncr,John Harlcy(1987)Thc Tllcmpcutic Pcrspcct市 c Mcdical PratSticc,Knowicdgc,and ldcntity in Amcrica,1820-
1885,Cambndgc,Mass:Harvald Univcrsity Prcss
VヽHght,David(1997)・ Cctting Out Of thc Asylum: Undcrstanding thc Conflncmcnt of ulc lnsanc in thc Ninctccnth
Ccntuヮ',SoCial Histow of Mcdicinc, 10, 137-155
針ンに 晃 イニ 慶 應義塾大学
Akihito SUZUKI Kcio Univcrsity
45
アーカイブズ学研究 No 18(20134)
「研究集会 医 療をめぐるアーカイブズ」参加記
廣 り‖ 和 花 waka HIROKAWA
2012年 11月 25日 (日)、神奈川県立公文書館にて開催 された日本アーカイブズ学会 2012年
度研究集会に参加 した。アーカイブズ学会の催 しに参加するのは実は初めてだったが、会はオー
プンな雰囲気で運営されてお り、行 き届いた準備のもと、報告 議 論ともに充実 した内容でたい
へん勉強になった。この場を借 りてまずは御礼を中し上げたい。
本研究集会は 「医療をめぐるアーカイブズJを テーマに、芹澤良子氏 「医療史研究と史料―ハ
ンセン病対策の事例から一Jお よび鈴木晃仁氏 「昭和戦前期精神病院の症例誌についてJの 二報
告が行われ、コメントは石原一則氏、司会進行は青木祐一氏によってなされた。各報告の内容
は、本号に掲載されるとのことであるので、簡潔にまとめるにとどめ、以下では、主に筆者が近
代 日本医学史を専門とする歴史研究者として、このテーマに関してこれまで考えてきたことと、
本集会に参加 しての感想や印象を述べてゆきたい。
医学 医 療に関する資料についての、アーカイブズ学的な恨1面からの研究は、特に日本国内で
は未開拓の分野である。アーカイブズ学の学会で、このテーマがメインに据えられたのは、この
研究集会が初めてといってもいいのではないだろうか。アーカイブズ学の分野では、医療に関す
る資料は、それが個人の病歴に関するものであるときには特に、個人情報の最たるものとして、
いかにそれを慎重に取 り扱うべ きかということが、断片的に論 じられるにすぎなかった。もちろ
ん、アーカイブズの現場では、さまざまなケースの蓄積や個別の判断事例が慎重に重ねられてき
たものと推察される。しか し、まとまったモノグラフは今のところ存在 していないため、これら
の現場の経験や洞察が十分に共有されず、資料の保存 公 開 利 用に生かされていないように見
える。開催趣旨でも触れられていたとお り、今日わたしたちの身の回りのさまざまな現場では、
膨大な 「医療Jを めぐる情報が日々生産され、適切な方法で保存されるべき資料やデータが目の
前に山積みになっている。このテーマでの研究集会は、時宜に叶った企LAlであつたと思う。
管見の限り、これまでにこの主題をめ ぐって学会で議論された記録 としては、1998年の日本
医史学会総会シンポジウム 「日本における医史料の蒐集と保存について一その現状 と提言―J、
同学会例会 ミニシンポジウム 「日本における医史料の保存についてJ(以 上の内容は 『日本医史
学雑誌』第45巻特集号、1999年 12月に収載)が まず挙げられる。ここでは、主に医学古典籍
を 「医史料Jの 中核 とみなし、それを集約的に保存収集する医学図書館、あるいは医学史料館が
構想 提 言されていたことがうかがわれる。しかし、ここで日指された方向性は、資料の現地保
存法則などを度外視 している等、アーカイブズ論としての視野の狭 さと限界性を有 してお り、現
在の医学史 医 療史研究の多様化 (現在では、医学史研究のために古典籍のみを保存すれば事足
りるというものではなくなっている)の 一方で、資料保存一般にかかるインフラ整備が厳 しさを
増 している状況下では、残念ながら実現にはほど遠いものとなっている。
最近の例では、20H年 10月 に開催された第 15回精神医学史学会でシンポジウム 「精神医療
史資料の保存 と利用Jが開催 され、筆者 もパネリス トの一人となった (シンポジウムの内容は 『精
神医学史研究』第 16巻 1号、2012年に収録 されている)。大会長をつ とめた橋本明氏は、共同
![Page 1: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: [Case Histories from a Psychiatric Hospital in Tokyo, c.1925-c.1945] in Japanese](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023033112/6331b59a4e014304030051a6/html5/thumbnails/24.jpg)