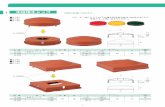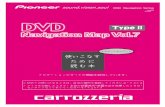松尾芭蕉の詠む俳諧恋句について(A Study on Matsuo Bashō’s Haikai Poems on Love)
Transcript of 松尾芭蕉の詠む俳諧恋句について(A Study on Matsuo Bashō’s Haikai Poems on Love)
1
松尾芭蕉俳谐恋句研究
松尾芭蕉の詠む俳諧恋句について
A Study on Matsuo Bashō’s Haikai Poems on Love
Zike Zhang
Department of Japanese Language and Culture
Peking University
2
内容提要
松尾芭蕉这个名字在日本可谓是家喻户晓。作为古往今来最杰出的俳句诗人,他留下的
佳作例如“古池冷落一片寂,忽闻青蛙跳水声”等俳句更是为人们广泛传颂。东明雅曾在其
著作《芭蕉的恋句》1中出,后世的人们在欣赏芭蕉的作品之时,眼前时常会浮现出如此情
景:一位老翁独自行走在风雨飘摇的原野中,时而驻足仰望松岛间慢慢升起的那轮明月,时
而远眺夜半时分横亘佐渡岛绚烂的银河,时而怀着一颗禅心小憩古池边,细细地聆听青蛙跳
入水池的声响……芭蕉就像是一名心中不怀任何杂念与欲望的修行者,向人们讲述着“旅
途”、“自然”以及“风雅闲寂”的精髓。
随着笔者步步深入品读芭蕉的作品,心中却开始出现了这样的疑问:仅用“旅途”、“自
然”和“风雅闲寂”这样的字眼,当真可以概括芭蕉全部的艺术人生吗?事实上除了“旅途”、
“自然”和“风雅闲寂”,他还以饱受相思之苦的少女、闺中思妇、对家中妻子的思念等为
主题进行了许多俳句创作。这些刻画恋爱的俳谐诗句被统称为恋句(分为前句和附句)。芭
蕉的恋句作品精炼巧妙,句句饱含作者深厚真挚的情感——无论哪一则都可谓是不输“古池
冷落一片寂,忽闻青蛙跳水声”的上乘佳作。本文以此疑问为出发点,着眼于芭蕉的恋句作
品,旨在考察这些句子映射出的芭蕉的人生轨迹和艺术境界。
本文以贞享元年至元禄七年中芭蕉俳谐中出现的恋句为研究对象,从中选取代表性的例
子进行分析研究,并从三个问题点切入,即:芭蕉是如何刻画恋爱这个主题的?他的恋句作
品反映出“蕉风”怎样的审美价值?他又是以何种的心境来进行创作的?笔者希望能够以此
来理解并把握“蕉风”恋句的整体特征。
关键词: 松尾芭蕉 蕉风俳谐 恋句 特征
1 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店.
3
要 旨
松尾芭蕉という名は、日本において知らない者はおそらくいないであろう。古今に
並ぶものなく優れた俳人として、日本人の誰もが「古池や蛙飛び込む水の音」や「荒
海や佐渡に横たふ天の川」などといったこの俳聖の名句の一句や二句は頭に入ってい
ると思われる。東明雅『芭蕉の恋句』1によると、後世に残された彼の発句・紀行文を
玩味しながら、芭蕉が或いは道中で野ざらしの心に風が身にしみ、或いは松島の月や
佐渡に横たわる天の川に眺め入り、或いは古池に飛び込む蛙の水音に聴き惚れるなど
といった情景は多くの人が脳裏に思い浮かべるという。なお、芭蕉翁は雑念も欲望も
なく心清らかな僧形というイメージが強く、いわば「旅・自然・わび・さび」の詩人
であったと認識されている。
しかし、芭蕉の諸作を読み進めていくうちに、「旅・自然・わび・さび」だけでは彼
のすべてを語り尽くせないことに気づいてきた。「旅・自然・わび・さび」のほかに
は、物思いに耽る少女や悲愴な恋に身を焼く女、別れた女房への未練などといったも
のも俳諧に多数詠まれている。これら恋愛の種々相の描かれた恋句は、いずれも「古
池や蛙飛び込む水の音」や「荒海や佐渡に横たふ天の川」などといった「旅・自然・
わび・さび」の句に負けないほど素晴らしいものであると考えられる。そこで、本稿
ではそれをきっかけに、芭蕉の詠んだ諸恋句という彼の生涯や芸術を象徴するような
もう一つの事実に焦点を当て、それらに絞って考察をしていくことにする。
本稿では貞享元年から元禄七年にかけての芭蕉俳諧における諸恋句を研究対象と
し、その中から選んだ代表的ものについて考察をしていき、恋はどのように詠まれて
いるのか、その中に「蕉風」のどのような美意識が表れているのか、また、芭蕉はど
のような心境と態度でそれらを詠んでいたのかなどといった「蕉風」恋句の特徴を把
握することを目的とする。
キーワード: 松尾芭蕉 蕉風俳諧 恋句 特徴
1 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店.
4
目 次はじめに ................................................................. 7
0.1 本稿の背景 ......................................................... 7
0.2 本稿の研究対象・目的 ............................................... 7
第一章 芭蕉初期の恋句(貞享時代) ......................................... 9
1.1「上品の恋」 ........................................................ 9
1.1.1 古典の俤(面影) ................................................ 9
1.1.2 古典語の使用 ................................................. 12
1.2「下世話の恋」 .................................................... 13
1.2.1 社会実相から生まれた庶民的な恋 ............................... 13
1.2.2 古典調を帯びた町人階級の恋 ................................... 15
第二章 芭蕉円熟期の恋句 ................................................ 18
2.1 蕉風芸術の熟成へ ................................................. 19
2.1.1 歌語の新しい解釈 ............................................. 19
2.1.2 田舎娘の「あはれ」 ........................................... 20
2.1.3 「余情付」の円熟 ............................................. 21
2.2 「軽み」の覚醒 ................................................... 23
2.2.1 人生無常の嘆き ............................................... 23
2.2.2 平淡な筆致で描かれる「あはれ」 ............................... 24
2.2.3 俗事の中に表れる真情 ......................................... 25
2.3 「軽み」の完成 ................................................... 26
2.3.1 生活感の溢れる句風 ........................................... 26
2.3.2 淡白な俳画を描く芭蕉 ......................................... 28
2.3.3 恋情の稀薄化 ................................................. 30
第三章 結論 ............................................................ 33
3.1 恋の「不易流行」 .................................................. 33
3.2 「軽み」の恋――「蕉風」恋句の完成 ................................ 36
3.2.1 「軽み」の恋の特徴 ............................................ 36
3.2.2 「軽み」の恋の求めるもの ...................................... 38
終わりに ................................................................ 41
文献リスト .............................................................. 42
5
はじめに
松尾芭蕉は「蕉風」(蕉風俳諧)と呼ばれる芸術性の極めて高い句風の創始者であり、
後世では俳聖として広く世間に知れ渡っている。東明雅『芭蕉の恋句』1によると、日
本人は主に芭蕉の発句・紀行文の類いを通して「蕉風」を感じ取るとのことである。
つまり、芭蕉の句といえば旅・自然・さび・わびであると人々に広く捉えられている。
0.1 問題提起
芭蕉の諸作を読み進めていくうちに、何か文脈にそうでもないと反論を促すような
ものも出てきたのである。ここで、まず次にあげた付合(「つけあい」とは、連歌・俳
諧で、五七五の長句と七七の短句を付け合わせること)について見てみよう。
① 13 星祭る髪はしらがのかるるまで 曽良
14 集(しゅう)に遊女の名をとむる月 芭蕉
(「さみだれを」歌仙 元禄 2)2
(振り仮名は筆者。元禄 2 は同歌仙または百韻の巻かれた年。13・14 はそれぞ
れの句が同歌仙または百韻のうち、何番に出たものかを指すもの、以下同様)
② 15 月見よと引起こされて恥しき 曽良
16 髪あふがするうすものの露 芭蕉
(「有難や」歌仙 元禄 2)3
上の二つの付合は、どちらも『奥の細道』の中に登場した恋句である。恋句(こい
く)とは恋の句のことで、連歌や俳諧で恋する心を詠み込んだ句のことであり、「遊女」
などの言葉が見られるのも恋がこれらの句の主題となっているからである。これらの
付合を見ると、他の句に決して見えない異質の感情が存在していると思われる。清僧
のような心境を持っているはずの芭蕉が「遊女」などの言葉を俳諧に読み込んだこと
から、これらの恋句に超然たる心よりは一層人間的なものが感じ取られる。例えば、
③の芭蕉の詠んだ付句に、一人の位の高い女性が侍女に髪を扇がせている薄絹一重の
姿が描かれている。これは「古池や蛙飛び込む水の音」に見られる閑寂の禅心とはっ
きり違ったものである。芭蕉の句になくてはならないはずの超然さはこの恋句におい
て完全につかめず、そのかわりにその女性の艶やかさとなまめかしさが示されている
と考えられる。
0.2 本稿の研究対象・目的
芭蕉の詠んだ恋句は「旅・自然・わび・さび」の句ほど現代人に親しまれていない
1 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店.
2 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三一三頁.
3 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三一六頁.
6
という(東明雅. 1979)。その原因は、現代人は常に「旅・自然・わび・さび」の句の
みで「蕉風」を感じ取っていることにあるであろう。しかし、常に「旅・自然・わび・
さび」の句に接してきたからといって、決して「旅・自然・わび・さび」をもって芭
蕉の生涯や芸術を述べ尽すことはできない。数多くの恋の句は、従来「蕉風」のあま
り知られていない一面として、彼の生涯や芸術を象徴するような一つの事実でもある
と考えてよい。つまり、恋の句も「蕉風」芸術の一環として、決して軽んじられてい
ない。一方で、寺田寅彦『寺田寅彦随筆集第三巻』(1993)によると、歌人(和歌を詠む
ことを専門とする人)が恋歌(恋い慕う思いを述べた歌や和歌)を詠むというのは、歌
というものの根元に返る一種の儀礼的行為とも見られるのであり、俳諧の恋句も、た
だ式法の上で恋句があるから詠むのではなく、和歌や古代歌謡に見られる恋歌の伝統
が、恋句という形になって残っているとされている。このことから、俳諧にとって恋
句は非常に重要な地位を占めていることがわかる。
そこで、蕉風俳諧における恋句に対し、考察を行う必要があろう。ここでは、芭蕉
がいつ生まれていつ死に、どのような生活をしてどのような作品を残したかを述べよ
うとは思わない。本稿では芭蕉の詠んだ諸恋句を研究対象とし、それらに絞って考察
をしていくことにする。そして、芭蕉の恋の句はどのように詠まれているのか、その
中に「蕉風」のどのような美意識が表れているのか、また、芭蕉はどのような心境と
態度でそれらを詠んでいたのかなどといった、「蕉風」恋句の特徴を把握することを
本稿の目的とする。
7
第一章 芭蕉初期の恋句
東明雅はその著『芭蕉の恋句』(以下、『恋句』と略称)で、貞享に入ってから、芭蕉
の詠んだ恋の句の内容を大別して「上品の恋」と「下世話の恋」という二つに分類で
きると述べている。つまり、二つの大きな主題として、雅な恋と俗な恋を芭蕉が俳諧
に取り入れていたということである。これについては、筆者も同意見である。しかし、
「上品の恋」・「下世話の恋」それぞれ具体的に何を指しているのかについて『恋句』
では明瞭に解釈されていないため、まず、その二種類の恋をより明確に定義すること
が必要であろう。本稿では私に「上品の恋」を『伊勢物語』や『源氏物語』などとい
った古典作品の中のシーンや、昔の貴族たちの生活様相を偲ばせるような古典的・王
朝的な恋とし、それに対し、「下世話の恋」を当時の社会の諸相を取り上げた庶民的
な恋であると定義しておく。
本章では芭蕉が貞享時代に詠んだ恋句を中心に、「上品の恋」を題材とする付合、
また、「下世話の恋」を題材とする付合から代表的なものを選び、二節に分けてそれ
ぞれ考察を行う。恋の句を考察していくにあたり、その具体的な方法として、主に前
句と付句とがどのような関係で結びついているか(以下、付心「つけごころ」)、また、
その両句の付け具合がうまくいっているか否か(以下、付味「つけあじ」)ということ
の吟味を基礎として検討していくことにする。代表的なものを考察・分析することに
よって、貞享時代における蕉風俳諧の恋の句の特徴を把握することを本章の目的とす
る。
1.1 「上品の恋」
本節では芭蕉が貞享時代に詠んだ「上品の恋」を主題とする句から選んだ代表的な
ものを考察していく。
1.1.1 古典の「俤」(面影)
芭蕉が古典的・王朝的な恋を俳諧に読み込み、「上品の恋」に仕上げるために、「俤」
という手法をよく使っている。「俤」とは、「面影」のことで、故事・古物語などを材
料にして句をつける時、その内容をほのかに示す表現でつける方法である。
(1)『伊勢物語』の「俤」
25 殿守(とのもり)がねぶたがりつるあさぼらけ 千里
26 はげたる眉をかくすきぬぎぬ 芭蕉
(「日の春を」百韻 貞享 3)1
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 二六八頁.
貞享三年(一六八六)の初春に巻かれた百韻で、発句は「日の春をさすがに鶴の歩ミ哉 其角」。連衆
は其角、文鱗、枳風、コ齋、芳重、杉風、仙化、李下、擧白、朱絃、蚊足、ちり、芭蕉、揚水、不卜、
千春、峽水、筆。
8
もともと芭蕉の俳諧はその殆どが三十六句の歌仙で、百韻は珍しい。さらにこの作
品の前半五十句までには芭蕉の評語が付いている。それで一層珍しくまた貴重なので
ある。そこで、その評語を参照しながら、この付合を考察してみよう。
この付合には、内裏の夜明け方、殿守たちは眠たがってあくびをかみころしている
し、曹司の内では女房が後朝1の別れに描き眉のはげた化粧くずれを恥ずかしがって
いるというシーンが描かれている。
まず、この付合の付心について見てみよう。前句に登場した殿守は宮内省に属し、
輿(こし)・てぐるまなどの行幸用具や宮中調度の帷帳に関すること、灯燭・薪炭・湯
沐(とうもく)など日に関すること、および宮殿の清掃をつかさどったもので、実務に
あたるものとして四十人ほどの職員がいた。眠たがっていたのはこの実務者どもで、
しきりにあくびをしているのが見えるのであろう。これは屋外の様子であると考えら
れる。
一方、付句では宮廷の女房がクローズアップされている。当時の貴族女性の眉は、
眉毛を除去して黛で、上を濃く、下と両端とをぼかして描くのが普通であった。とこ
ろで、この女房は昨夜自分の室に愛人を迎え、思わず寝過ごしてしまったらしい。後
朝の別れに、はげてしまってしどけなくなった眉を愛人に見られるのが恥ずかしく、
顔を隠している状態で、これは屋内の情景であろう。
かくして、屋外・屋内、男・女と対照して、宮廷の夜明けごろの風俗・情緒を描き
だしているのである。前句の殿守と付句の女房、異なる人物を向かい合わせて付けて
いるので、「向付」(むかいづけ)2という技法を用いている。「向付」は場面を転換させ
る上に、大変具合のよい付け方であると思われる。
ところで、この付句について、芭蕉自身は次のように説明している。
「朝ぼらけ」といふよりきぬぎぬ、常のこと也。「はげたる眉」といふは、寝過し
てしどけなき躰也。『伊勢物語』に「つとめて殿守司が見るに」などゝ言べきも、
この句の余情ならんか。3
これで、芭蕉がこの付けを思いついた契機がすべて説明されている。まず彼は「あ
さぼらけ」という語から「きぬぎぬ」という語を連想した。これは誰も思いつくこと
であろう。また彼は「殿守」という語から、『伊勢物語』第六十五段に「つとめて、と
のもづかさの見るに……」という文章があったことを思い出した。
むかし、おほやけ思して使うたまふ女の、色許されたる、ありけり。大御息所と
ていますかりける、いとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、ま
だいと若かりけるを、この女、あひ知りたりけり。……されば、なにのよき事、
と思ひて、行き通ひければ、みな人聞きて笑ひけり。つとめて、主殿司の見るに、
沓は取りて、奥に投げ入れてのぼりぬ。4
この一段は、さらに続くのであるが、上にあげたあたりが関係のあるところで、芭
蕉が思いうかべたところであろう。ここに描かれている若い男在原氏の放埒を、その
1 「きぬぎぬ」と読む。相会った男女が一夜をともにした翌朝。また、その朝の別れ。
2 俳諧で、前句に詠まれる人物に対し、別の人物を配する付け方。
3 大谷篤蔵等(校注). 1989. 『芭蕉全集第三巻 連句編(上)』. 富士見書房. 二七〇頁.
4 神野藤昭夫・関根賢司(編). 1999. 『新編伊勢物語』. おうふう. 一〇三頁.
9
まま句に作ったのではおもしろくない。芭蕉は恋にはまり込んでいる男の様子をひっ
くり返して、女の身の上として一句をまとめたのであろう。
このように、古典や歴史的事実をふまえて句を作るのを「俤」という。この付けは、
「向付」でもあり「俤」の付けでもある。芭蕉が「この句の余情ならんか」というの
も、この「俤」という意に近いであろう。なお、この「俤」について、『七部集大鑑』1の著者小沢何丸は、『源氏物語』「賢木」の巻で、源氏と尚侍の君(朧月夜尚侍)が密会
した時の「俤」であるというが、作者の芭蕉が『伊勢物語』の「俤」と言っている以
上、無用の弁というべきである。
さて、ではこの付合の付味はどうであろうか。付合には「位」(くらい)というもの
があり、前句と付句に出てくる人物・事物・言葉などがお互いに相応したものでなけ
ればならない。ところで、前句の「殿守」という語は、時代から言えば平安時代、社
会的に言えば貴族階級を偲ばせるものである。それで、付句にも、眉を描いた女の後
朝をもってきたのである。眉を描く風習と後朝という言葉とは、完全に前句の世界と
マッチしている。
次に、その殿守であるが、夜番をしていたせいか、朝からあくびばかりしている様
子はいかにもだらしない。芭蕉はそれを敏感に嗅ぎつけたのではないか。そこで、後
朝をことさらに、眉もはげかかった女の化粧くずれの顔で表現しているのである。こ
れで、前句の王朝時代的頽廃味は付句によって完璧なものとなったのである。
(2)『源氏物語』の「俤」
7 起(おき)もせできゝ知る匂ひおそろしき 東睡
8 乱れし鬢の汗ぬぐひ居(を)る 芭蕉
(「たび寐よし」半歌仙 貞享 4)2
忍んで来る男の匂いをふと悟った女は、そのまま起き上がりもできず、不安と期待
に身がふるえた。そして今は、乱れた鬢の汗を拭って身づくろいをしている。この付
合にはこのようなシーンが描かれていると思われる。
まず、この付合の付心について見てみよう。このような場面は平安時代の物語や日
記などの中にいつも出てくるところであろう。『軽みの時代(芭蕉恋句抄)』(1987)第
五篇で阿部正美は、『源氏物語』「帚木」の巻で、光源氏が空蝉に偲ぶ場面、また「葵」
の巻で、源氏と紫上の新枕のあとの場面をあげている。それらのことをふまえて、さ
らに「きゝ知る匂ひ」という点から、この付合は「宇治十帖」に登場する二人の男性、
薫君と匂宮、ことに匂宮の浮舟に対する行動にヒントを得ていると思われる。そこで、
それら全体を含めて、芭蕉のこの付けは『源氏物語』を「俤」にした付けであるとい
えよう。また、前句と付句との関係を見るに、前句は女性であり、付句もその女性の
動作を描写しているため、ここでの付け方は「其人(そのひと)」の付けである。なお、
「おもしろき」という語は、一般的に言えば、女性が異性をおそろしいと思う感情が
底辺に存在することは確かであるが、それだけの単純なものではない。おそろしく思
うとともに、それをひそかに待つ気持ちも含まれているのであろう。
1 何丸(撰釋). 『七部集大鑑』. 1893. 今古堂.
2 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 二八八頁.
貞享四年(一六八七)十二月、名古屋の俳人一井亭で催された歌仙で、発句は「たび寝よし宿は師走の
夕月夜 芭蕉」。連衆は芭蕉、一井、越人、昌碧、荷兮、楚竹、東睡。
10
では、このような付合の付味はどうであろうか。ここでこの付合の「俤」となった
『源氏物語』などでは、このような場合、汗もしとどになるのはやはり空蝉であり、
紫上であり、浮舟であろう。そして、そう考えることによってこの場面はずっと艶な
ものになる。芭蕉は『源氏物語』の筆者の朧化1の手法をそのままこの恋の付合に取り
入れていることで、古典的な格調をよりいっそう感じさせたと考えられる。
1.1.2 古典語の使用
「上品」と感じさせる要素として、俤のほかに、古典語、つまり古典的な意味をも
つ言葉の使用も恋の付合で重要な役割を果たしていると思われる。このような句は多
数詠まれているため、本稿ではいちいち触れることはできないが、そこでひとつの代
表的な例を次にあげ、それを見ながら説明していく。
12 芸者をとむる名月の関 桐葉
13 面白の遊女の秋の夜すがらや 芭蕉
(「何とはなしに」半歌仙 貞享 2)2
名月の夜、ある関所で通りかかった芸人を泊めて、月見の宴を催したが、その時、
遊女の芸のおもしろさに、興は一晩中尽きなかった。
まずこの付合の付心について見てみよう。前句の「芸者をとむる」関の人に対して、
芸を披露した遊女、この二つが向い合っている。このような付けもまた「向付」であ
る。
ここで説明しておかねばならないのは、芸者という言葉であろう。これは今日のい
わゆる芸妓ではない。ここでは中世以来用いられているように遊芸の達者の意で、た
とえば、能太夫・連歌師・狂言役者・俳諧師・音曲師・曲芸師などがすべて包括され
る。この語がすぐ芸妓(舞踊・音曲などで、酒宴に興を添えるのを業とする女性)を指
すようになったのは、江戸中期以後のこととされている3。
遊女とは、歌舞により、人を楽しませ、枕席にも侍った女の称とあるが、万葉時代
には遊行女婦(うかれめ)、それから傀儡女(くぐつめ)、白拍子(しらびょうし)など、
それぞれに歴史的変遷を重ねているということである4。江戸時代になり、吉原や島
原・新町などの遊里にかかえられた女、あるいは各所にいた私娼などを総称するもの
となり、今日でもこの意味で用いられることが最も多いけれども、この「面白の遊女
の秋の夜すがらや」という表現は、古典的で謡曲調であるから、江戸時代の遊女を詠
んだものとしてはふさわしくないと考えられる。
ここでは白拍子などを連想するのが最も適切であろう。白拍子とは平安末期から鎌
1 朧化(ろうか)とは、はっきりと断定せず、言い切らずにぼかすこと。例えば、『源氏物語』の最初の
文である「いづれの御時にか…」の中の「いづれ」は、「どの・どれ・だれ」の意に用いるもので、「い
つ」の意と解してはならない。「御時」は、帝の御治世の時を意味する。「いづれの御時」は、時代や帝
を特定せずに朧化する表現の一種と考えられる。
2 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 二六一頁.
貞享二年(一六八五)三月、『野ざらし紀行』の旅にあった芭蕉が、熱田に行って土地の門人、叩端・
桐葉の二人と巻いた三吟歌仙。発句は「何とはなしに何やら床し菫草 芭蕉」。連衆は芭蕉、叩端、桐
葉。
3 守屋毅(著). 2011. 『元禄文化 遊芸・悪所・芝居』. 講談社.
4 網野善彦(著). 2005. 『中世の非人と遊女』. 講談社.
11
倉時代にかけて流行した遊女で、はじめは水干(すいかん)・立烏帽子(たてえぼし)に
白鞘巻の太刀をさして舞ったので男舞といったが、のちには水干だけを用いたので白
拍子と言われ、多くは今様1をうたい、笛や鼓や銅拍子などではやしたのである。たま
たま、関所で通行の芸人をとめて月見の宴をした時、その中に白拍子がいて、その芸
が終夜一同を魅了したというわけであろう。
次にこの付合の付味を見てみよう。この付合に対し、石兮の『芭蕉翁附合集評註』
(以下、『評註』と略称)では「真の遊冶郎にはあらで、風流のたはれ人のしわざなるべ
し」2と評価している。遊冶郎とは酒色におぼれ道楽にふける男をいう。芸者をとめて
月見をした男が酒色耽溺にて身持ちの悪い道楽者(酒色・ばくちなどにふけり、本業
に身を入れない者)ではなく、本当に風流の心のわかった人の所為だというのであろ
う。これは首肯できるところである。少なくも、関を通る芸者をとめるほどの力があ
り、また風流も解する人とすれば、地方の豪族か国守クラスの人でなければならない
と考えられる。
このように、この付合で「芸者」・「遊女」という古典語が使われることによって、
一つの古典的な貴族の風雅の世界が作り出されたといえよう。無論、ほかに具体例も
多数存在しているが、大体同じような手法を使ったものであるため、ここでは詳述し
ない。
1.2 「下世話の恋」
前節では「上品の恋」を主題とする恋の句について考察したが、本節では「下世話
の恋」を主題とする句から選んだ代表的なものを見ていく。
1.2.1 社会実相から生まれた庶民的な恋
『伊勢物語』や『源氏物語』の中のシーンを偲ばせるような古典的・王朝的な恋を
多数詠んでいた一方、芭蕉は当時の社会の恋愛諸相を取り上げ、現実性の強い庶民的
な恋の句をも作っていた。ここでは二つの例をあげて考察していく。
(1)艶な恋
25 うちかづく前だれの香(か)をなつかしく 桂楫
26 たはれて君と酒買(かひ)にゆく 芭蕉
(「つくづくと」歌仙 貞享 2)3
この付合を現代語訳してみると、このようになる。ふざけ半分、君と酒を買いに行
こうということになり、頭から前だれをかぶると、その香りがまた何とも言えず胸を
ときめかし、心をとろかすのである。
まず、この付合の付心について見てみよう。前句の「前だれの香」をなつかしむ人
1 今様(いまよう)は、日本音楽の一種目。平安中期までに成立し、鎌倉初期にかけて流行した歌謡。
2 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店. 六七頁.
3 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 二六二頁.
貞享二年(一六八五)、芭蕉が熱田の門人たちと巻いた歌仙。発句は「つくづくと榎の花の袖にちる
桐葉」。連衆は桐葉、芭蕉、叩端、閑水、東藤、工山、桂楫。
12
と、付句の酒を買いに行く人とは同じ人であるため、「其人」の付けである。また、前
だれの香をなつかしく思うのは、「君」をつれて酒を買いに行く途中のことであるの
で、時間的には付句の事実のほうが先になると考えられる。このような付け方を「逆
付(ぎゃくづけ)」という。
では、このようなシーンはどんな場面で起きているのか。それを見るには、まず「前
だれ」という語に着目すべきであると思われる。守屋『元禄文化』によると、前だれ
とは、衣服の前のほうの汚れを防ぐために、体の前面、特に腰から下に垂れ下げる布
を言い、特殊な職業の人は男も用いたが、多くは女性用であり、特に遊里の遣手(や
りて)や色茶屋の女、あるいは飯盛女1などが用いた赤い前掛けをさすものであるとい
う。この付合のシーンを考えてみるに、ここの前だれは男性用のではなく女性用のも
のであるといってよい。また、付句に「君」という語があり、現代語では二人称代名
詞として男女の別なく用いられているけれども、中世から近世にかけて、この語は名
詞として遊女の意味に用いられてきたため2、この付合では、酒を買いに男と一緒に行
く女は江戸時代の遊女と見るべきであろう。
さらに、『好色二代男』3巻一ノ三「詰り肴には戎大黒(えびすだいこく)」の章に、
島原4に遊んだ客が夜中に起き出して、遊女などと一緒に揚屋5の台所に出て酒肴を物
色し、酒宴を張る話が出ている。普通、遊女、ことに太夫(たゆう)とか天神(てんじ
ん)とか言われる高級の遊女は、食物などには目もくれないように躾けられていると
いうことである6が、それも表向きであって、本当に馴染みの客になると、ことさらう
ちとけた姿を見せることもあり、それがまた客によっては、大変なよろこびであった。
この「詰り肴には戎大黒」の章にも、有名な太夫野秋が杓子で飯を盛る話などが出て
おり、客と一緒に酒を買いに行く話は出ていないが、興に乗っては、そのようなこと
もあり得たであろう。さすがに表に出るのは恥ずかしいので、客が女の前だれを借り
て頭にかぶって行くのも一興であろう。そこでこの付合は実は、その前だれを染めた
頬紅の香りが、脂粉の香りに通って一層艶かしく、男心をそそるというような光景を
描いていると考えよう。このころ、島原などに行って遊女と遊ぶというのはごく普通
であったが、芭蕉はこの社会実相に着目し、客と遊女とのたわむれなどといった濃艶
なシーンを、上手に句に詠み込んだのである。
さて、この付合の付味はどうだろうか。かぶった前だれの香り、女と酒を買いに行
くたわむれ、それぞれに艶冶な気分があるけれども、この使いも前句と付句が殆ど一
体の事実を言っており、びっしりとくっついているために、両句の間で響きあい、匂
い合うような趣は感じ取れないように思われる。このような付けは、談林の心付(前
句全体の意味によって付句を考え付ける)の名残とも言うべきものであろう。
(2)「あはれ」な恋
(1)に見られるように遊女などを取り上げ艶な恋を詠む方法は、「蕉風」が確立され
る前にすでに談林派によって多くなされたため、決して蕉風俳諧独特のものとはいえ
1 飯盛女(めしもりおんな)は、江戸時代、宿駅の旅宿におかれた非公認の遊女。宿泊客への給仕もし
た。
2 網野善彦(著). 2005. 『中世の非人と遊女』. 講談社.
3 井原西鶴(著). 1991. 『好色二代男・西鶴諸国ばなし(新 日本古典文学大系)』. 岩波書店.
4 島原(しまばら)は、京都市下京区西新屋敷にあった遊郭の通称。
5 揚屋(あげや)は、江戸時代、太夫・格子など上級の遊女を呼んで遊ぶ家。
6 守屋毅(著). 2011. 『元禄文化 遊芸・悪所・芝居』. 講談社.
13
ない。「蕉風」ならではの恋といえば、やはり「あはれ」が基調となっているものであ
ろう。(1)と対照的に考察するために、ここで同じ江戸時代遊女を詠むものをもう一
つあげてみよう。
9 床(とこ)ふけて語ればいとこなる男 荷兮
10 縁さまたげの恨みのこりし 芭蕉
(「はつ雪の」歌仙 貞享元年)1
この付合にはこのようなシーンが描かれているであろう。遊女が初会の男としみじ
みと語り合ってみると、客は意外にもその従弟に当たる男であった。二人はもともと
一緒になるはずの仲であったのに、妨げる人がいて添えなくなったのである。その悲
しみも忘れかけていた頃であったのに、今こうしてめぐり合ってみると、二人の仲を
さいた人のことがつくづく恨めしく思われる。
この付合を見るに(1)にあげたものと異質な感情が読み込まれていることにまず気
がつくであろう。題材は同じ遊女とその客であるが、それを興味的に、あるいは好色
的に取り上げることをせず、遊女というものの裏にあるしみじみとした哀れさが、こ
の付合の主題になっている。結ばれるべき縁であったものが、どのような理由による
のか、無惨に引き裂かれたあげく、自分は遊女の身に成り下がってしまった。いくら
泣いても泣ききれぬ女の気持ちに対し、芭蕉はただ、「縁を妨げられた恨みは今も残
っている」と、実にあっさりと言い捨てているが、それゆえにこそ、恨みの余情が綿々
と残るというものであろう。同じ遊女とその客を主題に句を詠んでいるが、この付合
には(1)の艶めかしさが少しも見られず、全く異なった「あはれ」を基調とした世界
を見せている。
能勢朝次『俳諧研究(一)』2によると、談林俳諧の恋の句が「をかし」(滑稽さ)を中
心に作られているのに対し、『冬の日』以降の蕉風俳諧の恋の句は次第に「あはれ」が
中心になっていくということである。談林の「をかし」に深く傾倒した時期もあった
が、貞享に入り、独自の「蕉風」を作り出すことに成功した芭蕉は、談林から離れ、
「蕉風」の道を極めていった。このような「あはれ」の出現が、蕉風俳諧を「蕉風」
たらしめる上でとても重要な要素であると考えてよいであろう。
1.2.2 古典調を帯びた町人階級の恋
「下世話の恋」を主題とした句のうち、古典的なイメージをもつ言葉を取り上げて
詠んだものもある。一見して「上品の恋」を詠んでいるような句であるが、実際は「下
世話の恋」を表現しているものである。本稿ではこのような句を「古典調を帯びた下
世話の恋」と呼ぶ。では、次の例を見てみよう。
8 餅二かさねえにしそふ帯 東睡
9 吉原の土手に子日(ねのひ)の松ひかん 芭蕉
1 大谷篤蔵等(校注). 1989. 『芭蕉全集第三巻 連句編(上)』. 富士見書房.
貞享元年(一六八四)に巻いた歌仙。発句は「はつ雪のことしも袴きてかへる 野水」。連衆は野水、
杜國、芭蕉、荷兮、重五、正平。
2 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣.
14
(「時雨々々に」付合 貞享 4) 1
この付合にはこのようなシーンが描かれていると思われる。吉原の太夫を根引きし
てわが妻とすることになった。その祝いの餅の二かさねに帯。これで女との縁もます
ます深くなることだろう。
まず「子日の松」というのは、平安時代、正月の初子の日に、貴族たちが狩衣(かり
ぎぬ)を着て野辺に出て、小松を引いて千代を祝い、若菜を摘んで歌宴を催したりし
たものである。近世に入ってから、この語は俳諧の季語としては残っていたが、実際
に野辺に小松を引きに行くことはなくなっていたということである2。
また、吉原の土手というのは、江戸の遊里新吉原の北にある荒川の堤防で、俗に日
本堤(にほんづつみ)と言われるところである。元和六年(一六二〇)につくられ、新吉
原通いの道として利用されたところで、優雅な子日の遊びなど行われるところではな
い。
吉原の松ということは、実は吉原の太夫職の遊女をいう。近世期の遊女には太夫・
天神・鹿恋(かこい)という位があって、最上級の位の太夫を松、次の天神を梅、鹿恋
を鹿と称したとされている3。そして、「子日の松ひかん」というのはその名ある太夫
を根引き(身うけ)して、わが物としようというのである。
さて、ではこの付合の付心はどうであろうか。前句の餅(新婚三日目にあたる夜餅
を食べる習俗)も帯も嫁娶の祝い物である。無論、これには人情はない。そしてこの
二つのものから、太夫根引きという人事を思いついて付けたので、「起情」の付けと
見られる。石兮の『評註』には、「前句はにひ枕の夜に餅を用ゆる事、『源氏物語』な
どにもある俤(おもかげ)にて、何まれかまれえにし定まりたるいはひなるべし。後句
は吉原の遊女の、いはひ事にとりなしたり」4とある。『源氏物語』の「俤」とは、1.1.2
でもあげた、光源氏と紫上の新枕の段(「葵」の巻)である。また、遊女の祝い事とは
おぼろげに言ってあるが、彼女たちの最も祝うべきことは、やはりよい人に身うけさ
れることであろう。
次にこの付合の付味について見てみよう。前句も祝いのめでたい気分があり、付句
も子日の松といい、太夫身うけといいめでたいことである。一応めでたい明るい気分
が両方にあることが認められるであろう。このことから、この付合には談林時代の心
付け的なものが残っていると思われる。心付けというのは、一つの付合は言葉の上で
直接結びつけるのではなく、前句の全体の意味・内容に応じ、付句をしているという、
談林俳諧でよく用いられる手法である。この付合では、前句は「餅」と「帯」という
祝い物に対し、芭蕉はそのめでたさに目をつけ、「太夫根引き」というめでたい情景
を想定し付句に詠み込み、それの明るい気分を前句に呼応させ、巧みに心付けをして
いる。また、「吉原」や「太夫の根引き」などは談林派によく使われる恋の詞であるた
め、芭蕉はそれを句に詠み込んだことから、この付合により談林調的な特徴を持たせ
たと考えられる。
この付合を取り上げたのは談林調時代の芭蕉ならいざしらず、貞享四年の頃になっ
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 二七八頁.
貞享四年(一六八七)冬の作品で、吉野の花見に行く芭蕉を送る餞別吟。歌仙として満尾せず十句まで
で終わっている。発句は「時雨々々に鎰(かぎ)かり置かん草の庵(いほ) 挙白」。連衆は挙白、芭蕉、
渓石、コ齋、キ角、トチ、嵐雪。
2 池田亀鑑(著). 2012. 『平安朝の生活と文学』. 筑摩書房.
3 網野善彦(著). 2005. 『中世の非人と遊女』. 講談社.
4 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店. 八十頁.
15
ても、このように、「吉原」や「太夫の根引き」などといった談林的な恋の詞を俳諧に
取り上げ、恋の句としていたのである。いわば、この時期の芭蕉は、蕉風俳諧を確立
しているにもかかわらず、なお談林の恋の詞を使うというのは、まだ談林派の名残が
濃いということであったろう。また、このような遊里の題材を取り上げる場合、その
取り上げ方が極めて鮮やかで洗練されているといえる。芭蕉の付句は、表面的には、
吉原の土手で子日の遊びをしようということだけであり、いかにも平安貴族社会の優
美な風習をそのまま受け継いでいるように見えるが、実際は「松ひかん」というとこ
ろに両様の意味をもたせることによって、巧みに俳諧化し、庶民化しているのである。
芭蕉は古典的なイメージをもつ言葉を取り上げ、それをまた当時の流行唄の文句や流
行語に巧みにマッチさせることによって、古典調を帯びた町人階級の恋の世界を作り
出していた。このような才能は芭蕉は特にすぐれていたといってよい。
1.3 まとめ
本章では、芭蕉初期の恋句について考察を加えた。『源氏物語』や『伊勢物語』など
の「俤」や、「芸者」・「遊女」などの古典語を用いた「上品の恋」が主流であるのに対
し、「下世話の恋」の句はさほど多くなく、それらのモチーフは皆社会実相に基づく
ものである。そして、「上品の恋」はもとより、「下世話の恋」も古典的なイメージを
持つ言葉をも取り上げて当時社会の恋愛の種々相を詠んでいることから、全体的に両
方とも古典調に染められていることが感じ取られる。これは、初期における芭蕉の恋
句の一つの重要な特徴であると考えられる。その上、この時期の諸恋句とその前後の
句の付合には艶やかなシーンが多く描かれ、「上品の恋」は昔の貴族階級や豪族クラ
スの人々の恋愛様相に、「下世話の恋」は比較的経済的に豊かな町人階級の享楽的生
活に焦点が当てられていること、またその主人公(「下世話の恋」)は遊女である場合
が多いことも特徴的であろう。「下世話の恋」の句のうち、悲惨な運命などといった
「あはれ」なことを描くものもあるが、数が少ないため、決して主流とはいえない。
また、句の付け方として、前句の全体的意味・内容に応じた「心付」の手法がよく
用いられることから、この時期の「蕉風」は談林調から受けた影響がまだ強いことが
窺える。
16
第二章 芭蕉円熟期の恋句(元禄時代)
東明雅はその著『芭蕉の恋句』で、芭蕉の恋の句の主題を「上品の恋」と「下世話
の恋」に分け、さらに貞享元年から元禄七年にかけての「上品の恋」・「下世話の恋」
を主題とする恋句の数の変化について統計をとった。それを表にしてみると、次のよ
うになる。
出所:東明雅『芭蕉の恋句』(1979:149)より筆者作成
表1. 芭蕉の恋句
この表によって、「上品の恋」・「下世話の恋」の恋句の数の推移が明確に示されて
いることがわかる。貞享元年から元禄二年にかけて、全体的に「上品の恋」・「下世話
の恋」の数は両方とも増える傾向にある。そして元禄二年を境に、「上品の恋」の恋句
の数が減少し始め、元禄四年までは激減しているが、その後は著しい変化を見せず、
元禄七年までは 5・7・8・5というように続いている。それに対し、「下世話の恋」の
数も元禄二年から元禄三年まで減少していたが、その後三年ほど横ばいが続き、元禄
五年から元禄七年までは数が激増している。
貞享時代は蕉風俳諧の初期にあたるといわれている1ため、その間に芭蕉の恋句が
次第に円熟していくにつれて、その数も増えていくのは決して考えられないわけでは
ない。また、元禄二年にかけて「上品の恋」・「下世話の恋」の数が増加していたのも、
蕉風俳諧がより洗練されていき、次第に円熟していくことの証であると思われる。と
りわけこの表の中で最も注目に値するのは、元禄二年以降「上品の恋」・「下世話の恋」
の数の変化であろう。このような恋句の数の推移から、元禄二年・三年あたりが境目
となり、それまでは時代物的な品高き恋が主流であったのに対し、元禄四年ごろから
は現実性の強い庶民的な恋が年とともに多くなっていき、芭蕉晩年の恋句の基調を築
いていったことが窺えよう。そこで元禄時代、つまり芭蕉円熟期の恋句の特徴を把握
するため、このような恋句の数の変化を一つの重要な手がかりとして、着目する必要
があろう。
本来、元禄時代の恋句の特徴を全面的に見るには「上品の恋」・「下世話の恋」の両
方とも考察せねばならないが、元禄時代に詠まれた「下世話の恋」の句数の変化、こ
とに元禄五年から元禄七年にかけてその数の上昇が非常に著しいため、本章では「下
世話の恋」の句を主な対象とし、年代順に沿って代表的なものを選び、考察していく
ことにする。
1 佐藤勝明(著). 2011. 『松尾芭蕉』. ひつじ書房.
貞
享
元
年
二
年
三
年
四
年
元
禄
元
年
二
年
三
年
四
年
五
年
六
年
七
年
合
計
上品の恋 26 11 4 30 19 45 24 5 7 8 5 184
下世話の恋 4 5 0 10 9 36 15 15 15 21 43 173
17
2.1 蕉風芸術の熟成へ
本節では元禄元年・二年の「下世話の恋」の句から選んだ代表的なものを見ていく。
2.1.1 歌語の新しい解釈
6 のた打(うつ)猪(しし)の帰る芋畑(いもばた) 路通
7 賤(しづ)の子が待恋(まつこひ)習ふ秋の風 芭蕉
(「衣装して」歌仙 元禄 2)1
この付合を現代語訳すると、このようになる。村娘が恋人を待ち明かしたが、約束
した人はついにあらわれず、芋畑を食い荒らし、のた打った猪も明け方には山へ帰っ
て、あとは秋風が吹くばかりである。
「のた打つ」とは、「ぬた(沼田)うつ」とも言い、猪が湿地の泥をかきおこしこねま
わして、その中を転び回るということである2。これはあぶや蚊に食われぬように泥を
ぬりつけるのだと言われるが、猪にはのみ・しらみなど寄生虫がいるので、それらを
駆除するためであろうとも言われている。ここで猪についてすこし述べると、猪が一
番好むのは芋であるが、猪は夜行性の動物なので、夜が訪れたら芋畑を食いあらし、
夜明け前に山に帰って行くのである。そのため、農家では猪小屋を作って番をするこ
とが多かった。この娘はあるいは猪小屋の近くでデートするつもりだったのであろう
か。
次にこの付合の付心について見てみよう。前句には人情がないが、それに対し付句
には「賤の子」が詠まれたので、これは前章 1.2.2と同じ、人情なしの句に人情を付
ける「起情」の付けであると考えてよい。だが、よく考えてみると、これは思いもか
けぬものを付け合わせたのではないか。石兮もその著『評註』に「くどけれど翁の恋
の句返すがえすもめでたし。まことに一として奇ならざるなし。のた打猪といふ前句
に、誰れか恋の句を思ひつかむ。されど賤の子といふにて、場所よくかなひたり」3と
述べている。
石兮もこのような付けに驚いたようである。「のた打」猪という、恋とは全く無関
係な前句に恋の句を付けたにもかかわらず、描き出された情景がこの付合にぴったり
似合っているということから、芭蕉円熟期のテクニックは非常に洗練されていること
がいえよう。
では、この付合の付け味はどうか。この付合を見ると、前句の「のた打猪」と付句
の「賤の子」と、石兮は「場所よくかなひたり」と言っているが、これもまた「位」
の付けであろう。田舎育ちの頑丈な娘が待人が来ないので眠れず寝床の上で輾転反側
する様子が、泥の中でのた打ちまわる猪のさまに似ていると想像するのは行き過ぎで
あろうが、一夜あけて猪の帰ったあとの荒らし尽くされた芋畑と、逢わざる恋の夜明
けの秋の風、いずれも興ざめのした感じの通うものがあると考えられる。
この付合をもう一度よく見てみると、これは前章の 1.2.1の「古典調を帯びた下世
話の恋」に似た性質を具えていると思われる。「賤の子」・「待恋」という歌語(主に和
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三〇四頁.
元禄二年(一六八九)の春、江戸で巻かれた歌仙。発句は「衣装そて梅改むる匂ひかな 曾良」。連衆
は芭蕉、曾良、前川、路通。
2 村松友次(著). 2004. 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』. 大修館書店.
3 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店. 一二四頁.
18
歌を詠む時に用いられる特殊な言葉や表現)は、古来、和歌の題材として最も有りふ
れたものであった。そのような題材としては、陳腐なものの中に、今まで誰も取り上
げなかったものがかくれているのを発見して、芭蕉は付けたのであった。一方で、こ
の付合に出てきた「のた打猪」という言葉は、そのまま和歌に用いられた実例がごく
少ないため、「賤の子」・「待恋」のように歌語とされてはいないが、それに似た「伏猪
の床」という歌語が存在するので、ここで芭蕉は「伏猪の床」の連想があって「のた
打猪」を付けたのだと考えられる。『芭蕉全集』1の頭注には、この句の参考として、
『夫木抄』の和歌が二首あげられている。
1. 恋をしてふす猪(ゐ)の床はまどろまでぬたうちさます夜半(よは)の寝覚めよ
2. 賤たまき数にもあらぬ命にてなどかくばかりわが恋ひわたる
無論、芭蕉は『夫木抄』など精読していたようであるので、これらの歌も記憶にあ
ったであろう。「のた打猪」のように、芭蕉は「伏猪の床」という歌語を巧みに俳諧化
することで付合に新しさを生み出したと考えられ、また、田舎娘の「待恋」という歌
語をその生活環境に即して如実に写し出した斬新さにも新しさがあると見てよい。た
とえ、『夫木抄』に「伏猪の床」があり「賤たまき」があっても、芭蕉の恋句の新しさ、
面白さは変わらないであろう。
2.1.2 田舎娘の「あはれ」
16 黒木ほすべき谷かげの小屋 北鯤
17 たがよめと身をやまかせむ物おもひ 芭蕉
(「かげろふの」歌仙 元禄 2)2 (同下)
人里から離れた谷かげで、毎日黒木を乾して生計を立てている一家がある。その小
屋で年ごろになった娘が、私はいつどんな人の妻となってこの身をまかせることにな
るのだろうかと、今日も思い悩んでいる。
黒木は竃で蒸し黒くふすべ薪とした木であり、京の八瀬・大原あたりで作られ、大
原女が頭にのせて京都の市中を売り歩いたもので、この句は、その黒木を蒸し作って
いる家の娘のことを詠んだものであると考えてよい。前句は「人情なし」の句で、付
句はそこに住む娘の心細さ、「あはれ」さを付けた「起情」の句と見られる。また、人
里離れした谷かげの一軒屋の暮らし、それは頼りなく、さびしく、心細いものであろ
う。その気分はそのまま、付句の娘の境遇・心境に照応している。その余情の性格か
ら見ても「匂い」の付け3であると言ってよいであろう。
片田舎の貧しい家に成長した娘たちも、それぞれ自分の未来について夢を持ってい
たであろうが、この作品の作られた時代、封建制度の厳しい家父長制の制約のもとで
は、その実現がいかに厳しいものであったかは、今日から想像もできないところであ
1 宮本三郎(校注). 1989. 『芭蕉全集第四巻 連句編(中)』. 富士見書房. 五二九頁.
2 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三〇六頁.
元禄二年(一六八九)二月、大垣の嗒山が江戸に来た時、その旅宿で興行された歌仙。『奥の細道』の
旅に出る一月半ほど前のもの。発句は「かげろふのわが肩に立かみこかな 芭蕉」。連衆は芭蕉、曾
良、嗒山、此筋、嵐蘭、北鯤、嵐竹。
3 連句の付合手法の一。前句と付句との間に気分・情趣の照応や調和をはかる付け方。特に、蕉風で用
いられた。
19
ろう。それだけに彼女たちの悩みは深刻であった。そして、その悩みは程度の差こそ
あれ、その時代のすべての女性に共通したものであり、内気な人ならば、現代女性で
も必ず体験するであろう悩みであり、物思いなのであった。芭蕉はこれら女性のいわ
ば運命に深く同情し、その「あはれ」を描き出している。
ついでながら、この芭蕉の句のあとに、嵐蘭が付けた句は次の通りである。
27 たがよめと身をやまかせむ物おもひ 芭蕉
28 あら野の百合に泪かけつつ 嵐蘭
清純な娘が、自分は誰の妻になったらよいのかと思い悩みながら、野末の百合の花
に泪を注いでいるというのは、いかにも浪漫的であろう。おそらくこの娘は、何人か
の候補者があり、その中の一人を決めかねて迷い悩んでいるのであろう。この世の汚
れをまだ知らない処女は練り上げた白絹のように美しいが、それだけにまたつきまと
う何か危うげな感じは、野の百合の清楚で甘美であるがまた何となくはかない、たよ
りない感じと通いあっている。この句にも、美しくてまたはかない人生の恋の「あは
れ」が描かれていると考えられる。
2.1.3 「余情付」の円熟
8 遊女四五人田舎わたらひ 曽良
9 落書に恋しき君が名も有(あり)て 芭蕉
(「馬かりて」歌仙 元禄 2) 1
この付合にはこのようなシーンが描かれているだろう。田舎をめぐり歩いて渡世す
る四五人の遊女が、泊まった宿の落書きの中に、ふと懐かしい人と同じ名があるのを
見つけたことであった。
まず、この付合の付心について見てみよう。人情の描かれた前句に対し、付句はそ
の遊女たちの泊まった宿の落書きをもって付けている。遊女たちのいる場所を描写し
た句であるから、「其場」の付けであろう。無論、恋人の名を発見した遊女たちは、そ
れにさまざまの反応を示したであろう。しかし、それら一切を読者の想像に委ね、句
の表面にはただ落書があったことだけを付ける。これが俳諧であり、芭蕉の付句の歯
切れがよく余韻の深いところである。
では、この付合の付け味はどうだろうか。遊女の身の「あはれ」さはもとより、そ
れも「田舎わたらひ」となると、その哀切さは格別で、いかにも昔は都あたりの女だ
ったらしく思われ、「恋しき君」も都にいた若い頃の恋人らしく思われる。今さら恋
人の名の落書きがあったとしても、もはやどうなるわけでもないのに、やはり嬉しく
懐かしく思うのは、ほかに希望とても持つことのない流れの女の身の上からなのであ
ろうか。「君が名も有て」と客観的に突き放して述べているところに、かえってこの
ような境遇の女性の「あはれ」さが偲ばれる。この付合では、付句の余情が前句にう
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三二六頁.
元禄二年(一六八九)七月末、曾良と加賀の北枝を連れて、芭蕉は山中温泉に行き、八月初めまで滞在
した。ここで腹を病む曾良は芭蕉と別れ、伊勢長島に直行することになったので、その餞別の意味で巻
いた歌仙。前半は三吟であるが、後半は芭蕉と北枝の両吟になる。「山中三吟」または「燕歌仙」と言
われ、芭蕉自身の評語が付いているので有名な一巻である。発句は「馬かりて燕追行わかれかな 北
枝」。
20
まく通いあい、その上余情の映発による「匂い」の付け方を用いることによって、遊
女の「あはれ」さを一段と引き立せることに成功した。まさに芸術性の極めて高い付
合である。
本節では、元禄元年・二年に詠まれた「下世話の恋」の句から代表的なものを三つ
あげ、それらの特徴について考察した。ここでそれらの作品を前章にあげた貞享時代
のものと比較してみよう。
2.1.1と 1.2.2の付合では、両方とも古典的なイメージを持つ言葉を取り上げた。
1.2.2では「子日の松」の古典的な意味をベースに、「松ひかん」という当時の流行語
を付句に詠み込むことで、「子日の松」は新たな時代的な意味が付加され、巧みに俳
諧化・庶民化されている。だが、2.1.1では単に「伏猪の床」という歌語が「のた打
猪」に庶民化されたのみにとどまらず、それを農家娘の生活環境にも転用させ、ずっ
と彼女を悩ましている恋煩いをより鮮明に描き出している。また、「子日の松」に比
べて、ここで「のた打猪」を用いることで一層農家娘の心の世界を窺えるので、「下世
話」の世界にうちとけており、「子日の松」に含まれているような「古典調」がそれほ
ど感じ取られないものである。しかし、2.1.1であれ 1.2.2であれ両方とも歌語を詠
み込むことで句を付けているため、用いられた手法にはさほど変わりが見られない。
よって、2.1.1のような「下世話の恋」の句は、実は「古典調を帯びた下世話の恋」
に対する一種の革新であると考えられる。
2.1.2の「あはれ」な田舎娘を描く付合からも、芭蕉の考える「あはれ」に変化が
あったことが窺えるであろう。前章の 1.2.1(2)では「恨みのこりし」によって、「あ
はれ」が直接的に伝わってくるのに対し、2.1.2では文の底流に流れている情が「あ
はれ」を感じさせている。前者の「あはれ」は読者に激しく共感を誘う哀切なもので
あるとすれば、後者の「あはれ」はまさに婉曲的に綿々と語られている、あらわにな
っていない哀愁であると思われる。このような顕在化しない「哀愁」を基調とした「あ
はれ」は元禄元年・二年の作品によく見られるものであり、「恨み」などといった言葉
をあえて読み込まなくても自ずと文脈のところどころから感じ取られるのが特徴で
ある。また、前章 1.2.1(1)のような艶な恋を題材とした「下世話の恋」の句は、「あ
はれ」が次第に主流となっていくにつれて数を減らしていったのである。
「余情付」は蕉風俳諧の一つの大きな特徴であると考えられている。貞享時代の作
品は談林派から受けた影響はまだ強かったため、句の付け方として談林派の「心付」
を多用していたが、元禄に入って、蕉風俳諧が次第に円熟期を迎えるとともに、「余
情付」という「蕉風」の俳諧テクニックがより磨かれることで、それがますます巧み
なものになっていった。2.1.3の付合のように、恋人の名前を発見した遊女たちの心
境は書かれていないものの、この付合の余情からすれば、その遊女の気持ちも推察す
ることができるだろう。もしこの付合に遊女の心境が明確に詠まれてしまったとする
と、かえってその趣が失われるのではなかろうか。
また、元禄元年・二年の諸恋句には、貞享時代に比べて、ごく普通の人の恋愛様相
を詠むものが多くなった。とある辺鄙なところに住む田舎娘や、また大富豪の娘など、
恋の句の主人公が遊女などの類いだけではなくなり、その対象はより大衆的になって
いったのである。
21
2.2 「軽み」の覚醒
本節では、元禄三年から五年までの「下世話の恋」の句について考察していく。
2.2.1 人生無常の嘆き
31 さまざまに品かはりたる恋をして 凡兆
32 浮世の果(はて)は皆小町なり 芭蕉
(「市中は」歌仙 元禄 3)1
この付合を現代語訳すると、次のようになる。女はみな若い時、さまざまな色恋を
体験するが、やがて盛りの齢が過ぎると、どのような美女も小町のなれの果てのよう
に老醜をさらして死んでゆくのだ。
人生無常の嘆きをそのままに付けたため、このような句は「観想」の付けであろう。
一見では、「小町」は小野小町のことであると連想される。彼女が晩年零落し老醜を
さらした伝説は、謡曲『鸚鵡小町』・『関寺小町』・『卒塔婆小町』によって有名であり、
その詞も「御身は小町が果ぞとよ」(『関寺小町』)、「小野の小町がなれの果にて候な
り」(『卒塔婆小町』)、などに関係があるのであろう。しかし、さらに見てみると、
この付合には「皆小町なり」とあるため、ここの「小町」はもう小野小町のことのみ
を指しているとは思えない。恐らくこの付合に詠み込まれた「小町」は、評判の美し
い娘という意味で、小野小町のかわりに世間にいる美貌を持つ若い女性を指している
のであろう。そこで、この付合も「俤」の付けであると考えられる。
さて、この付合の付味はどうだろうか。もともと『俳諧類船集』には、「色好(いろ
ごのみ)→小町」という付合語があるので、前句の「品かはりたる恋」から「小町」が
付けられるのは極めて自然であるが、それを小町という個人の運命として述べず、美
女衰頽の「あはれ」を人間の避け得ないものとして「浮世の果は皆」と一刀両断に処
理したところ、実に適切であり、芭蕉の句らしい力強さと冴えが見られる。前句の「品
かはりたる恋をして」という見果てぬ恋の余情と、付句の小町の婉麗にして悲惨なイ
メージ、盛者必衰の無常感とは気分の通いあうものがあることは確かであろう。
芭蕉の門人其角は、その著『雑談集』2の中に、この句について、いつか自分は「品
かはる恋」という句に対し、「百夜が中に雪の少将」(深草少将が小町のもとに百夜通
った故事による)という句をつけ、忍恋3の忍の字をうまく取り入れたと自讃していた。
ところが、その後、『猿蓑』の歌仙に、「品かはりたる恋をして」という句に付けた、
「浮世の果は皆小町なり」という芭蕉の句を聞いて、自分の句などまだまだ到底及ば
ぬと悟ったと書いている。その理由は次の通りである。
此句のさびやう、作の外をはなれて、日々の変にかけ、時の間の人情にうつりて、
しかも翁の衰病につかはれし境界にかなへる所、誠おろそかならず。
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三四三頁.
元禄三年(一六九〇)六月ごろ、幻住庵に住んでいた芭蕉が京に出てきて、凡兆・去来と巻いた歌仙。
発句は「市中(まちなか)は物のにほひや夏の月 凡兆」。この作品は『芭蕉七部集』の一つ『猿蓑』に
収録され、芭蕉俳諧の円熟期を代表する傑作といわれる。
2 http://members.jcom.home.ne.jp/michiko328/zoutan.html (最終アクセス 2013年 7月 22日)
3 忍恋(しのぶこい)とは、知られてはいけない、秘密の恋愛のこと。
22
其角によると、この句の中には、無常迅速とか盛者必衰とか、人間につきまとって
いる悲しい運命の影が詠み込まれ、一句を離れて日常一般のことにもあてはまる真理
とも考えられ、また、瞬間的な人間の感慨をあらわしたものとしても適切であり、そ
の上、師である芭蕉がいつも病がちで老人になってしまわれたその一生を表現された
ものとしても適切で、この付合は本当に水準の高いものということである。其角は芭
蕉の門人の第一人者であるだけに、よく師の句を理解しているといえよう。
2.2.2 平淡な筆致で描かれる「あはれ」
11 わかれんとつめたき小袖あたためて 千川
12 おさなきどちの恋のあどなさ 芭蕉
(「もらぬほど」半歌仙 元禄 4) 1
後朝に、冷たい小袖を暖めて着せようとする、この幼い二人の恋の何とまだあどけ
ないことであろう。
まずはこの付合の付心について見てみよう。前句の人たちの様子を説明している付
句であると見られ、「其人」の付けである。この付合によって、芭蕉がいかに恋の様々
な相に興味を持ち、そこに「あはれ」を見ていたかがわかるであろう。後朝にひやり
とする絹の感触を相手に与えようという心遣いから、わざわざ暖めて着せる思いやり、
それはまだ童男童女の恋といってもよい、無垢な心のあらわれであろう。そして、人
間はいつまでもそのような状態でいられるわけではない。知らず知らずのうちに汚れ、
堕落して行く。その前の、いわば光り輝く一瞬をとらえた恋の句であり、それだけに
「あはれ」が深い。
このような芭蕉の句を見ると、西鶴の浮世草子を連想させられる。『好色五人女』
巻四で、吉三郎とお七の幼い恋が、極めて美しく描かれている。お七が吉三郎の寝所
に忍んで行くところは次の通りである。
其後は心まかせになりて、吉三郎寝姿に寄添て、何共言葉なく、しどけなくもた
れかゝれば、吉三郎夢覚て、なほ身をふるはし、小夜着(こよぎ)の袂(たもと)を
引きかぶりしを引きのけ、「髪に用捨(ようしゃ)もなき事や」といへば、吉三郎せ
つなく、「わたくしは十六になります」といへば、お七、「わたくしも十六になり
ます」といへば、吉三郎かさねて、「長老様がこはや」といふ。「おれも長老様は
こはし」といふ。何とも、此恋はじめもどかし。……程なくあけぼのちかく、谷
中の鐘せはしく、吹上(ふきあげ)の榎の木朝風はげしく、「うらめしや、今寝ぬく
もる間もなく、あかぬは別れ、世界は広し、昼を夜の国もがな」と、俄に願ひ、
とても叶はぬ心をなやませしに、母の親、「是は」と、たづね来て、ひつたてゆか
れし。おもへば、むかし男の、鬼一口の雨の夜のこゝちして、吉三郎あきれ果て
かなしかりき。2
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三五八頁.
元禄四年(一六九一)初冬、美濃大垣の斜嶺亭での半歌仙。発句は「もらぬほどけふは時雨よ草の屋
(やね) 斜嶺」。連衆は斜嶺、如行、芭蕉、荊口その他。
2 井原西鶴(著). 麻生磯次・冨士昭雄(訳注). 1992. 『決定版対訳西鶴全集第3巻 好色五人女・好色
一代女』. 明治書院. 一〇四―一〇六頁.
23
いつもは恋の「をかし」を中心に描く西鶴も、この『好色五人女』では「あはれ」
を中心に描いており、少年少女の純愛にかぎりない同情を寄せているように見える。
まさに、西鶴がここで描いているところが、芭蕉の付合のシーンと全く重ね合わせる
ことができるであろう。ともに、近世文学の中でも最も浄らかなロマンチックな場面
である。
しかし、その表現は全く逆の手法を取っていると思われる。西鶴が微に入り細を穿
ってお七と吉三郎の動作、会話を写しているのに対し、芭蕉は全く描写をしない。前
句で千川が小袖をあたためる動作だけを描いたのを、芭蕉は説明した形になっている。
しかも、それはただの説明ではない。芭蕉の付句について言えば、むしろそれは抽象
的なものと見られる。恋愛生活の描写という立場から見れば、このところには殆ど何
の描写もないといえる。しかしこの付句は、前句への付句として、前句と並べるとき、
一瞬に実感的なものが濃厚になり、独立しては何の描写をも持たないように見えたが、
底に描写を貯えている事が感じられてくる。別れにあたって冷たくなった小袖を温め
て着せようとするという、普通の後朝の動作が、この付句によって、恰も「おさなき
どちの恋のあどな」さを象徴しているような、ピュアな、清らかな、思いやりのある
動作になってくると思われる。これは前句に寄りかかっている付句ではなく、前句の
動作に新しい名前を与えたような付句であると考えられる。
このような付け方は、この時期における芭蕉の新しい試みともいえる。こうした付
け方を用いた「あはれ」は、元禄元年・二年の薄々と感じられる「哀愁」を基調とし
た「あはれ」に比べて、より洗練されていると思われる。何の描写もせず、一見平淡
な世界から光り輝く一瞬をつかめ、そこに埋もれている「あはれ」を強く感じさせる
ことは、この時期の「あはれ」に、貞享時代に詠まれたものと全く異なった性質を持
たせたといえよう。
2.2.3 俗事の中に表れる真情
11 いそがしとさがしかねたる油筒(あぶらづつ) 尚白
12 ねぶと踏れてわかれ侘(わび)つつ 芭蕉
(「月見する」歌仙 元禄 3)1
この付合にはこのようなシーンが描かれている。朝、起き別れる時にねぶとを踏ま
れてしまい、その痛さについ別れかねているうちに、昨夜、いそがしまぎれに探し出
すことのできなかった油筒が目に入った。
女の部屋に忍んで行った男が、朝になって帰る時、なにかのはずみで女にねぶとを
踏まれ、事実痛いことも痛いのだが、その痛さを口実に、一刻でも女の傍らにへばり
ついていようとする有様であろう。普通ならば情緒纏綿たるべき後朝の別れに、あろ
うことか、いとしい男のねぶとを踏んづけたというのであるから、その意外さ・卑俗
さ、そして身体的欠陥の暴露が笑いをそそる。それは『犬筑波集』にでもありそうな
俳諧の滑稽2である。
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三四五頁.
元禄三年(一六九〇)八月、芭蕉と尚白の両吟歌仙。発句は「月見する座にうつくしき顔もなし 芭
蕉」。
2 山崎宗鑑(そうかん)編。慶長(1596‐1615)ころ刊。1冊。『新撰犬筑波集』の略称で、『菟玖波集(つ
くばしゆう)』などの連歌撰集に対して卑俗な俳諧の連歌の撰集の意。宗鑑編纂当時の書名は『誹諧連
24
しかし、『犬筑波集』の滑稽が滑稽のみに終わっているのに対し、この「わかれ侘び
つゝ」という言葉には、滑稽だけではないものが潜んでいるのを見落としてはならな
いであろう。この男はねぶとを踏みつけられてその痛さだけで起き上がれないのでは
なく、何かそれにかこつけて女に甘えてみたいような、親切にしてもらいたいような、
いろいろもやもやとした気分にひたっているのである。そのような気持ちは、はっき
りと名付けることはできないけれども、恋人同士や夫婦の間の機微として存在する。
それは恋の真情と言ってよいかもしれない。極めて曖昧なものであるが、芭蕉はこの
人情の機微を卑俗なものの中に見事にとらえたのである。文学は人情を言うものであ
るとか、真情は俗事の中にあらわれるとかいうのは、ちょうど元禄のこのころから儒
者の間に行われた説であったが、芭蕉はそれを知ってか知らずか、完璧に実践した。
元禄三年から五年までの「下世話」の恋句を振り返ってみると、それらの文脈には
前のものとは異なった新たな要素・美意識が読み取れるであろう。この時期の芭蕉は、
知命の齢に近くなり、その後五十一歳でなくなるのであるが、こうした人生の旅がそ
ろそろ終着駅に着く際に、彼の心境も前と変わってきたということである1。そして、
本節の 3-2-1にあげた付合にはまさにそのような心境が語られており、人生無常の余
情が綿々と伝わってくる。一方で、序章では、芭蕉は人生を無情迅速であると考え、
それゆえ残りの時間を使って自分の「風雅」の道を極めなければならないということ
を述べたが、そこで彼が極めたいと思ったのは、平明・率直・素朴など俳諧固有の味
わいを重視した「軽み」の句風であるという(同 66)。
阿部正美『軽みの時代 (芭蕉連句抄)』(1987)によると、日常卑近な題材の中に新
しい美を発見し、それを真率・平淡にさらりと表現することを、「軽み」という。な
お、このような「軽み」によって、恋句の題材や表現には大きな変化が生じたとも考
えられている。本節で取り上げた 3-2-2と 3-2-3の二つの付合は、いずれも華やかな
描写の施されなかった素朴で、人情の十分に含まれている恋の付合で、実に素晴らし
いものであると思われる。
2.3 「軽み」の完成
本節では、芭蕉が人生最後の二年間に詠んでいた「下世話の恋」の句について考察
を行う。
2.3.1 生活感の溢れる句風
13 上(うは)おきの干葉(ほしば)刻(きざむ)もうはの空 野坡
14 馬に出ぬ日は内で恋する 芭蕉
歌抄』『誹諧連歌』であったことが確実で、1524年(大永 4)ころから 40年(天文 9)ころまでの間に編纂
されたと推定される。逐次改編増補されたらしく、古写本は伝本によって内容の異同がはなはだしい。
収録句の作者名はすべて無記名で、なかには宗祇・宗長・宗碩(そうせき)、兼載などの著名な連歌師の
作品や、守武(もりたけ)および編者宗鑑自身の作品も含まれているが、大半は作者不明のままであり、
『新撰菟玖波集』成立(1495)後まもない当時の俳諧の盛行ぶりを推察するに足る。
1 佐藤勝明(著). 2011. 『松尾芭蕉』. ひつじ書房.
25
(「振売の」歌仙 元禄 6) 1
宿場の下働きの女が飯を炊く支度をしているが、男のことで頭がいっぱいで、上置
きの干葉を刻むのもうわの空である。相手の男は馬方2で、仕事に出ない日はいつもう
ちに籠って色事にふけっている。
まず、この付合の付心と付味について見てみよう。前句の干葉を刻む下女に対し、
その相手である馬方を付けたのであるから「向付」であると考えてよい。なお、『去来
抄』の「位」の説明の中に出ているので、芭蕉の恋句としては、最も有名なものの一
つであろう。『去来抄』の説明には次のように書かれている。「この前句は人の妻にも
あらず、武家・町屋の下女にもあらず、宿屋・問屋等の下女也」。問屋は街道筋にあり
旅人をとめ物質集散の中心となったもので、その実態は酒田の鐙屋(あぶみや)の描写
が『日本永代蔵』3巻二ノ五に出ている。宿屋は『好色一代女』巻六ノ二に出ている伊
勢松坂の旅宿の描写などを見ると推察がつくことであろう。そのような街道の宿屋・
問屋には出女(でおんな)・蓮葉女(はすはおんな)というものがあり、旅人を慰めるこ
とになっていたようであるが、この芭蕉の句に詠まれている女は、出女・蓮葉女の類
いではなく、その家に雇われて台所専門に勤める下女であろう。しかし、そのような
台所専門に勤める女も、時と場合によっては客の求めに応じて色を売ったりもする。
飯焼(めしたく)下女も見るを見まねに色つくりて、大客の折ふしは、次の間に行
て御機嫌を取。是を二瀬女(ふたせおんな)とはいふなり。4(振り仮名は筆者)
そこで、このような宿屋・問屋の下女は平素飯盛女の風習を見習い、自然と自堕落
になり、武家や堅気の町屋の下女とはやはり全く異なるものがあったのは当然である。
上置きとは、飯または雑煮の餅などの上にのせて食べるものであるが、干葉は干菜
(ほしな)と同じで、大根葉を干して貯え、水で膨らませて刻み、米の上に置いて炊く
と米の量を倹約することができたものである。これは武家でも堅気の町屋でも同じよ
うに食べたものであるとはいえ、その干葉を刻むのもうわの空だとそばから知られる
ような、うかれた雰囲気は武家や町屋の下女には見られない。そこがこの下女を宿場・
問屋の下女と見定めたところであろうし、それを見定めた眼力は実に素晴らしいもの
と思われる。
このように女の位が定まり、宿屋・問屋の下女ということになれば、その恋の相手
は自然と定まってくる。街道をすみかとしている馬方・駕籠(かご)かきの類をもって
来たことは当然であり、これで「位」というものが保たれることになったのである。
しかも、この馬方の描き方が極めて面白い。『芭蕉の研究』5の著者である小宮豊隆氏
は、次のように鑑賞している。
問屋あたりに使はれていゐる馬子が、何かの理由で、馬に出ないで、内に休んで
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三八三頁.
元禄六年(一六九三)十月芭蕉庵で興行された歌仙。発句は「振賣の鴈あはれ也えびす講 芭蕉」。連
衆は芭蕉、野坡、孤屋、利牛。
2 馬に人や荷物を運ばせるのを職業とする人。
3 井原西鶴(著). 堀切実(訳). 2009. 『日本永代蔵』. 角川学芸出版.
4 井原西鶴(著). 麻生磯次・冨士昭雄(訳注). 1992. 『決定版対訳西鶴全集第3巻 好色五人女・好色
一代女』. 明治書院. 三二六―三二七頁.
5 小宮豊隆(著). 1941. 『芭蕉の研究』. 岩波書店.
26
ゐるのである。さうして傍輩の下女か何かと、頻りにいちやつき合つてゐるので
ある。然も「馬に出ぬ日は」のは、の字の中には、この馬子の生活が、馬に出さへ
しなければ、必ず「内で恋する」事にきまつてゐでもするやうな、事の反覆もし
くは習慣を示唆する、特別な意味が籠められる。其所から又作者がこの馬子を取
り扱つてゐる、フモールも湧いて来る。芭蕉はこの十四字で、この男の恋愛のみ
ならず、この男の全生活をも描いて見せてゐるのである。1
これは実にすぐれた鑑賞であるといってよい。それにしても、芭蕉の句の切れ味は
実に見事といわざるを得ない。先の「浮世の果ては皆小町なり」という句の切れ味に
も似て、これが芭蕉の句の一つの特色であると思われるが、「皆小町なり」の句が、ど
うしても古典の世界とのつながりを断つことができないのに対し、この句は恋の中で
も最も卑しい鄙びたものであり、その表現も極めて端的・露骨でありながら、ユーモ
アが溢れるほどだと讃えられている。そして、このような卑俗な話を素材として取り
上げ、俳諧に詠み込んでいるからこそ、この付合に生き生きとした生活感も感じ取れ
る。こうした卑俗なことから生まれた生活感を追い求めるのが俳諧の味であり、「軽
み」の味でもあったといえよう。
この「振賣の」の巻は『炭俵』に収められている。そして、この『炭俵』こそ「軽
み」の俳諧を十分に発揮したものと言われている2。
2.3.2 淡白な俳画を描く芭蕉
28 赤鶏頭(あかけいとう)を庭の正面 惟然
29 定らぬ娘のこころ取りしづめ 芭蕉
(「猿蓑に」歌仙 元禄 7)3
つきつめた恋にいらいらしている娘の気持ちをなだめすかして、やっと取り鎮める
ことができた。庭の正面には真紅な鶏頭が狂ったように咲いている。
赤く燃える鶏頭の色は『図説俳句大歳時記』4の説明によると、「妖艶な感じを与え
るが、一面どこか暗い影があり」とされる。これが恋に狂って定まらない娘の心に通
っていることから、「うつり」5の付けと見られる。さまざまに思い乱れた娘が、やっ
と心をとりしずめ、奥の座敷にひとりいて、庭の正面に見える真紅な鶏頭に向かって
いる姿は、何か凄みがある。庭の正面に赤い鶏頭などと植えてあるのは、格式ある家
の庭とは言えないだろう。鶏頭は美しいけれども高貴な草花ではなく、撒けばどこで
も生えて咲く、いわば庶民の草花である。この娘もおそらく農家、それも中以下の百
姓の娘ではないだろうか。「取しづめ」という、馬か牛でも暴れているのを制御した
かのような、やや荒い語が用いられているのは、鶏頭と娘との「位」を考えての付け
1 中村俊定等(校注). 1989. 『芭蕉全集第五巻 連句編(下)』. 富士見書房. 八六五頁.
2 村松友次(著). 2004. 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』. 大修館書店.
3 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 四二〇頁.
元禄七年(一六九四)九月、前年沾圃と唱和した発句・脇を継いで満尾(連歌・俳諧で、百韻・歌仙な
どの一巻を完結すること)させた歌仙。発句は「猿蓑にもれたる霜の松露哉 沾圃」。連衆は芭蕉、沾
圃、支考、惟然。
4 角川書店(編集). 1973. 『図説俳句大歳時記〈秋〉』. 角川書店. 二一三頁.
5 蕉風俳諧の付け方の一。前句の余韻が後句に及んで互いに調和する付け方。「―、響き、匂ひは付け
やうのあんばいなり」(『去来抄』修行)
27
であろう。
これも翁の名長き附句にて、人のよくしれる句なり。つけごゝろ妙とやいはむ。
奇とやいはむ。喩ふるにものなし。さまざまに思ひみだれたる娘の、つひにはこゝ
ろとりしづめたるは、奥の座敷にひとりゐて、小庭の赤鶏頭にむかひてならむ、
なほその妙をとかむとするに口吃す。1
石兮の解釈では、娘が奥座敷に座っている間に一人でに気が鎮まったということに
なる。しかし、母親などがなだめすかして、やっと何とか一応落ち着かせた状態と見
るほうが、赤鶏頭に対し「うつり」がよりよいのではなかろうか。母親も娘もまだ上
気している顔つきが想像される。おそらくこの農家娘には思う人ができたが、相手に
自分の気持ちは伝わらずにいるので、結局焦り出したのであろう。自分の娘に落ち着
かせようとし、母親がずいぶん苦労をして、ずっと彼女の機嫌をとっていたので、何
とか冷静になってもらえたことが推測される。このような視点からすれば、この付合
に描かれている光景は、ごく写実的なものであると考えられる。このような恋心を抱
えている農家娘は、江戸時代には決して少なくなかったであろう。芭蕉がそれに着眼
し、真紅な鶏頭をもって灼熱した娘の恋心を象徴して、その当時の農家娘の恋愛模様
を上手に描き出している。
また、西鶴は『好色五人女』巻一に、次のように書いている。
とやかくものおもふ折ふし、里の童(わらんべ)の袖引連て、「清十郎ころさばお
なつもころせ」とうたひける。聞ば心に懸て、おなつそだてし姥に尋ければ、返
事しかねて泪をこぼす。さてはと狂乱になつて、「生ておもひをさしやうよりも」
と、子共の中にまじはり、音頭とつてうたひける。皆々、是をかなしく、さまざ
まとめてもやみがたく、間もなく泪雨ふりて、「むかひ通るは清十郎でないか、笠
がよく似た、すげ笠が、やはんはは」のけらけら笑ひ、うるはしき姿、いつとな
く取乱して狂出ける。2
この作品は貞享三年(一六八六)の出版で、広く世間に読まれていたものであったか
ら、芭蕉もあるいは読んでいたのかもしれない。ここで「赤鶏頭」の付合を西鶴の作
品と比較してみよう。西鶴は恋に狂った若い女性の姿や運命を彼には珍しく美しくま
た感傷的な筆致で描き上げたのに対し、芭蕉はそれを、比較的に素朴な、暗い赤鶏頭
で象徴しただけである。芭蕉がこのような手法を用いたのも、「軽み」の理念による
ものと思われる。実際の庶民の恋愛諸相に着目し、華やかなものを作品に読み込まず、
ごく庶民的なシーンをごく平淡な筆致で描き、その背後に含まれた真情を綿々と語っ
ているというのも、「軽み」の一つの特徴であると考えられる。もし西鶴の小説を極
彩色の浮世絵に例えるならば、芭蕉の句はまさに濃厚な色彩を取り扱わない、真情に
満ちた淡白な略体の俳画3であるといえよう。
1 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店. 一三八頁.
2 井原西鶴(著). 麻生磯次・冨士昭雄(訳注). 1992. 『決定版対訳西鶴全集第3巻 好色五人女・好色
一代女』. 明治書院. 二四―二五頁.
3 俳句を題材に、その句が描写する内容を表現し、その画面に題材となった俳句を賛した書画共存形式
の絵画。しかし、その本質とするところは、単に俳句の意味するところ、すなわちその内容が視覚化さ
れるという、形式的な一致にあるのではなく、俳諧の成立と展開の中で醸成されたものである。機知と
28
2.3.3 恋情の稀薄化
元禄六年・七年の諸作を鑑賞・解読系の著作を参照しながら考察するにあたり、同
じ付合に対し、読み手によってはそれが恋句として見るべきか否かについて意見が分
かれていることに気づいた。ここでその具体例を一つあげ、筆者の意見をも交えて見
ていこう。
35 隣へも知らせず嫁をつれて来て 野坡
36 屏風の陰にみゆるくはし盆 芭蕉
(「むめがゝに」歌仙 元禄 7)1 (同下)
隣家の人にも知らせずこっそり嫁を迎えたごく内々の祝言であるが、さすがに引き
回した屏風の陰は夫婦の閨らしく菓子盆などが見える。
前句で述べた婚礼の場の様子を付句で述べている。「その場」の付けであると見て
よい。石兮の『評註』に、
此二句に人情世態をつくせりといふべし。小家住のものなどの、隣へもしらせず
こつそりと嫁をつれて来たる也。後句は客などあるやうすにて、料理などするを、
隣り近所の人の何事ならむとさしのぞけば、屏風引きまはしたるかげに、菓子盆
の見ゆるに、さては婚礼にてありしよとさゝやくさま也。翁隠逸の身にてかゝる
事までをみつけおかれしはいぶかしき事也。すべて俳諧は第一人情世態にわたら
ざれば、ああれなる事をかしき事をいひ出づる事かたし。2
と述べているのは、この付合の情景や意義をよく言い尽くしていると思われる。
『三冊子』3の中に、この付合が「会釈付(あしらいづけ)」の例に引かれている。「会
釈付」とは「さもありつべき事を、直ちに事もなく付けたる句」(いかにもありそうな
ことを、そのまま手軽に付けた句)で、この付合については、「盆の目に立つ、味はふ
事もなくして付けたる句なり。心の付なし新しみあり」(菓子盆が特に目立つ所を詠
んだもので、前句の余情を深く味わうことなく、さらりと付けた句である。前句の心
を受けて付けた付け方に新しみがある)と評されている。軽い付句である。
能勢(1985)によると、「軽み」の俳諧になるにつれて、恋の情も薄くなっていった
という。つまり、「軽み」によって恋情が稀薄化されているといえる。確かにこの「む
めがゝに」の巻の恋句も、実に淡く、さっぱりとしたもので、中の恋情もそれ以前の
ものに比べて一層薄くなっていると思われる。しかし、表面には出ていないが、婚礼
のめでたい華やかな気分は確実に存在している。そのめでたさは「屏風」や「菓子」
によって間接的に描き出され、文脈の深層に緩やかに流れている。この句は「軽み」
の恋句として、また挙句として、上乗の恋情の稀薄化された句で、いかにも「軽み」
滑稽味・卑俗・即興性・日常的題材・平明さ・軽さといった概念は、俳諧が短歌から派生し、貞門・談
林を経て蕉風の『軽み』の完成に至る俳諧の本質を端的に示しているが、それはそのまま俳画の特質を
指摘する言葉でもある。
1 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三九一頁.
元禄七年(一六九四)一・二月ごろ、野坡亭で興行された歌仙。芭蕉・野坡の両吟。発句は「むめがゝ
にのつと日の出る山路かな 芭蕉」。
2 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店. 一四三頁.
3 向井去来. 服部土芳. 潁原退蔵(著). 1993. 『去来抄・三冊子・旅寝論』. 岩波書店.
29
を重んじた『炭俵』の恋句らしい素晴らしいものであると思われる。
ところが、この付合に感じ取られる恋情の濃さでは、それを恋句たらしめるのに十
分ではないと主張した『七部婆心録』の曲斎のように、恋句に非ずと断定する者もあ
り、今日でもその説を支持する人もいて、実は問題の句であるという1。なお、この付
合を恋の句と見ない人は、この巻の裏の折立(七句目と八句目)とその次にある付合を
恋句と見る。
7 御頭へ菊もらはるるめいわくさ 野坡
8 娘を堅う人にあはせぬ 芭蕉
歌仙一巻の中にはどこかに少なくとも一箇所は恋句がないと、それは半端物とされ
るのであるが、この裏の折立と次の句を恋句と見れば、本節の最初にあげた付合は無
理に恋句にしないでもよいというのである。だが、この付合にはっきりした恋の意、
あるいは恋の情があるだろうか。大意を示せば次の通りであろう。
丹精込めて作ったものを、上役にねだられるのは迷惑だと、菊作り一筋の趣味に生
きて、上役にへつらおうともせぬ老人である。彼は秘蔵娘を堅く守って、めったに他
人合わせようともしない。
確かに、年ごろになった娘をめったに人前に出さないのは、その句の裏に恋の心が
匂うからであろう。しかし、この付合では潔癖で堅気の老人のイメージが前面に出て、
まだ、恋の情を醸し出すまでにはなっていないようである。ただ、この芭蕉の句は、
次の野坡の付句次第では、十分な恋に発展する可能性があった。芭蕉はおそらくそれ
を期待していたのではなかったろうか。野坡は次のような句で受けている。
8 娘を堅う人にあはせぬ 芭蕉
9 奈良がよひおなじつらなる細基手(ほそもとで) 野坡
あいつの家では、娘を馬鹿に大事にしまっておくではないか。誰様の御令嬢ではあ
るまし、我々もあれも同じ奈良通いのしがない行商人なのに、と仲間で悪口をいって
いる。
この付合も恋句であるか否かが問題になっているということである2。ここでまず
恋の付合技法から考えてみよう。もし 7・8と 8・9はどれも恋の付合であれば、ここ
での 7・8・9 はそれぞれに「呼び出しの恋」(単独では恋句ではないが、付け句によ
り恋句になれば、恋句として扱う)・恋句・「恋離れ」(「恋の呼び出し」の句のように
単独では恋句にならず、その後は恋句を出さない)にあたるべきであろう。7は次の 8
の恋を詠むための仕掛けとして、8 の恋情を呼び出そうとする役割がある。そして 9
は 8の恋情から離れるのだが、8と合わせて読めば恋の余情が薄々感じ取れるはずで
ある。だが、よく考えてみると、「娘を堅う人にあはせぬ」という前句に、打越3が昔
気質の頑固な老人を付けているのに対し、この付句は奈良通いの小商人を付けている
のであって、前句自身には恋の意や情があるものの、打越の句や付句には殆どそれが
ないため、7・9は「呼び出しの恋」・「恋離れ」であるとは考えられない。その点、打
1 村松友次(著). 2004. 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』. 大修館書店.
2 村松友次(著). 2004. 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』. 大修館書店.
3 打越(うちこし)は、連歌・俳諧で、付句の二つ前の句。付句と打越の間に特定の同じ韻や縁語がある
ことを「打越を嫌う」といって避ける。
30
越・前句の付合を恋と見なければ、前句・付句の付合も恋と見ないのが当然であろう。
しかし、百歩譲ってこの付合を恋と見るにしても、その持つ恋の意・恋の情は、や
はり本節の最初にあげた付合には及ばないであろう。それは「隣へも知らせず」とい
う付合は前句・付句相まって、新婚の艶めかしさ・明るさを直接に描かず、一見地味
ではあるが、深層にはそのめでたい華やかな気分も含まれており、両者が巧みに融け
合っているからである。この付合は、恋情の稀薄化された句として、上手に「軽み」
を演出していると思われる。
芭蕉の人生最後の二年間の代表作を見ると、皆「軽み」に染められていることが特
徴的であろう。卑俗なことから生まれた生活感を追い求め、淡白な略体の徘画ように
恋を描き、地味・素朴な付け方で恋情を稀薄化させ、平明・率直に恋を語るというの
がまさに「軽み」の真髄のあらわれであるといっても過言ではなかろう。
31
第三章 結論
以上のように、貞享元年から元禄七年にかけての諸恋句から代表的なものを選び、
それぞれの解読をし、貞享元年―四年、元禄元年・二年、元禄三年―五年、元禄六年・
七年のように分け、時期別に芭蕉の恋句の特徴について考察してきた。本章では第一
章と第二章を踏まえて、「蕉風」恋句の全体的特徴を把握してみたい。
3.1 恋の「不易流行」
恋句とは、恋の句のことで、人が人を恋しく慕う心もちや、行いを俳諧に詠み込ん
だものを指している。なお、花や月のようなに、恋は定座1ではないが、「歌仙には必
ず恋句を二カ所入れねばならない。そして恋句が出たとき、最低一句で最高五句とい
うように恋をつけるのが式目であるとされている2。では、なぜ恋句は俳諧を詠む上で
欠かせないものであろうか。これについて、『去来抄』3には「恋なき巻ははしたもの」4と書かれてあり、つまり恋の句がない俳諧は不完全なものだということである5。な
お、俳諧の歴史を遡行すると、連歌を経て最終的には必ず和歌に行き着くということ
から、俳諧に恋句を詠むというのは、実は日本人が古典を継承させる意志のあらわれ
であるとも考えられる。そこで、俳諧では昔の恋歌などの古典文学の伝統に沿って、
その詠まれた事実や用いられた歌語を詠み込んだりすることがあるわけであるとい
う6。
本稿に取り上げた芭蕉の諸作を見ると、第一章 1.1.1の『伊勢物語』と『源氏物語』
の「俤」を用いた句、1.1.2の「芸者」・「遊女」という古典語の詠み込まれた句、1.2.2
の「子日の松」の取り上げられた句、また第二章 2.1.1の「賤の子」・「待恋」などの
描かれた句のように、古典や昔の伝統を借りて句を詠んでいることは確かである。そ
の上、特に貞享時代・元禄初期(元年と二年)の作品に目を通してみると、本稿に列挙
したもののように古典や昔の伝統を踏まえた恋句が多数存在していることに気がつ
く。
ここでもう一つの例をあげよう。
15 あの月も恋ゆゑにこそ悲しけれ 翠桃
16 露とも消ね胸のいたきに 芭蕉
(「秣おふ」歌仙 元禄 2)7
あの月を眺めても、この恋ゆえにこそ悲しいのだ、こんなに胸が張り裂けそうなつ
1 連歌・俳諧で、二大景物とされる月・花を詠むことに決められた句の位置。例えば、百韻の初表 7句
目を月の定座、歌仙初裏の 11句目、名残の裏 5句目を花の定座とするなど。
2 乾裕幸・白石悌三(著). 2001. 『連句への招待』. 和泉書院.
3 向井去来. 服部土芳. 潁原退蔵(著). 1993. 『去来抄・三冊子・旅寝論』. 岩波書店.
4 はたし物とは半端なもの、不完全なものの意味。
5 向井去来(著). 中村俊定(訳). 1998. 『去来抄―影印/解説/校註』. 笠間書院.
6 安東次男(著). 1992. 『連句入門―蕉風俳諧の構造』. 講談社.
7 井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社. 三〇七頁.
『奥の細道』の旅での最初の俳諧作品。発句は「秣おふ人を枝折(しおり)の夏野哉 芭蕉」。連衆は芭
蕉、翠桃、曽良、翅輪、桃里、二寸、秋鴉。
32
らい思いをするくらいなら、いっそのこと我が命など露となって消えてしまえ。
もっとも、叶わぬ恋のため露のように消えたいというのは決して新しい発想ではな
い。既に『万葉集』の中に多くその例を見る。
1. わが宿の夕陰草の白露の消(け)ぬがにもとなおもほゆるかも(594)
2. 秋萩の上におきたる白露の消(け)かもしなまし恋つつあらずは(1608)
3. 秋の田の穂の上における白露の消(け)ぬべく我はおもほゆるかも(2246)
4. 夕べおきて旦(あした)は消ゆる白露の消(け)ぬべき恋も我はするかも
(3039)1
そして、これが平安時代以降、代々の勅撰集の中に受け継がれて、発想を変え、お
びただしい量の恋歌となっているのである。『芭蕉全集第四巻 連句編(中)』の補註
には、『新古今和歌集』の例として、
1. 恋ひ侘びて野べの露とは消えぬとも誰か草葉のあはれとはみん
左近中将公衡
2. 同じくは我が身も露と消えなばつらき言の葉も見じ
藤原元真2
の二首があげられている。そこで、恋のため露と消ゆるというのは、いわば、和歌
の道ではもう使い古されたもので、一つの伝統であったことが窺えるであろう。芭蕉
はここで、その伝統を引き継いで、それを恋句に詠み込んだのである。
しかし、芭蕉はただそのような古典や昔の伝統を借りて自分の俳諧に詠み込んだわ
けではない。第一章の 1.2.2で既に述べたように、芭蕉はそれらの古典や昔の伝統を
巧みに俳諧化させ、庶民化させ、一種の新しい情趣を創りだしたのである。1.2.2で
は、「松ひかん」というところに、伝統的な意味を当時の流行語に巧みにマッチさせ
ることで、古典調を帯びた町人階級の恋のを描き出している。また、2.1.1では、「待
恋」という言葉を更に農家娘の生活環境にも転化させ、彼女を悩ましている恋煩いを
より鮮明に引き立たせ、1.2.2に見られる手法を円熟化させることに成功した。前に
あげた付合でも、月と露を結びつけることによって、「あの月も」と指すあたりの野
辺の露を連想させるとともに、露のようにはなかい命をも連想させた。そして「胸の
いたきに」には、つれない人を恨む気分がこめられ、それがはっきり言い切られてい
ないところに、綿々として尽きない情がたゆたっていると思われる。無論、他の例も
多数見られるが、ここでは詳述しない。かくして、芭蕉は古典や昔の伝統に生命を吹
き込み、俳諧において見事に蘇らせたともいえよう。
このような手法を用いたのは、まさに「蕉風」の「不易流行」によるものであると
思われる。「不易流行」とは松尾芭蕉が「奥の細道」の旅の中で見出した蕉風俳諧の理
念の一つであるという3。『去来抄』では、不易流行について、以下のように書かれて
いる。
1 佐竹昭広・木下正俊・小島憲之(共著). 1987.『萬葉集(本文篇)』.塙書房.八五・二〇〇・二六一・
三一七頁.
2 宮本三郎(校注). 1989. 『芭蕉全集第四巻 連句編(中)』. 富士見書房. 五〇三頁.
3 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣.
33
不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず。1
それを噛み砕いて言うと、「良い俳句が作りたかったら、まずは普遍的な俳句の基
礎をちゃんと学ぼう。でも、時代の変化に沿った新しさも追い求めないと、陳腐つま
らない句しか作れなくなるので、気を付けよう」という意味になるであろう。さらに、
「不易流行」について、土芳は『赤冊子』で次のように述べている。
師の風雅に万代不易あり。一時の変化あり。この二つにきはまり、その本(もと)
一なり。その一といふは風雅の誠なり。不易をしらざれば実に知れるにあらず。
不易といふは、新古によらず、変化流行にかかはらず、誠によく立ちたる姿也。
……変化にうつらざれざれば風あらたまらず。これに押し移らずといふは、一端
の流行に口質(くちつき)時を得たるばかりにて、その誠を責めざる故なり。せめ
ず心をこらさざるもの、誠の変化を知るとばかりいふ事なし。唯人にあやかりて
行くのみなり。責むるものはその地に足を据ゑがたく、一歩自然に進む理なり。
行末幾千変万化するとも、誠の変化は皆師の俳諧なり。かりにも古人の涎(よだ
れ)をなむる事なかれ。四時の推し移る如く物あらたまる、皆かくの如しとも云
えり。(振り仮名は筆者)2
土芳はまず、芭蕉の俳諧には「万代不易」ともいう、いつになっても見る人を感動
させることの変わらないものと、また一時の変化を示した新味提示的な作との両方面
のあることを述べ、師である芭蕉の俳諧はこの「不易」か「流行」かいずれかでない
ものはないと言っている。そしてこの「不易」も変化流行もその生まれてくる根元は
同一であって、それは「風雅の誠」を責めることを発するものであると論じたのであ
る。続いて、彼は「不易」と「流行」について説明を加える。「不易」とは、その作の
時代の新古ということとは無関係であり、また句風の変遷とか流行の変化ということ
からも超越したもので、何人をも感動させるに足るだけの句姿を持っていることを述
べている。ここで土芳の考えを現代的な表現を借りて言い換えると、「不易」はその
作品の与える芸術的感動が永遠性を持つものであり、俳諧の本質的なものに根ざして
いるがゆえに、不易を知らねば俳諧の本質は理解しがたい、というようにまとめられ
ると思われる。芭蕉は古典や昔の伝統を引き継いで俳諧に蘇らせたのも、まさにその
ためであろう。
次に「流行」ということについての土芳の説明は、流行というものの生じる原因を
「誠を責める結果、自分の現在の句境に満足出来なくなり、止むに止まれない勢いで、
一歩一歩前進するため」に生じるものであると見ている。理想を追って前進するとこ
ろから、新しい句境が開けてくるものであって、仏教でいうところの「無所住」(停
滞・定着することのない意)の精進に相当すると考えてよい。したがって、「流行」は、
新境地開発というものを指していると思われる。芭蕉の恋句は決して「不易」だけに
はとどまらず、芭蕉が追求している「風雅」が彼に、常に句に「流行」をもたらすこ
とを要求しているであろう。貞享時代の芭蕉の恋句は、古典や伝統にはまりがちな性
格が確かに顕著であったが、元禄に入って「蕉風」が次第に円熟していくうち、芭蕉
はそのような「不易」に満足しなくなり、新境地の開発に精を出し始めたのである。
そして彼は自ら俳諧に伝統を詠み込み、それに時代性を帯びさせ、数多くの素晴らし
1 向井去来「著」. 中村俊定「訳」. 1998. 『去来抄―影印/解説/校註』. 笠間書院. 三頁.
2 向井去来. 服部土芳. 潁原退蔵(著). 1993. 『去来抄・三冊子・旅寝論』. 岩波書店. 三五頁.
34
い恋句を詠んでいた。
新境地の開拓、新味の追求、これは芭蕉の生涯にわたっての念願であり、また同時
に実践でもあった。彼の一生は俳諧を新しくすることに捧げられた一生であった。恋
句は絶えず旧套から脱出し、新しい生命を宿すことのために、風雅の誠を責め心身を
苦しめるのであって、芭蕉ほどに自らの芸術境地を耐えず更新していった人物は、ま
さに前後に比類を見ないであろう。芭蕉は新しさの憧れに生き、新しさの実現に生き、
新しさの追求の道に「斃れて後已む」人というべきである。
3.2 「軽み」の恋――「蕉風」恋句の完成
「軽み」の恋について、第二章 2.2と 2.3では少しその定義と特徴について述べた
が、本節ではそれを踏まえて更に深く考察をしていく。
木のもとは汁も鱠(なます)もさくら哉
此の句の時、師のいはく、花見の句のかかりを少し得て、かるみ、、、
をしたりとなり。
(傍点は筆者)1
この「木のもとは」の句は元禄三年の作であり、この句を発句として伊賀の連中と
歌仙を巻いた際に、芭蕉がこのように土芳に告げたものであるという2。これによって
「軽み」という考えが、元禄三年の頃に既に芭蕉の心に兆していたと見られる。そし
て、この句はおそらく「軽み」という言葉を芭蕉自身が語った最初の例であろう。し
かし、「軽み」とは何かに至っては、それはあくまでも雰囲気的なものであり、明らか
に定義をもつ具体的なものであるとはいえない。
翁近く旅行思ひ立ち給へば、別屋に伴ひ、春は帰庵の事を打なげき、さて俳談を
尋ねけるに翁今思ふ体は、浅き砂川を見る如く、句の形・附心ともに軽き、、
なり。
其所に至りて意味ありと侍る。(『別座敷』序)
『別座敷』3は、子珊が序を付して、元禄七年夏に出版したものであるから、芭蕉が
元禄七年に最後の旅に出る際の送別の集いの時、この語は語られたものである。ここ
で「軽み」を形容して「浅き砂川を見る如く」と言い、また軽みは句の形にもまた付
け心にもわたって存在するものであることを告げている。「浅き砂川を見る如く」と
は、さらさらとして清くかつ滞らないことを言ったものであろう。これを見ると、『三
冊子』に書かれているものに比べて、「軽み」の意義が一層具体化されているように
思われるが、明瞭といえるほどのものではない。
3.2.1 「軽み」の恋の特徴
「軽み」の意義が具体的に語られているものは、杉風が甲斐の麋塒に送って、芭蕉
1 向井去来. 服部土芳. 潁原退蔵(著). 1993. 『去来抄・三冊子・旅寝論』. 岩波書店. 二一頁.
2 阿部正美(著). 1987. 『軽みの時代(芭蕉連句抄)』. 明治書院.
3 天理図書館綿屋文庫編. 1988. 『俳書叢刊』(復刻版). 臨川書店.
35
の元禄七年頃の俳諧観を告げた書簡である。これは安政六年刊行の『真澄の鏡』1によ
って紹介されていたものである。
(1)用語の平易と表現の安らかさ
翁近年申候は、俳諧も和歌の道なれば、とかく直ぐなる様にいたし候へ。もつと
も、言葉は世に申し習し片言も申し候へば、その句の姿によりて片言は申すべし。
それも、道理叶ひ申さぬ片言は無用。埒明き申すばかり用ふべし。2
ここでは「直ぐなるようにせよ」といい、「片言なども、句によっては用ひても良
し」ということを述べている。
段々句の姿重く、理にはまり、むつかしき句の道理入りほがに罷り成り候へば、
皆只今までの句体を打ち捨てて、軽くやすらかに、ふだんの言葉ばかりにて致す
べし。是を以て直ぐなりと申され候。3
近来の句風が姿は重くなり理に陥り、難しく入りほが(和歌・連歌・俳諧で、趣向を
こらしすぎて嫌みになること)な表現に成り行きつつあることを指摘して、そうした
句風を打ち捨てて平常の用語だけを用い、軽く安らかな句風を作るようにしようとい
い、用語の平易と表現の安らかさと軽さによって「直ぐなる」様は得られるものであ
るとの教えである。ここでもう一度本稿にあげた元禄時代の諸恋句を振り返ってみる
と、特に元禄三年以降のものは、前のものと比べて、用語の平易化と描写の平淡化と
いう特徴が一層感じ取られるであろう。
(2)「余情付」
前句へ附け候事、今日初めて俳諧仕り候者も附け申し候へば、必ず前句へ附く
べからず。随分はなれても附くるものなり。附け様は、前句へ糸ほどの縁を取り
て付べし。前句へ並べて句聞へ候へば、よしと申し置き候。句の成り行きやう段々
申し置き候へども、紙筆に尽く申上げず候。4
ここには俳諧で、前句に緊密にびっしりと付ける行き方を斥けて、軽く離れた付け
方を薦め、前句との間に糸ほどの縁をとるか、また前句と並べて、その意味が了解で
きるという程度のもので良いとする意見である。このことは、まさに「蕉風」の「余
情付」のことを指しているであろう。本稿にあげた貞享時代の付合を見ると、談林の
「心付」が多用されていることがわかる。だが、元禄時代に入って、「軽み」という美
意識が次第に確立されていくうちに、芭蕉は「心付」を排斥し始めた。そこで典型的
な例として、第一章 1.2.1(1)の付合と第二章 2.1.3の付合を比較してみると、前者は
前句の意味によってびっしり付句を付けているのに対し、2.1.3では芭蕉が前句に感
じられる情調に注目したため、付句は前後の句と余情の通いあうようなものである。
1 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣.
2 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一七頁.
3 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一七頁.
4 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一八頁.
36
後者の方が、より評判が良いといわれている1。
(3)題材の卑俗化・現実化
古事来歴いたすべからず、一向己の作なしと申し置き候。2
これは主として俳諧で、故事あり来歴あるような作をすることを戒めたものであろ
う。発句にはそうしたことは殆ど行われていないためである。なぜこれを斥けたのか。
全く自分の作品というべきものがないからだとある。それとともに古典や昔の伝統と
その境地などを狙わなくても、俳諧の素材は無限であるということに原因があると思
われる。それは次のものにおいて明らかに示されている。
古人も、賀の歌、其の外、作法の歌に、面白き事なし。山賤•田家•山家の景気な
らでは哀れ深き歌なし。俳諧もその如し。賤のうはさ、田家、山家の景気、専ら
に仕るべし。景気俳諧には多し。諸事の物に情あり。気をつけて致すべし。ふだ
んの所に、昔より言ひ残したる情、山々ありと申し置き候。3
ここでは和歌に例を取って、賀の歌やその他の儀礼的な歌には全く面白い作品はな
く、山賤とか田舎や山家などを詠んだ作品に「あはれ」の深い作品がある由をいい、
俳諧でもこれと同様であると述べ、素材としては通俗卑近な田舎人の生活や田園•山
家などの自然風景などに、専ら着眼すべきことを告げる。そのような平常卑近なとこ
ろにこそ昔の人の言い残した、また昔の人の詠もうともしなかった新しい詩味(しみ)
がある詩境があり、それはほとんど無尽蔵であろう。ただ大切なことは、そのような
日常卑近の物事なり景色の中から、そのものの本情をさぐり出して来ることであり、
これは十分に精神を集中してこれに当たらねばならないと述べている。このように、
「ふだんの所に、昔より言ひ残したる情が山々ある」がゆえに、古人の作品にすがっ
たり故事を踏まえたりしたところの「故事来歴の句」などを作ることを斥けたのであ
り、作者自身の目耳をもって自ら把握したものでなければ、自分の作品とし得るもの
でないというのである。貞享時代の恋句のように古典を踏まえたり故事を俤にしたよ
うな句が殆ど見えなくなっており、第二章 2.1.2 や 2.2.2、2.3.1 などのように、取
材はますます平俗卑近なところに求められていることは、芭蕉のこのような意図のあ
らわれであったことがいえよう。また、第二章の始めにあげた表をもう一度見てみる
と、芭蕉初期と円熟期における「上品の恋」と「下世話の恋」の数の逆転があったの
も、「軽み」によるものであると考えられる。
3.2.2 「軽み」の恋の求めるもの
翁近年の俳諧、世人知らず。古きと見えし門人どもに、見様申し聞かせ候。一ぺ
ん見ては只軽く埒もなくふだんの言葉にて、古きやうに見え申すべし。二へん見
申し候はば、言葉古きやうにて、句の新しき所見え申すべし。五へん見候はば、
1 村松友次(著). 2004. 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』. 大修館書店.
2 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一八頁.
3 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一八頁.
37
句は軽くても、意味深き所見え申すべし。六ぺん見候はば、前句へ附けやう、か
くべつ離れ、只今までの附けやうは、少しもなき所見え申すべし。七へん見候は
ば、前句の悪き句には附句も悪く、正直に致し候ところ見え申すべし。これにて
大かた合点いたすべしと申され候。1
これは『炭俵』に代表される俳風と、それ以前の俳諧との行き方の相違を芭蕉が告
げた言葉であると思われる。世の中の一般の俳人が、この晩年の芭蕉の行き方を知ら
ないばかりでなく、蕉門の古い弟子さえも十分にこれを理解していないので、その見
方を教えたというのである。新風である「軽み」の理解がいかに困難であったかがわ
かる。
「軽み」の新風は、当時古い門人に歓迎されなかったという2。その原因は、それが
「一ぺん見ては、只軽く埒もなくふだんの言葉」をもって表されており、その印象は
「古きやうに見える」からであったろう。貞享時代の諸恋句のように、表現技巧に輝
きがあるではなく、詠んでいる境涯が詩的興奮を起こさせるほどのものでもなく、平
凡卑近なことを平常の言葉で表現したのみのものであり、何となく談林派の昔に帰っ
たような句で、しかも談林ほどの刺激性もないとなれば、「古い」として顧みられな
いようなことも起きるのが自然であると考えられる。しかし芭蕉のいうごとく、二回、
三回、四回と繰り返して味わっていく中に、言葉は古いようでも、句においては古風
と異なり、どこか新しみがあることが感じられ、句体は軽く安らかに何の奇もないな
がらに、どこかに深い意味(深く自然なり人事なりに浸透した生命感)があることがわ
かってくるというのである。表現は平淡卑近であるが、その中に深い「もののあはれ」
が宿されているところに、「軽み」の恋の醍醐味があるという意である。また前句に
対する付け方も極めて淡々としたものであり、緊密•緊張の味が強く盛り上がってく
るというようなところがないことも「軽み」の恋の一つの特徴であると見られ、前句
の良し悪しによって付句も自然によくもなり悪くもなるという自然さのあるのも、
「軽み」の恋の一つの特徴であるといえよう。
さて、なぜ「軽み」が唱えられるに至ったのであろうか。芭蕉がその俳諧において、
新しい境地を開こうと努力し、専ら卑近平俗の世界に分け入って、その当時の社会の
恋愛諸相の中から、従来見残され言い残されていた恋における本情をさぐり、これを
平易な表現をもって詩化しようとしたところから生まれたものであると考えてよい。
「軽み」の恋の狙うところは、対象・素材はあくまでも庶民的な世界や自然の景色
に求める。表現においては繊細さを尽くすことを避けて平淡に平易に言い表わすこと
を心がけ、用語も平易な日常語を用い、片言などをも用いることを許すということで
ある3。俗談•平話をもって詩を作るというのが表現における狙いであろう。俳諧の付
合でも前句に緊密に付ける行き方を離れ、前句に並べて意味が通る程度、前句とは糸
筋ほどの幽かなつながりを持つ程度に、淡々と軽々とつけていく「余情付」の行き方
を取る。
「軽み」の恋は言語表現の平淡さを求めるが、詩情においては深く物事をさぐり、
平俗な恋愛様相における「もののあはれ」に徹することを求めるともいえる。そのよ
うな「あはれ」に深く打たれながらも、これを詠嘆的に直接に打ち出さず、余裕ある
1 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣. 一八頁.
2 阿部正美(著). 1987. 『軽みの時代(芭蕉連句抄)』. 明治書院.
3 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣.
38
非人情的な態度で淡々と余所ながらに語っていく。したがって、「句は軽くても、意
味は深き」1の表現となるであろう。
このような「軽み」というものが志向されるに至ったのは、従来の俳諧が「善尽く
し美尽くした境地にまで至り得」、しかもそれに満足して定着して、進取性を失う傾
向にあったことに起因するという2。すなわち貞享元年以来、元禄初期を経て、元禄
六・七年に至って、蕉風俳諧は伝統的な和歌や連歌の持つところの文芸美を、通俗文
芸たる俳諧の中に摂取し消化し渾融して、伝統の創造の総合を一応完成し得たのであ
る。それは尊ぶべき創造であり、それ自体においては理想的なるものであったが、そ
の境地にいつまでも尻を据えていることは停滞で進歩性を失うこととなり、やがては
旧染(古くからしみこんでいる習わし)の垢にまみれたものとなり終わる危険もあろ
う。それを芭蕉は恐れたということである3。そこで、俗の中に伝統的な文芸美を樹立
する境地をさらに進め、ひたすらに俗の中の本情の「あはれ」、俗の中にひそむ生命
の「あはれ」、そのようなものへまっしぐらに進み入ることと、そうした生命の表現
においても伝統的な美的表現手法を離れて、俗談平話をもって、平易に淡白に表現す
ることに向かったのであろう。
1 能勢朝次(著). 1985. 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』. 思文閣.
2 東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店.
3 佐藤勝明(著). 2011. 『松尾芭蕉』. ひつじ書房.
39
終わりに
本稿は芭蕉俳諧における恋句についての一考察であり、「旅・自然・わび・さび」に
代表される芭蕉の芸術の別の一面に対する理解を深めようとする試みでもある。芭蕉
の世界は、「旅・自然・わび・さび」だけでは決して象徴し尽くせないということは、
本稿の論述によって明らかとなったであろう。また、本稿にあげた芭蕉の作品のほか
にも、非常に優れた作品が多数存在しており、すべてここにあげることは非常に困難
であるため、本稿では筆者なりに選択した代表的なものを取り上げ、それらを主な研
究対象として考察を行うことにした。
本稿では元禄時代の諸恋句を考察する際、「下世話の恋」に焦点を当てることにし
たため、元禄時代における「上品の恋」の句に対する資料収集・検討が不足となって
しまったのである。より全面的に「蕉風」恋句の全体的特徴を突き止めるには、元禄
時代における「上品の恋」についてもよく研究せねばならない。そこで、元禄時代の
「上品の恋」を主題とする恋句に対する分析は、今後の課題として引き続き考察をし
ていきたいと思う。
40
文献リスト
1. 引用文献
井本農一・堀信夫(校注). 1970. 『芭蕉集(全)』. 集英社.
井原西鶴(著). 麻生磯次・冨士昭雄(訳注). 1992. 『決定版対訳西鶴全集第3巻
好色五人女・好色一代女』. 明治書院.
大谷篤蔵. 木村三四吾. 今栄蔵. 島居清. 富山奏(校注). 1989. 『芭蕉全集第三
巻 連句編(上)』. 富士見書房.
神野藤昭夫・関根賢司(編). 1999. 『新編伊勢物語』. おうふう.
佐竹昭広・木下正俊・小島憲之(共著). 1987.『萬葉集(本文篇)』.塙書房.
島居清. 久富哲雄(校注). 1989. 『芭蕉全集第十巻 俳書解題・総合索引』. 富
士見書房.
田中善信. 2005. 『全釈芭蕉書簡集』. 新典社.
中村俊定. 島居清. 大谷篤蔵(校注). 1989. 『芭蕉全集第五巻 連句編(下)』.
富士見書房.
夫木和歌抄研究会(編集). 2008. 『夫木和歌抄』. 風間書房.
向井去来. 服部土芳. 潁原退蔵(著). 1993. 『去来抄・三冊子・旅寝論』. 岩
波書店.
宮本三郎(校注). 1989. 『芭蕉全集第四巻 連句編(中)』. 富士見書房.
2. 参考文献
安東次男(著). 1992. 『連句入門―蕉風俳諧の構造』. 講談社.
阿部正美(著). 1987. 『軽みの時代(芭蕉連句抄)』. 明治書院.
網野善彦(著), 2005, 『中世の非人と遊女』, 講談社.
池田亀鑑(著), 2012, 『平安朝の生活と文学』, 筑摩書房.
石田穣二(訳). 1979. 『新版伊勢物語』. 角川ソフィア文庫.
乾裕幸・白石悌三(著). 2001. 『連句への招待』. 和泉書院.
井原西鶴(著), 1991, 『好色二代男・西鶴諸国ばなし(新 日本古典文学大系)』,
岩波書店.
井原西鶴(著), 谷脇理史(訳), 2008, 『好色五人女』, 角川学芸出版.
井原西鶴(著), 堀切実(訳), 2009, 『日本永代蔵』, 角川学芸出版.
井原西鶴(著), 村田穆(編), 1976, 『好色一代女 新潮日本古典集成』, 新潮社.
小沢何丸(撰釋). 『七部集大鑑』. 1893. 今古堂.
角川書店(編集), 1973, 『図説俳句大歳時記〈秋〉』, 角川書店.
小宮豊隆(著), 1941, 『芭蕉の研究』, 岩波書店.
佐藤勝明(著). 2011. 『松尾芭蕉』. ひつじ書房.
寺田寅彦(著). 1993. 『寺田寅彦随筆集 第三巻』. 岩波書店.
天理図書館綿屋文庫編. 1988. 『俳書叢刊』(復刻版). 臨川書店.
能勢朝次(著), 1985, 『能勢朝次著作集 第 9巻 俳諧研究 1』, 思文閣.
東明雅(著). 1979. 『芭蕉の恋句』. 岩波書店.
向井去来(著), 中村俊定(訳). 1998. 『去来抄―影印/解説/校註』. 笠間書院.
村松友次(著), 2004, 『対話の文芸 芭蕉連句鑑賞』, 大修館書店.
紫式部(著). 林文月(訳). 2011. 『源氏物語』(中国語版). 訳林出版社.
守屋毅(著), 2011, 『元禄文化 遊芸・悪所・芝居』, 講談社.