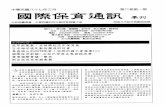平成29年度製造基盤技術実態等調査報告書 - 経済産業省
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 平成29年度製造基盤技術実態等調査報告書 - 経済産業省
目 次
【ロボット用アクチュエータ】
1.サーボモータ
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·················································· 1
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ···················· 4
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ······························· 5
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ················································ 6
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ·································································· 7
保護等級 防圧 センサレスサーボ(センサレス制御)
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ··········· 10
ファナック (日本) 安川電機 (日本) 三菱電機 (日本) パナソニック(日本)
⑦ 各国の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ······························· 18
Siemens (ドイツ) ABB (スイス) Bosch Rexroth (ドイツ) Kollmorgen (米国) Estun Automation(中国) TECO Electro Devices Co. Ltd(台湾)
⑧ サプライチェーン ······················································································ 27
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ······································ 27
⑩ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ···· 28
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑪ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ······························································· 31
⑫ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ····························· 32
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑬ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ·················································· 36
⾼速・⾼精度・⾼応答性に関連する技術 モータの⼩型化・軽量化 巻線技術(省エネルギー) 振動・騒音制御 巻線機 軸受と軸受材料 磁石 ホール素子(磁気センサー) 無方向性電磁鋼板(モータの材料)
⑭ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ···················· 41
2.減速機
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ················································ 49
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ·················· 50
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ····························· 51
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ·············································· 52
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ································································ 53
⻭⾞技術 振動・騒音制御
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ··········· 55
ナブテスコ株式会社(日本) 株式会社ハーモニックドライブシステムズ(日本) 住友重機械工業株式会社(日本) 日本電産シンポ株式会社(日本) 加茂精工株式会社 (日本)
⑦ 各国の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ······························· 64
Nantong Zhenkang Machinery Co, Ltd. (中国)
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ······································ 65
⑩ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者/所属機関 ········ 66
③中国 ⑤台湾
⑪ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ······························································· 67
⑫ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ····························· 68
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑬ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ·················································· 70
潤滑法 ⻭⾞加⼯機 取材資料
⑭ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ···················· 75
3.ロボット用ケーブル市場の現状 ···································································· 78
大電株式会社 (日本) 沖電線株式会社 太陽ケーブルテック(株) IGUS(ドイツ) SAB Bröckskes GmbH & Co. KG(ドイツ) Leoni(ドイツ)
4.中国のロボット産業発展計画(2016〜2020年) ············································· 84
中国のロボット市場概要 中資系メーカの現状 中国政府の対応とメーカの動き ロボット産業発展ロードマップ 日系メーカの進出状況 日本における今後の課題と方向性
【ロボット用センサモジュール】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·································· 96
(以下の内容を含む)
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等
からランキング。上位5位程度まで列記)
1. 関節⾓度位置センサ(ポテンションメータ、ロータリーエンコーダ) ························· 98 2. 歪みセンサ ················································································· 105 3. 姿勢制御センサ············································································ 108 4. 距離センサ(光電センサ、超⾳波センサ) ·············································· 131 5. ⼒センサ ···················································································· 145 6. ビジョンセンサ ··············································································· 157 7. セイフティレーザスキャナ/セイフティライトカーテン ········································ 180
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 188
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ··· 189
⑩平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ···················· 190
ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト 次世代人工知能・ロボット中核技術開発
⑪⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所) ································································· 192
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 196
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ··················· 196
図 産業用ロボット/センサ・マトリックス 図 産業用ロボット向けセンサ(まとめ) 図 産業用ロボットのキーセンサ及び主要メーカ
(補足)ニュースまとめ
【パワードスーツ(⾝体能⼒補完スーツ)】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 204
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 205
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 207
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 207
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 209
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 212
1. アスカ株式会社 2. 株式会社今仙技術研究所 3. CYBERDYNE株式会社(筑波大学発ベンチャー) 4. 住友理⼯株式会社 5. 本田技研工業株式会社 6. アシストモーション株式会社(信州大学発ベンチャー) 7. 株式会社テムザック技術研究所 8. トヨタ⾃動⾞株式会社
9. 株式会社ATOUN 10. 株式会社イノフィス(東京理科⼤学発ベンチャー) 11. 株式会社クボタ 12. 株式会社スマートサポート(北海道⼤学発ベンチャー企業) 13. パワーアシストインターナショナル株式会社(和歌山大学発ベンチャー企業) 14. 株式会社モリタホールディングス 15. スケルトニクス株式会社 16. 佐川電子株式会社 17. イクシー株式会社
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ······································ 234
1. Ekso Bionics Holdings(Nasdaq上場) 2. Lockheed Martin 3. United States Special Operations Command (略称US SOCOM) 4. BAE Systems, Inc. 5. Myomo(2017年6⽉16⽇ニューヨーク証券取引所に上場) 6. Parker Hannifin 7. 20 Knots Plus Ltd 8. Otto Bock 9. RB3D 10. ECA(Etudes et Constructions Aéronautiques) 11. Noonee 12. ReWalk Robotics(Nasdaq上場) 13. Rex Bionics(ロンドン証券取引所AIM市場上場) 14. MAWASHI 15. TSNIITOCHMASH 16. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 17. 中国北⽅⼯業公司 (NORINCO)
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 255
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ··· 255
⑩平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ···················· 257
⑪⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所) ································································· 259
(米国) (欧州) (中国) (台湾) (韓国)
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 272
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ··················· 272
【3D プリンタ/⾦属積層造形技術】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 275
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 279
図表 ものづくりプロセスにおける3D プリンタの活用 図表 ものづくりプロセスにおける3D プリンタの活用効果
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 281
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 283
①ユーザーの裾野拡大(コンシューマー分野) ②試作領域における⽤途の広がり(産業分野) ③試作品から最終製品への拡大(産業分野)
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 286
航空機 メディカル・デンタル ⾃動⾞
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 290
図表 松浦機械製作所の⾦属光造形複合加⼯機 図表 ソディックの⾦属3Dプリンタ
図表 DMG森精機「LASERTEC 30 SLM」 図表 オークマ「LASER EXシリーズ」
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ······································ 297
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 318
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 319
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ····························································· 322
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する 政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ··········· 327
①米国 ②欧州 ③中国 ④韓国 ⑤台湾
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 338
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 338
・熱源 ・インプロセスモニタリング ・⾦属粉末 ・⾦属粉末のリユース、リサイクリング
・ソフトウェア ・データベース
【⾞載マイコン】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ············································· 354
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 366
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 368
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 369
⑤ ②の各⽤途に求められる技術特性〜⾞載⽤マイコンの技術変遷 ····························· 376
⽇⽴製作所/旧ルネサス テクノロジ NEC/ ルネサス エレクトロニクス Freescale(NXP) Infineon
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 393
ルネサス エレクトロニクス
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ····························· 403
Intel/Mobileye NVIDIA NXP Semiconductors Infineon Technologies Samsung XILINX
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 434
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 434
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ····························································· 435
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ··························· 435
日本 米国 欧州
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 449
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 449
【スマートテキスタイル】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 451
(ⅰ)スマートテキスタイルの概要 (ⅱ)スマートテキスタイルの重要な要素技術 (a)配線材料(導電性繊維) (b)配線形成プロセス (c)実装・接合技術
(ⅲ)特定の用途(生体情報の計測)に関する技術の概要 生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS 非ウェアラブル) ウェアラブルデバイスの概要 (a)腕時計型(スマートウォッチ) (b)リストバンド型(スマートバンド) (c)眼鏡型(スマートグラス) (d)ウェア型 (e)その他のウェアラブルデバイス スマートテキスタイル(ウェア型デバイス)の強み・弱みと今後の課題 (a)スマートテキスタイルの強み (b)スマートテキスタイルの弱み (c)スマートテキスタイルの機会 (d)スマートテキスタイルの脅威 (e)今後の課題
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 464
センシング 発電機能 熱制御機能 発光機能
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 467
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 468
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 469
発電機能 熱制御機能 発光機能
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 470
東レ ゴールドウイン 東洋紡 グンゼ ミツフジ Xenoma POSH WELLNESS LABORATORY クラボウ エーアイシルク 帝人 ヤマハ バンドー化学
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ······································ 480
(ⅰ)米国 Under Armour Sensoria
(ⅱ)欧州 Interactive Wear AG (ドイツ) Clothing+(フィンランド)
(ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 Mcell
(ⅴ)台湾 AiQ
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 486
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 488
(ⅰ)米国 (ⅱ)欧州 (ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 (ⅴ)台湾
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ·················· 492
(補足)研究費の推移※日本の研究.com(検索ワード:スマートテキスタイル)で抽出
⑪⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無 ······························································································· 494
(ⅰ)米国 (ⅱ)欧州 欧州委員会の取り組み(FP6・FP7) 欧州技術プラットフォーム(ETP) 繊維系大学連合「AUTEX」 欧州繊維修士課程プログラム「E-TEAM」 欧州繊維研究機関ネットワーク「TEXTRANET」
(ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 韓国京畿道 光州科学技術院(NID) KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)
(ⅴ)台湾 TTRI(台湾繊維研究所)
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 503
セーレン ミツフジ カジナイロン パナソニック 太洋工業 セメダイン
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 508
【フレキシブルデバイス】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 511
(ⅰ) フレキシブルデバイスの概要 (ⅱ)フレキシブルデバイスの重要技術 (a)インク材料の開発 (b)印刷技術 (c)実装・接合技術
(ⅲ)特定の用途(生体情報の計測)に関する技術の概要 生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS 非ウェアラブル) ウェアラブルデバイスの概要 フレキシブルデバイスのポジショニング
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 521
表示デバイス:有機EL ディスプレイ キーデバイス:RFID キーデバイス:触覚センサ 電源デバイス:太陽電池
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 529
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 529
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 531
表示デバイス:有機EL ディスプレイ キーデバイス:RFID キーデバイス:触覚センサ 電源デバイス:太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 535
東京大学 山形大学 凸版印刷 アフォードセンス
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5 位程度まで列記) ···························· 538
(ⅰ)米国 MOLEX GSI Technologies
(ⅱ)欧州 FlexEnable(英国)/ISORG(フランス)
(ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 サムスンディスプレイ(SDC) LG ディスプレイ(LGD)
(ⅴ)台湾 E Ink Holdings
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 545
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ··· 547
(ⅰ)米国 (ⅱ)欧州 (ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 (ⅴ)台湾
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ·················· 550
⑪⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府 支援策の有無 ···················································································· 556
(ⅰ)米国 (ⅱ)欧州 (ⅲ)中国 (ⅳ)韓国 (ⅴ)台湾
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 565
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ··················· 566
【アラミド繊維】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ············································· 569
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 572
<デュポングループ> <帝人グループ>
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 575
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 575
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 582
コンポジット プロテクション ゴム補強
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 585
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ····························· 587
※防弾・防護⾐料市場 ※タイヤコード/ファブリック
⑧ サプライチェーン(東レ・デュポンのみ) ·························································· 593
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 594
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 597
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ····························································· 599
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ··························· 600
<米国> <欧州> <中国> <韓国> <台湾>
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 604
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 604
【セルロースナノファイバー(CNF)】
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 608
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 614
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 615
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 615
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 626
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 631
王子ホールディングス 日本製紙 大王製紙 北越紀州製紙 第一工業製薬
花王 星光PMC モリマシナリー 旭化成 服部商店 ダイセルファインケム 大阪ガス
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ····························· 671
<カナダ> <米国> <スウェーデン> <フィンランド> <ノルウェー> <フランス> <その他>
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 682
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 683
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による 研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる) ····································· 690
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する 政府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。 ··········· 697
<カナダ> <米国> <欧州> <ノルウェー/NIBIO> <韓国> <中国・台湾>
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 706
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 706
【ナノカーボン】
1.ナノカーボンの概要
2.カーボンナノチューブ
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ·············································· 716
(ⅰ) 合成方法 HiPco法 eDIPS法 スーパーグロース法
(ⅱ) 分離⽅法(単層CNT) 密度勾配超遠⼼分離法 誘電泳動法 カラムクロマトグラフィー法
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 721
(ⅰ) 単層CNT 透明電極 電気二重層キャパシタ電極 複合材料 リチウムイオン電池導電助剤 不揮発メモリ 電界効果トランジスタ
(ⅱ) 多層CNT リチウムイオン電池(LiB)導電助剤 【市場概況】 【カーボンブラック】 【VGCF】 【多層CNT】 樹脂複合材料 <⾃動⾞分野> ゴム・エラストマー複合材料 変位センサ 面状発熱体 導電性糸
その他
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 736
(ⅰ)単層CNT (ⅱ)多層CNT
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 737
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ······························································ 739
LiB導電助剤 樹脂・ゴム複合材
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 740
(ⅰ)単層CNT 日本ゼオン 名城ナノカーボン
(ⅱ)多層CNT 昭和電工 大陽日酸 浜松カーボニクス ⽇⽴造船 ⼾⽥⼯業 リンテック
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ····························· 747
(ⅰ)単層CNT OCSiAl(ロシア) Wisepower(韓国) SouthWest NanoTechnologies(米国) Thomas Swan(英国) KH Chemicals(韓国) NanoSoution(韓国)
(ⅱ)多層CNT Nanocyl(ベルギー) CNano Technology(米国) 中国科学院成都有機化学(中国)
深圳市三順中科新材料(中国) Hyperion Catalysis International(米国) Arkema(フランス) Hanwha Chemical(韓国) Kumho Petrochemical(韓国) その他
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 756
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 757
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ·················· 559
⑪米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び 主に技術開発に関する政府支援策の有無 ····················································· 760
米国 欧州 韓国 台湾
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 764
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 766
3.グラフェン
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 ············································· 769
スコッチテープ法 グラファ CVD法 イトの酸化・還元法 熱分解法
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) ················ 776
透明電極 太陽電池 OLED電極 トランジスタ 電気二重層キャパシタ電
リチウムイオン電池(負極材、導電助剤) 導電性インク センサ 放熱材料 その他
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア ··························· 787
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 ············································ 788
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 ····························································· 790
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) ········· 792
グラフェンプラットフォーム インキュベーション・アライアンス 仁科マテリアル アイテック ADEKA カネカ 大阪ガス 日本触媒 その他
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、 世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記) ····························· 798
世界シェア
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者 ···································· 801
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 ·· 802
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) ·················· 804
⑪⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び 主に技術開発に関する政府支援策の有無 ····················································· 805
米国 イギリス ドイツ EU 中国 韓国
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業 ················································ 813
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 ·················· 814
1.サーボモータ ① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
「サーボ(Servus:奴隷)」とは、命令に対して充実に動作することを意味し、サーボモータは、回転
検出器(エンコーダ)を搭載、回転⼦(ロータ)の位置と速度を検出することで、⾼精度・⾼分解能な位置決め運転を可能とする。サーボモータの種類は、大きく「パルスモータ」、「DC サーボモータ」、「同期形ACサーボモータ」、「誘導形ACサーボモータ」の4つに分けられる。各種のアクチュエータの中でも、ACサーボモータは、モーションコントロールの⾼速化、⾼精度化、メンテナンスフリー化が容易に実現できる特徴を持っていることから、サーボモータ市場の主流となっている。
サーボモータの分類と特徴
出所:神鋼電機より矢野経済研究所作成
パルスモータ DCサーボモータ 同期型ACサーボモータ 誘導型ACサーボモータ
長所オープンループ(パルス列入力)低コスト
小型で大トルク制御性が良い小容量で低コスト
高速・大トルク小型・軽量メンテナンスフリー
高速・大トルクメンテナンスフリーピークトルク大大容量可能
短所脱調磁気騒音トルク小
メンテナンス要ブラシ摩耗粉の発生火花による使用環境制約あり
大容量化不適中小容量で損失大制御回路が複雑
2
サーボモータの供給先別アプリケーションは工作機器、産業用ロボット、電子部品実装機、半導体製造装置、射出成型機、搬送機器など多岐に亘る。電子部品実装装置では、チップマウンタ、ボンディングマシン等があげられる、。半導体製造装置では、搬送システムやXYZ軸直交画像検査装置等で、液晶パネル製造装置ではパネルの搬送システム等で用いられる。最新の動向としては、ロボット及び工作機器向けの成⻑が⽬⽴つ。 半導体製造装置は、従来のPC向けからスマートフォン、タブレットPC向けに需要がシフトしている。ス
マートフォンは、ライフサイクルが短期化する傾向にあり、年間に 50 機種の市場投入を目指すとするLenovoのように、各スマートフォンメーカーは、ラインナップの拡充を推進している。これらを背景の1つとして、半導体製造装置向けのサーボモータは特に中国市場において短納期対応が求められる傾向にあり、サーボモータメーカは、需要動向を⾒据えた⽣産計画、在庫の確保等で顧客ニーズに応えている。なお、製造装置市場が中国ならびに新興国にシフトする流れを受け、各種産業装置メーカはミドル〜ローエンド機種に展開をシフトさせる動きを⾒せている。このため、サーボモータの低価格化が進んでいる。 サーボモータに求められる主要機能としては、主に⾼トルク・⾼出⼒、⾼応答性・⾼分解能、⾼精度、
高速などが挙げられ、技術的な研究動向としては、軽量化・⼩型化、コスト削減、構造のシンプル化(センサーレスサーボ)、省エネルギー、IoT・自動化、故障診断機能(メンテナンスフリー)などのキーワードにまとめられる。また、モータの使用環境や用途に応じて、防水、防塵、防爆、防圧(PSI)などの周辺技術が求められる。
サーボモータのアプリケーション別内訳推移(日系メーカ2011〜2013年)
出所:矢野経済研究所推計
前年⽐ 前年⽐⼯作機械・⾦属加⼯ 1054000 978000 93% 1017000 104%
ロボット 603800 545000 90% 533000 97.8%
電子部品実装機(各種マウンター) 499500 412000 83% 410000 100%
半導体製造装置 46400 443000 96% 438000 99%
液晶パネル製造装置 355000 307000 87% 344000 112%
射出成型機 304100 299000 98% 312200 104%
搬送機器(食品など) 391800 394000 101% 407500 103%
その他 571100 553200 97% 621170 112%
合計 4243300 3931200 92.6 4082870 104%
2012年2011年 2013年
3
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
近年のサーボモータ市場は、⼯作機器や、ロボット向け市場を中⼼に成⻑しており、ロボット用のサーボモータに求められる機能としては、一般的に高性能かつ小型であること、低コスト、メンテナンスフリー(⻑寿命)などが挙げられる。その他、付加的な機能としては、防水・防圧・防爆・防塵機能などがあり、各メーカは、用途や仕様環境に合わせてカスタマイズしている。 不⼆越は2017年以降の戦略として、従来の⾃動⾞向けのロボットから、⾷品や医療、薬品向けへと、
幅広いラインナップを拡充していく計画と発表しており、これらロボットに使用されるサーボモータには、防水・防圧・防爆・防塵機能、IP(保護等級)、PSI(防圧)機能が求められる。一方、潜水艦などの特殊な⽤途には、強⼒な防⽔・防圧機能が求められ、Kollmorgen社(米)は、水中専用機用のサーボモータに特化している。
4
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
サーボモータの市場規模は、2015 年時点の出荷台数ベースで約469 万台である。日系メーカは、世界シェアの約6割を占めており、シェア 1、2位は、それぞれ日本のファナックと安川電機が占めている。一方、サーボモータの約 11.1%は、産業⽤ロボット市場の成⻑が著しい中国で消費されており、中国では、パナソニックが 14.4%、三菱電機が 13%のシェアを占めている。国際ロボット連盟(IFR)は、産業用ロボット市場が、2017年から2019年まで13%の年平均成⻑率(CAGR)で成⻑していくと予測しており、一般的に産業用ロボット1台あたり、平均4~6台のサーボモータが使われていることから、今後サーボモータ市場もロボット市場の成⻑に伴い、持続的に成⻑していくと予想される。
サーボモータの世界市場シェア(2015年)
出所:各社情報より矢野経済研究所作成
ロボット市場の展望
出所:国際ロボット連盟(IFR)
5
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
AC サーボモータは、サーボ機構において位置と速度をともに制御することができるため、ステッパモータや、既存の DC モータを代替する形で様々な業界に導入されている。利⽤分野も⾮常に広い範囲に渡るため、特定業界への依存率が低く、市場安定性も⾼い。 モータ世界市場は、2018年時点で 104.3 億ドル規模に、AC サーボモータ市場は、2017 年〜
2021年の5年間 5.49%のCAGRで成⻑すると予測されている。その中で、安川電機(2017)は、国内ACサーボモータ市場は世界全体のCAGRを遥かに上回る成⻑率で推移していくと予測している。
日本のサーボモータ市場の将来予測
出所:矢野経済研究所推計
6
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
保護等級
サーボモータは、その使用環境や用途により、防塵や、防水機能が求められることがあり、それらの機能
に関しては、「IP」で示している。IP は、塵埃・異物及び、⽔の浸⼊に対する保護構造を数字で表したものであり、IEC(InterNational Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)の規格で定められている。これに基づくIP表示は、世界各国で使用されており、日本では、日本工業規格及び社団法人・日本電機工業会がIEC529 に準拠してIP表を規格化している。(JIS C 0920-1993 & JEM1030-1983)
IP規格・防水保護構造及び保護等級
出所:日本エイヴィーシー株式会社
7
IP規格・防水保護構造及び保護等級
出所:日本エイヴィーシー株式会社
防圧 防圧機能は、潜水艦や、高温、火気などによる爆発事故の可能性が高い環境で必要とされる。アメリ
カのKollmorgen社は、100~10000PSIの防圧サーボモータをラインナップしている。
8
センサレスサーボ(センサレス制御) 永久磁石同期発動機(PM モータ)は、⼩型・軽量及び⾼効率という特徴から、様々な用途に適
⽤されている。産業⽤のモータは、環境条件が劣悪な場所で使用されることがあり、位置センサが故障しやすいという問題から、センサレスサーボが、その解決策として研究されている。 「センサレス制御」とは、駆動する電動機の回転を検出するセンサ(エンコーダ)を取り付けずに、制御
に必要な回転数、磁極位置などを推定して駆動する制御方式である。永久磁石同期電動機を駆動する場合、回転⼦(界磁)の磁極位置を検出して、それに応じて固定⼦(電機⼦)の電流の極性、振幅などを制御するのが⼀般的である。センサレスサーボの⻑所としては、⼩形化、省配線、信頼性向上、低価格などが挙げられるが、制御性能は低下するため、⾼精度が求められる環境には適合しない。 センサレス制御の方法はさまざまな方法が考案されているが、一般的には、電動機の回転による誘導
起電⼒を利⽤して推定演算する。PM モータの位置センサレス制御の技術的課題としては、2009年以降、突極性や磁気飽和が少ないモータの場合に停⽌時、及び低速時の磁極位置推定が困難であるという課題がある。この対策として、2013年の技術学会では、「インバータの零電圧ベクトル帰還の電流を検出し、その微分情報を⽤いて速度起電⼒を推定する⽅式」が発表されている。従来は、定格速度の5%程度が推定可能な下減速度であったが、2%程度まで低速限界を拡⼤し、初期位相が推定できない場合でも、微小な逆転を検出して正常な回転方向に修正して指導できる。本方式により、センサレスに適した究極性や磁気飽和特性などの PM モータに関する制約を削減できるため、より用途の拡大が期待できる。一方、2017年の技術シンポジウムでは、「モータ磁気回路構成」とセンサレスサーボをペアにすることによって、低速域でもセンサレスサーボを簡素に実用化することに成功したと発表している。 センサレスサーボの代表的なモデルとしては、三菱電機の S-PM ギヤードモータ(永久磁石モータ)が
挙げられる。同社は、「センサ(エンコーダ)を使用せずにドライブユニットで回転子位置(磁極位置)と速度を推定し、PM モータを制御する方式」を採用しており、適応磁束オブザーバを用いた、PM センサレスベクトル制御により、サーボモータに迫る速度変動率を実現している。エンコーダなしで、出⼒電流と出⼒電圧から、モータ速度に⽐例するモータ誘起電圧を求め、速度を検出しており、速度検出⽅法以外は、サーボと同等の制御(ベクトル制御)を採⽤している。負荷が変化しても速度変動が少ない⾼精度な速度制御を実現しており、速度変動率はサーボモータに迫る±0.05%、従来の誘導モータでは対応できなかった半導体や液晶製造ラインなどの⾼精度搬送⽤途への適⽤が可能である。センサ不要による省配線、信頼性向上、機械装置の⼩型・軽量化を達成できるメリットを持つ。
9
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
ファナック (日本)
ファナックは、1972年に設⽴された、世界最⼤のFA(ファクトリー・オートメーション:CNC、サーボモータ事業を含む)の総合メーカである。ファナックの基本技術であるNCとサーボから成るFA事業と、その基本技術を応用したロボット事業およびロボマシン事業の三本柱によって、あらゆる分野での自動化を進めている。工作機械・ロボットのCNC(コンピュータ数値制御装置)と、多関節ロボットの分野では、2016年時点で、それぞれシェア60%超、25%超で1位を占めており、サーボモータ累計⽣産台数1,700万台を達成している。
10
ファナックのACサーボモータ製品ラインナップと概要
出所:ファナックより矢野経済研究所作成
ファナックのACサーボモータは、「αi-B」、「βi-B」、「Bi-B」、「LiS-B」、「DiS-B」の5つのラインナップに
分けられる。幅広いモデルを持つαi-B シリーズは、高分解能の検出器と最新のサーボ・スピンドル HRV制御技術によって、⾼速・⾼精度・⾼効率のナノ制御サーボを実現しており、あらゆる⼯作機械に適⽤可能な特徴を持つ。βi-B シリーズサーボにも、αi-B シリーズ同様、サーボ・スピンドル HRV 制御技術が適用されており、コストパフォーマンスに優れた、工作機械の送り軸、主軸用としての性能・機能を持っている。 一方、Bi-Bシリーズは、最新のネオジム磁石を採用した⼤トルク・⼤出⼒の⼤型サーボモータで構成さ
れている。モータのロータ内に埋め込む構造(IPM構造)とし、FEM解釈により磁気回路を最適化して、コンパクトでかつ⼤容量の同期サーボモータを実現している。標準サーボアンプを複数台駆動することにより、信頼性を維持し、保守性の向上を実現しながら、⼤出⼒を発揮させられ、電動射出成形機や電動プレス機の⽤途に最適とされる。定格出⼒60kW程度までは、モータ1台1台のアンプで駆動する方式を採⽤しているが、それ以上の⼤容量化のための「アンプ複数台駆動」、さらには「モータ複数台駆動」を適⽤している。「モータ複数台駆動」は、ボールネジャリンクの⼒を分散し、機構部に作⽤する⼒を許容値の範囲内に収めるのに必要不可⽋な技術となっている。 DiS-B series は、工作機械の回転テーブルや 5 軸加工機の回転軸に最適であり、ダイレクトドライ
ブにより⾼速⾼精度とメンテナンスフリーを実現している特徴がある。なお、LiS-B シリーズは、機構部にボールネジ等のたわみ要素や磨耗部品を使用しないことにより、サーボ系の剛性アップによるハイゲイン化、⾼精度化、機構部のメンテナンスフリー化を実現している。剛性の⾼い⻑ストローク軸が可能となり、さらに一本の磁石レール上に複数のコイルスライダを配置することで⼤きな推⼒を得られるため、マルチヘッド構成が容易になるなどのメリットを持つ。
11
ファナックが持つ⾼速・⾼精度のサーボ制御技術として、極めてなめらかな回転のサーボモータ、⾼精度の電流検出、⾼応答・⾼分解能のパルスコーダ等のハードウェアと、最新のサーボHRV制御の融合が挙げられる。共振追従型のHRVフィルタを適用することにより、周波数が変動する機械共振が回避可能になる。 一方、機械の状況変化に応じて最適制御を⾏う「スマートマシンコントロール技術」は、送り軸での反
転時のロストモーションを最適に補正する「スマートバックラッシ補正」及び機械先端の振動を抑制する「スマートマシニングポイントコントロール」により、加工点での動作を改善し、加工面品位を向上できる。 その他の周辺技術としては、サーボ学習制御技術、停電時の機械破損を防止する技術(停電バックアップ機能など、壊れる前に知らせる絶縁劣化検出機能、メンテナンスフリー化(バッテリー交換を不要)などが挙げられる。
サーボHRV技術の適⽤例
出所:ファナック
スマートバックラッシ補正適⽤例
出所:ファナック
12
安川電機 (日本)
安川電機は、1915 年に「電動機(モータ)とその応⽤」事業を⽬的に設⽴され、1977 年には、⽇
本初の全電気式産業用ロボット「MOTOMAN」を発売し、国内外の産業用ロボット市場をリードするメカトロニクスメーカとして成⻑してきた。現時点で、世界12 ヶ国に生産拠点、31 ヶ国にビジネス拠点を持っており、主⼒事業である、AC サーボ・インバーター事業(モーションコントロール事業)及び産業用ロボット事業では、2016年3月時点で、いずれも世界1位のシェアを持ち、ACサーボモータは、同時点で世界シェアの 20%を占める。なお、AC サーボモータの累計出荷台数は、2015 年時点で 1,300 万台を超えており、そのうち6割を輸出している。 ACサーボモータ・コントローラ事業は、中国市場を中⼼にスマートフォン関係や⾃動⾞関連での旺盛
な設備投資需要に伴い、堅調に成⻑してきた。中国市場が急成⻑する前の早い段階から、瀋陽市に⼯場を⽴ち上げたことにより、その後に急増した AC サーボモータの需要に対応し、中国市場に適した製品を開発することができた。AC サーボモータ事業を含めた、モーションコントロール事業の売上高は、2013 年まで中国経済が失速したことによる影響などから低迷していたが、新商品であるΣ-7 シリーズの発売や、中国での現地⽣産によるコスト削減、半導体・電⼦部品の需要の伸⻑などに伴い、2014 から右肩上がりに成⻑している。Σ-7 シリーズは、2015 年時点で、中国の AC サーボモータ市場シェアの 8割を占める。
安川電機のモーションコントロール事業部の売上高推移
出所:安川電機より矢野経済研究所作成
2012 2013 2014 2015 2016売上高(百万円) 149410 144333 162346 188116 187548前年⽐(%) NA (3.4) 12.5 15.9 (0.3)営業利益(百万円)5824 3248 16444 21748 22413前年⽐(%) NA (44.2) 406.3 32.3 3.1
13
安川電機のACサーボモータ製品ラインナップと概要
出所:安川電機より矢野経済研究所作成
安川電機の AC サーボモータは、仕様やサイズによって「Σ-S」、「Σ-V」、「Σ-7」の 3 つのラインナップに
分けられ、各ラインナップは、さらに「回転型」、「ダイレクトドライブ」、「リニア」、「リニアスライダ」などの細分化されたカテゴリーに分けられる。2013年に発売されたΣ-7シリーズは、現時点で世界最高の応答性能を持っており、Σ-7 シリーズの特徴である、業界最高レベルの 24 ビットシリアルエンコーダを搭載することで、更なる⾼精度化を実現している。⼀世代前のΣ-Vシリーズに⽐べると、筐体の⼩型化、発熱量の低減、オートチューニング機能・通信機能の搭載による操作性の向上が評価されている。 同社は、今後Σ-7 シリーズのラインナップを拡充することで、用途を拡大するとともに、市場の顧客ニー
ズに最適化した「市場別モデル」の構築を目標としており、2016年10月には、Σ-7シリーズの回転形サーボモータのオプション仕様として、「バッテリーレス絶対値エンコーダ搭載サーボモータ」がラインナップに追加された。同製品は、エンコーダの磁⽯とコイルによって⾃⼰発電することで多回転量を検出し、不揮発性メモリに保存するため、サーボパックの電源がオフの場合でも、バッテリー無しで多回転量を検出・保存することが可能である。なお、最新の研究動向としては、GaN パワー半導体モジュールを採用したアンプ内蔵サーボモータの開発など更なるパワー変換の⾼効率化、モータドライブの⼩型化を実現する技術開発が進められている。
14
三菱電機 (日本)
三菱電機のACサーボモータは、2015年時点で、世界シェア16%、中国シェア13%を占める。ライ
ンナップとしては、「MELSERVO-J4」、「MELSERVO-JN」、「MELSERVO-J3」、「MELSERVO その他」の4つのシリーズに分けられ、それぞれのシリーズは、「回転型サーボモータ」、「リニアサーボモータ」、「ダイレクトドライブモータ」の 3 つのタイプに分けられる。 その他、独⽴したカテゴリーとして、「センサーレスサーボ」も生産しており、全部で2,257種の豊富なモデルを持つ。 最新動向としては、モータの小型・軽量化トレンドに向けて、既存のダイレクトドライブモータシリーズより、⾼さ 18%減、質量50%減の、薄型ダイレクトドライブモータ2種が2017年1月に発売された。
三菱電機のサーボモータラインナップと概要
出所:三菱電機より⽮野経済研究所作成
15
回転型サーボモータ(HGシリーズ)は、総2,064種のモデルがあり、10 Wから55 kWまでの多彩な容量・仕様で、装置の⽤途に応じて⾃在に選定できる。⾼分解能絶対位置エンコーダ(4,194,304pulses/rev、22 ビット)と、IP55(最高で IP67)を標準採用しているため、高速・⾼トルクで、かつ⾼精度な位置決めを実現でき、対環境性にも優れている。なお、モータ極数とスロットの組み合わせの最適化により、トリクリップルを⼤幅に低減し、低速運転においても滑らかな駆動と安全性の向上が実現できる。ケーブルの引き出し方向を選択でき、負荷・反負荷側の取り付けも可能である。 リニアモータシリーズは、総 42 種のモデルがあり、「コア付き」、「コア付き液冷タイプ」、「コア付き相殺
型」、「コアレス」の4つのシリーズに分けられる。仕様としては、最⼤速度 3m/s(LM-H3 シリーズに対応、最⼤推⼒ 150N〜18000N に対応し、磁界解釈、⾼密度巻線技術により、⼩型でも⾼推⼒を発揮できる。なお、最小分解能0.005μm以上の多彩なシリアルI/Fエンコーダに対応でき、フルクローズト制御による⾼精度な位置決め、⾃在なマルチヘッド構成やタンデム構成が可能な特徴がある。そのほか、冷却タイプの場合、液冷⽅式を採⽤することで、連続推⼒が2倍にアップされる。コア付き相殺型の場合は、磁気吸引⼒相殺構造により、リニアガイドを⻑寿命化、低騒⾳化できるメリットがある。 ダイレクトドライブモータは、総16種のモデルがあり、最新の磁気設計技術と巻線技術により、高トルク
を実現し、高分解能絶対位置エンコーダ(1,048,576pulse/rev)を装備し、⾼精度化を実現する。装置への設置スペース縮小化と低重心化を可能とさせる、小型・扁平薄型化を実現している。伝達機構のないダイレクトモータの特徴上、低騒⾳で滑らかな駆動、たわみやねじれを解消、部品点数が削減されるなどのメリットがある センサーレスサーボは、PM モータ(磁石モータ)を、PM センサレスベクトル制御にて、⾼精度に制御
するドライブシステムである。同社の MM シリーズは、回転⼦に強⼒な永久磁⽯を組み込んだ、⾼性能・省エネーモータである。エンコーダなしでも、⾼精度・負荷変動に強く、安定した速度で運転できる。なお、ゼロ速制御・サーボロック機能により、モータ停⽌時に保持トルクを発⽣させ、外⼒による移動を防⽌できる。エンコーダを持たない⼩形・軽量なモータのため、機械の⼩形化を可能とし、冷却ファンがないため、低騒音であり、クリーンルームでの使用も可能となる。
16
パナソニック(日本)
パナソニックは、1935年に設⽴された、総合エレクトロニクスメーカである。同社の事業分野は、5つに
分かれており、モータ事業を含む「オートモーティブ&インダストリアルシステムズ」の売り上げは、2016 年時点で全体の 31%を占める。同社のサーボモータは、2015 年時点で、世界シェア約 1.6%(7.5 万台)、中国シェア 14.4%を占めており、同時点で、業界初のネットワーク対応 AC サーボモータシリーズ「MINAS A6」を発売し、業界最⼩・最軽量・最速応答を同時に達成している。今後の⽅向性としては、IoTや、工場の自動化に向けた機能を開発していくとしている。 パナソニックのACサーボモータは、大きく「MINAS A4」、「MINAS A5」、「MINAS A6」と、超小型シ
リーズである「MINAS E」の4つのラインナップシリーズに分けられ、全体で2,146種のモデルを持つ。なお、2016年からは、産業機械設備をスマートフォンで調整できる遠隔サポートサービスである、「FAサーボ無線接続システム」を発表している。このシステムは、「FAサーボ&モータ」に、独自開発した無線LANドングルを取り付け、ワイヤレス接続に対応し、産業機器設備や産業⽤ロボットなどの⽴ち上げのリードタイム短縮、生産性向上を達成している。
パナソニックのACサーボモータ製品のラインナップと概要
出所:パナソニックより矢野経済研究所作成
17
⑦ 各国の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等か
らランキング。上位5位程度まで列記)
Siemens (ドイツ)
Siemens の ACサーボモータは、「S-1FK7」、「S-1FT7」、「S-1FL6」、「S-1FU」、「Servo
Geared Motors」の5 つのラインナップシリーズに分けられる。 「S-1FK7」は、優れた過負荷能⼒、耐久性およびコンパクト性を特徴とし、仕様によって
「Standard」、「Compact」、「High Dynamic」、「High Inertia」の4種に分かれている。「S-1FT7」は、超⼩型の永久磁⽯同期モータであり、精度、ダイナミック、スピード設定範囲の厳しい要求、⾼い保護性と耐久性の要求に応えられる。なお、最新のエンコーダ技術が搭載されており、完全デジタル駆動システムと、制御システムの操作に最適化されている。⾃冷、液冷、外部冷却の 3 ウェイの冷却⽅式が選択でき、液冷⽅式を選択することによって、最⾼の性能が達成できる特徴がある。⾃然冷却の場合は、発⽣熱損失は表⾯積を介して取り除かれ、取り付けられたファンは、外部冷却を通して熱損失を避ける方式となる。 「S-1FU」は、⾮同期⾃動始動⽤の短絡ケージを備えた永久磁⽯同期モータであり、⼀定速度のドラ
イブとしての供給システム上、または、可変速度、単⼀、グループドライブとしてのコンバータ上で動作することができる。モータグループ内の複数のモータの同期運転の速度定数と、⾼精度が求められる場所で使用される。 「Servo Geared Motors」は、誘導機を備えた、一般的なギアモータと比較して、寸法が小さく、軽く、
動的応答が高い特徴を持ち、遊星ギアモータと比較して低コストのソリューションを提供する。ダイレクトマウントの結果、非常にコンパクトなデザイン性を持ち、ねじれ刃を使用することにより、稼動時の騒音を低減しており、メンテナンスフリーであることなどのメリットがある。交流負荷と連続運転のサイクリック運転に最適している。
18
ABB (スイス)
スイスの重電・産業機器大手である ABB は、2011 年に北⽶の産業⽤モータ⼤⼿である Baldor
Electric Company を、2017年4月にはオーストリアのFA機器大手であるB&R社を買収したことにより、2017年時点で、ACサーボモータの世界シェア1%弱を占めていると想定される。 ABB の ACサーボモータは、「BSM-N」、「BSM-C」、「SSBSM(防水)」、「BSM-N」の4つのライ
ンナップシリーズに分けられる。BSM-N シリーズは、低イナーシャ、高トルク、高い応答性能を特徴とし、90 種のモデルを持つ。強⼒なネオジム磁⽯を使⽤することにより、最⾼トルクを定格トルクの 4 倍まで引き出せるメリットがある。BSM-C シリーズは、ラインナップの中では、比較的高イナーシャモータで構成され、66種のモデルを持つ。ステンレス製のSSBSMシリーズは、イナーシャの高低によって N と C シリーズに分けられ、全部で 48 種類がある。フードなど、衛生的な環境が求められる用途で使えるよう、FDA 承認シャフトを使⽤、防⽔加⼯がされている特⻑がある。ブラシレスモータである BSM-N シリーズは、4 種のモデルがあり、⾼出⼒・⾼分解能・静⾳であることがメリットである。
ABBのACサーボモータ製品ラインナップと概要
出所:ABBより矢野経済研究所作成
20
Bosch Rexroth (ドイツ)
Bosch RexrothのACサーボモータは、大きく「IndraDyn S」、「IndraDyn A」の2つのラインナッ
プシリーズに分けられ、各4 つ、2 つの下位ラインナップを持つ。 「IndraDyn S」は、さらに「MS2N」、「MSK」、「MKE」、「MSM」の 4 つのシリーズに分けられる。
「MS2N」は、同社の最新シリーズであり、多彩な仕様の組み合わせによって、スペックがカスタムできる特徴を持つ、フレキシブルな同期モータである。「MSK」は、コンパクトでパワフル、多様な場面で使える特徴を持つ。「MKE」は、爆発が起きやすい環境での使用に向けて揮発されており、防爆型モータとして認定されている(ATEX/UL/CSA)。「MSM」は、マルチーターンエンコーダを使用することにより、高分解能、高ダイナミックを実現する。 「IndraDyn A」は、「MAD」と「MAF」の2 つのラインナップに分けられる。「MAD」は、ファン・クーリング
システムを採⽤しており、過酷な産業環境(主に⾦属鋳造、プリント機器)でも対応できる。なお、特別なベアリングを取り付けることで、高速適用、ラジアル荷重の増加にも耐えられる。「MAF」は、最低限のサイズで、高トルクが必要な場面に最適したモータであり、すばやいカップリング(駆動軸と従動軸をつなぐこと)や、液漏れ防⽌機能などがメンテナンスを簡単にするメリットがある。オプションの付け加えにより、場面に応じたカスタム化が可能となる。
Bosch RexrothのACサーボモータ製品ラインナップと概要
出所:Bosch Rexrothより矢野経済研究所作成
21
Kollmorgen (米国)
Kollmorgenは、1916年に設⽴された、総合モーション製品メーカである。モータ、ドライバ、コントローラ、ネットワーク製品等、幅広いモーション製品を供給しており、北⽶、アジア、ヨーロッパに拠点オフィス、工場があり、米国バージニア州に本社を置く。AC サーボモータのラインナップとしては、「AKM」、「AKMH」、「W」、「VLM」、「Kollmorgen Goldline®」、「Serviced Motors」の6つのラインナップシリーズを持つ。 AKM シリーズは、同社の標準サーボモータシリーズであり、8 種のフレームサイズ、多様な電源仕様、シャフトの種類、巻線のカスタム配置などのオプションの組み合わせにより、500,000 種類のモデルが製作可能な特徴を持つ。基本仕様としては、IP67 相当の防水・防塵機能と 100psi ウォッシュダウンに対応している。 AKMHシリーズは、AKMの性能をベースに、衛生・耐腐食を考慮し開発された、食品加工・包装機械専用サーボモータであり、UL/CE/IP69K の認証を取得している。FDA(アメリカ食品医薬品局)認可の部材を使用しており、衛生・耐腐食を考慮したハウジング設計・部材が特徴である。電源供給とフィードバックを⼀つのケーブルにまとめることによって省配線を実現しており、19種のモータタイプと3種の巻線タイプを選択できる。IP69Kのギアとの組み合わせも可能である。 W シリーズは、食品加工用機器に最適したモータであり、衛生面に優れた特徴を持つ。AKMH 同様
ステンレス製、防水機能を装備している。 Goldline®シリーズは、さらに「B/M(低イナーシャモータ)」、「BH/MH(中イナーシャモータ)」、
「EB(防爆型モータ)」、「S(水中機器専用モータ)」の4つのシリーズに分けられる。Sシリーズは、圧⼒バランス構造により、⽔深20,000フィート(約6,000m)まで動作できる。そのほか、電源、要求トルク、回転数等により専用コイル設計が可能な特徴を持つ。 Serviced Motors シリーズは、「F(高イナーシャモータ)」、「PMA」、「R」、「S」、「Centurion」の 5つのラインナップに分けられる。しかし、現時点では、既存に同シリーズを購買した顧客にしか販売しておらず、大体が他シリーズにカバーされている。
22
Estun Automation(中国)
中国のサーボシステム市場は、2015年時点で73.6億元規模であり、世界市場の約1割を占めて
いる。中国のサーボモータ市場は、約7割を輸入に頼っており、サーボ技術においても、後発なため、先進技術を適用したハイエンド製品は、ほぼ海外のブランドに頼っている。 Estunは、1993年設⽴の中資系四⼤産業ロボットメーカの1つである。同社のACサーボモータは、
「EMS」、「EMJ」、「EMG」、「EML」、「EMB」、「EMT/EMT2」の 6 つのラインナップシリーズに分けられる。
EstunのACサーボモータ製品ラインナップと概要
出所:Estunより矢野経済研究所作成
24
TECO Electro Devices Co. Ltd(台湾)
TECO(東元電機股份有限公司)は、1956 年に設⽴された、台湾発の世界有数のモータメーカ
である。1973 年からは、家電製品の⽣産も開始し、電⼦機器・情報機器の⽣産、通信事業のほか、投資事業や外⾷産業、物流にも進出するなど、積極的に事業の多⾓化を展開している。モータ事業は、創業後、日本を代表する複数の電気メーカとの技術提携など、パートナ関係を築き、1995 年にはWesting house社(アメリカ)のモータ事業部を買収して近年急速に売上を伸ばした。現時点では、産業用モータの分野で世界第3位を占めている。モータの製造拠点は東南アジアを中心に10ヶ所を超え、販売拠点も20以上の拠点を有しており、世界各国の⾼効率規格を達成している。
TECOが取得した規格のリストと概要
出所:TECOより矢野経済研究所作成
規制開始 TECO対応可能時期 (適合)機種
アメリカ EISA(エネルギー独⽴安全保障法)
NEMAPremium(IE3相当)
2010/12〜 AEHH,ASHH1-500HP(DesignB)
カナダ EEAct Premium(IE3相当)2011/1〜 同上
EU 欧州委員会規制No.640/2009 IE3 2015/1〜 AEHF,AEUF
0.75-375kW
韓国 エネルギー消費効率等級表⽰制度
IE3相当(KSC4202)2015/1〜 適合機種はあるが
未認証
中国 エネルギー消費効率等級表⽰制度
GB3級(IE2相当)2012/9〜 AEHM,AEUM
7.5-375kW
ブラジル ⼤統領令4508 EPActと同等(IE2相当)2009/12〜 適合機種はあるが
未認証
オーストラリア E3 Program LEVEL 1A/LEVEL 1B※2006/4〜 AEHB 0.75-185kW
ニュージーランド E3 Program LEVEL 1A/LEVEL 1B※2006/6〜 AEHB 0.75-185kW
※効率試験⽅法により、LEVEL 1AとLEVEL 1Bがあり、効率値が異なる(IE2<LEVEL 1A,1B<IE3)
国名 法律名 効率レベル
25
⑧ サプライチェーン
ファナック、安川電機、川崎重⼯、不⼆越、三菱電機などを代表とする国内のロボットメーカは、ほぼサーボモータ・ドライブを内製しており、海外メーカへの依存性は低いものと想定される。「メカトロ 2017」に出展しているメーカを対象に取材した結果、国内メーカの中では、三菱電機のサーボモータが好まれる傾向が⾒られた。 海外メーカの中でもABBは、北⽶の産業⽤モータ⼤⼿であるBaldor Electric Company を買収
し、サーボモータの内製と輸出に努めている。一方 KUKA は、コンパクトロボットの「KR Agilus」シリーズにKollmorgen社(米)のサーボモータを取り入れている。
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
ロボット⽤のサーボモータをキーワードに論⽂を発表している国内の研究者は以下のとおり。
出所:KAKENより矢野経済研究所作成
27
⑩ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な
研究者及び所属機関
「Science Direct」や、「Google Scholar」を⽤いた論⽂検索(2015〜2017年)を⾏い、各国のロボット用アクチュエータ研究者を抽出した。なお、中国については中国検索サイトを利⽤している。 ① 米国
米国の主な研究者及び所属機関
出所:Science Direct、Google Scholarより矢野経済研究所作成
② 欧州
欧州の主な研究者及び所属機関
出所:Science Direct、Google Scholarより矢野経済研究所作成
28
③ 中国
中国の国家⾃然科学基⾦委員会のロボット⽤サーボモータ関連プロジェクトに係わるメーカ及び研究機関は以下の通り。なお、研究者については、「Google Scholar」を用いて抽出した。
出所:Science Direct、Google Scholarより矢野経済研究所作成
中国の主な研究機関及びメーカ
出所:NSFC(国家⾃然科学基⾦委員会)より矢野経済研究所作成
研究機関 メーカ上海交通大学 上海新時達電気股份有限公司華中科技大学 深圳市汇川技術股份有限公司瀋陽工業大学 武漢華中数控股份有限公司南京理⼯⼤学 深圳市英威騰電気股份有限公司重慶理⼯⼤学 広州数控設備有限公司(GSK)合肥工業大学知能製造技術研究院 南京埃斯頓機器人工程有限公司航天科工伺服技術研究所 固高科技(深圳)有限公司
29
④ 韓国
韓国ロボット学会の学会⻑インタビューによると、韓国は⽇本に⽐べ、アクチュエータなどロボットの基幹部品に特化した⼈材が不⼗分な状況である。減速機やサーボモータに関しても、厳密に専門の研究者を分けられなかったため、以下にロボット用のアクチュエータで成果を挙げている研究者をまとめてリストアップした。
韓国のロボット用アクチュエータ研究者および研究機関
出所:韓国ロボット学会より矢野経済研究所作成
⑤ 台湾
文献調査レベルでは、ロボット用のアクチュエータを専門とする研究者及び研究機関はみつからなかった。
30
⑪ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
ロボット用アクチュエータに関連するプロジェクトを調べたところ、サーボモータと減速機を厳密に分けて研究している状況ではなかったので、調査結果を以下の一つの表にまとめた。
国内のロボット用アクチュエータ関連研究開発プロジェクト
出所:日本の研究.com より矢野経済研究所作成
期間 2012〜2016(1次)2016〜2018(2次) 2014〜2017 2014〜2017 2011〜2014 2011〜2013 2015〜2019 2015
資⾦拠出元 科研費 科研費 科研費 科研費 JST 科研費 JST予算⾦額(千円)
17,160(1次)14,560(2次) 5,070 3,510 19,500 18,000 3,900 17,000
参加機関 東北⼤学 愛媛大学 ⼤阪府⽴⼤学⼯業⾼等専門学校 大阪大学 国⽴⼤学法⼈福島⼤学 横浜国⽴⼤学 広島県⽴総合技術研究所
プロジェクト内容
①複数の⽀援機能を持つ⾞いすや歩⾏⽀援機、ハプティックデバイスなどの人間支援システムの開発。②DCサーボモータを回生ブレーキとして利⽤し、そのブレーキ⼒を制御することで、様々な支援機能が安全に実現。③安全かつ低消費電⼒な⾼機能人間支援システムの実現。
①歩⾏運動制御アルゴリズムの改善。②可変弾性機能を持つ特殊な関節の改良と導⼊。③弾性調節機能を装着するなど、最終モデルの歩⾏ロボットの改良。
①ロボットアームに接続する4種類のエンドエフェクタを製作し、その動作性能を調査。②ロボットアームの制御方法としてPTP制御及びCP制御について学習することができるようにプログラムを作成。③製作してきたロボットアームとエンドエフェクタの制御方法について検討。
①これまで研究してきた高性能な磁気波動型ギアをもとに、⾼トルク・⾼効率を実現できる新しい磁気ギアの原理モデルを考案。②解析シミュレーションを用いて磁気構造の最適化を実施し、最高性能の磁気波動型ギアを開発。③磁気ギアとアクチュエータを一体化した、世界初のメガトルクアクチュエータを開発。④メガトルクアクチュエータ設計のためにFEMを用いた大規模並列計算シミュレータを開発し、実機による実験結果との⽐較により解析精度検証。
2つの技術シーズ(⽴体カム機構,クラウン減速機構)を⽤いて直径10mm以下、⻑さ30mmのバックラッシュが極めて小さいモータ内蔵型ミリサイズ⾼出⼒関節アクチュエータを開発・事業化し、⾼精度内視鏡装置や超小型精密ロボットハンド等の先端医療機器・精密製造機械等への展開を目指したベンチャー企業の設⽴を⽬指す。
①⼩型・⾼効率・⾼トルク・高減速比の新しい複合遊星⻭⾞機構を提案し、実証することを目的とする。②モデルと実験の両面から、提案する複合遊星⻭⾞機構の諸性能を明らかにする。
ロボットの関節には精密な減速機が求められ、波動⻭⾞機構のものが多く使用されているが、回転方向の剛性や⾼速回転時の伝達効率に課題があるため、広島県の独自技術であるコルヌ⻭⾞を適⽤した減速機を試作開発する。
⼩型・⾼効率を実現する複合遊星⻭⾞機構
コルヌ⻭⾞を適⽤した産業用ロボット向け遊星⻭⾞減速機の開発
プロジェクト名
安全かつ低消費電⼒な高機能福祉システムを実現するハイブッリト型運動制御手法の構築
人体の筋骨格構造と弾性調節機能を持ちいた新しい歩⾏ロボットの設計と運動制御
組み合わせが可能なロボットアーム・ハンド教材の開発
磁気派動減速機内臓メガトルクアクチュエータを搭載した人間型ロボットの開発
モータ内蔵型ミリサイズ・バックラッシュレス関節アクチュエータの事業化
31
⑫ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
① 米国 各省の⽀出データ(Contract, Grant, Sub-Contract)をまとめている Federal Reporter や、USASPENDING.gov を⽤い、サーボモータや減速機関連プロジェクトの抽出を⾏った。以下に、サーボモータ関連プロジェクトをまとめる。 なお、USASPENDING.gov によると、NASA(アメリカ航空宇宙局)は、テキサス大学に、サーボモータ関連予算として、2015年から2017年の間211,402ドルを拠出している。
アメリカのロボット用サーボモータに関するプロジェクト
出所:Federal Reportrerより矢野経済研究所作成
プロジェクト名
SBIR PHASE I:A PNEUMATICALLY ACTUATEDROBOT SYSTEM
SBIR PHASE II:LOW-COST ULTRA-EFFICIENT50-GM, 300-WSERVOELECTRONICS MODULEWITH INTEGRAL SENSORS
期間 2016.01〜2016.12 2008.11〜2013.04資⾦拠出元 National Science Foundation National Science Foundation予算⾦額 180,000USD 1,024,000USD
参加機関 SUNSTREAM SCIENTIFICINCORPORATED
BARRETT TECHNOLOGY INC
プロジェクト目標
ダイナミックなシステムバリエーションに迅速に対応する⾼度な制御アルゴリズムと結合された、革新的なダイレクトドライブ空気圧ロボットアクチュエータの実現可能性を検討する。
ブラシレスサーボモータのコスト削減
32
② 欧州 欧州では、欧州最⼤の研究・イノベーション資⾦情勢プログラムである「Horizon2020」の資⾦
援助を受け、2015 年から広範囲なロボット関連のプロジェクトが稼働中である。プロジェクトの段階は、Call1、 Call2、 Call3 と分かれており、2016 年からは Call3ステージで新たに 17 個のプロジェクトが追加されている。欧州委員会の「Robotics 2020 Strategic Research Agenda(2013)」によると、ロボット⽤のアクチュエータに関しては、重量⽐とエネルギー効率の段階的な改善、新しい作動技術と新材料の採⽤などが課題とされており、外科⼿術⽤途において成⻑が期待されると展望している。 一方、欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)を対象
にサーボモータの研究開発プロジェクトを調査したが、現在進⾏中のプロジェクトは無かった。
欧州のロボット関連プロジェクトリスト(Call3ステージ)
出所:European Commissionより矢野経済研究所作成
An.Dy 意図しない接触に反応する能⼒を持つ安全認定ロボット(コボット)BADGER 地下空間で掘削、操縦、ローカライズ、マップ、ナビゲートが可能な⾃律地下ロボットシステムCo4Robots 様々な機能を備えた異なるマルチタスキングロボットが、オブジェクトハンドリング/輸送、ピックアップおよび配信操作などのサービスを提供CYBERLEGs Plus Plus障害を持つ⼈が⾝体活動を⾏うことを可能にする可動性を回復するための動⼒付きロボットオルソプロテーゼDreams4Cars ⾃動⾞事故のような稀な出来事に焦点を当て、ロボットは想定/未経験の状況で安全のためのリアクションができるHEPHAESTUS プレハブウォールの設置など、リスクが高く重要な建設作業を支援する3Dを使用したケーブルロボット
ILIAD 現在の倉庫施設、特に⾷品部⾨に迅速に導⼊して統合することができる、柔軟で堅固な信頼性の⾼い物流システム人間と共有する環境での安全な運用を保証しする
IMAGINE ロボットが⾃分の環境の構造とその⾏動によってどのように影響されるかを理解できるようにする
MoveCare 高齢者の衰退と社会的排除に対抗するための活動を監視、支援、促進することによって、⾃宅で⾼齢者の⾃⽴⽣活を⽀援するマルチアクタープラットフォーム
MULTIDRONE 堅牢性、安全性、安全性の向上した屋外イベントをカバーするメディア制作のマルチドローンプラットフォーム
REELER 主要な社会問題に取り組むこのプロジェクトは、ロボット主義者、ユーザー/影響を受ける利害関係者、政策⽴案者間の分散した責任のギャップを埋めることによって、REELERロードマップのガイドラインを策定する
REFILLS ⼩売市場における店舗内の物流ニーズに対応できるロボットシステムRobMoSys オープン、持続可能、迅速かつマルチドメインなロボットソフトウェアエコシステムを構築するためのモデルとソフトウェアを提案する
ROSIN 既存のオープンソースの「ロボットオペレーティングシステム(ROS)」フレームワークを構築し、世界的なコミュニティを活用して、⾼品質なインテリジェントなロボットソフトウェアコンポーネントの⼊⼿可能性を段階的に変更することを⽬指す
ROPOD ロジスティックタスクのための費⽤対効果と⼈にやさしい⾃動誘導⾞両(AGV)
SMARTsurg 泌尿器科、⾎管⼿術、軟部組織整形外科⼿術の実世界の⼿術シナリオに焦点を当てた、遠隔操作手術が可能なスマートウェアラブルロボット
VERSATILEセル ⾃動⾞、航空宇宙、ハンドリング、パッケージングなどの業界で、多数の異なる製品に⾃動的に適応できるデュアルロボットアームを備えた柔軟なロボット
33
③ 韓国 韓国の産業通商資源部は、2016年11月、2020年までに500億円を投資し、ロボットの需
要と供給⾯での戦略及び政策課題を提⽰していくことを⽬標とする「ロボット産業発展⽅案」を発表した。同時に、同年度からは、ロボットの市場拡⼤を促すための「知能型ロボット開発及び促進法」の改定も推進されている。 2017 年時点では、産業通商資源部の R&D 予算の 5 割が、ロボット知能、HRI(Human
Robot Interaction)などの源泉技術とアクチュエータ、制御機器、センサーなどの分野に執⾏されている。同部は、2017年以降から、研究者⼀⼈当たり年間1,000~3,000万円の研究費を支給するプログラムを導⼊し、有望なロボット製品・部品の中⻑期戦略をボトムアップ形式で提⽰していくと発表している。なお、ロボット基幹部品の国産化に向けた取り組みとしては、ロボットの供給企業と需要企業で「ロボット部品組合」を結成し、高価な生産・測定装備を共同で構築することにより、個別企業の試験費⽤を節約し、量産化を加速化させる案を打ち出されている。 ⼀⽅、韓国電気研究院は、ロボット、エネルギー、医療機器産業などを4次産業⾰命の核⼼研
究分野として選定し、ロボット用超精密サーボモータを含む 19 個の製品及び技術を当院のトップダウン課題として集中開発すると発表した(2017年5月)。当院の2017年の予算は約105億円規模である。
韓国のロボット用サーボモータに関するプロジェクト
出所:産業通商資源部より矢野経済研究所作成
推進課題 投資計画(〜2020年)尖端製造ロボットを活用したスマート工場高度化 10億円(2918年まで)サービスロボットの公共需要発掘、普及・拡散 24億円尖端ロボット常用化研究センター 100億円ヒューマノイドロボット研究センター 15億円人工知能・ICT融合ロボット人力構成 15億円ロボットシステム設計技術等核心技術開発支援 350億円海外でのテストベット構築等海外進出支援 12億円
合計 526億円
34
⑬ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
⾼速・⾼精度・⾼応答性に関連する技術
⾼速・⾼精度・⾼応答性に関連する技術としては、主に、巻線技術、使⽤される磁⽯の種類や配置関連技術が挙げられる。サーボモータの累計⽣産台数ベースで 1 位を占めるファナック社の製品には、最新のHRV(High Response Vector)制御や、スピンドルHRV技術が適用されている。以下に、それぞれの特徴をまとめる。 HRV(High Response Vector)制御:極めて滑らかな回転のサーボモータ、⾼精度の電流検出、高応答、高分解能のパルスコーダ等のハードウェアと、最新のHRV+制御の融合により、ナノレベルの⾼速・⾼精度加⼯が可能であり、共振追従型のHRV フィルタを使用することにより、周波数の変動する機械共振も回避できる。デジタルサーボ制御部へ位置指令をナノメータ単位で演算するナノ橋間、制御周期をさらに高速化したサーボHRV制御・スピンドルHRV制御、および高分解能パルスコーダを備えた「αi-Bシリーズ」を標準採⽤することにより、⾼精度を実現している。
サーボHRV+の適⽤例
出所:ファナック
36
スピンドルHRV制御:スピンドルHRV制御は、主軸の⾼応答・⾼精度を実現する制御⽅式である。⾼速電流制御により、ハイゲイン制御と共に、モータ⾼速回転時の発熱低減を実現し、ワークやツールのイナーシャが変化しても常に最適化速度で減速を⾏う、最低オリエンテーションを装備している。制御はナノ補間で⾏い、送り軸と同様に主軸においてもナノCNCシステムを実現しており、スピンドルモータの最⼤出⼒を利⽤して加減速し、調整レスで最短時間のタップ動作を実現するスマートリジットタップ機能を装備している。
スピンドルHRV制御の適⽤例
出所:ファナック
37
モータの⼩型化・軽量化 サーボモータの⼩型・軽量化には、巻線技術での整列度、点積率が影響する。一般的にモータの体
格は、要求されるトルク性能と温度上昇の許容値によって決まる。同じ出⼒・効率を維持したままモータを⼩型化する場合、体格が⼩さい上に同程度の損失が発⽣することや、放熱⾯積の縮⼩から過度な温度上昇が問題となる。温度上昇は永久磁⽯の磁⼒の低下や巻線抵抗値の増加を引き起こし、モータのトルク特性や精度を低下させるため、⼩型化と温度上昇はトレードオフの関係にある。従って、温度上昇とトルク性能をバランスよく設計することが小型化設計のポイントであり、モータにおける実際の駆動状態の温度を考慮した特性解析が必須である。 ⽇⽴製作所は、⼆次元有限要素法による電磁界解析と、熱等価回路網法による熱解析を連成し、
さらに数理計画法に基づく形状最適化技術を合わせることで、磁⽯モータの⼩型化設計を実現した(2010)。この解析では、まずモータの各種変数を設定し、それに基づき⼆次元磁界解析を⾏い、次いで熱解析を実施する。この結果が設定した体格最小化の目標を満たすまで、所定の制約条件の下で最適化エンジンが各種変数を再設定し、繰り返し計算がなされる。 一方、安川電機は、2015 年から、トランスフォーム社の「GaN パワー半導体」を採用することにより、
1/2 の体積⽐を実現した。⼀般的なサーボモータは、電⼒変換やモータ制御を⾏うアンプ部とサーボモータ部が分かれている。サーボモータとアンプは少なくとも 2 本の配線(電源配線とエンコーダー配線)が必要で、複数のサーボモータを駆動させるには、配線本数が多くなり取り扱いが煩雑で、多くのスペースを要する。アンプをサーボモータと⼀体化すれば取り扱いは容易になるが、アンプの⼩型化が難しく、モータから伝わる熱や振動の問題があった。この解決策として採用されたのが、GaN パワー半導体であり、電⼒損失が少なく、発熱の抑制が可能な特徴から、冷却機構の⼩型化(⾃然空冷化)が実現できた。さらに、同製品が持つ高周波スイッチング特性により、各種受動部品を振動・熱に強い小型サイズ品に置き換えることが可能になり、アンプの耐振動性、耐熱性を高めつつ、サーボモータと一体にできるまでのサイズまで小型化することに成功した。
38
巻線技術(省エネルギー) 巻線とは、電気エネルギーと磁気エネルギーを相互に交換するために用いる電線の総称であり、自動
⾞⽤電装品、産業⽤モータ、家庭⽤電化製品、電⼒⽤機器、情報通信機器などの基幹部材として使用される。巻線の種類は多岐にわたり、絹、糸、紙、フィルム、ガラスを銅などの導体に被覆した横巻線や、乾性油等の天然樹脂ワニスなどの絶縁材料を塗装焼き付けした合成エナメル線などがある。 巻線設計における設計パラメータとしては、「巻線径」、「巻数」、「占積率」、「巻線材料」などが挙げら
れる。巻線の仕方としては、大きくコイルを束にし、スロット間に注入する「分布巻」と、ティースにコイルを直巻する「集中巻」に分けられる。分布巻は、コギングトルクが⼩さくなるため、⾳振動⾯で有利であるが、銅損が比較的多くなる。集中巻は、音振動には優位を持つが、巻線係数が低くなりやすい。 巻線によって決まる特性としては、巻数に依存して変化する鎖交磁束数によって決まるトルク定数、巻
数・巻線径・巻線材料によって決まる巻線抵抗などが挙げられる。また、巻線の選定においては、巻線径及び巻線材料により電流値が制限される。巻線の持つジュール熱により温度上昇を招き、巻線抵抗が上昇するためである。従って、設計するモータに流す電流を考慮し巻線の選定を⾏う必要がある。量産工程では、巻線は巻線機を⽤いて⾏われ、巻線は張⼒や巻線プローブ位置などをプログラムでコントロールし占積率が上昇するように製造される。限られた巻線範囲を有効に使うためには占積率を上げる必要があるため、⾼点積率を達成する巻線技術が必要とされる。 山洋電気は、2016年の技術動向として、モータ損失の発⽣原因を定量的に分析し、損失が最少で
トルクが最⼤となる技術を開発した。ステータ・ロータコアの磁路設計と電磁鋼板の材質を最適にすることで鉄損を低減し、巻線スペースの拡⼤及び整列巻にすることで、巻線点積率を向上し、銅損を低減している。なお、同社が 2015 年から発売している、「⼩径 20角 AC サーボモータ」には、空芯で巻線し、それを円弧形状に機械的に曲げたものをコアに注⼊する、「⾼点積率巻線技術」を適⽤し、銅損を⼤幅に低減、出⼒領域の拡⼤と低損失化を実現した。また、フレーム断面を丸形状とし、さらに磁性体にして、磁気回路の⼀部とすることで、点積率の向上と軽量化を同時に達成している。
39
振動・騒音制御 サーボモータを使⽤する機械の⼩型軽量化と⾼応答化への要求に伴い、サーボモータは振動の⼤きな
環境で使⽤される場合が多い。サーボモータにおいては、反出⼒軸端に回転位置を検出するための光学式エンコーダを設けるが、このエンコーダが振動によって誤作動しないようにする必要がある。モータにおける騒音・振動の原因としては、機械的な要因として、軸受の摩擦、ブラシの摺動(DC モータの場合)、機械共振などが挙げられ、軸方向振動に起因してエンコーダが過大な振動を起こした場合、パルスカウンターエラーが発生しやすく、エンコーダの破損にいたる危険もある。このような問題は「モータの構造の工夫」が解決策となる。⼀例として、「定圧与圧接着後に両サイドのベアリング断⾯を機械的に保持する構造」があげられ、⾼い軸⽅向剛性と耐振動性の向上が⾒られる。⼀⽅、モータ⾃体の振動の原因としては、主に、コギングトルクとトルクリップルが挙げられ、これらを極めて小さく抑えることが求められる。そのためには、磁⽯の形状、配向⽅向、着磁状態を適切に選択することが重要である。 コギングトルクは、⾮励磁状態で回転⼦を動かした際に発⽣する磁気吸引⼒であり、制御を⾏う上で
は外乱となるため、数値が⼩さいほど⾼精度になる。コギングトルクは、磁気吸引⼒の変化がウネリとなって現れ、磁気吸引⼒はコアと磁⽯により決まるため、磁⽯の形状の影響(磁⽯の極数とスロット数の関係)に大きく影響される。一般に磁極数とスロット数の最小公倍数が大きいほど、コギングトルクは小さくなる。回転性能を向上させるための磁石の使い方としては、「スキュー着磁」と、磁石の配置を周方向にずらす「段スキュー」が挙げられる。ラジアル配向リング磁石を使用し、着磁によるスキューを導入する場合、⾒掛け上のコギングトルクの周期と等しい⾓度をスキュー角として取ればよく、このときコギングトルクの高調波成分も同時にゼロとなるため、⾮常に低いコギングトルクが得られることが⼀般化できる。⼀⽅、「極異方性配向」を採用することにより、コギングトルクはラジアル配向の約1/10と、大幅に低減でき、トルクリプルの減少にも効果が⾒られる。 なお、IPM モータ(磁石埋め込み型モータ)においては、「ロータスキュー」がトルクリプルと、コギングト
ルクの低減に効果的である。トルクリプルは、界磁磁極の構造によって存在する空間高調派に大きく影響され、永久磁⽯の配向と駆動電流波形の組合せにより、トルクリプルの⼤きさが変化する。正弦波電流駆動の場合は平⾏配向が、矩形波電流駆動の場合は、ラジアル配向の⽅が、トルクリップルが⼩さくなる。特に、平⾏配向と正弦波電流駆動の組合せでトルクリプルが⼩さくなる。 モータにおける騒音・振動の原因としては、機械的な要因として軸受の摩擦やブラシの摺動(DCモータ
の場合)、機械共振などが挙げられる。軸受は、3 種類あり、①流体軸受 ②玉軸受 ③焼結メタル軸受の順で静⾳性が⾼いと⾔われている。値段も同様の並びであり、流体軸受の価格は低下傾向となっているため、低負荷のファンなどに採用され始めている。また、玉軸受では、予圧によって動作の安定性が変わるため、騒⾳・振動の特性を良くする為には注意が必要となる。設計によっても⼤きく変化するが、機械的な摺動が起こる部分は、騒音の発生源となる。モータにとって機械共振は重要な要素のひとつであり、特に大型のモータでは、共振周波数が低下するため、多くの問題の原因となる場合が多い。機械共振については、「モーダル解析(実験モーダル・有限要素法CAE)」による分析法が一般的に使われ、設計段階で問題点を解決している。
40
⑭ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
巻線機 ⽇本のモータ⽤巻線機メーカのグローバル競争⼒は強く、2011 年時点で世界シェアの 4 割以上を占めている。国内の主要プレーヤーは、小田原エンジニアリング、日特エンジニアリング、べステックなどが挙げられ、グローバルでは、欧州に4社ほどプレーヤーがいる。
世界の巻線機市場規模
出所:日特エンジニアリング
41
モータ用巻線機市場では、小田原エンジニアリングがシェア 17%(2011 年時点)で世界 1 位を占めており、ファナック、三菱電機、パナソニックなどに納⼊している。⽇特エンジニアリングは、同市場で世界2~3 位を占めており、コイル用自動巻線機市場では、世界シェア約 4 割、国内シェア約7割で 1 位を占めている(2016年)。 ⼀⽅、株式会社べステックは、ブラシレスモータ巻線機、整列巻線機に特化して事業を展開しており、
ノズル巻線技術においては、業界随一のシェアを誇る。同社は、9割を輸出しており、国内では日産自動⾞、アイシン精機、イーグル⼯業、ブラザーエンタープライズ、⽇⽴アプライアンスなどに納⼊している。
モータ用巻線機市場シェア
出所:日特エンジニアリング
42
軸受と軸受材料 サーボモータには、ロータを支えるモータ用軸受と、必用に応じてエンコーダシャフトを支えるエンコーダ用
軸受の 2 種類が配置されている。モータ⽤軸受に求められている性能としては、「⾼温下での⻑寿命(焼き付き寿命)」、「耐摩耗性(フォールスブリネリング防止)」、「⾼密封性(グリース漏れ防⽌)」などがあげられる。エンコーダ⽤の軸受に求められる性能としては、「⾼清浄度(センサー誤作動防止)」、「高剛性」があげられる。国内の軸受メーカとしては、日本精工、NTN 株式会社、ジェイテクト、ポーライトなどが挙げられ、2016 年時点での日系メーカの世界シェアは、約3割弱を占めている。国内シェアでは、日本精工が1位を占めており、小型モータ用の軸受けでは、ポーライトが1位を占めている。 転がり軸受は、機械要素として、その寸法系列が国際的に標準化されており、これに⽤いられる材料
に関しても、ISO683/17(熱処理鋼、合⾦鋼、及び快削鋼/Part 17 玉軸受及び転び軸受用鋼)があるが、各国のそれぞれの規格体系の中で、メーカが独自の修正を加えている場合もある。 ⻑寿命軸受材料としては、転がり軸受けに「⾼炭素クロム軸受鋼」が頻繁に使われ、⾼温⽤軸受材
料としては、⼀般的に⾼速度鋼のSKH4や、Cr-Mo-V鋼(AISI M50)が多い。なお、600度以上の⾼温環境では、⾼速度鋼でも硬さが不⾜するので、Ni系合⾦のハステロイや Co 系合⾦のステライトなどが使われ、さらに高温の環境では、ファインセラミックスである窒化ケイ素、炭化ケイ素などが使用される。⾼温⽤材料は、その使⽤温度において、硬さ、疲れ強さ、組織変化及び寸法安定性が、使⽤⽬的に適する水準に達している必要があるため、特に硬さが求められる。 一方、ジェイテクトが開発し、2016 年から量産化している、セラミック⽟軸受が業界の注⽬を集めてい
る。セラミック素材のメリットは、外輪・内輪との⽟のすきま変化をより⼩さくでき、幅広い温度環境への対応が可能な点である。セラミック軸受は、特に高温や高速に使用されるため、その損傷は周辺の装置や機械の性能に重⼤な影響を与えることが多く、軸受け材料として、エンジニアリングセラミックスに求められる最も重要な性能は、転がり疲れ寿命に対する信頼性である。加工性やコストの問題が課題として残っているが、今後開発を通して、⾼温⽤・腐⾷環境⽤・真空無潤滑⽤の軸受けなどへの適⽤が期待されている。 軽量、易成形性、⾼耐⾷性などの観点から⾒てみると、⾼分⼦材料は、保持器を含む軸受け材料と
して広く使用されている。使用方法としては、単独での使用と、諸要求性能を満足させるために、各種の機能充てん剤を配合した複合材料として改質され使⽤されることが多い。
43
磁石 磁石は、モータにおいて主要部品のひとつであり、体積、重さ、コストなどその占める割合は他の部品と
⽐べても⼤きく、磁⽯の⼒・配向は、サーボモータのパワー、⼤きさ、形などに⼤いに影響する。磁⽯は材質(磁粉)と製法により種類が分類され、主な磁石の材質の種類としては、大きく「フェライト系」と「希土類系」の2種類に分けられる。 フェライト系は、フェライト(酸化鉄 Fe2O3)を主成分とする磁⽯であり、希⼟類系は希⼟類⾦属で
ある、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、コバルト(Co)、などを含んだ磁石で、一般的にフェライト系よりも強い磁⼒を持つが、原料を中国からの輸入に頼っているため、価格が高い。希土類系の中でも、ネオジム磁石は日本で発明された史上最強の永久磁石で、モータやアクチュエータ用の部品としてさまざまな工業製品に使われている。⼩型及び⾼出⼒モータほど、希⼟類磁⽯が使われていることが明確である。 産業⽤・⺠⽣品としては、フェライトとネオジムが⼤部分を占めており、駆動⽤モータは、ネオジムを代表
とする、⾼性能な希⼟類磁⽯を⽤いることが主流となっているが、希⼟類磁⽯の 90%は中国で生産されているため、材料の供給不安や価格変動といった課題があり、希⼟類磁⽯を使わずに、⽐較的経済的なフェライト磁⽯を⽤いる技術や、磁⽯を使わない技術についても研究開発が進められている。⽇⽴製作所と、山陽電気は、2012 年にレアアース(ネオジム、ディスプロシウム)を含んだ磁⽯を⽤いない、「レアアースフリーモータ」を開発している。なお、2016 年 7 月には、大同特殊鋼株式会社とホンダ技研株式会社が、共同で「重希土類完全フリー熱間加工ネオジム磁石」を世界で初めて開発・実用化に成功し、ハイブリット⾞の⾞載モータとして活⽤しており、今後他の産業分野でも活⽤度が増していくものと期待される。
重希土類完全フリー磁石
44
磁⽯メーカは製法や磁粉・添加物質を改良することで、特性の向上を⽬指しており、磁⽯の特性に⼤きく影響する要因として、「配向」を挙げている。磁⽯の成型⼯程を磁界中で⾏うことにより、磁⼒に⽅向性を持たせ、配向⽅向は磁⼒が強くなるため、特性の向上に効果的である。配向の処理がされている磁⽯を、「異⽅性磁⽯」と呼び、配向の処理のされていない磁⽯を「等⽅性磁⽯」と呼んでいる。ネオジム焼結磁⽯は、異⽅性が⼀般的であるが、磁⽯の材質によらず、異⽅性、等⽅性それぞれ提供されている場合が多い。
フェライト磁石とネオジム磁石の比較
45
ネオジム磁石 ネオジム磁⽯の需要は、今後ハイブリット⾃動⾞や電気⾃動⾞が増えていくに従い、持続的に増加し
ていくと想定される。⽇本のネオジム磁⽯メーカは、⾃動⾞向け等のハイスペックな磁⽯で⾼い競争⼒を持っている。国内市場は、⽇⽴⾦属、信越化学、TDKの3社がほぼ独占しており、そのうち⽇⽴⾦属のシェアは、2014年時点で6割を占めている。同社は、フェライト磁石に置いても、世界シェア1位を占めている。⽣産量ベースで⾒てみると、中国が世界の 6 割を生産しており、日系メーカは、全体の約 25%を占めているが、質においては優位を持っており、各社が中国やベトナムを代表とする海外拠点を確保することで、グローバル需要の獲得を図っている。
ネオジム磁⽯の⽣産量⾒通し
出所:JOGMEC
46
ホール素子(磁気センサー) ホール素子とは、「ホール効果」を利⽤した磁気センサであり、磁気量を電気量に変換するために⽤いられる。ホール効果とは、固体(半導体薄膜)に電流を流し、固体表面に対し垂直に磁界を加えた時、電流⽅向及び磁界⽅向それぞれに垂直な⽅向に、電圧が発⽣するという原理に基づくものである。 旭化成エレクトロニクスは、世界シェア7割で1位を占めており、残りの3割は、世界シェア2位の、ド
イツのMicronas社が占めている。国内においては、旭化成エレクトロニクスと日本セラミックス、ロームなどが主要プレーヤーであり、超音波センサーにおいては、日本セラミックがシェア7割で、世界1位を占めている。 旭化成エレクトロニクスは、業界最小の超小型ホール素子を開発しており、メンテナンスフリーモータや、その他用途に合わせた設計を実現している。モータにおいて、ホール素子を採用するメリットとしては、耐久性、汚れに強い特性、⼩型・軽量化が容易なことなどを挙げられる。
ブラシレスモータのホール素⼦採⽤例
出所:旭化成エレクトロニクス
47
無方向性電磁鋼板(モータの材料) 「無方向性電磁鋼板」とは、鉄にケイ素などを添加することにより製造される電磁鋼板の一種であり、
鉄存値(コア(鉄心)に磁気を与えた場合に熱エネルギーとして消費される電⼒損失の値)が⼩さいなど、磁気特性に優れており、所定の形状に打ち抜き、積層し、プレス加工を施すなどしてモータなどのコアに用いられる。電磁鋼板には、無方向性電磁鋼板と、方向性電磁鋼板の2種に分けられ、無方向性電磁鋼板は、すべての方向に均一な磁気特性を有しているのに対し、方向性電磁鋼板は、圧延方向に磁気特性を発揮し、主に変圧器のコアに使用される。 無方向性電磁鋼板には、板厚及び鉄損値に応じて様々な規格が存在し、板厚が薄く、鉄損値が小さい規格ほど高グレード、板圧が厚く、鉄損値が大きい規格ほど低グレードの製品である。国内ユーザは、国内拠点だけでなく海外拠点も含めて、大部分の無方向性電磁鋼板を国内メーカから調達しており、国内市場は、大手 3 社がほぼ独占している構造であったが、2011 年の新⽇鉄と住友⾦属との合併により、現時点では、合弁会社である、新⽇鉄住⾦のシェアが55%で、国内シェア1位を占めている。 同社の調査結果によると、国内市場における、海外メーカのシェアは、約5%ほどであり、国内メーカ製
品の価格が上昇した場合でも、海外メーカ⼀品に切り替えないとの応答が⼤多数であった。海外メーカは、国内メーカが生産するような高品質な製品を製造していないため、国内メーカが市場を独占しやすい構造となっている。なお、無方向性電磁鋼板においては、規格が同じであっても、メーカによって微妙な違いが存在するため、メーカの変更が容易でないことから、サーボモータ⽤の無⽅向性電磁鋼板も、サプライチェーンはある程度固定されているものと想定できる。
48
2.減速機 ① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
減速機は、⻭⾞などで動⼒の回転数を落とし、⾼いトルクを得るための機械装置である。構造は⻭⾞と軸、軸受、筐体、潤滑機構で構成されている。動⼒源と機械が必要とする回転数が異なる場合に、回転数を調節するほか、⼩さな動⼒源で⼤きなトルクを得る、⼤きな動きを⼩さな動きに変える、動⼒源が効率よく働けるように速度を変換するなどの役割を持つ。出⼒としては、回転の減速に反⽐例したトルクを得ることができる。 減速機の世界シェア1位から3位は、すべて日本の企業が占めている。1位は、ナブテスコ社(60%、
2016 年)であり、ハーモニック・ドライブ・システムズと住友重機がそれぞれ 15%の世界シェアを持つ。なお、可搬重量10㎏以上の産業用ロボットの減速機市場では、ナブテスコが約8割のシェアを持っており、小型精密減速機市場では、ハーモニック・ドライブ・システムズがシェア70%で、それぞれ世界1位を占めている。 ナブテスコ(2015)によると、ロボット⽤減速機に求められる性能としては、耐衝撃性、⻑寿命、低
振動、⾼剛性、⾼精度、⾼効率などが挙げられ、かつ軽量・コンパクトであることが求められる。この中でも、特に耐衝撃性と⻑寿命は、⽣産設備には⽋かせない要素であり、ロボットアームの誤操作による衝突の衝撃に耐えつつ、寿命が設備償却期限より⻑くなければならず、メーカによっては、寿命の差が 10倍に達することもある。なお、低振動と高剛性は、作業に支障をきたすアーム先端の振動を抑えるために必要な要素技術である。
49
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
小型・精密減速機の市場は、大きくロボット向けと一般産業向けに分けることができる。国内では、一般産業向けでは、日本電産シンポが圧倒的に強みを持っており、住友重機、アッペックスダイナミックスジャパン、ヴィッテンシュタイン(独)、坂⻄精機、加茂精⼯などが続いている。一方、ロボットの関節部に組み込まれる減速機の主要プレイヤーは、ハーモニックドライブシステムズやナブテスコであり、前者は小型、後者は中型に強みを持つ。総合的には、ハーモニックドライブシステムズ、ナブテスコ、日本電産シンポが国内3強と言える。 小型・精密減速機は、LCD製造装置、半導体製造装置、⾃動⾞、印刷機器、⾷品機器、工作機器、医療機器、航空宇宙など、様々な分野で活⽤されているが、産業用ロボット市場拡大の影響を受け、ロボット用減速機の割合は右肩上がりに成⻑し続けると予測される。
減速機の分野別国内市場規模推移と予測
出所:矢野経済研究所推計
50
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
減速機の市場規模は 2016 年時点の出荷台数ベースで、約 50 万台である。減速機の世界シェア1位から3位は、すべて日本の企業が占めており、1位のナブテスコ社(60%、2016年)に続き、ハーモニック・ドライブ・システムズと住友重機がそれぞれ 15%の世界シェアを持つ。なお、可搬重量 10 ㎏以上の産業用ロボットの減速機市場では、ナブテスコが約 8 割のシェアを持っており、小型精密減速機市場では、ハーモニック・ドライブ・システムズがシェア70%で、それぞれ世界1位を占めている。 一方、国際ロボット連盟(IFR)は、2019年までに、産業⽤ロボットの約4割が中国で消費されると
予測しており、中国政府は、2018~2019 年までの⽬標として、減速機を含むロボット⽤アクチュエータの⾃給率を 30%超まで引き上げる計画と発表している。このような影響から、中国の大手減速機メーカであるNANTONG ZHENKANG とShaanxi Qinchuan Machineryは、2018年まで、減速機の年間⽣産台数をそれぞれ 5 万台、6 万台に引き上げると発表した。両社の目標が達成できた場合、中国の減速機市場の⾃給率は30~40%になると予測される。
世界減速機市場シェア(2016年)
51
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
減速機市場は安定成⻑分野であったが、ロボットの需要が世界的に⼤きく⾼まることが⾒込まれていることから、ロボット用を中心に、減速機の需要は右肩上がりに増加していくと想定される。
減速機の国内およびグローバル市場規模推移と予測
出所:矢野経済研究所推計
52
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
⻭⾞技術 減速機において、⻭⾞は、減速⽐とトルク、速度伝達、騒⾳などに直結するため、⾮常に重要な要素
と⾔える。特に、バックラッシは、⾼精度な位置決めに直結するため、⽋かせない性能となっており、バックラッシ調整には⻭⾞技術が⽋かせない。⼀般的なバックラッシ低減技術としては、「⻭厚減少量が⼩さな⻭⾞を、正規の中⼼距離⼜は組⽴距離でセットして使う⽅法」を挙げられる。この⽅法では、バックラッシをゼロにはできないが、全ての種類の⻭⾞に適⽤可能な最もシンプルな⽅法であり、⻭溝の振れの⼩さな⻭⾞を使えば、バックラッシの変動は⼩さくできる。このほか、「中⼼距離調整⽅式」、「組⽴距離調整⽅式」、「⻭⾞を⼆つに分割する⽅法」などで低バックラッシを達成できる。⼀⽅、ゼロバックラッシには、「外⼒により強制的にバックラッシを除去する構造の⻭⾞」や、「ばね⼒などにより2分割した⻭⾞で相⼿⻭⾞の⻭を強く挟んでバックラッシを除去する⽅法」があげられ、油膜切れによる摩耗を防⽌するための、潤滑に注意が必要となる。ナブテスコ、ハーモニックドライブ、住友重機は、それぞれ独⾃の⻭⾞(ペリコロイト⻭⾞、IH⻭型、円弧⻭型)を採⽤することによって、⾼剛性、⾼精度を実現している。 ナブテスコの減速機は、ペリトロコイド⻭形の外⻭⻭⾞が、外側のケースと呼ばれるピンを配置した内⻭
⻭⾞と理論上180°の範囲で常にかみ合っているために、トルク負荷を複数の⻭で分担して受け持つことができる。また、インボリュート⻭形のような⻭元の丈夫さを備えており、これら⼆つの基本構造によって実現された特性により、⾮常に⾼い耐衝撃性を有しつつ⾼剛性であることから、可搬重量 10 キロ以上の大型産業ロボット用減速機として特に適した構造になっている。
ナブテスコの減速機
出所:ナブテスコ
53
振動・騒音制御 ナブテスコは、ロボット作動時の振動を制御するために、ロボットの稼動速度範囲における振動周波数に対して、減速機の持つ固有振動数を二段減速機構を採用することで、ロボットの固有振動数とずらし、振動問題を解決している。ナブテスコ独自の「RV構造」は、開発後も進化を続け、ロボットの組み⽴て性能向上やコンパクト化のために軸受を内蔵し、ケーブルが減速機を貫通することを可能にした中空減速機、CAE解釈(コンピューター⽀援設計)による動解釈により、徹底した軽量、⼩型化を図り、トルク密度の向上にも成功している。
54
ナブテスコの製品ラインナップと概要
出所:ナブテスコより矢野経済研究所作成
ナブテスコの減速機は、1985 年に産業⽤ロボットの衝撃に弱い点や、アームの振動が⼤きいという問題点を解決するために開発された。耐衝撃性を向上させるために、減速機内部の⻭⾞にはペリコロトイド⻭⾞を採⽤している。通常のインボリュート⻭⾞に⽐べて、同時噛み合い数が多いため衝撃に強く、壊れにくいという特徴を持ち、ペリトロコイド⻭⾞の隙間を極限まで減らすことで、⾼精度化を実現している。他社製品と⽐べ、中・⼤サイズの製品に優位を持っており、コンパクトかつ軽量で、出⼒密度は⾼い特徴などから、精密減速機 RV は産業⽤ロボット以外にも、医療、⾷品、半導体といった様々な分野で活⽤されている。2016年には累積⽣産600万台を達成しており、システム化の需要が旺盛な欧州と中国で、精密減速機とサーボモータを一体化した、新型アクチュエータの拡販機会に繋がると想定している。ラインナップとしては、大きく「コンポーネントタイプ」、「ギアヘッドタイプ」、「ギアヘッドタイプ(テーブルモデル)」、コンパクトアクチュエータの「AFシリーズ」の四つに分けられる。
56
株式会社ハーモニックドライブシステムズ(日本)
ハーモニックドライブシステムズは、1964年に同社の前⾝である株式会社⻑⾕川⻭⾞と米USMの技
術提携で、⽇本初の波動⻭⾞装置であるハーモニックドライブの実⽤化に成功。1970 年には両社の合弁により設⽴された。 事業内容は、大きくメカトロニクス製品と精密減速機の2つに分けられ、小型産業用ロボット用の波動
⻭⾞・減速機である「ハーモニックドライブ®」が主⼒製品である。同社の産業⽤ロボットの関節部品は、世界シェア5割を、精密減速機の世界シェアは、約15%を占めている。精密減速機世界トップであるナブテスコ社(シェア 60%)に比べると、小型減速機に強みを持っており、2016 年時点で、ロボット向け小型精密減速機市場においては、70%以上の市場シェアを持つ。2017 年時点で、売り上げの約35%は海外で発⽣しており、地域別に⾒てみると、北⽶が 15.2%、欧州が 6%、その他地域が13.9%となっている。 今後の動向としては、2017年3月から7月にかけて、15億円を投資し、穂⾼⼯場(⻑野県安曇
野市)の設備増強を実施している。これにより、穂⾼⼯場の波動⻭⾞装置ハーモニックドライブの⽉産⽣産能⼒はこれまでの 5 万台から 6 万 6000 台、現在と比べ 32%増加すると想定される。同社は、新興諸国の製造業における⾃動化、省⼒化の投資に加え、先進国でも産業⽤ロボット向けの需要が増加していく中で、半導体製造装置向けも高い水準を維持すると予測しており、精密減速機事業の売上高は右肩上がりに増加していくものと想定している。
ハーモニックドライブシステムズの受注額と売上高の推移
出所:ハーモニックドライブシステムズ
58
同社の減速機は、「ハーモニックドライブ®」、「アキュドライブ®」、「ハーモニックプラネタリ®」の3種に分けられ、全部で 12 個のラインナップに分けられる。ハーモニックドライブ®の最大の特徴は、3 つの基本部品で構成されているため、⼩型軽量化が容易であることである。⻭の噛み合い数が多く、噛み合い部分に隙間がないため、より⼤きなトルク、正確な位置決めが可能であり、独⾃の⻭型理論より⽣まれた IH⻭型の開発により、⻭底の曲げ応⼒と、⻭⾯荷重による⻭元応⼒を減少させ、製品の強度や性能を⾼めている。アキュアドライブ®とハーモニックプラネタリ®は、ハーモニックドライブ®の精密加工技術を、低減速比(1/3〜1/45)に⽣かした⾼精度・⾼剛性の遊星減速機であり、独⾃のバックラッシ除去機構により⾼い回転精度を実現している。
ハーモニックドライブシステムズの製品ラインナップと概要
出所:ハーモニックドライブシステムズより矢野経済研究所作成
ハーモニックプラネタリ®HPFシリーズの仕様
出所:ハーモニックドライブシステムズ
59
住友重機械工業株式会社(日本)
住友重機は、1934年設⽴の総合重機械メーカである。重⼯企業の中でもメカトロ分野に特に強み
を持っており、変減速機、プラスチック加⼯機械、医療機器(PET 診断用サイクロトロン、MRI 用極低温冷凍機では、国内シェア1位を占める。同社の事業領域は、⽣産関連およびインフラ関連から最先端技術分野まで 5 つのカテゴリーに分けられる。減速機の世界シェアは、ハーモニックドライブシステム社とほぼ同等の約15%であり、国内シェアでは1位を占めている。 変減速機事業では、ベルギーのハンセン社との提携で、グローバル共通製品となる⻭⾞減速機の開
発を進めており、2016 年には業界トップクラスのコンパクト性を備えた、⾼精度遊星減速機「IB シリーズ」のラインナップを拡充している。 減速機を含む機械コンポーネント事業の売り上げは、全体の 15.4% を占める。同事業部の実績は、
12年以降連続増加傾向にあり、売り上げの成⻑に伴い、営業利益の伸びも著しい。
機械コンポーネント事業の売上⾼と営業利益の推移
出所:住友重機
60
同社の減速機は、「サイクロ®減速機」、「IBシリーズ」、「精密制御用サイクロ®減速機(A、D、C、T、UA)」の3つのラインナップに分けられる。 サイクロ減速機の⻭⾞である「曲線板」は、⼀般的なインボリュートギヤと異なり、独⾃の滑らかな曲線
(エピトロコイド平⾏曲線)を持っており、かつ内⻭⾞にも独⾃の円弧⻭型を採⽤し、⻭の折損がない滑らかな転がり接触によって、耐衝撃性に優れたタフで⻑寿命な減速機を実現している。 「IB シリーズ」は、P1 と P2 の 2 つのラインナップに分かれており、共通点として、業界トップクラスのコン
パクト性、⾼剛性、⾼精度を特徴とする。内⻭⾞付きケースの採⽤により、コンパクト・⾼剛性を実現し、出⼒軸⽀持に⼤径精密アンギュラ軸受を採用し、コンパクトなケーシングで大きなラジアル荷重が受けられる。P2シリーズには、ヘリカルギヤを採用し、高い静粛性を実現している。 精密制御用サイクロ®減速機は、⾼精度位置決め⽤コンポーネントタイプのサイクロ減速機であり、位
置決め用のコンパクトタイプである。5 つのラインナップにわけられ、仕様や軸のオプションによってスペックが異なる特徴を持つ。
住友重機の製品ラインナップと概要
出所:住友重機より矢野経済研究所作成
61
日本電産シンポ株式会社(日本)
1952年に設⽴された⽇本電産シンポは、駆動機器、プレス機器、計測機器、⼯芸機器の4つの事
業を展開しており、減速機事業は駆動機器部門に含まれている。減速機のラインナップは、用途に応じて大きく5つに分けられ、2015年からロボット⽤の減速機のラインナップが追加されている。ロボット⽤の減速機は、小型用の精密制御用減速機「フレックスウェーブ WP シリーズ」と、中・大型用向けの「コロネット減速機ERシリーズ」の2 つに分けられる。 フレックスウェーブ WP シリーズは、同社が初めて開発したロボット用の減速機シリーズであり、ロボットの
関節に最適な⼩型・軽量・⾼精度の波動⻭⾞減速機である。構成部品が少なく、薄いため業界トップレベルの軽さを同時に実現しており、微細⻭形を採⽤することにより、バックラッシを低減している。 コロネックス減速機は、独⾃の精密制御遊星⻭⾞機構と独⾃の単純円弧(サークリュート)⻭形を
進化させた、「内接式遊星⻭⾞機構」を採⽤しており、⾼剛性を持つ。サークリュート⻭形は、摩擦損耗の極度に少ない⻑寿命⻭形であり、⻭形のピッチエラーは数ミクロンという世界最⾼⽔準の精度を達成、90%を超える⾼効率性と、省電⼒で⾼い経済性を持つ。なお、コロネックス減速機には、トルクリミッタがついており、過負荷時には⾃動的にモートル電流を遮断し、機械装置を停⽌させるため、安全な無⼈運転が可能となる。
日本電産シンポの製品ラインナップと概要
出所:日本電産シンポより矢野経済研究所作成
62
加茂精工株式会社 (日本)
1977 年設⽴の加茂精⼯は、減速機の分野で、初めて⻭⾞を使わずに、スチールボールを⽤いて駆動する「ボール減速機」を 1987 年に開発した。ノンバックラッシのボール減速機は世界初であり、ラインナップとしては、「JFRシリーズ」、「BREシリーズ」、「BRシリーズ」、「BBRシリーズ」、「CBRシリーズ」の5つがある。 構造としては、内外⻭⾞による差動⻭⾞機構の⼀種に類し、⻭⾞の⻭部による動⼒伝達とは異なり、
ボールの電動を介して動⼒を伝えるため、摩擦が少なく、ほとんどのボールが動⼒伝達に関与しているため、⼩型でも伝達容量が⼤きい。なお、⻭⾞を使⽤しないため、⻭打ち⾳が無く、静粛性が評価され、取り付けモータを選ばず、どのようなモデルでも対応できる⻑所を持つ。
ボール減速機の仕組み
出所:加茂精工株式会社
63
⑦ 各国の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等か
らランキング。上位5位程度まで列記)
Nantong Zhenkang Machinery Co, Ltd. (中国)
Nantong Zhenkang 社は、サブマージ溶接トラクター、溶接ワイヤーなどといった溶接装置事業をメ
イン事業として 2002 年に設⽴され、当分野では中国シェア 7 割を占めている。そのほか、RV ギヤー減速機事業も展開しており、2016 年時点では、約 12,000 台を出荷し、出荷台数ベースで世界シェア2.4%を占めている。中国政府が、今後産業用ロボットに使用されるサーボモータ、減速機、コントロールパネルの⾃給率を3割まで引き上げたいと発表したことから、同社は、2018年までに年間⽣産台数を5万台以上としていく方針である。 同社の RV ギヤー減速機は、「RV-E 」、「RV-C」、「RD」の 3 つのラインナップに分けられる。表に、
Nantong Zhenkangの製品ラインナップと概要を表す。
Nantong Zhenkangの製品ラインナップと概要
出所:Nantong Zhenkang より矢野経済研究所作成
64
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
ロボット用の減速機に関する論⽂を発表している研究者及び所属機関は、以下の通り。
国内のロボット用減速機の研究者及び所属機関
出所:KAKENより矢野経済研究所作成
65
⑩ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者/所属機関
※米国、欧州、韓国に関しては、サーボモータの章に掲載。
③ 中国 国家⾃然科学基⾦委員会でのプロジェクト検索結果により、中国の研究機関及び減速機メーカを特
定した。
中国の研究機関及び減速機メーカ
出所:NSFC(国家⾃然科学基⾦委員会)より矢野経済研究所作成
⑤ 台湾
文献調査レベルでは、ロボット用のアクチュエータを専門とする研究者及び研究機関はみつからなかったが、メーカは⼦申応⽤材料有限公司、台湾精鋭科技股份有限公司、世協電機股份有限公司の3社がある。
研究機関 メーカ
大連交通大学重慶大学機械伝動国家重点実験室
ハルビン工業大学北京理⼯⼤学
⻄安微電機研究所
份蘇州緑的谐波伝動科技有限公司秦川機床工具集団股份公司南通振康焊接電機有限公司
浙江恒豊泰減速機製造有限公司浙江双環伝動機械股份有限公司
巨輪股份有限公司天津百利天星伝動有限公司武漢精華減速機製造有限公司
大族激光科技産業集団股份有限公司上海⼒克精密機械有限公司
寧波中⼤⼒徳知能伝動股份有限公司山東帥克機械製造股份有限公司北京中技克美谐波伝動有限公司北京谐波伝動技術研究所
江蘇泰隆集団安徽聚隆機器人減速器有限公司
66
⑪ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
ロボット用アクチュエータに関連するプロジェクトを調べたところ、サーボモータと減速機を厳密に分けて研究している状況ではなかったので、調査結果はサーボモータの章にまとめた。
67
⑫ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
① 米国 各省の⽀出データ(Contract, Grant, Sub-Contract)をまとめているFederal Reporterや、
USASPENDING.gov を⽤い、サーボモータや減速機関連プロジェクトの抽出を⾏ったが、減速機関連は現在化道中のプロジェクトが⾒当たらなかった。 ② 欧州
欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)を対象に減速機の研究開発プロジェクトを調査した。2014年1月よりスタートしたフレームプログラム「HORIZON2020 」における、減速機関連のプロジェクトは以下の通りである。
出所:Cordis
SMARTGEARBOX
Development of a new gearbox withoutlubricants for low OM costs, higherefficiency, and oiless applications
期間 2014.11〜2017.12
資⾦拠出元 H2020-EU.2.1.2H2020-EU.2.3.1
予算⾦額(EUR) 153,041,875
EU拠出額(EUR) 107,129,313
参加機関
KISSSoft AG(スイス)、Studio TecnicoZocca(イタリア)、Cattini Srl(イタリア)、The Department of Engineering of FerraraUniversity(イタリア)、TEC Eurolab(イタリア)
プロジェクト内容イタリアの減速機メーカであるVARVEL社をコーディネータとし、潤滑油を必要としない⾰新的なギヤー材料及び冷却システムを開発。
プロジェクト名
68
③ 中国 中国政府は、減速機の技術的要素、⽣産能⼒、⾃動化などを⽬標に、開発プロジェクトを推進して
いる。
出所:NSFC(国家⾃然科学基⾦委員会)より矢野経済研究所作成
④ 韓国
韓国のロボット用のアクチュエータ関連プロジェクトに関しては、サーボモータの章に一緒にまとめてある。 ⑤ 台湾
⽂献調査レベルでは、減速機関連のプロジェクトは⾒つからなかった。
プロジェクト名
⼯信部「2016年知能製造総合標準化及び新モデル応用項目」ー産業用ロボット向け減速機工場のデジタル化
⼯信部「2015年知能製造専項」ー産業⽤ロボット⾼精度減速知能製造建設プロジェクト
国家高技術研究発展計画(863計画)ーロボット用RV減速機の研究·製造及び応用に関する研究
NSFC⻘年科学基⾦プロジェクトー産業⽤ロボット向け減速機の熱-流体-構造連成解析機能による非線形振動に関する研究
期間 2016.6⼊選、実施期間3年 2015 6入選 2015.6⼊選、実施期間3年 2017.1~2019.12
資⾦拠出元 財政部 財政部 科技部 NSFC (国家⾃然科学基⾦委員会)
予算⾦額 3.02億元 2.71億元 823万元 20万元
参加機関
秦川機床工具集団股份公司 浙江双環伝動機械股份有限公司 浙江双環伝動機械股份有限公司 大連交通大学 宋雪萍
プロジェクト目標
減速機のデジタル化と精密化生産を実現する。 産業⽤ロボット向け⾼精度減速機の設計、⽣産、検査、応用などの分野で知能自動化を実現する。年間6万台の⾼精度減速機の⽣産能⼒を有する。
国産ロボット用コア部品の設計、生産、検査、応用などの分野における技術的難関をブレークスルーする。
不明
69
⑬ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
潤滑法 減速機を構成する重要な要素のひとつとして潤滑法が挙げられ、潤滑剤は、⼤きくグリースと、油潤滑
剤の 2 種類に分けられる。ロボット用減速機の潤滑剤に求められる性能は、⾼⾯厚、起動時から⾼速域まで、広い温度範囲において、⾼効率や⻑寿命、耐漏れ性、低騒⾳など多岐にわたり、これらの多くは排反事象であるためバランスを保つことが難しく、ロボット⽤減速機に最適した潤滑剤は数少ない。 ⼀⽅、潤滑⽅式は、⼤きく全損式と、回収式に分けられ、減速機の機種、形式、仕様などに応じて、
それぞれに適した潤滑⽅式が採⽤されている。なお、⽅式によって減速機の寿命や、特徴などに差がみられる。基本的にはグリース潤滑は、速度、温度などの極端な条件には不向きであり、また冷却機能や洗浄機能はあまり期待できない。一方、ハウジング設計の容易さや、メンテナンスフリーなどの点では油潤滑に勝る点があり、条件によっては最適解になり得るものである。
油潤滑とグリース潤滑の⽐較
出所:潤滑通信社
対象 油潤滑 グリース潤滑
温度
油温90℃まで。軸受温度200℃まで。ただし,特殊な潤滑油であればさらに⾼温まで使用可能
一般に120℃以下。200/220℃まで使用できるが,取替え周期が短くなる
速度ファクタ(DN) 45〜50万まで 30〜35万まで荷重 あらゆる荷重に対応 中荷重
軸受タイプ あらゆるタイプに対応 スフェリカルローラスラスト軸受には不適
ハウジング設計 複雑なシールと給油装置が必要
比較的簡単
⻑時間メンテナンスフリー運転 不可能 運転条件特に温度にもよるが可能
他の機械要素との兼用 可能 不可能
トルク 循環給油,オイルミストの時,トルクは最も小さい
適当な充填量のときはオイルより小さい
ダスト雰囲気 ろ過装置を付ければ可能 コンタミ防止の特殊設計必要
70
油潤滑⽅式の種類と特徴
出所:潤滑通信社
分類 種類 適用範囲 特徴 備考
手差し
低・中速、低荷重(間歇運転される機械の軸受,摺動部,開放⻭⾞,チェーンなど)
装置が簡単であるが,頻繁給油が必要。ごみの侵入に注意。 安値
滴下 低・中荷重の軸受⼿差しに⽐べて⼈⼿が省け信頼性が⾼い。油量調整可能。温度,油⾯⾼さにより給油量が変化する。
灯心 低・中荷重の軸受給油量は灯⼼の数で調整。温度,油⾯の⾼さ,油の粘度により給油量が変化する。
安値
機⼒ 高速・高荷重シリンダー,摺動面,プレスの軸受
⾼圧で適量を正確に給油できる。⼤量の給油はできない。数⼗箇所まで集中給油可能。
設備費高価
集中(グリース) 低・中速,中荷重 集中化,自動化可能 設備費高価噴霧(オイルミスト)高速ころがり軸受 集中化,自動化可能 保全費高い
エアーオイル 工作機械用精密軸受,⾼速⾼精度スピンドル
工作機械用精密軸受,⾼速⾼精度スピンドル 集中化,自動化可能。常に新鮮な油を必要微⼩量供給可能。クーリング効果
油浴 低中⾼速軸受,⻭⾞多少の冷却効果が期待できる。油⾯変動により給油量,冷却効果が違う。油⾯管理が⼤切
メンテナンスフリー
飛まつ中小型減速機,中⼩型往復動圧縮機,内燃機関
多少の冷却効果が期待できる。低速または超⾼速に不適 メンテナンスフリー
パッド
中速,低・中荷重,鉄道⾞両,クレーンの⾞軸軸受,ドラム軸受
給油の煩雑さが避けられる。目詰まりに要注意。 安値
リング・ディスク 中速,低・中・高荷重,電動機,遠心ポンプ軸受
かなりの冷却効果。低速回転や⾼粘度油の使用には注意。縦軸には不適。
メンテナンスフリー
循環 大型機械設備用(高速,高温,高荷重)
給油量,給油温度,給油圧⼒の調整が細かく出来き,信頼性が高い。冷却効果⼤
高価
全損式
回収式
71
潤滑剤は、周辺温度、減速機の回転数などをべースに、粘度と銘柄が決められ、メーカと機種によって、使われている潤滑剤の仕様に差が⾒られる。⼀⽅、各メーカは、潤滑剤メーカとのすりあわせにより、各社製品に適合した独⾃の潤滑剤を開発していることが多く、潤滑剤メーカの優位を特定することは難しい。 ナブテスコの潤滑剤は、減速機本体各部品の様々な設計仕様との相関が⾼く、すりあわせ技術によっ
てのみ達成できる性能であるとし、潤滑剤メーカと共同で、ロボット⽤減速機に最適な専⽤グリースを開発し、製品と組み合わせることで、性能を保証する独⾃の仕組みをとっている。潤滑剤のラインナップとしては、低温回転性に優れた「RV グリース」、潤滑性能と潤滑剤交換性を両⽴させた「RV オイル」、RV減速機に最適した「VIGOグリース」の3種類がある。 住友重機は、グリース潤滑(メンテナンスフリー機種を含む)と油潤滑機種を揃えており、メンテナンスフリ
ー製品の場合、4~5 年が、⼀般のグリース機種では 3~6 ヶ⽉に⼀度交換が必要となる。油潤滑⽅式は半年から⼀年以内が寿命となる。 ハーモニックドライブシステムズは、ハーモニックドライブ⽤に⾃社で開発した潤滑剤を使⽤することを推
奨しており、標準指定潤滑オイルとしては、「⼯業⽤ギヤ油2種(極圧)ISO VG68」を指定している。
ハーモニックドライブ専用グリースの仕様
出所:ハーモニックドライブシステムズ
72
ハーモニックドライブの波動⻭⾞は、その構造から、⼩型化と軽量化で優位を持つ。通常の減速機では、モータなどの動⼒を必要な速度に落とすと同時に回転⼒を上げるという、本来の機能をするために、多くの部品を必要とする。しかし、波動⻭⾞減速機は、基本部品 3 点を入れ子のように組み合わせていくため、⼩型化(直径サイズ20ミリ以下)と省スペースを同時に実現していることから、可搬重量10キロ以下の小型産業用ロボット市場をほぼ独占している。一方、同社が持つ波動⻭⾞の構造原理に対する特許は既に切れているが、⽣産技術での参⼊障壁が⾼いため、波動⻭⾞減速機を量産できる世界で唯⼀のメーカとして⻑期にわたって市場を独占している。波動⻭⾞減速機の⽣産⽅法は、極めて⼿間がかかるものであり、噛み合わせる内⻭に、あえて⾦属のたわみを⽣み出すために弾性体を使⽤していることもあり、ミクロン、サブミクロン単位の精度を要求される⻭切りなどの加⼯プロセスは定量化することが難しい。単純に⼯作機械をプログラミングするだけではこの精度は出せないため、加⼯の度に誤差を測定し、補正をするという作業が必要であり、部品同⼠の噛み合わせを調整する最終組⽴⼯程は、⼿の感触で⻭⾞の削り位置を微妙に変える作業となる。この生産方法では、技術やノウハウといった暗黙知が極めて重要であるとしている。
ハーモニックドライブの構造
出所:ハーモニックドライブ
73
住友重機のサイクロ減速機の⻭⾞である「曲線板」は、⼀般的なインボリュートギヤと異なり、独⾃の滑らかな曲線(エピトロコイド平⾏曲線)を持っており、かつ内⻭⾞にも独⾃の円弧⻭型を採⽤し、⻭の折損がない滑らかな転がり接触によって、耐衝撃性に優れたタフで⻑寿命な減速機を実現している。サイクロ減速機は、トロコイド系曲線⻭形を持つ1枚、もしくは 2枚⻭数差の内接式遊⻭⾞機構と、円弧⻭形を持つ等速内⻭⾞機構を組み合わせ、円弧⻭形にローラを装着しており、ローラによって滑り接触に変換されるので、機械的損失を抑え、極めて高いギヤ効率が得られる。
サイクロ減速機の構造
出所:住友重機
⻭⾞の⻭形は、⼤きく「インボリュート⻭形」と「サイクロイド⻭形」があり、動⼒伝達⽤途では、⻭の噛
み合いがスムーズなため、⻭に負担が少なく、剛性の強いインボリュート⻭形が⼀般的に使⽤されている。 ⻭⾞の強度を決定する上では、精度と素材が重要な要素となる。⻭形や⻭スジ、ピッチなどの誤差を
押さえ、精度を⾼めていくことで、⻭⾞の不具合の発⽣を抑制し、ノイズを減少させられる。素材の選定においては、強度や市場の流通量などの理由から「S45C」という炭素鋼や、「SCM415」という合⾦鋼が多く⽤いられている。これらの素材は、熱処理を通して強度を上げることも可能である。
⻭⾞の不具合として発⽣する問題
出所:岡本工機株式会社
損傷 素材の疲労限度以上の曲げ応⼒が⻭に繰り返し加わった時に⽣じる⻲裂のこと。特に疲労折損は設計不良、過負荷等が原因で発⽣。
磨耗 ⻭形の多くがインボリュート曲線であるため、⻭の噛合いは滑りを伴う転がり接触であり、⻭⾯間の潤滑油膜が不⾜すると、⻭⾯の磨耗が発⽣。
⻭⾯疲労 ⻭⾯に繰り返し負荷が加わることで、⻭の表⾯下材料が疲労を起こすことで起こる損傷。
熱的損傷 ⻭⾯の摩擦等による発熱が原因で⽣じる温度上昇により⻭⾯が受ける損傷のこと。⻭⾞の⾼速化も⼤きな要因のひとつ。
74
⑭ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
⻭⾞加⼯機 減速機のコア部品である⻭⾞の精度に直結しているのは、⻭⾞⼯作機の性能である。⻭⾞⼯作機の
国内シェア1位は三菱重⼯が占めており、同社は、世界シェアにおいても 1,2 位を競っている(2016)。一方、⻭⾞加⼯において⾼いシェアを持つ、(株)神崎高級工機製作所、(株)不⼆越、(株)カシフジの3社は、2002 年から、⻭⾞加⼯分野の機械・⼯具事業において、包括提携GPA(Gear Production Alliance)を結んでいる。 カシフジは、⻭⾞加⼯機であるホブ盤において、現時点で国内シェア1位を占めており、⾃動⾞⽤ホブ
盤においては国内シェア 50%で1位を占めている。同社は製品の強みとして、加工時間の短縮、ミクロン単位の精度、耐熱性や、耐震性などを挙げており、業界初の完全ドライホブ盤加⼯や、ハードホビングにも対応している特徴がある。納入先としては、ジェイテクト、ナブテスコ、ハーモニックドライブ、日本電産、三菱電機、住友重機、パナソニックなどがある。(株)神崎⾼級⼯機製作所は、ギヤシェービング(⻭⾞の仕上げ)では、国内シェアの8割以上を占めており、シェービング盤、ホーニング盤など、⻭⾞の⾼精度仕上げ機械分野で強みを持っている。(株)不⼆越は、精密⻭⾞加⼯⼯具、ブローチ・ブローチ盤で、世界シェア25%、国内シェア90%を持つ。 3 社は、2016 年に合同で⻭⾞加⼯機を開発しており、GPA の取り組みの成果として、機械と工具
(ホブ)のコラボレーションにより、中型モジュールでハイス材ホブを多口化し、荒・仕上げ加工ともに従来の領域を超える加⼯を実現したと発表している。図にGPA(Gear Production Alliance)の概要と、⻭⾞加⼯⼯程と機械・⼯具の対応例を表す。
GPA(Gear Production Alliance)の概要
出所:カシフジ
75
⻭⾞加⼯⼯程と機械・⼯具の対応例
出所:不⼆越
一方、ナガセインテグレックスは、ナノ単位の超精密研削盤や微細加工機など、各種工作機器の分野で強みを持つ。製品は、大きく、カタログに載せている「汎用機」と、カスタマイズする「専用機」の 2 種類に分けられ、温度や湿度、振動などの使⽤環境を考慮した最適な設計がベースとなっている。同社は、数多くの要素技術を保有しており、これらを組み合わせることによって、ミクロン・サブミクロン単位の超⾼精度を達成している。
76
3.ロボット用ケーブル市場の現状
概要 ロボット用ケーブルとは、主に産業用ロボットや、工作機械などの内部配線に使用される電線であり、通称「FA ケーブル」とも称される。⽤途としては動⼒供給⽤と通信制御⽤に分けられ、中には両機能が1本になっているものもある。基本的な構造としては、導体と、その周りを包む絶縁体、さらにその周りを包むシースからなっている。絶縁の被覆材料の素材は、フッ素系、PVC(ビニール)系などがあり、高速転送を⾏う通信においては、ノイズ防⽌のため、シールドを施す場合もある。ロボット⽤ケーブルに求められている機能は様々であり、移動の速度に合わせられる「移動特性(低速用・高速用)」、使用環境に対応できる「耐薬品性・耐油性・耐熱性」、機器の動きに対応できる「耐屈曲性・耐捻回性」などが代表的である。ロボット⽤ケーブルは、使⽤される場所・部位により、要求される特性が異なる。 国内大手メーカとしては、大電株式会社、沖電線株式会社、太陽ケーブルテック(株)などが挙げられ、海外大手メーカでは、SAB Brockskes、LEONI、IGUSなどが代表的である。
産業用ロボットに使用される電線・ケーブルの種類 A 旋回部、あるいは手首部などの過酷な屈曲、捩れなどが加わる場所にしようされる超耐屈曲
ケーブル、あるいはスプリングケーブル。 B 一般関節部など、A に⽐べ、頻度や条件が緩い場所に使⽤される耐屈曲ケーブル。 C ティーチングボックス用のリード線で、ハンドリングで使用されるため、
可とう性(容易に曲げることができる性質)が要求されるケーブル。 D ロボット本体とコントロールユニットとの機器間連絡ケーブルで、使用方法には固定配線と移動
配線とがある。 E コントロールユニット内などの機器内固定配線用電線ケーブル。
出所:⽇⽴⾦属より⽮野経済研究所作成
78
ロボット⽤ケーブルの⽤途例
出所:⽇⽴⾦属
大電株式会社 (日本)
1951 年設⽴の⼤電株式会社は、電線・ケーブル事業及び、FA・産業機器の製造・販売を主な事業内容としており、2016年時点では、ロボットケーブル業界シェア40%で、国内1位を占めている。ロボット稼動用ケーブルのラインナップは、用途や素材、性能などに応じて、「稼動用ケーブル(16 シリーズ)」、「固定配線用ケーブル(1 シリーズ)」、「ネットワーク用ケーブル(12 シリーズ)」、「各種オプション(3 シリーズ)」、「ロボトップシリーズ(1シリーズ)」に分けられ、同社の推奨条件下では、屈曲寿命2000万回以上を達成できる。 ケーブル素材には、耐屈曲性、ハーネス加工性などを総合的に判断し、80ミクロン軟銅線を標準に採
用しているが、使用条件によっては、50 ミクロン導体、合⾦導体、⾼張⼒繊維⼊り導体などにカスタム製作することも可能である。シールドに関しては、錫メッキ軟銅線編祖シールドを標準としており、耐屈曲シールド、横巻きシールド、⾦属テープシールドなどのオプションも選択できる。シースは、難燃・耐油 PVC シースを標準としており、ポリウレタン、滑性PVC、耐寒性シース(ポリエステルエラストマー)にも変えられる。なお、絶縁材としては、硬く滑りが良い ETFE、架橋ポリエチレンを採用しており、断線防止技術として、50・80 ミクロンの極細線を使うことで、素線断線を防⽌し、素線を数⼗本ひねり合わせ、更にその束を3・7個ひねりにすることで断線を防止している。 関係者の取材によると、同社の主な取引先は、安川電機であり、国内シェア 4 割を占める強みとして
は、顧客のニーズに合わせてカスタマイズできる多様なラインナップを挙げられる。
79
沖電線株式会社
沖電線株式会社は、1936 年に設⽴され、電線事業、FPC(フレキシブル基板)事業、電極線事業、及び不動産賃貸事業を展開している。大電株式会社によると、沖電線は現時点で国内シェア2位を占めており、ファナックにCNC用ケーブルを含めたロボット用ケーブルを納入しているものと想定される。 ロボット用ケーブルのラインナップとしては、大きく「屈曲対応ケーブル」、「固定部対応ケーブル」、「摺動
対応ケーブル」、「捻回対応ケーブル」、「サーボモータ⽤ケーブル」の 5 つに分けられる。絶縁材料に独⾃開発の特殊エラストマーを採用することにより、低価格かつ、優れた可動性(屈曲性能2000万回以上)を達成し、最大で600Vまでの電圧に対応できる特徴を持つ。
80
太陽ケーブルテック(株)
1923 年設⽴の太陽ケーブルテックは、国内外に⽣産拠点を持ち、ロボット⽤ケーブルの他、インターフェイス用のケーブル、ネットワークケーブル、テフロン絶縁電線、ケーブル加工品、及び床暖房システムまで、広範囲なケーブル事業を展開している。主要な取引先としては、三菱電機、鶴⾒製作所、泉州電業、安川電機、森精機製作所、オリンパスなどが公表されている。 同社は、特許技術を応⽤し、合⾦素線と軟銅素線をコンポジットするという独⾃の製造法により、細
いが、曲げや引張に強いケーブルを開発、ケーブルベア試験で2千万回超の高屈曲性能を達成している。ロボット用ケーブルのラインナップは、大きくタ関節用の「EXT-3D シリーズ」、「EXT-PREM シリーズ」と、ケーブルベア用の「TBFシリーズ」、「EXT-01Gシリーズ」、「EXT-Ⅱシリーズ」に分けられる。多関節用は、絶縁体に高弾性TPE樹脂、絶縁体にETFE(フッ素)を採用することにより、3次元移動での高寿命と、高い移動屈曲特性を実現している。ケーブルベア用は、中低速と高速可動部でラインナップが分かれており、シースと絶縁体に特殊極細導体、高耐油性 PVC などを採用し、柔軟性や耐油性、耐熱性に優れている。
太陽ケーブルテックの製品ラインナップと概要
出所:太陽ケーブルテック(株)
81
IGUS(ドイツ)
IGUS は、1964 年にポリマー部品のサプライヤーとして設⽴され、1983 年からは、エナジーチェーンシ
ステム及び射出成形ポリマーベアリング事業を展開している。本社のドイツ以外に、35カ国に子会社や事業拠点を持っている。 ロボット用ケーブルとしては、「chainflex®シリーズ(10 種)」があり、グローバルでは 10万本、日本に
は 3 万本以上の在庫を備えている。ロボットケーブルシリーズには、3 次元動作や、ねじれ応⼒による負荷を吸収するため、異なる「軟」材質(レーヨンファイバー、PTFE 物質、充填材)を使用している。なお、ねじれ動作を伴うケーブルには、編組シールドに特別な負荷がかかるため、PTFE 混合材を使ったフィルムを採用することにより、ねじれに最適なシールド構造を作っている。外被には、耐摩耗性、ハロゲンフリー、難燃性に優れ発⽣しうる損傷から撚り構造を保護する機能を持つ「PUR 混合材」と、耐摩耗性、ハロゲンフリーで、光ファイバーケーブルや単芯ケーブルに求められる条件を満たし、かつ撚り構造を保護する「TPE(熱可塑性エラストマー)」を採用している。 同社は、ねじれ応⼒や3D動作などによる負荷に対する耐久性テストである、「イグス基準」を策定しており、この基準では3D動作用ケーブル保護管「トライフレックスR」に入れた状態で、少なくても1mあたり±180°のねじれ動作300万回の試験をクリアすることを条件としている。なお、チェーン⻑さ約2500mm の試験では、産業用ロボット等で頻繁に発生する⾼負荷(遠⼼⼒や⼤きな衝撃)下での使用において、270°のねじれ動作のクリアを条件としている。 SAB Bröckskes GmbH & Co. KG(ドイツ) SAB Bröckskesは、1947年に設⽴された、ケーブル⼤⼿である。同社は、世界13カ国に拠点を持ち、温度計、ケーブルハーネス、インダストリアルケーブルの 4 つの事業を展開している。同社資料によると、KUKA、ABB、Cloos、Motoman、Reis、b&m などのロボットメーカに製品を供給しており、年間1500 回以上カスタムケーブルを受注している。製品のラインナップとしては、用途によって 6 シリーズに分かれており、使用環境に応じて、素材やその他スペックをカスタマイズしている。 Leoni(ドイツ) Leoni は、1917 年に設⽴された、世界的なケーブル⼤⼿であり、世界 31 カ国に拠点を持つ。主に
⾃動⾞⽤のケーブル分野に強みを持っており、売り上げの 7 割は欧州、アジアは 14.8%を構成している。ロボット用ケーブルのラインナップとしては、現時点の在庫状況ベースで 63 種があり、カスタムでの製作も可能である。カスタム製作に関しては、要求される性能や仕様環境に合わせた素材を選択することができる。同社は、「両振り曲げ試験」、「屈曲寿命試験」、「ねじり試験」の 3 段階を通して品質を保障している。
82
4.中国のロボット産業発展計画(2016〜2020年)
中国のロボット市場概要 中国における産業ロボット出荷台数は、2011年から急増しており、2014年には、世界全体の25%
(7.5 万台)に達している。しかし、旺盛な需要に⽐べ、ロボットの⽣産量は、2015 年時点で約 3.3万台⽔準に留まっており、ロボットの利⽤密度は、世界平均を⼤きく下回っている(30 台/万人)。一方、安価な労働⼒への依存から脱却し、国内の製造業を⾼度化して国外への流失を防ぐことを⽬的として、中国政府は、2012 年以降ロボット産業の発展を後押しする政策を多数制定している。2015 年5⽉には、「中国製造2025」という中国版のインダストリー4.0戦略を公表し、その中でも重点推進の10大産業の第2分野として「高機能NC工作機械とロボット」産業の発展推進を挙げた。 2016年3月には、「ロボット産業発展計画(2016〜2020年)を公布し、ロボット産業発展の5
ヶ年計画全体⽬標及びロボット産業体系を形成する⽅針を⽰し、各地方政府も様々な産業用ロボットの発展促進施策を打ち出している。これらの計画の多くは、ハイテク化、自動化、ハイエンド化を目指す知能設備製造及び関連部品・主要素材の産業発展の促進を目的としている。 これら政策の影響を受け、中国では、2015年末時点で、1,026社のロボット関連企業が登場してい
る。最も多いのは、システムインテグレーダと言われるが、ロボット本体の製造にも約400社が参入しており、Siasun、GSK、Efort、Estun などが代表的である。中国市場における産業用ロボットメーカの国籍別シェアを⾒てみると、外資系ロボットメーカ主導の市場となっており、2011 年から 2014 年まで年平均54.5%のシェアを維持している。企業別シェアでは、ファナック、安川電気、KUKA、ABB の 4 社で約 6割を、中資系は8%を占めている。なお、KUKAは2016年8月、中国美的集団に買収されている。 産業用ロボット国籍別シェア推移 2015年中国産業用ロボットの企業別シェア
出所: FNA「中国産業用ロボット市場調査総覧」、
CRIA
84
中資系メーカの現状 中国ロボット産業連盟によると、中国の2015年のロボット⾃製率は35%程度であるが、2020年に
は政府目標である50%を超えると⾒込まれている。2012年時点で、中国のロボット技術は、⽇本の約7割を達成しているとされ、その差は主に基幹部品の質にある。国家政策の後押しにより、中資系ロボットメーカの規模はますます拡大しているが、基幹部品技術の欠如により生産コストが高く、企業の収益⼒は劣っている。 三大基幹部品である減速機、サーボモータ、コントローラの合計コストはロボット完成品の 7 割以上を
占めており、内製した場合に比べ、減速機は約4倍、サーボモータは2倍のコストがかかる。中国のロボットメーカは、精密減速機の約 75%をナブテスコやハーモニックドライブに頼っており、サーボモータは日本から50%、欧州、アメリカ、台湾から30%を輸入している(2017年時点)。 一方、外資系ロボットメーカは、中国の産業用ロボット需要の 7 割を占める多関節ロボット市場で圧
倒的なシェアを有し、基幹部品の一部を内製化することでノウハウを蓄積しているため、技術面でも中資系メーカを⼤きく上回っている。中資系ロボットメーカは、基幹部品の調達を外資系サプライヤーに⻑期間依存しているため、現状として、低価格攻勢を仕掛ける余地は限られている。
三大基幹部品の輸入状況
85
ロボット製品のコスト構造と中資系ロボット製品の低価格化余地
出所:FNA「中国産業用ロボット市場調査総覧」
中国内主要メーカの基幹部品の内製状況
出所:各社IR資料より⽮野経研究所作成
基幹部品 減速機 サーボモータ 制御装置ファナック ‐ ◎ ◎安川電機 ‐ ◎ ◎ABB ‐ ◎ ◎KUKA ‐ ‐ ◎瀋陽新松 ‐ ‐ ○広州数控設備 ○ ○ ○〜◎
主要外部調達先 ナブテスコ、ハーモニックドライブ
安川電機、ファナック、三洋電機、多摩川精機
ファナック
備考中資サプライヤーの製品は国際的に品質水準に満たない
ファナックと安川電機のサーボモータは、世界の4割を占めてい
る。
ファナックの数値制御装置における世界シェアは5割超広州数控設備は中資最大手だが、技術⼒では外資系メーカとして依然として差がある。
注)当該部品の技術を把握しており、一定の市場シェアを有するメーカは◎。当該部品を内製しているが、技術水準が不明なメーカは○。
86
減速機
中国の産業用ロボット用減速機市場規推移
出所:Research in China 中国の減速機市場は、2017年時点で、約595億円規模である。中国では、2017年時点で、上場・非上場を含め総 13 社が減速機を開発・製造しており、このうち 5 社は RV減速機に重点を置く。⼤抵は量産化する段階には⾄っておらず、開発した製品の質も劣っており、唯⼀Nantong Zhenkang社だけが実績を持っている。Anson Securities(2017)によると、同社の製品は輸⼊品に劣らず、現時点で国際的な精密寿命である 6,000 時間を遥かに越える20,000時間を達成しており、Estunを代表とする中国のロボットメーカは、同社の製品を導入することにより、ロボットの製作コストを削減している。なお、今後の中国の減速機メーカの課題としては、共通的に精度よりも寿命を延ばすことが挙げられている。
サーボモータ Anson Securities によると、減速機に比べると、サーボモータは比較的海外メーカの製品との技術的ギャップが小さく、ローエンドのサーボモータは、すでに国内で⼤量⽣産を実現している。しかし、ハイエンドのサーボモータに関しては、安定性、応答速度、使いやすさなどの技術的ギャップから輸入に頼っている。中国の主なサーボモータメーカには、Huichuan技術、広州ノースカロライナ、中華⼈⺠共和国CNC、Estonなどが挙げられる。
87
中国政府の対応とメーカの動き 政府のR&D補助⾦は、ロボット産業発展政策の枠組みの中で、州と都市に分けて施⾏されている。
福建省は、2017年3⽉に「ロボット産業の急速な発展を促進する上での⼈⺠政府の⾒解」を公表し、高性能ロボット・サーボモータの研究開発に注⼒する他、サーボドライブ、⾼精度減速機、 制御システム、視覚的認識システム、センサーやその他の要素技術に最⼤200万元の予算を割り当てている。 中国の大手家電メーカは、⾃社競争⼒強化の⼀環としてロボット及び知能装備の導⼊(製造知能
化)を推進する⼀⽅で、ロボット領域のビジネスにも積極的に進出している。以下に、各家電メーカの動きを表す。
ロボット事業に進出している中国の大手家電メーカ
出所:ロボスタ
88
ロボット産業発展ロードマップ
中国の知能製造業発展のロードマップ
出所:中国科技部「知能製造科技発展12・5専門計画」
中国は、「中国製造2025」の中でも、重点推進の10大産業の第2分野として「高機能NC工作
機械とロボット」産業の発展推進を挙げている。さらに、工業情報化部と国家発展改革委員会及び財政部は、2016年4月に「ロボット産業発展計画(2016-2020年)を共同で発表し、「第 13次5ヵ年計画(2016-2020 年)」期の中国ロボット産業の発展に向けた⻘写真を明らかにしている。当計画の目標は、2020年までに中国のロボット年間⽣産量を10万台、6軸以上のロボットを 5 万台以上、サービスロボットの年間販売収⼊を 300億元以上にし、2020年までに中の⾃主ブランドの競争⼒を引き上げることである。
89
中国政府は、2016年から2020年までのロボット産業発展計画として以下の5つの提案を挙げている。①「初期の拡充産業用ロボットの国内ブランドの開発と応用を促進するための政策」の枠組みの中で、産業⽤ロボットの使⽤状況を改善するための資⾦、補助⾦、税制及び関連企業への優遇税制政策を実施し、研究開発を促進する。なお、中小企業のロボット導入を促進するために、リース会社を設⽴し、ベンチャーキャピタルや⺠間資本による資⾦調達を奨励する。②技術研究開発を加速化し、産業技術のボトルネックを突破するための技術研究を活性化することにより、アプリケーションの要件、産業用ロボットのライフサイクルと信頼性、製造プロセス技術研究、主要部品技術、次世代技術開発、AI、センサー及び駆動・制御を含む広範囲の開発フラットフォームを構築する。③自国ブランド製品を用いての実証事業を強化するとともに、知的生産ニーズの開発を加速化する。④市場の主要分野における主要な技術的・財政的な突破口に焦点を当て、総合的な技術を把握するとともに、展示会などを通し、大規模なアプリケーションを形成することで、メーカの開発を促進し、消費者の多様なニーズに応じて、市場価格をセグメント化する。⑤学校と企業の⼈材育成を確⽴する。⼤型プロジェクトの実施を通して、研究機関や、中国科学院を中心とする合弁事業を実施する。 一方、中国企業は外国企業の資本を受け入れるだけでなく、買収もしている。代表的に、2004年に
中国を代表する大手機器メーカの上海電気集団総公司が、日本の工作機器メーカである池具を買収し、同社の開発・製造技術を導入して自社製品に活用している。
中国製造2025重点分野の技術ロードマップ
90
日系メーカの進出状況
主要国のロボット輸出入動向
出所:NEDO「ロボット⼤国」⽇本の実⼒現状
世界の産業⽤ロボット市場における、⽇系企業の国際競争⼒は⾼く、2013年時点で、アーク溶接ロ
ボットと双腕ロボットは、それぞれ世界シェアの 70.9%、82.4%を占めている。中国市場をはじめとする海外市場での競争激化が⾒込まれる中で、今後の中国産業⽤ロボット市場の拡⼤や中国現地のニーズの多様化を背景に、中国現地における製造工程の拡大及び取り扱う製品ラインナップの拡充などの検討が進んでいる。
91
日系ロボット関連メーカの中国進出状況
出所:FNA「中国産業用ロボット市場調査総覧」
2015年には、ナブテスコが現地(常州)での⽣産を開始、2016年時点で年間100,000台を供
給しており、2020 年には年間⽣産台数 200,000 台を達成できるものと予測されている。Anson Securities(2017)によると、2018年の中国の減速機需要量が46.2万台であることから、ナブテスコの現地生産が中国市場シェア確保において優位を持っていることが想定できる。このほか、ファナック、安川電機、パナソニック、三菱電機なども、コスト削減やシェア確保を⽬標に現地⽣産を開始している。
92
日本における今後の課題と方向性 中国機械連合会によると、「2012 年時点で中国製ロボットは⽇本製ロボットの 70%の性能であり、
課題はキーパーツを輸入品に頼っていることである。国をあげてキーパーツの国産化を推進する。」とコメントしている。NEDO はこれに対し、日本としては、残りの 3 割をいかに維持できるかが課題となり、コストパフォーマンスとトータルコストに着⽬した技術⼒で優位性を保持する必要があるとコメントしている(2014)。 日本ロボット学会産学連携委員会では、技術イノベーションによるコストダウンを追求しており、理想と
する材料や部品を業界間協⼒により開発することも視野に⼊れている。また、現在の産業⽤ロボットの構成にこだわらず、現実のニーズを反映させていくことも重要としている。 コストダウンのための設計製造技術面と制御技術面における要因抽出を踏まえ、これらを可能にする
ための⽬標として、「①ケーブルを⼀本も使わないロボット」、「②機械油を⼀切使わないロボット」、「③現⾏の半分以下のエネルギー消費」、「④⾃⾝の体重以上の可搬質量能⼒」の4つを挙げている(2015)。 ⽬標②において、機械油を利⽤しているのは減速機などであり、機械油を不要とすることでロボットの
構造設計の自由動の向上にもつながる。目標③、④は、エネルギーロスを低減するという意図によるものである。現状の産業用ロボットは、モータ内部での損失、減速機構内の摩擦など、全体で投入エネルギーの 3~4 割を損失している。その低減に向けては、設計製造技術面においては機械の随所にあるエネルギーロスを減らすことと、材料技術による軽量化によって根本的な仕事負荷を減らすという 2 点にまとめられる。
材料・要素技術からのコストダウンアプローチ
出所:日本機械工業連合会
93
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
(以下の内容を含む) -① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 -② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) -③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア -④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 -⑤ ②の各用途に求められる技術特性 -⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む) -⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記)
96
ロボットを構成する要素としては、骨格等の構造部・駆動・機構要素、センシング要素、制御・情報処理・判断要素に⼤きく分けられる。このうち、センシング要素はロボット自身の状態を知るための内界センサ(関節⾓度、姿勢、加速度)と周辺の状況を認識するための外界センサ(距離、対象有無、⼒、その他)に分けることができる。
表 産業用ロボットで主に使用されるセンサ
出所:各種資料を基にYRI作成
以降、各センサ別に①技術概要、②⽤途、③国際市場規模及び⽇本企業のシェア、④国際市場規模の将来予測、⑤各用途に求められる技術特性、⑥国内企業、⑦海外の主要な競合企業、についてみていく。
用途
内界センサ ポテンションメータ
ロータリエンコーダ
歪みセンサ ひずみゲージ
ロボットの構造材に取りつけることで異常加重が検出できる他、ロボットの部材の振動が検出できるため、振動制御(制振)に用いることがある。
傾斜計
加速度センサ
ジャイロ
外界センサ 超音波センサ障害物までの距離を測ったり、追跡対象までの距離を測ったりするのに使用する。
光電センサ 物体の有無や表面状態の変化等を検出。
⼒覚センサ
ロードセル
2次元
3次元
レーザスキャナ
ライトカーテン
ロボットの関節そのもの、もしくは駆動用のモータに⾓度、位置センサをとりつけ、関節⾓度からロボットの姿勢(リンクの状態)を求める。 屈曲関節に取りつける場合はポテンショメータが使われることもあるが、回転数が多い場合やモータに取りつける場合にはロータリーエンコーダが常用される。
ロボットの傾斜姿勢を求めるために使用するもので、一般的にはセンサの直交する3軸に対して3つのジャイロセンサと3つの加速度センサを取り付けたものを1つのセンサ(IMU)として構成することが多い。もしくは、ジャイロや加速度センサのバイアス誤差を補正するために、地磁気センサや傾斜センサ、GPSを取り付ける場合もある。
エリア管理等に用いられるセンサシステム
対象物との接点情報を得るために使用する。
画像認識による情報取得を目的とする。
その他
センサ
関節⾓度位置センサ
姿勢⾓度センサ
⼒センサ
ビジョンセンサ
97
関節⾓度位置センサ(ポテンションメータ、ロータリーエンコーダ) ①技術概要 ロボット等のサーボ系統の位置決めなどで用いられる回転角測定用の検出器としては、ポテンションメータやロータリーエンコーダ等の角位置センサが主に使用されている。 ポテンションメータは、回転⾓や移動量を電圧に変換する可変抵抗器で、回転⾓度を検出するロータリーポテンショメータと、直線上の位置を検出するリニアポテンショメータがある。抵抗部には⾦属巻線抵抗や導電性プラスチック抵抗体、磁気抵抗素子、ホール IC が使用されており、ロータリー型については単回転型と多回転型とがある。 ⾦属巻線抵抗 銅ニッケル系やニッケル・クロム系の抵抗線を芯線またはカードに均一テンションで巻きつけた抵抗素子と貴⾦属合⾦の接点との組合せにより計測を⾏うもの。⾓位置センサとしては⼀般的な⽅式で、現在も計測器をはじめ、様々な用途で使用されている。 抵抗温度係数が⼩さい フレキシブルな抵抗設計が可能(巻線ピッチ、抵抗線径) 接触抵抗が低い 導電性プラスチック抵抗体 導電性プラスチックを抵抗素子に用いた接触型のポテンションメータ。 分解能 ⻑寿命 高周波特性(巻線形ポテンションメータと比べインダクタンスが小さい) 磁気抵抗素子 磁気抵抗素子とマグネットを組み合わせた無接触のポテンションメータ。磁界の移動による磁気抵抗素子の中点電位の変化を検出するもので、接触形ポテンショメータに比べ、ノイズレス、高分解能、高速応答性、⻑寿命などに特⻑を有する。 ノイズレス 分解能 出⼒の滑らかさ 低トルク・低フリクション 高周波特性 高速性 低消費電流 ⻑寿命
98
ホールIC ホール素⼦とアンプを組合せ、ホール効果による電位の変化量を増幅できるようにしたもの。磁気抵抗素⼦を⽤いたポテンショメータと⽐べ出⼒電圧の幅が広くなり、温度補償回路により温度ドリフトの値も小さくなる。 ノイズレス 広い出⼒範囲 優れた温度特性 低トルク・低フリクション ⻑寿命 小型 ロータリーエンコーダは、回転の機械的変位量を電気信号に変換し、この信号を処理して位置・速度
などを検出するもので、⼊⼒軸の回転の変位を内蔵した格⼦円盤を基準にデジタル信号として出⼒する。 インクリメンタル形とアブソリュート形があり、インクリメンタル形は、外周部に窓を持つスリット円板(ガラ
スもしくは⾦属))と光電検出装置(発光ダイオード、フォトトランジスタ)を備え、光のオン/オフにより信号を発生させる方式である。発光ダイオードは一般的に赤外光であるが、高分解能製品ではレーザダイオードも使⽤されている。無接触検出で、静⽌状態でも検出出⼒を維持できるほか、スリット円板の製作に写真技術を⽤いることにより、⾼精度、⾼分解能が容易に実現できる。 アブソリュート形は、⼀部磁気式もあるが、⼤多数は光学式。出⼒信号数と同数の光学トラックを持
つスリット円板を持ち、各々の光学トラックには、その⾓度に対応する⾓度値が 2 値のコードにより明暗の模様として付けられている。光源と光センサを⼀列に並べたものにより、光のオン/オフを検出すると、その出⼒信号はシャフトの現在位置を⽰すデータとなっており、現在⾓度が直ちに判明する。アブソリュートエンコーダの出⼒信号はエンコーダの回転⾓度の現在値を⽰す信号であり、インクリメンタル形のようにカウンタを組み合わせる必要がないといった特⻑がある。 <インクリメンタル形> <アブソリュート形>
出所:オムロン資料
99
ロータリーエンコーダのポイント タイプ(インクリメンタル形 or アブソリュート形)〜コスト、原点復帰の可否、制御速度、耐ノイズ性等
分解能 外形寸法〜軸の形態(中空軸、シャフトタイプ等)も含む 軸許容荷重 許容最大回転数 最高応答周波数 ※最大応答周波数=(回転数/60)×分解能 保護構造〜ほこりのみ(IP50)、水もあり(IP52、IP64)、油有(防油) 軸の回転起動トルク 出⼒回路⽅式 ②用途 各種ポテンションメータは、導電プラスチックポテンションメータを中⼼に、⾃動⾞、建機の電⼦制御化に
伴い、⾓度センサ、位置センサとしての使⽤が増えているほか、FA、計測器、印刷機などの分野にも需要が拡がっている。一方、ロータリエンコーダは、もともと回転角測定用の検出器として考案されたものであるが、近年はロボットや情報機器の位置決めサーボ系に使用されるなど用途が拡がっており、モータ制御の重要な要素と位置付けられるようになっている。 実際、ステッピングモータでは脱調監視としてロータリーエンコーダが使用されている。ステッピングモータは、
パルス状の電流をコイルに流し、そのパルスに連動した動作⾓度だけ回転するモータである。そのため、フィードバック制御しなくても、基本的にはモーターの回転⽅向、回転⾓度はコントローラ側で認識できるが、何らかの障害が発⽣し、パルス電流通りに動作していない状態(脱調)になると、コントローラ側と実動作の間に誤差が生じる。⾼精度を必要とするアプリケーションでは誤差が問題になるため、誤差を検出してコントローラ側で補正するためにエンコーダが搭載されている。また、動作時の脱調監視だけでなくモータ負荷をエンコーダからのフィードバック信号により監視し、必要に応じて電流を供給することで、全体の消費電流を削減したステッピングモータも製品化されている。 このほか、工作機械のテーブル移動制御やインクジェットプリンタのインクヘッド動作制御にロータリエンコーダが使用されているケースがあるほか、表面実装可能な反射型エンコーダ IC の登場により、今まで採用が難しかった薄型・超小型のアクチュエータへの採用も増えている。
100
③国際市場規模及び日本企業のシェア ④国際市場規模の将来予測
⑤各用途に求められる技術特性 産業⽤ロボットのサーボモータでは、モータの反出⼒軸側にロータリーエンコーダを搭載し、ロータの位置と速度を検出することにより、⾼分解能、⾼応答な位置決め運転を⾏っている。当然、ロータリーエンコーダにも⾼分解能、⾼応答性、⾼精度が求められるほか、⼩型/薄型、高信頼性も重要な要素となってくる。また、サーボモータ⾃体のの⼩型・軽量化として、中空軸を採⽤する動きもみられるようになっている。 ⑥国内企業 ポテンションメータのメーカーとしては、東京コスモス電機、アルプス電気、パナソニック、帝国通信工業、
緑測器、日本電産コパル電子、日本抵抗器製作所が挙げられる。 東京コスモス電機は、産業機器用可変抵抗器(ポテンションメータ)の専門メーカーとして、炭素系混合体、巻線形、⾦属被覆形、⾼回転寿命形等の豊富なバリエーションを展開している。また、回転⾓度検出用に 2 出⼒薄型タイプ(RSM012)や基板実装タイプ(RSM12)などの小型非接触位置センサも製品化している。 アルプス電気は、ロータリタイプの抵抗式ポジションセンサを「RDC50 シリーズ」として展開している。小型、⾼精度、⾼耐熱性により、あらゆる位置検出ニーズに対応、⾃動⾞、カメラ、事務機器、ロボット、産業機械といった様々な分野で使用されている。 このほか、帝国通信工業、日本電産コパル電子等が非接触位置センサをはじめ、各種タイプのポテン
ションメータを展開している。
101
ロータリーエンコーダのメーカーとしては、ネミコン、多摩川精機、ニコン、光洋電子工業、シチズンマイクロ、シチズン千葉精密、ハーモニック・ドライブ・システムズ、マイクロテック・ラボラトリー等が挙げられる。 ネミコンは、2,000機種の豊富なラインナップを強みに、工作機械、産業用機器、検査機器、印刷機
器、医療機器、⾦銭機械等、様々なアプリケーションにエンコーダを納入している。 産業用ロボットのサーボモータでは、モータの反出⼒軸側にエンコーダを搭載しローターの位置と速度を
検出することにより、⾼分解能、⾼応答な位置決め運転を⾏っている。同社では⼩型普及型「38M」(外径:φ38、パルス:200〜4096、CEマーク取得)を主⼒に展開している。 多摩川精機ではエンコーダを「FA-CODER(エフエーコーダ)」のブランド名で展開、小形から高分解能
形まで各種シリーズをラインナップしている。サーボモータ向けでは中空軸を採用した薄型タイプなどが好調なようだ。 ニコンは、独自の光学技術と M 系列を応⽤したアブソリュートパターン技術を強みとしており、小型、高
信頼性を両⽴した同社のアブソリュートエンコーダは産業用ロボットや工作機械など、各種産業機械の分野で幅広く利⽤されている。特にロボットアーム等の回転変位を絶対値で検出できるセンサでは業界のスタンダードとなっている。 光洋電子工業は、得意とする精密加工技術を基にサーボモータ、工作機械、コンベア、エレベータ等
の⾓度、位置検出向けにインクリメンタル形、アブソリュート形を幅広く展開、インクリメント形では超⼩型、小型(φ50)、大型(φ78)、中空軸形をラインナップしている。 ⑦海外の主要な競合企業 ポテンションメータでは、Honeywell(米)、CTS Corp(米)、BOURNS(米)VISHAY(米)、ABB(スイス)、SIEMENS(ドイツ)、TE Connected(アイルランド)、TT Electronics(英国)、SONG HUEI ELECTRIC(台湾)、Taiwan Alpha Electronic(台湾)等がある。 Honeywellは、Sensing and Internet of Things部門において各種のポジションセンサを展開している。ポテンションメータはCERMET、巻線、導電プラスチックの各材料を使⽤したグレードをラインナップ。ロボットアームポジション向けでは640シリーズを提案している。 CTS Corpは、⾃動⾞⽤センサー、アクチュエータ、水晶発振器、タイミングデバイス、RFセラミックフィルタを始めとする高周波製品から、ポテンショメータ、抵抗ネットワーク、放熱機器までの幅広い製品ラインナップを有する。 ポテンションメータは、定番の 450 シリーズ、270 シリーズをはじめ、⾼回転寿命(〜1 万サイク)の295シリーズ、コンパクトタイプの250シリーズなど、様々なシリーズを展開している。 その他、BOURNS、VISHAY、ABB、SIEMENS も各種タイプを揃えた豊富なラインナップを特⻑としている。
102
図表 Honeywell ロボットアームポジション向けポテンションメータ(640シリーズ)
出所:Honeywell資料 ロータリエンコーダでは、Heidenhain(独)、Renishaw(英)、TURCK(独)、Kubler(独)、Leine&linde(スウェーデン)、Baumer(スイス)、P+F(Pepperl+Fuchs, 独)、Hengstler(独)、SICK(ドイツ)、Dynapar(米)の欧米メーカーに加え、Autonics(韓)、Rep Avago(中)、Yuheng Opt(中)、LJV(中)といったアジアのメーカーも一定の存在感を発揮している。 Heidenhain は、位置決めに必要なリニアエンコーダ、⾓度エンコーダ、ロータリエンコーダ等を開発・製
造している。同社のロータリエンコーダは、回転運動量、および回転速度を検出するセンサとして使⽤されるほか、送りネジ(ボールねじ)のような機械的位置の測定標準器と共に使⽤することで、直線運動量の検出センサとして使用できる。。その応⽤領域には電動モータ、⼯作機械、印刷機械、⽊⼯機械、繊維機械、ロボット、搬送機器の他に各種計測装置、試験、検査装置が含まれる。 Renishaw は光学式、磁気式、レーザ式のエンコーダを展開、その精度と信頼性の点からユーザーに
支持されている。産業用ロボット分野では、関連会社である RLS 社製の磁気式ロータリーエンコーダ AksIM シリーズをユニバーサルロボット(デンマーク)が採用している。このエンコーダは、ロボット関節部の実回転⾓度を直接モニターできるよう減速機の機械端に取り付けられている。減速機のモータ側にエンコーダを取り付けるタイプのロボットと比較すると、機械端に取り付けることでシステムエラーを排除することができ、その結果、±0.1mm という高い再現性を実現している。 AksIM シリーズは絶対位置が電源 ON 直後に確⽴される、バッテリーバックアップの不要のアブソリュ
ートエンコーダで、複数のセルフモニタリング機能を内蔵、ロボットの動作上の安全性をサポートしている。また、減速機と一体化するコンパクトな設計を採っているほか、中空リングのため、リングの中にケーブルを通すことができるといった特⻑を持つ。分解能は最大20bit で、システム精度は±0.1°、分解能より細かい再現性を有している。また、防水・防塵性能も IP64 と優れており、過酷な製造環境下での使用も可能となっている。
103
P+F は、⾼精度(±0.1°)の磁気式ロータリエンコーダ「ENA36IL」を産業用ロボット向けに投入し
ている。同製品は、リニアなホール効果とノンリニアなウィーガント効果を検出原理に取り⼊れることで、⾼い信頼性とロバスト性を実現、そのコンパクトなデザインを含め、様々なアプリケーションに幅広く利⽤できるとしている。 このほか、各社とも様々な形でロボット産業にアプローチしているが、中国 Yuheng Opt は 2017 年
12 月より国家プロジェクト「High-resolution angular displacement sensor development and industrialization」をスタートしている。詳細は明らかでないが、中国政府科技部が支援している。
104
歪みセンサ ①技術概要 物体に⼒が加わることによって⽣じるひずみなどの物理的な変化をひずみゲージの抵抗変化として測定
するもので、ひずみゲージには箔ひずみゲージ、線ひずみゲージ、半導体ひずみゲージなどがある。 一般的なひずみゲージは、電気絶縁体である樹脂ベース上に、抵抗材料の⾦属箔と引出線であるゲ
ージリードが取り付けられた構造を採っている。ひずみゲージを被測定箇所に専用の接着剤で接着。被測定箇所に発生したひずみは、接着剤、ひずみゲージのベースを介してひずみ受感部に伝達される。ひずみを精度よく測定するためには、被測定材料・使⽤温度など使用条件に合ったひずみゲージと接着剤を選択する必要がある。このため、抵抗材料(Cu-Ni系合⾦、Ni-Cr系合⾦)、ベース材料(ポリイミド、ステンレス鋼、アクリル、シリコーン、紙等)の様々な組み合わせがあり、製品の種類が相当に多いのもひずみゲージの特⻑である。
②用途 ひずみゲージは、構造が簡単で質量、容積が⼩さく測定対象物の応⼒状態を乱さない、標点距離を短くでき、局所的な評価ができる、周波数応答性が良く、応⼒の急激な変化に追随できる、多点の同時測定、遠隔測定ができる、出⼒が電気量なので、データ処理が容易といった特⻑から、荷重測定、変位測定、振動測定、圧⼒測定等、様々な利⽤のされ⽅がある。産業⽤ロボットでは、⼒覚センサ(別頁参照)に使用されるケースが多く、そのほか、微⼩振動のデータを集め、振動制御に利⽤するといった例もあるとみられる。
105
③国際市場規模及び日本企業のシェア ④国際市場規模の将来予測
なお、日本国内のシェア 40%を持つ共和電業の資料を参考に⾒積もった⽇本企業のシェアは 25%。
共和電業のほか、東京計測研究所、ミネベアがグローバル市場での認知度を得ているものとみられる。 ⑤各用途に求められる技術特性 ひずみセンサは、⾞載機器、産業機器、インフラ構造物などに搭載することで、物体に⼒が加わることによって⽣じるひずみなどの物理的な変化を⾼精度に測定することができるため、それらの状態管理・制御を効率的に⾏うことで、機器の円滑な動作を可能にしたり、故障の予兆診断などに活⽤できる。 ⾼温⾼湿な過酷な環境下で⻑期間にわたりセンサーに⼤きな負荷がかかるため、現在主流の抵抗線
式ひずみゲージでは、接合部分の有機材料が劣化することから、⻑期の使⽤が難しいという課題があほか、モーターなどの被測定物によっては電磁波ノイズの影響を受けるため、データを正しく測定できないといった問題もある。このため、⾼性能、⾼信頼、⻑寿命かつ適⽤範囲の広さ等が求められている。 ⑥国内企業 ひずみゲージのメーカーとしては、共和電業、東京計測研究所、ミネベア、昭和計測、東洋計測等が
挙げられる。ひずみゲージ自体の技術が成熟化しているため、既存メーカーから新たな技術製品の投入はあまりみられないが、センサ、計測器としての展開を強化したり、ソフトウェアやサービス(IOT 関連)の投入といった動きが活発である。 また、トップメーカーの共和電業は、独Hottinger Baldwin Messtechnik(HBM)と両社の一部
製品について相互供給による販売をおこなうことに合意、2018年4月よりそれぞれの販売圏内における相互販売を計画している。 ⼀⽅、⽇⽴製作所は2015年、センサー素⼦と制御回路を1チップ化した半導体ひずみセンサおよび
独自の接合技術を開発、グループの⽇⽴オートモティブシステムズが本格的な量産を開始している。 このひずみセンサは、独⾃開発した耐⾼温・低クリープ型の⾦属接合技術を活⽤することで、マイナス40度〜プラス120度の環境下で⻑期間にわたり⾼精度な計測が可能。共通のセンサー素⼦を⽤いながら、加重・圧⼒、トルク、引張り、せん断⼒といった幅広い物理量の変化に加え、低周波振動などの緩やかな変形も継続的に計測できることから、例えば精密機器のレベリングや流量計測といった使い⽅もで
106
きる。また、ひずみセンサーはCMOSプロセスを採⽤することで⼩型、低消費電⼒を実現、さらにセンサ素子を極小化することで電磁波ノイズの影響を最小限にとどめたことから、これまで搭載が困難であった小型医療機器やインフラ構造物などへの適⽤も可能となっている。⽇⽴オートモティブシステムズが2012年末から出荷しているトルクセンサが電動アシスト⾃転⾞⽤の機構部品にこのひずみセンサが搭載されており、最適なモーター駆動によるスムーズなアシスト制御を実現している。 このほか、東芝が2017年6月、従来HDDヘッドやMRAMに用いられているスピントロニクス技術を応⽤し、新たなひずみ検知素⼦「超⾼感度スピン型ひずみ検知素⼦」を開発したことを発表している。 本素子は、従来HDDヘッドの磁界センサとして用いられてきたMTJ(Magnetic tunnel junction)
素子に、ひずみによって磁性体の磁化の向きが変化する磁歪効果を応用することで、ひずみ検知素子として機能させたものである。磁性体層に磁歪効果の大きいアモルファスの鉄・ホウ素合⾦材料を採⽤し、ひずみ検知感度を⼤幅に向上させました。ひずみ検知感度は、従来の⾦属ひずみゲージの 2500 倍、半導体ひずみゲージの100倍以上で、本素⼦を搭載することで⾼精度に計測できるMEMSセンサを実現できるとしている。 ⑦海外の主要な競合企業 ひずみゲージのメーカーとしては、VISHAY(米)、Hottinger Baldwin Messtechnik(独)、
Zemic(オランダ)、Zhejiang Huangyan Testing Instrument Plant (中)、LCT(中)、OMEGA(米)、BMC(ベルギー)、Micron Instruments(米)等が挙げられる。 これらメーカーの多くは主にコンベンショナルな抵抗線式ひずみゲージを展開しているが、Micron
Instrumentsは半導体ひずみゲージ(P型シリコン)を製品化、ロードセルやトルクセンサ、加速度センサで豊富な実績を持っている。
107
姿勢制御センサ ①技術概要及び②用途 姿勢制御で主に⽤いられる傾斜⾓を検出するセンサとしては、傾斜⾓センサ、加速度センサ、ジャイロセンサがある。傾斜角センサは物体の傾きを検出するもので、吊るした錘に対する傾きを回転角センサ(磁気抵抗素子、エンコーダ等)で検出する振り子式と液体を⽤い液⾯の傾きを静電容量変化等で検出するフロート式がある。いずれも周波数特性が低く、ゆっくりとした動きや静止状態の傾斜角の測定には有効であるが、加速度が加わると重⼒加速度と異なった⽅向の加速度が合成され誤差が⼤きくなる。 加速度センサは、物体に加わる加速度を速度の時間変化率として検出するもので、加速度を測定し
適切な信号処理を⾏うことにより、傾きや動き、振動や衝撃等の情報が得られる。⼀般的に約 20G 以下の測定範囲をもつ加速度センサを低G加速度センサ、それ以上の測定範囲をもつものを⾼G加速度センサと呼ぶ。低G加速度センサは重⼒・傾きの検知や⼈の動き等の検知に適しており、⾼G加速度センサは主に衝撃の検知に使われる。 加速度センサの主な検出⽅法としては、静電型、圧電型、抵抗型、熱・流体型、動電型、磁気型が
ある。また、製造方法によりMEMS型と非MEMS型に分類されるほか、検出軸数により1軸、2軸、3軸等の加速度センサがある。XYZ の 3⽅向の加速度を1デバイスで測定できる 3 軸加速度センサ(MEMS)としては、静電容量型、ピエゾ抵抗型、熱検知型が代表的である。 静電型 センサ内の可動部(おもり)をキャパシタの⽚側の電極とした加速度センサで、可動部の相対的な変位量をキャパシタの静電容量変化により取り出し、加速度として検出する。 圧電型 材料に⼒を加えると応⼒に⽐例した分極が起こる圧電材料を⽤いた加速度センサ。圧電材料に発⽣する分極を電気的に取り出し、慣性⼒を求め、加速度を取得する。 抵抗型 材料に⼒を加えるとひずみに⽐例して電気抵抗が変化するピエゾ抵抗材料や歪みゲージを⽤いた加速度センサ。電気抵抗の変化をブリッジ回路などの周辺回路により電気的に取り出し、慣性⼒を求め、加速度を取得する。 熱・流体型 加速度センサに流体が封⼊された加速度センサ。加速度が加わると流体の移動が起こり、温度分布が変化する。この温度変化を検出して加速度を求める。主なセンシング⽅式と異なり、機械的な可動部がないという特徴がある。
108
動電型 電磁誘導を利⽤した加速度センサ。センサ内の可動部(おもり)を磁性体で形成し、コイルと対向して配置する。加速度により磁性体が変位すると誘導起電⼒が発⽣するので、この起電⼒から加速度を算出する。 磁気型 磁気を利⽤した種々の加速度センサ。ホール素⼦を利⽤したもの、磁気抵抗効果素⼦を利⽤したもの、磁歪効果素⼦を利⽤したもの、リードスイッチを利⽤したものなどが挙げられる。 ジャイロ(⾓速度)センサは、ある物体の⾓度が単位時間当たりどれだけ変化しているかという回転
⾓速度(単位:deg/second)を計測するもので、機械式(回転型、振動型)、流体式(ガスレートジャイロ)、光学式(光ファイバジャイロ、リングレーザージャイロ)などがある。性能・サイズ・コストにより様々な⽤途で使分けられているが、近年は⼩型ビデオ・カメラの⼿ブレ検出やゲーム等のモーションセンシング、⾃動⾞の横滑り防⽌等で振動型ジャイロセンサが使⽤されており、今後は⾃動⾞運転⽀援やロボットの動作制御などでさらなるニーズの拡⼤が⾒込まれている。
図 各種ジャイロセンサの⽐較(精度、価格)
出所:多摩川精機資料
109
⑤各用途に求められる技術特性 産業用ロボットの姿勢制御センサとしては、3軸加速度センサと3軸ジャイロセンサを組み合わせた6軸慣性センサ/IMU(inertial measurement unit)が一般的となっている。補正用に傾斜計や磁気センサ等を備えた IMU もあるが、ロボットの 3 次元制御では 6 軸慣性センサもしくは 3 軸慣性センサの採⽤が多く、予兆検知等、より⾼度な⽤途でのニーズが中心とみられる。 慣性センサは、その他、⾃動⾞、建設・⼟⽊機械等の⾃動運転技術、医療・介護⽀援(ヒューマン
アシストロボット、医療・介護機器)への応用も進んでいるが、小型、高分解能、低ノイズといったニーズはいずれの分野でも強く、MEMSジャイロ、MEMS加速度センサの導入が加速している。 ⑥国内企業及び⑦海外の主要な競合企業 ● 傾斜角センサ 日本企業としては、村田製作所、多摩川精機、オムロン、緑計器、セイコーエプソンが挙げられる。い
ずれも MEMS タイプをメインに展開しているものとみられる。村田製作所は、2012年1月に買収したフィンランドVTI Technologiesを⺟体とするMurata Electronics Oyにて傾斜センサを手掛けている。主⼒モデルは⾼性能アナログ 2軸傾斜センサ「SCA100Tシリーズ」、高性能アナログ差分型1軸傾斜センサ「SCA103T」、デジタル 1 軸傾斜センサ「SCA830 シリーズ」。「SCA100T シリーズ」はノイズ密度:14μg/√Hz、分解能:0.0025°(帯域幅10Hz)という性能の高さに加え、耐衝撃性に優れた堅牢な設計、⻑時間、広い温度範囲で優れた安定性を特⻑とする。「SCA103T」はノイズ密度:7μg/√Hz、分解能:-0.001°(帯域幅 10Hz)、同様に堅牢設計を採っており、ともに計測機器、大型⾞両、⽔準器、建築⽤⽔平器などで使用されている。 「SCA830シリーズ」は、優れた精度、安定性、広い温度範囲、湿度、振動での極めて安定した出⼒
を特⻑としており、⾃動⾞の傾斜計測に使⽤されている。スペックは測定⾓度:±90°, ±1g、温度範囲:-40〜125℃、感度:32,000LSB/g、帯域幅:6.25Hz。また、寸法:7.0×3.3×8.6mm (幅×高さ×⻑さ)、⾼度な⾃⼰診断機能、AEC-Q100 適合、RoHS準拠のデュアルフラットリード (DFL) プラスチックパッケージ、鉛フリーはんだ処理、SMD実装対応となっている。
113
表 村田製作所 傾斜センサのラインナップ
出所:村⽥製作所資料
オムロンは傾斜センサとして、±60°の広い測定⾓度、リニアリティ 1%の⾼精度、IP67 の高い防水防
塵性、ローコストで省スペースといった特⻑を持つ D5R を展開している。省スペースで防⽔性・耐久性に優れたシール構造タイプと基板実装タイプをラインナップしている。 緑計器は、MEMSタイプの⾼精度・⾼機能傾斜センサ「ESC3000Zシリーズ」、ホールICを内蔵した
振り子式傾斜センサ「WR シリーズ」、ピボット軸受のフロート式傾斜センサ「UV シリーズ」、板バネ振り子式傾斜センサ「PMP-SxxHTシリーズ」等を展開している。 「ESC3000Zシリーズ」は、⾼精度、⾼機能(ユーザーフレンドリー)を追求した傾斜計で、2出⼒:
X,Y 2 軸、広⾓度対応:〜±80°、⾼精度、安定した温度特性、堅牢(アルミダイキャスト筐体),IP67。また、機能面では振動条件下でも傾斜角計測可、フィールドで 0°位置を簡単ティーチング、豊富な出⼒バリエーション、ユーザによるパラメータ変更が可能等、ユーザーの使い勝⼿を考慮した機能を持たせている。 「WRシリーズ」は、側面取付タイプ、無接触・高信頼性(ホールICを使用した無接触、接点ノイズな
し)、広⾓度(90°〜360°を検出)、⾼精度(絶対直線性±0.4%FS)、耐環境性(EMS 100V/m)といった特⻑を持つ。
概要 分解能 サイズ 電源電圧高性能アナログ2軸傾斜センサ検出範囲:±30°/±0.5g、±90°/±1g、使⽤範囲温度:-40〜+125℃、帯域:18Hz(用途)計測機器、⼤型⾞両、プラットフォームのレベリングと安定化、垂直方向360°の計測、水準器、建築用水平器
0.0025° (帯域幅10Hz、アナログ出⼒)オフセット温度依存性: (-25〜85°C) ±0.008 °/°C
11.31×15.58×5.08㎜ 5V
概要 分解能 サイズ 電源電圧高性能アナログ差分型1軸傾斜センサ検出範囲:±15°/±0.26g、±30°/±0.5g、使⽤範囲温度:-40〜+125℃、帯域:18Hz(用途)計測機器、⼤型⾞両、プラットフォームのレベリングと安定化、回転式レーザーレベル、水準器
-0.001° (帯域幅10Hz、アナログ出⼒)オフセット温度依存性: (-25〜85°C) ±0.002 °/°C
11.31×15.58×5.08㎜ 5V
概要 分解能 サイズ 電源電圧アナログ1軸傾斜センサ検出範囲:±30°/±0.5g、±90°/±1g、使⽤範囲温度:-40〜+125℃、帯域:18Hz(用途)計測機器、⼤型⾞両
0.0025° (帯域幅10Hz、アナログ出⼒)オフセット温度依存性: (-25〜85°C) ±0.008 °/°C
11.31×15.58×5.08㎜ 5V
概要 分解能 サイズ 電源電圧デジタル1軸傾斜センサ検出範囲:±90°/±1g、使⽤範囲温度:-40〜+125℃、帯域:6.25Hz(用途)⾃動⾞傾斜測定
32,000LSB/g 7.0×3.3×8.6mm 3.3V
SCA61Tシリーズ
傾斜センサ
SCA830シリーズ
SCA100Tシリーズ
SCA103Tシリーズ
114
一方、海外の主要プレイヤとしては、Asm(独)、Balluff(独)、Baumer(独)、Dis Sensor(独)、Elobau(独)、Gefran(伊)、Gemac(独)、Geokon(米)、Ifm Electronic(独)などがあるが、多くの企業がMEMSベースの傾斜センサを展開している。 Asmは、MEMSベースの傾斜センサとして「POSITIL」を展開、「PTAM27」、「PTAM2」、「PTAM5」
をラインナップしている。計測範囲は±180°、無接触による信頼性の⾼さを特⻑としている。それぞれにアナログ/デジタル、1 軸/2 軸のタイプがあり、求められる防水防塵性に応じて、「PTAM27」(IP67)、「PTAM2」(IP67/IP69)、「PTAM5」(IP67/IP69, IP68 optional)を提案している。 Balluff は、豊富な MEMSベース傾斜センサのラインナップを強みに、⼩型・⾼精度、UL/CE認証、
インタフェイス:4…20 mA, 0…10 V、2軸対応、幅広い計測範囲にきめ細かく対応、キャリブレーション機能によるインストールのしやすさ、メンテナンスフリーオペレーション等を訴求している。 Gefran は、エントリーレベルからハイエンドまでの MEMSベース傾斜センサを展開している。農業や建
設分野での採用が多いものの、エントリーレベル品はマテリアルハンドリング装置などにも使用されているとしている。なお、エントリーレベル品は、計測範囲:±10° ±15° ±20° ±30° ±45° ±60° ±85° (dual axis XY) 360° (±180°) (single axis Z)、分解能:0.05° (±10° to ±20°); 0.05°(±30°); 0.1°(±45°); 0.1°(±60°); 0.1°(±85°); 0.1° (±180°) analog output; 0.05° CANopen output となっている。
● 加速度センサ及びジャイロセンサ 加速度センサの素⼦材料はセラミックスと半導体の 2 種類に区分され、セラミックスについてはコストや
サイズ面から一部の用途を除いて採用が少なくなってきている。 半導体素⼦は検知⽅法、加⼯プロセスによって参⼊メーカーが異なる。検知⽅法は
STMicroelectronics や Bosch などが採用している静電型、国内メーカーが中心のピエゾ抵抗型、MEMSICが独自に開発した熱検知型がある。 ⾞載分野については、⼤部分が静電型を採⽤している。エアバッグ⽤⾼ G センサは量産性とコストに
優れたサーフェイス MEMS による静電型が100%。ESCやRollOverなどで使われる低G センサは村田製作所(旧VTI Technologies)が採用するバルクタイプの静電型が50%程度のシェアを持つ。 ジャイロセンサの素子は、セラミックス、水晶、半導体の 3 種類に区分される。セラミック素子は村田製
作所が DVC/DSC の手ブレ補正用途で出荷しているが、コスト面で優れるものの、サイズ面で限界があるために数量は減少傾向にある。 ⽔晶素⼦については、⺠⽣向けでエプソンが製品化している。⽔晶の微細加⼯に技術により精度や
寸法、コスト⾯で⼤きな違いが出る、⽔晶⾃体が異⽅性エッチングに効果的であり、シリコン同様に機械的に安定した材料であることから、⾼精度・温度特性が良いなどの点で特⻑。コスト重視の⺠⽣より⾞載や産業用途に向いている。 半導体素子は、加工方法によりバルク、サーフェイスタイプに分かれる。バルクタイプは InvenSense、
パナソニック、村田製作所、サーフェイスタイプはSTMicroelectronics、Bosch、Analog Devicesなど。
115
半導体タイプは2軸、3軸タイプの量産が2009年から始まった。2011年頃までは、3軸ジャイロセンサを⼤⼝で量産していたのはInvenSense とSTMicroelectronicsの2社のみであったが、2012年にKionix、パナソニックが新型製品を投入、Boschも世界最⼩となる製品の量産を開始した。 また、同時期に3軸加速度センサと1 パッケージ化した6軸センサが量産化され、3軸地磁気センサ
を内蔵した9軸品も相次いで投⼊されている。⾞載向けについては1軸品が中心で、2軸の加速度センサとジャイロセンサを1パッケージ化したIMU(Inertial Measurement Unit)がエアバック ECUなどに実装されている。
表 加速度センサの参⼊メーカー
表 ジャイロセンサの参入メーカー
出所:矢野経済研究所作成
116
村田製作所 セラミックバイモルフ振動⼦を採⽤した⾓度センサを DVC/DSC の手ブレ補正、ゲームコントローラに出荷してきたが、2012年1月にフィンランドの大手MEMS加速度センサメーカーVTI Technologies を買収したことを契機に、VTI Technologies が保有していた 3D MEMS技術を活用した MEMS センサを主軸に事業展開を⾏うようになっている。なお、VTI Technologies は 2012 年 5 月、社名をMurata Electronics Oyに変更している。
表 村田製作所 加速度センサのラインナップ
出所:村⽥製作所資料
概要 感度 サイズ 電源電圧アナログ1軸加速度センサ(主に⾃動⾞⽤)検出範囲:±1.5〜±12.3g、帯域幅:50…400Hz、使⽤温度範囲:-40〜+125℃
0.15…2V/g 10.48×11.31×5.08mm 5V
概要 感度 サイズ 電源電圧デジタル1軸加速度センサ(⾛⾏安全⾃動⾞用途)検出範囲:±2.0g、帯域幅:50Hz、使用温度範囲:-40〜+125℃
900LSB/g 7.0×8.6×3.3mm 3.3V
概要 感度 サイズ 電源電圧アナログ2軸加速度センサ(⾃動⾞、計測機器)検出範囲:±1.7g、±4.0g、帯域幅:50Hz、115Hz、使⽤温度範囲:-40〜+125℃
1.2V/g0.55V/g
11.31×15.58×5.08mm 5V
概要 感度 サイズ 電源電圧デジタル2軸加速度センサ(⾛⾏安全⾃動⾞用途)検出範囲:±2.0g、帯域幅:45Hz、使用温度範囲:-40〜+125℃
900LSB/g 7.0×8.6×3.3mm 3.3V
概要 感度 サイズ 電源電圧デジタル3軸加速度センサ(⾛⾏安全⾃動⾞用途)検出範囲:±2.0g、±6.0g、帯域幅:45Hz、使⽤温度範囲:-40〜+125℃
900LSB/g650LSB/g
7.0×8.6×3.3mm 3.3V
概要 感度 サイズ 電源電圧デジタル3軸加速度センサ(産業機器向け)検出範囲:±1.5g、±3.0g、±6.0g、帯域幅:10/88Hz、使⽤温度範囲:-40〜+125℃
5400LSB/g(±1.5g)2700LSB/g(±3g)1350LSB/g(±6g)
7.0×8.6×3.3mm 3.3V
加速度センサ
SCA6x0シリーズ
SCA800シリーズ
SCA1000シリーズ
SCA2100シリーズ
SCA3100シリーズ
SCA3300シリーズ
117
加速度センサは、Murata Electoronics Oyのシリコン容量型3D MEMSテクノロジーをベースとしている。センシングエレメントと ASIC は、デュアルインラインまたはデュアルインフラットラインの LCPパッケージパッケージ内に配置され、表面実装用およびリフローはんだ付け用としてそれぞれ組み⽴てられる。センシングエレメントとASICはシリコンゲルでシールされ、⾼湿環境および温度変化に対して⾼度の性能と信頼性を発揮している。 ASIC には、校正係数付きのオンチップEEPROM メモリーを内蔵。また、デジタル起動の自己診断、
校正メモリーのパリティまたはチェックサムチェック、ならびに常時故障検知機能等の⾼度な故障検知機能を備える。ゼロ点温度依存性は 1mg/℃未満。センシングエレメントはオーバーダンピング (不活性ガス封入により高周波ノイズを低減) 構造を採っている。 主⼒は、⾃動⾞⽤途(横滑り防⽌装置、電⼦パーキングブレーキ、ロールオーバー検出、電⼦サスペンション)向けのデジタル 3軸加速度センサ「SCA3100シリーズ」、産業機器向けのデジタル3軸加速度センサ「SCA3300シリーズ」となっている。 「SCA3300 シリーズ」は寸法: 7.6×8.6×3.3mm (幅×⻑さ×⾼さ)、定レンジ:1.5g, 3.0g, 6.0g から選択可能、広範囲な自己診断機能搭載、グランドブレーキングバイアスの安定、低ノイズで耐振動性に優れている、優れたメカニカルダンピング特性、消費電流1mA(供給電源:3.0~3.6V 時)といった特⻑を有し、過酷な環境下で高安定性を求められる業務用水平器、⾓度計測制御装置、傾斜補正機、慣性計測装置、モーション解析/コントロール等で使用されている。
118
パナソニック ⾞載⽤ジャイロセンサ、DSC向け手ブレ補正用ジャイロセンサのトップメーカー。2016年7月には3軸加速度センサと 3 軸ジャイロセンサを搭載したモーションセンシングユニットを開発、市場が拡大中の産業⽤ロボットやサービスロボットなどのロボティクス分野における⾼精度な姿勢検出や位置推定をターゲットに2016年末よりサンプル提供を開始している。
表 パナソニック 加速度センサ及びジャイロセンサのラインナップ
出所:パナソニック資料
概要 感度 サイズ/重量 消費電⼒静電容量型の1軸加速度センサ。耐環境性が要求される輸送機器用途に最適なスタンドアロンタイプ。動作電圧(5 V.DC / 12 V.DC / 24V.DC)、加速度検出範囲(±2 g / ±0.5 g)に応じた製品ラインアップ。検出範囲:±0.5〜1.2g、使⽤温度範囲:-40〜+85℃
1.333 V/g 〜 3.0 V/g 58 × 36.5 × 33mm(直付タイプ)
10mA(5Vタイプ)
概要 0点出⼒ サイズ 電源電圧汎用ジャイロセンサ(SMDタイプ)。圧電薄膜表面に直接成形したMEMSシリコン音叉とベアチップICをセラミックパッケージで密封。お掃除ロボット⽤進⾏⽅向検出、カーナビゲーション用進⾏⽅向検出、ロボット用姿勢制御。検出範囲:±150°/s、使⽤温度範囲:-40〜+85℃
32768±800 LSB
*感度(Z軸)50 LSB/°/s
小形、低背(5.0㎜max.)
3.3V.DC対応
概要 0点出⼒ サイズ 電源電圧SMDタイプを採用した横転検知用。圧電薄膜表面に直接成形したMEMSシリコン音叉とベアチップICをセラミックパッケージで密封。⾃動⾞の横転検出、産業用機器の姿勢制御。検知範囲:±300°/s、使⽤温度範囲:-40〜+95℃
*感度6±0.3mV/(°・s-1)
小形、低背(5.0㎜max.)
5V対応
概要 0点出⼒ サイズ/重量 電源電圧SMDタイプの2軸⼀体⺠⽣⽤ジャイロセンサ。圧電薄膜表面に直接成形したMEMSシリコン音叉2つとベアチップICをセラミックパッケージで組み込んだ超小形。DSC、DVCの手振れ補正用途。検知範囲:±300°/s、使⽤温度範囲:-10〜+75℃
32768±4000 LSB
*感度(Z軸)50 LSB/°/s±5%
4.6×3.8×0.9㎜ 3V
概要 姿勢検出精度 外形3軸加速度センサ、3軸ジャイロセンサを内蔵したユニット。XYZ方向の3軸回転運動と3軸直進運動を合わせた6軸検出に対応。2016年末よりサンプル出荷。⾓速度計測範囲:±300dps(XYZ軸)、加速度計測範囲:±2.9G(XYZ軸)
0.2deg (XY軸)、1.0deg(Z軸)
*出⼒周期 1ms
74×49×16㎜ -
EWTS8RD
EWTS64G
GF1
加速度センサ
EWTS9P
モーションセンシングユニット
(開発品)
ジャイロセンサ
119
三菱電機 三菱電機は、⺠⽣・⼀般産業⽤途向けに±2g用のIC型加速度センサ(1軸)を有している。セン
サチップ形成プロセスに Si バルクマイクロマシニング技術を採⽤することで、⾼感度のセンサ出⼒を実現した。加速度検出⽅式は静電容量式を採⽤、ASIC に増幅回路・温度補償回路を内蔵しながら、⼩形・軽量の10ピンSOPパッケージにおさめた点を特⻑とする。同社では液晶プロジェクタ、カーナビ、傾斜計、産業機械の振動計測、ヘッドマウントディスプレイ、アミューズメント機器への展開を図っている。
表 三菱電機 加速度センサのラインナップ
出所:三菱電機資料
概要 感度 サイズ/重量 電源電圧⺠⽣・一般産業用途向け±2g用IC型加速度センサ。Siバルクマイクロマシニング技術を採用した静電容量式。検出範囲:±19.6m/s2、使⽤温度範囲:-40〜+85℃
*主軸感度1000mV/g
- 5V
加速度センサ
MAS1913P
120
セイコーエプソン ⽔晶デバイス事業と半導体事業を展開する強みを活し、独⾃のセンシング製品を開発・製造。精度・
安定性に優れる水晶素材に、独自技術「QMEMS」で微細細加⼯を施した⽔晶加速度センサをコアに加速度計等を展開している。*QMEMS:安定・⾼精度などの優れた特性を持つ⽔晶素材である「QUARTZ」と、「MEMS」(微細加工技術)を組み合わせた造語
表 セイコーエプソン 加速度センサのラインナップ
出所:セイコーエプソン資料
概要 分解能 サイズ/重量 消費電⼒3軸(X, Y, Z)の傾斜・振動測定⽤加速度センサ、低ノイズ・高分解能に特⻑。測定範囲:±45°(傾斜)/±5G(振動)、使⽤温度範囲(-20 to +85℃)、帯域:50Hz〜100Hz
0.002µrad/LSB(傾斜)0.06µG/LSB(振動)
24×24×19㎜Approx. 12g
< 100 mW
概要 分解能 サイズ/重量 消費電⼒低ドリフト⽔晶加速度センサを搭載した高安定・高分解能の傾斜計。屋外で使用可能な防塵・防滴品をラインアップ(IP67)。測定範囲:±45°、使⽤温度範囲:-25 to+70 ℃、帯域:2.5Hz
0.0001deg1.7µrad/LSB
52 x 52 x 25 mmApprox. 85g
-
概要 分解能 サイズ/重量 消費電⼒低ドリフト⽔晶加速度センサを搭載した低ノイズ・高分解能(微振動・⻑周期振動)の振動計。屋外で使用可能な防塵・防滴品をラインアップ(IP67)。測定範囲:±5G、使⽤温度範囲:-25 to+70 ℃、帯域:20Hz
1µG 52 x 52 x 25 mmApprox. 85g
-
概要 感度 サイズ/重量 消費電⼒⾓速度3軸および加速度3軸搭載の慣性計測ユニット(IMU)。姿勢制御・無人機・農機建機・カメラ制振等に組込みタイプ、防滴タイプをラインナップ。検出範囲:±200deg/s(ジャイロ)、±3G(加速度)、出⼒レート:〜2000Sps、計測帯域:DC 200Hz
(ジャイロ)0.0075deg/sec(加速度)0.125mG
24×24×10㎜10g
18mA, Typ, 3.3V
加速度センサ
M-G364PDC0(組込みタイプ)
M-A351A
M-A550T
M-A550A
概要 感度 サイズ/重量 消費電流超小型アナログジャイロセンサ。手ブレ補正システム検出用測定範囲:±100°/s、使⽤温度範囲:-20to +80℃
0.67mV/(°・s-1)Typ. 5.0×3.2×1.3㎜1.7mA Typ.
概要 感度 サイズ/重量 消費電流デジタル出⼒⾼精度ジャイロセンサ。⾞載⽤途向け(カーナビ、テレマティクス)測定範囲:±70°/s、使⽤温度範囲:-40to +85℃
370 LSB/(°/s) ±1.5% 5.0×3.2×1.3㎜3.5mA Typ.
概要 感度 サイズ/重量 消費電流デジタル出⼒⾼精度ジャイロセンサ。産業機器等の制振制御、姿勢制御向け測定範囲:±100°/s、使⽤温度範囲:-20to +80℃(カスタム:-40 to +85℃)
280LSB(°/s)±5%,16bit71680LSB(°/s)±5%,24bit
5.0×3.2×1.3㎜ 0.9mA Typ.
XV3500CB
Xv4001BD
XV7011BB
ジャイロセンサ
121
北陸電気⼯業 ピエゾ抵抗型3軸加速度センサを展開。2008年にデジタル出⼒タイプのピエゾ抵抗型3軸加速度センサHAAM-372を製品化、外形寸法を3.0mm×3.0mm×1.0mm Max と世界最小クラスサイズにとどめるとともに、0.2mA Typ(通常測定モード)の低消費電⼒を実現したことで、⼀時期ゲーム機等で採用された。
表 北陸電気⼯業 加速度センサのラインナップ
出所:北陸電気⼯業資料
TDK 2016年12月、米InvenSense を買収することを発表。2017年9月を目途にInvenSense を完全子会社化する予定である。 InvenSense は、慣性センサ、加速度センサ、ジャイロセンサなど各種センサおよび制御ソフトウェアの開発、製造、販売を手掛けており、特にスマートフォンやウェアラブル機器、ゲーム機、カメラの手振れ補正などの分野で強い。また、6 軸慣性センサ市場でのシェアは 6割を超える。TDK は中期経営計画において、⾃動⾞、産業機器、エネルギー、ICT を重点分野に掲げ、「センサ/アクチュエータ」、「エネルギーユニット」、「次世代電⼦部品」を中期的に成⻑させる製品と位置付けていた。 TDK は InvenSense買収の狙いとして、非光学式センサの製品ポートフォリオを拡充すること、InvenSense が強みを持つ慣性センサ技術を獲得することで、センサフュージョンなど、顧客のニーズによりマッチした製品を提供すること、TDK の販路や、Qualcomm と設⽴した合弁会社である RF360 Holdings Singapore を活用することで、InvenSenseの製品を、ICTや⾃動⾞、産業機器の各市場に向けて拡大していくことを挙げている。
概要 感度 サイズ 消費電流ピエゾ抵抗型3軸加速度センサ。検出範囲:±3G、使⽤温度範囲:-25〜+75℃、アナログ出⼒
330mV/g 3.0×3.0×1.0㎜ 0.35mA(Typ,Vdd=3.0V)
概要 感度 サイズ 消費電流ピエゾ抵抗型3軸加速度センサ。検出範囲:±2G、使⽤温度範囲:-25〜+75℃、アナログ出⼒
400mV/g 3.0×3.0×1.0㎜ 0.35mA(Typ,Vdd=3.0V)
加速度センサ
HAAM-346A
HAAM-346B
122
図 TDK InvenSense買収を踏まえたセンサ事業の今後の展開
出所:TDK資料 Analog Devices 同社は、様々な消費電⼒、ノイズ、帯域幅、温度仕様を組み合わせた、広範な加速度センサーのポ
ートフォリオを構築。オンチップで集積化したシグナル・コンディショニング機能にも特⻑を持つ。 2017 年には、ベアリング不良など機械故障の⼀般的な原因の早期検出に必要な、⾼分解能の振
動計測を可能とする、高周波MEMS加速度センサーADXL1001、ADXL1002を発表している。 ADXL1001/ADXL1002 は、2 つのフルスケール・レンジ・オプションを使用して広い周波数範囲にわ
たり超低ノイズ密度を実現したもので、⼯業⽤の状態監視に最適としている。ADXL1001(±100 g)および ADXL1002(±50 g)のノイズ密度は、それぞれ 30 µg/√Hz、 25 µg/√Hz(代表値)。安定性と再現性のある感度を備え、最⼤ 10,000 g の外部衝撃に耐える。また、⾼度なシステム・レベル機能を可能にする充実した静電気セルフ・テスト(ST)機能とオーバーレンジ(OR)インジケータが内蔵されている。 また、同社は同時期に、業界最先端のノイズ、全温度範囲にわたる最⼩オフセット・ドリフトを実現した
3軸MEMS加速度センサ「ADXL356/357」も投入している。アナログ出⼒のADXL356とデジタル出⼒のADXL357は低ノイズ密度、低0 gオフセット・ドリフト、低消費電⼒の3軸MEMS加速度計で、測定範囲は選択可能。ADXL356Bは範囲±10 g と範囲±20 gをサポートし、ADXL356Cは範囲±10 g および範囲±40 gをサポート、ADXL357は±10.24 g、±20.48 g、±40.96 gの範囲をサポートしている。いずれにおいても⻑時間安定性を提供し、最⼩のキャリブレーションで⾼精度なアプリケーションを可能にしている。ターゲットとする用途は、慣性計測ユニット(IMU)/姿勢方位基準装置(AHRS)、プラットホーム安定化装置、構造の健全性モニタリング、地震画像処理、傾斜検知、ロボット、
123
Kionix 2009年11⽉、同社はロームに買収され、それ以降はロームグループとして事業を展開している。同社は、⾼性能、低消費電⼒の加速度センサ、ジャイロスコープ、6 軸複合センサに加え、幅広いセンサの組み合わせ、オペレーティングシステム、ハードウェアプラットフォームをサポートする包括的なソフトウェアライブラリを提供している。特⻑的な製品としては、2x2x0.9mm加速度センサやKMX61Gデバイスがある。この小型加速度センサは⾼さわずか 0.7mmで、フル機能を備えた、低消費電⼒のセンサとなっている。KMX61G デバイスは、統合センサ フュージョン ソフトウェアと自動較正アルゴリズムで強化された、高性能かつ低消費電⼒の地磁気/加速度センサデバイスで、業界でも有数の正確なジャイロエミュレーションが可能となっている。 同社は 2017 年 2 月、3 軸の±2g、±4g、±8g、または±16g シリコン微細加⼯加速度センサ「KXTJ3-1057」を発表している。センサエレメントは、ガラスフリットを使用してデバイスに第2シリコンふたウェハを接合することで、ウェハレベルでハーメチックシールされたもので、Kionix独自のプラズマ微細加工プロセス技術が活かされている。 同製品は、2mm x 2mm x 0.9mmLGAプラスチックパッケージで提供され、1.71VDC〜3.6VDC
電源で動作。電圧レギュレータは、⼊⼒電源電圧範囲にわたって⼀定の内部動作電圧を維持するために使用される。この結果、⼊⼒電源電圧範囲にわたって安定した動作特性や実質的に検出できないレシオメトリック誤差を実現した。「KXTJ3-1057」の主な特⻑は以下の通り。Kionix では同社の主⼒製品である 3 軸加速度センサ「KTXTJ2」の次世代モデルと位置付けており、スマートフォン、タブレットおよびPC、ウェアラブルデバイス、IoTデバイス、ゲーム、玩具、タグなどへの拡販に取り組んでいく方針である。 小さなフットプリント:2mm x 2mm x 0.9mm LGAパッケージ 低消費電流:スタンバイで0.9µA、低電⼒で10μA、高分解能モードで155μA 広い電源電圧範囲:内部電圧レギュレータで1.71V〜3.6V 拡張されたユーザー構成可能g範囲:±2g、±4g、±8g、または±16g 最大3.4MHzのI2Cデジタル通信インターフェース 最小3.9mgに構成可能な閾値を備えた高分解能ウェイクアップ機能 0.781Hz〜1600Hzのユーザー構成可能出⼒データレート 設計を向上し、ポストリフローオフセットおよび感度シフトを実質的に排除 ⾼度に構成可能な割り込み制御 RoHS/REACH対応 一方、ロボットや産業機械の姿勢制御、プラットフォームの安定化、モーション制御、振動検出向けには、デジタル I²C 出⼒の低消費電⼒・⾼性能 3 軸加速度センサ「KXTIK シリーズ」を展開している。同製品は、8 ビット/12 ビットのモード、± 2g/4g/8g の g レンジ、12.5 Hz〜800 Hz の出⼒データレートなど、ユーザー選択可能なパラメータを特徴に持つ 3 軸加速度センサ「KXTIK-1004」等の 3×3×0.9mm ピンパッケージの製品を提案している。また、プラットフォームの安定化、振動検出では、5×5×1.2mmアナログ出⼒の「KXR94シリーズ」を中心に展開している。
126
MEMSIC MEMSセンサIC開発とMEMS技術をベースとしたセンサシステムソリューション、ワイヤレスセンサーネットワークソリューション開発を得意する MEMSIC は、独⾃の熱検知⽅式を採る加速度センサを展開している。熱検知方式は、他の方式と比較し、振動の影響を受けない、耐衝撃性に優れる、動作ノイズがない、優れたゼロg オフセット安定性といった特⻑を有している。
表 MEMSIC 加速度センサ 製品バリエーション
出所:MEMSIC資料
NXP Semiconductor 加速度センサ、回転速度センサ、温度センサ、⾓度センサ、圧⼒センサ、ジャイロスコープ、6 軸センサ、タッチ・センサ、磁気センサ、静電容量センサで構成されたセンシング・ソリューション・ポートフォリオを展開。加速度センサは MMAxxx ファミリ等、ジャイロスコープは FXAS21002C、6 軸モーションセンサは「FXOS8700CQ」を展開している。 加速度センサは、⾞載向けの MMAxxx ファミリ(1 軸/2 軸)に加え、IOT 業界向けに低 g レンジ(〜20g)、小形パッケージの 3 軸加速度センサ「FXLC95000CL」、「FXLN8361Q」等を提案している。「FXLC95000CL」は、32bit ColdFire MCU と3軸の低ノイズ加速度センサ(±2 g, ±4 g, ±8 g/16bit分解能)からなるインテリジェント/モーションセンシングプラットフォームとして提供、自動で⾼精度なセンシング及びセンサマネジメントが可能な点を訴求している。 「FXLN83xxQ」は、低消費電⼒、低gレンジ、アナログ出⼒の3軸加速度センサで、CMOS signal
conditioning & control ASICを内蔵したQFNパッケージ(3x3x1mm)で提供されている。
127
ジャイロスコープ「FXAS21002C」は2015年より展開しているもので、低い電⼒動作(アクティブモード Idd=2.7mA)を提供し、競合するソリューションに対してシステムレベル電⼒の大幅な削減を可能にする⾼度な組み込み機能を統合。最⼤±2000°/秒のフルスケール範囲を測定することができ、最大800Hzの出⼒データレート(ODR)を備える。NXPでは、ゲームコントローラ、電子コンパス安定化、強モーション制御向けジャイロスコープとして展開しているほか、加速度計および地磁気センサから構成される6軸ソリューション(3軸加速度+3軸ジャイロ及びASICで構成された「FXOS8700CQ」)にも同センサを組み込んでいる。
表 「FXAS21002C」の仕様
出所:NXP資料
Bosch Bosch Sensortecが加速度センサ及びジャイロスコープを展開している。 加速度センサはMEMSベースの「BMAファミリ」を展開している。12bit, 14bit, 16bitのデジタル加速度センサを主⼒として構成、いずれも⼩形・薄型のLGAパッケージで提供している。 Bosch は 2018 年 1⽉より超低消費電⼒タイプの加速度センサ「BMA400」を販売開始している。性能自体は、計測レンジ:±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g、分解能:12bit、ODR(output data rate):12.5Hz〜800Hz、ノイズ:Max. performance: < 220 μg/√Hz、Typical use case: < 320 μg/√Hz、Low power: < 600 μg/√Hz と従来のものと同等レベルでありながら、消費電⼒はMax. performance: 14 μA、Typical use case: < 8 μA、Low power use case: < 4 μA、Ultra low power/Auto-wake-up mode800 nA @ 25 Hz ODR と従来の1/10程度まで低減している。同社では、消費電⼒に対する要求の厳しいウエアラブルデバイス、IOTアプリケーション向けに需要開拓を進めていく⽅針である。なお、同製品は、CES 2018 Innovation Awardを受賞している。
128
図 新たな加速度センサ「BMA400」
出所:Bosch資料
ジャイロスコープは、BMG ファミリを展開している。主⼒グレードである「BMG250」は、16bit 分解能、125°/s〜2000°/s (dps)のフレキシブルな計測レンジを持つ、超小形、デジタルの 3 軸ジャイロセンサである。低ノイズの計測が可能で、低消費電⼒を売りにしている。実際、スマートフォン、タブレット、カメラモジュール、ヘッドマウントディスプレイ等で多く採用されている。 STMicroelectronics 同社では、最大±400gの測定範囲、1.71 ~ 3.6Vの電源電圧範囲を特徴とするアナログおよびデジタルのMEMS加速度センサを展開している。優れた省電⼒機能を備えており、スマートフォンや情報端末などの超低消費電⼒アプリケーションで強みを⾒せる。また、同社は、次世代の加速度センサとして、パッケージ・サイズ:2 x 2 x 1mmの超小形タイプを発表している。 加速度センサのポートフォリオには、広範な温度範囲と AEC-Q100 認定を取得した AIS32x ファミリ
に加え、リリースから10年間にわたり製造が続けられているSTの⻑期供給プログラムに対応したIISxxx製品などの⾞載⽤加速度センサが含まれている。 また、ジャイロセンサについても、幅広い製品群(30〜4000dps のフルスケールレンジ)を特⻑として
おり、いずれも0.01 dps/√Hz以下の分解能、⻑期安定性、ロバスト性を備える。
129
図 STMicroelectronics 加速度センサのポートフォリオ 出所 STMicroelectronics資料
図 STMicroelectronics ジャイロセンサのポートフォリオ 出所 STMicroelectronics資料
130
距離センサ(光電センサ、超音波センサ) ①技術概要
● 光電センサ 光電センサは、光のさまざまな性質を利⽤して物体の有無や表⾯状態の変化などを検出するセンサで、光を出す投光部と光を受ける受光部から構成されている。投光された光が検出物体によってさえぎられたり反射したりすると、受光部に到達する量が変化する。受光部は、この変化を検出して電気信号に変換し、出⼒している。赤外光以外にも、可視光(主に⾚、⾊判別⽤に緑、⻘)が使用されているケースもある。 特⻑としては、検出距離が⻑い、検出物体に対する制約が少ない、応答時間が短い、分解能が高い、
非接触で検出が可能、色の判別が可能、調整が容易等が挙げられる。 光電センサの検出方式としては、透過形、拡散反射形、回帰反射形がある。透過形は動作の安定
度が⾼く、検出距離が⻑い(数 cm〜数十 m)、検出物体の通過経路が変化しても検出位置は変わらない、検出物体のツヤ・色・傾きなどの影響が少ない等の特⻑がある。拡散反射形は、検出距離は数 cm〜数 m、取りつけ調整が容易、検出物体の表⾯状態(⾊、凹凸)で光の反射光量、検出安定性が変わり、距離も変化する。 一方、回帰反射形は、検出距離は数 cm〜数 m、配線・光軸調整が容易(⼯数が省ける)、検
出物体の色、傾き等の影響が少ない、検出物体を光が 2 回通過するため、透明体の検出に向く。ただ、検出物体の表面が鏡面体の場合、表面反射光の受光により、検出物体が無い状態と同じになり、検出できないことがある、近距離で不感帯をもつといったデメリットがある。検出物体(⼤きさ、透明度、移動速度)、センサ(検出距離、取付制限)、環境(周囲温度、⽔、油、薬品などの⾶散の有無)等から検出方法が選定される。 <透過形>
出所:オムロン資料
131
<拡散反射形>
<回帰反射形>
出所:オムロン資料
● 超音波式 超音波式センサは、超⾳波を使⽤して距離を測定するセンサ。センサヘッドから超⾳波を発信し、対
象物から反射してくる超⾳波を再度センサヘッドで受信します。超⾳波式センサは、発信から受信までの「時間」を計測することで対象物までの距離を測定することができる。光学式センサには投光部と受光部の 2 つがあるが、超音波式センサは 1 つの超⾳波素⼦が発信と受信の両⽅を⾏う。反射型の超音波式センサでは、1 つの振動⼦が発信と受信を交互に⾏なうため、センサの小型化が可能である。 超音波式センサの特⻑としては、透明体の検出が可能、ミスト・汚れに強い、複雑な形状の検出体でも検出可能などが挙げられる。
表 光学式及び超音波式の比較
出所:オムロン
132
②用途 光電センサは、主に物体検知用のセンサとして産業全般で幅広く使用されている。ボリュームゾーンとし
ては、半導体・液晶関連、⾃動⾞関連、電気・電⼦関連が挙げられるが、⾷品⼯場、医薬品⼯場等での導⼊が進んでいるほか、流通等の新たな分野での需要も⽴ち上がっている。 一方、超音波センサは、侵入者警報装置や自動ドアなどの物体検知、あるいは⾃動⾞の後⽅検知
装置などの距離計測に⽤いられることが多く、その他、魚群探知機や潜水艦のアクティブソナーとしても使用される。また、最近は物体検知⽤に産業⽤ロボット等の産業⽤としても利⽤されるようになっている。
表 光電センサの用途
出所:オプテックスエフエー資料
133
③国際市場規模及び日本企業のシェア ④国際市場規模の将来予測 ● 光電センサ 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)のセンサ・グローバル状況調査では、光電センサの世界市場規模を 530億円(2016年)と推計している。また、⽇本企業のシェアは 20%となっている。既存用途に加え、IO-LINK対応等の通信機能を搭載したモデル開発が進展、IOT関連の需要拡⼤も期待されていることから、光電センサの世界市場規模は今後も⾼い成⻑率(*2017 年〜2021年、CAGR:8%)で拡大していくことが予想される。 ソース:Orbis Research「Photoelectric Sensors in Global Market 2017 by Type,
Sensor System, Technology, Drivers & Strains, New Innovations, Applications and Forecast to 2021」 ● 超音波センサ 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)のセンサ・グローバル状況調査では、超音波センサの世界市場規模を180億円(2016年)と推計している。また、⽇本企業のシェアは17.0%としている。超音波センサは、センサや設備を含めた工場内のあらゆる機器をインターネットに接続し、品質・状態などの様々な情報を「⾒える化」する“スマートファクトリ”の中で、使い勝手のよい物体検知ツールとして普及していくとみられており、今後もCAGR(2016年〜2023年):10%以上の需要成⻑が期待される。 ソース:Crystal Market Research「Ultrasonic Sensors Market by Product and Application - Global Industry Analysis and Forecast To 2023」 ⑤各用途に求められる技術特性 光電センサ、超音波センサは、物体検出用のセンサとして FA 分野での利⽤が拡がる中で、通信機能の追加が進展している。また、セイフティレーザスキャン、セイフティライトカーテンといった侵入検知用センサとしての応用も進んでいる。同用途は作業環境の安全性確保が厳しく問われる中、需要が順調に拡大しており、距離センサの新たな⽤途として注⽬されるようになっている。ここでは、検出性能に加え、小型・軽量化、堅牢性などが重要視されている。 ⑥国内企業 ● 光電センサ 光電センサの主要メーカーとしては、オムロン、キーエンス、パナソニックSUNX、オプテックス・エフエーが挙げられる。国内市場シェア(2016 年)で⾒ると、オムロン:40%、キーエンス:20%、パナソニックSUNX:12%強、オプテックス・エフエー:10%強と⾒られる。 *YRI推計
134
オムロン 同社光電センサーのアンプ内蔵形は、業界トップクラスの検出距離、冷凍倉庫でも使⽤が可能な低
温動作保証、配線間違いが起こってもセンサーを保護、欧州 RoHS 指令完全適合が特徴となっている。 また、2016年7月には、次世代光電センサ(E3Zシリーズ及びE3S)も含んだIO-Link 対応機器として、スクリューレスクランプ端子台・M12 スマートクリックコネクタの 2 種類のマスタと、それぞれに対応する各種センサーを発売した。背景にはセンサとコントローラーを IO-Link マスタで接続することで、ON/OFF信号だけでなく受光量など安定稼働のために必要な情報を可視化することにある。オムロンでは、個体識別による⼯数削減、センサーの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急メンテによる設備稼働率向上、光電センサの光量不安定状態を事前把握や、突発停止を削減できるなどのメリットを提案している。 キーエンス 同社はアンプ分離型光電センサ、アンプ内蔵型光電センサを中核として光電センサ事業を⾏っている。
アンプ分離型は、ボタンを⼀回押すだけで、「感度設定」と「表⽰統⼀」を同時におこない、誰でも確実・簡単に感度設定ができ、誰が⾒ても同じ状態把握ができるために簡単に予防保全が可能であるなどの利便性がある。最⼤検出距離6mのハイパワータイプや、耐環境性を高めるためにPFAケースで覆われたタイプ、背景の影響をさける距離限定反射タイプなど、特徴的なセンサヘッドバリエーションを用意している。 アンプ内蔵型 LR-Z シリーズの特性は堅牢⻑寿命で⾊や傾きの影響を受けない汎⽤レーザセンサである。具体的には「CMOS イメージセンサ+レーザ光源」の組み合わせにより、ワークまでの距離で検出することが可能であり、センサが受光量をモニタし、受光量レベルが最適な状態になるように光量コントロールしている。調整幅は最大200万倍である。これにより、⿊・⾦属ワークを確実に検出できる。 さらに、「背景チューニング」により、ワークまでの距離と受光量で検出することが可能である。背景までの距離と受光量を登録し、それ以外の状態に変化すれば検出し、薄いワークや透明ワークにも対応することができる。その他ではアンプ中継型ミニ光電センサ、AC/DC フリー電源センサ、超小型アンプ内蔵型光電センサなどを上市している。 パナソニック SUNX 同社はアンプ内蔵型光電センサを中⼼に、アンプ分離型光電センサも販売している。基本製品である
小型ビームセンサ(アンプ内蔵)「EX-Zシリーズ」は、2016年6月同社製品で、ワイヤボンディングなしで実装可能な新しい半導体パッケージ技術を応用し、世界最薄の 3mm ボディ、スリットなしで微小物体 ø0.3mmを検出可能となっている。 具体的な用途として、パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LED のリード検出などを上げている。価格は8,500円から9,500円である。分離型では、操作の簡易性を追求、取り付けスペースを大幅に削減する薄さ 10mm のスリム性を訴求している。用途はリードフレームの位置決め、チップ
135
部品の表裏判別、ICの高さ検出、洗浄液の入った石英槽内のウェーハカセット検出などを上げている。 オプレックス・エフエー 同社は 2002 年 1 月、オプテックス株式会社の産業用光電センサー事業部門を分社化。京都市山科区にオプテックス・エフエー株式会社として設⽴した。1989 年 4 月には SICK GmbH(現、SICK AG社)とオプテックス株式会社が汎⽤型光電センサの開発を⽬的に合弁(出資⽐率50:50)にてジックオプテックス株式会社を京都市下京区に設⽴している。また、2011年3⽉三菱電機株式会社と産業機器用制御装置分野で協業を開始した。 同社光電センサー事業売上の半数はSICK AG社へのOEMであり、残りの半数が同社から日本マーケットへの販売となる。SICK AG社向け製品は、SICK AGのニーズを満たすローコスト製品が主軸となっており、同社から販売する製品は主に食品、医薬品など主に三品業界で、有効な作用を果たす光電センサが主軸となっている。 オプテックス・エフォー開発部は、当社基幹の開発部⾨として、画像センサー及び画像処理⽤ LED 照明を中心に開発。カメラ・照明・コントローラー・モニターが一体化したオールインワンタイプの画像センサや業界No.1 の印字検査用画像センサ、明るさを⾃動で管理する業界初のセンシング LED照明など、オンリーワンで競争⼒ある製品開発を⾏っている。ジックオプテックスは、最先端のセンサ技術が集積する日本市場での技術動向を踏まえ、短期間での開発が可能な強みを活かし、主に光電センサ・レーザ変位センサの開発を担っている。 同社新製品「FASTUS TOF-DLシリーズ」は、TOFセンサとして世界最小サイズを実現した。 2.5mまでの測定が可能な超⼩型レーザ距離センサである。特性はデジタルパネルの搭載により設定が簡単に⾏え、製造現場におけるループ制御やレベル測定、位置測定など、物体の⾼さ・距離に応じた制御を必要とする用途に強みがある。今後の期待できる需要分野としては物流やロボット、⾷品⽣産オートメーションなどを挙げている。また、特殊用途として、基板検出専用や耐薬品、コンベアの制御、エッジコントロール、幅測定などがある。 ● 超音波センサ 超音波センサを手掛ける日本企業としては、日本セラミック、村田製作所、デンソー、オムロン等が挙げられる。 日本セラミックは、振動子に圧電セラミックを用いた開放型、密閉型の超音波センサを幅広く展開して
おり、カスタム対応も⾏っている。⽇本国内の市場では⾼いシェアを有しているものとみられる。 村田製作所は、独自の圧電セラミック技術により、小型・高性能の空中超音波センサを商品化している。空中超⾳波センサは、⾦属板と圧電セラミックスを貼り合わせた構造の振動⼦に共振⼦を結合した複合振動体をベースに弾性固定し、ケースに収納した構造を採る。この振動子、共振子の設計・マッチングに同社の技術が活かされている。 製品ラインナップとしては、スキャナ、プリンタ、ATM などの紙葉重送検知⽤途に特化した⾼周波型超
音波センサのほか、開放型超音波センサ「MA40S4R」、「MA40S4S」、防滴型超音波センサ(自動
136
⾞⽤)がある。産業⽤として利⽤可能な「MA40S4R」は、使⽤温度範囲:-40℃〜85℃、中心周波数:40kHz、感度:-63dB typ. (0dB=10V/Pa)、指向性:80° (typ.)、静電容量:2550pF、静電容量公差:±20%。⼩型・軽量、⾼感度・⾼⾳圧が特⻑で、⾃動⾞⽤途(インフォテインメント)のほか、物体検知、距離計として幅広く使⽤されている。 オムロンは距離センサとして、レーザ式、LED式、超⾳波式、接触式、渦電流式などを幅広くラインナッ
プしており、そのうち、超音波センサは、デジタルアンプ分離式超⾳波センサ「E4C」、小型透過形超音波センサ「E4E2」を展開している。 「E4C」は、小型円柱ヘッドで、サイドビュータイプも品揃え、検出物体の距離と、検出位置(しきい値)
が、デジタル表示で分かる、ワーク有無の設定、背景の影響除去を簡単に設定できる(ティーチング機能)、アンプユニットにはアナログ出⼒タイプを品揃えといった特⻑を有している。 一方、「E4E2」は、小型アンプ内蔵タイプ、⼩型コンベアラインにも設置が容易、検出距離 500mm、
検出余裕度が確認できる安定表⽰灯付。小型透過形であるため、透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる点を訴求している。
表 オムロン 超音波センサ「E4Cシリーズ」製品ラインナップ
出所:オムロン資料
137
⑦海外の主要な競合企業 ●光電センサ 主な海外企業としては、Balluf(独)、SICK(独)、Schneider(仏)、Baumer(スイス)、
AVAGO(シンガポール)、Autonics(韓)等が挙げられる。 Balluf 同社は、ドイツに本社を置くセンサメーカーである。センサ分野で50年以上の実績があり、距離測定技術や、様々なファクトリーオートメーション分野における配線システムを開発してきた。世界市場展開の一環として2007年8⽉から⽇本でも⽀社としての展開を始めた。ドイツではメルセデスベンツなど有⼒自動⾞メーカへ部品供給を⾏い、⽇本でも⾃動⾞産業へのビジネスに注⼒している。 同社はインダストリー4.0 コンセプトにおける IO-Link準拠次世代光電センサの普及活動を2011年頃より始めた。2015年には認知度も⾼まり市場がゆっくりであるが⽴ち上がってきている。 現在の主流となっている光電センサは、基本的に「モノ」が有る無を判断するセンサである。次世代光電センサは計測的機能も果たすのが特徴である。位置関係の把握、ホコリなどの診断機能などがあり、それらの情報を上位ネットワークへと伝えることができる。また、どこのメーカーのどのセンサを利⽤しているのかが判別可能である。具体的には装置を止めての検査や定期的な掃除が必要なくなるというメリットがある。 同社IO-Linkインタフェース付き光電距離センサは、精度と効率を同時に追求したコンセプトとしている。頑丈な⾦属製ハウジングを備え、最⻑ 6 m までの距離範囲で動作。検出された距離は IO-Link インタフェースを介して出⼒。更に IO-Link モードでは、快適にコントローラーによって両スイッチポイントから設定したり、レーザーをオフにしたり、ボタンをロックすることが可能である。動作原理は、光線の伝播時間による測定原理により、三⾓測量法によるセンサやエネルギー量を測定する光電センサの場合よりも⻑い検出距離となる。 このセンサ技術は、従来の⼿法では技術やコストの⾯で障害となっていたアプリケーションにおいて利⽤
可野である。具体的には、遠く離れて小さな対象物を検出するケース、また「外部から」高温のプロセス内部やロボットセル中に接触する必要がある場合など、周囲環境の条件が厳しい中での使用が可能となっている。 今後期待される需要分野としては、モデルチェンジタイムが短く必要な設備投資には積極的な⾃動⾞産業、省⼈化をキーワードとする産業⽤ロボット、海外輸出も増加し包装や輸送時破損における安全性を重視する⾷品関係、更に⾼齢化及び介護スタッフの⼈員不⾜における介護ロボット産業⽤途などが挙げられる。同社の製品上の強みとしては、堅牢性、製品ラインアップの充実、光や超音波、磁気、静電容量など多様な検出技術があることを挙げている。
139
SICK 同社は光電センサについて、光学技術等の先進技術を活かした幅広い製品群を展開、最近は
ASIC技術(SIRIC)、LED技術による機能信頼性をユーザーに訴求している。 SIRICは、同社が独自に開発したセンサASICで、光電センサにデジタル信号処理を導⼊している点
が特⻑となっている。これにより、検出距離と⾛査距離が向上、外乱光および他のセンサからの光に対する耐性も高まったとしている。また、スマートセンサソリューションとして、これらのセンサをシームレスにオートメーションネットワークに統合することもできる。同社では、現在 IO-LINK 対応の光電センサ拡充を進めており、光電センサのメインラインである50種のうち、16種類についてはIO-LINK対応となっている。 Schneider Electric 同社では、光電センサを OsiSense XU として展開している。拡散、BGS(Background suppression)、再帰反射、透過の4つのフォームファクタに対応、マテリアルハンドリング、ラベリング、組⽴、⾷品・飲料などのカテゴリーで実績を積んでいる。 ラインナップとしては、直径 18mm の「XUB」(検出範囲:〜20m)、ミニチュアサイズの「XUM」
(同15m)、コンパクトタイプの「XUK」(同45m)及び「XUX」(同60m)等がある。1つのリファレンスでそれぞれのフォームファクタに対応できるマルチモード機能を搭載、セットアップ、メンテナンスの手間を最小限に抑えることができる点も売りの1 つとなっている。 Baumer 同社は、物体検出用に光電センサ「M18 Industrial standard」及び「M18 stainless steel sensors」を展開している。検出範囲は〜55m、レスポンス時間は 0.34ms以下となっている。光源は、標準のLEDのほか、Baumer PinPoint LED、赤外線LED、レーザ(Class 1)をラインナップ。レーザは小物部品の検出に最適としている。 Autonics 同社は、アンプ内蔵型、円柱型(BR シリーズ)、フォトマイクロセンサ(BS5 シリーズ)、U 字型(BUP シリーズ)等、幅広い製品を展開している。アンプ内蔵型は、強⼒センシング性能と超小型アンプ内蔵型の「BTSシリーズ」をはじめ、BGS検出方式を採用し、背景物体の影響を最小化した「BTFシリーズ」、超小型直接反射形の「BYDシリーズ」等がある。 2017年11月に発表した「BTSシリーズ」は、同社が独自に開発した高性能ワンチップフォト ICを採用。超小型サイズを実現することにより、生産ライン狭所スペースを活用した設置が可能となっている。主な特⻑としては、超小型サイズ実現で設置スペース最小化、最小0.15mmの微小物体検出、保護構造 IP67実現で粉塵及び洗浄、散水環境でも使用可能、最⼤検出距離1m(透過型)、検出 Spotの位置確認 (限定距離反射型、ミラー反射型)、動作表示灯、安定表示灯採用などとなっている。
140
● 超音波センサ 主な海外企業は、Honeywell(米)、Roclwell Automation(米)、Baumer(スイス)、
P+F(独)など。Honeywell(米)は、「940 シリーズ」を主⼒に超⾳波センサを展開している。同シリーズは、18mm のコンパクトなデジタル超音波センサで、センシングレンジ:200〜1500mm 及び150〜700mmの2 タイプをラインナップしている。
表 Honeywell 超音波センサ「940シリーズ」の仕様
出所:Honeywel資料
Rockwell Automation(米)は、Allen-Bradleyのブランドで超音波センサを展開している。同セ
ンサは、固体や液体の非接触検知を目的として設計された内蔵式のソリッドステート装置で、さまざまな検知範囲およびスタイルをラインナップしている。 「Bulletin 873C」(近接型超音波センサ)は、最大1 mの距離から固体および液体のターゲットを
検出するもので、アナログ電圧出⼒を備えた背景抑制ユニット、およびデジタル出⼒を備えた標準拡散モードという2 つのバージョンを取り揃えている。 「Bulletin 873E RightSound」(透明体超音波センサ)は、センダおよびレシーバで構成される対
⽴モードセンサで、レシーバはマイクロプロセッサベースであり、優れた温度安定性およびノイズイミュニティを備える。センダボリューム制御では、アプリケーションの検知距離およびその他の変数の量を調節可能となっている。 「Bulletin 873M」(汎用超音波センサ)は、音波を用いて固体や液体の対象物を検知するよう設
計。これらのコンパクトなセンサは、スペースが限られた場所でも使用できる高い柔軟性を備えており、標
141
準的な梱包や組⽴アプリケーションに最適となっている。同センサであれば、光電センサでは検知が困難な対象物(透明または光沢のあるもの、非反射物質など)でも検知可能である。このほか、簡単な押しボタン式セットアップを採用した「Bulletin 873P」(アナログ/ディスクリート出⼒超⾳波センサ)などがある。 Baumer(スイス)は、柔軟な物体検出センサとして高速、小型、ロバスト性に優れる超音波センサを幅広く展開。近接スイッチ(測距、スタック高測定)、再帰反射(形状等の判定、物体検出)、ビーム透過(高速検出、透明対象等の検出、透明性のモニタリング)等の検出方法を用いた用途提案を⾏っている。 主⼒モデルの1つである「U-500」は、センシング範囲:1,000 ㎜のスタンダード品であるが、信頼性、操作性に対するユーザーの評価が高いとしている。また、High-speed sensors はレスポンス時間がわずか1.3msと光電センサ等の競合技術と比較してもそん色のないレベルで、他社にはない製品と同社でも位置付けている。なお、High-speed sensors はセンシング範囲:70mm、検出精度(垂直/水平):0.5mm。小径ノズルを採用することで、φ3mm までの小さな物体も検出できる仕様となっている。
図 Baumer 超音波センサの製品バリエーション
出所 Baumer資料
142
図 Baumer 超⾳波センサの⽤途例
出所 Baumer資料 PEPPERL+FUCHS(独)も超⾳波センサの幅広い製品群を特⻑としている。同社はスペイン
Agrobot が開発するイチゴ収穫⽤全⾃動ロボットシステムに様々な形で協⼒、収穫⽤アームが地⾯にぶつからないようにするための衝突制御システムにロバスト性に優れた超音波センサ(UB400-12GM)を提供しているほか、収穫マシーンの⾃動運転を⽀援する距離検出⽤にも超⾳波センサが使⽤されているとしている。
図 P+F 超音波センサのバリエーション
出所:P+F資料
143
⼒センサ ①技術概要及び②用途 ⼒センサには⼒覚センサ、ロードセルなどがある。⼒覚センサは、⼒とトルク(モーメント)の大きさと方向を
3次元空間ベクトルで⽰すセンサである。各軸⽅向の⼒成分をFx、 Fy、 Fz で示し、各軸回りに作用するトルク成分を Tx、 Ty、 Tz で示すといった合計 6 軸⼒を測定するものが⼀般的である。用途に応じて 3 軸⼒、4 軸⼒⽤などの⼒覚センサも使われる。また、検出⽅式にはひずみゲージ⽅式、静電容量⽅式、圧電⽅式などがあり、現在はひずみゲージ⽅式の⼒覚センサが多⽤されている。 ひずみゲージ方式 起歪体表面にひずみゲージを貼り付け、負荷される⼒により起歪体が変化した際(ひずみを生じた時)のひずみゲージの電気抵抗変化量を軸⼒毎に検出する。ひずみを発生させる起歪体は、ロードセルなどの単軸の荷重変換器と異なり、6 軸⼒が同時に負荷されるにもかかわらず、各軸⼒をそれぞれ分離して検出する必要があるため、特殊な構造が採られている。干渉を減らす起歪体構造、干渉を減らすひずみゲージの配置などを採⽤し、さらに、出荷時の試験データを⽤いた⼲渉補正処理を⾏うことにより、精度向上が図られている。 静電容量⽅式 ⼒の印加によるダイアフラムの微⼩変形を静電容量の変化として検出する。この⽅式には、部品点数が少なく組み⽴ても⽐較的簡単という利点がある。 圧電方式 ⼒の印加により分極し、電荷が発⽣する物質(ピエゾ素⼦、⽔晶など)を⽤いる。動剛性を大きくできるため、急速な⼒の変化に対応でき、ダイナミックレンジを⼤きくできる。 ⼒覚センサは、ロボットや産業オートメーション機器、⾞体安全装置、医療システムなどの分野で採用
が広がる傾向にある。最近では、機構部品の製法を従来の切削加⼯と同様の精度を確保しつつ、量産化に適したプレス加工に置き換えることで大幅な低価格化(従来製品の 1/3 程度)を実現した静電容量⽅式の⼒覚センサも製品化された。センサは板状部品を積み重ねた構造となっており、従来の薄板精密打ち抜き加工を発展させ、厚板ステンレス鋼板の総せん断の打ち抜き加⼯⽅法を確⽴している。現在、産業用ロボットへの導入が進んでいる。
145
静電容量⽅式⼒覚センサの構造と外観
出所:ワコーテック資料
また、圧電⽅式ではセイコーエプソンが⾼剛性であるとともに、センシング技術を⽤いた⾼感度な⽔晶
圧電方式により0.1Nとわずかな⼒を感知できる⼒覚センサを2016年6月に市場に投入した。価格は69万〜72万円(税別)で、6軸ロボットやスカラロボット各種向けに6種類を揃えている。 ロードセルとは、⼒(質量、トルク)を電気信号に変換して出⼒するセンサであり、荷重変換機とも呼
ばれる。測定しようとする⼒を弾性体の変形(たわみ、ひずみ)などに変換し、さらに、変形量を電気抵抗、静電容量、圧電、光などの各変化で検出し、あらかじめ定めた校正曲線によって⼒を決定する。なかでも、電気抵抗変化を利⽤したひずみゲージ方式のロードセルが広く普及している。 様々な環境で使⽤されるロードセルには⾼い測定精度、優れた応答性、過酷な条件下の⻑期耐久
性・信頼性などが必要である。ひずみゲージ式の特⻑として、精度が⾼く温度変化の影響が小さい、出⼒が電気信号で⻑距離伝送が可能、計測できる荷重に対し⼩型である、などが挙げられる。主に電子はかり、試験機、流量計、産業⽤はかり、各種測定器などに使⽤されている。 ロードセルで⽤いられる起歪体の材料としてはニッケルクロムモリブデン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合
⾦などがある。要求特性は次のとおりである。 クリープが少ないこと。 直線性が広い範囲で保証される、⽐例限度の⾼い材料であること。 経年変化の少ない材料であるとともに、残留応⼒による形状変化を起こさないこと。 耐衝撃性が高いこと。 加⼯性が良いこと。
146
③国際市場規模及び日本企業のシェア
三菱電機、セイコーエプソン、ビー・エル・オートテック、ニッタ、ワコーテック、⽇本信号、⽇本リニアックス
等の日本企業も数多く参入しているが、全体では⾃動⾞、航空宇宙/防衛での大きな需要を抱える欧米企業のシェアが高いものとみられる。ただ、FA 分野での需要拡大を背景に、同分野で積極的な動きを⾒せる⽇本企業のシェアが⾼まりつつある。
図 ⼒覚センサ 方式別構成比(⾦額ベース)
147
⑤各用途に求められる技術特性 産業⽤ロボットでは、特に⼒覚センサのマテリアルハンドリングへの応⽤が⼤きなテーマとなっている。ハンドリング⾃体はソフトウェアの影響が⼤きいが、⼒覚センサにも繊細なセンシング(⾼感度)、ハイスピード動作、⾼精度、⾼分解能などの要求がある。⼒覚センサメーカーは半導体ひずみゲージ、静電容量、圧電とそれぞれに得意な方式でアプローチしている。
⑥国内企業
● ⼒覚センサ 三菱電機 同社は、電気・電⼦部品や⾃動⾞部品などの組⽴・はめ合い・検査⼯程の⾃動化システムを容易に
実現する、産業⽤ロボット・⼒覚センサーなどと専⽤プログラミングツールをパッケージ化した「MELFA ⼒覚応用アプリケーションパッケージ」を2015年6月より展開している。同パッケージは、独⾃の⼒覚センサーにより、ロボットハンドにかかる微⼩な⼒を検知できるため、従来は、ロボットには難しかったワークの倣い(ならい)・はめ合い作業が可能、ロボット作業のログデータ化により、品質管理や作業ミスの原因解析が可能、⼒覚センサに対応した「RT Toolbox2」が使用でき、簡単にプログラミングが可能といったメリットがある。 また、三菱電機は2017年11月21日、同社のAI 技術「Maisart」を、産業用ロボットのアームを
⼈の腕のように柔らかく動作させる⼒覚制御に適⽤し、動作時間を⼤幅短縮する⾼速化技術を開発したと発表した。熟練者によるロボットへのプログラミングや機器の調整作業を省き、組み付け動作時間を短縮できる。 同技術は、はめあい作業やコネクタおよび基板の挿入作業などの高速化を図ることにより、電気製品、
電⼦製品の組み⽴て⼯程の⽣産性向上が図れる。部品のはめあい作業では、短時間の学習で制御しパラメータを⾼精度に決定、⼈⼿調整時に 5.5秒(反⼒20N以下)だった動作時間を1.9秒(反⼒10N以下)と約3分の1に短縮し高速化を実現した。 従来、⼒覚制御を⾼精度に実施するためには、動作前にロボットを⼀時停⽌して、⼒覚センサに発生するロボットの姿勢によって変化する重⼒など外部の影響を補正する必要があったが、マイサートによりロボットを停止することなく、自動で⾼精度に⼒覚センサ出⼒を補正する。 安川電機 同社は、産業用ロボット MOTOMAN のオプションとして、6軸⼒センサユニット MotoFit を開発し、
2013年1月より発売している。同ユニットは、アーム先端に6軸⽅向からの⼒を検出する⾼精度センサを組み込み、その先に取り付けられるハンドに伝わる微妙な⼒を検出する。ワークを取り扱うハンドの直近にセンサを組み込むことで、繊細なセンシングが可能となり、ワークの接触・はめ合い位置の探り(反⼒が最⼩になる位置)・挿⼊の⼀連の動作が確実に⾏うことが可能としている。 精密部品の組み⽴てでは、⾮常に繊細な⼒加減を要求され、さらにワークの材質・サイズ・重さにより、
150
⼒加減が変わってくる。この微細な⼒加減をロボットにティーチングする⼒覚制御パラメータ⾃動調整機能を準備。画⾯上のガイダンスに沿って操作することで対象ワークに応じた適切なパラメータ設定を容易に⾏えるようになっている。適用コントローラは、YRC1000、YRC1000micro、DX200、FS100。精密かん合機能、⼒倣い・⼒変化検知機能として利⽤が拡がっている。 セイコーエプソン 2016 年6 月、同社 6軸ロボットやスカラロボットのオプションとして、⼒覚センサ「S250」シリーズの国
内受注を開始した。同社の 6 軸ロボット「C4/C8」シリーズと、スカラロボット「G/RS」シリーズに装着できる。 「S250」シリーズは、⾼剛性であるとともに、センシング技術を⽤いた⾼感度な⽔晶圧電⽅式により0.1N(ニュートン)とわずかな⼒を感知できる。このことにより、製造現場での繊細な部品の組み⽴てや、結合部のすき間が少ない部品同⼠のはめ込みなど、⾼精度な技術を求められる作業での⾃動化が可能となった。例えば、個体ごとにネジ⽳位置のバラつきがあった場合でも、ネジ⽳を⾒つけて締めることができるという。⼒加減が難しい⽔平⽅向や斜めのネジ締め作業にも対応している。価格は 69 万〜72 万円で、6軸ロボットやスカラロボット各種向けに6種類をそろえた。
図 ⼒覚センサ S250 シリーズ 出所:セイコーエプソン資料
表 ⼒覚センサ S250 シリーズの仕様
151
出所:セイコーエプソン資料
ワコーテック 同社は、静電容量型の⼒覚センサを「DynPick」のブランド名で展開している。主⼒とするのが、静電容量型6軸⼒覚センサで、定格荷重200N、500N、1000N をラインナップしている。ワコーテック独自のストッパー構造により過負荷対策を搭載、従来のひずみゲージ式⼒覚センサでは必須であったアンプBOX もセンサに内蔵している。産業⽤ロボットでの⼒制御、押し付け⼒管理、研磨、バリ取り、組⽴作業など様々な工程に対して提案している。 また、2016 年 3 月には微細な組⽴⼯程での利⽤を想定した、超⾼感度の 3 軸⼒覚センサ「WGF-3A」を発表している。同製品は6軸⼒覚センサでは検出できなかった、⼩さな⼒・荷重とモーメントを検出することが可能となっている。このため、同社は、定格荷重の並進⼒ F 成分とモーメント M 成分のバランスを改善。従来品のDyn Pick®では並進⼒FとモーメントMの⽐率が50:1であったのに対し、センサ内部の構造や回路等を⼤幅に⾒直し、定格荷重の F と M の⽐率を 10:1 という理想のバランスを実現している。 サンエテック サンエテックは、6 軸⼒覚センサ・SFT シリーズを展開している。⼩型・軽量、⼒ 3 軸(Fx,Fy,Fz)とモーメント 3 軸(Mx,My,Mz)を同時に検出、USB により簡単接続(標準品)、センサ内部にアンプと荷重演算用マイコンを内蔵、静的及び動的な測定が可能、回路の応答性が⾼く、⼀瞬の変動も検出可能、本体とケーブルはコネクタ接続により取り外しが可能といった特⻑を持つ。
152
表 サンエテック 6軸⼒覚センサ・SFTシリーズの仕様
出所:サンエテック資料
ビー・エル・オートテック 産業⽤ロボット周辺装置の専⾨メーカーとして、⼒覚センサ、エンドエフェクタ自動交換装置、位置誤
差修正装置等のロボット手首周辺装置を展開している。⼒覚センサは、薄型(ThinNANO センサ)、指先型(NANOセンサ)、小型(MICRO、MINI)の6軸⼒覚センサをラインナップ。さらに、センサ⽤増幅ユニットも取りそろえている。このうち、ThinNANO センサは、小型薄型(外径φ17mm×12mm)の変換器で、3 成分の⼒、3 成分のトルク情報として歪ゲージ信号をアナログ(6ch)により出⼒するシステムとなっている。 表 ThinNANOシリーズの主な仕様
出所:ビー・エル・オートテック
153
● ロードセル ロードセルを手掛ける日本企業としては、日本ティアック、テイアンドテイ、エー・アンド・デイ、ミネベアミツミ、共和電業、東京計器等。 ティアックは、ロードセルの製造販売を開始した 1980 年代から、独⾃の構造による⾼精度化、 小型
化を追求。最近では、独⾃の技術を⽤いて、⾼応答、⾼精度、 ⾼安定度を実現したロードセルや、グリーン調達や環境対応でご要求の増えているRoHS対応の モデルなどを製品化している。また、同社ではでは、ロードセルおよびロードセル指示計のTEDS (IEEE 1451.4 Transducer Electronic Data Sheet)対応を強⼒に推進。国内メーカーで一早く Manufacturer ID を取得し、TEDS 対応ロードセル、指示計を製品化している。 なお、TEDS 対応とは、モデル名、固有のシリアル番号、校正感度などを記した試験成績表
(TEST REPORT)を電子化、ロードセル内に設けたメモリの中に記録するもので、TEDS 対応するロードセル指⽰計と組み合わせることで、記録された情報を読み取り等価⼊⼒校正を⾃動化できる仕組みとなっている。 ティアンドティは、⻑年培ってきた⽣産技術と豊富な経験を基に、過酷な使⽤条件でも⻑期にわたり
性能を維持可能なロードセル製品群を展開している。主なラインナップとしては、「Lシリーズ」、「SBシリーズ」、「B シリーズ」、「PS シリーズ」など。「L シリーズ」は、200g〜2000kgまでの幅広いラインナップを有する⾼精度ロードセルで、汎用台はかり、工業用はかり、家庭用はかり、エレベーターなどで使用されている。 一方、「SBシリーズ」は圧縮・引っ張りの両方を測定できる⾼精度ロードセルで、建設資材はかり、ホッ
パースケール、タックルスケール、 吊りはかり、エレベーターなどで実績を持つ。その他、1t〜50t まで幅広いラインナップを有する⾼精度ロードセル「PSシリーズ」などがある。 このほか、エー・アンド・デイ、ミネベアミツミ、共和電業、東京計器がひずみゲージ技術を活かしたロード
セルを展開している。
⑦海外の主要な競合企業 TE Connectivity(スイス)、Siemens(独)、ATI Industrial Automation(米)、Honeywell(米)、Tekscan(米)、Futek Advanced Sensor Technology(米)、Vishay(米)、KAVLICO(米)、GEFRAN(伊)、HBM(独)、Flintec(スウェーデン)、Tecsis(独)などが⼒覚センサ(Force/Torque Sensor)を手掛けている。KAVLICO のように、航空宇宙/防衛分野での展開にフォーカスしているメーカーもあるが、上記のメーカーの多くは、⼒覚センサだけでなく、ロードセルも併せて展開していることが多い。ただ、ロボット及びエンドエフェクタ向けに取り組みを強化しているメーカーは、TE Connectivity、ATI Industrial Automation、Honeywell、HBMなどが中心とみられる。なお、ロードセルに関しては、Zhonghang Electric、Measuring Instruments等の中国メーカーも業界の中で⼀定の認知度を得ているようだ。
154
TE Connectivity Tyco Electronics を前身とする同社は、コネクタ、センサを主⼒事業としている。センサは、圧⼒、位置、温度、振動等、広範な製品群を有しており、FA向けではIOT⽤途での展開強化に注⼒している。 ⼒覚センサでは、フライトコントロールをはじめ、計測機器、プロセス制御機器、ロボットおよびエフェクタ
等のさまざまな用途向けに設計した⾼精度な⼒覚センサを展開。堅牢かつ⼩型の無接点トルクセンサをはじめ、オーバーロード保護を強化するメカニカルストップやステンレス鋼製ハウジングなどのさまざまな機能を備えた回転トルクセンサ、優れた温度安定度と最⼤8,000 lbf-ft の測定レンジの接着された⾦属箔ひずみゲージを使用して反作用トルクを測定するように設計されたスタティックトルクセンサなどをラインナップしている。また、低コストのロードセルをOEM生産している。 ATI Industrial Automation 同社は、ロボットエンドエフェクタ、ツールチェンジャ、⼒覚センサ等を展開している。⼒覚センサは、低コストな 6 軸⼒覚センサ「Axiom80」をはじめ、小型/ハイエンドの「Nano17 Titanium」、「Nano25 IP65/IP68」、ロープロファイルモデル「Mini40」等、幅広い製品ラインナップを整えている。 2017 年 9 月には、半導体ひずみゲージを採用した、新たなモデル「Axia80」を投入している。同モデルは 2 つのキャリブレーションプログラムが予めセットされており、ハイスピード動作/広範囲なセンシングレンジと高分解能/⾼精度のいずれの使い⽅もできるような仕様となっている。また、同社はトランスデューサ内部に回路等をビルトインすることで、性能はそのままに、⼩型化、低コスト化を図ったとしている。リアルタイムなフォースコントロールが必要な組⽴⼯程等のロボット⽤途に最適としてユーザー提案を⾏っている。
表 ATI Automation 「Axia80」概要
出所:ATI Automationa資料
155
Honeywell 同社は、⼒覚センサをセンサビジネスの注⼒製品の1 つと位置付けており、ベーシックな「TBFシリーズ」に加え、自己診断機能を備えた「FSA シリーズ」、0.0098N の分解能を持つ「FSG シリーズ」、低消費電⼒タイプの「1865シリーズ」等を展開している。
出所:Honeywell資料
156
ビジョンセンサ
①技術概要 ビジョンセンサとは、カメラでとらえた映像を画像処理することで、対象物の特徴量(⾯積、重⼼、⻑さ、位置など)を算出し、データや判定結果を出⼒するセンサである。キズ・汚れなどの外観検査/有無検査/色検査/寸法検査/印字検査など、光電センサ、近接センサのような単純なセンサでは検出できない用途でも、ビジョンセンサにより面で捉えることで安定して検出することが可能である。 マシンビジョンとして主に産業用途で用いられており、センサ形状によりラインセンサ、エリアセンサとがある。また、最近では、これら 2 次元画像に加え、3 次元により対象物を⽴体的に把握するものも出てきている。
図 ビジョンセンサの構成 出所:オムロン資料
ビ ジ ョ ン セ ン サ の 撮 像 素 子 は CCD ( Charged Coupled Device ) 及 び CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor)が⽤いられる。感度、画質、露光同時性に優れ、パターンノイズが少ないなどの理由から、ビジョンセンサには CCD が⻑く使⽤されてきたが、近年はCMOS の感度、画質が向上し、グローバルシャッタ機能の搭載により露光同時性の問題が解消したことから、解像度、⾼速動作、コストに勝る CMOS が使用されるケースが増えている。なお、マシンビジョンの分野ではモノクロカメラが⼀般的に使⽤されるが、医薬品やフィルムなどの検査といった「⾊識別の必要な用途」を中心にカラーカメラが用いられているケースもある。 2次元のビジョンセンサは、位置決めや検出、測定、読み込みといった様々な分野で一般的に使用さ
れているが、対象物の容量や形状、3D位置を分析する場合や2次元画像ではコントラストが十分に得られない場合などで3次元ビジョンセンサが用いられるようになってきており、特にロボットによるピッキング作業等で需要が本格化する兆しを⾒せている。 3次元の画像を得る技術としては以下のものがある。 ステレオビジョン・構造化光 レーザー三⾓測量 Time-of-Flightカメラ
157
ステレオビジョン・構造化光 ステレオビジョンは、2 つのカメラを使用し1つの対象物に対し2枚の2D画像を撮影、三⾓測量の原理を使⽤し奥⾏き情報を得ることで3D画像を生成する技術であるが、平らな面や暗い環境に弱いといった短所がある。このため、最近は空間形状に合うように構成された光のパターンを投影する構造化光を用いることで、より正確な測定結果を得るシステムが実用化されている。 (⻑所) 狭い範囲内で⾼い精度を実現 2Dのエリアスキャンカメラを使用可能 日光があっても支障がない 反射性の高い撮影しにくい面にも対応可能 (短所) 計算負荷が大きいため、リアルタイム制が低い 構造が複雑でコストが高い(構造化光) レーザー三⾓測量 2D カメラとレーザー光源を使用、カメラ前方の対象物や空間にレーザーで線や点を投影し、これを2D カメラで記録。画像内の位置情報から奥⾏き情報を得る⽅法である。 (⻑所) 精度が⾮常に⾼い 厳しい照明条件にも対応可能 反射面や反射性が高く、撮影しにくい面でも支障がない (短所) 対象物をレーザースキャンする必要があるため、速度が遅い 撮影距離が短い 精度を向上させるために⾼価な構成機器が必要 構造が複雑でコストが高い 安全性(目を害する可能性がある)
158
Time-of-Flight法(TOF) 投射した光が対象まで往復するのにかかる時間から距離や奥⾏きデータを取得する⽅法で、連続光式とパルス式がある。特にパルス式は精度の⾼い光パルスを⽣成し、⾼解像度かつ正確な測定が⾏えるようになったことからマシンビジョン分野への応用が急速に進んでいる。 (⻑所) ⼀回で撮影が完了し、スキャンする必要がない 高速 画像の複数個所の2D情報と3D情報が得られる X軸、Y軸の解像度が⾼い システムがコンパクト 暗い場所でも高い性能を発揮 構造やコントラストの有無に関係なく撮影可能 ⼗分に強い光源があれば撮影距離を延⻑可能 安価なシステムコスト リアルタイム性が高い (短所) 反射面や反射性が高く撮影しにくい面は苦手 散乱光に弱い 日光があると撮影が難しい
表 3次元カメラの技術比較
ステレオビジョン 構造化光 レーザー三⾓測量 Time-of-Flightカメラ
撮影距離 中程度〜⻑い 中程度 短い ⻑い
解像度 中程度 中程度 場合による 高い
奥⾏き精度 中程度〜非常に高い(撮影距離による) 中程度 非常に強い 中程度
ソフトウェアの構造 複雑 中程度 複雑 シンプル
リアルタイム性 低い 低い〜中程度 低い 高い
暗い環境での撮影 弱い 強い 強い 強い
屋外での撮影 強い 弱い 中程度 現在は弱いが、改善が⾒込まれる
コンパクトさ 中程度 中程度 かさばる 非常にコンパクト
運用コスト 高い 中程度〜高い 高い 中程度〜高い
出所:Basler資料より
159
②用途 イメージセンサは撮像系のアプリケーションで幅広く使⽤されているが、⾼感度、⾼速動作性といったFA
カメラと同様の特性が求められる⽤途として、動態・⽂字認識や動き検出といったセンシング機能が重視される監視カメラ、⾞載カメラが挙げられる。 要素技術としては、マシンビジョンシステム:⾼速・⾼精度・⾼安定検出、サーチ能⼒、ロバスト性、使
いやすさ(オートキャリブレーション機能等)、CMOSイメージセンサ:⾼解像度、⾼感度、⾼速動作性 画像処理部:⾼速処理、解析アルゴリズム、機能(補正機能・ノイズ除去)が挙げられる。
③国際市場規模及び日本企業のシェア ④国際市場規模の将来予測 ビジョンセンサ(カメラと画像処理部で構成されたシステム)の国際市場規模は 2016 年時点で441,430個(⾦額ベースで815億円。ボード、ソフト、スマートセンサーを含む、YRI調査値)と推計される。市場普及が⼀巡したことからここ数年はやや低い成⻑率となっているが、マシンビジョンの導⼊による自動化ニーズが様々な分野に拡大しているため、今後も安定した伸びを示すと予想される。 ビジョンセンサのメーカーとしては、キーエンス、オムロン、ファースト、オプテックス・エフエー、マイクロ・テクニ
カ、デグシス、ニレコなどがある。また、3次元ビジョンセンサではキーエンス、オムロン、三菱電機、Kyoto Robotics(旧3次元メディア)、キヤノン、リコーなどが製品を投入している。
<ビジョンセンサ 市場シェア, 2015年>
世界的にみると、トップシェアは米 Cognex、キーエンス、オムロンが 3 強を形成。これら 3 社は幅広い製品群をラインナップし、様々な分野での需要を取り込む一方、ファーストやオプテックス・エフエー、マイクロ・テクニカ、ニレコなどの他の日系メーカーは表面検査装置といったシステム単価が100万円以上のハイ
160
エンド品で一定のポジションを築いている。 また、ビジョンセンサで用いられるカメラ(FA カメラ)では、ラインセンサカメラが2016 年時点で 65,000台(⾦額ベースで 574 億円、YRI 調査値)、エリアセンサカメラが同 1040,000台(⾦額ベースで399億円、YRI調査値)となっている。 参入メーカーは、ラインセンサカメラでは日本エレクトロセンサデバイス(NED)、ジェイエイアイ、竹中システム機器、シーアイエス等、エリアセンサではソニー、センテック、東芝テリー、シーアイエス、ジェイエイアイ、⽇⽴国際電気、⽵中システム機器、ワテック、⽇興電機通信、池上通信機、NEDなどがある。 世界的にみると、独Basler AG、加Teledyne DALSA、英e2v、韓Vieworks、米IDS、独AVT、加PGRなどが存在感を示しており、特にラインセンサカメラでは海外メーカーのシェアが高い。
< ラインセンサカメラ 市場シェア, 2015年 >
< エリアセンサカメラ 市場シェア, 2015年 >
161
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測 現在の需要の中心である日本、欧州、米国のマシンビジョン・FA カメラ市場は成熟化しており、更新需要がメインであるが、製造業における設備投資が活発な中国等の地域で需要が拡大している。さらに、これまでの自動化ニーズに加え、「「インダストリー4.0」、「⼯場完全⾃動化」などのニーズの⾼度化を背景に日本、欧州、米国でも新たな市場の拡がりが期待されるため、今後もマシンビジョン・FA カメラ市場は安定成⻑が⾒込まれる。
図 世界マシンビジョン市場予測(2015〜2020、台数)
図 世界マシンビジョン市場予測(2015〜2020、⾦額)
162
図 世界エリアセンサカメラ市場予測(2015〜2020、台数)
図 世界エリアセンサカメラ市場予測(2015〜2020、⾦額)
なお、3D ビジョンセンサの市場規模については、有用なデータがなかったため、ここでは除外している。
164
⑤各用途に求められる技術特性 ビジョンセンサは、主にマシンビジョンを用いた外観検査システムとして市場を形成、自動化ニーズの高まりを背景とした産業⽤ロボットのマーケット拡⼤とともに、医薬、⾷品・飲料の製造ラインや倉庫、物流施設等での活用も進みつつある。3D ビジョンセンサが急速に注目を集めるようになったのも、ローディング(アンローディング)、ピックアンドプレイス、パレタイジング(デパレタイジング)、パーツフィーディング/組⽴など、より⾼度なマニピュレーションが必要とされる⽤途でのロボット導入のニーズの高まりが背景にある。こうした用途では、ロボットに「目」が必要。⾼速、⾼精度、⾼感度といった性能⾯だけでなく、⾼次の認識能⼒が重要となっており、その⼀つの答えとして、3D ビジョンセンサが位置付けられている。 また、、IOT、スマートファクトリ、Industry4.0 といった社会的な潮流の中で、産業⽤ロボットをはじめとする FA装置のあり方も変化していく方向が示されている。ファナックは、製造現場向けの IoT 基盤「FIELD system」を通じ、CNCや産業用ロボット、各種センサのデータを集積し、分析および制御を実現するとしている。実際、⽣産ラインの保守・運⽤の精度向上や工数低減を目的とした生産ラインの遠隔画像監視やセンサモニタリング、トレーサビリティ、リモートメンテナンスなどのソリューションが様々な企業から提案されており、センサ側の対応(主には通信機能)も浸透してきている。ビジョンセンサが提供する画像データは、様々なセンサデータの中でも情報量の多さが特徴で、このエッジデータをいかに活かしていく、ソフトウエアでの取り組みが従来にも増して重要となってきている。 こうした中、データ処理のツールとしてディープラーニングや強化学習等のAI技術を取り入れようという動きが活発化している。ディープラーニングは、⾳声認識や⾃然⾔語処理、画像認識といった分野で既に多くの実績を上げており、画像認識においてもこれまでにない認識精度を実現する技術として広く認められるようになってきている。当然、ビジョンセンサへの応用も進んでおり、Cognex が外観検査および識別用にディープラーニングベースの画像分析ソフトウェアを製品化しているほか、NEC が「RAPID 機械学習技術」を活用し、X 線画像を含む対象の製品画像を基に、⾦属や樹脂・ゴムなどの部品加⼯業の製造ラインなどで高速な検査を可能にする「AI Visual Inspection」をローンチしている。
165
⑥国内企業 マシンビジョンのメーカーはキーエンス、オムロン、ファースト、オプテックス・エフエー、マイクロ・テクニカ、デグシス、ニレコなどがある。また、FA カメラ関連のメーカーとしては、池上通信機、ワテック、東芝テリー、⽇⽴国際電気、ジェイエイアイコーポレーション、日本エレクトロセンサデバイスなどが挙げられる。 キーエンス 同社は、画像センサを「CV-X シリーズ」として展開している。同シリーズはコントローラ、カメラ、ソフトウェア等で構成されており、検査対象を選ばない⾼い対応能⼒、優れたユーザビリティを実現、画像処理とロ ボットを融合したロボットビジョンでは世界標準機種と自負している。 現在の「CV-X シリーズ」は Ver.4.2 となっている。画像処理を⻑期にわたり安定稼動させるにあたり、「⾼い検出能⼒」はもちろんのこと、「設定作成」「運用」「維持」が容易に誰にでもできることが重要な要素と同社では考えており、多数の導入実績から培ったノウハウを元にバージョンアップを図っている。 Ver.3.0 では 2100 万画素カメラ追加、3次元形状測定対応。Ver.3.1 ではカメラ、照明、検査を
融合できる「LumiTrax」を新開発。Ver.4.0 では業界最高性能コントローラ、最新サーチ機能追加。さらに、Ver.4.2では「マルチスペクトル撮像モード」搭載による 8色照明とアルゴリズムの融合により、ワークのわずかな色違いも正確に判別可能になっている。 「CV-X」では、処理速度、容量で選べる 8種類のコントローラをラインナップ。検査内容に応じて選べる22種類のカメラ、充実したソフトウェアタイプを取り揃えている。先に⾒た「LumiTrax」は、新開発の超高速カメラと超高速部分点灯照明を使用して対象ワークを撮像。異なる⽅向から照明を点灯した複数枚の画像を分析し、形状(凹凸)画像とテクスチャ(模様)画像を生成する全く新しい撮像方法となっている。安定検査を妨げるワークのばらつきや周囲環境の影響を排除できるため、従来多大な時間と経験を要していた画づくりを誰でも簡単に実現できるといったメリットがある。
166
出所:キーエンス
Ver.4.2で新たに追加された「マルチスペクトル撮像モード」は、8色LED と専用の制御IC を照明に搭載。点灯色制御・分割点灯・高速撮像との同期を複雑な制御なしに実現、8 色照明とアルゴリズムの融合による3 つの撮像モードで、色・形状・光沢・多品種への対応⼒が飛躍的に高まるとしている。
出所:キーエンス 外観・判別検査ツールやバリ・⽋け検査に最適化された輪郭⽋陥検査ツールといったスタンダードなものをはじめ、自動特徴抽出アルゴリズムによる高いロバスト性を提供するサーチツール「ShapeTrax」、高精度な寸法検査が可能な寸法幾何ツール、⽂字認識ツール「OCR2」等、キーエンス独自のアルゴリズムが盛り込まれた各種ツール、さらには、これらを⽀える前処理フィルタと、ソフトウェア⾯での⾼い競争⼒も「CX-Vシリーズ」の強みとなっている。
167
また、キーエンスは、業界最高のハードスペックを実現した画像処理システム「XG-X シリーズ」もラインアップしている。業界最多 14 コアによる圧倒的な画像処理性能をベースに、輪郭が不安定なワークであったり、ノイジーな画像であっても、ノイズと必要な情報を自動的に判別し、高速で安定したサーチを提供する「ShapeTrax3」をはじめ、処理の重い 3 次元画像処理などにフルにそのスペックが活かせるチューニングが施されている。 このほか、同社は、各種ロボットとの直結通信をサポートした「ロボットビジョンシステム」の提案にも⼒を入れている。同システムは、⾼精度なキャリブレーション機能を搭載。簡易な設定で画像センサとロボットの座標系の統一を⾏うことができ、安定した運用が可能となっている。加工部品の箱詰めやネジ締め位置検出、基板搭載時のデバイスのつかみズレ補正、外観検査時の位置決めなどで採用が進んでいるとしている。 なお、「CV-X」、「XG-X」のカメラに関しては 2100 万画素カメラを筆頭に、500 万画素カメラ、200万画素カメラ、31〜47万画素カメラをラインナップしている。 オムロン 同社は、カメラ一体型単機能タイプとして、スマートカメラ「FQ2シリーズ」、高速位置決め用スマートカメラ「FQ-Mシリーズ」を、カメラ別型タイプとして画像処理システム「FHシリーズ」などを展開している。 「FQ2 シリーズ」は、画像処理プロセッサ、ハイパワー照明、レンズ、I/O電源コネクタ、Ethernet コネクタを一体化したコンパクトな画像センサで、IP67 の防水性を備えている。外観検査、位置決め等、様々な用途に対して、オムロン独自のテンプレートを高速にサーチ・マッチングする技術を用いた「形状サーチIII」をはじめとする充実したメニューを取り揃え、最大 32 台まで増設できる汎⽤性の⾼さが特⻑となっている。画像素子は、1/3 インチカラーCMOS(処理分解能:752×480)もしくは 1/2 インチカラーCMOS(⾼解像度タイプ、処理分解能:928×828)となっている。 「FQ-Mシリーズ」は、位置決めアプリケーションのために開発されたEtherCAT通信対応のスマートカメラで、移動体の位置決めをより簡単かつ⾼精度に実現できるエンコーダ⼊⼒機能を備えている。設計ツールとして、オムロンのオートメーションソフトウェア「Sysmac studio」が視覚センサのセッティングから各機器間の接続、キャリブレーションをサポートしている。撮像素子は、1/3 インチカラーCMOS もしくは1/3 インチモノクロCMOS。HDR搭載、電子シャッタ方式(シャッタスピード:1/10〜1/30000sec)、処理分解能:752×480、フレームレート:60fps(16.7ms)となっている。 また、オムロンは、産業用カメラとして「3Z4S-CA シリーズ」を投入している。同社は FA 技術の開発⼒強化の一環として、2017 年 7 月にインダストリー用のマシンビジョン、医療及びラボ等での各種⽤途のカメラを手掛けるセンテック(現社名オムロンセンテック)をグループ会社化、超小型・高画質カメラの設計・開発技術を取り込んだ。「3Z4S-CA シリーズ」はその取り組みの第一段と位置付けるもので、ソニーのグローバルシャッターCMOS「Pregius」を搭載した GigE Vision CMOS モデル、USB3.0 モデル、CoaXPressモデルなど、多種多様なカメラからなるシリーズを投入している。 オムロンは、⾼画質・⾼速伝送・⼩型化カメラ設計技術と⾼速・⾼精度な画像処理技術を摺り合せ、取付け場所を選ばない超小型・高画質な「スマートカメラ」や、ロボットアームに組み込み、三次元で物体
168
の認識を⾏いピック&プレースを⾏う超⼩型カメラなどを開発。さらに、カメラと画像処理コントローラーを摺合せ、⼈の眼を代替する新たなオートメーション技術を確⽴し、ロボットによる組⽴⼯程の省⼈化や、光学式センサーの簡易カメラ化、品質トレーサビリティにおける製品の個体管理などの新たな市場を創出する方針である。 オプテックス・エフエー 同社は、ローコストの画像センサから、ミドル〜ハイエンドの画像検査装置まで幅広く展開。特に、印字検査機を得意としており、2013年10月には、印字検査⽤の⽂字認識画像センサ「MVS-OCR2シリーズ」を投入している。 「MVS-OCR2 シリーズ」は、食品製造ライン上での賞味期限・消費期限の日付印字検査を主な用
途とした⽂字認識タイプのカメラユニットで、2008 年に発売した「MVS-OCR シリーズ」の後継機種と位置付けている。 イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度と 2 倍以上の撮影視野を実現、ダンボールなど広い範囲での印字や⼩さな⽂字の読取りに威⼒を発揮する。また、アルゴリズムの改良により、暗い環境や⾊地上の⽂字においての印字抽出能⼒を⾼めた。操作性という点では、従来機で5段階のセットアップ工程を3段階に減らし、簡単設定および⽴上げ時間の短縮を実現。またカメラに接続するコントローラは従来機と共通機種(MVS-DN)としている。 同社では FA センサを「FACTUS」のブランドで展開しており、「MVS-OCR2 シリーズ」はクラス最小のコンパクトレーザ変位センサ、超⾼精度段差判別センサに続く、第 3 弾であった。その後、形状測定センサ、センシングバックライト照明、アンプ内蔵光電センサと様々なFAセンサ関連製品が追加されている。
169
⑦海外の主要な競合企業 マシンビジョンでは、米Cognex、独Basler、加Mantrox、加Teledyne DALSA、独SICKが有⼒プレイヤーとして認識されているほか、中国(Daheng New Epoch Technology、Shenzhen JT Automation Equipment)、台湾(DELTA、VECOW)、韓国等のメーカーも徐々に存在感を高めてきている。一方、FA カメラでは、独Basler AG、加Teledyne DALSA、英e2v、韓Vieworks、米IDS、独AVT、加PGRが日本企業と激しくシェアを争っている。 Cognex 同社はビジョンシステム、ソフトウェア、センサ等を展開。⾃動⾞をはじめ、製薬、電気・電⼦、⾷品・飲料の幅広い業界で数多くの実績を積み上げている。2016 年に 3D ビジョン技術を持つ AQSense(251万米ドル)、Enshape(539 万米ドル)を買収、2017 年にも同様に 3D マシンビジョンセンサの開発を⾏っていたChiaro Technologiesをグループに迎えるなど、3D ビジョン技術の取り込みに積極的な動きを⾒せている。 2D のビジョンセンサは、「In-Sight 2000」をメインに展開している。同社ビジョンシステムの基盤となる製品で、柔軟な製品選択ができるバリエーションを特⻑としている。 マシンビジョンは、「In-sight 8000シリーズ」(超コンパクトタイプ)、「In-sight 7000シリーズ」(シ
ステムをカスタマイズしやすいモジュラータイプ)、「In-sight 5000 シリーズ」(インダストリアルグレードの標準タイプ)を主⼒に、マルチスマートカメラシステム「In-Sight VC200」などもラインナップしている。 「In-Sight VC200」は、マルチカメラ用途に向けたスタンドアローンのビジョンシステムで、1つのコントロ
ーラに最大 4 つのカメラを搭載可能で、マルチビューのインスペクションシステムを容易に構築できる点が特徴となっている。 また、これらビジョンシステムのソフトウェアとして、「In-Sight Vision Software」を提供しており、最近
では、ディープラーニング技術の導入にも積極的である。「Cognex ViDi Suite」は、ディープラーニングベースの画像分析ツールで、Cognex がテストし、最適化したマシンラーニングの各種アルゴリズム、具体的には、ViDi blue(Fixturing)、ViDi red(Segmentation & Anomaly Detection)、ViDi green(Object and Scene Classification)で構成されている。 Basler 同社は、ファクトリーオートメーション、交通システム、リテール、医療・ライフサイエンスなどの⽤途に最適
な産業用カメラ、ネットワークカメラ、アクセサリーを幅広く取り揃えており、産業用カメラとしては、エリアスキャンカメラ、ラインスキャンカメラ、ネットワークカメラ、3D カメラなどを展開している。 エリアスキャンカメラは「Basler ace」、「Basler aviator」、ラインスキャンカメラ「Basler racer」、
「Basler runner」が主⼒モデルとなる。 「Basler ace」は、VGAから14MP までの解像度に対応、最大フレームレート 751fps、幅広いセン
サーラインナップ:CCD、CMOS、近赤外線モデル、各種インターフェース対応:USB 3.0、GigE、
170
Camera Link、柔軟性の高いI/O:レイテンシーとジッターを最小限に抑えることにより、各種用途で最⾼の精度を実現、といった特⻑を持つ。 classicは、CMOSIS、e2V、オン・セミコンダクターの CMOSセンサやソニーCCDセンサが搭載された
モデルで構成。一方、ace U は、ソニーPregius シリーズ、STARVIS シリーズやオン・セミコンダクター社製PYTHON センサ、さらに、ace L にはソニーPregius シリーズの中でも9MPから12MP までの高解像度に対応した⼤型のセンサ(最大1.1インチ)が搭載されている。 「Basler aviator」は、1MP、2MP(4:3、HDTV)、4MP の解像度に対応、最大フレームレート
120fps、GigEインターフェース、Camera Linkインターフェース対応、優れたリニアリティ、広いダイナミックレンジ、低ノイズといった性能を有しながらも、コストパフォーマンスに優れている点が特徴となっている。 Mantrox 同社は、マシンビジョン用のソフトウェア、スマートカメラ、コントローラ等を展開。スマートカメラは、防水防塵性に優れ、堅牢な構造を持つ「Iris GTR」を主⼒モデルとしてユーザー提案を⾏っている。同製品は、Microsoft® Windows®もしくはLinux®上で運用でき、「Matrox Imaging Library (MIL)」をはじめとする充実したソフトウェアサポートにより、ユーザーが自社のニーズに最適なマシンビジョンを構築できる汎⽤性の⾼さが特⻑となっている。 2017年11⽉には、ユーザーが既存の検査装置を新たなプロジェクトに使⽤する際の変更校正をスムーズに⾏うことのできるツール「Project Change Validator」を発表している。同ツールはフローチャートベースのマシンビジョンソフトウェア「Matrox Design Assistant 5.1」にて利⽤可能となっている。
図 Project Change Validator概要
出所:Mantrox資料
171
Teledyne DALSA 同社は CCD カメラ、CMOS カメラ、フレームグラバー、ソフトウェアライブラリと撮像から画像処理までの
必要な製品を全て取りそろえている。また、イメージセンサを自社で製造しており、半導体・電子部品検査、伝票・印刷スキャニング、穀物検査システムまであらゆる画像処理に対応している。2017年3 月には、画像センサやカメラなどの⾼性能イメージングソリューションで業界でも⾼い認知度を誇っていた英e2vを買収、撮像系技術を強化している。 高機能なPiranha4カメラから低価格なLineaカメラまで様々なアプリケーションに対応できるラインセ
ンサカメラをラインナップ。エリアカメラではカメラリンクや GigE インターフェースで VGA サイズから 12M モデルまで幅広くリリースしている。また、TDI(Time Delay Integration)カメラでは最新の Piranha XL 16K カメラ、標準の HS シリーズの他、低感度版の ES シリーズや、近⾚外領域に対応可能なHN シリーズがある。センサとしては CCD、CMOS センサーに対しそれぞれモノクロ、カラーと様々なラインナップがあり、最新のセンサでは4 ラインカラー(RGB+NIR)のセンサを搭載したカメラもリリースしている。 TDI カメラとは、CCD の特殊な読み出し⽅式で、⼀定速度で移動する対象物の移動⽅向・速度と
CCD の電荷転送⽅向・速度を合わせた撮像を⾏うもので、高速性に加え、移動する対象物を繰り返し露光することで、⾼い感度が得られるため、従来のラインセンサカメラでは不可能であった低照度レベルでの撮像が可能となっている。 「Piranha XL 16K カメラ」は、同社の最新型マルチライン CMOS カラーTDI ラインカメラで、
Camera Link HSインターフェースを採用することで、16K画素でありながら、最高70kHzのラインレートを実現した。また、TDIセンサー(12 ラインの積算構造)を各色4 ラインずつ使用することで、従来のカラーカメラに比べ明るく撮像できるといった特⻑を持つ。⾊ずれ補正や視差補正等の機能を搭載しているほか、TDIカメラでは使えなかった露光制御機能も追加されており、使い易さの面が向上している。 また、CMOS ラインカメラでは、2017 年 7 月より偏向フィルタ搭載ラインカメラ「Piranha4 Polarization カメラ」を投入している。同製品は、ラインセンサに 3 種類の異なる偏光フィルターを取り付けることにより、1度の撮像で3種類の異なる偏光結果を得ることが可能。得られた3種類の画像を用いることで周囲とわずかに異なる傾きの⽋陥(ゆがみや傷等)を検出することができる。従来の手法では検出が難しかった欠陥も偏光フィルタを搭載したこのカメラを用いることで容易に検出することが可能となっている。 SICK 同社はバリエーション豊富なハードと位置決め・検査・測定・読取りのアプリケーション用ツールを組み合
わせたビジョンセンサを提供している。柔軟な光学設計は、ほぼすべての使⽤領域に適しており、自動セットアップ、インテリジェントなアルゴリズム、直観的なユーザーインタフェースによって、簡易性が保証されている。 主⼒とするスマートカメラ「Inspector シリーズ」は、スマートカメラの性能とセンサの使いやすさを結び付けた多面的なビジョンツールボックスと位置付けており、産業利⽤向けに設計された頑強なIP 67の⾦属筐体、高速アプリケーションに適合したインテリジェントな画像処理を特⻑としている。筐体は交換式を採
172
用、ユーザーの光学的要件に合わせた調整が簡易にできるよう設計されている。また、Ethernet をはじめとする多くのインタフェースを通して制御、点検およびデータ収集時の広範なサポートを提供している。 ● 3次元(3D)ビジョンセンサ ロボットピッキングや装置環境の監視・制御などへの応用を背景に、3D ビジョンセンサの需要が拡大。
多くのメーカーが市場参⼊を⾏っている。国内の企業では、キーエンス、三菱電機、Kyoto Robotoics(旧3次元メディア)、キヤノン、リコーなどが製品を投入。Basler、SICK、IDS等の海外メーカーも動きが活発である。 キーエンス 同社は、3次元ビジョンセンサとして「XRシリーズ」及び「LJ-Vシリーズ」をラインナップしている。 「XRシリーズ」は、パターンプロジェクション方式の3次元ビジョンセンサで、超高速CMOS、マイクロミラ
ーデバイス×2等で構成されている。マイクロミラーデバイスはMEMS技術を駆使し高速のストライプパターン⽣成を実現。⾼輝度LED混合発光技術と合わせ、あらゆるワークでの安定計測を提供している。 2 方向から複数枚のストライプパターンを高速に投影。ワークからの反射光を、超高速 CMOS と専用
プロセッサがリアルタイムに解析することで3次元画像を生成する。2方向からの投影により、陰(死角)になる部分の影響を軽減。またそれぞれの反射光を比較・解析する独自のアルゴリズムにより、高いノイズ除去能⼒を実現した。 ワークが静止した状態で、3次元高さ画像と濃淡画像の同時撮像が可能。濃淡画像による位置検
出、高さ画像による高さ計測、また高さデータを元に濃淡画像に変換した高さ抽出後画像で形状検査を⾏なうなど、検出内容に合わせて最適な画像を選択することができるとしている。 「LJ-Vシリーズ」は、二次元三角測距方式を採用した3次元ビジョンセンサで、シリンドリカルレンズによ
り帯状に広げられたレーザ光が対象物の表面で拡散反射。その反射光を HSE3-CMOS 上で結像させ位置・形状の変化を検出することで、プロファイル形状を測定。さらにそのプロファイル形状をXG-X/CV-Xコントローラに取り込むことで3次元データによる画像処理を⾏う仕組みとなっている。 従来の変位計で一般的に使用されている赤色レーザは対象物の材質によって物体内部に光が浸透
したり、⾼温対象物の発光によりレーザ光が識別できなくなることがあった。これに対し、キーエンスはレーザ変位計として世界で初めてブルーレーザを採用。405 nmの短波⻑を極限まで絞り込むことによりシャープなラインビームを得ることで、より⾼精度な計測を実現している。 また、一般的なCMOSはダイナミックレンジが狭く、一つのレーザプロファイル中に高反射部と低反射部
が混在すると安定した形状を得ることができなかったが、ハイスピードカメラ並みの高速性と通常のCMO S比2,400倍の⾼ダイナミックレンジを両⽴させたレーザ変位計専⽤素⼦「HSE3-CMOS」を搭載、反射率の異なる材質・⾊合いが混在しても調整不要とした。 「LJ-V シリーズ」は、GP64-Processor を内蔵。CMOS撮像データの読み出し、高分解能サブピクセル処理のみならず、⾼精度リニアライズ、データ出⼒までの超⾼速パイプライン処理を実現。64,000 サンプリング/秒の超高速測定を可能としている。
173
キーエンスでは、3D寸法幾何、プロファイル計測/連続プロファイル計測、振動補正、2ヘッド死角除去、濃淡画像同時取得といった 3 次元検査で必要となる各種のツールも開発、「XR シリーズ」では、打痕、歪み等の検査、形状検査、高さ・寸法検査、「LJ-V シリーズ」では、形状検査、OCR、打痕・刻印検査等のアプリケーション提案を⾏っている。 三菱電機 同社は、産業用ロボット「MELFA」のオプション製品として、これまで自動化が難しかったロボットによるばら積み部品の取り出し・整列作業を可能にする⼩型 3 次元ビジョンセンサ「MELFA-3D Vision」を2013年2月より販売している。 「MELFA-3D Vision」は、三⾓測量⽅式(パターン投光型)の3次元ビジョンセンサで、⼩型軽量、⾼速、⾼精度計測(最⼩計測誤差 0.3mm)といった特⻑を持つ。事前に部品形状を登録することなく、乱雑に積み重なっているばら積み部品をひとつずつ画像認識する「モデルレス認識」技術を搭載しており、ばら積み部品の把持可能な箇所を高速検出が可能であるほか、ロボットハンドの開閉幅と爪の幅と高さを設定するだけで、部品の把持可能な箇所を最速約 1.2 秒で⾼速認識、パイプ、ボルト、ネジなどの小物部品にも適用可能である。同社では、パーツフィーダの置き換えとしてロボットビジョンでの利⽤を提案している。 Kyoto Robotics(旧社名3次元メディア) ⽴命館⼤学発ベンチャーである同社は、産業ロボットの「目」と「脳」にあたる 3 次元ビジョンセンサの研究開発をNEDOプロジェクトを通じて継続的に実施、2011年3月には世界初本格的3次元ロボットビジョンセンサ「TVS」を発売した。その後、川崎重工業、デンソー、ファナック、三菱電機、安川電機などの各ロボットメーカーと連携。様々なアップデートを通じ多様な機能を取り込むことで、現在は知能ピッキングコントローラとして、⾃動⾞メーカー、⾃動⾞部品メーカー、鉄鋼メーカー、家電メーカー、⾷品メーカー、建材メーカーなど70社以上の生産ラインに導入されている。なお、同社は2018年1月、社名をKyoto Roboticsに変更している。 「TVS」は、プロジェクタと4台のカメラを備え輪郭による 3DCAD マッチングを認識⽅法に採⽤した。そ
の後、「TVS2.0シリーズ」(2012年8月リリース)から「TVS3.0シリーズ」(2014年3月リリース)と段階的にアップデートされている。「TVS3.0シリーズ」からは輪郭と点群を併⽤したCADマッチングが導⼊されており、認識精度が向上している。最新モデルとなる「TVS4.0 シリーズ」では、小型ビジョンヘッド(2 カメラ 1 プロジェクタ一体型)を開発、高速計測エンジンによる撮像・計測時間の短縮化(TVS3から半減)、⾼輝度プロジェクタ採用による HDR 点群計測(⾦属光沢や⿊⾊ワークまで⾼速で点群計測可能)等の機能面の強化が図られている。
174
出所:Kyoto Robotics資料
キヤノン 同社は 2014 年 4 月、カメラや事務機で培ってきたオートフォーカス(AF)技術、画像認識技術、
情報処理技術を活⽤し、マシンビジョン市場に参入。その第一弾製品として、⾼速・⾼精度な3次元認識を実現する3D マシンビジョンシステム「RV1100」の販売を開始した。 「RV1100」はセンサ部分である 3D マシンビジョンヘッドと、認識処理を⾏う 3D マシンビジョン認識ソ
フトウェアから構成される。認識⽅式は、3DCADマッチング(パターンプロジェクション併用)をベースに計測距離データ、濃淡画像を利⽤した同社独⾃のものとなっている。プロジェクタと撮像センサを一体化させた3Dマシンビジョンは、難しい調整なしに導入が可能。また、軽量、コンパクトサイズのため、⽣産ラインの変更や移動に伴う移設にも⼿間がかからないほか、防塵防⽔、メンテナンスフリーといった特⻑を持つ。 2015年7月には、3Dマシンビジョンシステムの新モデルとして、「RV500」および「RV300」の2製品
を追加している。ともに小型部品への対応が大きな特徴となっている。
175
図 3次元マシンビジョンの動作フロー 出所:キヤノン資料
「RV1100」では1160×1160×600mm(縦×横×高さ)の計測範囲に合わせてシステムが最適
化されていたが、「RV500」では 540×540×200mm、「RV300」では 340×340×100mm という計測範囲が設定されている。また、認識に利⽤しているソフトウェアの改良により、認識時間も従来製品より改善しており、⾃動⾞だけでなく、IT 機器やデジタル家電などの生産ラインでの採用を視野にいれている。 また、2017年7月には、自動化が進む生産ラインの多様な部品供給ニーズへの対応を目的に、「3Dマシンビジョン認識ソフトウエア」をバージョンアップ。適用可能な部品供給工程の拡大やユーザビリティのさらなる向上を図っている。具体的には、アルゴリズム等を⾒直すことで、薄い板状や光沢性の高い部品など、⾼精度な3次元認識が可能な部品の範囲を拡大。ロボットのハンドが侵入しやすいコの字型パレットや、これまで計測範囲外であった大きなサイズのパレットにも対応を図っている。 また、ロボットが部品をピッキングするためは、事前にピッキングする位置や姿勢を登録する必要があり、これまでは、ロボットを実際に操作して登録を⾏っていたが、認識ソフトウエアのバージョンアップにより、ロボットを操作することなく、PC 画面上で登録することが可能になった。また、ユーザーインターフェースの改良も⾏い、セットアップやシステム運⽤の容易化や所要時間の削減を実現している。このほか、日本語と英語だけでなく、ドイツ語、フランス語、韓国語、中国語版の Windows に新たに対応するなどのアップデートを⾏っている。
176
表 キヤノン3次元マシンビジョンの主な仕様 出所:キヤノン資料)
リコー 同社は2015年3月、産業用ステレオカメラ「RICOH SV-M-S1」の発売を開始している。同製品は、パッシブ方式(三⾓測量⽅式ステレオマッチング)を採用、アクティブ⽅式(光切断・位相シフトなど)と異なり、連続⾼速3次元測定が可能な点が特徴となっている。また、リコー独自のキャリブレーション技術により、1m計測時に測距精度約±1mm を実現。撮影から画像処理、視差演算までを全てカメラ内部で⾏うことでデータ処理速度が向上するため、30fpsの高フレームレートで3次元データを計測できるとしている。測定視野は500 mm×400 mm、ワーキングディスタンスは800 mm〜1200 mmが設定されている。⽣産ラインをはじめ物流などの現場で使⽤される「ロボットピッキングシステム」や対象物の位置や⾼さを取得できるため「装置制御監視システム」などでの利⽤を提案している。 また、同年6月には、⾼速・⾼精度な3次元計測をサポートするステレオカメラ専⽤の⾼輝度LED照明プロジェクタ「RICOH SL-M-LE」も発売している。低反射ワークにも対応可能な⾼出⼒の明るさを確保、光源に LED を使⽤することで⻑寿命確保、RS-232C とデジタル I/O の 2種類の通信方式で外部制御が可能、カメラと別体構造であるため、被写体に対して最適な位置に照明を設置することが可能といったメリットを訴求している。
177
Basler 同社は 2016 年、パルス式 Time-of-Flight(ToF)方式を採用した「Basler Time-of-Flight
(ToF)カメラ」(tof640-20gm_850nm)を製品化している。解像度:640px×480px(VGA)、フレームレート:20fps、精度:±1cm、範囲範囲:0〜13mのモノクロカメラで、GigE インタフェースに対応している。近赤外線(850nm)に対応したハイパワーな 8 つの LED を備えており、範囲マップ、強度マップ、信頼性マップから構成される多視点画像を作成することにより、1 回の撮影で2D データと 3Dデータを同時に取得できる点が特徴となっている。同社では、同カメラを差別化製品と位置付けており、ロボット、産業オートメーション、物流、医療・ライフサイエンスなどの幅広い⽤途への展開を図っていく方針である。 フィンランドの研究機関である VTT Technical Research Centre of Finland Ltd が、欧州
R5-COP プロジェクトの⼀環として、ロボットの作業現場にある⽊製部材の検出と位置特定を⾏う再構成可能なロボットセンサーシステムを開発。3D 点群データを利⽤して検出と認識を⾏うこのシステムに、「Basler TOF カメラが」搭載されており、ROS(ロボットオペレーティングシステム)による柔軟性の高い構造を実現したとしている。
SICK SICK は、3D ビジョンシリーズとして、3 ビジョンセンサの幅広いポートフォリオを構築している。高品質の
3D 画像やコントラスト画像を供給する高速カメラから、すばやい開発と簡単な統合を可能にするインテリジェントで設定可能なスタンドアロン型のセンサにまで及ぶ。 3D 画像処理⽤のカメラとしては、「ScanningRuler」をラインナップしている。同製品は、レーザ光源
を内蔵、ミリメートルの精度での画像領域全体の3Dポイントクラウドを測定することができる。このデータを基に画像処理を実施することで、ピッキング時のパーツ位置特定や、ロボットの把持位置を算出するために使用可能となっている。 また、レーザ三⾓測量⽅式を採⽤したスマートカメラ IVC-3D も製品化している。同製品は画像取込
み、照明および解析の各機能を 1 台のカメラに統合したスマートカメラで、各種ツールを用いることで、コントラストや⾊に関係なく、⾼さ、体積、輪郭の測定を⾏うことができるとしている。 IDS Imaging Development Systems 同社は 3D ビジョン及びロボットビジョン向けにステレオ 3D カメラ「Ensenso シリーズ」を 2014 年より
展開している。「Ensensoシリーズ」は、認識⽅式に「射影テクスチャステレオビジョン」を採用。各モデルは CMOS センサ 2 台とプロジェクターを搭載しており、撮影する物体にパターンマスクを使用して高コントラストのテクスチャを投影することで、奥⾏き情報を持つ視差マップを取得する。また、同社ではパターンマスクの位置を圧電アクチュエータにより変えることで、視差マップの詳細度をさらに向上する FlexView 技術も開発している。「Ensenso シリーズ」では、FlexView 非搭載の「Ensenso N シリーズ」及びFlexView 搭載の⾼解像度モデル「Ensenso X シリーズ」をラインナップ。⽤途に応じて提案を⾏っている。
178
Ensenso 3D カメラの用途分野としては、物流のオートメーション、パレタイズ (デパレタイズ)、コンベアベルト装着、ファクトリーオートメーション、保管システムなどを想定。そのほか、カスタムメードの靴のインソールの製造や整形外科用途といった3D計測部にも適用可能としている。
その他 ifm electric が TOF カメラ、ISRA Vision がステレオ/三⾓測量⽅式のエリアプロファイルスキャナ
(APS3D)を製品化しているほか、ベルギーPickitが3Dロボットビジョンソリューションとして、構造化光方式を採用した3Dカメラ及びソフトウェア「Pick-it」を展開している。Pickitの3Dカメラは、画像処理スピード:30fps、精度:<3mm、再現性:<1mm の性能を有し、ABB、Universal Robot、Staubli、KUKA、ファナック、安川電機の産業用ロボットに対応している。
179
セイフティレーザスキャナ/セイフティライトカーテン ①技術概要 作業環境の安全性確保といった観点から、危険な機械の周辺に作業者がいないことを検出するレーザスキャナや指、腕、⼈体が危険領域に侵⼊を検知するライトカーテンなどのセイフティセンサが様々な工場で用いられてきたが、協同ロボットの本格実用化を背景に、人と機械の共同作業においていかに安全性を確保するかといった課題が注目されるようになっている。 ● セイフティレーザスキャナ セーフティレーザスキャナは、生産現場において人やワークなどが近づいたことを検出するための安全機器で、検出対象が警告領域に進⼊すると、警告⽤の信号を発し、セーフティ・レーザスキャナに接続されているブザーの音や表示灯の光を通じて注意を促す。さらに、防護領域(近づくと危険と判断される領域)まで近づくと、それまで機械の稼働を許可していた出⼒信号をオフにして、機械を停⽌させる仕組みとなっている。 検出には、一般的に赤外線レーザが用いられている。赤外線のため、⼈の⽬には⾒えず、仮に光が目
に入っても安全なエネルギレベル(クラス1)のレーザが使用される。 レーザはパルス波が採用され、扇状に少しずつ⾓度を変えながら照射される。レーザがセーフティ・レーザスキャナ本体の発信器から照射され、検出物体に当たって反射し、セーフティ・レーザスキャナ本体の受信器に戻るまでの時間を測定することで、検出物体までの距離を算出する。⼀般に、警告領域や防護領域といった検出領域の設定は、専⽤のソフトウエアで⾏う。ソフトがインストールされたパソコンとセーフティ・レーザスキャナを接続することで、パソコンの画⾯を⾒ながら任意の形状を検出領域として設定できる。さらに、いったん現場の状況をスキャンした上で、そのデータに基づいて検出領域を設定することも可能である。いまのところ、2 次元(面)の検出が中心であるが、今後は、3次元(空間)の検出技術の適用が進むものと考えられている。 ● セイフティライトカーテン セーフティ・ライトカーテンは、扉のない出入り口における人や物の通過を光線によって検出する安全装
置である。投光側ユニットと受光側ユニットを組み合わせて使用する。投光側ユニットから放たれる複数の平⾏な光線が、受光側ユニットで正確に受光されるようにユニットを設置。両者の間に遮る物体がない場合は、全ての光線が受光側ユニットに届くため、そのことをもって安全な状態であると⾒なし、受光側の出⼒をオンにして機械の運転を許可する。一方、人の手や体などによって光線の一部または全てが遮られたら、危険な状態であると判断し、受光側の出⼒をオフにして機械を停⽌する仕組みとなっている。ライトカーテンには、人や物体の進入を遮蔽する柵や扉がないので、実際に人や物体が光線を遮ってからそれを検知して機械(の可動部)を停止するまでの時間に基づいて、人や物体が危険源に接触しないようにするための距離(安全距離)を確保する必要がある。この安全距離によってライトカーテンの設置場所を決めることになる。
180
ライトカーテンの光源は、波⻑が 400n〜1500nm の範囲とすることが定められている。一般的には、エネルギ効率が⾼くて遠くまで届く、波⻑が900nm程度の⾚外線を出⼒するLEDが使用されている。 ライトカーテンの大きな特徴としてミューティング機能がある。これは、ワークを自動で危険区域に搬入するようなシステムにおいて、ワークはライトカーテンをそのまま通過させ、間違って進入しようとする人だけを検出するための機能で、ミーティング機能用のセンサを搭載する。 なお、セイフティライトカーテンでは国際規格で IEC 61496 などの安全基準が定められている。IEC
61496-1では、タイプ4ESPEが3つの累積故障に対して安全が確保されるよう規定しており、デュアルCPU による相互チェック、信号処理回路や出⼒回路の二重化による安全設計、さらにその安全動作を⽴証するためのFMEA(Failure Mode & Effects Analysis)が求められている。 ②用途 セイフティレーザスキャナ、セイフティライトカーテンともに、侵入検知を目的としたセイフティセンサであるため、製造ラインへの適用が圧倒的に多いが、最近は産業用ロボットや AGV へ搭載し、マルチモードで管理するといった⼿法が取られるケースも出てきている。こうした取り組みは、⾼度な動線管理が求められる倉庫や物流施設でもニーズが⾼まると⾒られており、協働ロボットのピックアンドプレイス用途への適用などと併せて需要が高まっていくと予想される。 ③国際市場規模及び日本企業のシェア ④国際市場規模の将来予測 ● セイフティレーザスキャナ Technavioでは、セイフティレーザスキャナの世界市場規模は2016年1.56億米ドル(約171億
円)と推計している。製造現場での事故を防ぐ目的から、セイフティレーザスキャナの導入が世界中で進んでいること、産業用ロボットをはじめとする FA 装置の普及が結果として工場内の危険領域の増加につながっていることなどから、今後も市場拡大が続き、2021年には1.82億米ドル(約200億円)となると予想している。ただ、セイフティレーザスキャナの導⼊コストはそれなりに⾼く、これが将来の市場成⻑を阻害する可能性がある。実際、代替技術としてセイフティライトカーテンやセイフティマットなども登場しており、アプリケーションや工場環境によっては、他の技術に需要がシフトすることもありうるとみられる。 製品開発のトレンドとしては、小型、超小型が挙げられる。ベンダーは小さく、狭い場所でも設置しやすいシステムの開発にしのぎを削っている。また、今後は協働ロボットなどで、ロボット本体にセイフティレーザスキャナを搭載するといった動きも出てくるとみられるほか、3Dセイフティレーザスキャナも新たなトレンドになっていく可能性がある。
181
図 セイフティレーザスキャナ市場規模(2106年〜2021年)
セイフティレーザスキャナの主要メーカーとしては、Leuze electronic(独)、オムロン、パナソニック、
Pepperl + Fuchs(独)、Rockwell Automation(米)、SICK(独)が挙げられる。その他、Banner Engineering(米)、TURCK(独)、北洋電機、IDEC、キーエンスが市場参入している。 日本企業のシェアは明らかでないが、マーケットでは小型化に対するニーズが強いことから、こうした小
型・高性能な製品を得意とする日本企業のシェアが今後は高まってくるものとみられる。 ⑤各用途に求められる技術特性 設置のしやすさなどからモバイルタイプ(移動式)の需要が⾼まっており、検出⾓度、検出範囲といっ
た性能⾯と⼩型・軽量化の両⽴が各⽤途ともに重要となってきている。また、製造ラインによっては堅牢構造、信頼性、ロバスト性も必要である。 ⑥国内企業、⑦海外の主要な競合企業 先にも⾒たように、セイフティレーザスキャナの主要メーカーとしては、Leuze electronic(独)、オムロン、パナソニック、Pepperl + Fuchs(独)、Rockwell Automation(米)、SICK(独)が挙げられる。また、キーエンスやIDECが小型のセイフティレーザスキャナを投入している。 Leuze electronic 幅広い FA 向けのセンサソリューションを展開しており、セイフティ関連ではセイフティレーザスキャナ「RSL400 ファミリー」及び「RS4ファミリー」等をラインナップしている。 「RSL400 ファミリー」の検出⾓度は 270°となっている。一方、「RS4 ファミリー」はフレキシブルフィールドモニタリングを特⻑としており、検出
182
⾓度は190°である。 オムロン 薄型(104.5mm)、軽量(1.3kg)で設置しやすいセーフティレーザスキャナ「OS32C」を展開している。防護エリア 4m、検出⾓度270°の優れた性能ながら、省電⼒(5W)かつ多機能を実現。防護エリア 1 つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑な AGV 軌警告エリアを 2 つ設定できるため、警告⾳、速度制御など、⽤途に合わせた使い⽅が可能なほか、Ethernet に対応、複数台使用の大規模アプリケーションでも、LAN 経由で動作状態の確認や非常停止原因の分析ができるといった特⻑を有している。 パナソニック タイプ3のセーフティレーザスキャナ「SD3-A1」を展開している。防護エリア4m、検出⾓度190°の小
型サイズ(W140×H195×D135mm)。各ゾーンの形状は範囲内で自由に設定可能で計8つのゾーンを切り換え可能である。また、独自のアルゴリズム「ダストサプレッション機能」により、小型の昆虫やホコリによる誤動作を低減、静止物を常時検出させ参照境界機能を有効にすることにより、セーフティレーザスキャナが静止物との位置関係を記憶。設置後の光軸ずれを監視することができる。さらに、応答時間を80〜640msの範囲で可変。複数台のセーフティレーザスキャナを接近して設置する場合、応答時間を調整することにより相互干渉を防せぐことが可能である。 P+F 独自のPulse Ranging Technology (PRT)により、360°の検出⾓度を実現した「R2000シリー
ズ」を展開している。同製品は、計測範囲:10m、最小検知サイズ:1mm となっている。 Rockwell Automation 同社は様々なセイフティデバイスを展開しており、セイフティレーザスキャナは「SafeZone シリーズ」をラインナップしている。同製品は、190°/270°の検出⾓度、2〜5mの計測範囲、30mm-150mmのコンフィギュアラブルな分解能を有し、Windowsベースの設定/診断ソフトウェアをバンドルしている。 SICK 移動式、据え置き式の両タイプのセイフティレーザスキャナをラインナップしている。2016 年には広範な検出距離とコンパクト形状を両⽴するスキャンテクノロジーsafeHDDM®を導入した「microScan3 Core」を市場投入している。フィールド検出距離は5.5 m、スキャン⾓度は275°。最大8つの設定可能なフィールド、最大 4 つの同時防護フィールドを設定可能である。また、構成メモリ付きシステムプラグおよびM12プラグコネクタを搭載、EtherNet/IP™ CIP Safety™またはPROFINET PROFIsafeを使用したI/Oまたはネットワーク経由での安全な統合が可能となっている。
183
キーエンス 同社は、業界最⻑の保護領域を実現した「SZ-V シリーズ」を投入している。同製品は、業界最⻑の保護領域8.4mを実現。⼤きな領域から⼩さな領域まで⾃由な領域設定を可能にしている。さらに、新搭載のアルゴリズムが反射型センサとしての性能を大幅に改善。スキャナの大敵であったホコリや汚れによる誤検知を削減し、不要な設備停⽌を防⽌することができる。なお、検出⾓度は190°となっている。 IDEC 同社はレーザスキャナ、ライトカーテン、セーフティコントローラ、イネーブル装置、非常停止用押ボタンスイッチ、積層表示灯、強制ガイド式リレー、安全スイッチ等のセイフティ関連製品を展開しており、これらハードを組み合わせた「ロボット安全パッケージ」としても提供している。 セイフティレーザスキャナでは、2017年4月にコンパクトな「SE2Lシリーズ」を投入している。同製品は、検出距離5m、検出⾓度 270°の優れた性能をコンパクトなボディで実現。また、段階の防護エリアを設定することができるデュアルプロテクション機能搭載、最大4台まで一括制御可能(マスタースレーブ機能)といった機能を追加している。さらに、AGV(無⼈搬送⾞)などのエンコーダからの⼊⼒により、⾼速時はエリアを広く、低速時は狭くするなど速度に応じたエリア切り替えが可能。ロボットなどでも動作モードによってエリアを切り替えることが可能となっている。
184
● セイフティライトカーテン Technavio では、セイフティライトカーテンの世界市場規模を2016年1.72億米ドル(約189億
円)と推計している。製薬、パッケージング、⾷品、⾃動⾞等、⾃動化が進んでいる業界を中⼼に事故防止の目的から導入が進展していることから、今後も市場拡大が続き、2021 年には 2.02 億米ドル(約 200 億円)となると予想している。多くのベンダは、ロバスト性、信頼性等を強化したセイフティライトカーテンを投入。ユーザーが⽣産スピードを落とすことなく、⾼い安全性を確保できるような機能追加が進められている。 セイフティライトカーテンの主なメーカーは、オムロン、パナソニック、Rockwell Automation、キーエンス、Pepperl + Fuchsが挙げられる。日本企業のシェアは明らかでないが、高性能品を中心に相応のシェアを有しているものとみられる。
図 セイフティライトカーテン市場規模(2106年〜2021年)
⑤各用途に求められる技術特性 セイフティライトカーテンは人命に関わるシステムであるため、ロバスト性、信頼性が極めて重要される。また、製造ラインでの使用が中心であるため、生産性の低下を防止するブランキング機能やミューティング機能といった機能面も各社の開発ターゲットとなっている。
185
⑥国内企業、⑦海外の主要な競合企業 オムロン、パナソニック、Rockwell Automation、キーエンス、Pepperl + Fuchsがキーベンダーとみ
られている。また、Banner Engineering、Carlo Gavazzi、Datalogic、ISB、K.A. Schmersal、Leuze Electronic、Orbital Systems、Pinnacle Systems、Reer等がセイフティライトカーテンを展開している。
オムロン 2016年7月、同社はPLe/安全カテゴリ 4 SIL3対応の「F3SJシリーズ」を投入している。同シリーズには、指検出や特殊な用途に対応する高機能な ADVANCE タイプ、省配線コネクタを採⽤し、配線工数を削減したEASYタイプ、直列連結・ミューティング機能を搭載したBASICタイプの3つのタイプをラインナップ。用途に応じ、無駄なく安全対策を構築できるようにした。 ADVANCEタイプは、9mmの光軸ピッチで指検出用途に対応。生産性の低下を防止するブランキン
グ機能や多彩なミューティング機能を搭載したセーフティライトカーテンで、すべての設定がパソコンでできるPC設定ツールも用意、従来は複雑な設定を簡単にし、現場の安全対策をサポートしている。
パナソニック 同社は、PLe/安全カテゴリ2 SIL1及びPLe/安全カテゴリ4 SIL3のセイフティライトカーテンを豊富にラインナップ。超薄型の Type2「SF2C」や Type4「SF4C」、耐環境性能(IP67)を向上させた「SF4B」、国内のプレス機械、シャーの安全をサポートする「SF4B-□G Ver.2」、韓国プレス対応の「SF4B-03」など、その幅広いラインナップが強みとなっている。 2016年12月には、スリム&高剛性ボディとハイパワー新光学系を合わせ持ち、さらにセーフティライトカーテンの状態がひと目でわかるデジタル表示灯を内蔵した、⼩型・堅牢セーフティライトカーテン「SF4D シリーズ」を発売している。最小検出物体に応じて光軸ピッチが 10mm/20mm/40mm のタイプから選択でき、標準タイプから国内プレス機械・シャー対応タイプまでの幅広い製品をラインアップする同社セーフティライトカーテンの標準モデルと位置付けている。 Rockwell Automation 同社は指検知等の Point of Operation Control(POC)ライトカーテン、体の侵入を検知するPerimeter Access Control(PAC)及びArea Access Control(AAC)ライトカーテンを展開している。POC ライトカーテンでは、プラグイン式モジュールを介して各トランシーバをセンダまたはレシーバとして使用できる「450L-Bセイフティライトカーテン」等、PAC/AACでは、複数のビームを照射する短距離セーフティ・ライト・カーテン「PAC GuardShield タイプ4 セイフティライトカーテン」等をラインナップしている。 キーエンス Ple/Type4 SIL3適合のセイフティライトカーテン「GL-Rシリーズ」を展開している。同シリーズは、LED周囲に円形反射板を配置し、ハイパワー化。検出距離0.2 mから15 mまでのフルレンジ対応を実現
186
したほか、堅牢性能、汚れに強い、光軸ブレなし、選べる配線システムを特⻑としている。指検出(光軸10mm ピッチ/検出体φ14mm)、手検出(光軸 20mmピッチ/検出体φ25mm)、腕・脚・体検出(光軸 40mm ピッチ/検出体 45mm)のそれぞれに対応したバリエーションを取り揃え、ユーザーに最適なセイフティライトカーテンを提供できる体制を整えている。 Pepperl + Fuchs 同社は、type 2/ SIL1のセイフティライトカーテン「SLCT30 シリーズ」を展開している。分解能:
30mm(⼿検出)、保護範囲(⾼さ):〜2,400mm、温度範囲:-30〜60℃のスリムデザインタイプとなっている。
187
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
センサ技術の技術開発に携わる研究者の抽出に当たって、日本の研究.com により各種センサのキーワード検索を⾏った。センサそのものの研究以外のケースも抽出されたため、リストの中からセンサ技術そのものの研究に関して整理を⾏っている。なお、これらの研究者が産業⽤ロボットも想定した研究を⾏っているかは定かでない点に留意が必要である。
出所:日本の研究.com
188
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機
関
Google Scholarを⽤いた論⽂検索を実施、「Industrial Robot × 各種センサ」での抽出を⾏った。なお、センサそのもの技術開発から外れるものは除外している。
189
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
産業用ロボットへの適用を想定したセンサ技術に関わる研究開発プロジェクトは、「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」(NEDO)、「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」(NEDO)が挙げられる。 ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト 国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構 事業年度:平成27年度〜平成31年度、平成29年度予算:17.5億円 <概要> 本制度では、ものづくり分野及びサービス分野を対象として、ロボット活⽤に係るユーザーニーズ、市場化出口を明確にした上で、特化すべき機能の選択と集中に向けた新規技術開発を実施する。加えて、ロボットの導入コストの2割削減に向け、ロボットの本体価格を引き下げるべく、汎用的な作業・工程に使える汎用ロボットや双腕多能工ロボットのプラットフォーム化(ハードウェア・ソフトウェアの共通化)を実施し、これらの各分野のロボット未活⽤領域において、ロボット導⼊を促進する基盤を整備する。また、⽇本の強みである基幹部品や最終製品であるハードウェアを生かしつつ、これを活用するためのソフトウェアを強化し、オープンイノベーションを促進する。特に、三品産業を含むものづくり分野、物流・バックヤード等のサービス分野、⽣活⽀援分野など、多くの潜在市場がありながら導⼊が進んでいないロボット未活⽤領域へ導入していく。さらに、特化すべき機能の選択と集中による技術開発促進と、メーカー・SIer・ユーザーを巻き込んだ協業等による、利活⽤促進を同時に進め、技術開発の実施を通じて、現場ニーズに応じてロボットシステムを開発できる人材育成を支援する。 「産業ロボット用3次元ビジョンセンサの⾼度化開発」(3次元メディア) 平成27年度〜平成29年度の期間で実施。開発内容は、カメラ・プロジェクタ一体型の 3 次元ビジョンセンサを開発することにより、初期設定や設置時間の短縮と⼩型軽量化を図る。また、画像処理ボードをヘッドに内蔵することにより、さらなる処理の⾼速化を実現し、ロボットの応⽤範囲を広げていくとしている。
190
次世代人工知能・ロボット中核技術開発 国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構 事業期間:平成27年度〜平成31年度、平成29年度予算:43.5億円 <概要> 本プロジェクトでは、単なる現在の⼈⼯知能・ロボット関連技術の延⻑上にとどまらない、⼈間の能⼒を超えることを狙う革新的な要素技術を研究開発する。具体的には、人工知能技術やセンサ、アクチュエータ等のロボット要素技術について、我が国と世界の状況に鑑み、速やかに実用化への道筋をつける革新的な要素技術を研究開発する。このうち、センサ関連では、研究開発項目「革新的なセンシング技術(スーパーセンシング)」の中で、屋外等の外乱の多い空間でも、的確に信号抽出ができる画期的な視覚・聴覚・⼒触覚・嗅覚・加速度センシングシステムやセンサと⾏動を連携させて、検知能⼒を向上させる⾏動センシング技術等の研究開発を実施するとしている。
191
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府
支援策の有無(有る場合は該当箇所)
①米国 Federal Reporter を利⽤し、⽶国内での技術開発プロジェクトを検索した。「Industrial robot,
Sensor Technology」のキーワードで抽出できたものとしては以下の2件がある。US IGNITEはIOTに関連した次世代技術の研究開発を促進する、National Science Foundation支援のNPOである。一方、SBIR(Small Business Innovation Research program)は、米国研究機関NIH(National Insitute of Health)がプログラムマネジメントするシードファンドとなっている。
プロジェクト名
US IGNITE: COLLABORATIVERESEARCH: TRACK 1: INDUSTRIALCLOUD ROBOTICS ACROSSSOFTWARE DEFINED NETWORKS
SBIR PHASE II: OBJECT POSEESTIMATION SYSTEM FOR PICKAND PLACE ROBOTS
期間2015.9〜2018.8 2016.4〜2018.8
資⾦拠出元National Science Foundation National Science Foundation
予算⾦額$424,261 $746,168
参加機関
UNIVERSITY OF VIRGINIACHARLOTTESVILLE
PERCEPTION ROBOTICS
192
②欧州 産業用ロボット関連の政府支援政策は「アクチュエータ」の章を参照。ここでは、Cordisのデータベースから抽出したセンサ関連の研究開発プロジェクトをまとめた。なお、抽出に当たっては、「Industrial Robot, Sensor Technology」をキーワードに現在稼働中のプロジェクトから、センサ関連にプロジェクト内容が当てはまっているものを抜き出している。
プロジェクト名
SPIRITA software framework for theefficient setup of industrialinspection robots
ROCHIRobotics Coverage HiringInnovation
ESMERAEuropean SMEs RoboticsApplications
期間2018-01-01 to 2021-02-28 2017-09-29 to 2018-09-28 2018-01-01 to 2022-02-28
資⾦拠出元H2020-ICT H2020-INNOSUP H2020-ICT
予算⾦額EUR 3 732 751,25 EUR 115 625 EUR 7 999 998
参加機関
PROFACTOR GMBH, IT+ROBOTICSSRL, INFRATEC GMBHINFRAROTSENSORIK UNDMESSTECHNIK, UNIVERSITA DEGLISTUDI DI PADOVA, CENTRORICERCHE FIAT SCPA,VOESTALPINE BOHLER AEROSPACEGMBH & CO KG, FISCHERADVANCED COMPOSITECOMPONENTS AG
IT+ROBOTICS SRL UNIVERSITY CAMPUS RIO PATRAS,COMMISSARIAT A L ENERGIEATOMIQUE ET AUX ENERGIESALTERNATIVES, TECHNISCHEUNIVERSITAET MUENCHEN,FUNDACION TEKNIKER, BLUEOCEAN ROBOTICS APS, R.U.RobotsLimited, COMAU SPA
プロジェクト名
SYMPLEXITYSymbiotic Human-Robot Solutionsfor Complex Surface FinishingOperations
System4RoboticsStimulate ScaleUps to developnovel and challenging TEchnologyand systems applicable to newMarkets for ROBOtic soLUTIONs
Productive4.0Electronics and ICT as enabler fordigital industry and optimizedsupply chain management coveringthe entire product lifecycle
期間2015-01-01 to 2018-12-31 2018-01-01 to 2020-12-31 2017-05-01 to 2020-04-30
資⾦拠出元H2020-FoF H2020-ICT H2020-ECSEL
予算⾦額 EUR 8 046 375 EUR 8 074 961,25 EUR 106 372 715,35
参加機関
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZURFOERDERUNG DER ANGEWANDTENFORSCHUNG E.V., HOCHSCHULEAALEN - TECHNIK UNDWIRTSCHAFT, etc
(Coordinator) FUNDINGBOXACCELERATOR SP ZOO
INFINEON TECHNOLOGIES AG, ABBA, NXP SEMICONDUCTORSGERMANY GMBH, ROBERT BOSCHGMBH, SAP SE, etc
193
このほか、センサ関連の大型研究開発プロジェクトとして、ドイツ連邦教育・研究所(BMBF)がスポンサードした「AMELI4.0」がある。期間は2015年12⽉〜2018年11月、Robert Bosch GmbH、 Siemens AG、Fraunhofer IPK、Binder Elektronik GmbH、Schaudt Mikrosa GmbH、 STACKFORCE GmbHが参加している。内容としては、インダストリ 4.0 を想定したMEMSベースのマルチ・スマートセンサシステム(intelligent, autonomous multi-sensor systems)となっている。
プロジェクト名
COVRBeing safe around collaborative andversatile robots in shared spaces
OPTOFORCERobot Learning for UnprecedentedQuality and EfficiencyImprovements in the ManufacturingIndustry
SILENSE(Ultra)Sound Interfaces and LowEnergy iNtegrated SEnsors
期間2018-01-01 to 2021-12-31 2017-12-01 to 2018-03-31 2017-05-01 to 2020-04-30
資⾦拠出元H2020-ICT H2020-SMEINST H2020-ECSEL
予算⾦額 EUR 10 705 433,75 EUR 71 429 EUR 29 330 610,84
参加機関
TEKNOLOGISK INSTITUT,CONSIGLIO NAZIONALE DELLERICERCHE, FRAUNHOFERGESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNGDER ANGEWANDTEN FORSCHUNGE.V., etc
OPTOFORCE KFT NXP SEMICONDUCTORS BELGIUM,INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM,SOLMATES BV, SYNOPSYSNETHERLANDS BV, TECHNISCHEUNIVERSITEIT DELF, etc
194
③韓国 産業通商資源部は、「ロボット産業核心技術開発」に、2017 年 88.4 億円、2018 年には74.7
億円の予算を支援すると発表している。また、2018年には、「センサー産業⾼度化専⾨技術開発事業」に、約14億円の予算を支援する計画と発表している。 韓国産業技術評価院(KEIT)は、2016 年から国内⼤学を中⼼に、ロボットに関する 6 つのプロジェクトを進めている。その枠組みとして、韓国科学技術院(KAIST)は、「能動可変形ねじりメカニズム基盤超軽量(50g)、高性能(250N, 100mm/s)のロボット用腱関節駆動モジュール及び位置・剛性制御のための応用技術」プロジェクトを進めている。研究目標としては、①ねじり基盤変速メカニズム位置・⼒制御のための超⼩型張⼒センサーの開発、②腱連結構造設計耐久性増⼤とマニピュレータプロトタイプ1種開発、③腱基盤マニピュレータ設計張⼒維持/メンテナンスアルゴリズムの開発などが挙げられる。 <主な研究者及び所属機関>
④中国 中国に関しては、「ロボット産業発展計画(2016〜2020 年)」、「ロボット産業の急速な発展を促進する上での⼈⺠政府の⾒解」(2017年3月)の中で、センサも触れられている。これらの詳細は、アクチュエータの頁に記載済みのため、ここでは割愛する。ただ、ロータリエンコーダを手掛けるYuheng Optが2017年12月より「High-resolution angular displacement sensor development and industrialization」をスタートしている。詳細は明らかでないが、中国政府科技部が支援している。 ⑤台湾 台湾工業技術院(ITRI)がMEMSガスセンサ等の研究開発を⾏っている例はあったが、産業⽤ロボットでの利⽤を想定したセンサ開発のプログラムは確認できなかった。
出所:Naver学術情報より矢野経済研究所作成
195
(補足)ニュースまとめ
このほかの補足情報(研究費データ及び研究者の動向)は、対象製品が多く、個別に情報収集を⾏うことができないため除外。
2009 11 ローム MEMS慣性センサを得意とするKionix(米)を買収。
2012 1 村田製作所 3D MEMS技術を保有するVTI Technologies(フィンランド)を買収
2016 Cognex 3Dビジョン技術を持つAQSense、Enshapeを買収
2017 Cognex 3Dマシンビジョンセンサの開発を⾏っていたChiaro Technologies
3 TeledyneDALSA
撮像系技術を強みとする英e2vを買収
5 TDK MEMS慣性センサ大手のInvenSense(米)を買収
※対象製品/メーカーが多いため、ここではセンサ関連のM&Aについてまとめた。
*各社ニュースリリースならびに新聞雑誌記事から抽出
202
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
人体に装着し、能力の向上や身体の補助をおこなう装置。別称として、「強化スーツ」、「ロボットスー
ツ」、「パワーアシストスーツ」、「ウェアラブルロボット」などがある。英名でも統一されておらず、
「exoskeleton」「powered exoskeleton」「powered armor」「wearable robot」など様々な称
呼がある。
パワードスーツには動力があるタイプとないタイプが存在する。動力があるタイプについては電動アクチュエ
ータや人工筋肉などを用いて、動作の補助や歩行支援などをおこなう。また、筋電位などを読み取りって
動く筋電義肢や重量物を体の負担にならないよう吊り上げるツールホールディングの様なものもある。動力
の無いタイプはゴムやバネを使用するサポーターの発展型であり、バイオメカニクスや人間工学などを応用
して効率的に機能するよう設計されている。
また、最近の傾向として、バッテリーパックとコントローラを除き、その他すべてに柔らかい素材だけを使っ
たパワードスーツ(英名:Soft exoskeleton)が注目を浴びている。特徴として、軽量であり、着脱が
容易で服の下に着用できるなどがある。しかし、アクチュエータのパワーが直接使用者の身体に影響を及
ぼすため、保護する仕組みが必要である。
素材としては軽くて丈夫なものが好まれる為、炭素繊維や CFRP が使われていることが多い。また、米
軍が開発中の TALOS はアラミド繊維を採用している。
パワードスーツを構成する重要技術として特に重要なものはセンサ、アクチュエータ、バッテリの3つにな
る。これは、パワードスーツが人に身につけて使用するものであり、長時間使用する機会も多いためである。
無動力式の物を除き、ほとんどはセンサを使用して人間の動きを把握し、それに合わせて駆動する。その
ため、センサの精度の高さはもちろん、日常的に稼動し続けるための耐久性や軽量さが求められる。また、
アクチュエータとバッテリについても、小型軽量で高出力・大容量の物が望まれる。
〇パワードスーツの用途
補助具型 体への負担を軽減する。人力以上のアシストはおこなわれない。介護や農業などの重
労働をおこなう人向け。
歩行支援型 杖・義足・脚サポーターの発展版。老化や麻痺などによる歩行困難を解決する。
筋電義肢型 筋電位などを読み取り、自動で動く義肢。
リハビリ型 歩行用リハビリ用機器の一種。歩行支援型も兼ねる製品もある。
アーマー型 銃弾から身を守るなど、軍事用に用いられる防具。戦闘用の機能を搭載していることが
多い。
能力拡大型 重いものを機械の力で持つなどを目的とする。ただし、急激な運動や機動による人間の
骨格や筋肉へのダメージを防ぐ技術が必要となる為、制御等に高度な技術が必要。
CYBERDYNE や ATOUN などが製品開発をしている。
動作拡大型 自分の動きに連動して、パワードスーツが動く。現在は観賞用として用いられている。
204
〇パワードスーツの動力
電動式 小型・軽量でかつ出力も大きいため、一般的に用いられている。
空気圧式 人工筋肉などに使われている。使用者が直接空気を供給するタイプとコンプレッサ
ーなどで充填するタイプに分かれる。
無動力式
(ゴム・バネなど)
人間工学のデザインなどに基づく、サポーターの発展型が多い。軽量で着用型が
多い。
油圧式 高出力であるが他の動力に比べて重くなるため、あまり使用されていない。
〇利用方法
装着型 最も一般的に用いられていて方法で、衣服の上などからパワードスーツを取り付ける。構造
上、着脱に時間がかかる傾向がある。
着衣型 衣服のように着るため、着脱が容易。無動力型で多く採用されている。
搭乗型 パワードスーツに乗り込む方法。動作拡大型で用いられている。
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
パワードスーツでは、転倒防止等のための安全設計、軽量設計(機能集約化等)が代表的な機能
要求として挙げられる。中でも、安全設計は人に装着するものであるため、極めて重要ファクタとして取り
扱われており、CPU やセンサ類の故障に起因する暴走等の異常動作を常時するための監視機能だけで
なく、CPU の二重化、通信系統の二重化といった冗長性の確保が求められる。また、人との親和性向上
のための制御系設計として、バックドライバビリティの確保に加え、自然な負荷アシスト機能、より簡易な
方法での高度な状態推定機能も各社の開発対象となっている。
実際、今後パワードスーツの導入が期待されるインダストリアルユース(工場などにおいて重労働の負担
を軽減する能力拡大型)では、重量物の梱包工程や住宅パネルの製造工程(サイバーダイン、旧アク
ティブリンク)、食料品製造現場(イノフィス)で試験的に導入され、作業者の腰の負担軽減等の効果
が得られた反面、単純な繰り返し動作でないため、行動範囲が狭まる、必要のないところでアシストやブ
レーキが作動するといった問題点が明らかになっている。このため、拘束を少なくし、精度よく状態推定を
行うためのより高度な制御として、9 軸モーションセンサ(3 軸ジャイロセンサ+3 軸加速度センサ+3 軸
電子コンパス)の応用が進められており、これに係る技術として、低消費電力・高速演算チップ、信号処
理アルゴリズム、無線機能等もアップグレードが必要となっている。
これらの安全設計や制御系設計といった技術は、広く産業用ロボット、サービスロボットに適用できる技
術として拡がりを持つほか、状態推定のためのセンサフュージョン(推定アルゴリズム)は移動物体の運
動推定、リアルタイム検出などにも通じるロボット工学の最新テーマとなっている。
実際、九州工業大学柴田教授は、機械学習を取り入れた状態推定をパワードスーツに応用する研究
205
「機械学習を用いた表面筋電位信号から手指の連続的状態推定とそのロボット応用」を行っており、表
面筋電位信号の電気力学的モデルと教師有学習アルゴリズムを適用することで、 五指の連続的姿勢
情報の推定が精度良く可能であることを明らかにしている。
また、これら制御系の技術だけでなく、人工筋肉などのアクチュエータ技術は産業用ロボットやサービスロ
ボット、パワードスーツなどのほか、生体内埋め込み型人工臓器や空気圧を電気エネルギーに変換し蓄
積するエナジー・ハーベスト・デバイスなどへの応用も期待される。さらに、サーボモータ技術の小型・静音
化(歯車の改良や高剛性ボディ等)、精密・軽量化技術(アルミ、チタン等)も産業全般に応用範
囲が拡がる研究開発テーマの 1 つと位置付けられる。
206
米 Grand View Research(以下、GVR)の調査によると、世界のパワードスーツ市場規模は
2016 年、50 億円規模であった。ヘルスケア分野(リハビリ支援、歩行補助)がメインアプリケーション
(シェア 50%超)となっており、その他、アーマー型などがデモンストレーション用に供給されている。
当該市場におけるキープレイヤーの 2016 年度売上高(公表ベース)で比較すると、Cyberdyne:
16.49 億円、Ekso Bionics:12M US ドル(13.44 億円, 112 円/US ドル)、Rewalk:5.8M
US ドル(6.5 億円, 112 円/US ドル)となっており、サイバーダインが相応の存在感(シェア換算で
33%程度)を確保している。GVR では、注目プレイヤーとして Rex Bionics、Hocoma、アクティブリン
ク(現 ATOUN)、Parker Hannifin Corporation を挙げており、特に Parker Hannifin
Corporation は U.S. Department of Defense(DoD)等から支援を受け、2015 年 10 月から
4 年間のデモンストレーションプログラムにおいて同社パワードスーツ“Indego”(既に FDA の認可も取得
済み)を供給、今後の生産台数拡大が期待されているとのことである。
地域別では、北米(シェア:50%)、欧州、日本、アジアの順にマーケットが形成されているが、今後
日本を含むアジアでの需要拡大に期待が集まるとの見方である。しかし、北米地域においても DARPA、
NASA、NIH が技術開発、実用化支援のための資金を相当に積み増しており、これの取り組みが市場
急拡大の引き金になるとしている。
こうしたことから、GVR では、2025 年の市場規模を全体で 33 億 US ドル、このうち、16 億 US ドルが
北米地域と予測しており、ヘルスケア、防衛だけでなく、インダストリアルユース(負担軽減等)での応用
も進むとの見方を示している。
208
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
現在、主流の補助具型、歩行支援型などで利用される装着型(外骨格型)パワードスーツでは、
主にセンサ及び動作制御に各社のノウハウがつぎ込まれている。センサとしては、姿勢制御のための角度
センサ、加速度センサ、ジャイロ(角速度)センサ、関節制御のためのトルクセンサ、荷重センサ等が使
用されている。姿勢制御にはロボットなどで多用される慣性計測ユニット( IMU; Inertial
Measurement Unit)が用いられるケースもあるが、これらセンサで得られる情報を融合し、協調制御
できるようなシステムを各社が自社の設計思想等に基づきながら設計している。
また、支援動作(パワーアシスト)の決定に際し、筋電位信号(BES)を読み取る方式を取り入れ
ているケースもある。サイバーダインは、人の筋電を計測することで、実動作の前の意思情報をくみ取り制
御する方法(サイバニック制御手法)を HAL 採用している。
HAL の基本的な制御ロジック
出所:サイバーダイン資料より
具体的には、HAL は、機器に内蔵された角度センサ、足底荷重センサ、体幹絶対角度センサから得ら
れた情報と、装着者の皮膚表面に貼り付けられた電極を通して得られた生体電位信号の情報とを用い
て支援動作を決定し、状態に応じて各関節に配置されたパワーユニットを駆動させることで、装着者の下
肢関節動作をアシストするように設計されている。
皮膚の表面では、様々な生体電位信号、あるいは外部からのノイズが重なり、それらを検出・解析す
るのは難易度が高いが、山海教授らは膨大なデータを収集し、解析と実験を繰り返すことで、歩行運動
をしながら、なおかつ制御用のコンピュータやモータなど強い電気信号(ノイズや磁界)を発する機器があ
る中でも、正確に信号を感知できるセンシング技術、キャリブレーション技術、信号を解析し、適切に制御
できるサイバニック制御手法を実現している。
ただ、パワードスーツの中でも、高アシスト力を要する能力拡大型(主に産業利用が想定される)では、
アクチュエータの高出力化などによりノイズが増加すること、生産現場等での利用を考慮するとキャリブレー
ションの手間等(筋電位は個人差があることに加え、その日の体調や環境によっても変化するため、使
用時にキャリブレーションが毎回必要との見解も多い)から、筋電センシング手法を採用せずに状態推定
を行うような機能を開発するケースも多い。
209
三菱重工では、重作業向けパワードアシストスーツ(PAS)の開発において、足裏センサ、慣性センサ
の情報により状態を推定できる独自のアルゴリズムを採用している。詳細は明らかでないが、同 PAS に実
装されている状態推定アルゴリズムとしては、棚上げ降ろしアシスト機能(足裏荷重の時間変化から足
の上げ下ろしを推定し、それをアシストするようなアクチュエータ指令を生成)、歩行アシスト機能(慣性
センサにより歩行中の脚の運びの情報を蓄積し、学習することで、次の歩行起動を生成)などを挙げて
いる。
パワードスーツに使用されるアクチュエータとしては、電動式(サーボモータ/減速機)が一般的。ただ、
例えば、歩行支援の場合、歩行に必要な主要関節となる腰、ひざ、足首などの複数箇所にモータを配
置する必要があり、消費電力の大きさ、電池駆動時間の短さが問題となっている。また、小型化も同様
に重要な課題と位置付けられており、日本電産などのサーボモータメーカーは軽薄短小のアシスト用サー
ボモータやトラクション減速機(関節駆動用減速機)を製品化している。
また、パナソニックは 2016 年に GaN パワートランジスタ製品「X-GaN」の表面実装型を製品化、パワ
ーアシストスーツを駆動する AC サーボモータのインバータにこれを用い、一体化することで、従来と比べ2/
3のサイズまで小型化できることを明らかにしている。
このほか、電動式ではなく、人工筋肉を用いたシステムの開発を行っている企業(日本ではイノフィス)
もある。人工筋肉とは、ゴムや導電性ポリマー、形状記憶合金、カーボン・ナノチューブなどで作られた伸
縮性のアクチュエータで、空気圧等で伸縮するゴムタイプの人工筋肉(マッキベン型人工筋肉)は作動
力が大きく、作業機械やロボット、パワードスーツなどへの応用が期待されている。
東京工業大学(鈴森康一教授)とブリヂストン(櫻井良フェローら)の研究チームは、内閣府総
合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)タフ・ロボティ
クス・チャレンジの一環として油圧駆動のハイパワー人工筋肉を開発している。
210
同人工筋肉は、ゴムチューブと高張力繊維から構成され、油圧で動作するもので、ゴムチューブと高張
力繊維によりなめらかな動きを実現するとともに、油圧での動作を可能とすることで高い力/自重比、高い
耐衝撃性/振動性、さらに、作業に応じて柔らかい動作も可能など、これまでにない特長を実現してい
る。
211
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
*その他、川崎重工(身体負担軽減)、エルエーピー(手のリハビリ、協力:神奈川工科大学)、
H2L(手指の電子制御、東京大学発ベンチャー)、玉川大学、山口大学、福岡県工業美術センター、
産業医科大学(協力:福岡県工業技術センター)、オーケー・ロボティクス(東京農工大発ベンチャ
ー)、広島大学(協力:ダイヤ工業)、ユーピーアール株式会社(協力:金沢大学、山本寛斎事
務所)などが研究開発を行っている。
組織名 商品名 主な用途 特記事項
アスカ株式会社 WPAL ウーパル 下肢麻痺者用電動レバーとボタンで操作
株式会社今仙技術研究所 ACSIVE アクシブ 歩行支援 無動力(バネと振り子)
CYBERDYNE株式会社 HAL 医療・歩行支援・負担軽減
電動センサーで生体電位信号を検知能力拡大・災害対策用を開発中関連機器売上 \1,649,940
住友理工株式会社 歩行アシストスーツ 歩行支援電動センサーで動きを検知2017/10発売予定
Honda歩行アシスト 歩行支援電動センサーで動きを検知
体重支持型歩行アシスト 負担軽減電動センサーで動きを検知研究開発中
アシストモーション株式会社 curaraパンツタイプ 歩行支援電動センサーで動きを検知体内埋め込み型を開発中
株式会社 MICOTOテクノロジー(旧:株式会社テムザック技術研究所)
Active Gear(変更の可能性あり)
下肢麻痺者用電動ボタンで操作研究開発中
トヨタ自動車株式会社 歩行支援ロボット 下肢麻痺者用
電動センサーで動きを検知ボタンでモード切替研究開発中
株式会社ATOUN AWN-03B 負担軽減電動センサーで動きを検知
株式会社イノフィス マッスルスーツ 負担軽減 空気供給による人工筋肉
ラクベスト 負担軽減電動ボタン等による調整
クボタウインチ型パワーアシストスーツWIN-1
ツールホールディング(荷物吊り上げ)
電動ボタン操作
株式会社スマートサポート スマートスーツ 負担軽減 無動力(ゴム)
パワーアシストインターナショナル株式会社
パワーアシストスーツBuddy バディ
負担軽減電動センサーで動きを検知製造販売:ニッカリ
株式会社モリタホールディングス rakunie ラクニエ 負担軽減 無動力(ベルトの張力)
スケルトニクス株式会社 スケルトニクス搭乗型パワードスーツ(動作拡大)
無動力(リンク構造)
佐川電子株式会社 パワードジャケットMK3搭乗型パワードスーツ(動作拡大)
電動センサーで動きを検知
イクシー株式会社Hackberry(handiiiシリーズ)
筋電義手
電動センサーで表面筋電位を検知ソフトウェア等をオープンソース化し、3Dプリンタにより数万円で作成可能
本田技研工業株式会社
株式会社クボタ
212
1. アスカ株式会社
住所:〒448-0002 愛知県刈谷市一里山町東吹戸 11 番地
TEL :0566-36-7771
FAX :0566-36-8090
自動車部品事業・配電盤事業・ロボットシステムを事業とする会社
商品①:WPAL(ウーパル)(協力:藤田保健衛生大、東名ブレース株式会社、株式会社ティム
ス、愛知県立芸術大学)
目的・機能:歩行支援 下肢麻痺者の起立・着座・歩行補助ロボット
価格:4,000,000 円(市場価格)https://www.hcr.or.jp/search/149780
リンク:
http://www.aska.co.jp/contribution/wpal.html
http://www.tomeibrace.co.jp/catalog/pdf/reha06.pdf
http://www.astf.or.jp/project/suishin/ikusei/files/22-2.pdf
ターゲット:主にリハビリ病院向けに臨床研究目的での販売
詳細:
歩行再建装具の内側系装具に動力と制御を付加した装着型歩行補助ロボット。
下肢麻痺者の車いすからの起立・着座・平地歩行のパワーアシストを目的とする。
従来の装具の問題である、歩行時の上肢への大きな負担と車いすからの起立・着座の困難である問題を
解決するために開発された。現在は主にリハビリ用に使われている。
内側股継手付き長下肢装具に,6個のモータ(両側・股・膝・足関節)が取り付けられている。それぞれ
のモータをタイミングよく動かすことによって,健常人に似た歩行パターンを再現できる。レバーやボタン、バッ
テリーなどの制御部を歩行器に内蔵することで、余分な負荷がかからず、着用者一人で操作することがで
きる。
213
2. 株式会社今仙技術研究所
住所:〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 3 丁目 1 番 8 号
TEL :(058)379-2727(代表)
FAX :(058)379-2726(代表)
福祉機器・電気及び機械応用製品の研究開発及び製造販売を事業とする会社
商品①:歩行支援機 ACSIVE(アクシブ)(協力:名古屋工業大学 佐野明人教授)
目的・機能:歩行支援 自立歩行の補助
価格:片脚用 180,000 円(税別) 両脚用 350,000 円(税別)
リンク:
http://www.imasengiken.co.jp/acsive/index.html(写真使用)
http://www.imasengiken.co.jp/acsive/acsive.html(写真使用)
ターゲット:現在安全に自立歩行できるが、病気・怪我・老化などで歩きの弱まった人
詳細:
バネと振り子の力によって作動する歩行支援機であり、弱った歩きの調子を整えることを目的とする。両足
用と片足用がある。無動力のため、軽量・充電不要・無音・平易な脱着などの特徴があり、長時間の使
用でも体への負担が少ない(トイレやお風呂、就寝中は外す必要あり)。腰ベルトとカーボンチューブの交換
によって腰と脚部の長さを調節できる。ダイヤルヘッドを回すことで簡単にバネのアシスト力を調整することも
できる。
214
3. CYBERDYNE 株式会社(筑波大学発ベンチャー)
住所:〒305-0818 茨城県つくば市学園南2丁目2番地1
TEL :029-855-3189
FAX :不明
筑波大学発のベンチャー企業。大株主の大和ハウス工業が一部商品の総販売代理店を展開。
商品①:HAL医療用(下肢)(JP 版・EU 版)
商品②:HAL福祉用(下肢)
商品③:HAL自立支援用(単関節)
商品④:HAL介護支援用(腰)
商品⑤:HAL作業支援用(腰)
商品⑥:フルボディHAL〈研究開発段階〉
商品⑦:HAL災害対策用〈研究開発段階〉
目的・機能:
商品①:医療・歩行支援 下肢の障害、脚力の弱体化の治療及び歩行補助
商品②:歩行支援 歩行や立ち座りのトレーニングをアシスト
商品③:関節動作支援 関節の曲げ伸ばし運動補助
商品④:腰部負担軽減 移乗介助や体位変換介助などの介護動作に特化して対応
商品⑤:腰部負担軽減 物を持ち上げる、動かすなどの重作業に特化して対応
商品⑥:上肢から下肢まで全身の身体機能を拡張し、人力では不可能な重作業を可能
商品⑦:強化全身フレーム(チタン・炭素強化プラスチック)、放射線遮へいジャケット、装着者用冷却
装置、バイタルセンシングシステムを装備。モジュール構造により、短時間での着脱、全天候かつ
不整地でのレスキュー活動が可能
価格:全て税別※個人向け商品はなし(2017/6/27 時点)
商品①:不明
商品②:レンタル/リース(期間 6 ヶ月・1 年・3 年・5 年)
(両脚)初期導入費用 550,000 円 月額 158,000 円~188,000 円
(単脚)初期導入費用 400,000 円 月額 118,000 円~139,000 円
商品③:5 年レンタルのみ 初期導入費用 400,000 円 月額 130,000 円
商品④:3 年レンタルのみ 初期導入費用 100,000 円 月額 78,000 円
商品⑤:不明
リンク:
https://www.cyberdyne.jp/
http://www.daiwahouse.co.jp/robot/hal/index.html
https://www.obayashi.co.jp/technofair2016/03robotics/03 02.html
https://www.limousinebus.co.jp/company/history.html
215
ターゲット:
商品①:医療機関
商品②:医療・福祉等の施設
商品③:医療・福祉等の施設
商品④:医療・福祉等の施設
商品⑤:物流、ものづくり、建設・土木業界などの身体への負担が大きい企業
詳細:
HAL®(Hybrid Assistive Limb®)は、身体機能を改善・補助・拡張・再生することができる、
世界初のサイボーグ型ロボット。独自開発したセンサが、脳から神経を通じて筋肉へ送られた信号のうち皮
膚表面から漏れ出た微弱な信号“生体電位信号” を読み取り、自動でHALが動作する。
商品①HAL医療用(下肢)は、日本及び EU 全域で医療機器として認証されており、世界初の機
能改善治療用ロボット医療機器となった。
商品⑤HAL作業支援用(腰)は、大林組や東京空港交通などの会社にて実際に使用されている。
216
4. 住友理工株式会社
住所:〒450-6316 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 JP タワー名古屋
TEL :052-571-0200
FAX :052-571-0225
商品①:歩行アシストスーツ〈研究開発段階〉(協力:九州大学)
目的・機能:足腰の運動機能が低下した高齢者の歩行訓練支援機器
価格: 未定
リンク:
https://www.sumitomoriko.co.jp/pressrelease/2016/%EF%BD%8E51910331.pdf
(画像)
http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/event/15/100500007/101400021/(画像)
ターゲット:足腰の運動機能が低下した高齢者
詳細:
着用者が歩く動作をセンサーで検知し、左右の脇腹にあるモータが左右の足に固定したベルトを巻き取る
ことで、足の振り出しを補助する。
柔軟な構造で、衣服の下に装着して日常生活で気軽に使える特徴を持つ。
217
5. 本田技研工業株式会社
住所:〒107-8556 東京都港区南青山 2-1-1
TEL :03-3423-1111(代表)
FAX :
商品①:Honda 歩行アシスト
商品②:体重支持型歩行アシスト〈研究開発段階〉
目的・機能:
商品①:脚力が低下した人の歩行補助
商品②:脚部負担軽減
価格: NA
リンク:
http://www.honda.co.jp/robotics/rhythm/index.html(画像)
http://www.honda.co.jp/robotics/weight/index.html
ターゲット:
商品①:高齢者など脚力が低下した人
商品②:脚部に負担のかかる生産現場、自力歩行できるが階段や坂道に苦労する人
詳細:
商品①Honda 歩行アシストは、「倒立振子モデル」に基づく効率的な歩行をサポートする歩行訓練機
器。歩行時の股関節の動きを左右のモータに内蔵された角度センサーで検知し、制御コンピュータがモータ
を駆動する。股関節の屈曲による下肢の振り出しと伸展による下肢の蹴り出しの誘導を行う。
商品②体重支持型歩行アシストは、機器につながった靴を履いてシートを持ち上げるだけでアシストを開
始できる。身体に機器を固定するベルト等は不要であり、脚の間に機器を配置する構造としたことで、幅
を取らず、人が歩くような自由自在な動きが可能。
218
6. アシストモーション株式会社(信州大学発ベンチャー)
住所:〒386-8567 長野県上田市常田 3-15-1
TEL :0263-35-4600(代表)
FAX :不明
2017 年 1 月設立の信州大学発のベンチャー。信州大繊維学部の橋本稔教授が社長を務める。※住
所等の記載がないため、信州大学の情報を記載
商品①:curara パンツタイプ(協力:東京都立産業技術研究センター)
目的・機能:
商品①:要介護者の自立支援を目的とする非外骨格型の身体装着型ロボット
価格: 不明
リンク:
http://www.shinshu-u.ac.jp/zukan/cooperation/curara2015.html
http://www.shinshu-u.ac.jp/zukan/cooperation/curara2016.html
http://www.shinshu-u.ac.jp/guidance/publication/summary/2015/curara/#page=1
https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/2938.pdf
https://www.iri-tokyo.jp/uploaded/attachment/4249.pdf(画像)
ターゲット: 生活動作に支援が必要な人
詳細:
信州大繊維学部の橋本稔教授が開発している curara には上肢モデルと下肢モデルがある。最新の
curara である下肢モデルの curara パンツタイプはユニットをパンツと一体化することにより、介助なしで装
着可能で着用時間も 3 分ほどとなった。
Curara の特徴として、神経振動子を制御に用いることで人に同調できる同調制御法、人とロボットの間
に生じる力を検出する相互作用トルク検出法、動きやすく、装置の着脱が容易な非外骨格構造の3つ
がある。2017 年 1 月には量産化及び商用化を目的に大学発ベンチャーが設立された。
219
7. 株式会社テムザック技術研究所
住所:〒683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎 2319-3
TEL :0859-30-4275
FAX :
商品①:Active Gear(アクティブギア)〈研究開発中〉(協力:台湾/工業技術研究院(ITRI)、鳥取大学医
学部附属病院、早稲田大学理工学術院ヒューマノイド研究所、株式会社アダチなど)※2014 年 3 月のプレスリリー
スから追加の情報はなく、企業ウェブページなどにも記載はない。
目的・機能:
商品①歩行補助だけにとどまらず、健常者と同じようにスポーツができる、といった生活範囲を広げる機器
価格: 未定
リンク:
http://www.tmsuk-rd.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/Active-Gear-tmsuk-rd-140324.pdf
(画像)
ターゲット: 歩行に介助が必要な人
詳細:
台湾の工業技術研究院(ITRI)がべースロボットを提供し、テムザック技術研究所が商品化開発する開発体制。
2014 年 3 月のプレスリリースから1~2年以内に商品として発売予定だったが、2014 年 3 月のプレスリリースから追
加の情報はなく、企業ウェブページなどにも記載はない。
プレスリリースによると
・股関節及び膝関節のパワー支援、歩行、立ち座りなどの移動に、無駄な力を省く
・腰部にて開閉装置付け、装着利便性を向上(着脱が簡単)
・歩行する際の動作指令を筋電位によらずコントロールクラッチにあるスイッチで行う
などの特徴がある。
220
8. トヨタ自動車株式会社
住所:〒471-8571 愛知県豊田市トヨタ町 1 番地
TEL :(0565)28-2121(代)
FAX :
商品①:歩行支援ロボット〈研究開発中〉
目的・機能:
商品①片足の麻痺により歩行が不自由になった人に自然で安全な歩行をアシストする
※2011 年のプレスリリースより情報なし
価格: 未定
リンク:
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/partner robot/technical presentation/
http://www.toyota.co.jp/jpn/tech/partner robot/family 2.html#h203(画像)
ターゲット: 片足に麻痺がある人
詳細:
2011 年にプレスリリースを行われた製品。リハビリでの機能回復をサポートし、リハビリ後は日常生活の
様々なシーンでの歩行と生活の動作をアシストすることで利用者が自立してより豊かでアクティブな生活を
おくれるようにサポートする。
製品の特長は、マルチセンサ・インテリジェント制御(協調制御)として、大腿部姿勢制御センサと足裏
荷重センサにより、装着する人の大腿部姿勢と足裏の荷重を検知。歩く人の歩幅や速度に合わせて膝の
アクチュエータの制御により、最適な歩行アシストを実現する。また、膝関節の特殊リンク機構により、足の
振り出しから、地面に足を着地して体重を支えるタイミングまで、確実に膝をロックすることで、膝折れするこ
となく、安心して歩行することができる。
221
9. 株式会社 ATOUN
住所:〒 631-0801 奈良県奈良市左京 6 丁目 5-2
TEL :0742-71-1878
FAX :0742-71-1888
パナソニック社内ベンチャーより設立し、三井物産株式会社と業務・資本提携
資本金 4 億 7200 万円(パナソニック(株)69.8% 三井物産(株)29.9%)
商品①:AWN-03B パワーアシストスーツ ATOUN MODEL A
商品②:AWN-03B パワーアシストスーツ ATOUN MODEL As
目的・機能:
商品①腰部負担軽減
商品②腰部・腕部負担軽減
価格:オープン価格
リンク:
http://atoun.co.jp/products/atoun-model-a/(写真使用)
http://atoun.co.jp/products/atoun-model-as/(写真使用)
ターゲット:物流、ものづくり、建設・土木業界などの身体への負担が大きい企業
詳細:
腰部負担の軽減に特化したアシストスーツ(商品②には腕の負担を軽減するアタッチメントが追加されて
いる)。使用者の腰の動きに追従してギアが回転し、太腿を引く力と背中から上体を引き上げる力が働く
ことによって腰への負担を軽減する。商品②には肩口から二股にのびるアームがあり、そこのベルトの先をグ
ローブなどにつなげることで腕部の負担も軽減する。
222
10. 株式会社イノフィス(東京理科大学発ベンチャー)
住所:〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-2-2 東京理科大学森戸記念館 3 階
TEL :03-5225-1083
FAX :03-3260-3400
商品①:マッスルスーツ 標準モデル・軽補助モデル・スタンドアロンモデルがある。さらに標準モデル・軽補
助モデルはエアー供給方法としてタンク式と外部供給式に分かれ、スタンドアローンモデル(2017 年)は
タイトフィットとソフトフィットに分かれる。
標準モデル 最大補助力 35.7kgf タンク式重量 8.1kg 外部供給式 6.6kg
軽補助モデル 最大補助力 25.5kgf タンク式重量 6.7kg 外部供給式 5.2kg
スタンドアローンモデル(2017 年) 最大補助力 25.5kgf タイトフィット 5.0kg ソフトフィット 5.1kg
目的・機能:
商品①:介護や重筋作業の現場で、人や物を持ち上げる際の体の負担を軽減
価格: 問い合わせ
リンク:
https://innophys.jp/
ターゲット:介護、物流、建設、農業などの肉体労働を主として働く人
詳細:
「マッスルスーツ」は外骨格型の装着型動作補助装置(ウェアラブルロボット)。空気圧式 McKibben 型
人工筋肉で標準モデルでは最大 35.7kgf、軽補助モデルとスタンドアローンモデルでは最大 25.5gf ほど
の補助力を実現し、装着者の動作をアシストする。非常に強い力で収縮する空気圧式の人工筋肉を原
動力としているため、バッテリーなどはないがエアーを供給する必要がある。
エアー供給方法はタンク、外部供給、スタンドアローンの3タイプがある。標準モデルと軽補助モデルはタン
ク式と外部供給式から選び、スタンドアローンモデルはスタンドアローン式のみである。タンク式は、機体に搭
載したタンクの中に充填しておいた空気を使う。1回の充填で約 20 回の動作が可能。大きな音がでるコ
ンプレッサー使用が難しい介護などに向いている。タンク式の場合、口にくわえたマウスピースに呼気を出し
入れする呼気スイッチでマッスルスーツの動作を制御する。
外部供給式はエアーコンプレッサーからホースを通して供給される空気を使用するタイプで、動作回数の制
限なく使用できる。タンクを搭載していないため、タンク式よりも標準モデル・軽補助モデルとも 1.5kg 軽
い。 重量物の持ち上げなどの繰り返し動作に適しており、電源が確保できる工場に向いている。外部供
給式は呼気スイッチと胸元に装着したセンサーで管理するタッチスイッチから制御方法を選べる。
スタンドアローン式は手押しのポンプで充填した空気を使用する。屋外で風雨にさらされるため、電子部品
の使用に抵抗がある農業などに向いている。また、スタンドアローンモデルはももパッドと脚の間の広さで、ス
ムーズな歩行が可能なソフトフィットと強い安定感があるタイトフィットの2種類ある。
223
11. 株式会社クボタ
住所:〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 47 号
TEL :06-6648-2111
FAX :
商品①:クボタアシストスーツARM―1D
商品②:クボタウインチ型パワーアシストスーツWIN-1
目的・機能:
商品①:主に果樹作業用 アームの角度を調整して肘を支え、腕をあげての作業を楽にする。
商品②:コンテナ積み下ろし・運搬作業用 インチワイヤによる吊り上げ
価格:
商品①:120,000 円(税別)希望小売価格
商品②:
リンク:
http://www.jnouki.kubota.co.jp/product/kanren/assist suit/index.html
http://www.jnouki.kubota.co.jp/product/kanren/win-1/
ターゲット:
商品①:主に果樹作業者
商品②:重量物の積み下ろしや運搬作業をする人
詳細:
商品①は 2013 年から発売開始した、果樹の棚下作業に特化した上体用。リュックサックのように背負う
タイプで、ベルトで使用者の体に調整することができる。腕とスーツの重量を胴体で支える構造のため、肩
に負担がかからず簡単に着脱できる。腕の動きを肩部分のラチェット機構と腕部分のセンサーで検知して
固定、レイドバルブでラチェット固定を解除する。上腕部を支えることで、腕を持ち上げる分の力が不要とな
り、作業が楽になる。
2016 年 3 月に改良され、腕の固定角度範囲を地面と水平から±90°まで可能とし、6°ごとに固定が可
能となり、その範囲で腕を動かせるようになった。電源として、単3電池4本で8時間以上の連続使用が
可能。
商品②は 2017 年 1 月に販売開始した。ウインチワイヤによって約 20kg のコンテナを吊り、上げ下げする
ことができる。使い方は、リュックサックのように背負い、肩の部分からぶら下がっているワイヤウインチの先をコ
ンテナの取手口に引っかけ、手で固定しながら運ぶ。膝にアシスト機能ついているため、コンテナの上げ下げ
時に、下肢に負担が行くこともない。
現在は、コンテナだけが対象となっているが、段ボール箱と米袋への対応を検討中ということで、農業でのさ
らなる利便と他分野での活躍が期待できる。
225
12. 株式会社スマートサポート(北海道大学発ベンチャー企業)
住所:〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目7番地 愛生舘ビル4階
TEL :011-206-1462
FAX :011-206-1463
商品①:スマートスーツ
目的・機能:
商品①:ゴムの張力で軽労化効果(人力作業の疲労・労力を軽減)を発生させる
価格:36,000 円(税別)試験販売中
リンク:
http://smartsupport.co.jp/
http://smartsuit.org/
http://smartsuit.org/news/renewal/
ターゲット: 農作業、配送作業、介護作業、運搬作業従事者向け
詳細:
作業姿勢の動作解析から、ロボット技術によって設計された“軽労化”スーツ。弾性体(ゴム)の張力だ
けで軽労化効果を発生させるため、安価で優れた着心地と高い安全性が特徴。
上半身を引き起こすアシスト効果と腹部を引き締め体幹を安定させるコルセット効果 2 つの補助効果によ
り、中腰姿勢の維持や重量物の持ち上げによるカラダへの疲労と負担を軽減させ腰痛等の疾病リスクを
予防する。
スマートスーツは何度も改良・リニューアルが施されており、初期型、ライト、プロ、イン型、アウト型などが存
在したが、今販売しているのは最新作の1種類のみである。最新作では、肩ベルト×2、腰ベルト、膝上
ベルト×2で体に固定させる。ベルトを別売りの専用エプロンで隠す、作業着の中にインすることもできる。
227
13. パワーアシストインターナショナル株式会社(和歌山大学発ベンチャー企業)
住所:〒640-8510 和歌山県和歌山市栄谷 930
TEL :073-457-8172
FAX :
和歌山大学発ベンチャー企業。この会社が 2016 年 10 月にパワーアシストスーツを製造・量産する予定
だったが特に情報はない。また、試験先で販売代理店となる予定だったニッカリが和歌山大学の特許を基
にパワーアシストスーツを発売した。
商品①:重作業用パワーアシストスーツ
商品②:軽作業用パワーアシストスーツ
商品③:パワーアシストスーツ Buddy バディ(製造販売:ニッカリ 特許和歌山大学)
目的・機能:
商品①:重量物(10~30kg)持ち上げ・運搬、傾斜地歩行、階段昇降、中腰作業
商品②:果物の収穫など(~10kg)の上向き作業、軽量物運搬、傾斜地歩行、階段昇降
商品②:荷上げ・荷下ろし作業、中腰、前傾作業、歩行のアシスト
価格:
リンク:
http://www.wakayama-u.ac.jp/support/pdf/other 1 2.pdf
http://www.wakayama-u.ac.jp/~eyagi/roboticslab/asist.html
http://www.nikkari.co.jp/product/assist/buddy
ターゲット:
詳細:
商品①
タイプ:重作業用電動式(上下半身一体型)
質量:7.4kg
動力:充電用100V バッテリ駆動
稼働可能時間:2 時間(バッテリ交換で連続使用可)
アシスト動作:重量物(10~30kg)持ち上げ・運搬、傾斜地歩行、階段昇降、中腰作業
操作:自動アシスト(腰・股関節)
使用環境:屋内外日常生活環境
【1】腰や股関節の関節角度と靴底にかかる力の変化によって、装着者の動きを感知
【2】制御用コンピュータで、感知した装着者の動きを計算し、その動作を補助するように
電動モータを作動
【3】重量物持ち上げ・中腰作業での腰関節アシストと運搬時の股関節アシスト
【4】10~30kg の米袋・果物の収穫コンテナの持ち上げと運搬作業の支援(10kg 分をアシストス
ーツが支援)
228
商品②
タイプ:軽作業用電動式(上下半身分離型)
質量:9.5kg
動力:充電用100V バッテリ駆動
稼働可能時間:2 時間(バッテリ交換で連続使用可)
アシスト動作:果物の収穫など(~10kg)の上向き作業、軽量物運搬、傾斜地歩行、階段昇降
操作自動アシスト(肩・股関節)
使用環境屋内外日常生活環境
商品③(製造販売:ニッカリ 特許和歌山大学)
外形寸法:高さ 580×幅 515×奥行 370mm
重量:6.5kg(5.6kg バッテリ除く)
稼働時間(注):約 3 時間(充電時間約 2 時間)
モータ:アシストスーツ専用 AC サーボモータ×2
バッテリ:22.2V リチウムイオンポリマ電池×1(過充放電保護回路付)
動作環境:0℃~40℃
使用場所:屋内または屋外(IP55 適合予定)
想定体格範囲(目安):身長 155~190cm、腹囲 90cm 以内 胸囲 100cm 以内
229
14. 株式会社モリタホールディングス
住所:大阪本社 〒541-0045 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 番 1 号京阪神御堂筋ビル 12 階
東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋 3 丁目 25 番 31 号
TEL :大阪本社 06-6208-1907 東京本社 03-5777-5777
FAX :
商品①:rakunie ラクニエ
目的・機能:
商品①:腰部サポートウェア 日常動作妨げず腰部に負荷のかる 低下」を解決し、日常動作妨げず腰
部に負荷のかる前屈姿勢時のみに高機能弾性材で腰部をサポートする
価格: 24,840 円 (税込)(モリタネットショップ価格)価格
http://morita119-netshop.com/shopdetail/000000000186/
リンク:
http://www.morita119.com/rakunie/
http://www.morita119.com/ir/pdf/20151029.pdf
http://www.morita119.com/ir/pdf/20120919.pdf
ターゲット: 介護・農業・整備業など
詳細:
2012年モデルと2015年モデルあり。ラクニエは前屈・中腰姿勢での腰をしっかりサポートしつつ、動きやす
さと着脱のしやすさを兼ね備えたサポートウェア。前屈時の背中の伸びで発生する弾性生地の張力で腰を
支える筋肉の負担を軽減する。腰を曲げない時や体をひねる時などはサポート力を発生しないため、過剰
なサポートによる筋力の低下を防ぐことができる。
・250g
・着脱30秒
・落ちないサポート力(5万回の伸縮でも約 0%の張力を維持)
・サポート力解除機能付き
・様々な職種・服装に対応
・手洗いOK
230
15. スケルトニクス株式会社
住所:〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 1100−16
TEL :050-3486-9802
FAX :
商品①:スケルトニクス
目的・機能:
商品①動作拡大
価格:
リンク:
http://skeletonics.com/skeletonics-series/
http://bizpow.bizocean.jp/edge/skeletonics/
ターゲット: SFやロボット愛好者向け
詳細:
スケルトニクス®は,腕や足の動きに追従して動くリンク機構を用いて四肢の動作すべてを拡大し、通常
の人体では表現できないダイナミックな腕や足の動きを実現できる動作拡大型スーツである。動力は人力
のみでアクチュエータは搭載されておらず、装着された人間にはスーツの重量と拡大率に比例した負荷がか
かる。
231
16. 佐川電子株式会社
住所:千葉県松戸市
TEL :080-5024-6312
FAX :
商品①:パワードジャケット MK3
目的・機能:
商品①世界で初めてとなる搭乗型パワードスーツ
価格: 1250 万円
リンク:
http://www.sagawaelectronics.com/index.html#poweredjacket
ターゲット:SFやロボット愛好者向け
詳細:
安全面の保障が出来ず、アート作品(鑑賞目的)という位置づけで販売。
モーションマスタースレーブと弾性関節により、搭乗者の動作を拡大・強化させる他、生卵を掴むような繊
細な動作も両立。歩行安定リンク機能や各部に備えられたサーボ・モータによる歩行アシスト機能により、
極めて高い安定性の保持を実現。
232
17. イクシー株式会社
住所:〒 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-5-18 ハギワラビル2F
TEL :
FAX :
E-mail:[email protected]
商品①:Hackberry
目的・機能:
商品①:3D プリンタで作成可能な日常用筋電義手。作成及び制御のソフトウェアをオープンソースして
いる。
価格:
商品①:3 万円程度で作成(材料費のみ、イクシー株式会社への支払いはなし)
リンク:
http://exiii.jp/
http://exiii-hackberry.com/
ターゲット:
商品①:義手が必要な方
詳細:
イクシーは 2013 年に使用する材料やソフトウェアにより高価な商品ばかりだった筋電義手(筋肉が発す
る微弱な電気で制御する電動の義手)に、スマートフォンや3Dプリンタを活用することで数万円で作成
できる handiii の開発を始めた。2014 年に handiii は文化庁メディア芸術祭エンターテイメント部門で優
秀賞を受賞した。Handiii の現行モデルが HACKberry であり、データやソースコードを無料で開放してい
る。現在は 3D プリンタを使用し、ABS などの樹脂と内蔵モータ6個で作成している。
また、株式会社 Xiborg が開発している競技用義足(主に CFRP と板バネから構成)のデザインも手が
けている。
233
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位 5 位程度まで列記)
(米国・欧州・その他)
国名 組織名 商品名 主な用途 特記事項
EksoGT 下肢麻痺者用 関連機器売上 $12,081,000
EksoVest 負担軽減 研究開発中
Fortis ツールホールディング
K-SRD軍事用・負担軽減能力向上
研究開発中
US SOCOM(United States SpecialOperations Command)
TALOS軍事用多機能スーツ
研究開発中
OLAD軍事用負担軽減
O-ArmX負担軽減ツールホールディング
軍事用アーマー(名称未定)
軍事用ボディーアーマー
研究開発中
Myomo MyoPro腕部麻痺者用筋電補助具
2017/6/16ニューヨーク証券取引所上場
Parker Hannifin Indego 下肢麻痺者用Vanderbilt Universityよりライセンス受領
イギリス 20 Knots Plus Ltd Marine Mojo軍事用対衝撃緩和
X3 waterproofprosthetic leg
筋電義足筋電義肢のトップシェアメーカーであり商品が多い為、一部のみ紹介
bebionic hand 筋電義手
C-Brace 下肢麻痺者用
フランス RB3D HERCULE V3 運搬補助 軍事用も開発中
フランス ECA Dynamics 未定軍事用・負担軽減能力向上
ECA、Wandercraftによる共同設立
スイス Noonee Chairless Chair 負担軽減チューリッヒ工科大学発ベンチャー飯田 史也教授プロジェクト参加
イスラエル ReWalk Robotics ReWalk 下肢麻痺者用 関連機器売上 $5,869,000
ニュージーランド
Rex Bionics REX 下肢麻痺者用 関連機器売上 £451,000
カナダ MAWASHI UPRISE 軍事用アーマー 研究開発中
ロシア TsNIITochMash Ratnik軍事用多機能スーツ
研究開発中
韓国Daewoo Shipbuilding& Marine Engineering
RoboShipbuilder
能力拡大 研究開発中
ドイツ Otto Bock
Ekso Bionics
Lockheed Martin
BAE Systems, Inc.(BAE Systems plc(英国)子会社)
アメリカ
234
1. Ekso Bionics Holdings(Nasdaq 上場)
国:アメリカ
TEL :1-510-984-1761
FAX :
商品①:EksoGT
商品②:EksoVest
目的・機能:
商品①:下肢麻痺者のリハビリ
商品②:ワーカーの上半身をサポート〈プリセール〉
売上高:$12,081,000
リンク:
http://eksobionics.com/eksohealth/products/
http://eksobionics.com/eksoworks/
ターゲット:
商品①:脊髄損傷による下肢麻痺者
商品②:工場や建設現場などの肉体労働者
詳細:
商品①はリハビリ機器。肩口にあるコントローラでリハビリ練習メニューを選択する。また、起立・歩行・着席
のサポートも行うことができる。チタンとアルミニウムから構成され、リチウムイオン電池を2つ搭載している。リ
ハビリ中に得たデータはワイヤレスで飛ばすことができ、そのデータを今後のリハビリに活かすことが可能。
商品②は労働者の上半身に装着して使用する。4.3kg と同系統の商品の中では比較的軽い。着用す
ることで、怪我の可能性を減る、作業効率がよくなる、スタミナが持続するなどのメリットがある。
235
2. Lockheed Martin
国:アメリカ
TEL :
FAX :
商品①:Fortis
商品②:K-SRD(FORTIS Knee Stress Release Device)(カナダ B-TEMIA 社ライセンス利用)
目的・機能:
商品①:無動力のツールホールディングスーツ
商品②:軍事用 身体の負担軽減及び能力向上スーツ
売上高:不明
リンク:
http://www.lockheedmartin.com/us/products/exoskeleton.html
http://news.lockheedmartin.com/2017-05-16-New-Lockheed-Martin-Exoskeleton-
Helps-Soldiers-Carry-Heavy-Gear#assets 117
http://gigazine.net/news/20170519-lockheed-martin-exoskeleton-k-srd/
ターゲット:
商品①:工場労働者
商品②:アメリカ軍
詳細:
Fortis は無動力のツールホールディングスーツである。リュックのように背負い、脚まである装置を身につけ
る。背部にあるクレーンの吊り具のようなモノに使用する機器を取り付けることで、負担を感じさせることなく
持ち運び出来るようになる。この結果、生産力の増加と怪我の可能性の減少が見込まれる。
K-SRD は腰部及び脚部の負担を減らし、機動性や荷物携行量の向上を可能とするパワードスーツ。軍
事用の特別なバッテリーを搭載し、人間工学に基づいたコントロール方法のコンピュータによってアクチュエー
タなどを制御している。
236
3. United States Special Operations Command (略称 US SOCOM)
国:アメリカ
TEL :(813) 826-9482 (Technical Industrial Liaison Office)
FAX :(813) 826-9488
商品①:Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS)
目的・機能:
商品①:軍事用フルボディアーマー
売上高:
リンク:
https://en.wikipedia.org/wiki/TALOS (uniform)
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/2018-the-year-the-us-military-goes-iron
-man-20832
ターゲット: 米軍
詳細:
兵士の防御力と身体能力を向上させることが目的の軍用パワードスーツであり、マサチューセッツ工科大学
(MIT)や特殊部隊「ネイビーシールズ」など 56 の企業、16 の政府機関、13 の大学、10 の国立研究
所が開発に参画している。2018 年7月にプロトタイプが完成する予定。
強度アーマー、高機動性、敵発見能力、音・光管理、指示・コントロール・コミュニケーション・コンピュータ
機能、健康状態確認及び自動応対機能(温度調整や酸素吸引など)、出力管理などを搭載すること
を目標としている。アーマーの素材は磁性流体を持たせたアラミド繊維のケブラーを使用予定。
237
4. BAE Systems, Inc.
国:アメリカ(本社イギリス)
TEL :+44 (0) 1483 816000
FAX :
商品①:OLAD(Orthotic Load Assistance Device)
商品②:O-ArmX
商品③:軍事用アーマー(名称未定)
目的・機能:
商品①:軍事用・負担軽減
商品②:労働用・負担軽減・ツールホールディング
商品③:軍事用・ボディーアーマー
動力:
商品①:電動(バッテリー)?
商品②:電動(バッテリー)
商品③:不明
開発関係者:
商品①:
Kelvin W. Hollander, Preston Clouse, Nathan Cahill, Alexander Boehler, Thomas G. Sugar
(SpringActive) Dr. Adarsh Ayyar (BAE Systems)
商品②:Dr. Adarsh Ayyar (BAE Systems)
商品③:不明
売上高:不明
リンク:
https://pdfs.semanticscholar.org/241f/da1489821b03498435ee38e97d1ebe4ae210.pdf
http://innercircle.engineering.asu.edu/wp-content/uploads/2015/03/NSRP-Panel-2015-Abstract-OLAD.pdf
http://www.thefirearmblog.com/blog/2017/06/14/bae-systems-develops-liquid-armor-canadian-troops/
ターゲット:
商品①:軍
商品②:肉体労働者
商品③:軍
詳細:
商品①:2013 年5月に発表された荷物の運搬を支援する軍用パワードスーツ。一般兵が運ぶべき荷物の
重量は23kgまでにすべきとされているが、実態として、45kg~60kgの荷物を運んでいた。このような状況であ
ったため、戦闘によらない筋骨格の怪我が問題となっていた。この問題を解決するため、BAE System と
SpringActive が共同で OLAD を開発した。
OLAD はバックパックと使用者の足に装着する構造であるため、身長に左右されず使用できる。ばねの特徴を
238
活かし、荷物の重量の大部分を地面に伝えているため、使用者は楽に荷物の運搬を行うことが出来る。
商品②:
O-ArmX は OLAD と ZeroG(Equipois 社開発)を組み合わせたツールホールディングタイプに充電バッテリー
(28Volt)を付けたパワードスーツである。OLADにより、使用者の背中、臀部、ひざ、くるぶしなどを保護すること
でけがを防ぐ。また、バッテリー付きであるため、45kg までの物体を zeroG のアームにツールを取り付けて動かす
ことが出来る。
商品③:
BAE Systems は Helios Global Technologies(カナダ)と共同でカナダ軍向けのリキッドアーマーの研究
を行う契約を結んだ。リキッドアーマーは同じ強度の個体アーマーよりも軽い。ケブラーを使えば約45%は薄く
なる。
239
5. Myomo(2017 年6月16日ニューヨーク証券取引所に上場)
国:アメリカ
TEL :877.736.9666
FAX :
商品①:MyoPro
目的・機能:
商品①:腕部麻痺者用筋電補助具
開発関係者:
商品①:
売上高:不明
リンク:
http://myomo.com/what-is-a-myopro-orthosis/
http://exoskeletonreport.com/2016/09/myopro-the-assistive-arm-exoskeleton-by-myomo-featured-in-solidworks/
ターゲット:
商品①:腕部麻痺者
詳細:
商品①:
筋肉のシグナルを使って腕部麻痺者の腕を再び動かせるようにする為の筋電義手。使用者が腕を動かそうとす
ると、高精度センサーが弱いシグナルを読み取ることでモーターを起動させ、腕を曲げたり手のひらの開く動作と閉
じる動作を動かすことが出来る。
240
6. Parker Hannifin
国:アメリカ
TEL :(1)844-846-3346
商品①:Indego
目的・機能:
商品①:下肢麻痺者用
動力:
商品①:電動(バッテリー)
開発関係者:
商品①:Michael Goldfarb, Don Truex (Vanderbilt University), Hugo Quintero, Spencer
Murray, Kevin Ha and Ryan Farris (Parker Hannifin)
売上高:不明
リンク:
http://www.indego.com/indego/en/home
http://www.parker.com/parkerimages/Parker.com/Literature/Exoskeleton/Parker%20Indego%20Brochure.pdf
ターゲット:
商品①:下肢麻痺者、病院
詳細:
商品①:
元々は、National Institute of Child Health and Human Development の補助金を受けて
Vanderbilt University の Michael Goldfarb 教授を中心に開発された下肢麻痺者用パワードスーツ。
2012 年に Parker Hannifin が製造販売のライセンスを得て、2015 年にヨーロッパで販売が開始された。
2016 年 3 月には U.S. Food and Drug Administration の許可を得てアメリカでも販売が始まった。また、
2015 年 10 月には U.S. Department of Defense と CONGRESSIONALLY DIRECTED MEDICAL
RESEARCH PROGRAMS の 資 金 供 与 を 受 け た Vanderbilt Medical Center in Nashville,
Tennessee, Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, and the James A. Haley Veterans’
Hospital in Tampa, Florida が Indego の更なる研究を 4 年間行うこととなった。
Indego は搭載された電動モーターにより、前方もしくは後方への体の傾きに反応して動く。また、体を後ろに傾
け続けることで、着座動作の補助も行うことが出来る。特徴として、12kg と軽いこと、モジュラーデザインであるた
め着脱が容易であること、スマートフォンのアプリを通して動きの設定やデータのモニタリングができることなどがあ
る。現在は、病院向けと個人向け双方に販売されている。病院では主にリハビリ用に、個人向けでは主に日常
用に使われている。
241
7. 20 Knots Plus Ltd
国:イギリス
TEL :+44[0]7787 828102
FAX :
商品①:Marine Mojo
目的・機能:
商品①:対衝撃緩和スーツ
売上高:不明
リンク:
http://www.20knots-plus.com/marine-mojo/
http://www.maritimejournal.com/news101/seawork/20kts-get-some-mojo-at-seawork
http://exoskeletonreport.com/product/marine-mojo/
ターゲット: 海軍
詳細:
Marine Mojo は主にモーターボートなどの小型高速艇に乗り込む軍人や沿岸警備隊向けの無動力パワード
スーツ。揺れや衝撃を Marine Mojo が緩和することで、身体への悪影響を防ぎ、疲労感を減らすことができ
る。重さは 1kg と軽く、着脱は容易で歩行に支障もないデザインとなっている。
242
8. Otto Bock
国:ドイツ
TEL :+49 5527 848-0
義肢の製造を事業とする会社。(商品が多い為、一部のみを紹介)
商品①:X3 waterproof prosthetic leg
商品②:bebionic hand
商品③:C-Brace
商品④:
目的・機能:
商品①:義足(耐水性・ランニングなどの運動が可能)
商品②:義手
商品③:脚部麻痺者用補助具
開発関係者:
商品①:
商品②:
商品③:
売上高:不明
リンク:
http://www.ottobockus.com/prosthetics/lower-limb-prosthetics/solution-overview/x3-prosthetic-leg/
http://www.ottobockus.com/prosthetics/upper-limb-prosthetics/solution-overview/bebionic-hand/
http://www.ottobockus.com/orthotics/solution-overview/orthotronic-mobility-system-c-brace/
ターゲット:
商品①:
詳細:
商品①:米軍と共同で開発した義足。マイクロプロセッサー、ジャイロスコープと加速度センサー付きの慣性計測ユニ
ット、油圧ユニット、モーメントセンサー、バッテリーなどを搭載している。そのため、脚のスピードとポジションを自動で調
節できる。ランニングなどのスポーツにも使用でき、自動スリープ昨日を備えているため、充電なしでも5日間使用でき
る。また、耐水性なため、装着したままシャワーを浴びることができる。
商品②:
14種類のグリップのパターンと手のポジションにより、食事やタイピングなどの日常動作を行うことが出来る義手。マイ
クロプロセッサー、5指それぞれに搭載のモーター、45kg まで持つことが出来る耐久性、掴んだ物を落とさないため
のオートグリップ機能などを備えている。
商品③:
243
9. RB3D
国:フランス
TEL :
商品①:HERCULE V3(ヴァージョン3)
目的・機能:
商品①:労働用
開発関係者:
商品①:
売上高:不明
リンク:http://www.rb3d.com/en/exo/
ターゲット:
商品①:屋内肉体労働者(倉庫業など)
詳細:
商品①:
HERCULE シリーズは軍事用と民間用双方の利用を考えられて製造されたパワードスーツである。V3 は民間向け運
搬用として造られた。HERCULE V3 を装着することで、腹部の前に机のようなスペースができ、そこに 40kgまで荷物
を置いて運ぶことが出来る。両手が荷物運搬時でもフリーとなるため、様々な作業に役立てることが出来る。また、
ARM製のCPUによって移動を制御しているので、安心して動ける。バッテリーは連続使用で4時間もつ。着脱につい
ては、ボタンでモードを切り替えてテープを剥がすだけなので、1,2分で可能。
245
10. ECA(Etudes et Constructions Aéronautiques)
国:フランス
TEL :
商品①:HERCULE V3(ヴァージョン3)
目的・機能:
商品①:軍事用・負担軽減・能力向上
開発関係者:
商品①:
売上高:不明
リンク:http://www.ecagroup.com/en/financial/eca-group-buys-humanoid-robotics
ターゲット:
商品①:軍
詳細:
商品①:
フランス防衛企業である ECA が医療用エクソスケルトン開発を手掛ける Wandercraft 社に出資をするとともに、
ECA Dynamics を共同で設立(2015 年 7 月)し、軍用エクソスケルトンの研究開発を進めていくことを明らかに
した。
*仏政府はロボット産業の加速化を目的にパリにAIリサーチセンサ-を開設するとともに、Innorobo(インダストリーイ
ニシアティブ, アクセラレータ)を後押し。
**Innorobo HP に世界のロボティックス関連組織/企業ダイレクトリー有り
https://www.thedisruptory.com/directory/
246
11. Noonee
国:スイス
TEL :
商品①:Chairless Chair
目的・機能:
商品①:労働用
開発関係者:
商品①:飯田 史也教授(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich)
売上高:不明
リンク:http://www.noonee.com/?lang=en
ターゲット:
商品①:肉体労働者
詳細:
商品①:
アルミとカーボンの軽量素材でできた下肢用パワードスーツ。立ち仕事や腰を痛める姿勢のときに骨格を固定すること
で下半身の疲労を防ぐことが出来る。ダンパーにはアクチュエータとバッテリーが搭載されており、衝撃を吸収し、移動
時などにも不便がない仕組みになっている。
247
12. ReWalk Robotics(Nasdaq 上場)
※安川電機と資本提携を結んでおり、安川電機の社員の取締役がいる。
国:イスラエル
TEL :+972 4 959 0123
FAX :
商品①:ReWalk PERSONAL
商品①:ReWalk REHABILITATION
目的・機能:
商品①:リハビリ 下肢麻痺者の起立・着座・歩行補助ロボット
売上高:$5,869,000
リンク:
http://rewalk.com/
ターゲット: 医療施設向け、個人向け
詳細:
膝関節、股関節部分にモータを搭載した外骨格型歩行装置。外骨格型装着ユニット・左右の杖・コミュ
ニケーター(腕時計型端末)の3つからなっており、コミュニケータで起立・歩行・着座のモードを切り替え
る。歩行は装着者の重心位置を角度センサーで検出することによりアシストする。
ReWalk Robotics はハーバード大学と協力し、Restore という名前の新試作型を作成。こちらは柔らか
い外骨格をベースとしている。
248
13. Rex Bionics(ロンドン証券取引所 AIM 市場上場)
国:ニュージーランド
TEL :+44(0)2074789014
FAX :
商品①:REX
目的・機能:
商品①:リハビリ 下肢麻痺者の起立・着座・歩行補助ロボット
売上高:€451,000 (2016 年度)
リンク:
http://www.rexbionics.com/
http://www.rexbionics.com/product-information/
ターゲット:病院、下肢に障がいのある富裕層
詳細:10 のリニアアクチュエータを搭載し、100kg の人まで対応。
custom carbon fiber でできた固定ベルトにより軽さとしっかりした固定力を確保。リチウムイオンポリマ二
次電池(29.6V, 16.5Ah)により 1 時間で充電が完了する。右手にあるコントローラで起立と着座を操作
するが、普段は両腕を自由に使うことが出来る。使用者一人では装着・脱着は難しい。
249
14. MAWASHI
国:カナダ
TEL :
FAX :
商品①:UPRISE
目的・機能:
商品①:軍事用アーマー
売上高:
リンク:
http://www.mawashi.net/fr/
http://news.militaryblog.jp/web/Canada-Tech-Firm-MAWASHI-develops-UPRISE/Tactical-Exoskeleton-for-SF-Operator.html
ターゲット:軍
詳細:
超 軽 量 の 兵 士 用 外 骨 格 ス ー ツ 「 UPRISE 」 ( Ultralight Passive Ruggedized Integrated Soldier
Exoskeleton)を開発中。UPRISEは高強度のチタン合金を使用した複雑構造を採ることで、戦闘展開時に必要と
なる動きに柔軟に追随するとともに、荷重等の兵士への負担を大幅に軽減ができるものとなっている。
同社は米国防総省の掲げる「人間増強システム(HAS: Human Augmentation Systems)」の参加メンバ
ーに選出されており、特殊部隊用の戦術エクソスケルトン(外骨格)の開発に携わっている。
250
15. TSNIITOCHMASH
国:ロシア
TEL :
FAX :
商品①:ラートニク (Ratnik)
目的・機能:
商品①:軍事用アーマー
売上高:
リンク:
http://www.military.com/video/logistics-and-supplies/uniforms/russian-ratnik-infantry-equipment-system/4722024906001
http://news.militaryblog.jp/web/Russian-3rd-Gen-Ratnik-combat-gear/to-feature-exoskeleton.html
ターゲット:軍
詳細:
国際軍事技術フォーラム「Army 2016」において、「ラートニク (Ratnik) 」システムの第 3 世代コンセプトモデルを展示。
システム全体の軽量化や、敵味方識別 (IFF: Identification Friend-or-Foe) システムの一体化など、使用素材の見直
しから指揮管理系統システムの開発に取り組んでいる。
※ロステク(国営軍事関連企業)も関与しているとされる。
251
16. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
国:韓国
TEL :
商品①:RoboShipbuilder
目的・機能:
商品①:労働用
開発関係者:
商品①:
売上高:不明
リンク:
http://www.marineinsight.com/future-shipping/exoskeleton-robot-caniron-man-suit-increase-productivity-in-shipyards/
https://www.newscientist.com/article/mg22329803-900-robotic-suit-gives-shipyard-workers-super-strength/
ターゲット:
商品①:肉体労働者
詳細:
商品①:
RoboShipbuilder は全身に装着するタイプのパワードスーツである。素材としては、カーボン、アルミ、鉄でできてい
る。背部のバックパックに組み込まれている油圧ジョイントと電動モーターにより、30kg の荷物を楽に持ち上げることが
出来る。重さは 28kg で、バッテリーは3時間もつ。
252
(中国・台湾)
中国におけるパワードスーツ開発・製造メーカは以下の通り。なお、台湾においてはめぼしい取り組みは
見られなかった。
17. 中国北方工業公司 (NORINCO)
NORINCO の 202 兵器研究所が軍用エクソスケルトンを研究開発しているとされる。
253
社名 所在地 株主構成 主要事業 パワードスーツ
上海傅利葉知能科技有限公
司(Fourier)上海市
2015年7月成立、民営企業 知能化技術開発 同社は2016年末上肢外骨格型
パワーアシストロボット「Fourier
M2」を発表。2017年3月、下肢
外骨格型「Fourier X1」が発表
され、中国で初の商用化。
尖叫知能科技(上海)有限
公司浙江杭州
2015年初成立、民営企業 外骨格型ロボットの研
究·開発、IoT技術
2016年11月、外骨格型パワー
アシストロボット「尖叫1号
(Scream One)」を発表、量
産の予定。
北京大艾機器人科技有限公
司(AI-ROBOTICS)北京
2016年4月、北京航空航天
大学の帥梅教授により設立
(研究プロジェクト成果の事業
化)
リハビリ支援ロボット 2017年1月、同社の下肢外骨
格型パワーアシストロボットは北京
市食品医薬品監督管理局
(BFDA)に認可され、年内に量
産の見込み。 製品シリーズ:
AiLegs、AiWalkers
北京鉄甲鋼拳科技有限公司 北京
2016年成立、民営企業 外骨格型ロボットの研
究·開発
2016年、上肢外骨格型パワーア
シストロボット「CEXO-1」を発表。
北京大成高科機器人技術有
限公司北京
2013年7月成立、民営企業 知能ロボット 開発中。ハルビン工業大学と共同
で外骨格型ロボットを開発する計
画。
楚天科技股份有限公司 湖南長沙
2000年成立(前身は長沙楚
天包装機械有限公司)、上
場会社
スマート医療機器 開発中。2016年12月、国防科
技大学と提携協議を結び、共同
で外骨格型ロボットを開発する計
画。
布法羅機器人科技(成都)
有限公司四川成都
成都電子科技大学の程洪教
授により設立
リハビリ支援ロボット 2016年9月、同社は外骨格型パ
ワーアシストロボット(AIDER) を
発表、量産の予定
成都偉達尔科技有限公司 四川成都
2016年2月成立、重慶迪馬
実業股份有限公司の子会社
重慶迪馬:軍用特
用車、不動産
開発中。成都電子科技大学と共
同で外骨格型ロボットを開発する
計画。
光啓技術股份有限公司 広東深圳
深圳光啓集団の傘下企業、上
場会社
メタマテリアル 開発中。メタマテリアル技術により
外骨格型ロボットを開発している。
寧波慈星股份有限公司 浙江寧波2003年成立、上場会社 メリヤス業の製造設備 開発中
蘇州瑞歩康医療科技有限公
司江蘇蘇州
2016年3月成立、民営企業 医療用ロボット、医療
機器
開発中
南京科遠自動化集団股份有
限公司江蘇南京
1993年成立、上場会社 自動化技術·製品 開発中。2016年3月、東南大学
と提携協議を結び、共同で外骨
格型ロボットを開発する計画。
広東金明精機股份有限公司 広東汕頭
1987年成立、上場会社 ブロー成形機 開発中。2015年7月、清華大学
と提携協議を結び、共同で外骨
格型ロボットを開発する計画。
254
⑩平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プ
ロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
(1)採用プロジェクト
・橋本義肢製作(株)
物体の形状に合わせて保持することができる多指機構を有し、軽量で極めて装飾性に優れた量産型筋
電義手
・(社福)兵庫県社会福祉事業団
ロボット技術を応用したリハビリテーション用短下肢装具の高付加価値化
(2) 採用プロジェクト
・福島県農業総合センター
・(株)イノフィス
マッスルスーツの広がる機能性能に関する要求に応えるための技術開発、実証試験を実施
(3)採用プロジェクト
・アクティブリンク株式会社
軽作業用 PAS の試作開発と評価
事業名 関係省庁 予算規模 事業期間
(1)障害者自立支援機器等開発促進事業に関わる補助金
厚生労働省補助率2/3資本金3億円超は1/2
H29年度
(2)福島イノベーション・コースト構想に基づく先端農林業ロボット研究開発事業に関わる補助金
農林水産省 上限10,000千円 H28~H29年度
(3)ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクトに係る助成金
NEDO年間50百万円~150百万円程度
H27~H29年度
(4)次世代人工知能・ロボット中核技術開発に関わる委託費※H29未決定
NEDO 年間20百万円以内 H27~最大H31年度
257
(4)採用プロジェクト
信州大学・(国研)産業技術総合研究所
可塑化 PVC ゲルを用いたウェアラブルロボット用ソフトアクチュエータの研究開発
豊田合成(株)・アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株)・再委託先:東京大学
スライドリングマテリアルを用いた柔軟センサーおよびアクチュエータの研究開発
中央大学・再委託先:株式会社明治ゴム化成
人間との親和性が高いウェアラブルアシスト機器のための 可変粘弾性特性を有する革新的ソフトアク
チュエータシステムの開発
・筑波大学
剛性と柔軟性を融合させるスマートメカニクス
東京工業大学・北海道大学・北陸先端科学技術大学院大学・共同実施:(国研)産業技術総
合研究所・関西大学・大阪大学
分子人工筋肉の研究開発
・東北大学 ・再委託先:名城大学
次世代ロボットのためのマルチセンサ実装プラットフォーム
・熊本大学
ロボットの全身を被覆する皮膚センサの確立と応用開発
258
⑪米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府
支援策の有無(有る場合は該当箇所)
(米国)
FEDERAL RePORTER によると 2016 年には Exoskeleton 関連のプロジェクトが 40 件開始して
おり、15,00 万 USD の予算が当てられた。また、USASPENDING.gov では、2016 年には 17 のプロ
ジェクトに対して$234 万 USD の補助金が与えられた。
さらに、CONGRESSIONALLY DIRECTED MEDICAL RESEARCH PROGRAMS の Search
Awards では 2016 年に 2 件のプロジェクトが採用され、合計 270 万 USD が拠出された。他にも、下
記の表のように公開されていない研究開発プロジェクトも多数あるものとみられている。
TALOS Warrior Web X1 Robotic Exoskeleton INDEGOTALOS (Tactical Assault Light Operator Suit), a robotic exoskeleton that United States Special Operations Command intended to design with the help of universities, laboratories, and the technology industry.
"Smart Suit", lightweight and conformal under-suit, employing a system (or web) of closed-loop controlled actuation, transmission, and functional structures that protect injury prone areas
in-space exercise machine, robotic power boost to astronauts and assistive walking device on Earth
a powered lower limb exoskeleton that can enable people with spinal cord injuries to walk
期間 2013~? ?(2013/5以前)~稼働中 ? 2013~2016
資金拠出元United States Special Operations Command
DARPA NASA Department of Defense
予算金額(US$)
? ? ? ?
政府拠出額(US$)
? ? ? ?
参加機関
56の企業16の政府機関
13の大学10の国立研究所
DARPAと9つの研究機関Wyss Institute, Boston Univesity, SRI International など
NASA, The Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), Oceaneering Space Systems
the Department of Defense, Parker Hannifin, the Mayo Clinic, Vanderbilt University
内容
兵士の防御力と身体能力を向上させることが目的の軍用パワードスーツ。身体能力を向上させる油圧式のパワードスーツのほか、コンピュータやデータリンク機能、暗視装置による装着者の支援機能を備え、また、硬化する液体を利用したリキッドアーマーや、傷口を自動で検出して泡で塞ぐ能力なども付与される予定。
TALOSのような攻撃を防ぐ防具ではなく、柔らかくて軽量な着用パワードスーツ。筋骨格の負傷を減らし、重量物の運搬を補助する機能を目指す。既に幾つかの成果があり、スタンフォード研究所(SRI)とアメリカ陸軍が共同開発した「SuperFlex」などがある。
宇宙滞在者用エクササイズマシーンであり、将来的に宇宙での活動補助能力、地球でのリハビリマシーンへの転用などが考えられている。
頸髄損傷による下半身麻痺者の歩行補助具
プロジェクト
259
(欧州)
2014 年 1 月よりスタートした欧州フレームワークプログラム「HORIZON 2020」における
EXOSKELETON(エクソスケルトン)関連のプロジェクトは以下の通り。また、こうした欧州の枠組以外
にも、英国が「Innovate UK」及び EPSRC(英国工学・物理科学研究会議)のファンディングプログラ
ムからエクソスケルトン関連に 22M ポンド(Innovate UK)+193M ポンド(EPSRC)+40M ポン
ド(その他のリサーチ協議会等)を拠出するなど、各国それぞれの取り組みも活発である。
Robo-Mate SPEXOR HUMEXE
Intelligent exoskeleton based on
human-robot interaction for
manipulation of heavy goods in Europe’
s factories of the future
Spinal Exoskeletal Robot for Low Back
Pain Prevention and Vocational
Reintegration
Human EXoskEleton for autonomous
movement control
期間 2013.9~2016.11 2016.1~2019.12 2015.10~2016.3
資金拠出元 FP7-2013-NMP-ICT-FOF H2020-ICT H2020-SMEINST
予算金額
(EUR)6,022,080 3,989,025 71,429
EU拠出額
(EUR)4,449,973 3,989,025 50,000
参加機関
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA(伊),
INDRA SAS(仏), FONDAZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
(蘭), NEDERLANDSE ORGANISATIE
VOOR TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO(蘭), UNIVERSITY
OF LIMERICK(アイルランド), MRK -
SYSTEME GMBH(独), FRAUNHOFER
GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG
DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
(独), COMPA SA(ルーマニア),
ROPARDO SRL(ルーマニア),
ACCELOPMENT AG(スイス), GUDEL AG
(スイス)
RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET
HEIDELBERG(独), STICHTING VU
(蘭), OTTO BOCK HEALTHCARE
GMBH(独), OTTO BOCK HEALTHCARE
PRODUCTS GMBH(独), S2P DOO(スロ
ベニア), STICHTING HELIOMARE(蘭)
TECNIMUSA S.L.(スペイン)
プロジェクト内容
産業利用を想定した軽量、ウエラブルなエクソスケ
ルトンの研究開発を推進。
腰痛防止のための補助器具(ウエアラブルロボッ
ト)の開発。
独自のコントロール技術を適用した下半身麻痺
患者向けの補助器具を開発。
プロジェクト名
260
e-walk MovAiD HANK
Biomechanical engineer for robotic
healthcare solutions
Movement Assisting Devices:
Manufacturing of personalized Kineto-
Dynamics parts and products for
workers, elderly and children
European advanced exoskeleton for
rehabilitation of Acquired Brain
Damage (ABD) and/or spinal cord
injury's patients.
期間 2017.9~2018.8 2015.9~2018.8 2016.3~2018.2
資金拠出元 H2020-INNOSUP H2020-FoF H2020-FTIPilot
予算金額
(EUR)103,300 5,954,375 1,984,950
EU拠出額
(EUR)103,300 5,136,875 1,514,527
参加機関 MARSI BIONICS SL(スペイン) BRUNEL UNIVERSITY LONDON(英),
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE(伊), NEDERLANDSE
ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST
NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO(蘭), SYNESIS-
SOCIETA CONSORTILE A
RESPONSABILITA LIMITATA(伊),
GAIT UP SA(スイス), AnyBody
Technology A/S(デンマーク), TTS
TECHNOLOGY TRANSFER SYSTEMS
SRL(伊), KMWE Systems eindhoven
B.V.(蘭), ALSTOM TRANSPORTE SA
(スペイン), OFFICINA ORTOPEDICA
MICHELOTTI SRL(伊),
INTERNATIONAL SOCIETY FOR
PROSTHETICS AND ORTHOTICS(デン
マーク)
FAAR INDUSTRY(仏), FONDAZIONE
SANTA LUCIA(伊), AGENCIA ESTATAL
CONSEJO SUPERIOR
DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS(ス
ペイン)
プロジェクト内容 神経筋疾患患者を対象としたエクソスケルトン
「ATLAS 2020」「ATLAS 2030」の研究促進。
作業従事者に向けた次世代MADs
(Movement Assistive Devices:動作支
援デバイス)の研究開発を推進。
脳にダメージを負った患者を対象としたリハビリテー
ションデバイスの研究開発。
プロジェクト名
261
XoSoft ERXOS EURECA
Soft modular biomimetic exoskeleton to
assist people with mobility impairments
ElectroRheological fluid based
eXOSkeleton devices for physical upper
limb rehabilitation
Enhanced Human Robot cooperation in
Cabin Assembly tasks
期間 2016.2~2019.1 2016.4~2016.9 2017.2~2020.1
資金拠出元 H2020-ICT H2020-SMEINST H2020-CS2-CFP03
予算金額
(EUR)5,422,863 71,429 1,402,998
EU拠出額
(EUR)3,680,028 50,000 1,242,386
参加機関 AGENCIA ESTATAL CONSEJO
SUPERIOR DEINVESTIGACIONES
CIENTIFICAS(スペイン), STICHTING
SAXION(蘭), UNIVERSITY OF
LIMERICK(愛), ZURCHER
HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN(スイス),
ROESSINGH RESEARCH AND
DEVELOPMENT BV(蘭),
ACCELOPMENT AG(スイス),
WALDKRANKENHAUS ST MARIEN
GGMBH(独), Össur hf(アイスランド)
SIGNO MOTUS SRL(伊) IT+ROBOTICS SRL(伊), PROTOM
GROUP SPA(伊)
プロジェクト内容 柔軟素材を使用した下肢麻痺患者用のパワード
スーツの研究開発を推進。
上肢患者用リハビリ向けのセミアクティブ・パワード
スーツの開発促進。
人とロボットの協同作業による航空機内装の組立
を想定したLightweight Mobile Arm
(LMA)及びウエアラブルな上腕外骨格の開発
を推進。
プロジェクト名
262
An.Dy RETRAINER NEPSpiNN
Advancing Anticipatory Behaviors in
Dyadic Human-Robot Collaboration
REaching and grasping Training based
on Robotic hybrid AssIstance for
Neurological patients: End users Real
life evaluation
Neuromorphic EMG Processing with
Spiking Neural Networks
期間 2017.1~2020.12 2015.1~2018.12 2017.9~2019.8
資金拠出元 H2020-ICT-2016-1 H2020-ICT-2014-1 H2020-MSCA-IF-2016
予算金額
(EUR)3,950,025 3,746,871 175,419
EU拠出額
(EUR)3,950,025 2,784,831 175,419
参加機関 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
ENINFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE
(仏),INSTITUT JOZEF STEFAN(スロベ
ニア),DEUTSCHES ZENTRUM FUER
LUFT - UND RAUMFAHRT EV
(独),XSENS TECHNOLOGIES B.V.
(蘭),IMK AUTOMOTIVE GMBH
(独),OTTO BOCK HEALTHCARE GMBH
(独),AnyBody Technology A/S(デン
マーク)
POLITECNICO DI MILANO
(伊),TECHNISCHE UNIVERSITAET
WIEN(オーストリア),ECOLE
POLYTECHNIQUE FEDERALE DE
LAUSANNE(スイス),OTTO BOCK
HEALTHCARE PRODUCTS GMBH(オース
トリア),CONGREGAZIONE DELLE SUORE
INFERMIERE DELL ADDOLORATA
(伊),ASKLEPIOS KLINIK ALSBACH
GMBH(独),TECHNISCHE
UNIVERSITAET BERLIN
(独),HASOMED HARD-UND
SOFTWARE FUER MEDIZIN
GESELLSCHAFT MBH(独)
UNIVERSITAET ZUERICH(スイス)
プロジェクト内容 人の動作に関する測定方法、モーショントラッキン
グ技術(ANDYSUIT)、人の行動を認識する
技術(ANDYMODEL)、予測支援技術
(ANDYCONTROL)等の研究開発を実施。
脳卒中生存者の腕・手機能の回復を促進するた
めの支援ロボットを研究開発ならびにデモンスト
レーションを実施。
表面筋電位信号(sEMG)と直接的にインター
フェースすることができる神経処理システムを研
究、ディープ・ニューラル・ネットワーク(DNN)に
よるsEMG解析ステージを実装したコンパクトな超
低消費電力チップを提案、ウェアラブルデバイスの
将来の実装に役立つ低遅延でリアルタイムなデー
タ処理技術の確立を目指す。
プロジェクト名
263
Softpro MyoBan
Synergy-based Open-source
Foundations and Technologies for
Prosthetics and RehabilitatiOn
wireless Body Area Networks for high
density MYOelectric neurorehabilitation
technologies
期間 2016.3~2020.2 2017.5~2019.4
資金拠出元 H2020-ICT-2015 H2020-MSCA-IF-2016
予算金額
(EUR)8,675,611 168,277
EU拠出額
(EUR)7,440,026 168,277
参加機関 UNIVERSITEIT TWENTE
(蘭),UNIVERSITA DI PISA
(伊),GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ
UNIVERSITAET HANNOVER
(独),EIDGENOESSISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
(スイス),UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA(伊),MEDIZINISCHE
HOCHSCHULE HANNOVER
(独),TWENTE MEDICAL SYSTEMS
INTERNATIONAL B.V.(蘭),HANKAMP
REHAB BV(蘭),BIOSERVO
TECHNOLOGIES AB(スウェーデ
ン),QBROBOTICS SRL
(伊),UNIVERSITAET ZUERICH(スイ
ス),SCUOLA IMT (ISTITUZIONI,
MERCATI, TECNOLOGIE) ALTI STUDI
DI LUCCA(伊)
OT BIOELETTRONICA DI BOTTIN
ANDREA E MERLO ENRICO & C. S.N.C.
(イタリア)
プロジェクト内容 上肢リハビリテーションのための新しいプロテーゼ、
外骨格、および補助デバイスを製造するためのソフ
トロボット技術研究を推進。
ワイヤレス、ポータブルな新たな非侵襲性マルチ
チャネル電気生理学(EMG)技術の研究開発
を実施。
プロジェクト名
264
(中国)
2016 年 4 月、工業情報化部及び国会発展改革委員会、財政部が共同で「ロボット産業発展計
画(2016-2020 年)」を発表、中国ロボット産業の発展に向けた青写真を明らかにした。これは、
2015 年 5 月に公表した「中国製造 2025」(中国版インダストリー4.0 戦略)の中で示された「高機
能 NC 工作機械及びロボット産業の発展推進」を踏まえたものとなっており、具体的には、自動車、機械、
電子、危険物製造、国防軍需、化工、軽工業関連のロボットや健康医療、家庭サービス、教育、レジャ
ー関連のロボット需要に応えるために、キーテクノロジーの獲得、中核・機能部品の製造技術、設備のイ
ンテグレーション(集成)能力向上等の目標を盛り込んだ。
この「ロボット産業発展計画(2016-2020 年)」の中で、中国政府は 2020 年までに中国のロボッ
ト年間生産量を 10 万台、6 軸以上のロボット年間生産量を 5 万台以上、サービスロボットの年間販売
収入 300 億元以上とする目標を掲げ、また期間内に 3 社以上の大手企業と 5 か所以上のロボット関
連産業群を育成するほか、産業用ロボットの平均呼称間隔(MTBF)を 8 万時間に引き上げるころな
ども目指している。
対象とするロボットは 10 大製品としてアーク溶接ロボット、真空(クリーンルーム)ロボット、プログラミン
グ・スマート産業用ロボット、人間支援型ロボット、両腕ロボット、重量級 AGV、消防救援ロボット、手術
ロボット、スマート型公共サービスロボット、スマート介護ロボットの 10 種を定めているが、これらに対する施
策と並行し、ロボット応用のモデルケースを推進する方針で、その中で、スマート義肢や外骨格型ロボット
の応用をテーマとして掲げている。なお、外骨格型ロボット等のパワードスーツは NSFC(国家自然科学
基金委員会)が中心となり、研究開発プロジェクトを支援しているものとみられる。
265
〇 ロボット産業5か年計画における10大製品目標
製品名 導入技術目標
アーク溶接ロボット
6軸多関節ロボット、中厚板アーク溶接ロボット(所定負荷≧10㎏)、薄板アーク溶接ロボット(所定負荷
6kg)。溶接隙間追跡と高圧接触感知、溶接隙間の広さに対するアーク追跡等のキーテクノロジー応用の実
現を目指す。
真空(クリーンルーム)ロボット
真空:最大負荷15kg、クリーン:最大負荷210㎏、重複定位精度±0.05~0.1㎜、真空環境下での転
動潤滑、直駆動制御、動態偏差計測、校正及び衝突計測、保護等の技術応用の実現を目指す。
プログラミング・スマート産業用ロボット
6軸以上、工作対象物の寸法範囲:1~1.3m以上。インテリジェントシステムを備え、自動的に情報生成
作業プロセスを獲得でき、自動プログラミング時間:1時間以下等の作業要望に応える。
人間支援型ロボット
6軸以上の多関節ロボット、自重負荷4㎏未満、重複定位精度±0.05㎜。力制御の精度5N未満、衝突
安全監視応急時間3s未満。本体感応皮膚のアーム安全感応距離1㎝未満、防護等級IP54.柔軟性、機
敏性、正確度の高い電子、医薬、精密計器の製造分野に適用。
両腕ロボット
片腕:6軸以上、関節運転速度≧180°/s。両腕の平均エネルギー消費500w未満、衝突計測機能付、
定位精度1㎜未満。2指、3指柔軟性手爪行程≧50㎜、把持力≧30N、重複定位精度0.05㎜未満で電
子等の部品組立ラインに適用。
重量級AGV
駆動方式:全輪駆動、最大負荷力:40,000㎏、最大速度:直線20m/min、カーブ半径:2m、補助
磁気誘導精度:±10㎜、衝突防止装置:レーザー装置、上昇装置:車体自動上昇、上昇高度:最大
100㎜。
消防救援ロボット
自然災害と悪性自己等の現場調査及び即時処理等の需要に応じ、高温高圧、有毒有害等の特殊環境に
おいて、人員捜索、災害場所の計測定位、定点投下、障害除去、消火及び救援などの任務を遂行できる。
手術ロボット
冗長性アーム:6軸以上、最高重複位置精度:1㎜以上、選択把持ポイントの測量誤差:1%以下で各
種関連手術を実施できる。
スマート型公共サービスロボット
誘導方式:レーザーSLAM、最大移動速度:0.6m/s、定位精度:±100㎜、定位航行角度:±5°、
最大作業時間:3h、片腕軸数:2~7、頭部の軸数:1~2。自主走行、人機械交互、解説・案内などの
機能を持つ。
スマート介護ロボット
高齢者の介護需要に応え、知能感知識別、自主移動などの機能を備え、ユーザーと交流し、高齢者の家事
補助と多様な介護サービスを実施できる。
*中国政府「ロボット産業発展計画(2016~2020年)」
〇 ロボット産業5ヵ年計画における5大重要部品目標部品名 重点実施内容
高精密減速機
高強度耐磨耗材料技術、加工工法最適化技術、高速潤滑技術、高精度組立技術、安全性・寿命計測
技術の発展と新型の伝動原理の探求により、ロボットに適用される高効率で低重量、長期間無修理可能な
減速機の開発。
高性能サーボモータ・ドライバ
高磁性材料の最適化、一体化最適設計や加工組立工法最適化等の技術に関する研究を通じサーボモー
タの効率を高め、高効率密度を実現させる。高回転力ダイレクトドライブモータや円盤式中空モータ等のロボッ
ト専用モータの開発。
高性能コントローラ
高性能関節サーボ、振動抑制技術、慣性動態保証技術及び多関節の精度、運動解析及びプランニング技
術の発展により、高速変負荷応用過程の運動精度を高め、動態性能の改善につなげる。
センサ
重点的に関節位置、トルク、視覚、触覚等のセンサを開発し、ロボット産業の需要に応える。
エンドエフェクタ
重点的に把持と操作機能の多指機敏ハンド及び迅速変換機能付き挟持器等のエンドエフェクタを開発し、ロ
ボット産業の需要に応える。
*中国政府「ロボット産業発展計画(2016~2020年)」
266
(台湾)
台湾工業技術院(ITRI)の研究チームが中心となり、脊椎損傷患者のための歩行支援ロボットの
研究プロジェクト「Wearable Walking Assistive Exoskelton Robot(2WA-EXO)」を進めてき
た。同プロジェクトは、経済部技術処及び能源局(エネルギー局)がサポートしている「科専計画
(Technology Development Program)」の 1 つで、2017 年 2 月に同研究チームがスピンオフし
「Free Bionics」を設立、2018 年の実用化を予定している。設立に当たっては、ODM 大手の
Wistron が支援(4.3 億円を投資し、Free Bionics 株式の 48.72%を取得)、2017 年 8 月には
医療機器販売の USCI ジャパンと契約を締結し、日本市場へ参入を果たしている。
なお、Wistron は Free Bionics とは別に、子会社でモーションアシストロボットの開発を進めており、この
分野ではカナダ BioniK Laboratories とパートナーシップを結んでいる。
(韓国)
韓国国内の国防分野では、国防科学研究所及び、LIGnex1、hyundai Rotem などが、民間用は、生産技術研究院とヒュンダイ自動車が技術開発を進めている。
表 韓国で開発されているパワードスーツの概要
プロジェクト名
NSFC面上プロジェクトー外骨
格型ロボットの可変剛性機構
原理及び回復メカニズムに関す
る研究
NSFC面上プロジェクトー外骨
格型ロボットのマンマシンシナ
ジーを実現する方法に関する
研究
NSFC聯合基金プロジェクトー
高齢者や障害者を助けるマル
チモーダル融合下肢外骨格型
ロボットに関する研究
NSFC面上プロジェクトーマンマ
シンシナジーを備えるリハビリ支
援上肢外骨格型ロボットに関
する研究
期間 2013.1~2016.12 2015.1~2018.12 2017.1~2021.12 2017.1~2020.12
資金拠出元
NSFC (国家自然科学基金
委員会)
NSFC (国家自然科学基金
委員会)
NSFC (国家自然科学基金
委員会)
NSFC (国家自然科学基金
委員会)
予算金額
82万元 80万元 260万元 63万元
参加機関
北京航空航天大学 帥梅 蘇州大学 李娟 中国科学院深圳先進技術研
究院 呉新宇
北京航空航天大学 張建斌
プロジェクト目標
不明 不明 不明 不明
名称 開発機関 開発年度HEXAR Hanyang Univercity 2008Hyper(1,2,3) 韓国生産技術研究員 2010~2012
Hyper2i韓国生産技術研究員,Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering
2013
HWR1 Hyundai Rotem 2013EHMA 国防科学研究所 2013RMX-HI Hyundai Rotem 2014H-LEX Hyundai Automobile 2015
267
Han Changsoo教授 &(株)Hexarsystems
Han Changsoo 教授は、韓国ロボット融合フォーラムの会長であり、韓国のウェアラブル・ロボット分野
の最高責任者である。Han教授は、2005年の着用型上肢外骨格ロボットの研究を始め、2006年
には、下肢外骨格ロボット・上肢外骨格ロボット、これらを応用した医療リハビリロボットなどを開発した。
2007 年には、開発したロボットを「HEXAR」として商標登録し、これを基盤に、筋力増強のための外
骨格ロボットとリハビリ用ロボットなど、様々な HEXAR シリーズを開発した。Han 教授が設立した、
Hexarsystems 社は、韓国のウェアラブル外骨格ロボットの大手企業である。
図 リハビリロボット「HEXAR-WA20」
出所:Hexarsystems
複合任務用着用型筋力増強ロボット技術開発事業
防衛事業庁は、2016 年から 2020 年までの 4 年間、22.7 億円(防衛事業庁 20 億円、国民安
全処 2.7 億円)を投資し、民間と軍用で活用可能な「複合任務用着用型筋力増強ロボット開発事
業」を行うと発表した。当事業では、政府機関である、国民安全処、国防科学研究所と、LIGnex1
(株)、IDIS などの民間企業が参加しており、防衛事業庁が 3 つ、国民安全処が 1 つの開発課題
を提示している。そのうち、起動能力に重点を置いた「高荷重上下股筋力増強ロボットの高速同期化
制御技術」は国防科学研究所が、「高荷重上下股筋力増強ロボットの統合運用制御技術」と、「着
用型筋力増強ロボット用高密度電源技術」は LIGnex1 が開発を担当する。一方、国民安全処の
掲げた、消防士のための「消防士筋力支援関連装置技術」は、国民安全処傘下の中央消防学校
で開発する。
268
図 防衛事業庁の筋力増強ロボット主要開発内容
出所: ロボット新聞
災難対応ロボット分野の源泉技術の共同研究
韓国・米国は、2016 年 10 月から、「災難対応ロボット分野の源泉技術の共同研究」に着手し、韓
米間のロボット技術協力を本格的に推進していくと発表した。同プロジェクトは、2015 年 4 月に韓国
の産業通商資源部と米国の国防部間に締結された、「災難対応ロボット分野協力約定」を継続した
ものであり、両国は、今後 3 年間、総額 600 万ドルを支援し、対象分野に関連する 6 つの課題を研
究する。プロジェクトには、アメリカのカーネギーメロン大学、MIT 大学、韓国の KAIST 大学、ソウル大
学などの研究機関が参加する。
269
表 研究課題内容詳細
出所:韓国産業通商資源部より矢野経済研究所作成
ソフト・ウェアラブルスーツ技術開発事業
未来創造科学部は、「2017 年 ICT 融合産業厳選技術開発公募事業」として、釜山市が提案した
「ソフト・ウェアラブルスーツ技術開発事業」を 2017 年 8月に選定しており、同年 9 月に設立予定の、
韓国ロボット融合研究院の釜山支院が、当プロジェクトを施行する。事業目標としては、「知能情報
技術を活用した老弱者の歩行安全技術開発」、「柔軟素材ソフトアクチュエータ・センサー及び柔軟
構造システム駆動制御技術開発」、「メタ素材・構造物を利用した衣服形態のソフト外骨格技術開
発」、「老弱者歩行安全支援のための衣服形態のソフト・ウェアラブルスーツ統合及び実証」を挙げて
いる。釜山市は、当事業に、2017 年から 2020 年までの 4 年間、政府の支援金 9 億円、市の予
算 1 億円、その他の民間投資を含め、約 11.8 億円を投資する予定である。
分野 チーム名 機関 研究目標
フラットフォーム1Seoul UnivercityIllinois Univercity
柔軟な4足歩行フラットフォームのために、収縮、膨張が可能で、触覚及び、引っ張る力を感知することが可能なロボットの外皮開発
フラットフォーム2Seoul UnivercityPennsylvaniaUnivercity
形態再構成が可能なトポロジートラス・フラットフォームの剛性分析、トポロジー合成及びシミュレーション
HRI遠隔制御 HRI-1 Korea UnivercityMIT
移動及び全身操作のためのヒューマン-ロボット両方向学習基盤のMultiModal遠隔制御技術
HRI-2KoreaTechStanford Univercity
蔓型フラットフォームのためのHRI技術:多重操作者及び多重フラットフォーム基盤の直観的遠隔操作のための、遠隔地状況認知向上モジュール及び、仮想訓練シミュレーター開発
HRI-3Hanyang UnivercityGeorgia Tech.
原子力発電所の災難時対応:人間・マルチーロボット協業のためのモバイルマニピュレーター及びリスク分析技術
災難環境モデリング及び状況認知技術
Cog-1KAISTCMU
3次元Semantic災難地域の地図作成のためのUGV,UAV協力DeepLearning 基盤SLAM技術
ロボットフラットフォーム技術
技術
270
消防士用パワードスーツ「Fironman」
4. 慶北道の浦項(浦項)では、2016 年~2021 年の 6 年間に渡り、71 億円の予算を投資、「国民安ロボット実証団地」が構築される予定である。慶北道の 2017 年の国民安全ロボット分野の予算は、6.7 億円(前年比 2.7 億円増)であり、代表的な実証事業として、FRT(株)、韓国生産技術院、LIGnex1、IDIS と共同で開発された、消防士用パワードスーツの「Fironman」が導入される。FRT(株)は、2017 年に、慶北道との MOU を締結し、Fironman の常用化を進めていくと発表している。
「Fironman」
出所:ロボット新聞
271
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
パワードスーツは現在のところ開発途上であるため、センサ、モータ、バッテリー等の構成技術にどのよう
な技術(要素)が使用されていくかは十分に定まっていないが、筋電位センサ、モーションセンサではより
高度な状態推定を目的とした高速演算プロセス、無線機能を内蔵したようなセンシングユニットが搭載さ
れていくとみられる。また、アクチュエータでは軽薄短小のサーボモータもしくは人工筋肉(作動力の点から
マッキベン型が有力)、バッテリーは安全性の観点から LFP を正極材に採用した LiB が主に用いられると
予想される。さらに、パワードスーツは軽量化が重要なテーマであることから、アルミ、チタン、CFRP 等の軽
量化材料も積極的に投入される可能性がある。
次頁にこれらパワードスーツの要素技術及び保有企業をまとめた。パワードスーツ向けに何らかの動きを
見せるメーカーは少ないが、これら要素技術を保有する企業を取り込みながら、パワードスーツの応用、
本格実用化に取り組んでいくことが重要である。
272
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
3D プリンタは、材料を付着することによって物体を 3 次元形状の数値表現から作製するプロセスであり、その多くが層の上に層を積むことによって実現される。2012年に⽶国の標準化機関であるASTM において Additive manufacturing(付加製造)との⽤語が定義され、材料の付着⽅法や供給⽅法により7 つの方式に分類されている。
3D プリンタ市場では、それぞれの方式別に樹脂、熱可塑性エラストマー(TPE)、⾦属、セラミックス、
ワックス、石膏などの様々な材料が開発・実⽤化されている。このうち、⾦属材料の積層造形技術としては、粉末床溶融結合(パウダーベッド法、PBF法)と指向性エネルギー堆積法(DED 法)がある。 粉末床溶融結合(パウダーベッド法、PBF 法)は、粉末をブレードあるいはローラなどでならし、できた
粉末床(パウダーベッド)をレーザあるいは電子ビームで溶融、焼結する工程を繰り返しながら積層造形する⽅法である。⾦属粉末においては、もっとも多く⽤いられている⽅法である。⾼密度・⾼強度製品の製造が可能(ほぼ真密度で、機械的性質は溶製材に匹敵)、⾼精度複雑形状品の製造が可能といった特⻑を有し、航空宇宙部品(タービンブレード、噴射ノズル等)、⾃動⾞⽤試作品(エンジン回りの部品等)、医療⽤部品(インプラント等)での適⽤例がある。 指向性エネルギー堆積法(デポジション法、DED 法)は、レーザ⾦属堆積法(LMD, Laser
Metal Deposition)とも⾔われ、⾦属粒⼦を溶融堆積させ、部品を造形する技術的である。局所的にレーザ光を照射し、⾦属が堆積される下地材料を溶融させ、この部分に⾦属粒⼦を供給することで造形を⾏う。パウダベッド法が塗布された粒⼦を溶かすのに対し、デポジション法は基本的には下地材料を溶かすプロセスであることが特⻑である。 具体的には、レーザ光を集光するレンズと一体化されたパウダノズルを持ち、窒素やアルゴンなどの不活
性ガスをキャリアガスとして⾦属粒⼦を供給し、レーザ照射部分にできた溶融プールに吹き付けることで、材料が堆積し、部品を造形する。また、繰り出した合⾦ワイヤを電⼦ビームまたはレーザにより溶融堆積させる方式もある。
名称 名称(英語) 主な材料 材料の形状
材料押出 Material extrusion 樹脂、TPEフィラメント
粉末床溶融結合 Powder bed fusion 樹脂、金属、セラミックス粉末
液槽光重合 Vat photopolymerization 樹脂液体
材料噴射 Material jetting 樹脂・ワックス 液体・固体
結合剤噴射 Binder jetting 石膏 粉末
指向性エネルギー堆積 Directed energy deposition 金属粉末・固体
シート積層 Sheet lamination樹脂、紙、金属 シート
〔各種資料より矢野経済研究所作成〕
3Dプリンタの方式と主な材料
275
デポジション法は、造形サイズ、造形速度で有利で、複合材からなる造形物(複層造形)の造形が容易である。これに対し、パウダベッド法は、最⼤造形サイズ分のパウダを備える貯蔵部分、⼤⾯積に均一にパウダを塗布する大型リコータ、造形物を不活性ガス雰囲気にするための⼤型チャンバが必要になるため、大型の造形は技術的、コスト的に難しい。デポジション法は、パウダを実際に造形物に使われる分だけ⽤意すればよく、不活性ガスチャンバも必ずしも必要でないため、可動領域の広いステージさえあれば、比較的低コストで大型造形装置を実現することができる。 造形速度では、パウダベッド法はレーザ出⼒が⾼いと照射部周辺のパウダが気流で流されてしまうといった問題があるため、使⽤できるレーザ出⼒が1kW程度に制限されるのに対し、デポジション法はレーザ出⼒が⾼くなっても造形プロセスに変化はないため、数kWのより出⼒の⾼いレーザを⽤いることができ、レーザ出⼒に応じてリニアに造形速度が上がっていくメリットがある。 ただ、デポジション法は、もともとレーザクラッディング(Laser Cladding)として、コーティングやリペア
⽤途向けに開発されてきた技術であるため、機械加⼯による後加⼯を前提とし、形状精度や造形表⾯の滑らかさはこれまであまり重視されてこなかった。このため、造形解像度、オーバーハング造形でパウダベッド法に劣り、造形ソフトも市販品がない状況である。造形解像度はパウダベッド法が 0.2 ㎜以下の解像度を実現しているのに対し、デポジション法は1~2mm程度と⼀桁劣る。また、90°近い⾓度でのオーバーハング形状や中空形状の造形も難しいなど、収束性の高いパウダノズルの開発、表面粗さを低減する造形技術、始点・終点での造形乱れを制御する技術等の開発課題を抱えている。 ⾦属粉末を⽤いた造形⽅法は、⽶・テキサス⼤学において開発された SLS 法が基礎となっている。
DTMが世界で初めて製品化した装置では⾦属粉末に樹脂を添加・コーティングした材料が⽤いられていたが、1994年に独・EOS が⾦属粉末のみを材料に⽤いた EOSINT シリーズをリリースした。その後は、独・Concept Laser、仏・Phenix systems、独・Realizer、英・Mining & Chemical Products(後に独・SLM Solutions と英・Renishawに分離)などが市場に参⼊した。
277
また、米・3D Systemsは2001年にDTM、2013年にはPhenix systems を買収した。これらのメーカーの PBF 装置は光源にレーザビームを採⽤しており、ファイバレーザの⾼出⼒化に伴い造形物の⾼密度化が進んだ。⼀⽅、1997年に設⽴されたスウェーデンArcamは、光源に電⼦ビームを利⽤した技術を開発し、2002年にPBF装置を市場に投入した。 その後は、欧米を中心にメーカー各社が PBF 装置の販売台数を順調に伸ばしてきたが、2016 年に
は PBF 法の有用性を示唆する買収劇が起こった。2016 年 9 月、GE が Arcam および SML Solutionsを買収する意向を発表した。SLM Solutionsについては⼀部株主の反対により買収を断念したものの、同年10月にConcept Laserの75%の株式を5億9900万ドルで買収することで合意。さらに、同年11月10⽇に終了した延⻑株式公開買い付けの結果を受け、GEがArcamの支配権を持つことでも合意に達した。 日本では、2003 年に松浦機械製作所が松下電⼯(現パナソニック)と共同で切削と PBF 法の⾦
属積層造形を組み合わせた複合機の販売をスタートさせた。2014年10月にはソディックが同様の機能を有する複合機「OPM250L」をリリースしている。また、アスペクトが2015 年 6⽉に⾦属粉末⽤ PBF装置「ラファエロ-HV 300F」を開発している。 また、ここ数年は⼯作機械メーカーによる複合機の開発も相次いでいる。2014年9月にDMG 森精
機が積層造形機能を組み込んだ複合型の5軸加⼯機、同年10月にはヤマザキマザックが旋削とマシニングによる複合加工と積層造形を統合した加工機を発表。さらに、オークマがミーリング、旋削、研削加⼯、⾦属積層造形を1台で⾏える複合機を開発している。
278
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
⾦属積層造形技術は、航空機部品への応用を推し進めるGE Aviationが先導し、量産部品への適用が進みつつある。3 プリンタ技術の中でも、従来技術と同等、それ以上の造形品質が得られることがこれを後押しするが、⼀⽅で、造形スピードの問題から、あくまでも少量⽣産のハイエンド部品に限定されるとの⾒⽅は強い。 航空機以外では、外科手術用インプラントに代表されるメディカル分野も特⻑的な取り組み(表⾯ポ
ーラス構造導入による機能性向上)を通じ、⾦属積層造形技術の優位性が⽰されようとしているが、次のターゲットとして期待される⾃動⾞分野では Daimler をはじめとする OEM の動きは活発であるが、いわゆる 10万個、100 万個のレベルを要求される量産部品への適用にはまだ時間が掛かるとみられている。 ⾦属積層造形技術が現在直⾯している課題、造形スピードや精度(公差や表⾯粗さ)のさらなるレベルアップに向けた取り組みが様々な⾓度から進められている。最近の装置開発の状況を⾒ても、パウダベッド法(レーザ)では、⾼速化、⾼精度化、⼤型化、さらには造形品の⾼品質化が進められており、レーザの⾼出⼒化(〜1kW)、多重光源化(〜4 台のレーザ)、造形エリアの大型化(□250 ㎜⇒□500 ㎜以上)、溶融池(メルトプール)のモニタリング機能付与などが図られている。また、パウダベッド法(電子ビーム)ではArcamが新たに航空宇宙部品向けのQ20及びインプラント用のQ10を投⼊、⾼出⼒化、⼤型化を⾏っている。 また、単純形状で大型製品の製造が可能、複層製品の製造が可能などのメリットを持つデポジション法では、真密度の複雑形状品の作製が可能な装置の開発が⾏われており、⾼速化・⾼精度化も進んできている。 いまのところ、システム及び材料のコストが高い、生産性が低く、高コストを正当化できないという声は強く、さらには、品質コントロールもビッグチャレンジと位置付けられている。複数のレーザを搭載し、造形スピードをアップさせるマルチプロセッシングヘッド化、溶融池をリアルタイムにモニタリングするインプロセスモニタリングの搭載が進展、モニタリングからのフィードバックを活かしたプロセスコントロール等により、造形スピードや精度は着実に向上してきている。しかし、⾦属積層技術をより発展させていくためには、マルチプロセッシングでは点や線といった従来の造形手法ではなく、面(エリア)での造形が必要、さらには、積層(Layer by Layer)ではなく、ワンステップで造形するといったレベルも模索していくべきと⾒なす専⾨家もいる。 これら次世代技術が、どこまで実現できるかは現時点で⾒えていないものの、⾦属積層造形技術のコストを正当化する⽅法論として、3D プリントの活用効果に改めて目を向け、装置や材料の開発をビジネスモデルやバリューチェーンに落とし込んでいく方向が強まっていくと予想される。 航空機部品で⽤いられることの多いインコネルやチタン等の特殊合⾦は部品製造時の材料ロスが⼤き
いことに着目した GE AVIATION、外科用インプラントのジェネレイティブデザイン(表面ポーラス構造)、パーソナライズに目をつけた AUTODESK(Within Medical)、トラックの補給部品を必要な場所で必要なだけ製造しようとするDaimler等、よりリーズナブルな⽅法で⾦属積層造形技術を活⽤しようとい
279
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
Wohlers Reportによると、2016年の3Dプリンタ市場(製品及びソフトウェア・サービス)は60億米ドル(約 6,600億円)と推計されている。
表 3Dプリンタ市場規模推移(トータル、製品、サービス)
台数ベースの3プリンタ市場規模(主に産業用となる5,000米ドル/台以上のシステム)では、
2016年:13,058台(同104.0%)と推移している。2015 年以降、期待されたほどの性能が得られないといった懸念が⼀部に拡がり、伸び率は低下傾向にある。⾦属造形⽤3Dプリンタの2016年出荷台数は957台と全体の10%弱のレベルに止まるが、航空機やメディカル、モータスポーツ関連の複雑形状パーツを中心に AM 技術の利⽤が拡⼤するため、⾦属造形⽤3Dプリンタの市場は今後も拡⼤基調が続くと⾒られている。
281
図 2016年における3D プリンタ市場(システム)におけるメーカーシェア
Wohlers Reportによると、2016年のメーカーシェア(5,000ドル以上のシステム、台数ベース)は、
Stratasys:35.6%、3D Systems:12.6%、Envisiontec:9.4%、Mcor:3.8%、EOS:3.1%、DWS:2.9%、Union Tech:2.7%、Carima:2.5%、その他:27.5%と続く。日本メーカーは“その他”に含まれるが、メーカー所在地に基づく累計出荷台数ベースで⾒ると、地域シェアは⽶国:46.3%、欧州:18.8%、イスラエル:26.2%、中国:4.5%、日本:2.8%、その他:1.5%となっている。
282
でいる。 国内ではローエンド機で得られる造形品の品質への落胆が⽣まれ、2015 年にはブームが⼀段落して
おり、海外でも同様の機運が⾼まる懸念がある。ただ、3Dプリンタの⾼性能化が続くことに加え、材料として多用されている PLA・ABS フィラメントにおいては日本メーカーから品質や機能を高めた製品が相次ぎ市場に投入されている。さらに、PPやPETG、PC、PA系などをベースとしたフィラメントの製品化により、ユーザーが製造したい造形品・⽤途に合わせて材料を選択できる環境が整えられつつある。さらに、欧州や米国、中国から韓国、台湾など需要地が拡大していくことも期待できよう。 ②試作領域における⽤途の広がり(産業分野) 3D プリンタは産業分野において、試作品のなかでも意匠確認等のデザインモデルの製造に多用されて
いたが、装置の⾼性能化と造形技術の進化、材料開発の進展に伴いワーキングモデルへの採⽤が進んだ。特に材料開発が⽤途拡⼤に⼤きく貢献しているものと考えられ、VP 法であれば光硬化樹脂に対する⾼温環境下で使⽤する際の耐熱性、勘合・着脱試験等を⾏うための靭性、⽔や気体等の流体を可視化したい場合の透明性などを⾼次で両⽴させたグレード開発が進んでいる。 また、パウダベッド法向けの樹脂市場ではSolvayやBASFがPA6粉末、東レではPSS粉末を開発
している。これらの材料は幅広い分野の最終製品向けで実績があり、最終製品と同じ材料で試作品を製造したいといったニーズに対応することが可能となった。また、PA6粉末やPPS粉末は耐熱性や機械的特性の点において、現在の主要材料である PA12 粉末がカバーしにくかったワーキングモデル・機能部品へも展開しやすい。メーカー各社は市場参入から間もないが、2018 年頃にはこれらの粉末の需要が本格化するであろう。 ③試作品から最終製品への拡大(産業分野) 従来から治工具や補聴器などの製造に3Dプリンタが使⽤されてきた。さらに、ここ数年で複雑形状部
品の製造が可能、⼀体化(部品点数削減)や軽量化が可能、開発期間の短縮化が可能などの効果が認められ、最終製品向けで3Dプリンタの適用が増えつつある。ME法では⾃動⾞外装パネル向けでASA フィラメント、航空機部品向けではPEI フィラメントの採⽤事例がある。パウダベッド法では航空機のエアダクトやロボットアーム、ボトル搬送⽤グリッパー、医療⽤ドリルガイド、⼈⼯装具・矯正器具、携帯機器用ケースなどで主にPA12粉末が使用されている。先述したPA6粉末やPPS粉末の上市、さらにはPA66 粉末や PBT粉末などの開発も進んでいるとみられるため、樹脂粉末を用いるパウダベッド法では2020年以降とはなるが、最終製品向けでの採⽤が広がる可能性が⾼い。 また、パウダベッド法では⾦属粉末の需要が最終製品向けで急増している。 航空機分野ではボーイング「777-200ER」に搭載されるジェットエンジン GE-94B ⽤の温度センサハ
ウジング、次期ジェットエンジ LEAP の燃料ノズル向けで Co-Cr-Mo粉末が採⽤されている。医療分野ではインプラント向けでTi6Al4V粉末、⻭科技⼯物向けではCo-Cr-Mo粉末などの需要が⽴ち上がった。この他、海外ではオイル&ガス分野が期待されており、既にガスタービンノズルやダウンホールツール用ノ
284
ズルなどでTi系合⾦などの採⽤実績があるようだ。 ⾦属粉末を⽤いる PBF 法はほぼ密度 100%の造形品を製造できるため、最終製品への適用が容
易である。そのため、今後も航空宇宙分野などの少ロット品向けを中⼼に、⾦属粉末市場は⾼い成⻑率が続くであろう。 さらに、3D プリンタメーカーによる装置開発の進展に伴い、最終製品向けでの需要はさらに拡大しそう
だ。Stratasys では 2016 年 8 月に「FDM 法」を応用した「Infinite-Build 3D Demonstrator」「Robotic Composite 3D Demonstrator」をリリースした。いずれの機種も量産ラインへの導⼊を想定しており、同社が提唱する「Direct Digital Manufacturing」(DDM)をさらに進化させるための次世代型3Dプリンタである。材料にはフィラメントではなくマイクロペレット状の樹脂を使用している。 「Infinite-Build 3D Demonstrator」は造形テーブルを垂直に⽴て、造形物を⽔平⽅向に動かす
ことで⻑さ⽅向の部品サイズの制約を解消しており、⼤型の⽴体モデルを短時間(現⾏機の 1/10)で造形できる。開発に当たっては米Boeing、米Ford Motor と連携を図った。 「Robotic Composite 3D Demonstrator」は8軸のロボティクスシステムを採⽤しており、材料を
押し出す方向と造形ヘッドを動かす方向を任意に制御することが可能である。Siemens のモーションコントロールハードウェア(産業用ロボットアーム)とStratasysの「FDM技術」を組み合わせて開発に成功した。この新たなシステムでは炭素繊維などの強化材を使う際に繊維の配向に配慮した造形ができるため、将来的にはRTMや射出成形よりも⾼い強度の造形品を製造できる可能性がある。
285
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
⾦属積層造形技術は、鋳造等のコンベンショナルなプロセスと同等、もしくはそれ以上の機械特性が得られることに加え、設計の⾃由度の⾼さにより軽量化が可能、材料ロスも削減できることなどから、航空機、メディカル・デンタル、モータスポーツ等で使⽤されるハイエンド、⼩量⽣産の部品の理想的な製造⽅法となりうるとされる。 航空機 同分野では、GE Aviation が先駆的な役割を果たしている。同社は、既に最新型エンジンである
「LEAPエンジン」(2016年春よりデリバー開始)の燃料ノズル製造にAM技術を適用、2020年までにはその他のエンジン・パーツへの適用拡大などにも取り組み、AM技術により10万個以上のパーツを製造する方針を有している。 GE Aviationは、ヘリコプター用エンジン「CT7」を分析した結果、約40%のエンジン部品でAM技術
が適用できると判断。再設計等を実施した結果、それまでの 900 部品を 16 部品に削減するとともに、35%の軽量化、30〜40%のコスト削減が可能と⾒積もった。例えば、CT7 の燃焼チャンバはそれまで50部品以上で構成していたが、AM技術を適用することで30%の軽量化が可能になったとしている。また、設計・テストの期間も従来の1年間が6か月になるなど、開発期間の短縮といったメリットもあったようだ。
286
メディカル・デンタル 複雑形状、少量⽣産という観点から、メディカル・デンタルでは早くから AM 技術の適用が進められてき
た。伊Lima Corporationは10年以上前より整形外科器具の製造にAM技術を利⽤。骨頭(丸くなっている部分)、臼蓋(骨盤のくぼみ)等の形状やポーラス状の表面形状といった複雑な形状をパウダベッド技術により高い再現性で実現している。 DePuy Synthes(Johnson & Johnsonグループ)は、Materialise とインプラント製造への3D
プリント技術導入に向けたパートナーシップを締結。患者それぞれの最適な形状、サイズを CT スキャンでモデル化し、3D プリントで製造するカスタムメイドなインプラント(材質は Ti合⾦及び PEEK)の実現に取り組む計画を明らかにしている。 3D プリント技術のメディカル・デンタル分野への全面導入はまだ難しいものの、補聴器でもカスタムメイ
ド品が定着しつつあるなど、⼀部のカテゴリーでは競争領域となっている。特にインプラントでは、頸骨や頭蓋、下顎、臼蓋窩 (寛骨) や脛骨、大腿骨の置換手術を中心に積層造形により作成されたインプラントで実施されていることが増えている。これら外科インプラントを製造する代表的な企業としては、アルゼンチン Novax DMA、スロバキアCEIT Biomedical Engineeringが挙げられる。両社ともチタン製カスタム外科インプラントの製造にフォーカス、ここ数年は3Dプリンタの導⼊に注⼒している。
ハイエンド・少量⽣産といった観点から、軽量化、コスト削減、部品点数削減等、AM技術のメリットが活かせる重点アプリケーションとしてポリマー、⾦属ともにAM技術の導入が進む。
⾦属に関しては、Co-Cr-Mo合⾦、インコネル、Tiが主なターゲット。耐久性等の特性に対するさらなる検証が重要と⾒られている。
より大型の部品を製造したいというニーズもある。 さらなる量産性の向上として、ハードに対する信頼性、メンテナンス性が重要視されている。
287
⾃動⾞ ⾃動⾞分野では、プロトタイピングに古くからAM技術が利⽤されてきたが、⽣産性の低さからモータスポーツなどの⼀部の少量⽣産部品を除き、量産部品での取り組みはあまり進んでいない。 2016年9月、PSAグループは米スタートアップDivergent 3D と戦略的提携を発表、両社でAM
技術を⽤いた⾞体構造の研究開発に取り組むことを明らかにしている。具体的には、CFRP 製の部品を3Dプリントで製造したジョイントで連結する構造を想定している。Divergent 3Dはこれにより投資額、製造コストを削減できるとしている。 *こうした技術(コンポジット部品のジョイントの製造に 3D プリンタを利⽤)は、既に⾃転⾞で量産化
の例がある(Robot Bike Companyが2016年5月にローンチ)。 2017年1月、Audi と EOS はEOSがAudiのAM技術導入をサポートするパートシップを締結し
たことを発表している。このパートナーシップの一環として、将来 Audi の本拠地であるインゴルシュタットに両社が協⼒して3D プリンタセンターを設置することも計画されている。 3D プリンタを量産部品の製造に導⼊した場合、⾦型に関わる労⼒・コストの削減、柔軟な製造オペレーション(受注生産)、部品製造に係るコスト構造の変化(スケールメリット前提とは異なる競争軸)などがメリットとして想定される。部品統合、軽量化等が様々な側⾯から環境負荷の低減につながる可能性もあるが、いまのところ AM 技術はシステム及び材料のコストが⾼く、⽣産も低いため、⾃動⾞分野ではその高コストを正当化できないとみられている。 ただ、⾃動⾞そのものの部品製造ではなく、⾦型や治具など、⽣産規模の⼩さなアプリケーションでは、AM 技術の適用が進む可能性もある。実際、オペルは、サイドウィンドウの⾞名ロゴを⽣産するための治
生体適合性に優れたTi合⾦での取り組みが活発。 ソフトウェアの充実化等により、⾼度な多孔質構造といった複雑形状の作成が可能に。 課題としては、生産スピード。 今後は、4D プリントコンセプト(時間とともに形状変化)の導入などに期待。
288
具を3D プリンタで造形している。3D プリンタを利⽤した治具は従来品よりもコストを最⼤90%、重量を70%削減できた。治具は、⾞両の部分的なマイナーチェンジであってもそれ専⽤の治具が必要である。3D プリンタを活用することで、これまでは治具の製造コストを考えてできなかったことにも取り組めるようになったとしている。
システム及び材料のコスト ⾃動⾞部品のオーダー規模に⾒合う⽣産性 アルミ、SUS等の汎⽤材料の適⽤ ⾦型、治具でのAM技術適用
289
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
日本では、2003 年に松浦機械製作所が松下電⼯(現パナソニック)と共同で切削と PBF 法の⾦属積層造形を組み合わせた複合機の販売をスタートさせた。2014年10月にはソディックが同様の機能を有する複合機「OPM250L」をリリースしている。 また、アスペクトが2015年6⽉に⾦属粉末⽤PBF装置「ラファエロ-HV 300F」をリリースした。同社
は 2010年より NEDO の「次世代素材等レーザ加⼯技術開発プロジェクト」においてチタン合⾦粉末から⾼速、⾼精度かつ要求強度を満⾜させた⼈⼯関節を成形することを⽬標として「ラファエロ-150V」の開発に成功。2013年からはアルミニウム粉末による造形研究に係るNEDOプロにも参画している。 加えて、ここ数年は⼯作機械メーカーによる複合機の開発も相次いでいる。⾦属3Dプリンタが設計の
柔軟性や迅速な製品開発といった効果を工作機械業界にもたらし、工作機械市場のなかで存在感を示し始めていることについて、⼯作機械メーカーの⾒⽅は様々である。 その中で近年⽬⽴っているのが、⼤⼿⼯作機械メーカーを中⼼に従来の切削機と⾦属 3D プリンタを
組み合わせたハイブリッド⼯作機械を上市するケースである。⾦属 3D プリンタ単体では既に欧州が先⾏しているが、加⼯は別途⾏えば良いというスタンスで精度の追求は優先されていない。これに対しハイブリッド 3D プリンタは、積層に切削を組み合わせることで⽇本が得意とする⾼精細、緻密性といった優位性を生かすことができる。 具体的には、2014年9月にDMG 森精機が積層造形機能を組み込んだ複合型の5軸加工機、
同年10月にはヤマザキマザックが旋削とマシニングによる複合加工と積層造形を統合した加工機を発表。さらに、オークマがミーリング、旋削、研削加⼯、⾦属積層造形を1台で⾏える複合機を開発している。 また、東芝機械、三菱重⼯が技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構(TRAFAM)
での開発成果を基に、2016年12月にそれぞれの開発試作機を公開している。両機ともレーザデポジション方式を採用、早期の製品化に取り組むことを明らかにしている。 ハイブリッド 3D プリンタの先駆けは松浦機械製作所が発売した LUMEX である。 「LUMEX」シリーズは、ファイバレーザによる「⾦属光造形」とマシニングセンタによる「⾼速・⾼精度切削加⼯」を融合したハイブリッド⾦属3Dプリンタとして2002年に商品化。2006年の「LUMEX Advance-25」の受注開始以降、⾼付加価値⾦型市場を中⼼に着実に販売実績を積み上げ、2017 年時点では 50 台以上の納入実績となっている。 松浦機械製作所は、2016年6月、最大工作物寸法がW600×D600×H500mm の「LUMEX Advance-60」を発表。さらに、大型機の開発時に取り組んだ高速化のノウハウを活かし、2017 年 4月には「LUMEX- Advance-25」のフルモデルチェンジを実施した。 具体的には、造形時間の短縮を⽬的に、⾦属粉末のスキージング動作の⾼速化、ガルバノ制御・造形条件(レーザ機能)の最適化などを挙げている。これにより、単位時間当たりの造形容量 14 ㏄/h(従来比 2 倍)を達成したとしている。さらに、オプションの⼤容量 1kW ファイバレーザの搭載により、造形容量 35cc/h(従来比 5 倍)も可能なほか、切削加⼯前粉末吸引機能による切削送り速度アップと⼤径⼯具使⽤の実現により、切削時間を従来⽐ 75%削減することができたとしている。
290
図表 松浦機械製作所の⾦属光造形複合加⼯機 機種 LUMEX Advance-25
最大工作物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
256×256×185 (OP)256×256×300
主軸回転速度(min-1) 45,000 (ツール:1/10テーパ特殊BT20)
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
260/260/100
造形容量(㏄/h) 14 レーザータイプ Yb ファイバーレーザ
ー,400W (OP)500, 1000W
機種 LUMEX Advance-60
最大工作物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
600×600×500
主軸回転速度(min-1) 45,000 (ツール:1/10テーパ特殊BT20)
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
610×610×100
造形容量(㏄/h) ― レーザータイプ Yb ファイバーレーザ
ー,1000W (OP)500W
出所:株式会社松浦機械製作所
また、新型の「LUMEX Avance-25」には、全⾃動粉末供給・回収・再利⽤システム(APR システム)をオプションで用意。オペレータが直接材料に触れることなく粉末供給から回収まで全⾃動で⾏うことができ、⾼い操作性を確保しつつ作業環境を良好に保つことが可能となっている。このほか、造形テーブルの上下移動を制御するU軸ストローク延⻑(185→300mm)のオプションもラインナップ。これにより、より大きく重いワーク(256×256×300mm/150kg)にも対応可能になっている。 これらハード面のバージョンアップのほか、松浦機械製作所は LUMEX 専用 CAM「LUMEX CAM 2016」 の性能も併せてアップ。機械とソフトの性能を同時にアップすることで、⾦属3Dプリンタのアプリケーション拡大を促していていく。
291
なお、対応⾦属はマルエージング鋼、Ti-6Al-4V、SUS630、SUS316L、コバルトクロム、ニッケルアロイ718、アルミニウムAlSi10Mg。チタン粉末及びアルミ粉末は不活性ガス雰囲気が必要となっている。 ソディックは2014年4月、⻑年ハイブリッド式⾦属3Dプリンタ等の開発を⾏ってきたOPMラボラトリ
ーを買収、同年11月、OPMラボラトリーとの共同開発により⾦属3Dプリンタ「OPM250L」を投入した。同装置は⾦属粉末を均⼀に敷き、その⾦属粉末をレーザ光でスキャンすることにより融合させ、その後、回転⼯具で⾼速ミーリングによる⾼精度仕上げ加⼯を⾏うことができるものとなっている。 ソディックは 2016年10月、大型3 次元造形物に対応したラージ・サイズ・モデル「OPM350L」の発売を開始している。造形物サイズはW350mm、⻑さ350mm、厚さ350mm。加⼯⾯質、加⼯精度は「OPM250L」と同等で、加⼯速度を⾶躍的に向上させた点が⼤きな特⻑となっている。 加⼯速度については、従来の加工方式(シングルモード)に対し、新たな加工方式(パラレルモード)
を導入、1台のレーザを高速に制御することで、複数箇所を同時に造形することが可能になり、造形時間の短縮化を実現している。また、造形する3次元形状に応じて、レーザによる積層回数と工具による切削仕上げ加⼯のバランスを最適にすることで、切削加⼯時間も図っている。 ⾦属3次元造形速度を⼤幅に向上した場合、加⼯エリア内の⾦属蒸気の集積物(ヒューム)が増
加するが、「OPM350L」ではレーザ加⼯時に発⽣するヒュームの回収能⼒を⼤幅に向上させるとともに、メンテナンス頻度の⾼いヒュームコレクタを新しく開発することで、メンテナンスの頻度を従来に⽐べて3分の1に削減した。また、切削加⼯に使⽤するHSK-E25ツールホルダのATC本数(工具交換装置)を20本とし、⾦属粉末の材料⾃動排出⾃動供給装置(Material Recovery System:MRS、オプション)を開発することで、無⼈による⻑時間連続運転を実現している。 「OPM350L」では、自社開発・製造の新型 NC装置「LN4RP」および高性能リニアモータを搭載。
CAD による3次元冷却配管内蔵⾦型の設計、CAE による樹脂温度シミュレーションを実施。設計されたCADデータから専用CAM「OS-FLASH」でのNCプログラム作成後、⾦型製造の⼯程をワンストップで⾏うことができる。「OS-FLASH」はOPMシリーズ専用のCAMシステムで、IGES、STEP、Parasolidなどの CAD データを⼊⼒としてレーザおよび切削データの両⽅を作成。独⾃のアルゴリズムにより⾼精度の切削パスを⾼速計算で作成することが可能である。 「OPM350L」の価格は7,000万円/台、24台/年の⽣産台数を計画している。ソディックでは「OPM
シリーズ」をプラスチック製品の成形⾦型づくりを根本から変える⾦型⼀体化製造システムと位置付けており、従来の⽣産システムでは不可能な成形品の⽣産性向上、リードタイムの短縮、⼤幅なコストダウンを実現することができるとしている。 また、グループ傘下のOPMラボラトリーは、⾦属3Dプリンタ技術の研究開発、設計・生産事業に加え、⾦属粉末材料開発、⾦属 3D プリンタ専⽤ソフトウェア開発、⾦型設計・⾦属光造形複合加⼯サービスビューロ等へと事業領域を拡⼤している。2014年12月にはソディックとDDM福井(量産加⼯センター)を設⽴、開発⽤を含め、トータル10台の⾦属3Dプリンタを設置している。また、設計キャパシティに関しても、2016年3月に東北デザインセンター(福島県)を設⽴、設計能⼒を5倍に増強している。
292
図表 ソディックの⾦属3Dプリンタ 機種 OPM250L
最大造形物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
250×250×250
主軸回転速度(min-1) 6000〜45,000 (HSK-E25)
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
260/260/260
造形容量(㏄/h) ― レーザータイプ Yb ファイバーレーザ
ー,500W
機種 OPM350L
最大工作物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
350×350×350
主軸回転速度(min-1) 45,000 (HSK-E25)
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
360/360/344
造形容量(㏄/h) ― レーザータイプ Yb ファイバーレーザ
ー,500W (OP)1000W
*⾦属粉末:マルエージング鋼、SUS420J2、SUS316、SUS630 出所:ソディック
アスペクトは、2003 年に東京⼤学⽣産技術研究所の研究⽀援や東京都助成⾦を得て「SEMplice 550」の開発を開始、2006年末に製品化した。その後、横浜国⽴⼤学との共同研究により中型サイズの「SEMplice 300」や小型サイズの「SEMplice 150」を開発。2012 年より第⼆世代の「ラファエロⅡシリーズ」に移⾏している。 ラファエロシリーズの最大の特徴は、装置デザインを一新したことに加え、SEMplice シリーズの約 2 倍
の生産性を実現。また、ビーム径を従来より約15〜20%絞り込むことにより、高精細加工性も改善した点が挙げられる。シリーズは「ラファエロⅡ550」(大型装置)、「ラファエロⅡ300」(クオーツヒータ搭載の中型装置)、「ラファエロ 150-HT」(スーパーエンプラ対応)等のポリマー用が中心であるが、その中で、真空下でTi-Al6-V4粉末やAlSi10Mg等の⾦属粉末をプロセスできる「ラファエロ-HV300」もライ
293
ンナップしている。 DMG森精機は2014年9月、⾦属材料粉末とレーザを同時に照射し、積層と溶融を⾏うダイレクト
エナジーデポジション(Directed Energy Deposition)を採用した「LASERTEC 65 3D」(5軸加工+AM 機能搭載機)を発表。異なる⾦属材料粉末の積層や⼩型製品の造形、インペラやブレードといった⾼付加価値製品の補修などで利⽤が進んでいる。 また、2017年6月には、新たにパウダベッド⽅式を⽤いた⾦属3Dプリンタ「LASERTEC 30 SLM」
の受注を開始している。同社は2017年2月にセレクティブレーザーメルティング(SLM)の技術⼒を持つ独REALIZERの株式を50.1%取得し子会社化。そのRELIZERとの共同開発により「LASERTEC 30 SLM」を製品化した。 LASERTEC 30 SLMの最大造形サイズは300×300×300mmで、積層厚さは20μ〜100μm。
インペラや⻭冠など、⼯具が届かず切削が難しい⼩物部品を精密に造形できるとしている。稼働軸を少なくして構造をシンプルにしたことで、設置面積を抑えたほか、粉末材料の供給・回収機構をカートリッジ内に収めた「材料粉末調整システム」も搭載する。これにより材料の再利⽤率を95〜98%に高められる上、材料の交換も容易になる。操作盤はタッチパネル式で、3D シミュレーションや積層プログラムを簡単な操作で実⾏できるとしている。また、DMG 森精機は、粉末材料と併せて加⼯・実験・製造データなど材料に関するデータベースも提供する。価格は 6950 万円(税別)から。オプションとして 5 軸加工機「HSC 20 linear」などによる仕上げ加工までを含めたトータルソリューションとして提案していく。
図表 DMG森精機「LASERTEC 30 SLM」 機種 LASERTEC 30 SLM
最大工作物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
300×300×300
主軸回転速度(min-1) ―
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
―
積層厚さ(μm) 20-100 レーザータイプ Yb ファイバーレーザ
ー,400-1000W
ヤマザキマザックは、2014 年 10 月、旋削とマシニングによる複合加工と積層造形を統合した加工機「INTEGREX I AM」を発表。ユーザーの研究開発部門などを中心に導入を進めてきた。2016年には新たに国産技術「マルチレーザ式⾦属積層技術」を採⽤したハイブリッド複合加⼯機「INTEGREX
294
i-200S AM」、ワイヤアーク式⾦属積層造形技術を採⽤した「VARIAXIS j-600AM」の開発を発表している。 「INTEGREX i-200S AM」の特⻑である「マルチレーザ式⾦属積層技術(M-LMD)」は、戦略的
イノベーション創造プログラム(SIP)による「高付加価値設計・製造を実現するレーザーコーティング技術の研究開発」プロジェクトで実現した。従来の同社モデルなどでも採用していたレーザによる積層方式は、レーザを中央から噴射し、周辺から⾦属粉末を噴射して溶かして積層していく⽅式であるのに対し、M-LMD は周辺6 ポイントからレーザを照射し、中⼼部から⾦属粉末を噴射する仕組みとなる。従来技術に⽐べ、加⼯点への安定した⾦属粉末供給を可能とし、⾶⾏中の⾦属粉末を効率よく溶融させ、⺟材への熱影響を低減することができる。これにより、微細な積層造形加⼯や熱影響が問題となる薄板⺟材への加⼯に有利で、⺟材を傷めずに薄いコーティングなどが⾏えるとしている。 一方、「VARIAXIS j-600AM」は、市販のワイヤアーク溶接装置を 5 軸⽴形マシニングセンタに取り
付けたもの。溶接トーチを制御することで、溶接作業の⾃動化と切削加⼯⼯程との融合による工程集約を実現する。ワイヤアーク溶接による積層は、⾦属パウダによる AM加工に比べ、短時間に多くの積層造形を⾏うことが可能であることが特徴である。⾦属パウダ式はまだ粉末が⾼額である場合も多く、材料も限られている。ワイヤアークを用いれば、市販品がそのまま使えるために、低コストで積層が実現できる。また、粉じん爆発の⼼配もなく、安全性の⾯でも有利としている。積層精度についてはそれほど⾼くはないが、後の切削⼯程を組み合わせることを考えれば積層スピードも速いという利点があり、⽤途によっては⾦属粉末よりも利便性が高いと同社ではみている。 さらに、同社はデポジション方式の AM 技術と⽴形 5 軸マシニングセンタをハイブリッド化した
「INTEGREX i-400AM」を2016年9月に発表している。同システムはツールマガジンに1kWファイバレーザをビルトイン、ミリングタレットにクラッディングヘッドとして用いることのできる構成を採っている。 オークマは2016年10月、ミーリング、旋削、研削加⼯、⾦属積層造形を1台で⾏える次世代型超複合加工機「LASER EX シリーズ」を発表している。「LASER EX シリーズ」は、ミーリング、旋削、研削加⼯に、焼⼊れ、⾦属積層造形を加えた究極の⼯程集約を世界で初めて1マシンで実現したもので、航空機エンジン基幹部品の品質要求に応えうる積層造形技術のソリューションと位置付けられている。 特⻑としては、デポジション⽅式による⾼効率⼤容量と⾼精細積層造形の両⽴、レーザ精密焼入れ
対応、多種なワークサイズ、形状への対応、航空機基幹部品の品質要求に応えうる世界最高水準の高信頼性、安定性を掲げており、多種多様なワークに対応するため「MU-8000V LASER EX」 、「MU-6300V LASER EX」、「MU-5000V LASER EX」、 「MULTUS U4000 LASER EX」 、「MULTUS U3000 LASER EX」の全 5機種でシリーズ展開している。このうち、ワークサイズφ1000mmに対応した「MU-8000V LASER EX」は世界最⼤の⾦属積層造形マシンとなっている。
295
図表 オークマ「LASER EXシリーズ」 機種 MU-8000V LASER EX
最大工作物寸法 (幅×奥⾏×⾼さ mm)
―
主軸回転速度(min-1) 50〜8000 (HSK-A63)
軸移動量(X/Y/Z) (mm)
925/870/600
積層厚さ(μm) ― レーザータイプ 600W
(OP)1, 2, 4kW
東芝、東芝機械は、従来よりも⾼速な造形を実現する⾦属3Dプリンタの試作機を共同開発している。レーザ⽅式の⾦属3Dプリンタでは、造形速度の向上が⼤きな課題となっている。試作機ではパウダベッドフュージョン⽅式に替えて、ノズルから⾦属パウダを噴射すると同時にレーザ光を照射することで⾦属パウダを溶融、凝固させるレーザメタルデポジション(LMD)方式を採用し、高速化した。 また、造形速度のさらなる向上として出⼒6kWのファイバレーザを適⽤、⾼精細造形のために流体シミュレーションを活用し、高収束ノズル(最小収束径:0.7mm)も開発している。その結果、359㎤/hの造形速度(出⼒4kW時)と0.3mmの造形幅を実現した。 ⾦属パウダの材料は、SUS、ニッケル基合⾦、鉄などに対応。供給経路を切り替えることで、材料を部分的に変更した複層造形も可能となっている。造形サイズは 300×300×100mm。機上に後処理⽤のレーザポリッシュ機構も搭載した。レーザポリッシュを施すことにより、表面粗さを14.1μm Raから3.9μm Raまで低減することができたとしている。 このほか、TRAFAMを通じた取り組みとして、三菱重⼯及び三菱重⼯⼯作機械が「マシニングセンタ方式レーザビーム3D プリンタ」、松浦機械製作所、古河電気工業が「大型高速レーザビーム3D プリンタ」、日本電子が「複層電子ビーム3Dプリンタ」、多田電機が「大型高速電子ビーム3Dプリンタ」の開発に取り組んでいる。
296
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記)
主な⾦属 3D プリンタメーカーとしては、3D Systems(米)、EOS(独)、Concept Laser(独)、Renishaw(英)、SLM(独)、Optomec(米)、Arcam(スウェーデン)が挙げられる。このうち、Arcam と Concept Laser には 2016年末に GE が資本参加しており、両社は現在 GE Additive ビジネスユニットの一部となっている。GE は、⾦属 AM 技術開発の中で極めて重要なポジションに⽴っており、⻑年の取り組みを経て、⾦属 AM 技術に対する大規模投資に乗り出している。Arcam及びConcept Laserの買収もその一環と位置付けている。 こうした GE の⾦属AM技術に対する積極的な姿勢も影響し、ここ数年、⾦属3D プリンタに参入す
る企業が増加、主だった企業だけでも Additive Industries、AddUp、ExOne、Markforged、Sisma、Trumpf、InssTek などがある。また、中国や韓国等のアジア地域でも動きが活発化、Hunan Farsoon(中国)、Beijing Long Yuan(中国)、Bright Laser Technologies(中国)、InssTek(韓国)、Sentrol(韓国)等の名前が業界でも徐々に聞かれるようになっている。
297
①米国
3D Systems
3D Systems は、1985 年に設⽴され、2001 年に材料メーカのスイス RPC を完全子会社化した。2009年以来20以上の小さな買収を繰り返し、3Dプリンタ市場の統合を目指してきた。2011年には米 Huntsman のアドバンス・マテリアル事業を買収し、光硬化樹脂「RenShape」にかかわる材料技術や知的財産などを自社内に取り込んでいる。2014 年 11 月時点では、合計で 48 社を買収しており、2017年3月までにデンタルマテリアル会社のVertexを含む3社を追加買収した。製品ラインアップとしては、廉価版製品の「Cube」シリーズを普及させている。 2016 年 3⽉には、アメリカのコロラド州に、ヘルスケアテクノロジーセンターを設⽴、医療関係の技術開発に努めている。また、同年1月には、新製品であるProx DMP320(販売価格:60万5千ドル)を発表した。Prox DMP320 は2014年に買収した LayerWise の⾦属AM技術をベースにしたもので、造形物サイズ:275×275×400mm、純チタン及びSUS/ニッケル基アロイのそれぞれに対応したコンフィグレーションを用意している。
3D Systemsの新モデルProx DMP320
出所:3D Systems
301
Optomec
Optomec は、急速に成⻑している AM サプライヤである。同社の特許取得済みエアロゾル・ジェット・システム(印刷電子機器用)と LENS 3D プリンタ(⾦属部品⽤)は、製品コストを削減し、性能を向上させるツールとして認知されている。これら印刷ソリューションは、電⼦インクから構造⾦属、さらには生物学的物質に⾄るまで、幅広い機能材料を使⽤できる特徴を持つ。 同社は、エレクトロニクス、エネルギー、ライフサイエンス、航空宇宙産業の生産アプリケーションをターゲ
ットに、世界中の 300 社以上に納入している。2016 年 9 月には、最廉価製品である「LENS 3D Metal Additive System(249,000 ドル)」を発表し、2017年11月にはそのハイブリッドバージョンである「LENS 3D Hybrid Machine Tool(275,000ドル)」を発表した。また、同時期に発表した「LENS 3D Metal Hybrid Controlled Atmosphere System」ではTi合⾦の造形に向けて酸素及び湿度レベルを 40ppm以下にコントロールできるチャンバを導入した。これら新モデルは、製造プロセスの時間とコストを削減し、最終製品の性能を向上させることができるとしている。
LENS 3D Hybrid Machine Tool
出所:Optomec
また、新製品の発売と同時に、Mastercamの開発社であるCNC Softwareとグローバル販売提携
を発表している。この提携により、Optomecは、LENSプロセス用に調整されたアディティブベースのプラグインと共に、Mastercam ソフトウェア製品を販売・サポートすることになる。さらに、プラグインは
302
Mastercamに統合され、ユーザーはプラットフォーム固有のCADモデリングとインポート、多軸ツールパスの⽣成と可視化、およびキネマティックな解析機能を利⽤できるようになる。 OptmecはEMS大手の台湾Lite-on Technologyグループが中国拠点に複数台のLENSシス
テムを導入、コンシューマ製品向け3Dアンテナ、3Dセンサの製品に利⽤していることを明らかにしている。
303
②欧州
EOS(ドイツ)
EOSは、1989年に設⽴された世界的なレーザ焼結システムのトップメーカで、2016年10⽉には累計2,400台のAM システムを出荷したことを明らかにしている。EOS のAM技術は、⾦属、プラスチックのレーザ焼結が中心。2016 年の出荷実績は、ポリマーAM システム:155 台、⾦属 AM システム:248台となっている。 イギリスのサウスハンプストン大学では、同社の技術を使って、無⼈⾶⾏機のプロトタイプを製作した。ま
た、スロバキアのコシツェ工科大学からのスピンオフ企業「CEIT Biomedical Engineering」が、チタン合⾦製の頭蓋顎顔⾯⾻イプラト⽣産に EOS のレーザ焼結技術を選定し、この製品は 2014 年 11 月に EU の医療機器認可を取得した。 EOS は 2014 年 3 月、同社の AM 造形装置「EOSINT M280」に使⽤できる軽量チタン合⾦
(EOS Titanium Ti64ELI)とステンレス鋼(EOS Stainless Steel 316L)を製品ポートフォリオに加えた。これらは耐腐⾷性で⽣体適合が⾼いため、特に医療分野に向いており、後者は手術器具や内視鏡手術、整形外科およびインプラント用に最適である。
EOSの代表モデルEOS M400-4
出所:EOS
304
また、同社は 2014 年にオーストリアの Plasmo Industrietechnik と提携した。Plasmo Industrietechnik は溶接加工における品質管理⽤プロセスモニタリング装置のメーカーで、レーザ溶接の品質管理・診断システムも提供している。その後、2015 年 11 月には、プロセスモニタリングシステム「EOSTATE MeltPool Monitoring」を発表している。同システムはフォトダイオード、カメラアダプタ、信号増幅器、フィルタ等で構成、Meltpool から発せられる光を検知することで、リアルタイムなモニタリングを⾏うものとなっている。 製品面では、2016年9月にEOS M400-4 Metal system(ベースプライスは142万ユーロ)を発売開始している。EOS M400のハイスループットバージョンと位置付けられており、4 つの400wレーザを搭載している。造形領域は 400×400×400、4 つのレーザをパラレル方式で制御することで、高いパフォーマンスを実現した。 2016年11月には、Shared Modules コンセプトを発表している。これは、造形前の準備(荷ほど
き、ふるい分け等)をパーツ製造と並⾏して⾏える追加モジュールを⽤意するもので、装置間で共有して利⽤するモジュールのイメージで展開していく。 また、同社はEOS Materials(米テキサス州)の取り組みに加え、、AM関連のスタートアップやサー
ビスを支援するイノベーションセンターも併設したサービス拠点をテキサス州に設置するなど、北⽶にも活動領域を広げている。
SLM Solutions(ドイツ)
SLM Solutions は、MTT Technologies が分離する形(もう一方は Renishaw が買収)で
2010年10⽉に設⽴された。2016年12月には、ドイツのルベックに69,700 ㎡の⽣産拠点を設⽴している。売上高は2014年3,360万ユーロ、2015年6,610万ユーロ、2016年8,070万ユーロと順調に拡大している。2016年9月に主要ユーザーの1つであったGEから買収提案がなされたが、価格面での折り合いがつかず破談。GEは同社の替わりにConcept Laser社を買収した経緯がある。 同社の製品ラインアップは、メタルプリンタを中心としており、タンデムレーザの SLM 500HL 及び
SLM280HL、クワッドレーザオプションの SLM500HLの3 つのモデルに分けられる。オープンシステムアーキテクチャを採っており、いずれのシステムでも多種のメタルパウダーに対応。さらに、クローズドループパウダーマネージメントやメルトプールのリアルタイムモニタリングも備わっている。 2016 年前半、SLM Solutions は SLM500HL のオプションを変更。400W×2、700W×2、
400W×2+1,000W×2、400W×4、700W×4 のバリエーションとなった。レーザは独⽴もしくは協調
305
での動作が可能で、例えば、400W レーザはレイヤ層のスキャニング、1,000W レーザは溶融結合に用いるといった使い方もできる。これにより、レーザベースのパウダベッドシステムの中では最⾼速度を誇る(105 cm3/h)としている。 このほか、周辺機器として⾦属粉末の⾃動ふるいステーション(PSA500)もラインナップ、スループットの向上を図っている。
SLM Solutionsの代表モデルSLM 500HL
出所:SLM Solutions
306
Concept Laser(ドイツ)
同社は2000年に設⽴された。同社のレーザ溶融システム「Laser CUSING」は、ファイバレーザにより⾦属粉末を溶解する技術で、多様な⾦属を使い3Dの部品を⽣産することができる。医療分野では、イタリアの医療機器メーカであるTsunami Medicalの脊椎関連製品の開発に関与している。2016年時点では、欧州のメタルベースAM市場シェア21.5%を占める。(Wohlers Report, 2017年) 2016 年12月、GEがConcept Laserの株式75%を買収したことで、現在は同時期に買収されたスウェーデン Arcam を含め、GE Additive ビジネスユニットの一部となっている。2017 年 3 月、GE AdditiveはConcept Laserの本社拡張におよそ1億ドルを投資するとともに、2018年にも350〜400人体制(買収前は200名)とすることを発表している。 また、GEは、⾦属積層造形に特化したマーケティング拠点を世界各地に開設する予定で、2017年4月にはその第 1 号をドイツのミュンヘンに設けると発表した。この新施設は、GE の既存の研究センターの隣に約 1000万ドル(約 11億3000万円)かけて建設され、Concept Laser製と Arcam製の⾦属3Dプリンタを最大10台導入する計画である。 2016年11月、Concept LaserはM Line Factory と名付けた新しい製品ラインを発表している。2018 年秋リリースのこの製品ラインは、“⾃動化された⼯場”に向けた新アーキテクチャを採用、プリンティング及びプロセッシング工程をそれぞれモジュールとして展開する。プリンティング工程を担う M Line Factory PRD Systemは最⼤造形領域:400×400×425mmで、400W/1000Wのレーザを1〜4つ搭載できる。⼀⽅、M Line Factory PGGはプロセスモジュールで、アンパック等のポストプロセッシングを担うシステムとなる。プロセスをモジュールに分けることで、各工程をシステムで分担し、製造工程全体の生産性を高める狙いがある。 Concept Laser はこのモジュール・アーキテクチャに向けたプロセスモニタリング用ソフトウェア(CL WRX3.0)を発表しているほか、2016年11月にはFA/ 搬送系に強いKUKAグループのSwisslogと戦略的パートナーシップを発表、粉末や部品の搬送システムを共同で開発する⽅針を明らかにしている。
307
Concept Laser M LINE FACTORY
出所:Concept Laser
Renishaw(イギリス)
Renishaw は、1973 年に設⽴された計測器向けプローブメーカーである。EOSINT M270 の使用がきっかけで2010年よりメタルパウダベッド技術の開発に着⼿。2011年にはMTT Technologies を買収し、同技術の事業化に本格的に乗り出した。なお、⾦属3Dプリンタ事業はMetrology Divisionに所属するAdditive Manufacturing Products Division(AMPD)が担当している。 Renishaw は造形物内部のストレスと歪みを減らすために、レーザエネルギーの制御と供給の仕方を
管理するユニークなスキャニング/プロセシング戦略を採⽤している。同社独自のポリマーベースリコーターも精密造形に寄与している。競合他社の多くはラージサイズのメタル 3D プリンティングに注⼒しているが、Renishawは精度により重点を置いている。
308
2015年5月、AMPDはMTT Technologies生産拠点のあった英Stoneに設置した大型施設に拠点を移転。同施設内には30以上の装置があり、システム及びアプリケーションのR&Dを⾏っている。同社はユーザーとの密接な関係構築をR&Dサイクルの中心に据えており、その強化策として世界各地にAMラボを設置し、ネットワーキング化する計画を有している。実際、2016年6月には、アメリカ、イギリス、カナダ、ドイツ、中国に続き、インドにも研究センター・販売代理店を設⽴している。 Renishawの代表モデルは、RenAMシリーズ(RenAM250 M, RenAM400 M, RenAM500 M)
である。RenAM250M 及び RenAM400M は造形領域:250×250×300mm、レーザはそれぞれ200W、400Wのものを搭載している。これらは複数の材料を造形できる。⼀⽅、上位モデルのRenAM 500M は造形領域:250×250×350mm、レーザ:500W。こちらは1つの材料を⽤いた造形に特化しており、自動のマテリアルハンドリング機能を備える。RenAM500Mの価格は約65万ドルである。
Renishawの代表モデルRenAM 500M
出所:Renishaw
309
Arcam(スウェーデン)
1997年に設⽴されたArcamは、スウェーデンChalmers University of Technology との共同
研究を基に、電⼦ビームにより⾦属を溶融させるEBM技術(Electron beam melting)を導入した⾦属3Dプリンタを開発。2002年に初号機EBM S12を市場投入した。 その後、2007年には医療⽤インプラント製造メーカである伊Adler Ortho GroupがArcam装置
を用い製造したインプラント(Fixa Ti-Por)を開発、CE認証を得るなど、同社⾦属3Dプリンタの量産部品への適⽤が本格化した。その年には航空機産業向けの⼤型装置Arcam A2もリリース、この医療機器産業(インプラント)及び航空機産業が同社の注⼒分野として育っていくこととなる。 2016年度の売上⾼はおよそ7,200万米ドル。2016年末にGEが同社の株式の76%を取得した
ことにより、現在はGE Additiveの一員として事業を展開している。 現在の主⼒モデルは、2016年5月に発表したArcam Q10plus及びArcam Q20plus。それぞ
れインプラント、航空機部品をターゲットとしたもので、従来モデルと比較し 15%の生産性アップに加え、形状精度、表⾯粗さも向上しているという。また、Arcam は X 線検出器等を用い自動で電子ビームの制御及びキャリブレーションを⾏うことのできるxQam Technologyも導入している。 EBM技術は様々な材料を扱うことができるが、特にTi合⾦及びコバルト・クロム合⾦をメインターゲット
としている。Arcam は2016 年、カナダ Montreal に⾦属粉末⼯場を建設、Ti 合⾦等の⾦属粉末の供給能⼒を拡⼤したほか、ドイツにセールスオフィスを設置している。
310
③中国
Farsoon
Farsoon は、DTM、3D System で⻑年レーザ焼結技術に従事していた Xu Xiaoshu 氏により
2009年に設⽴された。熱可塑性粉末およびレジンコートサンド用に8つのモデルラインアップがあり、主⼒とする 402 シリーズでは 30、60、100W の CO2レーザを搭載した3つのモデルを用意している。2016年11月には生産性を向上させた403Pを発表している。 ⾦属3Dプリンタは、パウダベッド方式のFS121M及びFS271Mを2017年1月より投入している。
造形領域は275×275×320mm、レーザは500Wのyb ファイバレーザを搭載している。 同社は樹脂粉末、レジンコートサンドをメインとするパウダービジネスも展開しており、2015年11月に
は独 BASF 及び Laser-Sinter-Service(LSS)と提携している。なお、Farsoon は 2016 年 11月、LSSの事業の⼤部分を取得、以降LSSは欧州におけるFarsoonのディストリビュータ、R&D拠点として役割を果たしている。 2016年9月には、重慶市とのジョイントベンチャーである「Chongqing Additive Manufacturing
Center」がオープンした。同センターは現時点で中国最大の 3D プリンタのアプリケーションセンターとなっている。また、同年12⽉にはアメリカに⼦会社を設⽴すると発表している。
Farsoon社の代表モデル403 P
出所:Farsoon
311
Beijing Long Yuan
同社は1994年に設⽴、1996年には最初のシステムであるAFS300 の販売を開始した。現在はパウダベッド方式を採用したシステムとして、ポリマー用(3 種)、サンド用(3 種)のほか、⾦属⽤としてAFS-M180 及び AFS-M260 を展開している。また、デポジション方式の AFS-D600、AFS-D800Vもラインナップしている。
Bright Laser Technologies
Bright Laser Technologies(BLT)は、⻄北⼯業⼤学の研究成果を基に2011年に設⽴された。BLTはパウダベッド⽅式及びデポジション⽅式の⾦属3Dプリンタをそれぞれ2つずつラインナップしている。2016年2月時点での従業員数は260名となっている。 BLTは中国航空宇宙産業においてEOSシステムのリセーラーであり、12のEOSシステムを含む、計
42台の⾦属3Dプリンタを保有するサービスビューロでもある。 2016 年 3 月、同社はメディカル、デンタル向けの BLT-S200 を投入している。同システムは 150×
150×200mm の造形領域を持ち、アルミ、チタン、SUS、銅等の⾦属材料に対応している。また、同年9月には同社システムにMaterialise Control Platform Softwareの搭載が発表された。
312
Eplus 3D
EPlus 3DはBeijing Long Yuan出身のTao Fengが中心となり、2014年に設⽴された。3D スキャン装置を手掛けるShining 3Dが出資した。Shining 3DはEPlus 3Dのディストリビュータでもある。同社はパウダベッド方式を採用した 3D プリンタをポリマー用(4 種)、サンド用(3 種)、⾦属⽤(2種)に展開している。
Huake 3D
同社は、華中科技⼤学等の⽀援を基に設⽴。Wuhan Binhu Mechanical & Electrical出身者が多く集まっているとされる。同社はパウダベッド方式を採用した 3D プリンタを幅広く⼿掛けており、⾦属用としてはHK M125及びHK M250を展開している。
313
④韓国
InssTek
InssTekは、3軸もしくは5軸制御のマルチパウダーフィードシステム(laser –aided direct metal tooling, DMT)を搭載したデポジション⽅式の⾦属3Dプリンタを展開している。 300Wレーザを搭載した3 軸モデルの造形領域は200×200×200mmとなっている。500Wレー
ザ搭載のバージョンもある。このほか、デスクトップモデルをラインナップするほか、トップラインとしてMX-Grand(6軸制御、4×1×1m、5kWレーザ)もある。
InssTek MX-Grand
出所:InssTek
314
Sentrol
Sentrol はCNC装置を手掛けるメーカーで、2015年よりパウダベッド⽅式の3D プリンタを展開している。造形領域150×150×100mmから600 ×400×400mm までのモデルをラインナップ。2015年時点では韓国に販売先が限られていたが、2016年より海外にも販路を拡⼤している。 同社は⾦属積層造形と CNC ミリングを複合化したハイブリッド装置の開発にも注⼒しているほか、ラージフォーマットのバインダージェット装置も展開している。
315
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者
及び所属機関
⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の⾦属積層技術に関する代表的な研究機関及び研究者は以下の通り。各国それぞれのソースから抽出している点に留意が必要である。 ①米国
アメリカの主な研究機関及び研究者
出所:FederalReporters、3dprintingindustry.com より矢野経済研究所作成
アメリカの製造イノベーション機構の設置状況
出所:矢野経済研究所作成
名称 分野 主導官庁 発表時期 設⽴場所
American Makes 3Dプリンティング 国防総省 2012年8⽉ オハイオ州ヤングスタウン
Power America パワーエレクトロニクス エネルギー省 2014年1⽉ノースカロライナ州ローリーLIFT
(Lightweight Innovations forTomorrow)
軽量⾦属材料 国防総省 2014年2⽉ ミシガン州デトロイト
DMDII(Digital Manufacturing & Design
Innovation Institute)デジタル製造・設計 国防総省 2014年2⽉ イリノイ州
シカゴ
IACMI(Institute for AdvancedComposites Manufacturing
Innovation)
先進複合材料製造 エネルギー省 2015年2⽉ テネシー州ノックスビル
319
③中国
出所:各種リリース等より矢野経済研究所作成
④韓国
韓国の主な研究機関及び研究者
出所:Naver学術情報検索より⽮野経済研究所作成 ⑤台湾
台湾の主な研究機関及び研究者
出所:ITRI及び3Dprint.com より矢野経済研究所作成
321
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
3D プリンタに関する国家プロジェクトとして、2014 年より「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム」が実施されている。また、その実施者として、技術研究組合次世代 3D 積層造形技術総合開発機構(Technology Research Association for Future Additive Manufacturing;以下TRAFAM)が2014年4⽉に設⽴された。 組合設⽴の⽬的は「我が国のものづくり産業がグローバル市場において持続的かつ発展的な競争⼒
を維持するために、少量多品種で⾼付加価値の製品・部品の製造に適した三次元積層造形技術や⾦属等の粉体材料の多様化・⾼機能複合化等の技術開発、鋳造技術の開発等を⾏う」というものである。
「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム」 プロジェクト概要
*内容は2016年3月の中間評価検討会時点のもの
出所:経済産業省 第1回「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム(次世代型産業用3Dプリンタ等技術開発)」 研究開発プロジェクト 中間評価検討会 資料
322
技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構の組織体制
出所:経済産業省 第1回「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム(次世代型産業用3Dプリンタ等技術開発)」 研究開発プロジェクト 中間評価検討会 資料
事業内容は、次世代型産業用 3D プリンタ技術開発と超精密三次元造形システム技術開発という
二つのプロジェクトに大きく分類される。 次世代型産業用3Dプリンタ技術開発においては世界最⾼⽔準の造形速度、造形精度を有する電
子ビーム方式及びレーザビーム⽅式の⾦属積層造形装置と⾦属粉末、制御ソフトウェアについて、それぞれの技術を持つ企業が連携する三位一体の開発が進められている。また、超精密三次元造形システム技術開発では鋳型⽤砂材料を⾼速で積層造形する三次元砂型積層造形装置と、材料(⼈⼯砂・バインダ)の開発及び性能評価を一体的に実施している。 これらのプロジェクトを推進していくため、TRAFAM では上図のように大学・研究機関や装置メーカーだ
けではなく、材料メーカーやユーザーが多数参画した「オールジャパン」の体制を敷いている。なお、2016年 12⽉より⾦型⽤ CAD/CAM システム、⽣産管理システム等の開発、販売、サポートを⾏っているC&GシステムズがTRAFAMに新たに参画した。
TRAFAM の技術開発終了時点の⽬標・指標は以下の表のとおり。次世代型産業⽤ 3D プリンタ技
術開発プロジェクトにおいては平成25年時点での既存の海外装置に⽐べ造形速度10倍、造形品の精度5倍(レーザービーム方式)、最大造形サイズ3倍、装置本体販売価格は半分と戦略的な数値を掲げた。プロジェクト開始から2年間の技術評価(中間評価)においては、いずれの技術開発項⽬も概ね計画通りに目標を達成。2019年の当該装置の実⽤化に向け技術開発を加速させている。
323
2016年12月にはTRAFAMのメンバーである東芝、東芝機械、産総研が共同開発した開発試作機及び三菱重⼯の開発試作機を公開している。両機ともにレーザデポジション(LMD)方式を採用、早期の製品化を目指すことを明らかにしている。また、⾦属3Dプリンタ以外に、鋳物⽤砂材料を⾼速で積層する3次元砂型積層造形装置の開発も進めており、2018年はじめの販売が予定されている。 経済産業省では、これらの成果を踏まえ、「三次元造形技術を核としたものづくり⾰命プログラム」の取
り組み内容をアップデート。2017 年度(予算額 3.5 億円/7.5 億円)は三次元積層造形技術の基盤整備として、①溶融凝固プロセス等の機構解明、②積層造形データベース開発、③要求凝固シミュレーション技術開発、④基盤となる造形物試作・評価を盛り込んでいる。また、鋼材の材料性能に起因する機械要素部品(⻭⾞等)の損傷を未然に回避し、機械製品の信頼性向上を図ることを⽬的に、効率的かつ⾼精度な、新たな鋼材評価技術の開発等を加えている。 さらに、2018年度(予算額3.3億円/3.5億円)では、開発中の3Dプリンタで造形した試験片に
ついて、国際認証取得済みの試験機関で疲労試験等を実施、そのデータを積層造形データベースに蓄積する仕組みを追加している。 また、次世代型産業用3Dプリンタ技術開発プロジェクトでは、⾦属粉末への要求特性を以下の図の
ように整理している。重要な要求特性として流動性が挙げられており、粒度分布と粉末形状、表⾯処理状態がこれに影響するとしている。そして、多様な要求特性に対応するための製造技術として粉末化技術、分級技術、修飾技術の開発を進めている。
技術開発終了時点の⽬標・指標
出所:TRAFAM 第2回シンポジウム講演集を基に矢野経済研究所作成
電子ビーム方式 レーザービーム方式
積層造形速度 10万cc/h 以上
造形物の精度 ±50µm 以下 ±20µm 以下 -
最大造形サイズ
装置本体の販売価格 2,000万円以下5,000万円以下
1,000×1,000×600mm 以上
次世代型産業用3Dプリンタ技術開発 超精密三次元造形システム技術開発
500cc/h 以上
324
3Dプリンタ⽤⾦属粉末への要求性能
出所:経済産業省 第1回「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム (次世代型産業用3Dプリンタ等技術開発)」 研究開発プロジェクト 中間評価検討会 資料
開発対象の⾦属は⾦属積層造形技術で先⾏する海外において広く使⽤されている鉄系
(SUS316L、SUS304、S30C)、銅系(純 Cu、銅合⾦)、ニッケル系(インコネル 718)、チタン系(Ti6Al4V)、アルミ系(AI-10Si-0.4Mg)である。個別要素技術の開発内容とアウトプット指標・目標値を以下に示す。 ①新アトマイズ法による高融点・高活性⾦属粉末製造技術の開発 ⽔冷銅るつぼを活⽤した⾼周波誘導加熱による、浮遊溶解とアルゴンガス噴射を組み合わせた装置の開発、及び⾦属粉末の微細化に向けた粒径の予測技術と可視化技術の活⽤による噴霧減少の数値化に取り組んでいる。 ②気体流による遠⼼分離式⾦属粉末分級機構の開発 微粉化により凝集した⾦属粉末を精度よく分級するため、空気流による粉砕・分離と分級を同時の⾏う二段式分級技術・装置の開発を進めている。 ③高機能粉末製造のための粉末装飾技術の開発 アトマイズノズルの開発や操業条件の適正化により銅系粉末の収率の向上を図るほか、流動性やリサイクル性などの向上を⽬的に⾦属粉末表⾯の装飾⽅法の開発、装飾材料の選定などを推し進めている。 ④アルミ合⾦粉末の製造技術開発 アルミ合⾦粉末に対する要求特性の明確化を図りながら、粒度分布の最適化などによってレーザビーム、電⼦ビーム両⽅式の積層造形で得られる造形品の相対密度向上に取り組んでいる。
325
個別要素技術のアウトプット指標・目標値
出所:経済産業省 第1回「三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム(次世代型産業用3Dプリンタ等 技術開発)」研究開発プロジェクト 中間評価検討会を基に矢野経済研究所作成
番号 開発担当企業 項目 最終目標 開発金属
噴霧現象の数値化 -
チタン合金粉末試作 チタン合金粉末粒径45µm以下
分級精度粉末粒径45µm以下とした場合の累積95%での粒度40µm以下
分級精度粉末粒径125~45µmとした場合、累積5%での粒度50µm以上、累積95%での粒度120µm以下
分級歩留篩分級での歩留に対して遠心分離式粉体分級機構法にて20%以上向上
銅系金属粉末製造技術開発 (ガスアトマイズ銅粉対象)
・粉末粒径45µm以下の収率:75%以上・粉末粒径105/45µmの中間粒度収率:30%以上
金属粉末修飾技術開発(ガスアトマイズ銅粉:45µm以下対象)
・粉末流動度:30秒/50g以下・酸化増加率:5%/20日以下
④東洋アルミニウム(株)
アルミニウム合金粉末の製造技術開発
レーザービーム/電子ビーム積層造形で密度99%以上を達成できるアルミニウム合金粉末
アルミニウム合金
山陽特殊製鋼(株)
②
鉄鋼材、耐熱鋼、ステンレス鋼、Ni基超合金(インコネル、ハステロイ)、Co-Cr合金
銅、銅合金福田金属箔粉工業(株)
③
①チタン合金、チタンアルミ合金
大同特殊鋼(株)
326
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
Pittsburgh(ペンシルバニア州)のAdditive Technology Centerに3年間で3,900万米ドルを投じるGE のように、⾃社の資本⼒を活かし AM技術のR&D を加速化させる取り組みも⼀部では⾒られる。2016年7月、ノルウェーの Norsk Titaniumは米Plattsburgh(ニューヨーク州)にある工場の拡張(主にはカスタマーベースの強化)にニューヨーク州政府の支援(2,500 万米ドル規模)を受けている。これはNorsk Titaniumが今後10年で同⼯場に対し10億⽶ドル規模の投資を⾏っていく計画の一部として、初期段階のリスクを州政府と分担するスキームである。 また、2017年2月、スイスOerlikonは2016年11月、5,000万米ドルを投じて米ミシガンにAM
向けメタルパウダーの製造工場を建設することを発表したが、2017 年 2 月にはドイツ及びロシアの大学機関とリサーチ・パートナーシップを締結、設計⾃由度や軽量化といった AM の技術領域にフォーカスした先進研究開発を共同で⾏っていくほか、⽶ノースカロライナに6,300万米ドルを投資し、製造ハブ拠点を設置する計画を明らかにしている。 このように、AM 技術の研究開発は世界規模での競争が加速化。企業の設備投資、研究開発投資
の額も数⼗億円規模の資⾦が動くようになりつつある。このため、各国政府・組織は⾃国の競争⼒を⾼める狙いから様々なプロジェクト、プログラムを通じ資⾦を注入している。
①米国 オバマ⼤統領は2011年6月24日、中国などの新興国にオフショアリングが進んだことで工場だけで
なく、R&D も国外に流出する可能性があるという危機感のもと、⽶国内への製造業回帰を重視する「先進製造パートナーシップ (Advanced Manufacturing Partnership:以下「AMP」)」を⽴ち上げた。 AMP は製造業に⼤きな影響をもたらす先進技術やその開発、インフラ整備、労働⼒の開発などの⾯
において官⺠連携を推奨している。その⽬的は、⽶国内で質の⾼い雇⽤を創出し、⽶国の国際競争⼒を高める新しい技術を特定することにある。そのため、政府は製造工程に焦点をあてた先端製造研究開発に22億ドル(約2,500億円)を投資している。
327
表 先進製造パートナーシップにおける4 つの重点領域 ①安全保障に係わる重要製品の国内製造(予算3億ドル)
国家安全に重要な国内製造能⼒を活性化する⾰新的技術
②先端材料の開発と普及にかかる時間の短縮(予算1億ドル) ⽶国企業による先端材料の発⾒・開発・製造と普及速度の倍増をめざし、研究・トレーニング・インフラに投資
③次世代ロボティクス(予算7,000万ドル) 次世代ロボット研究
④製造過程におけるエネルギー使⽤効率の向上(予算1.2億ドル) 企業の製造コストとエネルギー消費量の削減につながる⾰新的な製造プロセスと材料の開発
出所:独⽴⾏政法⼈科学技術振興機構 研究開発戦略センター 海外動向ユニット「米国:先進製造技術の研究開発動向」 また、AMP 同様、先端製造技術の研究開発強化施策のために設⽴されたのが、製造イノベーション
機構(IMIs)である。IMIs には 5 つの拠点があるが、そのひとつが 3D プリンタの研究開発拠点America Makesである(2012年8⽉設⽴)。America Makesには国防総省が協⼒し、設⽴当初は政府及び⺠間から合計8,900万ドル(約100億円)の投資を受けている。同じく国防総省が協⼒する研究開発拠点のひとつにデジタル設計、製造の研究開発拠点である DMDII がある(2014 年2⽉設⽴)。当該拠点では、サイバーセキュリティやスマート⼯場の可視化、サイバーフィジカル製造などが研究対象となっており、GE やボーイング、マイクロソフトなどが関わりながら、これらの技術の商業化を目指している。 America Makesはデザイン、材料、技術、労働⼒における連携促進により、AM技術における米国
の競争⼒を強化する組織である。現時点では、118 以上の企業や大学、研究機関、官庁などが広範なネットワークを形成している。その使命は、AM技術を発展させ、国家の製造セクターへの移転を加速し、⽶国製造業の競争⼒を⾼めることである。 中⼩企業や初期段階にある企業(スタートアップ)に焦点を当て、⽶国企業と既存の公的機関、⺠
間企業、⾮営利団体の産業経済的な開発リソースやビジネスインキュベーターをつないでまとめることが含まれていることも特徴的だ。この組織の所管官庁は国防総省であるとおり、航空⽤などのより実⽤的な部材開発が⾏われており、⼈材育成を⽬標として、学校などに積層製造装置を導⼊し、早くからその装置や製造方法に親しむことを推奨している。 同組織は、約1,100万ドルの資⾦を投⼊し、2016年3⽉から、Phase 1〜3の段階に分けて公
募テーマ(Project Call)を募った。当初は開発案件29件を採択し、現時点では、42件が進⾏中である。2018年からはPhase3の段階に移⾏する予定であり、さらに570万ドルの資⾦を投⼊し、公募テーマを募っている。Phase3 の開発案件は、2018 年 2⽉以降に公表される予定である。なお、⾦属関係での検討としては、⾦属粉末造形時のゆがみ予測と補正⽅法の研究、⾦属造形時の許容誤差と表⾯仕上げの⾃動終了の研究、⾦属積層造形⽤の新しい超低コスト粉の開発、⽶国の鋳物産業における積層造形テクノロジーの加速などが盛り込まれる⾒込みである。
328
主なAmerica Makesの採択案件
出所:2014 iNEMI Research Series
Project Call #1 Project Call #2 Project Call #3
レーザ/電子ビームによる造形プロセス等の解明。
航空機部品のAM量産に向けた品質保証技術の開発。
⾦属粉末のパウダーベッド⽅式において、変形を抑制するための機能などを有するサポート構造の設計検討を系統的
に実施。レーザ/電子ビームによる造形プロセスのモニタリング及び制御のための熱イメージ
ング技術の開発。
AM構造デザインを最適化するソフトウェアの開発。
パウダーベッドAMのオープンアーキテクチャーの清gy6尾システムの開発・実証。
低廉、⾼温対応の樹脂を材料とした、レーザービームによる造形プロセスの開発。航空宇宙分野や交通分野の部品、医療や商業向けを想定。(TRAFAM含まず)
造形に際しての物理ベースの熱歪予測と軽減するツールの評価・確認を実施。目標は、それらを利⽤した開発期間の⼤幅
削減。
多種のAM製造性要求の設計支援と新トポロジー最適化能⼒を持った統合設
計パッケージの開発。
329
②欧州 欧州委員会の取り組み 欧州の研究・改革活動は1984年以来、「欧州研究開発フレームワーク計画」として実施されている。その 7次計画となる、第7次研究開発フレームワーク計画「FP7」(2007年〜2013年)及び、その継続フレームワークプログラム「HORIZON2020」において、AM(Additive Manufacturing)に関する研究プロジェクトが存在する。FP7においては、60件以上のプロジェクトに2.25億€の予算が投入され、そのうち⾦属関連プロジェクトは全体の 11.3%を占める。なお、HORIZON2020 の枠組みの中では、2014年から2016年の間、20件以上のプロジェクトに、9,500万€の予算が投入されている。
EUのAM技術開発ロードマップ
出所:European Commission(2014)
330
欧州委員会の主な研究開発プロジェクト
出所:EU Cordisより矢野経済研究所作成
AMプラットフォーム AM プラットフォームは、製造関連分野の欧州テクノロジープラットフォーム(ETPs)の一部である「ManuFuture」から派生したもので、AM 分野のワークショップや会合などのイベント情報や記事・プレゼン資料の掲載など情報交換の場となっている。 欧州では、AM の分野で多くの企業・組織が事業や研究を⾏っているが、中核的な組織や場が無いこ
とから、一貫した AM の戦略や AM に対する理解、AM の普及に貢献することを目指している。欧州各国の研究機関・大学、コンサルティング会社、シーメンスやヘガネスなどがメンバーとなっている。なお、2014年2月にはAMの今後と発展に向けた優先課題を⽰した「戦略研究計画(SRA)」を発表し、⽣産性、材料、プロセスと安定性、品質、環境面、規格と認証、訓練・教育について提言している。
欧州工作機械工業連盟(CECIMO)の活動 CECIMO は、2014 年 6⽉の年次総会において、AM を協議し、同年 9 月には AM 作業部会を
設置した。同年11月下旬に作業部会の初回会合が開かれている。以下にその内容をまとめる。
CECIMOを⾦属3Dプリンティング分野の中心的位置づけとしてEU 政策⽴案者に明確にする。 ⾦属3Dプリンティングを工作機械業界のイメージ向上に活用し、鍵となる実現技術(KETs)としての役割を強調する。 ⼯作機械業界の⾦属AMの最新動向に対する認知を高める。 ⾦属 AM バリューチェーン関係者、欧州の政府機関、学会、研究コミュニティ、標準化機関と野協⼒関係を確⽴し、⾦属AM 分野で明確な主要パートナーとなる。
出所:JETRO(2015年4月)
セラミック複合材料hについて、AMの新アプローチを開発する。
高複雑形状のセラミック部品製造に向けたAM 装置を開発する。
次世代3D⾦属パーツ製造のレーザでポジション(2000cc/h)とアブレーションのハイブリッド装置を開発する。
フォトポリマーベースの材料を処理するための統合リソグラフィベースのAMシステム開発。
AMプロセスのパラメータの関数として、機械特性を予測する、フルセットのソフトウェアを開発する。
航空機部品の補修に関する研究。
航空宇宙、⾃動⾞、原発向けに、最⼤2mサイズの無⽋陥の⾦属AMパーツを政策。合わせて、品質保証、標準化等をカバー。工程ステップを減らし、従来より50%コストダウンを目指す。
ハイテクなメタル製品:AMとSM(AMの反対の技法)が並⾏できるハイブリッドマシーンの開発。
傾斜機能コーディングのためのレーザービーム/でポジション方式によるAM技術を用いた産業向け製造システムを開発・実証する。
AM分野での標準化組織の設⽴と⽀援を通してヨーロッパ標準化を統合・調整し、AM技術を推進する。
高生産性電子ビームによるAm装置のための⾼出⼒電⼦銃開発やパウダーベッド関連⾼出⼒電⼦銃利⽤の実証。
ロボットアーム/ジョイント、照明器具などに応用できるPolyJet技術による3Dマルチマテリアル印刷⽤の新しいインク材料の開発。
⾼精度医療インプラント製造の電⼦ビーム方式のAM技術の共同研究。具体的には、⾼精度電⼦銃設計技術、⾼密度粉体AMの技術開発。
⺠間航空機エンジン部品への付加積層の適用研究(設計、パウダーリサイクル、インプロセス非破壊検査等)。空輸に係わる環境への影響を低減させる。
カスタム部品や⼩ロットの部品を効率よく製造するプロセス(粉末をレーザー溶融する)を開発。
航空機、宇宙、モビリティ、機器分野の構造部品の品質向上のために特別に調整されたTiベースのナノアディティブ材料を開発、加⼯時材料の40%〜50%をセーブする。 同時に材料とプロセスの資格/認証をするためのプロトコルも開発。
331
ドイツ機械工業連盟(VDMA)の活動 ドイツは欧州の中でもAM分野に先⾏している。2012年の世界の⾦属AMシステム販売台数は190台で、うちドイツ企業がシェア7割を占めている。こういった状況から、VDMA内には、国内のAM関連企業を促進するため、VDMA付加製造協会が設けられている。当協会は、工業分野の3D プリンティングに焦点を当てており、関連分野の企業や研究機関の約 60 組織がメンバーとなり情報の交換や普及が⾏われている。 主な研究機関としては、ドイツのPaderborn大学に拠点を置く研究所である「DMRC」を挙げられる。先進AM技術研究機関であるDMRC、ノルトライン・ヴェストファーレン州は、2百万€以上の共同投資と、政府資⾦340万€、企業投資などを合わせた総額 1100 万を€を 5 年間の研究プロジェクトに投⼊している。⼀⽅、⾦属粉末の粉末床溶融結合技術の研究に関しては、フラウンホーファー研究所が中⼼となって研究を⾏っている。 イギリス イギリスでは、産業技術イノベーションの拠点として、2010年9月に「カタバルトセンター」を設置、拠点
形成事業としてのプログラム「カタバルトプログラム」を発表した。同プログラムでは、分野によって 11 箇所のセンターを設⽴しており、AM技術開発に関しては、2011年にMTC(Manufacturing Technology Center)が設⽴された。MTCでは、積層製造で重要な要素である、クラックや破壊防止技術に関しての研究が盛んに⾏われている。 なお、2014年のECの報告書によると、英国は、多くの業界セクターでAMに⼤規模の投資が⾏わ
れている。内訳としては、消費者団体から約250万ポンド、 ⾃動⾞業界から650万ポンド、 メディカル業界から300万ポンド、英国航空宇宙産業から1,300万ポンドの投資⾦が供与されている。 ベルギー ベルギーのフランダース地方政府は、AMの素材関連プログラム「STREAM」に投資している。このプロ
グラムには、大学、研究機関、業界団体などが参加しており、2014年からポリマーレーザー焼結およびセレクティブレーザ溶融技術の開発を目標とする3 つのプロジェクトを開始している。 フランス フランスのRapid Prototyping協会は、国家レベルでも国際レベルでもAM技術の標準化に大きく寄与している団体である。 2013年に新たな提案書が発⾏され、 2013年にメーカ向けの実験スペースや、新技術とアプリケーション開発目的のプロジェクトを企画している。 オランダ オランダでは、製品開発プロセスがAMの本質的部分とされており、オランダの研究機関であるTNOは、 多数の主要企業パートナーとの提携を通して、次世代AM技術開発に努めている。
332
ポーランド ポーランドは、2013年からAMに対する意識を⾼め、数多くの講義とワークショップを設け、独自の技
術開発のためのプロジェクトである「Lidar project」に、30万ドルの資⾦を投資している。 ポルトガル Leiria工科大学の研究所である「CDRSP」は、EUでも優秀な研究機関であり、国際的な AMカンファランスに焦点を当てている。 多くの研究プロジェクトは、科学技術財団と産業イノベーション機関の資⾦支援を受けている。CDRSPは、コインブラ大学とCENTIMFE と共同で、ポルトガルAM イニシアチブ「PAMI」を⽴ち上げており、PAMIは今後ポルトガルの研究インフラロードマップの一部として活動すると発表している(2015)。 スペイン パーソナル3D プリンタ開発のためのイニシアチブが多く⽴ち上げられる中、スペインの製造協会は、AM
に関するイニシアチブグループである「AEI-DIRECTMAN」を⽴ち上げている。(2015)その他には、⺠間の研究センターとして、Ascamm テクノロジーセンター、⾦属加⼯技術研究所AIMME、技術センターAITIIP、PRODINTECなどがある。 デンマーク デンマークの技術研究所、ポンプメーカーである Grundfos と Danfoss は、 「AM-Line 4.0」という
AM関連プロジェクトに推定1,460万ドルを寄付している。(2018年1月時点)
333
③中国 2013年4月、科学技術部は「国家ハイテク研究発展計画(863計画)」に、積層製造(3Dプリント)
技術に対する支援政策を策定した。積層製造のコア技術と製造装置研究・開発を目標とし、具体的には、航空宇宙分野や⾦型業界からのニーズに応じて、積層製造技術の課題を突破し、製造装置を研究開発。関連する領域に⽤途を展開し、産業化を後押しするものである。研究内容としては、航空宇宙用大型部品のレーザ溶解成型技術の研究及び応⽤、⾦型製造に向けの⼤レーザ焼結成形装備の研究開発及び応⽤、材料開発や応⼒緩和などの処理設備の開発などがある。 これらの成果を基にいくつかの企業が 3D プリンタ事業を⽴ち上げ、市場参⼊を果たしているが、2017年12月、中国工業情報化部(工信部)など政府12部門は共同で、付加製造(積層造形)産業の持続可能な発展をさらに後押しし、製造業発展の新たな原動⼒育成を加速するために「付加製造産業発展⾏動計画(2017-2020年)」を策定している。 「⾏動計画」によると、2020 年までに中国は、付加製造産業の年間売上⾼ 200 億元超、年平均
成⻑率 30%以上を⽬指す。⼯信部の責任者は、「⾏動計画」に基づいて業界の普及・応⽤を進め、2020年までに試験モデルプロジェクト 100件以上、重点製造業10分野での付加製造モデル応用を進める方針を示した。特に「3Dプリンタ+医療」、「3Dプリンタ+文化創造」、「3Dプリンタ+インターネット」のモデル応⽤を進め、イノベーション能⼒を⼤きく伸ばし、特⾊あるモデル企業と産業集積区の育成を急ぐとしている。 また、工信部は 2017 年 11 月に発表した「ハイエンド・スマート再製造⾏動計画(2018-2020
年)」においても、向こう 3 年に亘り、中国政府は医用画像機器、重機、石油ガス生産設備など重要分野のほか、3D プリンタ(付加製造技術)、特殊材料、スマート加⼯、⾮破壊検査などグリーンな基礎的汎用技術の再製造分野への応用に注目し、再製造産業の発展を促す考えを示している。 「計画」の発展目標によると、2020 年までに、中国はハイエンド・スマート再製造産業発展のネックと
なる解体、検査測定、成型加工など重要汎用技術でブレークスルーを遂げ、3D測定・成形などの技術で世界先端レベルを目指すとしている。 また、これら⾏動計画を後押しする取り組みとして、科技部は 2017 年 10 月、「付加製造&レーザ
積層造形重点専門プロジェクト2018年度申請指南」を発表している。この中で、合計7億元を投じ、付加製造プロジェクト21件、レーザ積層造形プロジェクト9件を支援することを明らかにした。
334
④韓国 韓国の3Dプリンタ関連企業は、2016年6月時点で約190社あり、2014年度の国内3Dプリン
ティング産業の総売上高は、約156億円規模である。韓国政府は、2020年までに世界の3Dプリンタ産業をリードする企業を5 つ以上育成するという目標を掲げており、2015年〜2017年の3年間、関連事業に 26 億円の予算を執⾏すると発表した。産業資源通商部は、その⼀環として「2015 年度装備連携型3Dプリンティング素材技術開発事業」を企画し、その傘下に6つのプロジェクトが現在進⾏中である。⼀次プロジェクトが終了したプロジェクトに関しては、2次プロジェクトに繋げており、2018年からも継続事業が発生している。 一方、蔚山市はスマート製造 3D プリンティングハブ都市基盤造成のため、計 21.8億円を投資し、
3D プリンティング需要連携型製造革新技術支援事業など 11個の事業を推進すると発表した。今後、蔚山所在のテクノ産業団地に「次世代造船・エネルギー部品 3D プリンティング製造工程研究センター」を設⽴する予定であり、2018年度には6億4千万円の予算を3Dプリンティング関連創業に振り向けるほか、新規雇⽤創出のための「知識産業センター設⽴」に7億6千万円の予算を執⾏する計画である。
韓国の現在進⾏中のプロジェクト概要
出所:産業通商資源部
表⾯精密度7㎛級大型部品直接製作用プラント型
⾦属3Dプリンタ開発
発電部品製作⽤3D⾦属ハイブリットプリンティングシステム
技術開発
個⼈カスタム型⻭科補形物製作用3Dプリンティング装備及び
適合素材の開発
⾼効率知能型⾦型政策のためのメタル基盤3Dプリンティング素材
及び装備の開発
3次元構造体一体型3D電⼦回路プリンティング装備
及び素材開発
3Dプリンティング装備素材出⼒物の性能及び品質評価体系開発
期間 2015.07〜2020 06 2015年〜2020年 2015年〜2017年 2015年〜2017年 2015年〜2017年 2015年〜2020年
資⾦拠出元
予算⾦額(円) 10億円以内 10億円以内 1 8億円以内 3億円以内 3億円以内 2億円以内
参加機関 Maxrotec及び5社 不明 Hebsiva KETI 不明 KCL
プロジェクト内容
大型部品に積層と後加工を直接政策でき、⾼い積層⾃由度のための5軸並列マシーンと作業空間拡張のためのプラント型⾦属3Dプ
リンタ開発を目標とする
発電部品製作用接合加工精密3Dハイブリットプリンティングシステムの開発、接合加工用3D積層・加⼯経路⽣成及び統合制御SW開発、難形状発電部品製作用3Dプリンティング製作工程最適化技術開発、接合加工3Dハイブリット積層メカニズム分析技術開発、3Dプリンティング発電部品性能向上及び耐久性試験技術
開発
⻭科補形物を出⼒できる⾼精密、高速デジタル3Dプリンティング装置開発、高精密・高速光硬化制御のための自動偏光制御技術開発、⻭科⽤補形物に適⽤可能な機械的、化学的安定性に優れた3Dプリンティング用複合素材開発、デンタル用3Dプリンティング実⾏及び制御、スライシングプロ
グラムの開発
高分子プラスチック部品のHigh-Cycle射出成型と能動冷却制御が可能な⾦型製作⽤メタル基盤3Dプリンティング装備及び普及型
素材開発
3次元構造物の中常用電子部品と導線部を積層し、電⼦回路が内臓された三次元構造物製作のための3Dプリンタに適切な電⼦回路素材及び⼯程技術を開発
する
3Dプリンティング装備及び素材と3Dプリンティングを通して製作した出⼒物に対する性能、品質、安全性、有害性の評価体制構築
産業通商資源部
プロジェクト名
2015年度装備連携型3Dプリンティング素材技術開発事業
335
出所:産業通商資源部
期間 2017.04〜2019.12 2015.09〜2018.08
資⾦拠出元 産業資源通商部 産業資源通商部
予算⾦額(円) 356,792,100 不明
参加機関 ハイビジョンシステム STi(韓国)、Torrecid(スペイン)
プロジェクト内容
⾃動⾞透明部品製作⽤90%透過度素材を含めた3種以上のレジン素材の開発及び多重光学エンジンを使用したコアシェル(Core-Shell)高速積層光重
合型3Dプリンタ装備の開発
セラミック企業であるTorrecidが素材の開発、STiが装備の開発を担当
プロジェクト名 装備連携形3Dプリンティング素材技術開発事業 生活セラミック製品及び産業セラミック基盤3Dプリンタ装備と素材開発
336
⑤台湾 台湾の工業技術研究院(ITRI)は、研究者を含めた職員が約 2 万名、特許は 1 万件以上を有
する組織であり、電⼦情報通信、ナノテクノロジー材料、バイオメディカルテクノロジー、先進製造システム、環境エネルギーなどの分野で研究開発を⾏っている。台湾の経済部などは、レーザ技術を活用した技術クラスターとして「レーザーバレー」の構築を計画しており、その一環として、2012年7月、ITRI南分院に⾦属⽤装置を導⼊し、医療⽤や装飾⽤などへの展開を⽬標に研究開発している。 2015 年 5 月には、ITRI が台湾初の装飾用向けのメタルプリンタを開発したと発表している。また、
2016年9月からは、台湾添加物製造業協会、台湾⾦型⼯業協会、中国⼯業デザイナー協会などの地域開発グループと提携し、技術開発を加速化させていく方針と発表している。
ITRIのメタルプリンタ「The AM100/AM250」
出所:3dprintingindustry.com
337
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
(要素技術)
・熱源
パウダベッド法(レーザ方式)はYb ファイバレーザ、パウダベッド法(電子ビーム方式)はタングステンフィラメント(最近のARCAM Q20ではLaB6を搭載)が主に用いられている。電子ビーム方式では最大3.5kWのレーザが使⽤できるため、レーザ⽅式と⽐べ⾼融点合⾦にも対応可能である。 レーザビームのスキャン速度は 7m/s であるのに対し、電子ビームは8000m/s と極めて高速である。
これは、電子ビームのスキャン方式が電子レンズによる電磁気的なビーム偏向であるのに対し、レーザビームのスキャン方式はガルバノメータミラーの機械的制御により偏向させていることが背景にある。 また、造形雰囲気についても異なる点がある。電⼦ビーム⽅式では⾼真空下で溶融造形を⾏うため
酸化の影響がない。また、ニッケル基合⾦やチタン合⾦などでは、造形物の酸素濃度が使⽤した粉末の酸素濃度よりも低下させる効果が認められており、⾼純度造形が可能になる。実際には造形中にHe ガスをわずかに導⼊するが、これは電⼦ビーム照射による⾦属粉末のチャージアップを防ぐためである。 レーザ⽅式ではアルゴン等の不活性ガスを充満させて造形を⾏うため、電⼦ビーム⽅式のように真空チ
ャンバに必要な耐圧設計が不要であり低剛性のチャンバ設計で⾜りるという利点がある。しかし、最近、レーザ方式においても造形中の酸化を防止する目的で真空タイプの装置が開発されている。また、レーザ方式の最新機種の中には、一旦真空排気を⾏ってからアルゴンガスを導⼊置換し造形する装置が開発されるなど、造形中の酸化防⽌に配慮した⾦属積層造形装置が開発されるようになっている。 このほか、電子ビーム方式では、パウダベッドの溶融プロセスの前にパウダベッドの予備加熱(ホットプロ
セス)が必要である。これは、電子ビームを予備加熱していないパウダベッドに照射すると粉末が霧状に舞い上がる(スモーク)現象が起こり、造形ができなくなるためである。予備加熱温度は⾦属粉末によって異なるが、およそ600〜1100℃の加熱温度が設定される。 これに対し、レーザ⽅式では、予備加熱をせず、室温と同程度の温度でパウダベッドを溶融するコール
ドプロセスを採ることが多い。ただ、この場合、造形物に残留応⼒が堆積しやすく、造形物のそりや曲がりが問題となるケースもある。特に脆性材料の造形時には造形物の変形を抑えるための設計が重要となることが知られている。
338
・インプロセスモニタリング
量産部品への適用時に問題となってくるのが、品質保証である。3Dプリンタメーカーではプロセスインプット(投入エネルギー、フィードストック)、ノイズ、副産物等をインプロセスでモニタリングすることで、品質保証に関するデータの提供を進めているが、副産物の検知は技術的に難易度が⾼く、⼗分にコントロールできていないケースが多いとされる。 また、メルトプールのインプロセスモニタリングは分光計や光学画像、赤外線画像を用いたシステムの導
入が進んできており、センサをレーザビーム軸に搭載し 3 次元位置と同期させたものなどは、より⾼精度な欠陥検出システムとして評価を高めているようだ。ただ、十分な分解能を得るためには、高いデータ取得率(レーザの場合は 10kHz、電子ビームはそれ以上)といった課題があるほか、マシンビジョンを用いた粉末床の状態観察についてもマイクロスケールで解析するには、⾼解像度が必要といった点が指摘されている。既存のセンシング技術、⽋陥検出アルゴリズムでは⼗分でないとの意⾒も根強く、業界では引き続き重要な研究開発対象とインプロセスモニタリングを位置付けている。
340
・⾦属粉末
⾦属積層造形技術の需要分野は航空宇宙、医療、⾃動⾞、産業機械、⾦型、宝飾品など。 最大のボリュームとなっている航空宇宙分野においては、パウダベッド法の導入によって複雑形状部品
の製作が可能、⼀体化(部品点数削減)や軽量化が可能、開発期間の短縮化が可能などの効果があることから採⽤事例は増加傾向にある。材料はCo-Cr-Mo粉末である。
341
医療分野では股関節や膝関節、頭蓋⾻などのインプラントやクラウン、ブリッジなどの⻭科技⼯物向けが中心となる。これらの用途は患者個々の体格や症状等に可能な限り適合化したカスタムメイド化が求められるため、PBF法の特⻑を活かしやすい⽤途といえる。材料はインプラントがTi6Al4V粉末、⻭科技工物はCo-Cr-Mo粉末など。 ⾃動⾞分野ではブレーキデスク向けなどの採⽤例があるが、メインは射出成形やアルミダイカストの⾦
型向けである。PBF 法を適⽤することで⾦型内に複雑な冷却⽔路を形成でき、冷却性能の向上による製品品質やサイクルタイムの改善につながる。材料はマルエージング鋼粉末が多⽤されているようである。 産業分野では熱交換器やガスバーナー、コントロールバルブなどの用途がある。コントロールバルブは、
2015 年 2 月より GE オイル&ガスが刈羽事業所(新潟県刈羽郡)のエネルギー産業用プラントにおいて生産を開始した。導入した装置は松浦機械製作所の「LUMEX Avance-25」。従来の製造方法では困難だった中空構造、曲面形状やメッシュ等、複雑な形状のものづくりが可能となるため、バルブ部品設計の⾃由度が⼤幅に向上。⼀体成形も可能となることから納期の短縮化に大きく貢献した。 この他、海外ではオイル&ガス分野での需要拡⼤が期待されている。油井やガス井は⽬的もエリアも異
なるためプロジェクトごとに掘削設備のカスタマイズが必要となる。そのため、特殊な交換用部品の在庫を確保しておき、必要となった場合には遠隔地に即時納品しなければならない。これを、サービスビューロの活用などにより必要な部品を現地で製造することで、在庫の保管コストや運送コストの削減につながる。既にガスタービンノズルやダウンホールツール⽤ノズルなどで採⽤実績がある。材料は Ti 系合⾦とみられる。
342
宝飾品は従来のロストワックス鋳造が⼀般的であったが、原型の製作などが不要で⽣産効率に優れる
ほか設計の⾃由度も⾼いパウダベッド法に対する認知度が⾼まっている。特に海外で同⽤途向けの需要が拡大傾向にある。 パウダベッド法向け⾦属粉末市場に参⼊している主な海外メーカーは以下の表のとおり。サンプル段階、
あるいは参入を表明したメーカーも含んでいるが、樹脂粉末に比べメーカー数の多さが特徴であろう。
343
⾦属粉末の製法は⽔アトマイズ法、ガスアトマイズ法、プラズマアトマイズ法に区分できる。 ⽔アトマイズ法は製造コストが安価な反⾯、冷却スピードが速く粉末の形状が不規則となる。⼀⽅、
ガスアトマイズ法は⽔アトマイズ法よりも冷却スピードが遅いため、粉化した溶融粒が凝固する間に表⾯張⼒により球状化する。また、ガスアトマイズ法の⼀つに位置付けられるプラズマアトマイズ法は溶解原料が細いワイヤ形状であることから製造スピードが遅いものの、粉末密度が低くなりサテライトの少ない球状の⾦属粉末を得られる。 メーカー各社の製法をみると、Arcam 傘下のAdvanced Powders and Coatings(AP&C)
がプラズマアトマイズ法を採用しており、その他のメーカーのほとんどはガスアトマイズ法である。また、Metalysisは独自開発の製法により、従来比で最大75%価格を抑えたTi粉末を製造するとリリースしている。LPW Technologyは主にサードパーティ品を手掛けるディストリビュータである。
⽇本では⼤阪チタニウムテクノロジーズが、流動性に優れ⾼密度充填が可能なチタン粉末の製造技
術を確⽴したことを 2016 年 7 月に発表した。2008〜2009 年頃に企業・⼤学・研究機関においてPBF法向け材料として球状チタン粉末のサンプル評価等をスタートしており、既に同社のチタン粉末を使⽤した造形品が国内外で⼀部実⽤化されている。需要分野は航空機や医療など。 粉末の製法はIAP(Induction Melting Gas Atomizing Process)法である。IAP法は溶解
原料である丸棒を高周波誘導コイルにより加熱することで溶湯を滴下させ、その溶湯流に⾼圧のアルゴンガスを噴霧して粉末を製造する。坩堝を使⽤しないことから不純物の汚染が極めて少なく、急冷凝固により微細組織を有する球状の粉末を得られる。溶解原料はスポンジチタンを圧縮して棒状としており、
粉末床溶融結合法向け金属粉末 主要海外メーカー
344
原料の連続供給、連続溶解、ガスの噴霧条件の最適化などにより⾼品質・低価格のチタン粉末の量産を可能とした。溶解能⼒は世界でトップクラスの規模となる 150t/年(純チタン100t/年、合⾦チタン40t/年)。
・⾦属粉末のリユース、リサイクリング
3Dプリンタを使い慣れたユーザーであれば、⾦属粉末をリユース、ブレンディングすることは多い。もちろん、バージン材料であっても、経時劣化することは知られているが、過去にいくつかの企業が⾏った実験においても、「⾦属粉末の再利⽤はAMプロセスにあまり影響を与えない」という結論となっている。 ・Stratasys Andrew Carter, process and manufacturing engineer at Stratasys Direct
Manufacturing がプロセス再現性アップ及び不必要な粉末の廃棄削減のためのパラメータを定義する狙いから、リアルデータを用いた8か月間のスタディ(インコネル625、パウダべッド/EOS、7台で55部品を造形)を実施。造形サンプルの物性は、パウダの再利⽤以上に、わずかな装置の振動で⼤きく影響を受ける。一部の粉末は工程中に劣化してしまう場合があるが、それは全体からみるとわずかであったとしている。これらを踏まえ、Stratasysは、効果的かつ経済的なパウダマネジメントプロセスが重要としている。
345
・ManSYS(FP7/2007-2013) 欧州FP7のプロジェクトにおいて、チタン合⾦粉末の再利⽤に関して「BENCHMARKING
SUMMARY BETWEEN SLM AND EBM RELATED TO POWDER RECYCLING」、「Investigation the effects of multiple power re-use cycles in AM」を実施。後者のプログラムを担当したRENISHAWは、「チタン合⾦(Ti6Al4V) 粉末の粒径は造形を繰り返してもあまり変わらない。⼀部、凝集している、⼤きな粒⼦に⼩さな粒⼦が引っ付いてしまっているケースもあるが、リユースはあまりAM プロセスに影響を与えないようだ」と結論付けている。 ・その他 Honeywell Federal Manufacturing and Technology 及び Lawrence Livermore
National Laboratory が 、 「 316L POWDER REUSE FOR METAL ADDITIVE MANUFACTURING」を実施、Solid Freeform Fabrication Symposium – An Additive Manufacturing ConferenceのReviewed Paperの中で、「リユースの影響はあまり⾒られなかった」と言及している。
なお、樹脂材料ではAMプロセスに一定の影響があるとされている。EOSはサステイナブル活動の一環として、「Polymer powder recycling program」をユーザーに提供している。これは、使用済みパウダを集め、調整して、レーザ焼結以外の⽤途で利⽤するスキームとなっている。
・ソフトウェア
3Dプリンタでは、3Dデータを作成する「3D-CAD」。3Dデータを積層造形が可能なデータに変換し、3D プリンタの制御コードである G-Code に変換する「スライサ」。スライサの操作やプリンタへのデータ送信などをおこなう「フロントエンド」。さらにプリンタ本体に組み込まれ、G-Code を解釈してモータやヒータをコントロールする「ファームウェア」が必要となる。 一般的に、3D プリンタへの入稿ファイルとしてはSTL形式(Stereolithography)が標準的である
が、CADデータからどのようにしてSTLデータに変換するかは、3D プリンタで造形を⾏う上で重要な要素となっており、偏差をうまく取りながらパラメータを設定できるかによっても形状精度、造形スピードが変わってくるとされる。また、3Dプリンタでは、造形物の⼤きさや配置、サポート材の有無、材料の特性(材質)、温度管理、造形スピード、造形パターン等を考慮する必要があるほか、プリンタごとの性能や機械的な特性も考慮したパラメータ設定が必要となる。そのため、最近はプリンタメーカーがスライサの機能を持たせた CAM を⾃社プリンタにバンドルしているケースも⾒られるようになっており、要求の厳しい産業利⽤では自社開発や有⼒ソフトウェアベンダとのコラボレーションが活発化している。
346
図 3Dプリンタにおけるデータ処理⼯程/ソフトウェア
出所:CANONホームページ 主要 3D プリンタメーカーの状況を⾒ると、松浦製作所:LUMEX CAM2016、ソディック:
OS-FLASH、3D System:3DXpert、EOS:ECOSPRINT2.0が自社開発のCAMソフトウェアを搭載している。また、Concept LaserはMaterialise、Optomecはmastercamをベースに自社装置にカスタマイズしたものをユーザーへ提供する体制を整えている。なお、Renishaw は自社開発のQuantAM とMagics(Materilise)を標準ソフトウェアとして提案している。これらCAMは⼊⼒データとして、STLのほか、IGES、STEP、Parasolidなどにも対応している。 もともと、デスクトップ型3Dプリンタの登場を契機として市場形成が本格化したことから、いわゆる愛好者を中⼼に様々なフォーラムが⽴ち上がり、その中から、フリーソフトなども登場した。こうした背景から、現在もSTL変換ツールやエディタ、スライサ、フロントエンドなどのフリーソフトや安価なソフトウェアが各種存在するほか、最近は3D-CADソフトウェアのプラグインとして、STLエディタ等の機能が盛り込まれるケースがみられるようになっている。
347
・データベース
⾦属材料の世界では、溶かし⽅(速度、強さ、順序等)をはじめ、様々な加⼯条件をある⼀定のレベルで標準化する⽬的から、材料規格に則った製品が多く流通している。3D プリンタでは、現在 ASME InternationalやISO(International Standards Organization)等が材料仕様や試験⼿法といったAM技術の様々な面について標準化作業を進めている途中である。 また、米Senvolが1,000以上のAM装置、850以上の材料に関する情報・データをまとめた
Senvol Databaseを作成している。同社はAmerica Makesをはじめ、SAE International、ASME等、様々なコミッティーでの活動を通じ、AM業界に深く関与しており、ここで培ったネットワークがデータベースの基礎となっている。このSenvol Databaseは、様々な材料を網羅したデータベースを展開する英GRANTAがGranta MI: Additive Manufacturing Package としてサービス化しており、このソフトウェアを利⽤することで、利⽤者は特性、タイプ、適合機種を比較しながら、材料を探すことができるようになっている。 なお、GRANTAは1994年に英ケンブリッジ大学からスピンアウトした材料データのサービスプロバイダで、データベースはASME(American Society of Mechanical Engineers)、NIMS(National Institute for Materials Science)をはじめ、業界団体や各材料のデータベース運営企業(Senvol等)のデータパートナーから得た情報を集約している。 このほか、米National Institute of Standards and Technology (NIST)が、よりオープンなデ
ータベースを構築する計画(Additive Manufacturing Materials Database /AMMD)を有している。これは、米政府が2011年から取り組む「Materials Genome Initiative」の一環として、NISTが取り組んでいる「Material Data Curation System (MDCS)」に紐づく取り組みと位置付けられている。現在のところ、関係者間でディスカッションが⾏われている段階で、運⽤までの具体的な計画等は明らかになっていない。
349
(補足)研究者の動向 〜“PATENTSCOPE”を使⽤。検索キーワード:3D PRINTER
発明者上位10名のうち、日本の研究者としてはHAGIWARA YASUAKI(SEIKO EPSON)、MIYAWAMA YOSHIYUKI(SEIKO EPSON)、笠⾕潔(リコー)、YAMADA AKITOSHI(CANON)が挙げられ、これら研究者の所属に海外企業は含まれていなかった。なお、海外名の発明者は SEIKO EPSONの所属となっており、彼らが海外企業・組織に移った形跡もデータベースからは確認できなかった。
351
(補足)ニュースまとめ
20164 GE AM技術の研究開発を目的に、4,000万米ドルを投じたPittsburgh(ペンシルバニア州)の開発センターがオープン。5 HP RAPID 2016にて同社初の3Dプリンティングシステムを公開。バルセロナにAM技術のR&D施設を設置する予定で、投資額は
Alcoa エアバスとメタル3Dプリンティングによる機体部品及びエンジン部品の供給契約を締結。6 Norsk Titanium ニューヨーク州に新設した航空宇宙向けAMワークショップ(チタン製部品を製造)に対して州政府から2,500万米ドルの助成
を授受。同社は今後10年間に同拠点へ10億米ドルを投資していく方針。リコー バインダージェット方式のメタルプリンタを発表。
7 オランダ政府 3Dプリンティング技術の開発プロジェクトに対し1.34億ユーロの追加投資を⾏うことを発表。Alcoa 米ペンシルバニア州PittsburghのAM向け⾦属粉末⼯場が稼働。Daimler メルセデスベンツブランドのトラックのスペアパーツを3Dプリンタ(ポリマー/パウダベッド)で製造する計画を発表。
8 Nano Dimension イスラエルに拠点を置く同社は、プリント基板用プリンタ「Dragonfly2020」の出荷を開始。Aurora Labs豪株式市場に上場。同社はマルチモード、マルチホッパーの⾦属3Dプリンタを開発している。SAP/UPS HP、Airbus APWorks、Sealed Air CorpがSAP/UPSの「Distributed Manufacturing initiative」の最初の採用企
業となったことを発表。9 Carbon 3D ニコン、BMW、JSR、GE Venturesから計8,100万米ドルの投資を受けたことを明らかにした。
Facebook 3Dプリンティング技術及びモジュラーエレクトロニクス技術を持つスタートアップNascent Objectsを買収。10 Siemens AM技術をend to end でサポートするソフトウェアを発表。
GE Aviation チェコPrague郊外に3Dプリンティング工場を建設する計画を明らかにした。11 GE Arcam及びConcept Laserの支配権を取得したことを発表。今後10年間に1万台のAM装置を製造するビジョンも明らかに
2017 1 DOD/NASA 3Dプリンタで製造した自動運転ドローンのデモンストレーションを実施。また、NASAは燃焼チャンバを除くすべての部品を3Dプリンタで製造したロケットエンジンのテストを実施したことを発表している。
OssDsign スウェーデンを拠点に持つOssDesignは、Ti骨格とリン酸カルシウムで構成された3Dプリンタ製のインプラントがFDAの承認を得たことを発表。
DMG 森精機 パウダベッド技術を保有する独ReaLizerの株式50.1%を取得。Oerlikon 先進のR&D施設と製造設備を持つ米拠点(ノースカロライナ州)への5,500万米ドルの投資を発表、米国でのAMビジネス
3 GE Concept Laserへの大型投資を発表。計画には⽣産能⼒の増強、従業員数の倍増等が含まれる。Daimler プラスチック部品の製造にAM技術を積極的に取り入れていくことを発表。具体的には、リコーのパウダベッドシステムを導入し、
PP及びPA6等の材料を用いた部品を製造していく。
352
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
⾞載半導体には、マイコン(MCU)、電源 IC、センサなど様々なものがあるが、クルマの制御系を担うマイコンでは、NXP Semiconductors(旧 Freescale Semiconductor)、Infineon Technologies、ルネサス エレクトロニクス、Texas Instruments が⻑年シェアを握り、業界のリーダーを担ってきた。しかし、ここ数年、⾃動運転技術の実⽤化に向けた開発が急ピッチで進む中、IT ハードウェア大手NVIDIA、Intelの存在感が急激に高まっており、“自動運転”を巡る主導権争いが本格化している。 大手GPUベンダーであるNVIDIAは“AIコンピューティング カンパニー”を標ぼう、HPCやデータセンタ
のみならず、⾃動⾞分野での取り組みを加速化している。また、Intelは2015年6月にFPGA大手のAlteraを買収、2017年3月には当時ADAS⽤の画像認識SoCで⾶ぶ⿃を落とす勢いであったイスラエルMobileyeを買収し、業界に大きなインパクトを与えた。
この背景として、①ADASシステムの⾼度化(⾃動運転の段階的導⼊)、②機械学習、ディープラーニング(深層学習)等の人工知能(AI)の応用、③要求されるコンピューティング性能の飛躍的な上昇、が挙げられる。 現在発売されているLV2以上の自動運転機能を備えるモデルとしては、日産セレナ(プロパイロット)、SUBARU レボーグ(アイサイト・ツーリングアシスト)、M-Benz E クラス(ドライブパイロット)、テスラ(オートパイロット)等が挙げられるが、例えば、⾼速道路における全⾞速域(〜100, 120km/h)での⾃動⾞線維持を可能とした⽇産(プロパイロット)やSUBARU(アイサイト・ツーリングアシスト)は、あくまでも「どのような場合にどう対応するか」というルールベースのシステムで実現しており、ハードウェアもカメラ等のセンサと画像認識⽤ SoC(例えば、Mobileye の EyeQ チップ)、制御用マイコン等を追加したものとなっている。
354
<画像認識SoC> Mobileye EyeQ3 *256GOPS, 2.5W, 40nm CMOS <ADAS用マイコン> NXP, 32-bit MCU, Power Arch, dual Core <MCU> ルネサス(SH7250シリーズ), SH2A-FPU
図 日産/プロパイロットのシステム概要 出所 ⽇産資料より
これに対し、完全な自動運転機能の提供(将来のアップグレードが含まれる)を謳うテスラは2016年10 月、それまで採用していた Mobileye のシステムから NVIDIA の AI コンピューティング・システム「DRIVE PX2」に変更することを発表、全てのテスラ⾞両(Model S, Model X, Model 3)に「DRIVE PX2」を搭載することを明らかにしている。 テスラが新たに設けた自動運転機能「エンハスト オートパイロット」では、交通状況に応じスピードを調
整し、⾞線を逸脱することなく⾛⾏できるだけでなく、⾞線変更や⾼速道路の乗り継ぎ、⾃動での駐⾞や出庫も可能としている。運転環境のモニタリングまでをシステム側でカバーする LV3(⾼速道路⾛⾏等の限定条件)以上を想定したものとなっているが、例えば、⾞線維持機能ひとつとっても、隣の⾞線を⾛っていた⾞が急に前⽅に⾶び出してきた時、どのように対処するか、運転環境のモニタリングレベルはもとより、判断、対処⽅法に係るところまでシステム側で処理しなければならなくなるため、周辺環境・シーンの理解や意味づけ、危険予測、⾏動決定に関わる判断を担うAI技術が必要となる。 *テスラ「エンハスト オートパイロット」は、既にソフトウェアのワイヤレスアップデートによる配信は始まって
いるものの、各種機能は検証が終了し、規制に関する承認が得られた後に段階的に実装される。
355
図 TESLAエンハンストオートパイロット機能
2017年5月、トヨタが機械学習、ディープラーニング(深層学習)等のAI を使った自動運転技術
の開発で NVIDIA と協業することを発表している。背景には、現時点で LV3 以上の自動運転技術の開発に使える実⽤的な⾞載AIシステムがNVIDIAの「DRIVE PX プラットフォーム」しかないことなどがある。 ディープラーニングとは、多層のニューラルネットワークを用いた機械学習の手法で、既に音声や画像、
⾃然⾔語の認識技術として広く活⽤されている。⾃動運転の分野でも早くから物体検出等の画像認識技術として応用が進められているが、ディープラーニングをはじめとする AI 技術では、膨⼤な計算量をこなせるコンピューティング性能が不可⽋で、特に並列処理を得意とするGPUの利⽤が拡がってきている。 GPU コンピューティングに強みを持つ NVIDIA が⾞載半導体分野で急速にプレゼンスを⾼めつつある
のも、AI技術の応用とそこで要求されるコンピューティング性能の飛躍的な上昇があるわけだが、NVIDIA はハードウェアのみならず、多岐に亘るソフトウェア開発キット(SDK)を取り揃え、OEM、Tier1の囲い込みを進めている。 一方、Intel も2017 年 1 月に自動運転向け開発プラットフォーム「Intel GO」を発表、Altera、
Mobileyeの資産を活用しながら、CPU、Field-Programmable Gate Array (FPGA)、ディープラーニング⽤のハードウェア・アクセラレーション・テクノロジーなどで構成する、並列処理と直列処理を最適に組み合わせたアーキテクチャを提供することを狙っている。 「Intel GO」は⾃動⾞(⾞載開発プラットフォーム)、コネクティビティ(⾃動⾞向け5Gプラットフォー
ム)、クラウド(データセンターテクノロジー)という3つのプラットフォームを統合したシステム開発を支援する“自動運転ソリューション”としての側面も有しており、Intel では業界に対する共通プラットフォームとして
356
NVIDIA/Tegra K1(GPU)、Mobileye/EyeQ 3(画像認識⽤SoC)の構成を採っており、テスラが採用するNVIDIA「DRIVE PX2」と比較するとかなり現実的なものとなっている。 *実搭載の zFAS に関する仕様等が明らかでないため詳細は不明であるが、LiDAR搭載によるセン
サ・フュージョンの負荷増に対して、I/OをCyclonV、画像認識をEyeQ 3、グラフィックス出⼒をTegra K1、アクチュエータ制御をAurixが担っているものとみられる。
358
YRIでは、2020年〜2021年にかけて⾼速道路限定のLV3が日米欧の主要OEM より発売されると⾒ているが、これらのモデルがどこまで制限なしの状態になるか、それによってもハードウェアに求められる仕様は異なってくるものとみられる。これに関しては、LiDAR等センサの開発状況なども影響してくるが、いずれにしても、2020年〜2021年の段階では画像認識・物体検出にディープラーニング等のAI技術が一部応用されるものの、本格的なAI技術の応⽤はより⾼度な環境認識、⾏動計画、予防安全が求められるLV3 (一般道/市街地)からとみる。つまり、LV3 (一般道/市街地)の採用(まずはE/Dセグメント)が始まる 2023 年以降(実質は OEM 各社のモデルがある程度出揃うであろう 2025 年前後)がGPU vs DSP/アクセラレータ、FPGAのターニングポイントになると予想される。
勝負のポイントとしては、演算性能、省電⼒性、リアルタイム性、安全/セキュリティが挙げられるが、セ
ンサ側の技術トレンドやソフトウェアの進化、システム全体の構成変化によっても、それぞれの競争⼒が変化する可能性がある。 LV3 以上ではカメラ、レーダ、LiDAR のセンサ・フュージョンが必須、その搭載個数も⾞両1台あたり
20〜30 個となるため、異なるフォーマット、データレート、抽象度のデータをリアルタイムに処理できるスループット性能が重要。さらに技術開発の遅れに懸念のあるLiDARではなく、TOFセンサを応用しようなど、センサ側の技術開発トレンドは未だルートが定まっていない。 同様に、ディープラーニング用の計算フレームワークや機械学習アルゴリズムについても日進月歩で、デ
ィープラーニングの推論フェイズにおけるデータ処理も処理速度の向上を⽬的に FP16 半精度浮動⼩数点 からINT16整数、INT8整数へと移⾏している。これにより演算性能、レイテンシの点でFPGAが有
359
利との声も聞かれるようになった。 これに対して、NVIDIAは第3世代SoC「XAVIER」に搭載する最新のGPUアーキテクチャ“Volta”
においてディープラーニングに最適化した新しいTENSOR CORE (4×4 マトリックスプロセッシングアレイ)を導⼊、推論⽤コンパイラ(TensorRT)により INT8 演算自動最適化を図るなどの対策を採っている。もちろん、さらに精度を落とした場合はどうかといった点は残るが、NVIDIAがひとまず先手を打った形となっている。
図 必要とされる演算性能
360
図 機械学習、ディープラーニングの適用範囲
また、システム全体の構成変化、具体的には統合OR分散という観点によっても、求められるコントロー
ルユニットのありようは異なる。いまのところ、NVIDIA「DRIVE PXプラットフォーム」のように、センサ等から得られる信号データを集中的に処理し、環境把握から⾏動計画決定までを統合的に⾏う⽅向に向きつつあるが、センサの種類、搭載個数が今後さらに増加していくことが予想される中、これらセンサで得られる膨⼤な信号データをどのように流していくか、データ通信の問題がいずれ浮上するため、将来的にはセンサ側にある程度のプレプロセッシングを任せる分散型のシステムネットワークに移⾏していく可能性がある。 いずれにしても、これらの解答がある程度⾒えてくるであろう 2025年以降、より具体的には LV3(一
般道/市街地)を含めた⾃動運転機能が量産⾞種にも普及する2030年を⼀つの節⽬に、⾞載半導体業界の勢⼒争いは⼀応の決着(⾃動運転技術を⽤いたサービスの多様化といった別フェイズへ移⾏する可能性はあるが)を迎えると予測する。 AI 技術の応用において、機械学習の動作や結果は公正公平(フェアネス)であることが重要とされ
る。⾃動運転では安全性に関わる部分がフェアネスと深く結びつく。⾞-⾞間通信(V2V)による危険予測では情報の偏りが⼀⽅に危機的状況を与えることも想定される。結局のところ、⾃動⾞社会全体できちんと安全性を担保しようとすればするほど、共通のプラットフォームの必要性が高まるため、自動運転技術は一定のレベルで標準化せざるを得ないとみられる。
361
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
ADAS/自動運転に関わる要素技術としては、センサ、チップ、ネットワークが挙げられる。これらは AI応用が期待されるIOTの世界にも関わりのある技術と言える。
出所 soracom資料より
スマートシティやスマートファクトリに向けて、様々なモノをネットワークにつながり、リアルタイムで情報のや
り取りをするサービスが登場しているが、最近は、通信量やリアルタイム性の観点からクラウド・コンピューティングをベースしたものだけでなく、エッジ・コンピューティングを活用したものも提示されるようになっている。
図 通信量とリアルタイム性からみたクラウド及びエッジの⽴ち位置
出所 NTT資料
366
図 エッジ・コンピューティングの重要性
出所 NTT資料
ADAS/自動運転はエッジ・コンピューティングの際たる例として、AI チップやネットワーク技術の研究開発が進められており、こうした技術が⼯作機械の制御、ビルの空調やエレベーターの運⽤管理、スマートグリッドによる電⼒供給制御など、よりリアルタイム性を求められる IOT アプリケーションにも応用されていく可能性がある。また、膨⼤な情報を超⾼速かつ効率的に処理できる技術は、エッジのみならず、⼤規模な並列処理が求められるクラウド・コンピューティングにも通ずるもので、既に半導体分野全般において、AIチップ(超⾼速・超⾼効率な演算能⼒)の開発競争が活発化している。
367
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
⾞載半導体における世界市場(2010〜2016年)及び2016年メーカーシェア
⾞載半導体の世界市場はここ数年、CAGR:+6.2%と伸⻑傾向にある。中国等の新興国における⾃動⾞の⽣産台数が拡⼤したほか、⾼級⾞を中⼼に MCU 及びセンサの一台当たりの搭載個数が増加していること、xEVの本格⽴ち上がりに伴う需要押し上げなどが背景にある。 Strategy Analyticsのデータ(⾦額ベース)によると、ルネサスは⾞載半導体市場全体で9.8%のポジションを確保しており、特にMCUでは30.9%のトップシェアを有する。2015年のデータ(Strategy Analyticsの数値を基にルネサスが推計)となるが、同社は⻑年の実績はもとより、最先端のプロセス技術、優れた⾞載品質を武器に世界No.1⾞載マイコン/SoC サプライヤのポジションを確⽴、特にコクピット、インスツルメントのカテゴリーでは40%を超えるシェアを有していると⾃信を⾒せる。 NXPによるFreescale Semiconductor買収、InfineonによるInternational Rectifier買収
等の影響から、⾞載半導体分野ではトップメーカー同⼠のシェア争いが激化しているが、ルネサスは得意
368
とするパワトレ、シャシー関連のマイコンに加え、ADAS/自動運転、xEVでの需要取り込みに注⼒、シェア拡大につなげていく方針である。
⾞載半導体分野におけるルネサスのポジション
出所 ルネサス資料
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
⾞載半導体市場は、⾃動⾞⽣産台数こそ中国市場の減速などを背景に 2〜3%の成⻑率に⽌まるものの、xEV に代表されるエコカーの世界的な普及、ADAS/⾃動運転の本格実⽤化等を背景に毎年8%程度の需要拡⼤が期待されている。特に ADAS/自動運転はレベル 2 からレベル 3、レベル 4/5 へと⾼度化するのに伴い、センサ搭載個数の増加やフュージョン、統合制御等に関わるハイパフォーマンスなMCUの採用が進むことでBoM コストが⼤幅に上昇すると⾒られている。
369
また、xEVをはじめとするエコカー(Clean Car)の市場浸透も⾞載半導体市場の拡⼤要因として挙げられる。矢野経済研究所では、2016年時のHEV/PHEV/EV/FCVからなる次世代⾞の販売台数を244万台(市場全体の2.4%)と推計している。今後、世界規模での燃費規制厳格化を背景に次世代⾞の市場が拡⼤していくことは確実で、次世代⾞は2020年に新⾞市場全体の6.0%に成⻑。2030年には約17%の規模に成⻑とすると予測している。 次世代⾞販売台数におけるタイプ別構成では2019年まではHEVが最大のシェアを占める一方、
2020年以降はEV/PHEVの普及が徐々に本格化。2030年にはEV/PHEVのシェアは80%超となるとみている。
図 次世代⾃動⾞(HEV/PHEV/EV/FCV)の市場予測(台数ベース)
374
⑤ ②の各⽤途に求められる技術特性〜⾞載⽤マイコンの技術変遷
高速演算性能
bit数 8ビット 16ビット 32ビット
アーキテクチャ CISC → RISC ハーバードアーキテクチャ
動作周波数 2MHz 10MHz 20MHz 40MHz 80MHz 300MHz
微細化 3.0μm 1.3μm → 0.5〜0.8μm0.15〜0.25μm 90nm
⾼度・複雑な制御
メモリ容量 4〜8kB 32kB
リアルタイム制御
機能安全(ISO26262)
→
150~200MHz
40nm, 55nm, 65nm
2000年代 2010年代
128〜256kB 1〜3MB 4〜8MB
単精度浮動⼩数点演算ユニット、DSP
周辺機能(多機能タイマー、高速A/D変換器
マルチコア
マイコン性能 1980年代 1990年代
376
⽇⽴製作所/旧ルネサス テクノロジ
1980 年代、⽶モトローラ社が組み込み用コンピュータとして開発した MC6800(5 μm プロセスのn-MOS)を⽇⽴製作所が独自に CMOS 化、HD6301v シリーズ(HD63B01V1)として販売していた。 HD6301v は CMOS3μm技術を採用、128Byte RAM、4kB ROM、29 パラレル I/O ライン、
16bit タイマを内蔵し、マイクロプログラム制御、パイプライン制御も備えることで、最⼩命令実⾏時間0.5μs(2MHz 動作時)、消費電⼒ 30mV(1MHz動作時)という 1980年頃の組み込み⽤ 8 bitシングルチップコンピュータとしては相応に高い機能を実現していた。 ⽇⽴製作所はその後、⾼速動作、C⾔語の効率的実⾏、ASIC展開の用意さなどを目的に命令コ
ード化順序を従来と逆転させるアーキテクチャ上の工夫などを実施、従来製品である HD6301v と比べC言語使用時で3倍のCPU性能を実現したH8/500ファミリ(H8/532)を製品化した。 H8/500 シリーズ(16bit))は 1.3μmCMOS プロセスを採用、9.8×9.9 ㎜に 42 万個のトラン
ジスタを集積するとともに、⼤容量 PROM(当時世界最大となる32kB)、⾼速⾼精度 A/D 変換器(世界最速となる変換時間 13.8μs)、多機能タイマ等を搭載するなど、世界でもトップクラスの高性能シングルマイクロコンピュータ(基本的なレジスタ間演算が0.2μs、10MHz動作時)であった。
CPU HD6301ファミリCPU
トランジスタ数 35,000個
動作周波数 2MHz
メモリ 128 Byte RAM
4 kB ROM
タイマ 16ビットFRT:1チャネル
シリアルI/F 1チャネル
I/Oポート 29
HD63B01V1
377
*パッケージ(84 ピンPLCC、84ピン窓付きLCC、80ピンQFP) ** PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier), QFP(Quad Flat Plastic Package) 1990年代以降、組み込み⽤途向けは動作クロック、消費電⼒当たりの性能(MIPS/ W)の観点
から32 ビットRISCマイクロコンピュータ(Reduced Instruction Set Computer、縮⼩命令セットコンピュータ)に移⾏。⽇⽴はいち早くSuperHシリーズを製品化し、大きな市場シェアを確保した。 SuperH シリーズのうち、⾞載⽤途(エンジン制御)で主に使⽤されたのは SH7051等の SH-2 コ
ア(1994年量産開始、0.8μm2層アルミ CMOSプロセス)を用いたものである。 SH7051 は、命令⻑を16bit に縮⼩するなどメモリ効率を向上させた、⾼速かつ⾼機能なプロセッサ
で、当時の競合CPUが10〜15MIPSであったのに対し、SH-2は25MIPSと頭一つ抜けていた。その性能面からSEGAの据置型ゲーム機(セガサターン)で全⾯的に採⽤されるなど価格競争⼒も⼗分で、特に高速性が要求されるリアルタイム制御などのアプリケーションで競争⼒を発揮、DRAMインターフェイスや⼊出⼒インターフェイス、周辺インターフェイスの内蔵ラインナップを増やすことで、組み込み用国産プロセッサの定番チップのポジションを確⽴した。 その後、⽇⽴製作所は2002年より0.18μmCMOSプロセスを採用したSH-2Eコア(32bit、単精度浮動⼩数点演算ユニット内蔵)を採⽤した SH7058 等の世代に移⾏、⾃動⾞のエンジン制御等、多数のパルス⼊出⼒制御が必要な用途に向けてタイマ機能のアップグレード(ATU-Ⅱ)やコントローラエリアネット ワーク(CAN)の搭載などを進めた。
CPU H8/500ファミリCPU
動作周波数 10 Mhz
メモリ 1 kB RAM
32 kB ROM(PROM/マスクROM)
タイマ 16ビットFRT:3チャネル+ 8ビットタイマ:1チャネル + PWMタイマ:3チャネル
ウォッチドッグタイマ:1チャネル
A/D変換器 10ビット、8チャネル *変換時間13.8μs
シリアルI/F 1チャネル
DTC
I/Oポート 入出力共通端子:57本、入力専用端子:8本
INTC 割り込みコントローラ
1チャネル*CPUの介在なしに、I/Oとメモリ間のデータ転送を実現することが可能。CPUの負担を軽減し、ソフトウェアの複雑化を防ぐのに有効
H8/532
378
*168ピン プラスチックQFP
*パッケージ(FP-256H/BP-272) ルネサステクノロジとなった 2002 年以降も、⾞載⽤マイコンについては SuperH シリーズが継続され、
2008年にはSH-2Aコアを用いた世代を投入している。 SH-2AはCPUコアの命令処理アーキテクチャの1つであるスーパースカラ方式(最大2つの命令を
同時に実⾏可能)に加え、データバスを命令⽤とデータ⽤に分離するハーバードアーキテクチャを採⽤することで、処理性能を⼤きく引き上げることに成功した。実際、従来の「SH-2」は最大動作周波数80MHz で104MIPS の処理性能であったのに対し、SH-2A は 200MHz 動作時に 360MIPS と約3.5倍の処理性能を実現。また、単位周波数1MHz当たりの処理性能は、スーパースカラ⽅式の採⽤
CPU SH-2コア
トランジスタ数 45万個
動作周波数 20 MHz
メモリ 10 kB RAM
256 kB フラッシュメモリ
タイマ
A/D変換器 10ビット、16チャネル
シリアルI/F 3チャネル
DMAC ダイレクトメモリアクセスコントローラ:4チャネル
I/Oポート 入出力:102 本 入力:16 本合計 118 本(兼用ポート)
INTC 割り込みコントローラ
WDT ウォッチドッグタイマ:1チャンネル
CMT:2チャネル + ATU※フリーランニングカウンタ 10 本、ダウンカウンタ 8 本、計 18 本最大 34 本のパルス入出力処理が可能
SH7051
CPU SH-2Eコア
※浮動小数点演算ユニット(FPU)内蔵
動作周波数 80 MHz
メモリ 48 kB RAM
1 MB フラッシュメモリ
タイマ
A/D変換器 10ビット、32チャネル
シリアルI/F 5チャネル
DMAC ダイレクトメモリアクセスコントローラ:4チャネル
I/Oポート 149本
INTC 割り込みコントローラ
WDT ウォッチドッグタイマ:1チャンネル
SH7058
ATU-IIコンペアマッチタイマ:2 ch
379
により、従来の1.3MIPSから1.8MIPSへと約1.4倍向上している。さらに、90nmプロセスによる大容量のフラッシュメモリを搭載しながらも、環境温度が 125℃での200MHz 動作時でも 900mW以下と低消費電⼒を実現した。
CPU SH-2A-FPUコア
ハーバードアーキテクチャ
動作周波数 200MHz 3.3V /5.0V
メモリ 128kB RAM
2.5MB フラッシュメモリ(ROMキャッシュ有)
128KB EEPROM
タイマ CMT:2チャネル + ATU-III
A/D変換器 12ビット、37チャネル (28+9)
RCAN コントロールエリアネットワーク(RCAN)×3チャネル
RSPI 3チャネル
I/Oポート 144
INTC 割り込みコントローラ
AUD-WDT
A-DMAC 66チャネル※専用ダイレクトメモリアクセスコントローラ
SH72544R
シリアル シリアルコミュニケーションインターフェース(SCD×5チャネル)高速シリアルインターフェース(High Speed SCD×3チャンネル)
DMAC 8チャネル※ダイレクトアクセスコントローラ
380
NEC/ ルネサス エレクトロニクス
1チップ・マイコン「78K シリーズ」で培ったノウハウを生かした組み込み制御に最適なマイクロコントローラとして 32 ビット RISC CPU コアアーキテクチャを採用した V850 シリーズを展開。第一世代の V850(0.5μmCMOS, 1996年)から、第⼆世代:V850ES(0.25μmCMOS, 2000年〜)、第三世 代 : V850E1 ( 0.15 μ mCMOS, 2005 年〜 ) 、 第 四 世 代 : V850E2(90nmCMOS+SGMONOS, 2009年〜)と続き、そのコアアーキテクチャは現在ルネサス エレクトロニクスが展開するRH850(40nmCMOS+SG-MONOS, 2012年〜)に受け継がれている。
機能 V850 V850ES V850E1 V850E2 V850E2M
最大動作周波数 20/33MHz 20/32/48/50MHz 66→100→150MHz 200HMz200MHz
命令数 47 80 80 89 98
最大プログラム・メモリ空間 16MB 16MB 64MB 512MB(内蔵128MB) 4GB
最大データ・メモリ空間 16MB 16MB 256MB 4GB 4GB
高性能化命令実⾏サイクル最適化同時2命令実⾏能⼒の強化単精度/倍精度⾼速FPU対応マルチCPU対応
高コード効率化
32ビット相対分岐命令
3オペランド命令
積和演算命令
ビット・サーチ命令
割り込み応答性 11〜18クロック
LD命令、ST命令のディスプレースメント拡張
4〜10クロック -
C⾔語対応命令追加
5段パイプラインハーバード・アーキテクチャ
7段パイプライン同時2命令実⾏
パイプライン改善・ノンブロッキング・ロード/ストア命令・命令の並列実⾏・分岐/ロード・パイプ追加・3オペランド操作の1スロット化
2バイト⻑命令CISC命令
CPU V850コア
動作周波数 33MHz
メモリ 128 kBフラッシュメモリ
41kB RAM
タイマ 16ビット・タイマ/カウンタ 5チャネル
A/D変換器 10ビット 8チャネル
I/Oポート 75
INTC プログラマブル割り込みコントローラ(49要因) ※割り込み応答時間 0.33μs
非同期:最大2チャネル
同期:最大4チャネル
専用ボーレート・ジェネレータ:3チャネル
V853
シリアルインタフェース
381
CPU V850E1コア (FPU内蔵)
動作周波数 128MHz
メモリ 1 MBフラッシュメモリ
60kB RAM
タイマ 16ビット・タイマ/カウンタ 5チャネル
16ビット・タイマ/カウンタ(モーションコントロール) 2チャネル
16ビット・タイマ/カウンタ(PWM) 2チャネル
A/D変換器 10ビット 20チャネル
I/Oポート 148
INTC プログラマブル割り込みコントローラ
シリアル アシンクロナス・シリアル・インタフェース(UARTC) 3チャネル
クロック同期式シリアル・インタフェース(CSIB) 2チャネル
クロック同期式シリアル・インタフェースH(CSIE) 2チャネル
CAN 2チャネル
FlexRay2チャネルDMA 8チャネル
V850E/PHO3
CPU V850E2Mデュアルコア
動作周波数 128 MHz
メモリ 1 MBフラッシュメモリ
80kB RAM
タイマ 16chの16ビットカウンタと専用のプリスケーラを内蔵したタイマユニット・A×2
4chの32ビットカウンタと専用のプリスケーラを内蔵したタイマユニット×1
モータ制御に適したタイマユニット(TSG2)×2
PWM出力が可能なタイマ・パタン・バッファ(TPBA)×1
2相エンコーダ制御に適したタイマユニット(ENCA)×2
32ビットのフリーラン・インターバル・タイマ(OSTM)×2
ウィンドウ・ウォッチドッグタイマ(WDTA)×1
A/D変換器 10/12ビット分解能×22チャネル(S/H 6チャネル+16チャネル)10/12ビット分解能×10チャネル(S/H 4チャネル+6チャネル)
INTC プログラマブル割り込みコントローラシリアルインタフェース
アシンクロナス・シリアル・インタフェース(UARTC) 3チャネル
クロック同期式シリアル・インタフェース(CSIB) 3チャネルクロック同期式シリアル・インタフェースH(CSIE) 1チャネルCAN 3チャネル
DMA 8チャネル
V850E2/PJ4
382
ルネサス エレクトロニクスは 2012 年、⾃動⾞の制御系システム向け 32 ビットマイコンの新ファミリRH850」発表した。業界最先端となる40nmプロセスを採用。メインCPUはハイエンドパワートレイン制御向けにTj=150℃下で世界最高速の動作周波数320MHz を実現するほか、メイン CPU に加え周辺制御用CPUを搭載し、マルチコア化することで、スケーラブルなCPU構成を採用。メインCPUには自動⾞⽤機能安全(ISO26262)への対応を考慮し、ロックステップ方式を導入している。また、フラッシュメモリに独自の MONOS(Metal-Oxide-Nitride-Oxide-Silicon)構造を採⽤することで⼤容量メモリの搭載を実現している。 周辺機能は実績ある90nm世代のパワートレイン用周辺機能を強化。⾞載アプリケーションに必要な
CAN、FlexRay、RHSB(Renesas High Speed Bus)などの通信機能をはじめ、2種類のA/D コンバータ (逐次比較型とΔΣ型)、デジタルフィルタエンジンおよびアドバンストタイマユニット (ATU-IV) などを内蔵した。 RH850/E1M-Sはリアルタイム制御に必要な同クラス最⾼速で⼤容量コードフラッシュ/⼤容量RAM
を搭載した 320 MHz 動作のマイコン。RH850/E1L は RH850/E1M-S の機能縮小版で最大240MHzで動作するマイコンとなっている。 また、ルネサス エレクトロニクスは2016年3月よりエンジン制御向けで⾞載制御⽤マイコンとして最⾼
クラスの動作周波数 320MHz、⼤容量コードフラッシュ/⼤容量 RAM を搭載したマイコンRH850/E1M-S2のサンプル出荷を開始している。 エンジン制御システムの応用性能を従来製品比30%向上させたCPU コア、センサ情報の通信規格
SENTに対応、⾞載ネットワーク⾼速化に向けCAN FDだけでなく、これからの⾃動⾞に求められる⾞載セキュリティ ICU-S にも対応した。また機能安全 (ISO26262)を実現する機能も多数内蔵することで認定取得簡素化につなげている。
383
※252 ピン BGA (17 x 17 ; 0.8 mm), 304 ピン BGA (19 x 19 ; 0.8 mm)
CPUコア 240/320MHz ロックステップコア、FPU周辺コントロールユニット(PCU) 80MHzメモリ プログラムフラッシュ 4MB
SRAM 320KBデータフラッシュ 64KBiキャッシュ 8KB
データ転送機能 DMA 16チャネルDTS 128チャネル
タイマ OSタイマ(OSTM) 3チャネルウォッチドッグ(WDT) 2チャネル
エンジン制御用タイマ(ATU-IV) 1ユニット
オートノマスパルスアダプタ 1ユニットモータ制御用タイマ(TSG2) 2チャネル
通信機能シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI3)
4チャネル
クロック同期式シリアルインターフェース(CSIH)
4チャネル
高速バス(RHSB) 2チャネル
LIN 1チャネルCAN 4チャネルFlexRay 1チャネル
アナログ 逐次比較型A/Dコンバータ 12ビット:48チャネル
ΔΣ A/Dコンバータ 8チャネル
デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル
セーフティマルチインプットシグネチャジェネレータ(MISG)、CRC、エラーコントロールモジュール(ECM)他
セキュリティID認証機能を用いてコードフラッシュへの書き込み/消去を保護
RH850/E1M-S
384
※QFP(20×20, 0.5mm)、QFP(24×24, 0.5mm)、BGA(17×17, 0.8mm)
CPUコア 160/240MHz ロックステップコア、FPU周辺コントロールユニット(PCU) 80MHzメモリ プログラムフラッシュ 2MB
SRAM 160KBデータフラッシュ 64KBiキャッシュ 8KB
データ転送機能 DMA 8チャネルDTS 128チャネル
タイマ OSタイマ(OSTM) 3チャネルウォッチドッグ(WDT) 2チャネル
エンジン制御用タイマ(ATU-IV) 1ユニット
オートノマスパルスアダプタ 1ユニットモータ制御用タイマ(TSG2) 1チャネル
通信機能シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI3)
4チャネル
クロック同期式シリアルインターフェース(CSIH)
3チャネル
高速バス(RHSB) 1チャネル
LIN 1チャネルCAN 4チャネル
アナログ 逐次比較型A/Dコンバータ 12ビット:36チャネルΔΣ A/Dコンバータ 2チャネル
デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル
セーフティマルチインプットシグネチャジェネレータ(MISG)、CRC、エラーコントロールモジュール(ECM)他
セキュリティID認証機能を用いてコードフラッシュへの書き込み/消去を保護
RH850/E1L
385
※252 ピン BGA (17 x 17 ; 0.8 mm), 304 ピン BGA (19 x 19 ; 0.8 mm)
CPUコア 240/320MHz ロックステップコア、FPU周辺コントロールユニット(PCU) 80MHzメモリ プログラムフラッシュ 4MB
SRAM 320KBデータフラッシュ 64KBiキャッシュ 8KB
データ転送機能 DMA 16チャネルDTS 128チャネル
タイマ OSタイマ(OSTM) 3チャネルウォッチドッグ(WDT) 2チャネルセキュアウォッチドッグタイマ(SWDT)
2チャネル
エンジン制御用タイマ(ATU-IV) 1ユニットオートノマスパルスアダプタ 1ユニット
モータ制御用タイマ(TSG2) 2チャネル
通信機能シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI3)
4チャネル
クロック同期式シリアルインターフェース(CSIH)
4チャネル
高速バス(RHSB) 2チャネルLINマスタインタフェース(RLIN2) 1チャネルCAN/CAN FD(選択可) 4チャネルFlexRay 1チャネルSingle Edge Nibble Transmission(R SENT)
6チャネル
アナログ 逐次比較型A/Dコンバータ 12ビット:48チャネル
ΔΣ A/Dコンバータ 8チャネル
デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル
セーフティマルチインプットシグネチャジェネレータ(MISG)、CRC、エラーコントロールモジュール(ECM)他
セキュリティハードウェアセキュリティモジュール ICU-S搭載(車載セキュリティ標準規格 SHE/EVITA-Lightに準拠)ID認証機能を用いてコードフラッシュへの書き込み/消去を保護
RH850/E1M-S2
386
Freescale(NXP)
米モトローラが開発した組み込み用 8bit マイクロコントローラ MC6800 の派生として製品化されたCISCマイクロコントローラ(MC68HC11A8)が、1980年代に⾞載⽤マイコンとして使⽤された。 MC68HC11A8(8bit CISC)は 8kB の ROM、256B の RAM に加え、512B のEEPROM
(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)が搭載されていたほか、3本のインプットキャプチャ機能や5種類のアウトプットコンペア出⼒を持つ16 bitタイマ、シフトレジスタ型のシリアルインターフェースであるSPI、非同期シリアル通信用のSCI、ストローブ信号やハンドシェーク信号対応のパラレルポート、8 bit分解能のA/Dコンバータが組み込まれていた。 その後、1990 年に CISC+Intelligent Timer機能(RISC)を備えた16MHz/32bitMCU
(MC68F375)を市場投入している。
2000年代に⼊ると、MPC5xx シリーズ(0.25μmCMOS)及び MPC55xx シリーズ(0.15μ
mCMOS)へ移⾏。Power Architcture(RISC方式)の採用、高機能タイマーの搭載、A/D変換器の多チャンネル化を進めた。
CPU 2MHz M68HC11※8bit CISC, HCMOSプロセス
メモリ 8KB ROM512B EEPROM256B RAM
タイマ 16ビット*1チャネル、8ビット*1チャネルA/D変換器 8ビットADC:8チャネル
SPI 1本※シフトレジスタ型シリアルインターフェース
SCI 1本※非同期シリアル通信用
IOポート 40
MC68HC11A8
CPU CPU32:32ビット68000ファミリCPU+上位オブジェクトコード互換16MHz
メモリ 256KB Flash EEPROM8KB SRAM
タイマ TPU3:1ユニット*16チャネル
A/D変換器 10ビットQADC64:16チャネル
QSPI 1本TouCAN 2モジュールSCI/UART 2チャネル
IOポート 114
MC68F375
387
*416ピン PBGAパッケージ MPC55xxシリーズは可変⻑エンコーディング技術(VLE)等を盛り込んだPower ISA v.2.03に準拠したPower PC e200 (32bit Power Architecture)をコアに使用したもので、パワートレイン向けのMPC5566はe200z6 コアが採用されていた。 e200z6コアは7ステージ/シングル命令発⾏のパイプラインを持ち、32エントリ・メモリマネジメントユニット(MMU), FPU対応SIMD、SPE等の機能をオンチップ化したもので、当時は0.13μmのデザインルールが用いられていた。 その後、後継となるMPC56xxシリーズは、90nmプロセス導入を目的にSTMicroelectronics と共同で開発を進め、e200z7 コア(10 ステージ、複数命令同時発⾏、32 エントリ・MMU 等)を用いたMPC5676R等、ハイエンドな⾞載⽤マイコンを製品化した。 現在の最新シリーズは、MPC57xx シリーズとなっており、特に機能安全/セキュリティを重視した設計
CPU 40MHz Power ArchitctureFPU内蔵
メモリ 1MBフラッシュ36KB SRAM
タイマ TPU3:3ユニット*16チャネルデータ転送 BBC
A/D変換器 10ビットQADC64E:40チャネル
QSPI 1本TouCAN 3モジュールSCI/UART 2本MIOS14 22チャネルGPIO 72
MPC565
CPU 132MHz 32ビットPower Architecture(RISC)e200z6コア, Power ISA 2.03 (VLE/32bit, MMU, FPU, SPE)
メモリ 3MBフラッシュ128KB SRAM32KB ユニファイドキャッシュ
タイマ eTPUs:2ユニット*32チャネルデータ転送 64チャネルeDMAINTC 339A/D変換器 12ビットeQADC:40チャネル
SPI 4本CAN 4チャネルSCI 2チャネルeMIOS 24チャネルGPIO 256セーフティ ECSM
MPC5566
388
(メインコア/ロックステップコアのマルチコア等を用いISO 26262/ASIL-Dに準拠)を採ることで高信頼性を実現する業界屈指の産業用マイクロコントローラ(Ultra-Reliable MCU)を唄っている。
CPU 180MHz 32ビットPower Architecture:2コアe200z7コア, VLE, DSP, SIMO(FPU対応)
メモリ 6MBフラッシュ (EEPROMエミュレーションjン対応ブロック搭載)384kB SRAM (48kB スタンバイRAM)16 kB Iキャッシュ, 16 kB Dキャッシュ
タイマ eTPU:3ユニット*1ユニット32チャネルデータ転送 64チャネルeDMAINTC Dual Core Interupt controller A/D変換器 12ビットeQADC:2ユニット *64チャネル入力対応
SPI Deserial serial peripheral interface (DSPI) modules ×5FlexCAN 4チャネルeSCI 3チャネルeMIOS 32チャネル CAN FlexCAN(コントローラエリアユニット)×4セーフティ Nexus Class 3+ リアルタイムデバッガー
MPC5676R
CPU 300MHz 32ビットPower Architecture:2メインコア, 300MHz ロックステップコアe200z7コア, VLE, DSP, SIMO(FPU対応)e200z4コアを用いたI/Oオペレーティング(200MHz)
メモリ 8MBフラッシュ with error code correction (ECC)596kB SRAM with ECC32KB ユニファイドキャッシュ
タイマ 248チャンネル タイマーモジュール(GTM104)データ転送 128 チャネルeDMAINTC Dual Core Interupt controller A/D変換器 84チャネルADC
含むΔΣ ADC×10通信プロトコル Ethernet コントローラ(FEC)
4×M-CAN, 1×TT-CAN6×LINFlex8×dSPI, 2×IIC5×PSI-5, 15×SENTZipwire support
2×dual-channel FlexRay コントローラ
セーフティ High-speed Nexus Aurora debug and trace support
MPC5777M
389
Infineon
リアルタイム組み込みシステム向けに最適化されたシングルコア 32 ビット MCU-DSP統合アーキテクチャを採用したTri-Coreシリーズを2000年頃より展開。第⼀世代品(AUDO, Automotive unified processor)はデザインルール 0.25μm、クロック周波数 40MHz、メモリは内蔵されていなかった。その後、2005年にフラッシュメモリを内蔵した第⼆世代(AUDO NG, Next Generatin, 代表的な製品はTC1796)を製品化、クロック周波数を150MHzまで高め、内蔵フラッシュメモリも充実化を図った。 以降、TC1797(AUDO Future, 0.13μm プロセス, 2008年〜)、TC1798(AUDO MAX,
90nmプロセス, 2010年〜)とTriCoreの性能向上を推し進めてきたが、2012年に最大3つの独⽴した 32 ビット TriCore プロセッサ・コアを搭載できるマルチコア・アーキテクチャを採用した AURIX を発表、65nmのデザインルールを採用した第一世代(パワートレイン向けはTC26x)を投入している。 同社では TriCore で培ってきた優れたリアルタイム・パフォーマンスに加え、安全機能、セキュリティ機能
を強化したAURIXは燃焼エンジン制御、電気⾃動⾞やハイブリッド⾃動⾞、トランスミッション制御ユニット、シ ャシー領域、ブレーキ・システム、電動パワーステアリング・システム、エアバッグ、先進の運転者⽀援システムなど、幅広い⾞載⽤アプリケーションで理想的なプラットフォームになるとしている。 ※現在、AURIXの第二世代(40nmデザインルール、最大ヘキサコア、TC39xなど)を開発中。
CPU TriCore@150MHz
32-bit Peripheral Control Processor(メモリ管理ユニット:MMU)
メモリ 2.5MB flash
96KB EEPROM
240KB RAM
DMA 16チャネル
A/D変換器 8/10/12ビットADC 16チャネル*2ユニット
10ビット FADC 4チャネル*1ユニット
タイマ GPTA:2モジュール
シリアルI/F ASC:2チャネル
SSC:2チャネル
ネットワーク MultiCAN:1モジュール
I/Oポート 127
TC1796
390
CPU TriCore@180MHz, DSP機能, FPU
32-bit Peripheral Control Processor(メモリ管理ユニット:MMU)
メモリ 4.0MB flash (ECC)
224KB RAM (ECC)
DMA 16チャネル
A/D変換器 ΔΣADC:4ユニット
12ビット逐次比較型 ADC:44チャネル
タイマ GTM
シリアルI/F 2xASC, 2xSSC, 2xMSC, 2xMLI
ネットワーク イーサネット 100Mbit
Multi CANモジュール(CAN:4ノード), FlexRay(2チャネル)
I/Oポート 224
TC1797
CPU Dual TriCore@300MHz, DSP機能
ロックステップコア
メモリ 4.0MB flash (ECC)
288KB RAM (ECC)
DMA 48チャネル
A/D変換器 ΔΣADC:3ユニット
12ビット逐次比較型 ADC:48チャネル
タイマ GTM
シリアルI/F ASC、QSPI、IIC
センサI/F SENT、PSI5、PSI5S
ネットワーク イーサネット 100Mbit
FlexRay、CAN、CAN FD、LIN、SPI
TC1798
CPU トリプル TriCore@200MHz, DSP機能
ロックステップコア
メモリ 4MB flash (ECC)
384KB EEPROM @125k サイクル
472KB RAM (ECC)
DMA 64チャネル
A/D変換器 6×ΔΣADC
8×12ビット逐次比較型 ADCユニット:60チャネル
タイマ GTM
シリアルI/F ASC、QSPI、IIC
センサI/F SENT、PSI5、PSI5S
ネットワーク イーサネット 100Mbit
FlexRay、CAN、CAN FD、LIN、SPI
TC27xD
391
2000年代⽇⽴製作所 HD6301ファミリー(HD63B01V1 )SH-2(SH-7051), 1994年量産開始 SH-2E(SH7068), 2002年 SH-2A-FPUコア(SH72544R), 2008年(ルネサステクノロジ) 8bit, CISC 32bit, RISC 32bit, RISC, 単精度浮動⼩数点演算ユニット内32bit, RISC, ハーバードアーキテクチャ
動作周波数 2MHz 動作周波数 20MHz 動作周波数 80MHz 動作周波数 200MHzプロセス 3.0μmCMOS プロセス 0.8μm2層アルミCMOS プロセス 0.18μmCMOS プロセス 90nmCMOSメモリー 128 Byte RAM メモリー 10 kB RAM メモリー 48 kB RAM メモリー 128 kB RAM
4 kB ROM 256 kB フラッシュメモリ 1 MB フラッシュメモリ 2.5MB フラッシュメモリ128 kB EEPROM
(三菱電機) H8/500シリーズ(H8/532) M16Cシリーズ(M16C/62P) M32Rシリーズ(M32196F) ,1997年〜 16 bit, SCIS 16bit, SCIS 32bit, RISC, FPU内蔵動作周波数 10MHz 動作周波数 10MHz 動作周波数 128MHzプロセス 1.3μmCMOS プロセス CMOS プロセス 0.18μmCMOSメモリー 1 kB RAM メモリー 10 kB RAM メモリー 64 kB RAM
32 kB ROM(PROM/マスクROM)128 + 4kB フラッシュ 1MB フラッシュ
ルネサス エレクトロニクス V850(V853), 1996年投⼊ V850E1(V850E/PHO3), 2005年〜 V850E2(V850E2/Px4), 2009年〜 RH850(RH850/E1x), 2012年〜(NEC) 32bit, RISC 32bit, RISC 32bit, RISC 32bit, 240/320 MHz ロックステップコア, FPU
動作周波数 33MHz 動作周波数 128MHz 動作周波数 80/160 MHz (heap clock)動作周波数 320MHzプロセス 0.5μmアルミ2層CMOS プロセス 0.15μmCMOS プロセス 90nmCMOS, SG-MONOSプロセス 40nmCMOS、SG-MONOSメモリー 41 kB RAM メモリー 60 kB RAM メモリー 1M プログラムフラッシュ メモリー 4MB プログラムフラッシュ
128 kB フラッシュメモリ 1MB フラッシュメモリ 80 kB SRAM 320 kB SRAM64 kB データフラッシュ
Freescale (NXP) MC68000ファミリ(MC68F375), 1990年〜 MPC5xxシリーズ(MPC565) MPC55xxシリーズ(MPC5566) MPC57xx(MPC5777M)8bit, CISC 32bit, CISC+RISC 32bit, Power Architcture, FPU内蔵32bit, Power Architcture, VLE, DSP32bit, Power Architcture, VLE, DSP, SIMO動作周波数 2MHz 動作周波数 16 MHz 動作周波数 40 MHz 動作周波数 180 MHz 動作周波数 300 MHzプロセス HCMOS プロセス CMOS プロセス 0.25μmCMOS プロセス 0.15μmCMOS プロセス 55nmCMOSメモリー 8 kB ROM メモリー 256 kB フラッシュEEPROMメモリー 1MB フラッシュ メモリー 3 MB フラッシュ メモリー 8MB フラッシュ
512 B EEPROM 8 kB SRAM 36 kB SRAM 128 kB SRAM 596 kB SRAM256 B RAM 32 kB ユニファイドキャッシュ 32 kB ユニファイドキャッシュ
Infineon Tri-Core(TC1796), 2005Tri-Core(TC1797), 2008Tri-Core(TC1798), 2010AURIX(TC27x), 201232bit, RISC/MCU/DSP32bit, デュアルコア 32bit, デュアルコア Tri-Coreベースのマルチコア・アーキテクチャ動作周波数 150MHz 動作周波数 180MHz 動作周波数 300MHz 動作周波数 200MHzプロセス 0.25μm プロセス 0.13μm プロセス 90nm プロセス 65nmメモリー 2.5 MB FLメモリー 4.0 MB FLメモリー 4.0MB FLメモリー 4 MB フラッシュ
96kB EEPROM 224kB RAM 288kB RAM 64 kB データフラッシュ240 kB RAM 472 kB SRAM
・トリプルコア (TriCore 1.6P×2, TriCore 1.6E)・2コア+ロックステップコア、センサI/F、ネットワークI/F(イーサネット、FlexRay)・第二世代(40nm、最大ヘキサコア)開発中
・最新プロセスによる高集積化・⼤容量PROM(当時世界最⼤となる32kB)・⾼速⾼精度A/D変換器(世界最速となる変換時間13.8μs)、多機能タイマ等を搭載
マイコンメーカー
・米モトローラ開発の組み込み用8bitマイクロコントローラMC6800の派生として製品化・充実したメモリ機能が特⻑
・CISC+Intelligent Timer機能(RISC)を備えた16MHz/32bitMCU・10ビットA/D変換器16チャネル、CANモジュール
・RISCコアに移⾏・40チャネルA/D変換器、1MBフラッシュメモリ
・Power PC e200コア使用(Power ISA v.2.03準拠)・高機能タイマーの搭載(eTPUs)、A/D変換器の多チャンネル化(eQADC)、セーフティ機能などに特⻑。
・AUDO Next Generation(第二世代)。クロック周波数を向上、内蔵フラッシュも充実化
・AUDO Future(第三世代)・CPUコア+32ビット周辺制御コア、TriCore 1.3(4ステージパイプライン)
・AUDO MAX(第四世代)・コアはTriCore 1.6 (5ステージパイプライン)
・V850ファミリの第一世代*第⼆世代は2000年(0.25μmCMOSプロセス,V850Eコアを使用したV850ES)。
・データ処理性能とリアルタイム制御を向上させたV850Eコアを2000年頃より投⼊・ALLフラッシュを打ち出す※V850E1コアを使用したV850第三世代シリーズ。
・V850ファミリの第4世代との位置付け・シャーシ向けのV850E2/Px4はデュアルコアによる機能安全(SIL3)に特⻑
・コアアーキテクチャはV850をベースに開発・CPUコア+周辺コア+ロックステップコア、40nmプロセス、エンジン制御用タイマ、MONOSフラッシュメモリで差別化
1980年代
・Ultra-Reliable MCUとして訴求・メインコア/ロックステップコアのマルチコア等を用いISO 26262/ASIL-Dに準拠
1990年代 2010年代
MC68HC11A8
・CMOS化による低消費電⼒化 ・リアルタイム制御(高速性)を目指し、RISCアーキテクチャを採用・周辺インターフェイスの内蔵ラインナップも増やし、組み込み用国産プロセッサの定番チップとしてシェアを確保
・多数のパルス⼊出⼒制御が必要な⽤途に向けてタイマ機能のアップグレード(ATU-Ⅱ)・コントローラエリアネット ワーク(CAN)の搭載など
・スーパースカラ方式およびハーバードアーキテクチャを採⽤し、200MHz動作時で400MIPSの⾼処理性能を実現・90nmプロセスによる⼤容量のフラッシュメモリを搭載
・三菱電機が開発した組み込み⽤マイコン・⾼級⾔語に適した徹底した直交性を持つ命令体系、コード効率の⾼さ、耐ノイズ性能の強さに特⻑
・三菱電機開発の32ビットRISCマイコン
392
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
本項では、ADAS/自動運転に関わる製品について、ルネサス エレクトロニクスの取り組みをまとめた。
ルネサス エレクトロニクス
同社は、⾞載情報端末向けSoC「R-CAR」をナビゲーション・プラットフォームから、統合コクピット・プラットフォーム、⾞載コンピューティング・プラットフォームへと発展させる形で、先進運転⽀援システム(ADAS)、自動運転へのアプローチを図っている。
出所:ルネサス エレクトロニクス資料 「R-CAR」の投入は 2011 年からである。ADAS のメイン用途となる Sensor Fusion/ADAS Control Unitに対しては、「R-CAR H1」(第一世代、2011年10月サンプル出荷)、「R-CAR H2」(第二世代、2013年3月サンプル出荷)、「R-CAR H3」(第三世代、2015年12月サンプル出荷)により対応を進めてきた。 「R-CAR H1」は、汎用OS対応の高性能CPU「ARM® Cortex®-A9 」(1GHz動作)を4つ、 ルネサスオリジナルの⾼信頼性リアルタイム処理 CPU「SH-4A」を1つ搭載し、高性能グラフィックス機能や、2つの画像認識処理コア、デュアル・フルHD処理に対応できる⾼性能動画処理IP、オーディオ処理専用DSPなどの豊富な周辺機能を内蔵したハイエンド⾞載情報端末向けのSoC として製品化した。 CPU性能12GIPSを実現し、様々なアプリケーションの同時制御やネットワーク経由による⼤容量データ処理が可能であるほか、デュアル ・ コア 「PowerVR SGX543MP2」(英 Imagination Technologies)を搭載、40Gflops(実効)、83M ポリゴン/秒のグラフィックス処理を実現している。また、トップ・ビュー等の運転者⽀援⽤にデュアル・コアの画像認識エンジン(IMP-X3)を搭載している。 現⾏モデル(2015年〜2017年)で搭載が進む第⼆世代の「R-CAR H2」は、「世界最高の応答
393
性能」、「快適なドライブを実現する運転⽀援機能」、「ソフトウェア開発の⼤幅な効率化」を⽬指し、開発されたもので、ARM「Cortex®-A15/A7」を⾞載向け SoC で初めて採用、業界最高性能となる25000DMIPS(R-Car H1比の約2倍)以上を実現し、GPU「PowerVR G6400」(H1比10倍のシェーダー演算能⼒)、画像認識エンジン「IMP-X4」(H1比4倍の性能向上)、ビデオコーデックモジュール(H.264/AVC等)等を備えた。 「R-CAR H2」は、統合コクピット・プラットフォームを担う SoC と位置付けられており、サラウンドモニタリングシステム等の先進運転支援システム(ADAS)向けには「R-CAR V2H」(2014年9月サンプル出荷)を当てた。 「R-CAR V2H」は、ADAS向けSoC第一弾として開発されたもので、CPU「ARM Cortex-A15(デュアルコア)」、GPU「PowerVR SGX531」、画像認識エンジン「IMP-X4」を採用した。製造は台湾TSMC の 28nm プロセス。サラウンドモニタリングに最適化された仕様とすることで、性能と消費電⼒のバランスを図ったとしており、カメラなどを含めたシステム全体の消費電⼒を 5〜6W 前後(SoC 単体で1.5W程度)に抑えた。
出所:ルネサス エレクトロニクス資料 これら第二世代「R-CAR」の後継となる「R-CAR H3」は、⾃動運転時代を⾒据えた⾞載コンピューティング・プラットフォームを⽬指したもので、⾞載カメラなど各種センサから⼊⼒される⼤量の情報を、リア
394
ルタイムかつ正確に処理を⾏うコンピューティング性能を強化するとことで、半⾃動運転に相当するレベル3 の自動運転システムへの対応を視野に入れる。 具体的には、ARM社の 64 ビットアーキテクチャ CPU コア「ARM® Cortex®-A57/A53 コア」を採用し、40,000DMIPS以上の処理性能を実現。また、グラフィクスコアに「PowerVR GX6650」を採用し、「R-Car H2」と比べて約3倍のシェーダー演算性能を実現した。加えて、認識処理に最適な構造を持つルネサス独⾃の並列プログラマブルコア「IMP-X5」を搭載、従来の「IMP-X4」と比較して 4 倍の認識処理性能を実現している。 「R-Car H3」は、⾞載向けSoC として世界で初めて16nmプロセスを採用し、スループット性能(処理速度)とローレイテンシ(低遅延時間)性能の向上を図るとともに、⾃動⾞⽤機能安全規格ISO26262(ASIL-B)に対応することで、⾞載情報システムだけでなく、安全運転⽀援システム等の幅広いアプリケーションに向けた⾞載コンピューティング・プラットフォームを担っていく製品と位置付けている。なお、量産は2018年を予定、2019年3月に月産10万個を計画している。
出所:ルネサス エレクトロニクス資料 2017年初めには、レベル3以上の⾼度な⾃動運転の開発に向けて、「R-Car H3」を搭載した⾞載用開発キット「R-Car スタータキット Premier」 2 セットと、高い安全性を実現するシャシー制御用ハイエンドマイコン「RH850/P1H-C」を搭載した「HAD(⾼度⾃動運転:Highly Automated Driving)ソリューションキット」を発表している。 RH850/P1x Series MCU • 2x RH850 G3M CPU's @ 240 Mhz (each with lockstep core)
395
• Flash 8MB • RAM 1MB • Security ICU-M • Ethernet 10/100 Mbps • CAN-FD 4 channels • UART/LIN 4 channels (2 enabled as LIN, 2 as UART on HAD Solution Kit) • Flexray 2 channels HADソリューションキット • Dimensions: 230 mm x 136 mm • External power supply 12V / 5A recommended (60W)
出所:ルネサス エレクトロニクス資料
このほか、2016年12月、ルネサス エレクトロニクスは⾞載⽤32bitマイコン「RH850ファミリ」として、
ADASや⾃動運転の主要センサである⾞載レーダ向けに「RH850/V1Rシリーズ」を発表している。 同シリーズの第一弾となる「RH850/V1R-M」は中距離レーダ向け製品で、アクセラレータとして DSP
を搭載。これにより、FFT といったレーダに必須のアルゴリズム、ビームフォーミング、窓関数、チャネルキャリビュレーション、ピーク検出など⾼速かつ低消費電⼒で実⾏することが可能としている。
396
また、40nm混載フラッシュメモリプロセスを採用することで、320MHzの動作周波数を実現する2個のG3MHコア(3.2DMIPS/MHz)と2MBのフラッシュメモリを搭載したほか、将来、増加することが⾒込まれる受信アンテナ数とデータ量への対応を⽬的に、レーダ信号⼊⼒⽤⾼速シリアルインタフェースとしてMIPI-CSI2(3unit×4lane)と 2MB のRAM を内蔵した。なお、サンプル出荷は2017年下半期から開始する予定である。 また、同社は、アナログ・デバイセズと共同で77/79 GHz帯レーダー・センサを開発。アナログ・デバイセズの Drive360™28nm CMOS レーダプラ ッ ト フ ォーム とルネサスのレーダ向けマイコン「RH850/V1R-M」を組み合わせることで、現在実用化されているレーダ・システムと比べ最大 3 倍の分解能を実現している。 「R-CAR V3M」は、⾃動運転に最適な、電⼒効率の⾼いディープラーニングの実装を⽬的に開発し
たスマートカメラ・ソリューションと位置付けるもので、ARM® Cortex®-A53 (800MHz) CPU×2、ロックステップ方式採用による ARM Cortex-R7 (800MHz) CPU×2、32 ビットの DDR3L-1600 向けメモリ・コントローラ、画像認識エンジン (IMP-X5-V3M)、信号処理プロセッサ (ISP)等を内蔵する。画像認識エンジンをディープラーニングの推論に利⽤し、低負荷での画像認識が可能な点が⼤きな特⻑である。 ※スマートカメラ向けの製品は3Wを越えないよう維持する計画。
出所:ルネサス エレクトロニクス資料
397
CPUコア ARM® Cortex®-A9Quad (NEON™搭載)1GHz, 10000DMIPS
メモリ 命令キャッシュ 32K バイトデータキャッシュ 32K バイト2次キャッシュ 1M バイト
CPUコア SH-4A800MHz1760DMIPS(Effective)、 5600MFLOPS
メモリ 命令キャッシュ 32K バイトデータキャッシュ 32K バイト
外部メモリ
外部拡張
グラフィクス PowerVR SGX543MP2(3D)250MHz, 2×4パイプライン, 40nmプロセス83MPoly/s, 2500MPix/s, 16GFlops/sルネサスグラフィックスプロセッサ(2D)
ビデオ機能 ビデオ表示インタフェース 2チャネル(RGB888)ビデオ入力インタフェース 4チャネル
ビデオ画像処理機能 色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理歪み補正モジュール 4チャネル画像認識エンジン IMP-X3
オーディオ機能 サウンドプロセッシングユニット 2チャネルサンプリングレート変換 10チャネルサウンドシリアルインタフェース 10チャネルMOSY DTCP暗号対応
ストレージインターフェース USB2.0ホストインタフェース 3ポート(wPHY)SDホストインタフェース 4チャネル(SDXC対応、UHS-I対応チャネ
車載インタフェース
CANインタフェース 2チャネル
暗号処理部 暗号処理エンジン AES、DES、ハッシュ関数、RSASecureRAM
周辺機器 DMAコントローラ LBSC内蔵DMAC : 3チャネルSuperHyway-DMAC : 4チャネルHPB内蔵DMAC : 39チャネル
32bitタイマ 9チャネルPWMタイマ 7チャネルI2C バスインタフェース 4チャネルSCI 8チャネルHSPI 3チャネル
割り込みコントローラ(INTC) 1チャネルクロック発振器(CPG) PLL内蔵オンチップデバッグ機能
電源電圧パッケージ 832 ピンFCBGA (27mm×27mm)性能消費電力
メディアRAM, JPEGアクセラレータ, TS インタフェース
マルチメディアカードインタフェース, SerialATAインタフェース
IEBusバスインタフェース, GPSベースバンド処理モジュール
CPU性能:12K DMIPS、グラフィックス処理:40GFLOPS(実効)、83MPoly/s
メディアローカルパス(MLB)インタフェース
1チャネル (3線/6線選択可能) (MediaLB Ver2.0に準拠、512fs(max)のデータ転送が可能)
NA
R-CAR H1(R8A77790)
DDR専用バスにDDR3-SDRAMを接続可能
データバス幅:32ビット x 2チャネル (4GB/s×2チャネル)最大動作周波数:500MHz
FLASH ROMやSRAMを直結可能データバス幅:8/16ビットPCIエクスプレス2.0 (1レーン)
3.3V(IO)、1.5V(DDR3)、1.2V(Core)、2.5V(PCIe, MLB)、1.8V(SDIF UHS-I)
Ethernetコントローラ IEEE802.3uに準拠したMAC内蔵、RMIIインタフェース、PHYデバイスと接続可能
398
CPUコア ARM® Cortex®-A15QuadVFPv4 Floating point, NEON
メモリ L1命令キャッシュ 32K バイトL1データキャッシュ 32K バイトL2キャッシュ 2M バイト
CPUコア ARM®Cortex®-A7 QuadVFPv4 Floating point, NEON
メモリ L1命令キャッシュ 32K バイトL1データキャッシュ 32K バイトL2キャッシュ 512Kバイト
CPUコア SH-4Aメモリ L1命令キャッシュ 32K バイト
L1データキャッシュ 32K バイト外部メモリ
外部拡張
グラフィクス PowerVR Series 6 G6400(3D)
ALUコア:128(FP32)、210GFlops/sビデオ機能
ビデオ入力インタフェース 4チャネルビデオcodecモジュール H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等
TS インタフェース 2チャネルビデオ画像処理機能 色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理歪み補正モジュール 4チャネル画像認識エンジン IMP-X4
オーディオ機能 オーディオDSPサンプリングレート変換 10チャネルサウンドシリアルインタフェース 10チャネルMOSY DTCP暗号対応
ストレージインターフェース USB3.0ホストインタフェース 1ポート(wPHY)USB2.0ホストインタフェース 3ポート(wPHY)SDホストインタフェース 4チャネル(SDXC対応、UHS-I対応チャネマルチメディアカードインタフェー 2チャネルSerialATAインタフェース 2チャネル
車載インタフェース
CANインタフェース 2チャネルIEBusバスインタフェースGPSベースバンド処理モジュー Galileo、GLONASS対応
暗号処理部 暗号処理エンジン AES、DES、ハッシュ関数、RSASecureRAM
IP変換モジュール, JPEGアクセラレータ
4×2 TMUs with Unified Saderアーキテクチャ、 400~533MHz
メディアローカルパス(MLB)インタフェース
1チャネル (3線/6線選択可能)
IEEE802.1BA、802.1AS、802.1QavおよびIEEE1722対応、GMII/MIIインタフェース
EthernetコントローラAVB対応
3チャネル(2チャネル: LVDS、1チャネル:RGB888)
R-CAR H2(R8A7790)
DDR専用バスにDDR3-SDRAMを接続可能最大動作周波数:800MHzデータバス幅:32ビット x 2チャネル (6.4GB/s×2チャネル)FLASH ROMやSRAMを直結可能
PCIエクスプレス2.0 (1レーン)データバス幅:8/16ビット
ビデオ表示インタフェース
399
周辺機器 DMAコントローラ LBSC内蔵DMAC : 3チャネルSYS-DMAC: 30チャネルRealtime-DMAC: 3チャネルAudio-DMAC: 26チャネルAudio(周辺)-DMAC: 29チャネル
32bitタイマ 12チャネルPWMタイマ 7チャネル
I2C バスインタフェース 8チャネル
割り込みコントローラ(INTC) 1チャネルクロック発振器(CPG) PLL内蔵オンチップデバッグ機能
電源電圧パッケージ 831 ピンFCBGA (27mm ×性能消費電力
R-CAR H2(R8A7790)
R-Car H1と比較して約6倍の消費電力効率
クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF)
4チャネル(SPI/IISサポート)
3.3/1.8V(IO)、1.5/1.35V(DDR3)、1.0V(Core)
CPU性能:25K DMIPS、グラフィックス処理:170 GFLOPS
Ethernetコントローラ IEEE802.3uに準拠したMAC内蔵、RMIIインタフェース、PHYデバイスと接続可能
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)
10チャネル
クワッド・シリアルペリフェラルインタフェース(QSPI) ×
1チャネル(boot対応)
CPUコア ARM® Cortex®-A15Dual, VFP, NEON1GHz, 7000DMIPS
メモリ L1命令キャッシュ 32K バイトwith ECCL1データキャッシュ 32K バイト with ECCL2キャッシュ 1M バイト with ECC
外部メモリ
外部拡張
画像認識 ルネサス画像認識コア IMP-X4視点変換 ルネサス視点変換コア IMR-LSX3, 6チャネル
ルネサス視点変換コア IMR-LX3 1チャンネル
グラフィクス PowerVR SGX531(3D)2/1 Pixel-/Vertexshade1.6GFLOPS (200MHz)ルネサスグラフィックスプロセッサ(2D)
ビデオ機能ディスプレイユニット
ネットワーク CAN 2チャネルEthernet AVB 1000 Mbps, 100 Mbps
IEEE802.3 PHYインタフェース 対応電源電圧パッケージ 647ピン FCBGA
データバス幅:8/16ビット
R-CAR V2H(R8A7792)
DDR専用バスにDDR3-SDRAMを接続可能データバス幅:32ビット x 1チャネル, 800MHzECCFLASH ROMやSRAMを直結可能
3.3/1.8V(IO)、1.5/1.35V(DDR3)、1.03V(Core)
外部メモリ上のデータを変換
6チャンネル 最大12ビット パラレル YCbCr4222 チャンネル(24ビット RGB)DRC(ダイナミックレンジコンプレッション) 2チャンネル
外部メモリ、Video InputまたはH.264/JPEGデコーダーからダイレクトにIMR-LSXへ接続、変換データを外部メモリへ格納
400
CPUコア ARM® Cortex®-A57Quad, NEON,1.5GHz
メモリ L1命令キャッシュ 48K バイトL1データキャッシュ 32K バイトL2キャッシュ 2M バイト
CPUコア ARM®Cortex®-A53 Quad, NEON, VFPv41.2GHz
メモリ L1命令キャッシュ 32K バイトL1データキャッシュ 32K バイトL2キャッシュ 512Kバイト
CPUコア ARM®Cortex®-R7, Dual Lock-Step対応メモリ L1命令キャッシュ 32K バイト
L1データキャッシュ 32K バイト外部メモリ
外部拡張3Dグラフィクス IMG PowerVR Series6XT GX6650
USC(Universal Sader Cluster):6ALUs:192(FP32), 384(FP16)600MHz, 230GFLOPS
ビデオ機能 ビデオ表示インタフェース 3チャネルビデオ入力インタフェース 8チャネルビデオcodecモジュール H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等IP変換モジュールJPEGアクセラレータTS インタフェース 2チャネルビデオ画像処理機能
歪み補正モジュール 4チャネル(IMR-LSX4)画像認識エンジン IMP-X5
オーディオ機能 オーディオDSPサンプリングレート変換 10チャネルサウンドシリアルインタフェース 10チャネルMOSY DTCP暗号対応
ストレージインターフェース USB3.0ホストインタフェース 1ポート(wPHY), DRD対応USB2.0ホストインタフェース 3ポート(wPHY)SDホストインタフェース 4チャネル(SDR104対応)マルチメディアカードインタフェー 2チャネルSerialATAインタフェース 1チャネル
車載インタフェース
CANインタフェース 2チャネル, CAN-FD対応RGMII
暗号処理部 暗号処理エンジン 2チャネル(AES、DES、ハッシュ関数、SecureRAM
メディアローカルパス(MLB)インタフェース
1チャネル(3線式)
Ethernet AVB (802.1BA)
リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、超解像、回転、Lossy圧縮、可逆データ伸張
Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵インタフェース
R-CAR H3_R8J77950(SiP), R8A77950(SoC)
DDR専用バスにLPDDR4-SDRAMを接続可能最大動作周波数:1600MHzデータバス幅: 32ビット × 4チャネル (12.8GB/s × 4チャネル)PCIエクスプレス2.0 (1レーン) x 2チャネル
401
周辺機器 DMAC SYS-DMAC x48チャネルRealtime-DMAC x16チャネルAudio-DMACx32チャネルAudio(周辺)-DMAC x29チャネル
32bitタイマ 26チャネルPWMタイマ 7チャネル
I2C バスインタフェース 7チャネル
割り込みコントローラ(INTC) 1チャネルクロック発振器(CPG) PLL内蔵オンチップデバッグ機能
電源電圧
性能消費電力 NA
R-CAR H3_R8J77950(SiP), R8A77950(SoC)
4チャネル(SPI/IISサポート)
3.3/1.8 V(IO), 1.1V(LPDDR4), 0.8V(core), 2.5V(EthernetAVB)
CPU性能:40K DMIPS、グラフィックス処理:290 GFLOPS(倍精度FP)
シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)
11チャネル
Ethernetコントローラ IEEE802.3uに準拠したMAC内蔵、RGMIIインタフェース、PHYデバイスと接続可能)
デジタルラジオインターフェース(DRIF)
4チャネル
クワッド・シリアルペリフェラルインタフェース(QSPI) ×
2チャネル(HyperFlash対応)
クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF)
パッケージ 1255 ピン SiPモジュール 0.8mmピッチ (42.5mm × 42.5mm), 1384 ピンFCBGA 0.5mmピッチ (21mm × 21mm)
402
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記)
本項では、ADAS/自動運転に関わる製品について、主要プレイヤーである Intel/Mobileye、NVIDIA、NXP Semiconductor、Infineon、Samsungについてまとめた。
Intel/Mobileye
Intel は 2009 年から Google のロボットカー(呼称、グーグルカー)の開発を支援するなど、水面下で自動運転技術の研究開発に携わってきたが、2015年3月に米FPGA大手のAltera を買収(買収⾦額:約167 億米ドル)、さらに、2017 年 3月には⾼度な画像認識技術により ADAS関連市場で存在感を高めていたイスラエルのMobileyeを約153億ドルで買収し、⾞載半導体分野、とりわけ、ADAS/自動運転関連での展開強化に本腰を入れている。 2017年1月、Intelは「インテル GO 自動運転ソリューション」を発表、その後のMobileye買収を経て、「インテルGO 自動運転ソリューション」の具体的な内容も徐々に出揃いつつある。 インテルは、「インテルGO」について⾃動⾞からクラウドまでを網羅した⾃動運転向けソリューションとして
提供していく考えで、⾞載開発プラットフォームはCPU、FPGA、ディープラーニング用のハードウェア・アクセラレーション・テクノロジーなどを含む柔軟性に優れたアーキテクチャを展開していく。
図 インテル® GO™ 自動運転ソリューション
出所 Intel資料より抜粋 また、⾃動⾞向け 5G プラットフォームは、サブ6 GHz および28 GHz ミリ波の2つの周波数帯でマ
ルチレイヤーの MIMO 伝送をサポート。グローバル・ネットワーク・パートナーが提供する 5G 対応の無線
403
アクセス・インフラストラクチャと相互運用性を備えたArria 10 FPGA及びRFIC を基盤として提供し、⾼精細マップのリアルタイムのダウンロード、⾞載インフォテインメント(IVI)用の HD コンテンツ、ファームウェアおよびソフトウェアの無線によるアップデート、⾞両からのセンサーデータのアップロードによるマシンラーニング、安全性向上、スマート・インターセクション、協調⾛⾏につながるユースケースを想定したアプリケーション開発およびテストを支援している。 インテル GO⾞載開発プラットフォームでは、Intel Atom プロセッサ版及びインテル Xeon プロセッサ
版のリファレンスがあるが、特に本命と目されるのがIntel Atomプロセッサ版である。これまでにBMW、デルファイ、Baidu がインテルの技術を採⽤して⾃動運転⾞の開発を進める計画を表明。BMW は Intel GOの発表と同日の2017年1月4日、インテルおよび Mobileyeとともに、Intel GO を搭載した自動運転⾞約40台の公道テストを2017年内に実施すると発表している。 <Intel Atom® プロセッサ版構成>
• 次世代の⾃動⾞向けIntel Atom® プロセッサ インテルの 14nm テクノロジーに基づく電⼒効率に優れたマイクロアーキテクチャーを採⽤。AEC-Q100 Grade 2 対応で、シングルプロセッサ・システムではSafety Elements out of Context (SEooC) でISO26262 ASIL C 認定、デュアルプロセッサー・システムではASIL D認定となる予定。 • Arria® 10 FPGA • Infineon* AURIX* マイクロコントローラ(MCU) • Elektrobit EB robinos • ON Semiconductor電源管理IC (PMIC)
404
インテルGOの中では、いまのところあまり触れられていないが、Intelグループの一員となったMobileyeの動きも活発である。 Mobileyeは1999年、独⾃のアルゴリズム処理により単眼カメラで⾞両検知が可能なビジョンシステムの研究開発を⾏っていたAmnon Shashua教授を創業者とし設⽴された。その後、同社が保有する画像処理アルゴリズムに最適化されたプロセッサチップ(EyeQ チップ)を開発。比較的低コストで前⽅⾞両衝突警報、突緩和システム、前⽅⾞間距離警報、アダプティブクルーズシステムなどの先進運転支援機能が実現可能といった点から多くの OEM・モデルで採用され、2017年末の時点でEyeQ チップ搭載の⾃動⾞台数は 2,400万台以上にまで拡⼤している。なお、同社はファブレスの⽴場を採っており、2005年よりSTMicro とチップの製造及び開発に関するパートナーシップ関係を結んでいる。 現在、EyeQ チップは第 3 世代の「EyeQ3」から第 4 世代目となる「EyeQ4」への移⾏期にあたる。これから本格的に搭載がはじまるEyeQ4はVMP(Vector Microcode Processors, 命令セットアーキテクチャ:VLIS, SIMD)、MPC(Multithreaded Processing Cluster, 並列処理)、PMA(Programmable Macro Array)及びマルチコア CPU 等で構成されており、演算性能:2.5TOPS、消費電⼒:3W という高いパフォーマンスを実現したものとなっている。 また、EyeQ4からは新たな機能としてマッピング及びローカライゼーションのend-to-endソリューションとしてRoad Experience Management™ (REM™)が追加された。レベル3以上の⾃動運転⾞では⾼度な状況認識のためにも⾼精度な地図情報(HD マップ)が必要とされるが、専⽤⾞による情報収集を基に HD マップを作成したとしても、⽇々変わる道路状況を⼗分にアップデートしきれないという問題がある。そのため、現在は ADAS 機能、⾃動運転機能が盛り込まれた⾃動⾞に搭載されたカメラ画像等からデータを収集し、クラウド上で⾼精度マップ作成⽤のプローブデータとして利⽤しようという動きもある。 しかし、最近の⾞載カメラは解像度が数 M ピクセルクラスまで上がっており、クラウドを介してやり取りす
るには重過ぎるといった課題がある。同様に、今後、⾃動運転技術の導⼊に伴い⾞⾞間/路⾞間通信による安全性向上等が期待されているが、通信遅延がクリティカルな状況を生み出す可能性があるなど、肥大化するプローブデータの取扱いが重要視されるようになってきている。Mobileye「REM」はこうした課題に応える技術として大きな注目を集めており、特にそのデータ圧縮技術(10KB/km 未満)に対する評価は高い。実際、EyeQ4 の実装が進む 2018 年中にも BMW、VW、日産が REM 技術の利⽤を開始する⾒込みである。 Mobileye はこの技術に関し、HERE 社との戦略的提携を発表した。Mobileye の“Roadbook”を
HERE の HD Live Map の中にレイヤーとして組み込み、Mobileye は HERE の Open Location Platform を活⽤するなど、お互いが近接したビジネス領域での協業を⾃動⾞⽤途に限らず展開していく。 また、日本におけるHDマップの作成においてゼンリン社と協⼒する。2018年10月にはREM技術と
ゼンリンの技術を⽤いてすべての⾼速道路上においてレベル3の自動運転ができるようHDマップを完成させる。さらには2020年にすべての⽇本国内の道路のHDマップ化を目指す。これはMobileye-ゼンリン-OEMの3者協⼒の取り組みとして進めていく⽅針である。
405
低消費電⼒性能は、今後の経済的な持続性に致命的な影響を与える。将来的にEV と自動運転⾞が共存していくことを考えると、⾞載におけるデータ処理に必要な消費電⼒の性能がEVの継続⾛⾏距離に与える影響は⼤きいとみられる。さらに将来に向けた拡張性を有した製品であるかどうかも重要である。EyeQチップを⽤いた拡張性の例として、例えば、レベル5⾞両の⾞載カメラ構成について、4台の1.3MPカメラと7台の8MPカメラを想定している。その際には、2個のEyeQ5チップによりパワーアップされ、インテル製の高性能CPU と組み合わされた⾼度に洗練されたシステムとなると考えている。
図Mobileye/EyeQ4 ブロックダイアグラム
出所 MIPSホームページ
406
<EyeQチップファミリ> EyeQ3:4 x VMP + 4 x CPU、40nm、2014年11⽉量産開始、0.25TOPs @ 3W EyeQ4H:6 x VMP + 2 x PMA + 2 x PMC + 4 x CPU、28nm、2.5TOPs @ 6W、2018年3⽉量産開始、採⽤⾃動⾞メーカー:BMW、VW、日産、現代・起亜、Ford、GM、ホンダ、など EyeQ5H:7nm、24TOPs @ 10W、1次試作サンプル2018年8⽉、量産開始2020年3月。なお、CES2018(2018年1月)では数か月後にEyeQ5/ATOMのサンプル出荷を開始予定とアナウンス
407
NVIDIA
NVIDIA は、グラフィックス処理や演算処理の⾼速化を主な⽬的とする GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)の開発販売を目的に 1993 年に設⽴された。家庭用ゲーム/3D グラフィックスの発展とともに成⻑、現在では世界を代表するGPUベンダーとなっている。 GPU は、定形かつ⼤量の演算を並列にパイプライン処理することが重視されており、高速の VRAM と
接続し、グラフィックスシェーディングに特化したプログラマブルな演算器(シェーダーユニット)を多数搭載している。最近ではこうした超並列演算性能をグラフィックス以外の計算にも活⽤する「GPGPU」が盛んに⾏われるようになっており、HPC分野等での利⽤も進んでいる。 現在、NVIDIA の GPU コアは Pascal 世代
(2016年4⽉〜)からVolta世代(2017年5⽉〜)への移⾏期となっている。Voltaは16nmプロセスから12nmプロセス(いずれも台湾TSMC)へのシフトにより、201 億個以上のトランジスタを搭載、新たに CUDA コアと Tensor コアを組み合わせた新しいGPUアーキテクチャを採用している。これは、HPC に加え、ビッグデータ解析や機械学習、ディープラーニング、AI といった⼤量の演算を要する⽤途や、超高速取引のように極限まで低レイテンシが求められる分野でのGPU利⽤が拡がっていることを受けたもので、Volta世代のファーストリリースとなったデータセンタ向けの Tesla V100(GV100 コア) は、前世代の NVIDIA Pascal アーキテクチャの 5 倍以上の速度となる1 秒あたり 100 テラフロップス (TFLOPS) のディープラーニング・パフォーマンスを実現している。 NVIDIAでは、既にVoltaの後継となるGPUコアの開発にも着手、微細化(10nm?)等により集
積度の向上を図ることで、さらなる超⾼速演算性能の実現に取り組む考えで、年平均 1.5 倍の性能向上(低消費電⼒化)に⾃信を⾒せる。
410
演算性能でみたGPU vs CPU 出所 NVIDIA資料
NVIDIA は、スーパーコンピュータ、ワークステーション、PC、モバイルといった各アプリケーションに対し
一つのアーキテクチャで対応する“ONE-ARCHITECTURE”を採っており、⾞載 AI プロセッサはモバイル用途のカテゴリーから派生する形で展開。Tegra K1から現⾏のParker(Pascal世代)へと製品化が進められ、2018年1QからはVolta世代のXavierがサンプル出荷となっている。
図 NVIDIA ONE-ARCHITECTURE 概念図
出所 NVIDIA資料
413
また、NVIDIA は⾞載 AI プロセッサを搭載した⾞載モジュールを「DRIVE PX」として製品化、ハー
ドウェア、ミドルウェア、Drive Works、Drive IX等の各種ソフトウェアを自動運転プラットフォームとしてユーザーへ提供している。
414
現⾏のDRIVE PXプラットフォームは、Pascal世代の「DRIVE PX2」をベースとしたものとなっている。 「DRIVE PX2」はTegra Parker×2+ディスクリートGPU×2+CPUコアで構成、120 SPECInt(整数演算性能)、20DL TOPS(ディープラーニング演算性能)の演算性能を誇るが、消費電⼒(最⼤出⼒時80W)の大きさを指摘する声も少なくなかった。これに対し、NVIDIAは2017年10月に開催したGPU EUROPE(ドイツ)において、Volta世代であるXAVIERを発表、2018年1Qからサンプル出荷を開始することを明らかにしている。 Xavier は、新たな GPU アーキテクチャである Volta、カスタム CPU 8 基の CPU コアアーキテク
チャ、新たなコンピューター・ビジョン・アクセラレータが統合されたSoCで、プロセッサは毎秒20兆回の演算を処理する性能ながら、消費電⼒はわずか 20w。ISO 26262 機能安全規格など、重要な自動⾞規格に準拠して設計されている。
図 DRIVE PX2概要 出所 NVIDIA資料
415
図 XAVIER概要 出所 NVIDIA資料
2017年10 月の GPU EUROPE では、レベル 5 の自動運転技術への適用を想定した「DRIVE
PX」の最新版、「DRIVE PX PEGASUS」も発表している。DRIVE PX PEGASUSは、2 つのXavierと2つの次世代GPU(Voltaの次)を搭載。また、システム全体のメモリ帯域を1TB/秒に高速化するとともに、機能安全の ASIL D、CAN、Flexray、16 個のセンサー⼊⼒(カメラやレーダー、ライダーなど)、複数の10G ビットイーサネットにも対応するなどの機能面の充実化を図っている。 この結果、DRIVE PX PEGASUSのディープラーニング演算時の処理能⼒は320TOPS という桁違
いのレベルに達し、これにより、⾃動⾞メーカーはレベル 5 の自動運転をこのナンバープレートサイズのボードだけで実現できるとしている。DRIVE PX PEGASUSは2018年の半ばにも出荷する⾒込みである。 レベル 4 以降の運転者が不要な⾃動運転技術は、商⽤⾞での実⽤化(いわゆるロボカー)が当面
のターゲットになってくるが、NVIDIA はドイツの郵便会社である DPDHL(Deutsche Post DHL Group)が、同社が計画している⾃動配送⾞に、NVIDIA の DRIVE PX をベースに作られている ZFの「ProAI self-driving system」を採用する計画であることを明らかにしている。それによれば、DPDHLが計画している24時間365⽇稼働する⾃動配送⾞のAIエンジンとして、DRIVE PX といった NVIDIA の⾃動⾞向けソリューションが採用され、“ラストワンマイル”と呼ばれる配送事業者の拠点から企業や個⼈宅などへの配送を⾃動配送⾞によって⾏なう計画としている。 また、NVIDIAは DRIVEプラットフォームにおいて、ハードウェアだけでなく、ソフトウェアの面からも自動
運転アプリケーションの開発をサポート、各種フレームワークに対応した NVIDIA ディープラーニング SDK
417
(ソフトウェア ライブラリ、フレームワーク、ソース パッケージ)をはじめ、シミュレーションツールや機能モジュール(API)等のソフトウェア開発キット(DRIVEWORKS)などの充実したソフトウェア環境を整備している。
出所 NVIDIA資料
418
ハードウエアに対する期待、整った開発環境から、現在、OEM、Tier1、研究機関、スタートアップ企業といった様々なレイヤーの企業がNVIDIA とパートナーシップを結び、自動運転技術の研究開発を後押ししている。
NVIDIA ⾞載製品パートナー 出所 NVIDIA資料
2018年1月初めのCES2018でのプレスカンファレンスにおいては、VWへの自動運転技術提供を
発表している。具体的には、フォルクスワーゲンのEVブランド「I.D.」から登場予定の「I.D. Buzz」(2022年頃の投⼊を計画するMPV)に、NVIDIAの自動運転技術「DRIVE IX」を提供する。「DRIVE IX」は、NVIDIA DRIVE PX ハードウェアとの組み合わせで AI Co-Pilot を実現するためのプラットフォームで、顔認識/視線追跡、ジェスチャー認識、⾃然⾔語処理、音声スピーチ機能、拡張読唇機能等のAI技術を活用していく方向性が示されたものとなっている。
420
NXP Semiconductors
2015年12月、NXPは⾞載半導体⼤⼿の⼀⾓であったFreescale Semiconductor と経営統合し、⾞載半導体分野でのトップメーカーとなっている。なお、Qualcommは2016年に380億米ドルで NXP を合併買収すると発表したが、当初の計画であった 2017年内の買収完了が中国規制当局との交渉難航等が影響し、2018年初頭にずれ込んでいる。 NXP はADAS/自動運転関連向けにドメインのマイコンをはじめ、レーダ・システム、V2X システム・ソリ
ューション、ビジョン・プロセッサ、センサ・フュージョン等の幅広い製品を展開している。
マイコンに関しては2017年10月、コネクテッドカー、電気⾃動⾞、⾃動運転⾞向けの制御/コンピュ
ーティング・コンセプトとして「NXP S32プロセッシング・プラットフォーム」を発表している。 「NXP S32 プロセッシング・プラットフォーム」は、統一化されたアーキテクチャのマイクロコントローラ/マイ
クロプロセッサ(MCU/MPU)製品群と、多様なアプリケーション・プラットフォームに対応可能な単一のソフトウェア環境を提供する、完全にスケーラブルな⾞載コンピューティング・アーキテクチャの実現を目指したもので、NXP の IP を使用した S32 マイコンが、異なるテクノロジー・ノード上においても共通のファンクションを構築し、一貫したアーキテクチャと挙動を示すハードウェアとソフトウェアを提供できる点が⼤きな特⻑となっている。これにより、ソフトウェアの流⽤性、再利⽤率が⾼まり、⾃動⾞開発の⼤きな問題であるソフトウェア開発負担を大幅に軽減できるとしている。このメリットの大きさから、既に大手OEM9社が次世代モデルの開発に採用しているようだ。
421
図 S32プロセッシング・プラットフォーム
S32プラットフォームは、インフォテインメント⽤プロセッサを除く、全ての⾞載プロセッシングをカバー(イン
フォテインメント用プロセッシング向けには「i.MX」ファミリを展開)。各 MCU/MPU は⾼度にハードウェア・アーキテクチャを共通化し、スケーラビリティ、互換性を備える。プロセスは16nmプロセスと40nmプロセスと2種類のプロセス・テクノロジーを最適な機能に対応するよう使い分けていく方針である。 全デバイス共通のハードウェアには、CANやLIN、I2C、Ethernetなど標準インターフェイスなどの基本
ペリフェラルセットに加え、セーフティ・コンセプト、セキュリティ・コンセプトに沿った仕組みを導入。セーフティ・コンセプトについては、機能安全規格「ISO 26262」に基づくテスト規格で最も高い安全性レベルである「ASIL-D」対応としている。セキュリティ・コンセプトに関しては、ローエンドのMCU も含む全ラインアップにハードウェア・セキュリティ・エンジン(HSE)を内蔵し、ソフトウェアの改ざん防⽌や⾞内外の通信を安全に⾏える環境を整える。 さらに全デバイスに共通する機能として、ゼロ・ダウンタイム OTA(Over-the-Air)機能を実施できるようにする考えである。市場投入後の機能追加やセキュリティ強化などのため、無線通信経由でソフトウェア・アップデートを⾏うOTA機能は、⾞載MCU/MPUの必須の機能となりつつある。S32プラットフォームでは、セキュアなゲートウェイを経由し、ECUの稼働を止めずにアップデートできるゼロ・ダウンタイムOTAを実現する計画である。 一方、ドメインごとに、より機能を強化する専用のハードウェアも充実化する方針である。S32 プラットフォームでは、ドメインをボディ向けなどの「汎用」、「セーフティ/パワートレイン」、「レーダ」、「ゲートウェイ」、「ビジョン」、「センサ・フュージョン/自動運転」と6つのアプリ/機能別ドメインを定義、それぞれのドメインに適したアクセラレータを開発設計し、搭載していく。機械学習などの AI活⽤が⾒込まれる「レーダ」、「ビジョン」、「センサ・フュージョン/自動運転」などのドメインでは、多彩な AI アクセラレータが⽤意される⾒込み
422
としている。 センサ・フュージョン向けでは、2017年9月に第2世代APEX-2 ビジョン・アクセラレータを使用したセーフティ・フュージョンと高性能プロセッシングを融合した「S32Vプロセッサ」のサンプル出荷を開始している。同製品は従来のGPUベース・ソリューションに⽐べ⾼速かつ低消費電⼒で画像データを処理する128パラレル・コンピューテーショナル・ベクトル・ユニットを備えたデュアル APEX-2 エンジンを搭載しており、低消費電⼒、⾼性能、機能安全、セキュリティが特⻑となっている。
図 S32V234 ブロックダイアグラム
出所 NXP資料 低消費電⼒:10w 未満のビジョン・プロセッシング・ソリューション。GPU 搭載または非搭載オプションともにファンレス設計可能
高性能:1GHz の Arm® Cortex®-A53 クワッドコアによる最高 10k DMIPS と、GC3000 Vivante GPUおよびデュアルAPEX-2 ビジョン・アクセラレータによりさらなる高性能を実現
機能安全:ISO 26262 とIEC 61508への準拠のため、Arm Cortex-M4 MCUコア、Arm Cortex-A53 セーフティ・クラスタ、エンド・ツー・エンド ECC、FCCU(Fault Collection and Control Unit)、FMEDA(Failure Modes Effects and Diagnostics Analysis)を搭載
セキュリティ:Cryptographic Service Engine(CSE)はSHEプロトコル仕様に適合、128ビット暗号化、真性乱数発生(RNG)可能
NXP は 2018 年頭、S32V を含むセンサ・フュージョン向けソリューションの導入加速化を目的に、Daimler 等を顧客に持つ LG Electronics、ビジョンセンシング等のアルゴリズムで優位な⽴場を築くHELLA Aglaia とのコラボレーションを発表、3社の技術を持ち寄りAutomotive Vision Platform と
423
して展開していくことを明らかにしている。当⾯のターゲットは歩⾏者や⾃転⾞への対応が求められることになる「NCAP 2020」に適用可能なビジョンセンシング・ソリューションの提供としているが、LV3 以上の自動運転⾞を⾒据えた取り組みもAutomotive Vision Platformの中で進めていく考えのようだ。 また、NXP は 2016 年に発表した ADAS 向けコンピューティングユニット「Bluebox」のアップデート「Bluebox 2.0」も近く発表予定である。「Bluebox」は「S32V」と高性能/高演算のARMコアのアーキテクチャを搭載した「LS2088A」を組み合わせたもので、9万DMIPS という⾼い処理能⼒を40Wの電⼒消費で実⾏できる点を訴求していた。「Bluebox 2.0」についての詳細は明らかでないが、同社は「Bluebox 2.0」をベースとした「Automated Drive Kit」を用意、これにAutonomouStuffが開発したソフトウェアと組み合わせた開発プラットフォームを⾃動運転⾞開発ソリューションとして市場投入していきたい考えを有しているようだ。
図 Bluebox ブロックダイアグラム 出所 NXP資料より
また、これら取り組みとは別に、NXPは2017年6月、コンチネンタル子会社のエレクトロビットとの提携を発表している。エレクトロビットはコネクテッドカーのインフラストラクチャ、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)技術、ナビゲーション、ドライバーアシスタント等に関わるソフトウェア技術を得意としており、先進的な状況検知とパス・プランニング機能を可能にする AI も搭載したソフトウェア・フレームワーク「EB robinos」などを手掛けている。NXP は「BlueBox」自動運転開発プラットフォームとこの「EB robinos」ソフトウェア・フレームワークを組み合わせることで、OEM が⾼度⾃動運転機能の開発を容易にすることを目指すとしている。 このほか、NXP は2017年12月、中国Baidu と提携したことを発表している。具体的には、Baiduが主導する「Apollo Open Autonomous Driving Platform」にNXPが参加、ミリ波レーダ、V2X、
424
セキュリティ、スマート・コネクティビティ、⾞内ユーザー・エクスペリエンス技術などの半導体製品やソリューションを提供するとともに、NXPとBaiduの両社でディープラーニングネットワーク向けのセンサ・データの統合と高性能プロセッサの開発に取り組むほか、Baidu の⾞内⾳声会話システムである Apollo 向けDuerOSにNXPのインフォテインメント・ソリューションを統合することなどが提携内容に盛り込まれている。 なお、⾞載インフォテインメント向けでは、NXP はサムスングループの Harman International との関係強化も図っており、製品仕様の共同作成、初期サンプルの交換、Rinspeedなどのパートナーとの新しい⾞両コンセプトのデモンストレーションを含む先⾏開発において一層の協⼒関係を構築していくことを明らかにしている。
425
Infineon Technologies
インフィニオンは ADAS/自動運転向けとして AURIX マイクロコントローラファミリ、⾞載⽤レーダ、TOFカメラセンサ、センサ・フュージョン⽤チップ等を展開している。特に⾞載⽤レーダではリーディングポジションを構築している。 AURIX マイクロコントローラファミリのハイエンドラインは、現在TC29x、TC27x、TC290(Bare die)
となっている。TC29xはTC1.6Pコア(FPU及び64KB PSPR, 32KB PCACHE, 240KB DSPR, 16KB DCACHE を内蔵)のトリプルコアをメインにメモリ:8MB フラッシュ及び 768KB フラッシュ(EEPROM機能)、DMA:128 チャンネル 、各種DSP を備える。インフィニオンがロードマップで明らかにしている第二世代の AURIX TC3xx は TC1.6P(300MHz)のマルチコア(最大 6 コア)、16MBフラッシュ、6MB超のコア内蔵RAM、その他、レーダプロセッシングに最適化されたSPU(Signal Processing Unite)、Gigabit EthernetmCAN FD等を備える⾒込みである。 同社は、NVIDIA/DRIVE PX プラットフォームのユーザーがAUTOSAR準拠のソフトウェアスタック上
で AURIX の機能を利⽤できるようにするなど、マイコンに関しては NVIDIA とのコラボレーションに軸足を置いている。 レベル 3⾃動運転機能を搭載した世界初の量産⾞となる Audi A8 では、コントロールユニットである
zFASに同社のマイコン(TC297T)が採用されている。同マイコンは最高1,800 DMIPSのリアルタイム・パフォーマンス、ロックステップコア、冗⻑性を持つ周辺機器、内蔵された監視システムなどを基に⾼度な機能安全性の実現に役割を果たしている。
426
また、Audi A8では正面とコーナーのレーダに同社のレーダ用センサチップ(RASIC ファミリー)が使用
されている。これは 77-GHz の⾼周波信号の送受信を⾏い、それを中央の運転⽀援コントローラ(zFAS)に送るものであるが、インフィニオンでは近い将来、レーダ IC、マイコン、電源をチップセット化し、⾞載⽤レーダソリューションとして展開する考えを有している。 このほか、インフィニオンは、単眼カメラで測距が可能な TOF(Time-of-Flight)カメラ用チップ
(REAL3 Image Sensor)の製品化に取り組んでいる。既にスマートフォン等のコンシューマエレクトロニクス向け製品(IRS1125C/IRS1645C)の量産化を⾏っており、現在⾞載グレード(IRS1125A)を開発中である。これらは解像度が〜100K ピクセルと低解像度のため、⾞載向けについてはインキャビン・センシング・アプリケーション向けでの展開を想定しているようだ。
428
Samsung
サムスン電子は2016年末に⽶⾃動⾞部品⼤⼿のHarman Internationalを80億米ドルで買収、⾃動⾞分野での展開強化を図っている。その後、2018年1月のCES2018において自動運転向けの開発プラットフォーム「DRVLINE」を発表した。 同社はエレクトロニクスデバイス(スマートフォン、TV等)、ホームアプライアンス(冷蔵庫、洗濯機等)
といった広範なプロダクトラインを有し、これらをインターネットで接続した IOT、Connected な生活空間の提供を現在の事業戦略の柱としている。⾃動⾞に関しても「Connected Car」をキーワードとしたビジネスモデルの構築を進めており、自動運転開発プラットフォーム「DRVLINE」はその基盤と位置付けられている。 「DRVLINE」は、OEMがソフトウェアをカスタマイズ/拡張したり、個々のコンポーネントや技術を必要に
応じて入れ替えることができる、モジュラーかつスケーラブルなハードウェア/ソフトウェアの提供を目指すもので、サムスングループ以外の企業も参画できるオープンなものとなっている。実際、ソフトウェア;TTTech、 AImotive、 Hella Aglaia、Renovo Auto、⾞載コンピューティング;Graphcore、ThinCi、Infineon、コミュニケーション;Autotalks、Valens、センサ;Quanergy、Tetravue、Oculii、 Innovizが既に「DRVLINE」に参加している。 サムスンは、ハーマンと共同開発した ADAS 向けカメラシステムが開発中であることを明らかにしている。同システムは⾞線逸脱警報、前⽅衝突警報、歩⾏者検出、⾃動ブレーキに対応したもので、2018 年中のサンプル出荷開始を予定しているようだ。また、高速データ通信が可能な 5G-ready antenna を含む5G Automotive Telematics Solutionの開発も順調に進んでいるとしており、既に欧州OEMでの採用が決定しているとしている。 このほか、Harman が得意とするインフォテインメント製品の延⻑として各種機能・デバイスを統合した
Digital Cockpit やこれに付随したクラウドサービス(Harman Ignite Platform)を提案するなど、同社は高性能コンピューティングからセンサ、AI、クラウド、通信に亘る広範な領域において⾞載分野での展開を強めている。
出所 Harman Internationalホームページ
430
XILINX
FPGA大手のXILINXは、FPGAのメインマーケットである通信・データセンタ分野に加え、⾞載分野を事業成⻑の柱と位置付けている。⾞載分野では ADAS 関連をメインのアプリケーションとしており 12 年以上の出荷実績を持つ。FPGA の⼀番の特⻑は ALL-PROGRAMMABLE という点にあるが、日々進化し続ける ADAS/AD技術に対し、Adaptability(適用性)、Aggregation(統合)、Acceleration(加速)の3点がユーザーに選ばれている理由としている。
ADAS/AD 関連の中では、フロントカメラモジュール向けが主⼒ビジネスとなっている。2017 年における同⽤途向けのユニット出荷量は470万個程度。これは当該マーケットのシェア 38%を示していると同社では推計している。また、最近開発が活発化している LiDAR 関連ではバレオ、コンチネンタルを含め、Velodyneを除く全ての企業がXILINXのFPGAを使用している。 FPGA の良さ(フレキシビリティ、アダプタビリティ)に加え、品質、コストに勝っている点が評価されてい
る。センサの技術は常に進化している段階。最近はハードウェアも OTA でアップデートしたいといったニーズもあり、この点も FPGA が選ばれる理由とのこと。この分野ではモービルアイが競合となるが、コストはXILINX が60米ドル(エンジニアリングコストを含む)に対して、モービルアイは EYEQ4 で65米ドル、EYEQ5では120米ドルになると聞いている。EYEQ5は消費電⼒もアップ、冷却のためにクルマの機構も変えないといけないなど制約が大きく、適用性の点でFPGAに優位性がある。 また、同社は新たなターゲットとして ADAS/AD ユニットを挙げている。いわゆるセンサで認識したものを
判断するためのユニットと位置付けることができるが、ここもセンサ同様にアプリケーション・デザイン、アルゴリズムが日々変化していることから、FPGA のスケーラビリティ(拡張性)に対するニーズが高まっており、実際、コンチネンタルがXILINXの技術を自動運転コントロールユニットに採用しているとのこと。 こうした動きを受け、XILINXは2018年1月より 16nm プロセスを採⽤した最新の⾞載⽤ファミリと
なる「XA Zynq UltraScale +MPSoC」の供給を開始している。64 ビットクワッドコアの「ARM
431
Cortex-A53 及びデュアルコアの「ARM Cortex-R5」をベースとするプロセッシングシステムとプログラマブルロジックである UltraScale アーキテクチャを 1 つのデバイスに統合した同ファミリは、最適な単位ワットあたり性能に加え、AEC-Q100試験規格への準拠が認定されており、ISO26262ASIL-Cレベルに完全適合している点が特⻑となっている。同社では、消費電⼒、レイテンシ、プライスの点で⾼い競争⼒を持っているとしている。
図 ADAS/ADユニット適用時のFPGAブロックダイアグラム
出所 XILINX資料
432
表 ADAS/AD関連の主要メーカ・製品 出所 各種量を基にYRI作成
ルネサス エレクトロニクス NXP Semiconductor
R-CAR H3(R8A77950,SOC) S32V234 Tegra X1 Tegra X2 (Parker)Tegra Xavier EyeQ 3 EyeQ 4 EyeQ 5
2018年より量産予定 Preproduction 2015(SDK) 2016(SDK) 2017(SDK) 2014 2017 2020(2018年上期よりサンプル)
Quad Cortex-A57, 48K IS,32K DS
Quad Cortex-A53, 1.0 GHz,32K IS, 32K DS
Quad Cortex-A57, 1.9GHz Dual Denver2.0, 128K IS,64K DS
カスタムARMv8 CPUコア 4×MIPS-1004,500MHz
4×MIPS interAptivCPU、1GHz
8×Multi-threadingCPU
Quad Cortex-A53, 32K IS,32K DS
Cortex-M4, 133 MH Quad Cortex-A53Quad Cortex-A57, 48K IS,32K DS
*Denver進化版 2×MPC cores, 1GHz
Cortex®-R7, Dual Lock-Step対応
L2キャッシュ:2MB+0.5MB L2キャッシュ:2MB+2MB 2×PMA, 750MHz
L2キャッシュ:2M+512K L2キャッシュ:512K+ECC Coherent HMP Architecture MIPS M5150 CPU
PowerVR GX6650, 192 ALUs(FP32)
GC3000 GPU, 50GFLOPS at600MHz
GPU Maxwell 256コア Pascal 256コア GPUVolta 512 CUDA CoresTensor Core
4×VMP3, 500MHz*Vector Microcode
6× VMP4 , 1GHz 18×Vision Processors
IMP-X5, IMR-LSX4Dual APEX2CL, ISPIMAGINGFull Quad Camera imaging,Dual ISP 650Mp/s
NA 1.5GPix/s ISP
H265, H264/AVC, MPEG-4 H264, MPEG 動画 H.265, VP9 4K 60 fps ビデオ H.265, VP9 4K 60 fps ビデオ 1.2GPix/s エンコーダ1.5GPix/s デコーダ
LPDDR4-SDRAM*12.8GB/s×4チャネル
×64 LPDDR2/DDR3L/DDR3外部メモリ 64bit LPDDR4, LPDDR3,*DDR3 25.6 GB/s
128bit LPDDR4, ECC*58.4 GB/s
256bit LPDDR4*137 GB/s
40K DMIPS, 290GFLOPS(倍精度)/460GFLOPS(単精
9.2K DMIPS 処理能⼒ 512GFLOPS(FP32)/1TFLOPS(FP16),
750GFLOPS(FP32)/1.5TFLOPS(FP16), 1.3GHz
20 TOPS(INT8), 160SPECINT
0.256 TOPS, 2.5W 2.5 TOPS, 3W 12 TOPS, 5W以下
16nm FinFET-TSMC NA 製造プロセス 20 nm SOC-TSMC 16nm FinFET-TSMC 12nm FinFet-TSMC40nm CMOS 28nm FD-SOI under 10nm FinFET
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ *MPC:Multithreaded Processing Cluster
R-CAR スタータキット Premier BlueBox Drive PX Drive PX2 (AutoChouffeur)Xavier AI Car Superchip *PMA:Programmable Macro Array
R-CAR H3搭載 S32V234 2×Tegra X1 2×Tegra X2 + 2×Pascal GP1×Tegra Xavier
LS2085-8×Cortex-A72
2×64bit DDR4メモリコントローラ(2.1GT/s)
40K DMIPS, 460GFLOPS(FP90K DMIPS 処理能⼒ 850GFLOPS(FP32)8TFLOPS(FP32), 24DL TOPS 20 TOPS(INT8), 160 SPECINT
5V/4A-8A 40W未満 消費電⼒ 10W 250 W 20W
SoC
CPU
ボード
NVIDIA Mobileye
433
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
日本 日本政府ではSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)のテーマの1つとして、⾃動⾛⾏(⾃動運転)システムが採択されている。SIP の創造推進費は500 億円で、10 のテーマからなる。⾃動⾛⾏システムの配分額は24.5億円で、座⻑はトヨタ⾃動⾞顧問の渡邉浩之⽒が務める。 ⾃動⾛⾏システム実現に向けてのロードマップは、ITSによる先読み情報を活用し、2017年までに準
⾃動⾛⾏システム(LV2)、2020 年代前半に準⾃動⾛⾏システム(LV3)を市場化する。さらに2020 年代後半以降に完全⾃動⾛⾏システム(LV4)の市場化を目指すとしている。このようなロードマップを実現するために、研究開発および施策テーマは 32 件となり、この中で投資要請および準備完了のテーマは 29 件となった(残り 3 件は将来の要請を⾒越して審議を継続)。SIP が担当する研究開発領域は、⾃動⾞メーカが取り組んでいる⾃⽴型システムなどの競争領域に対して、官⺠連携での取り組みが必要な基盤技術および協調型システム領域を中⼼にしている。
図 SIP⾃動⾛⾏ロードマップ 出所:内閣府資料
435
図 SIP⾃動⾛⾏研究テーマの概要
出所:内閣府資料 各研究テーマの実施にあたっては、警察庁、総務省、経済産業省、国⼟交通省が役割分担するとし
ている(下図参照)。また、各WG と意⾒交換会も設定されており、メンバーは⺠間企業やITS Japan、JARIなどで構成される。検討課題についてはテーマごとに幹事会社が決定しており、事故低減効果⾒積もりシミュレーションはトヨタ⾃動⾞、グローバルダイナミックマップは⽇産⾃動⾞、HMI(Human Machine Interface)がホンダ、V2P(⾞歩間)通信⽤アプリはマツダが担当する。
図 SIP⾃動⾛⾏システム 研究開発の実施体制
出所:内閣府資料
436
SIP とは別に⾃動⾛⾏ビジネス検討会が、国交省⾃動運転⾞局⻑と経産省製造産業局⻑の指摘勉強会として2015年5⽉に設置し、以下の①〜④について具体化を進めている
図 ⾃動⾛⾏ビジネス検討会 出所:国⼟交通省
2016年5月には自動運転の国際化基準に対応するために自動運転基準化研究所を設置してい
る。⾃動運転に関する国際基準策定の全体戦略を策定するとともに、WP29の議論への対処⽅針の検討と基礎調査、主要国政府/メーカ/研究機関との連携、標準化活動との連携、シンポジウムの開催などを進める。
図 自動運転基準化研究会の概要
出所:国⼟交通省
437
米国 ⽶国では、⽇本や欧州のような⾞両認証制度がなく、連邦政府の定める⾃動⾞基準(FMVSS)に基づき、各⾃動⾞メーカが⾃らの責任で認証を⾏い、⾞両を販売している。⾃動⾞メーカが⾃動運転⾞両の公道実験を⾏う場合は、州法に基づく所要の⼿続きを経る事が求められる。ミシガン州の場合は、ミシガン州認定の専用ナンバープレート(M プレート)を装着し、州が認めた保険に加入する事が必要である。また、⾃動⾞メーカの従業員(⾃動⾞メーカとの契約者)により運⾏され、⾞両の⾛⾏について監視し、必要に応じて運転操作可能な⼈が乗⾞する事なども規定されている。 自動運転の公道テストが可能とする州法がある州は、ネバダ、カリフォルニア、フロリダ、ノースダコダ、テ
ネシー、ユタ、ミシガンの7州とワシントン D.Cである(アリゾナ州は法律の制定を待たずに⾏政命令で承認)。この中で、カリフォルニア、ネバダ、フロリダ、ミシガンの4州で、自動運転試験に関するルールもしくは法案が策定されている カリフォルニア州では2015年12⽉に法案を策定し、無⼈⾛⾏の禁⽌やステアリング、ペダルの装着
義務などを規定している(Googleはこの法案に反対している) ミシガン州上院に自動運転の開発を容認するための法案が2016年5⽉に提出され、⾃動運転⾞
の⽣産と販売と認め、運転席が無⼈状態での⾃動運転⾛⾏を認めるとしている⇒成⽴すれば同州12.2マイルの道路で⾃動運転のテストを実施する事が容易になる。ペンシルベイア州ピッツバーグではウーバーが公道実験を開始しており、ウーバーが買収した自動運転トラックの開発会社Ottoはコロラド州近郊で自動運転トラックによる配送業務を実施している(Ottoのトラックは⾼速道路のみを⾃動運転による⾛⾏)。
438
図 ミシガン州M Cityの航空写真
出所:ミシガン大学 ITS Strategic PlanはUSDOT(⽶国運輸省)が2014年12月に公表した国家プロジェクトで、
2015年から2019年までの5年間、5項⽬の戦略テーマを実現する6プログラムから構成されている。6プログラムカテゴリーの中で、Connected Vehicle(CV)とAutomationの2つが優先プログラムに位置づけられており、CVの実⽤化と⾃動化の進展に注⼒している。また、USDOTは自動運転、コネクテッドカー、スマートセンサを交通ネットワークに組み込んだSmart Cityの実現するための予算として4,000万ドル(42億円)を提供するプロジェクトを発表し、2016年6月にオハイオ州コロンバス市を実施都市として決定している。Mobileye、NXPセミコンダクターズ、Amazon、AT&T、Continentalなどの企業からの支援を受けて、Smart Cityの実現を図る さらに、USDOTは、ホワイトハウスのスマートシティ構想の一環として、全米でスマートシティの技術を展
開するために役⽴つ新しいファンドを発表している。1億6500万ドル(約171億円)の基⾦は2つの助成⾦を通して得られる6500万ドルの公的基⾦と、先進輸送技術を対象にした1億ドルの基⾦に分けられ、スマートシティ構想を推進するために使われる。対象となる都市にはピッツバーグ、サンフランシスコ、ヒューストン、ロスアンゼルス、バッファロー、そしてメアリーズビルが含まれる。基⾦は、交通渋滞を緩和し、またドライバーと歩⾏者の安全性を向上させるソリューションへ使⽤するようにデザインされている。例えば、ピッツバーグは、プログラムを通して1100万ドルを得て、スマート交通信号機の設置を⾏う、そしてデンバーは600万ドルを得て、通勤時のトラフィックを緩和するためにコネクテッドカーの利⽤に向けて利⽤する。助成⾦のうちの約800万ドルは、カーシェアリング、デマンドベースのダイナミックバス、⾃転⾞シェアリングといったオンデマンドモビリティを、既存の公的交通ネットワークの中に構築するといった特定の目的に充てられている。 アメリカ⾃動⾞製造者同盟は⾃動⾞のサイバーセキュリティを強化するため、⾃動⾞情報共有分析セ
ンター(Auto ISAC)を創設することを発表している。Auto ISAC はサイバー脅威や脆弱性に関する情
440
報をOEMやサプライヤ、政府機関らで共有させ、インテリジェンスと分析のためのハブとして機能する自動運転が実現した際の外部からのハッキング防止が目的である。 このほか、自動運転とは直接結びついているわけではないが、アメリカ国防高等研究計画(DARPA)
がエレクトロニクス分野、特にマイクロエレクトロニクスを対象とした研究開発プログラムからなる“Electronics Resurgence Initiative”を推進。2018年以降のプログラムとして以下のプロジェクトを加えている。 The Three Dimensional Monolithic System-on-a-Chip (3DSoC) program The Foundations Required for Novel Compute (FRANC) program The Intelligent Design of Electronic Assets (IDEA) program The Posh Open Source Hardware (POSH) program The Software Defined Hardware (SDH) program The Domain-Specific System on a Chip (DDSoC) program
出所:DARPA資料 また、DARPAは2017年中より、超高速かつ低消費電⼒な非ノイマン型チップ技術-graph
analytic processor (GAP)の研究開発プログラムとして“HIVE — Hierarchical Identify Verify Exploit”を⽴ち上げている。期間は2017年のPhase 1(Concept)からPhase2(Initial prototypes, 2018~2019)、Phase 3(Chip fabrication, 2020~2021)の4年半を計画、研究予算は8,000万米ドルとなっている。 同プログラムへの参加組織は、Intel 、Qualcomm、国⽴研究所、⼤学研究機関。Intel、
Qualcommがそれぞれに設計したgraph analytic processor (GAP)のアーキテクチャを提案、また、
441
Pacific Northwest National Laboratory (Richland, Washington)、Georgia TechがGAPのソフトウェアツールを同様にそれぞれ開発し、その中から研究開発を進めていくアーキテクチャ及びソフトウェアツールを決定。DARPAは決定されたアーキテクチャ開発企業に5,000万米ドルを拠出、ソフトウェアツールについてもどちらか一方に700万米ドルを供与する予定となっている。 また、Northrup Grummanがグラフ分析(Graph analysis)に対するDoDのニーズなどを調
査・分析するためのボルチモア・センターを設⽴するために1,100万⽶ドルの資⾦提供(non matching fund)を受ける。
出所:DARPA資料
442
出所:DARPA資料 GAPは、データの複雑さなどのためにリアルタイムに認識が困難なサイバーセキュリティ、ソーシャルメディア分析、インフラストラクチャ・モニタリング等のグラフ分析での応用を想定したもので、CPUやGPU と比較し1,000倍のGTEPS/W(Giga Traversed Edges Per Second Per Watt)を実現することが大きな目標と位置付けられている。Intelはグラフ分析に適したarithmetic-processing-unit (APU)、超高速(terabytes per second以上)のメモリアクセス技術を含む新たなメモリアーキテクチャを提案しているようだ。
出所:DARPA資料
443
出所:DARPA資料
また、これらの取り組みと並⾏して、DARPAはMIT Lincoln Laboratory及びAmazon Web
Services(AWS)と共同で「HIVE Graph Challenge」を実施している。これは、ソーシャルメディア
444
やセンサデータ、科学データ等から得られるグラフや疎データの分析に向けた新たなチップ開発を促進するとともに、最終的には兆レベルのデータセットを構築することを目的としている。 DARPAはこの一環として、AWSの“AWS Public Datasets program”にDoDエージェンシとして
は初めて参加、「HIVE Graph Challenge」参加者は”AWS Cloud Credits for Research program”を通じ、様々なデータを⽤いアルゴリズムのテストが⾏える仕組みを整えている。
445
欧州 欧州でのHorizon 2020における⾃動⾛⾏システムの研究開発⾃体はFP7の最終募集(Call 10)
を主体として、様々なプロジェクトが予算総計約 7,000 万ユーロで進⾏中である。その中の代表的なプロジェクトとしては、AdaptIVe(Automated Driving Applications & Technologies for Intelligent Vehicles)がある。研究期間は2014年1⽉〜2017年6月の42 ヶ月間で、費用は総額 2,500 万ユーロである。主な参加国はフランス、ドイツ、イタリア、イギリス、オランダ、スペイン、スウェーデン、ギリシャの8カ国で、VWが代表幹事であり、Daimler、BMW、Bosch、Continental、その他の欧州⾃動⾞メーカ、⼤学・研究機関を合わせた29団体が参加している。 AdaptIVeのプロジェクト対象はSAEが定めた自動運転レベル規格(j3016)の6段階のうちの4段階で、運転アシスト(レベル1)から⾼度⾃動運転(レベル4)までが含まれる。SAEによるレベル5については、フルオートメーションのロボットタクシーとみなしているためにプロジェクト対象外としている。 CityMobil2(都市型交通実証プロジェクト)
予算:1,500万ユーロ 期間:2012年9⽉〜2016年8月 参加:12の欧州都市、45のパートナー企業・機関、5つのシステム製造会社 仏La Rochelle市(2014/12〜)、スイスのLausanne市(2015/4〜)等で⼤規模実証実験 などがある。
表 欧州における自動運転関連の研究開発プロジェクト
出所:各種資料をもとに⽮野経済研究所作製
プロジェクト名 期間 予算 内容 メンバー
AdaptIVe ’14-1〜 ’17-6
25.0Mユーロ/14.3Mユーロ
知的⾞両のための⾃動⾛⾏アプリと技術開発、⼈と⾞の統合、クロースエリア、高速道、市街地シナリオ
VOLKSWAGEN,BMW,CRF,DAIMLER,FORD,VOLVO,PSA,OPEL,PENAULT,BOSCH,CONTINENTAL,DELPHI 等約29社・機関
COMPANION ’13-10〜 ’16-09
5.4Mユーロ/3.4Mユーロ
貨物輸送の燃費と安全の改良のための⼤型⾞の統制⾞両プラトーニングのためのプラトーンの形成、協調、運用などの協調モビリティ技術開発
SCANIA,IDIADA,VOLKSWAGEN 等7社・機関
AUTONET2030’13-11〜 ’16-104.6Mユーロ/3.4Mユーロ
協調⾃動⾛⾏技術の開発・テスト。2020〜2030 展開を目指した、⾞⾞間通信とセンサーに基づく⾞線保持/ACCシステム開発
BROADBIT,VOLVO_TEC,CRF,HITACHI,EPFL 等9社・機関
I-GAME ’13-10〜 ’16-09
3.8Mユーロ/2.6Mユーロ
オランダGCDCの成果をベースとした⾞⾞間通信で支援されたより安全な⾃動⾛⾏システムの実⽤化を加速する技術開発
TNO,UNI_TUE,IDIADA,VIKTORIA
CITYMOBIL2’12-09〜 ’16-0815.8Mユーロ/9.5Mユーロ
CityMobileの実用化フレームワーク、法的フレームワーク、経済効果の記述。12都市の5ケースについて2セットの自動化⾞両で6〜8ヶ月のデモ評価
UNI_CTL,EPFL,DLR,INDUCT,ERTICO,INRIA,TECNALIA,POLIS,YAMAHA 等約45社・機関
CATS ’10-01〜 ’14-12
4.2Mユーロ/3.0Mユーロ
⼩型でクリーンな都市⾃動⾞の短期間レンタルと、プロドライバーにより運転される可変⻑のコンボイでのシャトルサービスの開発と実験
LOHR,INDUCT,INRIA 等11社・機関
V-CHARGE’11-06〜 ’15-09 8.7Mユーロ/
5.6Mユーロ指定地域(バレットパーキング、パーク&ライド等)での自動⾛⾏を考慮し、都市環境における⾼度なドライバー⽀援を提供できるスマートカーシステムの開発
UNI_ETH_ZURICH,BOSCH,UNI_OXFORD, VOLKSWAGEN,UNI_PR,UNI_TUB
VRA ’13-07〜 ’16-12
1.7Mユーロ/1.3Mユーロ
⾞両と道路の⾃動化に関する技術やその課題の欧州での共有と国際協調のネットワーク支援・プロモーション活動
ERTICO,IDIADA,TNO,VOLVO_TEC,DENSOI 等11社・機関
446
欧州各国で自動運転に関連する国家プロジェクトが稼動している。 英国運輸省では、2015年2月に「Driverless Cars」プロジェクトに係るアクションプランをまとめている。このプロジェクトでは、1,900 万ポンドの予算措置により、4 つの都市で⾃動運転技術の実証実験が⾏われる。グリニッジ、ミルトンキーンズ、コベントリー、ブリストルの4都市で、2015年から2018年まで実証実験を⾏う。⻑期的には完全⾃動運転を⽬標としながら、短・中期的にはドライバー⽀援型⾃動運転技術の向上を目指す。2018 年末までに、国際規制の⾒直し・改正すべき内容を整理する計画である。 フランスでは2014年に「The New Face of Industry in France」を発表。 その中の34分野の
一つとして「Driverless Vehicle」を設定し、フランスの⾃動⾞セクターを⾃動化のパイオニアにすることを目指すとしている。また、2,400台の⾞両・400基の路⾞協調システムを導⼊し、1,500kmの高速道路での実証プロジェクトを 2014 年より開始している。実証試験⽤の制度を整備(2015/7)、Paris-Bordeaux 間で自動運転の実証(2015/10)、無人シャトルバスの実証(Easymile 社他)なども実施している。 オランダは「Dutch Automated Vehicle Initiative(DAVI)」が開始(2013年3月)、インフ
ラ・環境大臣が試乗(2014年1月)、大規模実証法(2015年7月)、Easymile導⼊などが⾏われる。 フィンランド運輸通信省が「Intelligent Automation」のプランを発表(2015年1月)。フィンラン
ド北部、Tampere 市、Helsinki 地域での試験を実施、Vantaa 市での実証(CityMobil2、Easymile)などを⾏う。 ドイツでは「Strategy」(2015年9月)においてミュンヘン周辺(アウトバーン 9 号線)にテストベット
を設置することを明記した(Digital Motorway Test Bed)。2015 年には「Strategy for Automated and Connected Driving」を閣議決定した。ドイツが⾃動⾛⾏のイノベーションの先頭に⽴ち、その市場をリードし、実証、実⽤化を果たすことを⽬標に掲げている。 ドイツでは、型式認証済み⾞両をベースに改造された⾃動運転⾞両は、⼀般のナンバープレートの使
⽤が認められている。未登録⾞両については、⼀時的な公道⾛⾏⽤ナンバープレートを使⽤する事で試験⾞両の⾛⾏が認められている。Daimler は、Sクラスをベースにした⾃動運転⾞両を⾛⾏させて、マンハイムからプフォルツハイムまでの往復200kmの⾃動⾛⾏を実現している。 ドイツ北部のハンブルグ市は⾃動運転⾞が⾛⾏可能な試験地域と指定されおり、VW とスマートモビリ
ティのモデル都市として開発するために提携を発表している。安全で信頼性が⾼く、効率的で環境性に優れる移動手段の構築を目指して今後3年間協⼒を進める。 スウェーデンにおいては、「Drive Me」プロジェクト(Volvoが中心、750万ドルの官⺠共同実験)が
447
開始されている。VolvoはXC90 をベースにした自動運転用テストカーを提供しており、ヨーテボリ市の内部/周辺から選定された公道を使って毎日約50km⾛⾏、2017年には、100台規模まで増やす計画である。このプロジェクトには Autoliv も参加協⼒しており、同様のプロジェクトをイギリスのロンドン、中国でも今後実施する予定である。 オランダ、ドイツ、オーストリア政府の合意に基づき、幹線⾼速道路に路⾞協調システムを導⼊し実証実験を開始している。
表 欧州各国おける⾃動⾞関連の政府プロジェクト
出所:国⼟交通省資料
448
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
(ⅰ)スマートテキスタイルの概要
スマートテキスタイルの定義は様々であるが、欧州標準化委員会(CEN/TC248 WG31)では、ス
マートテキスタイル材料と他の繊維材料を以下のように階層化している。
• 繊維材料:それ自体、あるいは他の織物および非織物材料と組み合わせて使用して、織物製品を
製造することを意図した材料
• 機能性繊維材料: 材料、組成、構造および添加物によって特定の機能が追加された繊維材料
• スマート(インテリジェント)テキスタイル材料:環境と相互作用する、すなわち環境に応答する、また
は環境に適応する機能性繊維材料
また、導電性を付与したテキスタイルは E-テキスタイルとも呼ばれている。先述した CEN/TC248
WG31 では E-テキスタイルのポジショニングとして以下の概念図を示すとともに、E-テキスタイルの統合レ
ベルを 4 段階に区分した。
(a)電子デバイスはポケットやファスナーボタンなどを介して、テキスタイル製品を壊すことなく取り外せるよう
に取り付けられる。
(b)電子デバイスは圧着や接着などにより、テキスタイル製品を壊さなくては取り外せないように取り付けら
れる。
(c) 1 つまたは複数の構成要素からなる電子デバイスは、永久的または非永続的にテキスタイル製品に
取り付けられる(例えば 布地に織り込まれた配線に取り付けられた LED ランプ)。
(d)電子デバイスの全ての構成要素がテキスタイルで製作される。
E-テキスタイルのポジショニング
出所:www.textileworld.com
451
(ⅱ)スマートテキスタイルの重要な要素技術
スマートテキスタイル(主にE-テキスタイル)の重要な要素技術は、(a)配線材料(導電性繊維)、
(b)配線形成プロセス、(c)実装・接合技術と考えられている(出所:福井大学堀照夫客員教授の講
演資料など)。
(a)配線材料(導電性繊維)
従来からスマートテキスタイルの配線材料として導電性繊維が多用されている。導電性繊維には金属
繊維、金属めっき繊維、炭素繊維、有機導電性繊維、カーボン練込繊維などがあり、スマートテキスタイ
ル向けでは金属めっき繊維が主流である。体積抵抗値は 10-2Ω・cm 程度。ベースポリマーはナイロンが
一般的であるが、ポリエステルや PP、アラミドなどをベースとした導電性繊維や、PEDOT-pTS /シルク複
合素材なども開発されている。
(b)配線形成プロセス
スマートテキスタイルの配線形成プロセスとしては、導電性繊維を編み込む手法が広く検討されている
が、衣類のように既に加工された布の上に印刷工法(主にスクリーン印刷)を用いて配線を形成する手
法もある。
(c)実装・接合技術
スマートテキスタイルは回路材料と布地の耐熱性の不足により、ハンダ実装が難しい。代替手法として
導電性接着剤やACFなどの検討が進んでいる。また、基材が布地であるため繰り返し応力による実装デ
バイスの接続信頼性や洗濯耐性の確保が重要となる。
この他、フレキシブルデバイスを IoT 社会に広く普及させていくためには、
・自立型電源(一次電池、二次電池、キャパシタ、太陽電池等)
・通信/ネットワーク(光通信 ・BT/ZigBee ・無線 LAN ネットワーク等)
・アプリケーション(各産業・用途別に個別のアプリケーションを開発・提供)
・プラットフォーム(デバイスの接続管理やデータ収集・分析等の共通基盤的な機能)
といった領域で展開している企業との連携が欠かせないとされている。
452
(ⅲ)特定の用途(生体情報の計測)に関する技術の概要
生体情報は生体内情報(心電、血圧、内臓脂肪など)と生体外情報(活動量、睡眠、食事など)
に区分できる。生体内情報においては、心電図から計算される心拍や脈拍がその変動率を解析すること
で心不全の兆候を検出できるほか、心拍のゆらぎを解析することで自律神経系の緊張度合いの評価
(ストレスチェックや眠気検知等)も可能である。そのため、監視すべき最も重要なパラメータとの位置づ
けで、心拍や脈拍を主な測定ターゲットとした生体情報測定技術の開発が多くなされている。
生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS 非ウェアラブル)
従来、心拍や脈拍を計測する手法は電極を体に貼り付ける心電図測定といった接触型が一般的で
あり、その行為が長時間になればなるほど被測定者の自由を奪ったり、ストレスや緊張を与えたりするうえ、
皮膚のかぶれなどの問題も生じてくる。
これに対して、被測定者の時間的な拘束から開放し、測定そのものへのストレスを低減する非接触型
のセンシング技術の開発が活発する傾向にある。具体的には、圧電センサをベッドやソファーに搭載するも
の、マイクロ波(またはミリ波)レーダやカメラ画像を用いるものなどである。ただ、これらの非接触型のセン
シング技術はセンサが固定化されているため一定の場所でしか測定できない、あるいはセンサと非測定者
の距離が離れると測定精度が低下するといった空間的な制約を受ける。
こうした各種センサの時間的制約、および空間的制約を解消する手法として、近年はウェアラブルデバ
イスを用いて心拍・脈拍や活動量等の生体情報を取得する手法に注目が集まっている。
生体外情報の一つである活動量の測定では、日常の一日あたりの歩数を計測する歩数計を皮切り
に、エネルギー消費量を評価できる 1 軸式加速度センサ搭載型の活動量計、さらには身体の動きを3
次元(X, Y, Z)で解析できる3軸式加速度活動量計が開発されている。現在は 3 軸式が主流となっ
ており、衣類のポケットやベルトに装着するものから腕時計型・リストバンド型まで様々なタイプのものが製
品化されている。そして、Apple Watch に代表される腕時計型やリストバンド型のウェアラブルデバイスで
は、光電式容積脈波法(フォトプレチスモグラフィ)を用いたセンサを内蔵することで、生体内情報である心
拍の測定を可能としている。
これら生体内情報を取得するセンサの概要とメリット・デメリット、および上記の時間的制約と空間的制
約とを軸としたウェアラブルデバイスとそれ以外のセンサ(非ウェアラブル)を対象としたポジショニングマップ
を次ページ以降に掲げた。
453
生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS 非ウェアラブル)
〔矢野経済研究所作成〕
ウェアラブルデバイスの概要
身体に装着して使用する小型の電子機器は 1970 年代末頃から製品化され始めたが、その機能は
現在のウェアラブルデバイスと大きな隔たりがあった。インターネット接続機能や高度な無線通信機能を装
備した現代型のウェアラブルデバイスが技術的に実現可能となったのは 2000 年代中頃とされ、その関
連技術は PC やフィーチャーフォン、スマートフォン、タブレット PC 等に応用されて普及が進んだ。その結
果、様々なタイプのウェアラブルデバイスが製品化されているが、これを大別すると(a)腕時計型、(b)
リストバンド型、(c)眼鏡型、(d)ウェア型に分けられる。
(a)腕時計型(スマートウォッチ)
スマホの周辺機器として機能する「スマホ連携型」と、単独でネット接続機能や通話機能を持つ製品が
ある。また、OS の種類はアップルの「Apple Watch」(WatchOS)やサムスン電子の「Gear S」
(OS:Tizen)等の独自 OS と、Google の Android Wear に大別される。Android Wear は
台湾系ASUS(ASUSTeK Computer)の「Zen Watch」やLGエレクトロニクスの「LG G Watch」、
ソニーの「Smart Watch3」、モトローラの「Moto360(2nd)」、その他様々な製品に搭載されている。
(b)リストバンド型(スマートバンド)
腕回りに装着するウェアラブル端末で、センサと無線通信機能等を内蔵しており、ユーザーの生体情報
を収集し、スマホを介してインターネット接続・クラウドサービスと連携する。ブレスレット型などと呼ばれること
もあるが、前記の腕時計型端末の中で単独ではネット接続機能や通話機能を持たない「スマホ連携型」
ウォッチとの境界ははっきりしていない。搭載センサは活動量計(歩数、消費カロリー)が中心だが、脈拍
455
計や加速度センサ、GPS 等を搭載する製品が増えている。このタイプはウェアラブル端末の中で最も多
用されており、参入企業も多い。
(c)眼鏡型(スマートグラス)
ディスプレイ装着型とその他の製品がある。2015 年 1 月に販売を中止した「Google Glass」はディ
スプレイ装着型の代表で、眼前に情報を表示するとともに、内蔵センサで情報を収集する。複眼型の製
品が多いが、単眼型もある。
一方、ディスプレイ非装着型は通常の眼鏡の専門企業が開発に関与することが多く、この場合は通常
の高級眼鏡と同等のデザイン性と特性を保持しつつ内蔵センサやデバイスで情報を収集したり伝達する
機能を持たせたりしている。このタイプはジェイアイエヌの「JINS MEME」や、なまえめがねによる「雰囲気メ
ガネ」などが製品化済みである。
(d)ウェア型
導電性繊維などで作製した電極を衣服に熱圧着する、あるいは導電性繊維などを編み加工するといっ
た方法で、衣服そのものをウェアラブルデバイスとして利用するものである。
生体内情報の取得を目的としたデバイスの場合、心臓の活動に伴う心起電力によって生じる電位分
布の 2 点を電極で測定し、その電位差の時間経過から心電波形を計測する。この信号を衣類に装着し
たトランスミッターで、パソコンなどに無線で送信するといった仕組みが一般的である。心拍数は QSR 波の
ピーク間の時間(R-R 間隔)を算出することで得られる。また、トランスミッターに加速度センサを内蔵す
ることで姿勢や歩容など着用者の動作情報を推定できる。
ウェア型のウェアラブルデバイスで取得できる生体情報の例
(e)その他のウェアラブルデバイス
貼付型、コンタクトレンズ内蔵型、スポーツ用品(ラケット、ボール、シューズ等)内蔵型、指輪型・イ
ヤホン型・ペン型端末など多種多様なデバイスがある。まだ開発中の製品が多い。
456
スマートテキスタイル(ウェア型デバイス)の強み・弱みと今後の課題
生体情報を取得できるウェアラブルデバイスを対象に、タイプ別の機能一覧、および「機能」と「装着感」
を軸に作成したポジショニングマップを次ページ以降に掲げた。これらの内容と本事業で実施した企業ヒア
リングの結果をもとに、生体情報の取得を目的としたウェア型デバイスの強み・弱みと今後の課題をみてい
く。
(a)スマートテキスタイルの強み
繊維本来の特長
ウェアラブルデバイスは小型化・軽量化やフレキシブル化(折り曲げられる)の要求に対応しながら進化
を続けている。繊維で作られるウェア型デバイスは軽量化やフレキシブル化が容易であり、身体の動きへの
追従性に優れる伸縮性や通気性も付与できる。また、「衣類を着る」という日常的な行動の中で生体情
報を取得することが可能である。
取得情報の精度の高さ
ウェア型デバイスで得られる生体情報の精度は、他のウェアラブルデバイスやカメラなどよりも高いとされて
いる。
繊維産業の高い技術力(生地、高機能化・高性能化)
我が国の繊維産業は、生地の競争力が世界的に高い。
また、繊維に機能を付与したり、繊維の性能を高める技術において世界をリードしている。こうした繊維
が、織りや編みなどの後工程(中間製品)を経て、衣料のみならず、インテリア、産業資材、医療など
幅広い分野において展開されQOLの向上に貢献している(出所:経済産業省製造産業局生活製
品課「繊維産業の現状と課題」)。
(b)スマートテキスタイルの弱み
多機能化
腕時計型やリストバンド型は表示機能から環境状況、生体情報(活動量、物理)の取得までを可
能とする多機能デバイスといえ、通信機能や電源も内蔵している。一方、ウェア型は生体情報の中でも
心電波形のみを取得する製品が主流であり、付属のトランスミッターを装着することで活動量や位置情
報を取得する。また、通信デバイスや電源はトランスミッターに内蔵される。
ウェア型デバイスにおいては、単独で時計型までの多機能化を実現するには時間を要するものと考えら
れる。一方で心電波形のみ、あるいは活動量(加速度センサ)との組み合わせで十分な情報を得られ
ると考える企業も少なくない。
装着感
ウェア型デバイスは電極を体表面に密着させることで取得データの精度が高まることからコンプレッションタ
457
イプの製品が多く、利用者によっては日常的に着用することを避けてしまうケースが想定される。
顧客ニーズの吸い上げ
現在は繊維産業の上流に位置する企業が、ウェア型デバイスを製品化している。その結果、特に今後
の需要拡大が想定される介護や医療といった分野での顧客ニーズの吸い上げが難しい状況にある。実
証実験の事例は増加傾向にあるが、例えば医療分野では医師に協力をお願いしても事務的に使用す
るだけで、本当の課題やニーズは吸い上げにくいようである。
(c)スマートテキスタイルの機会
IT の進歩
空間的な制約の少ないウェア型デバイスとして普及を進めるためには、自立型電源をどのように構築し
ていくかは重要なテーマとなる。また、企業が多機能化の製品戦略を採用した場合は消費電力の低減も
不可欠となるが、近年は大容量のデータ処理が高速かつ少ない消費電力でできるようになってきている。
超高齢化社会の到来
超高齢社会の到来に伴う高齢者世帯数、要介護者及び認知症高齢者数の増加、在宅介護、介
護施設の増加が見込まれる一方、働き手である65歳未満の人口はこれまで以上に減少していく。こうし
た状況に対して、「日本再興戦略 2016」ではセンサーを活用した介護の質・生産性の向上が鍵となる
施策として示されている。
遠隔診療関連サービスの拡大
従来、医療現場では検査時などある時点での生体情報の測定にとどまっていたが、こうした方法だけで
は健康状態などを十分に把握できない恐れがある。例えば、不整脈であれば胸の痛みや動悸を感じても
一過性であることが多く、病院に行った時には発作症状はおさまっており、心電図検査を行っても異常が
出ないこともありうる。一方、ウェア型デバイスを用いて、長期にわたり生体情報を常時取得することにより、
患者の経時変化を把握することが可能となる。
特に、我が国において医療分野でウェア型デバイスの需要が拡大するか否かは、遠隔医療市場の動向
に大きく左右されるものと考えられる。
遠隔医療は医療機関間(D to D)の遠隔診断、医療機関と患者間(D to P)の遠隔診療に分
類される。また、それぞれ、①遠隔画像診断、②遠隔病理診断、③遠隔診療、④遠隔健康管理に分
けられる。
遠隔画像診断の領域では遠隔医療の活用が比較的進んでいるのに対し、遠隔診療は原則認められ
ていないと解釈されてきた。厚生労働省では 1997 年に遠隔診療に関する基本的な考え方や医師法
第 20 条等との関係から留意すべき事項を示している。基本的考え方とは、診療は医師と患者が「直接
対面して行われることが基本であり、遠隔診療はあくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべき」
というものである。
458
(d)スマートテキスタイルの脅威
ヘルスケア分野における需要の小ささ
リストバンド型のウェアラブルデバイスは米国のオバマケア施行を機にヘルスケア分野で急拡大し、その
後は世界規模で普及が進んだ。その過程で米・Fitbit 等のベンチャー企業が急成長したほか、中国・
Xiaomi が「Mi Band」を市場に投入し、その安価な価格などを武器に中国・アジアを中心に需要を取り
込んだ。日本市場も Fitbit が強みを見せているほか、オムロンやソニーなども実績を上げている。
しかしながら、国民皆保険制度があり、病気になることで莫大な費用が掛かるといったリスクが低い。
日々の忙しさから健康への優先順位が低くならざるを得ないといった環境にもあるため、リストバンド型の
利用は健康管理への関心の特に高い層や、新たなデバイスへの関心の強い層に限定される傾向にある。
そのため、米国や中国などに比べ日本におけるリストバンド型の市場規模は小さく、ウェア型の認知度が
高まりにくい環境にある。
標準化がなされていない
ウェア型デバイスの規格が策定されておらず、現状は「デバイス」と「衣類」の二つの規格を満たす必要
があることから、開発コストの上昇につながっている。また、特にブランド力の弱い中堅・中小企業にとっては
標準化がなされていないことで、市場での信頼性向上や差別化をしにくい状況となっている。
アルゴリズム解析
ウェア型デバイスを用いて精度の高い一時情報(心電波形)を取得できても、拍数や睡眠などの二
次情報を利用者に合わせて加工できなければ、その利用価値は低くならざるを得ない。現在、市場では
アルゴリズム解析の遅れにより事業化が遅れている事例がある。
(e)今後の課題
製品開発
ウェア型デバイスの「高い精度で心電波形を測定できる生体センサ」という強みを活かし、機能を絞り
込みながら装着感を高めていくような取り組みが今後の製品開発のテーマ一つになると考えられる。
なお、最近は自然な着心地で快適に日常を過ごせるよう装着感の改善が進んでいるほか、インナー
シャツではなく、アウターシャツに電極を組み込む非接触タイプの製品の開発も進んでいる。こうした非接
触タイプのウェア型デバイスは、かぶれなどの懸念がある貼付型よりも装着感を高められる。
スマートテキスタイルの標準化
ウェア型デバイス、あるいは部材を製品化・開発している企業の中には、中堅企業やスタートアップ企業
も存在する。開発コストの低減や製品の信頼性確保、速やかな普及などを図るためにも、標準化の作業
を急ぐ必要性は高いと考えられる。
460
オープンイノベーションの場づくり
現在は繊維業界と電気・電子業界という二方向のアプローチにより、ウェア型デバイスあるいはスマート
テキスタイルの製品開発が進められている。また、電気・電子業界ではプリンテッドエレクトロニクス技術と
MEMS 技術の二つ領域が出発点となろう。
今後のウェア型デバイスの普及のためには繊維と電気・電子の両業界の技術の融合は必須といえよう。
さらにはセンサ技術やネットワーク技術、アルゴリズム解析、アプリケーション開発、セキュリティ対策など幅
広い技術を組み合わせなければならない。
なかでも、参入企業の多くが市場の本格的な立ち上がりに必須としているのが、ウェア型デバイスで取得
したデータの活用・提供方法の確立である。先述のアルゴリズム解析の内容と重複するが、取得データが
波形としてアウトプットされるだけでは、利用者にとっての価値は低い。データをどのように判断し、どのような
方法で利用者に提供するのか、すなわちアルゴリズム解析とアプリケーション開発の重要性が増す。
このような幅広い技術を自社のリソースのみでカバーすることは難しいほか、新たな事業アイデア・提供サ
ービスの開発などにも取り組む必要がある。これらは、固定化された考えや既存の関係先では生まれにく
いことから、社外にある潜在的なリソースを探索することできるオープンイノベーションの場が必要と考えられ
る。
スマートテキスタイル(ウェア型デバイス)の SWOT分析
〔矢野経済研究所作成〕
強み(Strength) 弱み(Weakness)
・繊維本来の特長 ・多機能化
・取得情報の精度の高さ ・装着感
・繊維産業の高い技術力 ・顧客ニーズの吸い上げ
機会(Opportunity) 脅威(Tereat)
・ITの進歩 ・ヘルスケア分野での需要の小ささ
・超高齢化社会の到来 ・標準化がなされていない
・遠隔診療関連サービスの拡大 ・アルゴリズム解析の遅れ
461
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
スマートテキスタイル(主に E-テキスタイル)を機能別にみると、(ⅰ)センシング、(ⅱ)発電、
(ⅲ)熱制御、(ⅳ)発光に大別できる。
スマートテキスタイルが有する機能の製品例
〔矢野経済研究所作成〕
センシング
センシング機能を発現するスマートテキスタイルは、主に①の生体情報の取得を目的とした製品化が
進んでいる。その他、椅子やベッド、自動車シートなどへの適用が可能な感圧センサとしての応用も検討
されている。
発電機能
太陽電池や導電性材料(カーボンブラック、カーボンナノチューブ、グラフェン等)との複合化により、ス
マートテキスタイル自体が発電する機能である。ウェアラブルデバイスや、室内環境を測定するセンサなどの
電源としての活用が想定されており、日本では住江織物やウラセが開発を進めている。
住江織物は東京工業大学、信州大学と共同で布帛型太陽電池の開発に成功した。金属性の芯
材に p 型有機半導体:P3HT、n 型有機半導体:ICBA を塗り重ねた太陽電池糸(直径 0・
25mm)を用いた布帛は、10cm2の面積で 150μW を発電する。
ウラセの太陽電池テキスタイルは直径 1.2 mm の球状太陽電池を糸状に加工し、これをよこ糸とし
て織り込んだ織物である。2kg/m2 以下の重量で 13W/m2 以上の発電量を目標に開発を推し進めて
いる。
機能 概要 製品例
センシングセンサやマイクロチップを衣料やテキスタイルに組み込み、測定物の状
況を集積伝搬する、あるいは必要に応じて制御までを行う機能。
東レ「作業者みまもり用ウェア」
グンゼ「筋電ウェア」
発電太陽電池や導電性材料との複合化によりスマートテキスタイル自体が
発電する機能。
住江織物「布帛型太陽電池」
ウラセ「太陽電池テキスタイル」
熱制御冷温感対応(夏は涼しく、冬は暖かく感じる)、遠赤外線を発生さ
せて保湿性を向上させるなどの機能。
グンゼ「発熱ニット」
クラレ「CNTEC」
発光LEDやOLEDを組み込むことで衣料などから光が発する機能。繊維
自体を発光させる研究開発も進んでいる。SHINDO「LEDリボン」
464
太陽電池繊維の構成
熱制御機能
冷温感への対応(夏は涼しく、冬は暖かく感じる)、遠赤外線を発生させて保湿性を向上させるなど
の機能である。製品例としてグンゼ「発熱ニット」(開発中)、クラレ「CNTEC」などが挙げられる。
グンゼでは生地に導電性ニットで直接電気回路を形成し、外部から電源を供給することで特定部分
での発熱効果を得られる「発熱ニット」を開発している。柄表現の技術を用いて配線の長さや太さを変化
させることで抵抗値のコントロールが可能なほか、発熱部の位置を自由に設定できる。発熱ソックスや発
熱タイツなどへの応用を想定している。
クラレ「CNTEC」は、産官学(北海道大学、クラレリビング、茶久染色、松文産業、愛知県産業技
術研究所尾張技術センター)の共同プロジェクトで開発された導電性繊維である。精密糸染色技術を
応用し、多層カーボンナノチューブ分散液を均一にコーティングしたポリエステルマルチフィラメント加工糸を
織り込んで作られる。生地は柔軟で風合いが良好なほか、安定した導電性能と高い耐久性を有してい
る。2015 年から販売事業がクラレ本体に移管され、本格的な事業化に入った。用途は車両内装材、
融雪マット、屋根融雪向けなどである。
発熱ニット
465
発光機能
導電性繊維などで生地に配線を形成し、LED や OLED を実装することで衣類などから光が発する機
能であり、視認性やデザイン性の向上につながるものである。日本では SHINDO が LED リボンを開発し
ている。
LED リボン
466
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
発電機能
自立電源としての利用が期待されているため、高い発電性能が必要となる。先述した住江織物の太
陽電池は有機薄膜系であるが、通常屋外に設置される電力供給用の変換効率は 4~5%である。現
在、太陽電池市場の主流をなす結晶シリコン系が 20%近い高効率化を達成しているのに比べ発電性
能が劣る点に課題を残す。また、利用シーンや環境によるものの、長期間にわたり発電性能を維持する
ことが求められる。
熱制御機能
熱制御のコントロール(温度、場所・位置、面積)が重要である。
発光機能
生地に LED などのデバイスを実装する際、回路材料と布地の耐熱性の不足により、一般的に用いら
れているハンダ実装が難しい。代替手法として、スマートテキスタイルに適用できる低温実装可能な導電
性ペーストや ACF などの開発が求められている。また、基材が布地であるため、繰り返し応力による実装
デバイスの接続信頼性を高めることが重要となる。
469
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
生体センサ用として最終製品、および電極・センサを製品化(研究開発中のものを含む)している企
業・製品名は以下の表のとおりである。
〔矢野経済研究所作成〕
東レ
日本電信電話(以下、NTT)と共同で着衣するだけで生体情報を取得できる機能素材「hitoe」を
開発し、高まる健康志向に合わせ、先端材料と IT の融合による新たなソリューションを提示している。
「hitoe」はポリエステルナノファイバーニットをベースとし、生体適合性に優れる導電性高分子
(PEDOT/PSS)をナノファイバー間の空隙に高含浸させた生地である。繊維径は 700nm。ナノファイ
バー間に入り込んだ導電性高分子は脱落しにくいため、長期間の着用や 100 回以上の繰り返し洗濯で
も機能を維持できるほか、柔軟で伸縮性や通気性にも優れている。また、裏面の特殊コーティングにより
適度な透湿性と保湿性を付与した。
もともと導電性高分子をベースとする繊維導電化新技術を持つ NTT と東レのナノファイバー技術や
先端高次加工技術、ウェア製造における着圧制御素材設計や縫製技術などを提供する形で協業した。
ナノファイバー技術とは独自のポリマー流制御による精密複合紡糸技術を用いて、ナノオーダーの細さと異
種別 企業 製品名
Goldwin C3fit IN-pulse
東レ hitoe 作業者みまもり用ウェア
東洋紡 妊婦用スマートテキスタイル
グンゼ 筋電WEAR
ミツフジ hamon
Xenoma e-skin
POSH WELLNESS LABORATORY センサーシャツ、モニタリングシャツ、おむつセンサー
クラボウ Smartfit
東レ・NTT Hitoe
東洋紡 COCOMI(心美)
エーアイシルク フレキシブルシルク電極
帝人 圧電組紐
ヤマハ ストレッチャブル変位センサ
バンドー化学 伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH」
最終製品
電極・センサ
470
倒であり、胸が圧迫されて苦しいといった声も多かった。一方、「C3fit IN-pulse」は着用時のフィット感
や快適性を十分に考慮したことから、長時間のトレーニング時の着用でも違和感やセンサ位置のズレが
少なく、心拍数を正確に測れる。
取得した心拍数データは「hitoe トランスミッター 01」から無線でスマートフォンに送信され、アプリに表
示することができる。2015 年 9 月にはスポーツブラとしての機能を付与した女性用ブラトップを製品ライン
ナップに加えた。価格は男性用 8,000~10,000 円、女性用 8,000~9,000 円、トランスミッター
10,000 円(すべて税抜き)。販売開始以降、トレーニングや戦略的なレース展開に高い効果を発揮
することからトップアスリートを中心に普及が進んでいる。
C3fit IN-pulse Tee:MEN'S
東洋紡
2015 年 8 月に生体情報計測ウエアに適した機能性素材「COCOMI(心美)」の開発に成功したこと
を発表した。「COCOMI」は独自開発の導電ペーストをウレタン系樹脂製フィルムでサンドした構成である。
伸縮性があり、厚さは 0.3mm ミリ以下、シート抵抗は 1Ω/□以下。ウェアの裏地に熱圧着で簡単に貼
り付けられ、皮膚に密着させることで心拍数や呼吸数などを感知する。
2017 年 1 月にユニオンツールと共同で居眠り運転検知システムを開発し、中日臨海バスと提携した
実証実験も実施した。
472
さらに、2018 年 1 月には東北大学東北メディカル・メガバンク機構の富田博秋教授らのグループおよ
びユニオンツールと共同で、「産後うつ」の研究向けに新たな妊婦用のスマートテキスタイルの開発に成功
した。「COCOMI」が心臓から発生する微弱な電気信号を体表面でとらえて、ウェアラブル心拍センサ
「myBeat」が、その信号を外部に発信することなく、心拍情報として機器内に記録する仕組みとなってい
る。ウェアは妊婦の意見も取り入れ、着用しても圧迫感が小さく、着脱しやすいデザインとした。
グンゼ
2016 年 1 月に NEC の技術協力により着るだけで生体情報を計測できる衣料型ウェアラブルシステ
ムの開発、及びウェアラブル用機能テキスタイルとしてバイタルデータ取得用ウェア、導電性ニット線材、家
畜冷却システム「ウシブル」などのコンセプト提案をスタートすると発表した。
衣料型ウェアラブルシステムは肌着インナー(背中部分など)に導電性繊維を編み加工し、姿勢セン
サや配線として活用。肌着に実装したウェアラブル端末から微弱な電流を流し、導電性繊維が伸縮する
際の抵抗値の変化により姿勢・ゆがみ・癖など身体の状態を検知する。得られたデータはウェアラブル端
末から無線通信(BLE)でスマートフォンに自動送信され、専用アプリケーションからバイタルデータを確
認できるほか、スマートフォンを経由して NEC のクラウド上で管理することも可能である。
これまで、バイタルデータ取得を目的に製品化された衣料型ウェアラブルデバイスには、コンプレッションタ
イプが多かった。一方、グンゼが開発した姿勢センサは身体への追従性が高いニット素材で構成されてい
るため動きやすく、伸縮性や通気性にも優れる。グループの技術力を最大限活用し、身体の動きに伴う
皮膚と肌着の伸縮を計測した綿密なデータに基づく設計、および着用中の姿勢を測定できるデザインと
することで日常的(長時間)に着用できる快適性・心地良さを実現した。
測定項目は姿勢、心拍数、消費カロリーなど。
2017 年 9 月には RIZAP 向けに「衣料型ウエアラブルシステム」を用いた「筋電 WEAR」の提供を開
始した。
筋電ウェア
473
ミツフジ
ミツフジは 1956 年に西陣織工場として創業した。織物の加工・製造技術の向上に取り組むとともに、
1994 年に米国の銀メッキ製造会社と独占販売契約を締結し、新規事業として銀メッキ導電性繊維の
取り扱いを始めた。その後は、電磁波シールド性や抗菌性など銀が持つ特性を活かした用途開発を推進
し、2002 年に銀メッキ導電性繊維の総合ブランドとして「AGposs」を商標登録した。
2016年12月には「hamon」のブランド名でウェア型生体センサおよびトランスミッターの販売を開始し
た。無縫製ニット横編機(島精機製作所製)で作られた、着心地を重視したウェアに「AGposs」を用
いた電極を一体化しており、着用者の心電、心拍、筋電 、呼吸数などの情報の収集が可能である。収
集した情報はトランスミッターから Bluetooth を経由してスマートフォンで確認することができる。その後も
hamon®の新製品として使い切りウェア、冷暖房付き作業服「hamon Air Brave」を相次ぎ市場に
投入した。
また、2017 年 3 月には導電性繊維とウェアの量産体制の整備に向け、第三者割当増資と融資によ
る総額 30 億円の資金調達を実施した。引受先はカジナイロン、電通、前田建設工業、南都銀行、京
銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合、三菱 UFJ キャピタルと他数社が含まれている。2018
年 4 月には京都府南丹市に、2018 年 7 月には福島県川俣町に自社工場を竣工する予定である。
Xenoma
東京大学の染谷研究室からスピンオフし、2015 年 11 月に設立されたベンチャー企業である。JST の
ERATO「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」の研究開発成果をもとに、生地に伸縮配線と歪み
センサを縫い込んだシャツ「e-skin」を開発している。
「e-skin Shirt」には 14 個の伸縮センサが搭載されており、胸の部分にコントローラーとなる「e-skin
Hub」を取り付けて使用する。「e-skin Hub」には 6 軸のモーションセンサが備わっており、Bluetooth 経
由でスマホや PC に接続してデータを取り込む仕組みである。
2017 年 2 月には NEDO の STS 助成事業の支援を受けて開発キット「e-skin DK」の法人向け販
売を、同年 8 月には個人開発者向けに提供するため Kickstarter プロジェクトをスタートさせた。
474
POSH WELLNESS LABORATORY
北里大学医療衛生学部医療工学科の根武谷吾准教授の研究成果である EIT (Electrical
Impedance Tomography:電気インピーダンストモグラフィー)技術を活用した応用製品の開発・
販売や知財管理等を目的に 2016 年 4 月に設立された。EIT は体表面上に貼付した電極対から数
mA 以下の微弱な電流を生体に流し、体表上に生じた電圧を測定することで生体内部のインピーダンス
変化を画像化する技術である。
同社では、①センサシャツ、②モニタリングシャツ、③電気インピーダンスCT、④オムツセンサ、⑤液体識
別センサなどの製品化に取り組んでいる。センサシャツや電気インピーダンス CT、オムツセンサは非接触型
であり、洋服の上からでも心拍数などを計測できる点が他社製品との違いである
センサシャツは銀メッキ繊維を皮膚非接触型のセンサ電極として利用し、電極周辺の電気インピーダン
ス変化を測定する。肌着などを介して呼吸状態や心拍数などを数値化できるものであり、同社では睡眠
時無呼吸症候群の検査用途での実用化を目指している。現在はマスク型やリストバンド型の装置が用
いられているが、マスク型は息苦しさが生じてしまい、リストバンド型は呼吸の有無のみを測定するものであ
る。一方、スマートシャツは着ているだけで呼吸の換気量を容易に測定できるため、被験者の負担軽減
につながる。なお、量産段階ではシャツの縫製を旭化成アドバンスに委託する計画である。
電気インピーダンス CT は繊維電極を編み込んだ生地とフィルム基板を伸縮ベルトに包含した構成とな
っており、繊維電極に電流を供給し、かつ生体表面より得られる生体インピーダンスに関する電圧信号を
繊維電極から受け取ることで心肺機能を可視化する。主に、集中治療室(ICU)の患者への適用を
想定している。
ICU 内の患者に対しては肺機能及び循環機能のモニタと機能維持が不可欠であり、肺機能障害の
組織的診断にはX線 CT が有用である。ただ、多くの患者は意識障害により自ら体位変化を行えず、人
工呼吸器を装着している場合も多い。このような環境下において、電気インピーダンス CT を用いれば検
査室移動のために人工呼吸器を一時的に取り外すことが不要となり、患者のベッドサイドでモニタできる。
また、呼吸管理により肺障害を最小限に抑えれば人工呼吸器をつける患者が減り、ひいては医療費の
低減にもつながる。
また、おむつセンサは EIT 技術により下着の上にセンサを設置しても排便や排尿の検知が可能。液体
475
選別センサは液漏れの監視・検知や液体を識別できる導電性糸であり、包帯に縫い付けることで出血・
漏血センサになるほか、工場のパイプライン等に設置すれば雨水と排水・薬品などの識別をしながら漏れ
を検知できる。
クラボウ
2017 年 3 月に大阪大学、信州大学、日本気象協会と共同で、熱中症予防対策に特化したリスク
管理システムおよびスマート衣料「Smartfit」の開発を開始すると発表した。本システムは心拍数、体表
温度などの生体情報と気象情報、緊急搬送情報を融合した独自のアルゴリズムで解析し、熱中症のリ
スクを評価するというものである。解析された結果は、シャツの着用者のスマホや管理者のタブレットにリア
ルタイムで伝達される。同年 5 月から大手建設・運送会社の協力のもと 200 人規模のモニター調査を
実施し、システムの基礎アルゴリズムと基本アプリケーションを完成させた。さらに、同年 10 月には 2 回目
のモニター調査を開始し、2018 年度春からのシステム販売を目指している。なお、心拍センサの開発は
ユニオンツールが担っているほか、2 回目のモニター調査から KDDI(クラウド・通信環境の構築)、セック
(IoT プラットフォームの実装技術を活かしたシステム構築)が新たに開発プロジェクトに参画している。
エーアイシルク
2015 年 6 月に東北大学鳥光慶一教授の研究成果を中核技術としたフレキシブルシルク電極の製
造・販売等を目的に設立された。
鳥光教授は NTT 物性科学基礎研究所を経て、2012 年に東北大学大学院工学研究科教授に
着任した。NTT 物性科学基礎研究所在籍時から受容体タンパク質の機能解明と、その受容体の機能
を利用したナノバイオデバイスの構築による、脳の情報シグナル伝達機構の解明・利用と生体内エネルギ
ーで動作する自立型デバイスの実現に取り組んできた。その成果の一つとして、神経細胞の培養や動物
への埋め込み実験による PEDOT-PSS 修飾電極の優れた生体適合性と電気特性を確認し、生体電
極として使用できる PEDOT-PSS/シルク複合素材の開発に成功した。
その後は、化学重合法により PEDOT-PSS よりも導電性に優れる PEDOT-pTS をシルクへ均一にむ
らなく付着させることで、電気抵抗値の改善を図ったシルク複合素材を新たに開発。現在はフレキシブル
シルク電極としての展開を推し進めている。想定する用途はバイタル計測、嚥下運動計測、泌尿器関連
計測、脳神経系計測などである。
こうした用途におけるフレキシブルシルク電極の特長は、(ⅰ)安全で快適、(ⅱ)高い吸水性、
(ⅲ)導電率を自由に設定、(ⅳ)加工が容易で低コスト、となっている。
従来、貼り付け型の生体電極は金属製の電極板と皮膚との間に電解質溶液を含むゲル・ペーストを
塗布するため、連続使用すると生体に炎症や不快感が生じてしまう。体内埋め込み型の場合は金属、
またはカーボン等の疎水性の導電性材料を用いるため、生体電極と生体組織の境界部に生じる機械的
なストレスによって炎症が起こる懸念がある。
一方、フレキシブルシルク電極は肌触りがよく通気性のある天然由来のシルクを使用していることから生
476
体適合性が高く、不快感もなく長時間の使用が可能であり。そのため、接触による皮膚炎や生体内にお
ける炎症の発生リスクが非常に低い。
また、シルクは非常に吸水性の高い素材であるため、悪天候時の雨水や運動時の汗など計測の障害
となる水分を素早く吸収し精度の高い計測を可能にするほか、高い導電性(電気抵抗値:数百Ω程
度)によりノイズに邪魔されない精度の高い計測環境を提供できる。さらに、複雑な形状への加工も容
易であり、染色の技法で製造するため小規模設備での大量生産が可能である。
帝人
2017 年 1 月に関西大学システム理工学部の田實佳郎教授と共同で、圧電体を組紐状にした「圧
電組紐」を開発した。圧電体にポリ乳酸繊維を使用し、日本の伝統工芸である組紐の技術を用いること
で、1 本の紐で伸び縮み、曲げ伸ばし、ねじりといった動きのセンシングを可能とした。加えて、組紐に古く
から伝わる「結び」を用いることでより鋭敏に反応を示すセンサとしても活用できる。
さらに、2018 年1 月には 「圧電組紐」を活用し、センシングの簡便性とファッション性とを併せ持つ「圧
電刺繍(e-stitch)」の開発に成功した。さまざまな刺しゅうパターンを解析しており、クロスステッチは曲
げ、チェーンステッチは伸縮・ねじり・曲げ、フライステッチはねじりの動きが分かる。レディースウェアをはじめ、
ペットの見守りができる圧電刺繍ペットウェア、スポーツ分野での応用が期待される圧電刺繍インソールを
試作している。
477
ヤマハ
2012 年に静岡大学井上翼准教授のグループと、抵抗体に多層カーボンナノチューブ(CNT)を用
いた変位センサの共同開発をスタートさせた。通常、変位センサの抵抗体に用いられる金属や半導体は、
可逆的に伸縮可能な変形量が小さいため用途等に制限があった。同社が開発したストレッチャブル変位
センサは多層 CNT のナノ構造変化による電気抵抗変化から変位を検出するものであり、「薄い・軽い・
伸びる・自由な形」といった特長により応用範囲が広い。
ヤマハでは多層 CNT を紡績して得られる高配向 CNT シートと基材とを積層し、表面保護層や電極
を設けた後に切り出して変位センサとしている。CNT 層には相対的に剛性の低い領域(ギャップ)が存
在し、CNT の配向方向に引っ張るとギャップが伸びて電気抵抗値が上がり、収縮すると電気抵抗値が下
がる。また、ギャップ位置が固定されているため測定毎に異なる領域が伸縮することを防ぎ、感度の線形
性や再現性が高まっている。
2015 年 6 月にはセンサバンド×2(予備 1)と無線(BLE)モジュール×1、連動するアンドロイドア
プリを組み合わせた評価キットの販売を開始した。検出信号(電圧値)をワイヤレスでスマートフォン・タ
ブレットに送信できるほか、モジュール内蔵の 6 軸モーションセンサ(傾き、加速度、ジャイロ)との同時表
示・記録が可能である。
また、ストレッチャブル変位センサを指関節間に設置させたデータグローブを開発している。
CNT ナノ構造変化による動作原理 変位センサを組み込んだデータグローブ
バンドー化学
2015年に自社のゴム・ウレタン材料の配合設計とフィルムの加工技術、導電材料の分散技術を組み合
わせた伸縮性ひずみセンサ「C-STRETCH」を開発した。同センサは柔軟で弾性変形するエラストマー
(絶縁層)と、伸張変形に追従可能な伸縮電極層(導電層)が交互に積層された構造となっている。
478
静電容量式の採用により高精度の計測を実現しているほか、低ヒステリシスのため繰り返し再現性も高
い。また、低ひずみ~大ひずみまで直線性が良く、応答性に優れることから早い動きも計測できる。最大
伸度 200%まで計測が可能であり、10 万回の伸縮後(伸度 100%)でも性能劣化が生じない耐久
性を確保した。
センサとしての精度の高さに加え、非常に柔軟で大きく伸縮できることから、人体などの曲面に装着した
際には動きの追随性に優れ、装着した際の違和感も少ない。
2018年に開催された第4回ウェアラブル
EXPO では「C-STRETCH」を利用した呼吸数計測ツール、嚥下回数計測ツールを出展した。
呼吸数計測ツール 嚥下回数計測ツール
479
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位 5 位程度まで列記)
主なメーカとしては、Under Armour(米)、Sensoria(米)、Interactive Wear AG(ドイツ)、
Clothing plus(スイス)、Mcell(韓)、AiQ(台湾)などがあり、その他にも、Intelligent Clothing
Ltd.(英)、International Fashion Machines、Inc.(米)、Schoeller Textiles AG(スイス)、
Textronics、 Inc (米)、Vista Medical Ltd.(カナダ)、Textronics Inc.(米国)、
Gentherm Incorporated(米国)などがある。
(ⅰ)米国
Under Armour
Under Armour は、全ての人をより良く、より速く、より強くすることができるという考えに賭け、2016
年 1 月から、体重計、ウェアラブル・アクティビティトラッカー、心拍数測定用のチェストストラップをキットにし
た「Healthbox」を提供している。
2017 年に開催された CES(コンシューマー・エレクトロニクス・ショー)では、アスリートの睡眠中の回
復を助ける機能性衣類である「Smart Sleepwear」を発表した。衣類の中には、赤外線のパターンが
組み込まれており、睡眠中の赤外線の波長を吸収し、睡眠中の炎症を軽減させ、身体の回復に役立つ
という仕組みである。また、2018 年1月にはスマートシューズである「Hovr Phantom(130$)」、
「Hovr Sonic(110$)」を発表している。靴底には、ブル-トォースモジュール、加速設計、ジャイロスコー
プ、バッテリーが内蔵されており、バッテリー寿命は、製品の定格使用寿命とほぼ同一であるため、交換の
必要性はない とさ れている。また、同社は UA Record 、MapMyFitness 、Endomondo、
MyFitnessPal などのフィットネスプラットフォームと連携しており、これらプラットフォームはすべて、
Amazon のウェブサービス上で動作するように統一されている。
480
Sensoria
IoT 対応衣類の代表的なメーカである Sensoria は、2013 年 8 月にクラウドファンディング
「Indiegogo」の支援を受け設立され、2014 年 3 月から主力製品である「Smart Socks」を販売開
始した。
スマートソックスは導電性繊維とテキスタイルセンサで構成されており、別売品のアンクレットと組み合わ
せることで、運動情報をスマートフォンに転送できるシステムである。また、心臓病学者が設計しているアル
ゴリズム「Heart Sentinel」を導入しており、運動中のユーザの不規則な心拍数に応じてリアルタイムにア
ラートを鳴らすことにより、運動中に起こりうる心臓ショック、その他の事故を事前に防止できる。
同社の製品の材料には、遠赤外線技術を使用した耐久性のある「Emana 糸」を使用している。その
機能としては、乾燥性、快適性、紫外線遮断、皮膚の弾力性改善、セルライト・筋肉疲労防止などが
挙げられる。iOS、Android、その他の HRM デバイス向けのフィットネスアプリに対応しており、フィットネス
マニアをターゲットに開発を続けている。
2016 年 1 月には、米 Microsoft 社の人工知能「Azure」との提携を発表し、サッカーチーム向けの
システム「Microsoft Soccer Dashboard」を開発した。Sensoria のスマートシューズや衣類を使用して、
心拍数、加速度、減速、パス、ショットを監視し、フィールド上でのプレイヤーの動きを追跡することができ
る。各データは、Azureによって強化されたSensoria Cloudによって処理され、Sensoriaによって提供
される Microsoft Soccer Dashboard を介して表示される仕組みである。2017 年からは
VIVOBAREFOOT 社との提携を発表し、技術提携によるスマートシューズも発売しており、独自のアプリ
を通して、AI コーチ「Mara」によるリアルタイムコーチングサービスなども行っている。
481
(ⅱ)欧州
Interactive Wear AG (ドイツ)
2005 年に設立された Interactive Wear AG は、Infineon Technologies AG のウェアラブルビジ
ネスを買収することによってスマートテキスタイル分野で成長してきた。同社はヒーティング、ライティング、セ
ンシング、コネクションなど様々な技術を保有しており、これらを融合するための独自のプラットフォームも開
発している。IHK、Bluetooth、VDE、EtherCAT などの企業とパートナシップを提携しており、今まで
130 個以上の製品を開発した実績を持つ。使用しているマテリアルには銀コーティング素材、ステンレスス
チール、銅、グラフェン、カーボンマテリアルなどがある。
同社は、独自の IoT技術やスマートテキスタイル関連技術を融合して、数々の企業との提携で製品を
作り出しており、その事例としては、Bogner 社との協力で作った「Bogner Heat Jacket」、BMW 社に
提供したライダージャケットなどが挙げられる。
製品開発事例
482
Clothing+(フィンランド)
子供用の衣類ブランドである Reima Ltd 社の子会社として 2003 年に設立された。早い段階からス
マートテキスタイル製品の量産化に成功し、2017 年時点で累計出荷個数 5 千万個を達成している。
Suunto 社(トランスミッター・ソフトウェアアプリケーション)、Jabil 社(EMS 企業)などとの提携を通し
て技術的進歩を成し遂げ、グローバル・サプライチェーンを獲得している。今後の市場の拡大に応じて、中
国の蘇州市にフットウェア用の工場を、アメリカのフロリダ州に研究所を新設する計画と発表した(2018
年)。
同社は心拍数を図るセンサ技術に早い段階から着目し、世界最大の HRM ストラップブランドとのコラ
ボレーションにより、洗濯時にセンサを取り外す必要のない、世界最初の心拍センサソリューション「+
Peak+ HRM solution」を開発している。Peak +は過去および現在のデータを分析し、HRM ソリュー
ションから送信されたデータの意味を深く把握し、着用者のバイタルサイン評価を通じて物理的トレーニン
グのストレス、回復、および効果を表示する。また、同製品にはコンピュータに搭載された統合ソフトウェア
アプリケーションも含まれており、ユーザのパフォーマンスと全体的な健康状態をよりよく理解できるようにし、
サポート分析を通じて両方を改善できる。Clothing+は、ヘルスケアとフィットネスの2つの分野において、
すでに持っている様々なソリューションを融合し、企業にカスタマイズして提供するといったビジネスモデルを
提供している。
開発製品事例
Peak+ ソリューションの概要
〔出所:Clothing+〕
センサーの種類 測定項目
ECG 心拍数, 心電図, 心臓の活動性
EEG 脳派
EMG筋肉の動き, バイオ生体インピーダンス
(体組成、肺活動、脱水)
SCR 皮膚の伝導性、感情、活動
Accelerometer 動き、姿勢
Optical 心拍数、血中酸素濃度
Inductive/capacitive 心拍数,筋肉の動き
Temperature 体温、熱
Acoustic 関節の疲れ、心拍数
483
(ⅴ)台湾
AiQ
2009 年に台湾のテキスタイル会社 Tex-Ray の社内部門としてスタートし、2012 年に子会社となっ
た。製品には King’s Metal Fiber Technologies 社製のステンレススチール繊維や糸を使用しており、
汗、摩擦などに強く、材料自体が伝導性を持つため、他社製品のように銅や銀でコーティングせずに済む
という。
同社のスタンダード製品には織物電極形態の生体センサが縫い付けられており、生体情報をスマート
フォンに転送することができる。主力製品である「BioMan」スポーツシャツシリーズはユーザの心拍数、呼
吸、肌の温度、湿度、および電気生理学的信号(EKG、EEG、EMG)を測定でき、それぞれの機能
を組み合わせてカスタム制作できる。夜間運動のためライティング機能が付いた「NeoMan」モデルなども
発売されている。
AiQ の製品は医療用ガウン、病院の衣服や毛布自体がセンサとなることで、患者のバイタル信号への
アクセスを大幅に増やせることから、医療業界で注目されている。その他の製品としては、導電性繊維ベ
ースの高性能アンテナと RFID モジュールを組み合わせ、ソリューション全体をあらゆるアパレル、リネンなど
の繊維に容易に組み込むことができるテキスタイルタグ「RFID Laundry Tags」などが発売されている。
485
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
繊維学会・スマートテキスタイル研究会運営委員会名簿、および日本の研究者.com、J-GROBAL、
CiNii(検索ワード:スマートテキスタイル、E テキスタイル)を用いて国内の研究者を抽出した。結果は
以下のとおりである。
486
(補足)研究者の動向
~“PATENTSCOPE”を使用。検索キーワード:Smart Textile)
発明者 7 名のうち、日本の研究者としては INOUE SHIGEMI、OGOSHI MASAYUKI
(TECHNICAL RESEARCH & DEVELOPMENT INSTITUTE MINISTRY OF DEFENCE )
が挙げられたが、所属は海外企業ではなく、海外企業・組織に移った形跡はデータベースからは確認でき
なかった。
487
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な
研究者及び所属機関
Google Scholarの学術記事検索、IEEE(米国電気電子学会)のポータル、各国のニュースなどか
ら、各国の主な研究機関及び研究者を以下にまとめた。
(ⅰ)米国
アメリカの主な研究機関及び研究者
〔出所:FederalReporters、IEEE より矢野経済研究所作成〕
488
(ⅳ)韓国
韓国の主な研究機関及び研究者
〔出所:Naver 学術情報検索より矢野経済研究所作成〕
(ⅴ)台湾
台湾の主な研究機関及び研究者
〔出所:TTRI, IEEE, Google Scholar より矢野経済研究所作成〕
491
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プ
ロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
日本の研究者.com、KAKEN(検索ワード:スマートテキスタイル、Eテキスタイル)を用いて政府予
算による稼働中の研究開発プロジェクトを抽出した。結果は以下のとおりである。
プロジェクト名
縫製及び洗濯耐久性に優れたス
マートテキスタイル向けセンサー用並
びに配線用導電性縫い糸の開発
導電性織物の画像処理
ヘルスケア衣環境のための光ファイ
バセンサを導入したウェアラブルシス
テム
期間 2017年度 ~ 2019年度 2016年度 ~ 2019年度 2016年度 ~ 2020年度
予算金額 9,750万円 2,366万円 4,030万円
資金拠出元 経済産業省(サポイン事業) 文部科学省(科研費) 文部科学省(科研費)
概要
(1)堅ろうな金属皮膜を有するセン
サー用及び、(2)繊維内部に導電
性を持ち、その縫い目を通じてセン
サー部と電源等とを、接続する配線
用の導電性縫い糸の開発
(1)特定位置以外での絶縁性を保
ちつつ自動作製可能なパターンを
開発する、(2)感度向上 位置・信
号強度の空間的な分解能を高め
る(符合化織の提案)
光ファイバコア内を透過する近赤外
光の波長が橈骨動脈上の体表面
に貼り付けられたコア部分のセンサ
部で受ける歪に対して変化し、この
波長変位から各種バイタルサインを
計測するウェアラブルデバイスの開発
助成主体滋賀県産業支援プラザ
フジックス
豊浦 正広 山梨大学, 総合研究
部, 准教授
石澤 広明 信州大学, 学術研
究院繊維学系, 教授
プロジェクト名多層化した導電性編物製敷布に
よる褥瘡予防システムの開発
安全・快適を実現するスマートテキ
スタイルの創製
期間 2017年度 ~ 2019年度 2017年度 ~ 2019年度
予算金額 468万円 468万円
資金拠出元 文部科学省(科研費) 文部科学省(科研費)
概要 非公表 非公表
助成主体藤岡 潤 石川工業高等専門学
校, その他部局等, 准教授
竹本 由美子 武庫川女子大学,
生活環境学部, 講師
492
⑪米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府
支援策の有無
(ⅰ)米国
Federal Reporter より、「smart textile」、「e-textile」のキーワードで現在稼働中、あるいは近
年の関連プロジェクトを調査した。結果は以下のとおりである。
アメリカの主な研究開発プロジェクト
出所:Federal Reporter
プロジェクト名
CPS: SENSING PROCESSING
AND ACTION OF BIOMEDICAL
SMART TEXTILESFABRICATION
PFI: BIC WEARABLE SMART
TEXTILES BASED ON
PROGRAMMABLE AND
AUTOMATED KNITTING
TECHNOLOGY FOR
BIOMEDICAL AND SENSOR
ACTUATION APPLICATIONS
CAREER: TOWARD PERVASIVE
WEARABLE TECHNOLOGY: A
CUT-AND-SEWN, TEXTILE-
INTEGRATED SMART
CLOTHING PLATFORM
期間 2016.05~2020.0 2 2014.08~2017.07 2013.03~2018.02
資金拠出元 NIBIB National Science Foundation National Science Foundation
予算金額 369,994 USD(2016年予算) 799,577USD 99,636USD
参加機関DREXEL UNIVERSITY DREXEL UNIVERSITY UNIVERSITY OF MINNESOTA
TWIN CITIES
プロジェクト目標
①スマートファブリックセンサーとアクチュ
エーターを衣類に組み込み、深刻な静
脈血栓症(DVT)のための邪魔にな
らない予防オプションを提供する。②セ
ンシング - シームレスに編成され、バッ
テリーや煩わしいエレクトロニクスを必要
としない、控えめなレッグモビリティ測定
システムの開発。③信号処理 - モー
ションアーチファクトやセンサー位置の変
化などの非確定的な外乱に対して堅牢
性を持たせる、リアルタイムで予測的な
データ駆動制御システムの開発。④ア
クチュエーション - 遠隔操作治療のた
めに体内の組織を機械的に刺激するた
めの生物医学的スマートテキスタイルの
開発。
現在のかさばる医療監視装置を軽量
スマートな衣服で置き換えることを目指
す。ファブリックベースのコネクタ、マイクロ
波アンテナ、スーパーキャパシタ、ロボ
ティクスなどの知的財産を活用してス
マートファブリックのセンサとアクチュエー
タを快適な衣類に統合し、現時点では
不可能な目立たないセンシングと治療
オプションを提供する。
新しいハードウェア開発が要らず、多様
なアプリケーションの開発を容易にでき
る、センシングおよび作動技術のための
柔軟で適応性のある衣服「一体型
アーキテクチャ」の調査。さらに、このプロ
ジェクトで支援されている活動は、
STEMの分野における女性の参加を拡
大し、教育の分野間学識を奨励する。
494
(ⅱ)欧州
欧州委員会の取り組み(FP6・FP7)
欧州では、衣服や包装用紙などに半導体チップを埋め込もうという研究が盛んである。2007 年より大
面積エレクトロニクスを中心に、4 年間の「STELLA(Stretchable Electronics for Large Area
applications)」計画が、FP6(第 6 次フレームワーク)の枠組みの中で進められた。4 年間で総額
1316 万ユーロを投資している。
その継続プロジェクトとして、2010 年からは FP7(第 7 次フレームワーク計画)において「PASTA
(Integrating Platform for Advanced Smart Textile Applications)」計画が IMEC を中心
に進められた。PASTAは半導体の実装技術やプリント配線技術と、テキスタイル技術を組み合わせること
で、スマートテキスタイルを実現するためのプロジェクトである。当計画は4年間のプロジェクトであり、ベルギ
ーの研究開発機関である IMEC がプロジェクトリーダーとなった。パートナーとしては、フランスの原子力庁
CEA、フランスのスポーツソシエ社、ドイツのフラウンホッファ IZM、スイスのマイクロエレクトロニクス研究所で
ある CSEM など 8 団体が参加した。
PASTAの「スマートテキタイル」
〔出所:PASTA〕
495
PASTA参加機関
〔出所:PASTA〕
欧州技術プラットフォーム(ETP)
2004 年に設立された欧州技術プラットフォーム(ETP)は、欧州地域の繊維産業や大学・研究機
関から 650 人を超える専門家が登録する欧州最大の繊維技術ネットワークとなっている。同プラットフォ
ームは欧州繊維産業連盟(EURATEX)が中心となって運営しており、戦略的技術指針の作成と実
行、並びに欧州委員会などの研究政策立案者や資金計画管理者に繊維研究の優先事項を伝えるこ
とを重要な役割としている。
同組織は欧州全域の繊維産業の代表者らで構成され、SAATI 社(イタリア)の paolo Canonico 会
長が率いる運営評議会の戦略の下で活動している。同じく運営評議会に代表をだしているのが、欧州
繊維研究機関 2 つの主要団体である「欧州繊維研究機関ネットワーク(TEXTRANET)」と、「繊維
系大学連合(AUTEX)」である。 ETP は創設以来、欧州全域で繊維分野の共同研究プロジェクト
の立ち上げに貢献してきた。毎年カンファレンスを開催し、欧州の繊維関連の研究・技術革新に向けたビ
ジネスや知識ネットワークを形成・拡大するとともに、FP7などの公的研究資金制度がもたらす機会につい
ての情報提供の場としても活用されている。
2017 年のカンファレンスでは HORIZON 2020、COSME、LIFE、INTERREG を含むヨーロッパの
主要な研究・イノベーション・プログラムにわたる繊維関連の研究プロジェクトが取り上げられた。 全 28 の
プロジェクトは、2016 年 10 月に発表された SIRA(Strategic Innovation and Research
Agenda)の 4 つのテーマ:スマートで高性能な素材、高度なデジタル化された製造、バリューチェーンと
ビジネスモデル、循環経済と資源効率 魅力的な成長市場向けの高付加価値ソリューションに分けられ
る。
496
2017年 ETPカンファレンスのスマートテキスタイル関連プロジェクト
〔出所:ETP〕
2017年 ETPカンファレンスのプロジェクトリスト(全体)
〔出所:ETP〕
プログラム プロジェクト名 概要
H2020 1D -NEON
欧州のテキスタイル製造業に付加価値を
作り出すことを目的とする。スマートマテリ
アルを採用したテキスタイルの開発によっ
て、センシング、ライティング、エネルギー分
野に進出する。
H2020 ETEXWELD
革新的なe-テキスタイル製品を設計する
ために、様々な国、部門、専門分野の
専門家を集めて、溶接技術を使用した
インタラクティブな防護服と履物用の革新
的な電子繊維製品を開発する。
LIFE+ LIFE-ECOTEXNANO
リスクアセスメントを改善し、繊維加工産
業におけるナノ材料の安全な使用を促
進する革新的なツールを開発する。
497
繊維系大学連合「AUTEX」
1994 年に設立された AUTEX(繊維系大学連合) は、繊維教育・研究で国際的に定評のある
大学が集まった学際的団体である。欧州のほか、米国や中国にも会員が存在する。現時点では、30 カ
国から 39 の機関・団体がメンバーとなっている。ポーランドの Lodz 大学の Katarzyna Grabowska 教
授が会長を務めている。
AUTEX は、繊維教育の将来の発展や基礎研究、戦略的研究、応用研究で主導的役割を果たす
ことを目指している。繊維教育改善への大きな成果は、繊維教育の第一線の専門家が欧州各地で行う
欧州繊維修士課程プログラム(E-TEAM プログラム) の実現である。
欧州繊維修士課程プログラム「E-TEAM」
繊維工学分野の 2 年間の修士課程として、EU の全面的支援の下で開発された。国際的な高度
先進プログラムであり、繊維分野の最新動向が取り入れられている。このプログラムの目的の一つは、学
生が繊維に関心をもたない流れが続いていることを食い止めることにある。そのために、繊維以外の先端
異分野との学際的な形で導入され、講師は欧州の著名な教育専門家が集められている。プログラム内
容は技術革新、創造性、品質等、世界をリードする企業経営を求めて努力を続ける繊維産業の要求
を確実に満たしている。
繊維教育を提供する欧州の主要大学(8 カ国 20 大学) は、すべてこのプログラムに参加しており、
繊維に関連するあらゆる近代的領域が網羅されている。2 年コースの 4 期のうち、最初の 3 期は会員
大学で決められた順序で 1 期(4~ 6 カ月) ごとに学び、最後の 1 期は学生が志望する大学・教
授の下で卒業研究を行う。講義形式のほかにケーススタディ、論文発表、研究所での実際の作業などの
活動的な方法が用いられ、理論と実践を結びつけるために開講国での企業訪問も定期的に行われてい
る。
欧州繊維研究機関ネットワーク「TEXTRANET」
TEXTRANET(Textile Transfer Network、欧州繊維研究機関ネットワーク)は、オーストリア、
ベルギー、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、英国、ギリシャ、ハンガリー、リトアニア、ポーランド、ポルトガ
ル、ルーマニア、スウェーデン、スイス、スペイン、チュニジアの繊維研究機関で構成する団体で、(a)技
術的・商業的優位性の獲得、(b)会員間の情報交換、(c)国際プロジェクトの立ち上げ(特に欧
州の資金獲得に重点を置く)、(d)繊維分野と異業種分野の協力関係の拡大と維持、(e)欧州
繊維産業の技術発展を推進するフォーラムの開催など、多岐の活動を推進している。あわせて、欧州技
術プラットフォームを支える重要な柱の一つとしても機能している。
498
(ⅲ)中国
工業情報化部は、2016 年 9 月に「紡織工業発展計画(2016-2020)」を発表した。計画では
6 項目の重点任務、すなわち、イノベーション能力向上、三品戦略の実施、スマート製造推進、 緑色
発展の推進、地域の協調発展の促進、企業の総合実力向上を定めている。
骨子としては、繊維業界が品種を増やし、品質を向上させ、ブランド(品牌)力を向上させるという
「三品」戦略に重点が置かれ、スマート製造とグリーン製造を推進し、繊維強国を初歩的に建設するとい
った目標が打ち出されている。
また、同部は、2017 年 3 月に「2017 年消費品工業「三品」専項行動計画」を発表した。「計画」
では、企業におけるスマートウェアラブルデバイスの研究·開発·応用を推進し、スマートウェアラブルデバイス
関連コア技術の研究·開発を支持する方針が示された。スマートウェアラブルデバイス普及のための推薦
目録を作成し、豊富な新型民生用電子製品を供給する企業を育成するという。
(ⅳ)韓国
韓国ではスマートテキスタイルを対象とした国家プロジェクトが見当たらなかったため、個別の研究機関
等への支援策を以下に例示する。
韓国京畿道
ドイツと共同で、知能型電子繊維「Smart Textronics」融合技術を推進するための研究所を、
2017 年 9 月に安山市の京畿テクノパークに設立した。両国は、2016 年 11 月ドイツのアーヘン市にも
共同研究所「Dream2Lab2Fab」を設立している。京畿道、韓国生産技術院、Sung gyungwan
University、ノルトラインヴェストファーレン州、アーヘン工業大学との協力を通して、スマートテキストロニ
クス技術を開発し、普及・常用化を目指す。2021 年までに韓国政府が 17.6 億円、ドイツが 2900 万
ユーロを支援する。
光州科学技術院(NID)
NID の Ko 教授は、2016 年 6 月に未来創造科学部、教育部、産業通商資源部の支援を得て、
高性能・高集積素子が使用される、人工纖毛付きの電子繊維を開発した。人工纖毛を利用した電子
素材印刷法は、多様な動植物や物に適用できるため、ウェアラブルディスプレイ、パソコン、医療、環境モ
ニタリングセンサ分野などに活用できる。性能テストとしては、研究員のシャツにプリントし、1 万回以上の
変形と、洗濯・乾燥実験を行ったが、素材及び特性の変形は見らえず、研究チームは今後、姿勢矯正
や健康状態確認などに応用できると見込んでいる。
499
「人工纖毛付きの電子繊維」
KAIST(Korea Advanced Institute of Science and Technology)
2017年 11月にChoi Kyung Cheol教授の研究チームが、織物と有機発光ダイオード(OLED)
を融合した高柔軟性かつ高効率の衣類型ディスプレイ技術を開発した。衣類型ウェアラブルディスプレイを
実現するため、織物型(fabric)、繊維型(fiber)の 2 種類に分けて研究を進め、その結果は、国
際学術論文(Scientific Report)にも掲載されている。開発者の Choi 教授は、今後発光する衣類
は、ファッションだけでなく、自動車、光治療のようなヘルスケア産業にも大きな影響を及ぼすと展望してい
る。この研究は、産業通商資源部の支援のもとに、(株)KOLON GLOTEH との共同研究プロジェク
トの結果物である。
高柔軟性衣類型ディスプレイ
500
(ⅴ)台湾
TTRI(台湾繊維研究所)
1959 年に設立された TTRI(台湾繊維研究所)は、台湾の中小企業が創業初期に必要な R&
D 関連資源を提供しており、生産工程改善や販売販路の改善についてもアドバイスしている。TTRI の
サービス範囲は繊維、生地、縫製、小売までに至っており、台湾のテキスタイル産業には欠かせない中核
機関となっている。
2017 年 3 月には台湾経済産業省の技術開発プロジェクト「Small Business Innovation
Research Program (SBIR)」の支援を受けて、「台湾スマートテキスタイルアライアンス(TSTA)」を
結成した。この提携の主な目的は、革新的な製品の開発、産業基準の確立、市場調査であり、材料サ
プライヤ、繊維メーカー、エレクトロニクスおよびシステムサプライヤ、認定団体、デザイナーおよびマーケティ
ングチャネルを統合している。現時点では、Foxlink、HTC、Zentan、ECLAT、Everest Textile など
42 社がこの提携に加盟しており、台湾のスマートテキスタイル開発の健全なエコシステムを構築することを
共通の目標としている。
2017 年 5 月のに台湾で開かれた展示会「COMPUTEX」では、RUENTEX、Everest Textile、
AiQ / TexRay、Sunstar、Zentan、Maxtek Go-Go など、提携メンバーの 6 社が「台湾スマートテ
キスタイルアライアンス」のブースで、様々なスマートテキスタイル製品、スマートな衣料品アプリケーション、
ヘルスケアソリューション、インタラクティブテキスタイルファブリックを展示した。
501
TTRI は様々なテキスタイル関連の R&D プロジェクトを進めており、「DoIT Programs」の枠組みの
中で、スマートテキスタイル関連プロジェクトである「TTRI Innovation&Forward-Looking
Technology Research Program」が現在稼働中である。このプロジェクトの目的は、新しい材料と技
術を組み合わせて、研究開発分野のリスクを高め、提案されている主要産業技術、製品、サービス、革
新的な繊維製品の中長期的な開発に集中することである。
「TTRI Innovation&Forward-Looking Technology Research Program」
1.新しいナノグレードとバイオテクノロジーを統合し、高性能で多機能な複合繊維または繊維を確立す
る。
2.高度な技術と自然素材を研究し、統合されたスマートテキスタイルを開発することによって、新たな産
業技術を確立する。
3.技術繊維と織物を開発するための多様なアイデアやコンセプトの学際的なポートフォリオによって、技術
繊維に関する国家開発目標を達成する。
4.国家 IP 分析の能力を確立し、研究と設計能力を高めるためのコア技術を開発する。
〔出所:TTRI〕
502
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
「① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要」で述べた「スマートテキスタイル開発の重要技
術」において、現段階でスマートテキスタイル向けに配線材料、配線形成技術、実装・接合技術を製品
化(開発中のものを含む)あるいは適用しようとしている企業・製品・技術は以下の表のとおりである。
〔矢野経済研究所作成〕
種別 企業名 製品
セーレン 導電性繊維
ミツフジ 導電性繊維「Agposs」「AGfit」
カジナイロン 伸縮配線
セーレン 導電パターンファブリック(印刷・銀糸配線)
パナソニック ストレッチャブルデバイス「WEARABLE MAKER PATCH」
太洋工業 テキスタイルFPC
実装・接合技術 セメダイン 導電性接着剤「SX-ECA」
配線材料
配線形成技術
503
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
スマートテキスタイル向けの事業展開を積極的に行っている製造装置メーカーは、独自の生産技術「ホ
ールガーメント」を保有する島精機製作所である。「ホールガーメント」生産により得られるニット製品は、
一着まるごと編み機から直接、立体的に編み上がるため、裁断や縫製といった後工程が不要となる。さら
に、ニット本来の手触りと軽さを引き立て、ドレープ性、フィット感を高められる。ミツフジの着衣型生体セン
サ「hamon」で、同社の装置が使用されている。
508
(補足)ニュース・リリースまとめ
〔矢野経済研究所作成〕
企業・研究機関 詳細内容
2018 1 東北大学、ユニオンツール、東洋紡 「産後うつ」研究向け妊婦用スマートテキスタイルを開発
2018 1 帝人フロンティア、関西大学 圧電刺繍(e-stitch)の開発について
2017 10 東レ・ANA、コンビ、NTT 「赤ちゃんが泣かない!?ヒコーキ」プロジェクトを立ち上げる
2017 10クラボウ、大阪大学、信州大学、日
本気象協会、ユニオンツール、他
熱中症リスク管理システムの基礎アルゴリズムと基本アプリケーションの完成
について
2017 10 ミツフジ
福岡市と体調見守り実証実験をスタート
使い切りスマートウェアを発売
導電繊維の新製品「Agfit」を発売
2017 9 グンゼ グンゼ×RIZAPによる最先端衣料「筋電WEAR」が誕生
2017 7 ミツフジ 電通、前田建設工業、南都銀行、VCなどから総額30億円を調達
2017 6 旭化成※ 2018年にもスマート衣料に参入
2017 3クラボウ、大阪大学、信州大学、日
本気象協会、ユニオンツール
人センサー集団を活用した熱中症リスク管理システムとスマート衣料の開
発に着手
2017 1 日清紡ホールディングス※ 生体情報を取得できるスマートテキスタイルの開発に乗り出す
2017 1 東洋紡、ユニオンツール 居眠り運転検知システムを共同開発
2017 1 帝人、帝人フロンティア、関西大学 圧電組紐の開発と展開について
2016 12 ミツフジ ウェアラブル総合ブランド「hamon」の販売を開始
2016 9 東レ「hitoe メディカル電極」と「hitoe メディカルリード線」の一般医療機器とし
ての登録を完了
2016 7 東洋紡 「COCOMI」が、競走馬の心拍数測定用腹帯カバーに採用
2016 5東レ、NTTデータMSE、京都大学、
熊本大学、NTTドコモ
「hitoe」ウェアを活用したドライバー向け眠気検知システムを共同で開発
し、運送会社協力のもと実証実験を開始
2016 4 東京大学、NTTドコモ脈の揺らぎを自己管理するスマホアプリを開発。「hitoe」を活用した不整
脈と生活習慣病の関連性を解析する臨床研究を開始
2016 1 グンゼ NECの技術協力により、衣料型ウェアラブルシステムを開発
2016 1 NTTデータ、NTT DATA, Inc.米国インディカー・シリーズにおいて、「hitoe」の活用により走行時のドライ
バーの生体情報を取得する実証実験を実施
2015 8 JAL、NTT Com、東レ空港での屋外作業者が安全に働ける環境の整備を目指し、IoTを活用し
た安全管理システムの共同実証実験を開始
2015 8 東洋紡 「COCOMI」を開発し、生体情報計測ウエア市場に参入
2015 3 大林組、NTT Com IoTを活用した作業員向け安全管理システムの実証実験を開始
2015 1 帝人、関西大学 圧電ファブリックを開発
2014 12 ゴールドウイン 「C3fit IN-pulse(インパルス)」シリーズの販売開始
2014 1 東レ 「hitoe」の開発及び実用化について
※ニュースリリースではなく、新聞等のメディア情報
日付
509
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要 (ⅰ) フレキシブルデバイスの概要
あらゆる情報・電子機器がネットワークを介してモノとヒトの全てが繋がる IoT 社会の実現に向け、小型・軽量化、フレキシブル性を実現できるフレキシブルデバイスが注目されて久しい。フレキシブルデバイスは、これまでの PCB 基板上に実装されるエレクトロニクスデバイスとは異なり、プラスチックや紙などの柔軟性に富んだ基板上に形成される。
また、フレキシブルデバイスを多品種変量で製造するためのキーテクノロジーに、プリンテッドエレクトロニクス(PE)技術がある。PE 技術とはプリンティング(印刷)技術を活用し、電子回路/センサ/素子などを製造することと定義される。従来のフォトリソグラフィー技術を用いた真空プロセスに⽐べ、省エネルギー、高生産性、低初期投資といった優位性があるほか、低温・常圧で製造でき、大面積基板に対しても適用性が高いなどの特⻑を有する。
一方、PE 技術だけでは機能・信頼性の面で十分なデバイスが供給できないことから、近年はシリコン技術と PE 技術のハイブリッドな融合技術、いわゆるフレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)への注目が高まっている。
〔出所:矢野経済研究所「プリンテッド・エレクトロニクス製品の潜在市場性調査」 2015. 10〕
511
(ⅱ)フレキシブルデバイスの重要技術 PE 技術を用いたフレキシブルデバイス開発の重要項目は、(a)インクとなる有機・無機・⾦属のナノ材
料、(b)高精度に制御された印刷技術、(c)実装・接合技術である。 (a)インク材料の開発
インクジェット法やスクリーン印刷などの印刷プロセスによってフレキシブルデバイスを製作するためには有機半導体材料や絶縁材料などのインク開発が必要不可⽋である。
材料のインク化にあたっては、印刷性や密着性、印刷後のパターン安定性のため半導体、絶縁体それぞれの機能を損なわない界面活性剤や増粘剤、表面調整剤などを添加する必要がある。特に、導電インクとして⾦属の微粒子分解液を用いる場合、添加剤の除去と⾦属微粒子の低抵抗化のため焼成が必要となるが、この熱が他の材料へ及ぼす影響が大きいためできるだけ低温での焼成が望ましい。 (b)印刷技術
デバイスの設計に基づき印刷プロセスによるパターニングを⾏うには高精度な刷版の製作が求められる。版を必要としないインクジェット法であってもインクの着弾精度やノズルの詰まり防⽌など、インクジェットならではの課題も少なくない。パターニング精度の向上と印刷された膜との密着性向上のためにも、被印刷面の表面エネルギー制抑及びインクの表面弾⼒の表面処理などの被印刷表面の表面処理は⽋かせない。これはパターニング精度のみならず、フレキシブルデバイスの特性を左右する重要な課題である。
また、製造するフレキシブルデバイスによってパターンの線幅、膜厚が異なり、印刷方法を変える必要がある。印刷方法によって要求されるインクの粘度などが違うことから、同様な機能をもったフレキシブルデバイスであってもインクは共通で使用できない場合も生じる。さらに、印刷装置そのものもすべて異なるものを開発しなければならないケースも出てくる。なお、各種印刷技術の概要は次ページの表のとおりである。 (c)実装・接合技術
全てを印刷プロセルで形成できるデバイスはほとんどなく、接続やラミネートなどの接合が必要となる。既存の電気的接合技術であるハンダ付けは温度が高く、銀とは相性の問題もあり一般的には用いることができない。等方性あるいは異方性の導電性接着剤が主役になるものと考えられている。
また、近年はフレキシブル基材上への印刷や塗布による配線・デバイス形成に加え、従来の製造法で作製されたシリコン半導体チップ実装なども組み合わせてデバイスを構築するフレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス技術に対する注目度も高まっている。
512
(ⅲ)特定の用途(生体情報の計測)に関する技術の概要 生体情報は生体内情報(⼼電、⾎圧、内臓脂肪など)と生体外情報(活動量、睡眠、⾷事など)
に区分できる。生体内情報においては、⼼電図から計算される⼼拍や脈拍がその変動率を解析することで⼼不全の兆候を検出できるほか、⼼拍のゆらぎを解析することで⾃律神経系の緊張度合いの評価(ストレスチェックや眠気検知等)も可能である。そのため、監視すべき最も重要なパラメータとの位置づけで、⼼拍や脈拍を主な測定ターゲットとした生体情報測定技術の開発が多くなされている。
生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS ⾮ウェアラブル)
従来、⼼拍や脈拍を計測する手法は電極を体に貼り付ける⼼電図測定といった接触型が一般的であり、その⾏為が⻑時間になればなるほど被測定者の⾃由を奪ったり、ストレスや緊張を与えたりするうえ、皮膚のかぶれなどの問題も生じてくる。
これに対して、被測定者の時間的な拘束から開放し、測定そのものへのストレスを低減する⾮接触型のセンシング技術の開発が活発する傾向にある。具体的には、圧電センサをベッドやソファーに搭載するもの、マイクロ波(またはミリ波)レーダやカメラ画像を用いるものなどである。ただ、これらの⾮接触型のセンシング技術はセンサが固定化されているため一定の場所でしか測定できない、あるいはセンサと⾮測定者の距離が離れると測定精度が低下するといった空間的な制約を受ける。
こうした各種センサの時間的制約、および空間的制約を解消する手法として、近年はウェアラブルデバイスを用いて⼼拍・脈拍や活動量等の生体情報を取得する手法に注目が集まっている。
生体外情報の一つである活動量の測定では、日常の一日あたりの歩数を計測する歩数計を皮切りに、エネルギー消費量を評価できる 1 軸式加速度センサ搭載型の活動量計、さらには⾝体の動きを3次元(X, Y, Z)で解析できる3軸式加速度活動量計が開発されている。現在は 3 軸式が主流となっており、衣類のポケットやベルトに装着するものから腕時計型・リストバンド型まで様々なタイプのものが製品化されている。そして、Apple Watch に代表される腕時計型やリストバンド型のウェアラブルデバイスでは、光電式容積脈波法(フォトプレチスモグラフィ)を用いたセンサを内蔵することで、生体内情報である⼼拍の測定を可能としている。
これら生体内情報を取得するセンサの概要とメリット・デメリット、および上記の時間的制約と空間的制約とを軸としたウェアラブルデバイスとそれ以外のセンサ(⾮ウェアラブル)を対象としたポジショニングマップを次ページ以降に掲げた。
514
生体センサのポジショニングマップ(ウェアラブル VS 非ウェアラブル)
〔矢野経済研究所作成〕 ウェアラブルデバイスの概要 ⾝体に装着して使用する小型の電子機器は 1970 年代末頃から製品化され始めたが、その機能は
現在のウェアラブルデバイスと大きな隔たりがあった。インターネット接続機能や高度な無線通信機能を装備した現代型のウェアラブルデバイスが技術的に実現可能となったのは 2000 年代中頃とされ、その関連技術は PC やフィーチャーフォン、スマートフォン、タブレット PC 等に応用されて普及が進んだ。その結果、様々なタイプのウェアラブルデバイスが製品化されているが、これを大別すると(a)腕時計型、(b)リストバンド型、(c)眼鏡型、(d)ウェア型、(e)貼付型、(f)その他に分けられる。
(a)腕時計型(スマートウォッチ) スマホの周辺機器として機能する「スマホ連携型」と、単独でネット接続機能や通話機能を持つ製品が
ある。また、OS の種類はアップルの「Apple Watch」(WatchOS)やサムスン電子の「Gear S」(OS:Tizen)等の独⾃ OS と、Google の Android Wear に大別される。Android Wear は台湾系ASUS(ASUSTeK Computer)の「Zen Watch」やLGエレクトロニクスの「LG G Watch」、ソニーの「Smart Watch3」、モトローラの「Moto360(2nd)」、その他様々な製品に搭載されている。
(b)リストバンド型(スマートバンド) 腕回りに装着するウェアラブル端末で、センサと無線通信機能等を内蔵しており、ユーザーの生体情報
を収集し、スマホを介してインターネット接続・クラウドサービスと連携する。ブレスレット型などと呼ばれることもあるが、前記の腕時計型端末の中で単独ではネット接続機能や通話機能を持たない「スマホ連携型」ウォッチとの境界ははっきりしていない。搭載センサは活動量計(歩数、消費カロリー)が中⼼だが、脈拍
516
計や加速度センサ、GPS 等を搭載する製品が増えている。このタイプはウェアラブル端末の中で最も多用されており、参入企業も多い。
(c)眼鏡型(スマートグラス) ディスプレイ装着型とその他の製品がある。2015 年 1 月に販売を中⽌した「Google Glass」はディ
スプレイ装着型の代表で、眼前に情報を表示するとともに、内蔵センサで情報を収集する。複眼型の製品が多いが、単眼型もある。 一方、ディスプレイ⾮装着型は通常の眼鏡の専門企業が開発に関与することが多く、この場合は通常
の高級眼鏡と同等のデザイン性と特性を保持しつつ内蔵センサやデバイスで情報を収集したり伝達する機能を持たせたりしている。このタイプはジェイアイエヌの「JINS MEME」や、なまえめがねによる「雰囲気メガネ」などが製品化済みである。
(d)ウェア型 導電性繊維などで作製した電極を衣服に熱圧着する、あるいは導電性繊維などを編み加工するといっ
た方法で、衣服そのものをウェアラブルデバイスとして利用するものである。 生体内情報の取得を目的としたデバイスの場合、⼼臓の活動に伴う⼼起電⼒によって生じる電位分
布の 2 点を電極で測定し、その電位差の時間経過から⼼電波形を計測する。この信号を衣類に装着したトランスミッターで、パソコンなどに無線で送信するといった仕組みが一般的である。⼼拍数は QSR 波のピーク間の時間(R-R 間隔)を算出することで得られる。また、トランスミッターに加速度センサを内蔵することで姿勢や歩容など着用者の動作情報を推定できる。
(e)貼付型 絆創膏のように胸や背中に貼り付けることで、生体情報を取得できるものである。フィルム基板上に形
成したセンサモジュールを使い捨てタイプのパッチに挿入したものが多く、本調査のフレキシブルデバイスに
517
該当する。代表的な製品として米 Vital Connect の「HealthPatch MD」がある。
(f)その他 コンタクトレンズ内蔵型、スポーツ用品(ラケット、ボール、シューズ等)内蔵型、指輪型・イヤホン型・
ペン型端末など多種多様なデバイスがある。まだ開発中の製品が多い。
フレキシブルデバイスのポジショニング 生体情報を取得できるウェアラブルデバイスを対象に、タイプ別の機能一覧、および「機能」と「装着感」
を軸に作成したポジショニングマップを次ページ以降に掲げた。 腕時計型やリストバンド型は表示機能から環境状況、生体情報(活動量、物理)の取得までを可
能とする多機能デバイスといえ、通信機能や電源も内蔵している。ウェア型は生体情報の中でも⼼電波形のみを取得する製品が主流であり、付属のトランスミッターを装着することで活動量や位置情報を取得する。また、通信デバイスや電源はトランスミッターに内蔵される。ウェア単独でみれば、多くの機能を搭載していないデバイスといえる。 一方、貼付型は電極と加速度センサなどを一体化しているほか、現状のコンプレッションタイプのウェア型
と⽐べると装着感は良好である。さらに、東京大学が開発を進めているデバイスなどは多機能かつ装着感にも優れたものになると考えられる。
518
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む) 柔軟性に富んだ基板上に形成されるデバイスは、表示デバイスやキーデバイス、電源デバイスとして
様々な分野への適用が可能である。
日本では、2011 年 4 月に産業技術総合研究所(以下、産総研)がフレキシブルエレクトロニクス
研究センターを設⽴した。この研究センターではフレキシブルデバイスの開発研究、プリンタブルデバイス製造技術の開発研究を柱として、有機エレクトロニクス材料の評価基盤技術の整備にも取り組んでいる。フレキシブルデバイスとしては、「フィルム基板上に形成した超薄型、軽量、大面積の耐衝撃性に優れた情報入出⼒インターフェースデバイス」として、フレキシブルメモリやフレキシブルガスセンサ、フレキシブルRFID デバイス、フレキシブルディスプレイを例示している。
フレキシブルデバイスの適⽤例
フレキシブルメモリ フレキシブルガスセンサ フレキシブル RFID デバイス フレキシブルディスプレイ 〔出所:産総研 HP〕
また、2011年5月には産総研のフレキシブルエレクトロニクス研究センターを主体に、⺠間企業も加わ
った「次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合(Japan Advanced Printed Electronics Technology Research Association:JAPERA)」が結成された。JAPERA ではフレキシブルデバイス技術と印刷デバイス製造技術を開発し、電子ペーパーや給電シート、フレキシブルセンサ、デジタルサイネージ、入⼒デバイスへの応用を目指している。
521
JAPERA の事業概要
〔出所:JAPERA 資料〕
表示デバイス:有機 EL ディスプレイ ここ数年、有機 EL ディスプレイに対する注目が高まっている。有機 EL は駆動方式の違いによって
PMOLED と AMOLED に大別される。もともと PMOLED は携帯電話のサブディスプレイとして使用されてきたが、近年ではディスプレイ用途としてはAMOLEDが使用されるケースが多く、PMOLEDは高画質・高精細がそれほど求められない照明用などでの適用が検討されている。
AMOLED は LCD と同様な使用が可能であるため、⻑らく LCD の対抗馬として注目されている。OLED と LCD の違いの 1 つとして、LCD がバックライトを使用するのに対し、OLED は⾃発光によって発光することが挙げられる。常にバックライトがオン状態で駆動する LCD に対し、OLED は必要なところだけを光らせるため、理論的に低消費電⼒化が可能である。OLED は電流に反応し有機物⾃体が光を出すため、LCD に⽐べ駆動電圧が低く、LCD 対⽐ 30〜50%程度低電⼒消耗が図れる。その上、LCDに⽐べ高い応答速度、バックライトが不要な分、OLED ディスプレイは薄型化及び軽量化、フレキシブル化できる点に特⻑がある。
AMOLED は次世代ディスプレイとして注目されてきたが、ディスプレイメーカー数の少なさや製品⾃体の性能向上が課題となり、LCD と⽐肩するまでのポジションには至っていなかった。
522
しかしながら、韓国・サムスン電子が「Galaxy S シリーズ」に AMOLED ディスプレイを搭載したことで、その市場は再び成⻑軌道に乗り始めている。2017 年には米国・Apple が「iPhone Ⅹ」に AMOLEDディスプレイを搭載し、その後は Apple を追従して同じ部品・デバイスを求める中国向けの量の拡大も⾒込まれている。
スマートフォン向けの AMOLED ディスプレイには、TFT 基板及び封⽌材などの基材としてガラスを使用した Rigid タイプと、ガラス基板とエンキャップガラス(封⽌ガラス)をなくし、PI 基板と薄膜封⽌層(TFE:Thin Film Encapsulation)あるいはパッシブ層とバリアフィルムを設けた Flexible タイプがある。
Rigid タイプは、サムスン電子の初期「Galaxy S シリーズ」に採用されて以降、現在は「Galaxy A シリーズ」や「Galaxy J シリーズ」などのミドルエンド品のほか、中国スマートフォン向けにも採用されている。
一方、PI 基板を用いた Flexible タイプは曲面形状やフルスクリーン化など、スマートフォンのデザイン性の向上に貢献できる。これまでも、サムスン電子の Curved スマートフォンである「Galaxy Round(2013 年 10 月発売)」を皮切りに、「Galaxy Note Edge」、「Galaxy S6 Edge」、「Galaxy S6 Edge Plus」、「Galaxy S7 Edge」に採用されてきた。2017 年には「Galaxy S8」、「Galaxy S8+」、「Galaxy Note8」にも採用されており、採用モデルの数が増えている。
また、Apple は 2018 年の「iPhone」の新モデル向けで Flexible タイプの搭載を増やすものと⾒られるほか、スマートフォン市場をリードする Apple と SEC に追従し、中国のスマートフォンメーカーも Flexibleタイプを搭載した新モデルの開発を検討するところが増えている。
523
キーデバイス:RFID RFID(Radio Frequency Identification)は近距離無線技術を利用して個体識別を⾏うもの
で、ID が入った専用の情報媒体(IC タグ)などを使用する。バーコードや磁気カードなどと同様に専用機器・システムで⾃動的に情報を取り込んで認識する⾃動認識システムの一種で、中核部品となるIC メモリーのコストパフォーマンスが向上した 1990 年代後半から注目度が高まった。
⾃動認識には様々な種類があり、バーコードや 2 次元コード(QR コード)、カラーコードなどのコード認識技術は利用形態が RFID タグと似ている。ただし、RFID は情報容量が大きく、バーコードの情報量の約 100 倍、2 次元コードの数倍程度まで保存できる上、情報の書き換えが可能で、汚れにも強く、複数タグを同時に認識でき、遮蔽物の影響を受けにくいという利点がある。
コスト面では、RFID はまだバーコードや 2 次元コードと開きがあるが、近年は低コスト化しやすいUHF 帯の RFID タグを中⼼に需要が拡がり、海外では特にアパレル業界向けの伸びが目⽴つようになっている。一方、国内市場は海外に⽐べて RFID タグの使用量がまだ限られるが、タグや機器の高機能化や用途開発なども着実に進められており、関連機器や関連ソフトを含めた RFID ソリューションの総市場規模は拡大を続けている。
RFID タグの無線通信で使われる周波数帯は HF 帯(High Frequency=短波帯:
13.56MHz)と UHF 帯(433MHz、860〜960MHz)が主体だが、一部の特殊用途などでは LF 帯(Low Frequency=⻑波帯:135kHz 未満)やマイクロ波帯(2.45GHz)も使われている。
この場合、使用する周波数帯域が違うと通信方式も異なり、HF 帯や LF 帯には電磁誘導方式、UHF 帯やマイクロ波帯には電波方式が用いられる。電磁誘導方式はリーダライタで交流磁界を作るもので、それに反応したタグ/インレイ内のアンテナが誘電電流を発生させて IC チップを動作させる。
この方式は悪環境でも使用できる上、アンテナの指向性も広いため、特に⾮接触 IC カードで多用されている。ただし、通信距離は数 cm 以内にとどまり、外来ノイズの影響を受けやすいという問題もある。
一方、電波方式はリーダライタから電波を出してタグ/インレイのアンテナを反応させるもので、発生した電⼒で IC 回路を起動する。この方式は電磁誘導方式より通信距離が⻑いほか、指向性があるため交信エリアを限定しやすいという利点があるが、⾦属による反射や水による吸収などの問題も指摘されている。
現在最も多用されているのは電波方式を用いる UHF 帯タグで、通信距離が 5m 程度と⻑く、通信速度も速い上、他の帯域より低コスト化しやすいという利点がある。そのため欧米では 2000 年代になると UHF 帯タグの研究開発が活発化し、IC タグの国際標準化を担う⾮営利法人の EPC グローバル(EPC global Inc.)により UHF 帯タグの中⼼となる Class1 タイプの国際規格も策定された。このタイプは使用分野に応じた商品識別コード(Electronic Product Code=EPC)を 1 回だけ書き込めるパッシブタグで、860〜960MHz 帯を使う UHF 帯タグの第 2 世代規格(C1 Gen2)が策定され、世界標準となっている。これらの取り組みにより欧米では UHF 帯タグの需要が漸増し、現在はアパレル業界向けや小売向けをはじめ RFID タグの多数が UHF 帯となっている。
一方、HF 帯タグは水透過性が高くて遮蔽物の影響もない上、電磁誘導方式による近接交信のためセキュリティ性が高いことも指摘されている。また、1990 年代末に国際規格(ISO15693)になった
525
ため海外でも 2000 年代中頃まで多用されてきたが、UHF 帯タグより割高になることから、上記のように UHF 帯タグが規格化された後は同タグへの移⾏が進んだ。その結果、現在は RFID タグによる入退室管理や個品管理など主に HF 帯タグのセキュリティ性を活かせる用途で使われている。
ただし、今後はHF 帯タグの一種であるNFC タグが増加する⾒通しで、その動向が注目される。NFC(Near Field Communication)はソニーとフィリップス(現 Royal Philips)が共同開発したモバイル端末搭載用の RFID 国際規格で、スマートフォンやタブレットなどへの搭載が進んでいる。また、NFC タグを店頭の商品や表示物等に貼付し、NEC スマホをリーダーとして使用することで真贋判定や様々な販促情報を表示するような新しい NFC アプリの開発が世界的に活発化している。
RFID タグとコード認識システムの⽐較
〔矢野経済研究所作成〕
キーデバイス:触覚センサ 触覚センサは、対象物との接触状態を検出するセンサ(感覚器官として人間の手や足、胴体、部な
どが触っている状況、圧⼒、温度などを感知、検出できる機能)と定義できる。 触覚センサの国内市場はベンチャー系企業が事業展開するシーズ段階にある。参入している企業は、
ニッタ、タッチエンス、イーダブルシステム、シーエムシー技術開発、オーギャなど数社であり、2015 年の国内市場規模は 1 億円程度と推計される(矢野経済研究所「Yano E plus 2016 年 4 月号」より)。応用分野は産業用ロボット、⺠生用ロボット、ゲームなどのエンターテイメント系機器、寝具、ヘルスケア、⾃動⾞など幅広い。
電源デバイス:太陽電池 ・⾊素増感太陽電池(Dye-sensitized Solar Cell;DSC)
DSC はナノ多孔質半導体に増感材料を吸着させた電極が光エネルギーを吸収し、電気エネルギーへ変換する仕組みを利用して発電する。特⻑は、(a)材料が低コスト(シリコンが不要)、(b)塗布・印刷工程が中⼼なため製造コストも低い(真空装置が不要)、(c)⾊素を用いることによる高い
526
意匠性、(d)電荷の再結合の時間が⻑いため、室内など光量が少ない環境下でも安定して発電する、などである。
1960 年代後半に研究開発が開始されたものの、変換効率は 1〜2%の時期が続いた。その後、1991 年にスイス・ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)のグレッツェル教授のグループが、⽐表面積の大きな TiO2 ナノ粒子に増感⾊素を付着させた光電極を用いるセル(グレッツェル・セル)を開発。変換効率 7.1%を達成したことで、次世代の太陽電池として注目が集まることとなった。
・有機薄膜太陽電池(Organic Photovoltaics:OPV)
OPV は無機半導体であるシリコンと同様に半導体の pn 接合により発電する。基本的な動作原理は、(a)太陽光が入射すると有機物中で高いエネルギーの励起子を生成、(b)pn 接合の界面のエネルギー準位の違いによって励起子が解離、(c)⾃由キャリアとなった電子は陰極へ、正孔は陽極へそれぞれ拡散、④陰陽極の両端に電界が発生することで起電⼒が生じる、というものである。
研究開発の歴史は 30 年以上にわたるが、有機 EL を開発したイーストマンコダック社の C.W.Tangらが pn 接合型の有機薄膜太陽電池を 1986 年に発表し、1%近くの変換効率を達成したことから研究開発が盛んになった。その後はフラーレンの n 型半導体への適用や導電性高分子の開発、バルクヘテロ接合の導入などによって一層のブレークスルーが図られている。
・ペロブスカイト太陽電池
DSC はセンサ電源、OPV は建材一体型などとして製品化が進んでいるものの、広く普及しているとは⾔いにくい。一方、ここ数年でペロブスカイト太陽電池の研究開発が世界中で活発化している。
ペロブスカイトは灰チタン石(CaTiO3)をはじめとする、ABX3(A:有機カチオン、B:⾦属カチオン、X:ハロゲン化物アニオン)の結晶構造を持つ材料全般の総称である。2009 年に桐蔭横浜大学 宮坂教授らの研究チームが酸化チタンの可視光増感剤として CH3NH3PbI3 を用いることを報告した。
ペロブスカイト太陽電池のセル構造は以下の図に示すよう3つに大別され、現在は最も高い変換効率を得られるナノ構造型が主流となっている。
ペロブスカイト太陽電池の構造
〔矢野経済研究所作成〕
ナノ構造型 平面へテロ接合型 逆構造型
裏面電極(Au、Ag) 裏面電極(Au、Ag) 裏面電極(Au、Ag)
正孔輸送層(Spiro-OMeTAD) 正孔輸送層(Spiro-OMeTAD) 電子輸送層(PCBM)
電子輸送層(TiO2) 電子輸送層(TiO2、PCBM) 正孔輸送層(PEDOT:PSS)
透明導電膜(FTO) 透明導電膜(ITO) 透明導電膜(ITO)
基板(ガラス、フィルム) 基板(ガラス、フィルム) 基板(ガラス、フィルム)
多孔質酸化物層(TiO2)
/ペロブスカイト層ペロブスカイト層 ペロブスカイト層
527
ナノ構造型は⾊素増感太陽電池の⾊素層をペロブスカイト層に置き換えているほか、電解液の代わりに正孔輸送層として主に Spiro-OMeTAD を用いている。また、ペロブスカイト層の⽐表面積を広くして光を多くより吸収させるために、TiO2 などの多孔質酸化物層が設けられる。平面へテロ接合型は多孔膜酸化物を用いずに、薄膜を積層させることで製造プロセスを簡略化させている。最近ではナノ構造型と遜⾊のない変換効率を得られることが報告されている。逆構造型は透明導電膜に正孔輸送層を堆積させており、有機薄膜太陽電池に類似した構造を有する。
ペロブスカイト太陽電池の特⻑は、高い変換効率と安い製造コストである。
高い変換効率 ペロブスカイト結晶は典型的な化合物半導体であり、バンドギャップ励起による強い光吸収能⼒を有
する。3 つの構成要素(有機カチオン、⾦属カチオン、ハロゲン化物)の 1 つあるいは複数を変えることで、光吸収波⻑をほぼ⾃由に変えることが可能。ハロゲンにおいては、ヨウ化物が 800nm、臭化物は560nm、塩化物は 400nm 以下までの波⻑に強いバンドギャップ吸収を示す。太陽光を集光するにはより⻑波⻑を吸収するヨウ化物(CH3NH3PbI3)が有利であり、そのバンドギャップエネルギーはアモルファスシリコンに近い 1.55 eV(800 nm)である。
結晶シリコン太陽電池はバンドギャップが約 1.1eV で波⻑約 1100eV の赤外光までを吸収するが、Voc 値は 0.6V 以下であり、0.5V 以上は熱として失われる。一方、CH3NH3PbI3 からなるペロブスカイト太陽電池は Voc 値が約 1.1V と 70%以上の励起エネルギーを回収することができる。これは、ペロブスカイト結晶内で生じる光励起子の寿命が⻑く、電子と正孔の移動距離が⻑い(1μm 超)という物性が寄与しているものと考えられている。
安い製造コスト
透明導電膜と裏面電極以外は溶液塗布印刷法(スプレー法、スピンコート法など)で製膜する。高温加熱や高真空プロセスを必要としないため、作製方法が簡単で、製造コストも安価となる。
ナノ構造型の場合は 400℃程度の高温で形成しなければならない薄膜緻密チタニア層が必要であるため、耐熱性の低いプラスチック基板上にペロブスカイト太陽電池を作製できない。このため、低温焼結が可能な ALD 法(原子層堆積方法)等の採用や、薄膜緻密チタニア層を不要とする平面へテロ型や逆型構造の検討がなされている。
528
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
フレキシブルデバイスの世界市場規模は 2015 年で 10 億円と推計する(出所:矢野経済研究所「プリンテッド・エレクトロニクス製品の潜在市場性調査」 2015.10)。適用分野でみると、センサ向けが100%の構成⽐となり、そのほとんどがフィルム基板のタッチセンサである。
主な参入企業は NISSHA、アルプス電気、パナソニック、Dongwoo Fine-Chem(住友化学子会社)などの日系企業のほか、OFILM、Holtech といった中国企業が多い。数年前までは台湾企業も一定のシェアを有していたが、中国企業の台頭により現在は競争⼒を低下させている。
日系企業は Apple「Iphone」向けなどハイエンド製品を手掛けており、世界シェアは 20%程度と推計される(出所:矢野経済研究所「2017 年版静電容量方式タッチパネル・部材市場の徹底分析」)。 ④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
フレキシブルデバイスの世界市場規模は 2020 年で 1 兆 3,320 億円、2025 年には 4 兆 8,500億円にまで拡大するものと推計される(出所:矢野経済研究所「プリンテッド・エレクトロニクス製品の潜在市場性調査」 2015.10)。
2025 年における適用分野の内訳は、センサ 2 兆 6,490 億円(構成⽐ 54.6%)、ディスプレイ8,000 億円(同 16.5%)、照明 4,000 億円(同 8.2%)、電池 8,010 億円(同 16.5%)、RFID2,000 億円(同 4.1%)となろう。
529
⑤ ②の各用途に求められる技術特性 表示デバイス:有機 EL ディスプレイ
スマートフォンやタブレットに搭載される中小型の AMOLED ディスプレイには、蒸着用メタルマスクを使用し発光材料を成膜する FMM(Fine Metal Mask)による成膜方式が主に使用されている。FMMはメタルマスクの開口部を微細に加工し、きめ細やかに RGB を塗り分けることが出来るため、ディスプレイの高精細化・高解像度が実現できる。
TV向けなどの大型AMOLEDディスプレイは、White-OLED+カラーフィルター(CF)方式が使用されており、中小型 AMOLED ディスプレイと同様に蒸着用マスクによる成膜が⾏われている。ただし、FMMによる RGB を塗り分けする中小型ディスプレイとは異なり、大型ディスプレイではオープンマスクを用い、⻘⾊(B)やイエローグリーン(YG)などの発光層を形成し、2〜3 段階で垂直積層(Tandem)する構造が採用されている。同方法は FMM に⽐べ、発光材料の成膜がシンプルであるため、歩留まり向上が図れるほか製造が⽐較的容易であるため、大型 AMOLED ディスプレイのパターニング法として導入が進んでいる。
一方、2019 年からは印刷方式による AMOLED ディスプレイの出荷が始まると予測される。同方式による中型 AMOLED ディスプレイの量産開始を検討する JOLED は、ジャパンディスプレイの能美工場にて生産体制を整え、2019 年に販売開始する予定である。
蒸着(FMM:Fine Metal
Mask)White OLED+CF
塗布(Ink-jet Prining)
Laser Printing(LITI:Laser Induced
Thermal Imaging)
成膜性能 △~○ △ ○ ◎
パターン幅 ±15μm ±2.5μm ±10μm ±2.5μm
解像度 ~570ppi 326ppi~ ~204ppi 300~400ppi
開口率 40~50% 60~70%? ~60% 70~80%
メリット 量産実績
・大型化可能・量産実績・大型ディスプレイにおいてFMMより生産性が高い
・大型化可能・使用材料の最小化
・大型化、高解像度が実現可能・マルチレイヤなどの積層能力
デメリット・大型化・大規模な装備が必要・複雑な製造プロセス
・CFが必要・高消費電力
・材料サプライヤーが限定・生産性などが検証されていない
・Donor Filmが高価・剥離工程が必要・発光素子問題(青色リン光)
[各種報道資料により矢野経済研究所作成]
AMOLEDパネルの成膜技術概要
531
印刷方式は蒸着方式に⽐べ、真空環境やマスクが不要となるなどイニシャルコストを他方式よりも抑えれること、大型ディスプレイへの対応が容易であること、必要な場所に必要な分量を塗布するため材料ロスが少ないなどのメリットがある。AMOLED ディスプレイのコストダウンに加え、大型ディスプレイへの転用が期待されている。技術革新による印刷方式の進化によっては、今後同方式による AMOLED ディスプレイが市場の牽引役となる可能性もあると考えられる。
その他のパターニング技術として、レーザーによる成膜方式LITI(レーザー熱転写;Laser Induced Thermal Imaging)も検討されていたが、発光層を形成する際に使用するドナーフィルムが高価であること、高温成膜を⾏うため使用する材料には高耐熱性が求められること、製造プロセスの変更などがネックとなり、本格採用には至っていない。 キーデバイス:RFID
RFID タグの構成材料は基材、アンテナ、IC チップ、外装材に大別される。このうち基材には PET フィルムが使われることが多いが、一部の企業は独⾃の紙製基材を使って低コスト化を図っている。
アンテナについては、ダイポールアンテナをパターン化したパターンアンテナが多用されるほか、ループアンテナ(巻線アンテナ)も使われることがある。ただし、ループアンテナは⾮接触 IC カードが主体である。パターンアンテナの場合はアルミ箔などの⾦属箔をエッチングして作成することが多いが、型抜きのパターンアンテナを使う製品もある。
IC チップは半導体メモリーと、これを動作させるための交信用高周波回路や電源系回路等が組み込まれている。RFID タグ用のチップは米インピンジ社(Impinj,inc)と蘭 NXP セミコンダクターズ(NXP Semiconductors N.V.)、米エイリアンテクノロジー(Alien Technology Corporation)の 3 社が生産している。
外装材はコイン形や円筒形、ラベル形、カード形、その他様々な形状があり、軟質樹脂が多用されるが、⾦属対応型その他の一部の高機能タグ等では硬質樹脂に収めたハードタグもみられる。
RFID タグの構造例
〔矢野経済研究所作成〕
RFID は製造業をはじめ小売、運輸・物流、医療、⾷品など幅広い分野で採用されている。そのため、
例えば製造業であれば RFID タグの耐久性、ロバスト性等への要求が大きくなるといったように、分野ごとで求められる技術特性は異なる。とはいえ、全般的にいえることは、電子タグの普及に向けて大きな課題
532
となっている低価格化への対応である。 RFID タグは IC チップのような集積度を高める必要がないため、印刷プロセスとの相性は良い。既に
RFID タグの価格は 1 枚 10 円を切る水準になっているが、IC チップやアンテナほか周辺回路を印刷で形成することで、競合となる IC タグ並みの 1 枚1円以下といった価格の達成が目標となっている。
RFID タグの一般的なコスト構成
〔矢野経済研究所推定〕
キーデバイス:触覚センサ 市場が本格的に⽴ち上がっていないため詳細は不明であるが、センサとしての認識速度や認識安定
性の向上などに向けた技術開発が必要と考えられる。 電源デバイス:太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)
ペロブスカイト太陽電池においては、以下の表に示すように高性能化、⻑期信頼性の確保、大面積化(モジュール化)など多くの技術課題を抱えている。なかでも、フレキシブルデバイスとしての実用化に向け、フィルム基板を用いた Roll to Roll(R2R)プロセスの確⽴と新規材料開発が求められている。
〔出所:NEDO「発電コスト低減に向けた太陽電池技術開発に関する動向調査」
技術課題 主な取り組みの方向性
発電機構の解明ペロブスカイト結晶内での光キャリアの振る舞い解明X線回析を用いた発電層形成過程のリアルタイム解析
評価手法 I-V曲線測定におけるヒステリシス低減の研究
高性能化ペロブスカイト材料の改良界面制御技術開発タンデム化
長期信頼性新規ホール輸送材料の開発ペロブスカイト材料の改良封止技術の開発
大面積化 塗布技術の開発
低コスト化R2Rプロセスの確立新規ホール輸送材料や新規裏面電極材料の開発
環境安全性 鉛代替材料の開発
533
なお、日本では NEDO の「革新的低製造コスト太陽電池の研究開発」において、ペロブスカイト太陽電池の研究開発が進められている。最終目標(最終年度:2019 年度)は以下の 2 項目である。 量産時にモジュール製造コスト 15 円/W を実現しうる、太陽電池モジュール材料・構造生産プ
ロセスに関する要素技術の開発 実験室レベルの小型太陽電池モジューで変換効率 20%の達成
534
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
生体情報の取得を目的としたフレキシブルデバイス(スマートテキスタイルを除く)は、大学での研究開発が中⼼となっており、既に製品化を果たしている企業は凸版印刷など数少ない。また、参考情報となるが、兵庫県⽴大学発ベンチャーのアフォードセンスが MEMS 技術を応用して貼付型の生体センサ(シリコン基板)を製品化している。 東京大学
東京大学大学院工学系研究科の染谷隆夫教授らのグループでは、JST・ERATO「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」において、世界最軽量(3g/m2)かつ最薄(2μm)のフレキシブルな電子回路をはじめ、温度センサや圧⼒センサ、⾎中酸素濃度や脈拍数を計測できる有機光検出器、有機 LED などのフィルム基板を用いたフレキシブルデバイスを開発してきた。
2017 年 7 月には皮膚貼り付け型のナノメッシュ電極の開発に成功した。この電極は生体適合性の高い⾦とポリビニルアルコールに、ナノサイズのメッシュ構造を持たせたもので、少量の水で簡単に皮膚に貼り付けることができる。装着していることを感じないほど超軽量であり、温度、圧⼒センサの動作実証、および腕の筋電計測を実施し、1週間貼り付けても炎症反応を起こさない高い生体適合性も確認した。
山形大学
山形大学の有機エレクトロニクス研究センターでは有機 EL、有機太陽電池、有機トランジスタといった有機エレクトロニクス全般を網羅した研究開発を進めている。
2017 年にはフレキシブル基板に印刷法で有機センサを形成し、さらに Si チップを実装した「フレキシブル・ハイブリッド・センサ」を開発した。具体的には PEN 基板を用いて、マイクロ波通信回路およびセンシング回路には SI チップ(Si-LSI)を用い、センサ、印刷配線およびアンテナは有機材料を印刷で作製。
535
配線はAgインクをインクジェットで形成した。アンテナは Agインクをディスペンサーで塗布し、温度センサはPEDOT-PSS をディスペンサーで、圧⼒センサは強誘電体ポリマー(PVDF)を塗布して作製している。
フレキシブル・ハイブリッド・センサの外観
凸版印刷
2017 年 4 月に利用者が装着することなく、睡眠状態をリアルタイムに解析できるシート型生体センサを開発した。山形大学・新関教授の協⼒を得て開発した独⾃のアルゴリズムにより、⼼拍・呼吸データをもとに、レム/ノンレム睡眠といった睡眠の深さを計測できる。また、薄いシート形状のため、特別な施工をすることなく、ベッドマットレスの下に敷くだけで設置が可能となっている。
介護・看護業界や高齢者住宅向けへの導入を想定しており、販売価格は約 10 万円/台(生体センサのみ、管理 PC やクラウドサーバ、タブレット等は別途⾒積)。利用者の睡眠状態をリアルタイムに把握することで、施設スタッフが適切なタイミングでサポートできるだけでなく、集積された睡眠データにより日々の睡眠の質を確認し、投薬判断やリハビリメニューのカスタマイズに活用できるという。凸版印刷では、2018 年に関連受注を含めて約 2 億円の売上を目指している。
シート型生体センサの設置イメージ
536
アフォードセンス 兵庫県⽴大学大学院工学研究科の前中一介教授が研究統括者となった、前中センシング融合プ
ロジェクト「絆創膏型生体センサの研究開発」より創出された大学発ベンチャーである。同プロジェクトは科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)の一環として、2008 年 4 月から 2013 年 3 月にかけて⾏われた。基本構想は小型軽量、低消費電⼒の絆創膏状生体モニタリングデバイスを開発し、その有用性を検証するというものである。MEMS などの要素技術を用いた低消費電⼒な集積回路、多種類のセンサ群を融合したデバイス、粘着層付きの柔軟な基板、およびその基板上に電気回路を形成するための配線や実装技術などを同時に研究し、それぞれに有為な成果を得ている。このような研究成果を安全・安⼼な社会の構築につなげるため、2013 年 11 月にアフォードセンスが設⽴され、2014 年 12 月にはウェアラブル絆創膏型ワイヤレス生体センサ「Vitalgram」のサンプル出荷をスタートさせた。
537
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、世界シェア、出荷額等からランキング。上位 5 位程度まで列記) (ⅰ)米国 MOLEX
2015 年 5 月に PE 技術をベースとしたセンサシステム、医療用ウエアラブル機器、LED 照明、RFIDタグなどを展開していたSoligie(2005年設⽴)を買収し、プリント基板用ソリューションを拡充した。医療用ウェアラブル機器は⼼拍や歩数、消費カロリーのなどを測定するタイプのほか、汗によるグルコースモニタリングを⾏うバイオセンサなどもラインナップしている。ポリエステルや TPU などの薄く軽量な基板と、生体適合性のある銀/塩化銀インクを使用している。
GSI Technologies
医療・ヘルスケア向けセンサフィルムを主とするプリンテッドエレクトロニクス分野において、優れた技術⼒と Roll to Roll 生産設備を有し、診断電極および治療電極の開発・製造・販売を⾏っている。設⽴は 1985 年であり、2017 年に NISSHA グループの傘下に入った。
各種センサの基板には樹脂や紙を用いており、導電性インクは銀、銀/塩化銀、⾦、カーボン、⽩⾦化カーボン、ニッケル、亜鉛、ビスマス、タングステン、グラフェンなどから用途に応じて選択する。⼼拍の測定から⾎糖値測定器用センサ、マイクロ流路デバイス向けセンサ、バイオセンサなど豊富な品揃えとなっている。
538
その他、フレキシブルデバイスを製造している欧州の主な企業は以下の表のとおりである。
〔矢野経済研究所作成〕
(ⅲ)中国
中国では AM OLED ディスプレイの研究開発が中⼼となっている。Rigid タイプと Flexible タイプのいずれも手掛けている企業が多いが、深圳市柔宇科技(Rouyu Technology)では厚さ 10μm の超薄型 AMOLED ディスプレイを開発している。同社は 2012 年に米・スタンフォード大学のエンジニアリング卒業生によって、カリフォルニア、フリーモント、香港、シンセンに設⽴された。2017 年 1 月には米国で開催された「CES2017」で着用型携帯電話のプロトタイプ「FlexPhone」をリリースし、イノベーションアワードを受賞している。
企業名 地域 備考BASF NewBusiness ドイツ 新規有機半導体材料やバックプレーンのプロセス技術の開発に取り組んでいる。
Thin FilmElectronics ノルウェー PARC(Palo Alto Research Center Incorporated)共同で有機CMOS回
路を使った不揮発性プリンテッド・メモリを開発。NFCタグを製品化している。
ENFUCELL OY フィンランド 亜鉛と二酸化マンガン、電解質としての塩化亜鉛を用いた印刷プロセスによる薄膜電池「SoftBattery」を展開している。
YD YNVISIBLE ポルトガル 柔軟かつ薄型(50μm以下)のelectrochromic displayを開発。温度センサーなどと組み合わさたスマートラベルを提案している。
PragmaticPrinting 英国 超薄型、低コストのフレキシブル集積回路「FlexLogIC」を開発。2018年に量産
設備が稼動を開始する予定である。
Cypak スウェーデン 樹脂または紙基板へ印刷プロセスにより導電性インクの回路を直接形成したブリスターパック「Med-ic」などを製品化している。
540
その他、AM OLED ディスプレイを製造している主な企業は以下の表のとおりである。
〔出所:矢野経済研究所作成〕
(ⅳ)韓国
サムスン、LG といった大手財閥系グループがディスプレイ向けでの展開を強化している。
サムスンディスプレイ(SDC) サムスン電子(以下、SEC)の LCD 事業部から分社し、2012 年 4 月に設⽴された。同年 7 月に
は SEC とソニーの合弁会社であった S-LCD とサムスンモバイルディスプレイ(SMD)を吸収合併している。
SDC は AMOLED ディスプレイのバックプレーンに、低温ポリシリコン(LTPS)TFT 基板を使用している。LTPS は高温(500℃程度)でポリシリコンを生成するため、一般的に高温に耐えられる特殊なガラスを使用しているが、SDCはガラスに代わりポリイミド(PI)を用いたFlexible OLEDディスプレイを世界で初めて量産化に成功した。成膜方式は FMM(Fine Metal Mask)を使用した蒸着方式で⾏っている。
AMOLED ディスプレイのデバイス構造は Anode/HTL(P-doepd)/Prime layer(R′・G′・B′)
/EML/HBL(aETL)/ETL/EIL/Cathod となる。共通材料のうちホール層には HIL がなく、HTL だけとなっている。しかし、電極から輸送層へ電荷キャリアを注入するHILの役割をHTL材だけでは完全に補完できないため、HTL に P ドーパントが添加されている。
企業名 設⽴天馬微電子股份有限公司 1983年
京東方科技集团股份有限公司 1993年
維信諾科技有限公司 2001年
深圳市華星光電技術有限公司 2009年
昆山国显光電有限公司 2012年
上海和輝光電有限公司 2012年
541
発光層には赤⾊と緑⾊にリン光材を採用し、デバイスの耐久性向上と低消費電⼒につなげている。また、各発光⾊に応じて厚み調整を⾏い、光の⼲渉を利用して⾊の純度を高める(マイクロキャビティ効果)ため、発光層(RGB)には発光補助層(Prime 材)を設けている。
さらに、発光材料の発光効率及び寿命の向上のため、HBL(Hole Blocking Layer)を取り入れている。⻘⾊材料は蛍光材料である。ディスプレイの解像度は現在、5.8″サイズで 570ppi(Quad HD+:2,560×1,440)。ピクセルの高密度化による高い解像度を実現している。
AM OLED ディスプレイのデバイス構造(スマートフォン向け)
LG ディスプレイ(LGD) TV 向けに大型 AMOLED ディスプレイを供給する唯一の企業である。2017 年 7 月には総額 9.6
兆ウォンを投じて AMOLED ディスプレイの生産を強化する計画を打ち出した。グループ会社である LG エレクトロニクス(以下 LGE)のほか、ソニー、パナソニック、東芝などが TV 向けに搭載を増やしており、大型 AMOLED ディスプレイの販売は好調である。また、これまで課題とされていた大型サイズの製造における歩留まり低下の問題も改善され、生産性が向上している。
中小型サイズではスマートウォッチやスマートフォン向けに P-OLED(LGD では Flexible OLED ディスプレイを P-OLED(Plastic OLED)と呼称する)を供給している。
なお、LG グループは 2015 年 10 月に OLED 関連事業を LGD に統合し、同年 12 月には LG 化学(LGC)から OLED 照明事業を譲受した。これにより、OLED 関連製品の開発及び生産においてはLGD が担うこととなり、意思決定の一元化によるグループ全体の競争⼒強化につながっている。
LGD は発光層をパネル全面にベタで積層形成した⽩⾊発光と、CF によって RGB の発光を個別に取り出す W-OLED 方式を採用している。同方式は RGB の膜を 3 回に分けてそれぞれ決められた場所に形成する 3 ⾊蒸着方式に⽐べ、枠のみで遮蔽すれば⽩⾊形成が可能なほか、LCD ディスプレイで使用されている CF を活用できることというメリットがある。
542
W-OLED の発光層の構造は赤⾊(R)、緑⾊(G)、⻘⾊(B)をそれぞれ垂直積層する構造(Tandem 構造)を採用しているとみられる。かつては赤⾊と緑⾊を混ぜた⻩⾊(Y)と⻘⾊(B)を積層した構造を使用してきたが、高解像度と高⾊再現性を狙い発光層の構造を変更した。デバイス構造については不明である。
大型 AMOLED の素子構造
(ⅴ)台湾 E Ink Holdings
前⾝となる Prime View International(1992 年設⽴)がマイクロカプセルの基礎技術を保有する米国 E Ink を 2009 年に買収し、2010 年 6 月に現社名へと変更した。
同社では電気泳動方式の電子ペーパーの開発および製造を⾏っている。同方式は基材面にコーティングされた透明なマイクロカプセルの中に、帯電した⽩と⿊の粒子があり、電圧をかけて顔料粒子を移動させることで表示を⾏うというものである。
2013 年に 4096 ⾊のカラー表示に対応した電子ペーパー「Triton 2」を発売し、2016 年 5 月にはカラーフィルター⾮搭載型の電気泳動式ディスプレイとして世界初となるフルカラー(1677万7216⾊)表示の「Advanced Color ePaper(ACeP)」をリリースした。ただ、一般的な液晶ディスプレイなどと⽐較すると、リフレッシュレートが⾮常に遅いため映像表示には適しておらず、デジタルサイネージ専用となっている。
また、同年 9 月には 32 インチのフレキシブルカラー電子ペーパーディスプレーを、凸版印刷と共同で開発したと発表した。E Ink のカラー用「E Ink Pearl」前面板と、高精細フレキシブル基材による「Mobius」背面板の組み合わせによって構成しており、画素は 1280×720 ドット(カラー画素)で 4096 ⾊(RGB 各 4bit)を表示できる。
543
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
フレキシブルデバイスの技術開発に携わる日本国内の大学・代表的な研究者は以下のとおりである。東京大学、大阪大学、山形大学の 3 大学が研究開発に特に注⼒している。
〔各種資料より矢野経済研究所作成〕
545
(補足)研究者の動向 〜“PATENTSCOPE”を使用。検索キーワード:Flexible device)
発明者上位 10 名のうち、日本の研究者としては YAMAZAKI SHUNPEI、SAKAMOTO
NORIAKI 、 KOBAYASHI YOSHIYUKI 、 TAKAHASHI YUKITSUGU 、 MAEHARA EIJU 、SAKAMOTO JUNJI、IGARASHI YUUSUKE、OGINO HIROYUKI、KINOMURA KOJI が挙げられた。これらの研究者の所属は海外企業ではなく、海外企業・組織に移った形跡はデータベースからは確認できなかった。
546
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関 Google Scholarの学術記事検索、IEEE(米国電気電子学会)のポータル、各国のニュースなどから、各国の主な研究機関及び研究者を以下にまとめた。 (ⅰ)米国
アメリカの主な研究機関及び研究者
〔出所:FederalReporters、IEEE より矢野経済研究所作成〕
547
(ⅱ)欧州 欧州の主な研究機関及び研究者
〔出所:European Commission、Cordis より矢野経済研究所作成〕 (ⅲ)中国
〔出所:Google Scholars, IEEE より矢野経済研究所作成〕
548
(ⅳ)韓国
韓国の主な研究機関及び研究者
〔出所:Naver 学術情報検索より矢野経済研究所作成〕
(ⅴ)台湾
台湾の主な研究機関及び研究者
〔出所: IEEE, Google Scholar より矢野経済研究所作成〕
549
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者) 経済産業省 NEDO「超次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」 ※平成 29 年度事業規模(予定)需給勘定 476 百万円(委託事業)
本事業では、プリンテッドエレクトロニクスの本格的な実用化のために要求される製造技術の高度化、
信頼性向上及び標準化の推進等に資する基盤技術開発を⾏う。さらに、市場拡大・普及促進等に資する実用化技術開発を総合的に推進し、プリンテッドエレクトロニクスの普及のために必要な要素技術を確⽴することを目的として、平成 23 年度から平成 27 年度に実施した研究開発項目である「①印刷技術による高度フレキシブル電子基板の連続製造技術開発」、「②高度 TFT アレイ印刷製造のための材料・プロセス技術開発」、「③印刷技術による電子ペーパーの開発」、「④印刷技術によるフレキシブルセンサの開発」の成果も踏まえて、以下の研究開発項目を実施している。
・研究開発項目⑤ 「カスタマイズ化プロセス基盤技術の開発」 【実施期間】平成 28 年度〜平成 30 年度
(1)高生産性カスタマイズ化プロセス技術の開発 (2)高速高精度基板搬送技術の開発
【実施体制】次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合 ・研究開発項目⑥ 「フレキシブル複合機能デバイス技術の開発」 【実施期間】平成 28 年度〜平成 30 年度 (1) フレキシブルデバイスの高感度化、高信頼性化技術の開発 (2) フレキシブルデバイス実装技術の開発 (3) フレキシブルデバイスの機能複合化技術の開発 【実施体制】次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合、産業技術総合研究所/名古屋大学 ※次世代プリンテッドエレクトロニクス技術研究組合(JAPERA)
プリンテッドエレクトロニクス技術(印刷デバイス製造技術)を確⽴し、低電⼒社会の構築と産業技術の国際競争⼒強化を推進するため、当該技術開発を集中的に実施することを目的に 2011 年 3 月に組織化された。 <参加企業・研究機関> 旭化成、出光興産、コニカミノルタ、小森コーポレーション、産業技術総合研究所、JNC、住友化学、大日本印刷、DIC、帝人、東洋紡、凸版印刷、NISSHA、日本電気、富士フイルム、リコー
550
⽂部科学省 JST「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」 <概要> ・支援対象:大学等(18 拠点) ・事業規模:1〜10 億円/拠点・年(平成 29 年度予算 8,569 百万円) ・事業期間:平成 25 年度〜平成 33 年度
10 年後を⾒通した革新的な研究開発課題を特定し、企業や大学だけでは実現できない革新的な
イノベーションを産学連携で実現するとともに、革新的なイノベーションを連続的に創出する「イノベーションプラットフォーム」を我が国に整備することを目的としている。ハイリスクではあるものの実用化の期待が大きい異分野融合・連携型の基盤的テーマに対して、最⻑ 9 年度の集中的な支援をプログラムである。
フレキシブルデバイスの研究開発を担うのは、フロンティア有機システムイノベーション拠点である。実施体制、および研究開発テーマは以下のとおりである。
フロンティア有機システムイノベーション拠点の概要
中核機関 山形大学(研究リーダー:大場 好弘 理事・副学⻑)
参画機関
大日本印刷、積水ハウス、NECライティング、コニカミノルタ、日本ゼオン、カネカ、三菱重工業、Lumiotec、伊藤電子工業、KEN OKUYAMA DESIGN、東レエンジニアリング、JSR、横河電機、サトーホールディングス、DIC、ソニー、大塚化学、パイオラックスメディカルデバイス、住友ゴム工業、日本電気、パラマウントベッド、東北芸術工科大学、仙台高等専門学校、産業技術総合研究所
塗布プロセスによる高効率有機EL、透明フレキシブル有機ELパネル等の革新技術及び快適な生活を実現する光源や照明システムなどの開発・実証
壁に貼れる超薄型・軽量のフレキシブルディスプレイを実現するための技術開発
快眠に関するセンサ計測データを収集し解析する ICT 基盤システムの開発、および環境計測データと個人ビックデータの複合解析から快眠を支援するシステムの実現
採光性のある透明な有機太陽電池、超軽量フレキシブル太陽電池の開発
有機EL植物栽培や常温除湿乾燥技術など「⾷」に貢献する新たな技術の構築
唾液や汗に含まれる生理活性物質を高感度で検出できるストレスセンサ等の開発
有機FET型センサと無線通信回路を極薄フィルム上に印刷プロセスを使って一体形成することで、体に貼って使える新しい生体センサの実現
⾃己組織的にインクを微細な配線形状に形成する技術や、大面積・高精度インクジェット技術を開発し、ロール to ロール印刷に適合する革新的な電子デバイス製造技術の構築
ナノインプリント等の微細な成形加工技術を用いたデバイス形成技術の開発
独⾃の「中間水理論」に基づき設計した新しい生体親和性材料を用いた、⾎液中に現れる転移がん細胞を検出する技術や、新しいがん治療器具等の開発
研究開発テーマ
551
JST「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム(OPERA)」 <概要> ・支援内容:研究領域・共創コンソーシアム数 21 件 ・事業規模・内容:(新規)フィージビリ・スタディ 0.3 億円×4 領域、(継続)1.7 億円程度/年(平成 29 年度予算 1,155 百万円) ・事業期間:5 年度
産業界との協⼒の下、大学等が知的資産を総動員し、新たな基幹産業の育成に向けた「技術・シス
テム革新シナリオ」の作成と、それに基づく⾮競争領域における本格的な産学共同研究を通して、基礎研究や人材育成における産学パートナーシップを拡大し、わが国のオープンイノベーションの加速を目指すプログラムである。⺠間資⾦とのマッチングファンドにより、新たな基幹産業の育成の核となる革新的技術の創出を目指すとともに、その基幹産業の育成が図れる継続的な研究環境・研究体制・人材育成システムを持つプラットフォームを形成することを目的としている。
平成 28 年度の採択課題のうち、フレキシブルデバイスを対象としているものは以下のとおりである。
この他、科学研究費助成事業(科研費)において研究開発支援が実施されている。現在、稼動中のプロジェクトを日本の研究者.com、KAKEN(検索ワード:フレキシブルデバイス、プリンテッドエレクトニクス)を用いて抽出した結果は次ページのとおりである。
幹事機関 研究領域 主な参画機関
山形大学有機材料の極限機能創出と社会システム化をする基盤技術の構築およびソフトマターロボティクスへの展開
カネカ、帝人、等
552
プロジェクト名 拍動する⼼筋細胞シートを用いた伸縮性多点電極アレイによる薬物反応の評価
フレキシブルデバイスのための塗布型逆構造有機発光ダイオードの学理と製作 断線を⾃ら診断し⾃己修復する⾦属配線
期間 2017年度 〜 2022年度 2017年度 〜 2020年度 2016年度 〜 2019年度予算⾦額 20,423万円 4,420万円 1,846万円
概要独創性の高い伸縮性多点電極アレイを用いて、⼼筋細胞の多点・リアルタイム測定を可能とするツールを提供する。
不明⾃己修復配線の基礎的・学術的な研究。具体的な検討項目は材料・液体封⽌の 、修復電圧・修復領域の拡張などの検討。
助成主体 染谷 隆夫 東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授
内藤 裕義 大阪府⽴大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 岩瀬 英治 早稲田大学, 理工学術院, 准教授
プロジェクト名 切り紙構造を利用したフレキシブルディスプレイ 応⼒発光を利用したポリマーMEMSの構造信頼性新規評価体系構築への挑戦
フレキシブル透明回路を実装した三層積層式⾊分離型イメージセンサの創成
期間 2016年度 〜 2018年度 2016年度 〜 2018年度 2016年度 〜 2019年度予算⾦額 416万円 377万円 481万円
概要マイクロスケールの切り紙構造を作り、そこに機能性流体を配置することでフレキシブルデバイスとしての機能を持たせる。
屈曲変形に強い実用性のある素子を設計・製作するための素子の損傷防⽌技術の開発。
無機絶縁膜によるチャネル保護膜形成とそれを用いた薄膜トランジスタの特性・信頼性向上。
助成主体 武居 淳 お茶の水⼥子大学, ソフトマター教育研究センター, 特任助教
神谷 庄司 名古屋工業大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 古田 守 高知工科大学, 環境理工学群, 教授
プロジェクト名 原子状酸素支援分子線エピタキシー法による酸化亜鉛半導体フレキシブルデバイスの開発
高性能レアメタルフリーフレキシブル酸化物トランジスタおよび論理回路の開発
熱可塑性半導体エラストマー材料の創製とストレッチャブル電子デバイスへの応用
期間 2016年度 〜 2019年度 2016年度 〜 2019年度 2016年度 〜 2019年度予算⾦額 442万円 481万円 1,794万円
概要分子線エピタキシ法と原子状酸素ラジカルを利用した成膜プロセスにより、フレキシブル応用が可能なZnOデバイス作製技術の開発。
Zn2SnO4材料を用いて、ディスプレイ駆動やバイオセンサーに使用できる高性能TFTをフレキシブル基板に作製する。
高効率半導体高分子材料への高い伸縮性付与を実現し、新しい熱可塑性半導体エラストマー材料の創製とストレッチャブル電子デバイスに応用。
助成主体 村中 司 山梨大学, 総合研究部, 准教授 佐藤 和郎 地方独⽴⾏政法人大阪府⽴産業技術総合研究所, その他部局等, 主幹研究員
東原 知哉 山形大学, 大学院有機材料システム研究科, 准教授
553
〔矢野経済研究所作成〕
プロジェクト名 先進印刷技術を用いた層状分子集積システム構築とπ電子機能の創出
サブミクロンスケール選択的⾦属化プロセスによる革新的3次元実装技術の開発 革新的グリーンプリンテッドエレクトロニクスの開発
期間 2017年度 〜 2019年度 2017年度 〜 2020年度 2017年度 〜 2021年度
予算⾦額 754万円 4,420万円 1,586万円概要 不明 不明 不明
助成主体 ⻑谷川 達生 東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授
三成 剛生 物質・材料研究機構, 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点, 独⽴研究者
酒井 正俊 千葉大学, 大学院工学研究院, 准教授
プロジェクト名 量子効果デバイスに向けた大面積数ナノメートル厚の有機単結晶性絶縁膜製造技術の開発
光照射で濡れ性制御が可能なポリイミドの創成とエレクトロニクス・バイオ分野への応用
プリンテッドエレクトロニクスを指向した⾦属酸化物ナノ結晶の超低温結晶成⻑/接合
期間 2016年度 〜 2018年度 2016年度 〜 2018年度 2016年度 〜 2019年度
予算⾦額 364万円 481万円 390万円
概要
アルキル鎖とパイ電子骨格が連結した⾮対称な有機半導体分子が、きわめて高均質な極薄単結晶層を与えるという研究成果をもとに、半導体層ではない極薄絶縁層をデバイス機能として活用する。
プリンテッドエレクトロニクスなどに応用可能な,光照射により表面濡れ性を制御可能なポリイミドを創成する。
低温溶融アルキルアミン硝酸塩(低温フラックス)を用いた⾦属酸化物の「超低温結晶成⻑/界面(粒子間)接合技術」の開発。
助成主体 ⻑谷川 達生 東京大学, 大学院工学系研究科(工学部), 教授
津田 祐輔 久留米工業高等専門学校, 生物応用化学科, 教授 栗原 正人 山形大学, 理学部, 教授
554
⑪米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政府支援策の有無 (ⅰ)米国 FlexTech (SEMI Strategic Association Partner)
FlexTech はフレキシブルエレクトロニクスやプリンテッドエレクトロニクスの普及を目指す業界団体で、半導体や LED などの業界団体である SEMI と戦略的パートナー協定を結び、実質的に一部門となった。SEMI は FHE の展示やカンファレンスなどをおこなっており、日本でも 2017FLEX Japan を開催している。FlexTech が現在取り組んでいるプロジェクトを下記に記載する。 A Solid State thin film lithium rechargeable battery for functional electronic print (FEP) devices ・概要:このプロジェクトでは 50mm x 27mm x 0.25mm 以下のサイズで 500mAh の容量を持つ
プリントデバイス用薄型フレキシブル固体リチウム電池の製造を目指している。ENrG 社のフレキシブルセラミック基盤を使用する予定。この電池はウェアラブル機器や医療機器などに適しており、完成後は広く普及するとみられている。
・共同研究機関:ITN Energy Systems ・研究期間:15 ヶ月 ・支援⾦額:150 万米ドル Thin Film Power Source ・概要:50mm x 76mm に 0.25mm 以下の厚さで電圧 3 ボルトで 100mAh 以上の容量を持つ
プリンテッドエクトロニクスデバイスの極薄バッテリーの製造を目指している。こちらは上記の「フレキシブル固体リチウム電池」とは違い、リチウムを含め様々な材料を検討している。プリンテッドエクトロニクスデバイスへの搭載での運用が可能である。
・共同研究機関:Custom Electronics ・研究期間:不明 ・支援⾦額:54 万米ドル
556
Thin, Flexible, Printed Zinc Battery: An Embedded Power Source for Functional Electronics Print Devices ・概要:Imprint Energy 社の技術を活かして実用化を目指したプリントデバイス用薄型フレキシブルプ
リント亜鉛電池。プリンテッドエクトロニクスデバイスとして実用に耐えうる初の二次電池であり、4,000 サイクルの寿命を持つ。低コストであり、ディスプレイやセンサなど様々なプリンテッドエレクトロニクスデバイスでの使用が期待される。
・共同研究機関: Imprint Energy ・研究期間:不明 ・支援⾦額:98 万米ドル NextFlex
2015 年にアメリカ国防総省と FlexTech が設⽴したコンソーシアムであり、アメリカの企業や大学等研究機関、NPO、⾃治体、政府が協⼒しており、フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクスの競争前段階の基礎研究をおこなっている。この研究にはコストシェア方式が採用されており、2015 年に開始したプロジェクト「PROJECT CALL1.0」では 8 個の研究に対して 610 万米ドルが、2016 年に開始したプロジェクト「PROJECT CALL2.0」では 16 個の研究に 1,200 万米ドルが支援されている。「PROJECT CALL3.0」はまだ事業者や具体的な研究内容などは公開していないものの、下記 3 つの大テーマに対し、700 万米ドルが支援される予定である。なお、「PROJECT CALL1.0」「PROJECT CALL2.0」の各研究の期間は 9〜24 ヶ月である。
MRL & TRL
〔出所:NextFlex 資料〕
557
生産プロセス研究(Manufacturing Thrust Areas) Printed circuit elements for RF and high-speed application ・概要:1MHz-50GHz の周波帯に対応可能で、低抵抗コンダクタや伝送線路などをプリントで作成し
た高周波及び高速用プリント基板素材のプロトタイプを完成させる。 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:75 万米ドル Printed passives for FHE including materials, tools, and process documentation ・概要:プリンテッド受動部品の最適な製造方法を素材や装備などを含めて調査する。また、プリンテッド
受動部品の公差を±10%以内に収める。 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:50 万米ドル Z-axis interconnect and via formation ・概要:フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクスの Z 軸の連結についての手法やプロセスを研究する。 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:20 万米ドル Additive and semi-additive manufacturing methods for high density interconnects ・概要:高密集伝送路でのアディティブ法やセミアディティブ法などの製造テクニックの研究 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:50 万米ドル
558
技術基盤実証実験(Technology Platform Demonstrators) Control- and/or condition-based monitoring applications for physical or perishable assets ・概要:堅牢で平面以外に取り付け可能な温度や湿度、圧⼒など各種小型センサの研究 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:75 万米ドル Adaptive wearable or structural articles with soft robotics response ・概要: ソフトロボティックデバイスのプロトタイプの開発やウェアラブル対応の感覚機器やモニターの研究 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:100 万米ドル Development of a low-cost, high-performing multi-sensor system integrated in a user-friendly “wear and forget” format for medical or worker safety applications ・概要:低コストで3つ以上のセンサを搭載し、3日以上充電しなくても稼動する着用型センサを医療
用途と労働用途別に研究 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:医療用途 100 万米ドル、労働用途 50 万米ドル エージェンシー用特別プログラム(Agency Driven Project) 3D component placement and interconnect equipment development ・概要:3D 構造におけるセンサや電子装置の統合用ツールや軍事用に効果のある統合もしくはプリンテ
ッドセンサの研究 ・研究機関:不明 ・研究期間:不明 ・支援⾦額:40 万米ドル
559
(ⅱ)欧州 Horizon 2020
Horizon 2020 は欧州の研究開発・イノベーションに関するフレームワークプログラムである。このプログラムからは様々な分野への資⾦援助がおこなわれており、フレキシブルエレクトロニクスやプリンテッドエレクトロニクスについても様々な研究開発に支援がおこなわれている。
Horizon 2020 のフレキシブルデバイス関連トピックのうち、2014 年に開始して今も稼動しているプロジェクトは「Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies」が 1 件、「High-definition printing of multifunctional materials」が 3 件、「Industrial-scale production of nanomaterials for printing applications」が 4 件のプロジェクトある。
なお、「Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies」については、2016 年にもプロジェクト募集しているが、他の二つは募集していない。
下記の 4 件は「Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics (TOLAE) technologies」で 2017 年に開始したプロジェクトである。
Capacitive Identification Tokens ・概要:「c-tokens」というタッチスクリーンや NFC などに反応するデバイスを作るプロジェクト。
「c-tokens」は薄型軽量でフレキシブルなデバイスで低コストで製造できるようにする。 ・研究機関:Cartamundi Turnhout など(計 7 団体) ・研究期間:2017/1〜2019/12 ・支援⾦額:3,474,319 ユーロ PRINTED OPTOELECTRONIC DEVICES FROM NANOSHEET NETWORK ELECTROCHEMICALLY-GATED FIELD EFFECT TRANSISTORS ・概要:フレキシブルや透明といった特徴をつけた上で、使い捨てにできる程安くできる光学デバイスを作
成するために、セミコンダクターナノシートの開発を目指す。 ・研究機関:ruprecht-karls-universitat heidelberg ・研究期間:2016/5〜2018/5 ・支援⾦額:159,461 ユーロ INTERNATIONAL SMART COLLABORATIVE OPEN-ACCESS HYBRID PRINTED ELECTRONICS PILOT LINE ・概要:ハイブリッドプリンテッドエレクトロニクスにおいて、H-TOLAE テクノロジーを R&D 以上のレベルに
引上げることを目的とする研究をおこなう。 ・研究機関:centre for process innovation limited lbg など(11 組織) ・研究期間:2017/1〜2019/12 ・支援⾦額:7,998,652 ユーロ
560
PYroelectric Conformable SEnsor matrix for Large area applications in security and safety ・概要:低コストで薄い指紋センサーの製造を目指す。その他、500 dpiの高解像度や1〜4本の指ま
で対応できる広範囲対応のセンサーで、IGZO-TFT を採用するなどの特徴を持つ。 ・研究機関:Commissariat A L Energie Atomique ET Aux Energies Alternatives など
(計 8 団体) ・研究期間:2017/1〜2019/12 ・支援⾦額:3,814,298 ユーロ
561
(ⅲ)中国 中国国家発展改革委員会、工業情報化部は、2016年5 月18日に共同で「製造業の高度化
と重大プロジェクトパッケージの改造の実施に関する通知」(中国語名「关于实施制造业升级改造重大工程包的通知」)を発表した。「通知」では、製造業のハイエンド化、インテリジェント化、グリーン化、サービス化に向け、10 分野における重点プロジェクトをまとめて実施する方針が示されている。「通知」は、AMOLED などの次世代フレキシブルディスプレイ技術を発展させ、共通コア技術の共同開発及び産業化を推進する方針を明らかにしている。
国際電工委員会(IEC)は 2017 年 5 月、「IEC 62715-6-2 フレキシブルディスプレイデバイス
環境試験方法」という国際標準を発表した。該当標準はOLEDメーカ維信諾によって作成され、これまで初めて発表されたフレキシブルディスプレイ関連の国際標準である。
中国国家発展改革委員会、工業情報化部は、2014 年 10 月 13 日に 2014 年 10 月、「新
型ディスプレイ産業の新 3 年⾏動計画 2014-2016 年」を発表した。2016 年には新型ディスプレイ産業の出荷量(面積ベース)でシャープや LGディスプレイ並みの世界2位、世界シェア20%以上で 293 万平米以上(2014 年は 9%で 52 万平米)、産業の規模で 3,000 億元を目標にする。このために、中国政府は開発と製造設備に 850 億元の投資を⾏う。新 3 年計画によると、中国は技術面で、低温多結晶シリコン(LTPS)、酸化物(Oxide)を採用した液晶ディスプレイ(LCD)や、アクティブマトリクス方式有機 EL(AMOLED)に重点的に取り組んでいくとしている。
研究開発プロジェクト プロジェクト名 国家重点基礎研究開発計画(973 計画)
フレキシブルフォトニクス·電子デバイスに関する基礎研究 期間 2015.1~
資⾦拠出元 科技部
予算⾦額 1776 万元 参加機関 清華大学、電子科技大学、中科院半導体研究所、⻄安電子科技大
学、中国科学技術大学、中科院蘇州纳米技术与纳米仿生研究所、浙江大学、空军総医院
プロジェクト目標 健康医療向け次世代電子デバイスの開発ための基礎理論·技術研究
〔出所:中国語での文献調査結果より矢野経済研究所作成〕
562
(ⅳ)韓国 韓国では、2013年から2018年の6年間、政府予算約200億円を投入して、PETS(Printed
Electronics Total Solution)プロジェクトが進⾏中である。関連企業23社と、大学・研究機関22 箇所が参加し、①OLED 照明(Jusung)、②Digital signage(Samsung)、③Smart wall(LG)の 3 つの分野に分けて、技術開発を⾏っている。LG は、このプロジェクトの結果として、R2R 方式のフレキシブルディスプレイ生産過程・導入を通し、生産費用を削減、最終的な製品価格を引き下げることに成功したと発表している。
TFT-LCD 及び BLS などを制作している Hicel Co. Ltd は、2014 年に産業通商資源部、韓国産業技術振興院が 120 億円を投入した「Printed Electronics 技術の常用化」事業に主幹事業者として選定された。プロジェクトの目標は、Printed Electronics 関連電子部品の信頼性基準を定め、国内の RS(Reliability Standard) の規格化及び製品に関するR(Reliability)認証を獲得することである。
韓国の順天(Sooncheon)大学は、2008 年から世界最初の Printed Electronics 分野に
特化した学科を設けており、2013 年からは未来創造科学部の「BK21PLUS(2008 年 9 月〜2020 年 8 月)」の関連分野人材育成事業に選定されている。予算に関しては、2009 年から 4年間 10 億円の予算が投入されたと公表されている。
563
(ⅴ)台湾 2006 年から 2013 年の間、2 億ドルの予算を支援すると公表した。2007 年には、ITRI(台湾
工業技術研究院)内に、R2R の R&D プラットフォームを構築するための基盤となるオープンラボである「Flexible Electronics Pilot Lab」が設けられ、様々な研究機関・企業との提携により研究が進められた。予算の執⾏機関は、MOEA(台湾経済省)であり、2010 年の投資内訳を⾒てみると、研究機関へ 3,000 万ドル、大学へ 250 万ドル、産業へ 610 万ドルが投資された。Flexible Electronics Pilot Lab では、有機 EL 照明、超薄型タッチパネル、大面積圧⼒センサ、フレキシブルスピーカなど、革新的なデバイスのさまざまな統合技術を開発している。
以下に現在進⾏中のプロジェクトリストをまとめる。
現在進⾏中のプロジェクトリスト 1. R2R Production 2. Intelligent Vision System 3. Advanced lighting 4. New Semiconductor Architectures 5. IoT Data Links 6. Flexible AMOLED Technology 7. Transparent Display Application System Technology 8. Fan-Out Panel Level Packaging (FOPLP)Technology
〔出所:ITRI〕
564
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
これまでフレキシブルデバイスの実用化に向けてなされてきた研究開発は、ディスプレイやタッチセンサ、太陽電池、RFID タグといった生体センサ以外の用途をターゲットにしてきた。そのため、東京大学の染谷教授はフレキシブルデバイスを医療分野に応用するためには、以下の三つの特性を向上させる研究開発に取り組んでいく必要があるとしている(日経デジタルヘルス「次世代の生体センシング」より)。
・柔らかさ:複雑な形状の生体表面に追従できる柔らかさ。ぶつかっても壊れない耐久性 ・センサの高感度化:微弱な生体信号を検出するためのセンサの高感度化や高精度化 ・生体適合性:毒性がないことはもちろん、汗や体液に浸されても劣化しない信頼性
また、現段階でフレキシブルデバイスを用いた生体センサは実用化されていないため、構成技術を保有する企業は数少ないと考えられる。ただ、重要な構成技術である有機半導体材料や導電性ペースト関連においては研究開発が活発化する傾向にあるため、それらの企業を以下に掲げる。
〔矢野経済研究所作成〕
種別 企業名 備考
DIC グラビアオフセット印刷用導電インキ「GOAGT」をランナップ
ダイセル 低音焼成可能な銀ナノインキの顧客評価が進⾏中
日油 PE用銅ペーストを開発中
ナガセケムテックス 無溶剤タイプの導電インキ「IPC」、絶縁インキ「IPD」を顧客に訴求
タツタ電気 銅粒子表面に銀をコーティングしたPE配線用導電性ペーストを開発
ナミックス 銀ベースの高伸⻑導体ペーストを開発
石原ケミカル フォトシンタブル型導電性銅ナノインキを開発中
バンドー化学 低音焼結性⾦属インキを開発
Aglc 東京大学発ベンチャーとして2014年1月に設⽴。銀ナノインキの製造・販売
フューチャーインク 山形大学発ベンチャーとして2016年4月に設⽴。銀ナノインキの製造、販売
宇部興産 n型有機半導体材料を山形大学・産総研と共同開発
東京化成 DNTT前躯体を製品化
東ソー 塗布型有機半導体材料を開発中
三菱化学 太陽電池向けに有機半導体材料(ベンゾポルフィリン:BP)を開発
DIC 東京工業大学と有機トランジスタ材料を開発
出光興産 発光材料に加え、ETL、HTL、HILなどの周辺材料まで幅広く展開
導電性ペースト
有機半導体材料
565
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業 「⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業」と同様、生体センサのみを対象としていないが、
NEDO プロジェクト「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」の第 1 期(2015年度まで)において、JAPERA がフレキシブルデバイスの基盤となる位置合わせ、印刷、温度制御、乾燥・焼成などの要素技術を組み合わせた全印刷連続一貫生産ラインによるフレキシブル TFT アレイシートの製造技術の開発に成功した。
このほか、同プロジェクトでデバイス開発に取り組んだ、大日本印刷(大面積圧⼒センサ)、凸版印刷(大面積軽量単⾊電子ペーパー)、リコー(高反射型カラー電子ペーパー)がフレキシブルデバイスの製造プロセス技術を蓄積している。
また、東レエンジニアリングが 2016 年に山形大学の時任静士卓越研究教授らのグループと共同で新
規印刷プロセス技術を開発した。具体的な装置は、大面積・高精細ロール to ロールインクジェット印刷装置と、3次元物体表面にも回路が形成できる電子回路印刷装置である。
566
(補足)ニュース・リリースまとめ(2016 年 1 月〜2017 年 12 月)
〔矢野経済研究所作成〕
企業・研究機関 詳細内容
2017 10 NEDO・JAPERA 触覚動作を認識する高精度・高感度圧⼒センサーシステムを開発
2017 10 NISSHA GSI Technologiesのプリンテッドエレクトロニクス事業を取得
2017 9 エレファンテック 産業革新機構をリードインベスターとし、大和企業投資及びBeyondNext Ventureの計3社より総額5億円の資⾦調達を⾏う
2017 7 東京大学 ⻑期間皮膚に貼り付けても、かぶれて痒くならないメッシュセンサを開発
2017 6 凸版印刷 線幅10μmの印刷と位置決め技術で4⾊カラーインキのラインとスペースを⾃由に変え、組み合わせる新しいカラー表現印刷技術を確⽴
2017 6 産総研 印刷と低温プラズマ焼結で形成された銅の回路配線を用いた曲げられるラジオをツバに組み込んだ野球帽を試作
2017 4 産総研・大日本印刷圧電MEMS技術で作製した極薄PZT/Siひずみセンサーをフレキシブル基板上に集積化した、貼るだけで橋梁の劣化状態を把握できるフレキシブル面パターンセンサーを開発
2017 2 山形大学 有機溶媒に溶ける新しいN型有機半導体材料に関して、フューチャーインクとライセンス契約を結ぶことで合意
2017 2 早稲田大学 生体材料・メカトロニクス・MEMSの異分野若手研究者が結集し、基材が薄く柔らかい!「皮膚貼付型エレクトロニクス」を開発
2017 2 NEDO・JAPERA 印刷技術による圧⼒と温度の面内分布を同時に検出できるフレキシブルシートセンサーの開発に成功
2017 1 日本電子精機 島根県にセンサーデバイスの研究拠点を新設し、プリンテッドエレクトロニクス製造技術を活用したセンサーデバイス開発へ本格着手
2016 12 富士フイルム インクジェット技術で多様なニーズに応えるためインクジェット事業部を新設
2016 9 凸版印刷 台湾のE Ink Holdings(E Ink)と共同で32インチのフレキシブルカラー電子ペーパーを開発
2016 5 東京大学・大阪大学 ⻑期間体内に埋め込み可能なシート型生体電位センサーを開発
2016 4 リコー プリンテッドエレクトロニクス実用化へ圧電素材のインクと専用のインクジェット(IJ)装置で、2016年度中の試作提供開始を目指す
2016 4 住友化学 英Abingdon Healthとポイントオブケア向け次世代マルチプルバイオセンサデバイスを共同開発することに合意
2016 3 凸版印刷 ⽩⿊赤の3⾊に表示切替が可能な フレキシブル電子ペーパーディスプレイを国内で初めて開発
2016 2 セメダイン 東大発のベンチャー企業 AgIC(現エレファンテック)へ出資し、プリンテッドエレクトロニクス分野へ積極展開
2016 1 山形大学 プリンテッドエレクトロニクスに向けた新規印刷プロセス技術を開発
2016 1 大阪大学 医療機器と同じ計測精度を持つパッチ式脳波センサの開発に成功
2016 1 東京大学 曲げても正確に測れる圧⼒センサーの開発に成功
日付
567
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
アラミド繊維は、分子骨格が直線状のパラ系とジグザグ状のメタ系に大別され、前者を代表するブランドがデュポングループの「ケブラー」と帝人グループの「トワロン」、「テクノーラ」であり、後者はデュポンの「ノーメックス」と帝人の「コーネックス」が知られる。 *デュポングループ:デュポン及び東レ・デュポン、帝人グループ:帝人及びテイジン・アラミド B.V. 「ケブラー」は米デュポンが 1965年に開発した世界初のスーパー繊維である。日・米・英に生産拠点があり、全世界の⽣産能⼒は約 30,000 トン/年に及ぶ。日本国内ではデュポンと東レの合弁会社である東レ・デュポンが製造、販売しており、東海事業場に年産2,500 トンのプラントを有している。 一方、帝人「トワロン」は蘭アクゾが開発した繊維で、2000 年に帝⼈が当時のアコーディスから事業を
買収し、現在はテイジン・アラミド B.V.が継承している。オランダにおける⽣産能⼒は「ケブラー」に次ぐ年産 25,000 トン規模とみられ、日本国内では帝人が輸入販売している。また、「ケブラー」や「トワロン」の成分にジアミノフェニレンテラフタルアミドを共重合した「テクノーラ」は帝人が独自に開発した繊維で、1987年に商業⽣産を開始した。⽣産拠点は松⼭製造所(年産約2,000 トン)である。 パラ系アラミド繊維の「ケブラー」と「トワロン」は、ともに液晶紡糸法で製造されている。同じ重さの鋼鉄の約5倍の引張強度を持ち、耐熱性、耐摩耗性、耐切創性などに優れ、電気を通さないという特性もある。「テクノーラ」は液晶ではなく共重合タイプのポリマーを使⽤するため、製造時に延伸および熱処理工程が必要になる。「ケブラー」や「トワロン」よりも耐熱性や耐薬品性に優れている。
主なアラミド繊維の物性
出典:東レ・デュポンおよび帝人 ホームページより作成
メタ系アラミド繊維
ケブラー(標準タイプ)
テクノーラコーネックス
(レギュラータイプ)
密度 g/cm3 1.44 1.39 1.38
水分率 % 7 2 5.0~5.5
cN/dtex20.3 24.7 4.4~4.9
g/d 23 28 ‐
MPa 2920 ‐ 590~690
破断時伸度 % 3.6 4.6※ 35~45
cN/dtex 490 520 57~71
g/d 555 590 ‐
MPa 70500 ‐ 7800~9800
29 25 29以上
約400℃※マルチフィラメント(単糸1.7dtex)の値
約500℃
限界酸素指数(LOI)
引張強度
引張弾性率
分解温度
パラ系アラミド繊維
569
一般的に、アラミド繊維のような特徴的な機能(⾼強度、⾼弾性、⾼耐熱性、難燃性など)を持つ繊維をスーパー繊維と呼ぶが、スーパー繊維は第1世代のパラ系アラミド繊維が基準となり、第2世代の超⾼分⼦量ポリエチレン繊維やポリアリレート繊維、第 3世代の PBO 繊維がそれぞれ製品化されている。 パラ系アラミド繊維は⾼強度・⾼弾性率のほか、耐熱性や耐摩耗性、耐切創性、電気絶縁性などに
優れる。しかし、「ケブラー」(標準タイプ)などは⽔分率が7 %と吸湿性があるため、⾼温・多湿の環境下では加⽔分解が進んで強度が⼤幅に低下する。また、
有機溶媒やアルカリには耐性を⽰すものの酸には弱く、紫外線に⻑時間さらされる屋外での使⽤も不向きとされる。それに対して、超⾼分⼦量ポリエチレン繊維は⽔に浮くほどの軽さと耐⽔性、耐光性を備え、釣り⽷や⼤型船の係留⽤ロープなどの⽔回り⽤途の獲得に成功した。 ポリアリレート繊維の強みは⽔分率 0%という低吸湿性と寸法安定性(耐クリープ性)である。超高
分⼦量ポリエチレン繊維と同様、海洋ロープや漁網・ネットなどの⽔回り⽤途があるほか、高温/湿潤下での寸法安定性に優れていることからイヤホンコードやテンションメンバー(光ファイバー用)などの電気・電子分野にも進出している。 PBO 繊維は有機繊維としてはトップレベルの強度、弾性率、耐熱性、難燃性を兼ね備え、当初は防
弾⾐料分野で躍進したが、米国の訴訟問題を契機に同分野からは撤退、現在は消防服などの防護衣料や耐熱フェルトなどに使⽤され、主としてパラ/メタ系アラミド繊維と混合する形で性能を強化する役割を担っている。 PPS繊維やポリイミド繊維、フッ素繊維などの耐熱性・難燃性繊維についてはメタ系アラミド繊維と性能を⽐較することが多い。スーパー繊維も超⾼分⼦量ポリエチレン繊維を除けば耐熱性に優れるが、耐熱性・難燃性繊維には融点や分解点の⾼さだけでなく、⾼温下で⻑時間機能を維持する安定性が求められる。また、耐薬品性に優れているという共通点もある。これらの機能を活かした用途として最適なのがバグフィルターであり、PPS繊維やポリイミド繊維についてはフィルターに特化した形で利⽤されている。
570
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
*素材関連の技術である点を考慮し、ここではアラミド繊維の“⽤途”について考察を⾏っている。 パラ系アラミド繊維の主な需要分野は、①摩擦材・ガスケット、②防弾・防護⾐料、③タイヤ・ゴム資
材、④テンションメンバー(光ファイバー)である。摩擦材・ガスケット向けはアスベストの代替材料として普及しており、耐熱性や耐摩耗性を活かして⾃動⾞のクラッチ板やブレーキ・パッド、産業⽤ガスケットなどに使用されている。通常はパルプ状で出荷される。 防弾・防護⾐料向けは⽶国の軍事⽤途など海外需要が中⼼となっている。作業⽤の防護⼿袋なども
含まれる。フィラメントを使用した織物が製品化されている。 タイヤ・ゴム資材向けはパラ系アラミド繊維の強度や軽さが評価され、2輪/4輪⽤タイヤ、コンベアベルト、ホースなどの補強材として利⽤されている。耐屈曲疲労性にも優れる「テクノーラ」はこの分野での利用が最も多い。 テンションメンバー向けは主として光ファイバー⽤で、経済成⻑が著しい新興国で通信インフラが整備されるのに伴って需要が拡大している。その他にもアルミ押出成型用の耐熱フェルトや建築・土木関連、スピーカー、スポーツ用品の複合材などに使用されており、他素材と混合されることもある。 ここ数年のデュポングループ及び帝人グループの⽤途開拓に係る動きは以下の通り。 <デュポングループ> 米デュポンは、“Protection Solution”の裾野拡⼤に注⼒しており、近年はスポーツ分野や⼀般消費財へのアプローチを強めている。具体的には、スポーツギア、スマートフォン・オーディオ用品(ケーブル等)への応用を Adidas や Reebok、Belkin といったブランドメーカーと推進。これらの取り組みを“Dare Bigger(もっとでかく, 拙訳)”と銘打ち、X GamesやNitro Circus等の世界的有名イベントでの露出を図っている。
Belkin/充電ケーブル Adidas/FREAK X KEVLAR DIPPED CLEATS
572
Reebok/CrossFit Footwear
XD/フィットネス用品 <帝人グループ> 同グループはコンポジット、ロープ/ケーブル、プロテクション等、既存分野の深耕に注⼒。最新の“Aramid Vision #7”(アラミド事業の情報発信を目的としたマガジン)では航空輸送用 ULDs (Unit load devices)、係留ロープ、アウトドア⾐料、コンベヤベルト、航空宇宙(ロケット)をフィーチャーしている。このうち、航空輸送用ULDsでは米MACRO Industries, Incが「トワロン」を使用したコンポジットパネル(Macro-Lite)を開発、独PalNet Air Cargo ProductsがMCRO-Liteパネルを用いたAKEコンテナの認証を取得するなど、航空業界のさらなる軽量、⾼強度、⾼耐久に対する強い要望にマッチした取り組みとして、今後の需要本格化に期待している。
573
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
パラ系およびメタ系アラミド繊維の世界市場では、デュポングループと帝人グループによる 2 強時代が続いてきたが、近年は韓国や中国企業の台頭が目覚しく、価格競争が激化している。 パラ系アラミド繊維は、東レ・デュポンが国内向け(一部、輸出がある)に「ケブラー」を販売しており、帝人グループが「トワロン」と「テクノーラ」を国内外で販売している。「ケブラー」および「トワロン」の販売単価はキログラムあたり3,000〜6,000円程度とみられ、韓国企業の参⼊などで価格は下がる傾向にある。「テクノーラ」については原料および製法の違いから価格はやや⾼めの設定である。 生産量は「ケブラー」が年間 2,000 トン弱(東レ・デュポン分のみ)、「トワロン」は全世界で同
15,000〜20,000 トン、「テクノーラ」も同じく 1,500 トン弱と推計される。なお、帝人は 2019 年 1Qの稼働を視野にオランダ工場の設備増強を実施、「トワロン」の⽣産能⼒拡⼤を図る計画を有している。 パラ系アラミド繊維はスーパー繊維の代表格として世界で確固たる地位を築いている。今後は中国やインドといった新興市場の拡⼤が⾒込まれ、両グループともに増産に向けた設備投資に余念がない。アジア系企業の参入にも高付加価値製品で差別化を図る方針である。「テクノーラ」については、樹脂の機能向上材としてのパウダービジネスを展開し、コンクリート補強材などの加工品も拡充する。 東レ・デュポンおよび帝人グループのパラ系アラミド繊維(「ケブラー」、「トワロン」、「テクノーラ」)と帝
人のメタ系アラミド繊維(「コーネックス」)の市場規模推移を以下に示した。いずれもリーマン・ショックで市場が⼀時期冷え込んだものの2009年度からは回復基調にある。2011年度は震災の影響でパラ系は前年度から横ばいの19,600トン(数量ベース)、⾦額ベースでは895億円にとどまった。メタ系は欧州危機の影響も加わって前年度⽐12%減の1,450 トン(数量ベース)、⾦額ベースでは29億円と推計した。今後は新興国需要が拡大し、新規用途の開発も進むと考えられることから、2015 年度の市場規模はパラ系で 23,000 トン(同)、⾦額ベースでは 978億円、2020 年度には 28,000 トン(同)、⾦額ベースで1,138億円に拡大すると予測した。メタ系については2015年度の市場規模が1,700トン(同)、⾦額ベースでは30億6,000万円、2020年度には2,000トン(同)、⾦額ベースで36億円になると推計した。 2011 年度の需要分野別の動向(⾦額ベース)は、パラ系が摩擦材・ガスケット向けと防弾・防護
⾐料向けで過半数を占めると推計した。メタ系は安全防護⾐料向けがトップで 40%、バグフィルター向けが25%で続くと推計した。 国内外別の動向(⾦額ベース)をみると、パラ系は海外向け(海外生産分及び輸出)が 80%を占めるのに対し、メタ系は国内で生産されていることもあって内需が70%を占めると推計した。
575
<世界市場> 米 Grand View Research によると、2015 年のアラミド繊維市場(パラ系、メタ系)は 28.4 億USD(およそ 3,000 億円)規模。パラ系アラミド繊維の需要規模(グローバル)は 51874.2t(2015年)と推計している。 独、仏、英を中心に欧州が地域シェア 35.1%を占める最大の市場を形成し、次いで米国が
15,000t(地域シェア30%弱)の規模としている。ただ、近年は中国、インド等のアジア圏の需要が急成⻑しており、アジア地域のシェアが上昇中とのこと。同社では今後も同様の傾向が続くとみているが、欧州、⽶国も防衛を含むプロテクション分野の需要が拡⼤する⾒込みで、2025 年のアラミド繊維市場は80,000t程度まで成⻑すると予想される。 また、用途別でみると、主要用途である Security & Protection(防弾・防護⾐料等)、
Frictional Materials(摩擦材等)が安定した伸びを今後も示してい くほか 、Rubber Reinforcement(ゴム補強)、Tire Reinforcement(タイヤ補強)も需要成⻑が期待されている。 アラミド繊維は、もともとレーシングタイヤの補強⽤として使⽤されることが多かったが、軽量化やゴム使
⽤量の削減等を背景に⼀般の乗⽤⾞にも適⽤されるようになってきている。特に耐熱性の高さからアラミド繊維は⾼速⾛⾏時の熱変形を抑える効果が⾼く、アウトバーンなどでの⾼速⾛⾏が前提の欧州で需要が拡⼤しており、軽量化効果やロードノイズの低減効果等から日本のタイヤメーカーでも採用が徐々に増えている。実際、ブリヂストンやダンロップではハイエンドのプロダクトライン(ブリヂストン「REGNO」等)を中心にアラミド繊維補強材(ベルト等)を採用しており、より剛性が求められるランフラットタイヤなどではカーカスやサイドウォールの補強材にもアラミド繊維が使用され出しているようだ。
アラミド繊維の適⽤例(タイヤ) 出所:帝⼈資料
578
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
パラ系アラミド繊維の主要用途であるコンポジット(各種複合材)、プロテクション(防弾・防護衣料)、タイヤ・ゴム資材(ゴム補強)においてアラミド繊維に求められる技術特性としては、その機械特性を活かすための要素技術、例えば、コンポジットにおける樹脂との密着性向上のための表⾯改質・処理技術、プロテクションにおける着⽤快適性を⾼めるストレッチ性・染⾊性向上技術、ゴム補強における成形加工時の糸ほつれを抑える接着技術等が挙げられる。以下、各分野における具体的な課題点をいくつかの特許情報より整理した。 コンポジット ⾮導電、粘る(破断し難い)、軽量、振動減衰等に特⻑を有するものの、繊維の含⽔率が⾼い、樹脂との接着性が低いなどの課題がある。このため、樹脂との密着性向上のための表⾯改質・処理技術が求められている。また、短繊維(ステープル)を用いたコンポジットでは分散性の問題から強度⾯で⼗分な性能を発揮できていない。 “Surface Modification of Para-Aramid Fiber by Direct Fluorination and its Effect on the Interface of Aramid/Epoxy Composites” Tao Peng, Renqin Cai, Chaofeng Chen, etc Polymer Science & Technology Institute, Sichuan University Journal of Macromolecular Science, Vol 51, 2012 (アラミド繊維の直接フッ素化処理により、エポキシとの密着性が⼤幅に向上) パラ系アラミド紡績⽷は、パラ系アラミド⻑繊維を紡績⼯程に適合する⻑さに切断した短繊維(ステープル)を用い、天然繊維と同様にして製造することができるが、強度という観点では、⼀般的に紡績⽷は、⽷条が短繊維の集合体からなり、その短繊維が捲縮を有し、かつ⽷条の配列が低く、撚形態を有するため、上記したように⽷条を構成する⻑繊維の強度に⽐べて⽷条の強度が低下し易く、強度を要求される分野への展開が難しかった。これに対し、東レデュポンでは捲縮を有する⾼強度アラミド短繊維(⾼強度アラミド短繊維)を混綿することにより、低い混率でも紡績⽷の強度が⾶躍的に向上し、従来のアラミド短繊維を混綿した紡績⽷とは全く異なる挙動を⽰す紡績⽷が得られることを⾒出している。 (東レデュポン特許:2017-082351) プロテクション 防護服等における課題としては、アラミド繊維の染色性、着用快適性、ストレッチ性等が挙げられる。 アラミド繊維を含む布帛で構成された防護服は耐熱性に優れるものの染色することが困難であった。このため、カーボンブラックなどの顔料を繊維中に含有させ、⿊⾊や紺⾊等の濃⾊を表現することがあった。
582
しかしながら、カーボンブラックは⾚外線の吸収効率が⾼いため、⽕炎を受けたり、熱源の近くにいるときに布帛の温度が⾼くなり⽕傷になりやすいという問題がある。 (帝人特許:2017-008454) 通電/稼働中の電気設備付近で作業する人や、電気設備付近での事故に対応する救急隊員は、潜在的に電気アークフラッシュおよび/または火災にさらされる可能性がある。通常これらの作業に携わる⼈々を電気アークフラッシュおよび/または⽕災から保護するよう⾊々な設計仕様の規格がある。例えばNFPA 70EやDL-T320-2010 がその⼀例である。その中でも特に作業者が着⽤する防護⾐服に関しては前記規格に加えてASTM F1506やASTM F1959において詳しく定義されており、これらの安全基準・性能基準をクリアすることが要求される。その対策として、従来、種々の難燃・防炎性織物が提案されているが、これらを着用した場合、耐アーク性は高いものの、目付けが重いため着心地が悪く活動しにくいという問題点があった。 (帝人特許:2015-229805) ⼀般的なストレッチ性布帛としては、加⼯⽷(仮撚加⼯⽷、ニットデニット⽷、捲縮⽷などの嵩⾼⽷)や弾性繊維(弾性糸)を用いることが提案されている。しかし、炎や高熱など危険の大きい場面で使用される防護製品としての使用に耐え得る耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐洗濯性(耐塩素漂白などを含む)に加えて十分なストレッチ性(伸縮性)を兼備することが困難であった。さらには、燃焼時の有害ガス発⽣懸念を排除することが困難であった。 (帝人特許:2015-059290) ⽕炎、熱、アークなどからの防護性能を有し、染⾊堅牢度が⾼く、かつ経時的に⻩変しにくく、かつ吸放湿性に優れた紡績糸、および該紡績糸を用いた布帛および⾐料 (帝人特許:2014-210985) 染色が難しいアラミド繊維において色相を改善した、染色されたアラミド繊維及びその製造方法 (帝人特許:2013-204210) ゴム補強 動⼒伝達⽤ベルト、ゴムホース、タイヤ等のゴム製品には、強⼒が⼤きくかつ伸びが⼩さい特性を有するアラミド繊維コードが、ゴムを補強するために埋設されている。ゴム補強用アラミド繊維コードとしては、アラミド繊維の原⽷を複数本引き揃えて撚⽷とし、これをレゾルシン・ホルマリン・ゴムラテックス(RFL)溶液等の接着剤処理液に浸漬し、ゴムに対する接着性を付与したものが知られている。しかし、ゴム補強⽤アラミド繊維コードを⽤いた動⼒伝達⽤ベルトは、ベルトを輪切り状にカットしてベルトを成形する際に、ベルト側端に露出したアラミド繊維コードから単⽷がほつれて⽑⽻が発⽣し、更に使⽤時の擦過により単⽷
583
先端が広がり、ベルトの品位が損なわれるだけでなく、ベルト⾛⾏時にベルト側端からコードが⾶び出す問題がある。また、突出した⽷ほつれは、プーリーとの接触により切断されて⾶散し、近接する精密機器などの故障原因となることがあるため、突出した単⽷を切断除去する作業を⾏う必要があり、⽣産性を著しく低下させる問題もある。 前記課題を達成するため、本発明者等は鋭意検討を⾏った結果、交絡を有するアラミド繊維マルチフィラメントを撚⽷した撚⽷コードを⽤い、更に好ましくはアラミド繊維⾻格内に硬化性エポキシ化合物を浸透させたアラミド前処理⽷を⽤いることにより、⽷ほつれ性やエッジフレイ性に優れるゴム補強⽤アラミド繊維コードを得ることに成功し、本発明を完成するに至った。 (東レデュポン特許:2017-082352)
584
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
アラミド繊維には、フィラメントだけでなく、ステープル、カット・ファイバー、パルプ、紡績⽷がある。また、撚⽷や捲縮、スリット、組布等の⼆次加⼯を施した織編物、複合材料として使⽤されることも多い。東レ・デュポン、帝人ともに基本的にはフィラメントやカット・ファイバー等の「糸売り」がメインで、織編等の二次加⼯は外部で⾏っているが、近年は中国、韓国等のアラミド繊維メーカーの台頭が著しいことから、東レ・デュポン、帝人ともにアラミド繊維事業の高付加価値化を推進。東レ・デュポンは 2017 年 4 月、東レ・東海工場内に原糸から高次加工品まで一貫して試作評価・開発できる「ケブラーテクニカルセンター(KTC)」を設置、技術開発機能の強化を図っている。
帝人 テクノーラの代表銘柄
出所:帝人HP
種類 タイプ 代表銘柄(dtex) 用途フィラメントヤーン T-200 800, 1110, 1670dtex
T-200M 2500dtex
T-202 1670dtex ゴム補強
T-221 1110, 1670dtex ロープ・コード・一般産業資材
T-240110, 220, 440, 1110,1670dtex
T-240B(⿊原着) 440, 830, 1670dtex
T-241J T-7411670, 8330dtex
チョップドファイバー T-3201.7dtex ×1, 3, 6, 12mm 樹脂・セメント補強 石綿代替
T-321 1.7dtex ×30mm セメント補強
T-322EH 1.7dtex ×1, 3, 6mm 樹脂補強
T-32PNW 1.7dtex ×3mm
T-323SB 1.7dtex ×1, 3, 6mm ゴム補強
ステープルファイバー T-330 1.7dtex ×5mm 紡績 不織布
T-330B 1.7dtex ×38mm
T-330G
スパナイズドヤーン T-360 30/-, 20/-, 10/- 防護服
(牽切紡績) T-400 110, 220, 330, 440dtex 一般産業資材 ゴム補強
織編物 FRP一般産業資材
ゴム補強・ロープ・コード一般産業資材
585
東レ・デュポン「ケブラー」はフィラメント、カット・ファイバー、パルプ、ステープル、紡績糸の形態で販売しており、摩擦材(⾃動⾞⽤クラッチ板、ブレーキ・パッド、ガスケット)をはじめ、防護⾐料(安全防護服、手袋、消防服、スポーツウエアなど)、ロープ・コード/ロッド(電設工事用ロープ、ミシン糸、コンクリート補強材など)、テンションメンバー(光ファイバー・ケーブル)、コンポジット(建築土木の補修補強、航空機、船体、スピーカー、各種スポーツ用品)などで使用されている。
出所:東レ・デュポンHP
586
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記)
パラ系アラミド繊維の代表的なメーカーは以下の通り。また、近年は中国企業の商業⽣産が進んでいる。ただ、安定⽣産を⾏っている中国メーカーはYantai Tayho Advanced Materials(2016年時点で年産500t程度とみられている)のみとも言われており、その他のメーカーの実態は明らかでない。
出所:各種資料を基にYRI作成
メーカー 地域 工場 能⼒(t/年) 備考
Dupont 米国 Richimond 18,000
英国 Maydown 8,100
計 28,600t 日本 東海 2,500東レデュポン
帝人 オランダ Emmen 26,500Twaron、2019年1Q稼働予定で設備増強を計画
計 29,500t 日本 松山 3,0002017年10月に10%増強
KOLON 韓国 ⻲尾 2,000
HYOSUNG 韓国 蔚山 1,000
烟台泰和新材料股份有限公司Yantai Tayho Advanced Materials
中国 ⼭東省煙台市 1,500
旧社名:煙台氨綸股份有限公司スパンデックス、パラ/メタアラミド繊維
蘇州兆達特繊科技有限公司Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical
中国 江蘇省常熟市 1,000
パラアラミド繊維
中藍晨光化⼯研究院有限公司China Bluestar Chengrand R&D
中国 四川省成都市 1,000
中国化工集団公司グループパラ系アラミド繊維1万tプロジェクトあり
中国平煤神馬集団Shenma Industry
中国 河南省平頂山市 1,000
コークス、ナイロン化学工業
河北硅⾕化⼯有限公司Hebei Silicon Valley Chemica
中国 河北省邯鄲市 1,000
5,000t/年まで拡大する計画を保有
山東万聖博科技股份有限公司 中国 ⼭東省東営市 2,000
中国石化儀征化繊股份有限公司 中国 江蘇省揚州市 1,000
中国石化股份公司グループ3,000t/年まで拡大する計画を保有
江蘇瑞盛新材料科技有限公司 中国 江蘇省揚州市 開発中
中化国際股份有限公司傘下2016-2017年産500トンプロジェクト
江蘇中化兆達⾼性能材料有限公司 中国 江蘇省揚州市 開発中
江蘇揚農化工集団有限公司傘下2017.6-2020.2年産1万トンプロジェクト
南充易安新材料有限公司 中国 四川省南充市 開発中
嘉美印染有限公司子会社紡績、捺染
587
また、アラミド繊維を使⽤した製品(主にコンポジット材料、ファブリック等の中間材)を展開する企業は以下の通り。これら企業の抽出に際しては、ケミカル系の企業ライブラリ(Composite World, ThomasNet)、その他インターネット検索を⽤いた。 アラミド繊維製品を手掛ける企業(米国)
アラミド繊維製品を手掛ける企業(米国)
社名 所在地 アラミド繊維製品 ソースCoast-Line International米国 航空宇宙向けコンポジット CWComposite One 米国 コンポジット CWRock West Composites 米国 コンポジット用織物 CWArgosy International 米国 プリプレグ、コンポジット CWAssociated Industries 米国 プリプレグ、コンポジット CWBally Ribbon Mills 米国 テープ、織物 CWCoats 米国 コンポジット材料 CWConneaut Industries 米国 高機能ヤーン CWCST 米国 コンポジット材料 CWDupont Protection Solutions米国 各種ケブラー加工品 CWElectrical Fiber Systems 米国 機能性ヤーン CWEngineered Fibers Technology 米国 高機能繊維製品 CWEY Technologies 米国 高機能繊維製品 CWFiber-Line Inc 米国 高機能繊維製品 CWHoneywell Advanced Fibers and Composites米国 高機能繊維製品 CWLydall Performance Materials Inc米国 フェルト等 CWNeenah Technical Materials 米国 織編物 CWPerformance Engineered Nonwovens LLC米国 マット、ベール CWPharr Yarns LLC 米国 ヤーン、スパン CWSoutheast Nonwovens Inc 米国 ウェットレイド不織布 CW
社名 所在地 アラミド繊維製品 ソースStealth Composites 米国 NASAコントラクター CWTCR Composites 米国 コンポジットマテリアル、テープ CWTechFiber 米国 プロテクション用途向け織物 CWTHEMIX Plastics Inc 米国 コンポジット材料 CWVarinit Corp 米国 高機能繊維・ファブリック CWVectorply Corp 米国 ノンクリップ・スティッチ材料 CWZens Manufacturing 米国 チューブラーニット製品 TNCS Hyde Company 米国 ファブリック TNFabrico 米国 ファブリック TNGaskets, Inc 米国 ファブリック TNEastex Products, Inc 米国 ファブリック TNTex Tech Industries 米国 ファブリック TNBuffalo Felt Products 米国 フェルト TNConsolidated Cordage Corp米国 ファブリック TNApex Mills Corp 米国 ファブリック TNKinetic Composites 米国 ファブリック TNSaatiPrint 米国 ジオテキスタイル TNStern & Stern Industries 米国 クロス・ファブリック TNSampla Belting 米国 ファブリック TNDraper Knitting 米国 ファブリック TN
588
アラミド繊維製品を手掛ける企業(カナダ、欧州)
アラミド繊維製品を手掛ける企業(アジア)
社名 所在地 アラミド繊維製品 ソースTexonic カナダ 織編物 CWTextile Products カナダ ファブリック CWGrip Metal カナダ 異素材接着技術 CWNGF Canada Ltd カナダ 繊維表面加工 CWBarnet Europe GmbH 独 ファイバー、ポリマー、ヤーン等 CWc-m-p Gmbh 独 コンポジットマテリアル CWFreudenberg Vliesstoffe SE & Co独 高機能繊維製品 CWHaufler Composites GmbH 独 織物 CWBurgmann Packings Braided Compositesアイルランド コンポジット用プリフォーム CWChomarat 仏 コンポジットマテリアル、機能性テキスタイル CWDevold AMT AS ノルウェイ コンポジット材料 CWHavel Composites CZ sroチェコ コンポジット、ファブリック CWPRF Composite Materials英国 コンポジットマテリアル CWRebelco LDA ポルトガル コンポジットマテリアル CWSuprem SA スイス プリプレグ、ポリマー CW
社名 所在地 アラミド繊維製品 ソースXiamen Savings Environmental 中国 高耐熱フィルタ材料 -Yantai Metastar Special Paper中国 アラミド繊維紙 -Yichang Hedali Composite Materials中国 ハニカムパネル -Wuxi Boton Technology 中国 コンベヤベルト -Qifeng New Material 中国 アラミド繊維紙 -Dongguan Sovetl Special rope & webbing 中国 ファブリック -Zhejiang Mengtex Special Materials 中国 ファブリック -Wuxi GDE Technology 中国 ファブリック -Boto Corp 韓国 織編物 CWMoldex Composites Pvt インド コンポジット CWArrow Technical Textiles Pvtインド ファブリック -National Safety Solutionインド 防護服用生地 -Core Safety Group インド 防護服用生地 -Super Safety Services インド 防護服用生地Polymer Technologies Pte シンガポール機能性材料 CWTaiwan Electric Insulator 台湾 ファブリック -
589
○世界の主要なタイヤコード/ファブリックメーカー
BEKAERT ベルギースチールコード大手、世界中のタイや3本に1本が同社のスチールコードを使用している
JIANGSU XINGDA STEEL TIRE CORD CO. LTD.中国20年以上の研究を経て、2011年よりスチールコードの製造を開始。2017年には伊PirelliのSupplier Awardを獲得している
FORMOSA TAFFETA CO. LTD. 台湾ポリエステル・ナイロン編・織物メーカー
HYOSUNG GROUP 韓国ポリエステル/ナイロン/スチールのタイヤコードを生産する世界最大のタイヤコードメーカー
JIANGSU TAIJI INDUSTRY NEW MATERIALS CO. LTD. 中国ポリエステルコードを主力事業として展開、生産能力は3.6万t/年
PERFORMANCE FIBERS INC. 中国ポリエスエルコードファブリックを製造、生産能力は5.2万t/年
SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP.台湾ポリエステルをメインにフィルム、繊維ファブリック等を展開
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO. LTD. 中国中国石化大手
東レ 日本グループの東レハイブリッドコードが展開。2017年10月よりタイ拠点が稼働
ZHEJIANG HAILIDE NEW MATERIAL CO. LTD.中国2001年設立、タイヤコードファブリックの生産能力は3万t/年
東洋紡 日本2013年にポリエスエルタイヤコードから撤退
CENTURY ENKA LTD. インドナイロン、ポリエスエル繊維メーカー。タイヤコードファブリックの生産能力は1.2万t/年
CHINA SHENMA INDUSTRY CO. LTD.中国ナイロンチェーンを展開。2012年よりタイヤコードファブリックを製造
JUNMA GROUP & JUNMA TIRE CORD CO. LTD.中国タイヤコードのアジア大手。ナイロン、ポリエステル、スチールを展開
KORDSA GLOBAL トルコ1973年よりタイヤコードを製造。BS、コンチ、GY、MICHELIN等に供給
SABA TIRE CORD COMPLEX イラン2003年にタイヤコードを生産開始。近年は中国にも輸出
SRF LTD. インド1970年よりナイロンコードファブリックを製造
CORDENKA GMBH ドイツレーヨンタイヤコード専業メーカー。生産能力は3.2万t/年
GLANZSTOFF オーストリアチェコ、イタリア、ルクセンブルグに生産拠点を保有。年間3万tのファブリックを出荷
DUPONT 米-
KOLON INDUSTRIES INC. 韓国1973年よりタイヤコード事業(PET, Ny, aramid)を展開、Michelin,BS, GY, コンチを主要顧客に持つ
帝人 日本グループにユニオンタイヤコード等を持つ
YANTAI SPANDEX CO. LTD. 中国アラミド繊維・ヤーンを展開
* BS(ブリヂストン)、GY(グッドイヤー)
スチールタイヤコード/ファブリック
ポリエステルタイヤコードファブリック
ナイロンタイヤコードファブリック
レーヨンタイヤコードファブリック
アラミドタイヤコードファブリック
591
⑨ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
2012年〜2017年の期間にアラミド繊維に係る研究論⽂を発表している研究者は以下の通り。 *CiNiiを利⽤ 京都工芸繊維大学 奥林 ⾥⼦ “電子線照射技術を応用したアクリル糸およびアラミド繊維の加工” 繊維学会誌 Vol. 72(2016) 国⽴研究開発法⼈⼟⽊研究所寒地⼟⽊研究所 佐藤孝司、他 “埋込定着軸方向鉄筋とアラミド繊維シートにより補強したRC橋脚の正負交番載荷試験” 国⽴研究開発法人土木研究所寒地土木研究所月報 : monthly report (762) 首都大学東京都市環境学部 山口あかり、他 “アラミド繊維シートで補強した既存木造建物の柱-土台接合部の静的曲げ試験(構造)” 日本建築学会関東支部研究報告集 86(I) 釧路⼯業⾼等専⾨学校 岸徳光、他 “アラミド繊維シートと PET 繊維シートを併用して曲げ補強した RC 梁の耐衝撃挙動に関する実験的研究” 釧路⼯業⾼等専⾨学校紀要 国⽴研究開発法⼈⽇本原⼦⼒研究開発機構 ⻫藤徹、他 “アラミド繊維ロッド材料の極低温引張特性評価” 低温工学 50(8) 山形大学 Polymer Science and Engineering 高山哲生、他 “炭酸カルシウム微粒⼦分散が PP/アラミド繊維複合材料の⼒学特性に及ぼす影響” M&M 材料⼒学カンファレンス 2014 国⽴特別⽀援教育総合研究所教育情報部 土井幸輝、他 “⾼強度・軽量化を実現するアラミド繊維強化プラスチック製⽩杖の開発とその評価 : 上肢負担軽減効果の評価法に関する実験的検討 (福祉情報工学)” 電子情報通信学会技術研究報告 千葉⼤学 Chemical Analysis Center ⼭⼝謙太郎、他 “アラミド繊維シートで補強された組積体のせん断挙動” 都市・建築学研究 23 関東学院工学部 出雲淳一、他 “落橋防⽌⽤アラミド繊維ロープの引張特性” 関東学院大学工学部研究報告
594
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
*KAKEN及びJSTプロジェクトデータベースを利⽤。
プロジェクト名⾼強度繊維不織布を用いた防護材料の開発
衝撃的外⼒により損傷した鉄筋コンクリート部材の耐衝撃性向上法に関する研究
配向性を考慮したHPFRCCの繊維架橋則の構築と構造性能の評価
期間 (2016年度実施研究) 2014.04〜2017.03 2014.04〜2017.03
資⾦拠出元 - 科研費 科研費
予算⾦額 - 507万円 975万円
参加機関東京都⽴産業技術センター複合素材開発センター/榎本一郎
室蘭工業大学(小室雅人)釧路⼯業⾼等専⾨学校(岸徳光)
筑波大学(⾦久保利之)
プロジェクト目標
・ニードルパンチによるアラミド繊維不織布の製造・目標は厚さ2.0 mm、目付200 g/m2以上・防災頭巾として防炎性能、衝撃吸収性能に優れる
衝撃荷重の作用により損傷したRC 部材の合理的な耐衝撃性向上法として,アラミド繊維製連続繊維シート接着工法を研究。
高性能繊維補強セメント複合材料(HPFRCC)のマトリックス中における繊維の配向性を分布関数(楕円分布)で表現し、スナビング効果および有効強度係数を含めて精確に架橋則を評価することによって、HPFRCCの引張性状および構造性能の評価の構築を⾏うことを目的としている。
599
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
<米国> 各省の⽀出データ(Contract, Grant, Sub-Contract)をまとめているUSASPENDING.govを用い、Aramid Fiber関連プロジェクトの抽出を⾏ったが、以下のもの以外にはなかった。 また、Federal RePORTER(a searchable database of scientific awards from federal agencies)のプロジェクトサーチ上でも現在稼働中のプロジェクトは⾒当たらなかった。
ただ、US DOD(Department of Defense)が実施している官⺠パートナーシッププログラム(MD5 National Security Technology Accelerator)や DRAPA(The Defense Science Office)が主導するWarrior Web Programなどで取り組まれている研究開発プログラムは公開されていないものも多くあるものとみられる。
プロジェクト名-
期間 2016.03〜2017.1
資⾦拠出元 Department of Defense
予算⾦額 120,032USD
参加機関University of Illinnois
プロジェクト目標
Experimental andComputational Studies ofSingle High PerformanceAramid Fiber Failure*2015〜2016にも同様のプロジェクトを実施(拠出額:107,000USD)
600
※MD5 DOD が主導するイノベーションイニシアティブ:National Security Technology Accelerator(NSTXL)の一環として進められている防衛関連のTechnology Domain Awareness(TDA)〜官⺠ネットワーキングを⽬的としたコラボレーションプログラム。2017 年 8 月には、高機能織物の開発促進を目的としたハッソンイベントをMIT Media Labで実施している。 ※NSTXL DOD が資⾦を拠出するコンソーシアムで、⺠間技術の軍事応⽤を促進する各種プログラムを実施。事業規模は100MUSD(2015年4月)。 <欧州> 欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)を対象に Aramid
Fiberの研究開発プロジェクトを調査。現在、稼働しているプロジェクトはなかった。 ただ、英国、フランス等は防衛関連の研究開発プログラムを設置(英 Future Infantry Soldier
Technology (FIST) program、仏FELIN Infantry Combat Suite)している。 *Future Infantry Soldier Technology (FIST) program 英 Ministry of Defence (MOD)が2008 年より主導した次世代コンバットシステムプロジェクト(Thalesが契約)。現在はMorpheus Project として引き継がれている。 *FELIN Infantry Combat Suite Safran Electronics & Defenseがフランス政府の支援(調達費込みで11億EUR, 2011~2015)を受け、開発したボディアーマーを含むコンバットシステム。現在は"FELIN V1.3"にアップグレードされている。 <中国> 2010 年に⽰された「戦略的新興産業の育成・発展加速に関する国務院の決定」において、省エネ・環境保護、新世代情報技術、バイオ、ハイエンド装置製造、新エネルギー、新材料、⾃動⾞が「戦略的新興産業」として指定を受けている。このうち、新材料では新機能材料(レアアース、⾼性能膜材料、特殊ガラス、高機能陶器、半導体照明等)、新構造材料(特殊鋼、新型合⾦、エンジニアリングプラスチック等)、⾼性能繊維とその複合材料(炭素繊維、アラミド繊維、超⾼分⼦量ポリエチレン繊維等)が盛り込まれた。
601
<韓国> 韓国の産業資源通商部は 2010 年に、WPM:World Premier Materia 事業の国策課題とし
て、アラミド繊維を含む10大素材(WPM)及び、20大核心部品素材を選定し、2010年から2018年までに政府が開発支援としてそれぞれ1000億円/200億円を投資すると発表している。課題の目標は、世界最初に商業化できる素材・市場を新たに作り出し、持続的な市場⽀配⼒を持つ 10 大素材を開発することである。WPMと核⼼部品の投資計画は分離されており、WPMの場合、3~4段階の技術を選定し、事業化直前の8段階までの開発を目標に支援するとし、2016年4月にはWPM2段階事業成果展示会が開かれている。 テキスタイルライフ(2017 年 1 月)によると、韓国の⻲尾市は、既存のポリエステル・ナイロン原糸生産
中心の生産体制から、炭素繊維、アラミド繊維、フェルトなど、産業用繊維素材に、品目が変化しつつある。2016年末から未来成⻑産業として育成している「炭素産業クラスター造成事業」が、政府の予備妥当性調査を最終通過したことにより、炭素繊維生産基盤(生産設備及びインフラ)が拡大されると⾒込まれるためである。当事業は⻲尾市と、産業通商資源部、慶尚北道、全羅北道が共同で 2017年から2021年にかけて、約88億円を投資する計画であり、炭素繊維の源泉技術確保、研究開発、関連企業の技術開発支援のための核心装備構築などが含まれる。 ⻲尾市は今後産業⽤繊維の⽣産地として浮上すると期待されており、現時点で⻲尾市に原糸の生
プロジェクト名
「十二·五」973計画ー高性能アラミド繊維製造における科学技術問題点
「十二·五」863計画ー国産パラアラミド繊維複合材料の製造·応用におけるコア技術に関する研究
NSFC面上プロジェクトーCovalent Modification ofMultiwalled CarbonNanotubes with Para-aramid Nanofibers
期間 2011.1~2015.8 2012~2016 2017.1~2020.12
資⾦拠出元科技部 科技部 NSFC
(国家⾃然科学基⾦委員会)
予算⾦額 1685万元 1825万元 61万元
参加機関東華大学 軍需装備研究所、泰和新材料
股份有限公司、北京化⼯⼤学…
魯東⼤学
プロジェクト目標
①高性能パラアラミド繊維の国産化を実現する。国防、宇宙飛⾏、航空、経済などさまざまな分野のニーズを満たす。②製品は外国主流製品(eg.Kelvar 29)に負けない性能を有する。
①⾼強⼒パラアラミド繊維の量産·国産化を実現する。防弾チョッキ、ゴム補強材などに使われる。②⾼強⼒・⾼弾性率に優れた629/529Rパラアラミド繊維を開発する。
不明
602
産設備を持つKOLONグループは今後、諸設備を⾦泉市に移転し、代わりにアラミド繊維やタイヤーコード⽤の⾼強度⽷など、産業⽤繊維素材を中⼼に⽣産品⽬を再編するプロジェクトを推進している。このプロジェクトが完了すれば、KOLONグループは、化繊原⽷はほぼ⾦泉⼯場で、産業⽤⽷は⻲尾⼯場で生産することになる。 なお、現地⾔語によるインターネット検索を⾏ったものの、政府支援による研究開発プロジェクトの詳細に関する情報は得られなかった。 <台湾> 現地⾔語によるインターネット検索を⾏ったものの、抽出できた研究プロジェクトはなかった。
603
(補足)ニュース・リリースまとめ
日本 海外20122013 4 帝人 タングステン粒⼦をブレンドし放射線(X線、γ線)遮蔽機
能を付与したアラミド繊維を開発11 帝人 パラ系アラミド繊維「トワロン」を使った新たな複合材料を
20142015 2 帝人 炭素繊維やアラミド繊維で補強した木造建築物用集成
材「Advanced Fiber Reinforced Wood」を開発4 Kolon/DupontKolonがDupontに275MUSDを支払うことで合意。
2009年から続いた法廷闘争が終結
12 東レ ケブラー繊維を用いた山小屋の噴石防護用シートを発売 12 Yantai Tayhoアラミドペーパー(メタ系)の第2工場(1,000t/年)を稼働
2016 3 帝人 貨物輸送関連製品を扱う米国のマクロ・インダストリー社(アラバマ州)と、トワロンを使用した航空貨物コンテナ(ULD)の共同開発、製造、商業化で協⼒していくことに合意
12 帝人 デニム調アラミド繊維織物「Xfire DENIM」(エクスファイア・デニム)を開発し、消防団員が着用する防護⾐料向けなどに販売を開始
2017 4 帝人 アラミド繊維事業の管轄をオランダ拠点に移⾏ 3 Dupont Luminati Aerospaceと新たな防護服向けテキスタイルの開発でパートナーシップを締結
東レ・デュポン 東レ東海工場内に「ケブラーテクニカルセンター」を設置 6 Dupont防弾ベスト等の需要低迷をふけ、ケブラー工場(GooseCreek)を閉鎖
8 帝人 パラ系アラミド繊維「トワロン」、オランダの生産拠点でデボトル増強を実施し、2019年初夏の稼働を予定
Hyosung Ulsan工場のアラミド繊維⽣産能⼒を5,000t/年に拡大
10 帝人 ウェアラブルデバイスを内蔵した「スマート消防服」を開発 9 DupontDowDuPontが誕生
帝人 15億円を投じた松山事業所(松山市)のパラ系アラミド繊維「テクノーラ」の増強ラインが稼働
*各社ニュースリリースならびに新聞雑誌記事から抽出
605
(補足)研究費データ〜アラミド繊維
※科研費をはじめ、各省庁、JST、NEDO、AMED 等の競争的研究資⾦の研究費データベース(⽇本の研究.com)を⽤い、指定技術関連の研究費データを整理。
606
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
セルロースナノファイバー(CNF)は、植物細胞の根幹を構成するセルロース繊維をナノレベルに解繊したもので、繊維幅は3〜100nm、⻑さ5μm以上の極微細な繊維状物質である。「鉄の1/5の軽さ、鉄の 5 倍の強度」、「⽐表⾯積が⼤きい(⼩さいサイズで⾼性能)」、「熱変形が少なく寸法安定性に優れる」、「植物由来」、「ガスバリア性」といった優れた特性を有する。 1990 年代半ば頃から東京⼤学、京都⼤学、九州⼤等を始めとする⼤学や、産業技術総合研究所、森林総合研究所などの研究機関を中⼼に研究開発が進められ、2000 年代に入ると製紙メーカーを中心にサンプルワークが始まった。 2010 年代になると、政府・官公庁の主導により、森林資源の有効活⽤や国内製紙産業の再興、
⽇本から世界に発信する競争⼒のある新材料の開発促進などを背景に CNF を新たな産業として後押しする気運が高まった。2014年には国の成⻑戦略である「⽇本再興戦略」において、「セルロースナノファイバー(超微細植物結晶繊維)の研究開発等によるマテリアル利⽤の促進に向けた取組みを推進する。」という⼀⽂が記載されている(「⽇本再興戦略」改訂2014 平成26年6月24日)。これを受け、2014年8⽉には農林⽔産省、経済産業省、環境省など複数の省庁が連携し、関連する政策推進と政策連携を⽬的として「ナノセルロース推進関係省庁連絡会議」が創設された。同じく2014年にはナノセルロースの研究開発、事業化、標準化を加速するためのオールジャパン体制のコンソーシアム「ナノセルロースフォーラム」が設⽴され、産業技術総合研究所内に事務局が設置されている。 国及び公的機関の後押しもあり、日本国内の製紙メーカー、化学メーカー、機械メーカーなど幅広い業界から多くのメーカーが CNF 市場へと参入してきた。各社とも当初はラボスケールで少量を⽣産し、⽤途や供給先を限定したクローズドなサンプルワークが中心であったが、2016 年に⼤王製紙が 100t/年(固形分換算。以後、特に断りの無い場合、数量については固形分換算とする)規模のパイロットプラントを⽴ち上げたのに続き、2017年4月には日本製紙が国内初の CNF量産プラントを500t/年の能⼒で稼働させている。 メーカーサイドのこうした動きに対応する形で、特殊紙やブレーキパッド、樹脂加工品、安全靴、日用品など、幅広い分野で CNF を採用した開発品に関するリリースが相次いでいる。いずれも現時点では量産には至っておらず、試作やサンプルワークの段階と推定されるが、ここへきてCNF市場はこれまでの開発段階から実用化段階へとステージを変えつつある。新聞や雑誌で記事化される機会も増えるなどメディアの注⽬度も⾼く、⽇本発の新材料として、CNF はフィルム、樹脂成形、繊維、製紙など幅広いマーケットでの需要が期待されている。 <CNF製造技術> CNF はセルロースをナノ単位まで解す解繊の⽅法によって特性が異なる。参⼊メーカーの中には⽇本製紙のように複数の製法でプラントを⽴ち上げているケースもあるが、多くは単⼀の製法での展開であり、どの製法を採⽤するかによって各社の事業戦略も異なっている。
608
植物に含まれるセルロース繊維から CNF を取り出す手法としては、①触媒や酸などでセルロース分子鎖の⽔素結合を緩めてからミキサーなどにかける化学的解繊法、②原料をホモジナイザーなどの機械に投⼊、機械の⼒で微細化する機械的解繊法、③セルロースを分散させた液体(懸濁液)を高速で衝突させ、水の運動エネルギーと衝突の衝撃で解繊する水衝突解繊法の3 つに大別される。化学的解繊法を採用しているメーカーには日本製紙、王子ホールディングス(以下、王子 HD)、第⼀⼯業製薬、北越紀州製紙、旭化成、服部商店などがあり、機械的解繊法は大王製紙、モリマシナリー、星光 PMC、日本製紙、ダイセルファインケムなど、水衝突解繊法は中越パルプ工業、スギノマシンが事業化している。 各製法別のCNFの特性を具体的に⾒ると、化学的解繊法の最⼤の特⻑は、パルプ内の CNF の表面にある水酸基に触媒を反応させて水素結合を解くため、解繊後のCNFは他の方法で解繊されたものに比べて繊維幅が小さく、繊維径3〜4nmのシングルナノサイズに完全にナノ分散した繊維が得られるという点にある。可視光波⻑よりも細かく均⼀に分散しているため光の散乱が発⽣せず透明である。1本の繊維はアラミド繊維なみの弾性率(約138GPa)、石英ガラス並の寸法安定性(2.7ppm/K)、高い結晶化度(70〜90%)という物性を持ち、水中で3次元網目構造を形成し、チキソ性、分散安定性、乳化安定性などの特徴的なレオロジー挙動を示す。 無色透明であること、高結晶性、特異なレオロジーといった特⻑から、化粧品・⾷品・⽇⽤品など幅広い用途向けの機能性添加剤や、基材(フィルム、紙等)にバリア性などを付与する機能性コーティング剤としての用途が期待されている。また、CNF同士は強固に水素結合するため、単体で製膜すれば高い酸素バリア性を有するフィルムができる。 ⼀⽅で、表⾯に⽔酸基が多数存在する親⽔性の⾼い材料であり、油や有機溶剤に配合する際には疎⽔化処理が必要であること、⽔中で解繊し⽔分散液(スラリー)状での供給が基本であるため、添加の際には材料全体の⽔分調整が必要であるなどのデメリットがあり、メーカーサイドでは課題解決のため、疎⽔化グレードや⽔分含有量を減らしたパウダーグレードなどを開発・投⼊している。 機械的解繊法は、原料であるパルプを⽔に溶かした懸濁液を⾼圧ホモジナイザーやグラインダー、スクリュー押出機などにかけて微細化する⼿法である。剪断⼒・衝撃⼒などの物理的な⼒を利⽤し解繊するため、繊維幅は10数〜数10nm と化学的解繊法に比べ大きく、透明性にも欠ける。一方で、触媒や化学薬品などを使⽤せず、原料であるセルロースの物理的、化学的安定性といった基本特性を損なわずに解繊でき、疎⽔化パルプを使⽤することで容易に疎⽔性を付与できる。また、化学的解繊法ではCNF解繊⼯程で植物繊維に含まれるリグニンが除去されるのに対し、機械的解繊法では原料にリグニンが適度に残留したリグノパルプを使⽤することでCNF表面にリグニンを残したリグノCNFが得られる。リグニンは植物繊維の中で細胞壁同⼠を接着する役割を持つため、リグニンが残留した状態のCNFは耐熱性や強度が向上するというメリットがあることから、樹脂やゴムとの複合化⽤途に適している。 水衝突解繊法は、水の運動エネルギーでセルロース分子鎖の水素結合を緩め、衝突の衝撃で解繊するものである。具体的には、①水に懸濁した天然セルロース繊維を加圧装置で高圧をかけ、②チャンバー内で対向している2 つのノズルから1点に向かって高速ジェット噴射。③噴射された懸濁液が衝突して
609
発⽣する圧⼒が、セルロース繊維の中の弱い分⼦間相互作⽤を優先的に開裂させることで微細化を実現する。開裂の際に CNF の疎⽔表⾯が露出されることから親⽔性と疎⽔性を同時に持つ⼆⾯性の特⻑を持ち、樹脂との混合性が⽐較的良好で有機溶媒の使⽤も可能である。また、化学成分を⼀切使わない他、製造に必要なエネルギーも⽐較的少ない。⼆⾯性の特性を応⽤することで、疎⽔性材料に親⽔性能を、親⽔性材料に疎⽔性能を付与することができるようになり、紙やプラスチックの新しい使い方の開発につながるポテンシャルもある。
610
CNFサイズ 親水/疎水 特徴 課題
・高粘度、高親水性、透明性・疎水性物質(樹脂等)との混合性が悪い
・シート ・日本製紙
・大量生産しにくい ・フィルム ・第一工業製薬
・フィルター材料 ・北越紀州製紙
・機能性添加剤(増粘剤等 ・花王
・高粘度、高親水性、透明性 ・シート
・安価なリン酸を使用 ・フィルム
・ウェットパウダーの製造が可能 ・大量生産しにくい ・フィルター材料
・機能性添加剤(増粘剤等
・CNF解繊~樹脂混練までワンパスで対応可能
・少量多品種対応しにくい ・樹脂補強材
・大量生産が容易
・樹脂補強材
・機能性添加剤(食品、化粧品など)
・透明でない ・樹脂補強材 ・モリマシナリー
・専用の機械装置が必要
・パルプからの解繊も可能
・透明性が低い ・機能性添加剤 ・大王製紙
・ガスバリアシート
・機械補強材
・疎水物質との混合性が良好 ・専用の機械装置が必要 ・樹脂補強材
・エネルギー消費量が低い ・シート
・水とパルプのみで製造可能
・専用の機械装置が必要 ・機能性添加剤 ・スギノマシン
・樹脂補強材
[矢野経済研究所作成]
・中越パルプ工業
ウォータージェット -・ウォータージェットを用いた湿式微粒化装置で製造
20nm 親水性・セルロースに加え、キチン、キトサンなども解繊
水衝突
ACC九州大学/近藤教授
・パルプ懸濁液を2つのノズルで対抗噴射し衝突圧により解繊
10数nm
疎水性面/親水性面を同時に有する「二面性」
原料による
・木材チップからの直接解繊でリグノセルロースが得られる
-
・グレードの異なる解繊工程を組合わせて解繊
20~60nm 親水性
・古紙パルプからのCNF製造が可能
・星光PMC・日本製紙・王子ホールディングス
ホモジナイザー使用 -・パルプ分散液を高速(約750㎞/h)でホモジナイザー機構内に流し、壁面に当たる衝突圧で解繊
10~100nm
親水性・水とパルプ分散液のみで製造可能
・少量多品種対応しにくい必要以上のエネルギーが必要
・ダイセルファインケム機械的処理
二軸押出機使用(京都プロセス)
京都大学/矢野教授
・二軸押出機で変性パルプ、添加剤、樹脂を混練
4~60nm 疎水性
その他
-・製紙用のヒノキチップを二軸スクリュー装置で粗粉砕た後、グラインダーで解繊
20~300nm
親水性
・疎水性物質(樹脂等)との混合性が悪い
・王子ホールディングス
・場合によっては尿素を添加し加熱処理
化学処理
TEMPO触媒酸化法東京大学/磯貝教授
・材料にTEMPO触媒を添加後解繊処理
3~4nm 親水性
リン酸エステル化法 王子製紙
・材料にリン酸を添加後、解繊処理
4~60nm
セルロースナノファイバー 製法別概況
製法 開発 プロセス特性
主力用途 採用企業
611
主な製造技術の比較(性能VSコスト) 出所:“Cellulose nanofibrils (CNF) – a big hype on the edge of a breakthrough” VTT Technical Research Centre of Finland *Enzymatic – 酢酸菌等の微⽣物を利⽤したバクテリアナノセルロース。純度が⾼く、⽣分解性、保⽔性に優れる。
613
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
CNFはフィルムや不織布など⼀部の⽤途を除き単体で使⽤されるケースは少なく、樹脂や繊維などと複合化することで⾼結晶性、⾼強度、可撓性、寸法安定性といった性能を発揮し、強度アップや軽量化などを実現する。炭素繊維などと同じく、単体ではなく複合化にこそ用途・市場拡大の芽があり、樹脂や繊維、溶剤などと「いかに混ぜやすくするか」というテーマでの開発が課題の一つとなっている。 ナノセルロースに限らず、カーボンナノチューブ等のナノマテリアルでは、分散性が必ずつきまとう課題として挙げ
られる。⻑年の研究開発を通じ、分散性の課題は解消されつつあるともされるが、ナノマテリアルが当初期待されたような次世代材料としてのポテンシャルを⼗分に引き出せているまでには⾄っていない。特に樹脂、ゴムなどのコンポジット化技術においては、いわゆるナノマテリアルの「サイズ効果」を実用化レベルで引き出した成果はあまり⾒られないのが現状である。CNF は、バイオベースであること、ソースが豊富かつ安価で、製造コストを大幅に引き下げられる可能性があることなどのメリットがあるが、そうした産業、環境、社会に対するコンパティビリティ(compatibility)を有する魅⼒を活かし、ナノテクノロジーの深耕、RTM 等の新規周辺技術の普及、次世代材料のイノベーションスキーム確⽴等を促進していく機会として利⽤していくことも重要である。 *⾦沢⼯業⼤学・影⼭教授は、CNF コンポジットは流動性や耐熱性の点から既存の射出成形技術が利⽤
していくとの⾒解を有しており、RTM等、新規のコンポジット技術導入に期待を寄せている。 CNF に関わるメーカー各社ではこれまでも、⾮⽔系材料と複合化を⽬的とした疎⽔変性や、ユーザーサイド
の複合化プロセスでのハンドリング性向上のためのウェットパウダー化への取組みが進められてきた。非水性溶液や熱可塑性樹脂など、複合化が可能な材料の幅も広がっており、今後さらに⽤途開発の幅を広げるためには、樹脂や化学品など CNF を直接使用するユーザーとの共同開発にとどまらず、さらにその先の川下メーカーとの連携も必要であろう。 環境省と経済産業省、農林⽔産省との連携により平成 27(2015)年度〜平成 32(2020)年度に
亘り実施されている「セルロースナノファイバー(CNF)等の次世代素材活用推進事業」において、CNF 活用製品の性能評価モデル事業が進められており、CNF の⽤途開発を推進する分野として⾃動⾞、家電、住宅・建材、再生エネルギー、業務・産業機器の 5 分野がリストアップされている。これらは材料、部材、アッセンブリーなど川上から川下までの参入メーカー数も多く、さらに周辺の副資材や設備機器なども含めた業界の裾野も広い。性能、加⼯性、コストなど材料に対する要求事項は業界のどのポジションで展開しているかによっても異なるだろう。ここに向けて CNF を提案し、採⽤に向けて何がネックになっているのか、どのような課題を解決すれば良いのかを把握し、新たな製品開発に活かすなど、これまでの提案や用途開発の枠を超えた取組みをどう進めていけるかが、今後のCNF市場の⾏⽅を占うポイントとなる。 研究開発(⼤学・研究機関)〜川上(材料メーカー)〜川下(部材・加⼯・アッセンブリメーカー)まで
を国内に備える⽇本においては、新素材の開発〜提案、ユーザーからのフィードバック、開発改良の上での再提案、さらなるフィードバックというスパイラルが働く。CNF の実⽤化と市場確⽴に向けて、業種を超えた取組みが求められている。
614
③ ①及び②の用途に係る国際市場規模及び日本企業の世界シェア
現在、CNF を含むナノセルロースは商業生産が始まったばかりで、サンプル出荷のケースも多いため、実需ベースでの世界市場規模を算出するのは困難であるが、ボールペンインクや紙おむつなどでの応用が進む日本がナノセルロースの市場形成で世界を先⾏しているものとみられる。 2017 年7 月時点で実際に CNF を使用した製品が世に出ている例としては、ボールペンインク、紙おむつ、
ペーパークリーナー、ステレオ振動板など。CNF の⽣産量全てが実際の製品に使われているわけではなく、ほとんどはサンプル供給であるものと⾒られるが、その分を含めても 2017年の日本メーカー各社合計のCNF⽣産量は最大で10〜30t/年程度と推計される。 他国の状況も同様で、⽶国、カナダ、北欧諸国においても、CNF の生産はデモンストレーションレベルに止まっており、サンプル供給が多いとみられる。そのため、グローバルのCNF市場規模は100tを下回るレベルと推計される。その中で、⽇系メーカーのシェアがどの程度確保しているかは不明であるが、商業ベースでの実績から日系メーカーがマーケットのフロントランナーのポジションをキープしていると推察される。 なお、CFも含めたCNFでは、フィンランドUPMが音響機器やキッチン設備、学校用品などでバイオコンポジット(UPM Formi)の採⽤を伸ばしており、販売量もある程度まとまってきたと考えられる。また、カナダGreenCore CompositesがPP/CFコンポジットを“NCell”のブランド名で展開しており、⾃動⾞内装材等へ適用を図るなど、ボリューム⾯で⾒るとUPM等のCF勢がシェアを確保している可能性がある。
④ ①及び②の用途に係る国際市場規模の将来予測
経済産業省が2014年3月に発表した「平成25年度製造基盤技術実態等調査(製紙産業の課題に関する調査)」によると、2020 年前後の⽣産規模は 600〜900t/年程度とイメージされている。量産・市場投入されたものだけでなくパイロットプラントでの生産も含まれるものと考えられるが、同調査による開発に向けたロードマップの中では、TEMPO酸化や⼆軸混練などの現⾏技術で⽣産されるCNFは2020年までに実証実験を終了し、2020 年〜2025 年が導⼊準備期間、2025 年以降は普及・拡⼤期に⼊ると予想されている。 国内におけるCNFの研究開発開始から約20年、メーカーでのサンプルワーク開始から既に10数年が経過
し、2014年には産官学連携での展開が⾏われる中にあって、これまでCNFの事業化と市場⽴ち上がりのスピードは決して速いとは言えない。業界内には「CNF は話題が先⾏しているが、実際の需要がどこまで期待できるかは未知数」と⾒る向きもあり、2020 年に600〜900t/年という経済産業省の当初のイメージは現時点でやや遠い目標との声も聞かれる。
615
しかし、新素材である CNF は市場での注⽬度も⾼く、化粧品、⾷品、塗料、容器・包材、光学フィルム、⾃
動⾞など幅広い分野での採⽤が期待されている。もちろん、①生産・供給体制、②CNF の特性、③コストなどの点から市場の⽴ち上がりが当初のイメージよりも遅れているものの、①と②については2016年から2017年にかけて大きく改善している。 具体的に⾒ると、まず⽣産・供給体制については当初、CNFメーカーの⽣産能⼒の限界から市場にサンプル
が潤沢に⾏きわたらず、ユーザーの製品化が進まなかった。少量⽣産のためサンプルも⾼価であり、CNF メーカーサイドでは供給量や使⽤⽤途、供給先に制限をかけざるを得ず、市場では「CNFを使ってみたいがサンプルが手に入らない」というケースも多かったようだ。 しかし、2016年には4月に大王製紙が三島工場(愛媛県四国中央市)内に100t/年規模の機械解
繊⽅式のプラントを⽴ち上げたのに続き、2017年1月に王子ホールディングス(以下、王子HD)が富岡工場(徳島県阿南市)にリン酸エステル化法設備 40t/年、同年 7 月には日本製紙の富士工場(静岡県富士市)にCNF と樹脂の複合化プロセスの実証実験設備10t/年のパイロットプラントを稼働させている。ちなみに、大王製紙三島工場、王子 HD 富岡⼯場の能⼒は固形分換算だが、⽇本製紙富⼠⼯場の能⼒は固形分ではなく樹脂に混練した状態でのキャパシティであり、CNF の解繊量そのものは複合樹脂の含有量にもよるが2〜3t/年程度になるものと推計される。 さらに、商業⽣産を⽬的とした量産プラントの稼働も始まっている。2017年4月には国内初のCNFの商業
プラントが日本製紙の石巻工場(宮城県石巻市)で稼働を開始した。同工場はTEMPO酸化法によるプラントで、⽣産能⼒は500t/年。同年6⽉には中越パルプ⼯場の川内⼯場(⿅児島県川内市)で100t/年の能⼒を持つ⽔中カウンターコリジョン(Aqueous Counter Collision:ACC)法の設備が稼働している。
616
この他、2017年9月には日本製紙・江津工場(島根県江津市)に40t/年の CM(カルボキシメチル)化CNFのプラントが稼働予定であり、2017年に稼働あるいは稼働予定の量産プラントの⽣産能⼒は合計で640t/年となる。各社のパイロットプラントの⽣産能⼒を合わせると、CNFをラボベースではなく一定以上のボリュームで⽣産できるプラントの能⼒は 2017 年末には 880t/年程度となり、市場拡⼤のネックの⼀つであった⽣産・供給能⼒の限界はひとまず解消されたと⾔えるだろう。
617
二つ目の課題となっている CNF の特性であるが、これは表⾯に⽔酸基を持つ親⽔性材料であるという CNFの特性と、基本的に水中で解繊するため水分散液(スラリー)状での供給が中心となるCNFの形態とに起因する。 CNF の繊維表面には水酸基(OH)が多数存在し、⽔と親和性の⾼い材料であるため、⽔中で解繊され、
⽔分⼦と⾼い親和性を⽰して均⼀に分散される。しかし、油や有機溶剤などの⾮⽔系材料に混ぜると、⽔酸基同士が水素結合を形成するためCNFが凝集してしまい均一に分散することができない。そのため、これまではCNFの用途は水性のインクや化粧水などの添加剤向けが中心であり、用途開発にも限界があった。 これに対し CNF メーカーでは、原料パルプに酸などを加えて疎⽔変性した上での解繊や、CNF 表面の親水
性を持つ官能基に修飾基を結合させ、界⾯活性剤のように油などの疎⽔材料をはじく性能を持たせるなど、疎⽔性材料の中でもCNFの凝集を防ぐ技術を開発。2016年〜2017年にかけて、王⼦HD、第一工業製薬、花王、星光 PMC、服部商店といった各社が疎⽔化グレードを開発・投⼊し、親⽔性材料であることに起因する用途開発の課題は解決に向かっている。 また、CNF は表面の水酸基により水中に均一に分散される一方で、水を完全に抜いて乾燥させた場合、繊
維表面の水酸基同士が水素結合をおこして凝固してしまい、再び水に入れても再分散しないという特性を持つ。このため、CNFは基本的に濃度1〜2%のスラリーでの供給が多い。 CNF と他の材料の複合化の際、化粧品やインクなど液状の物であればスラリーでもあまり問題にならないが、
熱可塑性樹脂の補強材として使用する場合などでは脱水ブロセスが必要となり、熱をかけることによる樹脂の変⾊などが⽣じるリスクがある。液状材料への複合化の場合であっても、⾷品や医薬・化学薬品などでは製品の⽔分量を細かく調整しているケースも多く、CNF スラリーの⽔分量が多い場合は対象物の⽔分を減らしたり、添加後にユーザーサイドで⽔を抜く処理が必要となることもあった。 ⽔分量の多いスラリーは輸送効率も低いことから、コストや環境負荷という面でも問題となる。ユーザーサイド
では CNFのサンプルワークが進む中で、ハンドリングや環境対応といった面での課題を問題視するようになり、この解決策として王子 HD、日本製紙、大王製紙、ダイセルファインケム、大阪ガスなどの各社がパウダー状 CNFをラインナップしている。先にも述べたが、完全に乾燥させたCNFは凝集して再分散しないため、水分を含んだままの状態を維持したウェットパウダーとしての供給である。これにより、CNF メーカー各社ではユーザーの保有する設備や想定用途に合わせたCNFの提案が可能となり、ユーザーサイドでも添加の際に⽔分量を気にすることなく、取扱いが容易となった。
618
CNFが解決すべき課題のうち、生産・供給体制とCNFの特性の改良については、既にある程度の解決を⾒た。残るはコスト面での課題である。単純に、CNF の解繊にかかるコストだけを⾒れば、各社の設備が稼働し⼀定以上のボリュームでの⽣産・共有が始まれば、量産効果によりコストダウンは進むだろうが、疎⽔化やパウダー化が必要とされる場合、その分のコストはCNF価格に反映される。 需要拡大が期待される用途のうち、増粘剤や分散剤については、CNF の添加量が重量⽐で 1%にも満た
ないケースが多く、最終製品価格に占める CNF コストの割合は一部にとどまるため、コストが大きな問題にはならない可能性が高い。しかし、市場への CNF の普及・拡大のためには、一定以上のボリュームの確保が必須であり、⼀番の近道は、⾃動⾞や建築物の構造材などバルキーな⽤途での活⽤が期待される樹脂複合材での採用である。 樹脂の⾼強度化、軽量化のための補強材として使⽤する場合、CNF の添加量は重量⽐で 10〜20%程
度で開発が進んでいる。重量⽐での添加量が多いこと、⾃動⾞、建材、家電、容器包材など多くの分野で樹脂が占めるコスト⽐率が⾼いことから、コストダウンはCNF採用の必須条件となる。 この課題の解決策として、京都大学生存圏研究所の矢野浩之教授らが開発した京都プロセスが期待され
ている。⽮野教授の研究室では、もともと⽊材物理学(Wood Physics)分野で、植物細胞の活用した研究を⾏ってきた。中でも植物細胞分離で得るCNFの利⽤に注⽬し、2000年頃より⽊材由来セルロースをグラインダーで機械的に解繊してCNFを製造する技術を開発。2007年には新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「大学発事業創出実用化」プロジェクトに参画し、CNF を補強フィラーとして用いることで、ガラス繊維のような従来のフィラーと同等レベルの強度と同以下の熱変形性を付与できることを確認している。これを受け、PP、PE、ゴムなどの樹脂とのマスターバッチ技術を開発するとともに、2 軸押出機を利⽤した複合化技術を開発した。 京都プロセスはこの研究を応用して開発されたもので、パルプを化学変性して疎水化し、変性セルロースパウ
ダーとした後、複合化する樹脂(熱可塑性樹脂)とともに混練機に投入し溶融混練する。樹脂との混練中に、せん断応⼒によりパルプがナノレベルまで解繊され、樹脂中に CNF が均一に分散したナノコンポジットとなるというものである。従来のプロセスでは、①パルプなどの原料から CNF を取り出す工程、②CNF を疎水変性する工程、③疎水化CNFと樹脂との複合化の工程と大きく3 つの工程が必要であるが、京都プロセスではセルロースのナノ化と樹脂混練をワンパスで⾏うため、大幅なプロセス短縮とコストダウンが可能である。矢野教授は CNF複合樹脂価格について、従来プロセスで生産された場合には10,000円/㎏程度となるのに対し、⼯程数が少ない京都プロセスでは500〜1,000円/㎏程度まで下げることが可能であるとしている。
CNF、CNC 等のナノセルロースは、フィルム、樹脂成形、繊維、製紙など幅広い分野での適用が期待されている。既に増粘剤(ボールペン、カーケミカル)、吸着剤(大人用紙おむつ、トイレおそうじシート)として実用されているほか、凸版印刷や花王、大王製紙などがガスバリア包材への応用を本格的に進めている。 CNF⾃体は現状⾼価な材料であるため、先にも⾒たようにコストが⽐較的問題とされない増粘剤などでの利
⽤が中⼼とみられるが、中期的には実⽤化レベルの⾒えてきた紙フィラー、バリア包材、塗料・コーティング添加剤等がメインの用途として市場形成が進むとみられる。フィンランド VTT はナノセルロースのキーアプリケーションとして“Paper & Paper Board”、“Packaging”、“Paints and coatings”、”Oil & Gas“、”Cement“を挙げている。”Oil & Gas“、”Cement“は日本国内でそれほど表だって研究開発が進められているわけではないが、カナダでは掘削液へのCNC添加について活発に研究開発が⾏われており、CNCの有望⽤途として⾒なされて
620
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
現時点で CNF の活⽤が期待されている⽤途としては、①強度アップ・軽量化などを⽬的とした樹脂複合材料、②透明性、バリア性を活かしたフィルム・シート、③ナノサイズの孔径制御を活⽤した多孔性シート、④増粘剤・分散剤などの各種機能性添加剤などに⼤別されるが、多くは先⾏する競合材料があり、CNF を提案した場合に競合材料を代替するだけの動機がユーザーサイドにあるかが問題となってくる。 CNF複合樹脂の⽤途として特に期待されているのが⾃動⾞構造材であり、近年、NEDO や環境省が主導
し CNF の活⽤で⾃動⾞の軽量化を⽬指すプロジェクトが数多く⽴ち上げられた。2016 年 10⽉には環境省事業として、CO2削減に向けCNFの活用により2020年に⾃動⾞で10%程度の軽量化を⽬標とする世界初の NCV(Nano Cellulose Vehicle)プロジェクトが始動し、CNF軽量材料を実機に搭載することで軽量化による CO2 削減効果(例:⾃動⾞の燃費改善)等の性能評価および早期社会実装に向けた導⼊実証が進められている。 同プロジェクトでは、2020年までにCNF強化樹脂を導入することが可能で、かつエネルギー起源CO2削減
が期待され、CNF の特⻑を活かすことができる⾃動⾞部位の検討を⽬標としている。具体的には、①樹脂素材(内装材・外装材で既存樹脂素材である PP、PA を使用する部位は限りなく CNF 複合材で代替するとともに薄⾁化による軽量化を実現)、②⾦属素材(ドア等の外板をCNF強化樹脂で代替し、可能であればボディー、エンジン、構造部材へと採用を拡大)、③タイヤ・ガラス等(CNFを用いたカラータイヤやCNF強化ガラスの採用等)と、大きく3つの部材についてCNF強化樹脂で試作し強度等の性能評価を⾏うというものであるが、このうち②の⾦属素材代替については既存の⾦属材料だけでなく、先⾏する樹脂材料である CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics、炭素繊維強化樹脂)と競合することになる。 CFRP は⾃動⾞部材では既に⾞体構造部、外板・内板(ルーフ、ボンネットフード、トランクリッド、フェンダー
等)、プロペラシャフト等で採用されているが、いずれも 1,000 万円を超える⾼級価格帯の⾞種が中⼼であり、⼀般価格帯での採⽤は少ない。この背景には複数の要因が考えられるが、最も⼤きいのが既存の⾦属部材との価格差であり、既存材料である⾦属材料価格が普通鋼板及びハイテンで 80 円/㎏程度、ウルトラハイテンで90〜130円/㎏、アルミ合⾦板が500〜600円/㎏、マグネシウム合⾦は3,000円/㎏程度であるのに対し、CFRP(PAN系炭素繊維・標準弾性)は3,000〜5,000円/㎏と高価である。 これに対し CNFの価格(CNF複合樹脂の価格)は、先述のように京都プロセスによる CNF と樹脂との複
合化技術の本格的な運用が始まれば500〜1,000円/㎏程度が実現するとされており、CFRPよりも価格優位性が高く、価格だけを⾒ればアルミ合⾦板やマグネシウム合⾦板代替も射程距離に⼊る。⼀⽅、性能⾯での炭素繊維と比較すると、炭素繊維の比重は鉄の1/4、強度は鉄の10倍とされているのに対し、CNFの比重は鉄の1/5、強度は鉄の5倍とされており、CNFの⽅が軽量ではあるものの強度は炭素繊維に軍配が上がる。加えて、CNF は単体で使⽤されるわけではなく樹脂と複合化されるため、強度・成形性などは複合化する樹脂の性能に依存する部分も大きい。 さらに、現在の⾃動⾞部材の樹脂化状況を⾒ると、構造材(ボディーフレーム)では 2013 年に BMW が
CFRP を⾞体構造部(主要⾻格)に採⽤した EV(i3)を製品化した例を除き、樹脂化率はほぼ 0%。ボディー外板ではフェンダー部分などで⼀部採⽤例があるものの、⾼い成形性と均⼀な表⾯品質、耐デント性、
626
塗装適性などが要求されることから、こちらも樹脂化率はごく⼀部となっているものと⾒られる。 ⾃動⾞に使⽤されている⾦属素材をCNFで代替するには超えるべきハードルはまだまだ多い。CNF複合樹
脂の低コストかつ効率的な製造技術確⽴を⽬指して開発が進んでいる京都プロセスでは現在、星光 PMC、⽇本製紙といった各社が量産に向けた実証⽣産を⾏っているが、同プロセスによるCNF強化樹脂が完成したとしても、⾃動⾞の⾦属部材代替として検討されるようになるには、剛性、耐衝撃性など安全性に係る性能に加え、表⾯形状や塗装、成形への対応といった⾞体のデザイン及び外観に係る特性を⾦属素材に近づけるための研究開発が必須となると予測される。
CNFの活用が期待される用途のうち、透明性・バリア性を活かしたフィルム・シートについては、光学フィルムや
包装用フィルムのベースとして広く使用されている PET フィルム、高い透明性と光学等方性で偏光板を中心に
627
採用されているTACフィルムやCOPフィルム、透明性・成形性に優れるPMMAフィルムやといった高透明フィルム、透明蒸着フィルムや EVOH などの包装⽤バリアフィルム、フレキシブルディスプレイの基板材料やカバーなどの用途でガラス代替として使用されるハイバリアフィルムや透明PI フィルムといった材料と競合している。多くは採⽤されてからの歴史も古く、ユーザーサイドで製品や加工品の製造プロセスをこれら素材の使用を前提に最適化していることや価格がこなれていることなどから、CNF フィルムに限らず新たな材料で代替するハードルは⾼い。 ただ、フレキシブルディスプレイでのガラス代替については、現時点で開発途上のテーマであること、バリア性、
表⾯平滑性、線膨張係数、寸法安定性、表⾯性能、強度、光弾性係数など、要求される性能やフィルムの品質などのデファクトスタンダードが確⽴していない。価格についてもベースフィルムのうちPET、TACなど従来からある材料については樹脂価格とリンクする形でほぼ固まっているが、透明耐熱フィルム、⾼硬度フィルムなどは現在開発途上のものもあり、具体的な価格設定が決まっていないものもある。 こうした用途では、フィルムメーカー、コンバーターとユーザーであるディスプレイメーカーとの間で、試作、サンプル
供給、フィードバック、改良、再提案など、トライ&エラーを繰り返しながらの開発が進められており、新たな材料である CNF フィルムの参入の余地も大きい。CNF の中でも化学的解繊で取り出されたものは繊維幅 3〜4nm程度で可視光波⻑よりも細かいため光の散乱が発⽣せず、⽯英ガラス並の寸法安定性、⾼結晶といった特性から高透明・高光沢で、3H 程度の表⾯硬度のフィルムが得られ、無延伸のキャスト製膜とすることで光学等⽅性の高いガラスのような外観となる。また、⾼弾性率により折り曲げても⽩化しないという特性もある。 ⼀⽅で、耐湿性に⽋け⽔分に弱いこと、加熱による⻩変の発⽣といった課題がある。CNF フィルムはナノ化し
たセルロースをシート化した、いわば「透明な紙」とも⾔える材料であり、⽔や⾼熱への耐性の改善が求められている。例えば、OLED の基材フィルムとして使用する場合、プロセスによっては約400℃の高温への対応や、素⼦材料を⽔分から保護するため⾼レベルの⽔蒸気バリア性が求められる。さらに、光学部材として使⽤されるフィルムには、ハードコートやバリア性の付与、粘着などでウェットコートが施されるケースが多く、これら後加工への対応も求められている。 CNF フィルムについては現在、王子 HD が独自のシート化技術により、高品質の透明連続シートの製造技
術を開発し「アウロ・ヴェールTM」のブランド名で展開している。2017 年 5⽉には絞り加⼯などによる⽴体成形が可能な「アウロ・ヴェール 3DTM」をリリースした。従来の「アウロ・ヴェールTM」の特徴である透明性、フレキシブル性、低熱膨張性に加え、自由に成形加工ができるため、用途開発の幅の拡がりが期待される。 CNFを使⽤し、ナノサイズで孔径を制御した多孔性シートは、空気清浄⽤濾紙(エアフィルター)や繊維強
化プラスチック(FRP)の芯材としての採用が期待される用途である。 エアフィルターは空気中のゴミ、塵埃などを取り除き空気を正常化する目的で使用されるもので、用途や要求
される清浄度によって素材が異なる。レーヨンやポリエステルなどの合成繊維をするものもあるが、CNF はクリーンルームの空気清浄などに使用されるHEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルターや、さらにもう一段粒⼦捕集効果を高めたULPA フィルター(Ultra Low Penetration Air Filter)の上を⾏く極微細な微粒⼦への対応を実現する。 エアフィルターが捕集できる微粒⼦サイズについて、JIS規格(JIS Z 8122)ではHEPA フィルターは「定格
⾵量で粒径が 0.3μm の粒⼦に対して 99.97%以上」、ULPA フィルターについては「定格⾵量で粒径が0.15 µmの粒⼦に対して99.9995%以上」と規定されている。 これらはサブミクロンサイズの粒⼦に対応可能であるため、半導体や液晶などの製造設備(クリーンルーム)
628
内を超清浄空気にしたり、原⼦⼒の安全利⽤のため⼤気中への放射能汚染物質⾶散防⽌の他、医薬・製薬・⾷品⼯場における空気清浄といった⽤途では有効であるが、ウイルスや⼈体に有害なナノサイズの超微粒子はフィルターを通り抜けてしまう。CNF を使用することでナノサイズの網目が形成され、従来のエアフィルターでは対応が難しかったウイルス、微粒⼦などにも有効となり、感染症やパンデミックへの対応が求められる病院や、放射性物質対策が求められる用途での需要も期待される。 CNF の用途のうち、機能性添加剤では主に化粧品、⾷品、インク・塗料などの増粘剤・分散剤をターゲット
として開発が進められている。添加対象物の⾊や⾒栄えに影響しないよう無⾊透明であることが求められる他、低添加でも高い粘性の発現、チキソ性などが求められることから、繊維径3〜4nmのシングルナノサイズに解繊し、完全にナノ分散した繊維が得られる化学的解繊法(TEMPO 酸化法、リン酸エステル化法など)によるCNFが主に使用される。 ニッチ分野ではあるが、⼀般的な天然由来増粘剤に⽐べ低添加領域でも⾼い構造粘性を発現することに
加え、高いチキソトロピー(チキソ性)を持ち、せん断⼒が加わると⼩さい⼒であっても⾼粘度のゲル状から流動性の高い液体のような性質に代わるなど、CNF ならではの特性を活かせることからアプリケーションが広がる可能性が高い。 増粘剤では CNF が開発される以前から、キタンサンガムやグァーガム、カルボキシメチルセルロース(CMC)、
メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロースなど、各種の多糖類やセルロースが使用されてきた。これらの多くは水溶性であり、水に溶けることで粘性を発現するが、CNFは水に「溶ける」のではなく「分散」することで液体に粘性を付与する。可視光波⻑よりも細かいナノサイズの繊維が均⼀に分散するため透明であり、繊維が⽔中で三次元網目構造を形成し、チキソ性、分散安定性、乳化安定性などの特徴的なレオロジー挙動を示す。 特に、静⽌状態では⾼粘度のゲル状で、撹拌したり振り混ぜるなどのせん断⼒を加えることで⼩さい⼒であっ
ても⾼粘度のゲル状から流動性の⾼い液体のような変わるチキソ性に特徴があり、ゲル状でありながらスプレー噴射が可能である。これは競合する既存の増粘剤には無い性能であり、薬剤や化粧品などを下向きでスプレーするといった使い方が可能となる。2015年にはCNFのチキソ性を活かし、インク漏れせず早書きでも擦れたりせず筆記できるボールペンインクが実用化された。化粧品関連では、ベタつかず伸ばしやすいジェルやクリームなどの使い方が想定される。 この他、⽔よりも重いガラスビーズや⾦箔、酸化チタンなど、サイズ、密度ともに⼤きい個体を分散させても沈ま
ず、1 ヵ⽉以上の⻑期にわたり分散性が維持できる⾼い分散安定性を有する。⾼粘度な状態だけでなく、ある程度の流動性のある状態でも沈降防⽌が可能で、これも他の増粘剤には無いCNFならではの特性である。 このように、増粘剤・分散剤などの機能性添加剤では、CNF は競合素材に無い特性をアピールすることで化粧品や塗料など川下市場の製品に対してこれまでにない新しい使い⽅の提案が可能であり、先⾏素材は多いものの単純な代替を狙うのでなければ既存材料との競合にもなりにくいなど、今後の⽤途開発の上でも有望な分野であると言える。
629
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
先の表(主要メーカー各社のCNF⽣産能⼒)で⾒たように、⽇本国内でCNFの量産化に取り組み企業は、王子HD、⽇本製紙、北越紀州製紙、⼤王製紙、中越パルプ⼯業、星光PMC、花王、第一工業製薬、旭化成、服部商店、大阪ガス、ダイセルファインケム、モリマシナリーなどとなっている。 王子ホールディングス 同社は、1990 年代からセルロースナノファイバー(CNF)の研究を⾏っていたが、それが本格化したきっ
かけは、2006年に東⼤・磯⾙教授、斎藤准教授がTEMPO酸化CNFに関する発表を⾏い、製紙⽤パルプから高品質な CNF を製造できる道筋が示されたこと、2007 年以降に新エネルギー産業技術総合開発機構(NEDO)の「変性バイオナノファイバーの製造及び複合化技術開発」プロジェクト(平成19 年〜平成 21年)等が発⾜し、⼤学や研究機関、化学メーカーなど他分野との知⾒と技術交流が盛んになったことであった。 開発を本格化した当初、様々なプロセスでの CNF 製造にトライし、より少ないエネルギーで微細な繊
維を取り出す技術の研究開発を推進。原料パルプからCNFを製造するプロセスとしては、ホモジナイザーなどの機械を使⽤し、パルプを物理的に解繊する機械処理プロセス、パルプを化学前処理した後、機械処理するプロセスに⼤別される。同社では、各種の化学処理プロセスについての検討を⾏った結果、最も実⽤化に有望と考えられるリン酸エステル化法を確⽴した。 王子 HD ではリン酸エステル化法について、同社がこれまで検討してきた製法の中でも品質(透明性、
粘度など)や⽣産性に優れること、使⽤する原材料が⻑年に亘り⾷品や化粧品に使⽤される世の中になじみ深いものであること、⽐較的少ないエネルギー量でシングルナノサイズの均⼀な CNF が得られることなどから、将来の用途展開において最も妥当性が⾼いと判断。当初は研究所のラボ設備で少量ずつ⽣産してサンプルワークを⾏っていたが、2016年12月にはグループ企業である王子製紙の富岡工場(徳島県)に固形分換算40t/年規模の実証実験設備が完成、翌2017年1月より本格的なサンプル供給を開始した。 ラボベースでは製造能⼒の限界からサンプルの量や使⽤⽤途に制限をかけざるを得ない状況にあった
が、富岡工場での実証実験設備の稼働によりサンプル供給規模の拡大が実現。幅広い用途やユーザーに対応する体制が整った。また、サンプルワークと並⾏し、リン酸エステル化法の⽣産効率や品質の実証、さらなる品質向上のための開発など、将来の量産化を視野に⼊れた展開を進めていく⽅針である。 王子 HD ではリン酸エステル化 CNFについて、スラリー(水分散液)、ウェットパウダー、透明連続シ
ートの三形態でサンプルワークを進めている。 スラリー(水分散液)については、現在は2%での供給が中心。リン酸エステル化CNFの特⻑である
⾼透明、⾼粘度に加え、粒⼦分散安定性やチキソ性などを活かして増粘剤などを中⼼に⽤途開発やユーザーとの共同開発を推進してきた。
631
同社ではリン酸エステル化 CNF を使用した増粘剤について「アウロ・ヴィスコTM」のブランド名で展開し、
以前から幅広いユーザーと製品化に向けた共同開発を進めていたが、2017 年に⼊り国内の⼀般消費者向けカーケミカル⽤品の増粘剤として採⽤され、同年5月末よりユーザーへの提供を開始している。
リン酸エステル化 CNF スラリーは上記のような優れた特性が⾼く評価される⼀⽅で、濃度 1〜2%程
度の液体としての供給であるため、添加の際に対象物の⽔分量調整が必要であること、輸送の際には⼤量の⽔を運ぶこととなり、環境負荷やコストの⾯で課題がある。加えて、既存の増粘剤の多くは粉体で供給されており、ユーザー側でも粉体を前提とした生産ラインを組んでいる場合、スラリー状の増粘剤を採⽤しようとするとプロセスの変更や設備投資が必要となるケースも出てくる。そのため、サンプルワークを進め
632
るユーザーからは使い慣れた粉体での供給を求める声も上がっていた。 王子HDではCNFの用途及び市場の拡大のためには、ユーザーのハンドリング性の向上が重要である
と考え研究開発を進めた結果、パウダー状でありながら⽔への再分散が容易なウェットパウダー状の CNFの製造方法を世界で初めて開発。2015年10月よりサンプル供給を開始している。
CNF は水中では分散状態となる一方で、乾燥過程で分子同士が水素結合を起こして凝固してしま
い、再び水に入れても再分散しないため、パウダー化には課題があった。王子 HD が開発したウェットパウダー状CNFは、固形分含有量20%の粉状でありながら、再分散するのに⼗分な⽔分量を含み、再分散後の粘度や透明性は、相当するスラリーと同等の性能となる。 ユーザーにとっては CNF に含まれる⽔分量が少なくなるため、⾼濃度での添加がしやすくなる他、対象
物の⽔分量の調整・計算にかかる⼿間も低減されるというメリットがある。CNFをパウダー化する工程では、基本的に添加物は使⽤しないが、ハンドリング性が重視される⽤途の場合には、添加剤を付与して流動性の高いウェットパウダーとすることも可能である。 スラリーとパウダーの両方をラインナップしたことで、ユーザーの保有する設備や想定用途に合わせた
CNFの提案が可能となったことから、同社ではリン酸エステル化CNFのさらなる用途拡大に期待している。また、パウダーは⽔分量が少なく、スラリーに⽐べて輸送効率が⾼いことから環境負荷の低減につながるとし、CNFの早期の実用化に貢献できるとしている。 また、これまで同社が扱う CNF は、スラリー状、パウダー状ともに親⽔性材料であり、⽔には⾼分散す
るものの、油やアルコールなどの⾮⽔系材料に配合した場合は CNF 表面の水酸基同士が水素結合を
633
形成し凝集してしまうため分散できず、⽔系材料での使⽤に限られていた。しかし、塗料、インクなど増粘剤を使⽤する製品では⾮⽔系材料をベースにしたものも多く、ユーザー側からは⾮⽔系材料にも添加できる疎水化CNFが求められた。 王子HDではこれに応える形で研究開発を推進。多様な有機溶剤に分散可能なCNFの開発に成
功した。透明性や粘度などは親⽔性CNFと同様に高く、炭化水素、アルコール、ケトン、グリコール、非プロトン性極性溶媒など、多様な有機溶剤に分散可能である。2017 年 6 月にリリースしサンプル供給を開始したが、数多くのユーザーから引合いが来ているようだ。
このほか、王子 HD では CNF の開発を開始してから比較的早い段階で連続シート化をターゲットとし
た開発を推進。当初は三菱化学(現三菱ケミカル)との共同開発を進め、2013 年 3 月に世界初の連続シート化設備によるCNF透明シート、CNF多孔シート、樹脂複合化フィルムの開発に成功した。この際に多くの引き合いを得たが、同時に多くの要望、例えば透明性やその他物性の更なる向上、改善などを要求されることとなった。 その後、同社は独自のシート化技術、すなわちリン酸エステル化にて完全ナノ化された CNF を原料に
使用し、併せて同社が保有するコア技術により、高品質の透明連続シートの製造技術を開発した。PETフィルムや TAC フィルムなど光学用フィルムと同等の高い透明性を有し、折り曲げても白化しないという特徴を持つ。 これまでは研究所内で⼩規模に⽣産し、サンプルワークを並⾏して⽤途開発を進めてきたが、最近に
634
なってサンプル需要が拡大したことから 2017 年後半の稼働開始予定で新たな⽣産設備の導⼊を決定した。⽣産能⼒は25万㎡/年からスタートするが、需要により100万㎡/年程度までの能⼒増強も可能である。 王子 HD では CNF の透明連続シートについて「アウロ・ヴェールTM」のブランド名で展開している。「ア
ウロ・ヴェールTM」は強度、弾性率、低熱膨張性といった物理的特性が⾼く、なおかつフレキシブルで⾼透明といった特⻑を持つ。現在、サンプルワークと⽤途開発に取り組んでいるが、ガラスや光学フィルム並みの透明性や物理的特性の⾼さから、フレキシブルディスプレイ・デバイスでのガラス代替フィルムとして期待されている。特に、低熱膨張性では、従来の透明プラスチックフィルムは熱がかかることで寸法が変化してしまっていたのに対し「アウロ・ヴェールTM」は140〜180℃の線熱膨張係数がわずか9.0ppm/Kと極めて小さく、ガラスライクな使い方が可能である。シートの表⾯硬度は、後加⼯無しで PET フィルムのハードコートグレードやPMMAシート並となっている。
⼀⽅で、現状では耐湿性や加熱による⻩変の改善といった課題が挙げられており、いくつかの対応策
は⾒出しているものの、今後もこれらの解決に向けた研究開発を進めていく。また、先述のように 2017年後半には新設備が稼働し、サンプル供給能⼒も拡⼤することから、これまで以上に⽤途開発に向けた
項目 単位 条件 物性
全光線透過率 % 91.4
ヘイズ % 5
引張強度 MPa 223
引張弾性率 GPa 11.6
ガラス転移温度 ℃ 25~100℃ なし
線熱膨張係数 ppm/K 140~180℃ 9.0
[王子HD資料より]
25μm
アウロ・ヴェールの各種物性
635
取組みを加速させていくものと⾒られる。 2017 年 5⽉には絞り加⼯などによる⽴体成形が可能な「アウロ・ヴェール 3DTM」をリリースした。
従来の「アウロ・ヴェールTM」の特徴である透明性、フレキシブル性、低熱膨張性に加え、自由に成形加工ができるため、用途開発の幅の拡がりが期待される。
日本製紙 日本製紙では、紙パルプ関連市場の成熟の中で新たな柱となる事業を模索、パルプを原料とし、⾃
社が保有する技術やインフラが活用できる新素材としてセルロースナノファイバー(CNF)に注目、研究開発を開始した。2007年〜2009年にかけて、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ナノテク・先端部材実用化研究プロジェクト ステージⅠ」に参加。東京大学、花王と共同で PLA などのバイオマスベース樹脂のフィルムとTEMPO酸化CNF との複合化研究を⾏った。 その後、同プロジェクトのステージⅡ(2010年〜2012年)として、同社と凸版印刷、花王との3社
による TEMPO 酸化 CNF を利⽤した包装材料の共同開発に合意。3 社共同体制で原料選定、TEMPO 酸化 CNF の製造及び品質向上、パッケージング化と包装材料向けでの応⽤など、基礎研究から性能評価まで⼀貫した研究開発を⾏い、2010 年 6 月には TEMPO 酸化 CNF を用いた包装材料の共同開発について、3社連名でリリースを発表した。 日本製紙では上記共同開発に加え 2013 年には研究開発本部内に CNF 事業推進室を新設、
CNF 事業の早期事業化を⽬指し量産化技術の確⽴と⽤途開発を進めてきた。その後、2016 年 10⽉には製造技術・研究開発を⾏うCNF研究所とCNFを始めとする新素材の拡販を推進すべく新素材販売推進室へと改組した。さらに2017年6月29日付でCNFや無機物と⽊材パルプの複合材料な
636
ど、同社が重点的に技術開発している新素材の市場開発と販売拡大の迅速化を図る組織として新素材営業本部を⽴ち上げた。 CNF の生産拠点は別表の通り。2013 年に実証⽣産設備を導⼊し様々な製造プロセスの開発・実
験を⾏う岩国⼯場(⽣産能⼒ 30t/年)、TEMPO酸化法のプラントである石巻工場(同500t/年)、CNF と樹脂の複合化プロセスの実証実験設備を設置した富士工場(同 10t/年)、⾷品や化粧品、⼯業材料などへの添加剤(増粘剤)をターゲットとしたCM(カルボキシメチル)化CNFを生産する江津工場(同 30t/年)の 4 拠点で、このうち⽯巻⼯場と江津⼯場が量産プラント、岩国⼯場と富士工場は実証実験・パイロットプラントである。
先に述べたように、日本製紙では NEDO のプロジェクトに参加し CNF の研究開発を開始した当初から TEMPO 酸化法プロセスを採⽤してきたが、平⾏して他のプロセスについての研究も進めている。CNFは⽤途や使われ⽅によって顧客から要求される機能・性能などが異なり、また、原料パルプを解繊するプロセスによっても取り出されるCNFの特性に違いがある。同社ではCNFへの参入を決めた当初から幅広い用途・市場での展開を想定し、多方面の分野の顧客にサンプルを供給して顧客ニーズを吸い上げてきた。その結果、多様な分野で CNF を展開するには、一つのプロセスだけにとどまらず用途に合わせて最低化したプロセスへの対応が必要であると判断し、各拠点へのプロセス及び設備を導入している。 具体的には、2017年4⽉稼働の⽯巻の量産プラントはTEMPO酸化法での⽣産を⾏っているが、
2017年6⽉に⽴ち上げる富⼠⼯場の実証プラントは樹脂との複合化に最適化し、疎⽔化したパルプを樹脂との混練と同時にナノ解繊することにより安価で高品質な CNF 強化樹脂を創り出すプロセス(所謂京都プロセス)を採用している。また、2013 年稼働の岩国⼯場のパイロットプラントでは、様々な製造プロセスの検証を⾏うことができる設備となっている。 日本製紙では CNF について「Cellenpia(セレンピア)」のブランド名で展開、先述のように現在は
637
TEMPO酸化法によるCNFと、CM化CNFの2種類を量産している。 CNF はパルプなどの植物繊維をナノレベルまで解繊したものであり、解繊には複数の手法がある。
TEMPO酸化法はパルプにTEMPO触媒を作用させて繊維をほぐれやすくした後で機械的に解繊するもので、繊維幅3〜4nmの完全ナノ分散した繊維が得られる。可視光波⻑(400〜700nm)よりも細かく均一に分散しているため光の散乱が発生せず、無色透明であることに加え、1 本の繊維はアラミド繊維なみの弾性率(約 138GPa)、石英ガラス並の寸法安定性(2.7ppm/K)、⾼い結晶化度(70〜90%)という物性を持ち、水中で3次元網目構造を形成し、チキソ性、分散安定性、乳化安定性などの特徴的なレオロジー挙動を示す。また、CNF 同士は強固に水素結合するため、単体で成膜すれば高い酸素バリア性を有するフィルムができる。
こうした特徴により、少量をゴムや樹脂に添加することで強度アップが実現する他、インクや塗料などの
液体への添加で粘度の調整が可能となるため、液垂れ防⽌性を付与できるほか、⾼粘度でありながらスプレーで噴射するなど新しい使い方の提案にもつながる。 水中で解繊した CNF を⽔分散液(スラリー)状で供給する。これまでのサンプル供給では濃度 1%
程度のものが基本であったが、⾼濃度化も対応可能としている。ただ、スラリー状で供給する場合は 90数%以上が水分となるため、添加対象物の水分調整が必要となり、場合によっては添加後にユーザーサイドで⽔を抜く処理などが必要となるケースもある。また、輸送の際にも⼤部分が⽔であることから、コストや環境負荷低減という面でも課題があった。ユーザーの中には従来は粉末状増粘剤を採用していたところも多く、CNFに置き換える際に既存の設備が活用できる粉末状での供給を求める声が上がっていた。 しかし、スラリー状の CNF を完全に乾燥させた場合、⽔中分散していた分⼦が強⼒に⽔素結合して
凝固し、再び水中に入れても元に戻らないため再分散ができない。この問題を解決すべく、同社では水分散した CNF を固形化する技術を確⽴。⽔分量 10%程度、CNF含有量 90%程度の紛体化を実現し、CM化CNF として量産技術を確⽴した。 もともと同社では、セルロース誘導体など⽊材成分を利⽤した機能性ケミカル製品を展開する中で⾷
品添加物として使用されるカルボキシルメチルセルロース(CMC)の製造・販売を⾏っており、この CMC
638
製造技術を利⽤し、化学処理した⽊材パルプからCM化CNFを取り出す製法を確⽴した。CM化CNFは繊維幅が数nm〜数⼗nmとTEMPO酸化CNFよりもやや大きい「ミクロフィブリルセルロース」である。温度変化による粘度変化が⼩さく、増粘剤として使⽤してもネバツキが無い、チキソ性を有するといった特⻑を持つ。
⽔分量を 10%以下まで低下させてパウダー状としたことで、添加の際の⽔分量を気にすることなく、取
扱いを用意にした。同社ではCM化CNFについて食品や化粧品といった用途を想定しており、2017年9月より江津工場にて量産を開始する予定である。 TEMPO酸化CNF、CM化CNF ともに親⽔性材料であり、⽔系の材料への分散性は⾼いが、油や
アルコールなど⾮⽔系材料に配合した場合、CNF 同士が凝集してしまい複合化が難しくなるという問題がある。日本製紙ではこの問題に対応すべく疎水化 CNF を開発中であるが、用途やユーザーニーズによって疎水化の処方も変わってくることから、プロセスを含めて顧客の要望に最適化した疎水化 CNF を実現すべく研究開発を進めている。 CNFではPPやPE、PAなどの熱可塑性樹脂と複合化する樹脂強化用途も注目されているが、熱可
塑性樹脂とCNFとを複合化する場合、従来のTEMPO酸化プロセスではパルプからCNFを取り出す工程と、取り出した CNF と熱可塑性樹脂とを複合化する工程とに分かれるため、高コストとなってしまう。また、⽔性材料であるTEMPO酸化CNFを⾮⽔系の樹脂と複合化するには疎⽔化処理も必要となる。 日本製紙では、京都大学を拠点として実施されている NEDO プロジェクト「非可食性植物由来化学
製造プロセス技術開発 高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術開発」に参画し CNF 強化樹脂の開発に取り組んできた。同プロセスの実証実験設備を富士工場内に導入し、2017年6月より試験生産とサンプル供給を開始している。 個々では今後、ニーズに最適化した配合⽐率やCNFによる強化が最も効率的に実現する樹脂の選
定などを進め、⾃動⾞部品メーカー、樹脂メーカー、モルダーといったユーザーサイドとの情報交換を進めながら、CNF強化樹脂の実用化に向けた研究開発を進めていく。
639
日本製紙では CNF の研究開発を開始してからこれまで、500 社を超える企業にサンプルを供給してきた。平⾏して、⾃社及びグループ内で CNF を使用した製品開発に取り組んでおり、2015年10月には世界初となる CNF の実用化商品として、グループ会社である日本製紙クレシア㈱の大人用紙おむつ「肌ケア アクティ」シリーズが発売されている。 同製品は、TEMPO酸化CNFの表⾯に抗菌・消臭効果を持つ⾦属イオンや⾦属ナノ粒⼦を⾼密度
に付着させ、⼤量に保有させたままシート化させてもので、使⽤済おむつの臭いを低減し介護者の負担を減らしたものである。2016年4月には「肌ケア アクティ」シリーズに加え、軽失禁⽤ケア商品(尿取りパッド)「ポイズ」にも採用されている。当初、これら製品に使用する TEMPO 酸化 CNF は岩国のパイロットプラントで製造されていたが、2017 年 4⽉以降は量産設備が稼働した⽯巻⼯場での⽣産となっている。 大王製紙 大王製紙では愛媛大学の紙産業イノベーションセンター、産業技術総合研究所中国センター(セル
ロース材料グループ)と連携し、2012 年頃よりセルロースナノファイバー(CNF)の研究開発を開始、CNF製造における独自技術を開発した。2013年12月よりCNFのサンプル供給を開始、同業他社に比べ多少後発での展開となったものの、現在 200 社を超える企業にサンプルを供給しており、加えて国内各地の展示会やセミナーに参加しながら積極的なサンプルワーク及び営業活動を展開している。 もともと同社ではバイオマス関連をテーマとした新事業を模索する中で、バイオマスエネルギーなどの開
発が進んでいた北⽶、北欧などを中⼼に情報収集を進め、CNF に着⽬。⽊材チップから紙の原料となるパルプを製造、つまり⽊質からセルロースを分離するという製造技術が紙パルプメーカーである同社の保有技術とマッチしたこと、植物バイオマスから取り出した天然由来の繊維であるため低炭素社会の実現に貢献できること、ナノレベルまで解繊することで既存の紙やパルプには無い特異な性質が発現し、多種多様な⽤途へと展開することで将来性が期待できる材料であることから参⼊に踏み切った。 2016年4月には三島工場内に固形分換算で最大100t/年規模のパイロットプラントが稼働した。
同プラントは国⽴研究開発法⼈ 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「戦略的省エネルギー技術⾰新プログラム」の研究開発助成⾦⽀援を受けて建設されたものである。これにより、それまでのラボベースでの試作から、実証ベースでの製造コストの大幅削減を目指した製造技術の研究開発を進めている。 同社のパイロットプラントは、グレードの異なる解繊⼯程を組合わせた CNF 製造プロセスを採用してお
り、CNF製造にかかるエネルギーを従来の10%程度まで削減が可能である。具体的なプロセスは、①原料パルプを前処理⇒②粗解繊でMFC(ミクロフィブリルセルロース)化⇒③微解繊でCNF化という、前処理+2段機械処理によるもので、最終的に繊維幅20〜60nmのCNFを取り出す。大王製紙のプロセスで得られる CNF はやや粗いとも言えるが、同社では微細化すればするほど手間やエネルギーがかかりコストアップにつながること、また、シングルナノファイバーは透明でありインクや化粧品など液体の粘度調整
640
に適するといった特性もあるが、例えば特に透明性が必要とされない⽤途や、樹脂などとの複合化が求められる⽤途では必ずしもシングルナノファイバーレベルまでの微細化は必要とされず、むしろ省エネルギー、低コスト対応に対する要望が多いことなどから、現状の繊維幅で特に問題は無いと考えている。
パイロットプラント稼働により、研究開発やサンプル生産のコストダウンが実現、ユーザーにとっても従来よりもサンプルの調達がしやすくなるなど、⽤途開発・市場開拓に弾みがついた。⼤王製紙では 2017 年度内に後述する粉体 CNF の設備を設置し、更に、サンプルワークやより使いやすい製品開発などへの取組みを進めていく。
大王製紙の CNF の特徴の⼀つが、原料に複数の種類のパルプを⽤いることで多様な特性を持つ
CNFを生産・供給できるという点にある。競合メーカーの多くが、1〜2種類のパルプを原料としているのに対し、同社では①化学パルプ(広葉樹漂⽩品)、②化学パルプ(針葉樹漂⽩品)、③機械パルプ(漂白品)、④古紙パルプ(雑誌古紙パルプ・漂白品)と、3 種4品から選択でき、それぞれの原料に由来する様々な性能の付与が可能となっている。
具体的には、上記①②の化学パルプ由来品は疎水性のリグニン含有分が少ないため保水性が高く、
親⽔性材料との相性が良い。③の機械パルプ由来品は物理的な⼒で⽊材を破砕したパルプを原料とするためリグニン含有量が多く、脱⽔性に優れ加⼯効率が良いこと、疎⽔性材料との混練性向上といった
641
特⻑がある。④の古紙パルプ由来品は CNF 中に微細化された無機粒⼦が含まれており樹脂との複合化では安価に補強効果の発現が期待される。特に③機械パルプ由来品はリグニンを多く含み、疎水性材料との優れた混合性が期待できる。 CNF は、保水剤、増粘剤、樹脂・繊維の補強剤、エアフィルター部材、LiB 部材、バインダー、建材・
内装材の多機能化、化粧品・⾷品・医薬品関連など様々な⽤途が期待されるが、原料の種類が限定されている場合、付与できる性能にも限界があり、展開できる用途の幅も狭まってしまう。同社では特性の異なる複数の原料をラインナップすることで、⽤途によって要求される特性に合わせたCNFをユーザーが選ぶことができ、市場の中でのCNFの「出口」すなわち用途が広がる。この「複数のタイプから選択が可能」という点が、CNF事業における大王製紙の差別化のポイントと言える。 CNFは解繊プロセスで⽔を多く含み、固形分濃度2%程度のスラリーとして供給される。塗料やインク、
化粧品など⽔性材料と複合化する場合は特に問題にならないが、熱可塑性樹脂の補強剤として使⽤する場合などでは脱水プロセスが必要となり、樹脂の変色などが生じるリスクがある。また、CNF は親水性材料であり⽯油由来の樹脂とは混ざりにくい。CNF を脱水しパウダー状で供給すれば、ユーザーサイドでの脱⽔プロセスが不要になることに加え親油性の物質とも混合しやすくなることから、サンプルワークの中でパウダー状CNFを求める声が大きくなった。 大王製紙ではこれに応え、解繊後に乾燥処理を⾏うことで CNF をスラリーからパウダーにする技術を
開発した。CNF はそのまま、脱水乾燥すると凝集してしまうため分散剤などを使用しパウダー状としている。紙と同様で、空気中の水分との関係で数%~10%程度の⽔分を含む。同社ではこれを熱可塑性樹脂や合成ゴムなどの親油性樹脂との複合化により、⾃動⾞部材、タイヤ強化材、建材といった⽤途での需要に期待している。 大王製紙では三島工場の現在の CNF パイロット設備と併設してパウダー状 CNF 設備(乾燥設備)
のパイロット設置を計画しており、2017年内にはサンプル供給を開始したい考えである。 先にも述べたとおりCNFは親⽔性材料であり、油やアルコールなど⾮⽔系の材料と混ぜるとCNF表面
の親⽔基同⼠が⽔素結合し凝集してしまい、均⼀に分散できない。業界内には原料パルプを疎⽔化してから解繊した疎水化CNFで対応するという動きもあるが、大王製紙では現時点では疎水化CNFはラインナップしておらず、幅広い用途展開が期待できる石油由来樹脂との複合化についてはパウダー化によって親水性のままでも対応可能であるとしている。
⼤王製紙では応⽤及び⽤途開発にも⼒を⼊れており、「どのパルプが加⼯特性に優れているか」、「ど
の原料がどの⽤途に適合しているか」、「どの程度の温度で処理した⽅がいいか」など、基礎的な研究をはじめ、アプリケーション開発にも取り組みを進めている。 2016年6月には東京本社内にCNF共同研究先、販路開拓のための新組織「CNF事業化プロジ
ェクト」を⽴上げ、実際の顧客ニーズの吸い上げや製品開発、⽤途開発など市場対応⼒を強化した。以前から愛媛県にある技術開発部(現:新素材研究開発室)で CNF のサンプル供給や供給先の顧客との情報交換などを⾏っていたが、新組織の⽴ち上げによりニーズに対するより早く、よりきめ細かい対応が
642
可能となった。 現在開発中のアプリケーションとしては、CNF成形体、人工骨補強剤、ガスバリア包材、トイレ用ペー
パークリーナーなどがあり、このうちペーパークリーナーは⾃社で量産化、⾃社ブランド「エリエール」の商品「エリエールキレキラ!⽬に⾒えない汚れまで徹底トイレおそうじシートナノ EX」として2017年4月1日より発売を開始した。 同製品はトイレ用ペーパークリーナーに自社のCNFを配合したもので、CNFは三島工場のパイロットプ
ラントで生産されたものを使用している。紙の繊維にCNFの複合化と薬品処⽅で表⾯強度が2倍にアップし、⼒を⼊れて擦っても破れにくい上、ナノサイズの繊維が薬品効果と合わせ、菌や⽪脂汚れなどこれまで取りきれなかった微細な汚れまで確実にキャッチするため雑菌繁殖を防止する効果もある。もともと自社製品としてペーパークリーナーを扱っており、原料から最終製品まで全て⾃社内での⼀貫⽣産体制を構築している。自社製品に CNF を応用することで川下市場のニーズをキャッチし、今後の用途開発につなげていく。 ガスバリア包材は、紙にCNFをコーティングしPETなどの基材フィルムと組み合わせることで一般的に使
⽤されているガスバリアフィルムを代替、化⽯資源由来のプラスチックフィルムの使⽤料を削減しハイオマス由来のバリア包装資源への転換を提案するものである。 通常、ナノセルロースを用いたガスバリアフィルムは、均一にキャスト塗工層を形成した場合、非常に優
れたガスバリア性を発揮することが知られている。しかし、分散媒体となっている水が乾燥過程で微細な気泡を形成、蒸発の際に塗工層の均一性を低下させるという課題がある。 同社では、乾燥において加熱処理と⾃然乾燥の条件を与えてテストを⾏ったところ、加熱乾燥の際に
は⽔分が⼀気に気化してしまうため、膜の均⼀性を⼤きく低下し、酸素透過度が⾼くなる結果を⽰した。⼀⽅で、⾃然乾燥の場合は、理論通りにバリア性に優れた特性を⽰したが、乾燥時間が⻑く、⽣産効率に⽋けるというデメリットがあった。この結果をベースに、同社ではナノセルロース層の上に紙を設け、加熱乾燥させた結果、自然乾燥水準以上のバリア性能を持つナノセルロース積層ガスバリア紙を実現した。 加えて、このプロセスを応用し、ナノセルロース積層シートも開発している。製造プロセスは①フィルム基
材にナノセルロースを塗工し、②上質紙を貼り合わせ、③その後加熱乾燥する手順となっている。これにより、ガスバリア性能を持ちながら、紙の表⾯に印刷も可能にしていることが特⻑である。現段階では透明性や耐湿性、コストの面においての課題が残っているが、いずれも食品包材用途で活用できる可能性は⾼いと⾒ており、継続して開発を進めていく計画である。そのほか、セルロースの可⾷性と安全性を活かし、食品や化粧品向け増粘剤での用途開発も視野にいれているようだ。 現時点では技術的・外部環境的(規制など)なハードルが⾼いが、将来的には電気・電⼦、医療
などといった⾼付加価値を⾒出せる分野向けに⽤途開発を進めて⾏きたい考えである。
643
2016年10月にはCNFを高配合した成形品を開発した。CNF とパルプ繊維を複合化したもので、
CNF の配合率は50〜95%。軽量で⾼強度という CNFの特性を活かした⾼性能材料である。汎⽤プラスチックに⽐べて引張強度に優れるほか、CNF 自体に 200℃程度の耐熱性があるため耐熱性も⾼い⼀⽅で、熱弾性率が⾼く熱成形性が高い。 ⼀般的にプラスチックの強度や耐熱性と熱成形性はトレードオフであるが、CNF成形体を使用すること
で、これまでプラスチック材料が使⽤できなかった⾼強度⽤途や耐熱性を必要とするユーザーでの採⽤が期待される。 CNF成形体のサンプルは2016年10月19⽇〜21日まで東京ビッグサイトで開催された「モノづく
りマッチング Japan2016」機能性材料・加⼯技術展に展⽰され、その後サンプルワークが進められている。⼤王製紙では⾃動⾞部材、建材、家電筐体、電⼦基板、スポーツ・レジャー⽤品など、幅広い⽤途での展開に期待している。 CNF を利⽤した⼈⼯⾻補填材は、⼤王製紙と株式会社福⼭医科(以下「福⼭医科」)、学校法
⼈千葉⼯業⼤学(以下「千葉⼯業⼤学」)とが共同研究により開発された。⼈⼯⾻の補填の原料として利⽤されているリン酸カルシウム等に CNF をバインダーとして混合することでリン酸カルシウムの乾燥、成形が容易になる他、これを焼結することでリン酸カルシウム系⼈⼯⾻補填材が多孔質化され、従来の多孔質化のための⼿法であった発泡法よりも開気孔率が⾼まり、孔内に細胞や⾎液が⼊り込むことで⾃
■酸素バリア
構造 製造方法 酸素透過度(ml/㎡/day/atm)
紙/CNF/PET積層シート(加熱乾燥)
塗工⇒積層⇒加熱乾燥⇒完成 N.D.
CNF塗工PET(自然乾燥)
塗工⇒自然乾燥⇒完成 3.7
CNF塗工PET(加熱乾燥)
塗工⇒加熱乾燥⇒完成 64.8
PET単体 - 71.1
■水蒸気バリア
酸素(ml/㎡/day/atm)
水蒸気(g/㎡/day/atm)
紙/CNF・マイカ/セロファン積層シート(加熱乾燥)
塗工⇒積層⇒加熱乾燥⇒完成 N.D. 139
紙/CNF/セロファン積層シート(加熱乾燥)
塗工⇒積層⇒加熱乾燥⇒完成 N.D. 2,633
[大王製紙 資料より]
ガス透過度
CNFのバリア性能
構造 製造方法
644
家骨化しやすくなるといった効果が期待できる。また、孔内に薬剤を充填する治療などにも応⽤できると考えられる。 引き続き 3 者共同による人工骨補填材の開発を進めていくとともに、混練・乾燥・焼結による多孔質
化の効果はリン酸カルシウム以外のセラミック材料でも発現することから、⼤王製紙では軽量、断熱、吸⾳、吸着、濾過分離膜等の機能を持つ多孔質セラミック⽤バインダーとしてCNFの用途展開を進めていく方針である。
645
北越紀州製紙 北越紀州製紙がセルロースナノファイバー(CNF)事業に参入したのは 2009 年で、東京⼤学の磯
⾙明教授と共同で研究開発を開始した。当時、同社では紙パルプメーカーとして⻑年に亘りセルロースに関する研究開発を推進していたが、紙関連市場が成熟し既存の事業や製品需要が伸び悩む中で新たな展開を模索。その⼀環として新しいセルロース材料へとアンテナを拡⼤、CNFに注目した。CNFの解繊方法には複数のプロセスがあるが、同社では以前からセルロース関連の研究開発の中で東大・磯貝教授とつながりがあったこと、CNFの中で最も微細なサイズに解繊できる技術がTEMPO酸化法であったことなどから、TEMPO酸化法によるCNFを主体とした研究開発を進めた。 CNF事業に参入するメーカーの中には、CNFそのものを製品として販売するケースもあるが、同社では
基本的にCNFの⽤途開発を中⼼に展開しており、ガラス繊維不織布にCNFを複合化させた高機能エアフィルターや、水に分散した状態の CNF をほぼそのままの状態で取り出し断熱材や吸着材として使用できる超低密度多孔質体など、⼀歩川下に進んだ市場をターゲットとした開発を推進。具体的には、ガラス繊維との複合化や多孔質体の取り出しまで⾃社で⾏い、そこからユーザーに提案する。解繊したCNFそのものの外販は、現時点では特に考えていないようだ。 北越紀州製紙では CNF を始めとする新機能材料の開発及び応⽤展開をより強化するため、2017
年4月1⽇付で技術開発本部内に新組織「新機能材料開発室」を設置。これまで技術開発本部主体でサンプルワークなどを⾏っていたのを、実際の顧客と⽇々接触する営業部とも連携してユーザーニーズの掘り起しや開発シーズの収集などを推進する体制を整えた。これにより、開発中の製品の提案だけでなく、不織布や特殊紙など同社の既存の製品でも CNF を複合化することによる新たな機能・性能の付与や、ユーザーの要望を CNF を使用することで実現するという展開も可能になる。同社では今後、新機能材料開発室を中⼼に組織横断的に CNF の開発やユーザー提案を進めていくことで早期の事業化を目指していく考えである。
先にも述べたように、北越紀州製紙ではCNFの⽤途開発を進める中でエアフィルターへの応⽤を先⾏してきた。同社ではもともと特殊紙事業の中でガラス繊維不織布による空気清浄⽤濾紙(エアフィルター)をラインナップ。半導体や液晶などの製造設備(クリーンルーム)内を超清浄空気にしたり、原⼦⼒の安全利⽤のため⼤気中への放射能汚染物質⾶散防⽌の他、医薬・製薬・⾷品⼯場における空気清浄のために使用されるHEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルター⽤の⻑⾼性能濾紙では世界3大メーカーとしてのポジションにある。 従来、エアフィルターは微細なガラス繊維で不織布を形成し、繊維の隙間を微細化することで微粒⼦
を捕集する。繊維径や形成される繊維の隙間によって捕集できる微粒⼦のサイズは異なるが、JIS 規格(JIS Z 8122)では HEPA フィルターについては「定格⾵量で粒径が 0.3μm の粒⼦に対して99.97%以上」、もう⼀段粒⼦捕集効率を⾼めた UPLA フィルター(Ultra Low Penetration Air Filter)については「定格⾵量で粒径が 0.15 µm の粒⼦に対して 99.9995%以上」と規定されている。
646
ただ、従来のエアフィルターではサブミクロンサイズの粒⼦の捕集はできても、ウイルスや⼈体に有害なナノサイズの超微粒⼦への対応には課題がある。同社ではガラス繊維と CNF を複合化し、ガラス繊維の隙間にCNFを蜘蛛の巣のように張り巡らすことに成功した。ガラス繊維濾紙をCNFの分散液に含浸し、特殊な方法で乾燥させると、CNFがネットワークを形成しナノサイズの網目が形成される。CNFの使⽤量はガラス繊維に対して 0.1%程度で⼗分であり、CNF で形成されたネットワークが効率良く微粒⼦を捕集できる。従来のエアフィルターでは対応できなかったウイルス、超微粒⼦などの捕集も期待され、感染症やパンデミックへの対策が求められる病院や放射性物質対策が求められる用途に適用できる。
CNF を使用したエアフィルターは当初、ハガキサイズ以下の大きさから試作を始め、現在ではA3程度
のサイズまで作れるようになった。サンプルについては A4 サイズで供給しており、フィルターユニットに取り付けての実証実験なども進んでいる。同社では既存のガラス繊維エアフィルターのユーザーを中心に、新しい⽤途を含めた幅広い顧客層に提案してサンプルワークを⾏っており、従来にない性能のエアフィルターとして実⽤化に向けた改良・開発に取り組んでいる。 一般的にTEMPO酸化CNFは3〜4nm程度のサイズのCNFが液体に均一分散された状態であ
るが、これを乾燥させると、その過程でCNFが凝集し固まってフィルム状になる。⼀度凝集したCNFは再び液体に漬けても再解繊されず、「ナノサイズの繊維」ならではの性能が発揮されない。 北越紀州製紙では液体に均⼀分散したCNFを、分散状態をそのまま維持して液体から取り出す、つ
まり凝集を発生させずに水分だけを除去する技術を開発。高比表面積のスポンジ状繊維質多孔体(超低密度多孔質体)「エアロゲル」として、ユーザーへの提案を開始している。「エアロゲル」は 3 次元的なネットワーク構造を有し、ナノサイズの繊維がスポンジ形状を形成、高断熱性に加え、吸着体や触媒などの担持体、細胞培養基材、ガス貯蔵体といった用途が期待される。
647
先述のエアフィルターへの複合化が、ある程度出⼝となる⽤途を想定して開発されたのに対し、「エアロ
ゲル」は従来にない製品を形にしてユーザーに提案する中で新しい⽤途や使い⽅を模索するという、シーズ先⾏で開発された。同社は⻑年にわたる特殊紙事業の展開の中で、素材、機能、⾵合い、装飾など、様々な要素を探りながら紙の新たな可能性を広げる製品を創り出してきた。特殊紙の生産拠点である⻑岡⼯場では常時3,000アイテム程度の特殊紙を⽣産しており、新製品開発の技術的ノウハウと特殊製品の出口(用途)の実績を蓄積してきた。「エアロゲル」については、CNFを使用した特殊紙の新しい形と位置付けることもできよう。 現時点では小さいサイズのサンプルで顧客に提案している段階であるが、同社では2017年度中には
サンプルワークまで持って⾏きたい考えである。 CNF以外では、カナダの子会社によるセルロースナノクリスタル(CNC)の開発が進んでいる。CNC と
はセルロースを硫酸処理することで得られる棒状のセルロースナノ素材で、セルロース中の微⼩な結晶(クリスタル)部分を取り出していることから「ナノクリスタル」と呼ばれる。サイズは幅 5〜15nm×⻑さ100〜300nm程度とCNFよりも⻑さが短い。 パルプ繊維を化学処理することで繊維をその結晶まで細分化することにより製造される新素材であり、
液体分散状態が主流であるCNFとは異なり、乾燥状態で供給しやすく、化学薬品や塗料などに混ぜれば流動性の調整や摩擦係数を減らす効果が得られるほか、包装材料のガスバリア性向上といった性能も付与できる。 同社の連結子会社であるAlberta-Pacific Forest Industries Inc.(以下、Al-Pac)はカナダで
パルプ製造・販売事業を展開しており、2010 年よりカナダ・アルバータ州の研究機関である Innotech
648
Alberta と CNC に関する共同研究を進めている。2013 年にはカナダ・アルバータ州の Innotech Alberta内に400㎏/⽉の能⼒を有するCNCパイロットプラントが稼働。2016年11月にAl-Pacと、親会社である北越紀州製紙とが、CNCの商⽤材料開発に向けてアルバータ州政府との協⼒関係をさらに発展させることについて合意した。 CNFの多くが液体への分散体であるのに対し、CNCは乾燥状態での供給が容易であり、CNFとは違
った方向からのナノセルロース関連事業の展開が期待できる。北越紀州製紙では新機能材料開発室において、ナノセルロース関連の事業化に向けた用途開発やユーザーへの提案を進めていく考えである。
第一工業製薬 第一工業製薬がナノセルロース研究の取り組みを開始したのは 2005 年、その後 CNF研究の権威
者である東京大学の磯貝明教授らの発明である TEMPO酸化法による CNF に着目し研究開発を開始した。食品や医薬品の添加剤(増粘剤)である CMC(カルボキシメチルセルロースナトリウム)のトップメーカーであり、⻑年にわたるセルロース素材事業で蓄積してきた技術を応⽤した新材料開発を進める中で CNF に⾏きついたという経緯がある。以来、インクや化粧品など⼀般産業分野で粘度調整や分散安定化のための添加剤を中心に用途開発を進めている。 第一工業製薬では自社で扱うTEMPO酸化CNFについて「レオクリスタ」のブランド名で展開している。
「レオクリスタ」は繊維径3〜4nm程度の均⼀なCNFを液体に分散させたゲル状の製品で、CNF濃度は 2%。現在は工業用途向けに汎用グレード(I-2SX)、極性溶剤配合安定性向上品(I-2AX)、希釈分散性向上品(I-2AE)の 3 種をラインナップしており、外原規に対応した化粧品グレード(C-2SP)もある。 いずれもキタンサンガムや CMC、メチルセルロースなど⼀般的な天然由来増粘剤に⽐べ低添加領域
でも⾼い構造粘性を発現することに加え、⾼いチキソトロピー(チキソ性)を持ち、せん断⼒が加わると⼩さい⼒であっても⾼粘度のゲル状から流動性の⾼い液体のような性質に代わる特性がある。そのため、ゲル状でありながらスプレー化が可能であり、例えばボールペンインクでは漏れがなく且つ早書きでも擦れることなく筆記できる他、化粧品関連ではベタ付かず伸ばしやすいゲルやクリームといった使い方にも対応できる。
品番 特徴 CNF固形分(%)
レオクリスタ I-2SX 汎用グレード 2
レオクリスタ I-2AX 極性溶剤配合安定性向上品 2
レオクリスタ I-2AE 希釈分散性向上品 2
レオクリスタ C-2SP 化粧品グレード 2
[第一工業製薬 資料より]
レオクリスタの品番と特徴
649
これらの特性から、第⼀⼯業製薬では発売当初から化粧品や塗料・インク分野向けの増粘剤として
「レオクリスタ」を提案しサンプルワークを展開。2015 年にはインク⽤増粘剤⽤途での実⽤化に成功し、同年3⽉に筆記具メーカーの三菱鉛筆のゲルインクボールペン「ユニボール シグノ UMN-307」に採用され、北⽶地域での先⾏発売の後、同年9月には欧州地域でも販売されている。 化粧品⽤途については、肌に直接触れる製品であるため新規材料の採⽤には慎重になるユーザーも
少なくない。⼀⽅で「レオクリスタ」と同じセルロース系材料が化粧品原料として以前から多くの採⽤実績を重ねていることも事実である。 これまでのサンプルワークにより、「レオクリスタ」は従来の増粘剤と比べて保湿性・保水性に優れるほか、
増粘性は⾼いが曳⽷性を⽰さずべたつきのない使⽤感が得られる、粘度とチキソ性の両⽴によりスプレーした液は垂れずに付着性が向上するなどの機能メリットが認知されるようになり複数のユーザーで採用に向けた検討が進んでいる。
また、「レオクリスタ」は透明であり増粘剤として使用しても対象となる液体の色や透明性を損なわない
こと、乳化安定性が⾼く「レオクリスタ」で増粘した⽔にオリーブ油や流動パラフィンなど油性のものを混ぜて乳化させた液体は時間がたっても再分離することが無いこと、ある程度の流動性(粘度 150〜300mPa・s 程度)を維持した状態で酸化チタンや⾦箔のような無機物の粉体などを混ぜた際に⻑時間にわたり沈降防⽌効果が確認されており、こうした点もユーザーから評価されている。 ただ、TEMPO酸化CNFである「レオクリスタ」は表面に水酸基とカルボキシ基が多数存在する親水性
の⾼い材料であるため⽔中で解繊され、⽔分散体として製造される。⽔中では表⾯の親⽔性の官能基により水分子と高い親和性を示し、また水素結合を介して CNF が相互作用することで、前述の機能を
650
発現するが、油や有機溶剤などと混ぜると今度は⽔素結合によってCNFが凝集してしまい、均一に分散することができない。そのため、これまで「レオクリスタ」は水性のインク・化粧水などへの添加に限られていた。 第一工業製薬では、今後TEMPO酸化CNFのさらなる用途及び需要の拡大を狙うには油性インク
やアルコールのような⾮⽔性材料であっても⽔性材料と同様に均⼀分散し性能を発揮できるようにすることが必要と判断。有機溶剤となじみやすくした疎水変性タイプの開発に着手し、有機溶剤中で CNF 表面の水酸基による水素結合を抑制し CNF を有機溶剤となじみやすくした製品開発を推進し、開発品番「CNF N-03」「CNF N-04」として製品化に向けた研究開発に取り組んでいる。
開発品番「CNF N-03」は有機溶剤の増粘や微粒⼦の分散安定化などの⽤途を想定したもので、メ
タノール、MEK、酢酸エチル、トルエンなどの有機溶剤に混ぜると均一に分散し透明な分散液となる。一方、水にはなじまないため水に分散すると白濁・凝集が生じる。 また、疎水変性した CNF が有機溶剤中に分散した際、CNF 同士が緩やかに架橋しあうため、有機
溶剤を⾼粘度化することが可能となるほか、⽔性の⽔分散タイプと同様にチキソ性や微粒⼦の分散安定化といった効果が付与される。 「CNF N-03」は現時点で開発段階であり、各種インク・塗料や化粧品など幅広い⽤途での採⽤が
期待されている。
651
「CNF N-04」はアクリル系モノマーなどの溶剤系樹脂に混ぜることで樹脂への機能付与を図るもので
ある。DPHA などの透明・液状の樹脂に均⼀にナノサイズで分散するため透明性を損なわず、弾性率向上、帯電防止性付与、硬化収縮低減といった効果が得られる。 ハードコート⽤の塗剤などはアクリル系樹脂を塗液化することが多いが、樹脂は導電率が低く帯電しや
すいこと、塗膜を硬化させる際に硬化収縮が発⽣しソリや基材となるフィルム・シートの機械強度低下といった問題が生じる。ここに疎水変性した CNF を配合すれば、塗膜の硬化収縮の抑制が実現。現在、「CNF N-04」は樹脂(モノマー)メーカー、塗液メーカー、コンバーターといったユーザーへの提案が進められている。
項目 ブランク
CNF固形分(%) 0 2.5 5.0
ヘーズ値 0.77 0.79 0.98
押し込み弾性率(MPa) 6.9×103
7.5×103
7.7×103
表面固有抵抗値(Ω) 3.6×1016
1.7×1014
8.8×1013
[第一工業製薬 資料より]
CNF N-04配合
CNF N-04の添加により複合膜の膜物性を向上
652
花王 花王のセルロースナノファイバー(CNF)関連事業は、同社が環境問題への取組みを進める中で、
包装材料に使⽤するポリ乳酸(PLA)の性能を改善する添加剤としてCNFを使用したことからスタート。2005 年より新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「ナノテク・先端部材実用化研究プロジェクト」に参加し、2005 年〜2010 年にかけて東京⼤学及び⽇本製紙と共同で PLA などのバイオマスベース樹脂のフィルムとTEMPO酸化CNF との複合化研究を⾏った(ステージⅠ)。この研究は酸素透過性の低いCNFを⽤いて包装材料向けでの応用可能性を検討したものであり、食品保存用の容器包装などの⽤途向けに⾼機能包装材料として実⽤化可能性を確認した。 その後、同プロジェクトのステージⅡ(2010 年〜2012 年)では、技術アドバイザーとして凸版印刷
が参加。同社、日本製紙、凸版印刷の 3 社共同体制で原料選定、TEMPO 酸化 CNF の製造及び品質向上、パッケージング化と包装材料向けでの応⽤など、基礎研究から性能評価まで⼀貫した研究開発を⾏った。花王では2010年7月に3社によるTEMPO酸化CNF を使⽤した包装材料の共同開発をリリースしている。 現在はNEDOによるプロジェクトは終了しているが、花王ではこれまでの研究結果をベースに、CNFを
⽤いたアプリケーション開発を推進。①⾃社で使⽤する包装材料への CNF の利⽤、②他社への⽤途展開の2方向で事業化を進めている。 このうちPLAなど植物由来材料を使⽤した包装材料への性能付与では、PLAフィルムの表面にCNF
を配合した塗液をコーティングした結果、コート層の厚み 0.1〜1.0μm での酸素透過度は⾮コート品の約 1/7,000 の 0.1ml/㎡/day・atm 程度となった。塗液の材料や CNF の濃度は⾮公表であるが、既に⾃社で使⽤する包装材料として採⽤が始まっている他、サンプルとして社外に供給するケースも⼀部あるようだ。 同社は国内トップの洗剤・トイレタリーメーカーであり、化粧品、おむつなどの衛生用品、さらには油脂や
界⾯活性剤などの化学製品まで幅広く事業展開しており、これら製品の包装材料として多種多様な素材を採用している。こうした体制を活かし、PLAに限らず様々な素材を基材としてCNFによるガスバリアコーティングの開発を進めている。 パルプを解繊して生産される CNF は親⽔性が⾼く、⽔系材料には均⼀に分散するが、非水系溶液
や樹脂、ゴムなどに混ぜると凝集してしまい複合化しにくいという問題がある。CNF の用途開発を進める上では⽔系に限らず幅広い材料との複合化による⽤途拡⼤が必要となるが、同社では⽯鹸・洗剤など界面活性剤関連製品を扱う中で蓄積してきた界面制御技術を応用することで CNF 表面の疎水化を実現した。
653
具体的には、CNF表面の親水基である OH基に2種類の修飾基をグラフトし結合させる。この修飾
基は計算化学によって濡れ性と⽴体斥⼒の観点で選定、これが油などの疎⽔材料をはじくため、疎⽔性樹脂の中で CNF が凝集することなく孤⽴分散する。修飾基の種類やグラフトの際の配置に花王独⾃のノウハウがある。加えて、モルフォルジー解析を⾏うことで樹脂中の分散状態を可視化したところ、CNF が樹脂中でナノネットワークを形成していることが明らかになり、配合量が極少量であっても⾼強度、⾼靱性、低熱膨張性、高透明性等の機能を持たせることが可能となった。
TEMPO 酸化法による CNF は繊維⻑が 3〜4nm程度と極めて細かく均⼀であるため、照射した光
が散乱せず透過することからPMMAやPCなどの透明樹脂中に分散・複合化しても高い透明性が維持される。一方、従来樹脂強化のためのフィラーとして使用されてきたガラス繊維や炭素繊維は、樹脂と複合化すると透明性が損なわれるため、光の透過性が必要な光学⽤途や、中⾝の⾒える容器包材といっ
654
た用途への対応は難しい。 これらのことから、花王ではTEMPO酸化CNFについて、少量添加で性能を発揮することと⾼い透明
性を特徴としてアピールしつつサンプル供給を⾏っており、既存のフィラーの代替というよりも「CNF の特徴が活かせる用途」「CNF でなければならない⽤途」を開拓していく考えである。サンプル供給後には、ユーザーとの情報交換や CNF に対するニーズへのフィードバックなど、個々のユーザーとのつながりを密にしながら開発を進めている。 疎水化したCNFは液中に分散した形で供給されるため、まずはエポキシやPMMAなどの熱硬化型樹
脂向けに提案しているが、今後は熱可塑性樹脂への添加が可能なグレード開発も考えているようだ。 花王ではCNFの研究開発及びサンプル製造については和歌⼭研究所で⾏っている。現状ではサンプ
ルの製造もラボベース規模であり、パイロットプラントや量産設備の建設についてはサンプル供給先のユーザーサイドの製品開発動向にもよるため、現時点でははっきりしたことは決まっていない。ただ、現状の開発動向などから2020年頃にはある程度のボリュームを確保できるものと予想される。 星光PMC 星光 PMC は 2006 年より CNF の研究開発に着手、その後、2007 年には京都⼤学の⽮野浩之
教授をリーダーとする新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「大学発事業創出実用化」プロジェクトや、2010年に発⾜したNEDOプロジェクト「グリーン・サスティナブルケミカルプロセス(GSC)」に参加するなど、比較的早い時期よりCNF事業を展開している。 同社の CNF関連事業は、CNF 単体ではなく、樹脂と CNF の複合化を主⼒とし、NEDO プロジェク
トへの参加当初からCNF複合樹脂の開発を進めてきた。CNF市場には製紙メーカーも参入しており、その多くがCNFの生産・供給を柱としているが、星光PMCでは化学メーカーとしての自社の特徴や強みが活かせる展開を志向し、多くの製紙メーカーのように、パルプからCNFそのものを取り出すのではなく、パルプの改質(疎水性付与)による変性セルロースパウダー化と、それをナノ解繊した CNF を配合・分散した変性セルロース配合樹脂の製造をメインとしている。 2014 年3 月に NEDO による GSC プロジェクトが終了した後は、独⾃でマーケティングを推進。⻯ヶ
崎⼯場(茨城県⿓ヶ崎市)にパイロットプラントを導⼊し、⾃動⾞、建材、電⼦機器などの⽤途を中⼼にサンプルワークを推進。射出、押出、発泡などの各種樹脂加工への対応も含め、ユーザーと共同で各種サンプルの試作を進めてきたが、2017年に⼊り、本格採⽤が⾒込める案件が出てきたことから、パイロットプラントの⽣産能⼒を引き上げ量産体制に⼊るメドを付けた。現時点で量産⾒込みの⽤途などについて明らかにしていないが、現在の能⼒(24t/年)を 2017 年内に数倍まで引き上げる予定である。ここでは⽊材パルプの疎⽔化処理から、⼆軸押出機を使⽤し疎⽔変性パルプと解繊⽤樹脂、相溶化剤を溶融混練する中でのパルプのナノ解繊(CNF 化)と樹脂配合を経てマスターバッチ化までを一貫して⾏う。
655
星光PMCの変性CNF強化樹脂の製造プロセスを⾒ると、はじめに⽊材パルプを疎⽔変性して変性セルロースパウダーとする。この時点で変性セルロースパウダーはナノ解繊されていない。次に、変性セルロースパウダーを熱可塑性樹脂とともに二軸押出機に投入し溶融混練する。この過程で変性セルロースパウダーはナノ解繊され樹脂に分散・配合され、変性CNF強化樹脂(CNF配合のマスターバッチ)となる。一般的にCNFは親水性であり樹脂に混ざりにくいが、同社では木材パルプを疎水変性させることで樹脂への配合を可能とし、さらにナノ解繊〜樹脂への配合までを⼆軸押出機の中で⼀気に⾏うため、短いプロセスでCNF配合樹脂の製造が可能というメリットがある。
変性CNFを複合化する樹脂については様々なものを試験しているが、現時点ではPP及びPEをメイ
ンに考えているようだ。これ以外の樹脂についても研究開発は⾏っており、ユーザーからの要望が多ければ開発を進めることは可能であるが、CNFは耐熱性がさほど高くはなく、200℃程度までは対応可能であるが、それ以上の温度をかけると着⾊・炭化してしまうため、エンプラなど融点の⾼い樹脂との配合はしにくく、⽐較的低融点の汎⽤樹脂が中⼼となるものと⾒られる。 変性CNF強化樹脂(変性CNF/PP複合体)の特性は別表の通り。樹脂(PP)単体と比較して、
解繊用樹脂と混練して MB化した後に PP で希釈した変性CNF/PP複合体では、変性 CNF の配合率が増すに従い曲げ弾性率、曲げ強度、荷重たわみ温度(耐熱性)ともに⼤幅に向上する。
変性CNF配合樹脂の製造プロセス
656
こうした特性を活かせるマーケットとして星光PMCでは、ガラス繊維強化樹脂代替を挙げている。樹脂
にガラス繊維を複合化した樹脂は強度や熱特性がアップするが、ガラス繊維の⽐重が 2.5 前後と重く、軽量化ニーズとは逆⾏するという問題がある。⼀⽅、CNFの比重は1.2程度であり、PPやPEなど低比重の樹脂に混ぜてもガラス繊維強化品ほどには重くならない。近年、⾃動⾞部品などでは軽量化に対する要望が強くなっており、⾼強度と軽量化を両⽴させて材料が求められており、同社では変性CNF強化樹脂の⽤途として期待できると⾒ている。 この他、変性 CNF 強化樹脂は射出成形品の表面が自然な艶消しとなるほか、発泡加工も可能で
あり、CNFを配合することで⼀般的なものよりも発泡の泡が緻密になるなど、成形品の強度向上と共にしっとりとした質感を持たせたいというニーズにも対応している。
モリマシナリー 同社は、機械設計、電気・電⼦、熱処理、精密加⼯の 4 つのコア技術を有し、産業用精密機械の
開発・設計〜製造〜販売をオーダーメイドで⾏う精密機械メーカーである。系列に属さず、⾃社技術を基板に⾦属ロール成形機、フォーミングロール、⾃動⼯具交換装置、製薬⽤打錠機、リングダイ、⾃動⾞部品など、幅広いジャンルの機械を社内で⼀貫⽣産している。 セルロースナノファイバー(CNF)の研究開発を開始したのは 2008 年頃。本社のある岡⼭県が、県
内の⽊材資源のカスケード利⽤の推進に向け、間伐材や製材端材などの⽊質バイオマスを利⽤・活⽤した素材や製品の研究開発・事業化支援の施策として平成 16 年度(2004年度)から推進している「おかやまグリーンバイオ・プロジェクト」の一貫として木材チップからCNFを取り出す取組みを進めた際、同社が持つ機械関連の技術に着目したことによる。また、モリマシナリーでも以前から、木材チップを粉砕・解繊するための機械を扱っており、岡山県より木材チップからCNFを取り出せる解繊機の開発を持ち掛けられたのが始まりであった。 県からの要請を受けたモリマシナリーでは木材チップからCNFを取り出す機械の開発を推進。2011年
に完成させ、自社でCNFの製造を開始した。原料におかやまグリーンバイオ・プロジェクトが有効利⽤を促
変性CNF/樹脂複合体の特性
657
進している岡山県産のヒノキの木材チップを使用したものと、漂白パルプを使用したものの 2種類をラインナップし、用途やニーズに合わせて使い分けている。 モリマシナリーの CNFは「セルフィム(CellFiM)のブランド名で展開している。一般的なCNFは木材
に含まれる主要3成分(リグニン、セルロース、ヘミセルロース)のうちリグニンを0.1%程度まで少なくし、80〜90%がセルロース、残りはヘミセルロースのパルプを原料としている。一方、「セルフィム」は先述にようにセルロース原料グレードもあるが、⽊材チップ(ヒノキチップ)から直接取り出したものもある。⽊材チップ原料品はナノレベルに解繊したものにもリグニンが含まれる。CNF 市場への参入当初から「岡山県真庭地区の特産であるヒノキの有効利⽤」を⼀つの使命とし、チップから直接 CNF を解繊する方向で開発を進めてきたことが、リグノ CNFの開発につながった。 パルプを原料とした CNF は⽊材チップを細かくしたパルプを使⽤するため解繊時にかかる⼒がリグノ
CNF よりも少ないことから繊維⻑が⻑く、繊維幅が小さいなどアスペクト比が大きい傾向にある。繊維幅は30〜200nm、比表面積150g/㎡と、リグノCNFに比べサイズが小さく、着色も無いため配合する樹脂やゴムの色を気にせず使用できる。 一方、リグノ CNF の製造プロセスは、岡山県真庭で産出する製紙用のヒノキチップを、二軸スクリュー
解繊装置で粗粉砕し繊維状とし、⽔分量 95〜99%に調整した上で、自社開発の CNF製造装置で解繊処理する。リグノ CNF は繊維⻑が短く、また繊維幅は 50〜300nm程度と若⼲⼤きいため、アスペクト比が小さい傾向にある、比表面積は90㎡/g。疎水性であるため熱可塑性樹脂やゴムに混ぜやすく、補強材としての使用に適している。 ただ、リグノ CNF は茶褐⾊に着⾊されており、⽤途開発を進める中でユーザーサイドからは⾊の無いグ
レードを求める声が出された。また、CNF の用途や使い方の幅を広げるには、ユーザーの選択肢を広げることも必要であると判断。一般的なパルプを解繊した CNF もラインナップし、現在では、リグノ CNF と、パルプを原料としたCNFを2種類提案している。
658
リグノ CNF及びCNFは、固形分5%程度に調整したクリーム状のスラリーとして供給されるが、95%
が水分であるため、熱可塑性樹脂に配合しにくく、混ぜた後に熱などで水をぬく工程が必要となる。また、セルロースは親⽔性材料であり、セルロースを解繊した CNF は水には分散するが油やアルコールなどの疎⽔性材料に配合するとCNF表面のOHが水素結合をおこし凝集してしまう。 この課題を解決するため同社では、より樹脂に混ぜやすくすべく疎水化した CNF を乾燥させ粉体化し
たグレードを開発した。CNF を含水状態のまま疎水化し乾燥させるものだが、もともとリグノ CNF は疎水性のリグニンが含まれるためパルプ原料の CNF に⽐べ⾮⽔性材料と混ざりやすく、疎⽔化処理のために添加する成分を低く抑えることで価格の上昇も防げる。 CNF は乾燥し水の無い状態になると表面の親水基同士が水素結合し凝集する特性があり、脱水し
た粉体ではセルロースがナノサイズに分散しない。しかし疎⽔化し乾燥したものは数⼗〜数百μm の凝集体の状態であつたが、これを押出機やニーダーで PP、PE などの熱可塑性樹脂に混練することで再びナノレベルに分散し、樹脂に均一に配合される。
659
PEやPPなど成形性が高い樹脂に配合し、射出成形で細かい形状に成形することで、従来は折れや
破損の発⽣しやすかった端部や細部の強度をアップし、幅広い⽤途で需要が⾒込めるとしている。粉体リグノCNFは「セルフィム-P」のブランド名で2016年1月よりサンプル供給を開始、ユーザーとの共同開発なども進めている。PE、PP ともに⽇⽤品に多く使⽤される樹脂であるが、強度の問題で使⽤できない⽤途もあった。ここに「セルフィム-P」を提案することで、従来以上の⽤途拡⼤が期待できると同社では⾒ている。 「セルフィム」の具体的な⽤途開発例としては、岡⼭にあるゴム製品メーカーである丸五ゴム⼯業㈱と、
その関連会社で安全靴などの製造を⾏う㈱丸五が共同で試作した林⽤特殊安全靴やゴム製⼿袋がある。⼭間部では切株や筍などが靴底を破るケースも多く、作業者の安全確保が課題となっていた。作業靴の底部に使用するゴムに「セルフィム」を配合することで、踏み抜きによる破損の無い安全性の高い作業靴が実現する。同製品は2016年1月に東京ビッグサイトで開催されたnano tech 2016(国際ナノテクノロジー総合展・技術会議)に、モリマシナリー、丸五、丸五ゴムの3社により共同出展された。 モリマシナリーでは「セルフィム」について、木材チップやパルプを専用の機械を通すだけでナノサイズまで
解繊されるシンプルなプロセスで生産されており、低いコストで生産できること、製造にかかる環境負荷が低いこと、触媒などの薬品を使⽤しないことなどを強みとしており、特にコスト競争⼒はCNFの普及には重要なポイントであり、市場における「セルフィム」の強みと言える。 基本的に同社は機械メーカーであるが、今回の取り組みではマテリアルビジネスを展開しようとしており
それにはまず「セルフィム」を市場に普及させることが至上命題である。、商品化が実現するまでは自社で解繊したリグノCNF、CNFの提案とサンプルワークに⼒を⼊れていく。 「セルフィム」の⽣産拠点は美作⼯場(岡⼭県美作市)で、ここにチップを予備解繊〜ナノ解繊〜脱
⽔まで⾏う装置2台を保有している。1台当たりの⽣産能⼒は8時間稼働のケースで20t/年(固形分換算)程度と推計される。
660
旭化成 旭化成では 1990 年代後半からセルロースナノファイバー(CNF)の研究開発を開始した。もともと
同社では⾷品及び⾷品添加物の分野で、パルプを原料としてセルロース質の結晶領域を取り出し精製した結晶セルロース及び結晶セルロース剤である CEOLUS®(セオラス®)を 1970 年代より展開していた。セオラス®の分散性や粘度といった性能向上を⽬指す中で、ミクロンサイズであったセルロース質のさらなる微細化に取組み、サブミクロンからナノオーダーの繊維を取り出すことに成功したのが、同社のCNF事業のきっかけである。 当初同社ではユーザーに対し、当時開発した CNF を⽔分散体(スラリー)として提案、塗料、建材、
インクなどの用途を想定したサンプルワークを進めていた。しかし、当時は同社だけでなくユーザーサイドでもナノサイズの材料に馴染みがなく、⽤途や使い⽅を具体的にイメージしながらの事業展開には⾄らなかった。こうした中、旭化成では具体的な機能をイメージできなければ用途開発は難しいと判断、スラリーから⼀歩川下に降りての⽤途開発を決断し、2003年〜2004年頃からはCNFの多孔質シート(不織布)での展開に特化している。 CNF 不織布は、平均繊維径が 100nm以下の CNF からなる多孔質シート材料であり、旭化成独
⾃の抄紙技術を活かして開発された⾼い⽐表⾯積と空孔率を実現している。30nm、100nm の他、400nmの繊維径のシートを有し、繊維径が太くなるほど孔径は大きくなる。膜厚は3μm〜80μmで、単層シートとしての供給はもちろん、薄肉のシートは支持体との積層体としての供給にも対応している。 CNFを樹脂の強化材として使用する場合、樹脂中にいかに偏りなく均一に配合するかという点が課題
となるが、従来のようにスラリー状・パウダー状で配合する場合、均一に分散するまでミキサーにかける必要がある上に、特に配合量が少ないケースでは、強化対象樹脂に万遍なく⾏きわたるまである程度の時間がかかるが、CNF を不織布状として樹脂を含浸させれば、⼀定の⾯積の樹脂シートを容易に強化することが可能となる。 既存の繊維強化プラスチック(FRP)ではガラス繊維が使⽤されるケースが多いが、ガラスの重量が直
接シートに影響するため軽量化が困難であった。CNF を使⽤することで薄⾁・軽量化が実現する。同社の CNF不織布は現時点でサンプルワーク中であり、実際の製品に採⽤された例は無いが、FRP 関連では軽量化が求められる⾃動⾞部品や熱による膨張・反りなどが問題となるプリント基板などエレクトロニクス関連の⽤途が期待できると同社では⾒ている。 特にプリント基板向けでは電⼦機器の薄型・軽量化に合わせて基板も薄⾁化しているが、材料として
使用されるエポキシなどの樹脂は熱膨張により反りが生じ、IC チップ等が剥離してしまうという問題が⽣じる。CNF 不織布は熱安定性が⾼く、⾼温になっても寸法変化や反りが⽣じないため、これを芯材に使⽤することで薄肉の基板の熱膨張・熱反りの防止につながる。 強化プラスチック以外では、薄肉であることや微細な孔径を活かしたフィルターとしての用途も期待され
る。ただ、原料であるセルロースは⽔中で解繊・崩壊してしまう性質を持つため、同社ではCNFを化学修飾することで耐水性を持たせたグレードを開発。ドライ環境、ウェット環境のいずれにも使用できる機能性フィルターとしての使用も可能である。 旭化成では現在、CNF 不織布をプラスチックシートを始めとする樹脂加⼯、エレクトロニクス、⾃動⾞、
661
医療関連など幅広い業界にサンプル供給し、顧客ニーズの吸い上げと、それを受けての製品の改良開発を続けている。 CNF不織布の⽣産拠点は延岡⼯場で、パルプからCNFを解繊しシート化するまでを⼀貫して⾏うが、
⼀度シート(不織布)にしたCNFを再解繊することは非常に難しい。また、同社ではCNF不織布のサンプル供給は⾏っているが、スラリーや粉末状では提供していない。 今後の課題として、CNF 不織布の⽣産技術があり、⼯業的規模(1,000m以上)で安定に生産
できる技術を確⽴することが急務としている。
662
服部商店 同社がCNFの開発を始めたのは2014年〜2015年頃、淀⼯場で製造し⾃社ブランドとして販売し
ているエポキシ系接着剤・補修材の強度と可撓性を両⽴するための添加剤として着⽬したことがきっかけであった。 1995年の阪神⼤震災以降、関⻄地域ではビルや⾼架などの倒壊防⽌の観点から接着剤・補修材
には接着強度だけでなくある程度の可撓性を持たせて建築物に伝わる揺れや振動を逃がすという要望が⼤きくなった。しかし、エポキシ樹脂は「がっちりと固める」ことで接着強度を発揮する。樹脂の柔軟性と接着強度はトレードオフであるため、可撓性を持たせると強度が低下するという問題が⽣じる。これを解決すべく、同社では 2010年頃からカーボンや無機ウィスカーなど様々な添加剤を検討し研究開発を推進。最終的にCNFに⾏きついた。 CNF の開発を進める中で問題になったのが CNFの親水性である。CNFはパルプを原料とし、⽔中で
パルプの繊維をナノレベルまで解繊することで得られるが、繊維表面に水酸基(OH 基)があるため水には均⼀に分散してもエポキシのような疎⽔性材料に配合すると繊維の⽔酸基同⼠が⽔素結合をおこして凝集するため均一に分散しない。そこで同社では、⼀般的には⽔中で⾏われる解繊プロセスを⾮⽔系溶液中で⾏う⼿法を開発、疎⽔変性したパルプを⾮⽔系の溶液中で解繊することに成功した。
当初、服部商店ではこの疎水性 CNF を自社で扱う各種エポキシ樹脂製品、シーリング材、特殊接
着剤などの添加剤と位置付け、全量⾃社で消費することも考えたが、疎⽔性樹脂組成物に混ぜやすいCNF分散材は世の中に出回っておらず、市場のニーズも大きかったことから外販を決意。2016年10月にふじさんメッセ(静岡県富士市)で開催されたCNF関連の展示会「第2回CNFサンプル企業展示会」に出展したところ、多くのメーカーからサンプル供給のリクエストや共同開発の打診が来たことから服部商店の新たな製品として展開していくことを決定、非水系の溶液中でパルプを解繊した CNF 分散材「セナフ」として市場に正式に発表した。 現在、「セナフ」は淀工場内の実験設備で 3〜5 ㎏/⽇(溶液重量を含む。固形分は 2〜10%)
程度の少量⽣産であるが、2017年4⽉に淀⼯場に新建屋を完成させており、同年秋には30〜50㎏/⽇(同)程度の量産機を導⼊する予定である(⽉換算能⼒は最⼤1t/⽉程度、同)。
試験項目 条件 性能 単位 ブランク CNF(2%)
最大応力 MPa 0.96 2.63
伸び率 % 97 64
圧縮試験 25mm厚 10mm変位応力 MPa 0.912.23
[服部商店 資料より
引張試験 ダンベル1号
軟質エポキシに添加したCNF「セナフ」の特徴
663
服部商店の CNF「セナフ」は先に述べたように疎水化パルプを非水系溶液の中で解繊したもので、分散液の形で供給される。液の濃度は 2%、5%、10%をラインナップしているが、現在引合が来ているのは 5%品、10%品が多い。同社では解繊し分散液としたものをサンプル供給するだけでなく、ユーザーが希望する溶液中で解繊する受託加⼯や、ユーザーの使⽤条件に合わせた受託開発などを⾏っている。 先にも述べたが、同社の淀工場では以前からユーザーのプライベートブランドのOEM生産やユーザーが
求める化学品の受託開発などを中心に事業を展開しており、生産される製品の 70〜80%は OEM や受託生産であった。「セナフ」についても自社ブランドに固執せず、多様なユーザーのニーズに対応することが用途や需要の拡大につながると考えている。 また、「セナフ」の想定⽤途である各種塗料や接着剤、注⼊材などは溶液の種類や各種薬剤の配合、
濃度などがユーザーによって異なるケースも多く、標準的な製品をラインナップしてもニーズに合致するとは必ずしも限らないことから、ユーザーの要望に添った製品の開発・供給が可能な受託での展開のメリットは大きいとしている。 外販だけでなく自社のエポキシ樹脂、接着剤・塗料、シーリング材といった製品の補強材や性能アップ
のための⾃家消費も⾏っており、塗床材や注⼊材、接着剤などに使⽤される低臭気エポキシ「NEO ONE」を始め、建築用シーリング材「サンシール」、特殊接着剤に「セナフ」を配合した製品開発を進めている。
服部商店では「セナフ」について、原料の疎⽔化パルプを外部から購⼊し、解繊〜スラリー化までを⾃
社で⾏っている。解繊に使⽤する溶液は⽤途や複合化する対象樹脂によって異なるため⼀概には⾔えない。パルプは⽊材パルプを基本とし、サプライヤーは⾮公表であるが、疎⽔化処理以外は特別なものではないようだ。 近年、⽇本国内においては CNF市場への参入が相次ぎ、製紙メーカー、化学メーカーを始めとする
様々な業種のメーカーが市場参入している。現在は開発されて間もないこともあり、メーカー間の競争などは発生していないが、2017年後半〜2018年にかけて各社のCNF⽣産設備が⼀⻫に稼働を開始することから、本格的な市場⽴ち上がりと同時に競争の激化が懸念されている。
664
服部商店では他社に例を⾒ない「⾮⽔系溶液中での解繊」を実現したオンリーワン企業であること、CNFの開発当初から「エポキシその他の樹脂の性能補強」を志向しており、CNFの開発ありきであった競合他社とは事業の方向性が違うことなどから、市場での競合とのバッティングは少ないと考えている。 「セナフ」は社外のユーザーへのサンプル供給開始から日が浅く、自社及びユーザーサイドでトライ&エラ
ーを繰り返しながらのサンプルワークとフィードバックを元にした研究開発が続いている段階である。服部商店では「セナフ」の実績が業績に寄与するようになるには数年程度の時間を要すると⾒ており、早期の事業化に向けた開発を継続していく方針である。サンプルのリリースから5〜6年後の2021年〜2022年頃には、なんらかの形で実績を上げて⾏きたい考えである。
ダイセルファインケム 同社は WSP 事業部において、カルボキシメチルセルロースナトリウム(商品名:CMC ダイセル)、カ
ルボキシメチルセルロースアンモニウム(同:CMC ダイセルアンモニウム)、ヒドロキシエチルセルロース(同:HECダイセル)といった水溶性セルロース誘導体を主に取り扱っているが、その商品群の中でセルロースナノファイバー(CNF)にカテゴライズされるのが微小繊維状セルロース「セリッシュ」である。 ダイセルファインケムでは 1990 年代初頭より、セルロースを特殊な製法でサブミクロン〜ナノレベルまで微細化したミクロフィブリル繊維(微小繊維状セルロース)を「セリッシュ」のブランド名で展開している。1990 年には清酒濾過⽤、1991 年には⾷品⽤のグレードを投⼊、その後、不織布や化粧品など、⼯業・産業分野まで用途の幅を広げている。 「セリッシュ」は⾼度に精製した⾼純度パルプを原料とし、特殊な処理⽅法でミクロフィブリル化したもの
である。具体的には、パルプを水に分散させた懸濁液を高圧ホモジナイザーで機械的に解繊する。高圧ホモジナイザーに投⼊されたパルプ懸濁液には⾼い圧⼒がかけられ、機械中の隙間を⾼速で通過する過程で⼤きな剪断⼒・衝撃⼒と急激な減圧により⽣じるキャビテーションでセルロースの繊維が引裂かれ微細化される。 機械による物理的な解繊であり、触媒や化学薬品などを使⽤しないため、原料であるセルロースの物
理的、化学的安定性といった基本特性を損なわずにミクロフィブリル化できることが特徴である。サイズ(繊維の太さ)は0.1μm(100nm)〜0.01μm(10nm)程度と、化学解繊されたCNFに比べ太く、厳密に⾒れば「ナノ」というよりも「サブミクロン」に近いが、同社では昨今のニーズに合わせ平均の繊維径が 10〜数 10nm レベルになるよう微細化した「ナノセリッシュ」も開発している。「ナノセリッシュ」をどのような⽤途で、どのようなユーザーに提案していくかについては現在検討中であるが、例えばナノファイバーで抄紙を⾏い樹脂を含浸した透明フィルムなど、従来の「セリッシュ」の使われ⽅にこだわらない新たな開発も進めて⾏きたいとしている。
665
ダイセルファインケムではセリッシュの販売量については公表していないが、主な⽤途は濾過⽤及び⾷品
添加用、紙などの工業用である。 最も供給量が多いのは醸造酒や調味液の濾過助剤⽤であり、清酒やワイン、焼酎、醤油などの⽣産
工程ではなくてはならない材料となっている。具体的な使い⽅を⾒ると、酒などの液体中でむらなく分散させた「セリッシュ」を濾過機に投⼊し、プレコート層を形成させてから濾過を⾏う。 濾過機内で濾紙・濾布などの濾材上に均⼀に形成された「セリッシュ」の層により不純物が濾しとられ
る。濾過の最終段階で⼒をかけて⽔と空気を濾紙・濾布から押し出す(⽔押し・空気押し)と、濾紙・濾布の上で「セリッシュ」がシート状になり容易に剥離できるというものである。 濾過助剤としては「セリッシュ」の他に珪藻⼟や粉砕セルロースなどが使⽤されているが、「セリッシュ」は
666
サブミクロン〜ナノレベルの繊維が微細な網⽬構造を形成するため濾過の捕捉精度が⾼く、また、⾷品添加物にも認定された安全な物質である⾼純度セルロースを原料としているため⼈体に対する安全性が⾼い上に酒など濾過対象の液体への溶出物が少なく、味や⾹り、成分に影響しない。天然セルロースから⼈⼯的に解繊して作られるため物性の調整がしやすく、⽤途やユーザーのプロセスに最適化した濾過助剤を提案できるというメリットもある。 濾過助剤以外では⾷品添加物としての採⽤も多い。「セリッシュ」は微細繊維の網⽬構造が⽔を蓄え
るため保水性や粘性が高く、優れた保形性を有する。そのため、練り食品の保水性維持、ハンバーグやミートボールなどひき肉加工品の肉汁保持、加工食品のドリップ防止、触感の改善といった効果が得られる。 これらのメリットがユーザーから評価され、⻑年にわたり濾過助剤や⾷品添加物としての実績を上げてき
た。また、最近では「セリッシュ」をバインダーとして不織布に添加したり、保⽔性やチキソ性を化粧品へ付与するために添加するなど、工業・産業関連の新たな用途開発に取り組んでおり、実績も次第にあがりつつある。工業用・産業用では既存の競合品のベンチマークでの開発となっているが、ダイセルファインケムでは「セリッシュでなければならない」というニーズの発掘が不可⽋であると考えている。 「セリッシュ」は⽔中で解繊される親⽔性材料であり、樹脂、あるいは油やアルコールなどの⾮⽔系材料
との複合化が困難であるという課題があるが、昨今は複合化装置の改善によりセリッシュを樹脂へ配合する検討が進められており、今後はこうした“樹脂フィラー”としての実績も増えていくことを期待している。 「セリッシュ」の⽣産拠点は網⼲⼯場(兵庫県姫路市)で、⽣産能⼒は固形分換算で 600t/年
(ナノサイズだけでなくミクロフィブリルセルロースとしての能⼒)である。
大阪ガス 同社では2014年9月、セルロースナノファイバー(CNF)と石炭由来の化学素材「フルオレン」を複
合化した新素材「フルオレンセルロース」の開発に成功、2015年よりサンプル供給を開始している。 もともと同社では、ガスの製造から供給、電⼒事業などを扱うエネルギー企業の使命として環境対応に
かかわる事業に注⼒する⽅針を打ち出しており、その⼀環としてバイオマスに着⽬、⾃社の得意分野とバイオマスとのシナジーを模索していた。⼀⽅で、グループ会社である⼤阪ガスケミカル株式会社(以下、⼤阪ガスケミカル)では、⻑年にわたり蓄積してきた⽯炭化学を基に、コールタールに含まれるフルオレンと各種芳香環を結合させたフルオレン誘導体を事業化し、ディスプレイ、光学、半導体などの分野で実用化していた。大阪ガスケミカルが有するフルオレン関連の技術と知⾒から、フルオレンはバイオマスと相性が良いという事が判明、大阪ガスがバイオマス関連事業に参入するに当たり、フルオレンとの最適な組み合わせを探る中でCNFに⾏きついたという経緯がある。 その結果、⽔中で解繊される親⽔性材料である CNF には乾燥による凝集や油・アルコールなどの疎
⽔性材料との混ざりにくさといった課題があり、これを解決する⽅法としてフルオレンの使⽤が有効であると判断。CNF をフルオレンで修飾し、乾燥後も凝集せず有機溶剤にも高い分散性を示す「フルオレンセルロース」を開発した。
667
一般的にCNFは化粧品やインクなどの増粘剤としての使用や、ガラス繊維や炭素繊維と同様に樹脂と複合化して強化樹脂を製造するといった⽤途展開が期待されており、特に樹脂複合化では⾃動⾞や家電、その他、幅広い分野で樹脂成形品の軽量化と強度アップを実現する材料として注⽬を集めている。しかし、先に述べたように CNF は親⽔性材料であり、⽔の中では均⼀に分散するが疎⽔性材料に⼊れるとCNF表面の水酸基(OH基)同士が水素結合をおこして凝集するため均一に分散しない。パルプからナノレベルまで微細化した繊維を取り出すプロセスは全て水中で⾏われ、解繊された CNF は水分散したスラリーの形で供給されるため、そのままでは樹脂に混ぜにくい一方で、水分を完全に除去(乾燥)するとCNF同士が凝集し、樹脂中への均一分散は困難である。 これに対し大阪ガスでは、様々なフルオレン誘導体で CNF の表面を修飾することで疎水化を実現、
様々な有機溶媒や疎⽔性樹脂に分散可能としたことで、樹脂と複合化するコンパウンドや溶剤系塗料に混ぜるコーティングといった用途への展開を可能とした。また、詳細は非公表であるが、独自の技術で乾燥後も CNF が凝集しない技術を開発しパウダー状でも供給しており、ユーザーサイドでの脱水プロセスを不要としている。
現在、大阪ガスの「フルオレンセルロース」はパイロットベースで生産し、サンプルを供給するとともに用途
開発を進めている状態である。⽣産拠点及び能⼒は⾮公表。繊維のサイズは現状では数⼗ nm〜100数十nm程度が多いが、⽤途によってどの程度の繊維径・繊維⻑さのものが良いのかサンプルワークの中で検証している段階である。供給形態としては、先述の粉末状の他、溶媒液との混合スラリー、樹脂と混ぜたマスターバッチなどを想定しており、これもユーザーの要望や使い方に合わせた最適な形態を検証中となっている。サンプル供給先は多岐に亘るが、もともと同社のフルオレン誘導体のユーザーはコンパウンドメーカーが多く、「フルオレンセルロース」についてもコンパウンドメーカーからの引合が多いようだ。 「フルオレンセルロース」は分散性・相溶性、耐熱性、機械特性に優れる。様々な溶媒への分散性を
⾒ると、⽔、IPA(isopropyl alcohol)、ジオキサン、THF(tetrahydrofuran)、アセトンなどへの分散性が確認されている。
668
現在開発されている「フルオレンセルロース」複合化樹脂の例としては、ポリ乳酸(PLA)や PA6 など
が挙げられる。PLA は植物由来樹脂であり、石油由来樹脂に代わる環境対応樹脂として注目されているが、既存の樹脂に⽐べ強度が弱いという問題がある。そのため、各種添加剤で強化されるが、強度アップのために樹脂にフィラーや⽯油系材料を複合化した場合、植物由来で化⽯系材料を使⽤しないというPLAの価値が縮小してしまう。 植物由来の CNF の変性品である「フルオレンセルロース」を使用することで、樹脂、添加剤ともに全て
植物由来の強化樹脂とすることが可能となり、リサイクルも容易であるというメリットがある。 また、⾃動⾞部品や家電筐体、電気・電⼦機器などの⽤途ではPA6 にガラス繊維(GF)を配合し
た強化プラスチックが使用されるケースが多い。GF を配合することで強度や弾性率、耐摩耗性などが⼤幅にアップするが、重量が重く、薄型化・軽量化という昨今のユーザーニーズへの対応は難しくなるが、強化材を「フルオレンセルロース」に替えることで、機能を落とさずに軽量化が可能となる。
熱的特性 耐摩耗性
強度 弾性 強度 弾性MPa MPa MPa MPa ℃ mg
PLA 68 1300 91.0 4098 137 -
FLCF/PLA※2 82~87
1430~1490
97.8 5290 153 -
PA6 - 2850 114.0 2630 73 -
FLCF/PA6※4 99.1 5320 152.0 4590 142 4.98
GF/PA6※5 105.4 6060 165.0 527 205 5.73
[大阪ガス 資料より]
ポリ乳酸
ナイロン6※3
樹脂
機械特性
フルオレンセルロース配合樹脂の特性例
荷重たわみ
温度※1
引張試験 曲げ試験摩耗量
669
大阪ガスでは、大阪ガスケミカルでの事業化を目指して、上記を含め、様々な樹脂との複合化に向けて複数のユーザーとサンプルワークに取り組んでいる。大阪ガスグループでは、①添加剤向けや樹脂との複合化のための「フルオレンセルロース」フィラー単体、②あらかじめ樹脂と「フルオレンセルロース」を複合化させたマスターバッチやコンパウンドペレット、さらには③「フルオレンセルロース」が有機溶媒に分散するという特徴を活かした、塗料・コーティング向けの溶媒分散品など、幅広い形態でのサンプル供給によってユーザーの多様なニーズに対応していくことで、「フルオレンセルロース」の早期の事業化を実現させる方針である
670
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位5位程度まで列記)
世界に目を向けると、2011 年にスウェーデン Innventia がパイロットプラントで CNF の生産を始めて以降、⽶国、カナダ、欧州で本格量産化の前段階であるデモンストレーションプラントの建設が進んでおり、フィンランドStora Enso/UPM、ノルウェーBorregaard等が商業化に向けた投資を拡大している。また、CNC ではカナダ Celluforce や米 American Process がインダストリアルスケールでのプレコマーシャル⽣産を⾏っている。 加えて、CF(Cellulose Filament等)では、カナダKrugerが5t/日のデモンストレーションプラントを2014年から稼働しているほか、Performance BioFilaments Inc(クラフトパルプ大手のMercer Internationalと製紙メーカーのResolute Forest ProductのJV)が2018年の稼働を⽬指したコマーシャルプラント(5万t/年スケール)の建設計画を検討中である。
世界のナノセルロース生産状況
出所:TPPINANO資料を基に⽮野経済研究所作成
(単位:㎏/日) (単位:㎏/日)Paperlogic 米国 2000 CelluForce カナダ 1000University of Maine 米国 1000 American Process 米国 500
Borregaard ノルウェー 500 Holmen (Melodea)スウェーデン 100
American Process 米国 500 Alberta Innovates カナダ 20日本製紙 日本 150 US Forest Products Laboratory米国 10
Innventia スウェーデン 100 Blue Goose Biorefineriesカナダ 10
CTP/FCBA フランス 100 India Council for Ag. Research インド10
王子製紙 日本 100 FPInnovations カナダ 3Stora Enso フィンランド プリコマーシャル Melodea イスラエル パイロット
UPM フィンランド プリコマーシャル
FPInnovations カナダ パイロット
Norske Skog ノルウェー パイロットSAPPI オランダ パイロット
VTT スウェーデン パイロットLulea University of Technologyスウェーデン ラボ
US Forest Products Laboratory米国 ラボ
※王子製紙富岡工場:実証実験プラント、2017年より本格的にサンプル供給を開始。能⼒は40t/年
セルロースナノファイバー(CNF) セルロースナノクリスタル(CNC)
※日本製紙:岩国工場(実験プラント、30t/年)、江津工場(CM化CNF量産拠点、30t/年)に加え、石巻工場(TEMPO酸化法、500t/年、2017年4月稼働)、富士工場(京都プロセス、10t/年、2017年7月稼働)
671
<カナダ> ナノセルロースの研究開発では、⾮営利の研究組織である FPInnovations が中心な役割を担っている。
2009 年 2⽉〜2014 年 3 月、産学協同のネットワーク(ArboraNano-the Canadian Forest NanoProducts Network)の枠組みの中で様々なR&Dプログラムを実施。ここでの成果を基に商業化フェーズへと移⾏している。
同国のフロントランナーであるCelluForce がCNC “CelluForce NCC”の商業生産を2018年頃に予定している。
FPInnovations はカナダ国内の森林セクター研究組織(FERIC, Forintek Canada Corp, Parican)を統合する形で、2007年に設⽴された。Vancouver, Quebec City, Pointe-Chaireの3か所にリサーチセンターを有し、“Wood Products”, “Forest operations”, “Pulp and Paper”, “Canadian Wood Fibre Centre”の各ディビジョンで基礎研究から応⽤開発までを⾏っている。 産学協同ネットワーク“ArboraNano”は、FPInnovationsが旗振り役となり、2009年2月よりスタ
ート。運営・開発資⾦としてカナダ政府の Business-Led Network of Centres of Excellence(BL-NCE)より8.9MCADの拠出を受けた。
出所:ArboraNano資料
ArboraNano 参加メンバー・パートナー
メンバー : 22Alberta Innovates - BioSolutions
Bell Helicopter Textron Ltd. Bio Vision TechnologyCelluForce
FPInnovatons INRS - Institut Armand Frappler Kruger Inc. Marquis Alliance Energy GroupInc.
McGill UniversityNanoQuebec NORAM Engineering &Constructors
OMYA Canada Inc.
Ontario BioAuto Council Queen's UniversityUniversite de Sherbrooke Universite du Quebec a Trois-Rivieres
Universite du Quebec enAbittbi-Temiscamingue
University of AlbertaUniversity of British Columbia University of Waterloo
Universite LavalWoodbridge Foam Corporation
パートナー : 15Akzo Nobel Alberta Innovates - Technology
FuturesAlberta NanoAccelerator Alberta Pacific Forest Industries
Inc.BASF College Ahuntsic Cytec Groupe Lapemere & Verrault
Handy Chemicals Institut des CommunicationsGraphiques du Quebec
FQRNT MRNF
National Research Couincil -NINT
Natural Resources Canada University of Toronto
672
2009 年のスタート以来、ArboraNano は 25 のリサーチプロジェクトに対し 16MCAD を投資。“Functionalization & Compatibilization”, “Modelling”といった基礎から、”Composites &Form”, ”Adhesives”, ”Textiles”, ”Drilling Fluids”, ”Membranes”, ”Aerospace”, ”Health & Personal Care”, ”Coatings”などの応用までを幅広くカバーした。これらの取り組みを基に、現在カナダではナノセルロースの3つのパイロットプラントと2 つのデモンストレーションプラントが設置されている。 〇 CNC FPInnovationsは、Dr. Derek Grey(McGill University)の研究を基礎に2005年頃よりナ
ノセルロースの商業化に向けた取り組みをスタート。2006年にはMontrealの研究室にCNCのパイロットプラント(10㎏/週)を稼働させた。
出所:FPInnovations資料 その FPInnovations と北⽶有数の製紙会社である Domtar Corporation が設⽴した
CelluForce は、CNC “CelluForce NCC”のデモンストレーションプラント(1,000 ㎏/日)をDomtarのWindsor工場に建設。サンプル生産を含むトライアルを続けており、2018年頃から300t/年規模の商業⽣産に移⾏する計画である。 なお、CelluForce には世界最⼤の油⽥検層サービスを⾏う Schlumberger、ユーカリパルプ製造で
世界最大手のFibria Celluloseも資本参加、 オイル&ガスセクター、エレクトロニクスセクター、プラスチックセクターを手始めに、粘着・接着剤、セメント、塗料、コーティング、パーソナル・ヘルスケアなどへの展開を図っていく方針を明らかにしている。
673
※オイル&ガスセクター Dr. Yaman Bolukを中心としたグループがArboraNanoプロジェクトとして掘削液へのCNC添加について研究開発を実施。CNC 添加により油田採掘時の掘削液のロスが大幅に減少できることを明らかにした。掘削液は油田採掘コストの10%を占めるため、ロスの減少は採掘コストの低減に相応にインパクトをもたらすとして、カナダではCNCの有望用途の一つとして注目されている。 また、2014 年11月、製紙会社であるKurgerとFPInnovationsはKurgerのTrois-Rivieres
⼯場内に建設したセルロースフィラメントのデモンストレーションプラント(製造能⼒:5t/日)を稼働させた。投資額は 43.1MCAD、Natural Resouces Canada、the Quebec Ministry of Natural Resourcesから補助を受けている。 セルロースフィラメント(FiloCell)のプロファイルは、直径:30〜500nm、⻑さ:100〜2,000μm、
アスペクト比:100〜1,000。現在、商業生産に向けたアプリケーション開発を進めており、印刷紙や包装⽤紙、トイレットペーパー・キッチンペーパー等の補強材、プラスチック、粘着剤、不織布、コーティング向けの添加剤等をターゲットに挙げている。 Alberta Innovates-Technology Futures(AITF)は、2013年9月に酸加水分解法を導入
したCNCパイロット設備(100㎏/週、south Edmonton)を稼働。 Advanced Cellullosic Materials(旧 BioVision Technologies)は the National
Research Council(NRC)から酸化法技術のライセンスを受け、CNC のパイロットプラント(20 ㎏/週)を導入している。 ※当該企業のHP等は確認できないため、詳細は不明。 このほか、Blue Goose Biorefineriesが新たな酸化法CNC製造技術(R3TM)の開発を⾏って
おり、30㎏/週のパイロットプラントをSaskatoonに保有している。
674
<米国> United States Department of Agriculture(USDA) Forest Service, Forest Products Laboratory (FPL) が旗振り役となり、ナノセルロース材料の研究開発を推進。
FPLは2012年8月に1.7MUSDを費やし、University of Maine と共同でCNFのパイロットプラント(1,000㎏/日)を同大学のthe Process Development Center(PDC)に設置。同時期にウィスコンシン州 Madison にある FPL の研究所内に CNC のパイロットプラントも建設した。
また、US Forest Service とThe U.S. Endowment for Forestry and Communities が主導する官⺠パートナーシップ“P3Nano”を通じ、ナノセルロースの実用化に向けたリサーチプロジェクトを実施。 ※2016年の予算は2.25MUSD
Paperlogic(CNF)、American Process(CNF/CNC)といった⺠間企業による取り組みも加速している。
University of Maineは、FPL と2011年4月よりリサーチパートナシップを結んでおり、様々な形でCNF及びCNCにアカデミック/インダストリアルリサーチを実施している。同大学の“The Nanocellulose Research Program”はFPLが主導するリサーチコンソーシアムの一部を為している。なお、このリサーチコンソーシアムには、このほか Georgia Institute of Technology, North Carolina State University, Oregon State University, Pennsylvania State University, Purdue University, University of Tennesseeが参加しており、CNF/CNCの量産技術の開発等で共同研究を⾏っているほか、ナノセルロースの標準化等にも関わっている。 Paperlogic (Turners Falls Paperのリサーチ部門)が2015年5月にCNFのデモンストレー
ションプラント(2,000㎏/日)を設置。製造技術はUMaineのCNF製造技術をベースに改良を加えたGL&V(製紙関連装置メーカー)の技術を採用している。 American Process Inc が 2015 年 4 月より Thomaston バイオリファイナリーにて CNC 及び
Nanofibrilのプレコマーシャル⽣産を開始している。⽣産能⼒は500㎏/日。 同社は、バイオマスから糖類やエタノールを製造する技術を開発する⺠間企業で、2005 年よりバイオ
マス由来糖類の研究開発を進めてきた。その後、バイオマス由来の糖類及びエタノールの製造技術を開発。これらのデモンストレーションを進めるとともに、CNC 等のナノセルロースの製造をラボスケールで⾏ってきた。2015年1Qには独自技術によるCNC及びNanofibrilを“BioPlus”として発表、コンポジット、塗装、コーティング、パッケージング、フィルム、セメント、オイル&ガス、粘着剤、紙製品など、広範な用途でマーケッティング活動を⾏っている。 2017年1月、American Process IncはマレーシアMYBiomass とナノセルロースに関する共同
675
研究開発プロジェクトを⽴ち上げたほか、2016 年 9 月よりスタートした“BIOFOREVER PROJECT”(Horizon 2020)にも参画。さらに、Swansea University Medical School とはヒト細胞とナノセルロースを用いた3D プリンティングによる顔面再建技術の研究に取り組むなど、国内外で動きを活発化させている。 <スウェーデン> バイオエコノミーへの転換というビジョンを明確化。イノベーションプログラム“BioInnovation”に年間14億円を投入。政府運営の研究機関“RISE”がアクセラレータとして機能。
スウェーデン政府は、 “2050年中にバイオエコノミー(リニューアルブル、バイオロジカルなリソースを基
礎とする社会)への移⾏を完了する”というビジョンを実現するためのイノベーションプログラム“BioInnovation”を推進しており、林業・紙産業の新たな成⻑分野としてナノセルロースの研究開発を強⼒に⽀援している。 ※BioInnovation:Vinnova(Sweden’s Innovation agency)、the Energy Agency、Formas(A Swedish research council for sustainable development)及び60のステークホルダーが研究開発プロジェクトに資⾦を拠出する形を採っており、予算額は 1 億 SEK/年(およそ 14億円、14円/1スウェーデンクローネ)。 ナノセルロースの研究開発は、RISE Research Institutes of Sweden(以下、RISE)を中心に
進められている。RISE は複数の研究組織がネットワーク化し、企業、大学と共同でインダストリアルリサーチやイノベーションに取り組むイノベーションシステムのひとつで、スウェーデン政府が 100%出資する RISE ABが保有している。 ※2017 年 2⽉に組織体制の⾒直しがあり、それまでの参画組織である Inventia(pulp,
packaging, biofuel)、SP Technical Research Institute、Swedish ICT(Information and Communication Technology)が統合し、新生 RISE として始動。従来参画していたSwerea(Material Technology)はSweareaの⽴場から関っていく形に移⾏している。 RISE では、2025年までに国内の資源を⽤いたナノセルロース材料の製造技術を確⽴し、⼤規模な
デモンストレーションプラントを建設することを研究開発目標に掲げており、CNF では Inventia が 2011年よりストックホルムの研究施設内に100㎏/日のパイロットプラントを稼働させているほか、2017年からは評価のための移動式デモプラント(トンベースのナノセルロース製造が可能、製紙メーカーのBillerudKorsnasがプロジェクトに参加)を運用している。 一方、CNCでは、SP Technical Research Instituteが産業コンソーシアムの活動(製紙メーカ
ーの Holmen, MoRe Research 等が参加)を通じ、CNC のパイロットプラント(100 ㎏/日、SP Processum, Örnsköldsvik)を2015年に設置している。製造技術はイスラエルMelodeaの技術を
676
採用している。パイロットプラントの建設費等はVästernorrland County Administrative Board, Holmen, the Kempe Foundations, SP Technical Research Institute of Sweden and the Önnesjö Foundationが拠出した。SP Processumにはこのほか、バイオリアクターやスピン装置なども併設されており、ナノセルロース応用研究の一大拠点となっている。 これ以外の取り組みとしては、Wallenberg Wood Science Centerからスピンオフしたセルロースフォーム等の研究開発を⾏っているCelluTech ABやバリアコーティング、フィルター、バイオフィルム等をターゲットにナノセルロースの研究開発を⾏っているAHLSTROMが挙げられる。 <フィンランド> 国営研究機関:VTT を中心にナノセルロースの研究開発を推進。大手製紙メーカーの Stora Enso、UPMが事業化に取り組む。
Ministry of Employment and the Economyが主管するVTT Technical Research Centre of Finland を中心にナノセルロースの研究開発を実施。Tekes- the Finnish Funding Agency for Innovationが活動を支援している。 2013 年には Tekes が資⾦を拠出し、VTT、Aalto University, Tampere University of Technology , the University of Vaasaがナノセルロースの共同研究プロジェクト:Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC)を開始、2018年までの5年間に“新しいセルロースブランドの⽴ち上げ”、“ビジネスモデル、エコシステムの育成”、“ナノセルロースのデモンストレーションプラントの設置”を進めていく方針を打ち出している。 Stora Enso は 2011 年、10M ユーロを投じフィンランド Imatra 製紙工場内に microfibrillar
cellulose (MFC)のプレコマーシャルプラントを導入。液体パッケージング向け板紙への添加などに取り組んだ。その後、MFC を添加することにより原材料の削減が可能なほか、品質向上にもつながるなどのメリットがあるとして2015年にはMFCの商業生産を開始している。 同社は“Renewable Material Company”への転換を指向しており、2017年には12Mユーロを
投じ、2018年1Qの稼働予定でスウェーデンHylite製紙工場内にバイオコンポジット(いわゆる木粉コンパウンド)の生産ライン(15,000t/年)を整備するほか、MFC(Microfibrillated cellulose)及びMFC含有板紙の製造ライン増設に9.1Mユーロを投資することを明らかにしている。 MFC及びMFC含有板紙の増強は、スウェーデン Fors工場、フィンランド Imatra工場、Ingerois
工場の3拠点で実施、MFC含有の板紙の⽣産能⼒をトータル50万t/年に拡⼤する計画である。稼働は2017年末を予定しているが、これら設備のフル稼働には3〜5年は要すると⾒ている。 UPMは”Renewal and our Biofore strategy”の一環として、2008年頃よりfibril cellulose
の製造技術開発を本格的に進め、2011年秋にはプレコマーシャルプラントをEspooに導入し稼働を開始した。当初は紙パッケージ、コンクリート、塗料などへの配合をターゲットに⽤途開発を進めてきたが、マ
677
イクロサイズからナノサイズまでの fibril cellulose を製造できる同社技術の特⻑を活かすべく、MFC(microfibril cellulose)と PP、ABS 等のプラスチックを複合化したバイオコンポジット“UPM Formi”なども製品化している。 UPM Formi は射出成形の⽤途にデザインされたコンポジット材(セルロース材料の添加率は 20〜
50%)で、音響機器をはじめ、様々な用途で使用されている。キッチン設備メーカーである Puustelli グループは、キッチン設備への適用を進めているが、キッチン設備のフレームに使用することで、合板より約50%軽量化できるとしている。この結果、輸送費、カーボンフットプリントの低減につながる。また、圧⼒や湿気に対する耐性が合板と⽐べはるかに⾼いため、⻑期間の保証が達成可能、屋内へのホルムアルデヒドや他の化学物質の排出量が合板より少なく済むなどのメリットもあるとしている。
また、UPMは2017年にcellulose nanofibril(CNF)を添加したハイドロゲル“GrowDex”を3D
セルカルチャー(細胞培養)向けに販売開始している。 <ノルウェー> ノルウェー政府は、バイオエコノミーの促進に向けた動きを強めており、2015 年 7 月には the Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk)、the Norwegian Agricultural Economics Research Institute、the Norwegian Forest and Landscape Instituteの3つの研究組織を統合し、The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)を誕生させている。 ナノセルロースでは、the Research Council of Norway支援による The Norwegian Nanocellulose Technology Platform(NORCEL)がアクセラレータプログラムを提供している。運
678
営主体はthe Paper and Fibre Research Institute (PFI)。参画企業・組織(パートナー)はNTNU Biorefinery and fibre technology, NTNU Ugelstad laboratory, Department of Petroleum Engineering, Department of Clinical Dentistry, Østfoldforskning, CNR-ISTEC, Norut, The research council of Norway, Innventia, NorFab-node Nanolab となっている。 ノルウェーに拠点を置く製紙メーカーのBorregaardはExilva MFC (microfibrillar cellulose)の
製造ラインを Sarpsborg工場内に建設、2016年末より稼働を開始している。⽣産能⼒は 1,000t/年、将来の⽣産拡⼤も⾒据えた設計を採っているとしている。2017 年にはスウェーデンの製紙メーカーBillerudKorsnäs と共同でExilvaの用途開発(板紙等)を進めていくことを明らかにしている。 印刷紙を得意とする製紙メーカーの Norske Skog は、MFC を用いたファイバーボードの開発を推進
(Innovation Norwayより2.0MNOK支援)、同開発の継続プロジェクトに対しても2.0MNOKを獲得している。また、Innovation Norway は同社が進める紙を原料とした MFC のパイロットプラント(⽣産能⼒:1t/日)のプロジェクトも支援しており、プロジェクト予算:18.4MNOK のうち、4.5MNOKを拠出している。
<フランス> グルノーブル周辺に拠点を置く研究組織が中心となり、ナノセルロースの研究開発を進めている。これら研究組織(以下参照)はInstitutes Carnot PolyNat としてネットワーク化されており、様々な形でコラボレーションしている。 ・CNRS(フランス国⽴科学研究センター) CERMAV- The Center for Research on Vegetal Macromolecules LGP2-Laboratory of Pulp and Paper Science and Graphic Arts Rheology Laboratory 3SR Lab-The laboratory Soils, Solids, Structures, Risks DCM Lab-The Department of Molecular Chemistry DPM Lab-The Department of Molecular Pharmacochemistry
・INRA(Nantes)French National Institute for Agricultural Research ・LCPO (Laboratory of Chemistry of Organic Polymers) ・CTP(French Pulp and Paper Research and Technical Institute) ・FCBA (French Institute of Technology for Forest-based and furniture sectors) また、CTP と FCBA は“InTechFibers”というパートナーシップを結んでおり、この枠組みの中で、ウッド
679
チップ等からセルロース質等を抽出する抽出工程、ブリーチング工程、精製工程、パルピング工程、MCF製造工程などの各種装置をラボ及びパイロットベースで運用している。なお、MCF のパイロットプラントは30〜70㎏/⽇の⽣産能⼒を有している。 工業用ミネラルの世界的なメーカーである仏 Imerys Minerals は Micro-Fibrillated Cellulose(MFC)とミネラルをコンポジット化した製品を“FiberLean”として商品化、紙やパッケージングの添加剤として展開している。既にアジア及び米国の製紙メーカーが採用しており、ともにオンサイトのFiberLean製造設備が2016年3Qより稼働している。 これらの設備が稼働したことにより、Imerys MineralsのMFC⽣産能⼒は8,000t/年になるとしている。 <その他> 独J. Rettenmaire & Sohne Gmbhは1990年代よりMicro crystalline Cellulose(MCC)
を製造(Weissenborn 工場)、医薬品業界等に供給してきた経緯があり、そのファインチューンバージョンとして CNF(NFC-100-5、UFC-100)を製品化している。詳細は明らかでないが、パッケージング、インシュレータ材料、コンポジット、フィルタ・メンブレンなどの⽤途開拓を⾏っており、特に透明ポーラスフィルムのパッケージ分野への適用などに積極的なようだ。 ウッドパルプなどの溶解技術を保有するオランダ SAPPI は CNF のパイロットプラント(Brightlands
Chemelot Campus, Sittard-Geleen)を建設、2016年初めより稼働を開始している。同社はコンポジットや⾷品・医薬品などの⽤途開発を進め、本格的な商業⽣産フェイズに移⾏したい考えを有している。なお、CNF の製造技術は Edinburgh Napier University(Professor Rob English, Dr. Rhodri Williams)との 3 年間の共同研究により確⽴した低コストでエネルギー効率の⾼いプロセスを採用した。 英スコットランドに拠点を置くCelluCompは、根菜等を原料にCNFを製造・販売する目的で2004
年に創業したベンチャー企業。Scottish Enterprise 等の開発支援を受け、テンサイなどの廃棄物をソースとした CNF を“Curran”として製品化、2015 年には英 Glenrothes に 400t/年のデモンストレーションプラントを建設している。 同社では、コンポジットや塗料、コーティングをターゲット⽤途と位置付けており、特に塗料、コーティング
は CNF 添加により耐久性が向上するとして⼤⼿塗料メーカーの評価が進んでいるとしている。同社は2016 年に Scottish Enterprise と the European Investment Fund (EIF)によ るScottish-European Growth Co-Investment Programを通じ、仏ベンチャーキャピタルのFPCI CapAgro Innovation、エンジェル投資専門の仏 Sofinnova Partners、Scottish Investment Bankから計3.7M ポンドの投資を受けており、これらの資⾦を基に今後3年以内に10,000t/年にスケールアップしたい考えを明らかにしている。
680
このほか、独 Zeflo Technology が MFC の技術開発を⾏っており、紙・パルプの添加剤向け等で独BASF とパートナーシップを結ぶなどの動きを⾒せているほか、Friedrich-Schiller University の研究者が⽴ち上げた独JeNaCellも独自のバクテリアを用いたナノセルロース製造技術の実用化に取り組んでおり、独Evonikのバックアップを受けている。
681
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
日本国内のセルロースナノファイバーの技術開発に携わる大学・研究者は以下の通り(ナノセルロースフォーラムの会員名簿より抽出)。その他、産業技術総合研究所、理化学研究所、高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所、森林総合研究所等の国⽴機関、各都道府県ならびに市の産業技術研究所・産業技術センター・工業技術センターほかの研究者が関っている。
682
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者及び所属機関
※ナノセルロース研究の有⼒⼤学を中⼼に研究者をピックアップ。また、必要に応じて、Science Direct等の論⽂検索を実施。
<米国>
683
⑩ 平成29年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発
プロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
現在実施中の事業が対象(継続/新規両方含まれる)
経産省 「高機能リグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術開発」
期 間 : 2013〜2019年度 予算:4.2億円(平成28年度)、6.5億円(平成29年度) 参加機関 : 国⽴⼤学法⼈京都⼤学、王⼦ホールディングス株式会社、⽇本製紙株式会社、星光PMC株式会社、地⽅独⽴⾏政法⼈京都市産業技術研究所
概要: ⽊質バイオマスを原料とし、鋼鉄の 5 分の 1 の軽さで、5 倍以上の強度と樹脂への分散性、耐熱性に優れた高機能リグノセルロースナノファイバーについて、一貫製造プロセスおよびこれを⽤いた⾃動⾞部品や建材などの部材化に関する技術開発を⾏う。
事業目的: ⾼機能リグノセルロースナノファイバーの⼀貫製造プロセス開発、原料から最終部品まで俯瞰したリグノCNF材料の省エネ型の製造プロセス構築
成果目標:5 年間の事業機関を通じて、⽯油由来化学品と⽐較して同等以上の性能に加え、軽量化による省エネを可能とするコスト競争⼒のあるリグノCNF材料・化成品の製造技術の確⽴。
2016年の中間報告(NEDO):NEDOプロジェクトにおいて、京都大学を主体とする産学連携グループは、耐熱性と樹脂との相溶性に優れた軽量、⾼強度の⾼性能ナノ繊維と、この材料で補強した樹脂複合材料を⾼効率で連続的に製造するプロセス(京都プロセス)を開発。これらの技術をもとに、⽊材や⽵などの原料から樹脂複合材料まで⼀気通貫で製造するテストプラントを京都大学宇治キャンパス内に完成させ、稼働を開始している。2017 年からは、複数の企業や公的研究機関に向けてテストプラントを用いて製造したサンプルの提供を予定している。
経産省 「省エネルギーに関する国際標準化の獲得・普及促進事業委託費(継続)」
期 間 : 2014〜2018年度 予算: 22.0億円(平成29年度) 概要: 省エネルギーに資する製品やシステムなど我が国が強みを有する分野で、国際標準化に関する実証データ・関連技術情報を収集し、国際標準原案の開発・提案や、その過程で得られた知⾒をもとに普及を⾒据えた試験・認証基盤の構築等を実施。この取り組みの一環として、セルロ
690
ースナノファイバーに関する国際標準化事業として、CNFの特性評価・測定方法に係るISOの規格原案を産学官が共同で作成し、ISOに提案する方針である。
環境省 「セルロースナノファイバー等の次世代素材活用推進事業(継続)」 ※経済産業省・農林⽔産省連携事業
実施機関:2015〜2020 予算:33億円(平成28年度)、39億円(平成29年度) 参加機関:環境省、⺠間団体等 事業概要:1)CO2削減のためのCNF導⼊拡⼤戦略の⽴案、2)CNF活用製品の性能評
価モデル事業、3)CNF製品製造工程の低炭素化対策の実証事業、4)バイオプラスチックによるCO2削減効果の検証
事業目的:CNFは、⾃動⾞や家電等に活⽤することで、軽量化に寄与し、地球温暖化に貢献できると期待される。交代熱バイオプラスチックは、耐熱性が要求される⾦属部材を代替することで、軽量化による効果が期待される。CNF やバイオマスプラスチック等の次世代素材について、メーカ等と連携し、実際に CNF製品を搭載して削減効果検証、複合・成型加工プロセスの低炭素化の検証、リサイクル時の検証、リサイクル時の課題・解決策検討等を⾏い、早期社会実装を推進する。社会実装に向けて、⾃動⾞、家電、住宅、建材等の各分野においてモデル事業を実施し、CO2削減効果の評価・検証、関連する課題の解決策について実証を⾏う。
平成29年度 事業概要 (1)社会実装に向けたCNF活用製品の性能評価モデル事業(3,700百万円) 国内事業規模が大きく、CO2 削減ポテンシャルの⼤きい⾃動⾞(内装、外板等)、家電(送⾵ファン等)、住宅・建材(窓枠、断熱材、構造材等)、再エネ(⾵⼒ブレード等)、業務・産業機械等(空調ブレード等)においてメーカーと連携し、CNF 複合樹脂等の用途開発を実施するとともに、社会実装にむけて実機にCNF製品を搭載し活用時のCO2削減効果の評価・検証する。 (2) CNF 複合・成形加工プロセスの低炭素化対策の実証事業(300 百万円)CNF 樹脂複合材(材料)を製造する段階での CO2 排出量を評価し、その削減対策を実証する(乾式製法)。CNF樹脂複合材(材料)を、部材・製品へと成形する段階での CO2 排出量を評価し、その削減対策を実証する。 (3)バイオマスプラスチックによるCO2削減効果の検証(200百万円) 耐熱性が要求される各種機械製品について、⾦属部材等を、⾼耐熱バイオマスプラスチックにより代替
691
することの実現可能性及び CO2 削減効果を検証する(⾃動⾞エンジン周りの部材、家電、業務・産業機械の部材等)。 (4)リサイクル時の課題・解決策検討の実証事業(200百万円) CNF 樹脂複合材(材料)を製造する段階での易リサイクル性、リサイクル材料の性能評価等を⾏い、解決策について実証する。
図 CNF等の温暖化対策に資する次世代素材の社会実装スケジュール
出所:環境省
692
農林省 「「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業(拡充)うち「異分野融合共同研究」
実施機関:2014〜2016 予算:17.3億円 参加機関:農林⽔産省 事業概要: 異⽂化融合発展研究、「知」の集積と活⽤の場による研究開発モデル事業、事業化促進研究
事業⽬的:異分野融合発展研究において、実施課題の 8 割以上が農林⽔産業・⾷品産業の現場で、事業化の可能性が⾒込まれる。(平成 33 年度)「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業において、実施課題の 8 割以上で商品化・事業化が有望な研究成果を創出。(平成34年度) 事業化促進研究において、実施課題の9割以上で事業化。(平成30年度)
図 「知」の集積と活用の場の必要性と具体的な仕組み
出所:農林⽔産省
693
出所:ナノセルロースフォーラム
農林省 「新たな木材需要創出総合プロジェクト(拡充)」うち「⽊質バイオマスの利⽤拡⼤」
実施機関:2015〜2019 予算:各12億円、5億円 参加機関:農林⽔産省、各研究機関、⼤学 事業概要: (1)⽊質バイオマス利⽤⽀援体制構築事業(燃料の安定供給体制の強化等)、
(2)⽊質バイオマス利⽤⽀援体制構築事業(相談・サポート体制の確⽴)、(3)木質バイオマス加⼯・利⽤システム開発事業、(4)⽊質バイオマス加⼯・利⽤システム開発⽀援事業
事業目的: ⽊質バイオマスの利⽤促進を図るため、セルロースナノファイバー等のマテリアル利⽤の促進に向けた技術開発・調査等を支援
694
⽂部科学省 「ホワイトバイオテクノロジーによる次世代化成品創出プロジェクト(化石資源から脱却した次世代の化成品合成一貫プロセスの研究開発)」
実施機関:2016〜2020 予算:53億円 参加機関:⽂部科学省、経産省、⽂部科学省など他府庁、国⽴研究開発法⼈科学技術振興機構(JST)
事業概要:バイオマスから化成品等を製造するホワイトバイオテクノロジーを新たに着手するなど、温室効果ガス削減に⼤きな可能性を有し、かつ従来技術の延⻑線上にない、世界に先駆けた画期的な⾰新技術の研究開発を省庁連携により推進。
事業目的:化学とバイオの融合による新しいイノベーションを目指す。技術ボトルネックの抽出・解決を目指し、5〜10 年後を⾒据えた基盤技術研究。バイオマス由来⾼分⼦を出⼝とした次世代化成品創出に向けた研究開発。
“ナノファイバーが“右⼿と左⼿”を作り分ける新しい不⻫合成法の開発“(研究開発代表者:九州大学大学院農学研究院 北岡卓也教授)
“ナノコンポジット超微細発泡部材の創製”(研究開発代表者:京都大学大学院工学研究科 大嶋正裕教授)
696
⑪ ⽶国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する政
府⽀援策の有無(有る場合は該当箇所)※英⽂で検索できる範囲に限る。
<カナダ> 先にも⾒たように、カナダ政府が⽀援した産学共同ネットワーク“ArboraNano”(2009 年〜2014年)が果たした役割は⼤きく、その後のデモンストレーションプラント建設等の礎となった。カナダ政府はMinistry of Economy, Science and Innovation (MESI)の研究機関支援を通じ、ナノセルロースの産業化を後押ししており、技術開発のアクセラレータ的な機能を FPInnovation、Prime Quebec(旧NanoQuebec、2014年12⽉に組織変更)が担っている。 なお、現在活動中の政府支援プロジェクトに関する情報は収集できなかった。 <米国> USDA, FPLが中心となり、University of Maine, Georgia Tech等とリサーチコンソーシアムを組織しているほか、官⺠パートナーシップ“P3Nano”(The U.S. Enndowment for Forestry and Communities が支援、2016 年予算:2.25MUSD)等の活動もある。ただ、“P3Nano”の 2017年の活動は確認できておらず、Grant関連の検索においても、⽬⽴って⼤きなプロジェクトは⾒られなかった。なお、Georgia Tech の “The nanocellulose research program” は同大学のRenewable Bioproducts Instituteから同大学の歴史の中でも最大規模となる43.6MUSDの研究資⾦を獲得しており、NASAやDoDからも研究支援を得ているDr. Eric Mintz (Chemistry)率いるHigh Performance Polymers and Composites Centerなどのグループが活動資⾦として利⽤している。
697
その他、公的機関支援のナノセルロース関連研究プロジェクトは以下の通り(Federal reporterにて抽出)。なお、機関としては、NIEHS(National Institute of Environmental Health Sciences)、NSF(National Science Foundation)、FS(Forest Service),ARS (The Agricultural Research Service, USDA)が挙げられる。
プロジェクト名
ENGINEERED NANOMATERIALSYNTHESIS, CHARACTERIZATIONAND METHOD DEVELOPMENTCENTER FOR NANO-SAFETYRESEARCH
COLLABORATIVERESEARCH:ENGINEERING OFRECOVERABLE CELLULOSOMESFOR BIOMASS CONVERSION
COLLABORATIVE RESEARCH:ENGINEERING OF RECOVERABLECELLULOSOMES FORBIOCONVERSION
期間Project Start Date: 15-Jul-2016,Project End Date: 30-Jun-2021
Project Start Date: 01-Jul-2016Project End Date: 30-Jun-2019
Project Start Date: 01-Jul-2016Project End Date: 30-Jun-2019
資⾦拠出元NIEHS NSF NSF
予算⾦額 $795,552 $191,934 $206,995
参加機関
LOUISIANA STATE UNIV A & M COLBATON ROUGEProject leader: DEMOKRITOU,PHILIP
NORTH DAKOTA STATEUNIVERSITYProject leader: VORONOV, ANDRIY
UNIVERSITY OF GEORGIAProject leader: MINKO, SERGIY
プロジェクト名
COLLABORATIVE RESEARCH: ANINTEGRATEDEXPERIMENTAL/COMPUTATIONALSTUDY OF THE MECHANICS OFNANOFIBER NETWORKS
COLLABORATIVE RESEARCH: ANINTEGRATEDEXPERIMENTAL/COMPUTATIONALSTUDY OF THE MECHANICS OFNANOFIBER NETWORKS
CREST CENTER FOR RENEWABLEENERGY AND ADVANCEDMATERIALS (CREAM)
期間Project Start Date: 15-Aug-2016Project End Date: 31-Jul-2019
Project Start Date: 15-Aug-2016Project End Date: 31-Jul-2019
Project Start Date: 15-Jul-2016Project End Date: 30-Jun-2021
資⾦拠出元NSF NSF NSF
予算⾦額 $269,833 $312,305 $1,984,542
参加機関
RENSSELAER POLYTECHNICINSTITUTEProject leader: PICU, CATALIN R
UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGNProject leader: CHASIOTIS,IOANNIS
NORFOLK STATE UNIVERSITYProject leader: PRADHAN, ASWINIK
698
プロジェクト名
TECHNOLOGIES FOR IMPROVINGINDUSTRIAL BIOREFINERIES THATPRODUCE MARKETABLE BIOBASEDPRODUCTS
RENEWABLE BIOBASED PARTICLES SUSCHEM: CELLULOSENANOMATERIALS MODIFIED WITHCONJUGATED POLYMERS
期間Project Start Date: 01-Oct-2014Project End Date: 30-Sep-2019
Project Start Date: 19-May-2015Project End Date: 18-May-2020
Project Start Date: 01-Aug-2015Project End Date: 31-Jul-2019
資⾦拠出元ARS ARS NSF
予算⾦額 $1,870,892 $1,643,436 $558,490
参加機関
AGRICULTURAL RESEARCHSERVICEProject leader: ORTS, WILLIAM J
U.S. AGRICULTURAL RESEARCHSERVICEProject leader: JONG, LEI
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTSAMHERSTProject leader: CARTER, KENNETHR
プロジェクト名
SUSCHEM: MATERIAL ANDMORPHOMETRIC CONTROL OFBACTERIAL CELLULOSE VIAGENETIC ENGINEERING, POST-PROCESSING AND 3D-PRINTEDMOLDING
IMPROVE PERFORMANCE,DURABILITY & VALUE OF EXISTINGCOMPOSITES; DEVELOP NEXTGENERATION WOOD OR WOOD-DERIVED COMPOSITES.
ADVANCEMENT OF THE SCIENCEAND USE OF CELLULOSE NANO-MATERIALS
期間Project Start Date: 01-Sep-2015Project End Date: 31-Aug-2018
Project Start Date: 01-Oct-2012Project End Date: 30-Sep-2017
Project Start Date: 01-Oct-2012Project End Date: 30-Sep-2017
資⾦拠出元NSF FS FS
予算⾦額 $390,000 $619,710 $1,038,378
参加機関
MASSACHUSETTS INSTITUTE OFTECHNOLOGYProject leader: ORTIZ, CHRISTINE
US FOREST SERVICEProject leader: CAI, ZHIYONG
US FOREST SERVICEProject leader: RUDIE, ALAN W
プロジェクト名
PAPER AND FIBER PHYSICS ENZYMATIC AND MICROBIALPROCESSING OF WOOD ANDWOOD FIBER TO FUELS,NANOCELLULOSE AND OTHERCHEMICALS
GOALI: BEHAVIOR OF MATERIALSFROM NATURAL CELLULOSEFIBERS AND PLANT RESINS FORAUTOMOTIVE AND OTHERAPPLICATIONS
期間Project Start Date: 01-Oct-2012Project End Date: 30-Sep-2017
Project Start Date: 01-Oct-2012Project End Date: 30-Sep-2017
Project Start Date: 01-Sep-2015Project End Date: 31-Aug-2018
資⾦拠出元FS FS NSF
予算⾦額 $519,189 $859,591 $379,714
参加機関
US FOREST SERVICEProject leader: CONSIDINE, JOHNM
US FOREST SERVICEProject leader: KERSTEN, PHILIP J
UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANNARBORProject leader: ARGENTO, ALAN
699
<欧州> 欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)を対象に
Nanocellulose の研究開発プロジェクトを抽出。プログラムは現⾏の H2020 のほか、一部稼働中のものがあるためFP-7 もカバーした。 なお、北欧諸国(スウェーデン、フィンランド、ノルウェー)は、バイオエコノミーへの転換を政府⽬標とし
て明確に打ち出しており、それぞれ RISE(スウェーデン)、VTT(フィンランド)、NIBIO(ノルウェー)が主導する形で研究開発プロジェクトなども⾏っている。スウェーデンは“BioInnovation”、フィンランドは“Design Driven Value Chains in the World of Cellulose (DWoC) 2.0”、ノルウェーは“NORCEL”イノベーション等のイノベーション・アクセラレーションプログラムを実施ている。
INCOM
Industrial Production Processes for Nanoreinforced Composite Structures
期間 2013.9〜2017.8
資⾦拠出元 FP7-2013-NMP
予算⾦額(EUR) 4,957,734
EU拠出額(EUR) 3,599,997
参加機関
VTT Technical Research Center of Finland(フィンランド)、LULEA TECHNICAL UNIVERSITY(スウェーデン)、FRAUNHOFER SOCIETY FOR PROMOTION OF APPLIED RESEARCH EV(ドイツ)、TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK(デンマーク)、2B Srl(イタリア)、DIEHL AIRCABINGMBH(ドイツ)、AXON AUTOMOTIVE LIMITED(UK)、MILLIDIAN OY(フィンランド)、VMA-GETZMANN GMBH VERFAHRENSTECHNIK(ドイツ)、SurA Chemicals GmbH(ドイツ)、BERGIUS TRADING AB(スウェーデン)、CSI COMPOSITE SOLUTIONS AND INNOVATIONS OY(フィンランド)、EconCore N.V(ベルギー)
プロジェクト内容
NFCの1) 製造/改質プロセス、2)コンポジット化、3)メカニカルテスト・モデリングに関する研究開発を実施。
プロジェクト名
700
AquaComp
Demonstrating the unique properties of new nanocellulose composite forautomotive applications
期間 2015.10〜2017.9
資⾦拠出元 H2020-SMEINST
予算⾦額(EUR) 1,243,125
EU拠出額(EUR) 870,187
参加機関
ELASTOPOLI OY(フィンランド)
プロジェクト内容
Elastopoliが開発したウェットミキシング技術を用いたCNFコンポジット"AquaComp"を⾃動⾞分野等への展開拡大するためのデモンストレーションプロジェクト。
プロジェクト名
BET-EU
Materials Synergy Integration for a Better Europe
期間 2016.1〜2018.12
資⾦拠出元 H2020-TWINN
予算⾦額(EUR) 999,364
EU拠出額(EUR) 999,364
参加機関
UNINOVA-INSTITUTE OF DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES-ASSOCIATION(スウェーデン)、THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE(UK)、NEW ID FCT - FCT INNOVATION AND DEVELOPMENT ASSOCIATION(ポルトガル)、VTT Technical Research Center of Finland(フィンランド)、FRAUNHOFER SOCIETY FORPROMOTION OF APPLIED RESEARCH EV(ドイツ)、PORTUGUESE SOCIETY OF INNOVATION- BUSINESS CONSULTING AND FOMENTO DA INOVACAO SA(ポルトガル)
プロジェクト内容
"paper electronics"をターゲットにAdvanced Functional Materials & Nanotechnologiesに関る、CNFの研究実績を持つ研究機関のコラボレーションプロジェクト。 "a Strategic ResearchAgenda and a Science & Technology Roadmap"の作成も進めていく予定。
プロジェクト名
701
Nano-PieZoelecTrics
Novel Nanoporous PZT Materials for Efficient Utrasonic Biomedical Sensors
期間 2016.11〜2018.11
資⾦拠出元 H2020-MSCA
予算⾦額(EUR) 170,121
EU拠出額(EUR) 170,121
参加機関
UNIVERSITY OF BURGOS
プロジェクト内容
porous PZT-doped using alternative synthetic approaches (EISA method) andnew doping materials (porous Mg-Niobate, Graphene/Molybdenite andNanocellulose) の研究を実施
プロジェクト名
WoodNanoTech
Wood Nanotechnology for Multifunctional Structures
期間 2017.9〜2022.8
資⾦拠出元 ERC-2016-ADG
予算⾦額(EUR) 2,461,947
EU拠出額(EUR) 2,461,947
参加機関
ARTICLE TECHNICAL HOEGSKOLAN(スウェーデン)
プロジェクト内容
"wood photonics"- lighting systems, LED panels, wood lasers, electrochromicwindowsをターゲットとしたバイオコンポジットに関する研究を実施
プロジェクト名
702
NANOSELECT
Functional membranes/ filters with anti/low-fouling surfaces for water purificationthrough selective adsorption on biobased nanocrystals and fibrils
期間 2012.2〜2016.1
資⾦拠出元 FP-7-NMP
予算⾦額(EUR) 5,064,913
EU拠出額(EUR) 3,820,889
参加機関
LULEA TECHNICAL UNIVERSITY(スウェーデン)、VTT Technical Research Center of Finland(フィンランド)、MONETARY MATERIALS AND RESEARCH INSTITUTE(スイス)、UNIVERSITYOF MARIBOR(スロベニア)、FUNDACION CETENA(スペイン)、ACONDAQUA INGENIERIA DELAGUA SL(スペイン)、RISE(スウェーデン)、ALFA LAVAL CORPORATE AB(スウェーデン)
プロジェクト内容
ナノセルロース、ナノキチン等を用いたバイオベースフォーム・フィルター・メンブレン・吸着材の研究開発を実施。
プロジェクト名
NANOCELLUCOMP
The development of very high performance bioderived composite materials ofcellulose nanofibres and polysaccharides
期間 2011.3〜2014.3
資⾦拠出元 FP7-NMP
予算⾦額(EUR) 3,221,075
EU拠出額(EUR) 2,411,183
参加機関
Institute of Nanotechnology(UK)、Cellucomp Limited(UK)、UNIVERSITY OFSTRATHCLYDE(UK)、UNIVERSITY OF COPENHAGEN(デンマーク)、ARTICLE TECHNICALHOEGSKOLAN(スウェーデン)、THE UNIVERSITY OF READING(UK)、SWETREETECHNOLOGIES AB(スウェーデン)、AL.P.A.S. SRL(イタリア)、MONETARY MATERIALS ANDRESEARCH INSTITUTE(スイス)、NOVOZYMES A/S(デンマーク)、Biovelop AB(スウェーデン)、Cellutech AB(スウェーデン)
プロジェクト内容
食品廃棄物由来のNFCのメカニカル特性を活かすためのコンポジット技術等の研究開発を実施。
プロジェクト名
703
ECOPLAST
Research in new biomass-based composites from renewable resources withimproved properties for vehicle parts moulding
期間 2010.6〜2014.5
資⾦拠出元 FP7-NMP
予算⾦額(EUR) 3,941,755
EU拠出額(EUR) 2,820,000
参加機関
FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF INNOVATION, RESEARCH AND TECHNOLOGICALDEVELOPMENT IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF GALICIA(スペイン)、AIMPLAS -RESEARCH ASSOCIATION OF PLASTIC AND RELATED MATERIALS(スペイン)、PIEPASSOCIACAO POLO DE INOVACAO EMENGENHARIA DE POLIMEROS(ポルトガル)、MINHO'SUNIVERSITY(ポルトガル)、FRAUNHOFER SOCIETY FOR PROMOTION OF APPLIEDRESEARCH EV(ドイツ)、TECHNOLOGY RESEARCH CENTER VTT(スウェーデン)、FKURKUNSTSTOFF GMBH(ドイツ)、NANOBIOMATTERS SL(スペイン)、Biomer(ドイツ)、PallmannMaschinenfabrik GmbH & Co(ドイツ)、GROUP ANTOLIN-INGENIERIA SA(スペイン)、MEGATECH INDUSTRIES AMURRIO SL(スペイン)、PURAC BIOCHEM BV(オランダ)
プロジェクト内容
バイオベースコンポジット(PLA、SELP等/ナノフィラー)の⾃動⾞部品への適用を想定した研究開発を実施。
プロジェクト名
SUNPAP
Scale-Up Nanoparticles in Modern Papermaking
期間 2009.7〜2012.9
資⾦拠出元 FP7-NMP
予算⾦額(EUR) 9,809,162
EU拠出額(EUR) 6,765,000
参加機関
TECHNOLOGY RESEARCH CENTER VTT(フィンランド)、PAPER TECHNOLOGY FOUNDATION(ドイツ)、TECHNICAL CENTER FOR INDUSTRY DESPAPIERS CARTONS AND CELLULOSES(フランス)、POLYTECHNICAL INSTITUTE OF GRENOBLE(フランス)、KARLSTADSUNIVERSITY(スウェーデン)、CAVITRON vom Hagen and Funke Verfahrenstechnik GmbH(ドイツ)、Zimmer Maschinenbau GmbH(オーストリア)、Hansa Industrie Mixer GmbH&Co Kg(ドイツ)、POYRY FINLAND OY(フィンランド)、NANOSIGHT LIMITED(UK)、J. Rettenmaier & Söhne GmbH + CO KG(ドイツ)、STORA ENSO A(スウェーデン)、UPM-KYMMENE OYJ(フィンランド)、Ahlstrom research and services(フランス)、Schoeller Technocell GmbH & Co KG(ドイツ)、POYRY MANAGEMENT CONSULTING OY(フィンランド)、他
プロジェクト内容
製紙分野におけるNFC適用に向けた研究開発を実施。
プロジェクト名
704
<ノルウェー/NIBIO>
SUSTAINCOMP
Development of Sustainable Composite Materials
期間 2008.9〜2012.8
資⾦拠出元 FP7-NMP
予算⾦額(EUR) 9,373,540
EU拠出額(EUR) 6,500,000
参加機関
RISE INNVENTIA AB(スウェーデン)、3A TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG(スイス)、BORREGAARD INDUSTRIES LIMITED(UK)、NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFICRESEARCH CNRS(フランス)、ELASTOPOLI OY(フィンランド)、MONETARY MATERIALS ANDRESEARCH INSTITUTE(スイス)、FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY IN LAUSANNE(スイス)、WAVE-KORKEAKOULUSAATIO(フィンランド)、PACKAGING, TRANSPORTATION ANDLOGISTICS INSTITUTE OF TECHNOLOGY(スペイン)、K-TRON SCHWEIZ AG(スイス)、NOVAMONT SPA(イタリア)、PAPER AND FIBER INSTITUTE AS(ノルウェー)、POLYKEMI AB(スウェーデン)、ARTICLE TECHNICAL HOEGSKOLAN(スウェーデン)、SCA R&D CENTRE AB(スウェーデン)、STIFTELSEN SINTEF(ノルウェー)、BASF SE(ドイツ)
プロジェクト内容
メディカル、トランスポーテーション、パッケージング、コンストラクションセクターで幅広く使用することのできるバイオコンポジットの研究開発を実施。
プロジェクト名
プロジェクト名 BioMim- Advancing biomass technology
期間 2015.1〜2018.12
資⾦拠出元 The Research Council of Norway
予算⾦額(NOK) 2,730,000
参加機関
Project Leader: Gry Alfredsen, NIBIO
Partners-Norwegian University of Life Sciences, University of Oslo, Paper and Fibre ResearchInstitute, Borregaard, Kebony, Virginia Polytechnic Institute and State University (VirginiaTech), University of Tennessee, SP Technical Research Institute of Sweden, University ofCopenhagen, Tokyo University of Agriculture and Technology
プロジェクト内容
Work package 1: Raw materials - Preprocessing and characterizationWork package 2: Mimicking the CMF systemWork package 3: The role of LPMOs (and other redox enzymes)Work package 4: CMF-enzyme interactionsWork package 5: Wood protectionWork package 6: Proof-of-concept and LCAWork package 7: Project management and communication
705
<韓国> 韓国では、日本のナノセルローズフォーラム(NCF)のような役割を担う団体や組織が無く、企業、大
学・研究機関がそれぞれの研究のみに取り組んでいる状態である。韓国のナノセルロース分野に関する研究は、2007 年から始まっており、韓国⼭林省傘下の研究機関である、国⽴⼭林科学院で、⼀番活発に⾏われている。同院は、政府機関からの研究予算を受け、⾃主的な研究を⾏っており、⼭林科学研究(R&D)における年間予算は、2017 年時点で 43億円、そのうち⽊材利⽤および産業育成に、前年⽐21%増額された17億円の予算が当てられている。 同院は、2011年から 2016 年までの 5 年間の主な研究成果として、「CNF を適⽤した⾼強度ナノ
ペーパー」、「疎⽔化した撥⽔性・⾼強度ナノペーパー」、「ナノポアネットワーク構造ナノペーパーによるLiB用セパレーター」、「バクテリアナノセルロースを用いた固形状のフレキシブルスーパーキャパシタ」、「ナノペーパーを用いたフレキシブルバッテリ」などを挙げている。2016年8月には、「第3次ナノセルロース・ジョイント・シンポジウム」を開催し、「CNF の⼤量⽣産のためのパイロット製造設備構築に関する研究」、「国産木材を利⽤した CNF の製造特性と優秀な⽊質資源探索研究」、「CNF を適用した包装材の応用」、2017年4⽉の韓国⽊材⼯学会では、「CNFを活用した人工血管・人工骨の開発研究」、「ナノセルロースを適用した高分子複合素材」などの研究成果を発表している。 今後の計画としては、2020 年までに、段階的に CNF の⽣産能⼒を拡充し、⾼付加価値の複合材
料の開発にも取り組んでいくとしており、LG 化学(株)と共同でリチウムイオン電池分野での CNF の活用について研究していくと発表している。
<中国・台湾> 中国語による情報検索を⾏ったものの、ナノセルロースに関する政府政策及び研究開発プロジェクトの情報を得ることはできなかった。
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
参入企業の頁と重複するため、当該項目に関する記載事項なし。
706
(補足)ニュースリリースまとめ
日本 海外2011 SWE/InventiaCNFのパイロットプラントを稼働
FIN/StoraMFCのプレコマーシャルプラントを導入FIN/UPMFibril Celluloseのプレコマーシャルプラントを設置
2012 8 米FPL Maine大学と共同でパイロットプラントを設置2013 10 日本製紙 CNF事業推進室を新設。岩国工場(山口))の実験
プラントを稼働20148 AIST 「ナノセルロースフォーラム」設⽴ 11 加Kurgerセルロースフィラメントのデモンストレーションプラントを稼働
9 大阪ガス CNF/フッ素複合の「フルオレンセルロース」を開発2015 3第一工業製薬 インク用CNF増粘剤を実用化、ゲルインクボールペンで採
用される4 米American
ProcessCNC及びNanofibrilのプレコマーシャルプラント生産を開始
5 米PaperlogicCNFのデモンストレーションプラントを設置
10 日本製紙 世界初となるCNF実用化商品(大人用紙おむつ)を発売
英CelluCompCNFのデモンストレーションプラントを建設
2016 1 モリマシナリー紛体リグノCNFのサンプル供給を開始 NOR/Borregaard
MFCの製造ラインを導入、同年末より稼働開始
4 大王製紙 三島工場(愛媛)のパイロットプラントを稼働 仏ImerysMinerals
MFC,ミネラルをコンポジット化した「FiberLean」を商品化、紙やパッケージングの添加剤として展開
11 北越紀州製紙 加アルバータ州政府とCNCの商⽤材料開発でパートナーシップを締結
蘭SAPPI CNFパイロットプラントを稼働
2017 1 王子HD富岡工場(徳島)の実証実験設備を稼働、サンプル出荷開始
FIN/UPMCNFを添加したハイドロゲル「GrowDex」を細胞培養向けに販売開始
4 日本製紙 石巻工場(宮城)の量産プラント(TEMPO酸化法)を稼働
*各社ニュースリリースならびに新聞雑誌記事から抽出
713
1.ナノカーボンの概要
ナノ材料(Nanomaterial)とは、「少なくとも一次元が 1~100nm のもの」とする定義が多い。金
属、無機材料、カーボン、ポリマーなどがあり、類似する名称としてナノ物質(Nano-object)、ナノ粒
子(Nanoparticle)などがある。同じ物質でもナノレベルまで微粒子化すると、元の性質とは全く異な
る性質が現れるため、種々のナノ粒子が化学・電子・光・触媒等の幅広い分野で応用されている。
カーボンは「古くて新しい」材料と言われる。木炭や石炭などは古代から使用されてきた材料であり、20
世紀初頭にはカーボンブラックや活性炭、20 世紀後半には炭素繊維が工業化されるに至る。さらに、フ
ラーレンやカーボンナノチューブといった次世代材料が発見され、マイクロからナノへと研究領域が進化した。
また、ナノカーボンは共有結合性が強く 0 次元系(フラーレン)、1 次元系(カーボンナノチューブ)、2
次元系(グラフェン)、3 次元系(グラファイト、ダイアモンド)といった化学結合の形態として分類できる。
グラファイトから 1 層だけ取り出したのものがグラフェンであり、それを円筒状に丸めるとカーボンナノチューブ
になる。
ナノカーボンの位置づけ
〔出所:NEDO 資料〕
ナノカーボンの化学結合の形態
〔出所:各種資料より矢野経済研究所作成〕
フラーレン(0) CNT(1) グラフェン(2) グラファイト(3)
715
2.カーボンナノチューブ
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
カーボンナノチューブ((Carbon Nanotube:以下 CNT)は、1991 年に日本電気基礎研究所
の飯島澄男博士(当時)によって発見された。従来の材料ではなし得ない高い導電性と熱伝導性、
強度といった驚異的な特性により、化学的、電気的、機械的な広範にわたる分野での応用が期待され
ている。一般的には直径 1~数 10nm、長さ 1~数 10μm 程度のものを指すが、類似の構造体として
直径 100nm 以上の昭和電工「VGCF」がある。また、CNT は単層 CNT と多層 CNT に大別される。
(ⅰ) 合成方法
CNTの合成方法は触媒気相合成法と炭素固体原料法に大別される。また、触媒気相合成法(触
媒CVD法、単にCVD法ともいう)は浮遊流動反応法と触媒担持反応法に、炭素固体原料法はアー
ク合成法とレーザーアブレーション法に区分される。
浮遊流動反応法はトルエン、ベンゼン、メタンなどの気体原料とガス状にした浮遊触媒を炉内で反応
させる合成方法である。
触媒担持法は流動床法と固定床法(基板法)にさらに分類される。流動床法は細孔を有するアル
ミナ、マグネシア、ゼオライト、シリカなどにナノ微粒子として調製した触媒金属(Fe、Co、Ni、Mo など)
を担持させた反応系を用いものである。担持体によって触媒の安定性を図れるなどの特徴がある。固定
床法は金属触媒を載せた基板(Si など)上に CNT を成長させるものであり、高純度で配向性の良い
CNT を得られる。
アーク・プラズマ法はアーク合成法とレーザーアブレーション法とに分かれる。アーク合成法では大気圧よ
りやや低い圧力の Ar や H2 雰囲気下で、炭素棒の間にアーク放電を行うと陰極堆積物の中に CNT が
得られる。また、炭素棒中に Ni/Co などの触媒を混ぜてアーク放電を行うと煤の中に CNT が合成され
る。
CNTの主な合成法の比較
〔出所:各種資料より矢野経済研究所作成〕
項 目 アーク合成法 浮遊流動反応法 触媒担持反応法
合成方法2本の炭素電極に電圧を加え
て放電させる流動する気相中に浮遊した触媒金属微粒子から成長させる
触媒金属微粒子を坦持させた基板・担体から成長させる
原 料 黒鉛 炭化水素系ガス等 炭素化合物
触 媒 NiY、Co等 Fe、Co、Ni等 Si基板+Fe、Co、Ni等
反応温度 3,000℃以上 700℃ 500~1,200℃
純 度 × △ ○
合成効率 × ○ △
716
eDIPS 法
eDIPS(enhanced Direct Injection Pyrolytic Synthesis method)法は、2 種類の分解
温度の異なる炭素源を用いて単層 CNT を合成する手法である。NEDO プロジェクト「ナノカーボン応用
製品創製プロジェクト」において、2006 年に産総研が開発した。
その工程は、
A) 縦型の電気炉に囲まれた反応管の上部のノズルから有機金属触媒を混入した第一の炭素源
(有機溶剤)をキャリアガス(H2)で噴霧状にして供給するとともに、第二の炭素源(炭化水
素ガス)を第一の炭素源と混合するように供給する。
B) 反応管上部で有機金属触媒が分解し、生成した金属微粒子が浮遊しながら沈降していく。
C) CNT の生成ゾーンに到達すると、炭化水素の分解によって生じた炭素が触媒である金属微粒
子表面に析出することで、単層 CNT が長さ方向に急速に成長する。
D) その後、1000℃以上の成長領域での浮遊時間を 2~3 秒に制御することで太さ方向への成長
を防ぐことで、反応管下部に結晶性に優れた 1~2nm 径で長さ数 10µm の単層 CNT が綿状
に堆積する。
というものである。G/D 比は一般品が 10~20 であるのに対し、eDIPS 法で得られる単層 CNT は
100 以上を示す。純度は 99%以上、長さは 5~10µm。直径は 1~2nm の間で 0.1nm 単位でコ
ントロールできる。
e-DIPs法の概要
718
スーパーグロース法
スーパーグロース(SG)法は、2004 年に産総研の畠賢治博士らが開発した。従来の CVD 法の合
成雰囲気に ppm 程度の水分を添加することで触媒の寿命と活性度を飛躍的に向上させるものであり、
その結果 SG 法で合成される単層 CNT(以下、SGCNT)は高いアスペクト比、高純度、高比表面積、
高配向、長尺などの特長を有する。
SG 法が開発された当初は基板にシリコンウェハを用いていたが、NEDO プロジェクト「CNT 量産化技
術開発」(2006~2010 年度:産総研と日本ゼオンの共同研究)において、より安価な Ni-Fe-Cr
系 Ni 基合金からなる基板を用いることでシリコンウェハと同等の高効率成長が行えることを見出した。ま
た、Fe コロイドを金属基板に塗布するウェットプロセス触媒の形成方法の開発により、プロセスコストの低
減も実現している(当初はスパッタ)。さらに、CVD 炉内の流体シミュレーションモデルの構築やガスシャ
ワー合成システムの導入により A4 サイズの大面積合成技術を確立し、これらの技術知識を駆使した連
続合成炉でSGCNTの連続合成に成功した。SGCNTの炭素純度は99.9%以上、直径は平均約1
~5nm。長さは 100μm 以上、最大数 mm までの長尺化が可能である。
スーパーグロース法の概要
〔出所:産総研 Synthesiology Vol.9 No.3 p165-177(2016)〕
(ⅱ) 分離方法(単層 CNT)
単層 CNT は金属型と半導体型の混合物として合成されるため、電気的な応用を図るうえでは合成
時に金属型と半導体型を作り分ける、あるいは合成後に両者を分離精製する必要がある。現状では選
択的に合成するのは難しく、分離精製による方法が実用化に最も近いとされている。分離精製技術とし
ては密度勾配超遠心分離法、誘電泳動法、カラムクロマトグラフィー法などが報告されている。
719
密度勾配超遠心分離法
密度勾配超遠心分離(Density Gradient Ultracentrifugation:DGU)法は界面活性剤を
ブレンドした単層CNT水溶液を密度勾配遠心分離器にかけ、単層CNTの電気的性質によって溶液を
層状に分離させる手法である。Northwestern University の Mark Hersam 教授らのグループが単
層 CNT とイオン化した界面活性剤が選択的に結合し、単層 CNT の種類によってその粒子の密度の違
いが大きくなることに着目し、2006 年に Nature Nanotechonology に発表した。現在はカナダ・
NanoIntegris Technologies 社が DGU 法により半導体型と金属型を最大 99%の純度で分離さ
せた高純度単層 CNT を販売している。
日本では 2008 年に首都大学東京の柳和宏准教授らが、密度勾配液に多用されている安価なショ
糖を用いて単層 CNT の分離が可能なことを明らかにした。また、界面活性剤の組成や遠心分離におけ
る温度条件の最適化についても報告している。
DGU法による分離の概要
誘電泳動法
誘電泳動(Dielectrophoresis:DEP)は電界とそれにより誘導された電気双極子モーメントとの
相互作用により、粒子が高電界または低電界領域に駆動される現象である。2003 年にドイツ・KIT の
Ralph Krupke 教授らがドデシル硫酸ナトリウム(Sodium DodecylSulphate:SDS)を用いた可
溶化溶液において、誘電泳動による金属型と半導体型への単層 CNT の分離に成功した。
産総研では DNA の分離に利用されているアガロースゲル電気泳動法(2008 年)、電場を用いず
に分離する方法(2009 年)により単層 CNT の分離が可能であることを示した。
カラムクロマトグラフィー法
産総研が、2009 年にアガロースゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによる分離技術を開発した。この
方法で得られる単層CNT の純度は金属型~90%、半導体型~95%。操作が簡便であり、かつカラ
ムの繰り返し利用も可能である。2013 年にはアガロースカラムを用いた手法において、単層 CNT のゲル
720
への吸着力がその電気的性質だけでなく、溶液の環境(pH の増減や溶質濃度)にも依存することを
見出し、単層 CNT とゲルの吸着反応を制御することで分離工程の高効率化を実現した。
アガロースゲルビーズ充填カラムを用いた分離の概要
〔出所:産総研プレスリリース(2009/11)〕
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
CNT が有する高強度、軽量、高熱伝導、高電流密度といった特性、及び電気・電子的な特性がそ
れぞれ多方面で優位性を発揮できると期待されており、その応用分野と用途は多岐にわたる。
CNTの応用分野と用途
〔出所:NEDO「TSC Foresight」2015 年 10 月〕
721
(ⅰ) 単層 CNT
単層 CNTにおいて、金属型は透明電極に用いられる ITO代替などとして用途開発が進んでいる。半
導体型は室温で 10~100cm2/Vs の移動度をもつことに加え、機械的安定性(高強度、弾性体)、
化学的安定性(高耐熱性、耐薬品性)を有することから薄膜トランジスタや不揮発性メモリ、熱電変
換素子、超短時間パルスレーザーなどでの利用が検討されている。
透明電極
透明電極の材料としては、主に酸化インジウムスズ(Indium Tin Oxide:ITO)が用いられる。
ITO は希少金属であるインジウムを用いており、資源の枯渇や国際情勢に依存した供給の不安定性が
懸念されている。また、ITO 膜はもろく、曲げに弱いため、フレキシブルな電子デバイスには利用しにくい。こ
れらの問題を解決するため、ITO 代替材料として CNT の応用研究が進められてきた。
日本では、2013 年に産総研がセルロース系高分子を含む溶剤に eDIPS 法で合成した単層 CNT
を分散させたインクをプラスチック基板上に塗布し、パルス光焼成などの後処理によって高い導電性を示
す透明電極を作成することに成功した。
2015 年にはこの単層 CNT 透明電極の実用化に当たって障害となっていた、導電性の長期安定性
を飛躍的に向上させている。一般的に、CNT 薄膜の導電率は単独の CNT に比べて大幅に劣るため、
硝酸などの酸化剤を少量ドーピングするが、硝酸が揮発することでシート抵抗値が高くなるという課題があ
った。産総研では硝酸の代わりに、ヨウ化銅などの金属ハロゲン化物の薄膜を、CNT 膜の上または下に
真空蒸着法で作成した。さらに、数百 msec のパルス幅の光を照射して薄膜の温度を急速に上昇/降
下させることで金属ハロゲン化物を薄膜内で移動させて透明電極を製膜した。この透明電極は透過率
85%、シート抵抗 60Ω/□という世界最高レベルの透明性と導電性を示す。
現在、単層 CNT を製造するメーカーのほとんどが透明電極、なかでもフレキシブル性を持たせた透明
導電性フィルム向けに金属型の分散液を製品化している。ただ、シート抵抗の均一性と低抵抗化、透過
率向上などが課題となっており、採用が本格化しているとは言いにくい状況にある。透明導電性フィルムの
主力アプリケーションであるタッチパネル向けでは、非 ITO 系透明導電性フィルムとして Ag や Cu、銀塩な
どを使用したメタルメッシュフィルム、あるいは銀ナノワイヤーフィルムなどが一定の需要を形成している。
電気二重層キャパシタ電極
電気二重層キャパシタ(EDLC)は電極と電解液の界面に生じる電気二重層を誘電体として蓄電
するもので、米国 GE のアイディアを基に日系メーカーが実用化した。1980 年前後に NEC や旧・松下
電器産業、エルナーなどが製品化したが、当初はいずれも小容量品で、主にメモリバックアップ用に使われ
た。1990 年代になると HEV 用に大容量 EDLC が検討されたのを契機に大型蓄電デバイスとしての
可能性が注目されるようになり、中~大容量品の市場が立ち上がった。
現在、EDLCの電極材料には主に高純度の活性炭が用いられている。その市場規模はここ数年年率
3%強の伸びを示しており、2014 年に 990t(前年比 103.7%)となった。今後も携帯電話端末向
722
複合材料
ゴム/単層 CNT 複合材においては、日本ゼオンが SGCNT の長尺・高純度という特長を活かし、導
電ゴム複合体、産業用シール部材、シート系熱界面材料の開発に成功している。
導電ゴム複合体は1wt%以下の少量添加で10-4S/cm以上の導電性と50°(Duro-A)以下の
柔軟性を備えているほか、フィラー剥離が生じないことから非汚染性の特長も有する。適用可能なベース
ゴムは NBR、HNBR、ACM、フッ素ゴム、シリコーンゴムなど。レーザープリンターなどの高速化により、これ
まで以上の導電性が求められる導電ロール向けなどでの採用を想定している。
産業用シール部材では SGCNT 添加による耐熱性付与効果を利用し、230℃でも強度低下が小さ
い耐熱ゴム複合体(HNBR)を設計した。
SGCNT 含有のシート系熱界面材料(Thermal Interface Material:TIM)は厚み方向に高
い熱伝導率をもつ。TIM は熱源と放熱材料の間にある微小空隙を埋めるために用いられ、情報処理能
力の高まりとともに発熱問題が顕著化しているサーバーやパワーデバイス中の半導体温度を低下させるこ
とができる。従来、使われていたリース状の材料に熱伝導性の高いフィラーを添加した TIM(グリース系
TIM)は、均一に塗布しにくい、液だれするといった作業性・信頼性での問題があった。
日本ゼオンが 2016 年に開発したシート系 TIM は、添加する SGCNT および黒鉛の量と形状によっ
て 10~100W/m・K の範囲で熱伝導率を調整できるほか、独自の配合技術により高い柔軟性の維持
が可能である。0.1MPa の低圧力下においても良好な密着性を実現し、グリース系 TIM の熱抵抗が
0.10℃/W なのに対し、シート系 TIM では 0.05℃/W を示す。また、シート形状のため工程の簡易化
や生産性向上などの効果を期待できる。現在、日本ゼオンでは量産化に向けた安定生産技術の確立
に取り組んでいる。
熱対策における TIM
樹脂/単層 CNT では産総研と単層 CNT 融合新材料研究開発機構(以下、TASC)が射出成
形可能な PEEK/SGCNT(5wt%)複合材で、世界最高水準の耐熱性(450℃、2hour)と機
械強度(曲げ強度 1.8 倍、引張強度 1.2 倍)を同時に達成した。PEEK はガラス繊維や炭素繊維を
724
添加することにより、荷重たわみ温度を 300℃にまで高めることができるものの、連続使用温度は 240℃
程度であった。この成果により、300℃以下で使用され、より軽量化が求められる自動車部材、航空・宇
宙産業用部材などの用途でのアルミニウム代替を可能とした。
リチウムイオン電池導電助剤
リチウムイオン電池(Lithium-ion rechargeable battery:以下 LiB)導電助剤は多層 CNT
市場を牽引する用途となっている(後述詳細)。LiB の容量は活物質の量で決まるため、導電助剤や
バインダーの使用量を減らすことが好ましく、この点では添加量が少なくて済む単層 CNT は多層 CNT よ
りも有利といえる。一方、セルメーカー間の競争が激しさを増す中、材料コストの低減は必須である。また、
日本や韓国のLiBメーカーは不純物を嫌がる傾向にあるため、純度とコストとのバランスを最適化できるか
が課題となっている。
LiB 導電助剤として単層CNTの採用例は少ないが、ロシア・OCSiAlでは 2015年に韓国電子機器
メーカー「CM PARTNER」が開発した電動バイク向けに供給を開始した。単層 CNT の純度は 75%で
あるが、添加量は 0.1~0.2%程度とごく少量であるため、不純物に関する問題は生じていないようであ
る。
単層 CNT添加の LiB を搭載した電動バイク
725
(ⅱ) 多層 CNT
多層 CNT は樹脂複合材向けを中心に、その市場規模(昭和電工「VGCF」を含む)を拡大させて
きた。ここ数年は LiB 向けが多層 CNT 市場を牽引しており、2015 年(見込み)の応用分野別の需
要構成はエレクトロニクス 16.4%、自動車 8.6%、エネルギー71.4%、その他 3.6%になると推計され
る。具体的な用途は、エレクトロニクス分野や自動車分野が樹脂複合材料、エネルギー分野は LiB 導
電助剤である。
リチウムイオン電池(LiB)導電助剤
LiB に は 、 正 極 の 活 物 質 と し て コ バ ル ト 酸 リ チ ウ ム ( LiCoO2 : 以 下 LCO ) 、 三 元 系
(LiNiCoMnO2:NCM)、マンガン酸リチウム(LiMn2O4:以下 LMO)、ニッケル系(LiNiCoAlO2:
以下NCA)、リン酸鉄リチウム(LiFePO4:以下LFP)などの各種酸化物が用いられている。また、負
極にはリチウムイオンを層間に取り込み可逆的に吸蔵・放出することができる黒鉛系が活物質として主に
使用されている。
黒鉛系は導電性が良好なため、一部の LiB メーカーを除き導電助剤は使用されない。一方、正極の
活物質はいずれも黒鉛より導電性に劣るため、導電助剤を添加することにより LiB の内部抵抗を下げて
いる。また、LiB は充放電のサイクルの進行に伴い放電容量が減少する。この原因の一つとして活物質
粒子間の接点喪失が挙げられ、導電助剤は接点の失われた活物質同士をつなぐ役割も持つ。これによ
り充放電が繰り返されても電極としての形状が保たれることにより導電パスが確保され、結果として LiB の
長寿命化につながる。
727
LiB導電助剤 材料別平均価格
LiB導電助剤 主要メーカー一覧
デンカ
LiB 導電助剤としてアセチレンブラック(製品名:DENKA BLACK)のプ
レス品「FX-35」「HS-100」、及び紛状品を供給している。出力重視の
LiB には一次粒子径が大きくストラクチャの短い「HS-100」、容量重視の
場合は一次粒子径が小さくストラクチャの長い「FX-35」が好まれている。
Imerys
Graphite&Carbon
LiB 導電助剤用として「C-NERGY」シリーズを展開している。カーボンブラッ
クには「Super P Li」をベースに導電性の向上や金属不純物含有量の低
減を図った「SUPER C45」「SUPER C65」、黒鉛粉末には「TIMREX
KS6」をベースに開発した「KS6L」などがある。
ライオン・スペシャリティ・
ケミカルズ
ケッチェンブラックを微粉砕した 3 グレードを揃えている。主力グレードは
「CARBON ECP」。その他、導電性が良好な「CARBON ECP600JD」、
BET 比表面積を小さくしてハンドリング性を向上させた「LIONITE
ECP200L」がある。
日本黒鉛
アルカリ電池やマンガン電池の導電助剤として黒鉛粉末を供給してきた実
績が評価され、2000 年に入り LiB 向けでも採用が始まった。「SP」「UP」と
いう 2 つのシリーズをユーザーに提案している。
昭和電工 LiB 導電助剤として信州大学の遠藤守信教授の指導のもと開発した
「VGCF」を供給している。最近は中国向けの需要が拡大傾向にある。
CNano Technology 2009 年に中国・北京工場で多層 CNT の量産を開始した。「FloTube」
シリーズの商品名で多層 CNT を展開しており、中国市場で先行している。
中国科学院成都有
機 化 学 ( Times
Nano)
2001 年に中国科学院成都有機化学研究所(CIOC)の再編成を通じて
企業化がなされた。2006 年に多層 CNT を LiB 導電助剤として応用する
ことに成功。その後は、中国の大手 LiB メーカーなどで採用が進んでいる。
深圳市三順中科新
材料(SSZK)
中国科学院成都有機化学から技術支援を受け、2013 年に LiB 導電助
剤向けとして多層 CNT の量産化をスタートさせた。
729
<自動車分野>
欧州自動車メーカーを中心にフューエルシステム(燃料フィルタハウジング、チューブ、コネクタ、フューエ
ルフィラーキャップ等)で、燃料の滞留による腐食や静電気による発火の防止などを目的に樹脂/多層
CNT 複合材が採用されている。カーボンブラックを添加するケースもあるが、多層 CNT は添加量の低減
による耐衝撃性の向上などが可能となる。
2009 年にアウディ社が燃料フィルタハウジングに多層 CNT を添加した POM を採用。SAE(自動車
技術協会)が定めた電気伝導度の基準を満たすほか、POM の靭性や寸法安定性、耐摩耗性などの
物性を維持している点が評価された。
ボディ外板では、フェンダー等を樹脂化する際にプライマーレスで静電塗装が可能となるよう、樹脂へ導
電性を付与する目的で多層CNTが用いられる。1990年後半から欧米の自動車メーカーがフェンダー向
けで SABIC Innovative Plastics の PA/PPE「NORYL GTX」の採用を進めた。「NORYL GTX」は
電着塗装の際の 200~210℃という焼成温度に耐えられ、導電性も有するため塗装工程での塗着効
率に優れている。さらに、プレス成形のスチールと比較しデザインの選択肢が大幅に広がるメリットもある。
733
ゴム・エラストマー複合材料
耐疲労性、耐摩耗性の向上などを目的に O-ring、コンベアベルトなどの工業部品で検討が進んでい
る。2009 年には日信工業を中心とした企業グループが表面構造を制御した多層 CNT を複合化のフィ
ラーに用いることで、260℃、240MPa の耐久性を有する超高性能ゴム複合材の開発に成功した。アプ
リケーションは石油探査配管用シール材であり、この複合材を用いることで掘削範囲が格段に広がり、埋
蔵量に対する可採率が格段に上昇。ブラジル沖の大西洋の海溝など、これまで採掘不可能とされていた
油田への掘削も可能とした。
変位センサ
734
また、NEDO では CNT の世界市場が 2020 年に 290 億円(海外 210 億円、日本 80 億円)、
2030 年には 660 億円(海外 540 億円、日本 120 億円)になるとの予測を発表している。
CNTの世界市場規模推移及び予測
〔出所: NEDO 技術戦略研究センター「TSC Foresight」〕
738
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
CNT の用途に中で、既に実用化が始まっている LiB 導電助剤と樹脂・ゴム複合材の求められる技術
特性は以下のとおりである。
LiB 導電助剤
電気導電性
現在、主要用途となっている LiB 導電助剤においては、LiB の容量が活物質の量で決まるため、導電
助剤やバインダーの使用量を減らすことが好ましい。そのため、高い電気導電性により低い添加率で同様
の効果を発現させることが、活物質の高密度化による LiB の高容量化につながる。
純度
導電助剤に鉄系を中心とした不純物が含まれていると、長期保存中に鉄が電解液中に溶解し、これ
が活物質表面に析出して短絡要因になるとされている。そのため、不純物の低減は品質保証・信頼性
の観点から非常に重要である。
樹脂・ゴム複合材
分散性
添加量が多いと樹脂やゴムとしての性質を損なうため、少量添加で高い導電性が得られる材料が求
められている。CNT はカーボンブラックなど既存の導電性添加剤よりも高い導電性を発揮するものの、大
きなアスペクト比とバンドル形成力を解いて樹脂やゴムに均一に分散することが難しく、分散技術が重要
なポイントとなっている。
739
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
(ⅰ)単層 CNT
国内の単層 CNT メーカーは日本ゼオン、名城ナノカーボンの2社である。多層 CNT は昭和電工
(VGCF)が量産段階にあり、大陽日酸、浜松カーボニクス、日立造船、戸田工業、リンテックが事業
化に向けた研究開発やサンプル供給に取り組んでいる。
日本ゼオン
2006 年度より NEDO プロジェクト「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」へ参画し、産総研
とともに「CNT 量産化技術開発」を進めた。2010 年には SGCNT 量産実証プラント(生産能力:
600g/日、産総研つくばセンター内)で 500mm 角の金属基板上で連続合成に成功し、2015 年
11 月に徳山工場(山口県周南市)で SGCNT(製品名:ZEONANO SG101)の量産化を開
始した。SGCNT の生産能力は 2t/年。
また、2015 年 6 月には「ZEONANO SG101」の販売および応用製品の製造販売することを目的に、
100%子会社のゼオンナノテクノロジーを設立した。現在、同社では紛体のほか、分散液(濃度 0.1~
0.5wt%)、高強度耐熱ゴム材料、導電性ゴム材料、帯電防止樹脂材料、シート、導電性塗料をラ
インナップしている。
名城ナノカーボン
2005 年 4 月に設立された名城大学発ベンチャーである。CNT の発見者である飯島澄男教授に、そ
の発見につながる試料を提供した安藤教授らが設立メンバーとなっている。
2014 年に産総研から技術移転を受けた eDIPS 法による単層 CNT の工業生産プラントを尾張瀬
戸工場内(愛知県瀬戸市)に導入し、1 時間におよそ 10g の単層 CNT を合成できる体制を整備し
た。反応条件を最適化するとともに、同社独自の工程を加えることで従来の製造方法であるアーク放電
法に比べ 100 倍の製造スピードを達成し、2015 年に「MEIJO eDIPS」の製品名で供給を本格化させ
た。
740
単層 CNT「MEIJO eDIPS」の基本性能
〔出所:名城ナノカーボン資料〕
この他、名城ナノカーボンではアーク放電法により単層 CNT や CNT 分散液などを製品化している。ア
ーク放電法による単層 CNT は触媒に Ni・Y を用いており、高純度・高結晶かつ直径が均一(1.4nm)
であるといった特長がある。また、首都大学東京の柳和宏准教授らから技術移転を受け、密度勾配遠
心分離法による高効率分離精製技術を確立し、金属型「BlueMetal」および半導体型「Red
Semicon」の開発に成功した。両製品ともに純度は 99%超である。
CNT 分散液は単層、多層、金属型・半導体型といった幅広い製品をラインナップしている。溶媒は水
やエタノール、トルエン、MEK、NMP、IPA など。CNT 濃度は標準品で単層 CNT が 0.1wt%(内容
量:100ml~)、多層 CNT は 2wt%(内容量:1L~)。金属型・半導体型 CNT はともに
1mg/10ml あるいは 1mg/100ml である。
(ⅱ)多層 CNT
昭和電工
昭和電工の「VGCF」は信州大学の遠藤守信教授の指導のもと開発した「Vapor Grown Carbon
Fiber」(気相法炭素繊維)の略称で、同社の商標登録でもある。1996 年に川崎事業所(神奈川
県川崎市)において世界で初めて量産化に成功し、LiB 導電助剤としての販売をスタートさせた。その
後の需要拡大に伴い、生産能力を 2000 年に 40t/年、2007 年に 100t/年、2011 年には 200t/
年へと順次増強している。
2010 年 3 月には樹脂複合材向けに開発した「VGCF-X」(繊維径約 15nm)専用の量産設備
を大分コンビナート(大分県大分市)内に設置した。既存ユーティリティーを活用した 400t/年の生産
体制を整えたが、事業の効率化などを目的に 2012 年 6 月までに同設備を休止し、LiB 導電助剤用に
分散性を改良した「VGCF-H」(繊維径約 150nm)の生産・販売に特化した。
品番 EC1.0 EC1.5 EC2.0 EC1.5-P
形状 繊維状 繊維状 繊維状 繊維状
製法 eDIPS法 eDIPS法 eDIPS法 eDIPS法
炭素純度 >50% >90% >90% >99%
中心直径 1nm(±0.5) 1.5nm(±0.5) 2nm(±0.5) 1.5nm(±0.5)
741
「VGCF」は炭素源と触媒を反応器にキャリアガスとともに供給し、CVD 反応により成長させる。反応
後の焼成・黒鉛化処理によって結晶性を向上させ導電性や熱伝導性、機械的強度を高めるとともに、
金属不純物を除去することで LiB用途への適用を可能としている。「VGCF-H」は「VGCF」を解砕してか
さ密度を上げ、LiB 電極内の分散性を高めたグレードである。
「VGCF-H」 SEM像
大陽日酸
2002 年に科学技術振興機構(JST)の研究成果活用プラザ「中山プロジェクト」において、ガス供
給パートナーとして多層 CNT の大量合成技術の開発をスタートさせた。同プロジェクトでは鉄薄膜触媒
を用いた大気圧下の CVD 法において、成長初期に原料ガスのアセチレンの反応性を高めることなどによ
り 1 秒間に平均高さ 64µm の高速成長を実現した。さらに、2005~2009 年度に大阪府地域結集
型共同研究事業「ナノカーボン活用技術の創成」、2011~2012 年度には NEDO「革新的ナノカーボ
ン材料先導研究開発」といったプロジェクトに参画し、その成果として基板上に垂直配向した多層 CNT
(高配向 CNT)の大量合成技術、分散技術、および高機能フッ素樹脂等の開発に成功した。
大陽日酸が開発した多層 CNT は極めて細い直径(5~20nm、層数 4~12 層)と長尺(最長
で 600µm)であるほか、高い直線性を有する。アスペクト比は 5,000 以上、純度は 99.5%以上であ
る。基板サイズは6インチ。基板挿入からCNT成長までの製造プロセスに要する時間は約10分である。
分散液は溶媒に水、アルコール、及び有機系の MEK 等を用いて作製している。CNT 濃度は 0.05
~5wt%。同社では水系で両性イオン界面活性剤等、有機系ではアクリル系等の分散剤を用いること
VGCF-Hの代表特性
742
多層 CNT ドローイングシート 多層 CNT ワイヤー
戸田工業
分散性に優れた多層 CNT を開発している。2016 年 1 月には広島ガスの海田基地(広島県海田
町)敷地内にある既存の建物を活用し、実証のための設備を導入した。生産能力は月 500kg。
同社の多層 CNT は炭素の結合が切れやすく、溶媒への均一分散が容易であることから LiB 導電助
剤としての採用を想定している。2017 年 11 月には信州大学と共同で、多層 CNT を用いたバインダー
フリーの電極形成技術の開発にも成功した。
LiB には、一層の高密度化に向けた電極内での活物質高充填化の新技術、とりわけバインダーレス
化が求められている。活物質分散技術の進化により導電助剤の添加量低減が進んでいるものの、活物
質を集電箔に固定化し、加えて充放電反応に伴う電極の体積変化を最小限に抑制するためのバインダ
ーを減らすことは難しいとされていた。
戸田工業と信州大学の手嶋教授、是津准教授らの研究グループでは、戸田工業が開発した多層
CNT をバインダーの代わりに用い、信州大学の開発した固定化技術を活用することでバインダーレス化を
実現させた。この技術により電極密度を 3.8g/cm3 まで高密度化でき、信州大学が開発中の高電位
正極と酸化物系負極の組み合わせから構成される LiB では、700Wh/L 以上の体積エネルギー密度を
達成する見込みである(現在は 500-600Wh/L レベルまでの高エネルギー密度化が進んでいる)。ま
た、絶縁性樹脂であるバインダーではなく、低電気抵抗の多層 CNT を用いることにより、電極内電子抵
抗を既存電極の 1/3 以下、集電体界面の抵抗を 1/8 以下に低減することが可能となり、高出力化も
可能となった。
745
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位 5 位程度まで列記)
(ⅰ)単層 CNT
海外の主要単層 CNT メーカーおよび生産能力は以下の表のとおりである。
OCSiAl(ロシア)
「単層 CNT において年間数十万トンの生産を可能にし、価格を 100 分の 1 以下に引き下げられる
量産技術の開発」を標榜し、2009 年にロシアで設立された。生産拠点はロシアのノヴォシビルスク州・テ
クノパーク内にある。「Graphetron 1.0」と名付けられたこの設備は、2013 年 11 月より量産を開始し
た。生産能力は 10t/年。2017 年 7 月にはルクセンブルグ大公国経済省と、250t/年の単層 CNT 生
産施設の建設に関する提携に合意したことを発表した。
同社の単層 CNT「TUBALL」(粉末タイプ)のスペックは直径 1.8±4nm、長さ 5μm 以下、純度
75%となっている。この他、LiB 導電助剤「TUBALL BATT」をはじめ、LiB 集電箔「TUBAL FOIL」や
熱硬化性樹脂向け分散液「TUBALL MATRIX」、コーティング剤「TUBALL COAT」、透明電極向け
「TUBALL INK」などの製品がある。
「TUBALL BATT」」は単層 CNTを NMPや水に分散させており、LCO で 0.06%、LFPおよび NCM
では 0.1%の少量添加による活物質の高密度化が可能となっている。また、また、「TUBALL FOIL」は
単層 CNT で薄膜コーティング(厚み 50nm 以下)されたアルミニウム箔または銅箔であり、2015 年 8
月に市場に投入した。
企 業 拠 点生 産 能 力( t/ 年 )
備 考
OCSiAl ロシア 10 2013年11月量産開始
Wisepower 米国 0.52011年に米・Unidymを買収HiPco法
Raymor Industries カナダ 0.6
SouthWestNanoTechnologies
米国 1 CoMoCAT法
Thomas Swan 英国 1.2
KH Chemicals 韓国 1 CVD法(特許取得)
NanoSoution 韓国 - アーク放電法(能力:1.5~3 kg/月)
単層CNT 主要メーカー生産拠点一覧
747
Wisepower(韓国)
LED 照明や 2 次電池バッテリーパックなどを手掛けていたが、2011 年 1 月に CNT および CNT 応用
製品メーカーの米・Unidym を買収した。Unidym は 2007 年にフラーレンの発見でノーベル化学賞を
受賞したライス大学のリチャード・スモーリー教授が設立した Carbon Nanotechnologies(CNI)と
合併している。旧 CNI では HiPco 法(high-pressure carbon monoxide process)により世界
で初めて高純度単層 CNT の量産を開始しており、「HiPco」ブランドは CNT の基礎研究のスタンダード
な試料となっている。HiPco 法とは高温高圧下で Fe(CO)5 からできる鉄触媒と一酸化炭素を完全
気相反応させるものである。アーク放電に比べ高純度かつ直径範囲の小さい単層 CNT を得ることができ
る。
SouthWest NanoTechnologies(米国)
「CoMoCAT 法」と呼ばれる流動床反応炉を用いた CO 不均化反応によって単層 CNT を作製する。
CVD 法の一つであり、直径分布の非常に狭い単層 CNT の合成が可能なほか、触媒に用いる Co と
Mo の比率によってカイラリティを制御することもできる。主に試料として研究機関等で用いられている。
Thomas Swan(英国)
同社のカーボンナノ材料事業はケンブリッジ大学との連携のもと、2004 年にスタートした。「Elicarb」の
ブランド名で単層・多層 CNT を展開している。単層 CNT の生産能力は 1.2t/年。
KH Chemicals(韓国)
2001 年に韓国の浦項工科大学(通称・POSTECH)出身の夫婦が設立したベンチャー企業であ
る。生産拠点は韓国の江原道江陵(カンルン)市の科学産業団地にある。CVD 法により長尺かつ、
均一な品質の単層 CNT を製造している。生産能力は 1 t/年。反応時間が 10-3 秒と非常に早く短時
間で製造できることから生産効率が高いほか、原料ガスをリサイクルできる工程を確保している。
NanoSoution(韓国)
アーク放電法による単層CNT および多層 CNTの粉末品のほか、CNT 分散液や導電性コート剤など
のアプリケーション製品を展開している。設立は 2007 年。生産拠点は韓国の全州市にあり、単層 CNT
「SA シリーズ」の生産能力は 1.5~3 kg/月。
748
(ⅱ)多層 CNT
海外の主要多層 CNT メーカーおよび生産拠点は以下の表のとおりである。
〔矢野経済研究所作成〕
Nanocyl(ベルギー)
ベルギーを本拠とする CNT メーカーで、2002 年に Namur 及び Liege の大学からスピンオフする形
で設立された。以降、2004 年にパイロットプラントを設置し、2007 年より生産能力 40t/年の実用プラ
ントを稼働した。2011 年からは同 400t/年の本格的な量産プラントを運用するなど、CNT の事業化を
着実に進めている。本社及び製造拠点はベルギーSambreville。R&D 及び製造の施設を 2 か所有し
ており、多層 CNT 専用のプラント(CVD 法、生産能力 400t/年)のほか、開発・試作用 CNT プラン
ト(CVD 法、同 60t/年)、コンパウンド設備(3,500t/年)がある。
同社は多層 CNT の量産グレードとして「NC7000」を展開している。同製品はミクロンサイズに多層
企 業 拠 点生 産 能 力( t/ 年 )
備 考
Nanocyl ベルギー 400開発・試作用CNTプラント(CVD法、同60t/年)、コンパウンド設備3,500t/年
Hyperion CatalysisInternational
米国 200
SouthWestNanoTechnologies
米国 30
Arkema フランス 400 2011年量産プラント稼働
CNano Technology 中国 500 導電性ペースト2,000t/年
中国科学院成都有機化学 中国 200 2014年能力倍増
深圳市三順中科新材料 中国 600 2015年能力倍増
深圳市納米港 中国 200
LG Chem 韓国 400 2017年2月量産開始
JEIO 韓国 100
Kumho Petrochemical 韓国 50 2013年11月量産開始
Hanwha Chemical 韓国 50
HYOSUNG 韓国 40
多層CNT 主要メーカー生産拠点一覧
749
CNT が凝集したパウダーで、これを徐々に解きながらマトリックスに分散させる手法を採っている。主要特
性は以下の表のとおりである。
導電性の高さのほか、ミクロンサイズの凝集タイプであるため、針状のものと比べ安全性が極めて高いと
いった特徴がある。実際、同社は長年、HSE(健康・安全・環境)に関する取り組みを継続的に行って
おり、「NC7000」は欧州 REACH、米国 TSCA、カナダ CEPA 等の化学物質規制に適合した製品とし
て世界各地に供給可能な体制を整えている。
Nanocyl CNTの主要特性
750
中国科学院成都有機化学(中国)
1958 年に創設された中国科学院成都有機化学研究所(CIOC)の再編成により、2001 年に企業
化がなされた。総資産は 36 億ドル以上で、120 人以上の修士・博士を含む 300 人以上のスタッフを
抱えている。1996 年より CNT の量産及び応用研究を開始しており、2003 年には事業部門として中
科時代納米(Timesnano)を設立した。
Timesnano では CVD 法による単層、二層、多層の CNT 粉末、及びシリコン・石英を基板に用いた
CNT アレイ等をラインナップしている。多層 CNT(粉末)の生産能力は 200t/年。2014 年に増強を
図った。また、加工品としてペースト・分散液、塗料、マスターバッチ、エポキシ複合材、繊維、フィルムなど
がある。2011 年からはグラフェンの販売も開始した。
深圳市三順中科新材料(中国)
CNT やグラフェンなどのカーボンナノ材料と応用技術の開発、および製造販売を目的として 2011 年に
設立された。中国科学院成都有機化学公司(COCC)から技術支援を受け、2013 年に LiB 導電
助剤向けとして多層 CNT の量産を開始している。現在の生産品目は多層 CNT の粉末と NMP 及び
水に分散させたペースト、多層 CNT/カーボンブラックの複合品およびグラフェン。工場は深圳市竜華新
LiB用 主要グレード
752
区にあり、2015 年に多層 CNT 粉末の生産能力を従来の 300t/年から倍増となる 600t/年に引き上
げた。
Hyperion Catalysis International(米国)
1982 年設立。1983 年より米国・マサチューセッツ州で多層 CNT「FIBRIL」の生産を開始した。
当初は世界の研究者が「FIBRIL」の粉末を試料に用いていたが、1997 年に安全性を理由に粉末の
提供を中止し、マスターバッチ(あるいはコンパウンド)としての供給に切り替えた。このマスターバッチは多
層 CNT 含有量が 15~20wt%と非常に高く、樹脂希釈する際の均一分散が難しいとされている。現
在の主要用途は IC トレー、HDD 部品トレー、キャリアなどである。
Arkema(フランス)
Arkema グループは世界約 50 カ国・137 の生産点を持ち、High Performance Materials、
Industrial Specialties、Coating Solutions という 3 つのセグメントでグローバルに事業を展開してい
る。多層 CNT は 2003 年に研究を開始し、2006 年にフランス・lacq(ラック)で 20t/年の研究プラン
トを開設した。さらに、2011 年に生産能力 400t/年の量産プラントを稼働させている。同プラントではカ
ーボンリソースとしてバイオエタノールを利用し、触媒を用いた流動床反応器による合成プロセスを採用し
LiB用 主要グレード
753
ている。
同社の多層 CNT「Graphistrength」(パウダー)は直径 10~15nm、長さ 0.1~10µm、層数
5~15。スタンダード品の「C100」と高純度品の「C100 HP」をラインナップしている。「C100」は純度
90wt%超であり、粉末及びマスターバッチとして販売している。「C100 HP」は純度 99.9wt%超を実
現しており、リチウムイオン電池(LiB)等の導電助剤に最適なグレードである。
Hanwha Chemical(韓国)
韓国の大手企業「HANWHA(韓火)」グループの化学部門系列会社であり、樹脂、化成、太陽
光、バイオ医薬品、ナノ素材などを事業分野として持っている。2008 年に CNT メーカー「ILJIN
NANOTECH」を買収し、CNT 事業に参入した。現在は CNT の合成および分散、アプリケーション・複
合材の製造販売など、CNT バリューチェーンの全般に亘る事業展開を行っている。生産拠点は韓国の蔚
山(ウルサン)にあり、多層 CNT の生産能力は 50t/年。もともと単層 CNT と多層 CNT 両方を生産
していたが、現在は採算性と生産性などの問題により単層 CNT は生産を中止した。多層 CNT は
「HANOS」というブランド名で粉末タイプ、分散液(インク・ペースト)、コンパウンド、シートなどを製造販
売している。
Graphistrength® C100 HP Typical properties
754
Kumho Petrochemical(韓国)
韓国の総合石油化学企業であり、合成ゴムをはじめ樹脂、精密化学、電子素材、発電、建材、炭
素素材など多方面にわたった事業を展開している。カーボンブラックを代替する新素材の開発を目指し、
2013 年に量産を開始した。生産拠点は韓国の牙山(アサン)、生産能力は 50t/年。「K-Nanos」
というブランドのもと CNT 粉末、コンパウンド、分散液、CNT 複合材(一部)をラインナップしている。
その他
Applied Sciences(米国)、Catalytic Materials(米国)、Raymor Industries(カナダ)、
Thomas Swan & Co.Ltd.(英国)、深圳市納米港(中国)、LG chem(韓国)、JEIO (韓
国)、HYOSUNG(韓国)などが市場に参入している。
755
⑧ ①の技術開発に携わる国内の大学及び代表的な研究者
日本発の新材料である CNT の技術開発には、以下の表のとおり数多くの大学が携わっている。また、
単層 CNT のスーパーグロース法を見出した畠 賢治氏の所属する産業技術総合研究所においてもナノ
チューブ実用化研究センターを中心に活発な技術開発が進められている。
※ナフラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会名簿、および J-GROBAL を用いて代表的な研究者を抽出。
756
⑨ ①の技術開発に携わる米国・欧州・中国・韓国・台湾の代表的な研究者
及び所属機関
「Google Scholar」を用いて論文検索を行い、海外の CNT 研究者を抽出した。結果は以下のとお
りである。
757
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プ
ロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
経産省
NEDO「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」
期 間 : 平成 29 年度~平成 33 年度
予算 : 39 億 84 百万円(平成 28 年度~平成 29 年度)
参加機関 : 古河電気工業、日本ゼオン、産業技術総合研究所
概要: 有機系機能性材料を対象にマルチスケールシミュレーション等の計算科学を活用して、現
在不足している材料の「構造」と「機能」を結びつけたデータ群を作り出し、マテリアルズインフォマティ
クスと融合することで革新的な機能性材料の創成・開発の加速化を目指す。計算科学だけでなく、
実際に材料を試作するプロセス技術、これまで観測出来なかった計測技術も並行して開発し、機
能性材料の産業競争力の強化にも貢献していく。平成 29 年度より、ナノカーボン材料(CNT、グ
ラフェン)が研究対象に追加された。
文部科学省
ERATO「伊丹分子ナノカーボンプロジェクト」
期 間 : 平成 25 年度~平成 30 年度
予算 : 12 億円
研究総括 : 伊丹 健一郎(名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所・拠点長/
名古屋大学大学院 理学研究科・教授)
概要: ナノカーボンを構造的に純粋な分子として設計・合成するとともに、それらを基盤として圧
倒的に優れた機能性材料を創成し、それらの応用展開まで図ることにより、「分子ナノカーボン科学」
という新分野の確立と、イノベーションの創出を目指す。具体的にはテーマは以下の 3 テーマである。
・テーマ 1:構造が明確に定まったカーボンナノチューブとグラフェンナノリボン、さらには新奇な3次元
湾曲ナノカーボンの精密合成法を開発するとともに、その応用展開を図る
・テーマ 2:走査型プローブ顕微鏡、単一ナノ構造近接場分光イメージング、単一光子計数技術
ならびに X 線結晶構造解析を駆使した単一ナノカーボンの構造・物性解析を行い、ナノカーボンの
構造・物性やナノカーボン間の相互作用を明らかにする。
・テーマ 3:ナノカーボン分子の集合体や単結晶のユニークな特徴を活かした新しい吸着・磁性・光
学マテリアルの創出を目指す。
(補足)研究費の推移
「日本の研究.com」(検索ワード:カーボンナノチューブ、事業開始年度 2004 年度~)で抽出し
た研究課題は 1,620 件にのぼった。
759
Federal RePORTER を用いて、稼働中の CNT の研究開発プロジェクトを調査した結果は以下のと
おりである。
CNTの研究開発プロジェクト(NSF)
プロジェクト名 期間 予算金額(FY) 参加機関
01-Jan-2017
31-Dec-2020
01-Jul-2016
30-Jun-2019
01-Sep-2016
31-Aug-2019
01-Jun-2016
31-May-2019
15-Sep-2016
31-Aug-2018
01-Mar-2016
28-Feb-2021
01-Sep-2016
31-Aug-2019
15-Aug-2016
31-Jul-2018
01-Aug-2016
31-Jul-2019
01-May-2015
30-Apr-2018
15-Sep-2015
31-Aug-2018
15-Feb-2015
31-Jan-2020
01-Jul-2015
30-Jun-2018
01-Jul-2015
30-Jun-2018
01-Jul-2014
31-Mar-2018
RUI: WET PRINTING OF CARBON NANOTUBE-ENHANCED OSMOSIS MEMBRANES FOR WATERDESALINATION
$300,000 CAL POLY CORPORATION
CAREER: SYNTHESIS AND REACTIVITY OFPOLYAROMATIC HYDROCARBON BELTS: TOWARDS ABOTTOM-UP ORGANIC SYNTHESIS OF CARBONNANOTUBES
$400,704 UNIVERSITY OF OREGON
CAREER: ATOMIC-SCALE VISUALIZATION OFEXCITONIC STATES IN INDIVIDUAL CARBONNANOTUBES
$242,198 UNIVERSITY OF OREGON
COLLABORATIVE RESEARCH: CAVITY-ENHANCEDEXCITON EMISSION FROM CARBON NANOTUBES INTHE INTRINSIC REGIME
$341,910STEVENS INSTITUTE OFTECHNOLOGY
SNM: SCALABLE NANOMANUFACTURING OF CARBONNANOTUBE SHEET WRAPPED CARBON FIBERS FORLOW DENSITY AND HIGH STRENGTH COMPOSITES
$1,250,000UNIVERSITY OF TEXASDALLAS
COLLABORATIVE RESEARCH: THEORETICAL ANDEXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF INTER-MOLECULAR FORCES BETWEEN ENVIRONMENTALPOLLUTANTS AND CARBON NANOTUBES
$220,000SOUTHERN ILLINOISUNIVERSITY
UNDERSTANDING HOW INTERACTION OF SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES WITH BIOLOGICALINTERFACES IN THE GASTROINTESTINAL SYSTEMMAY ALTER CHEMICAL BIOAVAILABILITY
$299,999 UNIVERSITY OF FLORIDA
DESIGN AND ANALYSIS OF OPTIMIZATIONEXPERIMENTS WITH INTERNAL NOISE TO MAXIMIZEALIGNMENT OF CARBON NANOTUBES
$150,000 HARVARD UNIVERSITY
COLLABORATIVE RESEARCH: MICROWAVE HEATINGOF CARBON NANOTUBE COATINGS TO ENABLE RAPIDWELDING IN 3D-PRINTED POLYMER STRUCTURES
$150,000TEXAS ENGINEERINGEXPERIMENT STATION
SBIR PHASE II: BORON NITRIDE NANOTUBECYCLOTRON TARGETS FOR RECOIL-ESCAPEPRODUCTION OF CARBON-11 FOR PET/CT MEDICALIMAGING
$749,924 BTI TARGETRY LLC
CAREER: PRECISION CONTROL FOR SUSTAINABLECARBON NANOTUBE MANUFACTURING: ENABLINGNEXT GENERATION MATERIALS AND DEFINING THENEXT GENERATION ENGINEER
$500,000 YALE UNIVERSITY
INTRACELLULAR ELECTROCHEMISTRY WITH CARBONNANOTUBE-BASED SENSORS
$294,103ROCHESTER INSTITUTE OFTECHNOLOGY
SBIR PHASE II: HIGH QUALITY CARBON NANOTUBESFOR RADIO FREQUENCY APPLICATIONS
$750,000 CARBON TECHNOLOGY INC
CATALYST DESIGN FOR (N,M)-TARGETED CARBONNANOTUBE SYNTHESES
$366,433 RICE UNIVERSITY
MANUFACTURING ALIGNED ARRAYS OFSEMICONDUCTING CARBON NANOTUBES FOR FASTERAND MORE ENERGY EFFICIENT NEXT-GENERATIONELECTRONICS
$300,000UNIVERSITY OF WISCONSINMADISON
761
CNTの研究開発プロジェクト(NASA)
CNTの研究開発プロジェクト(NIEHS)
〔矢野経済研究所作成〕
欧州
欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)で CNT の研究開
発プロジェクトを調査した結果、稼働しているプロジェクトはなかった。EU をはじめ、ドイツ、英国などではグ
ラフェンの研究開発に重点的に取り組んでいることが背景にあるものと考えられる。
中国
中国においてもナノカーボン材料として、CNT よりもグラフェンの研究開発を重点化している。現在稼動
中の研究プロジェクトの詳細は不明であるが、2011 年までの「国家ハイテック発展計画(863 計画)」
(現在は国家重点研究計画に統合)や国家重点研究計画の研究プロジェクトは以下の表のとおりで
ある。
ナノテクノロジーに関連した国家重点研究計画における研究プロジェクト(2006~2011年)
プロジェクト名 期間 予算金額(FY) 参加機関
28-Jan-2016
27-Jan-2019
28-Jan-2016
27-Jan-2019
MESOSCOPIC DISTINCT ELEMENT METHOD ENABLEDMULTISCALE COMPUTATIONAL DESIGN OF CARBONNANOTUBE-BASED COMPOSITE MATERIALS
$364,219UNIVERSITY OFMINNESOTA TWIN CITIES
COMPUTATIONAL DESIGN OF CARBON NANOTUBENETWORK MATERIALS AND POLYMER MATRIXNANOCOMPOSITESCARBON NANOTUBE (CNT) BASEDCOMPOSITES CONSTITUTE A BROAD CLASS OFMULTIFUNCTIONAL HIERARCHICAL MATERIALS DERIVINGTHEIR PROPERTIES FROM THE INTIMATE CONNECTIONS BE
$341,094UNIVERSITY OF VIRGINIACHARLOTTESVILLE
プロジェクト名 期間 予算金額(FY) 参加機関
06-May-2014
29-Feb-2020
18-Sep-2012
31-May-2018
09-Dec-2013
31-Oct-2018
SYSTEMATIC ASSESSMENT OF MULTI-WALLEDCARBON NANOTUBES IN PULMONARY DISEASE
$333,000 WEST VIRGINIA UNIVERSITY
CARBON NANOTUBE STRUCTURE-ACTIVITYRELATIONSHIPS FOR PREDICTIVE TOXICOLOGY
$416,133UNIVERSITY OFCALIFORNIA LOS ANGELES
INDUCTION OF NEOPLASTIC TRANSFORMATION ANDCANCER STEM CELLS BY CARBON NANOTUBES
$335,250 WEST VIRGINIA UNIVERSITY
担当部門 研究プロジェクト名
北京大学 カーボンナノチューブによるナノデバイスの開発
中国科学院金属研究所 カーボンナノチューブの構造調製、成長メカニズム及び応用に関する研究 材料
762
「863 計画」における CNTの研究プロジェクト(2001~2010 年)
〔出所:科学技術振興機構「中国の科学技術の現状と動向」〕
韓国
韓国の産業資源通商部は 2010 年に、WPM:World Premier Materia 事業の国策課題とし
て、CNT 含む 10 大素材(WPM)及び、20 大核心部品素材を選定し、2010 年から 2018 年まで
に政府が開発支援としてそれぞれ 1000 億円/200 億円を投資すると発表している。課題の目標は、世
界最初に商業化できる素材・市場を新たに作り出し、持続的な市場支配力を持つ10大素材を開発す
ることである。
同プロジェクトにおいて、CNT の研究開発は韓国科学技術研究院(KIST)の全北分院「炭素融
合センター」(韓国・全州市)を中心に進められている。2009 年からの Step 1 のプロジェクトを経て、
2013 年 11 月に Step 2 のプロジェクトをスタートさせた。Step 2 では炭素融合センターのほか、韓国の
繊維メーカーと CNT アプリケーションメーカーなどが共同で炭素繊維と CNT との複合化によって強度と弾
性を向上させた超強度炭素繊維の実用化を目指している。
また、炭素融合センターでは CNT を紡糸した「CNT 繊維」の製造技術開発を推進している。具体的
な製造方法はウェット方式(湿式)とダイレクトスピニング方式(乾式)の二種類。ウェット方式はCNT
を溶剤に分散させ、粘度を高めにした状態から紡績を行う方法である。ウェット方式は強度の面では優れ
るが、ダイレクトスピニング方式と比べ量産性に欠けるというデメリットがある。一方で、ダイレクトスピニング
方式は、CNT を垂直成長させ、そのまま紡績を行う方法である。同方式では分散処理を別途行わない
ため、CNT 合成から紡績までワンステップ生産が可能であることから、大量生産が容易である。ただし、繊
維における CNT の適切な配分がウェット方式より劣っており、今後、配分性の改善における研究が必要
とされている。炭素融合センターでは CNT 繊維の研究終了時期をウェット方式は 2018 年までに、ダイレ
クトスピニング方式は 2020 年~2025 年までという目標を掲げている。
台湾
中国語による情報検索を行ったものの、CNT に関する政府政策及び研究開発プロジェクトの情報を
得ることはできなかった。
担当部門 研究プロジェクト名
上海大学 カーボンナノチューブを用いるFTC海水淡水化技術の開発
深圳市ナノ有限公司 カーボンナノチューブ導電体の静電防止コーティング用材料の開発
清華大学 高品質の単壁カーボンナノチューブの大量製造技術
南開大学 構造の制御可能な単壁カーボンナノチューブの製造及び電磁遮断ハイブリッド材料 の開発
763
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
CNT は「① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要」で述べた合成方法や分離方法のほ
か、分散に関わる技術が重要である。その強いファンデアワールス力、π-π相互作用のため、基本的には
水にも有機溶媒にも溶けない。
1998 年には海外から化学装飾による CNT 可溶化の報告がなされた。これは、強酸・超音波処理に
よって得た切断 CNT を塩化チオニルと反応させた後、オクタデシルアミンやオクタデシルアルコールとの反応
で長鎖基をもつC18-SWNT を合成する。これが二硫化炭素やジクロロベンゼンに溶解する。ただ、強酸
を用いるなど過酷な環境下となるため、 CNT の物性低下を招くとの指摘がある。その後、
SWNT-COOHとC18-NH2がポリイオンコンプレックスを形成し、テトラヒドロフランやクロロベンゼンに溶解
するといったイオン結合による可溶化が海外で発見された。
CNT可溶化の類型
764
こうした分散技術、あるいは分散剤に係わる技術を保有している企業は以下の表のとおり。また、三菱
商事では CNT の安全性確保に係わる技術を開発している。
〔矢野経済研究所作成〕
保有技術 企業名 備考
KJ特殊紙 高濃度かつ低粘度のCNT分散液を開発
大日精化工業樹脂にCNTを添加して複合材料にした際にCNT
を均一に配合する技術を保有
トーヨーカラー
インキや塗料の製造で蓄積された合成技術とナノレベ
ルの分散加工技術で、新たにCNT漆黒インキ・塗料
用分散体を開発
神戸天然物化学樹脂混練用スラリー、各種溶媒・水分散液、塗料
(UV・熱硬化)、インキ(各種印刷用)を開発
日本資材独自の顔料分散技術を駆使した有機系溶媒の分散
技術を保有
日本ゼオン劣化のない分散技術や孤立・均一分散技術等の研
究開発を推進し、高濃度SGCNT分散液を葉開発
名城ナノカーボン
独自のMN(meijo nano carbon method)法
の開発により水や各種有機溶媒への均一かつ安定的
な分散を実現
東京化成
単層CNT表面への非常に強い親和性を有し、スチル
ベン置換基部位の正電荷により単層CNT を水溶液
中で孤立分散させる分散剤を開発
富士化学
界面活性剤や酸・プラズマ処理などで分散性を高める
従来技術より単層CNTの特性を引き出しやすい無
機系添加剤を開発
東レ
半導体ポリマーと有機溶剤を主成分とした単層CNT
(半導体型)用分散剤を開発。電子移動度を従来
比2.6倍にまで高めた
造粒化技術 三菱商事
低分子量の樹脂を少量添加することにより、CNTを約
2mm径に造粒化(ビーズ化)し、取り扱い上の安全
性確保と生産性向上を実現する技術を確立
分散技術
分散剤
765
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
CNT の合成装置については CNT メーカーが自社で設計・製造しているケースが多いとみられ、外販し
ているのはアルバック、マイクロフェーズなどとなっている。その他、評価装置を島津製作所や堀場製作所が
製造・販売している。
〔矢野経済研究所作成〕
企業名 概要
日本ゼオン 垂直配向CNT(SGCNT )を合成するCVD装置
大陽日酸 垂直配向CNTを合成するCVD装置
日立造船 垂直配向CNT(VA-CNTs)を合成するCVD装置
アルバック マイクロ波プラズマCVD技術を利用した垂直配向CNTの合成装置
マイクロフェーズ 卓上型CVD合成装置
島津製作所 CNTの直径や分散状態などの評価分析装置
堀場製作所 CNT分散溶液の評価装置
766
(補足)ニュース・リリースまとめ(2017 年 1 月~2018 年 1 月 25 日)
〔各種報道資料より作成〕
企業・研究機関 詳細内容
2017 1 産総研 光照射でCNTの薄膜化を可能とする技術を開発
2017 2 東レ 半導体型CNT向け分散剤を開発
2017 2 三菱商事 CNTの造粒化技術の普及に乗り出す
2017 2日本ゼオン・サンアロー
・産総研CNT実用化へ向け新組織を立ち上げる
2017 2 古河電工 CNT電線をモーター用巻線で実証
2017 2 産総研 ナノ炭素材料の安全性試験総合手順書を公表
2017 3 岡山大学 CNTを光触媒に応用
2017 3 産総研 CNTを活用し脂肪燃焼組織を可視化
2017 3 大陽日酸 CNT紡績糸の製造技術を開発
2017 4 名古屋大学 カーボンナノベルトの合成に世界で初めて成功
2017 4 ニッタ CNT/CF複合材を開発、2~3年後の実用化を目指す
2017 4 物材研リチウム空気電池の空気極にCNTを採用し、LiBの15倍の
容量を達成
2017 5 日本ゼオン、古河電工 NEDO事業に参画
2017 6 産総研 CNTとの複合化で耐熱性を向上させたOリングを開発
2017 8 産総研 CNTを用いた電磁波遮断性能を持つ水性塗料を開発
2017 8 東京大学・名古屋大学 フラーレン内包で熱物性の制御ができることを実証
2017 8 三菱電機 家庭用スピーカーにCNT複合樹脂を採用
2017 9 産総研 スーパーグロース単層CNTの生分解性を確認
2017 10 物材研 ホルムアルデヒドを高感度で感知できるCNTセンサを開発
2017 11 東洋インキ CNTを安定的に分散させたスクリーン印刷用インキを開発
2017 12 東京大学 金属電極を使わない両面CNT太陽電池を開発
日付
767
(補足)研究者の動向 ~“PATENTSCOPE”を使用。検索キーワード:カーボンナノチューブ
発明者上位 10 名のうち、日本の研究者としては
が挙げられたが、所属は海外企業ではなく、海外企業・組織に移った形跡はデータベースからは確認できなかった。
768
3.グラフェン
① 指定技術または特定の用途に関する技術の概要
グラフェン(graphene)とは、炭素の同素体の一種であり、sp2 混成炭素原子が六角形のハニカム
格子を形成し、原子 1 個分の厚みを持つ 2 次元シート材料のことである。その存在は古くから知られてい
たが、2000 年代までは単層のグラフェンを分離することは困難とされていた。しかし、2004 年に英国マン
チェスター大学の Andre Geim、Konstantin Novoselov らの研究グループがグラファイト結晶の面をス
コッチテープで剥ぎ取るという物理的で簡便な手法(機械的剥離法)によりグラフェンの単離に成功した。
以来、グラフェンの電気・電子的、機械的、さらには化学的に特異な性質が明らかになり、「夢の材料」と
してさまざまな分野での研究が広がっている。
炭素原子が平面状につながったグラフェンは、同じ炭素の結晶であるダイヤモンドよりも炭素同士の結
合が強いこと、鉄の 200 倍の強い引っ張り強度、熱伝導性及び電気伝導性に優れるといった特性を有
する。こうした特性から、薄膜・高周波トランジスタや化学・バイオセンサーなどの半導体応用、リチウムイオ
ン電池、キャパシター、太陽電池などのエネルギー応用、透明電極、タッチパネル、配線材料などの金属
応用、複合材料、MEMS などの機械的応用、その他熱伝導材料や導電性ペーストなど幅広い分野で
の応用が検討されている。
●グラフェン製造技術
グラフェンの製造方法に関しては、先述したように、グラファイト結晶から機械的に剥離させるスコッチテー
プ法(機械的剥離法)のほか、グラファイトの酸化・還元による化学的剥離法、気相で原料ガスから化
学 的 に 合 成 す る 化 学 気 相 成 長 ( CVD : Chemical Vapor Deposition ) 法 、 MEB 法
(Molecular Beam Epitaxy、分子線エピタキシー法)などの直接成長法、熱分解法などの様々な
製法が報告されている。しかし、グラフェンは幅広い用途展開が期待されているものの、その作製法は未
だに確立されているとは言えず、様々な研究機関・企業では高品質グラフェンの量産化プロセスの技術確
立に向けて研究開発・改良を進めている。
性質 特性 グラフェン 備考
電荷移動度 20万cm2V
-1s
-1 Siの100倍、Cuの150倍
最大許容電流密度 >108A/cm
2 Cuの100倍
面抵抗 <50 Cuの35%未満、CNTの10%未満
厚さ 1原子層 -
重量 0.77mg/㎡ -
ヤング率 ~1.1TPa -
強度 1,100 鉄の200倍、タイヤモンドの2倍
柔軟性/伸縮性 円面積の~20% ITOの場合、1%未満
熱的性質 熱伝導率 ~5000W/mk タイヤモンドの2倍、CNTの1.5倍
光学的性質 透明度 ~98% ITOと同等
(各種資料をベースに矢野経済研究所作成)
グラフェンの主な特性
電気的性質
機械的性質
769
グラファイトの酸化・還元法は化学的処理によりグラフェンの剥離が出来ることから、機械的剥離法に
比べ大量合成に適しており、工業的に安価に合成できるという点では優れた合成法である。
近年では、酸化グラフェン系材料の優れた特性が注目されており、次世代電池材料や潤滑剤、水浄
化用、触媒などの各種機能材料用途への展開が研究されている。こうしたなか、2017年2月に日本触
媒は酸化グラフェン系材料の量産試作に成功した。
酸化グラフェン系材料の合成には、グラファイトの酸化反応を経由するが、強酸溶媒中において強力な
酸化剤を使用することから、従来は大量生産が困難で、研究目的用に極少量が非常に高価な価格
(固形分換算で1万円/g程度)で市販されているのみであある。また工業的な用途開発の遅れから、
その優れた特性が実用化するには至らなかった。日本触媒では、NEDO「低炭素社会を実現するナノ炭
素材料実用化プロジェクト(2010~2016 年度)」で、自社の化学品製造における化学反応を安定
に進行させる制御技術と、共同研究実施先である国立大学法人岡山大学がこれまでに解明した酸化
グラフェンの生成メカニズムに関する学術的な知見を融合させることにより、酸化反応における種々の課
題を解決した。
酸化反応プロセスから得られた酸化グラフェンは、厚さが極めて薄く(炭素原子 1 個分~数層)かつ
数μm 角レベルの大面積という従来にない優れた特性を有している。
酸化グラフェンからのグラフェン薄膜形成法
771
CVD 法
CVD 法は大面積基板に均一に薄膜を形成する方法として広く用いられている。CVD 法は炭化水素
に対し触媒効果を持つ基板を用いる熱CVD法と、マイクロ波などにより生成したラジカルを用いて触媒効
果は持たない基板についてもグラフェンを作製できるプラズマ CVD 法に分類される。
熱 CVD 法では Pt、Ni、Ir、Ru などの遷移金属や Cu の基板を用いて、炭素源に低分子のメチレン、
エチレン、プロピレンや一酸化炭素を 500~1,000℃の温度下で、ガスとして基板上へ吹き付ける。これ
により、炭素原子が基板上に堆積し、この堆積した炭素が基板に触媒が存在する状態で、高温でのアニ
ールによってグラフェンへと成長する。金属基板としては、格子の不整合が約 1.2%と小さい単結晶の Ni
がグラフェン形成に最適とされている。また、Ni 触媒では 1 層目が僅かな原料ガスの注入によって形成さ
れるものの、2 層目以降は時間を要することから層数制御が比較的容易と考えられている。
(出所:NEDOのNews Releaseより)
酸化グラフェン系材料
※データは代表値であって保証地ではない。修飾型酸化グラフェンの性質は官能基により異なる
(出所:NEDOのNews Releaseより)
酸化グラフェン系材料の諸物性表
772
熱分解法
熱分解法は、SiC を真空中で 1,200℃以上の高温加熱を行い、Si 原子を表面から昇華させること
でグラフェンを得る方法である。SiC 基板を 1,000℃以上の高温に加熱すると、表面に残った炭素原子
が自発的にグラフェンを形成する。エピタキシャル成長法によって作製されるグラフェンの寸法はSiC基板の
面積に依存しているため、グラフェンの大面積形成技術として注目されている。
一方、SiC 基板上に成長したグラフェンは層数分布を持つため、層数のグラフェンを大面積かつ均一に
成長させる技術が必要である。また、SiC の表面状態がグラフェン形成に大きく影響し、膜厚、電子移動
度、キャリア密度等の特性を左右するため、その制御が不可欠である。SiC 熱分解法によるグラフェンの
作製は、低エネルギー電子顕微鏡(LEEM:Low Energy Electron Microscopy)を用いて成長
機構の解明や成長条件の最適化を図るとともに、成長雰囲気と成長温度を制御することによる層数均
一化の高いグラフェン結晶を成長させるのが重要ポイントとなっている。
SiCの熱分解法による
グラフェン成長の模式図
775
② ①以外の用途(技術の多義性を考慮した展開及び将来の可能性を含む)
グラフェンは先述したように、電気、光学、機械などの多様な特性を兼ね備えることから、幅広い分野へ
の応用が期待されており、これらの実用化を目指した研究開発が進められている。グラフェンは、これまで
主に導電性材料や放熱材用への製品化開発が進められていたが、近年では、樹脂成形品、塗料、導
電インクなどの添加材用途としても注目されている。
透明電極
炭素原子 1 個分の厚さを持つグラフェンは、原子層レベルの薄さと優れた機械強度、高い導電性と熱
伝導性に加え、希少元素を用いないフレキシブルな透明電極として、ITO 代替の材料として注目されて
いる。現在、グラフェン透明電極の適用に向けて最も開発が進んでいる用途分野はタッチパネルである。
日本では、産総研を中心にグラフェンの透明導電性電極への産業応用に向けた取り組みが進められて
おり、2011 年にグラフェンの低温大面積合成技術を活かし、B6 サイズの静電容量タッチパネルを作製し
ている。グラフェン透明導電膜の特性はシート抵抗値 1~2kΩ/□、透過率 80%。2013 年は昇温温
度の早いグラフェンヒーターの試作品開発を進めるなど、透明電極グラフェンの Roll to Roll 成膜法の開
発にも取り組んでいる。先述したように、2016 年には A4 サイズの大面積グラフェンを開発するとともに、
グラフェン膜を PET フィルムに転写して透明導電フィルムの作製にも成功した(ドーピングなしの状態でグ
ラフェンのみの光透過率 92%(3.6 層)、シート抵抗は 500Ω/□以下)。
区分 具体的用途例 備考
トランジスタ、IC 高周波、高速トランジスタの開発、スピントロニクスへの応用
センサー バイオセンサー、イオンセンサー、赤外線センサーの開発
コンデンサー 高い導電性を活かした電気二重層キャパシタの電極材
RFIDタグ グラフェンインクによるアンテナの印刷
フレキシブルデバイス グラフェンインクによるポリイミドフィルムへの電極形成
LED ガラス基板上にグラフェン層を挿入してLED化
透明電極 ITO代替としてタッチパネル、太陽電池、有機EL等への応用
構造材料 樹脂成形品 強度や帯電防止、抗菌性を活かし、筐体、ギア、ボトル等への応用
リチウムイオン電池 負極材としての研究、開発
太陽電池 透明電極や中間電極材として研究、開発
燃料電池 電極触媒としてPt触媒代替
導電インク タッチパネルやプリンテッドエレクトロニクスへの応用
塗料 静電塗装用プライマーなどへの応用
3Dプリント材料 3Dプリント材料の1つとして研究開発
放熱シート スマートフォン用にモバイルヒートシンクとして製品化
ヒートスプレッタ 半導体用としても開発
光変調器 グラフェン導波路変調器の研究開発
(出所:平成26年度 日本企業の国際競争ポジションに関する情報収集(NEDO,2015))
エレクトロニク
ス
エネルギー
高機能
材料
その他
グラフェンの分野別用途
776
サムスングループは、2010 年 8 月に Sungkyunkwan University(成均館大学)、名城大学の
飯島澄男教授との共同で熱 CVD 法によるグラフェン透明電極(30 インチサイズ)を作製したと発表し
た。この透明電極は CH4 を原料ガスとして Cu 箔上にグラフェンを形成し、熱剥離シートに転写した後に
Cu 箔を硝酸でエッチングする。さらに、熱剥離シートと PET フィルムを接着し PET フィルムにグラフェンを積
層することで作製した。透明で柔らかいグラフェンシートの厚みは 130μm。シートに電極を印刷し、携帯
電話向けタッチパネルも試作した。その後は成均館大学や韓国科学技術院(KAIST)に加え、サムス
ン Techwin(2014 年 11 月に Hanwha グループが買収、現在は Hanwha Tehcwin に社名変
更)、HAESUNG SD などの官・学が連携し、CVD 法による大面積のグラフェンを作製し透明導電膜を
目標に見据えたグラフェン応用研究を進めている。
グラフェン透明導電性膜の形成には、先述した CVD 法のほか、グラファイト酸化・還元法などの適用も
進められている。CVD 法では、大面積の透明グラフェンフィルムが作製可能であるが、銅箔を犠牲触媒と
して用いることに加え、高温または真空中での処理が必要となるため、低コスト化は難しい。一方、グラフ
ァイト酸化・還元法は自動化による大量生産に向いているほか、CVD 法とは違い真空設備が不要であ
るため安価にグラフェンを作製できる。
しかし、グラファイト酸化・還元法によるグラフェンは表面抵抗が大きいという課題を持ち、特にOLEDや
太陽電池の電極として用いる場合、表面抵抗の低減が必要である。こうした中、東芝ではグラフェン超
薄膜と銀ナノワイヤーを用いた透明電極フィルムを開発した。同社はグラファイトから合成した酸化グラフェ
ン(GO)を、親水性石英ガラス上にディッピング塗布した後、水和ヒドラジン蒸気(90℃ホットプレート
上)で処理。その上に銀ナノワイヤー分散液を塗布し、60℃のアルゴン気流下で 30 分乾燥し、さらに、
777
その上にポリマー溶液をコートし真空下乾燥させた後、水中で基板から剥離、乾燥して電極フィルムを得
ている。
銀ナノワイヤーを用いた透明電極は、既にタッチパネル用に実用化されているが、10Ω/□以下の低い
表面抵抗が実現できることに加え、塗布形成と比較的に平坦化し易い。また、フレキシブルであり、使用
する銀の使用量も少ないため低コストに繋がる。さらに、金属グリッドと比べナノワイヤーの密度を大きく上
げられるため、還元型の酸化グラフェン(reduced GrapheneOxide:rGO)膜中のグラフェンドメイン
の欠陥や粒間の影響を小さくすることができるという利点を持つ。
太陽電池
グラフェンはキャリア密度が小さいため、可視光だけでなく赤外光に対する透過率が高い。バンドギャップ
のない半金属のため可視光の吸光度は ITO よい大きいものの、ITO が反射してしまう赤外光を有効利
用できれば変換効率向上につながる可能性がある。また、酸化物であれば酸素が抜けたり、光で分解さ
れるたりする恐れもあるが、グラフェンは酸や光、熱に強く、太陽電池の長期耐久性の向上に寄与できる
ほか、低コストやフレキシブル性、軽量性、機械強度といったメリットから太陽電池用グラフェン電極の実
用化に向けた研究開発も進められている。
グラフェン/銀ナノワイヤ/ポリマー積層透明電極フィルムの特徴
778
マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、2013 年 1 月に酸化亜鉛ナノワイヤー層にグラフ
ェンをコーティングしたフレキシブルシートを用いた太陽電池を作製したと発表した。グラフェン上に半導体ナ
ノ構造を形成する場合、もともとのグラフェンの電気特性や構造特性を損なわないようにすることが難しい
ため、同チームではグラフェンの性質に修正を加えるために、高分子コーティングを利用することにした。これ
によって、グラフェンに酸化亜鉛ナノワイヤー層を接合し、硫化鉛量子ドットまたは有機半導体高分子
P3HT からなる光電変換材料を重ね合わせることができるようになった。
光電変換材料に量子ドットを使った場合、太陽光標準スペクトル(AM1.5G)でのグラフェン太陽電
池の変換効率は4.2%と報告されている。高分子P3HTを使った場合は、同条件で変換効率0.5%。
グラフェン透明電極上への酸化亜鉛ナノワイヤー層の形成には、溶液プロセスを利用している。プロセス温
度は 175℃以下であり、シリコン太陽電池など高温処理を必要とする通常の半導体プロセスに比べて低
温で済むという特徴がある。グラフェンは CVD プロセスで成膜してから高分子層にコーティングする。グラフ
ェンの成膜面積は制約因子とならず、ガラスやプラスチックなど様々な基板に転写できるので、プロセスの
拡張性も高いと考えられる。
OLED 電極
グラフェンを利用した有機発光ダイオード(OLED)電極を作製する研究開発も進められている。
2016 年 6 月に韓国 KAIST の電気工学部、材料科学&工学部等の研究チームは POSTECH と共
同で、二酸化チタン(TiO2)と導電性ポリマーの間にグラフェンを透明電極として用い、高効率で柔軟な
OLED を開発した。
従来のボトム・エミッション OLED では、発光層からの光がデバイスを通って基板に出るために、アノード
が透明になっており、電極材料として ITO が使用される。しかし、ITO は脆いほか、折り曲げなどのフレキ
シブルデバイスでの適用が難しいため、韓国の研究チームは高屈折率の TiO2 層と低屈折率の導電性ポ
リマーのホール注入層との間にグラフェン電極を挟み、複合構造の透明なアノードを作製した。これにより、
OLED の効率と色域の改善につながるほか、低屈折率導電性ポリマーを使用したことで、OLED の表面
プラズモンポラリトンの損失も低減できる。こうしたアプローチにより、グラフェンベースの OLED では、
40.8%の高い外部量子効率と、160.3 lm/W のパワー効率を達成しており、曲げ半径 2.3 ㎜で
1,000 回の曲げサイクル後でも良好に動作が可能であるようだ。
ドイツ・フラウンホーファー協会の研究チームは、2017 年 2 月に CVD 法により、真空中で炭素の 1 原
779
高品質グラフェントランジスタの作製技術を発表した。この方法では従来のリソグラフィ、成膜、エッチング
工程を使って犠牲基板上にゲートスタック配列を形成し、任意の基板に転写。ゲートスタックが転写され
る基板の表面には、グラフェンのストリップを成膜しており、転写されたゲートスタック固有の構造によって、
基板上で自己整合プロセスが起こる。この自己整合プロセスを利用することで、ソース-ドレイン電極の精
密な配置が可能となり、アクセス抵抗あるいは寄生容量を最小化する。グラフェントランジスタの遮断周波
数は 427GHz であり、今後は InP 系など化合物半導体材料を用いた高電子移動度トランジスタ
(High Electron Mobility Transistor:HEMT)並みの性能になる可能性が高いとの指摘が多
い。
一方、グラフェンは単一の層であることから、ハンドギャップを持たないため、高いオン/オフ比が要求され
るデジタル信号用トランジスタとしては利用が難しいという問題がある。そこで、現在はバンドギャップを広げ
るために 2 層グラフェンを使う方法と、グラフェンナノリボンの構造をとるといった方法が試みられている。
グラフェンをナノリボンと呼ばれる細長いベルト状構造にして量子効果でバンドギャップを開く方法は、エッ
チ部の影響が非常に大きく、原子単位でリボン形状としなければならない。そのため実用化は難しいとの
見方がある。
2 層グラフェンに垂直電界を印加する方法では、2010 年に IBM が最大で 130meV のバンドギャッ
プを付与した。また、2012 年 5 月にサムスングループがグラフェンとシリコンのショットキーバリアの高さを制
御することによって、電子移動度を低下させずに電流のオン/オフ切り替えを可能とし、デバイスの電流オ
ン・オフ比 105 を実現した。
日本では、産総研と物質・材料研究機構(NIMS)が 2012 年 12 月に新しい動作原理のグラフェ
ントランジスタを開発した。このトランジスタでは、グラフェン上に 2 つの電極と 2 つのトップゲートを置き、トッ
プゲート間のグラフェンにヘリウムイオンを照射して結晶欠陥を導入した。2 つのトップゲートに独立した電
圧をかけて、効率的に電荷の動きを制御でき、200K(約‐73℃)で、約4桁の電流オン/オフ比を示し
た。さらに、トランジスタ極性を電気的に制御して反転させることができる。この技術は、既存のシリコン集
積回路の製造技術の中で利用でき、将来の動作電圧低減によって超低消費電力化されたエレクトロニ
クスの実現に貢献すると期待されている。
(出所:独立行政法人 産業技術総合研究所の発表資料(2012.12.11))
グラフェントランジスタの概念図
781
東北大学大学院理学研究科・原子分子材料科学高等研究機構(WPI-AIMR)では、2016年
10 月に3次元ナノ多孔質グラフェンを用いたグラフェントランジスタの3次元集積化に成功した。同研究
グループは以前より研究を進めてきた3次元ナノ多孔質グラフェンを用いて電気2重層トランジスタを作
製し、従来の平面構造のグラフェントランジスタと比較して100倍高い伝導度の応答と1,000倍高い電
気容量を示すグラフェントランジスタを開発した。3次元ナノ多孔質グラフェンはシリコン基板に比べて表面
積あたりの重さが1万倍程度軽く、高い易動度から消費電力の低減が見込まれていることから、省電力
かつ軽量・高性能なデバイス開発に寄与することが期待されている。
その他、ハンドギャップを広げる方法として、グラフェンに半径が 10nm 前後の微小な穴を高密度で形
成し、グラフェンを網目状に加工する方法(グラフレオンナノメッシュ)や、グラフェンの表面に水素原子を
部分的に吸着させることで、ナノメートルスケールの高抵抗なグラフェンの領域を高密度に発生させる方法
などもあり、今後も電子移動度を落とさずにバンドギャップを広げることがグラフェン FET 実用化に向けた研
究開発の大きなポイントとなっている。
一方、グラフェンの高い電子移動度を活かし、トランジスタ材料として期待されているものの、先述した
ように、グラフェンはバンドギャップを持たないため、大規模集積回路(LSI)素子としては消費電力の削
減に課題が残る。そこで最近では、太陽電池用と同様に、ハンドギャップを有する次世代の二次元材料
が注目を集めており、その代表として二硫化モリブデン(MoS2)が検討され始めている。こうしたなか、グ
ラフェンはトランジスタではなく、配線材料としての可能性を探る傾向も強くなっている。
電気二重層キャパシター電極
グラフェンは比表面積が大きいため、EDLC 電極に用いればエネルギー密度を向上させることが出来る。
また、高導電性ゆうえに出力密度の増大にもつながることから、グラフェンを用いた大容量・高速充放電
EDLC の開発が進んでいる。現状、グラフェンキャパシターはグラフェンをグラファイトから一枚ずつ単層で剥
離させ、高導電性のナノ粒子をグラフェン間のスペーサーとして導入した開発を進められている。
物質・材料研究機構は、単層 CNT をスペーサーとして用いたグラフェンとの複合化あるいは積層化など
による EDLC 電極の開発に注力している。グラフェンはグラファイトの層間の酸化物による膨張により酸化
グラフェンを剥離し、ヒドラジンにより還元してグラフェンを作製している。得られるグラフェンは剥離性と導電
性が良く、かつ親溶液性といった特長がある。また、グラフェンはグラファイトから容易に作製できるため、
CNT はもとよりリチウムよりも安価であるため、グラフェンの特性を活用し潜在している機能までも活用でき
れば、電気自動車用キャパシターとしての利用も期待されている。一方、現状は高密度のグラフェン積層
を作製することが課題となっている。
782
富士通研究所はグラフェンを使用したガスセンサーに関し、実環境中での特性検証や耐久性調査な
どを行った後、環境センサーとしての実用化を目指す。具体的には、グラフェンと他の分子などを組み合わ
せることにより、二酸化窒素、アンモニア以外のガスの検知も目指している。
2016 年 4 月に発表した NH3 を高感度に測定できるセンサーと組み合わせることにより、生活習慣病
の早期発見を目指した呼気中のガス成分の分析や、携帯可能で高感度なにおいセンサーに適用してい
く予定である。これにより、生活習慣病の早期発見のための呼気中のガス成分を体温計のように手軽に
分析する装置などの実現が期待されている。
NTT 物性科学基礎研究所では、マイクロデバイス技術との融合により、グラフェン表面をアプタマという
特殊な DNA 分子で機能化し、ガンマーかなどの生体内で重要なタンパク質を検出するオンチップ型アプ
タセンサー(バイオセンサー)を考案した。
動作原理は、例えば蛍光色素分子とグラフェンが相互作用すると、蛍光分子の発光エネルギーがグラ
フェンに移動し、蛍光色素が発光しなくなる。このようなエネルギー移動反応を生体分子の反応と巧みに
組み合わせることにより、生体分子の選択的な吸着などの目に見えない現象を光や電気などの測定可
能な物理量に置き換えられる。その結果、同一チップ上での複数タンパク質の同時検出や定量分析が
可能となるというものである。
放熱材料
グラフェンは優れた熱伝導性と機械的強度に加え、フレキシブル性を有しており、電子デバイス用放熱
材料としての応用も進んでいる。グラフェンを用いた放熱応用は放熱グリス、ヒートスプレッドシートのほか、
ポリマーとの複合による熱伝導用グラフェンナノ複合材、塗料やコーティング添加剤などで検討されている。
特に、小型・薄型化と高性能化を両立させる必要があるスマートフォンやタブレット端末などにおいては、
機器内部より発生、蓄積する熱をいかに拡散させるかが重要な課題である。この課題を解決するために、
熱伝導率が高く、機器内部から発生する熱を特定の場所に集中させず、効率よく拡散できるグラフェンで、
熱放散性を改善する取り組みが見られる。また、放熱材料以外に電磁波シールドシートや熱拡散シート、
グラフェンアプタセンサーの構造と動作原理
785
フィルターシート、抗酸化シート、各種機能性シートへの応用も期待できるほか、適度な柔軟性により 3
次元形状への適用も検討されている。
その他
タイヤの添加剤、水濾過、防錆塗料、抗菌材料などの用途でグラフェンの応用研究も広がっている。
グラフェンシートの冷却効果
786
⑤ ②の各用途に求められる技術特性
NEDO 技術戦略センターレポート「TSC Foresight(2015.10)」によれば、グラフェンのもつ二次
元形状と非常に優れた物性を産業化へと繋げるためには、用途先ごとに異なるブレークスルーが必要とな
るとしている。例えば、剥離法と CVD 法、熱分解法はその製造方法が大きく異なるため、適した用途分
野や技術課題が異なる。このため CVD 法や熱分解法によって作製されたグラフェンでは、面状の薄膜と
して用いられるため、電子デバイスなどの製造プロセス技術が適用できる用途が適している。一方、剥離
法によるグラフェンはその形状から、CNT と同様な分散、異種材料との複合化による利用が多いとされる。
用途ごとに求められるグラフェンのサイズと層数及びブレークスルー要素は以下の図のとおりである。
また、同レポートでは市場への波及効果が最も大きいと推定される透明電極、センサー、フォトニクス、
スピントロニクスなどのデバイス関連分野は、幅広い結晶サイズの数原子層グラフェンを合成する技術が
必要であるとしている。透明電極の製品で必要となる導電膜の各用途における価格と性能(電気特性)
についての到達目標を KPI(Key Performance Indicator)として指数化しており、グラフェンを基幹
材料として実用化するためには、量産化技術及び高結晶化技術のブレークスルーにより、現状よりも 2~
3 桁のコストダウンと性能向上が必要となるとの見解を示している。
(出所:NEDO TSC Foresight(2015.10))
各用途先に求められるグラフェンのサイズと層数及びブレークスルー要素
790
(出所:NEDO TSC Foresight(2015.10))
グラフェンの導電膜利用におけるKPI
●理論性能達成には、高結晶化技術にブレイクスルーが必要(金属・炭素材料を凌駕する力学・熱・電気特性)。
●基幹材料化には、量産化技術にブレイクスルーが必要(価格を一万分の一)。
791
⑥ ①に関係する国内企業、及び各企業の有する製品(研究開発中のものも含む)
グラフェンプラットフォーム
世界で初めて黒鉛(グラファイト)の結晶構造の変化がグラフェンの剥離生成に大きく影響することを
発見し、黒鉛材料「グラフェン前駆体」の製品特許を取得した。ある特定の結晶構造を持つグラフェン前
駆体を原料に用いて、通常の剥離プロセス(超音波、超臨界、高圧噴射、衝突、磨砕、酸化・還元、
マイクロ波(イオン液体中)、混練など)を行うと、一般的な黒鉛から直接剥離するのに比べ、生産効
率が劇的に向上できるメリットを有する。グラフェン前駆体は一般的な黒鉛と比べて結晶性が低く、剥離
しやすいことが理由であり、従来の剥離法で必要であった濃縮工程を経ずとも、高濃度のグラフェンを大
量生成でき、生産性の高さによる製造コストの低減にも繋がる。
黒鉛の結晶構造は、試料に X 線を照射したときの X 線の散乱・干渉によって生じる回折現象を調べ
る手法(X 線回折)で知ることができる。グラフェンプラットフォームでは、グラフェン前駆体は X 線回折で
測 定 し た 黒 鉛 結 晶 中 の 六 方 晶 ( Hexagonal ま た は AB Stacking ) お よ び 菱 面 体 晶
(Rhombohedral または ABC Stacking)の積分強度を比較し、菱面体晶の比率が 31%以上の
黒鉛材料と定義している。菱面体晶の比率が 31%以上の結晶構造をもつグラフェン前駆体は、同社の
特許製品であると同時に、このグラフェン前駆体を用いて製造された次ページの製品群についても併せて
自社の特許として取得している。
天然黒鉛からの高品質グラフェン量産技術(グラフェンプラットフォーム社特許)
792
インキュベーション・アライアンス
従来製法である CVD 法に比べ、高い生産性でナノカーボンの合成が可能な高速 CVD 法(InANA
法、特許出願済み)を開発している。同技術により原材料や触媒を変更することで、CNT に限らずフラ
ーレンやグラフェンなどのどんなナノカーボン材料でも大量生産を可能としており、グラフェンでは、高純度の
グラフェンフラワーを展開している。同製品は無基板・無触媒で花のようにグラフェンを成長したもので、黒
鉛からの剥離や黒鉛層間化合物からの膨張によるものではないため、純度が高く高品質である。また、
目的に応じた溶媒を使用して高純度の分散液での提供も可能である。
また、積層数が少なく、紐状のチューブ構造のグラフェンチューブやグラフェンクロス、グラフェンシートなども
ラインナップしている。
区分 詳細用途
蓄電製品 リチウムイオン電池等の二次電池、キャパシター、コンデンサー
導電性製品 導電性インク・ペースト、透明導電膜、電池電極部材等
熱伝導製品 ヒートシンク・スプレッダー、放熱材、シートヒーター等
強化複合製品 強化・高機能プラスチック、高機能ゴム・セラミックス素材、強化コンクリート等の建築資材等
潤滑物質 エンジンオイル、軸受けグリース等
(出所:グラフェンプラットフォームニュース)
793
仁科マテリアル
岡山大学発のベンチャー企業である仁科マテリアルは、2015年7月に高性能電池の電極などへの応
用が期待される酸化グラフェンを効率よく作る技術を開発した。新合成法は黒鉛を硫酸に入れた後、酸
化剤を加えて混ぜたり加熱したりする。従来の工法では加熱温度を 70℃以上にすると爆発しやすい物
質が出来るため、酸化グラフェン 100g を作るのが限界で、精製するまでに 20 時間ほどかかった。同社で
は酸化剤の量や加えるタイミングなどを工夫し、合成効率を高める条件を見つけ、1 日あたり 2kg ほど作
ることを可能とした。
仁科マテリアルは同技術を活かし、透明電極(太陽電池・タッチパネル)、ポリマー補強材、触媒担
体、機能性薄膜などを主要用途とする酸化グラフェンと、酸化グラフェンに金属ナノ粒子を担持する金
属・酸化グラフェン複合体を開発している。
酸化グラフェンの製品名は「Rap GO(TQ-11)」。要望に応じて水以外の溶媒に分散させることも
可能としている。そのほか、分散性が高い酸化グラフェン「Exfoliated GO」、酸性酸化グラフェン「Rap
Go(TQ-11)」、サイズ 10~30μm の「Large-size GO(TQ2)」、塩基性酸化グラフェン「Rap
bGO(TQ-11)」、乾燥酸化グラフェン「Rap dGO」、還元型酸化グラフェン「Rap rGO」、還元型 GO
紙面吸着タイプ(Rap rGO on Paper)、活性化グラファイトなどもラインアップしている。
2017 年 8 月には複数の国内の化学大手と酸化グラフェンの量産化での交渉を進めることを発表した。
高い再現性と安全性を担保した自社技術と化学大手が持つ酸化技術を融合させ、量産化によって潤
滑油添加剤への応用のほか、リチウムイオン電池の電極、熱伝導材料での用途開拓を想定している。
アイテック
アイテックは機能性ナノ粒子・材料創製や、超臨界水関連装置の製造などの高温高圧技術における
最先端ノウハウを活かし、複層構造のグラフェンコンポジットシートである「iGurafen」を開発に成功した。
2014 年 2 月に生産を開始し、現在では「iGurafen-α」、「iGurafen-Σ(SUMO)」、「iGurafen-
αS」をラインナップしている。
「iGurafen-α」は複層構造を有するため安価であるほか、高い電気・熱伝導性を持ちつつも樹脂に練
りこみやすい。熱伝導率はエポキシ樹脂への 50wt%充填にて、汎用アルミニウムと同等の 100W/mK
を達成しており、電気抵抗率は 0.0028Ω・cm と極めて良好な特徴を有する。樹脂と共にコンポジット
材料を作製し、ヒートシンク、放熱シート、導電性膜、スーパーキャパシター、電磁遮蔽等に用いることが
できる。
「iGurafen-Σ(SUMO)」は高熱・電気伝導度を持つ「iGurafen-α」の製造技術をベースに、独
794
自の SMOREX (Simultaneous Surface Modification and Rapid Expansion) 法を用いて開
発した。同製品は樹脂などとの親和性を高めるために、特殊な表面処理を施している。「iGurafen-α」
は炭素のみからなる素材であるため、そのままではコンポジットを形成することが困難な場合があるが、独
自の表面処理を施すことでそうした問題を解決した。
「iGurafen-Σ」は粒子表面が有機化合物で覆われており、表面の化学的親和性が高いのが特徴で
ある。熱伝導率は 50wt%充填で 61W/mK、電気抵抗率は 0.0073Ω・cm。樹脂などへの練りこみ
の際の分散性にも優れている。「iGurafen-α」と同様にヒートシンク、熱伝導性シート、導電性膜、スー
パーキャパシター、電磁遮蔽等への応用が可能なほか、「iGurafen-α」では樹脂とうまく混練できない用
途での使用も可能である。
「iGurafen-αS」は粒子径が 3~30μm と、「iGurafen-α」と比べ小さい粒子径を持つことが特徴で
あり、塗料やインキ関連のコーティング剤への応用に適した材料である。
ADEKA
2015 年 10 月に東京大学の研究グループが開発した「グラフェンの製造技術に関する特許」の独占ラ
イセンスを取得し、グラフェンの本格的なサンプル提供を開始した。同技術は短時間に高い収率で、高濃
度かつ高品質なグラフェンが得られることが特徴である。
この独自技術によって製造された「グラフェン分散液」の濃度は従来と比べて約 20 倍と、世界最高水
準の濃度を達成している。また、イオン液体を除去し、粉末品として取り出す技術を確立しており、粉末
での提供も可能である。粉末品は使用目的にあわせて簡便な方法で高品質なグラフェンに戻すこともで
きる。エネルギーデバイス用の電極や樹脂シート・フィルムのほか、さまざまな分野での用途拡大を見据え、
2020 年までの商業生産を目指している。
アイテックの「iGurafen」製品一覧
795
カネカ
2015 年 7 月に単層 CNT 融合新材料研究開発機構(TASC、2017 年 3 月に解散)が多層グ
ラフェンの開発に成功したことを発表した。このプロジェクトは、TASC の組合員であるカネカを中心に研究
が進められ、開発品の多層グラフェン(厚さ約 1μm)は大型粒子加速器のビーム形状測定センサー材
料として実装された。2015 年 8 月より高エネルギー加速器研究機構(KEK)への供給を開始している。
大阪ガス
石炭由来の「フルオレン」を水などと混ぜて添加剤に使い、黒鉛と高速で衝突させてグラフェンを取り出す
技術を確立している。真空装置などが不要となるため、グラフェンの価格をおよそ半分に引き下げられるほ
か、生産性も従来の2倍以上に高められる。量産化により1kg あたり1万円以下の価格を目指してお
り、2016 年 1 月には樹脂メーカーや電子機器メーカーなど約 10 社へのサンプル提供を開始した。
【グラフェン分散液】 【粉末品】
ADEKAのグラフェンサンプル品の外観
高品質多層グラフェンとその製造方法
796
⑦ 米国・欧州・中国・韓国・台湾の①に関する主要企業(競合企業を把握できるように、
世界シェア、出荷額等からランキング。上位 5 位程度まで列記)
グラフェンに関する主要企業は以下のとおりである。
地域 企業名 備考
Angstron Materials
・2007年に設立
・世界最大の高品質グラフェン・ナノプレートレット製造メーカー(化学剥離幅
1~50μm、厚み1~100nm)
Vorbeck Materials
・2006年にプリンストン大学の研究チームが開発した「Vor-X Graphene」
をベースにした導電性インクを開発し設立
・2009年に世界で初めて米国環境庁にてグラフェン使用製品の承認を取得
・「Vor-ink」はグラフェン層の分離によって作製しており、強度と電気伝導度
に優れる
Graphene Supermarket
・CVD equipmentとGraphene Laboratoryのグラフェン製造及びマーケ
ティング部門を提携して設立
・グラフェン・ナノプレートレット、CVDグラフェン、グラフェンパウダー及び二硫化
モリブデン(MoS2)等の2次元素材の製造技術を確保
XG Sciences・グラフェン・ナノプレートレットの量産工程及び製造技術を確保
・2012年に韓国ポスコの資本出資により、同会社の傘下に入る
NANOCS 炭素含有80%以上のシングルレイヤーグラフェン製造技術を確保
Nanolntegris ナノグラフェン水溶液、MONO(1~2層)、QUATTRO(3~4層)
Graphene Laboratories
・3Dプリント用などの開発
・グラフェンを中心に、窒化ホウ素 (BN)、六方晶窒化ホウ素 (h-BN)、二硫
化モリブデン (MoS2)、二硫化タングステン (WS2) 等を取り揃えている
・Graphene Supermarketの製品を取り扱う
American Graphite Technologies 3Dプリント用等の開発
Lomiko Metals(カナダ) グラファイト、グラフェン、3Dプリント用等の開発
Graphenea 酸化グラフェン、CVDによるグラフェン単層膜を販売
Graphene Nanotech 化学的剥離法による単層グラフェン等を製作・販売
イタリア Graphos 酸化グラフェン。300μmサイズまで製造可能
Graphene Master 単結晶グラフェン膜。CVD法による高面積成長法
Hqgrahene 2次元材料結晶を販売。剥離グラフェンも取り扱い材料の1つとして取り扱う
Applied Graphene Materials
・2010年にイギリスのDurham UniversityのKarl Coleman教授が開発
したグラフェン製造プロセスをもとに設立
・ボトムアッププロセスによるグラフェンパウダー、グラフェン・ナノプレートレット、分
散液を製造
Haydale Graphene Industries 低温プラズマ法によるグラフェン作製。CNTも製造
北米
スペイン
オランダ
英国
798
〔矢野経済研究所作成〕
地域 企業名 備考
The Sixth Element(Changzhou)
Materials Technology
・2011年に設立
・酸化グラフェン、グラフェンパウダー、CVD法によるグラフェンフィルムを製造(グラフェ
ン年間100t、参加グラフェン年間260tが生産可能)
・静電容量タッチパネルを製造するWuxi Garphene Filmを子会社として持つ
Ninbo Morsh Technology
(宁波墨西科技有限公司)
・2012年にShanhai Nanjiang Group(上海南江集团有限公司)によって
浙江省のNinboが設立。NinboはShanhai Nanjiang Groupの重慶研究所で
開発された技術を利用しグラフェンを製造
・2013年に300t/年のグラフェン製造ラインを構築
・グラフェンを用いたタッチパネル(15”炭層グラフェンフィルム)を製造・販売する
Chongqing Morsh Technologyにグラフェンを供給
XP Nano Material
・1998年に設立した会社
・CNTやグラフェン等の炭素ナノ材料の製造及び販売を行う
・多様なグラフェンパウダーをラインナップ
Jiangnan Shimoxi Academe
(江南石墨烯研究院)
・中国常州市が出資し2011年に設立した科学研究事業団体(約1.4万㎡規模
の総合研究開発センター)
・グラフェンの基礎研究及び工業化への製造プロセス研究を行う
2D Carbon(Chanzhou) Tech(常
州二维碳素科技股份有限公司)
・2011年12月に設立し、グラフェンフィルム及びタッチパネルを専門に研究開発・生
産
・120件以上の特許技術を保有。中国で上場したグラフェンメーカーの1つ
Chinese Academy of Sciences
Chongqing Green Intelligence
Technology Academe(中国科学
院重庆绿色智能技术研究院)
・2014年に中国政府傘下研究機関として設立
・3Dプリント、グラフェン等の次世代素材、部品関連研究開発を行う
N-BARO Tech・ナノ化合物をメインに生産
・化学的剥離法によるグラフェンを製造(50kg/Day)
Hanwha Chemical
・PE、PVC等の高分子化合物製造メーカー
・2007年よりナノ粒子、CNT、ナノ電子インクを開発し量産中
・XG Sciencesの株を取得。XG Sciences社のグラフェンをインドや中国等のアジ
ア地域向け販売権利を取得
Heasung DS
・1984年に設立。半導体用リードフレームの製造を主要事業としている
・2014年にサムスンTechwinから事業譲渡し、グラフェン製造を開始(CVD法)
・2015年に世界初に34”の大面積グラフェンを開発。グラフェンシート及び酸化グラ
フェンを製造・販売
Daejoo Electronic Materials
・2014年11月にイギリスのOxford大学と共同でグラフェンの工業化を推進
・酸化グラフェン及び還元グラフェンの量産技術を確保。GO、rGO、W-GO、W-
rGOの製品を販売している
・太陽電池用グラフェン電極、グラフェンインクを開発
IDT International
・2008年に化学的剥離によるグラフェンの製造プロセスを研究(グラファイトの酸
化・還元法)
・2012年に設立。2013年5月に韓国産業通商部のグラフェン部品・素材開発に
参加。グラフェンと酸化グラフェンを生産・販売
Iljin Group R&D(グラファイト酸化・還元法、CVD法)
SKC R&D
Standard Graphene 酸化グラフェン
マレーシア Graphene NanoChem
・燃料添加剤及び油田化学製品を扱うアドバンスケミカル事業と、グラフェン等のナ
ノ材料を取り扱うアドバンスマテリアル事業を展開
・グラフェンは独自のボトムアップ化学合成工程による製作。導電性インク、ゴムやポ
リマー等のグラフェン複合材料がメイン
韓国
中国
799
世界シェア
世界主要グラフェンメーカーの出荷額及び売上高については、情報入手が難しいため、主要メーカーの
市場シェア予測は困難である。しかし、機械的強度に加え、優れた熱伝導性と高い電子移動度などのグ
ラフェンの特性を活かし、多様な用途への応用可能性を見出してきた北米・欧州企業が世界グラフェン
市場で高いシェアを確保していると推定される。
一方、中国では豊かなグラファイトの生産量に加え、グラフェン関連事業における中国政府の優遇策
や助成金などにより研究開発が活発化している。中国粉体技术の統計資料では、中国でグラフェンの研
究開発及び生産、応用分野に関連する企業数は約 400 社程度と、世界のグラフェンメーカー数の 3/4
を占めているとしている。
800
⑩ 平成 29 年度時点に実施されている①の技術が関係する政府予算による研究開発プ
ロジェクトの概要(事業名、概要、予算規模、事業期間、関係機関及び研究者)
文部科学省
・CREST「二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資する基盤技術の創出」
※グラフェン関連の採択分(平成 27 年度)
革新的デバイス創製のためのグラフェンナノリボンのテイラーメイド合成
期 間 : 平成 27 年度~平成 32 年度
予算 : 平成 29 年度:25 百万円 ~ 83 百万円
研究代表者 : 佐藤 信太郎(富士通 アドバンストシステム開発本部 本部長付)
概要: トップダウンでは困難な幅とエッジが制御されたグラフェンナノリボン(GNR)のボトムアップ合
成技術を開発し、応用に応じた GNR のテイラーメイド合成を実現することで、革新的デバイス創製
の基礎とする。
糖鎖機能化グラフェンを用いた二次元生体モデルプラットフォームの創成
期 間 : 平成 27 年度 ~ 平成 32 年度
予算 : 平成 29 年度:25 百万円 ~ 83 百万円
研究代表者 : 松本 和彦(大阪大学産業科学研究所 教授)
概要: 糖鎖分子を結合したグラフェン上で、ウイルス感染過程を高精度・定量的に再現する。こ
れにより鳥インフルエンザウイルスがヒト感染性を得て世界流行を起こすメカニズムを解明し、インフル
エンザ診断の迅速・高感度化の実現を図る。
・科学研究費補助金 新学術領域研究(研究領域提案型)
原子層科学の推進
期 間 : 平成 25 年度~平成 29 年度
予算 : 平成 29 年度:36.53 百万円
研究代表者 : 齋藤 理一郎(東北大学理学研究科 教授)
概要: 炭素の 1 原子層であるグラフェン、また六方晶窒化ホウ素 h-BN、二硫化モリブデン
MoS2 原子層などとの原子層複合系(以下原子層と表記)において、 (ⅰ) 原子層の合成法の
確立(化学、工学)、(ⅱ) 原子層固有の物性の探求(物理、工学)、(ⅲ)原子層デバイスへの応
用(工学、物理)、(ⅳ)原子層電子状態の理論の構築(物理、化学)の 4 つの分野を有機的に連
携させ、総合的探求を行う。
(補足)研究費の推移
「日本の研究.com」(検索ワード:グラフェン、事業開始年度 2004 年度~)で抽出した研究課
題は 1,149 件にのぼった。
804
⑪米国・欧州・中国・韓国・台湾の政府(技術)戦略及び主に技術開発に関する
政府支援策の有無
米国
米国のナノテクノロジー政策は、2001 年の「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(National
Nanotechnology Initiative:NNI)」、2003 年の「21 世紀ナノテク研究開発法」の下で推進され
ている。グラフェン関連のプロジェクト一覧は以下の表のとおりである。
CNTの研究開発プロジェクト(NSF)
プロジェクト名 期間 資金拠出元 予算金額 参加機関
15-Sep-2016
31-Aug-2019
01-Sep-2016
31-Aug-2018
01-Aug-2016
31-Jul-2020
15-May-2016
30-Apr-2019
01-Sep-2016
28-Feb-2018
01-Aug-2016
31-Jul-2019
01-Jul-2016
30-Jun-2019
09-Aug-2015
30-Apr-2019
01-Feb-2016
31-Jan-2021
01-Jul-2016
30-Jun-2019
01-Aug-2016
31-Jul-2018
EAGER: INTERFACING NANOTUBES AND GRAPHENEINTO ORDERED CRYSTALLOGRAPHICORIENTATIONS THROUGH SUBSTRATE-INDUCEDSTRAIN
NSF $137,610 UNIVERSITY OF KENTUCKY
ELUCIDATING THE IMPACT OF ELECTROSTATICINTERACTIONS AND NUMBER OF LAYERS ON THEMECHANISMS OF ION INTERCALATION ONGRAPHENE ELECTRODES
NSF $260,000UNIVERSITY OF ILLINOISURBANA-CHAMPAIGN
PFI:AIR - TT: DEMONSTRATION AND DEVICE LEVELCHARACTERIZATION OF LITHIUM-ION BATTERIESWITH GRAPHENE AND GRAPHENE-SILICON BASEDANODES IN POUCH AND CYLINDRICAL CELL FORMFACTORS
NSF $200,000RENSSELAERPOLYTECHNIC INSTITUTE
CAREER: GRAPHENE-ENABLED SYNTHESIS ANDSURFACE MODIFICATION OF WATER SEPARATIONMEMBRANES
NSF $244,940UNIVERSITY OFCALIFORNIA BERKELEY
CAREER: CORRUGATED GRAPHENE SUPERLATTICESTRUCTURES BY STRAIN-INDUCED SHRINKNANOMANUFACTURING
NSF $510,000UNIVERSITY OF ILLINOISURBANA-CHAMPAIGN
GRAPHENE-BASED ALL-PROXIMITY-COUPLEDQUANTUM SPINTRONIC DEVICES
NSF $375,000UNIVERSITY OFCALIFORNIA RIVERSIDE
GOALI: INFEWS N/P/H2O: REAL-TIME AND LOW-COST MONITORING OF ORTHOPHOSPHATE IONSUSING NOVEL GRAPHENE-BASED TRANSISTORSENSORS
NSF $107,977UNIVERSITY OF WISCONSINMILWAUKEE
STRUCTURE DEPENDENCE IN THE OXYGENREDUCTION REACTION ELECTROCATALYZED BYWELL-DEFINED GRAPHENE NANOSTRUCTURES
NSF $450,000INDIANA UNIVERSITYBLOOMINGTON
NOVEL GRAPHENE-BASED LABEL-FREEBIOSENSOR ARRAY FOR SMART HEALTH ANDDRUG DISCOVERY
NSF $330,000 CLEMSON UNIVERSITY
EAGER: NOVEL GRAPHENE MODULATORS NSF $150,000UNIVERSITY OFCALIFORNIA SANTA
SUSCHEM: METAL-FREE CATALYSTS FOR OXYGENEVOLUTION AND OXYGEN REDUCTION REACTIONS:FROM MOLECULAR MODELS TO GRAPHENE-BASEDELECTROCATALYSTS
NSF $280,000BOWLING GREEN STATEUNIV BOWLING
805
プロジェクト名 期間 資金拠出元 予算金額 参加機関
01-Aug-2016
31-Jul-2019
15-Aug-2016
31-Jul-2019
01-Apr-2016
31-Mar-2018
15-Aug-2016
31-Jul-2019
01-May-2015
30-Apr-2020
01-Sep-2015
31-Aug-2018
01-Jun-2015
31-May-2020
01-Aug-2015
31-Jul-2018
01-Feb-2015
31-Jan-2020
01-Feb-2015
31-Jan-2020
01-Sep-2015
31-Aug-2018
01-May-2015
30-Apr-2018
01-Sep-2015
31-Aug-2018
15-Sep-2015
31-Aug-2018
01-Jul-2015
30-Jun-2018
15-Sep-2015
31-Aug-2018
UNS: DENDRITE-FREE STORAGE OF LITHIUMMETAL IN POROUS GRAPHENE NETWORKS
NSF $300,000RENSSELAERPOLYTECHNIC INSTITUTE
SCALABLE ASSEMBLY OF FLEXIBLE ANDTHERMALLY CONDUCTIVE GRAPHENE PAPERMACROSCOPIC STRUCTURES FOR EFFECTIVETHERMAL MANAGEMENT IN ELECTRONIC DEVICES
NSF $250,000RENSSELAERPOLYTECHNIC INSTITUTE
COLLABORATIVE RESEARCH: MODELING ANDSIMULATION OF THE GROWTH OF GRAPHENEMULTILAYERS AND HETEROSTRUCTURES
NSF $214,847UNIVERSITY OFCALIFORNIA IRVINE
COLLABORATIVE RESEARCH: EXPERIMENTAL ANDCOMPUTATIONAL NANOMECHANICS OF THE LOADTRANSFER MECHANISMS AT THE GRAPHENEPOLYMER INTERFACE
NSF $197,044STATE UNIVERSITY NEWYORK BINGHAMTON
GRAIN GROWTH IN GRAPHENE: NOVEL ASPECTS INTWO DIMENSIONS
NSF $247,275 UNIVERSITY OF AKRON
CAREER: CORROSION RESISTANCE OF NANO-METER GRAPHENE COATINGS IN AGGRESSIVEMICROBIAL ENVIRONMENT
NSF $500,000SOUTH DAKOTA SCHOOLOF MINES ANDTECHNOLOGY
STRUCTURED EPITAXIAL GRAPHENE ANDSEMICONDUCTING GRAPHENE FOR ADVANCEDDIGITAL ELECTRONICS
NSF $400,000GEORGIA TECH RESEARCHCORPORATION
CAREER: DEVELOPING GRAPHENE SUPERLATTICESIN A MASSIVE-MASSLESS HYBRID ELECTRONSYSTEM
NSF $300,220 WEST VIRGINIA UNIVERSITY
CAREER: DEVELOPMENT AND APPLICATION OFCRUMPLED GRAPHENE OXIDE-BASEDNANOCOMPOSITES AS A PLATFORM MATERIALFOR ADVANCED WATER TREATMENT
NSF $500,000 WASHINGTON UNIVERSITY
GOALI: GRAPHENE PAPER SENSOR FOR DISEASEDETECTION
NSF $349,250MICHIGANTECHNOLOGICALUNIVERSITY
GAS PHASE ION CHEMISTRY OF PAHS AND GIANTPAHS: MODELS FOR GRAPHENE INTERACTIONSAND SUPPORTED CATALYSIS
NSF $160,259VIRGINIA COMMONWEALTHUNIVERSITY
CAREER: FABRICATING FREE-STANDING THREE-DIMENSIONAL GRAPHENE NANOSTRUCTURESTHROUGH FUNCTIONALIZATION, FOLDING, ANDSELF-ASSEMBLY
NSF $500,000UNIVERSITY OFMINNESOTA TWIN CITIES
RESEARCH INITIATION AWARD: TOWARDBIONANOSCIENCE - BINDING OF AMINO ACIDSWITH GRAPHENE AND N-DOPED GRAPHENE
NSF $299,986CLARK ATLANTAUNIVERSITY
EXPLORING SYNAPTIC REMODELING WITHGRAPHENE OPTOELECTRONIC PROBES
NINDS $230,071 VANDERBILT UNIVERSITY
COLLABORATIVE RESEARCH: EXPERIMENTAL ANDCOMPUTATIONAL NANOMECHANICS OF THE LOADTRANSFER MECHANISMS AT THE GRAPHENEPOLYMER INTERFACE
NSF $202,956UNIVERSITY OF ILLINOISURBANA-CHAMPAIGN
ENVIRONMENT ASSISTED CRACKING OFGRAPHENE
NSF $237,313UNIVERSITY OF NORTHCAROLINA AT
806
CNTの研究開発プロジェクト(NASA、NIDDK)
〔矢野経済研究所作成〕
プロジェクト名 期間 資金拠出元 予算金額 参加機関
01-Sep-2015
31-Aug-2018
15-Sep-2015
31-Aug-2018
01-May-2015
30-Apr-2020
15-Sep-2015
31-Aug-2018
01-Aug-2015
31-Jul-2018
01-Sep-2014
31-Jan-2018
01-Sep-2014
31-Aug-2018
01-Aug-2014
28-Feb-2018
01-Jan-2014
31-Dec-2018
01-Sep-2014
31-Aug-2018
01-May-2014
30-Apr-2019
01-Sep-2014
31-Aug-2018
DMREF/COLLABORATIVE RESEARCH: GRAPHENEBASED ORIGAMI AND KIRIGAMI METAMATERIALS
NSF $300,000 HARVARD UNIVERSITY
DMREF/COLLABORATIVE RESEARCH: GRAPHENEBASED ORIGAMI AND KIRIGAMI METAMATERIALS
NSF $1,000,000CORNELL UNIVERSITYITHACA
CAREER: GRAPHENE-ENABLED SYNTHESIS ANDSURFACE MODIFICATION OF WATER SEPARATIONMEMBRANES
NSF $400,000UNIVERSITY OF MARYLANDCOLLEGE PK CAMPUS
CAREER: GRAPHENE-BASED ULTRA-RESPONSIVEPHOTO-SENSING DEVICES
NSF $400,000NORTHEASTERNUNIVERSITY
DMREF/COLLABORATIVE RESEARCH: GRAPHENEBASED ORIGAMI AND KIRIGAMI METAMATERIALS
NSF $300,000 SYRACUSE UNIVERSITY
HIGHLY CONDUCTIVE REDUCED GRAPHENE OXIDEFILMS FOR HIGH PERFORMANCE ELECTRONICDEVICES
NSF $300,000 CLEMSON UNIVERSITY
COLLABORATIVE RESEARCH: MODELING ANDSIMULATION OF THE GROWTH OF GRAPHENEMULTILAYERS AND HETEROSTRUCTURES
NSF $150,000UNIVERSITY OFPENNSYLVANIA
CAREER: STRUCTURE-PROPERTY-PROCESSINGRELATIONS FOR AGGREGATION-RESISTANTGRAPHENE
NSF $335,044TEXAS ENGINEERINGEXPERIMENT STATION
CAREER: ELECTROACTIVE GRAPHENE-POLYMERSYSTEM WITH EXTREME ACTUATION AND TUNABLEPROPERTIES
NSF $355,241MASSACHUSETTSINSTITUTE OFTECHNOLOGY
FRG: PREDICTIVE COMPUTATIONAL MODELING OFTWO-DIMENSIONAL MATERIALS BEYONDGRAPHENE: DEFECTS AND MORPHOLOGIES
NSF $403,205UNIVERSITY OF MICHIGANAT ANN ARBOR
GRAPHENE THERMOELECTRIC THZ DIRECT ANDHETERODYNE DETECTORS
NSF $360,000UNIVERSITY OFMASSACHUSETTSAMHERST
CAREER: NARROW GRAPHENE NANORIBBONS WITHTUNABLE ELECTRONIC PROPERTIES
NSF $538,477UNIVERSITY OF NEBRASKALINCOLN
プロジェクト名 期間 資金拠出元 予算金額 参加機関
15-Jan-2016
27-Jan-2018
01-Jul-2013
30-Apr-2018
PRECLINICAL EFFICACY AND SAFETY EVALUATIONOF GRAPHENE NANOPARTICLE-BASED MAGNETICRESONANCE IMAGING CONTRAST AGENT FORDIAGNOSIS OF RENAL FAILURE
NIDDK $717,997THERAGNOSTICTECHNOLOGIES INC
ULTRA-LOW POWER CMOS-COMPATIBLE INTEGRATEDPHOTONIC PLATFORM FOR TERABIT-SCALECOMMUNICATIONSOUR PROPOSED EFFORT EXPLOITSRECENT BREAKTHROUGH 3D MONOLITHIC INTEGRATIONOF PHOTONIC STRUCTURES, PARTICULARLY HIGH-SPEED GRAPHENESILICON DEVICES ON CMOS ELECTRO
NASA $500,000 COLUMBIA UNIVERSITY
807
イギリス
イギリスにおける科学技術イノベーションの主要所管省はビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)。
BEIS はこれまで科学技術・イノベーションを担ってきたビジネス・イノベーション・技能省(BIS)がエネル
ギー・気候変動省(DECC)と合併して新たに組織された。ナノテクロノジー・材料分野の研究開発につ
いては旧 BIS の頃からが推進されており、現在では BEIS に引き継がれている。
グラフェンに関する研究においては、2010 年にノーベル物理学賞を受賞したアンドレ・ガイム博士とコン
スタンチン・ノボセロフ博士の勤務大学であるマンチェスター大学にグラフェン・グローバル研究技術拠点とし
て、2013 年に「国立グラフェン研究所(NGI:National Graphene Institute)」が設立された。
NGI は BEIS を所管省として、主に基礎・応用研究にプロジェクトベースで助成を行っている研究会議
(RCs:Research Councils)の一つである工学・物理科学研究会議(EPSRC:Engineering
and Physical Sciences Research Council)により 3,800 万ボンドが、欧州地域開発ファンドによ
り 2,300 万ボンドが投資され、グラフェンの実用化・産業化を目指した研究開発が行われている。
NGI は「ハブ&スポーク」モデルのハブとして機能し、グラフェン研究に従事している英国の他の大学や
研究機関との連携研究を重視しているほか、世界的企業も当研究所との共同研究を行っている。世界
中から 35 社を超える企業がマンチェスター大学とのグラフェン開発プロジェクトに調印している。
ドイツ
2015 年に「材料からイノベーションへ」と題したナノテク・材料分野の基本計画を発表(連邦教育研
究所:BMBF)。BMBF は連邦政府の研究開発関連予算の約 60%を管理するほか、様々な研究
開発戦略を立案している。BMBF の「材料からイノベーションへ」の助成プログラムでは、①ナノテクプラット
フォームの構築、②エネルギー、交通、医療、建築、機械分野への応用、③持続可能で高効率な資源
利用、④産学連携を基本コンセプトとして、各プロジェクトが運営されることになっている。同プログラムは、
過去に実施された「ナノイニシアティブ・ アクションプラン 2010」、「アクションプラン・ナノテクノロジー2015」
の後継と位置づけられているだけでなく、応用分野として領域横断的に環境・エネルギーの FONA やライ
フサイエンスの健康研究基本プログラムとの連動を強く意識している。現状では 2025 年まで、毎年 1 億
ユーロ規模の助成を予定している。
プロジェクト名The Innovation Alliance Carbon Nanotubes
(Inno、CNT)
研究開発費 5,000万ユーロ
期間 2008年~2014年
ナノカーボンの種類 CNT
概要技術の実用化に焦点。計90の企業や研究機関が参
加し、27のプロジェクトに取り組んだ
助成主体 BMBF
(出所:NEDO TSC Foresight(2015.10)及び各種報道資料より作成)
808
EU
EU のナノテクノロジー・材料分野の研究政策に取り組む組織として、研究イノベーション総局内に、産
業技術局(Directorate D)がある。同局内に先進材料およびナノテクノロジーユニットがあり、こちらが
中心的な役割を果たしていると見られる。
ナノテクノロジー・材料分野においては、2004 年 5 月に採択された「EU ナノテクノロジー政策」が基本
となり推進されている。その後、Horizon2020 では、「産業リーダーシップ」において、6 つのキー技術のう
ち、ナノテクノロジーと先進材料の 2 つを指定しており、ナノテクロノジーはナノ材料・ナノデバイス・ナノシス
テムに関する研究や、ナノテクノロジーに関する安全面・社会的側面の研究、ナノ材料や部品の製造プロ
セスの改善に関する研究などが進められようとしている。一方、先進材料では、自動修復などの機能材
料、大規模かつ持続可能な材料 製造技術、計測・標準化・クオリティコントロール技術などが優先事項
に挙がっている。産業技術開発におけるナノテクノロジーと材料分野への投資は、それぞれ約 15 億ユーロ
と約 14 億ユーロと 7 年間で合計 29 億ユーロとなる。
欧州委員会の研究開発フレームワークプログラムに係るデータベース(CORDIS)を対象に
Graphene の研究開発プロジェクトを調査した結果、稼働中のプロジェクトは次ページの表のとおりとなっ
た。
809
LARGE-SCALE
PRODUCTION METHOD OF
GRAPHENE TO REACH THE
MARKET IN AN EFFECTIVE
WAY
Graphene-based disruptive
technologies
Multifunctional Graphene-
based Nanocomposites with
Robust Electromagnetic and
Thermal Properties for 3D-
printing Application
期間 2016.5.1~2021.4.30 2016.10.1~2018.9.30 2016.4.1~2018.3.31 2017.1.1~2020.12.31 2014.5.1~2019.4.30 2013.6.1~2018.5.31
資金拠出元ERC-COG - Consolidator
GrantSME instrument phase 2 European Commission等
Marie Skłodowska-Curie
Research and Innovation
Staff Exchange (RISE)
ERC Starting Grant ERC Advanced Grant
予算金額 1,995,625ユーロ
Total:2,151,980ユーロ。うち、
EUの寄与金額が1,506,386ユー
ロ
89,000,000ユーロ
Total:1,935,000ユーロ。うち、
EUの寄与金額が1,651,500ユー
ロ
EU:1,499,996ユーロ EU:2,025,600ユーロ
参加機関 BILKENT UNIVERSITESIGRAPHENETECH SOCIEDAD
LIMITADA
Chalmers University of
Technology(スウェーデン)のほ
か、企業・大学100ヶ所以上のパ
ートナー
Institute of Mechanics,
Bulgarian Academy of
Sciencesのほか、6ヶ所のパートナ
ー研究機関
Universiteit Leiden
FOUNDATION FOR
RESEARCH AND
TECHNOLOGY HELLAS
プロジェクト目標
The aim of this proposal is
to develop adaptive
camouflage systems using
graphene-enabled smart
surfaces.
Accelerating the uptake of
nanotechnologies advanced
materials or advanced
manufacturing and
processing technologies by
SMEs.
The second in the series of
EC-financed parts of the
Graphene Flagship.
Graphene 3D project
proposes highly innovative
pathway for the
development of optimized,
multifunctional graphene-
based polymer composites
and structures with desired
properties for specific
applications.
Graphene – a one atom
thin material – has the
potential to act as a sensor,
primarily the surface and
the edges of graphene. This
proposal aims at exploring
new biosensing routes by
exploiting the unique
surface and edge chemistry
of graphene.
This proposal aims via a
comprehensive and
interdisciplinary programme
of research to determine
the full response of
monolayer (atomic
thickness) graphene to
extreme axial tensional
deformation up to failure
and to measure directly its
tensile strength, stiffness,
strain-to-failure and, most
importantly, the effect of
orthogonal buckling to its
overall tensile properties.
(出所:CORDIS:Communtiy Research and Development Information Service) 検索ワード:Graphene)
プロジェクト名
Graphene based smart
surfaces: from visible to
microwave
HORIZON 2020
Sequencing biological
molecules with graphene
Tailoring Graphene to
Withstand Large
Deformations
810
中国
中国では、「第 13 次 5 ヵ年戦略的新興産業発展計画(2020年までにグローバルにおける新材料メ
ーカー育成が重点)」においてグラフェンを新材料の 1 つとして指定しており、中国国家自然科学基金委
員会により 3 億人民元がグラフェン関連産業に投入されている。中国のグラフェン関連政府プロジェクトは
以下のとおりである。
韓国
ナノテクロノジー・材料分野では、2013 年 7 月に韓国国務総理室直属の国家科学技術審議会
(NSTC:National Science and Technology Commission)において承認された「第 3 次科
学技術基本計画(2013~2017 年)」を主軸に推進されており、30 の重点国家戦略技術の 1 つと
して先端素材技術(無機・有機・炭素など)にて取り上げている。
グラフェン関連プロジェクトでは、「未来素材産業先導国への実現」というビジョンのもと、グラフェン関連
商用化技術の確保及びグラフェンのグローバル企業育成(総事業費 2,106 億ウォン。うち政府:834
億ウォン、民間 1,272 億ウォン)を目指し、その一環として、2015 年に「未来素材産業先導国への実
現に向けた、グラフェン事業化促進技術ロードマップ(2015~2020)」を発表している。
グラフェン事業化推進技術ロードマップ及びグラフェン関連主要プロジェクト概要は次ページの図表のと
おりである。
発表時期 プロジェクト名 詳細内容
2015年9月(中国制造2025)重点領域技術
路線路線図(2015年9月)
2020年までグラフェン産業の市場規模を100億人民元、2025年には
1,000億人民元以上に育成する、中国グラフェン産業に関する今後
10年間の発展ロードマップを提示
2015年11月グラフェン産業核心発展に関する意
見書
グラフェン材料の標準化及び原価削減、サプライチェーンの構築等によ
るグラフェン製造メーカーの競争力強化を目指し、2020年までに中国
のグラフェン産業システムの確立を目標とする
2016年3月新素材核心発展に関する指導意見
書グラフェンの基礎研究及び技術開発などの新素材研究を提示
2016年3月中華人民共和国国民経済及び社
会発展に関する13.5規格要綱
グラフェン、スーパー新素材等のナノ材料の開発に一層注力することを
表明
2016年5月 国家革新促進発展戦略要綱新素材産業分野においてナノ材料及びグラフェンを主力事業として挙げ
る
(出所:各種報道資料をもとに作成)
中国 グラフェン関連政府プロジェクト概要
811
⑫ ①の技術の構成(要素)技術及び保有企業
グラフェンの製造における要素技術及び保有企業は以下の表のとおりである。
保有技術 企業名 備考
グラファイトの酸化・剥離技術 仁科マテリアルグラファイトを化学的に酸化・剥離し、酸化グラフェンを製
造する技術を保有
グラフェン前駆体の製造技術グラフェン
プラットフォーム
結晶性が低く、剥離しやすいある特定の結晶構造を持っ
たグラファイトを製造
高速CVD法インキュベーション・
アライアンス
反応容器全体で3次元的にかつ同時多発的にCVDが進
行するため、高生産性と大量生産が可能(インキュベー
ション・アライアンスは同社独自の高速CVD法を「InALA
法」と提唱
高温・高圧技術及び、粒子の
表面改質技術アイテック 高純度グラフェン、大量生産が可能
グラファイトの酸化・剥離技術 ADEKAマイクロ波を照射してグラフェンを製造。化学的な処理を必
要とせずに高品質なグラフェンを大量に生産可能
高分子焼成法及び炭素化技
術カネカ
厚さ約2μmの薄い原料芳香族ポリイミド膜の製造技術と
最適な炭素化、グラファイト化プロセスにより、高品質多層
グラフェンを開発
グラファイトの酸化・剥離技術 大阪ガス
グラファイトを特殊な化学薬品と混ぜて、マイクロ波を当て
てグラフェンを製造。高生産性による製造コストの低減が
特徴
グラファイトの酸化・剥離技術 日本触媒
化学品製造における化学反応を安定して進行させる制
御技術と酸化グラフェンの生成メカニズムに関する知見を
活用し、還元型酸化グラフェンと修飾型酸化グラフェンなど
の酸化グラフェン系材料を開発
超臨界流体を用いたグラフェン
製造技術昭和電工
エタノールにグラファイトを溶かし、液体と気体が混じった超
臨界と呼ぶ状態でグラファイトの積み重なったシートを1枚
ずつはぎ取る方法。高純度が特徴
表面処理剤によるグラフェンの
安定分散技術東レ
グラファイトを酸化させて剥離した後、脳内の神経伝達物
質であるドーパミン(化学式はC8H11NO2)を吸着させ、
それを還元することで溶剤中での凝集を防ぎ、かつ安定に
分散できる表面処理グラフェンを開発
(出所:各種報道資料より作成)
813
⑬ ①の技術を実現するための周辺技術(装置・試験装置)及び保有企業
グラフェン関連装置・試験装置及び製造・装置メーカーの一覧は以下の表のとおりである。
グラフェン関連装置・試験装置 製造・装置メーカー名
ラマン分光分析装置、質量分析機等の各種分析機器サーモフィッシャージャパン(サーモフィッシャー・
サイエンティフィック)
グラフェン結晶薄膜・表面分析装置 ケニックス
分析計測機器(3D測定レーザー顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡
等)、粒度分布測定装置等島津製作所
プラズマを用いたグラフェン製造装置 グラフェンプラットフォーム
グラフェンCVD成膜装置(管状炉タイプの熱CVD装置)、卓上
CNT/グラフェン成膜装置マイクロフェーズ
NanoCVD卓上型グラフェン/CNT合成装置 デルモセラ・ジャパン
電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM) 日立ハイテクノロジーズ
粉末X線回折装置リガク、日産アーク、島津製作所、日立ハイテ
クサイエンス等
透過型電子顕微鏡日本電子、日立ハイテクノロジーズ、サーモフ
ィッシャージャパン等
スパッタリング装置 ULVAC、ケニックス
研究用ダイヤモンドCVD+グラフェン合成装置 HFCVD Graphene
Plus システムコーンズテクノロジー
(出所:各種報道資料より作成)
814
(補足)ニュース・リリースまとめ(2017 年 1 月~2018 年 1 月 20 日)
(出所:各種資料より作成)
日本 詳細内容
2018 1 名古屋大学
原子スケールで界面反応性や界面歪みを制御し、数百ナノメー
トルの広域にわたり結晶性の高いグラフェンのスタネンの創製に
世界で初めて成功
2017 11 東北大学層状半導体GaSeの巨大なスピン軌道相互作用を発見。従来
のグラフェンと異なる新しいスピントロニクス材料
2017 10東京大学、東北大
学
エピタキシャルグラフェンとシリコンカーバイの界面において、ダングリ
ングボンドを持った界面シリコン原子に由来する特徴的な低エネ
ルギーのフォノンを世界で初めて発見
2017 10 産総研 グラフェン-メソポーラスシリカ複合体の細孔の制御に成功
2017 9 熊本大学酸化グラフェンナノシートを重ねるだけで、シート間に圧力が発生
することを発見
2017 8信州大学、科学技
術振興機構
酸化グラフェン/グラフェンハイブリッド積層構造水処理膜の簡便
な生成法開発と高性能化に成功
2017 8 仁科マテリアル 酸化グラフェンの量産化の交渉に入る
2017 6 石原ケミカル 米Angstron Materialsの国内販売代理店として営業開始
2017 5 京都大学単一原子層薄膜によって赤外光を1桁波長の短い可視光に変
換することに成功
2017 3 岡山大学酸化グラフェンの剥がれる様子をリアルタイムで観察することに成
功
2017 2 日本触媒酸化グラフェン系材料の量産試作に成功し、サンプルワークを開
始
2017 2北陸先端科学技
術大学Si版グラフェン「シリセン」が凸凹な表面上で成長することを発見
日付
815
(出所:各種資料より作成)
詳細内容
2018 1 英国 マンチェスター大学RFIDデバイスにグラフェンセンサーを組み込んで、バッテリーレスのス
マート湿度モニターを実現
2018 1 韓国 KIST グラフェン基盤の硫化水素(H2S)センサーを開発
2018 1 韓国 Kyunghee大学 充電速度5倍の「グラフェンボール」バッテリーの開発に成功
2017 12 中国 浙江大学 120mAh/g容量のアルミニウム/グラフェン電池を開発
2017 12 韓国 BN鉄鋼ケミカル グラフェンを適用した船舶用減衰器の開発に成功
2017 12 韓国次世代融合技術研究
院体温・有害ガス検知のグラフェン繊維センサーを開発
2017 11 韓国 基礎科学研究院金属系光メタ表面材料とグラフェンを利用し、カメラレンズの厚みを大
幅に減らす技術を開発
2017 11 韓国 Samsung 充電速度5倍の「グラフェンボール」バッテリーの開発に成功
2017 10 韓国 コリアテック グラフェンナノボールの大量生産工程を開発
2017 10 韓国 Dongjin Semichem グラフェン放熱素材を用いた電装部品用ケースを開発
2017 9 中国 Tunghsu Opto独自のグラフェン温度管理材料を備える最新のグラフェンLEDライト
「Super Light」を発表
2017 8 英国 マンチェスター大学電気伝導性を持つ酸化グラフェン製のインクを用い、布に印刷できる
ウェアラブルバッテリーを開発
2017 7 米国
デンマーク工科大学、
オーフス大学、IBM、米
ブルックヘブン国立研究
所
グラフェン自己組織化による量子ドットパターニングに成功
2017 6 米国 Kickstarter 振動板にグラフェンを使用したヘッドフォンを開発
2017 4 英国 マンチェスター大学 酸化グラフェンで海水ろ過して飲用水に変える技術を開発
2017 4 韓国 ETRI/Hanwha グラフェンを使ったフレキシブル有機ELディスプレイの開発に成功
2017 4 米国米国立標準技術研究
所
グラフェンを利用して、液体や気体の試料を電子顕微鏡で簡便に観
察する技術を開発
2017 4 米国 オークリッジ国立研究所 グラフェンナノリボンの新しい作製手法、電子デバイスへの応用拡大
2017 3米国、
台湾
MIT、台湾・国立交通
大学
酸化グラフェンを利用して微量の血液サンプル中から細胞を捕獲し、
個々の細胞レベルでの分析・診断を行う新手法を開発
2017 4 米国 パデュー大学 高感度グラフェン光検出器の作製に成功
2017 3米国、
台湾
MIT、台湾・国立交通
大学
酸化グラフェンを利用して微量の血液サンプル中から細胞を捕獲し、
個々の細胞レベルでの分析・診断を行う新手法を開発
2017 3 米国 インディアナ大学 CO2から燃料生成できるグラフェン-レニウム複合体を開発
2017 2オースト
ラリア
連邦科学産業研究機
構大豆油をグラフェンに変えることを可能にする技術を開発
2017 2 米国 カンザス州立大学 グラフェンの簡易な量産手法「材料ガス爆発法」を発見
2017 1 英国 ケンビリッジ大学 グラフェンの超伝動化に成功
日付 海外
816