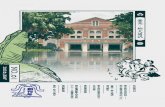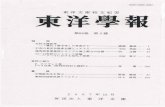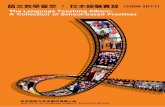南洋に お ける 日本人学校の 動態 - J-Stage
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 南洋に お ける 日本人学校の 動態 - J-Stage
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東 南 ア ジ ア 研 究 18巻 3号 1980年 12月
南洋に お け る 日本人学校の 動態*
小 島 勝ホ *
The Japanese School in Southeast Asia in the
Period before World War II
Masaru KOJIMA **
This article intends to clarify the educational
aspect of Japan覃s relations with Southeast Asi乱,
which was referred to as‘‘Nan アo.,,
Long・term
Japanese residents of‘‘Nanyo’, who had children Qf
school age were determined to send their children
to Japanese Schoo1. However, because such a
school was impossible to set up and maintain by
themsclves , they had to seek the cooperation of man ア
other Japanese. They particularly needed the
丘nancial help of those who had been sent there for
several years from their trading companies or banks .
These short −term residents derived some bene丘ts
frQm thc Japanese schooi, but its existence was not
cssential for them . If they had children Qf schQo1
age, theア could leave them behind in Japan. In
other words , the expectations of the long・termresidents regarding the Japanese school were differ・
ent from those who were there only temporarily .
The dormitories of the ∫apanese schQol playcd an
important part in stabilizing the lives of the long・
tetm residents because there were few Japaneseschools in
‘‘Nanyo .”
One Qf the functions of the Japanese school was
to remove the cultuTe of‘‘Nanyo ’冫
which the children
of long−term residents had learned and instill in
them 丘皿 1y the Japanese culture . This did, how −ever , provoke some cultural conflic し
は じ め に
「南洋 に於 き ま して は , 日本人 の 子供 が学
齢に 達 します と云 ふ と教育 す る方法 は あ りま
せ ん 。 仕 様 が な い か ら 日本 に 帰す 。 帰すに は
一人 で は 帰せ な い か ら母親が 付い て 帰 る 。 あ
とは父親一
人 で淋 し く生活 して居 らね ばな ら
ぬ , 彼等 の 生 活 が 斯 く して 漸 次荒 ん で 来 る こ
とは 当然 で ある 。 南洋 に 於 きま して 日本 人 の
*本論文 は , 昭和52年度文部省特定研究 「東 ア ジ
ア お よ び東南 ア ジ ア 地域 に お ける文化摩擦 の 研
究」の 中の 「日本の南方関与と文化摩擦」班で の
研究成 果の一部と して 執筆 さ れた もの で あ る 。
**竜谷大学文学部 ; Faculty ・f Letters, Ryuk ・ku
University
小 学校の 出来て 居 ります の は, 馬尼 刺 , 「ダ
バ オ」,『ミ ン タ ル 』,「ス ラ バ ヤ』, 「メ ダ ン 』,
新 嘉坡 , 恐 ら く此 位で ござ い ます 。 『タ ワ オ」
の 如 く比較的集団 して 邦人 が居 り , 殊 に 久 原 ,
三 菱 と云ふ 大資本 家 が居 る処 で す ら , 小学校
の 設 立 が ご ざ い ませ ん や う な次第で ご ざ い ま
す」[色部 1926: 65−66]。
大 正 15年 , 当時 台湾 総 督府 技 師 で あ っ た色
部米作は , 南 洋視 察 を終え て の 講 演 で教 育問
題 に ふ れ て , こ の よ う に 述 べ て い る。戦 前 の
南洋に お け る 日本人子弟 の 教 育に つ い て 考察
しよ うとす る時,こ の 淡 々 と した 口 述 の 背後
に え もい わ れ ぬ 錯綜 し た 問題 が動 め い て い る
の を感 じと る の で あ る 。 そ の 問題 が い か な る
460 一ユ04一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 : 南 洋 に お け る 日 本 人学 校 の 動 態
性 質 の もの か , ど の よ うな 脈 絡 に 位 置す る の
か を 見極 めた わ け で は ない が , 南洋に お ける
在外子 弟教 育 の 実 態 と そ の 問題 性 と の 関 連を
で きる 限 りこ れ か ら解 き明 か して みた い と思
う。まず , すで に こ の 口 述 の 中に い くつ か の
問題 性 が顔 をの ぞ か せ て い る。第 1 に , 子 ど
もが 当然 に 入 っ て ゆ くべ き通 過 集団 と して の
「学校」 が存在 しな い と い う こ と , そ の こ と
か ら , 母親 と子 ど もは 日 本 へ 「帰 る 」 .こ と に
な り , 父親は 「淋 し く」 「荒 ん だ 」独 り暮 ら
しを 強い られ る と い う こ と , 在留邦人 が 「集
団的 」 に な り , 有 力 商社 が あ る と こ ろ で もな
か な か 「日本 人 小学 校」が 設立 され な い とい
う事 実……。
南 洋で あ る か 否か に か か わ らず , 在外 子弟
教育 問題 は ,
一国 民 の 海 外進 出に 付随 し て 出
て くる問 題 で は あ る 。 し か し , 南 洋 に 住み つ
か ん とす る在 留邦 人 に と っ て は , 「住み つ く」
こ と の 是非を 問い 直 さ ね ば な らな い ほ ど, 深
刻 な 問題 と し て 迫 っ て く る 課 題 な の で あ っ
た 、子 ど もの 教育 の た め に , 事業 途 中に して
帰国 した 邦入 も少な か らず あ っ た と 聞 く。 す
な わ ち , 在 外 子 弟教育 の 整 備如 何 は ,凵本 の
南洋進 出 の 一つ の 重要 な 鍵 を 握 っ て い た と い
え よ う。本 稿で は , 在 外 子 弟 教育 の 一つ の 制
度 と して の 「日 木人学校」 に 焦点 を絞 っ て ,
そ の 成立 過程 ・動 向 をみ な が ら , す な わ ち
「日本人学校」 を“
窓”
に し て, 南 洋と関わ
っ た N 本 人 の一
側 面 を描 写 し て み た い と考え
る。
1 日本人 学校 の 成 立要 件
「日本 人小学 校 」 あ る い は 「口本小学校」
と称せ られ る 学校が で きた の は い つ ご ろ な の
だ ろ うか 、 普 通 , 「予備科」す な わ ち今 日 い
うと こ ろ の 「幼稚 園 」 が 付設 され て お り , 中
等 教育機 関が で きた と こ ろ もあ る 1) の で 「小
1) ミ ン タ ル 女学院が そ うで あ る 。
学 校」 と総 称 で きな い が , 大正 元 年 に シ ン ガ
ポ ール に 開校 され た の が そ の 嚆矢で ある 。以
下 , 大正 6 年 に マ ニ ラ , 大正 8 年 メ ダ ン , 大
正 13年ダ バ オ お よび ミ ン タ ル, 大正 14年バ ギ
オ な ら び に ス ラ バ ヤ , 大正 15年 バ ン コ クと続
い て い る。大正年間 で は こ の 8 校 で あ っ た 。
昭和 に入 る と , 昭和 2 年 に タ ワ オ , 昭和 3 年
バ タ ビ ヤ お よ び ボ ル ネ オ , 昭 和 4 年 に ス マ ラ
ン に 開 設 され,昭和 5 年 に は ス レ ン バ ン で,
昭和 7 年 に は バ トパ パ で 開校 されて い る 。 昭
和 8 年 に な る と急 に こ の 数は 増え ,バ ン ド ン,
イ n イ ロ ,セ ブ , そ れ に ダ バ オ 州 の マ ナ ン ブ
ラ ン , ラ サ ン,
バ ン ガ ス, ト ン カ ラ ン が開校
に 踏 み切 っ て い る の で あ る 。さ らに ダ バ オ州
で は , 昭和 9 年 に バ ヤ バ ス, デ ィ ゴ ス
, 昭 和
11年 に カ リ ナ ン, ダ リヤ オ ン
, カ テ ガ ン, 昭
和 13年 に ワ ガ ン に 日本 人 学 校 が で きて い る
[米 田 1940 : 147]。 目本人 学校 は第 2 次 大 戦
で 雲散霧消す る の で あ る が,そ の 直 前 の 数 は ,
マ レー地 域 で 5
, 「東 印度 」 6 , タ イ 1 , フ
ィ リ ピ ン 15, 英領北 ボ ル ネ オ 1 の 計 28校で あ
っ た [坂 本 1942 : 845]。
した が っ て , 冒頭 の 色 部米 作の 視 察講 演に
戻 る と ,バ ギ オ に も日本 人学 校 が あ っ た の で
あ り , タ ワ オ に 関 して は そ の 翌 年 , 開校 の 運
び とな っ た の で ある 。 い ずれ にせ よ , 日本人
学校 は 大正 年 間か ら ぼ つ ぼ つ 現 わ れ , 昭 和 8
年 ご ろに 急に 増殖 し , や が て 戦争 に よ り消滅
して しま う の で あ る 。
学齢 期に あ る子 ど もを もつ 親 な ら,誰 しも
子 ど もを学 校 へ や りた い と思 う で あ ろ う 。 少
な くと も自分 と 同等の , 願 わ くば 自分 よ り以
Lの 教 育 を 受 けさ せ た い とす る の が親 心 で あ
る 。 しか し , 南 洋 に お け る在 留邦人 に と っ て ,
こ の あ りき た りの 要求 を実現 さ せ る の に 非常
な 障害 を乗 り越 え ね ばな らな か っ た の で あ
る 。 実 現 途 ヒに し て つ い に 望 む 学 校 へ や れ な
か っ た 親 も多 い 。
当初 , 南 洋 に お い て は 一般 に , 英語 学校 ,
一 105 一 461
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto UnlverSlty
東南 ア ジ ア 研 究 18巻 3 号
オ ラ ン ダ学校 な ど の 植 民地支 配 国 の 学校 ,マ
レー
語学校 な ど の 現 地 人 の 学校 , そ して 支那
語 学校 な ど が あ っ た が,
日本人 子 弟 を 対象 に
した学校 は なか っ た 。そ れ で 在留邦人 は仕 方
な く, オ ラ ン ダ学校 な ど へ や っ た が , そ れ
さえ 遠隔地 等 々 の 理 由 の た め で き な い 親は ,
子 ど もを 「野 放 し」 に して い た の で あ る 。 し
た が っ て , 日本人 の た め の 学校 が で き る こ と
を , 子ど もを もつ 在留邦人 はか ね て か ら強 く
願望 して い た ので あ る 。 そ う した家族 が 10軒
くらい に な る と ,
“
集団的な 要求”
とな っ て
くるの で あ っ た 。 しか し 「学 校」と い っ て も,
そ れ ほ ど た や す くで き る もの で は な い 。 素 養
さ え 身に つ けれ ば よ い とす る塾 まが い の もの
で な く, 卒 業 資 格 が公 認 され て い る 正 規 の 学
校 で な くて はな らな い の で あ る 。 校舎, グ ラ
ン ド , 教室 , 設 備 , 教材 ……。そ れ に 教師 ら
の 人 件費 も相 当 な 額 に達 す る 。 10軒や 20軒 く
ら い の 家族 で 賄 え るわ けが な い 。
したが っ て, 「学校開設」の 目的に 向けて ,
子ど もを もた な い 在留邦人 も同 調 す る こ と が
少 な くと も必要 とな る。 こ の 場合 も, 在留 邦
人 に か な りの 資力が ある時 に の み 学校建設 は
可能 で, さ らに 銀行 や 有力商社の 邦人 も こ れ
と共 同歩調を と る こ とが , 重要 な要件 とな る
の で あ る 。 す な わ ち , 「日本人学 校実 現」 の
成否 は , 在留邦 人 の 経 済力 を前提 に , 学齢期
の, ある い は学 齢期 をひ か え た 子ど もを もた
な い 在留 邦人 が 在外 子弟教育 に 関わ っ て い か
ざ る を え な い 状況に な っ て い た か 否 か , そ し
て 銀 行 ・有力商社 の 邦人 も こ れ に 関与 して い
か ざ るを え な い 関係 が成立 して い た か 否か に
かか っ て い た と い え よ う。 在留邦人 の 生活空
間が 教 育 の 機能 を 分担 す る学校を 派生 さ せ う
る に 足 る コ ミ ュニ テ ィ
ーで あ っ た か 否 か , ま
た, 銀 行 ・有 力 商 社 の 邦 人 が , 在留邦人 の 特
定 の 要求に関与 せ ざ るを え な い 社会関係に あ
っ た か否 か と い う こ とが , 日 本 人 学校 成 立 の
要 とな る の で あ る。
で は こ こ で,
日本人 学校 の 経 営 が 軌 道 に の
る まで の 歴史を 具体的に 辿 りな が ら , こ の 問
題 を さ ら に 検討 し て み る こ と に し よ う。た と
え不 十分 で あ っ て も上 述 の よ うな状況 に あ る
な ら, 何 らか の き っ か け さ え与 え られ れ ば ,
日本入 学校開校 へ の 途 は開か れ た 。 例 え ば シ
ン ガ ポ ール で は 明治45年 7 月 , 歯科医で あ り
雑誌 『自由評 林」 を 主宰 し て い た 山本 作次 郎
が 中心 とな っ て, 医 師 ・西 村 竹四 郎 , 医師 ・
佐藤有太 らが小学校世話人会を つ くり, 小学
校 設立 に 着手 して い る。 マ ニ ラ で は大 正 4 年
11月 , 大正 天皇御大典奉祝 の 醵金か ら剰余 金
が 出た の を 機に , そ れ を児 童 育英資金 と し ,
翌 々年 2 月 , 帝国領事 ・杉村 恒造 ら22名が発
起 人 と な り, 小学校設 立 費 な らび に維 持費 の
負担を なす篤志家 を募 っ て , こ れ に 成 功 して
い る 。 ま た ス ラ バ ヤ で は , ス ラ バ ヤ ロ本人 会
が 動 き,バ タ ビ ヤ で は ,
三 宅 哲一郎総 領事 の
熱意が 功 を 奏 し て ,横 浜 正 金 銀 行が重 い 腰 を
上 げ, 学校設立 に合意 して い る e2) そ して バ
ン ド ン で は , 「突 然全 く 予 期 して い な か っ た
小墻龍一先 生 (京都 師範 出) の 出現 に よ り話
が 実 り 」 [前 田 1968 : 140 ],バ ン ド ン 日 本
人 会役 員が 主 と して 奔走 して 開校に こ ぎ つ け
て い る 。小墻龍一
は職を 求 め て い た の で あ っ
た [菅沼 1968 : 106]。
した が っ て , 問題 は 「き っ か け」 そ れ 自体
で は な く, そ う した 「き っ か け」を介 し て一
気 に 日 本人 学校成立 へ と向かわ せ る要 因の 複
合体 な の で あ る。す な わち , 子 どもを正規 の
日本人 学校 へ 入 れ た い 在留邦人 と 直接 に は 関
わ りの な い 在留邦人 ,そ れ に 2
,3 年 の 滞在
期間の こ と で ある か ら内地 の 小学校 へ 入 れ て
お けばすむ銀行 ・有力商社の 親 た ちが ,い か
に 協調す るか と い う こ と で あ る 。 「当事者」
が 「非当事者」 の 資力 を頼 ま ざ る を え な い 事
2)バ タ ビ ヤ 日本人 小学校の成立事情に つ い て は, 当 時 バ タ ビ ヤ 日 本 人 会 役 員 で あ っ た 石 居 太楼氏
の ご教示 に よ る 。
462 一 le6 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南 洋に お け る 日本人 学校の 動 態
態 , そ こ に 日本人 学校の 設立 ・経営を困難に
す る 一つ の 理 由が あ っ た。
シ ン ガ ポ ール の 場合 をみ て み よ う。「もと も
と公的 な機関の うしろ立て も,強力な経済的
裏付 け もな い もの だか ら, 経営の 見通 し も暗
い もの で あ っ た に ちが い な い 」[小林 1976:
118]。 大 正 元年 11月 3 目 , 教師 1 名 , 児 童28
名で 出発 した が, 開校式 早 々
, 訓 辞を 内諾 し
て い た 岩谷領事 が 自分 の 夫人 を代 理 と して 出
席 させ , 創 立有志 者 を 嘆 かせ て い る 。 有 志者
の ひ と り , 福 田 太 一は こ の 事情を 次の よ う に
語 っ て い る .「我 国民 教育 を 海 外で 始 め る と
言 ふ 大 切な場 合 に 帝国 を代表 す る領事 が 出席
しな い な どとは言語 道 断沙汰 の 限 りで あ る 。
夫 れ も 病気 で あ る と 云 ふ な ら致 し方 もな い
が , 其 の 時代 の 在留民 の 多 くは 殆 ん ど 暗 黒
世界 の 者ば か り で 各 自己 の 勢 力 争 に の み没頭
し, 己 の 意 に 満た ぬ もの を排斥す る に 日 も夜
も之 足 らぬ と云 ふ 様な 所 謂紳士 の 仮 面 を被 ぶ
る 徒輩 が 領事 を利 用 した の で , 出 る に 出 られ
ず , しか も約束 は反故 に さ れず万策 つ き て ?
夫 人 の 代 理 で あ る 。鳴 呼何 と 云 ふ 不 甲 斐な い
事で せ う u 創立 有志者が 嘆声を揚 げた の も誠
に 無理 か らぬ 事で ある 」 [福 田 1933 : 53]。
ま た 同 じ く福田 は , 厂寸時 で も 油 断を して 居
る と折角 嬉 々 と して 通 学す る天真爛漫 なる 無
心 な児童 がぱ っ た り来 ぬ 様 に な る の で す。之
は彼 の 非 国民 に等 し き徒輩が 其の 魔手 を子供
の 上 に ま で 延ばす結果で 「日 本小学校 』の 門
標が一夜 の 中に コ
ール タ
ール で 真 黒 に され た
の も其時分で あ りま した 。つ ま り小学校 を潰
し て 仕舞 へ ば 彼等 の 目的 は 達 せ られ る の で あ
る」[同上 論文 ;54]と述べ て い る 。 こ う した
障害 に 備 えて 「創立 者 は通 学児童 か ら一
仙た
りと も 授 業 料 を 徴収 す る の で な く , 皆私 財
を提供 して 学用 品 は 申迄 もな く時 に は菓 子 や
果 物 ま で 吝まず与 へ て 専 ら児童 の 歓心 を 買 ふ
た 」[同 所]と い う。
す な わ ち , 「こ の 学校開 設 に も , シ ン ガ ポ
一ル の 目本人は 三 つ に わか れて しま っ た の で
あ る」[小林 1976 ; 118ユ。 熱心 な 開設論者 と
賛助者 , 反 対論者 , そ れ に 無 関心 者。「開設
論者 と賛助者を た た きの めす た めに わ ざ わ ざ
新 聞 を発 行 した 人 もあ っ た」[同所] し , 「開
設 論 者 と反 対論者 と の 聞に は 日常生活に もい
が み あ い が 続 き , な ぐ り合 い の ケ ン カ を す る
こ と も再 三 に わ た っ た」[同所]そ うで あ る 。
学校 と い う特定 の , 教育 の 機能 が 派 生す る 際 ,
それ と同等 の 力学 を も っ た利 害関心 が こ れ に
まとわ りつ くと い う,諸機能 の 未分 化 な 状況
が , 当時の シ ン ガ ポ ール に あ っ た の で あ る。
こ の 意 味で , 開 校 はや や 「時期尚早 」で あ っ
た 。
つ ま り , 教育機能 の 担 い 手 と して の 「学校」
が , 構成 員 の 共有 す る利害関心 の“ 一つ
”
と
な る 時 , すな わ ち生 活領域全 体 に 瀰 漫す る諸
要 求 が 複 数 の ク ラ ス ター
と して 顕在化 し , 組
織 化 され る時 ,日本人学校 は広 い 支持を得 る
こ と が で き る の で ある 。 ま た 逆 に , 日本 人学
校 の 存在が , そ う した 組織化 を促進 す る こ と
も起 こ りう る 。 そ の 具体 的 な現 わ れ は , 「日
本人 会」 の 整備 とい うこ とで あ る 。
シ ン ガ ポ ール 日木人 会が で きた の は , 大正
4 年 9月で ある 。 そ して 時を 移 さず 10月 に 日
本人 学校は こ の 日本人 会 の 経 営に 委ね られ て
い る 。こ れ は , 日本入 学校が 「私的」 な もの
か ら 「公 的」 な もの へ と衣 がえ した こ とを意
味す る 。 した が っ て 創立 者 に と っ て は , 反 面 ,
「手放 す」 こ と へ の 未練 が残 っ た 。 引 き継 ぎ
の 段 に な っ て , 創 立者 側に 異議を唱え る人 も
出 た と い う [福 田 1933 : 54]。 し か し, 福 田
太一が 「私は創 立 当初 に 有志者 と の 間 に 若 し
堅 実 な公共団体 が 出来た な ら無条件 に 引渡す
べ き事 , 決 し て 小 学校を 私 有す る べ か ら ず と
の 言 質 を握 っ て い ま した の で 屡 々一
「司を慰 諭
し , 目出度 く日本人会 の 経営に 移 っ た の で あ
ります」[同所]と語 っ て い る よ うに ,日本人
学校 は 当初 か ら 「私 的 」 な ま ま で あ っ て は な
一 107 一 463
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東南 ア ジ ア研究 ]8巻 3号
ら な い もの だ っ た 。
と もか くも ,日 本 人 学校が公 的 性 格 を帯 び
る こ と に よ っ て, 大 正 7 年 7 月 5 日
, 在外 指
定学校職員退 隠料及遣族扶助料法第一条 に よ
り , 外務 ・文部両大臣よ り 「在外指定学校」
と して 認 め られ た の で あ る 。 こ れ に よ り ,シ
ン ガ ポ ール 日本小学校 の 教師は , 内地の 公立
学校 の 教師 と同様 の 待遇 を 与 え られ , 外務 省
か らの 補 助金 も学校 に 与 え られ る こ と に な っ
た 。 厂指定 申請 は , 3 年以上 も前か ら続 け られ
た が , 学校が公 的機関 に よ っ て 経 営 され て い
なか っ た か ら そ の 対象 に な らなか っ た」 [小
林 1976 : 119]わ け で あ る。在 留 邦人 全 体 ,
銀行 ・有力商社 そ れ に El本政府 か ら の 経済
的 , 社会的支持を得 て , 日本人学校 は確立 さ
れ る の で ある 。
同 様 の こ とは ,マ ニ ラ の 場 合 に もい え る 。
た だ こ の場合は , 日本人学校が 日本人 会 の 結
成を促 した の で ある 。 こ の 事 情は ,こ うで あ
る 。 「大正 13年 5 月 31 日 在留民 熱 意の 結晶 で
ある校舎が 新築 され る や , 其 の 落成 式席 上 に
於て 学校維待 費の 支 弁 方法 が 協議 され た が ,
ママ従来の 特志者支 出の 一
口 壹比 の維 持費 の み で
は 将来の 経営は不可能で あ るか ら, 此 の 際 日
本人 会な る名称を以 て よ り強力 な邦人団体を ママ組織 し,
一定の 会費を徴集す る こ と に して 小
学校経営 に 当 る べ きで ある と の 議 が 高 ま り…
…」[6 :105]。 同年 8 月 10H,1
,049名 の 会員
を も っ て マ ニ ラ 日本人 会が結成 され て い る 。
しか し, 単 に 日本人会が存在 しさえすれ ば
日 本人学校が設 立 ・維持さ れ る と は 限 ら な
い 。バ タ ビ ヤ の 場合, El本人 会 は大正 2 年の
早 くに で き て い る の に , 小学校が創立 された
の は昭 和 3 年で あ る 。 した が っ て 日本人 会 と
い っ て も, 銀行 ・有力商社 が大 きな経済力を
も っ て そ の 成員 に な っ て い るか ど うか が重要
な の で あ る 。 「在留民 の 面 倒を み る 使命を も
っ て い た 台湾銀行な ど は学校設 立 に 賛成 した
が , 横 浜正 金は 乗 り気 で な か っ た 。 横 浜 正 金
の 態度は 官僚的で , 日本人会長 に な る の も い
やが り , 三 井物 産と台湾 銀行 で か わ る がわ る
や っ て い た」 (石居太楼氏 談話) と い う。 結
局は , 先述 した よ う に , 横浜正 金 銀行 も学校
開設 に賛同 し, 三 宅哲一郎総領事 の 熱心 な働
き掛 け3} が実 っ た の で あ っ た が, こ う し た 銀
行 ・有力商社な ど の 学校設 立 に 直接的利益を
受 け な い ぼ か り か 負担 を 負わ さ れ る 邦 人 が ,
邦人 社会の 構成員で あ る こ とを 自覚 し , 反 対
し続けた 場合 に起 こ る孤 立 を考 慮 せ ざる を え
な い ほ ど , 邦人 社会の 組織化が 進ん で い る か
否か が ポ イ ン トにな る の で ある 。
昭和 5 年当時,台湾銀 行 シ ン ガ ポ ール 支店
長で あ っ た 宮 田章治が , 厂日本人 ノ 居 ル 土地
デ 日本人 ノ 努カ ヤ 発展状態 ヲ 知 ル = ハ 第一
二
日本小学校 ノ有無 ニ ヨ ッ テ 判断ガ ッ キ マ ス,
又 小 学校ガ ア ル ト シ テ 其学校 ノ生徒数 ヤ校舎
ノ外形 ヤ 種 々其 内容 ノ状態 ヲ 見 ル ト其土地 ノ
日本 人 ノ 盛衰 ガ大 体 見 当 ガ 付 ク ノ デ ア リ マ
ス 」[宮田 1933 : 14]と い み じ くもい っ た よ
う に , 日本人 学校 の 存否 ・整 備状況 は , 邦 人
社会 の“
写 し絵”
と もい え る の で あ っ た 。
H 日本人学校の拡張
と もか くも, 日本人学校 は シ ン ガ ポ ール や
マ ニ ラ な どを除 き全校生徒約30 〜 40名 くらい
の規模の ものが 多か っ た が ,
4)校舎を 整 え , 校
具 を拡 充 し , 学則 を 定 め, 教 師 を随 時 採用 し
3)昭和 5年 10月21日 か ら翌 6年 7月18日 まで ,仮
校舎と して 総領事館官邸 の 一部 を 貸 与 して い る
(バ タ ビ ヤ 日本人会 厂在外指定 学校定時報告書」
昭 和 10年 11月20日付)。な お,石居太楼氏 に よ
れば , 三 宅哲一
郎 が 横浜 正 金銀行 を 直接 に 説得
した事実は な い。
4)不完全で は あ るが ,主 な 日本人 学校 の 在籍児童
数 の 変遷を資料 1 (巻末)と して 掲 げる 。 なお
実数 は,外務省外交資料館 に お い て 「在外 日本
人 各学校関係雑件 ・在亜南 ノ 部」 に分類 さ れ て
い る各国民学校文書 , 泰 日 協会学校 (バ ン コ ク
日本人学校),1978再製.「参考資料 ・草創期に
お けるバ ン コ ク 日本人 学校」,河野辰二 (元 マ
ニ ラ 日 本人 学校校 長 ).1978 .『母 校 』 な ど ICよ っ た 。
464 一 108 一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南 洋 に お け る 日本人学 校 の 動 態
て ,
5) 複式学 級 に よ る 少人 数 教育を 確 立
して い っ た 。内地 の 小 学 令 に 基づ き , 次
第 に 体裁を 整 え て い っ た の で あ る 。 そ し
て,
日 本人 学校は , 在留邦人 の 子弟ば か
り で な く, 銀 行 ・有 力商社 の 子弟 の 多 く
を包摂 す る よ うに な り , 在 留邦 人 の 中で
も , 現地 人 を 母親 に もつ 「バ バ 日 本」 や
学校か ら遠 隔 の 地 に あ る 子弟を も包み 込
む 拡 大 の 道 を 辿 っ た 。 しか し学 校 が 大 き
くな れ ばな るほ ど , 在 留邦人 と銀行 ・有
力商社 員と の 問に 断 層 が で き る と い う問
題が あ っ た 。
そ の 最 も典 型 的 な 例 は ,シ ン ガ ポ ー
ル
で あ る。い わ ゆ る 「下町 族」と 「グ ダ ン 族」と
の 分離 と い う こ と で あ る [矢 野 1975 : 124−
131]。銀行 ・有 力商社 の 南方 進 出 に つ れ て ,
一般 に 「南洋各地 の 日本入 社会は , は じめ は
先住 者優 位 , す な わ ち 早 くか ら住み つ い て い
る もの が 発 言権 を もつ, と い う暗 黙 の 了 解が
あ っ た が , 時代 が 経 つ に つ れて 『グ ダ ン 族』
優位 の 傾 向 が 定着 す る」 [同 上 書 : 126]。 こ
の 傾 向は ,シ ン ガ ポ ー
ル 冂本 小学校にお い て
も あ て は ま っ た 。
す で に触 れ た よ うに , もと もと 「下 町 族」
と 「グ ダ ン 族」 と の 間 に は , 口本人 学 校 に 対
す る教 育観 に 大 きな 隔 た りが あ っ た 。 「グダ
ン 族 」 が 望 ん で い る の は , 子 ど もが 内地 の 進
学 階俤を 登 り つ め,
…流 の 会社 ・官庁 に 就職
し て くれ る こ と で ある 。 したが っ て, 粗末 な
口 本 人 学校 教育 を受 け さ せ るよ りは , た とえ
家族が 別れ 別れ に な ろ う と も内地で 教育を受
け させ た 方 が よ い の で あ る 。 も っ と も , 理 想
的な の は , 親 の 膝 下 で 家庭教育 を し っ か り や
5)教師の 採用に つ い て は , 各地 日本人会が , 日
本 人 学校教師,領事館関係,在 留 邦 人 らの 縁故
に よ り詮 衡 す る 場合 と, H 本人会 が 領事館 を
通 して外務省に 詮衡を 依頼す る 場 合 と が あ っ
た。外務省 は 募集 な ど を 経 て 詮衡 に あ た り, 採
用 さ れ た 教師 は,各府県 か ら領事館 へ の 「出 向 」
の辞令を受けて 赴任 した 。 な お ,バ タ ビ ヤ 日 本
人 小学校 の 教師採 用 に,「南洋協会」 が 詮 衡 に
あた っ た こ と もあ る 。
写真 1 完成され た シ ン ガ ポ ール 日本 小 学校
(昭和15年ご ろ 撮影)
り , 内地 と同一 の 学校教育 を 受 け さ せ , 内地
の 一流大学 へ 進学 さ せ る こ とで ある 。 した
が っ て ,日本 人学 校が 次第 に 整 備 さ れ て くる
と , ひ と まず こ こ へ 子 ど もをや り , 卒業 の 1
年か 1 年半前 に は 内地 の 学校 へ 入 れ て 進 学 の
準備 を さ せ る こ と に な る の で あ っ た 。
そ れ に 対 して 「下町 族」 の 方 は , 「立 派な ,
し っ か りした 日本人 に 育て て もら い た い と い
う の が一般的 な 希望 で あ っ た 」 (坂本三 郎 ・
元 シ ン ガ ポー
ル L−1本小 学校校 長談話 )。「下 町
族」 で も裕福 な 層 は , 「グダ ン 族」 と同様内
地 で の 進学 を 望 ん だ が , そ れ と て ゆ くゆ くは ,
シ ン ガ ポ ール の 地で わ が子が 働 くの を期待 も
し て い た の で あ る。か な り の 「下 町 族」 は ,
子 ど もが 日本小学校 を終え る と現地 の 英語学
校 へ や り , 中 に は 高等 科 へ 上 が っ た 段 階 で 夜
間 の 英語 学 校 へ や る 親 も い た 。
6; す な わ ち「下
町 族」 は, 「日本 人 」 と して の 素養 を し っ か
り培 っ た の ち , 現地 で 働 け る知 識 を 身 に つ け
て ほ し か っ た の で あ る 。 た だ , 在 留 邦 人 は
「口本本土 に 帰 っ て も幸せ に な る可能性 の な
い 少数 の 人 間 を の ぞ い て は ,だ れ し も, 日本
に 帰 る こ とを 夢見 た」 [同 一ヒ書 : 128]よ う に,
6) シ ン ガ ポ ール 日本小学校 の 初期 の こ ろは , 午前
中英語学校 へ や り, 午後 日本人学校の 「補習科」
へ や る 親 もい た。
一 109 一 465
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東南 ア ジ ア 研究 18巻 3号
そ の 「定着性」 の 弱 さ も手伝 っ て,
「英 国教
育」 か 「日本教育」か の 岐路に 悩 ん だ 親 も少
な くな か っ た よ うで あ る。 「入 学難 も少 く学
科 の 苦 しみ も少 な い 。 か つ 職業 に 就い て の 安
定 も早 い 」[西村 1941 :256 ]厂英 国教育」か
「大和 魂 を奪 は れ た 偶 像 人 形 」 [同 所]に な ら
な い 「日本教育」 か で ある 。い ずれに せ よ ,
「下 町族」 に は 日本人 と して の プ ラ イ ドが あ
り, わ が 子 に そ れを失 っ て ほ し くな い と い う
熱望 が あ っ た 。 ま た , 「日本 入」 と現 地 で 看
做 され る こ とが 就職 に も有利で あ っ た 。 「日
本 人 は 親切 で, 礼儀正 し く, 規 則 を よ く守 る
と い う こ とで 評 判 が 高 か っ た 」 (石 井肇 ・元 シ
ン ガ ポ ール 日本小学校校長談話) の で ある。
こ うし た 教育要 求 の 食 い 違 い か ら, 当時内
地 に は な か っ た 「英語 」 を設 け る に あ た っ て
も , 「腰か け支店 長 ク ラ ス に は , 必 要が な い
の で あ り , 在留邦人 に は現地 と うま くや っ て
ゆ く上 で 必 要 な の で あ っ た」 (鈴木 了 三 ・元
シ ン ガ ポ ール 日本小学校校長 談話 )。「グダ ン
族」 は 純 日本式 の 教育を , 「下町 族」 は現 地
で 生 活 して ゆ け る教 育の 加 味を も日本入学校
に 期待 した の で あ る 。 父兄会 に も 「グダ ン の
人 が大 部分で , 下 町で も よ い 家 の 人 が 出 て く
る」 (石 井肇氏談話)状態 で あ り, 暇で 教育
熱心 な 「グダ ン 族」 の 母 親 は , 入 れ か わ り毎
日の よ うに学校 を参観 し, 「下町族」 の 母 親
は , 忙 し く, 学校 に す っ か りまかせ て い た と
い う。 「下 町 族」 に は 劣等感や ひ け 目 もあ っ
た の で あ る 。
も っ と も,バ タ ビ ヤ の よ う に , 銀行 ・有力
商社員 の 「上 町」が 厂下町」 に 比 べ か な り少
数派で あ っ た と こ ろ で は , こ の 区別 が 「初め
は あ っ た が 次第 に な くな っ た 」 (石 居 太楼 氏
談話)。 しか も全 校児童数 も 40名 くらい で,
こ の 少入 数 の 中で 親 た ちが分離す る こ と は な
か っ た。 した が っ て , 日本人 社会の 邦人 数 ,
こ の 両者 の 人 口 の 比 率に よ っ て,
こ の 分 離 に
は さ ま ざ ま な 段 階が み られ た で あ ろ うが , 顕
466
在 化 した に せ よ し な か っ た に せ よ,
日本 人学
校 に 対す る 教育 観に 断 層 が あ っ た こ とは 事実
で あ る 。 そ し て,
シ ン ガ ポ ール の よ う に , 「グ
ダ ン 族」 の 勢 力が増 す に つ れ て , 内地 の 中学
校へ 進学す る児童 の 割合が 増 え た の で あ る
(表 1 参 照)。
した が っ て , 日本人 学校は こ う した方 向性
を 異に す る教育要求 に と もに 応 え るべ く拡 充
さ れ て い っ た の で あ るが ,こ の よ うな 当 事者
の 教育観 とは別 の 次 元 で , 日本人 学校は 内地
か ら の 役 割 期 待 を次第 に 色濃 く担 うよ う に な
っ て い っ た 。 そ れ は ,日本人 学校 に お け る教
育 が , 日本 の 移民 政 策 と して , 「南 進」政策
の 一環 と して 位置 づ け られ る よ うに な っ た こ
とを 意 味する 。 そ して こ れに 対応 して , 「在
外 子 弟教 育論 」 も展 開 され るの で あ る 。
も と も と , 日本人 学校 が で きる こ と は ,在
外邦人 の 生活 を安定 させ る の に 役立 ち , 入 口
問題 を抱 え て い た 国 策に 合致す る こ と で あ っ
た 。 南方進 出 の 足 場 を 固 め , 「出稼 ぎ根性 」
を な くさせ るた め に も, 日本人 学校は 有益 な
も の で あ っ た 。 大 正 6 年 8月 26日,
マ ニ ラ 日
本人 小学校 開校式 に あた り祝辞を述 べ た帝 国
総 領事杉村 恒造 も, 「本 島在留邦人 ノ増加 二
伴 ヒ 其 ノ 殖民 ノ 基礎益 々 健全ナ ラ ム コ ト ヲ冀
フ コ ト更 二 切 ナ ル 」 [6 : 4]折 , 「日本人 小学
校並 二 幼 稚 園 ノ 実現 ヲ見 ル ニ 至 リ シ バ 是 レ 小
官 ノ 本望 」[同所]と し , 生 徒に 「他 日 国家有
用 ノ 材 タ ラ ン コ ト ヲ期 セ ラ ル ヘ シ 」 [同所]と
説 い て い る 。
ま た , 内地で は 大正 自由教育 運 動 が起 こ る
な ど, 国家 教 育が や や弛 緩 し た こ ろ の大 正 13
年 5 月 31 日 , 同 じ く杉村 は,新校舎 の 落成式
に 臨 ん で , 「是 レ 偏 二 我 力在留 同 胞諸 氏力 世
界 ノ 文化 二 貢献 セ ラ ル S ノ 熱誠 ト職員諸氏 ノ
忠 実 トニ 帰 セ サ ル ヲ 得 ス 」 [同上 書 :9] と賛
辞を贈 り, 生 徒 に 対 して は , 「各 々 其 ノ分 二
応 シ テ 有用 ノ 人 材 タ ラ ム コ ト ヲ 期 ス ヘ シ 」
[同所]と諭して い る 。
一 110一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南洋 に お け る 日 本 人 学校 の 動 態
表 1
灘ほギ1匙1。趾 ・ 1 ・
笶正 耀1613
第 3 回i
8大正 8 年 度
第 4 回 8一木正 9 年度 1 .第 5 回 1
16大正 】0年度
1
匚e
一ρ0
… 1 ・
6 3 [ 1 1
創 立 以 来 ノ 卒 業 中 途 退 学 児 童 ノ 進 路
中 途 死 亡 内 地 帰 朝 者 当 地 居 住 者
退 学 其 他 毒 圏鑾 暑従事
i一鍵難 一1蓼瑳隠艟 数 艟 数 人 数
1比 率 趣 比 率 瑚 比 率
1騰 匱 率
2…
・ 」酊
1。。ら
1脚 ゜% … L 」 [ 一
…
・
−
f ・
1
ユ Ll6:6奮1、ら鵬 66% 丁 唖 催霧∫ ゴ
1:謡 鎌 :峯1;瓢 1題:声 5131 .25%
10
18.
11
22一
19
…
一
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
年一
年
墾
年.
年
6n
.7蛇
8
燈91410
元
正
正
正
正
和
第
大
第
大一第
大
第
木第
昭
.尸D
lqj
−「
1
6
13 0
10 0
」・1.... ・
1 12 1
「
1
19 33
47
53
一
一
.
一
一
一
ー
ロ ト
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
回
度
毒翼溝…
籌 翫戰駈一
堰振
和
和
和
和
和
和
和…
和
和
和…
和
第昭
第
昭
第
昭
第昭
第昭
第昭
第昭
第昭
第
昭
第昭
第昭
一
7
II 4 .
40.00%−f−1.5.55%1、10 i55.56%
61.11%
11 1
15 18 i o
22i4116 2
L .一一 旨一一
28 1 10 16 . 2
1 1 1
・・ 9 … 3・ … ・
8 36 3
52116 ・ 3610 1
6 1 47 0 1 1
73
16 1 57
i O
66
.
1
魁評 i ・・ 「す一
78 .騰搾 57 : 0 1
(新嘉坡 口本人倶楽部 (編).1939.『赤道を行 く
一 一 81読
一 [
..7−.
31.82% i10 145 .45%− 1 77響27% 42LO5 % E 6
52.63% .6 31 .58 % il
5 126 .31彡1づ 匸 57.89%
一
.9 127 .27%. 9 127
.27% 54.54彩 _一登一L旦6.36% i.
7」 β1.8−?.e,7t
−. 68・1薮6 . 一己6 唖 籀、、磐
1噬 1 1g.147 .旻p% 6 115 .00% …
一一皿 6雀巨0% .一一一「ユ亜一
131 .91% 10 −:21.28% 53,19% −21
.「互σ:
一巳8%
一一7「 1ま「47%
53.85% .23 14L一疂IL% 1.一空..−7.55%
: 49 ・06% 38」至3LQ5%」 5 …
E 58.90%132 .48.48% 1 91
ヒ 62.12彡6
1
39 50.00%! 10 :12.82% 二 .」2.82% 一 三
..一
一 8 : 50.op%
50.00% 40・00%
31,58%
一3 L−LS,75% 1[ 50.00% 3130 .00% II 2120 .00% 50.00% 4122 .22% li 3116 .67% − 3堅L89 % 一.一一 2 1iL8・18≦そを …−L− . _ 18.18% 5122 .73% 1旨 1
6.85/70111 115 .07%
囲 勿 4i
22.73%一專 Insr
’3工蒻
广 琶 II而 %
42 ユ 0%
鉱 157Zg%「可 1江℃5% 36.84%−9「127:
一含7% 1
−−6 1]∫8:19%
45.46彩一4 119:18軣彡丁
一.1 1 4.55%
22.7396
1」− 3r5−7%1一旦L望・8%
21.43%−5 5。%
1
.1。 [噬 00%
37.5。%〕」1 i
.環旦二弖0% − 8 E
−−17φg3
’一.tT.
40 .43 % 8 115 .38彡ぢEI 16 130.77% 46」 5%
匚逗 」蝿二 % .剛 .塁 ⊥髢彩 50、94%1 @ @ @ @ @
19 126.
05% − 4
・坦% .一一一一
6.0
刀Di
5 i 7.58
% 一一. 13 . 64%一一『
一 . 6
|7 幽6 彡ぢ 1− − 2 − − 2 . 57 %
ユb 二瑟右男 一 . 一一 … 一 そ して 昭
11 年 ご ろまで は , ま だ 硬 直し た 「 皇国
教育」に塗 りつ ぶさ れて は い なかっ た 。昭和
年 2 月発行の「 在 南 児 菫 教 育」 (第 16 号 )
掲載され た ,「 新嘉 坡 目本 小学校
育綱領」 7 ) をみると,
本 校は御聖
を奉 体 7 )資 料 2 ( 巻 末 ) と し て 転 載 す
。 新嘉 坡 案内 』 114 .) 一11Q し て 法令 の 示 す所 に 遵ひ 海 外に 在って発展せ
る 在留邦 人 の子 弟を 教 養 し 以 て 天 壌無窮 の
c 運 を 扶翼し 奉 る 皇 国民 の養成 に努む 」 [ 52 ] と し なが らも, 「教 師 の 体 験 ,教 育 的実 , 並 に 深 き 研 究 に 立 脚 し て 教 育 の 実際化,地方 化
努 め る 」 [ 同 所 ] と し て い る し , 「 総 合 的
o , ■
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto UnlverSlty
東南ア ジ ア研 究 18巻 3号
文化 入 格 の 養成 に 努め, 国際都市 , 外領に 在
留せ る日本人 の 子 弟教 育 な る こ とを 自覚 し漸
進 的 に善良 な る新嘉坡 日本小学校 の 校風 樹立
を期 す」 [同 所](傍点 筆 考 ) と 謳 っ て い る 。
ま た 同誌で , 金 田武治は 「第 二 世教育問題
を論ず」 と題 して 「在外 子弟教育 論」 を展 開
して い る 。 金 田 は , 「一時的浮動的 の 出稼移
民 の 如 きは人 ロ 問題 の 解決 に 対 し何等貢 献す
る と こ ろな きの み な らず 日 本文化の 扶殖 に も
役立 たな い 」[金 田 1936 :7]ゆえ , 「確乎た
る永住の 腹 を きめ……独 り在留 日本人 社会 の
み な らず広 く外人 間 に於て 政治的 社会 的経 済
的 に 発 言権 を有す る が 如 き有為 な る 日系市 民
を 作 る事 が 最 も肝 要 」 [同上 論文 : 8]と の 前
提 に 立 っ て , 教育問題 を次 の よ う に 論 じて い
る 。 「初等教育 は 日本精神の 涵養を絶対 第一
義 とす べ きで 第 二 世 は元 よ り全 部 日本人 小学
校 に 入学 せ しむ べ きで ある 。 然 しな が ら日 本
内地 と全 然同一
の 教育を施す事 は意 味を な さ
な い, よ ろ し く授業科 目 の 取捨選 択を行ひ 現
地に 即す る様適 当 に モ デ ィ フ ア イ し , 主要語
学 (当 地 に あ りて は 英語 , 支 那 語 , 馬 来語 の
如 き)及殖民地本国の 地歴 の概念 等を も習得
せ しむ る 必 要 が あ る 」 [同所 ]と 。 そ し て 「中
等以 上 の 教育は 出来得 る限 り其地外人 経 営 の
学校 に入学せ しめ其地市 民 と して の 資格教養
を作 り上 ぐべ きで あ る 」 [同上論文 : 8−9]と
して い る 。 金 田 自身 , 厂欧化 主 義 を 唱ふ る者
で は絶対 な い が , 同 時に 偏狭 な る国粋主 義 も
亦之を取 らな い 」[同上 論文 : 10]と言 明 して
い る の で あ る 。 日本人 学校が , 日本固有 の 文
化を基盤 に もちな が ら, 外在文化を で き る限
り包摂 して い くと い う , 今 日 い う と こ ろ の
“開 か れ た 日本人 学校
”
の 体系 を 認 め ら れ た
時代 で あ っ た。
しか し, 戦時体 制が深ま る に つ れ , 日本 人
学校 も国粋主 義的性格を 強 め て い っ た 。昭 和
14年 2月発 行の 『在南児童 教育』 (第 22 号)
で は 初 め て 表紙に 「堅 忍 持久」 の 標 語が 載せ
られ,
そ の 中で 鈴木了 三 校長 は , 厂国策 の 線
に そ ふ と云 ふ 事 が何か為政者に 無 定見 に 迎合
した り, 事大主 義的 に振舞ふ 事 で あ っ た り,
甚 だ しき は 保 身 術 め い た も の さ へ 介 在 し て ゐ
る現 状 で あ る」 [鈴 木 1939a ]と述 べ て 国策
路線 に 従 う こ と の 必 要 性を訴え た 。 そ して,
こ の 雑 誌の 第23号 (同年 8 月発行 )で 同 校長
は , 厂祖 国 を距 る こ と三 千 哩 の 南 国 シ ン ガ ポ
ール, 気 候 は必 ず しも育 英 の 事業 に適せ ず と
も 環境必 ず し も子 弟 の 教 育道 場 と して 最適
た らず と も, 吾等は常 に 粉骨砕身不退 転 の 信
念 と努力を以 っ て 興亜 聖業 の 継 承 者た る第二
国民 の 精神教育に 邁進 せ ね ば な ら ぬ 」 [鈴木
1939b ]と決 意 の ほ どを述 べ た の で あ る。 し
た が っ て , 校舎は 「聖 な る第二 世の 教育道 場」
[鈴木 1940 : 2]で な けれ ば な ら な か っ た 。
日本人 学校は , 囗本固有 の 文化 の 純度を ます
ます 強め て い くの だ っ た 。 「在外子弟教育論」
もそ れ に歩調 を 合わせ た の で ある 。
と こ ろ で , 南洋 に お ける 日本人 学校が担 わ
ね ばな らなか っ た 重要 な役割 と して ,さ らに
あ げ られ る の は , た と え 遠 隔地 の 子弟で もで
きる 限 り受 け容れて い くとい うこ と で あ る。
数 少な い 学校 し か 設 立 で きな い 事 情 か ら くる
当然 の 帰結 で あ る 。 す なわ ち , 「寄宿 舎」 と
い う もの が重 要 な機能を果た す の で あ る。
例え ば ,シ ン ガ ポ ール 日本小学校付属児 童
寄宿舎 は , 大正 14年 4 月 に 開 舎 し て い るが ,
昭 和 8 年 当時 の 状況 は表 2 の よ うな も の で あ
っ た 。
全校生徒 414名中,1割 弱 が入 舎 して い る 。
そ して , 週 日は 5 時40分 に 起 床 して 家庭 と同
様の 生 活を した の で ある 。 当時舎監で あ っ た
奥 川 寿 津 子 は , 「寄宿 舎 ト シ テ 規 律 的 ナ キ チ
ン ト シ タ 生活 ヲ要求 ス ル ト同 時 二 又 第ニ ノ 家
庭 ト シ テ 子 供 ガ ユ ツ タ リ ト落付イ テ 暖 イ 気 持
デ 勉強 シ テ ユ ク様 ナ 住居 ニ シ テ ヤ ラ ネ バ ナ ラ
ヌ トハ イ ッ モ 心 掛テ ヰ ル 」 [4 : 60] と述 べ て
い る。事実 , 学芸会 , 遠足 , 誕生 祝 い,
三 月
468 一112 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南洋 に お け る 日本人 学校 の 動 瓩1、
表 2
男 女 計 地 方 別
幼 稚 園 1 0
尋 1 5 4
2 6 3
3 2 4
4 2 3
5 2 1
6 3 0
高 1 1 1
計 22 16
lI9
!9 1 ジ ョ ホ
ール
6 1 ス マ トラ
5i マ ラ ッ カ
3 シ ン ガ ポ ール
3238
(『新嘉坡 日本人会 々 報』 1933.18 : 40−41.)
Qσ尸D13
2
38
五 月 節句 , 七 夕祭 , 月見 な ど の 催 しを行 な っ
た の で あ る。
とは い え , 年端 の 行か ぬ 児 童 が , 親元 を 離
れ て 寄 宿 生活 を送 るな ど 尋常 な光 景で は なか
ろ う。しか し ス ラ バ ヤ に お け る 寄 宿 舎 で も子
ど もの 多 くは , 「『行 きた くは な い , で もよ い
人 にな るん だ , よ い 日本人 にな るん だ , それ
で , ス ラ バ ヤ の 寄 宿舎へ 行 くの だ』 と健気 な
決 心 を小 さ い ハー
トに 描 い て ……総 て の 別 れ
の 悲 しみ も 打 忘 れ て 勇 ん で 来 る」S) [山
一.ド
1930](省略 は著者)の だ っ た と い う 。 親 の 心
配 も 通 りで は なか っ た が , 子 ど もは容 易 に
無邪気 な 世界 に 溶 け込 み , 「三 日 もた つ と朝
か ら女 の 児 で も二 杯 も御飯を た べ るや う に な
る 。さ う な っ た ら し め た も の 」 [「司所]な の で
あ っ た 。 ジ ャ ワ 地 域 に お い て 寄宿舎の 必 要度
は 高か っ た が , こ う して 寄宿舎 は“子 ど もの
世界”
を つ くり ,ほ ぼ 子 ど もの 現地 で の 生活
経験 を遮 断する こ と に な っ た 。 そ して そ の 中
で , 日本固有の 価 値観 に 沿 っ て 学 校外 で も生
活 指 導 を 徹 底 さ せ る機能を も っ た の で あ る 。
ま た 何 よ り も寄 宿舎 は , 日 本人 学 校 の も っ て
い る機能 と し て の 在留邦人 の 生 活 の 安定 化 を
補強 する も の で あ っ た 。地 方の 在 留邦人 が い
8)『爪 哇 日 報 』 は 漢 字 に ふ りか な を つ け て い る が,
省略す る 。 以 下 も同 じ。
うよ う に 1 「我 々 親達が 全 く後顧 の 憂 ひ な く
働 き得 る の は一
に掛 っ て こ の 完全な 寄宿舎の
有無 に 係は る ! [3]の で あ っ た 。
しか し, わが 子が通 え る学校 が あ る に 越 し
た こ とは な い 、.H 本人 会の 自負心 も手伝 っ て
各地 に 日本人 学校が 設 Vlさ れた が ,ほ と ん ど
は 恒常 的な 財政 難 に 悩 まさ れ 続 け た の で あ
る 。 ジ ャ ワ 地 域 に お い て もそ うで あ っ た 。 そ
こ で 出 て き た の が , 「組合 学校」構想 で あ る。
こ れは経費節減の た め, 複数の 日 本人学校 が
合 1司 し て 経 営 を 合理 化 ・一一本化 し , 寄 宿 舎本
位の 学校 に し よ う とする もの で,
昭 和 5 年 ご
ろ か ら論 じ られ て い る 。す な わ ち , 昭 和 5 年
4 月 25日付 『爪 哇 日 報 』 の 「爪 哇児 童 教育 に
関す る 「座談会』」 に お い て , 佐藤肇 は , 地
方 の 父 兄 が バ タ ビ ヤ 日本人 小 学校の 厄 介 に な
る こ とを 心 苦 しく思 っ て い る とい う話に な っ
た時, 「一校 へ 収容す る様学校組合を 組織 し
た ら何 うで す 。 詰 りバ タ ビ ヤ ,バ ン ド ン
, チ
エ リ ボ ン 等 の 日会が 組合 を作 り , 学校 に 関 す
る負担 は 組合 日会が 按分 して 之 を負担す る」
[1]こ とを提案 して い る。
また バ タ ビ ヤ 凵本 人小学校初代校長 ・藤原
誠一は , こ の 具体案 と し て 「ス マ ラ ン,
バ タ
ビ ヤ 両校 合同す べ し」 と題す る 論文を発 表 し
[藤原 1930],こ れ を受 け て
, 石 居 太楼 は 「組
合 学校 を 望む」 と い う論題の もとに , そ の 構
想を披瀝 して い る [石居 1930]。藤 原 は ,こ
の 寄宿舎本位 に よ っ て 言 語教育 が 助 か り, y )
予備科を 廃止 で き る こ と , 施 設 の 整 備 に よ り
教 師の 心持 ち も安定す る こ と , 教 師 の 受 け
持 ち の 軽 減 か ら く る 「余 力 で 当 地 に 於 け る
郷上 的教材並 に 郷 王化的指 導 の 研 究」[藤原
1930 :12月15 日]もで き る 点 な ど の 波及 効 果
を指摘 した 。 そ して 石居 は, 貧 弱 な 教育 施設
が 邦人 F弟 の 質 の 低下 を も ら して い る と い わ
れ る現 状を 嘆 じて , 各 1.i本人 会 の 「大同 団
9) 日 本 語 を 話 せ な い で 入 学 して く る 児 童 もか な り
い た 。
一113 一 469
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東南 ア ジ ア 研究 18巻 3号
結」 に よ り 「組合一校 中心学校」 を設立すれ
ば , 教育設 備 は 充実 し , 「蘭 語 を工 と す る 高
等科 な り実業補習学校」 の 経営 も十分可能で
あ る と し, 将来邦人 が 増加 して 小学校 が 分離
設 立 されれ ば ,こ れ が 中学校に な る 可 能性 も
ある と構想 し た の で ある。
こ れ は構想 に終 っ た が , 南洋 な らで は の 着
想 で あ っ た 。 い ず れ に せ よ, 全 般 に 日本人学
校は 財政難に 喘ぎなが ら も徐 々 に 制度 を 整 え
て い っ た が , やが て 戦 火 に み まわ れ る こ と に
な り , 消滅 し て ゆ くの で あ る 。 シ ン ガ ポー
ル
で は , 引 き湯 げ者 が 続 出す る 中 で , 戦争 に な
っ て も内地 へ は 帰 らな い と い う家 庭 の 生 徒50
名が 残 っ た た め , 教 師 13名Pt 5 名が居残 り教
育 に あ た っ た が , イ ン ドへ の 抑留生活 を 強 い
られ た (坂本三 郎氏談話)。 そ して 「昭 和 17
年 8 月 , 第一
次交換船……で 3 人 の 教員 と一
部の 邦 人 は再 び当時の 〈 昭 南島〉 に 下 船 , 国
民学校 と して もとの 校舎で 授業を 再開」[小林
1976 : 120 ]した が , 敗戦 に よ り終止符を う っ
て い る 。 イ ロ イ ロ 日本人 小学校で は , ア メ リ
カ 軍 の パ ナ イ 島上陸時 , 校長以 下 教職 員 ・全
児 童が玉 砕 した 。lo )
皿 教育の 実際と文化摩擦
で は ,こ こ で 日本人学校 の 教育の 中味は ど
うで あ っ た の か , そ れ が子 ど もの 生活 と ど の
よ うに 関連 した の か と い う問題 に 入 っ て ゆ こ
う。
「文化 摩擦」(cultural con 且ict)と い う概念
が あ る 、、異 質 な文 化 要素 が摩 擦 を起 こ す 現 象
を意 味する用語で あ る が ,南洋文化圏で 日本
10)「孤 立 無援 と な っ た イ ロ イ ロ 市 で は , 全 在 留 邦
入 が 高 江 州 会 長 と と も に,ま た 小学校で は 全児
童 ・職員が栢森功校長 (新潟県人 ) に 引率 され
て , 定 め られ た 自決 の 場 所へ お もむ き ,
一同静
か に 日 の 丸 の 旗 を 仰 い で 君 が 代 を 合唱 し,祖国
の 平 和 と繁栄を祈りな が ら,全員,悲 壮な 玉 砕
を遂げ た の で あ る」[金 ヶ 江 1968 :381〕。
人 子弟を教育する とい う営みを捉 える分析枠
組 と して 有 効 で あ る と 予 想 さ れ る。 し か し ,
そ れ は 半面 の 有効性 しか も っ て い な い と い え
るだ ろ う。 コ ン フ リ ク ト とは , 心 理 学 で は
「相反す る方向 を もつ 複数の 要求 ・衝動 ・動機
が , 同時 に 作用 し て 個 人 の 行 動 を支 配 しよ う
とする た め に 生ず る拮抗お よび緊 張 の 状態」
[池 内 1971 : 8]を さ し , 社会学 で は 「個人
間,集 団間 に 生 ず る敵対的行 動 , 対 立 ・抗 争
の 関係」[同所] (い わゆ る 厂社会摩擦」)を示
す用 語 で あ る が , 日本人 学校教育 に お い て,
“南 洋 文 化
”か
ト‘日 本 文 化
”か の 二 者 択
一に よ
る“
摩擦”
に苦 しん だ と い う例は 皆無 に 等 し
く, 中国人と の 「社会摩擦」 は あ っ た 11 ) も
の の, 原住 民 との 「社会摩擦」 は全 くと い 6
て よ い ほ ど な か っ た の で あ る 。 す なわ ち , 「文
化摩擦」 の 深刻な 局面は価 値観 の世界 に お い
て で あろ うが , 日本 固有の 価値観 は ほ とん ど
絶対的 なま で に 邦人 に 内面 化 され て お り, 現
地 文化 が そ れ よ り も価値 あ る もの と して 浮か
び上 が り , 両 者 が 同等の 力学を も っ て 個人 に
選 択を迫 る と い う状況 は まず な か っ た の で あ
る。邦人 の 価 値観 の 世界 で は , 日本文 化 と現
地文 化 に は大 きな落差が あ っ た 。イ ギ リス 。
オ ラ ン ダの よ うな支配 国 の文化 との間 には そ
うな る 可能性 は か な りあ っ た が , 「英 国教 育
か 日本教育 か」 の 問題 も生活 の 便宜 上 の“
摩
擦”
で あ り, 「文化 」摩擦 とは い い 難い 。 そ
れ らの 人 々 と直接 に接触 す る機 会 も乏 しか っ
た 。 そ して, 在 留邦人 は 生活 の 必 要上 , 現地
文化 に 溶 け込ん で 商売をや っ て ゆか ね ば な ら
ず , 「摩 擦」 は あ っ て はな らな い もの で あ っ
た 。
つ ま り, た と え 相容れ な い 文化 要素 が併存
して い よ うと も , す な わ ち 「潜 在 的 摩 擦」
11)例 え ば ,シ ン ガ ポール 日本小学校で は 満州事変
時 に,支 那 人 が 「児童の 登校に 際 して 投石 した
り暴行 を加 へ る こ と も70件 の 多 き に 及 ん だ 。 日
本小学校 は 臨時休校 の 止 む な き事 と な っ た 」
[高臼ヨ 1944: 194]Q
470 一 114一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南 洋に お け る 日 本 人 学校 の 動 態
(potential conflict )[Getzels & Guba 1954 :
166]が存在 して い よ うと も, 個人 の 意 識 に そ
れ らが 上 っ て こ な い ほ ど邦人 の 価 値世界 は堅
固 で あ り,閉 鎖 的で あ っ た の で あ る。そ して
支配 国 は 日本人 学校 の 教育活動 に 寛容 で あ
り, 原住民 ともど もほ と ん ど“
放任”
の 状態
で あ っ た 。
しか し , 無為 の 状態 な ら ば , 気 候に よ り大
き く規定 さ れ た“南 洋的 生 活 様式
”が
,日 本
文化の 濃 度を著 し く希薄 に して い っ た で あ ろ
う。 そ れ を食 い 1ヒめ よ う と す る 日本文化の 力
学 と生 活 全 体を覆 う臼然 な 力 学 と して の 南 洋
文化 と の 間の 「摩擦」, そ れ は あ っ た と い え
る。
以上 の こ とを 念 頭 に お き な が ら , 具体的事
実 に 即 し て , さ らに こ の 間題を 検討 し て み よ
う 。 まず カ リキ ュ ラ ム に つ い て で あ る。 カ リ
キ ュ ラ ム の 点 よ りみ た 摩 擦 と い え ば , 教 育 の
実 際場面で 子 ど もの 現 地で の 生活を 基盤に し
て 授 業を進 め て い か ね ば な らぬ こ と , 将 来現
地 で 生 活 し て ゆ け る人 間を も育て な けれ ば な
らなか っ た こ と と関連 して くる 。 カ リキ ュ ラ
ム と は, 「フ ォ
ーマ ル な 教育組織 に よ っ て 意
図的 に 配列 され る 学習経験 な い し そ の 連 続
休 」[Musgrave 1973 : 41]を意 味 し,「教科
指 導一1(academic curriculum )と 「生 活 指 導」
(moral curriculum )を 含 む と い え るが ,日 本
人学校 の 教 育場面で は , こ う した フ ォー
マ ル
・カ リキ ュ ラ ム の 実 施 に あ た っ て, 子 ど もの
現地生 活 と の 連 携を 考慮せ ざ る を え な い と い
う こ と が あ る 。 まず フ ォー
マ ル ・カ リキ ュ ラ
ム の 作成 自休が こ の 問題を孕 ん で くる 。
しか し , 結論を 先 に す るな ら , 日本 の 国 定
教科書 を は じめ と す る 教材を支 え る 「忠 孝」
な ど の 価値 観な い し原 則は 強固 な核 を形成 し
て お り , 現地文化 は せ い ぜ い そ の 周辺 部分 に
付着 して い た に 過 ぎ な い。 す な わ ち , 現地 の
文化 要 素 の 中で , 核 の 部 分 の 価 値 観 な い し原
則を流布す る の に 便宜 上 都合の よ い 要素だ け
が 拾わ れ , 教材 とな っ た とい っ て よ い 。こ う
した 現地文化 の 要素を 含む科 目 は 主 と して ,
英語 , 理 科 , 地 理 , 歴史で あ っ た が , 英 語 は
内地 で の 進 学 に も必 要 に な っ て く る も の で あ
り,理 科の 教材 で も現 地 の も の で 「間 に 合 わ
せ る」 こ とは あ っ て も別 に 問 題 は な い の で あ
る。地 理 , 歴史 に して も, 例え ば マ ニ ラ 日本
人 小学校で は , フ ィ リ ピ ン の 一般事情 を 盛 り
込 ん だ 『郷 土読 本』 [6 : 154−155ユを つ く っ た
が , それ は 副読本で あ り, 「授業の 合間 , 合
聞 に 投入 され る」 (石 黒 芳 男 ・元 マ ニ ラ 目 本 人
小学 校訓 導談話 ) もの に 過 ぎ なか っ た 。内地
で 流行 した 「郷 土 教育」 の 実 践 に お い て も ,
「現 地 」 が 「郷 土 」 に な り , 現地 文 化 が よ り
多 くもち込 ま れ る こ とは あ っ て も , 内地 の 教
科書 と の 矛 盾 を体験 した 記 録 や 発 言は み られ
な い 。 また生活指導 に して も , 原住民 の 生活
習慣 に 学 ん で 生 徒 を 指導 す る と い う こ と も皆
無 に 等 しか っ た 。
とは い え , 実際 の 授業 場面 で は , r一ど もの
イ メージ に 合 わ せ て 学習経験が な された はず
で あ る 。 「実 例」や 「挿 話」 の 形 で , 現地文化
が 少な か らず流れ込 ん だ で あ ろ う 。 しか し,
そ の 機能 は , フ ォー
マ ル ・カ リキ ュ ラ ム 浸 透
の ため の 「潤 滑油 」に しか 過 ぎ な か っ た と思
わ れ る。
さ ら に は , 「潤滑油」 た る べ く, 現
地 文化は 巧 み に 変 容さ せ ら れ て もち 込 ま れ た
と い っ て よ い で あ ろ う。
い ず れ に せ よ,“南洋 文化
”に よ る
“日本文
化”
の 「風 化 」を 防止 す る の が 日木人学校 の
重 要 な機 能 で あ った 。シ ン ガ ポ ール 日本小 学
校第 4 代校長 ・杉 本直樹 は ,周囲の 児 童 を み
て 次 の よ うな 点 を 嘆 い て い る。「周 囲 の 事象 ,
物 象に 対す る 心 の 底 の 底か らの 感 じ , 心 の 底
に 彫 りつ け た 様な 感 じ方 が も っ と もっ とあ っ
て い い と思 は れ る、……浅 い , 浅 い ,,彼等 の
感受 は 極 め て 浅 い 」 [杉本 1932 : 6], 「空気
の ぬ け た ゴ ム 鞠 。何 故か ……さ う した感 が し
て な ら な い 、,……周囲の 力に の み 依 っ て 形を
_ 115 一 471
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東南ア ジ ァ 研究 18巻 3号
写真 2 バ ギ オ 日本人小学校 の 生徒 た ち
左右 され る ゴ ム 鞠 。反 発性 の 乏 し い 児 童の 生
命の 創造 は 全 く支離滅裂で ある 」[同上 論文 :
6−7], 「内観 を 欠 く人 の 生 活 は 間 口 は 広 い 様
で も そ の 人 自身 の 血 の 通 づ た もの で は な い 。
……借 り物 の 生活一己 の 血 の 通 は ぬ 生 活
一 そ れ が 私 の 周 囲 に ある大部 分の 児 童 の 生
活 で はあ る ま い か」 [同 上 論文 : 8], 「読本 を
読 ませ て 見 る 。 曲 りな りに で も一通 り読めた
ら も う其 の 上 に 探 ら う と は せ ぬ 。彼 等 に は 世
界が余 り に 早 く陳腐 に な っ て 仕 舞ふ 」 [同 上
論 文 : 10], 「奮闘を楽 しむ気分が な い。 努 力
の 後の 歓喜を しみ じみ味 へ た経 験が乏 しい 。
……教 室 の 掃 除 をす れ ば塵 埃 を 吸 っ て 肺 が弱
くな る と 言 ふ 事 を余 り に よ く知 っ て 居 て, 掃
除 に 汗を 流 した 後 の 気分 を 味 へ た事 が な い 」
[同 と論文 :11], 「咋 EI定 めた 事 が 今 日 ま で
継続せ ぬ。 朝思 ひ 立 っ た 事 が 夜 ま で 続 か ぬ 。
一時間の 初 め に 決心 した 事が其 の 時間 の 終 り
ま で 持続 出来 ぬ 。……彼 等 の 初
一念 は常 に 彼
等 自身 に 依 一て 破 壊 さ れ て 居 る 。
……何故斯
も早感 , 早 忘な の だ ら う 。 薄志 弱行 な の だ ら
う 。 堅 忍 持久 の 質 が な い の だ ら う」 [同上 論
文 : 12]。杉 本 自身認 め て い る よ うに ,「余 り
に 酷 な批 評 」 で あ っ た か も しれ な い が ,こ う
した感受性 , 反発性 , 内観性 , 探求性 , 奮闘
性 , 固執性 の 欠如が 目を 引 い た の で ある 。
こ う した 児 童 の 性 向の原 因は ど こ に あ っ た
の だ ろ うか 。 気候が 神経の 働 き を鈍 らせ る影
472
響 は大 きい 。 しか し , 現地の 使用 人か ら
の 影響 もあ っ た 。 普通 の 邦人 家 庭 で, 子
守 , 炊 事 , 洗濯 , 車の 運 転な ど の 使用人
が 2,3 名い た が , 「忍 耐力 の 消耗す る の
も, 持久 力の 弱 る の も , 此 の一ヒ人 に 禍
され る の で は な い か 。父母 が丹念 に 教 へ
る 礼 儀作法 も, 清潔 も整頓 も , 後 か ら後
か ら と , 生 きた 模範の 土人 に 崩 され て 行
く」[堀之 内 1930]こ とが少な くなか っ
た と い う 。 子 ど も は 日 常 生活 の 中 で は ぐ
くまれ ,
“
い うよ う に は な らぬ が , す る
よ うに は な る”
の で あ っ た 。現 地 人 の 子 ど も
か ら受 け る“悪 影 響
”
を避 けよ うと , 親が 子
ど もを家 庭 に 「隔離 」 す る と , 子 ど もは ます
ます こ の 使 用人 の 影 響下 に 入 り, 「子 ど もの
世 界」 を喪失 して ,
“
早熟”
の 弊を 生 む の で
あ っ た 。 こ う した“弊 害
”
を除去す る た め に
も , 日本人 学校 や寄 宿舎で の 教育 作用 に 期待
が もた れ た ので あるが , 藤原誠一が , 「召使
達 か ら の 影 響を 受 け る の で せ うが , 子 供 が よ
く金銭 の 話 や , 男女の 話を した りします 。 今
言 っ た 様 な 点 に 付 い て 私は い つ も苦 し ん で ゐ
る の で あ ります」[2]と真情 を吐露 した よ う
に ,
“南 洋 文化 の 切 除
”に 伴 う摩擦 は小 さ く
な か っ た 。
しか し , 全 般 的 に み れ ば ,こ う した 摩擦 は
日本人学校教師 を恒常 的に 悩 ます ま で に は 至
らな か っ た 。 教 師自身 の 神経 が純化の 作用 を
受 けたの か もしれ ない が, 「日 本文 化の 保持」
へ 向 け て 多 く の 要 因 が 効果 的 に 働 い た の で あ
る 。 「帝国練習艦隊」 の 寄港を 見学す る こ と
に よ る ナ シ ョ ナ リズ ム の 発 揚,毎年 3 分の 1
の 児 童 が 内地 か ら転人 して き て 内地 の 教 育事
情 が流 入 す る こ と , 「餅 つ き」 な ど の 日 本 の
行事 の 導入 , 目本 の 風物 を撮 っ た映写機 ・ス
ラ イ ド の 活用 , 宮城 へ 向か っ て の 遙 拝 な ど の
儀式 , 角力 ・弓道 な ど の 奨 励, 故国か ら遠距
離 に ある こ とが 愛国心 を 増幅 させ る 心 理 的効
果 , 多民族間で の 民族意識……。 そ して 何よ
一 116 一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南 洋 に お け る 日 本 人 学 校 の 動 態
り も親た ちが 忠君愛 国の 精神 を確 固 と し て も
ち , 「一
等 国 民 」 の 矜 持が あ っ た こ と , こ れ
ら が 連動 し て , 他文 化 を 価 値 あ る も の と して
浮 上 させ な い 世 界 を 形成 して い た の で あ る 。
以 ヒ,南洋 に お け る 目本人 学校 の 問題 性 を
み て きた が , 教師 問 題 , 財 政 , 卒 業生 の 進路
な ど , 書 き残 した こ と も多 い 。 個 々 の 日 本 人
学 校 の 歩 み に も詳 し く立 ち 至 ら な い と い け な
い と思 う,,い ずれ 稿を改 め て 論 じて み た い と
考 え て い る 。
(付 記 )本 稿作成 に あた り , 特 に お 世話を
い た だ い た 次の 方 々 に お礼 申 し上 げ ます (順
不同)。
元 シ ン ガ ポ ール 日 本小 学 校 校 長 ・鈴 木 了 三,
坂本三 郎 , 石井肇 , 元 ・同 訓 導 ・上 田書雄 ,
山県獅子夫 , 元 ・同生徒 ・関清 , 坂 本嘉子 ,
烱 和子 , 魚 住 晴恵 , 元 新嘉坡 日 報 記 者 ・木村
二 郎 , それ に 福 田 庫 八 の 各 氏 。元 マ ニ ラ 日本
人 小 学校校 長 ・河 野 辰二 , 元 ・同 訓 導 ・石 黒
芳 男 , 元 バ タ ビ ヤ 日 本 人 小学校校長 ・遠 藤武
治 , 元 ・同 訓 導 ・遠藤 キ イ, 元 ・同生徒 ・花
岡泰 次 , 花岡泰隆 , 伊藤健一
郎 , 中安貞子 ,
そ れ に 石居太楼 の 各氏 u
6〔〕0
500
400
300
25〔1
2〔〕o
15〔1
10e
5〔〕名
378
ラ ン
173
ク
大.「1二 昭利
12 15 ‘〜 7891 () 11121314123456789101112131 ・1 ]51617
資料 1 日 本 人 学 校 在 籍 児 童 数 の 変 遷
一 117 一 473
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
東 南ア ジア 研究 】8巻 3号
資料 2 新嘉坡 日本小学校教育綱領
根本方針
本校 は 御聖旨を奉体 して 法令 の 示 す所 に 遵 ひ 海外
に 在 つ て 発展せ る 在留邦人 の 子弟 を 教養 し以 て 天 壌
無窮 の 皇運を扶翼 し奉 る皇国民 の 養成 に努む 。
一,国体観念を明徴 に して 祖国愛 の 精神 を作興 し
海外 に 在 つ て 日 本精神の 顕現発揚を忘れ ざ る
子 弟 を 教 養 す 。
二 ,時代 の 趨勢,教育 の 思 潮等を洞察 し付和雷同
す る こ とな く健実 な る思 慮 の 上 に 立 つ て 採長
補短 ,穏健中正 の 教育 を な す 。
三 ,教 師の 体 験 ,教 育的 事 実,並 に 深 き 研究 に 立
脚 して教育 の 実際化 , 地方化 に努め る。
四 ,家庭 と の 連絡 を 密接 にす る と と も に 団体的精
神 の 涵養 に 努 め児 童 を して 有為有守 , 生 気 あ
る第 二 世た らしむべ く努む 。
五 ,総合的文化人格 の 育成 に 努め,国際都市,外
領 に在留せる 日本人 の子弟教育なる ことを自
覚 し漸 進的 に 善良 な る 新嘉坡 日 本小学校 の 校
風樹立を期す e
六 ,本校児 童 を 分 か ち て , 1 当 地 に 永 住 の 目 的を
有 し日本語 に よ る学校教育は 本校を 以て 最後
と す る者 と 2 進 ん で 内 地 へ 進学す る もの と に
大別 し得れ ど も本校 の 教育方 針 の 根本 は 知
育,訓 育,体育 ともに一
方に偏す る こ と な し。
七,質実剛健 な る意志,創造的活動的人 格,頑健
に して 弾力あ る身体 の 持主 た ら しむ べ く注意
を払ふ 。
要 は 海外 に 在 留 す る第 二 世 の 教 育 な る 事 を 自 覚
し,児童の 現実生活を基調 とし一
歩一歩 と漸進的な
る 向上 を企 図 し,気候,環境等 よ り来 る放縦怠慢 の
気 風 に 感 染 す る事 な く崇 高 偉大 な る 国 民 的 人 格 の 基
礎を達成す べ く努力 す 。
知 育綱領 =実力 の 養成 , 不断 の 努カ
ー,教師自 ら知識 の 深化浄化 に 努む 。
二 ,善良 な る学 習 態 度 の 樹 立 に 力 を 尽 す 。
三 , 各科学習法 の 徹底的訓練 を 図 る 。
四,学習上 一直観化,具体化,作業化,郷土 化 に 最
善を尽す。
五 , 熱帯地 に 於け る学習方法を合理的且 つ 経済的 に
指導す る方法を 研究す。
要は児童自ら知 識の 吸収に興味を持ち自 ら研究 し
発 表 し吟味 し何事 も 自力 に 依 つ て 為 さ ん と す る試為
的態 度 の 養成 に努力 す。
訓育綱領 一健全 な る 思想,不屈 の 精神
一, 教師 自ら実践躬行 よ く児童を感化誘導 し得 る 力
を養ふ 。
二 ,酷暑 に め げず酷熱 に 撓 ま ず営 々 として 努 め 孜 々
と して 活 動 し得 る意 志 の 鍛 練 に 留 意 す 。
三 ,常に皇室を崇 び 国家を愛 し敬神 尊 祖 の 念 を 養
ふ 。
四 ,自治自律 を 旨と し雄大応揚な る 気風 と大国民 た
るの 襟度 の 快活な る心状に 導 く。
五 ,日本 人 た る の 自覚 を 促 し凡 べ て の 行動を厳正 な
る道徳的価値判断 と旺 盛な る意志的行為 に導 き
得 る善良進取 の 習慣を養ふ 。
六,個別的 に 温 情的指導 を な す は 勿論な る も特 に 国
際場裡 に在 つ て 活躍すべ き 日本 人 と して の 国体
的訓練に力を注ぎ其の方法を研究す 。
七 ,環 境 に 依 つ て 養 は れ る 日 本 人 気 質 (大家族 を 単
位 とし, 村 を 単位 とし,町,郡を単位 と して)
は当地 に於 い て は教育指導困難 な る も努 め て 此
の 方面 の 教化 に 心掛 く。
八,海外 に 在 る の 故を以つ て 特 に 日本古来 よ り子供
を 中心 と して 伝 は れ る 良風習 は な る べ く尊 重
し , 行事 の 行 ふ べ き もの は 努 め て 実施す 。
要 は勅語 , 詔書並 に 国民精神作興 に 関す る詔勅等
の 御趣 旨に 基 き 自覚 の 徹底を基調 と した る,自治 自
律道徳 の 実践を指導督励 し以つ て 日本人 と して 恥 じ
ざ る徳性の 涵養 に努力する に あり。
体育綱領 =抵抗弾力 の あ る 身体 , 元気 旺 盛 な る
意気
一,熱帯地 に成 長せ る児 童 の 体 質 が 比較的 脆 弱 な る
こ と を 自覚 せ しめ各 自 に よ り体格 体質 ,体力
の (個別的並 に 団体的 に )向上 を 重 ん ず る習慣
を養ふ 。
二 ,体育気分を 旺 盛 な ら しめ 体育趣味 の 涵 養 に 努
む 。
三 ,厳粛 な る規律的 行動を鍛練 し環境よ り来 る 遊
惰 , 安逸 , 倫安 , 姑息 の 気風を矯 め健全 に して
旺盛 なる児童 の 心身発育を助長せ しむ る こ とに
努む。
四 ,衛生思想 の 普及 に 留意 し其の 実践を図 る こ と。
474 一 118 一
N 工工一Eleotronio Library
Kyoto University
NII-Electronic Library Service
Kyoto University
小 島 :南 洋 に お け る 日 本人 学校 の 動 態
五 ,体育に 関す る 知識教育 に 意を用 ふ と同時 に 児童
の 体育 向上 に 関 し,よ り以上 の 研究をな す。
六,動作を機敏に な す と同時 に 元気 旺 盛 な る 意 気 の
養成に努力す。
要 は 健 全 な る精神 は 強健 な る身体に宿 る こ とに 留
意 し , 児 童 を して 身体 の 強健 が 自己 完成 の 根幹 た る
こ とを自覚 せ しめ ,積極的 に は 自己 身体 の 鍛 練 に 努
力 し,消極的 に は衛生思想 に 目覚 め て 清潔 を 愛 好 す
る習慣を養 ふ に あり。
文 献
藤 原誠 一・1930.「ス マ ラ ン ,バ タ ビ ヤ 両校合 同 す
べ し」 「爪 哇 円報 』 12月 15日〜12月 17口,
福田太一.1933.「憶出」『在南児童 教育』11 : 53−
54.Getzels, J. W .; and Guba , E . G .1954, Role
,
Role Conflict, and Effectivencss: An Elnpirical
Study . nmerican Socio/ogica / Rez,teecb 19 : 164−
175.
堀之 内吉内.1930.「爪 哇 に 於 け る子 弟教育 に 就 い
て 」『爪哇 目報』 1 月 1 日.
池内 一.1971.「コ ン フ リク トの 社会 心 理 学 」 『年
報 ・社会心理学』 12 : 8−35.
石居太楼.1930.「組合学校を望む」『爪哇 日報』12
月 18日〜12月 20凵 お よ び 工2月22 日〜12月 23H .
金 田武治,1936.「第 二 世教育問題を論ず」「在南 児
童教育』 16 : 5−10,
金 ケ 江清太郎.1968,r歩 い て 来 た 道一 ヒ リ ッ ピ
ン 物語一
』 東京 : 国政社.
小 林 昭 ,1976.「学校む か し昔」『シ ン ガ ポ ール 日
本人学校 10年 の 歩み』 118−120 ペ ージ 所収. シ
ン ガ ポ ール .
前 田 治行.1968.「バ ン ド ン 邦人 の 歩ん だ姿」 rジ ャ
ガ タ ラ 閑話 蘭印時代邦人 の 足 跡 一』武田
重三 郎 (編),133−141 ペ ージ 所収.長崎.
宮 田章治.1933.「祝辞 」r在南児童教育.111 :13−15.
Musgrave, P . W .1973.ノrnOtwle4
.ae , Czarrieulum and
Chan8e . Melbourne : Melbourne University
PreSS.
西 村 竹 四 郎,1941.『シ ン ガ ポール 三 十 五 年』東京 :
東水社,
坂本徳松.1942.「文化 ・宗教 」 『南方共栄圏 の 全貌 』
佐藤 弘 (編 ),795−863ペ ージ所収.東京 : 旺 文
社.
色部米作.1926.r南洋 に 於 け る 邦 人 の 事 業 』 (南支
那 及 南 洋調 査 118)台北 :台湾総督官房調 査課.
菅沼 毅.1968.「佐藤茂 の 歩 ん だ道」rジ ャ ガ タ ラ
閑話 蘭印時代邦人 の 足跡一
』武 田 重 三 郎
(編),101−109 ペ ージ 所 収.長 崎.
杉本直樹.1932.「私 の 周囲 の 児童を眺 め て 」 『在南
児童教育』 10 : 1−13.
鈴木 了 三 .1939 a .「二 十 二 号 発 刊 に 際 して 」 『在南
児童教育 』 22 : 巻頭.
一 ..1939b .「巻頭 の辞」 『在 南 児 童 教 育』
23 : 巻頭.
.一一.1940。「奉祝記念号発刊 の 辞」『在南児童
教育』 24 : 1−2.
高 田儀 三 郎.1944.「烈士 西村吉夫君を偲ぷ 』(直
筆 ).
山下兼秀.1930.「南洋爪哇 に 於 け る児 童教 育 の 展
望」『爪畦 日報』 1月24日.
矢野 暢.1975.『「南 進 」 の 系譜』 東京 :中央公論
社 .
米田正武 .1940.「在 比島邦人子弟の 学校教育 に 関
す る 調 査 」 「拓殖奨励館季報 』 1(4):127−186・
L1930 .「爪 哇 児 童教育 に 関す る 『座談会「1」 『爪
哇 日報』 4 月 25 日.2.1930.「バ タ ビ ヤ 父 兄 会に 於 け る藤 原校 長 の 感
想 と意 見」 『爪 哇 日 報』 12月 11日.3.地方 の 父.1930.「反対 の 人 々 に 」『爪哇 日報』
12月 30 日.
4.1934, 『新嘉坡 日本人会 々 報』19.
5.1936.『在南児童教育』16 : 2−4.6.1938.『創立二 十周年記念誌』
一一119 一 475
N 工工一Eleotronio Library