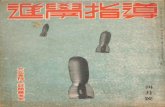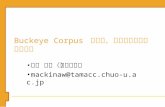旧満州における民族間の居住分化の状況(下)―南満州鉄道付属地都市の事例―...
Transcript of 旧満州における民族間の居住分化の状況(下)―南満州鉄道付属地都市の事例―...
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
1
旧満州における民族間の居住分化の状況(下)―南満州鉄道付属地都市の事例―
Rosalia AVILA TAPIES
ロサリア・アビラ・タピエス
Abstract:
In this article, the causes of the residential segregation between the Japanese and the
Chinese in the cities of the South Manchuria Railway Zone are analysed. These cities were
built and administered by the South Manchuria Railway Company (Mantetsu) between the
years 1907 and 1937.
The Chinese and Japanese were the two large ethnic groups residing in these railway
cities, and therefore, there were many possibilities of contact and exchange. In this study,
the nature of that inter-ethnic contact is examined through the analysis of the patterns of
residential distribution of each group and of the levels of segregation or coexistence (the
first part of this article), and through the determination and analysis of the causes of
segregation, employing quantitative and qualitative techniques (second part). Thus,
through the calculation of the Index of Dissimilarity (I.D.) for different pairs of ethnic
groups between 1920 and 1936, the existence of medium and high levels of segregation in
these cities was revealed. Specifically, segregation between the Japanese and the Chinese
for the years 1930 and 1936 obtained an approximate mean value of 50 (interpreted in the
sense that 50% of the Japanese or the Chinese should move to another residential district
to reach equidistribution). In this article, the examination of the causes of segregation
focused on this pair because it is quantitatively the most significant.
To discover the predictors of segregation, we applied multiple regression on two
differentiated studies: ① a cross-sectional study with multivariate analysis of the levels
of segregation between cities for the years 1930 and 1936, treated separately; and ② a
longitudinal study with multivariate analysis of the changes in levels of segregation
between 1930 and 1936. The independent variables considered were those that could
affect the redistribution of the population in the city (see Tables 3.a and 4.a).
The regression analyses revealed that: ① there was a negative and statistically
significant relation between the levels of residential segregation and the percentage of
domestic employees; that is, a higher presence of domestic employees (Japanese or
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
2
Chinese) implied less segregation; and that, ② there was a positive and significant
relation between changes in the levels of segregation and changes in the percentage of
Japanese population working in the transportation sector; that is, a greater increase of
Japanese population in the transportation sector was related to a greater increase of
segregation over time.
The association between presence of Japanese in the transportation sector (Mantetsu
employees) and residential segregation between the Japanese and the Chinese is
revealing; therefore, we have studied the residential policy of Mantetsu, considered to
have the greatest responsibility for urban management. In spite of the regulations about
the use of urban space, a specific residence zoning by races is not specified; in practice,
the company reserved urban space for its Japanese employees, for whom it established
reserved institutions and infrastructures, thus hindering the inter-ethnic contact and
contact between the different socio-economic Japanese classes. The spatial segregation
of the workers of Mantetsu fomented the creation and maintenance of stereotypes and
social distance, maintaining inter-ethnic relations at an occupational level (functional
integration), but rarely at a social level. The present study thus allows us to glimpse how
the imperialist utopia of Manchukuo and the principle of racial harmony did not affect the
residential segregationist policy of Mantetsu. We can see how the construction of the
empire and the business strategy of Mantetsu responded to different kinds of logics.
1. はじめに
2.定着フロンテイアの満州
3.多民族形成都市
4.民族間の居住分化
4. 1.南満州鉄道付属地の市街地
4.2.居住分化の指数
4.3.統計資料上の「民族」の概念及びその制限
4.4.民族間居住分化の時系列及び都市別変化の検討
5.次回
以上本号 (上)
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
3
6.前回より
20世紀前半の満州におけるロシアおよび日
本の植民地事業による都市設立は諸民族の
居住地域の拡大をもたらした。その結果、多
民族の共住空間となった満州の各都市では
国際交流の機会が生じた。
本論の研究対象である南満州の鉄道付属地
の各都市は、日本の支配下であっても中国の
領土内であり、漢族、満族、朝鮮人、西洋人
も多く暮らし、また日本人と他の民族の接触
が不可避な社会であった。しかし、一般的に
は植民都市(colonial city)の都市計画の
中心となる要素は民族間の居住分化(ethnic
residential segregation)にあるので、本論
では、前回に調べた日本人と他民族の相互間
の居住分化度を計量的に分析し、鉄道付属地
に住む最も大きな民族集団である日本人と
「満州人」1の間の居住分化の要因と満鉄の居
住政策との関連を検討するとともに、各民族
との国際交流の深さを推察する。
前回は、満鉄が経営した南満の鉄道付属地市
街を対象に1907年から1937年までの約30年間
について、地域的観点に立って各都市における
諸民族の存在形態と居住状況にアプローチし、
各々の民族の都市内居住分布パターンからそ
の都市における民族間の居住分化状況につい
て分析を行った。また、4民族の相互間の居住
分 化 度 を み る た め に 非 類 似 指 数 (Index of
Dissimilarity=I.D.)2を算出し、満州国の建設が
国際交流、具体的には諸民族の居住パターン
に与えた影響について考察した。
満鉄時代の鉄道付属地市街における日本人と
他の民族集団との居住分化度はいずれの時期
も概ね中位に止まっている。その中で最も低い
居住分化度は満州人と日本人の間でみられる。
(表1)満州人と日本人のI.D.の変化は20年代を
通して居住地分離現象の若干の増加がみられ
るが、30年代には横ばいとなる。また朝鮮人と日
本人のI.D.もほぼ横ばいで推移するが、その他
の外国人と日本人のI.D.は増加する。付属地市
街においては一般的には満州人は他の民族集
団より日本人に類似の居住分布パターンを示し、
日本人植民者の家族と出稼ぎ中国人男性の居
住分布パターンは他の民族と比べ相対的に類
似点が多い。つまり、出稼ぎ中国人は他の民族
より日本人との接触が多くあったことを意味して
いる。
表1 満鉄付属地市街における日本人と他の民
族集団との非類似指数(I.D.)の平均点
Average value of the Indexes of Dissimilarity between
Japanese and other ethnic groups in the SMR
municipal areas in 1920, 1926, 1930 and 1936
付属地市街の多数民族である日本人と満州人
の間の居住分化の状況が、1930年から1936年
の間でほとんど変化をみせていない点は興味深
い。対象期間内のI.D.の変化をみると、居住空
間パターンは概ね安定的で あり、満州 事 変
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
4
(1931年)や満州国成立(1932年)は満鉄付属
地における各民族の人口分布パターンに影響を
与えなかったといえる。
前回の調査で民族間の居住分化の程度は都
市により大きな変動がみられたので(表2)、今回
は統計的手法により民族間の居住分化の都市
別変動及び時系列変化について分析を行いそ
の要因を検討する。
表2 1936年のI.D.日本人-満州人ごとに満鉄付
属地市街のグループ分け
SMR municipal areas grouped according to I.D.
[Japanese-Manchurian] in 1936
7.満鉄付属地都市における居住分化の状況
および要因
居住分化の都市間変動および時系列変化に
ついて、その要因を検討する。居住分化の程度
に関する研究の多くは米国都市を対象として行
われているが、その研究は居住分化の全体的な
パターンに関するものが多く3、個別都市間の居
住分化の性格あるいはその変化要因について
考察したものは少ない。上述したように鉄道付属
地の市街地では、都市別民族間居住分化は共
時的にも通時的にも変化を示すので、それを明
らかにするために統計的な分析を行った。その
分析方法と分析結果を示す。
7.1.満鉄付属地都市における居住分化の要
因
まず、満鉄が地方事務所を設けていた主要満
鉄沿線都市(満鉄付属地市街地)の14都市
(1930年)と17都市(1936年4)を対象とした。
分析の視点の一つは、一時点の被説明変数I.D.
に影響を及ぼす独立変数に関する情報を収集
す る た め に 共 時 的 な デ ー タ 解 析
(Cross-sectional data analysis)を行う。他の一つ
は、変数間の時間的な変化の情報を収集するた
めに 通 時 的 なデー タ 解 析 (Longitudinal data
analysis)を行う。共時的な多変量データ解析は
一時点の各満鉄沿線都市の居住分化を同時点
の他の特徴と関連させて分析する。ここでは、二
つの時点を選んで(1930、36年)各時点毎に分
析を行った。この分析結果に基づき都市間のI.D.
の変動について説明する。分析時点を満州国
成立の前後の二時点とするのは、利用資料の存
在に制約されたためであるが、同時に同国成立
が各独立変数の説明力にどのように影響するか
をみるためである。変化の要因分析の対象期間
は1930-36年である。この分析ではI.D.の増減と
対象都市の他の変数との関係を分析することに
なるので、この作業からは居住分化度の形成要
因を特定することは難しい。
利用可能なデータの制約から分析は満鉄沿
線都市に限定せざるを得なかったが、満鉄付属
地 に は 全 日 本 人 人 口 の 85.9 % ( 1930 年 ) と
51.6%(1936年)が集中5していたので、民族間
居住分化の研究にとってはとりあえず分析可能
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
5
なデータと 考える。K.E. TaeuberおよびA.F.
Taeuber6が指摘した共時的なデータ分析の困
難性7はここでも同様であるが、米国の都市と比
べ満鉄沿線都市の歴史は短くまた都市間の共
通点も多いので、共時的な分析がある程度有効
と考える。
分析手法としては、I.D.を従属変数とするステ
ップワイズ型重回帰分析 (Multiple Regression
using Stepwise Method) を用いた8。独立変数
にはI.D.に影響を及ぼすと考えられる人口関連
データを中心に諸変数を採用した。共時的分析
では民族別にみた人口比、性比、7つの産業大
分類別産業別人口比、満鉄社員地帯比の4変
数を用意した。
時間的変化の分析では、従属変数として対象
期間内のI.D.の変化(1936年と1930年のI.D.の
差)を用いる。この変化がマイナスの場合は居住
分化が低くなったことを意味し、プラスの場合は
その逆である。I.D.は諸民族集団に対する日本
人の空間分布を計る係数であるので、どのような
変化が民族集団間の人口分布に影響を及ぼす
かという観点から変数の選択を行ったが、結果と
して変数の数は共時的分析の場合より少なくな
った。具体的には、特定産業従事者人口の変動
(工業に従事する満州人比率の変化、交通業に
従事する日本人比率の変化など)、民族別人口
比の変化、満鉄社員比率の変化、である。さらに、
都市内人口分布に多くの影響を与える満鉄の
貸付宅地総面積の変化、同宅地の民族別構成
比の変化などをとりあげた。構成比の変化につ
いては、1930年から1936年にかけてポイントの増
減を独立変数とした。
7.2.居住分化の要因分析結果
1930年から1936年への鉄道付属地における
満州 人と 日 本 人の I.D.の 変 化は、50.82か ら
49.08と横ばいであった。また朝鮮人と日本人の
I.D.は56.53から57.52へと推移しており、これもほ
とんど変化をみせていない。つまり、対象期間内
のI.D.の変化をみると、民族集団間の居住空間
パターンは安定的であり、満州事変また満州国
の成立は満鉄付属地における各民族の人口分
布パターンに影響を与えなかったといえる。
共時的な分析では(表3)、1930年と1936年の
各時点で居住分化度に影響を与える重要変数
は「家事使用人domestic service」の比率である。
つまり居住分化と家事従事者との関係はマイナ
スを示し、家事従事者の比率が高い都市では居
住分化の程度が低くなっている。
1930年の分析対象としてとりあげた14都市に
ついてみると、日本人家事従事者の比率が高い
都市では満州人と日本人の居住分化の程度が
低いという関係があらわれる。変数間の相関係
数 を み る と 、 「 日 本 人 家 事 使 用 人 domestic
service-Jap.」と最も高い相関を示すのは「満州
人公務及び自由業public ad. & professional
serv.-Man.」である。つまり、満州事変前の1930
年には満州人居住地区さらに言えば彼らの住宅
に日本人家事従事者が居住していたことが、両
者の相関を高めている理由であろう。家事従事
者が主に女中として雇用主の家に住み込むの
は、当時の日本においては一般的であった。
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
6
表3 共時的な多変量データ解析の結果表(1930,36年)
a) Descriptive statistics for SMR municipal areas, for the years 1930 and 1936
b) Correlations between independent variables and I.D. [Japanese-Manchurian]
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
7
c) Results of the regression analysis
1936年の対象17都市における都市別の居住
分化の変化は、主に満州人の家事従事者の存
在が影響を及ぼしていると言える。つまり、満州
人の家事従事者の比率が高い都市では、居住
分化の程度が低くなっている。しかも満州国建
国以後、同変数の説明力は高くなっている。日
本人の家に居住する満州人家事従事者が増加
した結果であると思われ、支配民族としての富裕
日本人の増大と被支配民族としての満州人の関
係が顕著になりつつあることを示す。また日本人
と朝鮮人の間でも同様の傾向がみられ、日本人
と朝鮮人との間にも支配と被支配の関係が満州
においても構築されつつあることを示唆してい
る。
時間的変化の分析の結果によると(表4)、
1930年から1936年の間における満州人に対す
る 日 本 人 の 居 住 分 化 の 変 化 は 、 「 交 通 業
transport-Jap.」に従事する日本人の比率の変
化により説明ができる。交通業は日本人の産業
別人口の中の最大部門を形成しており、満鉄付
属地で働く日本人の約30%を占め、その大部分
は最も富裕な満鉄社員であった。交通業に従事
する日本人の比率が増加する都市では、居住
分化の程度も高くなるという関係が認められる。
これは、同時に富裕日本人との間の居住分化の
進展と対応するものである。日本人と朝鮮人との
間でも同様の傾向が見られる9。
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
8
表4 通時的な多変量データ解析の結果表 (1930、36年)
a) Correlations between independent variables and I.D. [Japanese-Manchurian] change between 1930 and 1936
b) Results of the regression analysis
8.満鉄時代における付属地の居住政策
以上から居住分化の変化において交通業す
なわち満鉄のもつ重要性が明らかとなった。満
鉄は企業として拡大するだけでなく、社員のみな
らず鉄道付属地に住む日本人の生活を支える
施設を建設し10、都市形成の面でも重要な役割
を果たした。このことが居住分化の変化にどのよ
う に 影 響 を 与 え た か 、 満 鉄 の 居 住 政 策
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
9
(residential policy)について検討する。1908年策
定の満鉄市街地計画に基づいて鉄道沿線に計
画的な街区形成が始まるが、都市計画で最も重
要な事項は土地利用の決定・規制 (land use
regulations)であり、満鉄は市街地形成にあたり、
次の4種類の用途地域に分ける地域制(zoning)
を採用した。住宅地区、商業地区、工業地区、
糧桟地区である。また状況によっては住宅、商
業の混合した混合地区が設定された11。
a) 住宅地区:「住民の保健に適することが最
大の要件たるを以て、なるべく工場の如き煤
煙悪臭などを感ずるの地を遠ざかり、比較的
高燥閑雅にして商業地域に近く日常生活に
便なる地を選んで」住宅地区を設定した。
b) 商業地区:「市街の中枢となるべきものであ
るから、停車場を中心として幹線道路に沿ひ
交通運輸の至便る地域」を選定した。
c) 工業地区:「給水ならびに動力の供給容易
にして、鉄道線路に近く、なるべく住宅地区が
遠ざかつた地区」を工業地区に選定した。
d) 混合地区:「市街計画上住宅、商業の両地
区が画然と決定されることは理想であるが、土
地の状況四囲の関係により独立の地域に設
定し得ざるものがある。此の場合は己むを得
ず混合地区とし、商業住宅に建設すべき種類
の建物を適宜建築し得る地区」とした。
e) 糧桟地区:「満州特産物たる大豆、豆油、
粟、高梁等の保管並取引の為、施設をなすべ
き地区とするものにして、その地区を有せしめ
たるは長春、公主嶺、開原、遼陽等であって、
何れも運輸の関係上貨物ヤード付近」に設定
したのである。
全体的な都市計画では民族別土地利用規制
は決められておらず、満鉄貸付土地面積の状況
を見ると、日本人以外の他民族も土地を借りるこ
とが可能であった。例えば、満州人が借りていた
宅地用地の件数は全体の27.7%を占めた12。し
かし、満鉄社員をはじめ日本人官僚、軍人、大
企業社員のための住宅地区計画があり、満鉄付
属地の一定の地域を占めて特殊な住宅地区を
形成していた例が多くあった。例えば、鞍山付属
地の都市計画で見られるように、「鉄道線路の東
部を日本人商業住宅地域、公共施設物用地及
び公園とし東北部の高地を理想的住宅地となし
社員の住宅に充て、西部は日支人雑居の商業
住宅地域とし其の北方は製鉄所用地とせり・・・」、
といったケースがあった13。奉天付属地市街地
でも、日本人用特殊住宅区及び一般住宅区が
あり、満鉄社宅(家族社宅・独身社宅)、郵便局
官舎、警察官舎、軍事官舎などの特殊住宅は
一定の地域を占めて特殊な住宅区を形成して
いた。その他に満鉄社宅を一カ所に集中してい
た例もある14。社宅の集中は中国人の国家主義
者の攻撃から満鉄社員を防衛するためと考えら
れる。日本人社員にとって言葉も通じぬ満州で
の生活はかなり困難が予想されるが、そのような
状況下で新たな住宅を社員自らが探すことは容
易ではなかった15。また、寒地向住宅の建設な
ど極寒地での居住になれていない日本人の不
安を防ぐ必要があった。住宅供給は社員確保の
ための優遇策であり、社員の生活基盤となる住
宅を給することは、社員の生活を安定させること
であり、それが会社の業績向上に結びつくものと
考えられたため、満鉄は設立時にすべての社
員・傭人に対して住宅(社宅)の確保を約してい
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
10
た16。
9.満鉄社宅街での生活
日本人満鉄社員の多くが満鉄社宅街に居住
し、満鉄社員消費組合、満鉄社員倶楽部などの
文化的・社会的な機関や、満鉄の直営の病院や
学校などの福利厚生施設を中心に生活してい
た。満鉄は満州生活への不安を抱えて入満する
社員家族のために、社宅また社会文化施設の
建設、消費組合の推進を行った。満鉄社員は
「護政策」17を受けていて、「付属地に住んでい
れば日本内地と同じように手厚い保護を受けら
れたので、苦労して中国語を勉強しなくても結構
商売ができ生活ができた。教育をはじめいろい
ろな面で内地と同じ保護助成策があり、これがか
えって日本人に満鉄や政府にたいする依頼心を
起こさせ、中国人社会に飛び込んで一緒にやろ
うという気風を弱くした」18。旧社員の回顧録をま
とめている「満鉄会報」からも同様のことが感じ取
れる。「私など奉天で生まれ、満鉄社宅で育ち満
鉄で働き、社員会館で結婚披露をし、子供を生
み何の不安もなく・・・」19と書いた女性もいた。
満鉄付属地に駐屯する関東軍の存在も安心感
を与えた。「市内(奉天付属地市街)を歩く軍人
の姿も内地にくらべて一段と立派に見えた」20。
日本人居住区を出入りした満州人の使用人や、
日本人女性が満州人の市場を往来するほかは、
あまり互いの居住区に足を踏み入れることはな
かったようである21。日常接触する満州人は使
用人や洗濯婦、車夫のような下級労働者であっ
た。日本人体験者の回想の中では、「家の中
は・・・ショウハイ(ボーイ)がいる」22。「学校で・・・
掃除は現地の少年(ボーイ)がしてくれる」23とい
う文書がよくみられる。映画監督である山田洋次
は、1931年大阪宝塚で生まれ、父が満鉄に勤め
ていたので満州へ移住し、そこで小学校に入学
し16歳の引き揚げまで過ごすことになった。父の
満鉄時代、瀟洒な西洋風の満鉄社宅に住み、
中国人のメイドにかしずかれて、何不自由なく暮
していた24という。
3人の満州移住体験者へのインタビューでも、
「満人に付き合ったのは会社の中だけで、しかも
満人はもっとも低い仕事やっており、言葉は通じ
ず」、「家の満人助手以外に他の満人と接触が
なかった」、「学校では日本人だけ」、「日本語だ
けで生活ができた」といった話が多い。その1人
は1940年に繊維企業の転勤で満州の都市へ移
住し、その後転職してからも他の満州都市で日
本の会社に入っている25。また他の2人は満鉄
技師の子として満州に生まれ、父親の転勤によ
りいくつかの都市に居住し、また都市内でも数度
か転宅があった26。このように彼らは幾度かの移
動をしているにもかかわらず、いつも現地の満州
人街からはなれた日本人の家や会社の独身社
宅、または家族社宅に居住していた。家族社宅
には上層、中層、下層の区別があり、日本人社
員の資格給額に応じて特甲・甲・乙・丙・丁・の
区別があり、階級的に組織されていた。
満鉄社員の多くが社宅区に居住することによ
り現地民との間に壁をつくった。このような隔離
的な居住分化によって日本人の民族内の一致
団結、及び民族的な結合性が煽られたのである。
三宅氏によると、日本人の優越感が煽られ植民
者と現地民の関係は、支配、被支配の枠組みに
規制されたものとなる27。この空間的な隔離は、
他の民族に対してステレオタイプを促進し、社会
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
11
階級の格差によりそれを維持し、人々の交流を
困難にした。
10.ゲートキーパーの満鉄
このように鉄道付属地では外部要因である満
鉄の住宅供給が日本人の集住の原因として説
明できる。日本人満鉄社員は社宅に住み、朝鮮
人や外国人、一般の日本人は満鉄の社宅街に
入り込むことができず、他民族は通常日本人に
とって条件の悪い他の地区に集住する傾向にな
りがちだった。満鉄は門番gatekeeperであり、皆
に土地を貸す権利をもち、民族間や社会階級間
の門番役gatekeeping role28としてある空間に
「だれを居住させるか」を決定することができ、付
属地の都市における居住分化の状況を永続化
できた。満鉄社員などが住むホワイト・カラー地
区は、都市の中心部や高燥地などの立地条件
のよいところにあった。他民族に対してだけでな
く(ethnic segregation)、他の一般の日本人に対
しても隔離して(social segregation)建設された満
鉄 社 宅 街 は 、 門 番 化 さ れ た 集 団 ( gated
community)や砦の自己完結的なエンクレーブ
であり、民族間居住分化の拡大に大きな影響を
与えた。
このように満鉄の植民地理念に基づく都市計
画により民族間居住分化の発生をある程度説明
出来る。社宅区は、計画的・秩序的に会社内の
社員の地位により住む場所あるいは住む家の大
きさなども決められ、満鉄社員は他の民族からだ
けではなく、他の産業に従事する日本人からも
隔離する。同時期の英国の植民地でも見られる
ように、諸民族間居住分化だけでなく諸経済階
級間居住分化、つまり、日本人の満鉄社員や公
務員の「ホワイト・カラー」人口と、日本から移住し
てきた中小商人や料理屋、芸者・娼婦などの職
業・階層にある多数の日本人29の間に社会的な
居住分化があった。英国の植民都市と同じく30、
所得及び経済階級による居住分化は日本の植
民地主義の資本主義的な性格の反映といえる。
11.おわりに
旧満州への日本人の人口移動は帝国主義下
で行われていたにもかかわらず、「日本が行
った侵略のうちで、満州国だけはロマンをも
っています」31と言われ、また、満州国の建
国はひとつの社会実験でもあった。「満州建
国ノ精神ハ之ヲ要約シテ 一、日満一徳一心、
二、民族協和、三、王道楽土ノ建設・・・」
32、とくに「五族協和」(日、満、支、鮮、蒙、)
による「王道楽土」(徳で国を治め楽園を実
現する)という満州建国のスローガンは、日
本内地でもまた満州国でも特に強く言われ
ていた33。王道楽土・五族協和の一員となる
ため多くの日本人が都市から満州国へ移住
し、農民も移民として大量に満州国へと渡っ
た。このスローガンの検証を目的の一つとし
て、日本人の人口移動における移住パターン
の分析34、その結果成立した満州日本人社会
の構成35、満鉄付属地市街における日本人と
満州人や朝鮮人、外国人との間の居住分化の
状況、という視点で日本人と他民族との関係
について研究を行った。
研究対象とした鉄道付属地における居住分
化の要因から考えると、満州国の建設理念であ
った五民族協和などの帝国主義的なユートピア
(imperialistic utopia36)と満鉄創業時の企業理
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
12
念・目標の間には論理的枠組みに違いがあり、
満鉄という企業経営の結果、満鉄付属地市街地
での国際交流は民族間の社会的な統合(social
integration)によるというよりも、むしろ職務上の統
合(functional integration)37によるものといえるで
あろう。今後の課題は、満州に成立した諸民族
混住社会の性格について研究を深めるとともに、
満州国時代の大都市(奉天市、新京市、ハルビ
ン市など)の民族間の居住分化の状況を検討す
る。
謝辞
応地利明先生(現滋賀県立大学)をはじめ、
京都大学大学院文学研究科の地理学専攻教
室の先生方には様々なご意見、ご助言をいただ
いた。記して感謝申し上げる。
© アビラ・タピエス、ロサリア 「旧満州におけ
る民族間の居住分化の状況(下)―南満州鉄道
付属地都市の事例―」甲南大学紀要文学編139
歴史文化特集、2004、193-208頁。
(Avila Tàpies, R. ‘The residential segregation
by ethnic groups in colonial Manchuria: the case
of the cities of the South Manchuria Railway
(second part)’. Bulletin of Konan
University-Letters 139, 2004, p. 193-208)
1 「満州人」という一つのカテゴリーの中には漢族や満族、モンゴル族、回族人及びその他の現地の人々を
含む。大勢は新来者の漢族である。
2 I.D.は居住地域の民族間における居住分化の程度あるいは混合度を示し、都市に在住する各々の社会集団
の各地区毎の比率を求め、各地区毎にその差を計算し、その合計に 0.5 を乗じた数値で示される。同指数 0
(分化が無い=社会集団は均一な地区間分布を示す)から 100(完全な分化がある=共住する地区がない)
までの係数値を示す。つまり、分化をなくすために社会集団が集住する地区から移動しなければならない人
口の割合を I.D.は示している。
n
IDxy=0.5Σ|Xi-Yi| Xi:i番目の地区内のX人口, 比率 i=1 Yi:i番目の地区内のY人口, 比率
3 アメリカの都市のためだけではなく、多様なコンテクストでは I.D. に基づく居住分化の研究がある。英
国の植民地における民族間居住分化の研究、Christopher, A.J., “Roots of urban segregation: South Africa
at Union, 1910”, Journal of Historical Geography 14-2, 1988, pp.151-169. ; 及び、“Apartheid and Urban
Segregation Levels in South Africa”, Urban Studies 27-3, 1990, pp.421-440.;及び、“Urban segregation
levels in the British overseas Empire and its successors, in the twentieth century”, Trans. Inst. Br. Geogr. 17, 1992, pp.95-107. 北アイランドのカトリック及びプロテスタント教徒間の居住分化の研究、
Poole、M.& Doherty, P., Ethnic Residential Segregation in Northern Ireland, Univ. of Ulster ed., 1996,
299p. イスラエルの個人居住分化の新しい研究、Benenson, I.; Omer, I., Multi-scale approach to measuring residential segregation and the case of Yaffo, Tel-Aviv: URL:http://www.geocomputation.org/2000/GC047/Gc047.htm 2004 年 10 月 30 日検索。
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
13
4 南満州鉄道付属地別のデータは 1936 年が最後の統計年度であり、1937 以降は満州国の資料に含まれ細か
い町丁別のデータが存在しない。
5 副島圓昭 「戦前期中国在留日本人人口統計」和歌山大学教育学部紀要人文科学第 33 集、1984、1-35 頁。
より計算。
6 Taeuber, K.E.; Taeuber, A.F., Negroes in Cities: Residential Segregation and Neighborhood Change,
Aldine Publishing Co., 1965, 284p. 「pp. 69-70」
7 このアプローチが現代アメリカの黒人と白人の居住分化の都市間の差異を説明するためにあまり使われ
てない理由は、ある一時点の各都市の居住分化に影響を及ぼす都市の特徴があまりに多いためである。
8 SPSS(Statistical Products and Service Solution) Base 7.5J for Windows を用いた。
9 本論では日本人と朝鮮人の間の居住分化の原因分析を行わない。
10 西沢泰彦『-図説-満鉄「満州」の巨人』河出書房新社、2000、「10 頁」。
11 満鉄総裁室地方部残務整理委員会『満鉄付属地経営沿革全史』上巻、龍渓書舎、1977、「195 頁。」(初版
1939)。及び、越沢明 『植民地満州の都市計画』アジア経済研究所、1978、192 頁。「21 頁。」
12 しかし一件当たりの面積は日本人より小さく、鉄道付属地の宅地用地の 13.77%であった。(南満州鉄道
株式会社地方部「昭和 11 年度地方経営統計年報」1936)
13 満鉄庶務部調査課『南満州鉄道株式会社第二次十年史』南満州鉄道株式会社編、1928、1352 頁。「1118
頁。」
14 越智喜市「奉天付属地都市の発展景域」満鉄教育研究所発行研究要報 10、1937、100 頁。
15 西沢泰彦 2000: 28 頁。
16 この満鉄創業時の理念は実現しなかった。住宅供給が社員の急激な増加に対応できなかったからである。
その時に他の施策が実行された。西沢泰彦 2000: 「28 頁」。
17 福田寛『満州奉天日本人史』謙光社、1976、376 頁。「291 頁。」
18 福田寛 1976: 291 頁。
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
14
19 満鉄会報」24 号、1961 年 5 月 15 日。
20 満鉄の建築と技術人編集委員会『満鉄の建築と技術人』満鉄建築会、1976、361 頁。「258 頁。」
21 三宅ちさと「民衆とアジア−植民者としての日本人と植民地−」日本学報 12、1993、47-68 頁。
22 朝日新聞社編『女たちの太平洋戦争-〈1〉被害者そして加害者-』朝日新聞社、1991、222 頁。「19 頁。」
23 朝日新聞社 1991: 12 頁。
24 榎 本 清 「 追 悼 ・ 渥 美 清 2 ( 男 は つ ら い よ ) の 世 界 、 映 画 監 督 山 田 洋 次 の 原 点 - 上 - 」
URL:http://www.asahi-net.or.jp/^hh2s-fjmt/jsm/96c/ratsumi.htm 2004 年 12 月 1 検索
25 繊維企業の元社員 A さん(1995 年 2 月インタビュー)
26 満鉄技師の大連市生まれ子弟 B さん(1996 年 4 月、1998 年 10 月インタビュー)および、満鉄技師の
新京市生まれ C さん(1998 年 12 月インタビュー)
27 三宅ちさと 1993: 55 頁。
28 Knox, P., Urban Social Geography: an Introduction, Longman, 1995, 186p.「pp.186」
29 橋谷弘『帝国日本と植民地都市』吉川弘文館、2004、196 頁。「49 頁。」、「66~69 頁。」
30 Home, R., Of Planting and Planning: The making of British colonial cities, E & Fn Spon eds., 1997, 249p.
31 武藤富男『私と満州国』(山室信一『キメラ−満州国の肖像』中央公論社、1993 から引用)
32 『民族協和の満州国』1939
33 日録 20 世紀・1932 昭和 7 年「関東軍、「満州国」建国!」講談社、1998 年 1 月 6・13 日、「4 頁。」
34 2002 年度の本紀要に掲載の著者の論文「近代における旧満州への日本人の移住およびその定着パターン
について」を参照。
35 著者の博士論文「近現代日本における人口移動研究―空間的社会的構造パターン―」2000 、1.3.1.日本
人社会の特性変化を参照。及び、塚瀬進『満州の日本人』2004、237 頁。「6-44 頁。」
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
15
36 Matsusaka, Y. T., The Making of Japanese Manchuria 1904-1932, Harvard Univ. Pr., 2001, 522p.
37 Christopher 1988
Resumen:
Avila Tàpies, Rosalia: ‘La segregación residencial por grupos étnicos en la Manchuria colonial: el caso de
las ciudades del Ferrocarril del Sur de Manchuria (segunda parte)’. Boletín de la Universidad de Konan
-Letras 139, 2004, p. 193-208.
Se analiza en este artículo las causas de la segregación residencial entre japoneses y chinos en las
ciudades de la “zona anexa” al ferrocarril surmanchuriano. Estas ciudades fueron construidas y
administradas por la Empresa del Ferrocarril del Sur de Manchuria(Mantetsu) entre los años 1907 y
1937.
Chinos y japoneses fueron los dos grandes grupos étnicos residentes en estas ciudades ferroviarias, y
existía por ello muchas posibilidades de contacto e intercambio. En este estudio se ha examinado el
carácter de ese contacto interétnico a partir del análisis de los patrones de distribución residencial de
cada grupo y de sus niveles de segregación o convivencia (primera parte de este artículo), y de la
averiguación y análisis de las causas de la segregación a través de técnicas cuantitativas y cualitativas
(segunda parte). Así pues, y con el cálculo del Indice de Disimilitud (I.D.) para distintos pares de grupos
étnicos entre los años 1920 y1936, se puso en evidencia la existencia de niveles medios y altos de
segregación en estas ciudades. Concretamente la segregación entre japoneses y chinos para los años 930
y 1936 obtenía un valor medio aprox. de 50 (interpretándose como que el 50% de los japoneses, o chinos,
debían cambiar de distrito de residencia para alcanzar la equidistribución). En el artículo que nos ocupa,
el examen de las causas de la segregación se ha centrado en este par, por ser el más significativo
cuantitativamente.
Para descubrir los predictores de la segregación se ha aplicado una regresión múltiple en dos estudios
diferenciados: ① un estudio transversal con análisis multivariante de las variaciones de niveles de
segregación entre ciudades para los años 1930 y 1936, tratados separadamente; y, ② un estudio
longitudinal con análisis multivariante de los cambios de niveles de segregación entre 1930 y 1936. Las
variables independientes consideradas fueron aquellas que pudieran afectar la redistribución de la
población en la ciudad (ver tablas 3.a y 4.a)
Los análisis de regresión revelaron que: ① hubo una relación negativa y estadísticamente significativa
甲南大学紀要文学編歴史文化特集 139 (2004)
16
entre niveles de segregación residencial y porcentaje de empleados en el servicio doméstico; es decir, a
mayor presencia de empleados en el servicio doméstico (japoneses o chinos) menor segregación, y que,
② existió una relación positiva y significativa entre los cambios en los niveles de segregación y los
cambios en el porcentaje de población japonesa ocupada en el sector transporte; es decir, a mayor
aumento de población japonesa en el sector transporte, mayor aumento de la segregación a través del
tiempo.
Es reveladora la asociación entre la presencia de japoneses en el sector transporte (empleados de
Mantetsu) y la segregación residencial entre japoneses y chinos, por ello hemos estudiado la política
residencial de Mantetsu, como máximo responsible urbanístico. A pesar de que en sus regulaciones sobre
el uso del suelo urbano no se especifica una zonificación residencial por razas, en la práctica la empresa
reservaba espacio urbano de calidad para la residencia de sus empleados japoneses, para los que
estableció instituciones e infraestructuras de uso reservado, obstaculizando así el contacto interétnico y
entre las distintas clases socio-económicas japonesas. La segregación espacial de los trabajadores de
Mantetsu fomentó la creación y el mantenimiento de estereotipos y la distancia social, manteniendo las
relaciones interétnicas a nivel laboral (integración funcional), pero raramente a nivel social.
El presente estudio deja entrever, pues, cómo la utopía imperialista de Manchukuo y el principio de
armonía entre las razas, no afectó a la política residencial segregacionista de Mantetsu.Vemos, entonces,
cómo la construcción del imperio y la estrategia empresarial de Mantetsu respondían a lógicas distintas.