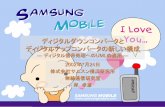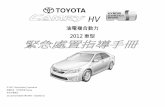コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The...
Transcript of コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The...
本発表の流れ
1
• コプト語の概要
• コプト語と言語類型論
• リサーチ・クエッション,目的,コプト語の動詞類体系
2
• 「トマスによる福音書」における調査
• 前名詞形動詞+目的語は「名詞抱合」か?
• 前名詞形動詞の軽動詞性
3
• 前名詞形動詞の諸用法の歴史ー r=を中心に ー
• 軽動詞r=の文法化
コプト語概要
アフロ・アジア語族のエジプト語派を単独で構成するエジプト語の歴史的最終段階. エジプトで話されていた.
エジプト語は,紀元前3,300年頃のナカダIIIA期の(原)ヒエログリフの資料から,現代のコプト・キリスト教会の典礼言語として用いられるコプト語まで約5,300年間の文献資料を持つ(おそらく1つの言語で文献が残された期間としては,世界最長).
コプト語は,紀元後3世紀前後からコプト文字で主な文献が書かれた.
9世紀以降,エジプトのアラビア語化が進んだ結果,母語話者が減っていき,遅くとも17世紀にはいなくなった.
クラウディオス・ラビーブらの20世紀コプト語復興運動の結果,少数ながらも「母語話者」が「復活」した.
地理
マックス・プランク進化人類学研究所(ライプツィヒ)によるglottolog 2.2のlanguoidsより(http://glottolog.org/resource/languoid/id/copt1239.bigmap.html#5/33.578/28.718, 最終確認日2014年6月4日)
コプト語と言語類型論
2008年にライプツィヒ大学およびマックス・プランク進化人類学研究所で開催された,Language Typology and Egyptian-Coptic Linguisticsという国際会議以降,コプト語を含むエジプト語を,それまでの独特な文法理論に基づいたものではなく,言語類型論的な基準に合わせて記述し,世界の言語の中でどのような位置にあるか,どの言語類型にあてはまるかを追求する動きが加
速している.
コプト語では,その筆頭にヘブライ大学のEitan Grossmanや,ウプサラ大学のÅke Engshedenがいる.また,類型論者のMartin Haspelmathもいくつかの議論を提起している.
これらの成果の一部は,今年の夏,Mouton de GruyterからEgyptian-Coptic Linguistics in Typological Perspectiveというタイトルで出版予定である(Martin Haspelmath私信)
本発表の目的
前述の流れに乗って,類型論的な基準からコプト語文法を考える.他動詞+目的語を表すのにコプト語は,次の2つの標示法がある.
1. 絶対形動詞+対格前置詞n-/mmo-+目的語2. 前名詞形動詞+名詞目的語 or
前人称形動詞+代名詞目的語
この現象は,統語類型論で論じられているDifferential Object Marking(DOM)だと捉えられる.
Engsheden (2003)は,このDOMについて研究をおこない,animacyがコプト語のDOMには関係がないことを述べている.
前人称動詞+代名詞目的語の場合は,Engsheden (2003)によって,ある程度詳しく論じられてきた.だが,前名詞形動詞+名詞目的語の機能は十分に論じられてこなかった.
そこで,本稿は,絶対形の構文との差異もふまえながら「前名詞形」の形態統語論的性格を明らかにすることを目的とする.
共時的な面はもちろん,通時的な面も考察する.
コプト語の動詞類の活用体系
動詞類
動詞 準動詞
語順:(TAM)SVO 語順:VSO
自動詞 他動詞
絶対形 状態形 命令形 前名詞形 前人称形
Layton (2011) をもとに,コプト語の動詞類 (verbals) の体系を樹形図であらわすと次のようになる.
補足 特殊な用語について
動詞 絶対形 a-f-čô 「彼は言った」
前名詞形 a-f-če-col 「彼は嘘を言った」
前人称形 a-f-čoo-s 「彼はそれを言った」
準動詞 前名詞形 peče-iêsous 「イエスは言った」
前人称形 peča-f 「彼は言った」
前名詞形 (prenominal form)は,その名のとおり,名詞の前にくる形式.
前人称形 (prepersonal form)は,人称代名詞の前にくる形.
状態形(stative form)は状態や状態受動を表す.
準動詞(verboid)は,動詞と比べ,TAM(テンス・アスペクト・ムード)標識がつかない.
動詞の活用
a. b. c. d. e. f.
絶対形 = free form
sôtm kôt tamo čise sôlsl eire
前名詞形 = bound bound before full
full NPsetm- ket- tame- čest- slsl- r-
前人称形 = bound bound before
suffixed pronounsótm- kót- tamo- čast- slsôl- aa-
意味 ‘hear’ ‘build’ ‘inform’ ‘raise’ ‘comfort’ ‘do’
表 1 Haspelmath (2014: 2, this article is a preprint edition of the one in the forthcoming book)
前名詞形の形態
• 絶対形を基本形,前名詞形を派生形と見た場合.• 形態音韻論に着目すれば,絶対形から前名詞形が派生される過程は,いくつかのパターンが存在する.
1.母音が弱化もしくは消失する
• 母音の弱化 sôtm > setm-• 母音の消失 sôlsl > slsl-
eire > r-
2.母音が弱化・消失し t が末尾に加えられるčise > čest-
3.形が変わらない
fi > fi-
調査
『ナグ・ハマディ写本第二巻』(N32-51, Layton 2004:189-205)の「トマスによる福音書」において前名詞形が用いられる文脈を見つけ出した.
成立時期は,紀元後3世紀前後,方言は,リュコポリス方言的要素が所々みられるサイード方言である.
動詞 準動詞
絶対形 前人称形 前名詞形 状態形 命令形 前名詞形 前人称形
421 129 104 91 7 128 68
動詞 準動詞
絶対形 前人称形 前名詞形 状態形 命令形 前名詞形 前人称形
421 129 104 91 7 128 68
総計(述べ語数)949
語彙頻度の視覚化 語形が複数ある場合,動詞は絶対形で,準動詞は,前名詞形で,そのレンマを代表させた.
語彙頻度が多かったレンマ1. peče- 準動詞「Sは言った」x1542. eire 動詞 「SはOをする」x853. čô 動詞「SはOを言う」x424. šôpe 動詞「SはOになる」x415. ei 動詞「Sは来る」x366. oun- 準動詞「Sはある」x367. he 動詞「Sは落ちる」x268. bôk動詞「Sは行く」x259. ti 動詞「Sは与える」x25
前名詞形と絶対形の例
(1a.) 前名詞形
ϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ […] (N38:6-10)
f-r-ouoeín e-p-kosmós […]
3MS-do-light DAT-DEF.MS-world
「[…]それは世界を照らしている」
(1b.) 絶対形
ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲛ̄ⲁ̄ (N35:18-19)
etetna-eíre n-ou-kakón n-n-etm-pn(éum)a
2PL:2FUT-do ACC-a-evil ACC-DEF.PL-2PL-spirit
「あなたがたは己の精神に悪をなすだろう」
前名詞形+名詞は名詞抱合か
コプト語を類型論から分析しているグロスマンとイェンモロは,「前名詞形+名詞」は「名詞抱合 (noun incorporation)」であるとみなしている.(Grossman & Iemmolo 2013)
類型論からコプト語を分析したハスペルマートは,コプト語の「前名詞形+名詞」の「名詞抱合」性を示唆している.(Haspelmath 2014)
抱合は,アメリカ両大陸(モホーク語,古典ナワトル語など)ニューギニア島(イマス語など),北東アジア(アイヌ語など),オーストラリアの言語に見られ,アフリカ大陸の言語にはあまりみられない.
(2) 典型的な名詞抱合の例:アイヌ語(佐藤 1992: 198)
ku-wákka-ku = wákka ku-kú1SG-water-drink water 1SG-drink「私は水を飲む」
コプト語のstress groupと前名詞形の主要部標示性コプト語学において,分綴は,伝統的なbound group (Layton 2011) またはstress group (Haspelmath 2014, to appear)に基づいてなされ,group中の要素は,ハイフンなどで書かれる.このbound groupにおいて前名詞形は強勢をもたないと考えられている.
絶対形を基本形と考えると,前名詞形の対格標示は,前名詞形自体でなされていると考えられる.このため,前名詞形は,主要部標示型 (head-marking)である.
名詞抱合を持つ言語は,主要部標示型の格標示の言語である傾向がある(Johanna Nichols私信).
強勢,主要部標示型の点から見て,コプト語の前名詞形が名詞抱合をもつということは十分ありえそうにみえる.
「名詞抱合」説への反例
(3)では,前名詞形動詞čne-「尋ねる」は名詞句ou-kouein-šêre sêm「小さな男の赤子」を「抱合」している.統語論的単位である「名詞句」を抱合するのだから,少なくともこの「抱合」は形態論的抱合ではない.Mithun(1984)は,抱合はあくまでも形態論的手段であるとしている.
(3) […] ⲉϫⲛⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ […] ⲉⲧⲃⲉⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲡⲱⲛϩ (N33:6)
e-čne-[ou-koueí n-šêre šêm] […] etbe-p-topos m-p-ônh
to-ask-[INDEF.SG-small LK-son small] […] about-DEF.MS-place GEN-DEF.MS-life
「[…]小さな男の赤子(šêre sêm)に生命の場所について尋ねること」
しかし,今回調べたデータのなかには, 次のように名詞句を「抱合」する例も数多く存在した.
「統語論的抱合」(擬似抱合)
このマオリ語の例では,通常は対格標識とともに表される目的語名詞句が動詞に抱合されている.
このタイプの「抱合」は,「統語論的抱合」または「擬似抱合」(pseudo-incorporation)と呼ばれ,オセアニア諸語などにみられる.
コプト語の「抱合」は,このタイプであろう.
以下では,「前名詞形」を1つの語とみなし,コプト語学のstress group (Haspelmath 2014)の記号ではなく,クリティック境界 (clitic boundary)を表す記号として=を用いて記していく.
(5) Maori (Collberg 1997: 39)
E [rukuruku koura nunui] ana ia
T/A [dive.RED crayfish big.RED] PROG 3SG
‘He is diving for big crayfish. (lit. big-crayfish-diving)’
前名詞形と共起する目的語
今回調査した「トマスによる福音書」では,前名詞形が軽動詞として使われやすいことがわかった.
まず,前名詞形として用いられた動詞で,使用頻度が2以上だったものの,前名詞形の頻度と,対応する絶対形の頻度を示す.
以下,これらの特徴を考察する.
前名詞形 r= (59) ti=(9) či=(6) če=(4) fi=(3) meste= (3) neč= (2)
絶対形 eire (7) ti (9) či (3) čô (11) fi (2) moste (3) nouče (7)
意味 する 与える 受ける 言う 取る 憎む 投げる
英語の軽動詞との類似性
英語の軽動詞
do
make
take
give
have
tell a lieなどのtell
前名詞形の頻度が1以上の動詞
r= 「する,作る,なす」
či=「受ける,取る」
fi=「取る,運ぶ」
ti=「与える」
če=「言う,告げる」
meste=「憎む」
neč=「投げる」
軽動詞性が強い例(予稿集(8)+α)
r=nêsteue する=断食 「断食する」
r=hôb する=仕事 「仕事する」
r=šeleet する=結婚 「結婚する」
r=rro する=支配者 「支配する」
r=špêre する=驚き 「驚く」
r=tima する=誉める 「誉める」
r=metanoei する=悔いる 「悔いる」
r=hote する=恐怖 「恐れる」
ti=tkas 与える=痛み 「痛める (cf. give a pain)」
či=tipe 受け取る=味 「味わう (cf. . take a taste)」
fi=roouš 取る=心配 「心配する (lit. 心配を取る) 」
če=col 言う=嘘 「嘘つくな(lit. 嘘を言うな)
ti=eleêmosunê 与える=お布施する 「お布施する」
軽動詞的な用法を見せた前名詞形動詞r= (絶対形;eire)「する,作る,なす」頻度 59
ti= (絶対形;ti)「与える」頻度9
či=(絶対形;či)「受け取る,取る」頻度6
fi=(絶対形;fi)「取る,取っていく,運ぶ」頻度4
če=(絶対形;čô)「言う,告げる」頻度3
前名詞形
89%
絶対形
11%
eire/r=「する」前名詞形
0%
絶対形
100%
tôhm/tehm=「招く」
ギリシア語動詞を目的語に取る場合
(7a.) ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ (N51:5)
mare=f=arna m=p=kosmos
OPT=3MS=refuse ACC=DEF.Ms=world
「彼は世を拒絶するべきである」
(6a.) ϥⲛⲁⲣⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩⲁ (N41:16)
f=na=r=tima m=p=oua
3MS=FUT=do=honour ACC=DEF.MS=one
「彼はその一人を誉めるであろう」
この場合,r=は明らかに軽動詞である.ギリシア語動詞は,不定法現在形がapocopeを経て借用されていると考えられており,実質的には,裸名詞として用いられている.
しかし,ギリシア語動詞がそのまま動詞として用いられている例もみられた.このような用法から,(6a.)のr=は語彙的な機能をなしていないと考えられる.
裸名詞を目的語にとる場合
(6b.) ϥⲣϭⲣⲱϩ ⲙⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ (N44:6)
f=r=crôh m=p=ma têr-f
3MS-do-need ACC-DEF.MS-place all-3MS
「彼には全てが必要だ.」
r=以外では,ti=tkas (与える=痛み)「痛める (cf. give a pain)」(N38:24),či=tipe(受け取る=味)「味わう (cf. . take a taste)」(N32:13),fi=roouš(取る=心配)「心配する (lit. 心配を取る) cf. take concern of…」(N39:24),mpr=če=col(否定命令=言う=嘘)「嘘つくな(lit. 嘘を言うな)cf. tell a lie」(N33:18)
コプト語は,名詞は,定冠詞,不定冠詞,ゼロ冠詞のどれかをとる. 今回,前名詞形は,絶対形よりも,裸名詞を目的語に取る傾向が確認された.
eire/r=の目的語
絶対形eire(x7)
• 代名詞x1
• 定冠詞+名詞(句)x4
• 不定冠詞+名詞(句)x2
• 裸名詞x0
前名詞形r=(x59)
• 定冠詞+名詞句x3
• 裸名詞x56
裸名詞
定冠詞+
名詞
(句)
不定冠詞+
名詞
(句)
代名詞
裸名詞
定冠詞+名
詞(句)
r=「する,作る,なす」
r=nêsteue する=断食 「断食する」
r=ouoein 作る=光 「照らす」
r=hôb する=仕事 「仕事する」
r=šeleet する=結婚 「結婚する」
r=crôh する=必要 「必要とする」
r=rro する=支配者 「支配する」
r=špre する=驚き 「驚く」
r=tima する=誉める 「誉める」
r=metanoei する=悔いる 「悔いる」
r=hote する=恐怖 「恐れる」
など
ti/ti=「与える」の目的語
絶対形(x9)
絶対形の目的語は,ギリシア語動詞,裸名詞ともに頻度は0であった.
前名詞形(x9)
裸名詞(x6)定冠詞句(x3)
ti=eleêmosunê 与える=お布施する「お布施する」
ti=tkas 与える=痛み 「痛める」
ti=erôte 与える=乳 「乳を与える」
ti=karpos 与える=実 「実る」など
či/či=「受け取る」の目的語
絶対形(x3)
裸名詞(x1)
裸名詞+修飾語句(x1)
定冠詞+名詞(x1)
前名詞形(x6)
以下の6つ.
či=tipe 受け取る=味 「味わう」(x4)
či=erôte 受け取る=乳「乳を飲む」(x2)
fi/fi= 「取る」の目的語
絶対形(x2)
定冠詞+名詞(句)(x2)
前名詞形(x3)
以下の3パターン.
fi=roouš 取る=心配「心配する」(x1)
fi=ône 取る=石 「石を取る」(x1) *軽動詞的でない?
fi=t=sôše 取る=定冠詞=畑 「その畑を取る」(x1)
čô/če=「言う」の目的語
絶対形(x10)
絶対形の目的語は,裸名詞,ギリシア語動詞ともに頻度は0であった.
前名詞形(x4)
全て裸名詞であった.
če=col 言う=嘘 「嘘を言う」 (x1)
če=oua 言う=1つ 「ひとこと言う」(x3)
軽動詞的でない前名詞形動詞
頻度1以上で,軽動詞的用法のなかった前名詞形動詞は,以下の2つであった.
1. meste= (絶対形;moste)「憎む」頻度3
2. neč=/nouč=(絶対形;nouje)「投げる」頻度2
mesto/meste=「憎む」
絶対形(x3)
全て定冠詞句.
前名詞形(x3)
全て定冠詞句
meste-p-ef-eiôt
hate-DEF.M-his-father「彼の父を憎む(こと)」
など
nouče/neč=「投げる」
絶対形(x7)
不定冠詞句(x1)
定冠詞句(x6)
前名詞形(x2)
neč=êlp 投げるぶどう酒「ぶどう酒を注ぐ」
nouč=êlp 投げる=ぶどう酒「ぶどう酒を注ぐ」
裸名詞と軽動詞性
名詞が裸 (bare) の場合,個別的なことではなく,一般的・抽象的なことをあらわす.
前名詞形+裸名詞のほうが前名詞形+定冠詞+名詞よりも,個別性が低く,語彙化しており,軽動詞構文的である.
ただし,コプト語の場合,目的語がギリシア語動詞の借用語の場合をのぞき,英語の軽動詞構文のように,目的語が動詞派生名詞である場合や,インド諸語のvector verbのように動詞が連続する場合は少ない.
しかしながら,Amakawa (2005) がdo the dishes, do economyも軽動詞構文の1種としているように軽動詞を広く捉えることもできる.この広義の軽動詞なら,今まで見てきた例の多くが当てはまる.
いずれにせよ,前名詞形の頻度が1以上の動詞は,neč=とmeste=以外の前名詞形動詞の意味は漂白化されており,かなり軽く,伴った名詞を動詞化するような文法的機能を帯びている.
まとめ
「前名詞形」という形式の統語論的機能
今回調べた範囲では,
1. 従来言われてきたような「名詞抱合」はなく,「統語論的抱合」または「擬似抱合」を構成する傾向がある.
2. 頻度では,裸名詞が目的語であることが圧倒的に多い.
3. それらに対応する絶対形は,前名詞形に比べ,裸名詞はすくない.
4. 頻度が大きい動詞は,意味の漂白化がおこり,名詞やギリシア語動詞借用語を動詞として機能させることが多い.
r=+目的語の歴史的発達
エジプト語史 年代
(先古期エジプト語) 紀元前3,300-3,000年頃
古期エジプト語 紀元前3,000-2,100年頃
中期エジプト語 紀元前2,100-1,300年頃
後期エジプト語 紀元前1,300-700年頃
民衆文字エジプト語 紀元前700-紀元後400年頃
コプト語 紀元後200年前後-(現在)
コプト語のeire/r=に対応する語はコプト語以前のエジプト語では,英国式綴りならir ,ヨーロッパ大陸式綴りなら,jr.
では,この用法の歴史はどうであったか.エジプト語は,5,000年の歴史をたどることができる.
自動詞用法
a. 古期エジプト語 (『ピラミッド・テクスト』412b)
mrr.f irr.f
like.3MS act.3MS
「彼は好きな時に行動する」
b. 中期エジプト語 (Englund 1995: 41)
irr Hm.k m mrr.f
act majesty.2MS as like.3MS
「陛下は,ご自分のお好きなように行動なさる.」
(9)
他動詞用法
(10) 中期エジプト語の他動詞的用法 (Englund 1995: 47)
Dd mAat ir mAat
speak justice do justice
「正義を言え,正義をなせ」
(補) 古期エジプト語 (Allen 2013: 107; 『ピラミッド・テクスト』 625a )
jr.k jrrt jsjrtdo.2MS do.NOM.F Osiris
「あなたはオシリス神がよくなしたことをなせ」(j = i)
民衆文字エジプト語における軽動詞的用法の発達
(10a.) 民衆文字エジプト語 (Johnson 2000: 64-65)
pA iir mwt
DEF.MS do.PST.PTCP die.INF
「死んだ(lit. 死をなした)者」
(10b.) pA nt ir ḥry
DEF.MS REL do ruler
「支配する(lit. 支配者をなす)者」
(11)
a.
b.
他動詞-n-目的語の用法の発達
• Engsheden (2003: 338)によると,この構文は,古くは紀元前6世紀ころのRylands IXパピルスで観察されるが,民衆文字エジプト語の対格標識n-の表記は省略されることが多く,あいまいである.
• コプト語の対格標識n-は,さかのぼると,古期エジプト語では,基本的にinやfromの意味の前置詞mであった.
eire/r= の歴史的発達
自動詞用法 他動詞-目的語 他動詞-n-目的語
非軽動詞 軽動詞
• 古期
• 中期
• 後期
• 民衆文字
• コプト
紀元前3,000年
紀元前2,000年
紀元前1,000年
紀元後0年
補足:Grammaticalization Cline
• Hopper & Traugott (1993):
• content item > grammatical word > clitic > inflectional affix (p. 7)
• full verb > (vector verb) > auxiliary > clitic > affix (p. 108)
• vector verb; aka. light verb.
通時的考察のまとめ
調べたかぎりでは,r= の軽動詞用法は,民衆文字エジプト語の前後で他動詞用法から意味の漂白化・文法化を経て生じた.
エジプト語は,中期エジプト語までは統合的であったが,後期エジプト語から迂言法の発達とともに,分析的言語に変化していったと言われる .Haspelmath はさらに,コプト語に至るにつれて逆に統合的になっている(synthesis-analysis-synthesis cycle; anasynthesis)と言っている(Haspelmath 2014: 16).
この変化のなかで,ir を用いた迂言法の一部は,コプト語の過去時制標識(もしくは助動詞)のa-に文法化したといわれている (Haspelmath 2014: 16, Allen 2013: 155).
今回みた, ir (>eire/r=)の軽動詞的用法は,後期エジプト語以降の迂言法の発達に伴った,文法化の一角を担っているといえよう.
参考文献1. Allen, James P. (2013) The Ancient Egyptian language: A historical study. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Amakawa, Toyoko(2005)A Constuction Grammar Approach to Light Verbs in English. Ph. D. thesis. Tsukuba University.
3. Collberg, Sheila Dooley. (1997) Determiners and incorporation in Maori. Lund University, Dept. of Linguistics Working Papers 46, 25–44
4. Englund, Gertie. (1995) Middle Egyptian: An introduction. 2nd ed. Uppsala: Uppsala University Department of Egyptology.
5. Grossman, Eitan and Iemmolo, Giorgio. (2013) A rare case of Differential Marking on A/S: the case of
6. Coptic. Handout at the 10th conference of Association for Linguistic Typology.
7. Haspelmath, Martin. (2014) A grammatical overview of Egyptian and Coptic. MS. Available on https://www.academia.edu/4774575/A_grammatical_overview_of_Egyptian_and_Coptic (accessed on 2014-5-6) (also in Martin Haspelmath, Eitan Grossman and Tonio Sebastian Richter (eds.) (forthcoming) Egyptian-Coptic Linguistics in Typological Perspective. Mouton de Gruyter.)
8. Hopper, Paul J. and Elizabeth Traugott. (1993) Grammaticalization. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Hopper, Paul J. and Elizabeth Traugott. (2003) Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Johnson, Janet H. (2000) Thus wrote ‘Onchsheshonqy: An introductory grammar of Demotic. 3rd ed. Studies in Ancient Oriental Civilization, No. 45. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago.
11. Kammerzell, Frank. (2000) Egyptian possessive constructions: a diachronic typological perspective. Sprachtypol. Univ. Forsch. (STUF)53, 97-108.
12. Layton, Bentley. (2011) A Coptic grammar: With chrestomathy and glossary. Sahidic dialect. 3rd ed. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
13. Layton (2004) Coptic Gnostic chrestomathy. Leuven: Peeters.
14. Mithun, Marianne. (1984) The Evolution of Noun Incorporation. Language. Vol. 60, No. 4, 847-894.15. 佐藤知己(1992)「「抱合」からみた北方の諸言語」宮岡伯人(編)『北の言語:類型と歴史』東京:三省堂.191-201.
![Page 1: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: コプト・エジプト語の他動詞の「前名詞形」の軽動詞性と文法化[The "Prenominal" Form of Verbs in Coptic Egyptian -Frequency, Light-Verbalness and Grammaticalization-]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012515/631a725620bd5bb1740c49fd/html5/thumbnails/45.jpg)


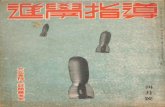

![コプト語の複数定冠詞(ハンドアウト)[Coptic Plural Definite Article (handout)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321a6dc64690856e108cc3b/coptic-plural-definite-article.jpg)