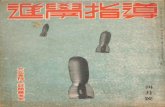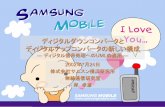「OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた 事業環境の調査」
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of 「OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた 事業環境の調査」
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
1
概 要
現状、日本のソフトウェア産業は、首都圏に売上高の 73%が集中しており、地方の IT 産
業は、受託ソフトウェア開発のピラミッド構造の下層に位置している。沖縄の IT 産業は、
その地方のひとつとして、大都市を中心としたソフトウェア開発の二次、三次請けとして、
最下層に位置付けられている。その結果、沖縄県内 IT企業は、低単価による低収益、不安
定な受注、技術開発・技術者育成の投資余裕の欠如に悩み、発展が阻害されている状況に
ある。この状況に鑑み、沖縄の IT産業は従来の下請け体質から脱却した自立的な体質へと
変革する取り組みが求められている。そのためには、自社のオリジナリティーの高い製品、
特徴ある製品(得意分野)や商材などを持つことで競争力・技術力を増し、上位へのアプロ
ーチを行えるような事業環境の構築が必要である。これらの課題を解決するために着目し
たのが無償かつ技術情報(ソースコード)が公開されているオープンソースソフトウェア
(以降、OSS)である。膨大な数の OSS を選別し、日本語への改訂・修正などをすることで商
材の材料として利用する。これにより、ゼロからの開発と比べ、低コストで製品を創出す
ることが可能となる。この OSS を活用した商材開発は、沖縄の IT 企業が下請け構造から脱
却する効果を高めるものと期待され、事業化を推進すべきとの認識が強まっている。しか
しながら、OSS を商材化する上で、膨大なソフト数から有望商材として掘り起こすことは容
易ではない。また、これを事業として展開するためには、独自のノウハウも必要であり、
中小企業が多い沖縄の IT企業が単独で実施するのは困難な状況である。このことから、本
調査では、沖縄における OSS を活用した事業環境の創出を図るため、諸リソースの確保、
沖縄の関係 IT企業が連携した推進体制構築、およびその体制を有効に機能させるための条
件などについて、分析・検討を行った。
その結果、国内市場における OSS 活用商材の市場規模は、2010 年までに最大で 10 兆円を
超える市場に拡大する可能性を秘める高い市場性があること、また併せて国内のみならず
近隣市場であるアジア地域においても、OSS をベースとした独自商材によって他国企業との
連携などを通じ市場進出可能性を有していることが認識できた。さらに、現実的に商材と
なる可能性を有する OSS の存在が予備調査で確認できたことにより、市場性と材料の両面
で環境条件が整っていることを裏付ける結果が得られた。
一方、県内 IT企業においては、IT業界における一次、二次の業務レベルへの向上を果た
したいという願望を抱いているものの、“製品ではなく、企業そのものを売り込む営業アプ
ローチ”で、受託開発(SI)、技術者派遣を強みとしている企業が多く、下請け企業の典型
ともいえる事業活動状況にある。事業での OSS に対する取り組みについては、県内 IT 企業
には、既に事業で OSS を活用している企業が全体の半数強存在しているが、このうち 9 割
の企業が OSS を活用して事業を遂行していく上で、人材育成面、技術面での支援構造の必
要性を訴えている。OSS を活用していない企業でも、8割弱が OSS の活用に前向きな姿勢を
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
2
とっており、このうち既に具体的な検討を始めている企業が 5 割存在するが、同じく支援
構造の必要性を訴えている。なお、OSS を活用する上では、ライセンス、著作権違反に関す
る考慮が必要不可欠であるが、県内 IT企業においては、これらに対する考慮が著しく欠け
ている状況にある。ライセンス、著作権違反に関する考慮については、一企業で必要十分
なだけの考慮を行うことは、県内 IT 企業の企業体力では難しいのが実情である。このこと
から、県内 IT産業全体として企業各々の事業における OSS の活用を果たし、これを基にし
た事業成果を導くためは、人材育成、技術面での支援構造の構築が必要不可欠であるとい
える。県内 IT企業における社員教育については、座学偏重で習得した知識を実践する場が
少ないことが明らかとなった。OSS が扱える技術者の増加を目指す上で、コミュニティ参加
などの実践を取り入れた人材育成の方法に見直す必要がある。また、企業の新たな人材と
なる学生の有効な獲得手段としてインターンシップがある。しかしながら、教育機関側、
企業側双方で実施の有用性は認識しているものの、制度運用における多くの課題が存在し
ており、双方での改善策の施行や企業の技術者と新規の共同作業(例えば、開発)に携わる
機会を創設するなどの運用内容の見直しによる活性化策が必要な状況にある。
OSS ベース商材構築に向けての事業連携を目指す上での、県内 IT 企業を中心とした推進
体制の構築については、“「独自製品」を持ち、企業特性(得意分野)を明確化するとともに
優れたパートナーの獲得/協同の画策、高度人材醸成機会獲得に直結する受託案件数の拡大、
および営業力の強化を目指す”ことを改善目標とした上で、OSS をベースとした製品開発を
軸に県内 IT 企業の共通課題を解決する機能を「共用センター」として整備し、低投資・短
期間(高効率)の開発で市場にマッチした製品を有することが、県内 IT産業の構造変革に向
けた目標達成に際して、最も有効な方策であると断定した。
県内 IT 企業が OSS をベースとした製品を有することにより、近隣の巨大市場である中
国にも開拓の可能性が広がる。中国では、ヒアリングしたすべての企業が沖縄を文化的に
も類似項が多いことなども含め多角的な観点で認知しており、沖縄の IT 企業との提携に関
し、情報・リソースの共有や製品をベースとした共同開発を含む協業などで可能性がある
と考えている。投資ベースで沖縄での OSS ベースの製品共同開発にも前向きな姿勢を示し
ている。県内 IT 企業が独自のソフトウェア製品を保有し、これを軸とすれば、製品品質や
市場適合性などにも左右されるのは前提条件として存在するが、日本・中国市場における
市場開拓において、中国 IT 企業との相互補完関係を築くことができる可能性がある。併せ
て、沖縄 IT津梁パークと山東斉魯ソフトウェアパークなどに代表される国営のソフトウェ
アパークとの連携などが、これをさらに強固な流れとしていくものと推察される。
共用センターで実現すべき事項としては、OSS をベースとして独自の商材を創出するため
に必要となる取り組みの作業標準の整備とこれを支える環境の整備が中心となる。商材の
基となる OSS を継続して探索するためのスクリーニング、マーケットニーズを探索するた
めの市場調査の実施、探索した OSS の動作検証・品質評価・機能網羅性検証・ライセンス
検証などを経て、日本語へのローカライズや国際化の作業が必要であり、これら一連の作
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
3
業が共用センターで具備すべき作業標準の要素となる。この共用センターの取り組みは、
OSS を活用した地方における IT 産業振興の有効モデルのひとつとして位置付けることがで
きる。また、県内 IT 業界全体の浮揚に直結することから、この作業標準の整備とこれを支
える環境の整備は、国・県などによる公的な整備を行うことが肝要である。また、同時に、
県内 IT 企業が同センターを活用して高い効果を生み出すために、県内 IT 業界が必要とし
ている人材育成面、技術サポート面での不安要素解消に向けた支援、企業の生産物のプロ
モーション支援を実施することが望ましい。これらの要素については、各企業の事業活動
の一環としての要素が強く、同センターと併せて民間が独自に整備することが肝要である。
この共用センターの運営については、県内 IT業界が主体的に自立化を目指すことが目的と
なることから、その主体者は中立性に鑑み、県内 IT 企業が共同で設立した NPO や LLP など
が担い、県外 IT企業はこの目的を達成するための支援の役割を果たすことが望ましいとい
える。
図 OSS 活用推進センターを基盤としたビジネス環境
以上のことから、この「共用センター」は、「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調査報
告書」にあるとおり、県内の IT 産業を内製・自主自立体質へと変革する機会を継続的に創
出するため、変革の源泉となる、商材創出/獲得、技術スキル定着化、市場開拓力獲得とこ
れらの支援を行うためのセンター機構として「OSS 活用推進センター」を整備し、県内の
IT 産業に属する IT 企業の OSS 関連ビジネスを推進する上での支援の役割を担うことを基
本コンセプトとするのが、本調査の県内 IT 企業の調査結果を鑑みて、妥当であるといえる。
LLP(有限責任事業組合) or NPO(非営利活動法人)
インフラ(システム環境など)
OSS商材生成手法
企業連携・営業支援
商材生成プロジェクト
人材育成(実践教育)県内IT企業
教育機関
OSS活用推進センター
県内IT企業
県外支援企業
県内IT企業
・・・・・・
公的支援による整備が望まれる領域
・実践教育手法の検討・確立・商材生成手法の検討・確立・活動の前提となるシステム等設備
民間で整備すべき領域
ベンダ ユーザ企業 SI企業 海外IT企業
インターンシップ
商材生成
連携・提携
関連団体
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
4
各企業が各々独自にビジネスを推進している中には、各企業が競争する領域と協調可能な
領域が存在する。
県内の情報産業を成長させるためには、産業を構成する各 IT企業の協調領域を中心とし、県内 IT産業の共用センターとして事業活動の下支えを行う「OSS活用推進センター」設置が必要不可欠な要素のひとつといえる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
5
目 次
第 1 章 はじめに.................................................................................................................... 10 1.1 本調査の背景と目的................................................................................................... 10
1.1.1 調査の背景および趣旨 ........................................................................................ 10 1.1.2 調査の目的............................................................................................................ 11
1.2 調査の概要 .................................................................................................................. 11 1.2.1 調査項目 ............................................................................................................... 11 1.2.2 調査方法 .............................................................................................................. 12 1.2.3 調査方法に関する補足 ........................................................................................ 15
1.3 調査実施条件.............................................................................................................. 15 1.3.1 体制および役割 ................................................................................................... 15 1.3.2 作業スケジュール................................................................................................ 15
1.4 本報告書の構成 .......................................................................................................... 16 第 2 章 OSS を材料としたビジネスの国内市場調査 ................................................................ 18
2.1 OSSを活用したビジネスモデル ................................................................................ 18 2.2 国内 OSSベース商材の販売状況 .............................................................................. 19
2.2.1 OSSベース商材販売事例収集の対象 .................................................................. 19 2.2.2 収集の手順........................................................................................................... 19 2.2.3 OSSベース商材の販売事例................................................................................. 20
2.3 OSSを利用した ITサービス提供状況....................................................................... 26 2.3.1 ITサービス提供事例収集の対象 ......................................................................... 26 2.3.2 収集の手順........................................................................................................... 26 2.3.3 OSSを利用した ITサービス提供事例 ................................................................ 27
2.4 OSS活用商材の潜在的市場規模推定......................................................................... 41 2.4.1 調査指針 .............................................................................................................. 41 2.4.2 比較対象とする IT市場の概要 ........................................................................... 44 2.4.3 IT市場規模および OSS市場規模の比較 ............................................................ 45 2.4.4 OSS普及に向けての課題 .................................................................................... 45 2.4.5 市場規模の推定 ................................................................................................... 48
第 3 章 商材化の可能性を有する OSS の予備調査 ................................................................ 57 3.1 調査指針..................................................................................................................... 57 3.2 商材化の可能性を持つカテゴリ ................................................................................ 58
3.2.1 ソフトウェア分類の考察..................................................................................... 59 3.2.2 適用するソフトウェア分類 ................................................................................. 59 3.2.3 探索対象分類の抽出 ............................................................................................ 61
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
6
3.3 商材化の可能性を持つ有望 OSS ............................................................................... 68 3.3.1 探索・抽出手順 ................................................................................................... 68 3.3.2 探索・抽出結果 ................................................................................................... 71 3.3.3 今後の課題......................................................................................................... 131
第 4 章 県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件の調査 .......................... 132 4.1 県内 IT企業の OSS活用ビジネスを展開するための条件・整備内容.................... 132
4.1.1 アンケート調査の手順 ...................................................................................... 132 4.1.2 アンケート調査の実施 ...................................................................................... 133 4.1.3 まとめと考察 ..................................................................................................... 158
4.2 OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容........................................................................................................................................ 160
4.2.1 アンケート調査結果と分析 ............................................................................... 160 4.2.2 まとめと考察 ..................................................................................................... 161
第 5 章 OSS を活用したインターンシップの可能性調査......................................................... 163 5.1 県内大学の IT分野におけるインターンシップ制度の整備状況............................. 163
5.1.1 インターンシップ制度調査の対象校 ................................................................ 163 5.1.2 ヒアリング調査の実施 ...................................................................................... 163 5.1.3 インターンシップ制度の整備状況に関する分析と考察 ................................... 170
5.2 県内企業におけるインターンシップ経験者の採用意向 .......................................... 171 5.2.1 アンケート結果の分析と考察 ........................................................................... 171 5.2.2 ヒアリング結果の分析と考察 ........................................................................... 173 5.2.3 まとめ................................................................................................................ 173
第 6 章 海外の IT 企業における OSS ベース商材創出の調査................................................ 176 6.1 アジア地域における IT企業動向 ............................................................................ 176
6.1.1 アジア地域の OSS関連 IT企業現況 ................................................................ 176 6.1.2 アジア地域の IT企業における OSSベース商材創出に関する可能性の検討 .. 177
6.2 欧米地域における IT企業動向 ................................................................................ 186 6.2.1 欧米地域の OSS関連 IT企業現況.................................................................... 186
第 7 章 事業連携に向けた体制構築 .................................................................................... 190 7.1 県内 IT企業による OSS関連事業に向けた体制構築 ............................................. 190
7.1.1 県内 IT企業の課題 ........................................................................................... 190 7.1.2 課題解消に向けた方策立案と実施内容の検討.................................................. 193 7.1.3 県内 IT企業による OSS関連事業に向けて設定すべき具体的目標................. 196 7.1.4 共用センターで実現すべき事項........................................................................ 196 7.1.5 事業実現へのアプローチ................................................................................... 197 7.1.6 県内 IT企業の共用センター活用の可能性 ....................................................... 197
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
7
第 8 章 調査結果総括......................................................................................................... 199 8.1 総括 .......................................................................................................................... 199 8.2 提言 .......................................................................................................................... 210
付 録 .................................................................................................................................. 224
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
8
登録商標などについて
本文書中に記載されている会社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標で
ある。
なお、本書では、™、Ⓒ、Ⓡなどを記載しない。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
9
用語定義
用語 意味
クローズド・イノベーション 自社内で研究開発からマーケティングまでを行う事業創
造スタイル
オープン・イノベーション 他社や大学などの研究成果を取り入れ、イノベーションを
起こしていく事業創造スタイル
パラダイムシフト その時代や分野において当然のことと考えられていた認
識(パラダイム)が革命的かつ非連続的に変化(シフト)する
こと
デュアルライセンス 一つのソフトウェアを GPL とその他の私有ライセンスの
両方でリリースするライセンス形態のこと
LAMP ソリューション Linux,Apache,MySQL,PHP の4つの OSS により構成され
るWebサーバ向けの代表的なOSSのソリューション構成の
こと
国際化(I18N) ソフトウェアの多言語対応の段階の一つであり、ソフトウ
ェアに様々な言語で利用するための設計や仕様などを組
み込むこと。文字列処理を多バイト文字に対応できるよう
にしたり、メニュー項目などの表示内容をプログラムの外
部に設定ファイルなどで分離したりといった改造のこと
を指す。これに対し、特定の言語に対応させることをロー
カライゼーション(Localization)という。なお、I18N は
internationalization を省略した記述法で国際的に活用
されている
リポジトリ 何らかのデータや情報、プログラムなどが体系立てて保管
されている場所のこと。アプリケーションやシステムの設
定情報が記録されているファイルやフォルダ、複数の開発
者が参加するプログラミング環境においてソースコード
や仕様に関する情報をまとめて保管してくれるシステム
などを指すことが多い
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
10
第1章 はじめに
1.1 本調査の背景と目的
本調査の背景と目的を以下に示す。
1.1.1 調査の背景および趣旨
現状、日本のソフトウェア産業(10 兆円市場)は、首都圏に売上高の 73%が集中しており、地方の IT産業は、図 1.1-1に示すとおり、受託ソフトウェア開発のピラミッド構造の下層に位置している。沖縄県の IT 産業は、その地方のひとつとして、大都市を中心としたソフトウェア開発の二次請け、三次請けとして、最下層に位置付けられている。その結果、県内 IT 企業は、低単価による低収益、不安定な受注、技術開発・技術者育成の投資余裕の欠如に悩み、発展が阻害されている状況に
ある。
図 1.1-1 日本のソフトウェア産業における沖縄 IT 企業の位置付け
この産業構造の位置付けから図 1.1-2 に示すように脱却した自立的な体質への変革が望
まれており、これを実現するためにオリジナリティーの高い製品、特徴ある製品や商材な
ど、いわゆるソフトウェア商材が必要である。これを持つことにより競争力(技術力)を増
強するとともに、企業個々のオリジナリティーを保持しうる環境を創造し、下請け体質か
ら脱却した、自立的な体質への変革を達成することが望まれる。
受託ソフトウェア開発の構造
大手メーカ・SI企業
大手関連企業(首都圏)
大手関連企業(地方)
地方SI企業
地方ソフトハウス
企画・提案
全体設計・PM
機能設計
詳細設計・プログラミング
プログラミング
沖縄IT企業の位置付け
仕事の流れ 発注主導権 人月単価高
低無
有
■低い人月単価■不安定な受注■技術開発の投資余裕なし■高度技術者の育成余裕なし
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
11
図 1.1-2 沖縄 IT 企業の自立的な体質への変革
1.1.2 調査の目的
1.1.1 で説明した課題を解決する上で、比較的容易に実現し得る商材開発の材料として、
表 1.1.2-1 に示す理由から OSS が有効であるといえる。
本調査では、この OSS を活用してソフトウェア商材を創出することに関する実現可能性
を資金、ノウハウ、人材などリソース確保、ビジネス構築体制、ビジネス環境などの面か
ら検討する。
表 1.1.2-1OSS が独自ソフトウェアの商材として有望な理由
理由 詳細
1 少ない投資 原則無償で入手可能
2 技術情報公開 ソースコードが公開されており、技術ノウハウを習得できる
3 高付加価値化 商用ソフトウェアに比べ、独自に改良して高付加価値化しやすい
4 有望ソフト多数 世界中に数万種類あり、日本で知られていないものも多数存在
5 タイムリー ユーザ企業の IT 化に直接役立つ業務応用ソフトウェアへの適用
が始まったところ
1.2 調査の概要
前述の背景および目的のため、本調査の調査項目およびその方法を以下に示す。
1.2.1 調査項目
本調査の調査項目を以下に示す。
大手メーカ・SI企業
大手関連企業(首都圏)
大手関連企業(地方)
地方SI企業
地方ソフトハウス
受託開発中小規模システム開発案件の直接受注
大手メーカ・SI企業
大手関連企業(首都圏)
地方SI企業・ソフトハウス
ユーザ企業 ユーザ企業
人材派遣
独自の競争力を有する商材が
あれば
現在の構造 変革後の構造
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
12
(1)OSS を材料としたビジネスの国内市場調査
A.OSS を活用したビジネスモデル
B.国内 OSS ベース商材の販売状況
C.OSS を利用した ITサービス提供状況
D.OSS 活用商材の潜在的市場規模推定
(2)商材化の可能性を有する OSS の予備調査
A.商材化の可能性を持つカテゴリ
B.商材化の可能性を持つ有望 OSS
(3)県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件調査
A.県内 IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容
B.OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内
容
(4)OSS を活用したインターンシップの可能性調査
A.県内大学の IT分野におけるインターンシップ制度の整備状況
B.県内企業におけるインターンシップ経験者の採用意向
(5)海外の IT企業における OSS ベース商材創出の調査
A.アジア地域における IT 企業現況
B.アジア地域の IT 企業における OSS ベース商材創出に関する可能性の検討
C.欧米地域における IT企業現況
(6)事業推進に向けた体制構築
A.県内 IT 企業による OSS ベースの事業に向けた体制構築
B.体制を有効に機能させるための条件およびビジネス環境の分析と検討
1.2.2 調査方法
1.2.1 で挙げた各調査項目の調査方法を以下に示す。
(1) OSS ベース商材国内市場調査
A.OSS を活用したビジネスモデル
OSS を活用したビジネスモデルについて、市場の状況を踏まえ取りまとめる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
13
B.国内 OSS ベース商材の販売状況
国内 OSS ベース商材の販売事例を 5~10例程度選定する。
選定は、インターネット上の IT 系ニュース、検索サイトなどを利用し、主として
インターネットを介して宣伝されている情報に基づき抽出する。
C.OSS を利用した ITサービス提供状況
同様に OSS を利用した ITサービス事例を 5~10 例程度選定する。
それらに関して、サービスの提供状況と、関連調査結果から各ニーズを抽出する。
D.OSS 活用商材の潜在的市場規模推定
各分野における IT市場規模および OSS 市場規模を比較するとともに、潜在的な市場
規模も併せて推定する。
(2)商材化の可能性を有する OSS の予備調査
A.商材化の可能性を持つカテゴリ
商材化の可能性を持つ OSS のカテゴリ案の選定は、グローバル調査企業がまとめ
た IT 産業に関するレポートやインターネット上で公開されている各種報告書などの
ソフトウェア分類を基に検討する。
B.商材化の可能性を持つ有望 OSS
ソフトウェア分類毎に有望な OSS をピックアップする。探索は、sourceforge.net,
freshmeat.net など、OSS リポジトリに登録されているものを対象とする。
(3)県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件の調査
A.県内 IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容
県内 IT 企業を対象として、OSS 活用ビジネスに関する意識や課題の認識など、OSS
活用ビジネスを展開するための条件および整備内容に関して、アンケート調査など
を通じ、情報収集と分析・検討を行う。
B.OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容
上記の県内 IT企業の OSS 活用ビジネスを展開するために整備すべき条件および整
備内容に関しても、アンケート調査などを通じ、情報収集と分析・検討を行う。
(4)OSS を活用したインターンシップの可能性調査
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
14
A.県内大学の IT分野におけるインターンシップ制度の整備状況
沖縄県内の大学のうち情報系学科・専攻を有する大学を中心として、IT 分野に
関連したインターンシップ制度の整備状況を担当教官もしくは担当係にヒアリン
グ調査で収集し、分析する。
B.県内企業におけるインターンシップ経験者の採用意向
県内 IT 企業を対象として、OSS を活用したインターンシップ経験者の採用意向
に関するアンケート調査を実施する。
アンケートは、「(3)県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件の
調査」で実施するアンケートと同時に実施する。
(5)海外の IT企業における OSS ベース商材創出の調査
A.アジアにおける IT企業現況
欧米地域における IT 企業の状況把握や OSS ビジネスの考え方、市場規模などを
インターネット上の IT系ニュース、検索サイトなどの情報源から調査する。
B.アジア地域の IT 企業における OSS ベース商材創出に関する可能性の検討
アジア地域、特に中国の IT 企業における OSS をベースとした商材創出意向、も
しくは沖縄 IT企業との連携(条件の明確化も含む)、さらに沖縄発ソフトウェア製
品の利用可能性、県内 IT企業との提携に関する可能性について、ヒアリング調査
を行う。
C.欧米地域における IT企業現況
欧米地域における IT 企業の状況把握や OSS ビジネスの考え方、市場規模などを
インターネット上の IT系ニュース、検索サイトなどの情報源から調査し、県内 IT
企業が OSS を活用したビジネスに有益となる参考情報を調査する。
(6)事業連携に向けた体制構築
A.県内 IT 企業により行われる OSS ベースの事業に向けた体制構築
県内 IT 企業が OSS ベースの商材構築事業に向けた体制構築およびその体制を有
効に機能させるための条件やビジネス環境について、分析・検証を行う。
B.上記体制を有効に機能させるための条件およびビジネス環境の分析と検討
これらの検討においては、上記の体制と計画が有効に機能するための条件を検
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
15
討する。条件の検討に際しては標準的な手法を用いて課題を抽出し、課題を克服
するために何が必要かを検討する。
検討した結果は、調査(1)~(5)までを含めて調査報告書としてとりまとめる。
1.2.3 調査方法に関する補足
(1)検討委員会の設置・運営
調査にあたっては、IT スキルやビジネスに関する専門家から構成される検討委
員会を設置し、調査精度向上を目的とした助言を求める。
同検討委員会の開催は、調査の進捗に応じて 3回程度開催するが、必要に応じて
専門部会を設置することも想定する。
なお、検討委員の選定は、事前に沖縄総合事務局と協議して行う。
1.3 調査実施条件
本調査の主体となる体制とその役割、外部の協力体制、作業スケジュールを以下に示す。
1.3.1 体制および役割
本調査の実施体制および役割を図 1.3.1-1 に示す。
図 1.3.1-1 本調査の実施体制および役割
1.3.2 作業スケジュール
本調査作業のスケジュールを表 1.3.2-1 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
16
表 1.3.2-1 調査作業スケジュール
作業項目 1 月 2月 3月 備考
プロジェクト管理
OSS ベース商材
国内市場調査
事前準備
実施
取り纏め
商材化の可能性を
有する OSS の予備調査
事前準備
実施
取り纏め
県内 IT 企業の OSS 活用
条件および OSS技術者育
成条件の調査
事前準備
実施
取り纏め
OSS を活用したインター
ンシップの可能性調査
事前準備
実施
取り纏め
海外の IT 企業における
OSS ベース商材創出の調
査
事前準備
実施
取り纏め
体制構築検討
事前準備
実施
取り纏め
報告書とりまとめ事前準備
実施
検討委員会
凡例 ▲ :計画 ▲ :実績
1.4 本報告書の構成
本報告書の構成を表 1.4-1 に示す。
▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲
1/27 2/26 3/27
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
17
表 1.4-1 本報告書の構成
構 成 概 要 対応ページ
第 1章 本調査の前提および概要を示す。 10~17
第 2 章 OSSを材料としたビジネスの国内市場の調査結果を取り
まとめる。
18~56
第 3 章 商材化の可能性を有する OSS の予備調査結果を取りま
とめる。
57~131
第 4 章 県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件
について取りまとめる。
132~162
第 5 章 県内大学におけるインターンシップ制度の整備状況お
よびインターンシップ経験者の県内 IT 企業における採
用意向について取りまとめる。
163~175
第 6 章 アジア地域、欧州地域、北米地域の IT 企業の OSS 活動
動向および沖縄 IT 企業が OSS を活用したビジネスでの
市場性について取りまとめる。
176~189
第 7 章 県内における OSS を活用したビジネスの事業推進に向
けた体制の検討結果、体制を有効に機能させるための条
件およびビジネス環境について取りまとめる。
190~198
第 8 章 調査結果の総括および提言を取りまとめる。 199~221
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
18
第2章 OSS を材料としたビジネスの国内市場調査
本調査では、国内 OSS ベース商材の販売状況および OSS を利用した IT サービス提供状況
とそれらのニーズを調査し、OSS 活用商材の潜在的市場規模を検討した結果を示す。
2.1 OSSを活用したビジネスモデル
企業のビジネスモデルは、従来の企業における閉鎖型の製品開発およびライセンス販売モ
デル(クローズド・イノベーション)からオープン・イノベーションの概念に裏打ちされた
開放型の製品開発、および新たなビジネスモデルの創出へとビジネス活動の本質が変化し
てきている。クローズド・イノベーションとオープン・イノベーションの概念の違いを表
2.1-1 に示す。
表 2.1-1 クローズド・イノベーションとオープン・イノベーションの概念の違い
クローズド・イノベーション オープン・イノベーション
企業内の要員が企業のために働く 全ての人と一緒に働けるわけではないが、企
業内外の両方の人々と一緒に働く必要がある
研究開発から利益を得るために、企業は自ら
アイデアを出し、開発し、出荷する
企業外の研究開発から利益を得ることがで
き、その利益のために企業内の研究開発が一
部の役割を果たす
「利益の源泉」となる製品/サービスを一から
創り出し、マーケットに一番に持ち込み、市
場シェアを獲得(先行者利益の追求)
利益を得るためには、必ずしもその研究を一
から作り出す必要はない
イノベーションを最初にマーケットに持ち込
むことに重要視する
最初にマーケットに持ち込むよりも、良いビ
ジネスモデルを確立することに重点を置く
ある産業の中で多くの、そして最高のアイデ
アを生み出すことができれば、勝利できる
企業内外の両方から生み出されたアイデアを
最高の形で使えれば、勝利できる
企業は競合企業が自分たちのアイデアから利
益を受けることがないよう、イノベーショ
ン・プロセスをコントロールしなければなら
ない
企業は自らのイノベーション・プロセスを利
用する他者から利益を得られるようにし、自
らのビジネスモデルを前進させることができ
る場合、常に他者の IP(知的財産)を買う必要
がある
出典:Chesbrough, Henry(2003) Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology.
Harvard Business School Press, Boston.
Chesbrough, Henry(2006)Open business models:How to thrive in the new innovation landscape. Harvard
Business School Press, Boston.
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
19
このビジネスモデルのパラダイムシフトにオープンソースが果たしている役割は非常に
大きいものと言え、現段階においても OSS を活用した多様なビジネスモデルが存在し、生
まれている。
市場における OSS を活用した主なビジネスモデルを図 2.1-1 に示す。
図 2.1-1 OSS を活用した主なビジネスモデル
ビジネスモデル
中核 付加要素(狙い所)
OSS の創出 付加サービス販売
デュアルライセンス販売
商用製品へのアップグレード
上位グレードの商用製品へのアップグレード
パートナーシッププログラム
他者開発 OSS の
カスタマイズ
付加サービス
パートナーシッププログラム
商用製品の機能補完/
強化
商用製品に OSS を組み込んだ商用製品創出
商用製品と OSS を融合した商用パッケージ創出
商用製品ラインナップに OSS を融合したラインナップ強化
その他 OSS の活用 システム構築
保守
教育
IT サービスでの活用
なお、これらのビジネスモデルは、すべて企業プロモーションに活用されている可能性が
高いと推察する。
2.2 国内 OSSベース商材の販売状況
国内 OSS ベース商材の販売状況を以下に示す。
2.2.1 OSSベース商材販売事例収集の対象
事例収集は、インターネット上の IT 系ニュース、検索サイトなどを利用し、主として
インターネットを介して宣伝されている情報に基づき抽出することとした。
2.2.2 収集の手順
販売事例情報収集の手順を以下に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
20
①インターネット検索サイトを活用し、OSS を活用した商材の販売事例を収集する。
なお、収集する販売事例は、国内の事例を対象とする。
②収集した販売事例から特徴的な販売事例を抽出する。
③抽出した販売事例を表 2.2.2-1 に示す形式でとりまとめる。
表 2.2.2-1 販売事例のとりまとめ形式
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
販売事例で用いている OSS の名称とソフトウェア分類を記述
2 事例概要 抽出した販売事例の概要を記述
3 ビジネスモデルの形態 販売事例におけるビジネスモデルの形態を記述
4 事例収集源 事例の収集源を記述
2.2.3 OSSベース商材の販売事例
抽出した販売事例を表 2.2.3-1~表 2.2.3-9 に示す。
表 2.2.3-1 販売事例(Compiere)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
Compiere(ERP)
2 事例概要 流通業やサービス業の中小企業で利用されることを
想定したオープンソースERP・CRMソリューションパッケージである。
最も基本的なソフトウェアである「コミュニティエディシ
ョン」とサポート契約付きの「スタンダードエディショ
ン」、は GPL2 ライセンスで配布されるが、商用ライセンス版の「プロフェッショナルエディション」、も存在す
る。「スタンダードエディション」、および「プロフェッシ
ョナルエディション」の利用に関しては、Compiere社との契約が必要であり、利用料が発生する。これらの
上位バージョンでは、標準機能に加え、PDF 出力機能など付加的機能を利用可能となっている。
日本では、株式会社アルマスが中心となり、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
21
Compiere を活用したビジネスを推進している。利用料を徴収する上位バージョンの販売に加え、ユーザ
マニュアルやスターターキットなどのドキュメント販売
や、トレーニング(講習会)の提供、導入コンサルティングが同社のビジネスモデルである。
4 ビジネスモデルの形態 コミュニティ運営、技術コンサル、サポート、パートナ
ープログラム
5 事例収集源 www.compiere-japan.com
表 2.2.3-2 販売事例(ERP5)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
ERP5(ERP)
2 事例概要 Nexedi社が中心となり開発を進めている ERP ソリューションパッケージである。同ソフトウェアの利用によ
り CRM(顧客管理)、MRP(生産管理)、SCM(サプライチェーン管理)、DMS(文書管理)、KM(知識管理)、HRM(人事管理)といったビジネスの中核を成す様々な経営管理システムを実現する。
ERP5 自体は GPL により提供されている。ERP5 を用いた様々な経営管理システムソリューションの構築
が Nexedi 社のビジネスモデルである。またシステム構築だけでなく、ERP5 導入に関するコンサルティングや、トレーニングおよびサポートの提供、カスタマイ
ズ、研究開発といった様々なサービスを提供する。
3 ビジネスモデルの形態 コミュニティ運営、技術コンサル、サポート、パートナ
ープログラム
4 事例収集源 www.nexedi.co.jp ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071009/284038/
表 2.2.3-3 販売事例(OpenPNE)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
OpenPNE(運用管理・監視ソフトウェア)
2 事例概要 株式会社手嶋屋が中心となり開発を進めてきた SNS
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
22
エンジンである。ソフトウェアは PHP ライセンスで提供される。社内 SNS のような組織内部での利用に向けたダウンロードサービスの他、セットアップ済みの
SNS システムをすぐに利用できるホスティングサービスの提供も行われている。なお、ホスティングサービ
スではOpenPNEの基本機能に加えてサービスの監視やバックアップ、復旧サービスなどの付加機能を利
用することができる。ホスティングサービスの利用にあ
たっては、利用者数の規模に応じた月額利用料が設
定されている。
また株式会社手嶋屋では、ホスティングサービスを含
むASPサービスだけでなく、OpenPNE管理ソフトウェア(OpenPNE Manager)の有償提供、運用サポート、OpenPNE カスタマイズサービス、技術サポートなども提供し、これらのビジネスが OpenPNE に関連した同社の主要なビジネスモデルとなっている。
3 ビジネスモデルの形態 コミュニティ運営、技術コンサル、サポート、パートナ
ープログラム
4 事例収集源 www.openpne.jp
表 2.2.3-4 販売事例(Hinemos)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
Hinemos(運用管理・監視ソフトウェア)
2 事例概要 複数のコンピュータを統一的に運用管理するための
機能を備えた、運用管理・監視ソフトウェアである。
Hinemosでは、WebサーバやAPサーバなど、多数のコンピュータをグループにまとめ、監視管理、ジョブ
管理、性能管理、一括制御などの管理業務を実現す
る。 Hinemos は株式会社 NTT データが開発を進めたOSS であり、ソフトウェアは GPL で公開されている。なお、Hinemos 開発の起源は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による平成 16年度オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業において遂行された
「分散ファシリティ統合マネージャの開発」である。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
23
株式会社 NTT データおよびパートナー企業におい
ては、Hinemos の導入時や運用時における技術サ
ポートを提供するビジネスを展開している。また定期
的にセミナーやハンズオン研修(いずれも有償)を行う
ことも、Hinemos に関連した同社ビジネスのひとつで
ある。
3 ビジネスモデルの形態 技術コンサル、サポート、パートナープログラム
4 事例収集源 www.hinemos.info
表 2.2.3-5 販売事例(MTAIS-eLG)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分
類
三 菱 電 機 自 治 体 総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム
MTAIS-eLG(業務パッケージ)
2 事例概要 三菱電機株式会社が開発した電子自治体向けシス
テムを「三菱電機自治体総合行政情報システム
MTAIS-eLG(エムタイズ イーエルジー)」を OSSとし
て公開したものである。本システムは申請書の受付や
審査を行う「電子申請システム」であり、財団法人地
方自治情報センターにおいて共同アウトソーシング
事業によるシステム一覧に登録されている。
MTAIS-eLG に関する同社のビジネスは、基本シス
テムを OSS として公開することにより低コスト化し、そ
の上で支援サービスを提供するモデルである。具体
的には、自治体がMTAIS-eLGを導入する際の導入
支援やカスタマイズ支援、運用支援などのサービスを
自治体向けに提供する。
3 ビジネスモデルの形態 技術コンサル、サポート、パートナープログラム
4 事例収集源 www.incom.co.jp/newsroom/desc.php/1255
表 2.2.3-6 販売事例(Star Office)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分
類
Star Office(オフィス向けソフトウェア)
2 事例概要 サン・マイクロシステムズが販売するオフィス向け製品
である。元々、ドイツの StarDivision 社により開発さ
れていたが、サン・マイクロシステムズが同社を買収
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
24
し、OSS として公開した。なお、OSS として公開されているバージョンは Open Office と呼ばれる。なお、商標の問題があり、日本を含むアジア圏では Star Suite という製品名が用いられている。現在、開発の中心は OpenOffice.org のコミュニティであるが、サン・マイクロシステムズも開発に深くコミッ
トしている。OpenOffice.org の開発成果に、フォントやテンプレート集などの付加価値を加えたものが商
用製品版の Star Office (Star Suite)である。一般消費者向けのリテール製品は、日本ではソース
ネクスト株式会社などを通じて販売されている。一般
的なソフトウェアのパッケージ販売だけでなく、USBメモリに入れてハードウェア込みで販売するなど、ユ
ニークな販売方法も採用されている。
3 ビジネスモデルの形態 ビジネスモデル:変形デュアルライセンスによる商用
製品販売、構築、保守
4 事例収集源 www.sun.com/software/staroffice/index.jsp
表 2.2.3-7 販売事例(Open Office.org)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
Open Office.org(オフィス向けソフトウェア)
2 事例概要 OpenOffice.org は、他社による導入支援サービスの提供例が存在する。
株式会社クリアコードでは、企業、自治体向けに
Linux、Mozilla Firefox、OpenOffice.orgなどの導入支援サービス、ソフトウェア(システム)開発サービスを有償で提供している。
ま た 株 式 会 社 ア シ ス ト も 、 OSS で あ る
OpenOffice.orgやMozilla製品を導入することで経費 削 減 を 狙 う ソ リ ュ ー シ ョ ン を 提 供 す る 。
OpenOffice.org や Mozilla 製品を利用した同社のビジネスモデルは、OpenOffice.orgやMozilla製品への移行を支援するコンサルティングや、ヘルプデス
ク・サービス、トレーニング・サービスの提供(いずれも有償)が中心である。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
25
3 ビジネスモデルの形態 コンサルティング、技術サポート、トレーニングなど
4 事例収集源 www.clear-code.com www.ashisuto.co.jp/solution/OSS/
表 2.2.3-8 販売事例(Asterisk)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
Asterisk(IP-PBX ソフトウェア)
2 事例概要 米国 Digium社により開発された IP-PBX ソフトウェアである。GPL(ver.2)によりOSSとして公開されている。2008 年末に、秋田県大館市が Asterisk を採用して IP電話システムを構築したことでシステム構築コストを 20分の 1以上圧縮した事例を発表したことにより、脚光を浴びた。
Digium社のビジネスモデルは、他の OSS活用ビジネスと同様、サポートサービス、カスタマイズや
Asterisk ベースシステムの開発、トレーニングや認証サービスの有償提供が中心となっている。またユニ
ークなところでは、Asterisk をベースとする音声録音、自動応答(IVR, Interactive Voice Response)システムの開発も同社ビジネスのひとつである。
3 ビジネスモデルの形態 OSS+CSSによる商用製品販売、構築、保守4 事例収集源 www.digium.com
表 2.2.3-9 販売事例(PowerGres)
項番 項目名 内容
1 OSS 名とソフトウェア分類
PowerGres(データベース)
2 事例概要 SRA OSS社(日本支社)では、OSSとして公開、提供さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス 管 理 シ ス テ ム の
PostgreSQL と商用製品のデータベースの一部を融合し、さらにデータベース操作ツールやサポートなど
の付加価値を高めた製品を、PowerGres として販売している。PowerGres ファミリーは、PowerGres on Windows/Linux、PowerGres Plus、PowerGres HAなど、多様な製品群から構成される。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
26
また PowerGres の販売に限らず、 Linux とPosgreSQLを用いたシステム開発に関するコンサルテ ィ ング 、 LibSylph(OSS メ ールク ラ イア ン ト
Sylpheed のコア部分をライブラリ化したもの)組み込みコンサルティングなども有償で提供している。さら
に、それらの OSSによるシステムの運用サポートプログラムや、同ソフトウェアに関するトレーニングプログ
ラムの提供、PostgreSQL 技術者認定試験の実施と、同社における OSS関連のビジネスモデルは幅広い。
3 ビジネスモデルの形態 OSS+CSSによる商用製品販売、構築、保守4 事例収集源 powergres.sraOSS.co.jp/s/ja/welcome.php
2.3 OSSを利用した ITサービス提供状況
OSS を利用した ITサービスの提供販売状況を以下に示す。
2.3.1 ITサービス提供事例収集の対象
事例収集は、インターネット上の IT 系ニュース、検索サイトなどを利用し、主としてイ
ンターネットを介して宣伝されている情報に基づき抽出することとした。
2.3.2 収集の手順
IT サービス提供事例の収集手順を以下に示す。
①インターネット検索サイトを活用し、OSS を活用した商材の販売事例を収集する。
なお、収集する販売事例は、国内の事例を対象とする。
②収集した ITサービス提供事例から特徴的な事例を抽出する。
③抽出した ITサービス提供事例を表 2.3.2-1 に示す形式でとりまとめる。
表 2.3.2-1 IT サービス提供事例のとりまとめ形式
項番 項目名 内容
1 事例概要 抽出した販売事例の概要を記述
2 サービス提供状況 ITサービスの提供状況を記述3 OSS 名およびソフトウェ 用いている OSS名およびソフトウェアの分類を記述
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
27
ア分類
4 事例収集源 事例の収集源を記述
2.3.3 OSSを利用した ITサービス提供事例
OSS を利用した ITサービス提供事例を表 2.3.3-1~表 2.3.3-10 に示す。
表 2.3.3-1 販売事例(mixi)
項番 項目名 内容
1 事例概要 mixi が提供するサービスの根幹である、会員同士の
コミュニケーションや情報交換を目的としたコミュニテ
ィ型招待制SNSサービスで OSS を活用している。
mixi では、イニシャルコストを抑える目的で初期段階
から Apache(Web サーバ)、MySQL(DBMS)などの
OSS を利用していたが、人気の向上に伴い、急激に
加入者が増加したため、スケーリングの課題に直面し
てきた。特にDBMSに関しては、更新系トラヒックが
多いというSNSの特性上、単純なレプリケーションに
よる負荷分散では解決できない課題があったが、
MySQL や OSS をベースに開発した機能によって解
決し、mixi 独自のSNSシステムとして付加価値の高
いサービスを提供し続けている。
これらの知見のいくつかは OSS として公開され、多く
の技術者が活用できるようになっている。
URL : http://mixi.co.jp/ 2 サービス提供状況 2004 年 2 月から2台のレンタルサーバから開始した
サービスは、順調に会員数を伸ばし 2008 年 10 月時
点ではおよそ 1500 万人、月間ページビューは 136億 PV となっている。SNS特有の広告収入によるビジ
ネスモデルが核であり日記サービスを中心に若者(20代、30 代)に高い支持を得ている。2008 年上期にお
ける売上高はおよそ50億円で前年同期比 26%増と
なっている。
事例にあるように、サービス基盤は「オープン」なもの
を活用している。OSS という視点以外にオープン・ス
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
28
タンダードという視点での取り組みも行っている。
例えば、OpenID(ユーザ認証)、OpenSocial(SNS
向けAPI)対応なども特徴的といえる。
3 使用 OSS 名およびソフ
トウェア分類
Linux(OS)、Apache(HTTP サーバ)、MySQL(リレ
ーショナル DBMS)、Perl(プログラミング言語 )、TokyoTyrant*1、TokyoCabinet*2、Memcached(分散型メモリキャッシュシステム)、Hyper Estraier(全文検索システム) など
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081028/317965/?ST=desktop&P=2 (ITPro) ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060330/233820/ (ITPro) techtarget.ITmedia.co.jp/tt/news/0709/12/news01.html (ITMedia)
*1:mixi が独自開発した分散キャッシュソフトウェアで OSS として公開*2: mixi が独自開発したデータベース管理ソフトウェアで OSS として公開
表 2.3.3-2 販売事例(楽天)
項番 項目名 内容
1 事例概要 1997 年に立ち上げ。事業の核となる「楽天市場」、
「楽天オークション」、「楽天ブックス」など、ECサービ
スのシステムにおいて、OSS を積極的に活用してい
る。基本ソフトウェアに Linux や MySQL などが使わ
れているが、サービス基盤開発で、PHP、Java、
Ruby などのプログラミング言語やフレームワークが
利用されているのが特徴的である。開発するアプリケ
ーションによって開発環境や言語が異なるのは、「異
質」とも言われるが、このスタイルは「外部に対し情報
を提供すれば、我々が必要とする情報も入手しやす
くなる」と担当者がコメントしている。これは、OSS を必
ず優先させるということではなく、適材適所で必要な
機能を見合うコストで実現する、ということを意識して
きた結果だと推察する。
また、コミュニティ活動への貢献も大きい。
URL : http://www.rakuten.co.jp/ 2 サービス提供状況 2008 年 12 月末の時点で 7 つの事業領域でビジネス
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
29
展開しており、2008年度の売上はおよそ 2,500億円にのぼる。このうちの約4割が立ち上げ当初から続い
ているEC事業である。特に約 750億円を売り上げているオンラインショッピングモール「楽天市場」は、都
市近郊に物理的店舗を持てない中・小規模な事業者
にビジネスチャンスを与えている。これは、営業活動
やマーケティング費となどの経費を削減できる点で、
大手量販店と比較しても価格競争力を維持できると
いうメリットがあるためである。
また、消費者の視点から見ても、出店店舗を審査す
る仕組みがあることから、よい製品・サービスを、より
安く、より安全に購入することができる、というニーズ
を満たすことになる。その結果、店舗数約 2万 6,000社(2009年3月時点)、会員ID数は5,000万に(2008年 12 月)まで増加した。これは、一時間のシステムダウンが、億単位の損失となる規模である。CEOの三
木谷氏が現在のサービスに求める信頼性・可用性を
原子力発電所の運用に例えたのは、IT 技術レベルの高さを物語っているといえる。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Linux(OS)、MySQL(リレーショナル DBMS)、PHP(プログラミング言語)、Ruby(プログラミング言語)、Ruby on Rails(アプリケーションフレームワーク)
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/members/SI/OSS/20031007/1/(ITPro) ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071http://www.rakuten.co.jp/info/history.html219/289701/ (ITPRo) www.atmarkIT.co.jp/news/200311/13/rakuten.html (@IT) ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081201/320423/ (ITPro) www.rakuten.co.jp/info/history.html(自社サイト)
表 2.3.3-3 販売事例(Yahoo!)
項番 項目名 内容
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
30
1 事例概要 1994年に米国で Yahoo Inc.が設立され、2 年遅れの 1996年に井上雅博CEOがインターネットビジネスの先駆けとして Yahoo! Japanを立ち上げ、1997年に株式公開した。筆頭株主はソフトバンクである。サ
ービス開始当初は「日本ではインターネットは普及し
ない」と見られていたが、2001 年に ADSL 回線を使った定額インターネット接続サービスを提供すること
で、多くのインターネットユーザを獲得し、爆発的な成
長を遂げた。事業としての成功だけでなく、日本にお
けるインターネットの普及に大きく貢献したといっても
過言ではない。
1996 年から提供が開始されたポータルサイトサービスは、オープンソースのOSであるFreeBSDが使わ
れ、また、サービスやデータベースは、独自の技術に
よって開発されていた。
1999年頃からOSSを使った運用へと切り替えを行ってきた。1999年にWebサーバを Apacheに、DBMSを MySQL に、2002 年には、サービス開発環境をPHPベースに移行した。中でも大規模なサービスの
開発にPHP を採用しているのは特徴的であり、PHPで運用されている日本最大のサイトが Yahoo! Japanであることは広く知られている。
また、Yahoo!は、独自のサービスを安定的に提供するプラットフォームを構築するという観点で、Oracleなどの商用ソフトウェアも活用している。
OSSであるPHPを採用した理由として・スクリプト言語であること
・国際化に対応していること
・トレーニングコストが安価であること
・パフォーマンスが良いこと
などを挙げているが、Yahoo!は、PHPのコア開発者が社員として在籍していることが背景にあることから、
PHPがあたかも Yahoo!独自の技術であるかのように扱うことができ、生産物をPHPコミュニティにフィード
バックすることで、エコシステムを維持しつつ、収益性
のあるサービスを開発、提供していく体制を早期から
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
31
築き上げてきた。
最近では、2007 年に買収したメールを中心としたオープンソースのグループウェアである傘下の Zimbraのユーザ数が 4,000 万を突破したことが記憶に新しい。
URL : http://www.yahoo.co.jp/ 注:サービスプラットフォームで使われている技術基盤
は、規模や展開時期の違いはあるものの本家米国の
Yahoo! Inc.と日本法人である、Yahoo! Japan の間で
大きな差異はそれほど無いと推察されることから、本
情報は、米国法人の情報をベースに説明している。
2 サービス提供状況 現在(2009 年 3 月)に至っては、広告、ビジネスサービス、パーソナルサービスの 3 つの事業を柱に 140を超えるサービスにより年間 3,000億円を売上、営業利益は 4割を超えている。売上の半分は広告収入によるもので、従来のディスプレイ広告から興味・関心
連動型広告によるユーザニーズの取り込みも確実に
行い、事業規模は安定して 2桁台の成長を見せている一方、70%の高い営業利益率のパーソナルサービス領域でも 2桁近い伸びを見せている。また、2007年7月時点のアクティブユーザ数は1996万人、2008 年 3 月時の月間PVは 431 億PVとなっている。オークションに出店している店舗数でも
32,000 店以上(2008 年 12 月末時点)であり、ECを専門としている楽天よりも多い。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
FreeBSD(OS)、PHP(プログラミング言語)
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070920/282665/?ST=lin-server&P=3
表 2.3.3-4 販売事例(クックパッド)
項番 項目名 内容
1 事例概要 1997年に有限会社コインが 1998年に料理のレシ
ピ情報を提供するSNSサイトとして事業を開
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
32
始したサービスで、「毎日の料理を楽しくするこ
とで、心からの笑顔を増やすこと」を掲げて提供
を行っている。
サービス開始当初は、Web2.0 の典型的なスタイルである広告収入によるビジネスモデルではな
く、ユーザから会員費(500 円/月)を徴収するモデルで運営されていたが、想定していた加入者数を
獲得ができなかったことから、広告収入に頼るビ
ジネスモデルに切り替え、口コミによる加入者の
獲得を成功させ、現在に至っている。
収益モデルとしては 3つの領域がある。①認知ブランディング
サイト運営により加入者を獲得し、囲い込む
②個人向け
有料会員としてのインセンティブの提供と
いったサービスの差別化
③法人向け
広告収入の源泉
重要なポイントは、広告を提供する企業とユーザ
の間をつなぐ仕組みを確立したことにあり、少子
高齢化などにより飽和した食品業界にビジネス
の機会を与える一方で、多様化するライフスタイ
ルを持つユーザに情報を提供ることにより両者
のニーズを満たす形を創り出したことにある。こ
れは「スイッチボード利益型ビジネスモデル」と
いわれている(例えば、レシピコンテストを実施し、食品企業の製品をプレゼントするといった企
画などがある)。クックパッドでは、OS に Linux(CentOS)、DBMS (MySQL)などが利用されている。特徴的なのは口コミや人気検索といったSNSに必要となるサービスが
Ruby on Railsのフレームワークで利用されていて、このフレームワークと利用するサイトの規模は、月間3
億PVを処理し、世界第 3位を誇っていることである。OSS を利用する理由としては、①コスト削減 ②柔軟性 ③スケーラビリティー ④開発 などにあると推察さ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
33
れる。特に、クックパッドの場合においては、新しいサ
ービス、機能をOSSの活用によって開発することは、合理的な選択だといえる。
一方で、受注情報、顧客管理、営業力強化、ビジネ
ス分析、といった自社の基幹部分には商用の IT サービスである SalesForce.com が利用されている。また、同じく商用の仮想化ソフトウェアである VMWare ESXiによりほとんどのサーバが仮想化されている。
URL : http://cookpad.com/ 2 サービス提供状況 現在(2009年1月)の会員数は 550万人におよびそ
のうちの 90%以上が女性であり、その多くが 20代、30代の主婦層といわれている。ユーザから投稿されるレシピは 2003 年の時点で5万品を超えページビューも 20008年 11月においては、3億月間PVを記録している。収益については公開されていないが、2006年の時点で 3年後に 10億円の売上目標をに掲げており、実績として過去年間 200%の成長を見せているという情報もあることから、数十億円規模のビジネ
スを展開していると推測される。従業員数は 40人(2008年 11月時点)。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Linux(OS)、MySQL(リレーショナル DBMS)、Ruby(プログラミング言語)、Ruby on Rails(アプリケーションフレームワーク)
4 事例収集源 www.slideshare.net/hashikem/rails-presentation-667968
表 2.3.3-5 販売事例(野村総研 証券 ASP)
項番 項目名 内容
1 事例概要 株式会社野村総合研究所の提供する「証券オンライ
ントレード ASP」サービスは、毎秒 24,000 件トランザクションという大量のデータ処理と高信頼性、高セキ
ュ リ テ ィ を OpenStandia で 実現 し て い る 。
OpenStandia とは、「JBOSS,Tomcat,MySQL,Hibernate,Strus,Spring」を初めとしたオープンソ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
34
ースのワンストップサポートビスの総称である。
なお、提供される全 OSS の検証とチューニングは野
村総合研究所が実施しており、商用製品に引けを取
らないサービス提供を、OSS を利用することで安価に
提供し続けている。
URL :非公開
2 サービス提供状況 金融業界から自治体に至る 200 社(200 プロジェクト)以上のユーザに利用されてきている。
また、「時価の変動をリアルタイムに把握し、素
早く注文を出したい」といったユーザの要望や
「初期・運用コストを大幅に削減したい」といっ
た事業主の要望を効果的・柔軟に応えるサービス
であるとして、契約者数も、毎月増加している。
3 OSS 名およびソフトウェ
ア分類
JBOSS(アプリケーションサーバ)、Tomcat(アプリケ
ーションサーバ)、MySQL(リレーショナル DBMS)、Hibernate(オブジェクト関係マッピングフレームワー
ク)、Strus(アプリケーションフレームワーク)、Springアプリケーションフレームワーク
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061108/252963
表 2.3.3-6 販売事例(DeNA モバゲータウン)
項番 項目名 内容
1 事例概要 株式会社ディー・エヌ・エーが提供する「モバゲータ
ウン」は、本格的なリアルタイム対戦ゲームから手軽
に楽しめるミニゲームまで、数々の高品質ゲームを無
料で提供するサービスである。さらに、他のユーザと
ゲームに関するコミュニケーションを図るため、SNSサービスも提供している。
本サービスの利用者数の増加は目覚しく、システム
面の柔軟なスケールアウトが要求されている。
モバゲータウンを支えるシステム基盤は、オープンソ
ースのソフトウェア群 LAMP(Linux+Apache+
MySQL+Perl)をベースに開発・運用されている。
LAMP を活用することにより「システム構築コストや運
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
35
用コストの減少」や「仕様の高頻度修正」、「短納期リ
リース」など可能とし、利用者が満足するサービスを、
提供し続けている。
また、同システムで使用しているフレームワーク
「MobaSiF*1」はオープンソースとして公開され、多く
の技術者が共有できるものとなっている。
URL : http://mbga.jp/ 2 サービス提供状況 2006 年 2 月のサービス開始以降、順調に会員数を
伸ばし、2008年 12月時点では約 1,234万人であり(参考:前年同期に比べ 369 万人増)、1 日のページビューは約 5億 PVを超えている。なお、10 台のサーバから開始した本サービスは、現時点で約450台のデータベースサーバ、約300台のWeb サーバ、その他に検索用、動画配信用、対戦ゲーム用といったサービス系のサーバ 250 台にまで拡大している。
ビジネスモデルは、アバター(ユーザの分身)関連収入、広告収入が核であり、若者(10 代がユーザの 4割、16歳・17歳の男性に限ると人口の 6割以上を占める)の支持を得ている。2008 年第 3 四半期(2008年 10 月~12 月)の売上高は 49億 4200万円万円で前年同期比 97.1%増となっている。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Linux(OS)、MySQL(リレーショナル DBMS)、Perl(プログラミング言語)、MobaSiF*1
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080517/302112/
*1: DeNa が独自開発したフレームワークソフトウェアで OSS として公開
表 2.3.3-7 販売事例(GREE)
項番 項目名 内容
1 事例概要 グリー株式会社が提供する「GREE」は、会員同士のコミュニケーションや情報交換を目的としたコミュニテ
ィ型の招待制SNSサービスである。
「GREE」は、(GREE 本体を除く)すべてのソフトウェ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
36
アをオープンソースで構築しており、既存のソースコ
ードを享受しつつ、必要に応じて改良を加えるといっ
たオープンソースのメリットを最大限に活かしている。
GREE を支えるシステム基盤は、OS が Debian/ GNU Linux、DBMSがMySQL、全文検索機能がMySQL 4.0.xと Senna、WebサーバがApache、画像処理系が ImageMagick、プログラミング言語がPHP である。さらに、キャッシュサーバ、アプリケーションフレームワーク、外部監視、グラフ化、周辺ツール
まで全てオープンソースが利用されている。
URL : http://gree.jp/ 2 サービス提供状況 2006 年 2 月のサービス開始以降、順調に会員数を
伸ばし、2008 年 10 月時点では約 700 万人超であり、2009 年 3 月時点の月間ページビューは 100 億PV超となっている。 (参考:2008年 3月、5月、8月時点の会員数は、それぞれ、約 400万人、約 500万人、約 600万人。現在、mixi、モバゲータウンに次ぐ規模) なお、2008年 12月に東証マザーズへの上場を果たした。
GREE の月間ページビューの 95%以上が携帯電話からのアクセスであり(参考:mixiは 65%程度) グリーはすでに実質的に携帯SNSに近い。 ビジネスモデルは、有料課金収入、広告収入が核で
あり、若者(19歳以下が約 30%、20代が約 40%、30代が約 25%)の支持を得ている(参考:mixi より若年層が多くモバゲータウンに近い利用者層)2008年 6月期の売上高は 29億 3748万円で前年同期比 9倍増となっている。なお、経常利益は 10億5125円。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
MySQL(リレーショナル DBMS)、PHP(プログラミング言語)、Senna*1
4 事例収集源 www.atmarkIT.co.jp/news/200602/10/gree.html*1: 未来検索ブラジルが公開している OSS 検索エンジン
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
37
表 2.3.3-8 販売事例(ニコニコ動画)
項番 項目名 内容
1 事例概要 株式会社ドワンゴは、インターネット上での多彩なエ
ンタテイメントコンテンツを提供している。中でも、動
画配信サービス(ニコニコ動画)の利用者数の増加は
目覚しく、システム面でも柔軟なスケールアウトが要
求されている。
ニコニコ動画システムを支えるシステム基盤は「フロン
トエンド: Web サーバ、メッセージサーバ、バックエン
ド:DB サーバ、キャッシュサーバ」から構成される。ま
た、各サーバでは、以下の通り OSS が利用されてい
る。 ・Web サーバ:「Apache + PHP + Smarty(PHP
のテンプレートエンジン) + memcached」
・メッセージサーバ:「niwavided(Flash Player と
通信を行いコメントの配信および投稿を受け付
けるデーモン。独自開発) →C++で記述」
・DB サーバ:「MySQL」
・キャッシュサーバ:「memcached」
そして、Apache や MySQL などのチューニングを限
界まで実施することにこだわり、限界に達したら柔軟
にサーバを追加するというアーキテクチャー基本方針
をとっている。本基本方針のもと、増え続ける利用者
が満足するサービスを、提供し続けている。
URL : http://nicovideo.jp/ 2 サービス提供状況 2006 年 10 月のサービス開始以降、順調に会員数を
伸ばし、2009 年 1 月時点では約 1109 万人(無料会
員数:約 1083 万人、有料会員数:約 26 万人(3 月に
は 30 万人を突破))となっている。(参考:2008 年 1 月
時点の会員数:約 600 万人。うち、有料会員は約 19万人)また、動画に書き込むことができるという特徴が強い
ユーザ支持を得ており、YouTube と比較しても、利用
頻度や視聴ページ数、滞在時間は約 2~3 倍となっ
ている。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
38
ビジネスモデルは、有料サービス収入や広告収入、
アフィリエイト収入が核であり、若者(10 代、20 代)の支持を得ている。
2008 年第 3 四半期(2008年 10 月~12 月)の売上高は 46億 6000万円で前年同期比 16.4%増、営業利益は 4億 9600万円、当期純利益は 2億 8600万円となっている。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Linux(OS)、MySQL(リレーショナル DBMS).、PHP(プログラミング言語)
4 事例収集源 info.dwango.co.jp/rd/files/niconico_douga_study_20070425/koizuka.swf
表 2.3.3-9 販売事例(Google)
項番 項目名 内容
1 事例概要 Linux から、アプリケーション開発に至るまで幅広くOSS を利用し、業界をリードしている企業である。社内には数多くのオープンソースの技術者が存在して
いる。例えば、Andrew Mortonは、Linux OSの中核であるカーネルのメンテナ(主要開発者)として有名である。
非公式であるがGoogle がオープンソースを使う理由として、OSSのプロジェクトを支援することで優れた技術者を発掘し採用する機会を得る、ということと、OSSの機能、品質が向上することは、OSS のヘビーユーザである Google 自身に大きなメリットとなる、という2つを挙げている。
実際、Googleは多岐にわたるOSSを利用している。利用シーンとしては以下のような分類ができる。
・自社内のシステムのための利用(たとえばデータセンターで使われるGFS)・ユーザにインターネットから提供する Web サービス(ホスティング型電子メールサービスの Gmail、Spreadsheetなど)・ユーザの環境で動くアプリケーション
(Google Earth、AndroidChromeなど)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
39
現在全世界で30万台ものサーバが稼働しているといわれている。
URL : http://www.google.co.jp/ 2 サービス提供状況 1998 年から操業した Yahoo!とならぶ世界最大の検
索エンジン。日本では、Yahoo!に市場シェアトップを譲っているが、2009 年1月における米国検索市場では約60%(Yahoo!は約20%)で圧倒的なシェアを誇っている。Google の日本法人は、日本史上に与える影響は大きいものの、Yahoo!の場合と異なり、本家から独立した経営はしていないため、以下は米国、日本
を含めたWorld Wideからの視点で記述する。提供
されているサービスは数多く、Google Earth やG-mail のように独自に開発されるものもあれば、YouTube などのように企業買収によって獲得されたものもある。いずれにしてもニーズに対してタイムリー
にサービスを提供しているといえる。事業を支えてい
るのは広告収入で、検索連動型広告を提供する、
AdWords とサイト運用者にアフィリエイト広告を提供するAdSenseの2つに、2008年 7月から新たなアフィリエイト広告サービスとして、Google Affiliate Network も(現在、米国内のみで提供中)で提供され追加された。2008年度の総売上は、112億(約1兆千億円)で営業利益は 30%ほどである。四半期ごとに着実に収益を伸ばしており、ニーズをタイムリーに満
たそうという姿勢がうかがえる。また、それは勤務時間
の 20%を自分の気に入ったプロジェクトに割くよう義務付ける「20 percent time」という社風にも現れている。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Linux(OS)、Python(プログラミング言語)など※AndroidChromeなどを OSS として独自に公開
4 事例収集源 ITpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20070330/267048/
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
40
表 2.3.3-10 販売事例(pepbiz)
項番 項目名 内容
1 事例概要 株式会社アセン トネッ ト ワークスが提供する
「Pepbiz.jp」は、中小企業向けのオープンソースの業務アプリケーションを SaaS 形式で提供するポータルサイトである。現在のサービスは 4カテゴリ 10製品から提供されている。カテゴリおよび製品は、以下の
通りである。
・ホームページ構築サービス
CMS「Joomla」e-コマース「Virtuemart」・営業管理&顧客サポートサービス
CRM「VtigerCRM」、「SugerCRM」顧客サポートシステム「SupportSuite」・コミュニケーションサービス
グループウェア「Zimbra」Web会議「dimdim」・情報・基幹系サービス
ERP「TinyERP」プロジェクト管理「DotProject」ドキュメント管理「KnowladgeTree」
URL : http://pepbiz.jp/ 2 サービス提供状況 2008年5月のサービス開始以降、旅行代理店やEC
サイト運営会社などをターゲット顧客としてサービスを
提供している。同社の年間目標は、顧客企業 1000社、売り上げ月額 2100万円である。
3 OSS 名およびソフトウェア分類
Joomla(CMS) 、 Virtuemart(e- コ マ ー ス ) 、VtigerCRM(CRM) 、 SugerCRM(CRM) 、
Zimbra(グループウェア)、dimdim(Web 会議システム )、TinyERP(ERP)、DotProject(プロジェクト管理)、KnowladgeTree(ドキュメント管理)
4 事例収集源 www.atmarkIT.co.jp/news/200805/27/pepbiz.html
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
41
2.4 OSS活用商材の潜在的市場規模推定
情報サービス産業の 3業態(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、およびインタ
ーネット付随サービス業)の市場概要、OSS 市場規模、および潜在的な OSS 市場の推定規模
を示す。
2.4.1 調査指針
本調査を進めるにあたり、(独)情報処理推進機構(IPA)において OSS の情報サービス産業
における活用状況や普及発展に向けた課題について、経済産業省が定義している情報サー
ビス産業の分類に属する業種(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネッ
ト付随サービスなど)を対象とした「IPA 2008 年度オープンソフトウェア利用促進事業オー
プンソースソフトウェア活用ビジネス実態調査」(以下、IPA 実態調査)に本調査の収集対象
情報がほぼ網羅されていることから、IPA 実態調査の報告書を本調査の情報収集源として活
用することとした。IPA 実態調査は、情報サービス産業の分類に属する業種の企業に対し、
アンケート総数:4,729 社(有効回答数:802 社)および有効回答数の中からの特徴的な 20
社へのヒアリング調査結果に基づき、国内での OSS 活用ビジネスの実態および市場状況を
とりまとめた内容となっている。
(1)IPA 実態調査で有効回答を得た企業の概要
IPA 実態調査で有効回答を得た企業 802 社に関する企業規模を表 2.4.1-1 に、地域を表
2.4.1-2 に、資本金規模を表 2.4.1-3 に、従業員数規模を表 2.4.1-4 にそれぞれ示す。
表 2.4.1-1 有効回答企業の規模
会社数 構成比(%)
大企業 42 5.2
中小企業*1 756 94.3
不明 4 0.5
合計 802 100.0※IPA 実態調査 表 3-8「調査企業と回答企業との規模の比較」の一部を引用
表 2.4.1-2 有効回答企業の地域
会社数 構成比(%)
都市圏*2 506 63.1
地方圏 296 36.9
*1 中小企業は、中小企業金融公庫法などの中小企業関連法令での定義に従い「資本金 3 億円以下または従業員数 300人以下の企業」、としている。
*2 都市圏:埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 愛知県, 京都府, 大阪府, 兵庫県
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
42
合計 802 100.0※IPA 実態調査 表 3-9「調査企業と回答企業との地域の比較」の一部を引用
表 2.4.1-3 有効回答企業の資本金規模
会社数 構成比(%)
1,000 万円以下 132 16.5
1,000 万円以上~5,000 万円未満 344 42.9
5,000 万円以上~1 億円未満 133 16.6
1 億円以上~10 億円未満 158 19.7
10 億円以上 25 3.1
不明 10 1.2
合計 802 100.0※IPA 実態調査 表 3-10「調査企業と回答企業との資本金の比較」の一部を引用
表 2.4.1-4 有効回答企業の従業員数
会社数 構成比(%)
1 人以上~30 人未満 230 28.7
30 以上~100 人未満 325 40.5
100 人以上~300 人未満 159 19.8
300 人以上~1,000 人未満 56 7.0
1,000 人以上 21 2.6
不明 11 1.4
合計 802 100.0※IPA 実態調査 表 3-10「調査企業と回答企業との従業員数の比較」の一部を引用
(2)各業態に含まれる業種の関連定義と事業概要
IPA 実態調査では、「経済産業省 2007 年度特定サービス産業実態調査報告書(以下、METI
実態調査)」に定義されている業態区分を基にそれらに含まれる業種区分を定義している。
IPA 実態調査における業態区分と業種区分の関連定義を表 2.4.1-5 に示す。
表 2.4.1-5 各業態に含まれる業種の関連定義
業態区分 IPA 実態調査で関連付けた業種区分 METI 実態調査
ソフトウェア業 受注ソフトウェア開発
ソフトウェア・プロダクツ
受注ソフトウェア開発
ソフトウェア・プロダクツ
情報処理・提供サービ
ス業
情報処理サービス
システムなど管理運営受託
データベースサービス
情報処理サービス
システムなど管理運営受託
データベースサービス
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
43
インターネット付随サ
ービス業 インターネット付随サービス -
その他 その他
(ハードウェア販売、教育など)-
出典:IPA 実態調査 表 3-6「各業態の定義」
各業態に関連付けた業種区分の事業内容定義を表 2.4.1-6 に示す。
表 2.4.1-6 各業種区分の事業内容定義
IT 関連事業区分 概要
1.受注ソフトウェア開発
特定のユーザからの受注により、新たに開発・作成するオーダーメードのソフトウェアをいい、システムインテグレーション・サービスや保守業務も含める。
2.ソフトウェア・プロダクツ
不特定多数のユーザを対象として開発・作成するイージーオーダーまたはレディメードのソフトウェア プロダクツ。他の企業で開発したソフトウェアであっても、自社ブランド名で販売する場合はここに含める。
3.情報処理サービス
オンライン情報処理、オフライン情報処理、ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)サービス(ソフトウェアの作成から一貫して行うものに限る)、情報処理コンサルティング・サービス(IT 関連投資に係わる企画コンサルティングのみ)
4.システムなど管理運営受託
ユーザの情報処理システム、電子計算機室などの管理運営を受託するサービス業務、アウトソーシングサービス(インターネットデータセンターは含めない)。
5.データベースサービス
コンピュータに各種データを収集、加工、蓄積し、要求に応じて情報として提供する業務。インターネットなどのネットワーク経由でのデータベースの提供業務も含む。(情報の収集、加工を行い、情報提供を行っているものに限る。)
6.インターネット付随サービ
ス
ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダー)業務(ソフトウェアの作成を伴わないもの)、IDC(インターネットデータセンター)業務、コンテンツ配信業務(ただし、不動産情報、気象情報および経済情報などの情報を収集・加工し、情報の提供を行う業務は、「データベースサービス」に含める。)、インターネットを利用する事業などをサポートするサービス業務(広告のためにインターネット上に場所を提供している広告媒体などのポータル事業および課金・決済・回収代行などのプラットフォーム事業など)
7.その他(ハードウェア販売、
教育など)
ハードウェア販売、情報サービス業に関わる研修・講師、データパンチなど。
出典:IPA 実態調査 表 3-7「各業種区分の定義」
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
44
(3)IPA 実態調査における市場規模の概念
IPA の実態調査における市場規模の概念定義を図 2.4.1-1 に示す。
図 2.4.1-1 IPA の実態調査における市場規模の概念定義
出典:IPA 実態調査 図 7-1「市場規模の概念」
2.4.2 比較対象とする IT市場の概要
IT 市場のうち、本調査の比較対象とするソフトウェア業、情報処理・提供サービス業に
ついては、METI 実態調査に掲載されている。しかしながら、インターネット付随サービス
業は、特定サービス実態調査においては、情報処理・提供サービス業などのその他一部の
業務として認識されているものの、業態としておらず、専門業態が調査対象外になってい
る。このため、IPA 実態調査では、総務省が 5年毎に実施している事業所・企業統計調査に
おける 2006 年時点の企業数(2,188 社)に、IPA 実態調査結果の 1 企業あたりの平均売上高
(1,681 百万円)を乗算した金額を市場規模と推定している。
これら各業態の市場規模を表 2.4.2-1 に示す。
表 2.4.2-1 各業態の市場規模
業態 2007 年
ソフトウェア業 約 13兆 4,097億円情報処理・提供サービス業 約 5兆 4,164億円インターネット付随サービス業 約 2兆 5,000億円
全体の市場規模
実際のOSS活用市場の規模(普及阻害要因が現状のままの場合)
実際のOSS活用市場の規模
(普及阻害要因を解消した場合)
潜在的なOSS活用市場の規模
「特定サービス産業実態調査」、「事業所・企業統計調査」を利用して定義
顧客向け製品・サービスで、1つでもOSSを活用しているものを「OSS活用市場」と定義
各種の普及阻害要因が解消された場合のOSS活用
市場の規模
市場環境が整った場合に、到達するであろうと思われ
る市場規模
普及阻害要因の解消による市場拡大
環境整備に伴う市場拡大
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
45
2.4.3 IT市場規模および OSS市場規模の比較
METI 実態調査におけるソフトウェア業の年間売上高は 13 兆 4,097 億円で、IPA 実態調査
におけるソフトウェア業の OSS 活用市場規模は、市場全体の約 5%にあたる約 6,900 億円と
推計しており、2010 年には約 7,800 億円規模に成長すると予測している。
同じく、METI 実態調査における情報処理・提供サービス業の年間売上高は 5 兆 4,164 億
円で、IPA 実態調査における情報処理・提供サービス業の OSS 活用市場規模は、市場全体の
約 3%にあたる約 1,700 億円と推計しており、2010 年には約 2,000 億円規模に成長すると予
測している。
また、インターネット付随サービス業については、IPA 実態調査において年間売上高が約
2兆 5,000 億円であるのに対し、OSS 活用市場規模は市場全体の約 84%にあたる約 2兆 1,000
億円と推計しており、2010 年までに約 2兆 5,800 億円規模に成長すると予測している。
以上の各業態における市場規模および OSS 市場規模の比較を表 2.4.3-1 に示す。
表 2.4.3-1 各業態の市場規模および OSS 市場規模の比較
2007 年
全体市場規模
OSS 活用市場規模
2007 年 2010 年
ソフトウェア業 13 兆 4,097 億円 約 6,900 億円 約7,800億円
情報処理・提供サービス業 5 兆 4,164 億円 約 1,700 億円 約2,000億円
インターネット
付随サービス業
約 2 兆 5,000 億円 約 2 兆 1,000 億円 約 2 兆 5,800 億円
2.4.4 OSS普及に向けての課題
IPA 実態調査によると、OSS 普及に向けて幾つかの課題があることが明確となっている。
(1)人材確保に関する課題
IPA 実態調査の表 2.4.4-1 に示す OSS 利用の人材確保に関する課題を見ると、「OSS に
総合的に精通した上級技術者」、「システム全体の中で OSS を利用すべき部分を見極める
人材」、「OSS 案件をマネジメントできる人材」の 3点について、回答企業の5割以上が課
題として挙げている。これらの課題を解消するには、市場に供給される新規人材および
企業に所属している既存の技術者に対する課題解消の取り組みが必要である。
また、この調査結果から傾向として読み取れるポイントは、「システム全体の中で OSS
を利用すべき部分を見極める」、「OSS 案件をマネジメントできる人材」、「顧客業務の細か
なニーズに合わせて OSS を改変できる」など、実業務を実施する上で必要となる人材、
という視点で課題が挙げられている点が特徴であり、既に OSS が IT 企業の案件に取り入
れられていることがうかがえる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
46
表 2.4.4-1 OSS 利用の人材確保面の課題 (N=693)
※IPA 実態調査 表 5-1「OSS 利用の人材確保面の課題」を引用
(2)人材育成に関する課題
IPA 実態調査の表 2.4.4-2 に示す人材育成に関する課題を見ると、「OSS 技術者が参照
する体系的な学習教材が少ないこと」を回答企業の5割以上が課題として挙げている。
これらの課題を解消するには、人材育成企業などがビジネスとして OSS 研修を充実化す
る、出版社によるガイドの作成などに期待する一方、活用を目指す企業がコミュニティ
に参加しガイドや教材作成に寄与することも望まれる。
表 2.4.4-2 OSS 利用の人材育成面の課題 (N=653)
出典:IPA 実態調査 表 5-5「OSS 利用の人材育成面の課題」
(3)サポートに関する課題
IPA 実態調査の表 2.4.4-3 に示すサポートに関する課題を見ると、「OSS の専門的な技
術サポートを緊急時に受けられないこと」を回答企業の 5 割以上が課題として挙げてお
り、「OSS のサポートを受けられる先が少ないこと」、「OSS 利用に参考となる資料が日本
語でないこと」が続いている。特に「OSS の専門的な技術サポートを緊急時に受けられな
いこと」が他の課題よりも飛び抜けて高く、IT 企業が大きな課題であると考えているこ
とがわかる。これらの課題を解消するには、他の IT 企業の技術サポートを活用する方法
が挙げられるが、これだけでは解決しないものも多く、根本的な解決をするには、OSS を
活用する各 IT企業が OSS に関する人材育成を積極的に実施する、活用する OSS コミュニ
会社数 構成比(%)OSS技術者が参照する体系的な学習教材が少ないこと 353 54.1OSS技術者のレベルを評価するノウハウがないこと 317 48.5OSS技術者を育成する研修機関が少ないこと 245 37.5OSS技術者のレベルを客観的に評価できる資格等がないこと 141 21.6OSS技術者を育成するIT系の教育機関(大学、専門学校等)が少ない 101 15.5その他 26 4.0合計 653 -
会社数 構成比(%)OSSに総合的に精通した上級技術者 499 72.0システム全体の中でOSSを利用すべき部分を見極める 373 53.8OSS案件をマネジメントできる人材 366 52.8複数のOSSに精通する人材 338 48.8顧客業務の細かなニーズに合わせてOSSを改変できる 267 38.5OSSそのものを開発する人材 166 24.0その他 16 2.3合計 693 -
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
47
ティに戦略的に参画するなどの対策が必要であるといえる。
表 2.4.4-3 OSS 利用のサポート面の課題 (N=703)
出典: IPA 実態調査 表 5-9「OSS 利用のサポート面の課題」
(4)ライセンスに関する課題
IPA 実態調査の表 2.4.4-4 に示すライセンスに関する課題を見ると、「ライセンスが複
雑で把握しにくいこと」、「ライセンスを把握している人材が社内にいないこと」が課題
として挙げられており、OSS に関するライセンス情報が把握しにくいことがわかる。
表 2.4.4-4 OSS 利用のライセンス面の課題 (N=702)
出典:IPA 実態調査 表 5-13「OSS 利用のライセンス面の課題」
(5)その他の課題
IPA 実態調査の表 2.4.4-5 に示すその他の課題としては、「OSS を利用したシステム構
築の経験が足りないこと」、「種類が多すぎるため、本当に利用価値のある OSS がわかり
にくいこと」、「OSS の個別技術・ソフトウェアの評価・成熟度が把握しにくいこと」の順
で挙げられている。
会社数 構成比(%)ライセンスが複雑で把握しにくいこと 288 41.0ライセンスを把握している人材が社内にいないこと 241 34.3ライセンスを解りやすく説明する資料がないこと 213 30.3ソフトウェアの著作権に関する訴訟リスクを感じること 187 26.6ライセンスしだいで自社が付加したソースコードを公開する必要があること 148 21.1ライセンスに関して社外に問い合わせできる先がないこと 148 21.1わからない 131 18.7その他 20 2.8合計 702 -
会社数 構成比(%)OSSの専門的な技術サポートを緊急時に受けられないこと 410 58.3OSSのサポートを受けられる先が少ないこと 283 40.3OSS利用に参考となる資料が日本語でないこと 258 36.7OSS利用に参考となる資料が少ないこと 189 26.9OSSのサポートが必要な部分だけ柔軟に受けられないこと 158 22.5OSSのコミュニティにどのように接触してよいかがわからないこと 117 16.6OSSのコミュニティが充実していない(活発でない)こと 72 10.2わからない 79 11.2その他 16 2.3合計 703 -
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
48
表 2.4.4-5 OSS 利用のその他の課題 (N=708)
出典:IPA 実態調査 表 5-13「OSS 利用のその他の課題」
以上のように、IPA 実態調査において、人材確保、人材育成、サポート、ライセンス認識
などの課題が明確になっているが、これら各 IT企業が課題と認識している事項は、IT 企業
が OSS をビジネスに活用する上での阻害要因であるといえる。
IPA 実態調査では、これらの阻害要因が解消された場合を想定した阻害要因解消後の市場
規模を推定している。この阻害要因解消後の OSS 市場規模を表 2.4.4-6 に示す。
表 2.4.4-6 阻害要因解消後の OSS 市場規模
OSS 活用市場規模
2007 年度 阻害要因解消後
ソフトウェア業 約 6,900 億円 約 1兆 8000 億円
情報処理・提供サービス業 約 1,700 億円 約 5,400 億円
インターネット付随サービス業 約 2 兆 1,000 億円 約 2兆 5900 億円
また、同じく、「OSS の性能向上による適用領域の拡大」、「OSS 活用ビジネスの成長」、「政
府を中心とするオープンな標準に基づく IT調達の拡大」などが実現した場合に到達する市
場規模の推定を「潜在的な OSS 活用市場の規模」として算出している。
2.4.5 市場規模の推定
(1)OSS を活用したソフトウェア業の市場規模
IPA 実態調査におけるソフトウェア業の市場規模試算結果について、図 2.4.5-1 に示
す。
会社数 構成比(%)OSSを利用したシステム構築の経験が足りないこと 338 47.7種類が多すぎるため、本当に利用価値のあるOSSがわかりにくいこと 249 35.2OSSの個別技術・ソフトウェアの評価・成熟度が把握しにくいこと 238 33.6顧客側にOSSに対する不安が存在すること 204 28.8OSSを利用したソリューション営業力が弱いこと 203 28.7OSSの認知度が一般的に低いこと 150 21.2現場と経営層のOSSに対する知識レベルや、意識レベルが異なること 130 18.4自社の得意とするOSSに合うアライアンス先を探しにくいこと 83 11.7わからない 85 12.0その他 17 2.4合計 708 -
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
49
図 2.4.5-1IPA 実態調査における市場規模試算結果概要(ソフトウェア業)※IPA 実態調査 図 7-4「2008 年度調査における市場規模試算結果概要」からデータを引用
2007 年の OSS 活用市場規模は 6,872 億円(全体市場の 5.4%)、潜在的な OSS 活用市場規模
は 2兆 8,221 億円(同 21.1%)と推察されており、2010 年には OSS 活用市場規模が 7,844 億
円(同 5.5%)(前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された場合の OSS 活用市場規模は、1
兆 8,358 億円(同 13.4%))、潜在的な OSS 活用市場規模は 4兆 9,720 億円(同 36.3%)まで成
長すると推察されている。
また、同様の考え方に基づいて算出されている 2017 年までの市場規模試算結果を図
2.4.5-2 に示す。
6,241億円(4.4%)
14兆1,326億円(100%)
6,872億円(5.4%)
2兆8,221億円(21.1%)
13兆3,078億円(100%)
7,844億円(5.5%)
1兆8,358億円(13.4%)
4兆9,720億円(36.3%)
2010年
13兆7,122億円(100%)
2007年
2005年
OSS活用市場規模 潜在的OSS活用市場規模
阻害要因解消後のOSS活用市場規模
全体市場規模
0 5 10 15
OSS活用市場は年平均3.3%で成長OSS活用市場は年平均3.3%で成長
OSS活用市場は年平均4.5%で成長OSS活用市場は年平均4.5%で成長
(兆)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
50
0
25,000
50,000
75,000
100,000
125,000
150,000
2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年
OSS活用市場 阻害要因解消後の市場
潜在的な市場 全体市場(百万円)
【現在(2007年)】全体市場 13兆3708億円(100 %)
潜在的な市場 2兆8221億円(21.1%)OSS活用市場 6872億円( 5.4 %)
【現在(2007年)】全体市場 13兆3708億円(100 %)
潜在的な市場 2兆8221億円(21.1%)OSS活用市場 6872億円( 5.4 %)
【3年後(2010年)】全体市場 13兆7122億円(100%)
潜在的な市場 4兆9720億円(36.3%)阻害要因解消後の市場 1兆8358億円(13.4%)
OSS活用市場 7844億円(5.5%)
【3年後(2010年)】全体市場 13兆7122億円(100%)
潜在的な市場 4兆9720億円(36.3%)阻害要因解消後の市場 1兆8358億円(13.4%)
OSS活用市場 7844億円(5.5%)
【10年後(2017年)】全体市場 14兆5431億円(100% )
潜在的な市場 6兆2573億円(43.0%)阻害要因解消後の市場 5兆2463億円(36.1%)
OSS活用市場 1兆703億円(7.4% )
【10年後(2017年)】全体市場 14兆5431億円(100% )
潜在的な市場 6兆2573億円(43.0%)阻害要因解消後の市場 5兆2463億円(36.1%)
OSS活用市場 1兆703億円(7.4% )
全体市場は0.8%で成長(特サビの直近3年の平均より算出)
全体市場は0.8%で成長(特サビの直近3年の平均より算出)
潜在的な市場は10年間平均年8.3%で成長
潜在的な市場は10年間平均年8.3%で成長
阻害要因解消後の市場は10年間平均年22.5%で成長(参考:2007年度調査は22.7%)
阻害要因解消後の市場は10年間平均年22.5%で成長(参考:2007年度調査は22.7%)
OSS活用市場は10年間、年平均4.5%で成長(参考:2007年度調査は6.9%)
OSS活用市場は10年間、年平均4.5%で成長(参考:2007年度調査は6.9%)
図 2.4.5-2 2005~2017 年までの市場規模試算結果
出典:IPA 実態調査 図 7-7「2017 年までの市場規模の変化」
この調査結果によると、OSS 活用市場は、2007 年時点で 6,872 億円(同 5.4%)以降、年平
均 4.5%の割合で成長し、2017 年までに 1兆 703 億円(同 7.4%)にまで拡大すると推定されて
いる。前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された後の OSS 活用市場は、3 年後の 2010
年に 1 兆 8,358 億円(同 13.4%)で順調に推移するが、以降急速に成長し、2017 年までに 5
兆 2,463 億円にまで拡大すると推察されている。潜在的な OSS 活用市場については、前述
のとおり 2007 年時点で 2兆 8,221 億円(同 22.1%)となっており、以降、2010 年まで急拡大
し、2017 年までに 6兆 2,573 億円(同 43.0%)にまで拡大すると推察されている。
なお、IPA 実態調査では、2007 年のソフトウェア業における OSS 活用市場について、「業
務別市場規模」、「IT ソリューション別市場規模」、「ビジネスモデル類型別市場規模」の 3
つの観点での市場規模も算出している。ソフトウェア業における業務別市場規模を表
2.4.5-1 に、IT ソリューション別市場規模を表 2.4.5-2 に、ビジネスモデル類型別市場規
模を表 2.4.5-3 にそれぞれ示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
51
表 2.4.5-1 業務別市場規模の算出結果
出典:IPA 実態調査 表 7-4「業務別市場規模の算出結果」
表 2.4.5-2 IT ソリューション別市場規模の算出結果
・ビジネスモデル類型別市場規模>
2007 年度調査において類型化された、システム開発/提供系のビジネスモデル類型別の
OSS 活用市場規模を算出した([表 2-1]参照)。
[表 2-1]ビジネスモデル類型別市場規模の算出結果
出典:IPA 実態調査 表 7-5「IT ソリューション別市場規模の算出結果」
表 2.4.5-3 ビジネスモデル類型別市場規模の算出結果
出典: IPA 実態調査 表 7-6「ビジネスモデル類型別市場規模の算出結果」
(2)OSS を活用した情報処理・提供サービス業の市場規模
IPA 実態調査における情報処理・提供サービス業の市場規模試算結果について、図 2.4.5-3
に示す。
業務別市場規模 (参考)2007年度調査結果
投入した工数割合(%) 業務別規模(億円) 投入した工数割合(%) 業務別規模(億円)
開発業務 83.8 5,756 81.3 2,802
OS関連 3.3 228 3.6 124
ミドルウェア関連 6.5 446 6.3 217
パッケージ型ソフトウェア関連 13.1 904 16.0 551
アプリケーション開発関連 60.8 4,178 55.4 1,909
運用・保守業務 11.8 808 12.7 438
その他 4.5 308 6.0 207
合計 100.0 6,872 100.0 3,447
ITインフラソリューション別市場規模 (参考)2007年度調査結果
ITソリューション別の売上高構成比(%)
業務別規模(億円)ITソリューション別の売上高構成比(%)
業務別規模(億円)
インフラソリューション 18.5 1,268 14.2 489
基幹系システムソリューション 40.2 2,761 41.6 1,433
管理系システムソリューション 7.1 485 7.3 252
情報系システムソリューション 29.7 2,043 18.0 620
運用・保守ソリューション 2.3 161 - -
その他 2.2 155 18.8 648
合計 100.0 6,872 100.0 3,443
ビジネスモデル類型別市場規模
受託システム開発型(OSS顧客提供) 65 70.8 4,863
OSS内包パッケージソフト販売型 19 14.7 1,007
本業ビジネス補完型 30 14.6 1,003
OSSスタック型 0 0.0 0
コマーシャルOSS型 0 0.0 0
合計 114 100.0 6,872
※四捨五入処理により内訳と合計は一致しない
有効回答数(社) OSS売上高構成比率(%)ビジネスモデル別市場規模(億円)
※
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
52
図 2.4.5-3IPA 実態調査における市場規模試算結果概要(情報処理・提供サービス業)※IPA 実態調査 図 7-4「2008 年度調査における市場規模試算結果概要(情報処理・提供サービス業)」からデータを引用
2007 年の OSS 活用市場規模は 1,724 億円(全体市場の 3.2%)、潜在的な OSS 活用市場規模
は 7,915 億円(同 14.6%)と推察されており、2010 年には OSS 活用市場規模が 1,987 億円(同
3.4%)(前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された場合の OSS 活用市場規模は、5,367 億
円(同 9.1%))、潜在的な OSS 活用市場規模は 2兆 413 億円(同 34.6%)まで成長すると推察さ
れている。また、同様の考え方に基づいて算出されている 2017 年までの市場規模試算結果
を図 2.4.5-4 に示す。
図 2.4.5-4 2005~2017 年までの市場規模試算結果(情報処理・提供サービス業)
出典:IPA 実態調査 図 7-11「2017 年までの市場規模の変化」、
1,607億円(3.2%)
5兆653億円(100%)
1, 724億円(3.2%)
7,915億円(14.6%)
5兆4,211億円(100%)
1,987億円(3.4%)
5,367億円(9.1%)
2兆413億円(34.6%)
2010年
5兆8,971億円(100%)
2007年
2005年
OSS活用市場規模 潜在的OSS活用市場規模
阻害要因解消後のOSS活用市場規模
全体市場規模
0 1 7
OSS活用市場は年平均2.4%で成長OSS活用市場は年平均2.4%で成長
OSS活用市場は年平均4.9%で成長OSS活用市場は年平均4.9%で成長
(兆)2 3 4 5 6
0
20,000
40,000
60,000
80,000
2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年
OSS活用市場 阻害要因解消後の市場
潜在的な市場 全体市場(百万円)
【現在(2007年)】全体市場 5兆4211億円(100%)
潜在的な市場 7915億円(14.6%)OSS活用市場 1724億円( 3.2 %)
【現在(2007年)】全体市場 5兆4211億円(100%)
潜在的な市場 7915億円(14.6%)OSS活用市場 1724億円( 3.2 %)
全体市場は2.8%で成長(特サビの2007年直近3年の平均より算出)
全体市場は2.8%で成長(特サビの2007年直近3年の平均より算出)
潜在的な市場は10年間平均年17.0%で成長
潜在的な市場は10年間平均年17.0%で成長
阻害要因解消後の市場は10年間平均年34.2%で成長
阻害要因解消後の市場は10年間平均年34.2%で成長
OSS活用市場は10年間、年平均年4.9%で成長
OSS活用市場は10年間、年平均年4.9%で成長
【3年後(2010年)】全体市場 5兆8971億円(100%)
潜在的な市場 2兆413億円(34.6%)阻害要因解消後の市場 5367億円(9.1%)
OSS活用市場 1987億円(3.4%)
【3年後(2010年)】全体市場 5兆8971億円(100%)
潜在的な市場 2兆413億円(34.6%)阻害要因解消後の市場 5367億円(9.1%)
OSS活用市場 1987億円(3.4%)
【10年後(2017年)】全体市場 7兆1766億円(100%)
潜在的な市場 3兆7889億円(52.8%)阻害要因解消後の市場 3兆2767億円(45.7%)
OSS活用市場 2768億円(3.9% )
【10年後(2017年)】全体市場 7兆1766億円(100%)
潜在的な市場 3兆7889億円(52.8%)阻害要因解消後の市場 3兆2767億円(45.7%)
OSS活用市場 2768億円(3.9% )
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
53
この調査結果によると、OSS 活用市場は、2007 年時点で 1,724 億円(同 3.2%)以降、年平
均 4.0%の割合で成長し、2017 年までに 2,768 億円(同 3.9%)に成長すると推定されている。
前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された後の OSS 活用市場は、3 年後の 2010 年に
5,367 億円(同 9.1%)で順調に推移するが、以降急速に成長し、2017 年までに 3 兆 2,767 億
円にまで拡大すると推察されている。潜在的な OSS 活用市場については、前述のとおり 2007
年時点で 7,915 億円(同 14.6%)となっており、以降、2010 年まで急拡大し、2017 年までに
3兆 7,889 億円(同 52.8%)にまで拡大すると推察されている。
情報処理・提供サービス業は、METI 実態調査では IT システムの構築や ITシステムを活
用した各種サービスの提供業務を内包する業態であり、TCO 削減を求める顧客への対応とし
て OSS に対応、また、これに付随したサービスの提供が進んでいる。これらは、顧客によ
るオープン・スタンダードに準拠した調達の意識向上など、幾つかの要因を背景として、
今後益々活用が促進する市場であると推察する。
なお、IPA 実態調査では、2007 年の情報処理・提供サービス業における OSS 活用市場に
ついて、「業務別市場規模」、「ITソリューション別市場規模」、「ビジネスモデル類型別市場
規模」の 3つの観点での市場規模も算出している。情報処理・提供サービス業の業務別市
場規模を表 2.4.5-4 に、IT ソリューション別市場規模を表 2.4.5-5 に、ビジネスモデル類
型別市場規模を表 2.4.5-6 にそれぞれ示す。
表 2.4.5-4 業務別市場規模の算出結果
出典:IPA 実態調査 表 7-12「業務別市場規模の算出結果」、
表 2.4.5-5 IT ソリューション別市場規模の算出結果
出典:IPA 実態調査 表 7-13「IT ソリューション別市場規模の算出結果」、
業務別市場規模
投入した工数割合(%) 業務別規模(億円)
開発業務 55.6 958
OS関連 4.4 76
ミドルウェア関連 6.4 110
パッケージ型ソフトウェア関連 11.8 203
アプリケーション開発関連 33.0 570
運用・保守業務 36.2 625
その他 8.2 141
合計 100.0 1,724
ITインフラソリューション別市場規模
ITソリューション別の売上高構成比(%)
業務別規模(億円)
インフラソリューション 3.8 65
基幹系システムソリューション 14.7 254
管理系システムソリューション 2.1 36
情報系システムソリューション 10.2 175
運用・保守ソリューション 69.2 1,194
その他 0.0 0
合計 100.0 1,724
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
54
表 2.4.5-6 ビジネスモデル類型別市場規模の算出結果
出典:IPA 実態調査 表 7-14「ビジネスモデル類型別市場規模の算出結果」、
(3)OSS を活用したインターネット付随サービス業の市場規模
IPA 実態調査における情報処理・提供サービス業の市場規模試算結果について、図
2.4.5-5 に示す。
図 2.4.6-5IPA 実態調査における市場規模試算結果概要(インターネット付随サービス業)※IPA 実態調査 図 7-4「2008 年度調査における市場規模試算結果概要(インターネット付随サービス業)」からデータを
引用
2007 年の OSS 活用市場規模は 2兆 1,103 億円(全体市場の 84.5%)、潜在的な OSS 活用市
場規模は 2兆 4,440 億円(同 98.0%)と推察されており、2010 年には OSS 活用市場規模が 2
兆 5,812 億円(同 84.5%)(前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された場合の OSS 活用市
場規模は、2兆5,918億円(同84.9%))、潜在的なOSS活用市場規模は2兆9,893億円(同98.0%)
まで成長すると推察されている。
また、同様の考え方に基づいて算出されている 2017 年までの市場規模試算結果を図
2.4.5-6 に示す。
1兆8,229億円(84.5%)
2兆1,615億円(100%)
2兆1,103億円(84.5%)
2兆4,440億円(98.0%)
2兆4,961億円(100%)
2兆5,812億円(84.5%)
2兆5,918億円(84.9%)
2兆9,893億円(98.0%)
2010年
3兆531億円(100%)
2007年
2005年
OSS活用市場規模 潜在的OSS活用市場規模
阻害要因解消後のOSS活用市場規模
全体市場規模
0 2
OSS活用市場は年平均6.9%で成長OSS活用市場は年平均6.9%で成長
(兆)1
OSS活用市場は年平均7.1%で成長OSS活用市場は年平均7.1%で成長
3
ビジネスモデル類型別市場規模
有効回答数(社) OSS売上高構成比率(%) ビジネスモデル別市場規模(億円)
受託システム開発型(OSS顧客提供) 11 57.2 985
OSS内包パッケージソフト販売型 2 0.8 15
本業ビジネス補完型 4 5.9 101
OSSスタック型 2 3.3 56
コマーシャルOSS型 0 0.0 0
データベースサービス型 2 32.9 567
合計 21 100.0 1,724
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
55
15,000
25,000
35,000
45,000
55,000
2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年
OSS活用市場 阻害要因解決後の市場
潜在的な市場 全体市場(百万円)
【現在(2007年)】全体市場 2兆4961億円 (100%)
潜在的な市場 2兆4440億円(98.0%)OSS活用市場 2兆1103億円(84.5%)
【現在(2007年)】全体市場 2兆4961億円 (100%)
潜在的な市場 2兆4440億円(98.0%)OSS活用市場 2兆1103億円(84.5%)
全体市場は6.9%で成長全体市場は6.9%で成長
【3年後(2010年)】全体市場 3兆531億円 (100%)
潜在的な市場 2兆9893億円(98.0%)阻害要因解消後の市場 2兆5918億円(84.9%)
OSS活用市場 2兆5812億円(84.5%)
【3年後(2010年)】全体市場 3兆531億円 (100%)
潜在的な市場 2兆9893億円(98.0%)阻害要因解消後の市場 2兆5918億円(84.9%)
OSS活用市場 2兆5812億円(84.5%)
【10年後(2017年)】全体市場 4兆8848億円 (100%)
潜在的な市場 4兆7828億円(97.9%)阻害要因解消後の市場 4兆1467億円(84.9%)
OSS活用市場 4兆1298億円(84.5%)
【10年後(2017年)】全体市場 4兆8848億円 (100%)
潜在的な市場 4兆7828億円(97.9%)阻害要因解消後の市場 4兆1467億円(84.9%)
OSS活用市場 4兆1298億円(84.5%)
OSS市場は10年間、年平均6.9%で成長
OSS市場は10年間、年平均6.9%で成長
潜在的な市場は10年間平均年6.9%で成長
潜在的な市場は10年間平均年6.9%で成長
阻害要因解消後の市場は、10年間平均年7.0%で成長
阻害要因解消後の市場は、10年間平均年7.0%で成長
図 2.4.5-6 2005~2017 年までの市場規模試算結果(インターネット付随サービス業)
出典:IPA 実態調査 図 7-15「2017 年までの市場規模の変化」
この調査結果によると、OSS 活用市場は、2007 年時点で 2 兆 1,103 億円(同 84.5%)以降、
年平均 6.9%の割合で成長し、2017 年までに 4 兆 1,298 億円(同 84.5%)にまで拡大すると推
定されている。前述の(1)~(5)に挙げた阻害要因が解消された後の OSS 活用市場は、3年後
の 2010 年に 2 兆 5,918 億円(同 84.9%)で順調に推移し、2017 年までに 4 兆 1,467 億円(同
84.9%)にまで拡大すると推察されている。潜在的な OSS 活用市場については、前述のとお
り 2007 年時点で 2 兆 4,440 億円(同 98.0%)となっており、以降、2017 年までに 4 兆 7,828
億円(同 97.9%)にまで拡大すると推察されている。
なお、インターネット付随サービス業市場では、OSS 活用の割合が他業態と比較し、非常
に高い。これは、IPA 実態調査でも触れているが、「インターネット付随サービス業市場で
は、OSS に関する普及阻害要因がほとんどない状態であることを示しているのではないか」
と推察することができ、これは、IT サービスのプラットフォームなどで LAMP ソリューショ
ンなどに代表される OSS が積極的に活用されていることが大きな要因のひとつではないか
と推察する。
(4)その他 OSS 関連ビジネスの市場規模
IPA 実態調査におけるその他の OSS 関連ビジネスの市場規模(教育、出版事業)試算結果に
ついて、表 2.4.5-7 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
56
表 2.4.5-7 OSS の間接市場の算出結果
間接市場 (参考)昨年度調査結果
OSS市場規模に対する割合(%)
間接需要規模(億円)OSS市場規模に対する割合(%)
間接需要規模(億円)
教育事業 0.81 69.6 1.0 34
出版事業 0.15 12.9 0.2 6.9
出典:IPA 実態調査 表 7-20「OSS の間接市場の算出結果」
(5)まとめ
IPA 実態調査における「ソフトウェア業」、「情報処理・提供サービス業」、「インターネッ
ト付随サービス業」、および「その他 OSS 関連ビジネス」の市場規模算出結果を集計し、IT
市場全体としての OSS 活用市場規模、潜在的 OSS 市場規模、阻害要因解消後の OSS 活用市
場規模を算定した。
算定結果を図 2.4.5-7 に示す。
図 2.4.5-7 IT 市場における OSS 活用市場規模算定結果
2007 年の OSS 活用市場規模は 2兆 9,782 億円(全体市場の 14.0%)、潜在的な OSS 活用市
場規模は 6兆 1,176 億円(同 28.8%)と推察でき、2010 年には OSS 活用市場規模が 3兆 5,726
億円(同 15.8%)(阻害要因が解消された場合の OSS 活用市場規模は、4兆 9,643 億円(同
22.0%))、潜在的な OSS 活用市場規模は 10 兆 26 億円(同 44.1%)まで成長するものと推察さ
れる。
以上の算定結果から、国内の IT市場において OSS 活用市場は着実に成長を遂げるものと
予測できるとともに、同市場に根ざす IT 企業にとって、欠かすことのできないビジネスの
材料として着実に定着化していくことがうかがえる。
2兆9,782億円(14.0%)
6兆1,176億円(28.8%)
21兆2,250億円(100%)
3兆5,726億円(15.8%)
4兆9,643億円(22.0%)
10兆26億円(44.1%)
2010年
22兆6,624億円(100%)
2007年
2005年
OSS活用市場規模 潜在的OSS活用市場規模
阻害要因解消後のOSS活用市場規模
全体市場規模
0 10 (兆)20
2兆6,077億円(12.2%)
21兆3,594億円(100%)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
57
第3章 商材化の可能性を有する OSS の予備調査
本章では、商材化の可能性を有する OSS の予備調査の結果を示す。
3.1 調査指針
本調査では、商材開発の材料となる OSS を抽出することを念頭に、次の調査指針に従い、
対象となる OSS を抽出するための予備調査を実施する。
なお、今後 IT企業が OSS をベースとして商材開発を行う上では、定期的に市場のトレン
ドを調査し、これを踏まえて材料となる OSS を抽出するための有効な方法を持つことが必
要不可欠であることから、この調査指針は、その有効な方法の一つとなるよう考慮し、調
査手順を以下の通り定める。
①市場におけるソフトウェア分類を調査し、この調査結果を材料として本調査で活用す
るソフトウェア分類を検討する。
②①で抽出したソフトウェア分類の中で市場が拡大している分類を対象として、それぞ
れ数種を抽出する。「(独)情報処理推進機構 2007 年度オープンソースソフトウェア活
用基盤整備事業 OSS オフィスアプリケーションカタログ作成調査報告書」において、
ソフトウェア調査の主要情報源としている下記の 3サイトを対象とする。
主要情報源は、以下の通り。
freshmeat.net
UNIX およびクロスプラットフォームで動作するソフトウェアで、OSS として公開
されているソフトウェアを中心に約 40,000 のソフトウェアプロジェクトの情報が
登録されている。なお、情報は英語で記載されている。
sourceforge.jp
OSS の開発者に対して、cvs/svn リポジトリ、Wiki システム、メーリングリストな
どのリソースを無料で提供している。日本語のインタフェースで利用できる。約
2,000 のプロジェクトの情報が登録されている。
sourceforge.net
OSS の開発者に対して、cvs/svn リポジトリ、Wiki システム、メーリングリストな
どのリソースを無料で提供している。OSS の情報源としては世界最大で約 170,000
のプロジェクト情報が登録されている。なお、情報は英語で記載されている。
調査対象を評価する方法として、本調査の趣旨に沿う評価基準を作成する
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
58
③作成した評価基準を用いて、②で絞り込んだ分類に属する OSS を前述の情報源を対象
として調査・評価し、分類毎に上位 5~10 程度の OSS をサンプルとして抽出する。
図 3.1-1 商材化の可能性を有する OSS の抽出の流れ
3.2 商材化の可能性を持つカテゴリ
商材化の可能性を持つ OSS のソフトウェア分類案の選定は、調査企業がまとめた IT産業
に関するレポートやインターネット上で公開されている各種報告書で利用されている分類
を基に検討する。
(1)ソフトウェア分類を有する情報先一覧
インターネット上で公開されている、ソフトウェア分類を有する情報源の収集結果を
表 3.2-1 に示す。
表 3.2-1 ソフトウェア分類を有する情報源一覧
ソフトウェア分類 情報源
Wikipedia Software カテゴリ en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_categories
Gartner www.gartner.com/DisplayDocument?id=491788&ref=g_sITelink
IDC IDC ソフトウェア市場定義 2008 年版と国内ソフトウェア市場 2007 年~
2012 年の予測
2020Software www.2020software.com/software/default.asp
Soft3K www.soft3k.com/cat-Business.htm
Gear Download www.geardownload.com/category.html
評価
基準
評価
基準
評価
基準
評価
基準
サイトのO
SS
情報
評価
基準
ソフトウェア分類
分類別市場
調査による
絞込み
絞り込んだ分類絞り込んだ OSS
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
59
3.2.1 ソフトウェア分類の考察
収集した情報を充実度、整理度合い、網羅性、本調査に対する適合性の 4 つの観点で考
察し、それぞれの項目について、3:よい、2:どちらでもない、2:悪い、の 3段階評価で
判定する。
収集した情報の考察結果を表 3.2.1-1 に示す。
表 3.2-1 ソフトウェア分類の考察結果
ソフトウェア分類 充実度 整理度 網羅性 適合性 合計 総評
Wikipedia
Software カテゴリ
3 3 3 1 10
ソフトウェア分類および細分
化が最も進んでいるが、特定企
業の製品ラインナップにまで
分類が及んでおり、本調査のソ
フトウェア分類としては不適
合と判断する。
Gartner
3 2 3 3 11
大分類34、中分類58となっ
ており、ソフトウェア分類とし
ては比較的充実しており、かつ
網羅的な内容となっているが、
中分類までしか定義されてい
ない部分、小分類まで定義され
ている部分とまちまちになっ
ている。
IDC
3 3 3 3 12
大分類3、中分類19、小分類
81となっており、全てのカテ
ゴリで階層的に整理されて、か
つ網羅的な内容となっている。
2020Software1 1 1 1 4
ソフトウェア分類が少なく(5分
類)、大雑把な分類になってい
る。
Soft3K2 2 1 1 6
ソフトウェア分類が少なく(25分
類)、大雑把な分類になってい
る。
Gear Download
2 3 2 1 8
大分類12、中分類130とな
っているが、デスクトップのソ
フトウェア分類の割合が多く、
偏りがある。
【凡例】3:よい 2:どちらでもない 1:悪い
以上の評価結果より、IDC のソフトウェア分類を本調査のベースとすることとする。
3.2.2 適用するソフトウェア分類
本調査のベースとする IDC のソフトウェア分類を表 3.2.2-1 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
60
表 3.2.2-1 IDC のソフトウェア分類
大分類 中分類 小分類
アプリケーション
ソフトウェア
コラボレーティブアプリケ
ーション
統合コラボレーティブ環境
メッセージングアプリケーション
チームコラボレーティブアプリケーション
会議アプリケーション
その他コラボレーティブアプリケーション
コンテンツアプリケーショ
ン
コンテンツ管理アプリケーション
オーサリング/パブリッシング
アプリケーション
検索/ディスカバリーソフトウェア
エンタープライズポータル
ERM アプリケーション ファイナンシャル/会計アプリケーション
HCM アプリケーション
給与計算ソフトウェア
調達アプリケーション
注文管理ソフトウェア
ファイナンシャルパフォーマンス/戦略管理
ソフトウェア
プロジェクト/ポートフォリオ管理ソフトウ
ェア
エンタープライズ資産管理ソフトウェア
SCM アプリケーション ロジスティクスアプリケーション
生産管理(PP)アプリケーション
在庫管理アプリケーション
オペレーション/製造管理
アプリケーション
サービスオペレーション管理
アプリケーション
製造アプリケーション
その他バックオフィスアプリケーション
(e-Learning など)
エンジニアリングアプリケ
ーション
メカニカル CAD
メカニカル CAE
メカニカル CAM
製品情報管理(PIM)
その他エンジニアリングアプリケーション
CRM アプリケーション セールス
マーケティング
カスタマーサービスアプリケーション
コンタクトセンター
アプリケーション
開発/デプロイメ
ントソフトウェア
情報/データ管理ソフトウ
ェア
リレーショナル DBMS
ノンリレーショナル DBMS
データベース開発/管理ツール
データ統合/アクセスソフトウェア
アプリケーション開発ソフ
トウェア
統合開発環境
3GL
ソフトウェア構築コンポーネント
ビジネスルール管理システムモデル駆動型開
発ソフトウェア
Web サイト設計/開発ツール
品質ライフサイクルツール 自動ソフトウェア品質(ASQ)ツール
ソフトウェア構成管理(SCM)
アプリケーションサーバミ
ドルウェア
アプリケーションサーバソフトウェアプラッ
トフォーム
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
61
トランザクション処理モニター
その他アプリケーションサーバミドルウェア
インテグレーション/プロ
セスオートメーションミド
ルウェア
BtoB ミドルウェア
エンタープライズサービスバス/
コネクティビティミドルウェア
イベント駆動型ミドルウェア
プロセスオートメーションミドルウェア
その他インテグレーション/
プロセスオートメーションミドルウェア
その他開発ツール その他プログラマー向け開発ツール/ユーテ
ィリティ
データアクセス/解析/デ
リバリーソフトウェア
エンドユーザクエリー/レポート/
解析ツール
先進解析ソフトウェア
空間情報管理
システムインフラ
ストラクチャ
ソフトウェア
システム/ネットワーク管
理ソフトウェア
イベントオートメーションツール
ジョブスケジューリングツール
出力管理ツール
パフォーマンス管理ソフトウェア
変更/コンフィギュレーション管理
ソフトウェア
問題管理アプリケーション
ネットワーク管理ソフトウェア
セキュリティソフトウェア アイデンティティ/アクセス管理
ソフトウェア
セキュアコンテンツ/脅威管理ソフトウェア
セキュリティ/脆弱性管理ソフトウェア
その他セキュリティソフトウェア
ストレージソフトウェア データ保護/リカバリーソフトウェア
ストレージレプリケーションソフトウェア
アーカイビングソフトウェア
ファイルシステムソフトウェア
ストレージインフラストラクチャソフトウェ
ア
ストレージデバイス管理ソフトウェア
その他ストレージソフトウェア
システムソフトウェア OS とサブシステムソフトウェア
アベイラビリティ/クラスタリング
ソフトウェア
バーチャルユーザインタフェース
ソフトウェア
バーチャルマシンソフトウェア
その他システムソフトウェア
出典:IDC2008, ソフトウェア市場定義 2008 年版と国内ソフトウェア市場 2008 年~2012 年の予測
3.2.3 探索対象分類の抽出
前項のソフトウェア分類を基に商材のベースとなる OSS の探索をするソフトウェア分類
を抽出する。
なお、抽出する分類は、IDC の今後の中長期予測において、市場伸び率が 5%を超える分
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
62
類を抽出することとする。
(1)国内アプリケーションソフトウェア領域における探索分類の抽出
国内アプリケーションソフトウェア市場概況と探索対象分類の抽出結果を以下に示す。
(A)国内アプリケーションソフトウェア市場概況
IDC「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」より、
国内アプリケーションソフトウェアの市場概況を抜粋する。
また、IDCによる「国内アプリケーションソフトウェア市場予測」を図3.2.3-1に示
す。
図3.2.3-1 国内アプリケーションソフトウェア市場予測
出展:IDC 2008, 「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」
国内アプリケーションソフトウェア市場は、エンタープライズアプリケーションに
回復が見られるものの、2006年から2007年にかけてのJ-Sox法対応が一段落したこ
と、サブプライムローン問題など2008年第2四半期頃より経済の先行き不透明感が
増したことなどを背景に、カスタムソフトウェアからパッケージアプリケーション
への移行は今後も継続する一方で、投資規模や移行タイミングには慎重な姿勢が見
られる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
63
(B)探索対象分類の抽出
国内アプリケーションソフトウェア領域における、CAGR(年平均成長率)を基に
した探索対象分類の抽出結果を表3.2.3-1に示す。
表3.2.3-1 アプリケーションソフトウェア領域での探索対象分類抽出結果
分類CAGR5%超
の分類評価
コンシューマーアプリケーション 3.4%
コラボレーティブアプリケーション 6.1% ○
コンテンツアプリケーション 7.8% ○
エンタープライズリソース管理(ERM)アプリケーション 4.6%
SCMアプリケーション 4.3%
オペレーション/製造管理アプリケーション 5.0% ○
エンジニアリングアプリケーション 6.9% ○
CRMアプリケーション 5.3% ○
※太字:抽出したソフトウェア分類
(2)国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア領域における探索対象分類
の抽出
国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア市場概況と探索対象分類の
抽出結果を以下に示す。
(A)国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア市場概況
IDC「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」より、
国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェアの市場概況を抜粋する。
全般的にメインフレーム市場縮小の影響によって、アプリケーション開発/デプロ
イメントソフトウェア市場の成長率は高くない。2007年における情報/データ管理
ソフトウェア市場は強いデータベース需要から堅調な成長を示したが、今後は製品
のコモディティ化による価格低下を予測しており、高い成長率を維持することは難
しい。
アプリケーション設計/構築ツール市場では、Windows系、COBOL系を除き、オー
プンソース環境が主流になりつつあり、成長率は高くないと予測する。
アプリケーションサーバミドルウェア市場では、UNIXシステムからWindows、Linux
システムに行こうすると予測し、全体的には堅実な成長を維持するものと予測す
る。
インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウェア市場は新しい製品
開発が活発に進められている市場であるが、市場の立ち上がりに遅れ感があり、成
長の抑制要因となっている。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
64
また、IDCによる「国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア市場予
測」を図3.2.3-2に示す。
図3.2.3-2 国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア市場予測
出展:IDC 2008, 「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」
(B)探索対象分類の抽出
国内アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア領域における、CAGRを基
にした探索対象分類の抽出結果を表3.2.3-2に示す。
表3.2.3-2 アプリケーション開発/デプロイメントソフトウェア領域での探索対象分類抽出結果
分類CAGR5%超
の分類評価
情報/データ管理ソフトウェア 2.4%
アプリケーション設計/構築ツール -0.2%
品質ライフサイクルツール 8.3% ○
アプリケーションデプロイメントソフトウェア 1.9%
インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウェア 5.4% ○
その他開発ツール -6.4%
データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア 5.4% ○
※太字:抽出したソフトウェア分類
(3)国内システムインフラストラクチャソフトウェアにおける探索対象分類の抽出
国内システムインフラストラクチャソフトウェア市場概況と探索対象分類の抽出結
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
65
果を以下に示す。
(A)国内システムインフラストラクチャソフトウェア市場概況
IDC「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」より、
国内システムインフラストラクチャソフトウェアの市場概況を抜粋する。
また、IDCによる「国内システムインフラストラクチャソフトウェア市場予測」を図
3.2.3-3に示す。
図3.2.3-3 国内システムインフラストラクチャソフトウェア市場予測
出展:IDC 2008, 「国内ソフトウェア市場2007年の実績と2008~2012年の予測アップデート」
全般的に比較的高めの成長を見込んでいる。2008 年の国内システム/ネットワー
ク管理ソフトウェア市場は、メインフレームからの代替による需要の抑制要因はあ
るものの、前年比 8.4%増を見込んでおり、2012 年には 3,506 億円規模にまで成長
するとみている。増大するデータと複雑化するシステム、信頼性と可用性を両立し
た運用など、システム管理者に対する付加は高まる一方であり、運用管理オートメ
ーション化に対する投資は今後も継続していくとみている。
2008 年国内セキュリティソフトウェア市場は 8.3%の成長を見込んでおり、2012 年
には 2,319 億円規模にまで成長すると見込んでいる。アイデンティティアクセス管
理、メッセージセキュリティ管理、Web セキュリティ管理製品といった製品群が
市場を牽引すると見ている。2008 年ストレージソフトウェア市場は、前年比 10.0%
増を見込んでおり、2012 年には 121 億円規模にまで成長すると予測する。仮想化
テクノロジーの発展や省電力に対する要求など、ストレージソフトウェアのビジネ
スチャンスはいっそうの拡大が見込まれている。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
66
(B)探索対象分類の抽出
国内システムインフラストラクチャソフトウェア領域における、CAGRを基にした探
索対象分類の抽出結果を表3.2.3-3に示す。
表3.2.3-3 システムインフラストラクチャソフトウェア領域での探索対象分類抽出結果
分類CAGR5%超
の分類評価
システム/ネットワーク管理ソフトウェア 6.5% ○
セキュリティソフトウェア 5.8% ○
ストレージソフトウェア 8.7% ○
システムソフトウェア 5.4% ○
※太字:抽出したソフトウェア分類
(4)抽出した探索対象分類
探索対象ソフトウェア分類を抽出した結果を表3.2.3-4に示す。
表3.2.3-4 抽出した探索対象ソフトウェア分類
大分類 中分類
アプリケーションソフトウェア コラボレーティブアプリケーション
コンテンツアプリケーション
オペレーション/製造管理アプリケーション
エンジニアリングアプリケーション
CRMアプリケーション
アプリケーション開発/
デプロイメント
品質ライフサイクルツール
インテグレーション/
プロセスオートメーションミドルウェア
データアクセス/解析/
デリバリーソフトウェア
システムインフラストラクチャ システム/ネットワーク管理ソフトウェア
セキュリティソフトウェア
ストレージソフトウェア
システムソフトウェア
探索対象ソフトウェア分類の詳細を表3.2.3-5に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
67
表 3.2.3-5 探索対象ソフトウェア分類の詳細
大分類 中分類 小分類
アプリケーション
ソフトウェア
コラボレーティブアプリケ
ーション統合コラボレーティブ環境
メッセージングアプリケーション
チームコラボレーティブアプリケーション
会議アプリケーション
その他コラボレーティブアプリケーション
コンテンツアプリケーショ
ンコンテンツ管理アプリケーション
オーサリング/パブリッシング
アプリケーション
検索/ディスカバリーソフトウェア
エンタープライズポータル
オペレーション/製造管理
アプリケーション
サービスオペレーション管理
アプリケーション
製造アプリケーション
その他バックオフィスアプリケーション
(e-learning など)
エンジニアリングアプリケ
ーションメカニカル CAD
メカニカル CAE
メカニカル CAM
製品情報管理(PIM)
その他エンジニアリングアプリケーション
CRMアプリケーション セールス
マーケティング
カスタマーサービスアプリケーション
コンタクトセンター
国内アプリケーシ
ョン開発/デプロ
イメントソフトウ
ェア
品質ライフサイクルツール 自動ソフトウェア品質(ASQ)ツール
ソフトウェア構成管理(SCM)
インテグレーション/プロ
セスオートメーションミド
ルウェア
BtoB ミドルウェア
エンタープライズサービスバス/
コネクティビティミドルウェア
イベント駆動型ミドルウェア
プロセスオートメーションミドルウェア
その他インテグレーション/
プロセスオートメーションミドルウェア
データアクセス/解析/デ
リバリーソフトウェア
エンドユーザクエリー/レポート/
解析ツール
先進解析ソフトウェア
空間情報管理
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
68
システムインフラ
ストラクチャ
ソフトウェア
システム/ネットワーク管
理ソフトウェアイベントオートメーションツール
ジョブスケジューリングツール
出力管理ツール
パフォーマンス管理ソフトウェア
変更/コンフィギュレーション管理
ソフトウェア
問題管理アプリケーション
ネットワーク管理ソフトウェア
セキュリティソフトウェア アイデンティティ/アクセス管理
ソフトウェア
セキュアコンテンツ/脅威管理ソフトウェア
セキュリティ/脆弱性管理ソフトウェア
その他セキュリティソフトウェア
ストレージソフトウェア データ保護/リカバリーソフトウェア
ストレージレプリケーションソフトウェア
アーカイビングソフトウェア
ファイルシステムソフトウェア
ストレージインフラストラクチャ
ソフトウェア
ストレージデバイス管理ソフトウェア
その他ストレージソフトウェア
システムソフトウェア OS とサブシステムソフトウェア
アベイラビリティ/クラスタリング
ソフトウェア
バーチャルユーザインタフェース
ソフトウェア
バーチャルマシンソフトウェア
その他システムソフトウェア
3.3 商材化の可能性を持つ有望 OSS
前項で抽出した探索対象のソフトウェア分類を基に商材のベースとなる OSS を探索・抽
出する。
探索・抽出手順および結果を以下に示す。
3.3.1 探索・抽出手順
OSS の探索手順を以下に示す。
なお、探索・抽出にあたっては、有識者による探索専門グループを設置し、作業にあた
ることとした。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
69
①sourceforge および freshmeat を情報源として、予め抽出したソフトウェア分類(中分
類)を対象として、OSS を探索する。なお、探索を行う上で、以下の条件に該当するも
のは対象外とする。
・開発元のホームページがない、もしくは開発が継続されていない。
・開発が活発でない、もしくはユーザコミュニティなどでのアクセス、ダウンロー
ドが少ない。
・ソフトウェアの機能が未熟で基本機能も実装が進んでいない。
・非 OSS 用のキットのみが公開されている。
・日本で既に普及している。
②以下の作業を行い、表 3.3.1-1 に示すフォーマットを網羅するよう調査する。
・ソフトウェアのホームページにアクセスし、関連情報を調査する。
・検出した OSS のソフトウェア名称を検索サイトのキーワードとして検索し、イン
ターネットから抽出できる情報を調査する。
・情報が少ないものについては、ソフトウェアパッケージの中を展開し、構成物に
含まれているドキュメントから情報を取得する。
表 3.3.1-1 OSS 抽出結果フォーマット
項目 内容
ソフトウェア名称 対象ソフトウェアの名称を記述
ソフトウェア分類 対象ソフトウェアの分類を記述
ソフトウェア種別 対象ソフトウェアの種別を記述
使用言語 対象ソフトウェアのプログラミング言語を記述
機能概要/用途 対象ソフトウェアの機能概要、用途を記述
対応言語
ソフトウェア 対象ソフトウェアの言語対応情報を記述
マニュアル 対象ソフトウェアのマニュアルの言語対応状況を記述
対応プラットフォーム 対象ソフトウェアが対応しているプラットフォームを記述
ライセンス 対象ソフトウェアのライセンス情報を記述
公式ホームページ 対象ソフトウェアの公式ホームページを記述
(開発/ユーザコミュニティサイトも全て記述)
参考情報 対象ソフトウェアに対する情報収集源を記述
評価結果
機能充実度 点数 備考
言語対応
(ソフトウェア)
点数 備考
言語対応
(マニュアルな
ど)
点数 備考
言語対応 点数 備考
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
70
(FAQ)
技術情報 点数 備考
構成物管理 点数 備考
開発安定性 点数 備考
ユーザ評価・
知名度
点数 備考
合計 合計点
③対象となる OSS を検出した場合は、評価基準による評価を行なった後、探索専門グル
ープで評価基準のポイントが高いもののみをサンプルとして抽出する。
評価基準は、(独)情報処理推進機構(IPA)の「2007 年度オープンソースソフトウェア活
用基盤整備事業 OSS オフィスアプリケーションのカタログ作成調査報告書」で適用さ
れているソフトウェアの成熟度評価を参考に、本調査の目的である商材のベースとな
る OSS を探索することに焦点を絞り、日本の視点で見た希少性に注目し、評価基準を
作成した。
本調査の評価基準を表 3.3.1-2 に示す。
表 3.3.1-2 OSS の評価基準
評価項目 レベル 詳細
機能充実度 5 商用製品と同など以上(市場要求を十分に満足させる)機能を有し
ており、競合ソフトの機能への追随や差別化などの段階にある
4 商用製品とほぼ同など(弱冠の機能不足)の機能を有しており、開
発・機能保有状況が明確化されている、あるいは開発計画が整備
されている
3 必要十分な機能を有している
2 基礎的な機能を有しているが、必要十分なレベルに至っていない
1 基礎的な機能もまだ完成しておらず、プロトタイプ的なレベルに
ある
言語対応
(ソフトウェア)
5 国際化(I18N)対応されているが、日本語に対応していない
4 国際化(I18N)対応されていないが、対応中の状況にある
3 国際化(I18N)対応されていないが、対応計画を有している
2 国際化(I18N)対応されておらず、対応計画もない
1 国際化(I18N)対応されており、日本語にも既に対応している
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 複数の言語版が存在するが、日本語版はない
4 複数言語が存在せず、日本語版もない
3 作成されていない
2 日本語版が存在しないが、作成中の状況にある
1 日本語版が存在する
言語対応
(FAQ)
5 複数の言語に対応しているが、日本語には対応していない
4 複数言語が存在せず、日本語にも対応していない
3 日本語に対応中の状況にある
2 日本語に対応している
1 存在しない
技術情報 5 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報が整備されて
おり、日本語の記述も存在する
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
71
4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報が整備されて
いるが、日本語の記述は存在しない
3 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報が整備されて
いるが不足している
2 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報のうち、いず
れかの情報が欠損している
1 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報が未整備な状
況にある
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利用方法などの
情報が集積されており、かつわかり易く管理されている
4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利用方法などの
集積、管理されている
3 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能が集積、管理され
ているが、情報量や種類が少ない、または情報収集を行うのが難
しい
2 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能モジュールなどが
集積、管理されているが、情報量が少なく、更新されていない
1 情報が集積、管理されていない
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフトウェアと同な
どの安定した開発が遂行されている
4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定した開発が行わ
れている
3 比較的開発は安定して遂行されている
2 開発の将来計画がわからない
1 開発が中断している。または、機能を実現するために十分な開発
者が揃っていない
ユーザ評価・
知名度
5 日本ではユーザがほとんど存在しない、もしくは少ないが、海外
でのユーザ数や動作実績は多い
4 日本ではユーザがほとんど存在しない、もしくは少ないが、海外
でのユーザ数や動作実績が比較的多い
3 日本でもユーザがほとんど存在せず、海外でもユーザ数や動作実
績は少ない
2 日本、海外ともにユーザ数や動作実績がほとんどない
1 日本でのユーザが存在する
3.3.2 探索・抽出結果
探索後、前項の評価基準を基に評価し、コラボレーティブアプリケーション(5本)、コン
テンツアプリケーション(5 本)、オペレーション/製造管理アプリケーション(5本)、エン
ジニアリングアプリケーション(3本)、CRM アプリケーション(4本)、品質ライフサイクル
ツール(2本)、インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウェア(4 本)、デー
タアクセス/解析/デリバリーソフトウェア(5本)、システム/ネットワーク管理ソフトウ
ェア(5 本)、セキュリティソフトウェア(6本)、ストレージソフトウェア(5 本)、システム
ソフトウェア(6 本)を抽出した。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
72
抽出した OSS をソフトウェア種別毎に示す。
(A)コラボレーティブアプリケーション
コラボレーティブアプリケーションで抽出した OSS を表 3.3.2-1 から表 3.3.2-5 に
示す。
表 3.3.2-1 OSS 抽出結果(Simple Groupware)
項目 内容
ソフトウェア名称 Simple Groupware
ソフトウェア分類 コラボレーティブアプリケーション
ソフトウェア種別 統合コラボレーティブ環境
使用言語 JavaScript、PHP
機能概要/用途 エンタープライズ対応のグループウェア
E メール、カレンダー、連絡先、タスク管理、文章管理
(WebDAV)、携帯電話と Outlook の同期(SyncML)、全文検索
機能を有している
対応言語
ソフトウェア 英語、クロアチア語、フランス語、スロバキア語、チェコ
語、ハンガリー語、スペイン語、ドイツ語、デンマーク語、
イタリア語、スウェーデン語、ポルトガル語、オランダ語、
ロシア語、トルコ語、ギリシャ語、ウクライナ語、ポーラ
ンド語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows(NT/2000/XP)
All POSIX(Linux/BSD/UNIX-likeOSes)
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.simple-groupware.de/cms/
参考情報 sourceforge.net/projects/simplgroup/
freshmeat.net/projects/simplegroupware/
評価結果
機能充実度 4 グループウェアとして必要な機能が搭載されてお
り、さらに、Simple Groupware Solutions Markup
Language (sgsML)という開発ツールが提供されてお
り、独自機能を開発することができるようになって
いる
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、クロアチア語、フランス語、スロバキア語、
チェコ語、ハンガリー語、スペイン語、ドイツ語、
デンマーク語、イタリア語、スウェーデン語、ポル
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
73
トガル語、オランダ語、ロシア語、トルコ語、ギリ
シャ語、ウクライナ語、ポーランド語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
4 英語(公式サイト、sourceforge.net、Google Group
のフォーラムの FAQ)
日本語対応なし
技術情報 4 英語(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績など
の情報を sourceforge.net で管理)
日本語対応なし
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用法などの情報が集積されており、公式ホームペー
ジからの情報収集が容易
開発安定性 5 開発ロードマップが示され、商用ソフトウェアと同
などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 35
表 3.3.2-2 OSS 抽出結果(Foswiki)
項目 内容
ソフトウェア名称 Foswiki
ソフトウェア分類 コラボレーションアプリケーション
ソフトウェア種別 チームコラボレーションアプリケーション
使用言語 Perl
機能概要/用途 Wiki ベースのチームコラボレーションアプリケーション
他のアプリケーションを組み込むことで動的なウェブコン
テンツの作成が可能
対応言語
ソフトウェア デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ニュー
ジーランド語、ポルトガル語、中国語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム MS Windows/Mac OSX/Linux
ライセンス GNU General Public License (GPL)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
74
公式ホームページ foswiki.org
参考情報 sourceforge.net/projects/foswiki/
freshmeat.net/projects/foswiki/
評価結
果
機能充実度 3 Wiki の機能として必要十分な機能を有している。
言語対応
(ソフトウェア)
1 国際化対応済
日本語対応しているが、完全対応までは至っていない
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
4 英語(公式サイトで FAQ 提供)
日本語対応なし
技術情報 4 英語(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの
情報を sourceforge.net で管理)
日本語対応なし
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利用
法などの情報が集積されており、公式ホームページか
らの情報収集が容易
開発安定性 5 開発ロードマップが示され、商用ソフトウェアと同等
レベルの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本で
ほとんど知られていない
合計 27
表 3.3.2-3 OSS 抽出結果(Kablink)
項目 内容
ソフトウェア名称 Kablink(formerly ICEcore)
ソフトウェア分類 コラボレーションアプリケーション
ソフトウェア種別 統合コラボレーティブ環境
チームコラボレーションアプリケーション
会議アプリケーション
使用言語 Java、JavaScript、JSP
機能概要/用途 エンタープライズ向けのコラボレーティブアプリケーショ
ン
リアルタイムコミュニケーション、会議アプリケーション、
ドキュメント共有、ワークフロー、コンテンツマネジメン
ト、Wiki、ブログなどの機能を搭載している
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
75
対応言語
ソフトウェア 中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
日本語、ポーランド語、ポルトガル語、スペイン語、スウ
ェーデン語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス Common Public Attribution License 1.0 (CPAL)
公式ホームページ www.kablink.org
参考情報 sourceforge.net/projects/icecore/
評価結果
機能充実度 5 商用製品とほぼ同等レベルの機能を有しており、開
発計画が整備されている
本アプリケーションをベースに機能拡張した、
Novell 社の商用製品(Teaming + Conferencing ソリ
ューション)が存在する
言語対応
(ソフトウェア)
1 国際化対応済
日本語に対応しているが、完全対応までは至ってい
ない
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
5 英語
技術情報 4 英語(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績など
の情報を sourceforge.net で管理)
日本語対応なし
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用法などの情報が集積管理されている
開発安定性 4 開発ロードマップが示され、安定した開発が遂行さ
れている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 31
表 3.3.2-4 OSS 抽出結果(OntoWiki)
項目 内容
ソフトウェア名称 OntoWiki(Powl)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
76
ソフトウェア分類 コラボレーションアプリケーション
ソフトウェア種別 チームコラボレーションアプリケーション
その他コラボレーションアプリケーション
使用言語 PHP
機能概要/用途 Wiki ベースのナレッジマネジメント(知識管理)アプリケー
ション
文字情報、画像や位置情報、カレンダーによる日付情報など
のデータマッピング機能
対応言語ソフトウェア 英語、ドイツ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ ontowiki.net/Projects/OntoWiki
参考情報 sourceforge.net/projects/powl/
freshmeat.net/projects/ontowiki/
code.google.com/p/ontowiki/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有している
言語対応
(ソフトウェア)
5 国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 英語(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績など
の情報を Google Code で管理)
日本語対応なし
構成物管理 3 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用法などの情報が集積管理されているが、情報量や
種類が少ない
開発安定性 4 開発ロードマップが示され、安定した開発が遂行さ
れている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 31
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
77
表 3.3.2-5 OSS 抽出結果(Tine)
項目 内容
ソフトウェア名称 Tine
ソフトウェア分類 コラボレーションアプリケーション
ソフトウェア種別 チームコラボレーションアプリケーション
使用言語 JavaScript、PHP
機能概要/用途 グループウェア/社内情報ポータルアプリケーション
デスクトップアプリケーションのようなリッチなインタフ
ェースを持つ
アドレス帳、電話(VoIP) 、CRM、タスク管理、タイムトラ
ッキング機能、ActiveSync 機能など有する
対応言語ソフトウェア 英語、ドイツ語、ロシア語、中国語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス Affero GNU Public License
公式ホームページ www.tine20.org
参考情報 freshmeat.net/projects/tine20
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発、
機能保有状況が明確化され、開発計画が整備されて
いる
言語対応
(ソフトウェア)
5 国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語、ドイツ語、ロシア語、中国語
言語対応
(FAQ)
5 英語、ドイツ語、ロシア語、中国語
技術情報 4 英語、ドイツ語、ロシア語、中国語
(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されている)
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの情報が集積されており、かつ、わかり
易く管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・ 4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
78
知名度 ではほとんど知られていない
合計 36
(B)コンテンツアプリケーション
コンテンツアプリケーションで抽出した OSS を表 3.3.2-6 から表 3.3.2-10 に示す。
表 3.3.2-6 OSS 抽出結果(Liimbas)
項目 内容
ソフトウェア名称 Limbas
ソフトウェア分類 コンテンツアプリケーション
ソフトウェア種別 エンタープライズポータル
使用言語 PHP
機能概要/用途 エンタープライズポータルソリューションを提供するウ
ェブアプリケーション
CMS、CRM、文章管理、PDF レポート、グループウェア、ワ
ークフロー、チケットシステム、プロジェクト管理、ショ
ップ、コールセンターなどの機能を実装している
対応言語ソフトウェア 英語、ドイツ語、フランス語
マニュアル 英語、ドイツ語
対応プラットフォーム All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.limbas.org
参考情報 sourceforge.net/projects/limbas/
freshmeat.net/projects/limbas/
評価結果
機能充実度 4 必要十分な機能を有し、開発計画が整備されている
言語対応
(ソフトウェア)
5 国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語、ドイツ語、フランス語
言語対応
(FAQ)
5 英語、ドイツ語、フランス語
技術情報 3 英語(バグ情報、セキュリティ情報、動作実績など
の情報を sourceforge.net で管理)
日本語対応なし
構成物管理 3 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
79
用法などの情報が集積管理されているが、情報収集
を行うのが難しい
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
3 日本、海外ともにユーザ数や動作実績が少ない
合計 31
表 3.3.2-7 OSS 抽出結果(webEdition CMS)
項目 内容
ソフトウェア名称 webEdition CMS
ソフトウェア分類 コンテンツアプリケーション
ソフトウェア種別 コンテンツ管理アプリケーション
使用言語 PHP
機能概要/用途 コンテンツ管理アプリケーション
タスク管理、ワークフロー、顧客管理、ニュースレター機
能を有している
拡張アプリケーションの作成が容易なのが特徴
対応言語ソフトウェア 英語、フィンランド語、ドイツ語、オランダ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ www.webedition.de
参考情報 sourceforge.net/projects/webedition/
評価結果
機能充実度 2 基礎的な機能を有しているが、必要十分なレベルに
至っていない
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、フィンランド語、ドイツ語、オランダ語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 3 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが不足している
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
80
構成物管理 3 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能が集
積、管理されているが、情報量や種類が少ない、ま
たは情報収集を行うのが難しい
開発安定性 4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定し
た開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
3 日本、海外ともにユーザ数や動作実績が少ない
合計 29
表 3.3.2-8 OSS 抽出結果(BIGACE Web CMS)
項目 内容
ソフトウェア名称 BIGACE Web CMS
ソフトウェア分類 コンテンツアプリケーション
ソフトウェア種別 コンテンツ管理アプリケーション
使用言語 JavaScript、PHP
機能概要/用途 Easy-to-Use マルチサイト、多言語、マルチユーザ対応に
したコンテンツマネジメントシステム
コンテンツのバージョン管理、ワークフロー、全文検索な
どの機能を有し、プラグインの追加による機能拡張が可能
対応言語ソフトウェア 英語、ドイツ語
マニュアル 英語、ドイツ語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.bigace.de
参考情報 sourceforge.net/projects/bigace/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、ドイツ語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語、ドイツ語
言語対応
(FAQ)
5 英語、ドイツ語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
81
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
3 日本、海外ともにユーザ数や動作実績が少ない
合計 35
表 3.3.2-9 OSS 抽出結果(LogicalDOC)
項目 内容
ソフトウェア名称 LogicalDOC - Document management、DMS
ソフトウェア分類 コンテンツアプリケーション
ソフトウェア種別 コンテンツ管理アプリケーション
検索/ディスカバリーソフトウェア
使用言語 Java、JavaScript、JSP
機能概要/用途 ウェブベースのドキュメントマネジメントシステム
(DMS)
フォルダの構成管理、インポート機能、全文検索インデ
ックス、バージョン管理、.NET との相互運用、WebDAV な
どの機能を有する
対応言語
ソフトウェア オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
スペイン語
マニュアル オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
スペイン語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)
All BSD Platforms
(FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS X)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ www.logicaldoc.com/cmsPublic/-/websitelogicaldoc/e
n.html
www.logicaldoc.info/wiki/index.php?title=Main_Page
参考情報 http://sourceforge.net/projects/logicaldoc/
http://freshmeat.net/projects/logicaldoc/
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
82
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同等レベルの機能を有しており、開
発・機能保有状況が明確化されている、あるいは開
発計画が整備されている
言語対応
(ソフトウェア)
5 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリ
ア語、スペイン語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
4 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリ
ア語、スペイン語
言語対応
(FAQ)
4 オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリ
ア語、スペイン語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同等レベルの安定した開発が遂行されて
いる
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 34
表 3.3.2-10 OSS 抽出結果(Nuxeo)
項目 内容
ソフトウェア名称 Nuxeo
ソフトウェア分類 コンテンツアプリケーション
ソフトウェア種別 コンテンツ管理アプリケーション
エンタープライズポータル
使用言語 Java
機能概要/用途 エンタープライズコンテンツ管理(ECM)システム
Web コンテンツ管理、ドキュメント管理、レコード管理、
コラボレーションツール、イントラネットポータル、ワ
ークフローアプリケーション、バージョン管理機能を付
加したドキュメントライフサイクルの実現、アクセス権
限管理機能、ドキュメントアプローバル機能を実現した
ワークフロー機能、ドキュメント間の関連を管理する機
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
83
能の追加、オーディットトレール機能の実現
IE/Firefox/MS Office に対するプラグインなどが提供さ
れている
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ www.nuxeo.org
doc.nuxeo.org/xwiki/bin/view/Main/
jira.nuxeo.org/browse/NXP?report=com.atlassian.jir
a.plugin.system.project:openissues-panel
参考情報 jira.nuxeo.org/secure/Dashboard.jspa
www.nuxeo.com
評価結果
機能充実度 5 商用製品と同など以上機能を有しており、競合ソフ
トの機能への追随や差別化などの段階にある
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 35
(C)オペレーション/製造管理アプリケーション
オペレーション/製造管理アプリケーションで抽出した OSS を表 3.3.2-11 から表
3.3.2-15 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
84
表 3.3.2-11 OSS 抽出結果(webERP)
項目 内容
ソフトウェア名称 webERP
ソフトウェア分類 オペレーション/製造管理アプリケーション
ソフトウェア種別 サービスオペレーション管理アプリケーション
使用言語 PHP
機能概要/用途 Web ベースの統合会計 ERP システム
多言語対応、複数通貨、在庫管理、販売分析、柔軟な価格
設定、メール送信用の PDF ファイルの作成機能など実装す
る
対応言語
ソフトウェア ポルトガル語、中国語、オランダ語、英語、フランス語、
ドイツ語、インドネシア語、ポーランド語、ロシア語、ス
ペイン語、トルコ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.weberp.org
参考情報 sourceforge.net/projects/web-erp/
freshmeat.net/projects/weberp/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同など(弱冠の機能不足)の機能を有
しており、開発・機能保有状況が明確化されている。
言語対応
(ソフトウェア)
1 ポルトガル語、中国語、オランダ語、英語、フラン
ス語、ドイツ語、インドネシア語、ポーランド語、
ロシア語、スペイン語、トルコ語
国際化対応済
日本語の言語ファイルは存在するが、語調が統一さ
れていない不完全な状態
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
4 英語(オンライン)
技術情報 4 公式サイトおよび sourceforge.net 上にて、技術情
報の管理が行われている。日本語の記述は存在しな
い
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
85
開発安定性 4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定し
た開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 29
表 3.3.2-12 OSS 抽出結果(Openbravo ERP)
項目 内容
ソフトウェア名称 Openbravo ERP
ソフトウェア分類 オペレーション/製造管理アプリケーション
ソフトウェア種別 サービスオペレーション管理アプリケーション
使用言語 Java、JavaScript、PL/SQL
機能概要/用途 小規模から大規模向けの Web ベース ERP システム。
財務、サプライチェーン、製造業など幅広い分野の業務に
対応した機能を有する。MVC & MDD フレームワーク構造に
よる容易なカスタマイズを実現。
対応言語
ソフトウェア 中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、マレ
ーシア語、ポーランド語、ポルトガル語、スペイン語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
公式ホームページ www.openbravo.com/product/erp/
参考情報 sourceforge.net/projects/openbravo/
freshmeat.net/projects/openbravo/
評価結果
機能充実度 5 多機能でインタフェースが洗練されており、商用製
品と同など以上(市場要求を十分に満足させる)機
能を有しており、競合ソフトの機能への追随や差別
化などの段階にある
言語対応
(ソフトウェア)
5 中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、
マレーシア語、ポーランド語、ポルトガル語、スペ
イン語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語(コミュニティ Wiki で提供)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
86
言語対応
(FAQ)
5 英語(コミュニティ Wiki で提供)
技術情報 5 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの情報が集積されており、かつ、わかり
易く管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
5 海外でのユーザ数や動作実績は多いが、日本ではほ
とんど知られていない
合計 40
表 3.3.2-13 OSS 抽出結果(TimeTrex)
項目 内容
ソフトウェア名称 TimeTrex
ソフトウェア分類 オペレーション/製造管理アプリケーション
ソフトウェア種別 その他バックオフィスアプリケーション
使用言語 PHP
機能概要/用途 統合給与管理アプリケーション
給与管理、勤怠管理、タイムシート、従業員スケジュール、
人件費管理の機能を有する
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
公式ホームページ www.timetrex.com
参考情報 sourceforge.net/projects/timetrex/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同など(弱冠の機能不足)の機能を
有しており、開発・機能保有状況が明確化されてい
る
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応 4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
87
(マニュアルなど)
言語対応
(FAQ)
4 英語(コミュニティフォーラムにて管理)
技術情報 3 コミュニティフォーラムのみの管理であり、情報量
が少なく情報収集が難しい
構成物管理 3 コミュニティフォーラムのみの管理であり、情報量
が少なく、情報収集が難しい
開発安定性 4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定し
た開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
3 日本、海外ともにユーザ数や動作実績が少ない
合計 30
表 3.3.2-14 OSS 抽出結果(OrangeHRM)
項目 内容
ソフトウェア名称 OrangeHRM
ソフトウェア分類 オペレーション/製造管理アプリケーション
ソフトウェア種別 その他バックオフィスアプリケーション
使用言語 PHP
機能概要/用途 人的資源管理アプリケーション
人事情報管理、福利厚生、休暇管理、出勤管理、採用情報
などの機能を有する
対応言語
ソフトウェア デンマーク語、オランダ語、英語、ドイツ語、スペイン語、
日本語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.orangehrm.com
参考情報 sourceforge.net/projects/orangehrm/
freshmeat.net/projects/orangehrm/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
1 デンマーク語、オランダ語、英語、ドイツ語、スペ
イン語、日本語
国際化対応済
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
88
日本語の言語ファイルは存在するが、未翻訳メッセ
ージがあるなど不完全な状態
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語(コミュニティ Wiki にて管理)
技術情報 4 コミュニティ Wiki および sourceforge.net で管理
されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの情報が集積されており、かつ、わかり
易く管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 31
表 3.3.2-15 OSS 抽出結果(Claroline)
項目 内容
ソフトウェア名称 Claroline
ソフトウェア分類 オペレーション/製造管理アプリケーション
ソフトウェア種別 その他バックオフィスアプリケーション
使用言語 JavaScript、PHP
機能概要/用途 e ラーニング/e ワーキングアプリケーション。講師による
効果的なオンラインコースの作成、学生の習熟度管理、学
習活動などをウェブで実現
フォーラム、ドキュメント、ポジトリ、カレンダー、SCORM
などの機能を有する
35 もの言語に対応し、ワールドワイドのユーザと開発コ
ミュニティを持つ
対応言語
ソフトウェア アラビア語、ポルトガル語、ベルギー語、カタルニア語、
中国語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オラン
ダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ガルシア語、
ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、
イタリア語、日本語、マレーシア語、ペルシャ語、ポーラ
ンド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
89
ニア語、スペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、
ベトナム語
マニュアル 英語、アラビア語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、
イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、スロベニア語、
スペイン語
対応プラットフォーム All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP)、All BSD
Platforms (FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS X)、
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.claroline.net
groups.google.com/group/claroline-devs
参考情報 sourceforge.net/projects/claroline/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同など(弱冠の機能不足)の機能を
有しており、開発・機能保有状況が明確化されてお
り、開発計画が整備されている
言語対応
(ソフトウェア)
1 アラビア語、ポルトガル語、ベルギー語、カタルニ
ア語、中国語、クロアチア語、チェコ語、デンマー
ク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フラン
ス語、ガルシア語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガ
リー語、インドネシア語、イタリア語、日本語、マ
レーシア語、ペルシャ語、ポーランド語、ポルトガ
ル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベニア語、ス
ペイン語、スウェーデン語、タイ語、トルコ語、ベ
トナム語
日本語の言語ファイルは存在するが、未翻訳メッセ
ージが多く不完全な状態
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語、アラビア語、オランダ語、フランス語、ドイ
ツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、
スロベニア語、スペイン語
言語対応
(FAQ)
5 英語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が公式フォーラムおよび sourceforge.net で整備
されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 5 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの情報が集積されており、かつ、わかり
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
90
易く管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップが示されているなど、商用ソフト
ウェアと同などの安定した開発が遂行されている
ユーザ評価・
知名度
5 97 ヵ国、1,379 組織と海外でのユーザ数および動作
実績が多いが、日本ではほとんどしられていない
合計 34
(D)エンジニアリングアプリケーション
エンジニアリングアプリケーションで抽出した OSS を表 3.3.2-16 から表 3.3.2-18
に示す。
表 3.3.2-16 OSS 抽出結果(BRL-CAD)
項目 内容
ソフトウェア名称 BRL-CAD
ソフトウェア分類 エンジニアリングアプリケーション
ソフトウェア種別 メカニカル CAD
使用言語 C、C++、Java、PHP、Tcl、Unix Shell
機能概要/用途 アメリカ陸軍開発のオープンソース CAD システム
Constructive Solid Geometry(CSG)を用いる 3D-CAD で、多
くの OS に対応している
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)、64-bit MS Windows
All BSD Platforms
(FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS X)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
FreeBSD、Linux、OS X、Solaris、Win2K、WinXP、SGI IRIX
ライセンス BSD License、GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ brlcad.org
参考情報 sourceforge.net/projects/brlcad/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
2 国際化対応されておらず、対応計画もない
言語対応 4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
91
(マニュアルなど)
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定し
た開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 30
表 3.3.2-17 OSS 抽出結果(Sweet Home 3D)
項目 内容
ソフトウェア名称 Sweet Home 3D
ソフトウェア分類 エンジニアリングアプリケーション
ソフトウェア種別 その他エンジニアリングアプリケーション
使用言語 Java
機能概要/用途 3D の間取りソフト
平面図からリアルタイムに 3D の間取り作成が可能
対応言語
ソフトウェア 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、ハ
ンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ロシア語、スペ
イン語、スウェーデン語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)、Linux、OS X
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.sweethome3d.eu
参考情報 sourceforge.net/projects/sweethome3d/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有している
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ
語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ロ
シア語、スペイン語、スウェーデン語
国際化対応済
日本語対応なし
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
92
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ
語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ロ
シア語、スペイン語、スウェーデン語
言語対応
(FAQ)
5 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ
語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ロ
シア語、スペイン語、スウェーデン語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 33
表 3.3.2-18 OSS 抽出結果(FreeCAD)
項目 内容
ソフトウェア名称 FreeCAD
ソフトウェア分類 エンジニアリングアプリケーション
ソフトウェア種別 メカニカル CAD
メカニカル CAE
使用言語 C++、Python
機能概要/用途 3D CAD モデラーアプリケーション
マクロレコーディングやワークベンチ機能を搭載してお
り、サーバとしての運用も可能
モジュール構造の設計になっており高い拡張性を有する
対応言語ソフトウェア 英語、ドイツ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス GNU General Public License (GPL)
GNU Library or Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ juergen-riegel.net/FreeCAD/Docu/index.php?title=Mai
n_Page
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
93
参考情報 http://sourceforge.net/projects/free-cad/
http://freshmeat.net/projects/freecad/
評価結果
機能充実度 2 基礎的な機能を有しているが、必要十分なレベ
ルに至っていない
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、ドイツ語
国際化対応済
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの
情報が整備されているが、日本語の記述は存在
しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能
の利用方法などの集積、管理されている
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、
日本ではユーザは少ない
合計 30
(E)CRM アプリケーション
CRM アプリケーションで抽出した OSS を表 3.3.2-19 から表 3.3.2-22 に示す。
表 3.3.2-19 OSS 抽出結果(OneOrZero Helpdesk)
項目 内容
ソフトウェア名称 OneOrZero Helpdesk
ソフトウェア分類 CRM アプリケーション
ソフトウェア種別 コンタクトセンター
使用言語 JavaScript、PHP
機能概要/用途 エンタープライズヘルプデスクシステム
企業やグループ(小規模から大規模)における情報やリクエ
ストの管理を可能にする
ヘルプデスク、タスク管理、レポート検索、レポート作成、
ノーティスメールなどの機能を有する
対応言語ソフトウェア 英語、ポルトガル語、デンマーク語、オランダ語、フラン
ス語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、イタリア語、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
94
ロシア語、スペイン語、ヘブライ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Cygwin (MS Windows)
All 32-bit MS Windows (95/98/NT/2000/XP)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.oneorzero.com
参考情報 sourceforge.net/projects/oneorzero/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
1 国際化対応済
日本語の言語ファイルは存在するが、不完全な状態
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
5 フォーラム形式で多言語の FAQ が提供されている
が、日本語には対応していない
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が公式フォーラムと sourceforge.net で整備されて
いるが、日本語の記述は存在しない。
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 29
表 3.3.2-20 OSS 抽出結果(opentaps Open Source ERP+CRM)
項目 内容
ソフトウェア名称 opentaps Open Source ERP+CRM
ソフトウェア分類 CRM アプリケーション
ソフトウェア種別 セールス/マーケティング
使用言語 Java
機能概要/用途 ERP および CRM の統合アプリケーションスイート
e-コマース、在庫管理、倉庫管理、受注管理、クライアン
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
95
ト管理、総勘定元管理、MRP、POS などの機能を有する
対応言語
ソフトウェア 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、
中国語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)
All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.opentaps.org
参考情報 sourceforge.net/projects/opentaps/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
1 国際化対応済
日本語対応しているが、不完全
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンラインマニュアル
言語対応
(FAQ)
4 英語(sourceforge.net 上のフォーラムで管理)
技術情報 4 sourceforge.net 上で、バグ情報、セキュリティ情
報、動作実績などの情報が整備されているが、日本
語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 4 メンテナンスも極め細かく遂行されており、安定し
た開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 29
表 3.3.2-21 OSS 抽出結果(hipergate CRM)
項目 内容
ソフトウェア名称 hipergate CRM
ソフトウェア分類 CRM アプリケーション
ソフトウェア種別 セールス/マーケティング
使用言語 Java、JSP
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
96
機能概要/用途 CRM+グループウェアの統合アプリケーションスイート
セールスオートメーション、カスタマーサービス、コンテ
ンツ管理、プロジェクト管理、バグトラキング、グループ
ウェア、ウェブメール、カレンダー、フォーラム、ファイ
ル共有などの機能を有する
対応言語
ソフトウェア 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ガルシア語、
ドイツ語、イタリア語、ロシア語、スロバキア語、スペイ
ン語、タイ語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP)、All 32-bit MS Windows
(95/98/NT/2000/XP)、All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like
OSes)、Linux、Win2K、WinXP、OS 非依存
ライセンス Affero GNU Public License
公式ホームページ www.hipergate.org
参考情報 sourceforge.net/projects/hipergate/
freshmeat.net/projects/hipergate/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発・
機能保有状況が明確化されている
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ガルシ
ア語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、スロバキ
ア語、スペイン語、タイ語
国際化対応済
日本語対応なし
言語対応
(マニュアルなど)
5 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんど知られていない
合計 33
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
97
表 3.3.2-22 OSS 抽出結果(Support Incident Tracker)
項目 内容
ソフトウェア名称 Support Incident Tracker (SiT!)
ソフトウェア分類 CRM アプリケーション
ソフトウェア種別 カスタマーサービスアプリケーション/コンタクトセンタ
ー
使用言語 PHP
機能概要/用途 ヘルプデスク/サポートチケットシステム
技術情報のトラッキング機能、コンタクト管理、eメール、
問い合わせ情報管理機能などを有する
対応言語
ソフトウェア 英語、中国語、デンマーク語、フランス語、ドイツ語、イ
タリア語、日本語、リトアニア語、ポルトガル語、スペイ
ン語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ sitracker.org
参考情報 sourceforge.net/projects/sitracker/
freshmeat.net/projects/sitracker/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ同などの機能を有しており、開発計
画が整備されている
言語対応
(ソフトウェア)
1 国際化対応済
日本語の言語ファイルは存在するが、未翻訳メッセ
ージがあり不完全な状態
言語対応
(マニュアルなど)
4 英語(オンライン)
言語対応
(FAQ)
4 英語(コミュニティフォーラムで管理)
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない。
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外でのユーザ数や動作実績が比較的多いが、日本
ではほとんどしられていない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
98
合計 28
(F)品質ライフサイクルツール
品質ライフサイクルツールで抽出した OSS を表 3.3.2-23 から表 3.3.2-24 に示す。
表 3.3.2-23 OSS 抽出結果(Codestriker)
項目 内容
ソフトウェア名称 Codestriker
ソフトウェア分類 品質ライフサイクルツール
ソフトウェア種別 ソフトウェア構成管理
使用言語 Perl
機能概要/用途 オンラインのソースコードレビュー支援ソフトウェア
ソースコードマネジメント(SCM)により生成された Diff フ
ァイルとリポジトリパスに従ってパッチファイルへコメン
トの登録ができ、登録したコメントの一覧や検索機能を実
装する
CVS や Subversion などのバージョン管理システムとの統合
が可能
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ codestriker.sourceforge.net
参考情報 sourceforge.net/projects/codestriker/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有している
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化対応されておらず、対応計画もない
言語対応
(マニュアルなど)
4 英国(オンラインマニュアル)
言語対応
(FAQ)
4 英国
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
99
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
3 日本、海外でもユーザ数や動作実績は少ない
合計 27
表 3.3.2-24 OSS 抽出結果(Canoo Webtest)
項目 内容
ソフトウェア名称 Canoo Webtest
ソフトウェア分類 品質ライフサイクルツール
ソフトウェア種別 自動ソフトウェア品質(ASQ)ツール
使用言語 Java
機能概要/用途 Javaで作成された Webアプリケーション用の自動機能試験
ツール
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス Apache License V2.0
公式ホームページ webtest.canoo.com/webtest/manual/WebTestHome.html
参考情報 sourceforge.net/projects/webtest/
www.opensourcetesting.org
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有している。
言語対応
(ソフトウェア)
2 国際化対応されておらず、対応計画もない
言語対応
(マニュアルなど)
4 複数言語が存在せず、日本語版もない。英語版のオ
ンラインマニュアルが提供されている。
言語対応
(FAQ)
4 複数言語が存在せず、日本語にも対応していない。
技術情報 4 バグ情報、セキュリティ情報、動作実績などの情報
が整備されているが、日本語の記述は存在しない。
構成物管理 4 ソフトウェアキット、ドキュメント、追加機能の利
用方法などの集積、管理されている。
開発安定性 3 比較的開発は安定して遂行されている。
ユーザ評価・
知名度
4 日本ではユーザが少ないが、海外でのユーザ数や動
作実績が比較的多い。
合計 28
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
100
(G)インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウェア
インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウェアで抽出した OSS を表
3.3.2-25 から表 3.3.2-28 に示す。
表 3.3.2-25 OSS 抽出結果(ChainBuilder ESB)
項目 内容
ソフトウェア名称 ChainBuilder ESB
ソフトウェア分類 インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウ
ェア
ソフトウェア種別 エンタープライズサービスバス/コネクティビティミドル
ウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 ChainBuilder ESB は、SOA(Service Oriented Architecture:
サービス指向アーキテクチャー)を実現するための
Enterprise Service Bus ソリューション
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する OS(JDK5 以上)
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.chainforge.net
参考情報 sourceforge.net/projects/bostech-cbesb/
評価結果
機能充実度 4 コンポーネント開発用の Eclipse プラグインだけで
なく、モニタリング用に Web インタフェースコンソ
ールが提供されている
また、2009 年のロードマップも提供されており、開
発計画が整備されている
言語対応
(ソフトウェア)
3 英語
コミュニティフォーラムにてツール類の国際化が議
論されている状態(今後対応要との結論)
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 コミュニティ内では英語の情報しかなく、Web サイ
ト全体でも日本語の情報はほとんどない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
101
構成物管理 4 コミュニティサイト内で、ソフトウェアキットの提
供はもとより、チュートリアルドキュメントも充実
している
開発安定性 5 開発ロードマップおよび追加予定機能などをコミュ
ニティサイトで提供している
ユーザ評価・
知名度
5 英語圏での動作実績が多いが、日本ではほとんど知
られていない
合計 33
表 3.3.2-26 OSS 抽出結果(osESB)
項目 内容
ソフトウェア名称 osESB
ソフトウェア分類 インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウ
ェア
ソフトウェア種別 エンタープライズサービスバス
使用言語 Java
機能概要/用途 J2EE(Java2 Enterprise Edition)アプリケーションサーバ上
で動作する Enterprise Service Bus ソリューション
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム WebLogic
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.osesb.org
参考情報 sourceforge.net/projects/osesb/
評価結果
機能充実度 2 最低限 ESB を動作させる機能は有しているが、モニ
タリングツールなどが無く、商用ソフトと比較して
機能的に見劣りする
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 1 動作させるのに最低限のドキュメントしかない。よ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
102
り詳細情報を得るためには JavaDoc 出力による関数
説明からソースコードを読むしかない
構成物管理 2 同上
開発安定性 2 2008 年まで活動している状況はあるが、それ以降の
情報はない
ユーザ評価・
知名度
2 実績情報がほとんどない
合計 19
表 3.3.2-27 OSS 抽出結果(JBI4Ejb)
項目 内容
ソフトウェア名称 JBI4Ejb
ソフトウェア分類 インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウ
ェア
ソフトウェア種別 コネクティビティミドルウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 既存のEJB(Enterprise Java Beans)がJBI ESB(Java Business
Integration Enterprise Service Bus)と対話することを可
能にする JBI の仕様に沿ったコンポーネント
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム JDK5 以上、OpenESB2.0、Servicemix 3.1
ライセンス LGPL
公式ホームページ jbi4ejb.sourceforge.net
参考情報 sourceforge.net/projects/jbi4ejb
評価結果
機能充実度 2 基本的な機能のみで、監視ツールなどの周辺ツール
が不足している
言語対応
(ソフトウェア)
4 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 1 最新のセキュリティ情報などは提供されていない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
103
構成物管理 4 ドキュメント情報は充実しているが、最新情報にア
ップデートされていない
開発安定性 2 ロードマップは提供されているが機能的なものだけ
で、リリース時期については明記されていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外ではよく利用されているが、日本では知られて
いない
合計 25
表 3.3.2-28 OSS 抽出結果(Eclipse Equinox)
項目 内容
ソフトウェア名称 Eclipse Equinox
ソフトウェア分類 インテグレーション/プロセスオートメーションミドルウ
ェア
ソフトウェア種別 イベント駆動型ミドルウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 遠隔から管理できる Java ベースのサービスプラットフォー
ムの仕様である OSGi(Open Services Gateway initiative)
の実装版
OSGi の様々なサービスを提供するフレームワークを提供す
る
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java、Eclipse
ライセンス Eclipse Public License(EPL)
公式ホームページ www.eclipse.org/equinox/
参考情報 www.e-sysware.co.jp/product/server.html
評価結果
機能充実度 4 監視ツールや最適化ツールなどの周辺ツールの機能
が不足している
開発計画もしっかりと管理されている
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語
Eclipse プラグインなので、国際化はされているが、
日本語化はまだされていない
言語対応
(マニュアルな
ど)
1 英語
一部日本語版も存在するが、コミュニティがリリー
スしているものではなく、商材化している日本の会
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
104
社がリリースしている
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 コミュニティサイトでセキュリティ情報も含めて管
理されているが日本語版が存在しない
構成物管理 5 コミュニティの情報は非常に多く、最新情報も整理
されて管理されている
開発安定性 5 開発ロードマップも示されており、これまでもの実
績からも安定して開発されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外では非常によく利用されているが、日本では知
られていない
合計 32
(H)データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
データアクセス/解析/デリバリーソフトウェアで抽出した OSS を表 3.3.2-29 から
表 3.3.2-33 に示す。
表 3.3.2-29 OSS 抽出結果(RapidMiner )
項目 内容
ソフトウェア名称 RapidMiner
ソフトウェア分類 データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
ソフトウェア種別 エンドユーザクエリー/レポート/解析ツール
使用言語 Java
機能概要/用途 ドイツで開発されている、データウェアハウス、データマイ
ニング、BI(Business Intelligence)など、アプリケーショ
ン範囲が広いデータ解析ツール
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス Affero GNU Public License
公式ホームページ rapid-i.com
参考情報 Sourceforge.net/projects/yale/
評価結果
機能充実度 4 データマイニングツールしてだけでなく、
ETL(Extract Transform Load) 、 OLAP(Online
Analytical Processing) 、 BI(Business
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
105
Intelligence)ツールとしても利用でき、帳票機能も
備えている
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、ドイツ語
国際化対応済
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 英語、ドイツ語
言語対応
(FAQ)
5 英語、ドイツ語
技術情報 4 コミュニティから最新情報が提供されている
構成物管理 5 チュートリアルなどのドキュメントも豊富でコミュ
ニティサイトにて管理されている
開発安定性 4 ユーザフォーラムでも活発に議論が行われている
が、開発ロードマップなどは示されていない
ユーザ評価・
知名度
5 海外での実績は非常に多いが、日本での実績は確認
できない
合計 37
表 3.3.2-30 OSS 抽出結果(uEngine BPM)
項目 内容
ソフトウェア名称 uEngine BPM
ソフトウェア分類 データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
ソフトウェア種別 エンドユーザクエリー/レポート/解析ツール
使用言語 Java
機能概要/用途 韓国企業が開発したビジネスプロセスやワークフローを管
理するソフトウェア
対応言語ソフトウェア 英語、韓国語
マニュアル 英語、韓国語
対応プラットフォーム Java 環境
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ www.uengine.org
参考情報 sourceforge.net/projects/uengine
評価結果
機能充実度 4 コンポーネントフレームワークで作られており利用
者がコンポーネントを追加できるような仕組みを提
供している
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
106
言語対応
(ソフトウェア)
5 韓国語、英語
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 韓国語、英語
言語対応
(FAQ)
5 韓国語、英語
技術情報 5 最新情報も企業のサイトから提供されている
構成物管理 4 韓国語のみの情報もあるため、わかりやすく提供さ
れているとは言えないが、必要十分な情報は提供さ
れている
開発安定性 4 定期的にリリースされており開発安定性はあるが、
ロードマップは提示されていない
ユーザ評価・
知名度
5 韓国での実績は多数だが、日本では知られていない
合計 37
表 3.3.2-31 OSS 抽出結果(OpenI)
項目 内容
ソフトウェア名称 OpenI
ソフトウェア分類 データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
ソフトウェア種別 エンドユーザクエリー/レポート/解析ツール
使用言語 Java、JSP
機能概要/用途 Web ベースの BI(Business Intelligence)アプリケーション
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動く環境
ライセンス Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
公式ホームページ sourceforge.net/projects/openi
参考情報 なし
評価結果
機能充実度 2 基本的なレポート機能はそろっているが、わかりや
すいユーザインタフェース機能などが備わっていな
い
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
107
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 2 バグ情報などの情報はあるが、あまり活発に行われ
ていない
構成物管理 2 最新情報が少ない
開発安定性 開発が中断しているとまでは言えないが、将来計画
などはリリースされていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外での利用実績が多いが、日本では知られてない。
合計 20
表 3.3.2-32 OSS 抽出結果(pocOLAP)
項目 内容
ソフトウェア名称 pocOLAP
ソフトウェア分類 データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
ソフトウェア種別 エンドユーザクエリー/レポート/解析ツール
使用言語 Java
機能概要/用途 軽量な OLAP(Online Analytical Processing)ツール
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス MIT License
公式ホームページ sourceforge.net/projects/pocolap/
参考情報 なし
評価結果
機能充実度 2 ユーザインタフェースが悪く、使い勝手が悪い
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
3 マニュアル自体が作成されていない
言語対応
(FAQ)
1 存在していない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
108
技術情報 2 セキュリティ情報などが提供されているが、最新情
報に更新されてはない
構成物管理 2 情報量が少ない
開発安定性 2 開発中断はされていないが、頻繁に開発されている
というほどでもない
ユーザ評価・
知名度
2 日本でも海外でも動作実績についての情報はほとん
どない
合計 16
表 3.3.2-33 OSS 抽出結果(GeoTools)
項目 内容
ソフトウェア名称 GeoTools
ソフトウェア分類 データアクセス/解析/デリバリーソフトウェア
ソフトウェア種別 空間情報管理
使用言語 Java
機能概要/用途 Java 用の GIS(Geographic Information System)ツールキッ
トであり、OGC(Open Geospatial Consortium)による OpenGIS
仕様に基づいて実装されたライブラリを提供する
対応言語ソフトウェア 英語、フランス語
マニュアル 英語、フランス語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ geotools.codehaus.org/
参考情報 sourceforge.net/projects/geotools/
評価結果
機能充実度 4 サポートしているデータフォーマットが豊富である
開発をサポートしてくれる環境が不足している
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、フランス語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 英語、フランス語
言語対応
(FAQ)
5 英語、フランス語
技術情報 3 最新情報が整備されているとは言えない
構成物管理 4 ドキュメント類は多く充実しているが、わかり易く
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
109
管理されているとは言えない
開発安定性 3 ロードマップも提供されているが、最新版ではない
開発自体は安定的に続けられている
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績が圧倒的に多く、日本でも一部で利用
されている
合計 33
(I)システム/ネットワーク管理ソフトウェア
システム/ネットワーク管理ソフトウェアで抽出した OSS を表 3.3.2-34 から表
3.3.2-38 に示す。
表 3.3.2-34 OSS 抽出結果(Quartz)
項目 内容
ソフトウェア名称 Quartz
ソフトウェア分類 システム/ネットワーク管理ソフトウェア
ソフトウェア種別 ジョブスケジューリングツール
使用言語 Java
機能概要/用途 J2SE または J2EE アプリケーション用の企業システムの運用
ジョブスケジューラ
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス Apache Software License、BSD License
公式ホームページ www.opensymphony.com/quartz/
参考情報 sourceforge.net/projects/quartz/
評価結果
機能充実度 3 基本的な機能は揃っているが GUI でわかりやすいユ
ーザインタフェースがない
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 公式ホームページにて最新情報がわかりやすく提供
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
110
されている
日本語の情報はない
構成物管理 4 必要な情報は提供されているが、公式ホームページ
内でのキーワード検索機能がない
開発安定性 4 開発ロードマップの提示はないが、定期的にリリー
スされ開発は安定している
ユーザ評価・
知名度
3 海外でも実績情報は少なく、日本でもほとんど知ら
れていない
合計 28
表 3.3.2-35 OSS 抽出結果(openQRM)
項目 内容
ソフトウェア名称 openQRM
ソフトウェア分類 システム/ネットワーク管理ソフトウェア
ソフトウェア種別 パフォーマンス管理ソフトウェア
使用言語 C、Java、JavaScript、Perl、PHP、Unix Shell
機能概要/用途 企業のデータセンターの既存コンポーネントと統合するシ
ステム管理プラットフォーム
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All BSD Platforms (FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS
X)、All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス GNU General Public License (GPL)、Mozilla Public License
1.1 (MPL 1.1)
公式ホームページ www.openqrm.com
参考情報 Sourceforge.net/projects/openqrm/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能は備わっているが、GUI などのわか
りやすいインタフェースが不足している
Windows 版はない
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応 4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
111
(FAQ)
技術情報 5 公式ホームページにて最新情報が提供されている
構成物管理 5 公式ホームページにてわかりやすく管理されている
開発安定性 4 ロードマップが提供されているが機能面のみ提示
で、リリース時期などは提示されていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績は多が、日本では知られていない
合計 31
表 3.3.2-36 OSS 抽出結果(Zenoss)
項目 内容
ソフトウェア名称 Zenoss
ソフトウェア分類 システム/ネットワーク管理ソフトウェア
ソフトウェア種別 パフォーマンス管理ソフトウェア
使用言語 Python、Zope
機能概要/用途 ブラウザベースのシステムモニタリングソフトウェア
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP) 、 All BSD Platforms
(FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS X) 、 All POSIX
(Linux/BSD/UNIX-like OSes)、Linux、OS X
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.zenoss.com
参考情報 sourceforge.net/projects/zenoss/
評価結果
機能充実度 3 既に商用化されたバージョンが存在している。基本
的な機能は実装されている
コミュニティバージョンと商用バージョンとの違い
は、アクセス権限コントロールやレポート機能など
がある
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応 4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
112
(FAQ)
技術情報 2 セキュリティ情報が提供されていない。
構成物管理 4 情報量は多くあるが、必要な情報を探すのに手間ど
うため、わかりやすく情報が提供されているとは言
えない
開発安定性 3 定期的に新バージョンがリリースされている
ロードマップなどは提示されていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外での動作実績が多い
日本でも本ソフトを紹介しているサイトは存在する
が、実際に利用されているケースは少ない
合計 26
表 3.3.2-37 OSS 抽出結果(Hyperic HQ)
項目 内容
ソフトウェア名称 Hyperic HQ
ソフトウェア分類 システム/ネットワーク管理ソフトウェア
ソフトウェア種別 パフォーマンス管理ソフトウェア
使用言語 Groovy、Java、JavaScript
機能概要/用途 大規模リソース監視ソフトウェアである。パフォーマンスな
どを自動収集して表示する
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.hyperic.com
参考情報 sourceforge.net/projects/hyperic-hq/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有しているが、商用製品と比較す
ると周辺ツール機能が不足している
言語対応
(ソフトウェア)
3 英語
国際化についてユーザフォーラム内で議論中
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
113
技術情報 3 セキュリティ情報について積極的に情報を提供して
いない(サポート契約が必要)
構成物管理 5 情報量が多くわかりやすく提供されている
開発安定性 4 ロードマップは提供されていないが、定期的に新場
ジョンがリリースされている
ユーザ評価・
知名度
5 海外での実績は多いが、日本では知られていない
合計 31
表 3.3.2-38 OSS 抽出結果(Osmius)
項目 内容
ソフトウェア名称 Osmius
ソフトウェア分類 システム/ネットワーク管理ソフトウェア
ソフトウェア種別 ネットワーク管理ソフトウェア
使用言語 C++、Java
機能概要/用途 ネットワークを監視するツール
対応言語ソフトウェア 英語、スペイン語
マニュアル 英語、スペイン語
対応プラットフォーム ほとんどの OS に対応
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ osmius.net
参考情報 sourceforge.net/projects/osmius/
評価結果
機能充実度 4 商用製品とほぼ変わらない機能を有している
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、スペイン語
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 英語、スペイン語
言語対応
(FAQ)
5 英語、スペイン語
技術情報 4 日本語の情報がない
構成物管理 5 ムービーを使ったデモなど、ドキュメントが充実し
ている
開発安定性 4 ロードマップは提供されていないが、定期的に新場
ジョンがリリースされている
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
114
ユーザ評価・
知名度
3 日本・海外ともに実績は少ない
合計 35
(J)セキュリティソフトウェア
システム/ネットワーク管理ソフトウェアで抽出した OSS を表 3.3.2-39 から表
3.3.2-44 に示す。
表 3.3.2-39 OSS 抽出結果(AccesStream)
項目 内容
ソフトウェア名称 AccesStream
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 アイデンティティ/アクセス管理ソフトウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 Java ベースのエンタープライズ向け ID アクセス管理技術プ
ロジェクト
認証、監査、レポーティング、ユーザープロファイル管理、
セキュリティポリシー、シングルサインオン、ディレクトリ
のサポートなどの機能開発を目指している
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Java が動作する環境
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.accesstream.com
参考情報 sourceforge.net/projects/accesstream/
評価結果
機能充実度 2 最低限の機能のみ存在し、ユーザが簡単に仕えるよ
うな仕組みがない
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 情報は積極低に提示しているが、日本語は存在しな
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
115
い
構成物管理 3 マニュアル類の情報が少ない
開発安定性 5 ロードマップも提供されており、着実に新バージョ
ンをリリースしている
ユーザ評価・
知名度
2 日本・海外ともに動作実績はほとんどない
合計 26
表 3.3.2-40 OSS 抽出結果(Ratproxy)
項目 内容
ソフトウェア名称 Ratproxy
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 セキュリティ/脆弱性管理ソフトウェア
使用言語 C 言語
機能概要/用途 プロキシサーバとして動作する OSS
同ソフトウェアを経由してWebアプリケーションを操作する
ことで、XSS(Cross Site Scripting)問題や不適切な
XSRF(Cross Site Request Forgeries)対処など、各種の脆弱
性を検出できる
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All BSD Platforms (FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS
X)、Linux
ライセンス Apache Software License
公式ホームページ code.google.com/p/ratproxy/
参考情報 freshmeat.net/projects/ratproxy/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を備えているが、GUI ツールなど使
い勝手を向上させるツールが不足している
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
2 英語
言語対応
(FAQ)
2 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
116
技術情報 2 セキュリティ情報などはあまり提示されていない
構成物管理 2 情報提供は少ない
開発安定性 3 定期的に新バージョンがリリースされている
ユーザ評価・
知名度
3 日本・海外でも動作実績は少ない
合計 19
表 3.3.2-41 OSS 抽出結果(IPCop)
項目 内容
ソフトウェア名称 IPCop
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 その他セキュリティソフトウェア
使用言語 C、Perl、Unix Shell
機能概要/用途 インストールしたコンピュータとネットワークを保護する
ことを唯一の目的とした特化型Linuxディストリビューショ
ン
対応言語ソフトウェア 英語、フランス語
マニュアル 英語、フランス語
対応プラットフォーム Project is an Operating System Distribution、Project is
an Operating System Kernel、Linux
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.ipcop.org
参考情報 sourceforge.net/projects/ipcop/
評価結果
機能充実度 4 アドオンによる機能拡張が可能であるため、機能が
充実している
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語版、フランス語
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 英語版、フランス語
言語対応
(FAQ)
5 英語版、フランス語
技術情報 4 最新情報も積極的に提示しているが、日本語版はな
い
構成物管理 5 情報が豊富にあり、わかりやすく管理されている
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
117
開発安定性 5 開発ロードマップが提供され、定期的に新バージョ
ンがリリースされている
ユーザ評価・
知名度
5 海外での実績は多いが、日本ではほとんど知られて
いない
合計 38
表 3.3.2-42 OSS 抽出結果(EJBCA)
項目 内容
ソフトウェア名称 EJBCA
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 その他セキュリティソフトウェア
使用言語 Java、JavaScript、JSP
機能概要/用途 J2EE の技術を使用し、認証局をつくるためのプラットフォー
ム
対応言語
ソフトウェア 英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、スウェ
ーデン語
マニュアル 英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、スウェ
ーデン語
対応プラットフォーム 32-bit MS Windows (NT/2000/XP) 、 All POSIX
(Linux/BSD/UNIX-like OSes)、OS 非依存、Linux、Solaris、
WinXP
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ www.ejbca.org
参考情報 sourceforge.net/projects/ejbca/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有しているが、監視ツールの不足
などがある
言語対応
(ソフトウェア)
5 英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
スウェーデン語
言語対応
(マニュアルな
ど)
5 英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
スウェーデン語
言語対応
(FAQ)
5 英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
スウェーデン語
技術情報 2 バグ情報・セキュリティ情報はしっかりと提供され
ているが、動作実績情報が少ない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
118
構成物管理 5 情報が集積され、わかりやすく管理されている
開発安定性 4 メンテナンスもきめ細かく遂行され、安定した開発
が行われている
ユーザ評価・
知名度
3 日本・海外ともにユーザ実績は少ない
合計 32
表 3.3.2-43 OSS 抽出結果(Network Security Toolkit)
項目 内容
ソフトウェア名称 Network Security Toolkit (NST)
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 その他セキュリティソフトウェア
使用言語 JavaScript、Perl、PHP、Python、Tcl、Unix Shell
機能概要/用途 広範なオープンソース・ネットワーク・アプリケーションを
同梱し、ネットワーク・セキュリティ管理者がそれらを簡単
に使えるように作られているネットワークの監視・解析・セ
キュリティのためのライブ CD Linux ディストリビューショ
ン
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.networksecuritytoolkit.org/nst/index.html
参考情報 sourceforge.net/projects/nst/
評価結果
機能充実度 4 セキュリティの高いツールが多く同梱されている
インストールを簡単にするなど、使い勝手をよくす
るための機能が不足している
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 2 バグ情報・セキュリティ情報は提供されているが、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
119
実績情報の提供がない
構成物管理 4 情報提供は行われているが、欲しい情報を探すのに
手間が掛かる
開発安定性 3 ロードマップなどは提供されていないが、比較的開
発は安定して遂行されている
ユーザ評価・
知名度
4 海外では比較的多く利用されているが、日本ではほ
とんど知られていない
合計 27
表 3.3.2-44 OSS 抽出結果(PacketFence)
項目 内容
ソフトウェア名称 PacketFence
ソフトウェア分類 セキュリティソフトウェア
ソフトウェア種別 その他セキュリティソフトウェア
使用言語 Perl、PHP
機能概要/用途 ネットワークポリシーを実装する一つの方法として、DHCP
ベースのフィンガープリンティングを使用し、ネットワーク
アドミニストレーションコントロール(NAC)のソリューショ
ンを提供している
対応言語ソフトウェア ドイツ語、英語、フランス語
マニュアル ドイツ語、英語、フランス語
対応プラットフォーム Linux
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.packetfence.org
参考情報 sourceforge.net/projects/packetfence/
評価結果
機能充実度 4 アクセス権限について機能不足が見られるが、それ
以外は基本的な機能を有している
言語対応
(ソフトウェア)
5 ドイツ語、英語、フランス語
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 ドイツ語、英語、フランス語
言語対応
(FAQ)
4 ドイツ語、英語、フランス語
技術情報 1 バグ情報・セキュリティ情報・動作実績のいずれの
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
120
情報も不足している
構成物管理 2 情報量が少ない
開発安定性 3 製品リリースは定期的に行われており、安定的に開
発されている
ユーザ評価・
知名度
4 日本での実績はほとんどない
海外での動作実績は比較的多い
合計 27
(K)ストレージソフトウェア
ストレージソフトウェアで抽出した OSS を表 3.3.2-45 から表 3.3.2-49 に示す。
表 3.3.2-45 OSS 抽出結果(SymmetricDS)
項目 内容
ソフトウェア名称 SymmetricDS
ソフトウェア分類 ストレージソフトウェア
ソフトウェア種別 ストレージレプリケーションソフトウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 データ同期/レプリケーションソリューションです。プラッ
トフォームから独立して、データベースの種類にとらわれ
ず、データベースストアの間で変更を複製する事ができる
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ symmetricds.codehaus.org
参考情報 sourceforge.net/projects/symmetricds/
評価結果
機能充実度 4 機能は充実しているが使い勝手を向上させるユーザ
インタフェースが不足している
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
121
技術情報 2 動作実績情報がない
構成物管理 5 情報提供は積極的に行われており、情報自体も比較
的見つけやすい
開発安定性 4 ロードマップも提供されているが日付は提示されて
いない。機能面だけのロードマップが提供されてい
る。新バージョンは比較的定期的にリリースされて
いる
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績が比較的多いが、日本での知名度はほ
とんどない
合計 29
表 3.3.2-46 OSS 抽出結果(HAMMER Filesystem)
項目 内容
ソフトウェア名称 HAMMER Filesystem
ソフトウェア分類 ストレージソフトウェア
ソフトウェア種別 ファイルシステムソフトウェア
使用言語 C 言語
機能概要/用途 Sun Microsystems の ZFS(Zettabyte File System)とよく似
た機能を提供しつつもZFSの冗長な部分を排除した設計にな
った新しいファイルシステム
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム BSD
ライセンス Barkley Software License(BSD)
公式ホームページ www.dragonflybsd.org/hammer/
参考情報 なし
評価結果
機能充実度 4 商用 ZFS の機能を全て満たしているわけではない
言語対応
(ソフトウェア)
4 英語
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
5 中国語、デンマーク語、オランダ語、英語、ドイツ
語、ハンガリー語、イタリア語、ノルウェー語、ポ
ーランド語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
122
スウェーデン語、ウクライナ語
技術情報 2 バグ情報・セキュリティ情報は存在するが、動作実
績情報はない
構成物管理 5 情報は多く、わかりやすく提供されている
開発安定性 4 きめ細かく新バージョンがリリースされていおり、
開発安定性は高い。ロードマップは提供されていな
い
ユーザ評価・
知名度
1 日本でのユーザは存在し、海外との差はほとんどな
い
合計 29
表 3.3.2-47 OSS 抽出結果(Openfiler)
項目 内容
ソフトウェア名称 Openfiler
ソフトウェア分類 ストレージソフトウェア
ソフトウェア種別 ストレージデバイス管理ソフトウェア
使用言語 C、Java、PHP
機能概要/用途 NAS(Network Attached Storage)を提供する Linux ベースの
ディストリビューション
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)、Linux
ライセンス GNU General Public License (GPL)
公式ホームページ www.openfiler.com
参考情報 sourceforge.net/projects/openfiler/
評価結果
機能充実度 5 CD 起動する事により、PC を NAS 化してしまうという
ソフトウェアで、商用にはない(競合ソフトとの差別
化に繋がる)
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
123
技術情報 3 バグ情報・セキュリティ情報は提供されているが、
動作実績情報が不足している
構成物管理 3 情報提供は行われているが、情報量が少ない
開発安定性 3 リリースも定期的に行われており、比較的開発は安
定している
ユーザ評価・
知名度
4 海外で比較的多く利用されている。日本でのユーザ
も存在する
合計 28
表 3.3.2-48 OSS 抽出結果(Hypertable)
項目 内容
ソフトウェア名称 Hypertable
ソフトウェア分類 ストレージソフトウェア
ソフトウェア種別 その他ストレージソフトウェア
使用言語 C++、Java
機能概要/用途 高い性能を持つ分散データストレージシステムで、最大限の
パフォーマンスとスケーラビリティー、リライアビリティー
が求められるアプリケーション向けに設計されている
サーバの増設することでパフォーマンスを向上させること
が簡単にでき、大容量データをリアルタイムに処理するシス
テムに適している
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All BSD Platforms (FreeBSD/NetBSD/OpenBSD/Apple Mac OS
X)、All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)
ライセンス Apache Software License
公式ホームページ hypertable.org
参考情報 sourceforge.net/projects/hypertable/
評価結果
機能充実度 5 商用ソフトと比較して機能面で劣るところはない。
OSS という事でのアドバンテージが大きい
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画がない
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
124
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 情報は整備されているが、日本語での提供がない
構成物管理 4 情報量は多いが、まとまってはいない
開発安定性 4 きめ細かくリリースされているが、ロードマップは
提供されていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績が多く、日本でのユーザも存在する。
合計 31
表 3.3.2-49 OSS 抽出結果(HBase)
項目 内容
ソフトウェア名称 HBase
ソフトウェア分類 ストレージソフトウェア
ソフトウェア種別 その他ストレージソフトウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 BigTable のオープンソースクローン
Hadoop に依存しており、データは HDFS 上に安全に保存され
る
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス Apache License V2.0
公式ホームページ Hadoop.apache.org/hbase/
参考情報 なし
評価結果
機能充実度 5 商用ソフトと比較して機能面で劣るところはない
OSS という事でのアドバンテージが大きい
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 3 情報は整備されているが、情報量が少ない
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
125
構成物管理 3 情報がすくなく、まとまってはいない
開発安定性 4 きめ細かくリリースされているが、ロードマップは
提供されていない
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績が多く、日本でのユーザも存在する
合計 29
(L)システムソフトウェア
システムソフトウェアで抽出した OSS を表 3.3.2-50 から表 3.3.2-55 に示す。
表 3.3.2-50 OSS 抽出結果(HAIKU)
項目 内容
ソフトウェア名称 HAIKU
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 OS とサブシステムソフトウェア
使用言語 C、C++
機能概要/用途 オープンソースで開発されているデスクトップ向けオペレ
ーティングシステムで、BeOS の再現を目指している
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム x86(Intel、AMD 互換)
ライセンス MIT License
公式ホームページ www.haiku-os.org
参考情報 なし
評価結果
機能充実度 2 テストリリースの段階
言語対応
(ソフトウェア)
1 英語、日本語
国際化に対応済
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 3 情報量が少ない
構成物管理 3 情報量が少ない(一部日本語ドキュメント有)
開発安定性 3 はっきりとしたロードマップはないが、開発は比較
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
126
的安定して行われている
ユーザ評価・
知名度
1 海外にユーザが多く、日本では海外に比べると格段
に少ない
合計 21
表 3.3.2-51 OSS 抽出結果(Maemo)
項目 内容
ソフトウェア名称 Maemo
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 OS とサブシステムソフトウェア
使用言語 C 言語
機能概要/用途 Linux ベースのモバイル向けプラットフォーム
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス GNU Lesser General Public License (LGPL)
公式ホームページ maemo.org
参考情報 freshmeat.net/projects/maemo/
評価結果
機能充実度 4 実際に商用ソフトウェアとして利用されている
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 4 情報は十分に整備されているが、日本語の情報はな
い
構成物管理 4 情報は十分に提供されているが、わかりやすく提供
されてはいない
開発安定性 4 メンテナンスも細かく行われており、安定して開発
されている
ユーザ評価・
知名度
5 日本でのユーザは少ないが、海外では多数の利用実
績が報告されている
合計 31
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
127
表 3.3.2-52 OSS 抽出結果(Syllable)
項目 内容
ソフトウェア名称 Syllable
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 OS とサブシステムソフトウェア
使用言語 Assembly、C、C++、REBOL、Unix Shell
機能概要/用途 低レベルのハードウェア環境下での高速動作を目指した新
型 OS
対応言語
ソフトウェア ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、スロベニア
語
マニュアル ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、スロベニア
語
対応プラットフォーム All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)、 Project is an
Operating System Distribution、Linux、Other Operating
Systems、Other
ライセンス BSD License、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser
General Public License (LGPL)、MIT License
公式ホームページ web.syllable.org/pages/
参考情報 sourceforge.net/projects/syllable/
評価結果
機能充実度 2 まだ開発途上の OS なので、バグが多く残っている。
言語対応
(ソフトウェア)
5 ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、ス
ロベニア語
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、ス
ロベニア語
言語対応
(FAQ)
4 ドイツ語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、ス
ロベニア語
技術情報 3 動作実績情報が不足している
構成物管理 3 ひと通り情報は揃っているが、情報量や種類が少な
い
開発安定性 3 比較的安定して継続的に開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
5 海外での実績は多数存在するが、日本ではユーザは
ほとんどいない
合計 29
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
128
表 3.3.2-53 OSS 抽出結果(OpenSSI)
項目 内容
ソフトウェア名称 OpenSSI
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 アベイラビリティ/クラスタリングソフトウェア
使用言語 Assembly、C、Perl、Unix Shell
機能概要/用途 シングル・システム・イメージ・クラスタリング製品である。
クラスタ運用中にノードの挿抜が可能
Mosix のプロセス・マイグレーション機構を採用し、クラス
タ内の CPU 負荷を動的に分散させることができる
スレッド化プロセスの移動も可能
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム All POSIX (Linux/BSD/UNIX-like OSes)、 Project is an
Operating System Kernel、Linux
ライセンス GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General
Public License (LGPL)
公式ホームページ Openssi.org
参考情報 sourceforge.net/projects/ssic-linux/
評価結果
機能充実度 3 必要十分な機能を有しているが、使い勝手を向上さ
せるためのツール類が不足している
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 2 バグ情報・セキュリティ情報は提供されているが、
動作実績情報がない
構成物管理 3 情報量が少ない
開発安定性 1 開発が 2006 年で中断している
ユーザ評価・
知名度
3 日本ではほとんど利用されておらず、海外でも動作
実績は少ない
合計 22
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
129
表 3.3.2-54 OSS 抽出結果(Carrot2)
項目 内容
ソフトウェア名称 Carrot2
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 アベイラビリティ/クラスタリングソフトウェア
使用言語 Java
機能概要/用途 検索結果クラスタリングエンジン
検索結果を自動的に分析していくつかのカテゴリに分類し
て表示する機能を備えている
同エンジンはWebアプリケーションにおいてもスタンドアロ
ンアプリケーションに組み込んでも活用することができる
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム OS 非依存
ライセンス BSD License
公式ホームページ Project.carrot2.org
参考情報 sourceforge.net/projects/carrot2/
評価結果
機能充実度 3 単体として商用製品と比較するものではなく、商用
製品に組み込む製品である
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
国際化の計画なし
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 1 最新情報は提供されていない
構成物管理 5 ドキュメント類は充実している
開発安定性 3 比較的安定して開発が行われている
ユーザ評価・
知名度
4 海外での実績が比較的多いが、日本での動作実績は
少ない
合計 26
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
130
表 3.3.2-55 OSS 抽出結果(Touchlib)
項目 内容
ソフトウェア名称 Touchlib
ソフトウェア分類 システムソフトウェア
ソフトウェア種別 バーチャルユーザーインタフェースソフトウェア
使用言語 C++
機能概要/用途 iPod Touch や MacBook AIR などで採用が進められているマル
チタッチシステム
マウスでは実現が難しい、複数の指による直感的な操作が可
能
ズームや回転が複数の指によって、スムーズに実現する
対応言語ソフトウェア 英語
マニュアル 英語
対応プラットフォーム Windows、MacOSX
ライセンス New BSD license
公式ホームページ nuigroup.com/touchlib/
参考情報 code.google.com/p/touchlib/
評価結果
機能充実度 3 単体で商材になるようなソフトウェアではなく、製
品に組み込むタイプの OSS
言語対応
(ソフトウェア)
2 英語
言語対応
(マニュアルな
ど)
4 英語
言語対応
(FAQ)
4 英語
技術情報 2 バグ情報、セキュリティ情報が開示されていない。
動作実績情報は存在する
構成物管理 3 情報量が少なく、情報収集を行うのが難しい
開発安定性 2 開発の将来計画が開示されていない
ユーザ評価・
知名度
2 日本・海外でも動作実績はほとんどないが、アーリ
ーアダプターから注目されているソフトウェアであ
る
2008 年から開発が開始された
合計 22
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
131
3.3.3 今後の課題
本調査において、今後成長が期待される各ソフトウェア分類における OSS ベースの商材
開発の材料をサンプル抽出することができたが、今回対象とした情報源を網羅できたわけ
ではなく、単独で公開している OSS などが世界中に散見しており、さらにより多くの有望
な OSS が存在することから、継続的な探索および抽出を実施することが望まれる。また、
本調査で実施した OSS の抽出方法は、今後、探索および抽出を実施していく上での有効な
実施方法のひとつとなりえるものと考える。
さらに、抽出した OSS は、商材化のベースとなる可能性を秘めた対象ソフトウェアであ
るといえるが、今後、動作確認、著作権違反有無などを実施し、さらに精査する必要があ
る。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
132
第4章 県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成条件の調査
本章では、県内 IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容および OSS
活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容について、
アンケート調査を踏まえて検討した結果を示す。
4.1 県内 IT企業の OSS活用ビジネスを展開するための条件・整備内容
県内 IT 企業を対象として、OSS 活用ビジネスに関する意識や課題の認識など、OSS 活用
ビジネスを展開するための条件および整備内容に関するアンケート調査を実施し、その結
果を分析する。
4.1.1 アンケート調査の手順
県内 IT 企業を対象に OSS 活用ビジネスに関する意識や課題の認識など、OSS 活用ビジネ
スを展開するための条件および整備内容に関するアンケート調査を実施する手順を以下に
示す。
なお、アンケートは、県内 IT業界全般の OSS および活用ビジネスに関する意識や課題の
認識把握のための調査を行った後、OSS 活用ビジネスの実施が想定される業種にターゲット
を絞った調査の 2回を実施することとした。
①第 1回アンケートの作成
OSS に関する県内 IT 業界全体の傾向を掴むことを目的として、第 1 回アンケート
を作成する。
②第 1回アンケートの実施
OSS に関する県内 IT 業界全体の傾向を掴むため、沖縄県庁が有する県内 IT企業リ
ストに掲載されている企業すべてを対象にアンケート調査票を郵送で送付
なお、Web でアンケート回答ができるよう、アンケートシステムも整備する。
③第1回アンケート結果の分析
回収したアンケート調査票を基に OSS に関する県内 IT業界全体の傾向を掴む。
④第 2回アンケートの作成
③の分析結果を踏まえ、OSS 活用ビジネスに関する意識や課題の認識など、OSS 活
用ビジネスを展開するための条件および整備内容に関するアンケート調査票を作
成する。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
133
⑤第 2回アンケート調査対象の抽出
沖縄県庁が有する県内 IT 企業リストのうち、OSS ベースの商材創出活動を実施す
る可能性があると推測される業種に対照を絞り、アンケート調査対象を抽出する。
⑥第 2回アンケートの実施
⑤で抽出した県内IT企業を対象として、OSSに関する県内IT企業の実情およびOSS
活用に向けた意識、課題を把握するため、第 1回アンケートで収集した各社のメー
ルアドレスを活用し、アンケート調査票を送付する。
⑦第 2回アンケート結果の分析
回収したアンケート結果を分析し、OSS に関する県内 IT 企業の実情および OSS 活
用に向けた意識、課題を把握する。
4.1.2 アンケート調査の実施
アンケート調査の実施結果を以下に示す。
なお、実施にあたっては、効率性の観点から、OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成
を行うために整備すべき条件・整備内容に関するアンケート調査も一緒に実施する。
(1)第 1回アンケート調査対象の抽出
沖縄県庁が有する県内 IT企業リストに掲載されている全企業 308 社を対象にアンケ
ート調査票を郵送で送付した。
県内 IT 企業の対象業種と発送数を表 4.1.2-1 に示す。
なお、この対象業種の区分は、沖縄県庁が有する県内 IT 企業リストを活用している。
表 4.1.2-1 第 1 回アンケートにおける県内 IT 企業の対象業種と発送数
業態 業種 回答数
コンテンツ作成 Web ページ作成 47
テレビ放送 1
CG 制作 4
CD-ROM 制作 1
ゲーム制作 2
ASP 5
情報サービス コールセンター 38
デジタルデータ提供サービス 12
データセンター 12
データエントリ 5
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
134
受託計算 4
ソフトウェア開発 GIS 7
システムインテグレータ 43
委託開発 15
要員派遣(ソフトウェア) 3
ソフトウェア開発 91
通信関連設備 2
通信ネットワーク 通信キャリア 7
インターネットサービス・プロバ
イダ
12
合計 308
(1)OSS に関する県内 IT業界全体の傾向を掴むためのアンケート(第 1回)の作成
OSS に関する県内 IT 業界全体の傾向を掴むためのアンケート調査票を作成した。
作成したアンケート項目を図 4.1.2-1 に示す。
図 4.1.2-1 第 1 回アンケートの項目
図 4.1.2-1 第 1 回アンケートの項目
・OSS および関連製品の使用有無
・OSS および関連ビジネスに係る経費概算
・OSS 関連サービスの使用状況
(委託,契約に基づく処理,サポートおよび開発,運用保守など含む)・OSS 関連売上(製品使用料,サービス料など含む)・OSS 関連サービスの使用意向
・OSS 商材関連の売上概算
・OSS を活用したビジネス展開を図る際に必要とする支援サービス内容
・OSS を活用しビジネス展開を図る際に必要と考えるスキル
・過去 5 年間のインターンシップ受け入れ状況
・インターンシップ制度の創設時期
・過去 5 年間のインターンシップ累積受け入れ人数
・インターンシップの受け入れ対象学校種別
・インターンシップの期間
・インターンシップ制度利用向上に向けての必要施策
・インターンシップ経験者の採用意向
・教育機関側に対しての要望事項
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
135
(2)第 1 回アンケート調査の実施日程
第 1回アンケートの調査日程を表 4.1.2-1 に示す。
表 4.1.2-1 アンケート調査日程
送付日程 回収完了日
第 1回アンケート 2月 22 日 3 月 6日
(3)第 1 回アンケート調査回収結果
第 1 回アンケートは、県内 IT 業界の全業種に対して送付した。送付数は 308 件で、
うち、有効回答数が 100 件(郵送による回答が 78 件、アンケートシステムによる回答
が 22件)となった。
有効回答数の業種内訳を表 4.1.2-2 に示す。
表 4.1.2-2 第1回アンケートにおける有効回答数の業種内訳
業態 業種 回答数
コンテンツ作成 Web ページ作成 6
テレビ放送 1
CG 制作 2
CD-ROM 制作 0
ゲーム制作 0
ASP 2
情報サービス コールセンター 5
デジタルデータ提供サービス 4
データセンター 2
データエントリ 2
受託計算 2
ソフトウェア開発 GIS 2
システムインテグレータ 17
委託開発 5
要員派遣(ソフトウェア) 1
ソフトウェア開発 45
通信関連設備 1
通信ネットワーク 通信キャリア 2
インターネットサービス・プロバイダ 1
合計 100
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
136
(4)第1回アンケート結果の分析
第 1 回アンケートの分析結果を以下に示す。
(A)県内 IT 業界における OSS 対応状況
県内 IT 業界における OSS 商材に係る経費概算(図 4.1.2-3)において、10 万円以上と回
答している企業が 21 社あり、これらの企業は明らかに OSS を活用してビジネスを実施
していると断定できる。
OSS および関連製品の使用有無(図 4.1.2-2)で使用中と回答した企業数は 64 社あり、こ
こから OSS を活用してビジネスを実施していると断定できる 21 社を差し引くと、43 社
となる。この 43 社は、OSS を活用しているもの、どのような状態か特定できない企業群
である。OSS 商材に係る経費概算(図 4.1.2-3)で 10 万円未満と回答している企業は 79 社
存在するが、10 万円未満の回答には、OSS を活用していない企業とほぼ経費をかけずに
OSS が活用できている企業の 2 種類が含まれるものと推察されることから、この 79 社か
ら前述の OSS を活用しているもの、どのような状態か特定できない企業群である 43 社
を差し引くと、36 社となり、この企業群は、前述の 2 種類のうち、OSS を活用していな
い企業だと断定することができる。
なお、OSS を活用していない企業の主な3大理由は、①必要なものが見つからない、
②実績がないので不安、③サポートできるか不安 であった。
図 4.1.2-2 県内 IT 業界における OSS および関連製品の使用有無
使用中
未使用
64%36%
N=100
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
137
図 4.1.2-3 県内 IT 業界における OSS 商材に係る経費概算
OSS関連サービス(契約に基づく処理、サポートおよび開発、運用保守など含む)の使用状況(表 4.1.2-3)では 30社が活用していると回答しており、OSSの保守サービスの活用度合いが最も高く、以降、知的所有権に関するサービス、OSS の導入・構築・サービス、技術コンサルティング・サービスと続いている。また、活用していないと回答した企業 70社のうち、自社で OSSの活用や保守ができると回答している企業が 34社あり、OSSおよび関連製品の使用有無(図 4.1.2-2)で使用中と回答した 64社からこの 34社を差し引いた 30社は、OSS 関連サービスを活用していると回答している企業数と合致する。このことから、県内IT業界において、OSSを活用している企業のうち、約 53%が自社で OSSの活用や保守ができる企業であり、約 47%が OSS関連サービスを活用している企業であると考えられる。
表 4.1.2-3 OSS 関連サービスの使用状況
状況 回答数および内容
使用中 30 使用中のサービス
(複数回答)OSSの保守サービス 19知的所有権に関するサービス 9OSSの導入・構築・サービス 8技術コンサルティング・サービス 5
未使用 70 未使用の理由
(複数回答)自社で対応できる 34 実績がないか、少ないので不安 22 自社で提供可能なサービスレベルが
不安 11
値段が高い 4
10万円未満
10万円~100万円未満
100万円~500万円未満
500万円~1,000万円未満
1,000万円~5,000万円未満
5,000万円以上
79%12%
7% 2%
N=100
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
138
県内 IT 業界における OSS 商材関連の売上概算を図 4.1.2-4 に示す。
OSS を活用している企業のうち、19 社は 100 万円以上の OSS 関連売上があり、さらにそ
の中でも 11 社は 1,000 万円以上の売上がある。OSS を活用していない企業だと断定した 36
社を 100 万円未満の 81社から差し引いて求められる 45社が、OSS を活用している企業のう
ち 100 万円未満の売上しかない企業数となる。
このことから、OSS を活用している企業のうち、約 7 割強の企業が OSS をビジネスに活か
せていない(収益につなげられていない)か、もしくは社内に限定した使用などにとどまっ
ているものと推察する。
図 4.1.2-4 県内 IT 業界における OSS 商材の売上概算
(B)県内 IT 業界が OSS ビジネスの実現に必要な支援内容とスキル
県内 IT 業界が OSS ビジネスの実現に必要な支援内容と必要と考えるスキルをそれぞ
れ表 4.1.2-4 と表 4.1.2-5 に示す。
県内 IT 業界が OSS ビジネスの実現に必要と挙げた支援希望内容を見ると、人材育成
面、技術・保守サポート面での不安要素があり、この解消に向けた支援サービスを求
めていることがわかる。
また、県内 IT業界が OSS ビジネスの実現に必要と考えるスキルを見ると、システム
インテグレーションにおける上流工程のスキルが上位を占めており、IT 業界のハイア
ラーキにおける一次、二次の業務レベル、いわゆるプライムコンストラクターになれ
る、もしくはレベルの向上を果たしたいという願望と県内 IT 業界のウィークポイント
が読み取れる。
表 4.1.2-4 OSS 製品を活用しビジネス展開を図る際に必要とする支援サービス(複数回答)
必要とする支援サービス内容 回答数
導入・開発支援 44
81%8%5% 3% 3%
81, 81%
8, 8%5, 5% 3, 3% 3, 3%
100万円未満
100万円~1,000万円未満
1,000~5,000万円未満
5,000万円~1億円未満
1億円以上
N=100
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
139
人材育成・教育支援 29運用支援 26販売支援 25製品戦略・マーケティング支援 23広告・宣伝・セミナー支援 19その他 3
表 4.1.2-5 OSS 製品を活用しビジネス展開を図る際に必要と考えるスキル(複数回答)
必要と考えるスキル 回答数
システムコンサルティング 34市場把握・ビジネス計画 33システム・業務アプリケーション提案 29システム設計 29営業販売力 25システム導入構築 22システムサポート 22プログラミング 14業務アプリケーションコンサルティング 12業務アプリケーション設計 8業務アプリケーション構築 5業務アプリケーションサポート 5その他 1
(5)第 2 回アンケートの作成
第 1回アンケート調査結果の分析結果を踏まえ、OSS 活用ビジネスに関する意識や課
題の認識など、OSS 活用ビジネスを展開するための条件および整備内容に関するアンケ
ート調査票を作成した。
作成したアンケート項目を図 4.1.2-5 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
140
図 4.1.2-1 第 1 回アンケートの項目
図 4.1.2-5 第 2 回アンケートの項目
・OSS 活用有無
・OSS 未活用企業の未活用理由
・OSS 未活用企業の OSS に対する興味の有無
・OSS 未活用企業が活用に踏み切れる材料
・OSS 未活用企業が活用している主なソフトウェア
・OSS の認知度
・商用ソフトウェアと比較した OSS の長所/短所
・OSS に期待すること
・OSS を活用してデメリットとなった事項
・実施しているビジネスモデル
・OSS の著作権やライセンスに関する考慮状況
・取り扱っている OSS ・主な販路
・OSS に関する技術的な後ろ盾(開発・保守)の必要性・有無
・OSS コミュニティとの関わり
・営業の要員数
・技術者の要員数
・人材確保,育成方法
・コーポレートプロモーションの方法
・プロダクトプロモーションの方法
・主なビジネス
・ターゲット市場
・海外進出の有無
・企業としての具体的な強み・弱み・課題
・OSS を活用し続ける上で抱えている課題
・課題改善の具体的な方策
・企業としての今後の方向性
・OSS を活用する上でのリスク
・製品開発での許容可能な投資額
・技術者との共同作業に携わった学生に関する方針
(新規採用・優先交渉など)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
141
(6)第 2 回アンケート調査対象の抽出
沖縄県庁が有する県内 IT 企業リストのうち、OSS ベースの商材創出活動を実施する
可能性があると推測されるソフトウェア開発業に対象を絞り、アンケート調査対象を
抽出した。抽出したアンケート調査対象を表 4.1.2-6 に示す。
表 4.1.2-6 第 2 回アンケートにおける県内 IT 企業の対象業種と発送数
業態 業種 発送数
ソフトウェア開発 GIS 7
システムインテグレータ 43
委託開発 15
要員派遣(ソフトウェア) 3
ソフトウェア開発 91
通信関連設備 2
合計 161
(7)第 2回アンケート調査の実施日程
第 2回アンケートの調査日程を表 4.1.2-7 に示す。
表 4.1.2-7 アンケート調査日程
送付日程 回収完了日
第 2回アンケート 3月9日 3月12日
(8)第 2回アンケート調査回収結果
第 2 回アンケートは、ソフトウェア開発業に対し、第 1 回アンケート調査で回収し
たメールアドレスに送付した。送付数は 161 件で、うち、有効回答数が 79件となった。
有効回答数の業種内訳を表 4.1.2-8 に示す。
表 4.1.2-8 第 2 回アンケートにおける有効回答数の業種内訳
業態 業種 発送数
ソフトウェア開発 GIS 7
システムインテグレータ 43
委託開発 15
要員派遣(ソフトウェア) 3
ソフトウェア開発 91
通信関連設備 2
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
142
合計 79
(9)第 2 回アンケート結果の分析
第 2回アンケート結果の分析を以下に示す。
(A)県内 IT 企業の営業、技術者数
県内 IT企業の営業、技術者数を表 4.1.2-9 に示す。
表 4.1.2-9 県内 IT 企業の営業、技術者数
営業OSS 有知識
技術者
OSS 関連
有資格者
非 OSS
技術者
なし 7 7 11 5
1~5人 50 28 4 16
6~10 人 7 6 5 10
11~15 人 2 4 0 9
16~20 人 3 6 0 2
21~50 人 1 7 0 8
51~100 人 1 2 0 2
101 人以上 1 1 0 9
回答なし 7 18 20 23
(B)県内 IT 企業の OSS に関する認知度
県内 IT 企業の OSS に関する認知度に関する調査結果を表 4.1.2-10~表 4.1.2-12 に
示す。
表 4.1.2-10 「自由に使用・利用(改造を含む)・配布することができる」ことの認識度
OSS 活用企業 OSS 未活用企業
詳しく把握している 14 3
把握している 26 29
聞いたことがある 0 6
知らない 0 1
表 4.1.2-11 「ソースコードが公開されている」ことの認識度
OSS 活用企業 OSS 未活用企業
詳しく把握している 15 3
把握している 24 26
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
143
聞いたことがある 0 9
知らない 1 1
表 4.1.2-12 「複数のライセンスがあり、ライセンス毎に活用できる条件や範囲が異なる」ことの認識度
OSS 活用企業 OSS 未活用企業
詳しく把握している 6 1
把握している 26 18
聞いたことがある 4 13
知らない 4 6
この結果を見ると、県内 IT企業では、未だ OSS に関する知識の浸透が薄いことがわ
かる。
(B)県内 IT 企業が考える商用製品と OSS を比べた際のメリット・デメリット
既に OSS をビジネスに活かしている企業が考える商用製品と比べた OSS のメリット
を図 4.1.2-6 に、OSS をビジネスに活かしていない企業が考える商用製品と比べた OSS
のメリットを図 4.1.2-7 に示す。
また、OSS をビジネスに活かしていない企業が考える商用製品と比べた OSS のメリッ
トを図 4.1.2-8 に、OSS をビジネスに活かしていない企業が考える商用製品と比べた
OSS のデメリットを図 4.1.2-9 に示す。
図 4.1.2-6 既に OSS をビジネスに活かしている企業が考える商用製品と比べた OSS のメリット
0 10 20 30 40
1
OSSを活用することで開発スピードを向上させることができる(納期を短縮製品開発に活用できる
特定ベンダに依存していない
ソースコードを参照し、変更することができる
多くの種類のOSSが利用できる
低価格で顧客に提供できる
N=40
85.0%
80.0%
72.5%
62.5%
62.5%
50.0%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
144
図 4.1.2-7 OSS をビジネスに活かしていない企業が考える商用製品と比べた OSS のメリット
OSS を活用している企業、OSS を活用していない企業の双方が捉えているメリットを
比較してみると、「低価格で顧客に提供できる」、「ソースコードを参照し、変更するこ
とができる」、「多くの種類の OSS が利用できる」という 3 つの点を最大のメリットと
して見ていることがわかる。
全体的なメリットの捉え方を見てみると、OSS を活用している企業のほうが、より多
くの事項をメリットとして捉えていることがわかる。また、OSS を活用していない企業
は、知識だけでも認識することが可能な2つの点をメリットとして捉えている企業が
多いのに対し、OSS を活用している企業では、「低価格で顧客に提供できる」、「多くの
種類の OSS が利用できる」という実体験に基づくと推察されるメリットを高く評価し
ている。
なお、「その他」には、人材育成の材料にしやすい、という意見が多かった。
0 10 20 30
1
製品開発に活用できる
OSSを活用することで開発スピードを向上させることができる(納期を短縮
その他
多くの種類のOSSが利用できる
ソースコードを参照し、変更することができる
低価格で顧客に提供できる
69.2%
61.5%
46.2%
43.6%
30.8%
28.2%
N=39
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
145
図 4.1.2-8 既に OSS をビジネスに活かしている企業が考える商用製品と比べた OSS のデメリット
図 4.1.2-9 OSS をビジネスに活かしていない企業が考える商用製品と比べた OSS のデメリット
0 10 20 30
1
セキュリティホールに対するコミュニティの対応に不安がある
バグ改修や顧客からの要請対応に手間がかかる
バージョンアップの計画が把握しにくい
その他
緊急時の技術的サポートが得にくい
いつまで存続するかわからない
N=40
27.5%
37.5%
40.0%
60.0%
60.0%
70.0%
0 5 10 15 20 25
1
頻繁にバージョンアップされており開発スケジュールが設定しにくい
特定ベンダに依存していない
セキュリティホールに対するコミュニティの対応に不安がある
バグ改修や顧客の要請対応に手間がかかる
バージョンアップの計画が把握しにくい
その他
緊急時の技術的サポートが得にくい
いつまで存続するかわからない
N=39
40.0%
46.7%
53.3%
53.3%
56.7%
60.0%
66.7%
73.3%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
146
OSS を活用している企業は、OSS コミュニティの開発継続の不安定さをデメリットに
挙げており、また、技術サポートが得にくいと捉えている。
一方、OSS を活用していない企業も同じ項目をデメリットとして捉えているが、他の
点もあまり差がない割合でデメリットとして捉えており、このことから、知識先行で
“リスクあり”と捉えているように見受けられる。
(C)県内 IT 企業の OSS 活用のリスク面に対する考え
県内IT企業のOSS活用のリスク面に対する考えを図4.1.2-10、図 4.1.2-11に示す。
図 4.1.2-10 OSS を活用している企業の OSS 活用のリスクに対する考え
0 5 10 15 20
1
リスクがあり対応する術がない
特にリスクはない
リスクがあり対応する術を検討中
リスクはあるが他社と連携して対応できる
リスクはあるが自社で対応できる
N=40
5.0%
7.5%
22.5%
35.0%
40.0%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
147
図 4.1.2-11 OSS を活用していない企業の OSS 活用のリスクに対する考え
OSS を活用している企業は、4割が「リスクはあるが自社で対応できる」と回答して
いる。その他、4割弱が「リスクはあるが他社と提携して対応できる」と回答している。
OSS を活用していない企業は、5割弱が「リスクに対応する術を検討中」と回答してい
ることから、OSS を活用していない企業の 5割弱が OSS の活用を検討中であると断定で
きる。なお、図 4.1.2-12 にあるとおり、活用の興味は OSS を活用していない企業の 8
割弱に達しており、活用を検討する割合が今後さらに増加することが見込まれる。
図 4.1.2-12 OSS を活用していない企業の OSS に対する活用の興味
0 5 10 15 20
1
リスクがあり対応する術がない
リスクはあるがj自社で対応できる
特にリスクはない
リスクはあるが他社と連携して対応できる
リスクがあり対応する術を検討中
N=39
5.1%
7.7%
7.7%
25.6%
46.2%
興味がある
どちらとも言えない
興味がない
N=39
78.4%24.3%
2.7%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
148
(D)OSS を活用していない企業が OSS を活用しない理由と活用決断の要素
OSS を活用していない企業が OSS を活用しない理由を図 4.1.2-13 に、活用決断の要
素を図 4.1.2-14 に示す。
図 4.1.2-13 OSS をビジネスに活かしていない企業が OSS を活用しない理由
ここで挙げられている 4 大理由「緊急時の技術的サポートが得にくい」、「利用して
いる OSS がいつまで存続するかわからない」、「バグ改修や顧客の要請対応に手間がか
かる」、「頻繁にバージョンアップされており開発スケジュールが設定しにくい」とい
う点は、(B)で挙げた対処策などで解消できるものである。
0 5 10 15 20
1
商用パッケージを利用しないため売上高が下がる
自社の商用パッケージと競合する
バージョンアップの計画が把握しにくい
コミュニティの開発計画と顧客の開発要請が合わない
顧客が自らソースコードを書き換えてしまう可能性がある
トータルで顧客のIT投資額が高くなる懸念がある
セキュリティホールに対するコミュニティの対応に不安がある
その他
頻繁にバージョンアップされており開発スケジュールが設定しにくい
バグ改修や顧客の要請対応に手間がかかる
利用しているOSSがいつまで存続するかわからない
緊急時の技術的サポートが得にくい
N=39
0%
0%
2.6%
5.1%
5.1%
12.8%
17.9%
20.5%
20.5%
25.6%
30.8%
43.6%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
149
図 4.1.2-14 OSS をビジネスに活かしていない企業の活用決断要素
活用決断要素としては、OSS を扱うことができる技術者の増加が 1番目に挙げられて
おり、まさに OSS 技術者の醸成が活用しない理由を解消するために必要不可欠な要素
であるといえる。また、2 番目には、「社内における OSS に関する意識向上・改善」が
挙げられているが、これについては、企業幹部に対する OSS の正しい認知の醸成が必
要不可欠である。
(E)OSS を活用している企業の OSS 活用方法
OSS を活用している企業の OSS 活用方法を図 4.1.2-15 に示す。
図 4.1.2-15 OSS を活用している企業の OSS 活用の方法
0 10 20 30 40
1
OSSをカスタマイズして活用
商材に組み込んで活用
間接的に活用
N=40
27.5%
62.5%
77.5%
0 5 10 15 20 25
1
その他
現在以上の活用事例の増加
ユーザニーズの高まり
サポートの充実(商用・非商用問わず)
社内におけるOSSに関する意識向上・改善
OSSを扱うことができる技術者の増加
2.6%
33.3%
35.9%
38.5%
38.5%
51.3%
N=39
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
150
間接的に活用(教育サービス、システム構築での活用など)している企業が、OSS を活
用している企業の 8割弱に達しており、OSS を活用する企業においては、システム構築
などで定常的に OSS が活用されていることが推察される。また、6割強が OSS を商材化
している、もしくは自社のオリジナリティーを高めるための材料として活用している。
このことから、OSS を活用している企業のうち、7割強が OSS を活用するスキルを持ち
合わせているが、うち、6割強は、ソースコードを読み、改変できる技術力を有してお
り保守も実施できるものと推察される。OSS をカスタマイズして活用していると回答し
ている 3割弱の企業は、開発コミュニティに参加しているようである。
(F)OSS を活用している企業における著作権、ライセンスに関する考慮状況
OSS を活用している企業における著作権、ライセンスに関する考慮状況を図 4.1.2-16
に示す。
図 4.1.2-16 OSS を活用している企業におけるライセンスに関する考慮状況
OSS を活用している企業においては、OSS を活用する際にライセンスに関する考慮を
行っていると 6割弱が回答している。考慮内容は下記のとおり。
・顧客に著作権やライセンスについて事前に説明する
・作りこんだ機能のソース公開
・ライセンスに抵触しないビジネスを実施している。主にはサービスビジネス中心に
事業を実施している
・新たな OSS を採用する際に適用されているライセンスを確認(改編は行っていないた
考慮している
考慮してない
N=25
56.0%44.0%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
151
め独自でソースコード公開は行っていない)
・パッケージを作成する際に OSS のライブラリなどが著作権侵害やライセンス違反に
ならないよう、パッケージに同封する OSS のライセンスを手動でチェックしている
・Apache License および LGPL の利用に限定している
・OSS のインストールを代行する形態のサービスを提供
・ライセンス状況を熟読し、ライセンス範囲内で活用
・顧客にソースコード公開の意思を確認し、適切なライセンスの OSS を提案している
・ライセンスを調査後、著作者などに直接交渉を行い、対応している
このことから、OSS を活用している企業でライセンスに関する考慮をしている企業にお
いても、ソースコードに宣言されているライセンス憲章については、考慮されている
もののソースコードそのものの著作権違反については、考慮が行き届いていないこと
が推測される。
また、著作権、ライセンスに関する考慮をしていない企業が 4 割強存在するが、こ
れについては、各企業において、「OSS を活用する上での著作権、ライセンスに関する
考慮の必要性」の浸透を図る、ソースコードレベルで著作権違反に対する調査を実施
するなど、何らかの方法で対策を講じていく必要がある。
なお、県内 IT 企業が活用している OSS を以下に示す。
Linux(33)、PostgreSQL(31)、Apache(31)、MySQL(29)、PHP(29)、Tomcat(20)、
Perl(18)、 OpenSSL(18)、 Samba(18)、 Sendmail(17)、 Mozilla Firefox(16)、
Postfix(15)、qmail(15)、VNC(14)、Squid(12)、Struts(12)、Ruby(11)、
Open Office.org(10)、Xen(10)、Webalizer(9)、Mozilla Thunderbird(8)、Webmin(8)、
Pukiwiki(8)、Spring(7)、Seasar2(7)、XOOPS(7)、Analog(7)、SpamAssassin(6)、
Snort(6)、CramAV(5)、Phython(5)、Ruby on Rails(5)、Nagios(5)、Tripwire(4)、
JBOSS(3)、Zope(3)、OpenPNE(3)、GIMP(3)、SugarCRM(2)、NET-SNMP(2)、Hinemos(1)、
Apache Geronimo(1)、Plone(1)、osCommerce(1)、Asterisk(1)、Geeklog(1)、bind(1)、
radius(1)、OpenLDAP(1)、delegate(1)、EC-Cube(1)、Zencart(1)、Moodle(1)、
MRTG(1)、Swatch(1)、Aipo4(1)、Eclipse(1)、WordPress(1)、NetCommons(1)、
PodeRosa(1)、CheckStyle(1)、FindBugs(1)、Maven(1)、Jmeter(1)、Ibatis(1)、
Hibernate(1)、Hudson(1)
※()は、使用している企業数
※ライセンスの内容上、qmail は厳密には OSS ではない
(G)OSS を活用している企業における技術的な後ろ盾(開発・保守)の必要度
OSS を活用している企業における技術的な後ろ盾(開発・保守)の必要度を図 4.1.2-17
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
152
に示す。
図 4.1.2-17 OSS を活用している企業における技術的な後ろ盾(開発・保守)の必要度
この結果を見ると、OSS を活用している企業でも後ろ盾が必要だと考えている企業は、
9割に達している。この理由として、以下の事項を挙げている。
・予防措置(技術的に対応できない場合や緊急の場合)
・OSS のサポート(障害などの原因を特定できない、Update 情報、脆弱性情報などの
入手のため)
・OSS に対する知識・技術不足の補完
一方、必要だと思わない企業は、「自社内で対応すべき」、「保守も含めサポート可能
な体制がとれる OSS を選択すべき」、「ソースコードが公開されているので自社内で解
決可能」と回答している。
必要だと考えている企業の技術的な後ろ盾(開発・保守)の有無は、図 4.1.2-18 に示
すとおり、約 4割にすぎず(技術的な後ろ盾になっているものとしては、属人的な「コ
ミュニティ」、「知人」との回答が割弱、「県外 SI 企業」、「ベンダ」が約 2 割となって
いる)、技術的な後ろ盾(開発・保守)を有していない 5 割強の企業は、OSS サポートに
関して、全ての企業が技術的な後ろ盾が欲しいと回答している。
必要だと思っている
必要だと思わない
N=40
90.0%
10.0%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
153
図 4.1.2-18 必要だと思っている企業の技術的な後ろ盾(開発・保守)の有無
(H)県内 IT 企業の主な販路
OSS を活用している企業の主な販路を図 4.1.2-19 に、OSS を活用していない企業の
主な販路を図 4.1.2-20 にそれぞれ示す。
※ユーザのうち、①、②の順で比率が高い
図 4.1.2-19 OSS を活用している企業の主な販路
既に有している
有していない
55.6%44.4%
N=40
0 5 10 15 20 25 30
1
ベンダー
県内SI企業
県外SI企業
ユーザー
N=40
8.9%
25.0%
32.5%
67.5%
①官公庁・外郭団体向け
②サービス業
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
154
※ユーザのうち、①、②、③の順で比率が高い
図 4.1.2-20 OSS を活用してない企業の主な販路
OSS を活用している企業、OSS を活用していない企業の主な販路を比較すると、双方
の比率には特徴的な差がないことがわかる。ただし、両者ともに、ユーザの割合が突
出しており、このユーザのうち、官公庁・外郭団体向けの比率が最も高く、次にサー
ビス業が続いている。これは、県内 IT企業のユーザが県内に多いことを表しているも
のと考えられる。なお、OSS を活用している企業のユーザの比率が 1 割程度高いのは、
官公庁・外郭団体の OSS 関連の採用が多いことが理由として推察される。
また、アンケートでは、国内だけではなく海外の販路に関しても用意したが、結果
として、OSS を活用している企業では、現時点で、ベトナム、カンボジア、インドに販
路を有する企業が 3 社存在し、また、今後、米国、ヨーロッパ各国、アジア各国、香
港への進出を計画している企業が 4社存在することがわかった。
一方、OSS を活用していない企業では、販路を有している企業はなく、進出を計画し
ている企業が 2社程度存在している状況であることがわかった。
この結果だけでは断定することはできないものの、OSS を活用している企業のほうが、
グローバルに視野を向けている傾向が高いものと推察する。
(I)県内 IT 企業のプロモーション手段
県内 IT企業のプロモーション手段について、コーポレートプロモーションと製品プ
ロモーションの 2つに分け、アンケートした結果を図 4.1.2-21~図 4.1.2.24 に示す。
0 5 10 15 20 25
1
ベンダー
県外SI企業
県内SI企業
ユーザー
①官公庁・外郭団体向け サービス業向け
②商業向け
③教育,学習支援向け
N=39
7.7%
20.5%
33.3%
56.4%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
155
図 4.1.2-21 OSS を活用している企業のコーポレートプロモーション手段
図 4.1.2-22 OSS を活用していない企業のコーポレートプロモーション手段
全般的に、県内 IT企業のコーポレートプロモーションは、手段の内容を鑑みると営
業アプローチの割合が高い。
OSS を活用している企業は、営業アプローチとホームページによるアプローチの割合
が高いが、OSS を活用していない企業は、営業アプローチが突出しており、ホームペー
ジの割合は OSS を活用している企業が 6割弱なのに対し、2割強にとどまっている。
OSS を活用している企業は、営業アプローチの割合は、OSS を活用している企業のほ
0 5 10 15 20
1
その他
イベント開催
イベント参加
ホームページ
特に実施していない
口コミ
営業アプローチ
N=390%
7.7%
15.4%
25.6%
28.2%
30.8%
48.7%
0 10 20 30 40
1
その他
特に実施していない
口コミ
イベント開催
イベント参加
ホームページ
営業アプローチ
N=40
5.0%
17.5%
17.5%
27.5%
30.0%
57.5%
72.5%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
156
うが約 1.5 倍高く、特に実施していない割合と口コミの割合が、OSS を活用している企
業のほうが約 1割低い。この他の項目では、イベント開催の割合は、OSS を活用してい
る企業のほうが 2割高く、また、イベント参加およびホームページの割合は、OSS を活
用している企業のほうが 2倍以上高い。
以上のことから、OSS を活用している企業のほうが OSS を活用ていない企業に比べ、
コーポレートプロモーションが活発であることがわかる。
なお、イベント関連が活発なのは、OSS を活用している企業の特徴であるといえる。
図 4.1.2-23 OSS を活用している企業の製品プロモーション手段
図 4.1.2-24 OSS を活用していない企業の製品プロモーション手段
0 5 10 15 20 25
1
その他
イベント参加
イベント開催
口コミ
特に実施していない
営業アプローチ
ホームページ
N=40
5.0%
15.0%
20.0%
22.5%
25.0%
40.0%
50.0%
0 5 10 15 20
1
その他
イベント開催
イベント参加
ホームページ
口コミ
特に実施していない
営業アプローチ
N=390%
2.6%
5.1%
15.4%
17.9%
41.0%
48.7%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
157
製品プロモーション手段については、両者で対照的な差が出ている。
OSS を活用している企業は、ホームページでのプロモーションの割合が 5割、続いて
営業アプローチが 4割となっているのに対し、OSS を活用していない企業は、営業アプ
ローチが 5 割弱、これに続いて、特に実施していない割合が、4 割となっている。OSS
を活用していない企業の状況は、下請け業務の受託活動の典型と想起させる内容とな
っており、これは、OSS を活用していない企業がビジネスの強みの回答内容にも現れて
いる(ビジネスの強みとして約 6割弱の企業が「受託開発(SI)」、「技術者派遣」と回答
する企業が約 6割強と回答)。
(J)県内 IT 企業の製品開発における許容投資額
県内 IT 企業の製品開発における許容投資額を図 4.1.2-25、図 4.1.2-26 に示す。
この結果を見る限り、県内 IT 企業が許容できる製品開発投資額は非常に限られてい
ることがわかる。
図 4.1.2-25 OSS を活用している企業が考える製品開発許容投資額
図 4.1.2-26 OSS を活用していない企業が考える製品開発許容投資額
3人月(120万相当)以下
10人月以上(400万以上)
4~5人月(160~200万相当)
6~9人月(240~360万相当)
N=40
65.0%25.0%
7.5% 2.5%
3人月(120万相当)以内
4~5人月(160~200万相当)
6~9人月(240~360万相当)
10人月以上(400万以上)
N=39
96.7%26.7%3.3% 3.3%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
158
4.1.3 まとめと考察
第 1 回アンケート分析結果および第 2 回アンケート分析結果のまとめと考察を以下に示
す。
(A)県内 IT 業界全体での OSS 関連状況のまとめと考察
OSS および関連製品使用中の企業数が、有効回答数中 64 社存在し、うち、19 社は
100 万円以上の OSS 関連売上がある(中でも 11 社は 1,000 万円以上の売上がある)が、
45 社は、OSS をビジネスに活かせていない(収益につなげられていない)か、もしくは
社内に限定した使用などにとどまっているものと推察される。また、64 社の中でも、
自社で OSS の活用や保守ができる企業が 34 社あり、他の 30 社は、①OSS の保守サ
ービスの活用、②知的所有権に関するサービス、③OSS の導入・構築・サービス、④
技術コンサルティング・サービスなどの OSS 関連サービスを活用している。なお、ほ
ぼ経費をかけずに OSS が活用できている企業が 43 社ある。
一方、OSS を活用していない企業数は、有効回答数中 36 社存在し、活用しない主な
理由は、高い順に①必要なものが見つからない、②実績がないので不安、③サポート
できるか不安、となっている。
県内 IT 業界では、OSS ビジネスの実現に向けて、人材育成面、技術・保守サポート
面での不安要素を解消するための支援サービスを求めており、また、OSS ビジネスの
実現に必要と考えるスキルは、システムインテグレーションにおける上流工程のスキ
ルが上位を占めている。このことから、IT 業界のハイアラーキにおける一次、二次の
業務レベル、いわゆるプライムコンストラクターになれる、もしくはレベルの向上を
果たしたいという願望と県内 IT 業界のウィークポイントが読み取れる。
(B)県内 IT 企業での OSS 関連状況のまとめと考察
県内 IT 企業が考える商用製品と OSS を比べた際のメリット・デメリットとしては、
OSS を活用している企業、OSS を活用していない企業ともに、「低価格で顧客に提供で
きる」、「ソースコードを参照し、変更することができる」、「多くの種類の OSS が利用
できる」という 3つの点を OSS 活用の最大のメリットとして捉えている。
OSS を活用している企業のほうが、より多くの事項をメリットとして捉えており、特
に「低価格で顧客に提供できる」、「多くの種類の OSS が利用できる」という実体験に
基づくと推察されるメリットを高く評価しているが、OSS コミュニティの開発継続の不
安定さおよび技術サポートの得にくさを抱いている。なお、この点については、開発
コミュニティの開発活動に参加することで軽減できる可能性が高い。既に参加してい
る企業は、日本でも見受けられ、これらの企業では、活用する OSS の開発プロジェク
トの状況を把握しており、また、ソースコードを常に参照していることから、OSS を活
用する上での不安は抱いていない。OSS コミュニティの開発継続の不安定さなどの不安
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
159
要素の解消には、県内 IT企業が活用する OSS の開発コミュニティの開発活動への参画、
ユーザコミュニティなどの活動に参画し情報収集を行うとともに、技術蓄積や技術の
研鑽、オープン・スタンダードに対応している OSS を選択し他の OSS での代替が可能
な状況を確保しておくことなど、複数の対処策が存在する。
また、OSS を活用している企業は、4 割が「リスクはあるが自社で対応できる」、他
の 4 割弱が「リスクはあるが他社と提携して対応できる」と考えている。
OSS を活用している企業のビジネスについては、間接的に活用(教育サービス、シス
テム構築での活用など)している企業が 8割弱に達しており、システム構築などで定常
的に OSS が活用されていることが推察される。さらに 6割強が OSS を商材化している、
もしくは自社のオリジナリティーを高めるための材料として活用しており、7 割強が
OSS を活用するスキルを持ち合わせているが、6割強は、ソースコードを読み、改変で
きる技術力を有しており、保守も実施できるものと推察される。
OSS を活用する際にライセンスに関する考慮については、6割弱が行っているが、ソ
ースコードに宣言されているライセンス憲章については、考慮されているもののソー
スコードそのものの著作権違反については、考慮が行き届いていないことが推測され
る。また、著作権、ライセンスに関する考慮をしていない企業が 4 割強存在するが、
これは、各企業において、「OSS を活用する上での著作権、ライセンスに関する考慮の
必要性」の浸透を図る、ソースコードレベルで著作権違反に対する調査を実施するな
ど、何らかの方法で対策を講じていく必要がある。
OSS 活用ビジネスを遂行していく上で後ろ盾が必要だと考えている企業は、OSS を活
用している企業の 9 割に達しており、その理由として、「予防措置(技術的に対応でき
ない場合や緊急の場合)」、「OSS のサポート(障害などの原因を特定できない、Update
情報、脆弱性情報などの入手のため)」、「OSS に対する知識・技術不足の補完」を挙げ
ている。一方、必要だと思わない企業は、自社内での対応やサポートできる OSS の吟
味、という点を重視している。ただし、必要だと考えている企業で実際に技術的な後
ろ盾(開発・保守)を有しているのは、約 4割にすぎず(技術的な後ろ盾になっているも
のとしては、属人的な「コミュニティ」、「知人」との回答が 5 割弱、「県外 SI 企業」、
「ベンダ」が約 2割となっている)、技術的な後ろ盾(開発・保守)を有していない 5割
強の企業は、OSS サポートに関して、全ての企業が技術的な後ろ盾が欲しいと考えてい
る。
一方、OSS を活用していない企業は、知識だけでも認識することが可能な点をメリッ
トと捉えている企業が多く、同じように知識先行で“リスクあり”と捉えているよう
に見受けられるが、うち、5割弱がOSS活用のリスクに対応する術を検討中としており、
さらに、OSS を活用していない企業の 8割弱が OSS の活用に興味を抱いており、活用を
検討する割合が今後さらに増加することが見込まれる。
OSS を活用する決断要素としては、OSS を扱うことができる技術者の増加と企業幹部
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
160
に対する OSS の正しい認知の醸成が必要不可欠な要件となっている。
県内 IT 企業の主な販路としては、OSS を活用している企業、OSS を活用していない
企業の間に特徴的な差がないが、両者ともに、ユーザの割合が突出しており、この中
で特に官公庁・外郭団体向けの比率が最も高く、次にサービス業が続いている(県内 IT
企業のユーザが県内に多いことを表しているものと考えられる)。なお、OSS を活用し
ている企業のユーザの比率が 1 割程度高いのは、官公庁・外郭団体の OSS 関連の採用
が多いことが理由として推察される。なお、OSS を活用している企業では、現時点で、
ベトナム、カンボジア、インドに販路を有する企業が 3社存在し、また、今後、米国、
ヨーロッパ各国、アジア各国、香港への進出を計画している企業が 4 社存在するが、
OSS を活用していない企業では、海外に販路を有している企業はなく、進出を計画して
いる企業がわずか 2社程度であった。この結果から、断定することはできないものの、
OSS を活用している企業のほうが、グローバルに視野を向けている傾向が高いものと推
察する。
さらに、県内 IT企業のプロモーション手段については、全般的に、コーポレートプ
ロモーションの手段として、営業アプローチの割合が高い。OSS を活用している企業の
方が OSS を活用していない企業に比べ、コーポレートプロモーションが活発であり、
特に、OSS を活用している企業では、OSS ビジネスの特徴であるイベント関連でのプロ
モーションが活発である。製品プロモーションについては、両者で対照的な差があり、
OSS を活用している企業は、ホームページでのプロモーションの割合が最も高く、続い
て営業アプローチとなっているのに対し、OSS を活用していない企業は、営業アプロー
チの割合が最も高く、続いて特に実施していないという割合が高くなっている。OSS を
活用していない企業の状況は、下請け業務の受託活動の典型のように想起させる内容
となっており、OSS を活用していない企業がビジネスの強みは、約 6割弱の企業が「受
託開発(SI)」、「技術者派遣」であるとしており、これを裏付けている。
4.2 OSS活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容
上記の県内 IT企業の OSS 活用ビジネスを展開するために整備すべき条件および整備内容
に関しても、上記アンケートおよびヒアリング作業を通じて情報収集と分析を行う
なお、県内 IT 企業を対象として、OSS 活用ビジネスにおける人材育成に関する意識や課
題の認識など、人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容に関するアンケート調査
を効率性の観点から 4.1 とともに実施した。
結果を以下に示す。
4.2.1 アンケート調査結果と分析
県内 IT 企業の人材育成方法を図 4.2.1-1、図 4.2.1-2 に示す。
この結果を見ると、人材育成の方法が、社内独自研修と ITOP に偏っていることがわかる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
161
図 4.2.1-1 OSS を活用している企業の人材育成方法
図 4.2.1-2 OSS を活用していない企業の人材育成方法
4.2.2 まとめと考察
アンケートの分析・考察結果を踏まえ、OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うため
に整備すべき条件・整備内容に関する考察を以下に示す。
県内 IT 企業の人材育成方法は、割合的に社内独自研修と ITOP に大きく偏っているが、
社内独自研修の内容は定かではないものの ITOP は座学中心のカリキュラムであり、OSS を
0 10 20 30 40
1
その他
県内のOJT
APITT
特に実施していない
県外のOJT
ITOP
社内独自研修
N=40
10.0%
12.5%
12.5%
15.0%
30.0%
45.0%
75.0%
0 5 10 15 20 25
1
その他
APITT
県内のOJT
県外のOJT
特に実施していない
ITOP
社内独自研修
N=39
2.6%
7.7%
15.4%
17.9%
23.1%
35.9%
53.8%
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
162
扱うことができる技術者の増加を目指すのであれば、座学ではなく、コミュニティへの参
加などの検討など、実践を取り入れる形で人材育成の方法を見直す必要がある。
また、県内 IT 企業では、未だ、OSS に関する知識の浸透が薄いことから、特に企業の経
営幹部向けに OSS に関する認知度向上のための取り組みを図っていく必要がある。
なお、これらの取り組みは、OSS を活用していない企業が OSS を活用する決断を促す効果
をもたらすものと考える。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
163
第5章 OSS を活用したインターンシップの可能性調査
本章では、県内大学の IT 分野におけるインターンシップ制度の整備状況と県内企業に対
しインターンシップ経験者の採用意向を調査した結果を示す。
5.1 県内大学の IT分野におけるインターンシップ制度の整備状況
県内の大学を対象とし、IT 分野に関連したインターンシップ制度の整備状況について、
公開情報などを参考としつつ、担当教官もしくは担当係へのヒアリング調査を実施し、よ
り詳細な情報を収集する。
5.1.1 インターンシップ制度調査の対象校
インターンシップ制度の調査対象を表 5.1.1-1 に示す。
表 5.1.1-1 インターンシップ制度調査対象
名称
琉球大学
沖縄国際大学
名桜大学
沖縄工業高など専門学校*1
*1:一般的に短大の扱い
5.1.2 ヒアリング調査の実施
(1)ヒアリング調査内容
ヒアリング調査内容を図 5.1.3-1 のとおり、定める。
ただし、ヒアリングを実施する上で、より詳細な分析につながりそうな内容がヒアリ
ングできる場合は、この調査内容にとどまらず、ヒアリング内容を柔軟に拡張するもの
とする。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
164
図 5.1.3-1 ヒアリング内容
(2)ヒアリング手順
ヒアリング調査手順を以下に示す。
① 琉球大学におけるヒアリング対象者の探索およびアポイントメント
② 沖縄国際大学におけるヒアリング対象者の探索およびアポイントメント
③ 名桜大学におけるヒアリング対象者の探索およびアポイントメント
④ 沖縄工業高専におけるヒアリング対象者の探索およびアポイントメント
⑤ 琉球大学へのヒアリング調査
⑥ 沖縄国際大学へのヒアリング調査
⑦ 名桜大学へのヒアリング調査
・ インターンシップ制度の有無
・ インターンシップ制度の創設時期
・ 現状におけるインターンシップの参加学生数および年次
・ インターンシップ受け入れ先の企業種別
・ インターンシップの期間
・ インターンシップ制度による学生派遣に対する興味
・ インターンシップ制度の利用促進策
・ インターンシップ受入企業への要望
・ 学内での IPA OSS カリキュラムによる IT 教育支援
・ 学内における OSS に対する取り組み ・ 学内における OSS を教えられる講師の数
・ 現行インターンシップ制度に対する学生の興味
・ 学生が興味を持つインターンシップ制度の内容と形態
・ インターンシップ制度改善の可能性
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
165
⑧ 沖縄工業高専へのヒアリング調査
(3)ヒアリング調査結果
ヒアリング調査結果を表 5.1.3-2 に示す。
表 5.1.3-2 ヒアリング調査結果
琉球大学 沖縄国際大学 名桜大学 沖縄工業高専
インターンシッ
プ制度の有無
あり あり あり あり
インターンシッ
プ制度の創設時
期
1998 年以前 2001 年頃 1997 年 2006 年頃
現状におけるイ
ンターンシップ
の参加学生数お
よび年次
20 名以上
2、3年次が中心
200 名強
3 年生中心で実施
されている(2 年
生、4 年生はレア
ケース)
100 名程度
3 年次が中心で
4 年次はレアケ
ース(必修科目)
160 名(全学生)
4年次 (必修科
目)
インターンシッ
プ制度での取得
単位数
1 単位(通常講座
の半分)
夏季が多い
2 単位:60 時間以
上 (1 週 間 ~ 10
日)、4 単位:120
時間以上(2 週間
以上)※1 単位当
たり 30 時間とな
っている
基礎編で 2 単位
(通常科目と同
など)
夏季集中講座 4
単位
2 単位
インターンシッ
プ受け入れ先の
企業種別
情報通信業(OSS
関連業務もあり)
・ほぼ全ての業種
が対象であり、IT
系だけではない
・IT 系は 3割程度
・また、県内企業
が 9割
・IT 関連、流通
業、公務、番組
制作、ツアー会
社、病院関係、
製造業など
・ほぼ 100%県内
・製造業、電気業、
情報通信業、学術
研究、教育機関、
公務、番組制作
業、新聞社
・県内:5.5、県
外:4.5 の割合
インターンシッ
プの期間
1~4週間 2~3週間 2 週間(事前講
義まで換算する
と 15 週間)
2~4週間
インターンシッ
プ制度による学
生派遣に対する
興味
あり あり あり あり
インターンシッ
プの前後で学生
は大分成長する
インターンシッ
プ制度の利用促
進策
インターンシッ
プ制度の利用促
進策はない
学生からの要望
が発生した場合、
大学事務が企業
との調整を行い、
受け入れ条件が
合致したら実施
・受入企業の紹介
サービスの整備
(どこ企業がなに
をやっているの
か把握できてお
らず、現状は先生
の 個 人 的 な 知
識・人脈に依存し
ている)
・必修
・金融特区、情
報特区構想の中
で学生と企業の
ニーズのマッチ
ングを図るた
め、3 年次を対
象に、県が仲介
している
・必修
・受け入れ実施に
おける資金補助
制度(宿泊費、旅
費、日当などの補
助制度があると
うれしい)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
166
する。企業発のイ
ンターンシップ
希望は事務が先
生と調整する
・受入企業には、
甘やかさず、より
厳しく対応して
いただくことを
望む
インターンシッ
プ受入企業への
要望
IT 関係の仕事が
どういうものな
のか、学生が認識
できる内容にし
てほしい(OJT 形
式を希望)
特になし 特になし ・学生に達成感が
感じられるもの
(目に見える成果
があるとうれし
い)
・担当者が業務で
忙しくて、何もし
てくれない企業
もあったので、イ
ンターンシップ
担当者をつけて
ほしい(インター
ンシップ先で県
外が多いのは、受
入企業側の制度
が充実している
から)
学 内 で の IPA
OSS カリキュラ
ムによる IT 教
育支援
・独自のカリキュ
ラムで教育して
いる
・CCNA を利用して
いる(カスタマイ
ズしている)
・IPA の OSS カリ
キュラムがある
ことは認識して
いなかったが、今
後取り組みたい
・先生が技術の進
歩についていけ
ないので、教員向
け教育があると
よい。
・独自のカリキ
ュラムで教育し
ている
・IPA のカリキュ
ラムの1/3の科目
は、既に実施して
いる
学内における
OSS に対する取
り組み
1 年次は、OS X 環
境下で、ダービ
ー、Linux, UNIX,
E-Max,Tex、2 年
次は、Posix-API,
Linux。OS X,
Linuxベースの PC
クラスタ、3 年次
は、OSS のソース
コードを読む実
習(①OSS のソー
スコードを読む
準備を 1 ヶ月、②
集中して 3 日読
む、③読んだ後の
感想を Blog に残
・授業では、1 年
次から Java を利
用しており、ゼミ
な ど で は 、 VB,
CSS, HSP, PHP,
Ruby を使う場合
もある(Web アプ
リケーションで
の利用が一般的)
・Flash に代わる
OSS を探している
・授業では、2、
3年次はJavaプ
ログラミング
を、4 年次の演
習では Python
をセロから勉強
する
・3、4年次には、
Linux の概要お
よび活用、管理
を実習する
・Linux の運用と
Web サーバ開発を
講義で行ってい
る
・プログラミング
には、gcc を利用。
・Open Office.org
のシェアが 50%を
超えたら、使いた
い(授業によって
は、Windows 上で
なければ動かな
いソフトがある
から)
・卒業研究では、
組み込みがテー
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
167
す)と Web サービ
スを立ち上げる
実践型の取り組
みを実施してい
る
マの場合では OSS
のソースまで読
み込む場合があ
る
学内における
OSS を教えられ
る講師の数
6 名程度 4、5名程度 4、5名程度 15 名(60 名中)程
度
現行インターン
シップ制度に対
する学生の興味
・学生個人による ・学生の自由選択
でインターンシ
ップを実施して
いる。中心となる
3 年生は、1400 人
在籍している
・4 月に受入れ可
能企業の調査・調
整を実施し、5 月
にインターンシ
ップ希望者向け
説明会に 400人強
が自主参加する
そのうち、面接が
可能となった学
生は 300 人弱。実
際にインターン
シップを実施し
た学生は 200人強
・学生のインター
ンシップへの意
識、人気は高い
・必修 ・必修
学生が興味を持
つインターンシ
ップ制度の内容
と形態
・学生の自由選択
になっている
・単位制度に特徴
がある
・夏休みを利用し
ての実施が多い
・IT 業界に対して
は、ジョブシャド
ーではなく実際
にプログラミン
グなどの実作業
を行うことが良
いと学生も思っ
ている
・必修科目とな
っていて、分野
は学生が選択で
きる
・これまで座学
で学んだものが
活かせるのかど
うなのかを試す
試金石と考えて
いる
・学科設置も他
大学とバッティ
ングしないよう
に設計している
・インターンシ
ップ制度も沖縄
で一番はじめに
やり始めたの
で、他大学と比
較すると、行き
卒業研究で OSS活
用推進センター
などの組織と連
携することは十
分にありえる
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
168
先のバリエーシ
ョンに特徴があ
る。
インターンシッ
プ制度改善の可
能性
・可能性はある ・受入れ企業が不
足しているので、
開拓する必要が
ある
入れ企業が増え
さえすれば、イン
ターンシップは
さらに活性化す
る
・これまで徐々
に改善を加えて
きているが、現
状では制度を変
える予定はない
・制度を変える予
定はない
その他 ・学生部から就職
状況システム構
築を受託し、生徒
で開発している。
・Linux ベースの
PC ク ラ ス タ
(Linux, Xen 利
用)180 台の管理
を学生が実施し
ている
・県外・海外から
講師を招いてセ
ミナーを実施し
てほしい
・学生がグループ
で外の仕事を引
き受けることが
できるような橋
渡し的存在にな
ってほしい(元締
め的な役割が理
想)
・インターンシッ
プで、実務的なも
のを体験させて
ほしい。
・アルバイトを兼
ねて、県外にイン
ターンできる仕
組みを作ってほ
しい
・プログラムコン
テストの実施を
希望
・学生をアジアの
企業にインター
ンシップしたい
・沖縄の OSS ポー
・起業しようとし
ている学生がい
るので、学生ベン
チャーが OSS活用
推進センターを
利用できる方法
を考えてもらい
たい
・アジア企業への
インターンシッ
プに興味がある。
・Windows 系ソフ
トはライセンス
料金が高いため、
Linux 系に移行し
ていきたい。
・OSS を利用する
不安材料は、マニ
ュアルが Webベー
スであること。
・学校の先生は情
報利用に関して
保守的であるた
め、新しい技術は
導入したがらず、
なれた環境から
離れたくない
・就職率アップ
に役立っている
・他の強化に時間
をとられてしま
い、学生における
プログラミング
の優先順位が低
い
・授業でプログラ
ミングをすると
やらされ感があ
り、嫌やになって
しまうので、必要
に迫られるよう
な環境条件が必
要
・OSS 活用推進セ
ンターで、OSS に
関して共同研究
に取り組む可能
性は十分にある。
・学校の中だけで
はなく、実務関係
で協力していき
たい(1、2 年生の
見学会とか)。
・非常勤で学生に
刺激を与えられ
るような講義を
講師にしてもら
いたい
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
169
タルサイトを立
ち上げてほしい
・OSS の啓蒙活動
をしてほしい
・沖縄発の OSS プ
ロジェクトを立
ち上げてほしい
・インターンシッ
プに参加する人
にメリットがあ
るような形が望
ましい(例えば、
資格取得など)
(4)ヒアリング調査結果の分析
ヒアリング調査結果の分析を以下に示す。
・各大学とも夏休みなどまとまった時期にインターンシップを実施することが多く、
期間は 1週間から 1ヶ月と幅広い。
また、学校毎に修得単位制度が異なっており、インターンシップの期間により修得
単位の種類と量が多い学校は、同学校の参加学生が他の学校と比較し飛び抜けて多
いことから、学生のインターンシップの参加意向の高さの要因のひとつとなってい
るものと推察する。
・インターンシップの参加年次は 3 年次(高専は 4 年次)が多く、ほとんどの学校でイ
ンターンシップ先を学生が選定するようになっている(「インターンシップの前後で
学生は大分成長する」という声もある)。インターンシップの参加は、就職活動への
心理的起因や前項目の状況からすると単位取得の駆け込み需要などあるのではない
かと推察される。
また、インターンシップ先はバラエティに富んでいるが、いずれの学校も IT関係が
含まれている。
さらに、インターンシップ制度は、学生の就職活動の一環として運用されている向
きもある。
・インターンシップ受入企業の紹介サービスの整備をほとんどの学校が望んでいる。
理由としては、「教育機関として企業が何をやっているのか把握できておらず、適切
なインターンシップ先が探索できない」ことや「インターンシップの受入れ企業が不
足しており、受入れ企業が増えさえすれば、さらに活性化する」と考えていること、
「インターンシップ先は、先生の人脈に依存していることが多い」ことから形骸化す
る、などが挙げられる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
170
・インターンシップの内容としては、総じて、実務に関われる内容を望んでいる。
特に、授業でプログラミングをするとやらされ感があり、嫌になる傾向が高いため、
必要に迫られるような環境として、インターンシップの場が求められている。
一部では、インターンシップに参加する人にメリットがあるような形が望ましい(例
えば、資格取得など)との声もあった。
5.1.3 インターンシップ制度の整備状況に関する分析と考察
現状のインターンシップ制度には、次のような問題点・課題が内在していることが、ヒア
リング調査結果から判明した。
・インターンシップ制度の学生視点での価値化が図られていない
インターンシップで取得できる単位が大学間でまちまちであるが、学生の視点に
立ってみれば、基本単位である 2 単位以上が取得できなければ、講座としての魅
力がなく、純粋にインターンシップそのものの価値が修得するか否かを左右する
のではないかと推察する。実際、インターンシップによる単位修得が1単位の学
校は、インターンシップの修得者が非常に少なく、学生にとって価値のある 2 単
位、4単位の学校は、修得者が非常に多い。
・学校におけるインターンシップ受入先探索が難しい
インターンシップ受入先の探索は、先生毎のコネクションに依存していることが
わかる。これは、受け入れ先の固定化や広がりを期待するのが難しい状況である
ともいえる。また、ほとんどの学校が、インターンシップ受入の観点で、企業が
どのような業務を実施しているのか把握できておらず、需要と供給のマッチング
が図れていないという問題点も存在する。
多くの学校で、インターンシップ受入企業紹介サービスなどの整備を望む声があ
る。
・教育機関側と受入企業側でのインターンシップの狙いが合致していない
教育機関側では、インターンシップの内容として、学生が実務に関われる内容を望
んでいるが、受入企業側としては企業へのアンケートにおける「インターンシップ
修得学生の採用意向」の設問結果にある「責任範囲における瑕疵担保などにおける
保障が難しい」という問題をはらんでおり、この点は学生がインターンシップで実
務に関わることに対する大きな障壁であると考えられる。
この結果を踏まえ、インターンシップ制度は、既に一部の学校では実現できているが、
多くの学校ができていない「学生視点でのインターンシップ制度の価値化」として、単位
制度の充実化を各学校が改善していくことが求められる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
171
同様に、学生視点での価値化につながり、かつ、教育機関と受入企業の需要供給のマッ
チングと双方の価値化を図るための「受入企業紹介サービス」なども充実化させる必要が
ある。現状制度上では、“学生を送り出す教育機関側が学生の責任を担保することをより明
確化する”、“企業側において、実務従事に対するボーダーを下げる工夫をする”、などの対
策が必要であると考える。
5.2 県内企業におけるインターンシップ経験者の採用意向
県内 IT 企業を対象として、OSS を活用したインターンシップ経験者の採用意向調査結
果を以下に示す。
なお、アンケートは、効率性の観点から「県内 IT企業の OSS 活用条件および OSS 技術
者育成条件の調査」で実施するアンケートと同時に実施し、ヒアリング調査により詳細
な情報収集を実施した。
5.2.1 アンケート結果の分析と考察
アンケートは、2 回実施した。第 1 回アンケート結果において、インターンシップ受入制
度の創設時期は、表 5.2.1-1 に示すとおり、「10 年未満」と回答している企業が有効回答数
全体の約 4 割(N=100 で 40 社)であり、「過去 5 年以内でのインターンシップ受け入れ」に
ついては、約 5 割(N=100 で 45 社)の企業が「ある」と回答している。
表 5.2.1-1 インターンシップ受入制度の創設時期に関する調査結果 (N=100)
企業数 合計
5 年未満 22 22.0%5 年~10 年未満 18 18.0%10 年以上前 5 5.0%受け入れていない 55 55.0%
また、企業におけるインターンシップ制度への要望は、以下のような順番となっている。
①インターンシップ実施における資金補助制度(企業側への助成など)②インターンシップ元教育機関の制度の充実(ルールの明確化)③インターンシップ元教育機関の紹介サービス(取りまとめ)④企業側のインターンシップ制度の明確化
以上のアンケート結果を踏まえると、企業においては学生の人材育成の一部を社会貢献
として担うなどの意識を持っている、という捉え方と社会的責務があるものの“業務の一
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
172
環”として受け入れたい、という潜在的要求を垣間見ることができる。また、受入制度を
有する企業のほぼ半数である 50.7%が 10年未満であることやインターンシップ制度に関す
る教育機関側および企業側双方のルールの明確化やインターンシップ元教育機関の紹介サ
ービスの整備を要望に挙げていることから、沖縄では、インターンシップ制度は企業、学
校双方で整備されているものの、運用面ではまだまだ未整備の課題が存在するものと推察
される。 さらに、インターンシップ経験者の採用意向としては、表 5.2.1-2 のとおり、「前向きに
考えている」、「採用時の参考にする」を併せ、6 割の企業が採用に際しての有効条件と見な
していることがわかる。
表 5.2.1-2 企業のインターンシップ経験者採用意向調査結果 (N=100)
企業数 割合
前向きに考えている 23 23.0%採用時の参考にする 37 37.0%考えていない 12 12.0%その他 28 28.0%
その上で、受入企業側としての教育機関への要望は、「学生のレベル向上」を挙げる企業
が多く、全体の 60%を占めている。また、その他、「制度の明確化」、「期間延長」なども要
望として挙げられており、前述したインターンシップ制度上のルールの明確化や 1~4 週間
と短い期間での受け入れは、企業側からの視点として、実業を体験させるには困難であり、
受け入れる上では有効なリソースとして活用したいがそれもままならず、単なる社会体験
で終わってしまう、と考えているのではないかと推察する。 従来のインターンシップ制度は、各企業のなんらかの既存業務に学生を就業体験させる
というスキームである。このスキームをより発展的な視点で、「自社技術者とともに新規の
共同作業(例えば、開発)に携わった学生は、製品販売時の営業、SE、保守の即戦力となる
か、もしくは社内での人材育成費用の削減につながる可能性があります。このような位置
付けの学生を新規採用したい、もしくは優先的に交渉しようと思いますか?」という設問
を第 2 回アンケートにおいて設定した。この回答を表 5.2.1-3 に示す。
表 5.2.1-3 インターンシップ経験者の採用意向調査結果 (N=79)
OSS 活用企業 OSS 非活用企業 合計
思う 28 24 52(65.8%)どちらともいえない 12 13 25(31.6%)思わない 0 2 2( 2.6%)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
173
新規の共同作業に携わった学生の新規採用に関して 65.2%の企業が優先的に交渉する意
思を示していることがわかる。
一方、34.8%の企業が「どちらともいえない」、「思わない」と回答しており、その主な理
由としては、「人物本位で採用する」、「企業戦略上の理由」、「責任範囲における瑕疵担保な
どにおける保障が難しい」などが挙げられている。人物本位で採用するのは、企業におけ
る採用の考え方として当然のことであるが、「責任範囲における瑕疵担保などにおける保障
が難しい」という点に関しては、インターンシップ制度における教育機関側、企業側双方
に係る課題であるといえる。
5.2.2 ヒアリング結果の分析と考察
ヒアリングは、アンケート結果を前提として、OSS 活用ビジネス展開に言及し実施した。
結果としては、インターンシップ経験者を「積極的に採用したい」、「採用したい」、「技術
ニーズがマッチすれば採用したい」という回答が多かった。
インターンシップ制度は、教育機関から見れば学生の就職希望業種における社会体験と
就職先へのコネクション強化の意味合いを持つが、既存のインターンシップ制度では、実
質的には社会体験の要素が強い。一方、企業の視点では、社会的貢献活動の一環としての
位置付けと優秀な人材の獲得の意味合いを持っているものの「実務で活用したい」、「人材
不足で即戦力を獲得したい」という希望が垣間見える。一部では、教育機関と企業の思惑
が合致しているものの、企業側の要望のほうが教育機関のそれを上回っているものとヒア
リング結果から推察される。
5.2.3 まとめ
OSS を活用したインターンシップの可能性調査の取りまとめ結果を以下に示す。
(A)インターンシップの制度上の課題
インターンシップの実施時期は、各大学とも夏休み期間中が多く、期間は 1 週間か
ら 1 ヶ月。参加対象年次は 3 年次(高専は 4 年次)が多く、ほとんどの学校が、インタ
ーンシップ先を学生が選定している。インターンシップ先は、バラエティに富んでい
るが、いずれの学校も IT関係が含まれている。
インターンシップは、学校、学生双方にとって、事実上就職活動の一環として運用
されているものと推察されるが、学校毎に修得単位制度が異なっており、インターン
シップの期間により修得単位の種類と量が多い学校は、同学校の参加学生が他の学校
と比較し飛び抜けて多いことから、学生のインターンシップの参加意向の高さの要因
のひとつとなっているものと推察でき、この点は、学生にとって非常に重要なポイン
トであると思われる。学生の視点に立ってみれば、基本単位である 2 単位以上が取得
できなければ、講座としての魅力がなく、純粋にインターンシップそのものの価値が
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
174
修得するか否かを左右している可能性も否めない。インターンシップ制度は、既に一
部では実現できているものの多くの学校ができていない「学生視点でのインターンシ
ップ制度の価値化」、として、単位制度の充実化を各学校が改善していくことが求めら
れる。
インターンシップ制度は、教育機関側から見れば、学生の就職希望業種における社
会体験と就職先へのコネクション強化の意味合いを持つが、既存のインターンシップ
制度では、実質的には社会体験の要素が強い。一方の企業の視点では、社会的貢献活
動の一環としての位置付けと優秀な人材の獲得の意味合いを持っているものの「実務
で活用したい」、「人材不足で即戦力を獲得したい」という希望が垣間見え、一部では、
教育機関と企業の思惑が合致しているものの、企業側の要望のほうが教育機関のそれ
を上回っている。この点は、インターンシップ運営上の課題のひとつとして捉えるこ
とができる。
インターンシップの制度運営上の課題としては、教育機関側が、企業が何をやって
いるのか把握できておらず、適切なインターンシップ先が探索できないことやインタ
ーンシップ先が先生個々人の人脈に依存していることが多いことから、受け入れ先が
形骸化し、広がりを期待することが難しい、などの課題がある。また、教育機関側と
企業側のインターンシップに関する需要と供給のマッチングが図れていないという点
も課題である。
多くの学校で、インターンシップ受入企業紹介サービスなどの整備を望む声があり、
同様に企業側からも望む声が多い。教育機関と受入企業の需要供給のマッチングと双方
の価値化を図るための「受入企業紹介サービス」を整備すると、学生視点においても、
価値化につながる。
実務面においては、教育機関側としては学生が実務に関わり体験させることを望んで
いるが、実務に関わらせることは、責任範囲における瑕疵担保などの保障が難しい、と
いう問題をはらんでおり、現状制度上では、この問題が学生を実務に関わらせることに
対する大きな障壁であると考えられることから、“学生を送り出す教育機関側が学生の
責任を担保することをより明確化する”、“企業側において、実務従事に対するボーダー
を下げる工夫をする”、などの対策を検討する必要があると考える。
以上のことから、教育機関側、企業側双方でインターンシップを行う有用性は認識
しているものの、制度の整備不足や双方の狙いが合致していないことは明らかである。
この希少な機会をより有効に実現するには、以下の環境整備が必要である。
・教育機関側の整備として、学生視点での価値化を行い、学生のインターンシップ
に対するモチベーションを向上させる
・受入れ可能企業のリスト化と企業特性の検索の利便性を向上させ、企業と学生の
アンマッチを低減する
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
175
・企業側の整備として、受入れ条件の明確化と学校への申し入れを行い、学校の企
業リスト化に協力する
・企業側の整備として、受入れ時の社会体験内容を明確化し、場当たり的な作業を
させない
・企業側の整備として、既存業務だけでなく、担保の問題を軽減できる可能性のあ
る新規業務分野までインターンシップの適用領域を広げる
このような環境条件を検討・整備することにより、インターンシップが活性化し、
OSS ベース商材で企業がビジネスする際の要員確保の有益な手段のひとつになる可能
性を向上させられるものと考える。
(B)企業によるインターンシップ経験者の採用意向
インターンシップ経験者の採用意向としては、6 割の企業が採用に際しての有効条件
と見なしている。
企業側としての教育機関への要望は、「学生のレベル向上」を挙げる企業が多く、全
体の 60%を占めている。また、「制度の明確化」、「期間延長」なども要望として挙げら
れており、前述したインターンシップ制度上のルールの明確化や 1~4 週間と短い期間
での受け入れは、企業側からの視点からみると、実業を体験させるのは困難である。
受け入れる上では有効なリソースとして活用したいがそれもままならず、単なる社会
体験で終わってしまう、と考えているのではないかと推察する。
従来のインターンシップ制度は、各企業のなんらかの既存業務に学生を就業体験さ
せるというスキームである。このスキームをより発展的な視点で、「貴社技術者ととも
に新規の共同作業(例えば、開発)に携わった学生は、製品販売時の営業、SE、保守の
即戦力となるか、もしくは社内での人材育成費用の削減につながる可能性があります。
このような位置付けの学生を新規採用したい、もしくは優先的に交渉しようと思いま
すか?」という設問に対しては、新規の共同作業に携わった学生の新規採用に関して、
3割強の企業が、採用の考え方として当然のことであるが、人物本位での採用、を挙げ
ており、既存のインターンシップの内容よりも若干高い 7 割弱の企業が、優先的に交
渉する意思を示している。
よって、インターンシップの内容を見直すなど、受け入れ企業側での視点を変えて
みることにより、企業側の人材獲得によい効果を獲得できる可能性が生まれるのでは
ないかと考える。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
176
第6章 海外の IT 企業における OSS ベース商材創出の調査
本章では、海外の IT 企業における OSS ベース商材創出の調査として、アジア地域およ
び欧米地域における IT 企業動向を示す。
6.1 アジア地域における IT企業動向
アジア地域について、特に隣国である中国にフォーカスを当て、中国市場における OSS
の動向および IT 企業の動向を以下に示す。
6.1.1 アジア地域の OSS関連 IT企業現況
アジア各国では、IT の推進は国家的な課題として強く認識されており、政府・公共機関
主導による OSS の普及推進が盛んである。アジア各国政府の OSS 普及推進の取り組みは、
IT 企業の動向と密接な関係性があることから、はじめにアジア各国政府の取り組みについ
て触れる。
現在、アジアでは、20カ国・地域の政府において、政府主導によるOSSの普及促進に向け
た取り組みが進んでいる。アジア各国の政府がOSSの普及を推進するには、いくつかの理由
がある。
アジアは、日本から見ればオフショア拠点として活用している国が多いが、IT産業を振
興することにより、先進国からのオフショア開発を通した外貨獲得の手段として高く認知
されている。このため、各国ともIT人材の育成に力が注がれており、OSSが手軽な技術情
報収集の手段、かつ教材として活用されている。さらに、アジア各国では、WTO加盟やFTA
締結などに積極姿勢を見せている国も少なくないが、これらを推進する上で、これまでほ
ぼ野放し状態であったソフトウェアの海賊版の普及率を低減することが、政府が解決しな
ければならない急務の課題となっておいる。また、併せて商用ソフトウェアに係る適正な
ライセンス費用を支払うことは困難、もしくは資金不足などのリスク要因となることから、
海賊版からOSSへの移行やOSSの新規採用が、政府主導により推し進められている。
中国などでは、当初、「一国の基幹システムが他国のOSに席捲されているのは、国家安全
保障やセキュリティの観点で問題がある(ソースコードが公開されていないソフトウェア
は脆弱性が含まれても検出できず、また、何らかの事故が発生しても迅速に対応できない)」
として、LinuxやOSSの普及を促進してきた。2001年からソフトウェア分野において、政府
政策として自国製品の採用を進めており、数々の国家プロジェクトによりOSSを生み出して
きた。代表的なソフトウェアとしては、デスクトップOSの揚帆(Yangfan)LinuxサーバOSの
紅旗(Red Flag)Linuxがある。近年では、ハードウェア(サーバ、ストレージなど)について
も、自国生産および自国製品の採用を国家政策として推進している。現在では、国際的な
協調関係を保ちつつ、中国国内における産業振興の材料として普及推進を続けており、政
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
177
府・公共系およびインフラ系システムの多くにLinux、OSSが導入されている。
中国での Linux、OSS に関係する IT 企業は、2001 年頃から北京を中心にベンチャー企
業が数多く誕生し、現在では、多くの省(プロヴィンス)単位で、省政府が OSS を推進する
動きが顕著であり、この動きとともにベンチャー企業や既存 IT 企業の OSS 活用が多い状
況にある。特に、広東省は、Linux、OSS の普及推進としては最後発であるが、広東 Linuxセンター(GDLC)という省政府所管の推進拠点を中心として、広東 Linux 連盟という企業連
携団体や近隣省の大学・高校などにおける Linux、OSS の人材育成などでの連携も盛んに
行われている。また、広東 Linux センターは、同省内にある香港特別行政区の香港 OSS セ
ンターと連携を密にしている。香港では、中国本土をターゲットとした OSS を活用する IT企業が数多く誕生しており、香港 OSS センターを活用し、人材育成や技術開発などを進め
ている。
6.1.2 アジア地域の IT企業における OSSベース商材創出に関する可能性の検討
アジア地域の中でも特に市場性の高い中国にフォーカスを当て、中国の IT企業を対象に
OSS ベース商材創出に関する可能性の検討をヒアリングにより情報収集する。
(1)ヒアリング調査内容
ヒアリング調査内容を図 6.1.2-1 のとおり、定める。
ただし、より詳細な分析につながりそうな内容がヒアリングできる場合は、この調
査内容にとどまらず、ヒアリング内容を柔軟に拡張するものとする。
・企業情報(属性、業種、ターゲット市場、従業員数、売上規模)
・OSS の認知度
・OSS 活用有無
・OSS 未活用企業の未活用理由
・OSS 未活用企業の OSS に対する興味の有無
・実施しているビジネスモデル
・商用ソフトウェアと比較した OSS の長所/短所
・OSS の活用実績
・OSS の著作権やライセンスに関する考慮状況
・主な販路
・OSS コミュニティとの関わり
・人材確保,育成方法
・ターゲット市場
・中国 IT企業における沖縄の認知度
・中国市場をターゲットとした提携や協業、共同開発ができる可能性
・沖縄の企業と提携、協業、共同開発をする上での条件
・企業への開発ノウハウの享受を目的とした OJT に対する興味の有無
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
178
図 6.1.2-1 中国企業に対するヒアリング内容
(2)ヒアリング手順
ヒアリング調査手順を以下に示す。
①ヒアリング対象地域の選定
② 各地域におけるヒアリング対象企業の探索およびアポイントメント
③ 各地域の IT企業に対するヒアリング調査
(3)ヒアリング対象地域の選定
中国は、華北、華中、華南と3つの経済圏に区分されており、中国の IT企業の状況
を把握するためには、各経済圏において IT 企業が集積している地域を対象に IT 企業
を探索し、ヒアリング調査を実施することが必要である。この観点から、華北地区の
中心である北京市、華中地区の中心である上海市、華南地区の中心である広東省広州
市を対象地域として、IT企業を探索する。
また、華北には、山東省済南市に IT 産業の醸成に力を入れている政府主導のソフト
パークが存在することから、併せて、ヒアリング対象地域として選定する。
(4)ヒアリング対象企業の選定
各地域におけるヒアリングの調査対象企業は、沖縄の企業規模と比較し、遜色のな
いと考えられる 2,000 名程度を上限とし、小規模・中規模・大規模が企業を選定した。
各地域で選定した企業の一覧を表 6.1.2-1 に示す。
表 6.1.2-1 ヒアリング調査対象企業一覧
地域企業内容
業務種別 要員数(人) 売上規模(円)
華
北
北京 北京企業 1:組込機器製造・販売
1,000~2,000 5 億以上
北京企業 2:国内向けソフトウェア開発・オ
フショア
100~500 2~5 億
北京企業 3:国内向けソフトウェア開発
50 未満 1~2 億
北京企業 4:国内・海外向け SI・ソフトウェ
ア開発/販売
500~1,000 5 億以上
済南
(山東省)
済南企業 1:国内向けソフトウェア開発・オ
フショア
100~500 0.5~1 億
済南企業 2: 1,000~2,000 5 億以上
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
179
国内・海外向け SI・ソフトウェ
ア開発/販売
済南企業 3:国内向け SI・ソフトウェア開発
100~500 2~5 億
済南企業 4:組込機器製造・販売
100~500 5 億以上
済南企業 5:国内向け SI・ソフトウェア開発
500~1,000 5 億以上
済南企業 6:人材派遣・オフショア
50 未満 0.1~0.5 億
済南企業 7:国内・海外向け SI・ソフトウェ
ア開発/販売
50~100 1~2 億
済南企業 8:国内向け SI・ソフトウェア開発、
システム運用管理受託
100~500 5 億以上
華
中
上海 上海企業 1:国内向けシステム運用管理受
託、データベースサービス、ハ
ード販売、教育
100~500 1~2 億
上海企業 2:国内向け SI・受託ソフトウェア
開発、ハード販売、教育
100~500 1~2 億
上海企業 3:国内向け SI・ソフトウェア開発、
ハード販売、教育
50~100 2~5 億
上海企業 4:国内向け SI・受託ソフトウェア
開発、システム管理運営受託、
ハード販売、教育
50 未満 2~5 億
華
南
広州
(広東省)
広州企業 1:国内向け SI・受託ソフトウェア
開発、システム管理運営受託、
ハード販売、教育
50~100 2~5 億
広州企業 2:国内向け SI・ソフトウェア開発、
システム管理運営受託、ハード
販売
100~500 5 億以上
広州企業 3:国内向け SI・ソフトウェア開発、
システム管理運営受託、ハード
販売
100~500 2~5 億
(5)ヒアリング調査の実施
ヒアリング調査の実施内容を以下に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
180
(A)ヒアリング調査結果
各地域での企業ヒアリング調査結果を以下に示す。
① 華北地域(北京)の IT企業
北京には、国営企業の本社が数多く立地しており、また、日系企業の進出も数多い。
国営企業をターゲットとして活動している IT 企業、その他オフショア、日系企業を
ターゲットとしている企業が多く、民需領域をターゲットとしている企業は上海な
どと比較すると傾向的には少ない。
北京の IT 企業では、OSS の認識が進んでおり、ビジネスでの活用が図られている。
組み込み機器メーカーでは、WidnowsCE などと並び Linux も組み込み機器の OSとして活用されている。また、国内向けソフトウェア開発などでは、特定の OSS(Linux, Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, Struts, Spring など)が定常的に活
用されている。OSS を活用した独自のミドルウェアプラットフォームを開発してい
る企業も存在している。SI などでは、ユーザの指定がない限り、OSS を優先的に活
用し、適合するものが見つからない場合は商用製品を活用する、という方針を有し
ている企業が多い。活用する上では、ほとんどの企業が、活用する OSS を自社の技
術者がソースコードを解析し、ノウハウ蓄積を図っているが、自社の技術者がソー
スコードを解析してサポート力を蓄積しているものの、保障の面では自社の対応だ
けでは不安がある、と回答している。
そもそも北京では、政府が Linux や OSS の普及促進を図ってきたこともあり、多く
の IT企業での活用が定着化している大きな要因となっていることが伺える。
OSS のコミュニティ活動を行っている企業も見受けられ、また、SourceForge など
のリポジトリを定常的に活用している企業も存在していることがわかった。
特筆すべきは、北京の組み込み機器メーカーでは、「Windows 系には、ハードの制御
面で課題がある」、「0 ベースで開発してきたが、今後は OSS を使って開発の効率化
を図っていき、自社での解析によって、安全性も担保する」との意見があった。ユ
ーザからは、「Windows ベースでは安全性などに問題があるので、OSS に変えてほ
しい」という要望が増えてきているという。
今回ヒアリングした北京の IT企業は、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との
関係性の理解とともに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文
化的にも類似項が多いことも認識している。県内 IT 企業と北京の IT 企業との提携
の可能性についても、非常に前向きな回答が得られた。OSS ベースの製品開発を沖縄
で共同実施できるか否かという質問に対しては、組み込み機器メーカーの除き、ソ
フトウェア開発企業は、自費で渡航し参画することが可能と回答している。
以上のことから、北京のソフトウェア開発企業では、概ね、県内 IT企業が OSS ベー
スの製品創出を前提とした柔軟な提携の推進を実現できる可能性が高いものと推察
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
181
される。
② 山東斎魯ソフトパーク立地 IT 企業
済南の IT企業は、国内限定で政府・公共機関、インフラ企業などをターゲットにし
ている企業と日本・欧米向けのオフショアと国内向けの SIを実施している企業の2
つに大別できる。
政府・公共機関、インフラ企業などをターゲットにしている企業が存在するのは、
山東省が北京に隣接しているという地理的条件が作用しているものと考えられる。
済南 IT 企業では、OSS は知っているが、どのソフトウェアが OSS であるか、という
認識が薄い状態にあることがわかった。OSS の認知度が高い企業でも、OSS のライセ
ンスは GPL、という認識が強く、ビジネスにならない、と考えている。しかしながら、
SI においては、非常に狭い範囲の OSS(Linux, Apache, Tomcat, MySQL, PostgreSQL)
などを定常的に活用しており、ユーザの指定がない限り、これらの OSS を SI の材料
として活用するという方針を有している企業が多い。
なお、日本・欧米向けのオフショアと国内向けの SI を実施している企業のうちの1
企業は、OW2*1に加盟しており、積極的に OSS の活動を実施し、自社のビジネスに取
り入れている企業がある。
これらの企業が入居している山東斉魯ソフトウェアパークは、中国全土で国家ソフ
トウェア産業基地に指定されている 11 の省政府直轄ソフトウェアパークの中でも特
に、近隣大学に 50 万人の学生を有するなど人材が豊富で、かつ、入居企業に対し、
入居条件、税務面、資金面、インフラ面などで手厚い支援政策(国家優遇政策と地
方優遇政策を併用)を展開している。これは、中国の中で山東省が IT 産業育成では
比較的後発であるため、条件面の整備が行き届いているものといえる。
山東斉魯ソフトウェアパークの入居企業優遇政策を表 6.1.2-3~表 6.1.2-5 に示す。
表 6.1.2-3 入居企業優遇政策(国家優遇政策)
項目 基数 比率 優遇策 優遇条件
企業所得税 利潤総額 25% 2 年間免除
以降 3年間
50%
ソフトウェア企業と認定され
る場合
利潤総額 25% 15% 高新技術企業と認定される場
合
利潤総額 25% 15% 技術先進型企業と認定される
場合
増値税 課税収入 17% 免税 オフショア開発でソフトウェ
アを輸出する場合
営業税 課税収入 5% 免税 技術先進型企業と認定される
*1 オープンソースのミドルウェア、EAI、電子商取引、クラスタリング、グリッド・コンピ
ューティングに関する非営利の国際コンソーシアム
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
182
場合
個人所得税 給与 5-45% - -
表 6.1.2-4 入居企業優遇政策(地方優遇政策)
項目 国 省 市 区
増値税 75% 0 10% 15% *1
営業税 - 20% 32% 48% *1
企業所得税 68% 12.8% 12.8% 19.2% *1
個人所得税 60% 15% 10% *2 15%
*1:山東斉魯ソフトウェアパーク産業発展資金
*2:年給 10 万元以上の高級人材に 80%を返還
表 6.1.2-5 入居企業優遇政策(地方優遇政策:補助金)
補助内容
人材育成 人材育成補助金
高級人材個人所得税の一部返還
IT 専門家受け入れに対する補助
国際認証費用の補助
海外宣伝活動および人材招聘に対する補助
事務室レンタル料金補助
オフショア開発による輸出額に対する奨励
国際通信用ネットワーク構築への補助
モデル区インフラ設置などの建設への補助
同パークは、同時に、国家サービスアウトソーシング基地都市(全国で 20都市)の指
定も受けており、国際的な企業連携を積極的に推進している。特に日本との関係は
重要視されており、全大学に日本語学科の設置やスピーチ大会、パーク内に日本の
業務向けのトレーニングセンターを設置するなどの取り組みを行っており、これら
を背景として、実務面での連携も深まっている状況にある。
今回ヒアリングした済南の IT企業は、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との
関係性の理解とともに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文
化的にも類似項が多いことも認識している。県内 IT 企業と済南の IT 企業との提携
の可能性についても、非常に前向きな回答が得られた。「共同で発展を模索していく
上でリソースの共有を図ることができる」、「OSS をベースとした製品を活用し、中国
市場開拓に向けた活動を展開できる」、「県内 IT 企業は製品ノウハウを、済南の IT
企業は、中国市場におけるマーケティングや人脈を活用による市場開拓という点で、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
183
お互いに強みを補完できる」、「中国市場におけるユーザの要求が多様化してきてお
り、この要求に対応するために日本の IT 企業との提携は重要」などの意見があった。
OSS ベースの製品開発を沖縄で共同実施できるか否かという質問に対しては、自費で
渡航し参画することが可能と回答した企業がほとんどであるが、これは、各社が日
本の企業に対する期待の表れなのかもしれないが、山東斉魯ソフトウェアパークの
支援政策が背景にあるためだとも推察される。
なお、済南では、山東斉魯ソフトウェアパークの責任者にもヒアリングを実施した。
同責任者は、県内 IT 企業と済南の IT 企業の提携促進、県内 IT 企業の山東斉魯ソフ
トウェアパークへの入居促進を推進していきたいとの希望を有している。また、「沖
縄 IT津梁パーク」を訪問前から認識しており、両パーク間での連携も模索したいと
の意向を示していた。山東斉魯ソフトウェアパークをはじめとした、これら国家の
ソフトウェアパークの大きな目的は、環境面で悪影響のない IT分野を主要産業とし
て醸成し、中国における仕事を増やし、雇用を継続的に創出することにあるが、同
パークでは、日本から中国へ、という一方通行的な視点ではなく、沖縄と双方向で
の発展を模索する、という視点を有していると見受けられるため、両パークの関係
強化、および県内 IT 企業が OSS ベースの製品創出を前提として、済南の IT 企業と
の柔軟な提携の推進が実現できる可能性が高いものと推察される。
③ 華中地域(上海市)の IT企業
上海は、中国の中でも、事実上、商業の中心としての位置付けを担っており、これ
を裏付けるかの如く、ヒアリングした企業は、製造・流通・情報通信・不動産・建
設などの民需領域を主要ターゲットとしている。
上海の IT 企業では、OSS に対する認知度が低く、現状活用していないことがわかっ
た。商用製品と比べた場合の OSS に対するイメージも、ソフトウェア技術の自由な
促進やローエンドに対して広く活用されていることは認識しているものの、「OSS は
実質的に大手企業の独占を強化する」、「商用ソフトウェアの信頼性、拡張性、高可
用性の特性を持っていない」など、誤解や理解不足の状況にあることがわかった。
ただし、すべての企業が県内 IT 企業との提携の可能性はあると回答しており、その
条件としては、商用ソフトウェアをベースとし、コスト面、操作性に優れているこ
とを条件として挙げている。
今回ヒアリングした上海の企業は、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との関
係性の理解とともに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文化
的にも類似項が多いことも認識している。県内 IT 企業と上海の IT 企業との提携に
ついて、前向きな回答が得られた。「ユーザからのコスト削減要求が増しており、こ
れを踏まえた新たな製品を模索していく必要がある」、「中国では著作権管理が厳し
くなってきたため、提携によりコスト削減の可能性が見出せることを期待する」と
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
184
いう意見が大半であった。OSS ベースの製品開発を沖縄で共同実施できるか否かとい
う質問に対しては、実施する意思がないと回答した企業がほとんどであり、これは、
上海の IT企業の OSS に対する認知が進んでいないことが大きな要因となっているも
のと考えられる。
④ 華南地域(広東省広州)の IT企業
広東省政府は、Linux/OSS を IT 産業におけるソフトウェア関連企業醸成のための主
軸として定義しており、広東 Linux センター (GDLC)という省政府所管の推進拠点
を設置している。同センターでは、省政府のソフトウェア調達リストに登録するた
めの認証作業も実施している。
同省では、後発で IT 産業の醸成を開始したが、省内には、IT 関連の製造業の集積拠
点として深圳があり、また、広州には自動車産業が集積されているなどの良好な環
境が存在しており、組込ソフトウェアの企業醸成にも力を入れている。近年では、
広州、珠海などにソフトウェアパークを整備し、ソフトウェア関連企業の誘致およ
び自国企業の醸成を推進している。
広州の IT 企業のターゲットは、国営企業、外資企業、民需領域と幅広い。
広州の IT企業では、OSS の認識が進んでおり、ビジネスでの積極的な活用が図られ
ている。OSS をベースとした商用ソフトウェアの開発も盛んに行われている。SI などでも、ユーザの指定がない限り、OSS を優先的に活用し、適合するものが見つか
らない場合は商用製品を活用する、という方針を有している企業が多い。活用する
上では、ほとんどの企業が、活用する OSS を自社の技術者がソースコードを解析し、
ノウハウ蓄積を図っており、サポート力を蓄積している企業も多い。 広州では、省政府が積極的に Linux/OSS を推進していることもあり、OSS に関連す
る国際イベントの開催や全国を対象としたイベントの開催が比較的多く、広州の IT企業と OSS のコミュニティ関係者との接点が得やすい状況となっている。これを背
景として、OSS のコミュニティ活動を行っている企業も見受けられる。 今回ヒアリングした広州の IT企業は、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との
関係性の理解とともに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文
化的にも類似項が多いことも認識している。県内 IT 企業と広州の IT 企業との提携
の可能性についても、前向きな回答が得られた。OSS ベースの製品開発を沖縄で共同
実施できるか否かという質問に対しては、自費で渡航することは不可能との回答で
あるが、何らかの補助が得られれば参画したいと回答している。
以上のことから、広州の IT 企業では、県内 IT企業と広州の IT企業が沖縄で OSS ベ
ースの商用ソフトウェアを共同開発することは難しいが、県内 IT企業が OSS ベース
の製品創出を前提とした提携の推進は実現できる可能性があるものと推察される。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
185
(6)まとめ
アジア各国では、前述のとおり、OSS の普及推進が盛んであるが、本調査において、OSS
に対する中国国内での地域毎の企業傾向が明確となった。華北では、政府系、インフラ
系をターゲットとした企業やオフショアに取り組む企業が多い。華北の中心である北京
では、認知が進んでおり、周辺地域においては、北京と比較し若干認知度合いが劣るも
のの、Linux/OSS を定常的にビジネスで活用している実情にあることがわかった。この地
域では、早い段階から政府による Linux/OSS 普及推進政策が実施され企業における定着
化が進んだものと推察される。華中では、国内の民需系をターゲットとした企業が多い。
中心である上海では、企業における Linux/OSS の認知が進んでおらず、受託システム開
発などでの活用も乏しいようである。上海では、政府方針として Windows を継続して推
奨していることや独自製品保有よりも他社製品を活用したカスタマイズド・ビジネスが
主体になっている、などがこの要因として考えられる。華南では、環境条件から組み込
みソフトウェアに関連する企業が多く、また、国内の政府系、インフラ系、民需系をタ
ーゲットとした企業が混在している。全土からみると華南は、IT 産業政策の推進が後発
的な位置付けであるものの、中心である広東省は、製造業が数多く立地する深圳、自動
車業界が数多く立地する広州を要しており、組み込みソフトウェアに対するビジネスが
実施し易い環境にあることや、省政府での積極的な Linux/OSS の普及推進政策により、
認知が進んでおり、多くの企業で Linux/OSS を活用している状況にある。この影響は、
良い意味で省内の香港、澳門両特別区にも及んでおり、両区にも組み込みソフトウェア
企業や Linux/OSS を活用している IT 企業が数多く存在する。
中国の企業において、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との関係性の理解とと
もに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文化的にも類似項が多い
ことも認識している。この県内 IT企業との提携に関しては、いずれの地域でも情報・リ
ソースの共有や製品をベースとした、共同開発を含む協業などで可能性があると考えて
いることがわかった。県内 IT企業と沖縄で OSS ベースの製品開発を共同実施する、とい
う一歩踏み込んだ協業については、華北、華南という Linux/OSS の認知が比較的進んで
いる地域では、多くの企業が自費渡航での参画が可能と考えていることがわかった。こ
れは、OSS の認知度が進んでいることだけでなく、OSS が自社製品の材料となる可能があ
ることを認識していることや、ビジネスが安定しており投資余裕があること、政府から
の補助など何らかの支援が得られることなどが背景にあるものと推察される。
中国の多くの企業は、IT 業界に立脚しはじめた当初は、単価の安さを強みとしてオフ
ショアを主軸としたビジネスを展開し、オフショア業務において下流工程から上流工程
へと段階的に活用の幅が拡がり、要素技術やノウハウを蓄積し続けている。現在では、
これを背景として、業種が 100%オフショアの企業も存在すれば、100%国内市場に向いて
いる企業もあり、多くの企業がこの狭間に存在している。このオフショアが主軸、もし
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
186
くは主要の一つとなっている企業が多い中国企業の実情からすれば、県内 IT 企業は、あ
る種中国の IT 企業のコンペティタであり、単価も近年では拮抗しつつある状況にある。
しかしながら、システム開発やソフトウェア開発に係る経年でのさまざまな蓄積ノウハ
ウやソフトウェア製品の企画などの観点から見れば、県内 IT企業で強みが見出せる部分
が存在しているといえる。一方の中国の IT企業には、生産力の高さや中国という巨大市
場における有効な人脈を保有している可能性とマーケティング力などに強みがあると考
えられる。県内 IT企業が独自のソフトウェア製品を保有し、これを軸とすれば、製品品
質や市場適合性などにも左右されるのは前提条件として存在するが、コンペティタとし
てではなく、日本・中国市場における市場開拓において、相互補完の関係を築くことが
できる可能性を有しているものと考える。沖縄 IT津梁パークと山東斉魯ソフトウェアパ
ークなどに代表される国営のソフトウェアパークとの連携などが、これをさらに強固な
流れとしていくものと推察されることから、日本側、中国側相互で具体的な検討が始ま
ることを期待したい。
6.2 欧米地域における IT企業動向
OSS 活用ビジネスは、出現の経緯やエコシステムの遵守意識が高いことを背景として、
新たなビジネスモデルや商材が米国、欧州各国から創出される頻度が比較的高い。欧米地
域での IT 企業の状況把握を実施することは、今後、県内 IT 企業の OSS ビジネスにとって
有益な参考情報となることから、付加的な位置付けとして、調査を行う。
6.2.1 欧米地域の OSS関連 IT企業現況
欧米地域の OSS 関連の現況および IT 企業の現況を以下に示す。
(1)欧州と北米の OSS の取り組みに関する共通点・相違点
欧州と北米の OSS の取り組みに関する共通点・相違点を以下に示す。
(A)共通点
欧州と米国の共通点について、以下に記す。
・ベンダの特徴
OSS に対するメリットを十分に把握しており、製造業・金融業を初めとし多く
の企業・行政機関へのサービス提供が進んでいる。社員数は、10人から 99人と
いった中小規模の割合が多く、都市圏に集中しているわけではない。さらに、
地域に根ざしたビジネスを行うことを主流としている。
・技術者の不足
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
187
大学や専門学校などの教育機関では、OSS 技術者育成カリキュラムが充実して
いる。一方、技術者の不足は深刻である。例えば、ソフトウェアベンダの米
Actuate が 2008 年 9 月に公表した調査結果によると、「オープンソースの専門技
術者が社内にいない」、と答えた回答者の割合が 60%に上った。このことからも
わかるように、OSS 人材の確保は急務となっている。
(B)相違点
欧州と米国の相違点について、以下に記す。
・ベンダ数の割合および収入の違い
米国に本社を置くソフトウェア企業が、OSS ビジネスを展開する企業の約 7割
を占めている。一方、欧州は約 2 割である。また、歳入の割合も米国が約 6 割
であるのに対し、欧州は約 2 割とほぼベンダ数の割合に比例した形となってい
る。これは、OSS はローカルビジネスが主流であることに起因する。
・OSS ビジネスの違い
欧州では、現状の米国商用製品の支配から脱却することを目的とし、欧州発
のもしくは自国発のソフトウェア企業を育成することに主眼が置かれている。
また、米国と比べリセラーやシステムインテグレータがより投資をする傾向
にある。
一方、米国では Microsoft などの巨大な商用ソフトウェア企業の圧倒的支配
を打破することに主眼が置かれている。欧州と比較すると、OSS という新しいソ
フトウェアモデルへの投資が有効であると判断しているベンチャーキャピタル
がより投資を行う傾向にある。
欧州のビジネスモデルは、サービス販売とサポートが主流であり、米国も基
本的に同様である。しかし、欧州は製品のデュアルライセンス提供に否定的で
あるが、米国では一般的となっている。これは、欧州では技術革新を目指した
開発手法のあり方に主眼が置かれており、一方、米国では利益追求型のビジネ
スモデルを志向するプレイヤーが OSS サービスを行う傾向が強いことに起因す
る。
欧州のユーザはオープンソースライセンス(GPL、EUPL)の下で自由に利用した
いと考える傾向が強く、補償は重視しない。一方、米国のユーザは補償を重視
する傾向にあり、デュアルライセンスが一般的となっている一因となっている。
さらに、欧州の OSS の主たる導入目的はベンダロックインの回避であること
に対し、米国はコスト削減である。
欧州はリセラーやシステムインテグレータによる販売形態が主流である。し
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
188
かし、米国はベンダによる直売が主流である。これは、米国での IT 産業の構造
として、システムインテグレータが少ないためである。
(2)欧米地域と北米地域における政府の OSS に関する取り組み 欧州は各国の政府主導でオープンソースの啓蒙や普及に取り組む傾向が強い。さら
に、欧州連合(EU)も OSS 普及に貢献している。例えば、EU には電子政府サービス部門
(IDABC)が存在する。IDABC にはオープンソースのコードやアプリケーションを共有す
るための、公的機関向けのリソースサイト(OSOR)も創設されている。欧州の中でも OSS
普及推進に強く取り組んでいるのは、ドイツ・イギリス・フランスである。なお、ソ
フトウェアベンダの米 Actuate が 2008 年 9月に公表した調査結果によると、「OSS をア
クティブに利用している」、と答えた割合はドイツ、イギリス、フランスでそれぞれ 51%、
42%、42%であった。
一方、米国でのオープンソースの利用は、コスト削減と果敢な技術革新を模索して
いる私企業によって推進されているため、政策主導での取り組みは目立っていない。
さらに、上述の調査結果も 40%である。地域別では、西海岸側が東海岸側に比べ普及が
目立っているが、これはシリコンバレーに代表されるベンチャーキャピタルが西海岸
側に集中しており、それら企業がローカルビジネスを展開するという傾向に起因する
ものである。
なお、欧州は米国に比べコミュニティが充実しているという特徴がある。
(3)欧州と米国における OSS の市場規模
2007 年米 IDC 社の調査レポート*1によると、2006 年におけるワールドワイドの OSS サ
ービス市場規模は、1.8.BUS$(約 1,800 億円)と予測している。ここでいう市場規模は、
コンサルティング、システムインテグレーション、ソフトウェアデプロイメント、保守、
技術サポート、トレーニングといった OSS を直接的なビジネスの商材としているモデル
を対象としており、Web2.0 企業など、OSS を活用して自らのビジネスに新たな付加価値
を醸成するケースや事業プロセスの効率化を図ることを目的として自社システムに OSS
を取り込むようなビジネスケースは、ここには含まれていない*2。
2007年OSSの市場規模を米国と欧州が全世界のGDP*3に占める割合とほぼ等しいと仮定
して算出すると、約 53 %の 950MUS$(約 950 億円)*4となる。
市場の伸びという観点では、2011 年にはワールドワイドで 5.8BUS$(約 5800 億円)の市場規
模になると予測さており、2007 年からの CAGR は約 26%となる。アジアなどの新興市場にお
*1 http://news.cnet.com/8301-13846_3-9967346-62.html *2 OSS には共通的な市場定義というものがなく、調査会社の独自定義により市場規模も大きく異なることを注意され
たい。たとえば Gartner 社の定義では、2007 年ワールドワイドの OSS 市場は、数兆円規模とされる。*3 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal) *4 IT 領域において欧米が実際に占める割合は 70-80%という見方もある。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
189
ける OSS 活用促進といった成長要因に加え、市場をけん引する欧米諸国でも、継続して CAGR
10~20%台の成長が期待される。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
190
第7章 事業連携に向けた体制構築
OSS ベース商材構築に向けての事業連携を目指し、県内 IT 企業を中心とした推進体制の
構築を検討した。検討結果を以下に示す。
7.1 県内 IT企業による OSS関連事業に向けた体制構築
県内 IT 企業に共通の構造として、発注元と発注先は、収益構造が大きく異なっており、
発注元は損益確保の主導権を持つことから利益を出しやすく、一方の発注先では、発注
元のコストセービングの指針の下、収益を上げづらいという背景がある。
沖縄において、今後真の自立経済振興と雇用創出を継続的に推進し続けていくために
は、損益確保の主導権が持ち得て、県外 IT企業への依存性が低い、内製型ビジネス構造
への変革のための取り組みを早期のうちに実現していく必要がある。
この損益確保の主導権を持つためには、競争力のある製品や関連ノウハウ、技術力を
保有する必要があり、県内 IT 企業が市場競争力を有する活動形態へと変革させていくた
めの取り組みが必要である。その上での県内 IT 企業の課題およびその解決に向けた方策
を以下に示す。
7.1.1 県内 IT企業の課題
県内 IT 企業が抱えている潜在的な課題および意識している課題について、以下に示す。
(1)県内 IT 企業の内製・自主自立型ビジネス構造への変革に向けた課題
「経済産業省平成 15、16 年度特定サービス産業実態調査報告書(情報サービス業編)」、によると、県内 IT 産業の状況は下記のとおり。
① 2000 年で全国平均の 60%と規模が小さく、1996 年からの 10 年間で企業規模の
縮小化が進んでいる。
② 年間売上高も全国レベルと比べると小さく、微増の状況である。
③ 従業員 1 人当たりの売上も低く、生産性が低い。 ④ 同業者からの受注率は他府県と比較すると 2.5 倍以上となり、依存体質が高い。
また、「(財)産業研究所(JIPRI) 平成 16 年度沖縄における IT 関連人材の確保などに
関する調査研究(委託先:(社)沖縄県情報産業協会)」、によると、県内 IT 企業において
は、下記の課題が挙げられている。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
191
① 経営者層のコア・コンピタンスの欠如
にわとりタマゴ論的議論(仕事が先か人材が先か)が常にあり、経営者層は仕事を
優先し、各企業の人材育成が後手に回っている。
② 下請けの位置付けが永きに渡り日常化
伝統的な下請け体質であることから、視点として、自立化の指針を持っていない
企業が多い。(体験に乏しく、イメージを抱けない可能性も否めない)。しかしながら、安い人件費、地代家賃を強みとする県内 IT 産業における下請け
戦略の限界が訪れつつあり、創意工夫が生み出す付加価値ビジネスへの転換が急
務である。
③ 即戦力を育成するためのカリキュラムがない
一般的な研修で得た知識をスキル化するためには、実践経験による定着化が必要
であるが、経験できる案件総数が少ないこと、また、得た知識を活かせる業務に
必ずマッチングできるわけではないことから、スキルとして定着化できる可能性
が高まらない。
④ 業務受託が要請ベース
従来の下請けの構図では、基本的に要請ベースであり、依頼したい・接近したい
と思わせる動機付けが薄い。国内および海外企業が、先方から接してくる強みを
生み出し、継続的に保持する必要がある。
(2)県内 IT 企業へのアンケート、ヒアリングから導かれた現況における課題
県内 IT 企業からのヒアリング結果から以下の現況における課題が挙げられる。
① 営業、技術者数から見て、県内 IT 企業は、小・零細規模の企業が多い。
② 人材育成面、技術・保守サポート面での不安要素を抱いている。
③ IT 業界のハイアラーキにおける一次、二次の業務レベルに匹敵する営業力、技術
力が備わっていない。
④ 県内 IT 企業の約 4 割の企業が OSS を活用してビジネスを行っているが、このう
ち約 7 割の企業が収益に結び付く取り組みが実施できていない。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
192
⑤ OSS を活用している企業の 4 割が OSS のライセンスに対する考慮なしに活用し
ており、また、ほぼ全ての企業が著作権違反に対する調査を実施せずに OSS を活
用している。
⑥ OSS を活用している企業の約 9 割が OSS を活用していく上でのサポートの後ろ
盾がほしいと考えている。
⑦ 県内 IT 企業では、プロモーション活動の実態把握結果からみて、下請け業務の
受託活動が主体となっている。
⑧ 企業のオリジナリティーを確立する取り組みを行っている企業は、県内 IT 企業
全体からすれば、ごく僅かしか存在しない。
⑨ 県内 IT 企業は、同業者への依存比率が比較的高い傾向にある。
⑩ アンケートの結果により、県内 IT 企業の多くは、アプローチはしているものの、
営業力が弱いと考えている。
(3)課題のまとめ
(1)、(2)の内容を踏まえ、県内 IT企業における課題(まとめ)を図 7.1.1-1 のとお
り、とりまとめる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
193
図 7.1.1-1 県内 IT 企業における課題(まとめ)
7.1.2 課題解消に向けた方策立案と実施内容の検討
前項でとりまとめた県内 IT 企業における課題を解消するための方策について検討する。
検討結果を図 7.1.2-1 に示す。
経営者層のコア・コンピタンスの欠如
下請けの位置付けが永きに渡り日常化
即戦力を育成するためのカリキュラムがない
業務受託が要請ベース
営業,技術者数から見て、県内IT企業は、小,零細規模の企業が多い
人材育成面,技術・保守サポート面での不安要素を抱いている
IT業界のハイアラーキにおける一次,二次レベルの業務レベルに匹敵する営業力、技術力が備わっていない
県内IT企業でOSSを活用している企業のうち、約7割の企業が収益に結び付いていない
OSSを活用している企業の4割がOSSのライセンスに対する考慮なしに活用しており、また、ほぼ全ての企業が著作権違反に対する調査を実施せずにOSSを活用している
OSSを活用している企業の約9割がOSSを活用していく上でのサポートの後ろ盾がほしいと考えている
県内IT企業では、プロモーション活動の実態把握結果からみて、下請け業務の受託活動が主体となっている
企業のオリジナリティー性を確立する取り組みを行っている企業は、県内IT企業全体からすれば、ごく僅か
県内IT企業の多くは、アプローチはしているものの、営業力が弱いと考えている
技術者単価が低い
企業のオリジナリティーが乏しい
技術者不足
営業力が弱い
企業規模が小さい
長期展望での人材育成が困難
短絡的視点で仕事を受託
企業規模拡大が困難
情報収集力が低い
同業者への依存度が高い
県内IT企業は、同業者への依存比率が比較的高い傾向にある
■現況
■課題(まとめ)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
194
図 7.1.2-1 県内 IT 企業における課題を解消するための改善目標検討
上記の方策検討結果を踏まえ、改善のための総括的目標を以下のように定めた。
定めた改善目標を具体的に推進するための実施案について検討する。
この検討結果を表 7.1.2-1 および表 7.1.2-2 に示す。
「独自製品」を持ち、企業特性(得意分野)を明確化するとともに
優れたパートナーの獲得/協同の画策、高度人材醸成機会獲得に
直結する受託案件数の拡大、および営業力の強化を目指す
■課題■課題
マーケティング力の強化
得意分野の創出
優良パートナーの獲得と協同
経営者層の意識改革
即戦力技術者の醸成
新規市場の開拓
商談の主導権獲得
自社商材の保有
■改善目標■改善目標
6
2
4
5
2
5
6
4
重要度重要度
技術者単価が低い
企業のオリジナリティーが乏しい
技術者不足
営業力が弱い
短絡的視点で仕事を受託
企業規模拡大が困難
情報収集力が弱い
同業者への依存度が高い
長期展望での人材育成が困難
企業規模が小さい
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
195
表 7.1.2-1 とりまとめた方策を実現する上での実施案検討結果(1)
表 7.1.2-2 とりまとめた方策を実現する上での実施案検討結果(2)
以上の検討結果より、IT 産業構造における下請けの位置付けとなっていることが多い
県内 IT 企業が、OSS をベースとした製品開発を中心とした県内 IT 企業に共通の課題を解
決する機能を「共用センター」として整備し、低投資・短期間(高効率)・市場にマッチ
したタイムリーな製品を保有することが最も有効な方策であるものと断定する。
①OSSを利用した商品開発②販売会社との連携③商品開発でOJT実施④国内市場で実績のある技術会社,販売会社との協同
実現内容の検討対応策案
自社の投資で実施
他企業と協同で実施
バーチャルセンター(インターネット利用)
共用センターを運用
実現性
投資リスク
創出機会
効果
柔軟性
評点
拡張性
【凡例】◎:3点 ○:2点 △:1点 ×:0点
○ △
△ × △ △ △ △
○ ○ △ ○
○ ○ ○ ○ △ △
○ ○ ◎ ◎ ○ ◎
5
10
10
15
自社商材の保有
①公的資金を活用した商品開発
①実務PJでのOJT実施
マーケティング力の強化
①販売会社との連携
得意分野の創出③指針を定めビジネス実績を蓄積
優れたパートナーの獲得と協同
①国内市場で実績のある技術会社,販売会社との協同
目標 実施施策(案)
②OSSを利用した商品開発
③一般開発要件から自社商材の作成
④他社商品のOEM提供
【凡例】◎:3点 ○:2点 △:1点 ×:0点
○ ◎ ◎
◎ ×
14
②商品開発でのOJT実施
③販売市場・売れ筋商品の目利き
②社内技術営業の配置
④有スキル保有者の雇用
②海外の先進的企業との協同
実現性 投資リスク 創出機会実施機会
◎
△ △○
△ ◎ ○
◎
○
◎
○
△
○
◎
◎
△
◎
△
◎
◎ ◎
◎
効果
◎
◎
△
△
◎
○
○ ◎
◎ ○
◎△ ◎
○
○ △ ◎
◎△
◎ ○ ◎
◎○ △
拡張性柔軟性
◎
△
△
×
○
◎
○
◎
○
◎
○
△
○
10
6
7
12
15
13
10
10
12
9
13
8
評点
※
※本構想の国内での整備と実績が整った後で、実現可能性が高まる
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
196
7.1.3 県内 IT企業による OSS関連事業に向けて設定すべき具体的目標
沖縄県の情報産業を下請け・誘致体質から、内製・自主自立体質へと変革する機会を継
続的に創出していくことを主たる狙いとし、これを達成する上で設定すべき具体的な目標
を以下のように検討した。
① 国内大手企業の製品獲得のトレンドを踏まえ、県内 IT 企業が OSS ベースの商材を創
出することで、国内大手企業が県内 IT企業に自ら接触する動機を作り出すとともに、
国内、国外への事業開拓機会を創出する。
② OSS のソースコードに接する事により、IT 技術者により高度な技術情報に接する機会
を与え、より高いレベルでの活躍の場を提供する。
③ 県内 IT 企業向けに、創出した OSS ベースソフトウェア商材の保守窓口を提供する事
により県内 IT 企業の弱点を補強し、業界における競争力を醸成する。
④ 県内 IT 企業の共同事業参画する機会を創出することにより、ソフトウェア生産におけ
るノウハウを実践の場を通じて享受しつつ、ビジネスの源泉となる技術力を醸成する。
⑤ 沖縄県内 IT 企業とアジア諸国の IT 企業が参画する機会を創出することにより、パー
トナー確保の源泉とする。
7.1.4 共用センターで実現すべき事項
OSS をベースとして独自の商材を実施するのに必要な作業としては、第 3 章で商材のベ
ースとなる OSS を調査したように、商材の材料となり易いのは、海外でシェアが高いが、
国内では知名度が低い OSS がターゲットのひとつとして考えられる。このような観点で商
材の基となる OSS を継続して探索するためのスクリーニング、およびマーケットニーズを
探索するための市場調査を実施する必要があり、さらに、動作検証、品質評価、機能網羅
性検証などを経て、日本語へのローカライズや必要に応じて国際化をする作業が必要とな
り、共用センターでは、これらの作業がコアの要素と捉えることができる。
さらに、県内 IT 企業のアンケート結果から導かれる必要要素としては、県内 IT 業界が
OSS ビジネスの実現に必要としている支援内容とスキルとして挙げられている事項である
人材育成面、技術サポート面での不安要素の解消に向けた支援サービスを具備すべきであ
ると考える。また、県内 IT 企業のプロモーション手段の調査結果から判明しているプロモ
ーション力の弱さを補うための対策を講じる必要もあるだろう。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
197
7.1.5 事業実現へのアプローチ
7.1.1~7.1.4 で検討した、県内 IT 企業による OSS ベースの事業は、沖縄での自立化を目
指すことを目的とし、その主体者は特定の県内 IT 企業ではなく、県内 IT 企業が共同で設
立した NPO や LLP などがそのポジションを担い、県外 IT 企業はこの目的を達成するための
サポートの役割を果たすことが望ましいといえる。
また、その主体者の構成企業としては、県内 IT 企業の中で OSS を活用し独自商材を保
有し、自立ビジネスを目指す企業が候補となる。連携先としては、(独)情報処理推進機構
(IPA)などの公的機関、The Linux Foundation などの主要 OSS 団体や各国に設置されてい
る OSS センター機関、県内では(財)沖縄県産業振興公社などが考えられる。
なお、以下に事業推進スケジュールの案を図 7.1.5-1 に示す。
図 7.1.5-1 事業推進スケジュール(案)
7.1.6 県内 IT企業の共用センター活用の可能性
県内 IT 企業においては、IT 業界の一次、二次の企業レベルに近づく願望を抱いているこ
とが、アンケート結果から判明しているが、OSS 活用状況として、既に OSS を活用している
企業が全企業中約 4割存在している。また、OSS を活用していない企業のうち、約 5割弱が
OSS 活用のリスクに対応する術を検討中としており、さらに、8割弱が OSS の活用に興味を
抱いている状況にある。OSS を活用している企業においては、9割の企業が技術的な後ろ盾
が必要だと考えており、そのうち、約 6割の企業が現状後ろ盾を有していない状況である。
なお、本調査において、アンケート調査した際、同時に、共用センターが設立された場
2009 2010 2011
商材創出作業標準の策定(手法の検証・確立,レベル最適化)
実践教育モデルの策定(手法の検証・確立)
運営組織の整備
運用移行準備
設備整備
運用開始
組織・基盤整備 センター運用
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
198
合の活用意向を調査したところ、既に OSS を活用している企業の約 8割が、「是非活用した
い」、「活用を検討する」と肯定的に回答しており、OSS を活用していない企業においても、
肯定的に回答した企業が 5割存在している。
これらの状況から、県内 IT企業が、共用センターを活用する潜在的なポテンシャルは大
いにあるものといえる。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
199
第8章 調査結果総括
8.1 総括
本調査結果の総括を以下に示す。
(1)OSS 活用商材の潜在的市場規模
「第 2 章 OSS を材料としたビジネスの国内市場調査」において、国内 OSS ベース商材
の販売状況および OSS を利用した IT サービス提供状況とそれらのニーズを調査し、OSS
活用商材の潜在的市場規模を検討した。
(A)OSS のビジネスモデル
従来の企業における閉鎖型の製品開発およびライセンス販売モデル(クローズド・イ
ノベーション)からオープン・イノベーションの概念に裏打ちされた開放型の製品開発、
および新たなオープン・イノベーションの概念によるビジネスモデルの創出へとビジ
ネス活動の本質が変化してきている。このビジネスモデルのパラダイムシフトにオー
プンソースが果たしている役割は非常に大きいものと言え、現段階においても OSS を
活用した多様なビジネスモデルが存在し、生まれている。
市場における OSS を活用した主なビジネスモデルを表 8.1-1 に示す。
表 8.1-1 OSS を活用した主なビジネスモデル
ビジネスモデル
中核 付加要素(狙い所)
OSS の創出 付加サービス販売
デュアルライセンス販売
商用製品へのアップグレード
上位グレードの商用製品へのアップグレード
パートナーシッププログラム
他者開発 OSS の
カスタマイズ
付加サービス
パートナーシッププログラム
商用製品の機能補完/強化 商用製品に OSS を組み込んだ商用製品創出
商用製品と OSS を融合した商用パッケージ創出
商用製品ラインナップに OSS を融合したラインナップ強化
その他 OSS の活用 システム構築
保守
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
200
教育
IT サービスでの活用
(B)OSS 活用商材の潜在的市場規模
IPA 実態調査における「ソフトウェア業」、「情報処理・提供サービス業」、「インター
ネット付随サービス業」、および「その他 OSS 関連ビジネス」の市場規模算出結果を基
に算出した、IT 市場全体としての OSS 活用市場規模、潜在的 OSS 市場規模、阻害要因
解消後の OSS 活用市場規模の算定結果を図 8.1-1 に示す。
図 8.1-1 IT 市場における OSS 活用市場規模算定結果
2007 年の OSS 活用市場規模は 2 兆 9,782 億円(全体市場の 14.0%)、潜在的な OSS 活用市
場規模は 6 兆 1,176 億円(同 28.8%)と推察でき、2010 年には OSS 活用市場規模が 3 兆 5,726
億円(同 15.8%)(阻害要因が解消された場合のOSS活用市場規模は、4兆 9,643億円(同 22.0%))、
潜在的な OSS 活用市場規模は 10 兆 26 億円(同 44.1%)まで成長するものと推察される。
以上の算定結果から、国内の IT 市場において OSS 活用市場は着実に成長を遂げるものと
予測できるとともに、同市場に根ざす IT 企業にとって、欠かすことのできないビジネスの
材料として着実に定着化していくことがうかがえる。
(2)商材化の可能性を有する OSS
「第 3章 商材化の可能性を有する OSS の予備調査」において、OSS ベースに商材を開
発することを想定し、今後数年にわたり、市場の伸び率の高いソフトウェア分類を探索
2兆9,782億円(14.0%)
6兆1,176億円(28.8%)
21兆2,250億円(100%)
3兆5,726億円(15.8%)
4兆9,643億円(22.0%)
10兆26億円(44.1%)
2010年
22兆6,624億円(100%)
2007年
2005年
OSS活用市場規模 潜在的OSS活用市場規模
阻害要因解消後のOSS活用市場規模
全体市場規模
0 10 (兆)20
2兆6,077億円(12.2%)
21兆3,594億円(100%)
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
201
することを前提に、この分類に属する OSS を独自に作成した OSS ベース商材の材料を探
索するための評価基準を用いて評価を行い、インターネットの OSS リポジトリを情報源
として、商材化の可能性を有する OSS をサンプルとして抽出した。
結果として、コラボレーティブアプリケーション(5 本)、コンテンツアプリケーション
(5 本)、オペレーション/製造管理アプリケーション(5本)、エンジニアリングアプリケ
ーション(3 本)、CRM アプリケーション(4 本)、品質ライフサイクルツール(2 本)、イン
テグレーション/プロセスオートメーションミドルウェア(4 本)、データアクセス/解析
/デリバリーソフトウェア(5本)、システム/ネットワーク管理ソフトウェア(5本)、セ
キュリティソフトウェア(6 本)、ストレージソフトウェア(5本)、システムソフトウェア
(6 本)を抽出した。
なお、本調査において、今後成長が期待される各ソフトウェア分類における OSS ベー
スの商材開発の材料をサンプル抽出することができたが、今回対象とした情報源を網羅
できたわけではなく、また、単独で公開している OSS などが世界中に散見しており、さ
らにより多くの有望な OSS が存在するため、継続的な探索および抽出を実施することが
望まれる。また、本調査で実施した OSS の抽出方法は、今後、探索および抽出を実施し
ていく上での有効な実施方法のひとつとなりえるものと考える。
さらに、抽出した OSS は、商材化のベースとなる可能性を秘めた対象ソフトウェアで
あるとはいえるが、今後、動作確認、著作権違反有無などを実施し、さらに精査する必
要がある。
(3)県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成の条件
「第 4 章 県内 IT 企業の OSS 活用条件および OSS 技術者育成の条件」において、県内
IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容およびビジネス展開に必要
な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容について、アンケート調査を踏まえて
検討した。
(A)県内 IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容に関する考察
県内 IT 企業の OSS 活用ビジネスを展開するための条件・整備内容を検討する上で、
基礎情報となる県内 IT企業の販路とプロモーション手段について、調査した。県内 IT
企業の主な販路としては、OSS を活用している企業、OSS を活用していない企業の間に
特徴的な差はない。両者ともに、ユーザの割合が突出しており、この中で特に官公庁・
外郭団体向けの比率が最も高く、次にサービス業が続いている(県内 IT 企業のユーザ
が県内に多いことを表しているものと考えられる)。なお、OSS を活用している企業の
ユーザの比率が 1 割程度高いのは、官公庁・外郭団体の OSS 関連の採用が多いことが
理由として推察される。なお、OSS を活用している企業では、現時点で、ベトナム、カ
ンボジア、インドに販路を有する企業が 3 社存在し、また、今後、米国、ヨーロッパ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
202
各国、アジア各国、香港への進出を計画している企業が 4社存在するが、OSS を活用し
ていない企業では、海外に販路を有している企業はなく、進出を計画している企業が
わずか 2社程度であった。この結果から、断定することはできないものの、OSS を活用
している企業のほうが、グローバルに視野を向けている傾向が高いものと推察する。
さらに、プロモーション手段については、全般的に、コーポレートプロモーションの
手段として、営業アプローチの割合が高い。OSS を活用している企業のほうが OSS を活
用していない企業に比べ、コーポレートプロモーションが活発であり、特に、OSS を活
用している企業では、OSS ビジネスの特徴であるイベント関連でのプロモーションが活
発である。製品プロモーションについては、両者で対照的な差があり、OSS を活用して
いる企業は、ホームページでのプロモーションの割合が最も高く、続いて営業アプロ
ーチとなっているのに対し、OSS を活用していない企業は、営業アプローチの割合が最
も高く、続いて特に実施していないという割合が高くなっている。OSS を活用していな
い企業の状況は、下請け業務の受託活動の典型と想起させる内容となっており、OSS を
活用していない企業がビジネスの強みは、約 6 割弱の企業が「受託開発(SI)」、「技術
者派遣」であるとしており、これを裏付けている。
県内 IT 企業が考える商用製品と OSS を比べた際のメリット・デメリットとしては、
OSS を活用している企業、OSS を活用していない企業ともに、「低価格で顧客に提供で
きる」、「ソースコードを参照し変更することができる」、「多くの種類の OSS が利用で
きる」という 3つの点を OSS 活用の最大のメリットとして捉えている。
OSS を活用している企業のほうが、より多くの事項をメリットとして捉えており、特
に「低価格で顧客に提供できる」、「多くの種類の OSS が利用できる」という実体験に
基づくと推察されるメリットを高く評価しているが、OSS コミュニティの開発継続の不
安定さおよび技術サポートの得にくさを抱いている。
県内には、OSS および関連製品使用中の企業が一定数存在するものの、その中の多
くの企業が OSS をビジネスに活かせていない(収益につなげられていない)か、もしく
は社内に限定した使用などにとどまっているものと推察される。また、自社で OSS の
活用や保守ができる企業が OSS を活用している企業の半数強存在しており、その他半
数は、外部の OSS 関連サービスを活用していることがわかった。
OSS を活用している企業のビジネスについては、間接的に活用(教育サービス、シス
テム構築での活用など)している企業が 8割弱に達しており、システム構築などで定常
的に OSS が活用されていると断定できる。さらに 6割強が OSS を商材化している、もし
くは自社のオリジナリティーを高めるための材料として活用しており、7割強が OSS を
活用するスキルを持ち合わせているが、6割強は、ソースコードを読み、改変できる技
術力を有しており保守も実施できるものと推察される。
OSS を活用している企業の OSS を活用する際にライセンスに関する考慮については、
6割弱が行っているが、ソースコードに宣言されているライセンス憲章については、考
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
203
慮されているもののソースコードそのものの著作権違反については、考慮が行き届い
ていないことが推測され、さらに著作権、ライセンスに関する考慮をしていない企業
が 4 割強存在しており、大きな課題のひとつであるといえる。これについては、各企
業において、「OSS を活用する上での著作権、ライセンスに関する考慮の必要性」の浸
透を図る、ソースコードレベルで著作権違反に対する調査を実施するなど、何らかの
方法で対策を講じていく必要がある。
OSS 活用ビジネスを遂行していく上で後ろ盾が必要だと考えている企業は、OSS を活
用している企業の 9 割に達しており、その理由として、「予防措置(技術的に対応でき
ない場合や緊急の場合)」、「OSS のサポート(障害などの原因を特定できない、Update
情報、脆弱性情報などの入手のため)」、「OSS に対する知識・技術不足の補完」を挙げ
ている。一方、必要だと思わない企業は、自社内での対応やサポートできる OSS の吟
味、という点を重視している。ただし、必要だと考えている企業で実際に技術的な後
ろ盾(開発・保守)を有しているのは、約 4 割にすぎず、技術的な後ろ盾(開発・保守)
を有していない 5割強の企業は、OSS サポートに関して、全ての企業が技術的な後ろ盾
が欲しいと考えている。
一方、OSS を活用していない企業は、知識だけでも認識することが可能な点をメリッ
トと捉えている企業が多く、同じように知識先行で“リスクあり”と捉えているよう
に見受けられるが、うち、5割弱がOSS活用のリスクに対応する術を検討中としており、
さらに、OSSを活用していない企業の8割弱がOSSの活用に興味を抱いていることから、
活用を検討する割合が今後さらに増加することが見込まれる。
OSS を活用する決断要素としては、OSS を扱うことができる技術者の増加と企業幹部に対する OSSの正しい認知の醸成が必要不可欠な要件となっている。
県内 IT 企業では、OSS ビジネスの実現に向けて、人材育成面、技術・保守サポート
面での不安要素を解消するための支援サービスを求めており、また、OSS ビジネスの
実現に必要と考えるスキルは、システムインテグレーションにおける上流工程のスキ
ルが上位を占めている。このことから、IT 業界のハイアラーキにおける一次、二次の
業務レベル、いわゆるプライムコンストラクターになれる、もしくはレベルの向上を
果たしたいという願望と県内 IT 業界のウィークポイントが読み取れる。
(B)OSS 活用ビジネスの展開に必要な人材育成を行うために整備すべき条件・整備内容に
関する考察
県内 IT 企業の人材育成方法は、割合的に社内独自研修と ITOP に大きく偏っている
が、社内独自研修の内容は定かではないものの ITOP は座学中心のカリキュラムであり、
OSS を扱うことができる技術者の増加を目指すのであれば、座学ではなく、コミュニテ
ィへの参加などの検討など、実践を取り入れる形で人材育成の方法を見直す必要があ
る。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
204
また、県内 IT企業では、未だ OSS に関する知識の浸透が薄いことから、特に企業の
経営幹部向けに OSS に関する認知度向上のための取り組みを図っていく必要がある。
なお、これらの取り組みは、OSS を活用していない企業が OSS を活用する決断を促す
効果をもたらすものと考える。
(4)OSS を活用したインターンシップの可能性
「第 5 章 OSS を活用したインターンシップの可能性調査」において、教育機関へのヒ
アリング調査とインターンシップ学生を受け入れる企業へのアンケート調査により、OSS
を活用したインターンシップの可能性を考察した。
各教育機関のインターンシップでは、インターンシップ先がバラエティに富んでお
り、いずれの学校も IT関係が含まれている。インターンシップの実施時期は、各大学
とも夏休み期間中が多く、期間は 1週間から 1ヶ月。参加対象年次は3年次(高専は4
年次)が多く、ほとんどの学校が、インターンシップ先を学生が選定している。
インターンシップは、学校、学生双方にとって、事実上就職活動の一環として運用
されているものと推察されるが、学校毎に修得単位制度が異なっており、インターン
シップの期間により修得単位の種類と量が多い学校は、同学校の参加学生が他の学校
と比較し飛び抜けて多いことから、学生のインターンシップの参加意向の高さの要因
のひとつとなっているものと推察される。これは、学生にとって非常に重要なポイン
トであると思われる。学生の視点に立ってみれば、基本単位である 2 単位以上が取得
できなければ、講座としての魅力はなく、純粋にインターンシップそのものの価値が
修得するか否かを左右している可能性も否めない。インターンシップ制度は、既に一
部の学校では実現できているものの多くの学校ができていない「学生視点でのインタ
ーンシップ制度の価値化」として、単位制度の充実化を各学校が改善していくことが
求められる。
インターンシップ制度は、教育機関側から見れば、学生の就職希望業種における社
会体験と就職先へのコネクション強化の意味合いを持つが、既存のインターンシップ
制度では、実質的には社会体験の要素が強い。一方、企業の視点では、社会的貢献活
動の一環としての位置付けと優秀な人材の獲得の意味合いを持っているものの「実務
で活用したい」、「人材不足で即戦力を獲得したい」という希望が垣間見え、一部は、
教育機関と企業の思惑が合致しているものの、企業側の要望のほうが教育機関のそれ
を上回っている。これは、インターンシップ運営上の課題のひとつとして捉えること
ができる。
インターンシップの制度運営上の課題としては、教育機関側が、企業が何をやって
いるのか把握できておらず、適切なインターンシップ先が探索できないことやインタ
ーンシップ先は先生個々人の人脈に依存していることが多いことから、受け入れが形
骸化し、広がりを期待するのが難しくなる、などの課題がある。また、教育機関側と
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
205
企業側のインターンシップに関する需要と供給のマッチングが図れていないという点
も課題である。
多くの学校で、インターンシップ受入企業紹介サービスなどの整備を望む声があり、
同様に企業側からも望む声が多い。教育機関と受入企業の需要供給のマッチングと双方
の価値化を図るための「受入企業紹介サービス」を整備すると、学生視点においても、
価値化につながる。
実務面においては、教育機関側としては学生が実務に関わり体験させることを望んで
いるが、実務に関わらせることは、責任範囲における瑕疵担保などの保障が難しい、と
いう問題をはらんでおり、現状制度上では、この問題が学生を実務に関わらせることに
対する大きな障壁であると考えられることから、“学生を送り出す教育機関側が学生の
責任を担保することをより明確化する”、“企業側において、実務従事に対するボーダー
を下げる工夫をする”、などの対策を検討する必要があると考える。
以上のことから、教育機関側、企業側双方でインターンシップを行う有用性は認識
しているものの、制度の整備不足や双方の狙いが合致していないことは明らかである。
この希少な機会をより有効に実現するには、以下の環境整備が必要である。
・教育機関側の整備として、学生視点での価値化を行い、学生のインターンシップ
に対するモチベーションを向上させる
・受入れ可能企業のリスト化と企業特性の検索の利便性を向上させ、企業と学生の
アンマッチを低減する
・企業側の整備として、受け入れ条件の明確化と教育機関への申し入れを行い、教
育機関の企業リスト化に協力する
・企業側の整備として、受け入れ時の社会体験内容を明確化させ、場当たり的な作
業をさせない
・企業側の整備として、既存業務だけでなく、担保の問題を軽減できる可能性のあ
る新規業務分野までインターンシップの適用領域を広げる
このような環境条件を検討・整備することにより、インターンシップが活性化し、
OSS ベース商材で企業がビジネスする際の要員確保の有益な手段のひとつになる可能
性を向上させられるものと考える。
一方、企業側のインターンシップ経験者の採用意向としては、6 割の企業が採用に際
しての有効条件と見なしている。
企業側としての教育機関への要望は、「学生のレベル向上」を挙げる企業が多く、全
体の 60%を占めている。また、「制度の明確化」、「期間延長」なども要望として挙げら
れており、前述したインターンシップ制度上のルールの明確化や 1~4 週間と短い期間
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
206
での受け入れは、企業側からの視点として、実業を体験させるには困難であり、受け
入れる上では有効なリソースとして活用したいがそれもままならず、単なる社会体験
で終わってしまう、と考えているのではないかと推察する。
従来のインターンシップ制度は、各企業のなんらかの既存業務に学生を就業体験さ
せるというスキームである。このスキームをより発展的な視点で捉えるべきである。
「貴社技術者とともに新規の共同作業(例えば、開発)に携わった学生は、製品販売時の
営業、SE、保守の即戦力となるか、もしくは社内での人材育成費用の削減につなが
る可能性があります。このような位置付けの学生を新規採用したい、もしくは優先的
に交渉しようと思いますか?」という設問に対しては、示唆に富む回答が得られた。
通常、新規の共同作業に携わった学生の新規採用に関して、3割強の企業人物本位での
採用、を挙げている。これは採用の考え方として当然のことであるが、この質問に対
しては、7 割弱の企業が、共同作業に携わった学生を優先的に交渉する意思を示してい
る。これは、既存のインターンシップの内容よりも若干高い。 よって、インターンシップの内容を見直すなど、受け入れ企業側での視点を変えて
みることにより、企業側の人材獲得によい効果を与える可能性があるものと考える。
(5)海外の IT企業における OSS ベース商材創出の調査
「第 6 章 海外の IT 企業における OSS ベース商材創出の調査」において、アジア地域
に対しては、県内 IT 企業の具体的な海外進出市場としての可能性を検討し、欧米地域に
おいては、同地域での IT 企業の状況把握を実施することが、今後、県内 IT 企業の OSSビジネスにとって有益な参考情報となることから、付加的な位置付けとして、調査を行
った。
アジア各国では、OSS の普及推進が盛んであるが、本調査においては、特に OSS に対す
る中国国内での地域毎の企業傾向が明確となった。華北では、政府系、インフラ系をタ
ーゲットとした企業やオフショアに取り組む企業が多い。華北の中心である北京では、
認知が進んでおり、周辺地域においては、北京と比較し若干認知度合いが劣るものの、
Linux/OSS を定常的にビジネスで活用している実情にあることがわかった。この地域では、
早い段階から政府による Linux/OSS 普及推進政策が実施され企業における定着化が進ん
だものと推察される。華中では、国内の民需系をターゲットとした企業が多い。中心で
ある上海では、企業における Linux/OSS の認知が進んでおらず、受託システム開発など
での活用も乏しいようである。上海では、政府方針として Windows を継続して推奨して
いることや独自製品保有よりも他社製品を活用したカスタマイズド・ビジネスが主体に
なっている、などがこの要因として考えられる。華南では、環境条件から組み込みソフ
トウェアに関連する企業が多く、また、国内の政府系、インフラ系、民需系をターゲッ
トとした企業が混在している。全土からみると華南は、IT 産業政策の推進が後発的な位
置付けであるものの、中心である広東省は、製造業が数多く立地する深圳、自動車業界
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
207
が数多く立地する広州を要しており、組み込みソフトウェアに対するビジネスが実施し
易い環境にあることや、省政府での積極的な Linux/OSS の普及推進政策により、認知が
進んでおり、多くの企業で Linux/OSS を活用している状況にある。この影響は、良い意
味で省内の香港、澳門両特別区にも及んでおり、両区にも組み込みソフトウェア企業や
Linux/OSS を活用している IT企業が数多く存在する。
中国の企業において、すべての企業が沖縄の歴史的背景、中国との関係性の理解とと
もに世界有数の観光地であるという認識を持っており、また、文化的にも類似項が多い
ことも認識している。この県内 IT企業との提携に関しては、いずれの地域でも情報・リ
ソースの共有や製品をベースとした、共同開発を含む協業などで可能性があると考えて
いることがわかった。県内 IT企業と沖縄で OSS ベースの製品開発を共同実施する、とい
う一歩踏み込んだ協業については、華北、華南という Linux/OSS の認知が比較的進んで
いる地域では、多くの企業が自費渡航での参画が可能と考えていることがわかった。こ
れは、OSS の認知度が進んでいることだけでなく、OSS が自社製品の材料となる可能があ
ることを認識していることや、ビジネスが安定しており投資余裕があること、政府から
の補助など何らかの支援が得られることなどが背景にあるものと推察される。
中国の多くの企業は、IT 業界に立脚しはじめた当初は、単価の安さを強みとしてオフ
ショアを主軸としたビジネスを展開し、オフショア業務において下流工程から上流工程
へと段階的に活用の幅が拡がり、要素技術やノウハウを蓄積し続けている。現在では、
これを背景として、業種が 100%オフショアの企業も存在すれば、100%国内市場に向いて
いる企業もあり、多くの企業がこの狭間に存在している。このオフショアが主軸、もし
くは主要の一つとなっている企業が多い中国企業の実情からすれば、県内 IT 企業は、あ
る種中国の IT 企業のコンペティタであり、単価も近年では拮抗しつつある状況にある。
しかしながら、システム開発やソフトウェア開発に係る経年でのさまざまな蓄積ノウハ
ウやソフトウェア製品の企画などの観点から見れば、県内 IT企業で強みが見出せる部分
が存在しているといえる。一方の中国の IT企業には、生産力の高さや中国という巨大市
場における有効な人脈を保有している可能性とマーケティング力などに強みがあると考
えられる。県内 IT企業が独自のソフトウェア製品を保有し、これを軸とすれば、製品品
質や市場適合性などにも左右されるのは前提条件として存在するが、コンペティタとし
てではなく、日本・中国市場における市場開拓において、相互補完の関係を築くことが
できる可能性を有しているものと考える。沖縄 IT津梁パークと山東斉魯ソフトウェアパ
ークなどに代表される国営のソフトウェアパークとの連携などが、これをさらに強固な
流れとしていくものと推察されることから、日本側、中国側相互で具体的な検討が始ま
ることを期待したい。
(6)事業連携に向けた体制構築
「第 7 章 事業連携に向けた体制構築」において、OSS ベース商材構築に向けての事業
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
208
連携を目指し、県内 IT企業を中心とした推進体制の構築を検討した。
県内 IT 企業に共通の構造として、発注元と発注先は、収益構造が大きく異なっており、
発注元は損益確保の主導権を持つことから利益が出しやすく、一方の発注先では、発注
元のコストセービングの指針の下、収益を上げづらいという背景がある。
沖縄において、今後真の自立経済振興と雇用創出を継続的に推進し続けていくために
は、損益確保の主導権が持ち得て、県外 IT企業への依存性が低い、内製型ビジネス構造
への変革のための取り組みを早期のうちに実現していく必要がある。
この損益確保の主導権を持つためには、競争力のある製品や関連ノウハウ、技術力を
保有する必要があり、県内 IT 企業が市場競争力を有する活動形態へと変革させていくた
めの取り組みが必要である。その上での県内 IT 企業の課題およびその解決に向けた方策
を検討した結果、以下の改善目標を定めた。
「独自製品」を持ち、企業特性(得意分野)を明確化するとともに優れた
パートナーの獲得/協同の画策、高度人材醸成機会獲得に直結する受託
案件数の拡大、および営業力の強化を目指す
この改善目標を具体的に推進するための実施案について検討した結果、IT 産業構造におけ
る下請けの位置付けとなっていることが多い県内 IT 企業が、OSS をベースとした製品開
発を中心とした県内 IT 企業に共通の課題を解決する機能を「共用センター」として整備
し、低投資・短期間(高効率)・市場にマッチしたタイムリーな製品を保有することが最も
有効な方策であると断定する。
さらに、沖縄県の情報産業を下請け・誘致体質から、内製・自主自立体質へと変革す
る機会を継続的に創出していくことを主たる狙いとし、これを達成する上で設定すべき
目標を以下のように検討した。
① 国内大手企業の製品獲得のトレンドを踏まえ、県内 IT 企業が OSS ベースの商材を
創出することで、国内大手企業が県内 IT 企業に自ら接触する動機を作り出すとと
もに、国内、国外への事業開拓機会を創出する。
② OSS のソースコードに接する事により、IT 技術者により高度な技術情報に接する機
会を与え、より高いレベルでの活躍の場を提供する。
③ 県内 IT 企業向けに、創出した OSS ベースソフトウェア商材の保守窓口を提供する
ことにより県内 IT 企業の弱点を補強し、業界における競争力を醸成する。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
209
④ 県内 IT 企業の共同事業参画する機会を創出することにより、ソフトウェア生産にお
けるノウハウを実践の場を通じて享受しつつ、ビジネスの源泉となる技術力を醸成
する。
⑤ 沖縄県内 IT 企業とアジア諸国の IT 企業が参画する機会を創出することにより、パ
ートナー確保の源泉とする。
事業実現へのアプローチとして、共用センターで実現すべき事項としては、OSS をベー
スとして独自の商材を実施するのに必要な作業が中心となる。第 3 章で商材のベースとな
る OSS を調査したように、商材の材料となり易いのは、海外でシェアが高いが、国内では
知名度が低い OSS がターゲットのひとつとして考えられる。このような観点で商材の基と
なる OSS を継続して探索するためのスクリーニング、およびマーケットニーズを探索する
ための市場調査を実施する必要があり、さらに、動作検証、品質評価、機能網羅性検証な
どを経て、日本語へのローカライズや必要に応じて国際化をする作業が必要となり、共用
センターでは、これらの作業がコアの要素となるものと捉えることができる。
さらに、県内 IT 企業のアンケート結果から導かれる必要要素としては、県内 IT 業界が
OSS ビジネスの実現に必要としている支援内容とスキルとして挙げられている事項である
人材育成面、技術サポート面での不安要素の解消に向けた支援サービスを具備すべきであ
ると考える。また、県内 IT 企業のプロモーション手段の調査結果から判明しているプロモ
ーション力の弱さを補うための対策を講じる必要もある。
県内 IT 企業による OSS ベースの事業は、沖縄での自立化を目指すことを目的とし、そ
の主体者は特定の県内 IT 企業ではなく、中立性に鑑み、県内 IT 企業による NPO や LLPなどがそのポジションを担い、県外 IT 企業はこの目的を達成するためのサポートの役割を
果たすことが望ましいといえる。
また、その主体者の構成企業としては、県内 IT 企業の中で OSS を活用し独自商材を保
有し、自立ビジネスを目指す企業が候補となる。連携先としては、(独)情報処理推進機構
(IPA)などの公的機関、The Linux Foundation などの主要 OSS 団体、県内では、(財)沖縄
県産業振興公社などが考えられる。
なお、以下に事業を推進する理想的なスケジュールを図 7.1.4-2 に示す。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
210
図 7.1.4-2 事業スケジュール(案)
県内 IT 企業による共用センター活用の可能性に関しては、県内 IT 企業においては、IT
業界の一次、二次の企業レベルに近づく願望を抱いていることが、アンケート結果から判
明しているが、OSS 活用状況として、既に OSS を活用している企業が全体の約 4 割存在し、
また、OSS を活用していない企業のうち、約 5割弱が OSS 活用のリスクに対応する術を検討
中としており、さらに、8割弱が OSS の活用に興味を抱いている状況にある。OSS を活用し
ている企業においては、9割の企業が技術的な後ろ盾が必要だと考えており、そのうち、約
6割の企業が現状後ろ盾を有していない状況である。
なお、本調査において、アンケート調査した際、同時に、共用センターが設立された場
合の活用意向を調査したところ、既に OSS を活用している企業の約 8 割が「是非活用した
い」、「活用を検討する」と肯定的に回答しており、OSS を活用していない企業においても、
肯定的に回答した企業が 5割存在している。
これらの結果から、県内 IT企業が、共用センターを活用する潜在的なポテンシャルは大
いにあるものといえる。
8.2 提言
本調査で新たに得た情報、および知見を活かし、「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調
査報告書」に記載されている OSS 活用推進センターの構想提案をベースとした、OSS 商材活
用ビジネスの創出に向けた事業環境に関する提言を以下に示す。
F/S
2009 2010
運用組織・基盤整備
・市場調査・市場調査
・実現性検討・実現性検討
・詳細計画策定・詳細計画策定
2008 2011
Phase0 PhaseⅠ PhaseⅡ
・運用開始
(NPO,LLPなど)
・ユニット設備整備・ユニット設備整備
・ソフトウェア創出手法の確立・ソフトウェア創出手法の確立//検証検証
・実践教育モデル・実践教育モデル//手法確立手法確立
・県内・県内//県外企業参加スキーム確立県外企業参加スキーム確立
・インターンシップスキーム・インターンシップスキーム//手法確立手法確立
・企業コラボレーションスキーム・企業コラボレーションスキーム//手法確立手法確立
・実践による全スキーム・実践による全スキーム//手法の改善検証手法の改善検証
・運用移行準備・運用移行準備
・組織化
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
211
「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調査報告書」に記載されている OSS 活用推進センタ
ーの構想提案の事業概要抜粋を以下に示す。
事業概要
本事業は、県内の情報産業を内製・自主自立体質へと変革する機会を継続的に創出する
ため、変革の源泉となる、商材創出/獲得,技術スキル定着化、市場開拓力獲得とこれらの
支援を行うためのセンター機構を整備、後に独立した支援事業を運営する基盤を確立する
ことにより、県内 IT 産業の事業拡大およびこれに伴う雇用拡大を目指すものである。
本事業の遂行に必要となるセンターの全体俯瞰図を以下に示す。
企 業 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン ユ ニ ッ ト
人 材 育 成 管 理 ユ ニ ッ ト
マ ー ケ テ ィ ン グ ・ ス ク リ ー ニ ン グ ユ ニ ッ ト
評 価 ・ 検 証 ユ ニ ッ ト
カ タ ロ グ D B 管 理 ユ ニ ッ ト
サ ポ ー ト Q & A ユ ニ ッ ト
海外IT企業・国内ユ|ザ参 照 ・ 活 用
ロ ー カ ラ イ ゼ ー シ ョ ン ユ ニ ッ ト
カ タ ロ グ D B
県 内大 学
海 外主 要団 体
県 外IT
企 業
県 内 IT 企 業
参 画
仲 介(代 理 店 / S I)O S SO S SO SS ベ ー ス
商 用
コ ラ ボソ リ ュ ー シ ョ ン
コ ラ ボソ リ ュ ー シ ョ ン
提 携
参 画O S S開 発
コ ミ ュ ニ テ ィ
海 外 IT 企 業 ・ 国 内 ユ ー ザ
提 案
イ ン タ ー ンシ ッ プ
A S EA NIT 企 業
提 携
O JT 派 遣
引 き 合 い ・ S I受 注
技 術 移 転
ナ レ ッ ジ D B
<OSS活用推進センター俯瞰図>
同センターは、大別して 3つの機能で構成される。
<OSS活用推進センター機能一覧>
マーケティング・マーケティング・スク リーニングユニットスクリ ーニ ングユニ ット
評価評価 ・検証・検証 ユニットユニット
ローカ ライロ ーカライゼーションユニットゼーションユ ニット
カタ ログDB管理ユニットカ タロ グDB管 理ユニット
企業 コラボ レーションユニット企業コラボレ ーションユニット
人材育 成人材育成 管理管 理ユニットユニット
サポートQ&Aユ ニットサポートQ&Aユニット
■対 象OSSのロ ーカライズ
■カタログDBの 運用管理(取り扱い企業 情報の 収集・管 理を含 む)
■カタログDBに よるWeb代行販 売■カタログDBに 掲載するOSSの 試用環境の 提供
■ 機能不足検出 時の微小 開発の実 施
■ カタ ログDBに登録さ れた OSSに関す る人材 教育実施■ ローカライゼーション,ス タッキング検証に おける実践
教 育のステータス管理■ 県内IT企業 ,ASEAN諸国企業,学 生を対 象とした
イ ンターンシップ受け入れ
■ 対象OSSの定 性評価
■沖縄 企業へ のOSSソリューションの技 術移転■県外 企業と沖縄 企業との マッチング■ASEAN諸国 企業のコ ネクション管理
■セミナー・イベ ントの開催
■カタログDB登録済 OSS に対するサポートおよびQ&A整備
■市場 調査,スク リーニングの実施■OSSバ ージョンアップに 対する定点観測の 実施
商 材 創出 機 能
商流 コ ーディネート
機 能
人材 育 成管 理
機 能
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
212
1)商材創出機能
OSS は、現在、世界中に開発 PJ が点在し、その数はさらに増大の一途を辿っている。
商材創出機能では、商材創出の基となる OSS の調査、スクリーニングにより、SI や SaaS、
Web2.0 などのビジネスで活用しうる OSS を発掘し、これを商材として整備するために必
要な取り組みを行う。
【【OSSOSS単体の場合単体の場合】】
OSSの調査・スクリーニングを実施【マーケティング・スクリーニングユニット】
対象OSSの定性評価を実施【ソフトウェア評価ユニット】
カタログDBに登録【カタログDB管理ユニット】
対象OSSのローカライズを実施【ローカライゼーションユニット】
【【新ソリューション創出新ソリューション創出の場合の場合】】
OSSの組み合わせを検討/検証し、新ソリューションのプロトタイプを開発
【評価・検証ユニット】
作業参画県内IT企業と県外企業をマッチング【企業コラボレーションユニット】
OSSカタログDB
対象OSSの定性評価を実施【ソフトウェア評価ユニット】
カタログDBに登録【カタログDB管理ユニット】
対象OSSのローカライズを実施【ローカライゼーションユニット】
機能不足時は機能追加を検討
世界中で増加するOSS世界中で増加するOSS
これらの作業においては、センター要員の他、県内 IT 企業の参画を前提とし、共同で商
材創出工程の各作業を遂行することにより、県内 IT 企業における実践的な生産ノウハ
ウ,技術スキルの醸成を目指す。
また、県内 IT 企業の視点から、OSS ベースの商材を取り扱う上で保守に関しては商用ソ
フトウェアを取り扱う際の同等条件が必要であると想定することから、県内 IT 企業向け
に、創出した OSS ベース商材の 2次的保守窓口の機能を提供する。
2)商流コーディネート機能
県外 IT 企業の参画調整および OSS ベース商材に関する企業間の提携/業務委託の窓口,
仲介を遂行する。
また、カタログ DB,セミナー,イベントなどを通じたプロモーション活動を展開する。
3)人材育成管理機能
商材創出機能の「OSS ベース商材の創出フロー」に基づき、県内 IT 企業,ASEAN 諸国企
業の PJ による実践訓練を実施し、OSS ベース商材を取り扱うことを可能とする商材スキ
ル,技術スキルの醸成や OSS ベース商材の生産ノウハウを醸成する。この時の個々人の
教育状況を管理し、その状況に応じて随時レベルアップ対策を実施する。
なお、県内 IT 企業の新規即戦力醸成を目的として、インターンシップ学生の受け入れや
パートナー候補獲得を目的とした ASEAN 諸国企業の受け入れも併せて実施する。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
213
この「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調査報告書」に記載されている OSS 活用推進セ
ンターの事業構想において、本調査で新たに得た情報、および知見を踏まえ、改良、改善
すべき点を提言事項としてとりまとめる。
(1)事業構想に反映すべき、本調査で新たに得た情報および知見
本調査で新たに得た、OSS 活用推進センターの事業構想に反映すべき情報および知見
と各事項の重要度を表 8.2-1 に示す。
表 8.2-1 本調査で新たに得た情報、および知見と各事項の重要度
項番本調査で得た情報・知見
重要度事項 詳細
1 県内 IT 企業が許容でき
る製品開発投資額
県内 IT 企業が許容できる製品開発投資
額は、7割弱が 3人月(120 万未満)と非
常に限られている。
重要
2 コーポレートプロモー
ションの手段
営業アプローチの割合が高い。OSS を活
用している企業のほうがOSSを活用して
いない企業に比べ、コーポレートプロモ
ーションが活発であり、特に、OSS を活
用している企業では、OSS ビジネスの特
徴であるイベント関連でのプロモーシ
ョンが活発である。
重要
3 県内 IT 企業が抱いてい
る不安要素
OSS を活用している企業のほうが、より
多くの事項をメリットとして捉えてお
り、特に「低価格で顧客に提供できる」、
「多くの種類の OSS が利用できる」とい
う実体験に基づくと推察されるメリッ
トを高く評価しているが、OSS コミュニ
ティの開発継続の不安定さおよび技術
サポートの得にくさを抱いている。OSS
活用ビジネスを遂行していく上で後ろ
盾が必要だと考えている企業は、OSS を
活用している企業の 9割に達しており、
そのうち、技術的な後ろ盾(開発・保守)
を有していない 5 割強の企業は、OSS サ
ポートに関して、全ての企業が技術的な
後ろ盾が欲しいと考えている。また、OSS
ビジネスの実現に向けて、人材育成面、
技術・保守サポート面での不安要素を解
消するための支援サービスを求めてい
る。
重要
4 OSS のライセンス、著作
権に関する考慮
OSS を活用している企業の OSS を活用す
る際にライセンスに関する考慮につい
ては、6割弱が行っているが、ソースコ
ードに宣言されているライセンス憲章
重要
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
214
については、考慮されているもののソー
スコードそのものの著作権違反につい
ては、考慮が行き届いていないことが推
測され、さらに著作権、ライセンスに関
する考慮をしていない企業が4割強存在
しており、大きな課題のひとつであると
いえる。これについては、各企業におい
て、「OSS を活用する上での著作権、ラ
イセンスに関する考慮の必要性」の浸透
を図る、ソースコードレベルで著作権違
反に対する調査を実施するなど、何らか
の方法で対策を講じていく必要がある。
5 OSS を活用していない企
業の OSS 活用決断要素
OSS を活用していない企業のうち、5割
弱がOSS活用のリスクに対応する術を検
討しており、さらに、OSS を活用してい
ない企業の8割弱がOSSの活用に興味を
抱いており、活用を検討する割合が今後
さらに増加することが見込まれる。OSS
を活用する決断要素としては、OSS を扱
うことができる技術者の増加と企業幹
部に対するOSSの正しい認知の醸成が必
要不可欠な要件であり、OSS に関する認
知度向上のための取り組みを図ってい
く必要がある。
重要
6 企業における人材育成
の方法
県内 IT 企業は、OSS を扱うことができる
技術者の増加を目指すのであれば、座学
ではなく、コミュニティへの参加などの
検討など、実践を取り入れる形で人材育
成の方法を見直す必要がある。
重要
7 受入企業紹介サービス
の整備
多くの学校で、インターンシップ受入企
業紹介サービスなどの整備を望む声が
あり、同様に企業側からも望む声が多
い。教育機関と受入企業の需要供給のマ
ッチングと双方の価値化を図るための
「受入企業紹介サービス」を整備する
と、学生視点においても、価値化につな
がる。
重要
8 県内 IT 企業の主な販路 OSS を活用している企業、OSS を活用し
ていない企業の間に特徴的な差がない
が、両者ともに、ユーザの割合が突出(特
に官公庁・外郭団体向けの比率が最も高
く、次にサービス業が続いている(県内
IT 企業のユーザが県内に多いことを表
しているものと考えられる)している。
参考
9 OSS 活用企業のスタンス OSS を活用している企業は、OSS を活用
していない企業よりも、グローバルに視
野を向けている傾向が高い。
参考
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
215
10 製品プロモーションの
手段
OSS を活用している企業は、ホームペー
ジでのプロモーションの割合が最も高
く、続いて営業アプローチとなっている
のに対し、OSS を活用していない企業は、
営業アプローチの割合が最も高く、続い
て特に実施していないという割合が高
くなっている。OSS を活用していない企
業の状況は、下請け業務の受託活動の典
型と想起させる内容となっており、OSS
を活用していない企業がビジネスの強
みは、約6割弱の企業が「受託開発(SI)」、
「技術者派遣」であるとしており、これ
を裏付けている。
参考
11 学生視点によるインタ
ーンシップ制度の充実
化
教育機関側の整備として、学生視点での
価値化を行い、学生のインターンシップ
に対するモチベーションを向上させる。
「インターンシップ制度の学生視点で
の価値化」として、単位制度の充実化を
各学校が改善していくことが求められ
る。
参考
12 インターンシップ制度
の実務面における課題
実務面においては、教育機関側としては学
生が実務に関わり体験させることを望んで
いるが、実務に関わらせることは、責任範
囲における瑕疵担保などの保障が難しい、
という問題をはらんでおり、現状制度上で
は、この問題が学生を実務に関わらせるこ
とに対する大きな障壁であると考えられるこ
とから、“学生を送り出す教育機関側が学
生の責任を担保することをより明確化す
る”、“企業側において、実務従事に対する
ボーダーを下げる工夫をする”、“教育機関
として、インターンシップ期間の延長を検討
する”などの対策を検討する必要がある。
参考
13 企業におけるインター
ンシップ経験者の採用
意向
新たなインターンシップ制度のスキームとし
て、企業の技術者とともに新規の共同作業
(例えば、開発)に学生を携わらせる場合は、既存のインターンシップの内容よりも若
干高い 7 割弱の企業が、優先的に交渉する意思を示している。
参考
14 共用センターが設立さ
れた場合の活用意向
共用センターが設立された場合の活用
意向としては、既に OSS を活用している
企業の約 8割が、「是非活用したい」、「活
用を検討する」と肯定的に回答してお
り、OSS を活用していない企業において
も、肯定的に回答した企業が 5割存在し
ている。
参考
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
216
(2)OSS 活用推進センターが保有する機能について
OSS 活用推進センターでの保有が検討されている機能に関し、本調査で新たに得た情
報、および知見を踏まえた事業構想への提言を以下に示す。
(A)全体
「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調査報告書」に記載されている OSS 活用推進セ
ンターの機能概要では、商材創出機能(マーケティング・スクリーニング、評価・検証、
ローカライゼーション)、人材育成機能(人材育成管理)、商流コーディネート機能(カ
タログ DB 管理、企業コラボレーション支援)という 3 つの機能要素を有する構想とな
っているが、表 8.2-1 に示した、本調査で新たに得た、事業構想に反映すべき情報、
および知見は、この 3 つの機能要素の範囲であり、包含されると考えられるため、機
能要素としては、必要十分であるといえる。
(B)機能詳細
本調査で新たに得た、事業構想に反映すべき情報、および知見を踏まえた、機能要
素の詳細を以下に示す。
(a)商材創出機能
表 8.2-1 にある「県内 IT企業が許容できる製品開発投資額の限界」(項番 1)、「県
内 IT企業が抱いている不安要素」(項番 3)を解消するための技術要素などの後ろ盾の
必要性、「OSS のライセンス、著作権に関する考慮の必要性」(項番 4)などについては、
この機能の範囲に含まれるものである。
この機能を実現するにあたり、下記に示す①から③の各作業を OSS ベース商材創出
の作業基準として整備する必要がある。
前述の項目を鑑みて改善した商材創出機能の各要素を以下に示す。
①マーケティング・スクリーニング
・市場調査、スクリーニングの実施
IDC などから毎年公開されるソフトウェア分類と各分類の市場予測を踏まえ、
CAGR(年平均成長率)の高いソフトウェア分類を抽出し、当該分野を商材開発のベ
ースとなりえるソフトウェアを探索する領域の中心とするのが妥当であると考え
る。
なお、商材開発のベースとなる OSS を探索する上で、有望な OSS 探索先もリスト
アップする必要がある。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
217
ただし、OSS 活用推進センターを活用する各企業が独自に取り扱いたい OSS がある
場合は、これを優先することが望ましい。
・OSS バージョンアップに対する定点観測の実施
抽出した OSS の情報源を一定期間で定点観測し、バージョンアップ、バグフィッ
クス、セキュリティパッチなどのリリースの有無を継続的に観測し、活用する企
業に対し、情報提供することが望ましいが、活用する企業が個別に実施可能な場
合は、企業が実施することが対象 OSS に対する技術力、知識向上の点でより望ま
しい。
・その他
これらの作業においては、このセンター要員の他、県内 IT企業の参画を前提とし、
共同で商材創出工程の各作業を遂行することにより、県内 IT 企業における実践的
な生産ノウハウ、技術スキルの醸成を目指す。
また、県内IT企業のOSS活用における技術的観点での後ろ盾が必要との視点から、
OSS ベースの商材を取り扱う上で、保守に関しては商用ソフトウェアを取り扱う際
と同等の条件を必要とすることから、県内 IT 企業向けに、創出した OSS ベース商
材の一元的な 2次的保守窓口の機能を提供することが望ましい。
②評価・検証
・対象 OSS の定性評価
対象 OSS の動作検証、品質評価、機能網羅性検証、およびライセンス、著作権違
反などのリスク評価を行う必要がある。これにより、対象 OSS を商材開発で活用
する上での課題を抽出する。
・スタッキング検証
抽出した対象 OSS 単体だけでなく、他の OSS と組み合わせることで、更なる製品
価値が生まれる可能性があるため、複数の OSS を組み合わせて、新たなスタック
を創出するための検証を必要に応じて行う。
・機能不足検出時の開発の実施
対象 OSS の定性評価で抽出した課題も含め、機能不足検出時に微少開発を実施す
るか否かという点については、対象 OSS を活用する企業の考えに大きく依存する
ものであり、商材開発に関わる企業がセンターにおいて開発を実施することが望
ましい。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
218
また、対象 OSS のライセンス形態にもよるが、開発したソースコードは、対象 OSS
の開発コミュニティに対して、商材開発に関わる企業が還元することを義務付け
ることが、開発企業の OSS に対するリスク軽減に寄与することから、望ましい。
③ローカライゼーション
・対象 OSS のローカライズ
「内閣府沖縄 IT津梁パーク構想事業調査報告書」では、対象 OSS のローカライズ
(現地語化)作業が記載されているが、対象 OSS がインターナショナライズ(国際化)
されていない場合は、インターナショナライズ作業を行う必要があり、さらに、
日本語化を行う必要がある。
また、他国に対して市場進出する際には、対象国の言語でのローカライズが必要
となる。本来、当該作業には、専門知識が必要であるが、OSS 活用推進センターで
は、各企業が対象 OSS のインターナショナライズおよびローカライズを容易に実
施できるよう、機能を実装することが望まれる。
④サポート Q&A
・カタログ DB登録済 OSS に対するサポートおよび Q&A整備
商流コーディネート機能の作業によって、カタログ DBに登録された OSS に対する
サポートと Q&A の整備を商材開発に参画した企業とともに、整備する必要がある。
なお、既に市場において普及し、システム構築などで活用されているメジャーな
OSS については、その限りではないが、OSS 活用ビジネスには必要不可欠な要素で
あることから、この対応策については、事業化の検討をする上での課題のひとつ
である。
(b)人材育成機能
表 8.2-1 にある、実践を取り入れる形での人材育成の方法見直し「企業の人材育成
の方法」(項番 6)、企業と教育機関のマッチングを図る受入企業紹介サービスの整備
「受入企業紹介サービスの整備」(項番 7)、「学生視点によるインターンシップ制度
の充実化」(項番 11)、「インターンシップ制度の実務面における課題」(項番 12)など
については、教育機関側での対応が必要な要素も含まれているものの、OSS 活用推進
センターで実施される OSS ベースの商材開発において、企業の技術者と学生が共同で
作業を実施すること、OSS 活用推進センターで行われるすべての開発プロジェクトに
関して教育機関にインターンシップの斡旋を行うことにより、各項目の課題を吸収す
ることができるものと考える。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
219
なお、「企業におけるインターンシップ経験者の採用意向」(項番 13)は、共同開発
に参画した学生に関しては、県内 IT 企業が非常に高い採用意向を示していることが、
本調査のアンケート結果からわかっており、教育機関側の意向と企業側の意向が合致
するものといえる。
前述の項目を鑑みて改善した人材育成機能の各要素を以下に示す。
①人材育成管理
・カタログ DBに登録された OSS に関する人材教育実施
カタログ DB に登録された OSS に関する県内 IT 企業の人材を対象とした人材教育を
実施していくことが望ましい。
・ローカライゼーション、スタッキング検証における実践教育のステータス管理
商材創出機能の OSS ベース商材創出の作業標準に基づき、県内 IT企業が組成するプ
ロジェクトを通じて企業技術者の実践訓練を実施し、OSS ベース商材を取り扱うこと
を可能とする商材スキル、技術スキルの醸成や OSS ベース商材の生産ノウハウを醸
成する。
なお、この時の個々人の教育状況を管理し、その状況に応じて随時レベルアップ対
策を実施することが望ましく、この相乗効果が、県内 IT 企業が OSS を活用する上で
抱いている不安要素を払拭する有効な効果を生むものと考える。
・県内 IT企業、ASEAN 諸国企業、県内学生を対象としたインターンシップ受け入れ
前述のとおり、OSS 活用推進センターで IT 企業により組成される各プロジェクトに
関して、教育機関にインターンシップの斡旋を行うことにより、県内学生に対する
実務参画への門戸を開くことが可能となり、また、企業としては、有望な人材を手
に入れる可能性を高める効果が生まれることになる。
なお、学生のみならず、他の県内 IT 企業や将来的には、県内 IT 企業が他国への市
場開拓を標榜する場合、随時、ASEAN などをはじめとしたアジア諸国の企業人材を参
画させることが、パートナー獲得の現実的な手段のひとつとして有効である可能性
があることから、この可能性について、今後検討する必要がある。
(c)商流コーディネート機能
表 8.2-1 にある「コーポレートプロモーションの手段」(項番 2)、「製品プロモー
ションの手段」(項番 10)については、商流コーディネート機能の中で、OSS 特有のイ
ベント、セミナーなどの対応でカバーする必要がある。
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
220
また、同様に、「OSS を活用していない企業の OSS 活用決断要素」(項番 5)として、
OSS を活用していない企業において、OSS を扱うことができる技術者の増加と企業幹部
に対する OSS の正しい認知の醸成を OSS 活用推進センターで推進していくことが、県
内 IT企業に対する幅広い効果を生み出すためには、必要不可欠である。本調査のアン
ケート結果にあるとおり、OSS 活用推進センターが発足した場合の県内 IT企業の活用
意向は非常に高いことから、企業幹部に対する OSS の正しい認知の醸成は OSS 活用推
進センターの活用定着化に欠かせない要素であるといえる。
なお、「OSS 活用企業のスタンス」(項番 9)として、海外販路開拓に前向きであるが、
OSS 活用推進センターがこれらの支援を行うことは今後の課題のひとつであるといえ
る。
①カタログ DB管理
・カタログ DBの運用管理(取り扱い企業情報の収集・管理を含む)
OSS 活用推進センターを活用して開発された商材を取り扱い企業情報、カタログな
どとともに、カタログ DB に格納し、Web で市場にアピールできる環境を整備、運
用することが望ましい。
・カタログ DBによる Web 代行販売
零細の IT企業などでは、仮に商材が開発できても、投資がままならず、販売施策
がなおざりになるケースが多いことから、カタログ DBに登録した商材を Web 経由
で販売できるよう、コマース機能を整備することが望ましい。
・カタログ DBに掲載する OSS の試用環境の提供
カタログ DB に登録した OSS を試用できるよう、試用環境を整備し、Web 経由で提
供することが望ましい。
②企業コラボレーション支援
・県内 IT企業への OSS ソリューションの技術移転
OSS 活用推進センターで商材開発されたソフトウェアは、ベースとなる OSS のライ
センス形態にもよるが、独自の版権が主張できる場合もあることが想定される。
これを踏まえて、当該状況が生じた場合、商材開発のプロジェクトを組成した県
内 IT企業に対し、商材の技術移転を行う必要がある。
・県外企業と県内 IT 企業とのマッチング
OSS 活用推進センターを活用して商材を保有した県内 IT 企業と県外企業のマッチ
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
221
ング支援を行うことが望ましい。この機会の創出は、OSS 特有のイベントやセミナ
ーなどもひとつの要素となるものと想定する。
・アジア諸国企業のコネクション管理
人材育成機能において、商材開発プロジェクトに ASEAN をはじめとしたアジア諸
国の企業人材を参画させる場合、当該企業とのコネクションを OSS 活用推進セン
ターとして管理し、将来他企業が他国への市場参画する際の足掛かり情報として
蓄積していくことが望ましい。この可能性については、今後検討する必要がある。
なお、特に中国に関しては、沖縄 IT 津梁パークと本調査で調査対象となった山東
斉魯ソフトウェアパークなどに代表される国営のソフトウェアパークとの連携な
どが、これをさらに強固な流れとしていくものと推察されることから、日本側、
中国側相互で具体的な検討が始まることが期待される。
・セミナー・イベントの開催
OSS を取り巻く活動では、セミナー、イベントが非常に多く、沖縄で OSS 系のイベ
ントを開催することにより、他地域から技術者が自らの意思で参画してくること
も珍しくない。この事実を踏まえ、OSS 活用推進センターは、沖縄発のセミナー企
画、イベント開催を推進し、県内 IT 企業と他地域技術者との交流をコーディネー
トしていくことが望ましい。
(3)OSS 活用推進センターの位置付けについて
OSS 活用推進センターは、「内閣府沖縄 IT 津梁パーク構想事業調査報告書」にある
とおり、県内の情報産業を内製・自主自立体質へと変革する機会を継続的に創出する
ため、変革の源泉となる、商材創出/獲得、技術スキル定着化、市場開拓力獲得とこれ
らの支援を行うためのセンター機構を整備し、県内の情報産業に属する IT 企業が OSS関連ビジネスを推進する上での支援の役割を担うことを基本コンセプトとするのが、
本調査の県内 IT 企業の調査結果を鑑みても、妥当である。各企業では、現状において
もそれぞれ独自にビジネスを推進しているが、その中には、各企業が競争する領域と
協調可能な領域が存在する。県内の情報産業の成長においての重要な要素であり、産
業を構成する各企業のビジネスを成長させる上で、各企業の協調可能な領域を中心に
県内情報産業の共用センターとしてビジネス活動の下支えを行うことこそが、OSS 活
用推進センターのミッションであるべきだと考える。
この共用センターとしての OSS 活用推進センターを活用し、商材開発を行った県内
IT 企業は、それぞれ独自に商材を軸としたビジネス戦略を策定することとなる。本調
査において挙げたとおり、OSS 活用ビジネスには、さまざまな形態のビジネスモデルが
あり、各社の戦略において、パッケージ販売、XaaS アプローチによる ITサービス提供、
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
222
システム構築、保守サービスなど、さまざまなビジネス形態へと波及していくことと
なる。
図 8.2-1 OSS 活用推進センターを基盤としたビジネス環境
この取り組みは、OSS を活用した地方において実現性の高い IT 産業振興の有効モデ
ルのひとつとして位置付けることができ、また、県内 IT 業界全体の浮揚に直結するこ
とから、この作業標準の整備とこれを支える環境の整備は、国・県などによる公的な
整備を行うことが肝要である。また、同時に、県内 IT企業が同センターを活用して高
い効果を生み出すために、県内 IT業界が必要としている人材育成面、技術サポート面
での不安要素解消に向けた支援、企業の生産物のプロモーション支援を実施すること
が望ましい。これらの要素については、各企業の事業活動の一環としての要素が強く、
同センターと併せて民間が独自に整備することが肝要である。
LLP(有限責任事業組合) or NPO(非営利活動法人)
インフラ(システム環境など)
OSS商材生成手法
企業連携・営業支援
商材生成プロジェクト
人材育成(実践教育)県内IT企業
教育機関
OSS活用推進センター
県内IT企業
県外支援企業
県内IT企業
・・・・・・
公的支援による整備が望まれる領域
・実践教育手法の検討・確立・商材生成手法の検討・確立・活動の前提となるシステム等設備
民間で整備すべき領域
ベンダ ユーザ企業 SI企業 海外IT企業
インターンシップ
商材生成
連携・提携
関連団体
OSS 商材活用ビジネスの創出に向けた事業環境の調査 報告書
223
引用文献一覧
・(独)情報処理推進機構 2007 年度オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業 OSS オフ
ィスアプリケーションのカタログ作成調査報告書
・(独)情報処理推進機構 2008 年度オープンソフトウェア利用促進事業 第2回オープンソ
ースソフトウェア活用ビジネス実態調査報告書
・IDC2008, 国内ソフトウェア市場 2007 年の実績と 2008~2012 年の予測アップデート
・IDC2008, ソフトウェア市場定義 2008 年版と国内ソフトウェア市場 2008 年~2012 年の予
測