メタ言語否定と尺度性 六甲英語学研究 第7号 pp 1-37 2004年
Transcript of メタ言語否定と尺度性 六甲英語学研究 第7号 pp 1-37 2004年
『六甲英語学研究』第 7 号 , pp. xx-xx, 2004 年
メタ言語否定と尺度性*
田中廣明
1. はじめに
本稿では、第 2 節で「メタ言語否定(metalinguisitic negation: 以下 MN)」、
第 3 節で「一般的会話の推意(generalized conversational implicature)」のうち
の特に数字表現の「尺度推意(scalar implicature)」と呼ばれる推意について
考察する。この 2 つについては近年、新 Grice 学派(Laurence Horn, Stephen
Levinson)と関連性理論(Robyn Carston, Deirdre Wilson)の間での論争が見ら
れる。Grice の what is said と what is implicated の区別以来、何が真理条件
に貢献するかという古く、また新しい問題である。
まず、第 2 節では MN について考察する。MN とは以下のような表現で
ある(Carston 1996)(Horn1985, 1989)。
(1) a. We don’t eat tom[a:touz] here, we eat tom[eiDouz]. (発音)
b. He isn’t neurotic OR paranoid; he’s both. (一般的会話の推意)
c. The king of France isn’t bald―there is no king of France. (前提)
d. I didn’t manage to trap two monGEESE―I managed to trap two
monGOOSES. (形態素)
e. Grandma isn’t feeling lousy, Johnny; she is indisposed. (スタイル/
使用域)
(1)は、通常の否定とは異なる。(1a)は、通常の否定ととると「トマトを
食べない」のであるが、その後の節(修正節という)でもう一度、「トマト
を食べる」と言っており、矛盾することになる。そこで、これは「トマト」
のもつ中心的な意味(命題)を否定しているのではなく、「発音」のみを否
定していると解釈するのである。これが MN の一般的解釈である。(1b)は
2 田中廣明
どちらか一方が真であれば良いという「一般的会話の推意 (generalized
conversational implicature)」、(1c)はフランスには王様がいるという「存在前
提(existential presupposition)」、(1d)は mongoose の複数形の「形態素」、(1e)
は気分が悪いという「informal なスタイル」のみを否定してる。
これに対し、通常の否定は、文の骨格をなす、真理条件を問える意味、
すなわち命題内容を否定していると考えられる。これを「記述的否定
(descriptive negation: 以下 DN)」という。(2)では、「カバを見たのではなく、
サイを見た」のであるから、(1)と同じように後ろに修正節があっても、矛
盾した言い方にはならない。
(2) We didn’t see the hippopotami―we saw the rhinoceroses.
(吉村 2000a)
では、この MN の特徴を明らかにするために、以下の点を議論の中心と
してたてておこう。以下、第 2 節では、この順序で考察を進める。
(3) a. MN は「量の推意(Quantity implicature)」を否定するとされるが、
果たしてそうなのか。
b.MN と後ろの修正節は矛盾関係(contradiction)にあるとされるが、
果たしてそうなのか。
c. 吉村(200a, b)の express/communicate について。
d. MN は「エコー否定」である。エコーのもとになっているのは
何であるのか。
次に第 3 節では、数字表現についてその尺度性を取り上げる。第 2 節で
述べる量の推意は、some からの推論過程を経て not all を推意する中で生じ
る推意とされているが、Grice あるいは Horn に対して、数字表現だけは例
外的に扱わなければならないと批判が生じている。数字の意味は推意なの
であろうか表意なのであろうかという問題である。本稿では、推意という
Girce 流の立場を堅持し、数字から生じる意味を考察する。
メタ言語否定と尺度性 3
2. メタ言語否定
2.1.「量の推意」の否定
Levinson(2000)は、Horn (1989)と同様に、「量の推意(Quantity implicature)
(尺度推意(scalar implicature)あるいは Q 推意(Q-based implicature)とも言わ
れる)」から、MN を説明している。量の推意とは、Grice (1975)の「量の
公理(Maxim of Quantity)」の前半部「必要とされている情報をすべて与えよ」
から、「それ以上ではない」という推意が生じることをいう。MN はその推
意を否定しているとされる。次例で考えてみよう。
(4) A:Is he happy?
B: He is not happy; he is ecstatic.
(4)の He is happy.は「ちょうど happy であり、それ以上ではない」という(量
の公理の前半部から生じる)量の推意が生じている。(4B)の MN は、その
推意のほうを否定し「それ以上でないことはない」すなわち「有頂天
(ecstatic)である」ことを述べている。Levinson と Horn の説明では、話し手
B は happy の上限を破る否定を行っていることになる。
はたしてそうであろうか。happy と ecstatic を比べると ecstatic のほうが
「幸福さ」という尺度上で強いところにある。(4)は尺度上で強い表現を修
正表現に持ってくる MN の典型例である。それだからこそ、推意否定で説
明しやすくなっている。
しかし、実際には MN の話し手 B は、彼(He)については最初から ecstatic
という強い表現のほうを信じていると考えられる。A が、B の信念(予想)
に反して、自分が信じている情報より少ない量の情報を述べたのである。
B はそれ以下ではないと思っていたのに、A からそれ以下だとされたので
反論しているのである。つまり、B は「より少ないことはない(happy では
ない)」ことを主張していることになる。
これは、Grice の「量の公理」の後半部に関係する。B は「必要以上の情
報は与えるな(必要とされる最小限の情報を与えよ)」が成立すると信じて
いることになる。すなわち、それ以下ではないと思っているからこそ、そ
4 田中廣明
れ以下の情報を与えられるとそうではないと反論しているのである。
次の例で考えてみよう。
(5) カリエスを心配して病院に行った友人がいる。当人はカリエス
だと信じ込んでいたようで、医者にもそう伝えた。医者は検査
をして、こう言った。
「大丈夫。カリエスではありませんでした。あなたはガンです。」
(永六輔『大往生』)1)
Levinson, Horn 流の説明では、「カリエスである」という友人の言葉から
「カリエス以上ではない」という推意が生じ、それを否定して「ガンです」
とするのがこの医者の MN であるとなる。しかし、この医者は「この人は
ガンである」という自分の信念が否定されるものではないことを述べてい
るのである。なぜなら、この医者は自分の尺度で述べ、友人の尺度とは違
うことを主張しているからである。この医者の尺度、すなわち「死病」と
いう尺度上では、<ガン, カリエス>という強弱の順序になる(< p, q >とい
う尺度では p が q より強いとする)。ところが、この友人の尺度には「死病」
という基準は存在しない。<ガン, カリエス>という尺度の強弱は存在せず、
自分が死ぬなどとは思ってもみないことなのである。
以下の図示を参考にされたい。
(6) 話し手の尺度:○○○○○○○○○○|×××××××××××××××
MNの話し手(医者)の下限
<〔 ガン 〕, [ カリエス ] >
MN を聞いた聞き手(患者)の上限
聞き手の尺度:××××××××××|○○○○○○○○○○○○○○○
このように、MN の話し手とそれを聞いた聞き手(=先行発話の話し手)
の尺度は異なると考えるのが妥当であろう。MN を聞いてはじめて、聞き
手は自分が思っていた「それ以上ではない」という推意が成り立たないと
メタ言語否定と尺度性 5
気付くのである。(5)では、医者の言葉を聞いた友人(患者)は、「カリエ
スでない」ことはないと解釈が可能となる。Levinson, Horn 流の説明が必
要となるのは MN の話し手ではなくそれを聞いた聞き手である。逆に、MN
の話し手は自分自身が信じる尺度の下限〔ガン〕を持っていることになる。
MN は、その下限より下ではないという否定である。聞き手の尺度の上限
[カリエス]は尺度上で弱い方の項目で、聞き手は、その上限より上でない
ことはないと解釈するのである。
MN の話し手(医者)は下限〔ガン〕をもともと認識しており、それ以
下[カリエス]ではないと MN を用いる。その際、[カリエス]は先行発話の話
し手(=聞き手、患者)から与えられた弱い方の項目である。一方聞き手
(患者)は、上限[カリエス]を持っており、それ以上〔ガン〕ではないと
MN を解釈する。〔ガン〕は MN の話し手(医者)が設定した強い方の項目
である。当然、聞き手は MN を聞く前(先行発話での段階)では、このよ
うな尺度は持っておらず、MN を聞いてはじめて自分の尺度を話し手の尺
度に合わせている。
2.2. 矛盾
Burton-Roberts(1989)は、MN はすべて「意味論的(真理条件的)な矛盾
(semantic(truth-functional) contradiction)」を表すとする。すなわち、最初の
節(前半部)を聞いた聞き手は、通常の記述的否定(DN)と解釈するが、後
の修正節(後半部)を聞いて、前半部と矛盾する解釈に陥ってしまい、前
半部の否定を語用論的、メタ言語的に再解釈するとしている。3)
では、上述した話し手の発話意図(MN の話し手の下限)と聞き手の解
釈(聞き手の下限)の違いからどのようなことが説明できるであろうか。
(7) A: Is that haggis good?
B: That haggis is not good; it’s excellent. (van der Sandt 1991 一部改)
(7)の場合、MN の話し手 B が否定しているものは「excellent ではない」と
いう A の言葉から生じた推意である。すなわち B にとってはこの否定は矛
6 田中廣明
盾ではないことになる。B は「ハギスがおいしくない(=まずい)」とは思
っていない。B はあくまでも、ハギスのおいしさという同じ尺度上で並ん
だ<excellent, good>の good を否定しているのであるから、「good ではなく
excellent である」と言っても、何ら矛盾しない。ところが、B の発話を聞
いた聞き手 A は、「good ではない」と言われると「まずい」のではないか
と解釈してしまう。そのため、excellent という言葉を聞いて矛盾を感じて
しまうのである。
このような、MN の話し手の発話とその聞き手の解釈の不一致は、MN
のすべての例についてみられる特徴である。
(8) 「古田は言っています。『私は4番バッターじゃなくて、4番目
です』と。」(1997 年 10 月 19 日、朝日放送アナウンサーがプロ
野球中継(ヤクルト・巨人戦)で述べたコメント)
(8)では、古田は「あなた方が思うような 4 番ではない」と言っており、否
定しているのは「4 番バッターが持つ打線の中心のスラッガーとしての役
割」のみである。古田の中では、「4 番バッターでない」ことと「4 番目」
であることは矛盾していない。(5)も同様で、医者が否定しているのはあく
まで、「カリエス」に付随する「死病ではない(治る)」というこの友人が
疑いもしない推意の方である。それゆえ、この医者にとっては、「カリエス
でない」ことと「ガンである」ことは矛盾しない。ところが、(8)(5)を聞い
た聞き手は、「4 番バッターではない」=「4 番以外である」、「カリエスで
はない」=「ガン(というような死病)ではない」ととるのが通常の解釈
であるため、矛盾を感じてしまう。
Carston (1996)は、矛盾が MN の唯一、決定的な特徴ではないことを以下
の点から例証している。次の(9)は、Burton-Roberts (1989)は矛盾が感じられ
ないとして MN に入れないが、Carston (1996)は、彼女の基準(エコー否定
であること。後述を参照)からすると、MN の例になるという。すなわち、
(9)は矛盾ではない MN であるため、矛盾は MN の唯一、決定的な特徴では
ないことになる。
メタ言語否定と尺度性 7
(9) X: You seem amused by my problem.
Y: I’m not Amused by it; I’m Bemused by it.
この例では、矛盾が感じられていないのであろうか。(9)の話し手 Y は何
を否定しているのであろうか。もし Y が X の言葉を引き取って命題内容の
みを否定しているとするならば、すなわち「amused ではない(面白がって
いるのではない)」とのみ言っているならば、そのあとで「bemused である
(当惑しているのだ)」と修正しているのであるから、命題内容として違う
種類の命題なので、Y にとっても聞き手 X にとっても矛盾は感じられない。
つまり、Burton-Roberts(1989)の言うようにこれは MN ではなく、(2)と同じ
ように DN ということになる。ところが、(9)には、MN 的なおかしさが存
在する。それは、amusedと bemusedが音声的に韻を踏んでいるからである。
もし、bemused が puzzled とか confused ならその種のおかしさは生じるこ
とはなく、単なる DN になる。
この例は、話し手にとっても、聞き手にとっても命題内容に矛盾は感じ
られないので、Carston の言うような MN ではない。ところが、Y が韻を踏
んだ表現で修正しているため、聞き手 X にとっては、まさか似た音がこな
いだろうという前提が破られ、ギャップを感じてしまう。この点でこの例
は MN 的と言うことができるが、話し手 Y が命題内容プラス音声まで含ん
で否定しているため、上述のような純粋なMN ではない。また、純粋な DN
でもない。
2.3. express / communicate
吉村(2000a, b: 22-23)は、「メタ言語否定によって否定されるものは、ま
さに、このエコーの元になるものによって、 express されているが、
communicate されていないものである」とする。express されているものと
は、「ある言語形式を用いることによって、必然的に伴われるもの」であり、
communicate されているものとは、「(まわりにある様々な情報から)聴者
が取り上げてくれるように話者が意図していることを話者が明らかにした
8 田中廣明
想定」(Sperber and Wilson 1986/1995)であるとする。
次の吉村(2000b)の例で考えてみよう。
(10) A: You resemble Mr. Yoshioka very much, who taught me English in
my high school days. You must be his daughter.
B:I’m not his daughter―he’s my father.
A は大学の若手教官、B は新入生とすると、「…A は、自分が明示的に伝達
しようとした『恩師と B が親子である』というポイントと異なる部分に異
議を唱えた B に少し面くらい、B の自立心のようなものを感じる。…(中
略)…(この参照点構造による概念化は)express されていると考えなけれ
ばならないが、それは A が意図的に communicate しようとした内容ではな
い」と吉村(2000b: 23)は考えている。すなわち、A が言おうとした内容(A
の発話意図)と、B がそれから否定しようとした内容(B の発話意図)は
異なることになる。A は自分が述べよう(express)とする内容の中に、B が
取り込もう(communicate)とする内容があると気付いていない、あるいは意
図していない。A は「恩師と B が親子である」と言っているのであるが、
その中に付随する意味(推意)として「(B から見れば)恩師は B の父親
であるにすぎない」とまでは言っていないことになる。そうすると、express
されるものは communicate されるものを包含し、 express されるが、
communicate されるものが活性化(activate)されていないことなる。つまり、
A は推意として発していないのであるが、B が勝手にその推意の部分を否
定しているのである。
(11)
メタ言語否定と尺度性 9
この吉村(2000a, b)の見方は、かなりの部分で的を射ていると思われる。確
かに、(1a-d)や(4)(7)のような「量の推意」の否定とされているものはこれ
で説明が可能である。(7)の good には、A は communicate すなわち意図し
ていないのであるが、言語形式上、それ以上ではないという量の推意を
express していることになる。(1a)の発音の問題でも、先行発話で発音して
いるからには、その発音を communicate(意図)せずに express している。
ところが、いくつかの例で、この区別は微妙な問題を提起する。
(12) [妹の Jill が元夫 (Ross)とつき合っているのを不愉快に思い、
「Ross とデートできなくても男なんて五万といるじゃない」と
Rachel が言っている場面]
Jill: Hey, you have no right to tell me what to do.
Rachel: I’m not telling you what to do, I’m telling you what not to do.
(Friends 米 TV)
(12)では、Jill は You’re telling me what to do.(お姉さんはああしろ(こう
しろ)と言っているじゃないの)を意図しているのに対して、Rachel は「あ
あしろなんて言ってないわ、するなって言ってるのよ」と切り返している。
express されるもの
communicate され
るもの
10 田中廣明
通常は、<tell … what to do>と<tell … what not to do>には強弱の関係はな
く、Jill の言葉からは、<tell … what not to do>まで express していると見る
ことはできない。ところが、この例が MN と感じられるのは、Rachel の本
音を言うと、Jill に Ross とつき合うなと「命令」したいためである。Rachel
にとって、「命令」という尺度では、「肯定命令(tell … what to do)」より、
「禁止(tell … what not to do)」のほうが強い。この「禁止」は Rachel がも
ともと持っていたために、communicate している意図であり、Jill の言葉に
は express されていないと考えるべきである。
では、次例を考えてみよう。
(13) [海岸で拾ったボトルに入ったメッセージを、新聞に無断で載せ
られて怒っている場面]
Editor in Chief: Theresa, it’s not your letter.
Theresa: Yeah, I know. It’s not my letter. I found it.
E: Is this any personal? Is that why you’re pissed off?
T: I’m not pissed off. I’m just … a little pissed off.
(Message in a Bottle. 1999 年米映画)
pissed off と a little pissed off は強弱が逆になり、弱い表現を修正表現に持
ってきている。編集長の you’re pissed off という言葉に、a little pissed off
が推意されており、express されていると考えられるかもしれない。また、
弱い修正表現であるため、純粋なMN であるかどうかも疑わしいと考えら
れるかもしれない。しかし、Theresa の発話意図を考えてみると、なるべく
冷静になろうという意図が感じられる。日本語でも「怒ってなんかいない」
という言い方はよく聞かれるが、この場合も(かっとなっていると損なの
で)冷静にしておこうという意図が働いている。この「冷静さ」という尺
度では、pissed off より a little pissed off のほうが強い表現となっている。
もちろん、この冷静さの尺度は Theresa の意図にあることで、編集長の
pissed off という言葉にはない(express されていない)と考えるべきである。
このように、MN の話し手の発話意図と先行発話の話し手(聞き手)の
メタ言語否定と尺度性 11
意図を分けて考えると、express/communicate は MN の唯一、決定的(crucial)
な特徴ではないと思われる。しかし、(1a-e)、(4)(7)(10)のように、言語形式
上、潜在的に、communicate していないがどうしても express してしまう表
現形式も存在する。これはおそらくは、express/communicate という概念が
人間の communication に必要なかなり上位の概念であり、その中に MN の
一部も含まれていると考えるべきであろう。例えば、自分では知らず知ら
ずのうちに express してしまって、相手に communicate されてしまうような
誤解(misunderstanding)や曲解(distortion)なども express/communicate で説明
が可能である。4)
2.4. エコー否定
Carston (1996, 1998a, b)は、MN の唯一、決定的な特徴はエコー否定であ
ると主張している。ここでは、(1)以外の用例にすべて先行発話をつけてき
た。そこから分かるとおり、Carston の言うように、MN はエコー否定であ
ることは間違いない。問題は、何をエコーしているのかである。エコーし
た内容が先行発話の命題を含むかどうか、すなわち自分の信念として否定
できる内容であるかどうかである。
エコーするものは次の 3 つが候補となる。それは、①「命題」のみ、②
「命題」以外の「推意、音声など」、③「命題」プラス「推意、音声など」
(van der Sandt 1991)である。①はほぼ Burton-Roberts(1989)の言うことに等
しい。すなわち、命題部分をエコーし、修正節を聞いて矛盾であると感じ、
メタ言語的な解釈へ向かう方策である。②は、ここで述べている立場であ
る。MN の話し手が自分の尺度で、相手の言葉のうちの「命題」以外の部
分を引き取ってメタ言語否定している。③とすると、否定演算子が 2 種類
あることになる。「命題」と「使用条件」の両方を引き取っておいて、「命
題」のみを否定するエコー否定(DN)と「使用条件」のみを否定するエコ
ー否定(MN)に分けなければならない。これも否定するものと否定されるも
のを考えた場合、複雑すぎて受け入れられないとする立場が大勢を占めて
いる(Carston 1998a, Burton-Roberts 1989)。結論として、MN のエコー否定
では、エコーするものは「命題」以外の部分であり、それを話し手の信念
12 田中廣明
として、すなわち真偽値の問える命題としてではなく、否定していること
になる。
Carston(1996: 320-321)のいうエコーとは、相手の言ったこと 5)を(エコ
ーすることによって)解釈することである。解釈する際には、相手の言葉
に対して話し手は袂を分かち、自分はそう思っていないということを示し
ている(「分離的態度(dissociative attitude)」という)。
次例を考えてみよう。
(14) A: Mary seems happy these days.
B: She isn’t HAPPY; she just put on a brave face. (Carston 1996: 324)
(14B)は先行発話をエコーしている。その先行発話に対して、相手とは違っ
た態度を表明している。ここでは、先行発話に対する不快感とか、拒絶で
あろう。つまり、「分離的」である。(4)や(7)のような典型的な MN でも同
じことになる。では、(14)は MN であろうか。それとも DN であろうか。
それを解く鍵は、何をエコーしているのかにある。Carston (1996)は、真偽
値を問える命題内容をエコーしているとする。(14)は、相手(A)の言葉を受
けて「幸せではない」といっているのであるが、「幸せである」というエコ
ーした命題内容に自分の信念として否定を述べている。すなわち、「幸せで
ある」という命題は「偽」であると判断を加えていることになる。なぜな
ら、後ろで、「彼女は精一杯そう取り繕っている(平気な顔をしている)だ
けだ」と、「幸せではない」ことの理由を述べているからである。 (1a-e)
の MN のように、後ろに矛盾する修正表現を持ってきているのではない。
つまり、(14)は DN になる。
先行発話とは違う(分離的)態度を表明しても、エコーの元になるもの
は「命題」ということがある。ところが、これでは MN との区別がつかな
い。
(15) A: Don’t deprive us of your lecture on negation.
B: I won’t deprive you of my lecture on negation; I’ll spare you it.
メタ言語否定と尺度性 13
(Carston 1998a)
(15)も(14)と同様、「分離的態度」の表明である。B は A に反論し、不快感
を表している。ところが、これは典型的な MN である。エコーの元になる
ものが違うのである。この場合は、deprive の持つ「・・・を奪う」というマ
イナスの推意をエコーしていると考えられる。
このように、MN のエコーの元になるものを「命題」以外の推意など言
外の意味とするのは、第 2 節で述べたように、MN の話し手と聞き手(=
先行発話の話し手)の尺度(信念)が違うからである。MN の話し手は相
手とは違うように思っているからこそ、相手の命題内容に直接関与
(commit)できないということができる。
3. 尺度性
3.1. 尺度推意は推意か表意か:数字表現
吉村(2004), Carston (1998a)によれば、and then 読みの and や some and not
all 読みの some は、論理演算子の作用域に入るため Grice や Horn(新 Grice
学派)の言う「一般的会話の推意(generalized conversational implicature)」で
はなく、発話の命題内容に貢献する真理条件的意味(表出命題、明示的意
味)であるとする。
(16) It’s better to do your PhD and get a job than to get a job and do your
PhD.
(17) If each side in the soccer game got three goals, then the game was a
draw.
(18) If some of the children have already arrived the others will be here
shortly. (Carston 1996, 1998a)
(16) は better than 構文と言われ、and は and then と解釈しなければ It’s better
to p than to p.となり矛盾した表現となる。同様に、(17)も three を exactly three
と解釈して初めて同点になる。(18)も some and not all の意味でなければ他
14 田中廣明
の人たち(the others)がここへすぐ到着することにはならない。and の then、
three の exactly、some の and not all の意味は、推意であると真理条件を問
えない意味になってしまい、文全体の真理条件に貢献しない。したがって、
真理条件に貢献する意味、すなわち表意とするほかはないことになる。
以下では、一般的会話の推意とされているもののうち、(17)の数字表現
(基数(cardinal numbers))をとりあげ、Carston、吉村があげている問題は、
再考の余地があることを述べる。まず、次例を考えてみよう。
(19) a. Three boys carried a sofa up the stairs. (exactly three の意味)
b. She can have 2,000 calories without putting on weight.(at most 2,000
の意味)
c. If you fail three times, you are excluded. (at least three の意味)
田中(2003)でもふれたが、数字表現は some などの量化詞とは異なり、常
に一般的会話の推意をプラスした exactly 読みでなければならないように
見える。(19a)の Three boys carried a sofa up the stairs.は「3 人が一緒になっ
てソファを運んだ」というグループ読みが普通であり、three は 3 人以上で
も 3 人以下でもない exactly three の意味になる。3 人で運んだからと言って
2 人で運んだ、1 人で運んだことにならないからである。この場合、3 と言
っても 2 や 1 を含意(entail)しない。すなわち<3, 2, 1>という尺度は存在し
ない。これが exactly 読みである。
次に、(19b)の She can have 2,000 calories without putting on weight は 2,000
カロリーまでなら摂っても良いと言っており at most 2000 の読みである(以
下 at most 読みと言う)。さらに、(19c)の If you fail three times, you are
excluded は、3 回失敗すれば閉め出されるのであり、当然 3 回以上失敗し
ても閉め出されることになり at least three の意味である(以下、at least 読
み)。
3.2. at least 読みと exactly 読み
このように、数字表現には、概略、3 つの読み(at least, at most, exactly
メタ言語否定と尺度性 15
読み)があり、その理論的な派生方法が議論されている。以下は、
Capone(ms.)がまとめた研究者間での取り扱いの差異である。現在の理論間
の大きな対立は、新 Grice 学派(20a)と関連性理論(20c)の間に見られ、(20c)
の Carston(1998a)(関連性理論)から、(20a)の新 Grice 学派への批判が顕著
である。
(20) a. 尺度の下限を設定する at least 読みを意味論(字義的意味(literal
meaning))に置く。上限を設定する一般的会話の推意(generalized
conversational implicature)が生まれ、exactly 読みとなる(Levinson
2000, Horn 1989 などの新グライス学派)。
b. at least 読みと exactly 読みで、意味論的に多義(ambiguous)とす
る(Higginbotham 1983)。
c. 数字表現は「意味の不確定性(underspecified semantics)」に関わ
り、次に at least, at most, exactly へ意味が拡充(enrichment)される
(Carston 1998a, 2002)。
d. exactly 読みをデフォルトとする(Jaszczolt 1999, 2002)。
3.2.1. at least three は冗漫か
Copone(ms.)は Carston(1998a)の書評をしている。そのうちの、第一の問
題を考えてみよう。Carston(1998a)は(20a)の at least 意味論を否定する。な
ぜなら、もし at least 読みを数字の字義通りの意味に認めると、more than
あるいは at least が明示的に述べられた文は「冗漫(redundant)」か「不自然
(odd)」になるはずであるからであるとする。
(21) More than three people came.
ところが(21)は何の冗漫さ、不自然さもない。そこで at least を根本に据え
るのはおかしいと言うことになる。そのほか、at least, exactly をつけても
同じ冗漫性が生じてしまい、((20a)のように at least 読みを字義的意味とす
ると)at least n(n は数字表現)が、また((20d)のように exactly 読みを
16 田中廣明
字義的意味とすると)exactly n の意味が指定できなくなる。
以上が Carston からの新 Grice 学派批判の一つである。しかしながら、こ
の Carston の反論には無理がある。説明言語(メタ言語)としての非明示
的な AT LEAST と、コミュニケーション上の伝達される意味としての明示
的な at least は意味が違って当然だからである 6)。Sadock(1978)で述べられ
ているように、会話の推意とは本来的に推意を明示的に言葉にしても「冗
漫性」は感じられない。some but not all や almost but not quite が典型例であ
る。補強性(reinforcibility)と言われ、取り消し可能性(cancellability)と並んで
会話の推意のテストに用いられる。
明示的に表現される at least は尺度の下限に言及し、それ以下は当ては
まらないところから、それ以上が当てはまると述べている 7)。Kay (1997:
102-103)は、数字 n で示される量の上限(upper bound)を押さえる(阻止する)
働きであるとする。次例を考えてみよう。
(21) World -- Reuters: Violence in Baghdad Kills at Least 25 Iraqis
(Yahoo! News, Mon, Dec 06, 2004)
(20)はニュースの速報である。バグダッドで少なくとも 25 人のイラク人が
テロの犠牲になったことを伝えている。ニュースの場合、テレビ・新聞は
速報では正確な数を把握できずに伝えることが多い。25 人は確認できたが、
それ以上であるかもしれないとするのが at least の用法である。20 人では
ないのである。また、25 人以上であるかもしれないことを、積極的に述べ
ている。
では、推意として非明示的な AT LEAST を考えてみよう。(19c)の If you
fail three times, you are excluded のような文である。ここでは、3 回失敗する
ことは閉め出されることの十分条件である。一般に、十分条件とは、相手
に課する責任の下限である。閉め出されるためにはそれ以上の、あるいは
またそれ以外の条件があっても良い。条件の十分性である。You must not fail
three times と言っているのである。3 回以下では閉め出されることはないと
言っているだけで、3 回以上のことは積極的には述べていない。
メタ言語否定と尺度性 17
同じことが(22)にも当てはまる。吉村(2004: 66-67)が Carston から指摘し
ているように、電話をかけるためには 10 ペンスあればよいのである。
(22) A: Can you help me out?
B: I have 10p.
Aの「お助けしましょうか」に対して B は「電話をかけるには 10 ペンス
あるから大丈夫」であると述べている。つまり、なるほど 10 ペンス以下で
はだめだが、10 ペンス以上は云々とは明示的には述べていない。推意とし
て暗にほのめかしているだけである。
推意としての AT LEAST と明示的な at least をまとめると次のようになる。
ここでは、Grice 流にしたがって、字義通りの意味としての AT LEAST を付け
加えておく(ただし、数字表現でこのレベルの意味が存在するかどうかは
置いておく。n は数字)。
(23) a. 字義通りの意味としての AT LEAST n:n 以下は成り立たない下限
設定の意味
b. 推意としての AT LEAST n:n 以下は成り立たない下限設定の
み + それ以上の数量の暗示的な許容
c. 明示的な at least n:n 以下は成り立たない下限設定 + それ以上
の数量の明示的な許容
言葉として表現される at least はそれ以上の数量が当てはまることを明示
的に述べている。推意として暗に述べていた部分を顕在化したに過ぎない。
したがって、at least がもともと存在するからと言って、明示的に at least
を付け加えることが冗漫になるとは言えないことになる。
本来(23a)の字義通りの意味としての AT LEAST は、Grice では、それ以上
が成り立つとわざわざ言っているのではなく、数字の n は n 以下の数を意
味論的に含意する(entail)ことを述べているにすぎない。n は n 以下のゼロ
から累積的に増えていって n になれば当該の述語が成り立つと言っている
18 田中廣明
のである。Grice が意図したのはこの関係である。そうだからこそ、田中
(2003)で述べたように、「He is happy という文は、意味論的に下限を設定し
「幸福以下でない(=at least happy)」という解釈が成立するから、He is not
happy は「幸福以下(=不幸)である」という意味となる。」この否定は通
常の DN である。AT LEAST の意味指定は、DN のために必要なのである。そ
うでないと、数字表現も含めて、なぜ MN でない DN が一般的な否定にな
るのかが説明できない。ただし、数字表現の場合、一般の量化表現とは異
なり、字義通りの意味の段階で、at least 読みが成立しているかどうかは問
題があり、(19c)(22)の at least 読みが推意なのか、Carston の言う表意なの
かは議論が分かれる。
Grice, Horn の図式によれば、字義通りの at least 読みから尺度推意の at
most へ、さらに伝達される意味としての exactly 読みは次のようになる。
(24) A: How many children do you have?
B: I have three.
① 字義通りの意味:I have at least three children.
② 尺度推意:I have at most three children.
③ 伝達される意味:I have exactly three children.
(① + ② = ③) (吉村 2004: 65)
確かに、「子供の数は?」と聞かれて、「3 人である」と答える場合、3
以上も許容される意味ではない。そうすると、字義通りの意味で at least
読みを認めるわけにはいかない。このことは、B を否定文にした I don’t have
three children.が(He is not happy とは異なり)4 人以上も 2 人以下も表すこ
とからも分かる。肯定文の I have three children.が字義的には exactly three
children であるからである。ところが、(19c)(22)のように、数字表現でも推
意としての AT LEAST 読みが生じている。では、AT LEAST 読みはどう扱
えばよいか、exactly 読みと併せて後述する。
3.2.2. exactly 読みは冗漫か
メタ言語否定と尺度性 19
Carston の新 Grice 学派への at least 意味論批判と同じことが、今度は、
exactly 読みにも当てはまることになる。exactly three が「冗漫」になるは
ずだからである。明示的な exactlyと非明示的な EXACTLY を比べてみよう。
(25) "I drew blood, I looked at the syringe, and it was 8 cc’s.”
“Was it exactly 8 cc’s?”
“No. It could have been as little as 7.9 or as much as 8.1.”
(Official O.J. Simpson Trial Transcripts (LOS ANGELES,
CALIFORNIA; MONDAY, JULY 31, 1995))
「注射器に血液を吸い取ったのは 8cc きっかりだったか」という質問に「最
低でも 7.9cc で最大でも 8.1cc だった」という否定の返事である。ここでは、
注射器の目盛りでの 8 という整数の範囲内には 7.9 から 8.1 まで入るわけ
であり、「8cc 吸い取った」のは間違いではない。その厳密さを尋ねられる
と No となる。質問者の厳密さは「近似値(approximation)、おおざっぱな数」
との対比が含意される。尺度で書くなら、<approximately 8cc, exactly 8cc.>
となり、「厳密に 8cc でおよそ 8cc ではないのですね」と尋ねている。
ところが、非明示的な EXACTLY はどうであろうか。数字が exactly 読み
ということは、(i)「それ以上でもそれ以下でもない」という exactly から生
じる推意があるのか、(ii)exactly という意味(すなわち表意)として用いら
れているのかのいずれかである。Carston の exactly 読みはあくまでも(ii)の
意味でしかなく、(i)ではない。それが数字の通常の使い方であるからであ
る。すなわち、明示的に exactly のつかない数字は、exactly の持つ「およ
そ・・・ではない」という推意が生じていない。このことは、(24)の exactly
を削除すると、 “Was it 8cc’s?”が「本当に 8cc だったのか(7, 6, あるいは
9, 10…ではなかったのか)」を尋ねる言い方になることからも分かる。「厳
密に 8cc であったか」の意味と取り、No…のように続けるのが不自然なの
である。
しかし、次例は、一見したところ、「厳密に 8 個」ととれそうである。
20 田中廣明
(26) THE COURT: I have eight bags in my chambers that are the same
general color, general size.
MR. COCHRAN: Eight?
THE COURT: Eight, do you want to count them?
MR. COCHRAN: No, no.
(Official O.J. Simpson Trial Transcripts, March 29, 1995. Morning
session.)
(26)の判事の 8 個のバッグがあるという言葉に、Cochran 氏は 8 個ですかと
疑問を呈し、判事が 8 個だと念を押している。ここでの 8 という数字につ
いてのやりとりは、数字の「厳密さ」を述べているのではなく、「正しさ」
を述べている。このように、数字だけでは exactly の持つ「厳密に n で、お
よそ n なのではない」という推意は生じていない。数字の正しさしか述べ
ていないのである。
では、exactly 読みとされる(19a)はどうであろうか。
(19) a. Three boys carried a sofa up the stairs.
(19a)は at most 読みでも、at least 読みでもないという意味では、exactly 読
みなのであるが、これも「およそ 3 人ではない」という読みではなく、3
人がひとまとまりで、つまりバラバラでなくというグループ読みを述べて
いる。田中(2003)で述べたが、3 という数字は尺度上の点を指す働きしかな
く、どういう尺度上にあるかによって at most, at least なのかが決まってく
るのである。
3.3. 尺度
次に、Capone(ms.)があげている Carston 批判を見てみよう。Carston(1998a,
2002)の語用論的な自由拡充(free enrichment)7)は、拡充される前の意味論
(基礎表意)に次のような変数(variable)を仮定している。当該の文は、Three
students arrived.とする。
メタ言語否定と尺度性 21
(27) [X [three]]
X は文脈ごとにその値が指定される変数である。「この考え方は、(例えば
基数詞 n が)あるときには at least n を伝達すると解釈され、あるときには
at most n、exactly n と解釈されることをうまく説明する」(吉村 2004: 66)。
X についてはそれでよい。しかし、three の意味は何であろうか、というの
が Capone(ms)の指摘である。at least three、at most three、exactly three に共
通する three の意味は何であろうか。
Horn(1996, ms)は、数字を意味拡充がなされた真理条件的な表現として扱
うと述べている。これは、数字は、some などの数量詞とは異なり、尺度推
意を持たないという分析である。
(28) A: Do you have two children?
B1: No, three.
B2: ?Yes, (in fact) three.
(29) A: Did many of the guests leave?
B1: #No, all of them.
B2: Yes, (in fact) all of them.
(28)は、(29)のように many から not all への推論が可能な尺度表現とすると、
two から not three へ推論し、その尺度推意である not three を打ち消す B1
が容認可能なはずである。しかし、(29)とは正反対の振る舞いをする。こ
れは、(28)の two が EXACTLY 読みで数字の正確さを述べているからであ
る 9)。「2 人子どもがいるかどうか」を尋ねることは、数字の正確さを尋ね
ており、子どもの数の多寡を尋ねているのではない。したがって、B2 でい
ったん肯定して(つまり、2 という数字は正確であると述べて)おいて、3
人と修正するのは矛盾していることになる。これに対し、(29)の B2 は many
から not all への尺度推意を in fact で取り消しており、数量的な尺度から推
22 田中廣明
論できる推意である。
(28)は「子どもは 2 人ですか」という子どもの数の正確さを尋ねており
尺度推意は生じていないが、次の(30)のように単に数(の多さ)を問題と
する文脈では、尺度推意が生じる。
(30) Moulton: Oh, wait. Sear doesn't have E-Mail.
Sear: yes I do. two, in fact. three, really
Discussion on MicroMuse Public Channel on Christmas Night
http://underground.musenet.org:8080/WCE/Bullies.html
(30)では、Sear はメールドレスをもっているかどうかを尋ねており、2 ある
いはそれ以上の 3 という数字を出すことによって、一般的なメールアドレ
スの数(1つ)より多いことを強調して述べている。こうなると、Levinson
(2000: 88)の主張にもあるように、数字の正確さの問題ではなく、尺度上に
ある数の多さということになる(Finally, in the right context, where an exact
specification is irrelevant, the implicature is implicitly cancelled as in (9e): “Joh
has three children, if not four/ and perhaps more / or possibly five.”(最後に言っ
ておくが、正確な数の特定が関連しない文脈では、(9e)(ジョンの子ども
は、4 人とまで言わないにしても 3 人 / 3 人かもっと多いか / 3 人どころか
ひょっとして 5 人である)のようにこの推意は非明示的に取り消される)。
しかし、話題が数字の正確さかどうかは微妙な問題である。次の(31)は、
一見、AT LEAST 読みと考えられる。
(31) The double purpose of the parser coerced us to implement a scheme
where two (in fact three) kinds of information are propagated during
parsing. http://www.hulubei.net/tudor/cslang/doc/cslang_2.html
(31)は(29)と同じ at least 読みのように見える。しかし、「構文解析プログラ
ム(parser)の二重の目的」から 2 種類の情報を扱うという予測が可能で、2
種類という数字がすでに確立しているのである。ところが話し手は「実際
メタ言語否定と尺度性 23
には 3 種類だが・・・」と修正している。2 種類がそれまで、一般的に考
えられていた数字、3 種類が実情(あるいは話し手の信念)である。in fact
は単に一般論を(話し手のほうから)修正するつなぎ語に過ぎない。そう
すると、この 2 は exactly 読みの 2 であることが分かる。話し手は、メタ言
語否定と同じく、自分の持つ尺度上で 3 と言っているに過ぎない。2 は他
人の考えなのである。
しかし、次例のように明示的な at least 読みの数字表現も存在する。
(32) In fact, what happened that night, Your Honor, is that there were at
least four, in fact five witnesses that came forward in one way or
another and indicated that the shooter ran away.
www.justice4danielfaulkner.com/pcra/95-09-11.html
こちらは、at least 読みと考えて差し支えない。数量が本当はもっと多かっ
たと述べているのである。数字の正確さだけを問題としているのではない。
以上をまとめると、以下のような図式で理解することができる。
(33) 基礎的表意 尺度上の基礎的表意 尺度推意
非明示的表現
点としての数字=EXACTLY n AT LEAST AT MOST
明示的表現 exactly n at least n at most n
基礎的表意は字義的意味(文字通りの意味)と考えてよい。ここでは、Grice
流の推論過程を考えている。数字表現の場合、この基礎的表意に exactly
読みを考えざるを得ない。なぜなら、数字そのものは「点」を表すからで
ある。その上に、尺度性がいわば乗っているような意味構造を成している。
尺度性
尺度上の基礎的表意 尺度推意
AT LEAST n AT MOST n
尺度推意(exactly)
尺度性の明示(at least, at most)
24 田中廣明
そこで、通常の尺度推意が生じるのである。明示的な exactly, at least(at most)
表現は、非明示的表現とはまったく異なる。なぜなら、exactly n はそれ自
身で(たとえば approximately n との)尺度推意を形成し、at least n, at most
n は本来持っている尺度性が明示されるからである。
(33)の図式中では、EXACTLY n は (19a)(26)(28B1)、AT LEAST n は
(19c)(22)(30)である。(31)は問題があり、EXACTLY n で推意が生じている
例ではない。メタ言語否定(ただし、明示的な not によるものではない)
の例で、第 1 節で主張したように、話し手の持つ尺度に合わせようとした
メタ言語的な修正表現である。明示的な exactly n は(25)、at least n は(21)(33)
である。
3.5. 埋め込み文の推意(Embedded Implicatures)
(17)(18)で述べたように、尺度推意への大きな反論の一つに、埋め込み文
テストと呼ばれるテストがある。埋め込み文の中には推意が生じないとい
うテストである。
(17) If each side in the soccer game got three goals, then the game was a
draw.
(18) If some of the children have already arrived the others will be here
shortly. (Carston 1996, 1998a)
(17)(18)では(Grice 流の)尺度推意が生きているため、それが尺度推意で
あるかどうかは議論が分かれている。(17)は at least から at most を付け足し
た exactly 読みとしないと、意味をなさない。(18)も some but not all まで意
味をとらないと、帰結節の「子供たちの残りがすぐに到着する」という意
味が出てこない。
では、なぜ埋め込み文で推意が生じないのであろうか。Recanati(ms.)が
Anscombre and Ducrot(1978)10)からまとめたところによれば、推意の基本的
な性格とは(34a)のようなものであり、したがって(34b)から(34e)にあるよう
に埋め込み文で推意は生じない。
メタ言語否定と尺度性 25
(34) a. 会話の推意とは、発話行為(an act of saying)の結果語用論的に生
じる意味である。
b. 発話行為を行うのは、(真理条件の問える)完全発話(断定文)
によってのみである。選言文の選言肢、条件文の前件などで行
うことはできない。
c. したがって、下位発話レベル(埋め込み文のレベル、すなわち
選言肢や条件文の前言などの非断定文のレベル)では推意は生
じ得ない。
d. (選言肢や条件文の前言などの)論理演算子の作用域内で推意
が生じているということは、論理演算子が作用している節レベ
ル、すなわち下位発話レベルで生じていること(という誤った
結論)になる。
e. したがって、論理演算子の作用域内では推意は生じない。
問題は、なぜ推意が埋め込み文のレベルで生じているかである。解決法は
2 つあるように思われる。(i)推意の再考、すなわち推意か表意かの問題、
(ii)推意はなぜ発話レベルでしか生じないのか、すなわち(34a)の見直し。議
論の大半は、(i)に集中している。以下、Carston (2004)の Levinson(2000)批
判と Chierchia(2001)から考察する。
Carston(2004)は、一貫して、この推意を認めない。この推意はすべて発
話の命題内容に貢献する真理条件的意味(表出命題)ととらえているから
である。これに対し、Levinson(2000)は、一般的会話の推意 (Generalized
Conversational Implicature)ととらえ、埋め込み文の場合、埋め込み文内のあ
る特定の語彙項目に付随した推意が、語用論的に真理条件に侵入して、発
話全体の真理条件に貢献しているとする。これを Levinson は語用論的侵入
(pragmatic intrusion)と呼ぶ。いわば、埋め込み節内で「局所的(local)」に推
意と真理条件が計算され、全体に貢献していると考えるのである。
これに対し Carston(2004)は以下のように反論する。
26 田中廣明
(35) Premise 1: If someone left a manhole cover off and you broke your leg,
you can sue them.
Premise 2: Someone left a manhole cover off and Meg broke her leg.
Conclusion: Meg can sue them.
(35)は、「肯定式あるいは構成的仮言三段論法(modus ponendo ponens: MPP)」
と呼ばれ、妥当な推論(valid argument)である。前提条件 1 でも前提条件 2
でも and に「そのため」という「因果関係(cause effect relation)」を認めな
いと推論ができない。また次の three にも exactly 読みを認めないと推論が
できない。
(36) Premise 1: If both teams scored three goals then the result was a draw.
Premise 2: Both teams scored three goals.
Conclusion: The result was a draw.
ところが、Levison の語用論的侵入方式では、前提条件 1 と前提条件 2 の種
類が異なると Carston(2004)は言う。1 は推意の語用論的侵入により真理条
件に貢献する what is said での意味、2 は推意としての意味となり、妥当な
推論ができないとする。
さらに、Carston は Levinson の言うあらゆる一般的会話の推意が if 節内
の表出命題に貢献しているわけではないとする。いわば「過剰生成
(overgenrerate)」しているのである。
(37) If Sue is a linguist or an anthropologist, she is familiar with the
linguistic relativity hypothesis.
(38) If John’s action caused the car to stop then he is responsible for the
crash.
(37)の or は Q 推意では not and すなわち「言語学者と人類学者の両方では
ない」という推意(「除外(exclusive)の or」)が生じているはずであるが、if
メタ言語否定と尺度性 27
節ではその意味はない。(38)は Levinson の言う M 推意(普通でない(有標
の)形式を用いるのは、普通でない(有標の)意味と解釈せよ)が生じて
いるはずであり、「普通でない車の止め方をした」という推意が if 節内で
も生じているはずであるが、そうではない。(37)は「包含(inclusive)の or」、
(38)は cause…to do の「直接性対間接性」が意図されない意味である。それ
ぞれの推意が if 節内の真理条件の算出に侵入していないことになる。とこ
ろが、それぞれの if 節の内容を独立させると、(37)は「排除の or」、(38)は
「間接性、異常性」の推意が得られる。以上の 2 点が Carston(2004)の
Levinson 批判である。Carston は、推意は本来的に global(全体的)であるか
らして、局所的(local)に埋め込み文から積み上げていくのはおかしいと考
える。そのため、Levinson が提唱した推意の埋め込み節への侵入(intrusion)
にも異を唱えるのである。それよりは、そもそも GCI(一般的会話の推意)
という範疇は認められず、真理条件に貢献した表意のレベルにあると考え
ている。一つ一つに積み上げにしても、語彙のレベルで表として肉付けさ
れていけば、その都度関連性を計算でき、問題はないと考える。
(38)と(39)は or と cause…to do の基礎表意(字義的意味)だけが生じてい
ると解釈できる。独立文(非埋め込み節)で用いられた場合の推意が生じ
ないのであるから、直観的には、if 節が何らかの制限を加えていると考え
ざるを得ない。(38)(39)とも if 節は、帰結節に対しての十分条件しか述べて
いない。(38)では、言語相対説に通じているためには、言語学者であって
も人類学者であっても良い。(39)も推意を認めた、いわば、詳細化(enrich)
した意味をとすると、if 節の十分条件性にそぐわない意味になる。
Levinson, Carston に対して、推意は局所的に計算でき、その中でもある
一定の埋め込み節には推意は成立しないとしたのが Chierchia (2001)である。
Chierchia(2001)は、any などを認可する下方含意(downward entailment)の環
境(以下、「DE 環境」と呼ぶ)では、この尺度推意などの GCI は阻止(block)
(あるいは棚上げ(suspend))されるとする。例えば、John doesn’t smoke は
John doesn’t smoke Kent を含意(entail)する 11)。そのため、否定文は DE 環境
である。例えば、John met some of the students を否定文に入れると、
28 田中廣明
(39) a. It is not the case that John met some of the students. (=John met none
of the students)12)
b. It is not the case John met some but not all of the students.
c. #It is not the case that John met some of the students, but in fact John
met all the students.
d. John met some of the students.
e. John met some of the students, in fact all the students.
(39d)の肯定文の some は not all を尺度推意として持つ。その尺度は{all,
many, some}(all は many, some を含意する)となるからである。ところが、
(39a)は、not some(=no(none))が{not all, not many, not some(non(none))}と
いう尺度は持たない。すなわち、not some(no(none))と聞いても(39b)のよう
な not all という尺度推意は持たない。not some の尺度は{not some(no(none)),
not many, not all}であり、not some(non(none))が not many, not all を含意する。
これは、まさに、DE 環境にほかならない。ゼロ(not some(no(none)))が真な
ら、多くはない(not many)、全部はない(not all)も真になるからである。つ
まり、(39d)のように、some から生じる not all という推意を in fact を使っ
て取り消しはできないと言うことになる。なぜなら、not all という推意が
生じていないからである 13)。
if も DE 環境である。通例は DE 環境に入れた尺度表現は尺度推意を持
たずに、字義通りの意味しかない。
(40) a. If Paul or Bill come, Mary will be upset.
b. #But if Paul and Bill both come, Mary won7t be.
c. If Paul comes, Mary or Sue will be upset. (Chierchia 2001)
(40a)の or は「包含の or(inclusive)」であり、字義通りの意味でしかない。
Mary があわてるには Paul と Bill の両方来てもかまわない読みが優先され
る。したがって、(40b)のように、Paul と Bill の両方が来ればと「除外の
or(exclusive)」を意味するように後に続けるのは不自然である。ところが、
メタ言語否定と尺度性 29
DE 環境にない if 節の後件に or を用いると、Mary か Sue のどちらか一方
で両方ではないという読みになり、尺度推意が生じている。
(41) a. If Katie has a personal connection with a guest or I do, then
obviously, we'll take the lead in one of those things.
(CNN Larry King Live. April 1, 2001)
b. And if I come in and I want to wear, you know, a wild sport jacket
and maybe no tie or a turtle neck, and all of a sudden a major story
breaks, I am going to look out of place interviewing a secretary of
state, if I am sitting there in a turtle neck or in something wild.
(ibid.)
c. Before we talk all about the first 100 days in your life here, the one
thing that immediately comes to mind is -- and everyone's talking
about it, there are wags saying if it were Reagan or Clinton, they'd
have gone to Washington to greet those Navy men. The Bushes went
to Texas. How did you feel about that decision?
(CNN Larry King Live, April 18, 2001)
(41a)は inclusive 読みと考えられる or である。Katie か私が番組のゲストと
個人的な関係があれば、(プロデューサーではなくて)私たちが番組に呼ん
でインタービューをする優先権を持つ、と言っており、「Katie か私のどち
らか一方が・・・」が最低条件で両方でもかまわない。これに対し、(41b)
は、一見 exclusive 読みと考えられる。私がタートルネックとだらしない物
を一度に着ることはできないからである。しかし、(41b)はどちらか一方で
あればよいのであって(つまりどちらかが最低条件で)、両方ではないこと
が条件とはなっていない。同様に、(41c)もレーガンかクリントンならと言
っており、exclusive or のように見える。しかし、ここでもどちらか一方で
両方でないことが条件になっていない。その証拠に主節で they を使ってい
る。
orの意味は、(41a)のように、埋め込み節で inclusive読みが通例としても、
30 田中廣明
(41b)(41c)のように、独立文(非埋め込み節)の exclusive 読みが、条件文
内部では inclusive 読みになるものがある。つまり、(41a)にしても、(41b)(41c)
にしても尺度性が阻止されると考えた方がよい。独立文(非埋め込み節)
では、{and, or}という順序対(ordered pair)が存在する。それゆえ、or を使え
ば not and という尺度推意が生じ、exclusive 読みになる。しかし、埋め込
み節(条件文)になるとその順序対(尺度性)が消えてしまう。両方一度
に当てはまるという and の意味が矛盾するのである。例えば、I’m sitting
there in a turtle neck or something wild.あるいは It was Reagan or Clinton と言
えば、exclusive 読みとして A or B and not both(A and B)と言う「文字通りの
意味プラス推意」が「伝達される意味(communicative meaning)」として最
終的に伝わる。論理的には、私は両方着て座っていられないし、レーガン
とクリントンが両方一度にというわけではないので、条件文でも not both
の意味が保持される。しかし、そうしながら、後件の条件となる前件とし
ては、not both の意味が貢献していない。いわば背景的に隠されてしまう
のである。
では逆に推意が生じている例はどうであろうか。
(42) It was a two course meal. But everyone who had skipped the first or the
second course enjoyed it more. (Chierchia et al. 2004)
(43) It was a two course meal. If I had skipped the first or the second course,
I could have enjoyed it more. ((42a)を条件文に変更)
(42)(43)とも exclusive 読みと考えられる。まず、コースが 2 つあること、
次に、両方はぶけば(skip both)、食事を食べたことにならず帰結が成り立た
ない、という推論が働く。つまり not skip both という推意が保持される。
DE 環境であるので、{and, or}が{not-or, not-and}という含意関係に代わり、
元の not and を推意できなくなるはずであるが、not-and(not skip both)が前
提条件になっており、{and, or}からの尺度推意 not-and あるいは、DE 環境
での not-and という断定が保持されたままである。Chierchia(2001)の「DE
環境が尺度推意を阻止する(あるいは棚上げにする)」という条件は、阻止
メタ言語否定と尺度性 31
(棚上げ)されない場合、何がその阻止を阻止するのかを明示しなければ
ならない。
では、埋め込み節の場合の推意の阻止現象をどのように局所的に(積み
上げて)計算するのであろうか。Chierchia et al. (2004)では、次のような局
所的な派生過程を考えている。
(44) a. 尺度表現αを局所的に含む文は、字義通りの意味とαからの尺
度推意を計算する。
b. 字義通りの意味と尺度推意を比較する。
c. より情報量の多い方を選ぶ。すなわち、限定的な文脈に当ては
まるような解釈をする。
しかし、局所的に推意が計算されることと DE 環境が推意を阻止すること
は、優先順位はどちらが上かという問題を生じさせる。
(18) If some of the children have already arrived the others will be here
shortly.
(18)では、if 節が DE 環境を提供しているのに、some が尺度計算をさせて
いる。尺度計算の DE 環境による阻止を阻止するのは、the others…という
後件の意味である。すなわち、「そのほかの子どもたち」が対照的な「子ど
もの一部」という部分集合を呼び起こすのである。そうすると、some に尺
度推意(some and not all)を認めないと都合が悪くなる。いわば、全体を解釈
してもう一度再解釈しているのである。このように、Chierchia が言うよう
に、純粋に局所的な積み上げ方式の計算方法には疑問が残る。例えば、(45)
の some of は尺度推意を持つであろうか。
(45) Chances are that if you were to sell some of that stock right now, you're
not going to owe any income tax whatsoever.
(CNN Larry King Live, January 2, 2001)
32 田中廣明
「株をいくらか売れば税金を払わなくてよい」と言うと、DE 環境が阻止
されているようである。ただし、決定的な証拠はない。(41b)(41c)と同じよ
うに、not all の部分が後件の条件になっているかどうかが不明なためであ
る。むしろ、not all の推意が表面に出ていないと考えた方がよい。
Horn(ms.)は、この問題に対して、埋め込み文の推意計算は再解釈
(reinterpretation)を経て生じるとする。
(46) a. If some of my friends come to the party, I’ll be happy—but if all of
them do, I’ll be in trouble.
b. If it’s warm, we’ll lie out in the sun. But if it’s (VERY warm/hot),
we’ll go inside and sit in front of the air-conditioner.
(47) a. Because the police recovered some of the missing gold, they will
later recover it all.
b. Because the police recovered some of the gold, the thieves are
expected to return later #(for the rest).
(48) a. #Because it’s warm out [i.e. because it’s warm but not hot], you
should still wear a long-sleeved shirt.
b. #Because you ate some of your stewed eel [i.e. and not all], you
don’t get desert.
Horn は Levinson にならって DE 環境を if 節から because 節へと広げている
(その可否についてはここでは議論しない)。if 節, because 節に尺度推意が
読み込まれるのは、その尺度推意の取り消し表現((46a)の all など)が生
じて初めて推意としての計算ができるという。(47a)では「今は全部ではな
いが、警察はやがて全部取り返す」という意味が読み込まれる。(47b)では
推意の取り消しになっていないために for the rest だけを述べても再解釈で
きない。(48a)(48b)も同様に、because 節の段階だけでは尺度推意の計算が
メタ言語否定と尺度性 33
できないと考えている。一度全文を解釈し、前へ戻って再解釈するのは、
第 2 節で扱ったメタ言語否定と同様の解釈になる。そうすると、Carston が
あげている(18)の解釈はどうなるのかなど、問題は残る。
尺度推意が、Recanati の言うように、本来は発話行為としての働きを持
ち、埋め込み節とは相容れないというのが基本であろう。もし埋め込まれ
るとすると、再解釈される場面でメタ言語的に用いられると言うことがで
きる。
6 おわりに
第 2 節ではメタ言語否定について考察した。MNの話し手の発話意図と、
聞き手の解釈を分けて考えると、MN の特質が浮かび上がってくるように
思われる。MN の話し手は下限を、それを聞いた聞き手は上限を設定して
いると考えられる。そうすると、 MN と後ろの修正節は矛盾関係
(contradiction)にあるが、それは、MN の話し手の意識の中では矛盾ではな
く、聞き手(=先行発話の話し手)にとっての矛盾となること、吉村(2000a,
b)の express/communicate という区別がうまく説明できること、最後に MN
と DN のエコー特性をうまく説明できることを見た。
第 3 節では、尺度推意が推意か表意かという問題を考察した。あくまで
も、尺度性を認めた上での、推意を基本に置かなければならないとした。
ただし、Grice 本来の what is said と what is implicated の二分法ではすべて
をとらえているとは言い難く、推意は「基礎表意+推意」のレベルでの位
置を占めると思われる。最後に、埋め込み文での推意の位置は、Horn の言
うように、全体の真理条件が終わったあとに、もう一度戻って再解釈され、
その際には語句レベルで棚上げにされていた推意計算がもう一度なされる
と考察した。
*本稿の第 2 節は、2000 年 12 月 2 日に、神戸研究学園都市大学交流センター・
UNITY で開催された、日本語用論学会第 3 回大会で発表したものに大幅な修
正・加筆を加えたものである。大会で有益なコメントをいただいた、小泉保先
生、西山佑司先生、吉村あき子先生にお礼を申し上げる。
34 田中廣明
注
1) この例は「大丈夫」をとれば不可になるのではないかという指摘があった。
「大丈夫」はこの友人を安心させておいて、「ガンです」で下に落とすブラ
ック・ユーモアとしての働きがある。日本語で、 (4)(7)と同じ構造をしてい
る実例に次のようなものがあった。
[日頃お笑いタレントをしている磯野貴理子がめずらしくドラマで女優をし
ているのを聞いて ]
薬丸裕英:貴理子さん女優?
磯野貴理子:女優じゃないですよ。大女優ですよ。(笑)(『はなまるマ
ーケット』TBS テレビ。2000 年 12 月 11 日放送)
2) ただし、これだけでは上述した (1a)の発音や (1d)の形態素、 (1e)の使用域な
ど、「尺度」の考えにくい例は説明し切れていない。そのためには、「尺度の
下限」という基準を、MN の話し手が「正しいと信じる項目」まで含めた方
がよいと思われれる。正しい項目は、正しくない項目と強、弱の順序対
(ordered pair)をなす。
3) 「惑わし発話 (garden path utterance)」という。
4) 次例の B は A の「あなたのしていることにいい気持ちではない」という言
葉から、A が意図していないが言語表現の中には生じているはずの「私を信
用していない」という推意を誤解 (曲解 )して述べている。そのため、最後に
A は「そこまで言っていない」と修正している。A は「信用していない」を
express しているが communicate はしていないことになる: (A)“ I’m not very
happy about what you’re doing.” (B)“ In other words, you don ’t trust me?” (A)
“ I wouldn’t quite say that.” (田中 1998: 238)
5) 本来は、Sperber and Wilson(1986/1995)でアイロニーの説明に使われている。
「誰か他人に帰属する思考 (attributed thought)」という。
6) かつての kill を CAUSE TO DIE で意味分解したときの議論を思い起こして
もらいたい
7) さらに、Caopne(ms.)の報告によれば、At least three students came.は数字をは
っきりさせる必要のない「予備アンケート (threshold questionnaire)」や確定的
メタ言語否定と尺度性 35
な数字の情報を求めない質問に対しての答えとして用いられると言う。
8) ここで「意味拡充」と言った場合、意味論的な意味あるいは真理条件を問え
る字義通りの意味のことではない。一般的な意味のことを言う。
9) I have three children の three がなぜ at least three ではなく、exactly three になる
のかは、否定文 (DN)にしてみると分かる。I don’t have three children.と言えば
子供の数は 2 人でもよいし、4 人でもよい。exactly の意味で 3 以上でも以下
でもないとしておかないと、3 以上でないことはなく(つまり 4 以上)、3 以
下でないことはない(つまり 2 以下)、という読みにならないからである。
at least 3 としておくと、2 以下の読みしか出てこない。
10) 筆者は Anscombre and Ducrot (1978)は未見。(34)は Recanati(ms.)からの引用
である。参考文献には書誌情報は挙げておくので参照されたい。
11) No man smokes.は NO (MAN, SMOKES)という関係でとらえることができ、
MAN∩SMOKES=φと、MAN と SMOKES の外延の集合がゼロになる。タバ
コを吸う人がいないのであるから、下位集合のケントを吸う人もいないこと
になる。肯定文は逆の含意関係にある。He smokes Kent が He smokes を含意
する。上方含意 (Upward Entailment)と言う。
12) ただし、 It is not the case を第 2 節で扱ったメタ言語否定を解釈する場合を
除く。
13) {not some(no(none)), not many, not all}という尺度が書けるのであるから、not
all と言えば、not some(no(non))の否定、すなわち、not (not some) = some が尺
度推意されることになる。Not all the students came.と言えば、Some of the
students came.と言ったことになる。ただし、この推論は some が not all を推
意する場合に比べて、弱いとされている。 I don’t have many matches left.と言
っても、 I have some matches left.を推意するかどうかは明確ではないからで
ある。
参考文献
Anscombre, J-C., and O. Ducrot. 1978. “Echelles Implicatives, Échelles
Argumentatives et lois de Discours,” Semantikos 2 (2-3), 43-66.
Burton-Roberts, N. 1989. “On Horn’s Dilemma: Presupposition and Negation.”
36 田中廣明
Journal of Linguistics 25, 95-125.
Capone, A. (ms.) “Some Considerations on Carston’s Paper ‘Informativeness,
Relevance and Scalar Implicature.’”
Carston, R. 1996. “Metalinguistic Negation and Echoic Use.” Journal of
Pragmatics 25, 309-330.
― . 1998a. “Negation, ‘Presupposition’ and the Semantics/Pragmatics
Distinction.” Journal of Linguistics 34, 309-350.
―. 1998b. Pragmatics and the Explicit-Implicit Distinction. Ph.D. Dissertation.
University College London.
―. 2004. “Truth-Conditional Content and Conversational Implicature.” In C.
Bianchi (ed.) The Semantics/Pragmatics Distinction. Stanford: CSLI
Publications.
Chierchia, G. 2001. “Scalar Implicature, Polarity Phenomena, and the
Syntax/Pragmatics Interface.” Unpublished ms. of University of Milan.
(Forthcoming in A. Belletti (ed.) Structures and Beyond, Oxford: OUP).
Chierchia, G., M.T. Guasti, A. Gualmini, L. Meroni, S. Crain and F. Foppolo.
2004. “Semantic and Pragmatic Competence in Children’s and Adults’
Comprehension of Or.” In I.A. Novek and D. Sperber (eds.) Experimental
Pragmatics. 283-300. Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave
Macmillan.
Grice, P. 1975. “Logic and Conversation.” In P. Cole and J. Morgan (eds.) Syntax
and Semantics, vol. 3, Speech Acts, pp. 41-58. New York: Academic Press.
Horn, L. 1985. “Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity.” Language
61, 121-174.
―. 1989. A Natural History of Negation. Chicago: The University of Chicago
Press.
―. (ms.) “The Border Wars: A Neo-Gricean Perspective.”
Levinson, S.C. 2000. Presumptive Meanings: The Theory of Generalized
Conversational Implicature. Cambridge, Ma.: MIT Press.
Recanati, F. (ms.) “Embedded Implicatures.”
メタ言語否定と尺度性 37
Sadock, J.M. 1978. “On Testing for Conversational Implicature.” In P. Cole (ed.)
Syntax and Sematnics 9: Pragmatics. 281-297. New York: Academic Press.
Sperber, D. and D. Wilson. 1986/19952. Relevance: Communication and
Cognition. Oxford: Blackwell.
田中廣明. 1998. 『語法と語用論の接点』東京: 開拓社.
―. 2003. 「尺度推意とメタ言語否定」『英語青年』第 149 巻 第 6 号, 370-372.
van der Sandt, R.A. 1991. “Denial.” CLS 27/2: The Parasession on Negation,
331-344.
吉村あき子. 2000a. 「メタ言語否定と関連性理論」『学習院大学言語研究所
研究集会:関連性理論研究は認知・言語の研究に何を寄与しうるか』
口頭発表.
―. 2000b.「メタ言語否定と関連性理論」『英語青年』第 146 巻 第 7 号,
438-439.
―. 2004. 「第 2 章 表意と推意」東森勲・吉村あき子(著)『関連性理論
の新展開―認知とコミュニケーション』23-68. 東京:研究社.






































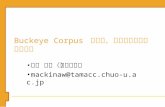




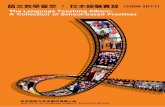
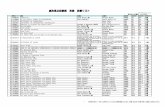









![コプト語の複数定冠詞(ハンドアウト)[Coptic Plural Definite Article (handout)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321a6dc64690856e108cc3b/coptic-plural-definite-article.jpg)



