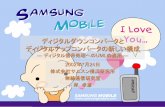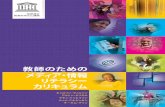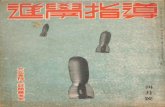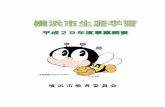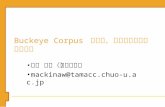方言習得における親の母方言の影響―形態音韻規則の習得に注目して―
Transcript of 方言習得における親の母方言の影響―形態音韻規則の習得に注目して―
方言習得における親の母方言の影響 *
―形態音韻規則の習得に注目して―
Parental influence in dialect acquisition
― The acquisition of morpho-phonological rules ―
竹村亜紀子
Akiko Takemura
国立国語研究所
National Institute for Japanese Language and Linguistics
ABSTRACT. This paper reports the parental influence in dialect acquisition in Japanese. Traditionally, it has
been said that the children acquire the local dialect wherever they are born and raised, however there are some
cases where that tendency is not observed. This article reports such cases in the Kinki dialect of Japanese and the
Kagoshima dialect of Japanese, with a focus on the acquisition of morpho-phonological rules and the impact of
parental origins. It reveals that the speakers with non-locally born parents acquire the dialectal phonological
system in its major aspects, but fail to fully acquire morpho-phonological rules. For more detailed contents and
explanation, please refer to the author’s dissertation completed at Kobe University.
Keywords: 方言習得、親、母方言、語彙アクセント、アクセント規則、習得
1.はじめに
一般的に子供は生まれ育った土地のことばを習得すると言われているが、先行研究の中には親の出
身地によって子供が習得することばが異なることを報告している (Trudgill 1986, Payne 1976, 杉藤
1984, 柴田 1958) 。本稿では親の母方言 (出身地に付随する方言) によって子供のアクセント習得が異
なるかどうかを近畿方言および鹿児島方言で調査した結果を報告する。本研究では当該方言 (近畿方言
/鹿児島方言) 地域に生育し両親の出身地は異なる話者を研究対象として調査を行った。本研究で明ら
かになった点は (1) 両親の出身地による方言習得の違いがあること、 (2) 方言接触がない環境 (両
親ともに近畿/鹿児島方言話者) で育った話者は規則的要素 (形態音韻規則) は変化しにくく、 (3)
方言接触の環境で育った話者 (片/両親が非近畿/非鹿児島方言話者) は規則的要素 (形態音韻規則)
の習得が異なっているということである。形態音韻規則から逸脱した例が多いということは、つまり
形態音韻規則が内在化されていないと思われる。子供の方言習得には様々な要因が関わっており、習
得に関して何が主たる要因であるかをここで議論することはふさわしくない。だが周縁的に扱われて
きた親の母方言の影響について、「形態音韻規則の習得」という側面からその影響の有無とその実態を
捉えることを試みる。
2.問題の所在
一口に「アクセントの習得」といっても、その習得には 2種類ある。那須 (2004) によるとアクセン
トの習得には「語彙アクセントの習得」と「アクセント規則の習得」の 2 種類があることを指摘して
いる。前者は各語彙に備わったアクセントを習得することであり、後者は複合語アクセントのように
大きなユニットを形成する際に適用される規則のことを指す。子供の言語習得を考えたときにどちら
が容易かというと後者が挙げられるであろう。語彙それぞれに備わったアクセントを一つ一つ覚えて
いく「語彙アクセント」の習得よりも、有限の規則を習得しそれを適用していく「アクセント規則」
の習得の方が容易であるように思われる。
同じ地域に生育した話者であれば一様にその土地のことばを習得すると言われているが、語彙アク
セントも有限のアクセント規則も同じように習得するのであろうか。そこで本研究では、同じ地域に
生育しながらも両親の出身地が異なる話者がどのようなアクセント―語彙アクセントとアクセント規
則―を習得しているのかを調べることを目的としている。話者の両親がその土地の出身者ではない場
合、両親の出身地に付随する方言、つまり話者の生育地と異なる方言を聞く環境であったと考えられ
る。そこで本研究では両親の出身地が当該方言地域とそうではない場合の環境で育った話者を対象に
調査を行った。
先行研究でも方言習得に関する研究は多いが (Trudgill 1986, Payne 1976, 杉藤 1984, 柴田 1958) 、
次のような問題点が挙げられる。
(1) 方言習得の調査では語形・アクセント型についての「語彙的」要素の習得が中心で、アクセ
ント規則の習得といった「規則的」要素の習得に関する研究が少ない点
(2) 調査対象者が言語形成期にある子供が中心であり、言語形成期を終えた話者が最終的にどの
ような方言を習得しているのか不明である点
上記のような問題点を踏まえ、本研究では言語形成期を終えた話者を研究対象とし、親の出身地の
違いによって方言習得の差はあるのか、もしあるとすれば、その違いはどこに現れてくるのかを調べ
る。「どこに」というのは「語彙的」要素の習得が困難なのか、あるいは「規則的」要素の習得が困難
なのかという点である。もし一般的に言われている「子供は生まれ育った土地のことばを習得する」
ということが当てはまるのであれば、異なる方言を聞いて育ったとしても「語彙的」要素の習得と「規
則的」要素の習得との間に違いはないはずである。とくに本稿ではアクセントの「規則的」習得に着
目しているため、語彙的アクセントの習得との比較については竹村 (2010) をされたい。
本研究の調査を行う上でポイントとなるのは、どのような「アクセント規則」をターゲットとして
使うのかという点である。そこで本研究では「複合語アクセント規則」の習得ができているかどうか
をターゲットとし、近畿方言と鹿児島方言で調査を行うことにした。なぜこの2つの方言を対象方言
にしたのかというと、両方言とも複合語を形成する際に明確な形態音韻規則である「式保存」の法則
があるからと言えるであろう 1 。この形態音韻規則を用いることによって音に関する規則を習得した
かどうかを調べることが可能となる。
3.近畿方言での調査および結果
3.1 近畿方言の韻律的特徴
近畿方言は「式」と「アクセント」の両方をもつ方言である。近畿方言には複合語を形成する際、
式保存の法則 (和田 1943) と呼ばれる形態音韻規則がある。これは「前部要素の式が複合語全体の式
を決める」というものである。 (3) に示したように高い音で始まる高起式の単語「きゃべつ」と低い
音で始まる低起式の単語「いちご」を使って、複合語を形成した際にどのようになるのか、具体例を
みてみる (太字および下線で示したところは高く発音される (卓立が置かれている) ことを示してい
る) 。
(3) (a) 高起式: きゃべつ + はたけ ⇒ きゃべつばたけ
(b) 低起式: いちご + はたけ ⇒ いちごばたけ
(3a) の高起式の単語「きゃべつ」の場合、後部要素の「はたけ (畑) 」という単語をつけて複合語
を形成した際には高起式で始まる複合語となる。一方 (3b) の低起式の単語「いちご」の場合、後部
要素の「はたけ (畑) 」を付けても低起式で始まる複合語となる。
3.2 近畿方言調査
調査の対象者は 18歳から 39 歳までの 81名 (男性 10 名、女性 71 名) である (表 1参照) 。調査対象
者は両親の出身地が近畿方言の地域かうかで4つのグループに分けた。両親ともに近畿方言地域の話
者は Group 1 に、両親ともに非近畿方言地域以外の話者は Group 4 に入る。
表1 近畿方言調査 調査対象者の内訳
(男性/女性) 父親
合計 当該地域出身 他
母
親
当該地域出身 [Group 1] 21 名 (0/21) [Group 2] 18 名 (1/17) 39 名 (1/38)
他 [Group 3] 21 名 (1/20) [Group 4] 21 名 (8/13) 42 名 (9/33)
合計 42 名(1/41) 39 名 (9/30) 81 名 (10/71)
調査語彙は二音節名詞 (単語単独形式) 、名詞句 (助詞付き形式) 、新造複合語形式の三種類である
(調査語彙の詳細は竹村 (2010) を参照のこと) 。近畿方言の複合語については複合語全体が 5モーラ以
下の場合、「式保存の法則」の例外が多い (中井 1996) ということから、複合語全体が 5 モーラ以
上になるように後部要素は 3モーラ以上の単語を使うことにした。調査は筆者が用意した調査語彙
を読みあげてもらう読み上げ形式である。アクセントは筆者が聴取し、その場で書き取りを行ったが、
後で確認ができるように録音も行った。
3.3 近畿方言調査での結果―新造複合語のアクセント
ここでは紙面の関係上、新造複合語を発音する際に「式保存の法則」に則って発音されていたかど
うか、その結果について提示する。新造複合語を発音する際に全部要素の高起式・低起式に従って新
造複合語全体が高起式・低起式で読まれているかどうかを調べた。ここでポイントとなるのは前部要
素のアクセントが伝統的な近畿方言で読まれているかどうかではなく、「式保存の法則」に則って新造
複合語を発音したかどうかという点である。先ほどの (3a) の「きゃべつばたけ」の例であれば、前
部要素の「きゃべつ」が低起式で読まれたとしても、新造複合語が低起式の「きゃべつばたけ」と読
まれているのであれば、その話者は式保存の法則に則って発音しているものとした。
図1は近畿方言で新造複合語を読む際に「式保存の法則」に則って発音したかどうか (前部要素の
式と複合語全体の式が同じかどうか) を示したもので、両親の出身地 (Group 1 ~Group 4) によって棒
グラフの模様が異なる。この図からわかるように Group 4 (両親 non-native) の場合、「式保存の法則」
から逸脱していることがわかる。
図1 近畿方言 新造複合語における「式保存の
法則」の一致率と逸脱率
図2 近畿方言 新造複合語における「式保存の
法則」逸脱の内訳
表2 近畿方言 新造複合語形式における「式保存の法則」からの逸脱の結果
式 核
語例 Group1
(21 人)
Group2
(18 人)
Group3
(21 人)
Group4
(21 人) 式の有無 式の一致 核の有無
京阪式
伝統的な
近畿方言 ○ ○ ○
なつ ⇒ なつやすみ 1990/2100
(94.8%)
1453/1800
(80.7%)
1555/2100
(74.0%)
975/2100
(46.4%) あき ⇒ あきやすみ
新しい
近畿方言 ○ × ○
なつ ⇒ なつやすみ 94/2100
(4.5%)
217/1800
(12.1%)
314/2100
(15.0%)
638/2100
(30.4%) あき ⇒ あきやすみ
東京式 × × ○ なつ ⇒ なつやすみ
な ⇒ なつやすみ
15/2100
(0.7%)
125/1800
(6.9%)
215/2100
(10.2%)
475/2100
(22.6%)
式有・核無 ○ ○ ×
はこ ⇒ はこびらき
やま ⇒ やまがかり
ふね ⇒ ふねまつり
1/2100
(0.05%)
5/1800
(0.3%)
16/2100
(0.8%)
4/2100
(0.2%)
○ × × はこ ⇒ はこびらき
式無・核無 × × ×
やま ⇒ やまがかり 0/2100
(0%)
0/1800
(0%)
0/2100
(0%)
8/2100
(0.4%) ふね ⇒ ふねまつ
0%
20%
40%
60%
80%
100%
伝統的な近畿方言 逸脱
Group1 Group2 Group3 Group4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Group1 Group2 Group3 Group4
式無・無核
式有・核無
東京
新近畿
では「式保存の法則」から逸脱したものの中でどのような逸脱をしているのだろうか。その内訳を
示したものが図2および表2である。表2の「伝統的な近畿方言」は「式保存の法則」に則って新造
複合語を発音したことを示している。問題となるのは次の段の「新しい近畿方言」で太い点線で囲っ
た部分である。これは高起式あるいは低起式があって近畿方言らしく聞こえるけれども、新造複合語
を発音するときには前部要素の式とは別の式で発音したことを意味している。
近畿方言における「式保存の法則」の習得度合をみると、やはり両親ともに近畿方言地域出身者
(Group 1) である場合には「式保存の法則」の習得率が高いということが表2の「伝統的な近畿方言」
というところをみるとわかる。一方、両親ともに非近畿方言地域出身者 (Group 4) の場合には、表2
の「伝統的な近畿方言」の割合が 50%であるが、逸脱パターンの多くが「新しい近畿方言」であるこ
とがわかる。これは近畿方言らしく聞こえるけれども「式保存の法則」からの逸脱していることを示
している。また「東京式」と分類された逸脱例が Group 4 (両親 non-native) に多いことも特徴である。
とくに両親ともに非近畿方言地域出身者 (Group 4) の場合には近畿方言らしく聞こえる韻律的特徴
(高起式、低起式) は習得しているように見えるが、「式保存の法則」というアクセントに関する規則的
要素は習得されていないようにみえることが明らかとなった (統計分析の結果については竹村 (2010)
を参照のこと) 。
4.鹿児島方言での調査および結果
4.1 鹿児島方言の韻律的特徴
鹿児島方言は2つのアクセント (A型と B 型) をもつ二型アクセントで、音節を単位とするシラビー
ム方言である (平山 1951、木部 2008) 。
(4) (a) A型: おんな (女) 末尾から二音節目が高く発音される
(b) B 型: おとこ (男) 末尾の一音節目が高く発音される
また近畿方言と同様に形態音韻規則があり、「複合語音韻規則」 (平山 1951、上野 1997、早田 1999) 、
あるいは「平山の法則」 (窪薗 2006, 2007) と呼ばれている 2 。これは複合語あるいは助詞がついた名
詞句を構成する際、最初の要素のアクセント型が複合語全体のアクセント型を決めるというもので、
近畿方言の「式保存の法則」とよく似ている。 (5) に鹿児島方言の A型および B 型の語例を示す。
(5) (a) A型: ゆき (雪) 、ゆきが、ゆきから、ゆきもんだい、ゆきもんだいが
(b) B 型: あめ (雨) 、あめが、あめから、あめもんだい、あめもんだいが
この「平山の法則」に則って名詞句および複合語を読むことができるかどうかが「規則的」要素を
習得しているかどうかに関わっているといえるであろう。
4.2 鹿児島方言調査
調査の対象者は 15 歳から 28 歳までの 55名 (男性 13名、女性 42 名) である (表 3 参照) 。調査対象
者は両親の出身地が鹿児島方言の地域がどうかで4つのグループに分けた。両親ともに鹿児島方言地
域の話者は Group 1 に、両親ともに非鹿児島方言地域以外の話者は Group 4 に入る 3。調査語彙は窪薗
(2006) で使用した名詞 (単語単独形式) 、その名詞に助詞「が」をけた名詞句 (助詞付き形式) 、そし
てその名詞を用いて作成した新造複合語形式の三種類である (調査語彙の詳細は竹村 (2010) を参照
のこと) 。鹿児島方言の新造複合語は特に若年層については変化が著しく、「平山の法則」を逸脱して
いる変化があると言われている (窪薗 2006, 2007) 4 。調査は筆者が用意した調査語彙を読みあげても
らう読み上げ形式である。アクセントは筆者が聴取し、その場で書き取りを行ったが、後で確認がで
きるように録音も行った。
表3 鹿児島方言調査 調査対象者の内訳
(男性/女性) 父親
合計 当該地域出身 他
母
親
当該地域出身 [Group 1] 18 名 (4/14) [Group 2] 13 名 (2/11) 31 名 (6/25)
他 [Group 3] 16 名 (4/12) [Group 4] 8名 (3/5) 24 名 (7/17)
合計 34 名 (8/26) 21 名 (5/16) 55 名 (13/42)
4.3 鹿児島方言調査での結果―助詞付き形式のアクセント
近畿方言の調査結果との整合性を保つのであれば、鹿児島方言での調査結果は新造複合語形式で「平
山の法則」に則って発音しているかどうかを提示すべきであるが、先述のとおり鹿児島における若年
層の新造複合語では「平山の法則」は保たれていない。そのため本論文では助詞付き形式において「平
山の法則」に則って発音できているかどうかを報告する。
表4 鹿児島方言 助詞付き形式における「平山の法則」からの逸脱の結果
単語 A型 単語 B 型
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
AA
(正答)
350/392
(89.3%)
158/235
(67.2%)
134/255
(52.5%)
46/86
(53.5%)
BB
(正答)
345/456
(75.7%)
166/368
(45.1%)
202/286
(52.3%)
48/211
(22.7%)
AB
(B 転)
34/42
(81.0%)
47/77
(61.0%)
78/121
(64.5%)
9/40
(22.5%)
BA
(A転/
ア移無)
109/111
(98.2%)
200/202
(99.0%)
173/184
(94.0%)
138/163
(84.7%)
AC1&2
(移無)
8/42
(19.0%)
26/77
(33.8%)
30/121
(24.7%)
22/40
(55.0%)
AC3
(東京)
0/42
(0.0%)
4/77
(5.2%)
13/77
(10.7%)
9/40
(22.5%)
BC
(東京)
2/111
(1.8%)
2/202
(1.0%)
11/184
(6.0%)
25/163
(15.3%)
合計 42/42
(100%)
77/77
(100%)
121/121
(100%)
40/40
(100%) 合計
111/111
(100%)
202/202
(100%)
184/184
(100%)
163/163
(100%)
表4は助詞付き形式においてどの程度「平山の法則」に則って発音したか、またどの程度その法則
から逸脱したかを示している。左半分の「単語 A型」および右半分の「単語 B型」は調査語彙の単語
単独形式が A型/B型のどちらの型で読まれたのかを示している。上から 3 段目の AA (正答) および
BB (正答) はどの程度「平山の法則」に則って助詞付き形式を発音したかを示している。この AA (正
答) および BB (正答) 以下の点線で囲った部分は「平山の法則」から逸脱したものの内訳を表している
(図 3、図 5) 。
図3 鹿児島方言 助詞付き形式における「平山
の法則」に則って発音したものと逸脱の割合 (A
型で読まれた単語)
図4 鹿児島方言 助詞付き形式における「平山
の法則」からの逸脱の内訳 (A型で読まれた単語)
図5 鹿児島方言 助詞付き形式における「平山
の法則」に則って発音したものと逸脱の割合 (B
型で読まれた単語)
図6 鹿児島方言 助詞付き形式における「平山
の法則」からの逸脱の内訳 (B 型で読まれた単語)
では「平山の法則」から逸脱した内訳はどのようになっているのだろうか。その内訳は表4の点線
で囲った部分である。この部分をみてみると、逸脱パターンとして多いものはグループによって異な
るが AB (B 転) と BA (A転) が多いことに気が付く。この AB (B 転) および BA (A転) は A型で単語
0%
20%
40%
60%
80%
100%
AA A型逸脱
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
AC3
AC2
AC1
AB
0%
20%
40%
60%
80%
100%
BB B型逸脱
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
BC
BA
を発音したものを助詞付き形式のときに B 型で言ったもの (B 型に転化したもの) (例:ロンドン (A
型) ⇒ロンドンが (B型) ) 、あるいは B 型で単語を発音したものを助詞付き形式のときに A型で言っ
たもの (A型に転化したもの) (例:コーヒー (B 型) ⇒コーヒーが (A型) ) を表している。
この AB (B転) および BA (A転) という逸脱パターンは鹿児島方言の A型/B型に当てはまってい
るため鹿児島方言らしく聞こえるが、「平山の法則」から逸脱しているという側面からみるとアクセン
トの規則的要素の習得が不十分とみることができる。さらにこの AB (B 転) および BA (A転) の割合
を比較してみるとBA (A転) の逸脱パターンの方が多いことがわかる (図6) 。AB (B転) およびBA (A
転) 以外の逸脱パターンとして多いのは AC1 および AC2 と呼ばれる逸脱パターンである。これは助詞
の「が」がついた形式においても卓立の位置が移動しないように見え、また鹿児島の A/B 型のパタ
ーンではない別の型 (C 型) で発音されていることを示している。
例えば逸脱パターンの AC1 は単語単独形式で「ロンドン」と言って、助詞の「が」が付いたときに
は「ロンドンが」と卓立に位置が移動していない (しかし音節が卓立を担っている) ものを表し、逸脱
パターンの AC2 は単語単独形式で「たべもの」と言って、助詞の「が」が付いたときには「たべもの
が」と卓立に位置が移動していない (しかしモーラが卓立を担っている) ものを表している。AB (B 転)
および AC1 & AC2 (卓立の位置が移動しない) という逸脱パターンを合わせると、BA (A転) の逸脱パ
ターンと同等の割合になるところがポイントである。つまり「平山の法則」から逸脱する場合でもで
きるだけ鹿児島方言の韻律的特徴 (A/B 型の保持、音節性の保持) の中で逸脱していることがわかる。
先の近畿方言の調査結果と同様に、両親が非鹿児島方言地域の出身者 (Group 4) は鹿児島方言らし
く聞こえる韻律的特徴は習得しているように見えるが「平山の法則」というアクセントの規則的要素
は習得できていない点が明らかとなった (統計分析の結果については竹村 (2010) を参照のこと) 。
5.考察-アクセント規則の習得
本稿で中心的に扱ったのは両親の出身地の違いによるアクセント規則の習得である。本研究では調
査を行った方言―近畿方言および鹿児島方言―に存在する「式保存の法則」および「平山の法則」を
用いて、それぞれの法則がどの程度できているのかを調べた。両方言で行った調査の結果から明らか
になったことは両親ともに当該方言地域の出身の話者 (Group 1) と両親ともに非当該方言地域の出
身の話者 (Group 4) とではアクセント規則の習得が同じではない点である。前者の両親ともに当該方
言地域の出身の話者 (Group 1) というのは方言接触がない環境 (両親ともに近畿/鹿児島方言話者
で生育地も近畿/鹿児島方言) で育った話者いうことができよう。このような話者は規則的な要素 (形
態音韻規則) は比較的変化しにくいと考えられる。
しかし、両親ともに非当該方言地域出身の話者はいわば方言接触の環境―家庭外は当該方言 (近畿方
言/鹿児島方言) 家庭内では非当該方言―で育ったということができる。つまり異なった方言に接す
る環境で育った話者は音に関する形態音韻規則を内在化させることができない可能性があることを示
唆している。このような傾向は他の言語でも観察される。アメリカのフィラデルフィア方言の Short-a
と呼ばれる複雑な音韻規則の習得も両親の出身地がフィラデルフィアかどうかによって Short-aの習得
が異なることを報告している (Payne 1976) 5。日本語だけではなく他の言語でも両親の出身地に付随す
る母方言の違いによって、その子供が習得する方言が異なるという点は示唆に富んでいるのではない
だろうか。これまで一般的に「子供は生育地の方言を習得する」と言われてきたが、形態音韻規則-
あるいは広い意味での文法-の習得という側面から親の母方言とその子供の方言習得を捉える必要が
あるのではないだろうか。
しかしながら、本研究結果で注意しなければならない点がいくつかある。まず一点目は両親ともに
非当該方言地域の出身の話者 (Group 4) の全員がアクセント規則の習得が不十分というわけではない
点である。両親ともに非当該方言地域の出身の話者 (Group 4) の中には両親ともに当該方言地域の出
身の話者 (Group 1) とほとんど違いがないアクセント規則の習得度合を示す話者がいることにも言及
しておかなければならない。本稿で示した両方言の調査結果はあくまで筆者が両親の出身地によって
分けた各グループ全体の平均である。そのため各グループ内の話者ごとに方言習得の違いがあること
も確かである (個人差については竹村 (2010) を参照のこと) 。また本研究の結果から「両親の出身地
のみによって子供の方言習得が決まる」ということを主張したいわけではないことを強調しておかな
ければならない。
また二点目は両親が当該方言地域に移住してきてから母方言を日常生活で保持している保障はな
いという点である。あるいは当該方言地域に移住してきてから当該方言を話している/話す努力をし
ているという可能性もある。そのため言語形成期を過ぎて移住した話者が移住先でどのようなアクセ
ントを習得するのか―語彙的アクセントの習得およびアクセント規則の習得―を調べる必要がある。
このことは第二言語習得と第二方言習得との違いにも広がりをみせる問題となるであろうが、これは
今後の研究課題としたい。
6.まとめ
本稿では両親の出身地の違いによって当該方言アクセントの習得―とくにアクセント規則の習得―
の実態を近畿方言と鹿児島方言で調査結果について報告・考察を行った。その両方言の調査結果から
分かったことは (1) 両親の出身地のよる方言習得の違いがあること、 (2) 方言接触がない環境 (両
親ともに近畿/鹿児島方言話者) で育った話者は規則的な要素 (形態音韻規則) は変化しにくく、 (3)
方言接触の環境で育った話者 (片/両親が非近畿/非鹿児島方言話者) は伝統的な文法的要素の習得
が不完全であるために規則的な要素 (形態音韻規則) が異なっているということである。形態音韻規則
から逸脱した例が多いということは、つまり形態音韻規則が内在化されていないと思われることであ
る。また方言接触の環境で育った話者は調査を行った地域の当該方言らしく聞こえる―つまり近畿方
言らしく聞こえる、あるいは鹿児島方言らしく聞こえる―疑似的な鹿児島方言が多く観察されること
も明らかとなった。
方言習得の研究において親の母方言の影響は看過されがちであるが、少なからずその影響があるこ
とが明らかになった。だが方言習得について第二言語習得と比べると研究事例の報告は多くなく、ま
だ未解明の部分も多い。アクセントだけではなく、方言習得に関する網羅的な調査は今後の研究課題
としたい。
**************************************************************************************
注
* 本稿は日本音韻論学会 2012年度春季研究発表会 (2012年 6月 15日、於 首都大学東京・秋葉原サ
テライトキャンパス) で行った学位取得者講演の内容をまとめたものである。詳細については著者の博
士学位論文『方言習得における親の母方言の影響』 (2010年 9 月、神戸大学) を参照のこと。
1 二型アクセントをもつ鹿児島方言では、複合語を形成する際のアクセントは「式」ではないが、本論
文では一種の「式」と捉えて式保存の法則とみなすことにする。
2 この論文の中では「平山の法則」と呼ぶことにする。
3 鹿児島県の中でも一型アクセント地域 (例えば志布志市) 、あるいは鹿児島の二型アクセントとは異
なるアクセント地域 (例えば奄美大島) の出身の親の場合は非鹿児島方言地域出身者とした。
4 「平山の法則」に従って新造複合語を読むのであれば、複合語の前部要素のアクセント型が複合語全
体に引き継がれるはずであるが、若年層は後部要素に着目して複合語を発音していると言われている。
後部要素によってアクセントが決まるというのは東京方言の複合語アクセント規則と同じである具体
例としては、後部要素が「コーナー」であれば東京方言では起伏式で発音されるので鹿児島方言の A
型で発音し、「~病」であれば東京方言では平板式で発音されるので B 型で発音するというものである。
5 Payne (1976) によると両親がフィラデルフィア以外の出身で、フィラデルフィアで生まれ育った子
供 7人の Short-a の習得を調べたところ、部分的な Short-a の規則を習得したが完璧な Short-a の規則は
習得していないと報告している。
参考文献
早田輝洋 1999 『音調のタイポロジー』大修館書店.
平山輝男 1951 『九州方言音調の研究』.学界の指針社.
木部暢子 2008 「内的変化による方言の誕生」 小林隆・木部暢子・高橋顕志・安部清哉・熊谷康雄 (著)
『方言の形成』 岩波書店.
窪薗晴夫 2006『アクセントの法則』岩波書店.
------------ 2007 鹿児島方言のアクセント変化―複合法則の崩壊―.神戸言語学論叢 第 5 号 西光義弘
教授還暦記念号.神戸大学文学部 言語学研究室.
中井幸比古 1996 「京都アクセントにおける式保存について」 平山輝男博士米寿記念会 (編) 『日本
語研究諸領域の視点 (下) 』1051-1035.明治書院.
那須昭夫 2004 『若年層京阪式アクセントにおける式保存の動態―若年層京都方言話者の複合語音調
形成に関する調査資料―』 平成 15年度大阪外国語大学特定運営経費 (B) .
Payne, Arvilla. 1976. The acquisition of the phonological system of a second dialect. Ph.D
dissertation. University of Pennsylvania.
杉藤美代子 1984「親の方言アクセントが子供のアクセント型の発話に与える影響」『柴田さんと今田
さん』 和泉書院.
柴田武 1958 『日本の方言』岩波書店.
竹村亜紀子 2010 「言習得における親の母方言の影響」戸大学博士学位論文.
Trudgill, Peter. 1986. Dialect in contact. Basil Blackwell.
上野善道 1997「複合名詞から見た日本語諸方言のアクセント」杉藤美代子監修『アクセント・イント
ネーション・リズムとポーズ』 (日本語音声[2]) .三省堂.
和田實 1943 「複合語アクセントの後部成素として見た二音節名詞」『方言研究』7: 1-26.