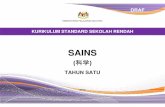外国人留学生科目「自律学習」における メタ認知のつまづきを探る
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 外国人留学生科目「自律学習」における メタ認知のつまづきを探る
外国人留学生科目「自律学習」における メタ認知のつまづきを探る
小林ひとみ(神田外語大学)
第21回 大学教育研究フォーラム 2015年3月13日(金) 部会7 口頭発表4 予稿集p.108
1
自己調整の 下位過程
メタ認知的 知識
メタ認知的活動
学習観 モニタ リング
コント ロール
学生A
上達 ○ 高次 ○ 認知主義的
学生B
初歩 ○ 低次 ○ 非認知主義的
2
気づき:学習観→視点→メタ認知?
研究の動機
2013年
• 外国人留学生科目「自律学習」担当開始
• 評価どうする?! (次ページ参照)
2014年
• 学生いろいろ、学習いろいろ
• そうだ、研究しよう
2015年
• 研究を拡大して、評価のしくみを作っちゃおう
(4月から)
3
Planning and
Reflection on
the Learning
Workflow
30%
In-Class Self-
Learning
Activities
Approaches
25%
Weekly
Learning Plan
and Report
(Learning Log)
25%
Attendance
15%
Class
Participation
5%
「自律学習」
成績内訳
4
先行研究 自己調整学習とは
「自分で自分を動かし、
学習計画を立て①、
学習進捗を把握し② 、
学習結果を評価する③
学習の過程」
(ジマーマンとシャンク, 2006)
5
①予見
②遂行 ③自己内省
自己調整学習とメタ認知的活動
(三宮, 2008)
メタレベル
対象レベル
メタレベル
対象レベル
メタレベル
対象レベル
7
課題分析 達成度予想
目標設定 計画
方略選択 動機づけ
課題再分析 遂行状況点検 方略点検
予想適合評価
目標修正 計画修正 方略変更
達成度評価 原因分析
目標再設定 再計画
方略再選択
①予見
②遂行 ③自己内省
実践の概要
女性
Basic 入門
男性
女性
1 初級前半
男性
2 初級後半
女性
男性
男性
女性
3 初中級
9
「自律学習1b」2014年後期 履修外国人交換留学生・聴講生(イオン㈱社員)8名 7名:2014年9月~ 1名:2014年4月~, 早期帰国のため13回目まで出席
学生A 学生B
出身, 母国での教員, 本学での所属クラス・担任教員が同じ。 履修科目もほぼ同じ。
第1回
•教材紹介
•Can-do・学習ス
タイル質問紙回答
•時間管理指導
•サイクル1学習計
画設計
第2回
•サイクル1学習計
画修正アドバイジ
ング
•ノートテイキング
指導
第3-7回[サイクル1]
•自己調整学習スト
ラテジー指導
•目標設定・学習計
画設計
•学習遂行
•自己内省
10
[宿題] Weekly Learning Log ※第7回のみ: ・問題分析 ・サイクル2学習 計画設計
3回目が初。 4回目によい例提示。
第4回
学期の折り返し
第8回
•サイクル2学習計画
修正アドバイジン
グ
•他学生Weekly
Learning Log評価
第9-13回[サイクル2]
•自己調整学習スト
ラテジー指導
•目標設定・学習計
画設計
•学習遂行
•自己内省
第14回
•春休み学習計画修
正アドバイジング
•他学生Weekly
Learning Log評価
•期末自己評価
11
[宿題] Weekly Learning Log ※13回目のみ: ・期末振り返り ・春休み学習計画 設計
[宿題] Weekly Learning Log
予稿集発表要旨作成に分析が間に合う最新の回
第11回
13
第2回:ノート作成法
第3回:学習ログの効果
第4回: 3つの学習スキル:認知・運動・態度
第5回:ポモドーロ・テクニック
第6回:深い学習, Learning how to learn
第7回: Fixed mindset vs. Growth mindset
第9回: Rote Learning vs. Meaningful Learning
第10回:集中学習 vs. 分散学習
第11回:原因帰属
第12回:結果期待 vs. 効力期待, 自己効力感
第13回:学習ストラテジーチェックリスト
第14回:自己調整学習とは
14
まいしゅう べんきょうを はじめる まえに、ここに よていを postして ください。したの テンプレートを つかって ください。
1) Post your plan for today's learning using the template below.
Note: Start yourself learning after you have finished posting.
-----------copy and paste the template below-----------
★What are you going to achieve today? (goal setting)
●what are you going to do to try to achieve today's goal?
◆what are you going to give attention to, to achieve today's goal?
■What resource(s) are you going to use today? List them all (book title, URL, etc.).
-----------copy and paste the template above-----------
15
1) Take picture(s) of your notebook or learning resource to show how you achieved today's learning.
2) Post your reflection on today's learning with the picture(s).
Note: Use the template below.
3) If you didn't finish submitting your reflection in class, you can do so until 23:59.
-----------copy and paste the template below-----------
■Facts on Learning
a. Amount of learning
just right(ちょうどいい)/ too much(おおすぎる)/ too little(すくなすぎる) →
b. Difficulty of material(s)
just right(ちょうどいい)/ too hard(むずかしすぎる)/ too easy(やさしすぎる) →
c. Something you missed doing
none/ yes, I have → (when yes) →
d. Most important action to help you learn →
→reason:
e. Next time what are you going to try to do? →
→reason:
f. Something you started to do/ new idea for learning →
◆Finding(s) from facts →
●Lesson(s) you got →
★Statement on learning →
-----------copy and paste the template above-----------
16
Post your learning log using the template below.
1) Take up to 5 pictures as evidence of learning to show how you achieved last week's personal learning (excluding Bekka class).
2) Post your reflection on last week's learning with the picture(s).
-----------copy and paste the template below-----------
■Facts on Learning
a. Amount of learning
just right(ちょうどいい)/ too much(おおすぎる)/ too little(すくなすぎる) →
b. Difficulty of material(s)
just right(ちょうどいい)/ too hard(むずかしすぎる)/ too easy(やさしすぎる) →
c. Something you missed doing
none/ yes, I have → (when yes) →
d. Most important action to help you learn →
→reason:
e. Next time what are you going to try to do? →
→reason:
f. Something you started to do/ new idea for learning →
◆Finding(s) from facts →
●Lesson(s) you got →
★Statement on learning →
-----------copy and paste the template above-----------
方法 第4回
ほうこく 第4回 Log
第7回 問題分析
第11回 ほうこく
第11回 Log
第4回 ほうこく
第4回 Log
第7回 問題分析
第11回 ほうこく
第11回 Log
学生A
学生B
SCAT Steps for Coding and Theorization 質的データの分析手法 http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/
17
• SCAT とは何か
質的研究では,主に観察や面接(インタビュー)によって,質的データ(言語記録)を作成し,それを分析します.その際,記録を分析して理論を書くということは,大変楽しい作業でもありますが,慣れない人にとっては困難な作業でもあります.それは,質的研究には量的研究における統計学的手法のような定式的な分析手続きが存在しないためです.
そこで,多くのやり方ではデータにコードを付し(コーディングと呼びます),それをもとに理論化を行います.しかし,そのコードがうまく付けられないという人もいますし,また,コードは付けられたのだけれど,そこから理論化(結論記述)に発展させられないという人もいます.質的研究に魅力を感じながらもそれに着手できないことがある のは,多くはこのようなデータ分析の難しさのためだといえます.
SCATはそのような分析の困難さという問題を克服するために開発された手法です.SCATは,マトリクスの中にセグメント化したデータを記述し,そのそれぞれに,
〈1〉データの中の着目すべき語句
〈2〉それを言いかえるためのデータ外の語句
〈3〉それを説明するための語句
〈4〉そこから浮き上がるテーマ・構成概念
の順にコードを考えて付していく4ステップのコーディングと,そのテーマ・構成概念を紡いでストーリー・ラインを記述し,そこから理論を記述する手続きとからなる分析手法です。この手法は,一つだけのケースのデータやアンケートの自由記述欄などの比較的小さな質的データの分析にも有効です.また,初学者が着手しやすい方法です.(この手法は,現在のところ,日本人の開発した唯一の完全にオリジナルな「テクスト形式の質的データ」の分析手法でもあります.)
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/~otani/scat/#02 18
• 自己調整の下位過程に関する記述例
20
・To better understand the N4 listening practice sessions.
(第11回Log)
・I'm slowly improving! (第11回Log)
・I am shy and I don‘t remember things very well, making
learning a new language in that new language’s country
rather challenging. (第7回問題分析)
・very awkward speaker when attempting to communicate in
Japanese. (第7回問題分析)
上達
初歩
学生A
学生B
【低い自己効力感、マイナスの自己反応】
【特定目標、プラスの自己反応】
結果と考察
21
・if you won’t practice, you will forget. (第4回ほうこく)
・Kanji are easy to forget. (第4回ほうこく)
・it takes baby steps to reach a big goal. (第4回Log)
・I write things in columns, go five ish kanji at a time, and
then move on when I have mastered these. Then at the
end I write down the English meanings, then the romanji,
and then the kanji. (第4回ほうこく)
○
学生A
学生B
• メタ認知的知識に関する記述例
• メタ認知的モニタリングに関する記述例
22
・It's easier for me to remember the meaning of the
Kanji. I enjoy reading and translating the most.
Since I don't practice speaking or reading out loud,
it's easy to forget how to say or pronounce them. (
第7回問題分析)
・I picked a few hard kanji but most of them were
simpler in concept and strokes. I did this because I
was worried that I would run out of time. (第4回ほうこ
く)
高次の モニタリング
低次の モニタリング
学生A
学生B
【遂行行動】
【自己の行動パターン】
• メタ認知的コントロールに関する記述例
23
・Listening more to Japanese media instead of
English media. (第11回ほうこく)
・Take every opportunity to use Japanese! (第
11回Log)
・pick harder kanji before class. If I really want, I
can pick more too. I figured very roughly 3
minutes per kanji is needed to memorize? (第4
回ほうこく)
○
学生A
学生B
• 学習観に関する記述例
24
・Never give up! (第11回ほうこく)
・Listening without having an interaction will
only let you improve so much. (第11回Log)
・I can be shy and I hate messing up. (第7回問題
分析)
・well... it was indeed a partially memorized
speech.... (第11回Log)
認知主義的
非認知主義的
学生A
学生B
【結果重視志向、暗記重視志向】
【失敗活用志向、方略志向】
結論:生き方の違いが学習に表れる
自己調整の 下位過程
メタ認知的 知識
メタ認知的活動
学習観 モニタ リング
コント ロール
学生A
上達 ○ 高次 ○ 認知主義的
学生B
初歩 ○ 低次 ○ 非認知主義的
25
• B. J. ジマーマン,D. H. シャンク (2014) 自己調整学習ハンドブック. 北大路書房
• B. J. ジマーマン,D. H. シャンク (2006) 自己調整学習の理論. 北大路書房
• Nelson, T. O. & Narens, L. (1994). Why investigate metacognition? In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp.1-25). Cambridge, MA: The MIT Press.
• 市川伸一 (編) (2014). 学力と学習支援の心理学. 放送大学教育振興会
• 桜美林大学日本語プログラム「グループさくら」 (編) (2007). 自律を目指すことばの学習―さくら先生のチュートリアル―. 凡人社
• 大谷尚 (2011) SCAT: Steps for Coding and Theorization―明示的手続きで着手しやすく小規模データに適用可能な質的データ分析手法―. 感性工学,10(3):155-160
• 小嶋英夫・尾関直子・廣森友人(編) (2010). 英語教育学大系 第6巻 成長する英語学習者――学習者要因と自律学習. 大修館書店
• 三宮真智子 (2008) メタ認知 学習力を支える高次認知機能. 北大路書房
• 自己調整学習研究会(編) (2012). 自己調整学習―理論と実践の新たな展開へ. 北大路書房
※当日の発表資料等をhttp://goo.gl/PcUXHyにアップロードする予定です。ご参照ください。
参考文献など
27
付録 • 第1回教材
o Can-doアンケート(JF Can-doを元に作成) http://goo.gl/TxoOo1
o 学習スタイルアンケート http://goo.gl/EOvsCJ
o 時間管理シート http://goo.gl/5DpV2u
o 学習計画設計 http://goo.gl/R3iok3
※7回目, 13回目も使用, リンク先は13回目用の文言
• 第7回教材
o 問題分析(桜美林大学, 2007を元に作成) http://goo.gl/CzK7oV
• 第8回教材
o 他学生Weekly Learning Log評価
※指示の文言: ”Feedback to the other students' and your own Learning
Log.”
ルーブリックは以下の通り, 14回目も使用
28
1/14は じりつ学習の さいごの じゅぎょうです。この 日は べんきょうは しません。学生は 小さい レポートを 書きます(英語も日本語もOKです)。レポートの トピックは あきがっきの じりつ学習についてです。たとえば、
・べんきょうの よていや ほうほうは よかったですか。
・べんきょうは たくさん できましたか。
・あたらしい べんきょうの ほうほうを しりましたか。
レポートの アイディアの ために しつもんを つくりました。下の 1から7までの しつもんに こたえて ください。この しゅくだいを わすれると レポートを 書く ことが とても むずかしく なります!しめきりは 1/9(金曜日)の 23:59です。
-----------copy and paste the template below-----------
<1.じりつ学習の べんきょうの よていは どうでしたか。 よかったですか。 どうしてですか。>
<2.じりつ学習の べんきょうの ほうほうは どうでしたか。 よかったですか。 どうしてですか。>
<3.じりつ学習の べんきょうは 自分の 大きい ゴールに やくにたちます(useful)か。 どうしてですか。>
<4.じりつ学習の べんきょうで あたらしい べんきょうの ほうほうを つかいましたか。 どんな ほうほうですか。 どうして その ほうほうを つかったんですか。>
<5.日本語の べんきょうで 何か トラブルが ありますか。 どんな トラブルですか。>
<6.5の トラブルは どうやって かいけつ(solve)しますか。>
<7.来年の 今日、日本語を つかって 何が できたら うれしいですか。 あたらしい ゴールを かいて ください。>
-----------copy and paste the template above----------- 29
• 第13回教材
o 期末振り返り
1. Rubricを つかって、じぶんの evaluationを します。どうして その scoreですか。たくさん くわしく(in detail) せつめいして ください。このpostは final gradingに 入ります!
2. ほかの 学生の postを よみます。そして、コメントを かきます。
日本語も えいごも スペインごも OKです。
30
• 第14回教材
o 期末自己評価(ルーブリック:小嶋ほか, 2010を元に作成)
5
The learner uses awareness of previous learning experiences and / or needs analysis activities to come to an excellent understanding of their needs and subsequent description of learning goals. And / or the strategies and materials chosen logically match these needs and show a clear focus. And / or the learner shows a willingness to reflect extensively, and refocus their needs if necessary and to choose strategies and materials according to their changing needs over time.
4
The learner uses awareness of previous learning experiences and / or needs analysis activities to come to a good understanding of their needs and subsequent description of learning goals although there is still some room for improvement. And / or the strategies and materials chosen are suitable for the learner to be able to develop. And / or the learner might be able to reflect and refocus their needs if necessary and to choose strategies and materials according to their changing needs over time, although may require some assistance with this from a learning advisor.
31
3
The learner uses awareness of previous learning experiences and / or needs analysis activities to come to an understanding of their needs, although this may take time or be a little unfocused. And / or the strategies and materials chosen are suitable for the learner to be able to develop. And / or the learner shows a limited ability to reflect and reluctance to refocus their needs and to choose strategies and materials according to their changing needs even if necessary and even with support from a learning advisor.
2
The learner struggles to reflect and focus on their needs and only sometimes selects strategies and materials appropriate for the learner to be able to develop. And / or the learner is unable to refocus their needs even with support from a learning advisor.
1
The planning of work is very haphazard. And / or the learner rarely selects strategies and materials appropriate for the learner to be able to develop. And / or the learner remains unaware of the need to refocus their needs even with guidance from a learning advisor. There is little if any evidence of reflection.
0 The planning of work is non-existent. And / or the learner doesn't select strategies and materials appropriate for the learner to be able to develop.
• 学生Aの期末自己評価
I think I would be around a 4. I can choose appropriate materials pretty well, but I tend to lean towards the easier material. I should always try to keep choosing hard, but not too difficult material, to learn from.
I feel pretty confident as I get better I can find and switch to better materials. I would like to start some N3 Kanji and reading if I am able to over the break. My listening has not yet caught up, but it is improving. Throughout the semester I practiced all N4 Kanji and am getting close to the end of the N4 level.
I have a pretty good idea of my needs because of my big goal of passing the JPLT N3. There are lists available of the Kanji used for the test, there are plenty of listening practice available, and N3 reading and grammar help is online. Using these resources will keep me on track to help pass the test.
Since we keep logs of what we have done, and we also get to review and grade other students logs we get a good idea of where we are. We can also see if our logs are too big or too small.
These reasons are why I think I am around a 4.
32
• 学生Bの期末自己評価
My problem is that I get stuck in a rut. I understand and recognize the need to change my learning studies, and oftentimes I do change what I do to learn, but sometimes I choose to stick with what is familiar, especially if the new one asks for me to change something like notes and such, which usually requires me re-writing things that I have already done. A case of laziness.
I however do try to learn from new things, and I do try to look back to see if things are working or not. Sometimes too the way that I have chosen to learn seems pretty unconventional but it works wonders for me, like my style of memorizing kanji, which consists of blocks of words written over and over and over. It might seem like a waste of paper but it works for me.
Being forced to stop and think about what work I have done, seeing if I achieved my goal or not, and seeing how the past work will affect what I need to study in the future is something that I need a little more of too. I do it sometimes but other times I am rushing to finish something, like finish half a book of notes or something, so I don't stop to reflect to see if it is working or not. If I did stop to think about what i need to I could maybe change the course of my studying before I waste my time taking the notes.
The nice thing though is that this class has helped me by giving me information about new ways to learn things. It does not tell me exactly how to do things, but it gives me a format. Therefore I am able to tailor the new learning idea to what I need.
Overall I think I am open to ideas, and I know what to do with the ideas, but I don't always actually DO the new things. That is my shortcoming.
I would rate myself a 3, 3.5.
33