英語専門講読2(Miyagawa and Saito)
Transcript of 英語専門講読2(Miyagawa and Saito)
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 1
英語専門講読Ⅱ(月曜4限) 担当:長南一豪(チョウナンカズヒデ)
授業の目標
1.日本語を知る。
2.英語で書かれた論文が読めるようになる。
3.言語学、とくに生成文法の考え方を学ぶ。
テキスト
Miyagawa, S. and Saito, M. (eds.) (2008) The Oxford Handbook of Japanese Linguistics, Oxford.
(プリント配布)
授業の進め方
予習:テキストの指定された部分を読み、プリントを穴埋めしておく。
授業:プリントに沿って質疑を行う。全訳はしない。質問歓迎。
復習:必ず前回部分を読み復習してから、次回の予習をすること。
※1回に進む範囲は 4ページ程度。穴埋め箇所にしぼって予習しておけばよい。
※休んだ場合は、プリントを「講義支援システム」から入手すること。
成績評価
期末テストに平常点(出席・授業参加)を加算する。
テストはすべて論述形式。約6問中2問を選択。テキスト・プリント・辞書持ち込み可。
(例)「日本語の○○についてどのような分析がなされているか、説明しなさい。」
参考文献
Tsujimura, N. (2007) An Introduction to Japanese Linguistics, 2nd edition, Blackwell.
Tsujimura, N. (ed.) (1999) The Handbook of Japanese Linguistics, Blackwell.
渡辺明 『生成文法』 東京大学出版会, 2009
長谷川信子 『生成日本語学入門』 大修館書店, 1999.
竹沢幸一・J. Whitman 『格と語順と統語構造』(日英語比較選書 9) 研究社, 1998.
西垣内泰介・石居康男 『英語から日本語を見る』(英語学モノグラフシリーズ 13)研究社, 2003.
岸本秀樹 『統語構造と文法関係』(日英語対照研究シリーズ 8) くろしお出版, 2005.
三原健一・平岩健 『新日本語の統語構造』 松柏社, 2006.
三原健一 『構造から見る日本語文法』 開拓社, 2008.
角田太作 『世界の言語と日本語』くろしお出版, 1991.(改訂版 2009)
Miyagawa, S. (2012) Case, Argument Structure, and Word Order, Routledge.
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 2
授業計画・内容
春学期
6.主格目的語構文
(1) 太郎が 本を 読む。
(2) 太郎が 本が 好きだ。
8.「が」「の」交替
(3) 私は 太郎が 来た 理由を 知っている。
(4) 私は 太郎の 来た 理由を 知っている。
10.日本語文法の獲得
(5) 黄色いの お花
(6) 絵美ちゃんが かいたの シンデレラ
秋学期
11.遊離数量詞
(7) 学生が 3人 研究室に 来た。
(8) 学生が 研究室に 3人 来た。
(9) 学生が 3人 本を 買った。
(10) * 学生が 本を 3人 買った。
12.動詞複合語
(11) 流れる(自) +落ちる (自) → 流れ落ちる
(12) 流れる(自) +落とす (他) → *流れ落とす
(13) 着る (他) +くずす (他) → 着くずす
(14) 着る (他) +くずれる(自) → 着くずれる
(15) 太郎が 着物を 着くずす。
(16) * 太郎が 着物を 着くずれる。
(17) 着物が 着くずれる。
3.「が」「は」と情報構造
(18) 太郎が 来た。
(19) 太郎は 来た。
(20) 雨が 降っている。
(21) (花子ではなく)太郎が 来た。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 3
11 遊離数量詞
(Floating Numeral Quantifier)
用語の確認
numeral quantifier base generate 基底生成する
stranding view 残置説 c-command
adverb view host NP ホスト名詞句
underlying structure VP-internal 動詞句内
11.1 はじめに
◎日本語の数量詞
・日本語の数量詞はさまざまな位置にあらわれる。
(1) a. 昨日 [3人の 歌手] が 歌った。
b. 昨日 [歌手 3人] が 歌った。
c. 歌手が 昨日 3人 歌った。
・この現象は長年注目を集めているが、とくに重要なものは次の問いである。
「(1c)の構文は統語的にどのように派生されるのか?」
・研究者たちは、(1a)と(1b)では数量詞と名詞句「歌手」は同一の名詞投射内にあることには同意する
が、(1c)に関しては意見が分かれている。
・この問題に関して、少なくとも2つの対立する説がある。
(ⅰ) 残置説
・(1c)の数量詞とホスト名詞句は で ていて、ホスト名詞句は数量詞を残して
構造の へ移動している。
・この説では、(1c)の数量詞は「遊離」していることになる。
(ⅱ) 副詞説
・(1c)の数量詞は、ちょうど副詞のように、動詞投射の として されている。
・この説では、(1c)の数量詞は遊離しているわけではなく、元位置に基底生成されている。
・本章では、どちらの説を採るかとは無関係に「遊離数量詞」(FNQ)という用語を用いることにする。
予習範囲(10/1):p.287~289
・遊離数量詞とはどんな現象か
・遊離数量詞に課される c統御条件とは何か?
英語にも日本語と同じように「遊離数量詞」が
存在するだろうか?
(ヒント)次の文を訳しなさい。
「生徒たちは全員来た」(現在完了を用いて)
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 4
◎語順に関する制約
・遊離数量詞にはよく知られた語順の制約がある。
と遊離数量詞は隣接する必要があるが、 と遊離数量詞は隣接する必要がない。
(2) a. * 学生が 本を 3人 買った。
a’. 学生が 3人 本を 買った。
b. 本を 学生が 3冊 買った。
・多くの研究者たちはこの制約を説明しようと試みてきた。その代表が Miyagawaの残置分析である。
しかし、残置説には数多くの反例があり、代案である副詞説が提案されている。
11.2 残置説とその統語的意味合い
・(1c)や(2b)のように、日本語の遊離数量詞は表層で 。
しかし、 というのは正しくない。
・遊離数量詞に関する分布的制約は、(2a)以外にも存在する。
◎c統御条件
・Miyagawaは、遊離数量詞の分布はある構造的条件によって原理づけられていると主張した。それは
条件である。彼は遊離数量詞は 場合に容認されない
ことを発見した。
(3) a. 友だちが 2人 新宿で 会った。
b. * 友だちが 新宿で 2人 会った。
・主語は動詞句外に生成され、「新宿で」が動詞句内にあると仮定すると、(3a)の構造は(4a)になる。こ
の構造で は を c 統御している。一方(3b)では、遊離数量詞が動詞句内
になければならないため(4b)となるが、この場合 は を c 統御していな
いので、非文法的となっている。
(4) a. S b. S
VP VP
・(3b)とは異なり(1c)は文法的である。それは、「昨日」のような時の副詞は VP外にあるためである。
c 統御:Xを支配する最初の枝分かれ節点がY
を支配する場合、XはYを c統御する。
(樹形図において、Xから1つ上がってその下
にYがあれば、XはYを c統御する)
‘vice versa’とはどういう意味?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 5
11 遊離数量詞 その2
(Floating Numeral Quantifier)
用語の確認
argument 項 passive
adjunct unaccusative verb 非対格動詞
trace unergative verb 非能格動詞
11.2 残置説とその統語的意味合い(続き)
◎相互 c統御条件
・Miyagawaはさらに、もう一つの方向の c統御も成り立たなければならないことを観察している。す
なわち、ホスト名詞句は 。(5)では、遊離数量詞は
ホスト名詞句を c統御しているが、ホスト名詞句「友
だち」は埋め込まれているため、
。
(5) * [友だちの 車]が 3人 故障した。
・Miyagawaは、遊離数量詞は(6)の相互 c統御条件を満たさなければならないと主張した。
(6) 相互 c統御条件:
◎項と付加部の区別
・Miyagawaはさらに、相互 c統御条件はよく知られた観察事実も説明することができることを示して
いる。それは、遊離数量詞は ではなく と関連づけなければならないということであ
る。具体的に言えば、 ・ ・Inoueの言う「擬似目的語」は遊離数量詞の先行詞
になることができるが、 は遊離数量詞のホストになることができない。
(7) a. 学生が 3人 本を 買った。
b. 花子が ペンを 3本 買った。
(8) a. * 学生たちは 車で 2台 来た。
・Miyagawaは、項と付加部には構造的な違いがあると主張する。
(7)の助詞は名詞句に小辞化されているが、(8)の助詞はそれ自身
の投射を持ち、名詞句は後置詞句内に埋め込まれている。
予習範囲(10/8):p.289~291
・遊離数量詞の相互 c統御条件とは何か?
・遊離数量詞が痕跡の証拠になるのはなぜか?
・「擬似目的語」とは、(7c)の「学生に会う」
のように、対格「を」ではないが目的語
のようにふるまう名詞句のこと。
(5)の樹形図
NP PP
NP P
本-を 車 で
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 6
◎移動の痕跡の証拠
・さらに重要なこととして、Miyagawaは、遊離数量詞は名詞句痕跡の証拠になると主張している。(9)
の例からわかるように、遊離数量詞は や の主語とは関連づけられるが、
の主語とは関連づけることができない。
(9) a. 車が どろぼうに 2台 盗まれた。
b. 学生が オフィスに 2人 来た。
c. * 子どもが ゲラゲラと 2人 笑った。
・Miyagawaの分析は、受身動詞と非対格動詞の主語は、非能格動詞の主語とは異なるというよく知ら
れた仮説に基づいている。それは、前者は として基底生成されるというものである。
・(9a,b)の主語は、目的語位置、すなわち動詞句内で遊離数量詞に隣接する位置に基底生成され、遊離
数量詞を残して へ移動すると仮定する。遊離数量詞の左に が存在する
と考えると、相互 c統御条件は満たされている。すなわち、 と
は互いに c 統御している。一方、非能格動詞の主語は(10b)のようにもともと動詞句外の位置にある。
この構造において ので、相互 c統御条件違反となる。
(10) a. 受身動詞(9a) b. 非能格動詞(9c)
NP1 VP NP1 VP
車が 子どもが
PP/Adv t1 FNQ V PP/Adv FNQ V
・Miyagawaの分析は、 は、動詞句内後置詞や副詞が間にある場合、遊離数量詞と関連
づけられないという事実からも支持される。
(11) ?* 子どもが このかぎで 2人 ドアを 開けた。
・まとめ:名詞句痕跡を仮定することで、Miyagawaによる遊離数量詞分析は、なぜ非対格動詞・受身
動詞の主語は VP内の遊離数量詞と関連づけられるが、非能格動詞・他動詞の主語は関連づけられな
いのかを説明できる。前者の主語は の項であるため、 位置に生成され、主語の
と遊離数量詞がたがいに c統御している。一方、後者の主語は の項であるため、
もともと目的語位置にあるわけではなく、相互 c統御条件を満たしていない。
・自動詞は一般に、非対格動詞と非能格動
詞に分類される。
非対格動詞は「物」が主語で状態変化を
あらわし、非能格動詞は「人」が主語で
動作をあらわす。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 7
11 遊離数量詞 その3
(Floating Numeral Quantifier)
用語の確認
mutual c-command requirement
unergative verb
locality restriction 局所性制約
PP (postpositional phrase)
(17) 遊離数量詞の分布的制約
構造的制約
a. * ホスト名詞句が埋め込まれた名詞句である (5)
b. * ホスト名詞句が後置詞句内の名詞句である (8)
局所的制約
c. * ホスト名詞句が外項であり、VP内の副詞/後置詞句がある (3)
d. * 主語 i-目的語-遊離数量詞 i (2)
11.3 論争
・前節では、残置説のもとでは、遊離数量詞のいくつかの分布的制約は、遊離数量詞とホスト名詞句の
依存関係に関する統語的な局所性制約に分類されることを見た。
・残置説は強力であるが、問題がないわけではない。
11.3.1 残置説に対する反例
・残置説は、遊離数量詞の分布が統語的に制約されているという観察によって支持されている。しかし
ながら、何人かの言語学者は、(17)の経験的一般化に反対している。
(Ⅰ) (18)(19)は、 にもかかわらず文法的である。
・(18)では、(5)と反対に、ホスト名詞句が 、遊離数量詞を c統御できない。
・(19)では、(8)と反対に、ホスト名詞句が 、遊離数量詞を c統御できない。
(18) a. 山田先生が [学生の 髪]を 3人 切った。
(19) a. 元旦に 教え子から 5人 年賀状を もらった。
予習範囲(10/15):p.293~296
・残置説に対する反例はどんな文か?
・残置説と副詞説にはどんな問題があるか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 8
(Ⅱ) にもかかわらず遊離数量詞が認可される例が存在する。
・(20)では、(9c)や(11)とは異なり、 の主語が遊離数量詞のホストであり、VP
内の修飾語が主語と遊離数量詞の間にある。
ので、残置説はこれらの例は非文法的であることを予測するはずである。
(20) b. 学生が 図書館で 5人 勉強していた。
c. 学生が ナイフで これまで に 2人 手を けがした。
(21) NP [VP PP/Adv [VP FNQ (O) V]]
・(22)は、目的語が という(2)の観察の反例になる。
(22) a. A:この新刊雑誌、売ってますか?
B:ええ、今朝も 学生が それを 5人 買っていきましたよ。
◎残置説 対 副詞説
・これらの反例は、残置説の妥当性に異議を唱える。とくに(20)と(22)は、遊離数量詞とホスト名詞句
の局所性条件に疑いを投げかけている。
・(20)の場合、 と言うこ
とができるかもしれない。そうすれば(20)では相互 c統御条件が満たされているだろう。しかし、(22)
では、理論に大きな修正をしない限り、 明白な方法は存在しないようであり、
主語 i-目的語-遊離数量詞 i語順が(少なくともある場合に)容認可能であるという事実は、残置説
にとって依然として問題である。
・(22)の反例を提示した研究者は、 必要がない
と主張し、残置説の代わりとなる分析を提案している。その主要なものは副詞説であり、遊離数量詞
はホスト名詞句との局所的関係を持つ必要がない VP(または V’)副詞であるとする。
・残置説と副詞説は、局所性に関して異なる予測をする。残置説では、遊離数量詞とホスト名詞句が
ことを予測する(*主語 i-目的語-遊離数量詞 iは不可)。一方、副詞説は、
それらが ことを予測する(主語 i-目的語-遊離数量詞 iは可能)。
・経験的には、主語 i-目的語-遊離数量詞 iはある場合に可能であり、ある場合には不可能である。し
たがって、我々がどちらの説を採用したとしても、(23)の問題に直面する。
(23) a. 残置説のもとでは、 ?
b. 副詞説のもとでは、 ?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 9
11 遊離数量詞 その4
(Floating Numeral Quantifier)
用語の確認
scramble hybrid view 雑種説
prosody 韻律 distributive 分配的
stress locality
11.3.2 局所性の再考
・主語 i-目的語-遊離数量詞 iが可能であるような(22)の反例を提示した研究者たちは、遊離数量詞と
ホスト名詞句の間には と結論づけ、残置説を否定している。一
方、(22)の例は と考える必要はないと主張する研究者もいる。すなわち、た
とえ(22)のような例が存在しても、残置説を維持することは可能である。
11.3.2.1 残置説
・Miyagawa and Arikawaは(22)の例を認めながらも、これらの例は局所性に対する反例にはならない
と主張する。彼らは、(22)の文は非文法的な主語 i-目的語-遊離数量詞 iとは異なる構造と関連づけ
られるので、統語的局所性は維持されていると言う。
(24) a. * 学生が 酒を 3人 飲んだ。
b. ? 学生が 酒を 今までに 3人 飲んだ。
・Miyagawa and Arikawaは、この2つは構造的に異なっており、その違いは
と主張する。(24a)は中立的な抑揚を持ち、遊離数量詞と先行する目的語は同じ抑揚句で発音される。
一方、(24b)は 、遊離数量詞が目的語と句として分離している
ことを標示している。
・Miyagawa and Arikawaは、(24b)でも局所性は保持されていると主張する。具体的に言えば、日本
語の主語は 、(24b)は(25)のように派生されると主張する。
・この派生において、 は満たされており、局所性の違反はない。したがって、(24b)
の例は残置説に対する反例とは考えない。
(25) [TP S1 [TP O2 [vP t’2 [NumP t1 FNQ] [VP t2 V]]]]
予習範囲(10/22):p.296~299
・残置説は局所性の反例をどう説明するか?
・Ishiiの「雑種説」とはどのようなものか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 10
11.3.2.2 「雑種」説
・Ishii は、主語 i-目的語-遊離数量詞 i の複雑な容認性は、2種類の数量詞が存在するためであると
主張する。主語 i-目的語-遊離数量詞 iが容認不可能である場合、その文は
を含んでおり、 ことを予測する。一方、主語 i-目的語-遊離
数量詞 iが容認可能である場合、遊離数量詞は であり、
ことを予測する。
・ここで重要な役割を果たしているのは、 解釈と 解釈の区別である。Kuroda に
よれば、分配的解釈は を意味し、非分配的解釈は
を意味する。(27)ではこの2つの解釈が、「 」(分配のみ)および「 」
(非分配のみ)という時間表現によって強制されている。
(27) a. この一週間の間に 囚人が 3人 逃げ出した。
b. その時 突然 囚人が 3人 暴れ出した。
・Ishii は、相互 c 統御条件に対する反例は が可能だが は不可能であると主
張する。Ishiiによれば、(22a)の文は「 」という意味(分
配)は可能だが、「 」という意味(非分配)は不可能である。
・Ishiiの主張は、(28)によってさらに支持される。
(28) A: この雑誌 人気ありますか?
B:*ええ、さっきも そこで 学生さんが 最新号を 5人 奪い合っていましたよ。
B’: ええ、さっきも そこで 学生さんが 5人 最新号を 奪い合っていましたよ。
・(28B)が示すように、この文は相互 c 統御条件に違反している場合は容認不可能であるが、局所性違
反がなければ容認可能である。このことから Ishiiは、2種類の遊離数量詞、すなわち と
が存在すると主張する。残置型にはいかなる意味制約もないが、
。副詞型は という意味制約によって確認される。この
種の遊離数量詞は副詞であるので、 。
・まとめ:残置説は厳しい局所性条件に従う必要があるので、(22)のような反例が問題となる。雑種説
では、主語 i-目的語-遊離数量詞 iが不可能である場合、遊離数量詞は によって派生し、局
所性制約が存在する。一方、主語 i-目的語-遊離数量詞 iが可能である場合、遊離数量詞は で
あり、局所性制約は存在しない。(22)の反例は局所性に対する真の反例ではなく、単に異なる種類の
遊離数量詞、すなわち副詞型を含んでいるだけである。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 11
11 遊離数量詞 その5
(Floating Numeral Quantifier)
用語の確認
pragmatic 語用論(的) emphatic particle 焦点助詞
new information 新情報 aspectual 時相的
indefinite NP 不定名詞句 delimitedness 限定性(完結性)
11.3.4 副詞説
・Miyagawaの残置説は、遊離数量詞の局所性条件に合致する分布制約をうまく説明する。しかし、局
所性に対する反例が存在する。Miyagawa and Arikawaや Ishiiは修正案を提示したが、やはり十分
ではない。そこで、何人かの学者は副詞説を提唱する。副詞説では局所性は重要な役割を果たさない
ので、なぜ主語 i-目的語-遊離数量詞 iはある場合に容認不可能なのかを説明する必要がある。
11.3.4.1 語用論的考慮
・Takami は局所性に対する反例に基づき、Miyagawa の残置分析を否定する。彼の分析の要点は、遊
離数量詞の分布は統語的要因によるのではなく、 によるというものである。
・日本語では、もっとも重要な情報(すなわち新情報)は
と主張されている。Takamiは、遊離数量詞はこの情報構造に従うと主張する。
(38) a. ?* 学生が 本を 4人 買った。
b. 学生が {それ/その本}を 4人 買った。
・(38a,b)では、遊離数量詞は として解釈され、動詞の前に置かれている。こ
の2つの容認可能性の違いは、目的語の情報資格から来ている。
・(38a)では、目的語は であり、 を持つと解釈される。したがって、目的語と
遊離数量詞は、 ということに関して矛盾がある。(38b)では、目的語
は であり、それほど重要な情報を持たない。したがって、最適な情報構造が維持される。
・さらに Takamiは、主語 i-目的語-遊離数量詞 i語順は、遊離数量詞の後に「 」「 」
のような焦点助詞がくる場合には容認可能であることを観察する。焦点助詞は、遊離数量詞がもっと
も重要な情報を持つ合図であるので、文は最適な情報構造を具現化している。
(39) 学生が レポートを 3人だけ 提出した。
予習範囲(10/29):p.302~305
・Takamiの「語用論」はどのようなものか?
・Takami分析にはどんな問題があるか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 12
・(22b=40)の場合、目的語「家」は予測可能な情報であるので、動詞の前に置く必要がない。
(40) 僕は アパート住まいだけど、最近 同僚が 家を 4、5人 次々と 建てた。
・Takami 分析は、(41)のように、動詞が非能格動詞で動詞句内副詞が主語と遊離数量詞の間にあるよ
うな場合も説明できると主張する。(41a)の「ゲラゲラと」は ので、
が、「舞台で」のような場所や時の副詞は「場面設定」として機
能し、 ので、遊離数量詞が動詞の前にくることが可能になる。
(41) a. * 子どもが ゲラゲラと 2人 笑った。
b. 子どもが 舞台で 10人 踊った。
・以上のように、Takami 分析は主語 i-目的語-遊離数量詞 iや外項が遊離数量詞のホストである場合
の複雑な判断を説明する。しかし、この分析にも問題がないわけではない。(42)では、Takami 分析
では「 」は「ゲラゲラと」と同様に重要な新情報を持つはずであるが、(41a)と(42)の容認
可能性は異なっている。さらに、「適切な」情報構造の決定は、必ずしも直接的ではない。遊離数量
詞は新情報を持つと同時に、他の要素も新情報をあらわしている。したがって、問題は
ということである。
(42) 学生が ナイフで これまでに 2人 ケガした。
11.3.4.2 時相的考慮
・Mihara は、Takami の語用論条件は不十分であり、遊離数量詞は時相的限定性(完結性)も必要と
すると主張する。具体的に言うと、遊離数量詞を持つ文は をあらわさなければな
らず、遊離数量詞はその状況の結果の数え上げと結びつけられなければならない。
・(22)について、「今朝も」のような時の副詞がないと文は悪く聞こえるが、それらの副詞は、描写され
ている状況のもとでの当該の数え上げが完結していることを合図している。
(43) a. 外国人観光客が 去年 徳島を 五千人 訪れた。
・「だけ」「とも」のような焦点副詞があれば、文が時相的に完結する。
・非対格動詞・非能格動詞の違いについては、非対格動詞は内在的に時相的に完結しているが、非能格
動詞は意味的に完結していないためである。非能格動詞が遊離数量詞とともにあらわれる場合には、
(45b)のように時相的に限定する表現が必要である。
(45) a. ?? 学生が 図書館で 30人 勉強した。
b. 閉館間際まで 学生が 図書館で 30人 勉強した。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 13
12 動詞複合語
(V-V Compounds)
用語の確認
compound 複合語 agent 動作主
lexical 語彙的 honorification
syntactic biclausal 複文
head 主要部 accusative
argument dative 与格
12.1 はじめに
・言語理論における形態論の位置は、長年論争となっている。かつては統語論が語形成の唯一の仕組み
であるとされていたが、Chomsky(1970)が「語彙論者仮説」を提案し、「語彙主義」が 80年代中ごろ
まで主流となった。Baker(1988)が転換点となり、語形成の統語的研究法が復活する。Halle and
Marantz(1993)による分散形態論の出現は、この傾向に拍車を掛けている。
・日本語の複合述語はさまざまな扱いを受けてきた。初期の Kuroda(1965), Kuno(1973)は統語的方法
で分析した。Miyagawa(1980)らはレキシコンで形成されると考えた。Kageyama(1989)はレキシコ
ン・統語の両方で作られると提案した。分散形態論を適用した研究には Nishiyama(1998)がある。
・本章では、動詞複合語に関する3つの語彙的分析(Kageyama, Li, Fukushima)と1つの統語的分析
(Nishiyama)を取り上げ、それぞれの特徴と問題点を考察する。
12.2 中心となるデータ
(1) a. ジョンが 着物を 着くずした。
b. * ジョンが 着物を 着くずれた。
c. 着物が 着くずれた。
d. ジョンは いつも かばんを 持ち歩く。
・(1a)は の組み合わせで、この型が一般的である。(1b)のように V2が の
場合、この複合語は 。(1c)のように複合語全体が自動詞として機能する
のであれば、文法的である。(1c)で注目すべきことは、自動詞である V1 の がこの文に具
現化されていない点である。(1d)は異なる型をもつ他の種類の他動詞-自動詞の組み合わせで、この
場合は 。
予習範囲(11/12):p.321~324
・動詞複合語にはどのような問題があるか?
・「語彙的複合語」とは何か?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 14
12.3 問題と論争
12.3.1 前置き
12.3.1.1 相複合語と心理複合語
・多くの研究者は、(1)のような複合語に「 」動詞複合語という用語を用いる。この用語は、
別の種類の複合語、すなわち「 」動詞複合語が存在することを含意している。
(2) a. ジョンが ビルを 押し倒した。
b. ジョンが 走り始めた。
c. ジョンが 本を 読み飽きた。
・(2a)は(1)と同様の で、(2b,c)は Kageyama が と呼ぶものである。
(2b,c)では、V2は相または心理をあらわしている。これらの例は 構造を持つと考えるのが妥
当であり、英語の 、 に対応し
ている。同様の構造は(2a)にはあてはまらないようだ。Kageyamaは(2a)と(2b,c)の違いを示している。
・たとえば、 。
(3) a. ジョンが 走り始めて、ビルも [そうし] 始めた。
b. * メアリが スーザンを 押し倒して、ジョンも ビルを [そうし] 始めた。
・他の違いは尊敬化に関するものである。
(4) a. お-走り-になり-始める b. お-走り始め-になる
c. * お-押し-になり-倒す d. お-押し倒し-になる
・(4a,b)が示すように、相複合語は 。
しかし(4c,d)では、 。
・このような違いに基づき、Kageyama は(2b,c)の複合語は統語で形成され、(2a)はレキシコンで形成
されると提案した。以下では、(2a)のような「語彙的」複合語を中心に考察する。
12.3.1.2 主要部性
・日本語の動詞複合語では という研究者間の一般的同意がある。
これは当初、形態論における右側主要部の普遍性から動機づけられた。他の証拠は格形式である。
(5) ジョンが メアリ-に/*を 追いついた。
・それ自体では、「追い」は 目的語、「つい」は 目的語をとる。この2つが組み合わさ
り複合語になると目的語は 標識をとる。これは格形式において V2が優先されることを示す。
・格に加えて、他動性や項の具現化も主要部に強く影響される。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 15
12 動詞複合語 その2
(V-V Compounds)
用語の確認
argument structure θ-role 主題役割
transitive back-formation 逆形成
unaccusative inherit 継承する
12.3.2 語彙的分析
・本節では 3つの語彙的説明を振り返る。Kageyamaと Liは共通の特性を持つので一緒に議論する。
12.3.2.1 Kageyama 1993と Li 1993
・Kageyamaと Liは、複合語を作り出す語彙過程として「 」を提案した。
(6) a. ジョンが ビルを 押し倒した。
b. 同定
「押す」(θ1(動作主), θ2(主題))+倒す(θ1(動作主), θ2(主題))
同定
→「押し倒す」(θ1(動作主), θ2(主題))
・この合成の過程において、2つの動詞の卓越した主題役割どうし、および卓越していない主題役割ど
うしが同定される。結果として、 を持つ ができる。
・次に、 の組み合わせを見てみよう。
(1) b. * ジョンが 着物を 着くずれた。
c. 着物が 着くずれた。
・Kageyama は(1b)を、 制約によって不可能と
する。(1c)を可能にするため、Kageyama は(1a)の対応する他動詞-他動詞からの によっ
て派生されると提案する。すなわち(1c)は他動詞と非対格動詞が直接合成して派生するのではなく、
対応する他動詞-他動詞からの脱他動化によって派生する。
・しかし逆形成には問題がある。
(7) 工場が 汚水を たれ流す。
・(7)は の組み合わせである。Kageyamaはこれを逆形成によって派生させるだ
ろう。しかし(7)は逆形成によって派生されることはできない。なぜならば、(7)の組み合わせにはも
予習範囲(11/19):p.324~327
・Kageyamaの項構造合成とはどのようなものか?
・Kageyama分析にはどんな問題点があるか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 16
とになる あるいは の組み合わせは存在しないから
である。(「*たれ流れる」「*たらし流す」)。
・Liは(1b)を、主要部のもっとも卓越した項は、
制約によって不可能とする。(1b)における非対格動詞 V2 のもっとも卓越し
た項(主題)は、複合語の を割り当てられているので、この制約に違反している。(1a)の
他動詞-他動詞の組では、V2 のもっとも卓越した項(動作主)は、複合語の を割り当て
られており、この制約に従っている。しかし、Liは(1c)がどのようにして可能なのかを論じていない。
・主要部性について、Liが V1が日本語複合動詞の主要部であると仮定する理由は、以下である。
(8) * ジョンが メアリを 踊り飽きた。
・V1が複合動詞の主要部であるという仮定のもとで、Liは卓越性制約によって(8)を不可能とする。な
ぜなら、V1のもっとも卓越した項が文の を割り当てられていないからである。
・12.2節で、 の組み合わせを持つ他の型が存在することを見た。
(9) a. ジョンは いつも かばんを 持ち歩く。
b. ジョンが 子どもを 連れ去った。
・(9)の特別な性質は、複合動詞の目的語はもともと である点である。V2 は自
動詞で目的語をとらない。すなわち、目的語の は存在しない。
・Kageyamaによると、(9a)は以下のように作られる。
(10) V1(動作主, 主題)+V2(動作主)→V-V(動作主, 主題)
同定
・ここでは V1 と V2 の動作主役割が同定され、 。主題に関して
は、項の継承は通常 V2で起こるものの、(10)の V2は主題を持たない。そのため、V1の主題項が複
合語に継承可能である。しかし、(9b)の複合語が項構造合成によって作られるのは不可能である。な
ぜなら、Kageyamaによれば V2「去る」は非対格動詞であり、唯一項は主題であるからである。
・Kageyama は、(9b)の複合語は項構造ではなく語彙概念構造によって作られると仮定する。しかし、
複合語が項構造によって作られるか、それとも語彙概念構造で作られるかを予測するような原理的な
方法はないと思われる。
12.3.2.2 Fukushima 2005
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 17
12 動詞複合語 その3
(V-V Compounds)
用語の確認
serial verb 連続動詞 agent 動作主
inactive 不活性 external argument 外項
control コントロールする c-select 範疇選択する
12.3.3 統語的分析:Nishiyama 1998a
・語彙的分析と対照的に、Nishiyamaは動詞複合語に対する統語的説明を提案している。この最初の動
機は、動詞複合語と通言語的に広く知られている との並行性である。
・Collins による連続動詞構文の分析を日本語の動詞複合語に拡張して、Nishiyama は(22a)は(22b)の
ように分析されると提案している。
(22) a. ジョンが ビルを 押し倒した。 b. vP NP v’ VP v NP V’ i VP V NP V PRO i
・ (非対格動詞)の組み合わせは、以下のように分析される。
(1) b. * ジョンが 着物を 着くずれた。
c. 着物が 着くずれた。 (23) vP VP v(不活性) NP V’ i VP V2 NP V1 PRO i
予習範囲(11/26):p.331~335
・Nishiyamaの統語的分析はどのようなものか?
・Nishiyamaの仮定する vとは何か?
・各動詞は内項の役割( )のみを付与し、外項の
役割( )は別の主要部 vによって付与される。
・内項の役割の項共有は によって行われ、
複合化は主要部移動による。
・vは で、外項を導入しない。
・vと VPの間には選択制限があり、不活性な vは非対格動
詞が主要部である VPを選択する。
・表層の主語は非対格動詞の であり、主
節 VPの指定部に生成される。
・V1は他動詞であるが、埋め込まれた VP内に は
ない。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 18
・(19)の例も同様に説明される。
(19) a. (太郎の) ほほが 泣き濡れた。
・他動詞-非対格動詞の組み合わせの鏡像として、非対格動詞-他動詞の組み合わせも存在する。
(24) ジョンが スープを ふきこぼした。
・Nishiyama分析では、(24)は(22b)の他動詞-他動詞の組み合わせとほぼ同じ構造を持つ。活性的な v
は V2 として他動詞 VP を選択するが、他動詞 V2 が V1 として他動詞を選択するという条件はなく、
他動詞 V2は V1として非対格動詞 VPを自由に選択できる。
・二重目的動詞の場合(25)
・次に(9a)を考えよう。(p.334)
(9) a. ジョンは いつも かばんを 持ち歩く。
・この例では はなく、 は明示的に具現化されている。
・この明示的目的語が格が必要であるとすれば、Burzio の一般化により埋め込み節に外項が存在する。
Nishiyamaは移動動詞は以下のように vPを範疇選択すると仮定する。 (29) vP NP v’ i VP v(活性) vP V NP v’ PRO i VP v(活性) VP V
・この分析は基本的に(9b)の「連れ去る」にも拡張できる。
・(22b),(23)で見たように、VP 補部化が Nishiyama 分析における他の型の組み合わせに重要である。
したがって、(29)のような vP の選択は何らかの形で制約されていなければならない。Nishiyama で
は、これは のみが vP を範疇選択すると仮定されている。Fukushima はこれに反論し、
「倒れる」は「去る」と同様に移動動詞であるのに、V1が自動詞の場合 V2にならないと主張する。
(30) a. ジョンが ビルを 押し倒した。
b. * ジョンが メアリを 押し倒れた。
・しかし「場所の変化」という概念で「移動動詞」を定義すれば、(9)は説明できるかもしれない。
・ジョンは活性的な vによって導入される動作主であ
る。
・これは PROをコントロールしている。PROは埋め
込み節の である。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 19
12 動詞複合語 その4
(V-V Compounds)
用語の確認
Distribured Morphology 分散形態論 root 語根
categorially neutral 範疇的に中立(な) merge 併合(する)
functional head 機能的主要部 compositional 合成的
12.3.4 複雑で予測されない場合
・これまで、動詞の組み合わせと項の具現化が直接的である場合を見た。各分析は独自の仕組みと仮定
を用いているが、議論されているデータは「体系的」で、文法によって生成されているようだ。
・本節ではもっと例外的な場合を考察する。一般に特異性はレキシコンの特質であると考えられている
が、形態論に対する統語的分析法は特異性をどのように扱うのかを見ることにする。
12.3.4.1 特異性と分散形態論
12.3.4.1.1 非合成性
・以下の例は、 複合語を示している。
(31) a. 落ち着く 落ちる-着く(自)
b. 叱りつける 叱る-つける(他)
c. 取り締まる 取る-締まる(自)
・(31a)は、各動詞の本来の意味は 、複合語は全体として新たな意味になっている。(31b)
では、V1「叱る」は本来の意味を保持しているが、V2 の意味的寄与は修飾に限定されているようで
ある。このようなずれは(31c)ではさらに進み、新たな意味に加えて奇妙な主題関係も持っている。
V2は本来 であるのに複合語全体は であり、右側主要部性に違反している。
・従来、このような非合成的複合語はレキシコンで作られるとされてきた。しかし、近年の分散形態論
は、レキシコンを語形成の場と考えることを破棄している。
・Volpe は、派生形態論に関して、Marantz の提案する分散形態論によって分析することを提案する。
Marantzによると、語根は 、v, n, aといった機能的主要部によって選択され
ることで範疇的資格を得る。
(32) a. compárable b. cómparable
c. separatable d. separable
予習範囲(12/3):p.335~339
・ 分散形態論とはどのような考え方か?
・comparableの 2つの意味はどう説明されるか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 20
・Aronoffによると、compárableや separatableは対応する動詞 , の意味に対し
て透明であるが、cómparable や separable は 。すなわち、
compárableは「 」だが、cómparableは「 」という意味である。
Volpeは、このことは以下のように説明されると提案する。
(33) a. compárable b. cómparable
a compáre a √compar- -able -able v √compar-
・(33a)では compárableは機能的主要部 vを含んでおり、それによってこの語が の点で
なぜ動詞 compare に似ているのかが説明される。一方(33b)には v 節点はなく、それによってなぜ
cómparableが が説明される。Volpeによると、語根はそれ自体では解
釈不可能であり、それが機能的主要部に選択された時に意味が固定される。
・この考え方を(30)の動詞複合語における特異性の派生にも適用しよう。(30a)は直接的な例であるが、
[vP [VP V1 V2] v] という構造において、意味は 。したがって
動詞の本来の意味にかかわらず、新しく作られた複合語は新たな意味を持つ。
12.3.4.1.2 名詞化
・Fukushimaは派生形態論の観点から動詞複合語の興味深い特性を述べている。
としてのみあらわれることができる複合語が存在する。
(34) a. 立ち食い b. 押し売り
・各形態素はそれ自体では動詞であることが可能だが、上の複合語は対応する動詞を持たない。すなわ
ち、「* 」「* 」は存在しない。Fukushima は、このことは動詞複合語に対
する統語的分析の問題点であると主張している。
・この「範疇中立的としての語根」分析では、レキシコンにおいて「名詞化」過程は存在せず、いわゆ
る派生名詞が本来動詞であるという必要はない。
(35) a. He hammered the nail with a rock.
(訳)
b. * She taped the picture to the wall with pushpins.
(訳)
・動詞 hammerは対応する名詞とは別個の付加部を認可するが、動詞 tapeは認可しない。これは、動
詞 hammerは名詞 hammerを含まないが、動詞 tapeは名詞 tapeを含んでいるためと考えられる。
・「寒さ」(名詞)や「寒がる」(動詞)
は「寒い」という形容詞から作られる
のだろうか、それとも範疇的に中立な
「√寒」から作られるのだろうか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 21
3 「は」「が」と情報構造
用語の確認
theme 主題 predicate
contrast 対照 subordinate clause
neutral description 中立叙述 stage-level 場面レベル
exhaustive listing 総記 individual-level 個体レベル
3.1 はじめに
・Kuno は以下のように述べている。「『は』と『が』の意味の違いには、日本語の学習者と教育者の双
方が常に悩まされている」悩まされている者のリストには、理論言語学者も加えることができる。
3.2 中心となるデータ
3.2.1 主題の「は」と対照の「は」
・Kunoによると、「は」と「が」の2つずつの用法は以下のように区別される。
(1) a. 文の の「は」 ジョンは 学生です。
b. の「は」 ジョンが パイは 食べたが...
c. 行為や一時的状態の の「が」 雨が 降っている。
d. の「が」 ジョンが 学生です。
・「主題」の「は」は、プラハ学派の言う文の「主題」を表していると考えて、Kunoはこのように名付
けた。この用法では、「は」はいかなる対照の意味も持たない。したがって、今後は「非対照」の「は」
と呼ぶことにする。
・(1a)の文は、 を伝えるために用いられ、他の個体の特性に関する含意はない。
しかし対照の「は」は、談話モデルにおいて を生み出している。
(2) a. 誰が パーティに 来たか?
b. ジョンは 来た。 (含意:他の人については不明)
c. ジョンが 来た。 (完全な返答)
・(2b)の大文字(プリントでは太字)は を示している。
Kunoによれば、「は」の対照読みはつねに と関連するが、非対照の「は」句には
それはない。
予習範囲(12/10):p.54~57
・「は」の2つの意味とはどのようなものか?
・「が」の2つの意味とはどのようなものか?
・以下の違いはどのように説明すれ
ばよいだろうか?
a. 誰が 来ましたか?
b. *誰は 来ましたか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 22
・対照の「は」は、非対照の「は」よりも分布が自由である。
3.2.1.1 節の種類
・一般に、非対照の「は」は「根現象」である。これは、「言う」や「知っている」のようなある種の
動詞補部を除き、 という意味である。
・(3a)の「森さん」は「知っている」に埋め込まれており、対照の解釈である必要はないが、(3b)は埋
め込み動詞は「残念に思う」であり、対照に解釈される。
(3) a. ジョンは 森さんは トヨタの社員であることを 知っている。
b. ジョンは 森さんは トヨタの平社員であることを 残念に思う。
・Kurodaの一般化は、非対照の「は」は「提題」の文脈においてのみあらわれるとする。Hojiは、橋
渡し動詞の補部に言及している。しかし、どのような場合に「非対照」の「は」が可能であるかに関
する詳細な一覧は、まだ明らかでないようだ。
・対照の「は」は、すべてではないが、広い範囲の従属節において可能である。
3.2.1.2 繰り返し
・Kuno によると、非対照の「は」は 、したがって多くても一つし
か含むことができない。しかし、対照の「は」は繰り返すことができる。さらに、非対照の「は」は
なければならないが、対照の「は」は節内部に可能である。したがって、以下の例で
は、最初の「は」句のみが である。
(4) 私は たばこは 吸いますが 酒は 飲みません。
・しかし、非対照の「は」は本当に唯一でなければならないかに関しては議論がある。Kuroda は、繰
り返すことができるというのがすべての「は」句の基本的特性であるとしている。
(5) パリでは 正夫は エッフェル塔と ノートルダムの塔に 登った。
・ここで「は」句が の付加部と であることは偶然
ではない。主語と場面設定的な副詞は非対照読みになりやすいが、
他の項の「は」標示は対照読みが強く好まれる。この事実は広く
知られているものの、まだ十分な説明は与えられていない。
3.2.1.3 移動
・Saitoは、先頭に「は」句を持つ文は派生と2つの可能性があると主張する。すなわち、「は」句は痕
跡を残して文の先頭位置に移動したか、あるいは先頭位置に生成されたもののいずれかである。Hoji
は、移動した「は」句は対照解釈を持ち、移動していない場合は非対照であると主張している。
・(5)を以下のように変えると、どん
な意味になるだろうか?
(5)’ パリでは 正夫は エッフェ
ル塔は 登った。
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 23
3 「は」「が」と情報構造 その2
用語の確認
neutral description unaccusative verb 非対格動詞
exhaustive listing unergative verb
focus 焦点 stage-level
new information 新情報 individual-level
3.2.2 総記の「が」と中立叙述の「が」
3.2.2.1 相互関係と述語の種類
・Kurodaは「が」はある場合に「総記」の読みになることを指摘したが、この読みと
には相互関係がある。主節では、 レベル述語の「が」標示された主語は総記と中立叙述読み
のいずれかになるが、 レベル述語の「が」標示された主語は 読みのみを持つ。
(6) a. ジョンが 来た。 (総記・中立叙述)
b. ジョンが 学生です。 (総記)
3.2.2.2 節の種類
3.3 問題と分析
・前節で議論されたさまざまなデータから、いくつかの疑問が生じる。第一に、「が」と「は」の解釈
の特徴はともに 。これは還元できない事実だろうか、それともそれぞれの場合にお
ける異なる用法や解釈には何らかの があるのだろうか? 第二に、これらの特
徴は「総記」や「主題」という概念を用いているが、どのように定義されるのか?
3.3.1 「が」と焦点
・「が」句の 読みは、その構成素のせまい と同じものと考えるべきであると広く仮定
されてきた。「焦点」は文献では広い範囲の意味で用いられている。ここでは、おおよそ、発話の
部分という意味で用いることにする。「題述」とも呼ばれる。
・焦点的な構成素の指示物は本文的に新しいものである必要はないことに注意することが重要である。
(7B)の を焦点として分析することに矛盾はない。
(7) A: Who did your parents contact?
B: My mother phoned ME, of course.
予習範囲(12/17):p.57~61
・「が」の2つの意味はどのようなものか?
・総記の「が」と英語の焦点はどんな関係にあるか?
2012秋 専門講読月 4 CHONAN 24
・典型的な質問-回答の組では、回答の焦点は質問における に対応する部分である。
(8) c. A: What were you reading?
B: I was reading [F a great novel by YOSHIMOTO].
d. A: Who is the author of the novel you were reading?
B: I was reading a great novel by [F YOSHIMOTO].
・(8)の例は、英語の焦点は高アクセントを持つ要素から「投射」することが可能であるという事実を示
している。Bの文の焦点が YOSHIMOTOであるか、それともいくつかのもっと大きな構成素である
かは、文脈のみで決まる。
・「が」の総記と中立叙述の区別を再記述する一つの可能な方法は、「が」は 標識であるという
ことである。焦点の投射は、ある方法で に影響される。これは Diesingによって提案
されたが、彼女は日本語の「中立叙述」の「が」の分布は英語の主語からの焦点投射の分布と同じで
あることを観察し、それは 動詞と レベル述語の主語に制限されていると主張する。
・したがって、(10)は主語の 焦点の解釈のみが可能であるが、(11)は 焦点で解釈する
ことが可能であり、その結果文全体が となる。
(10) b. [F The EMPEROR] was playing pool.
(11) b. [F [F The EMPEROR] arrived].
・Diesingの主張によると、この例は Kunoの例と同じ現象を示している。
(12) a. [F ジョンが] 学生です。 (総記)
b. [F [F ジョンが] 来た]。 (中立叙述/総記)
・Diesing の提案は、焦点は外項主語位置( 動詞・ 動詞・ レベル述語の主語
位置)からは投射されることはできないが、 動詞・ レベル述語の主語はもともと
動詞句内の低い位置にあるというものであった。このような構造的違いによって、述語の種類による
「が」の異なる読みの相互関係が説明される。
・しかしながら、「が」の総記読みがせまい焦点の例であることは、「が」それ自体が焦点標識であると
いうことにはならない。「が」を焦点標識として分析することには、よく知られた問題点がある。第
一に、「が」は主語以外の構成素には生じない。第二に、節の種類との関係は英語と同じでない。
・Heycockは、「が」標識と情報構造のもっと弱い関係を提案している。そこでは、「が」は、間接的・
否定的な意味を除いて情報的資格を持たない。すなわち、「が」で標示される主語は、「は」では標示
されないということである。



































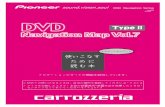






![大坂城本丸の能舞台をイエズス会日本報告の原本から読み解く [Reading Hideyoshi’s Noh Stage at Osaka Castle from the Original Jesuit Japan Letters]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322f4bd61d7e169b00cdc70/-1677550357.jpg)


