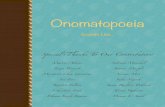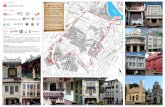文喜 E - J-Stage
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 文喜 E - J-Stage
源テ中全平1 国成
4司'>- 講師
氏マ古李 12/¥ 物 文喜E平成
日 神
百ぷ女白仁』1
聖,て同cとa、
三口は口五 学吏回
12 本 'し、なrJ" ~~ 学I>: 年 女 戸 女 社女
10 月
子 大 大子子 子 ぜ 秋大 大 大14 学 学 山子L 学 学 読 季dEE3 h 日
後 野 久 原 牒 ま 同z 藤 口 保 岡 谷れ 大
女 る JzEz h
子 祥 武 田 文 の シ大 ン子- 子 彦 淳 子 寿 カh ポ
芦原平
学代文童近世中 平 歴 ジ
安 世 安 ウ
講堂文 文 文
史 ム学 月ヴー 円子己 学
¥/
寿
資料1
〈平安朝の時空から〉
『源氏物語』の時代と社会
同志社女子大学
慌
谷
嵯峨源氏
『新撰姓氏録」の源朝臣の項をみると、「源朝臣信、年六晴
間」を官頭に、弘・常(四歳)、明(二歳)、貞姫・潔姫(六
歳)、全姫(四歳)、善姫(二歳)の弟妹たちを挙げ、「信ら
八人、これ今上の親王なり。市して弘仁五年五月八日勅によ
り姓を賜い、左京一条一坊に貫す。すなわち信をもって戸主
となす」とある。ここにいう弘仁五年(八一四)五月八日の
詔勅は『類衆三一代格』(巻十七。なお同文が『河海抄」に引
く「日本後紀』逸文にもみえる)に所収されており、いまそ
のなかから賜姓の理由、方法などを語っている部分を抽出す
れば、
-1-
お
お
ま
・:男女、やや衆し。未だ子の道を識らずして、還た人
かた
Uけ
な
ふ
う
い
ん
か
さ
の父と為せり。辱くも封巴(封地)を累ね、空しく府
お
も
い
た
庫を費す。朕、懐い傷む。親王の号を除き朝臣の姓を賜
あまね
い、編く同籍と為し、公に従事し、出身の初は一に六位
に叙せんと思う。ただ前に親王を号すは更に改むべから
ず。同母後産も猶また列を一にす:・(
『清和源氏」教育社)
桓 50
武
よL 璽
f工工源内 正仁 54 順
融聖子 ;JJ U159事tT聖字丁多重量事
(醍60 穏辛宝{三醐丁子
村62 朱61 保 ι上雀主碗一事
女 康理理
明方延ア「為時室
一寸紫式部母
清原元輔ー凡少納言
一一1理
能
藤原倫寧|下女道綱母、婿姶日記作者
丁女菅原孝標室、更級日記作者の母
「女J
1
8
女義懐室
一TIl--「中
清
藤原文範
|1為雅
「
為
信
甘朱雀
宇59多
妻 車60
醐親 |王 l
品喜 安一有L 祐貴 子寸一上一丁姫
雅信
ム子
道長妻
一」警)康子l朱ー王明親子 土親 J雀条て[.王王 jjL長最重量
搭王良王成'--" '--"
泉
2-
高藤定方計五一一大弐
藤原良門ム
権介正六位上藤原朝臣兼済僻笹韓日輔自年
少橡正六位上新井宿頑固府淵
Lh同…糊
権大嫁正六位上安倍朝臣晴忠時制撤軒納欄一県出口
大目正六位上宇目可宿禰春利野町才師帥…臣
少目
権少目
権少目
加賀国
権介従五位上惟宗朝臣允亮
大目
少目
(中略)
淡路園
守従五位下藤原朝臣民時
捺権像
権目正六位上井上宿禰惟方
自権目
阿波圏
構守正五位下藤原朝臣兼隆
(下略)
47寸望後 Hi 「ziア守子f??
福耳子
長徳二年大間書
大間書
神祇官
(中略)
越前園
守従四位上源朝臣園盛
権守
兼
3-
停修理権大夫藤原朝臣正
暦四年給多治比茂助改任
『続群書類従』巻第二百六十七
除目l県百(国司)と司召・受領・大間室
7申文
四等官
1守・介・橡・目
国の等級!大国1十三一上国
1三十五
中国1十
国務条々事(『朝野群載」)入国と任国での受領の守るべき
心得四十三ヵ条の内
一揮吉日時入境事在京之問。未及吉日時者。逗留漫下。
其間官人雑仕等。慮外来着。令申事由者。随形百上。可
問園風。但可随形。専不可云無益事。外国之者。境迎之
日。必推量官長之賢愚。
一境迎事官人雑仕等。任例来向。或園随身印鑑参向。
或園引卒官人雑仕等参曾。其儀式随土風雨巳。参著之問。
若嘗悪日者。暫返園廃。吉日領之。
一擦吉日時入舘事著舘日時。在京之問。於陰陽家。令
撰定。若卒去交替之時。或改居所可也。
一著舘日。先令奉行任符事著園之日。先有此事。其儀
式。先新司以任符授目。々百史生。令臆覧。々畢長官以下
登時奉行。
一受領印鑑事揮定吉日。可領印鐙。但領印鑑之日。即
令前司奉行任符。乃後領之。又著舘日儀式。前司差官人。
分付印鎗。其儀前司差次官以下目以上一一陶人。令資印鉛。
令参新司舘。即官人就座之後。鉛取書生。以御鉛置新司
前。盟副都ドo
新司無答抑制害五。
諸国(『延喜式』巻第二十二「民部上」)
-近国二十二ヵ国
山城上大和大河内大和泉下摂津上[畿内]伊賀下
伊勢大志摩下尾張上参河上[東海道]近江大美濃
上〔東山道]若狭中[北陸道]丹波上丹後中但馬上
因幡上[山陰道]播磨大美作上備前上[山陽道]紀
伊上淡路下[南海道]
-中国十六ヵ国
遠江上駿河上伊豆下甲斐上[東海道]飛騨下信濃
上[東山道]越前大加賀上能登中越中上[北陸道]
伯脅上出雲上[山陰道]備中上備後上[山陽道]
阿波上讃岐上[南海道]
-遠国三十ヵ国
相
模
上
武
蔵
大
安
房
中
上
総
大
下
総
大
常
陸
大
[
東
海
道]上野大下野大陸奥大出羽上[東山道]越後土
佐渡中[北陸道]石見中隠岐下[山陰道]安芸上周
防上長門中[山陽道]伊諌上土佐中[南海道]筑前
上
筑
後
上
豊
前
上
豊
後
上
肥
前
上
肥
後
大
日
向
中
大
隅中薩摩中萱岐嶋下対馬嶋下[西海道]
「陸奥園、出羽田、佐渡園、隠岐園、萱岐嶋、対馬嶋:::
四国二嶋為遁要」
4
-R五畿内〈ウチックニ〉脅東海道〈ウヘツミチ〉十五箇国脅東山
道〈ヤマチ〉八箇国脅北陸道〈キタノミチ、クカノミチ〉七箇国脅
山陰道〈ブモトノミチ、ヵケトモノミチ、ソトモノミチ〉八箇国脅山陽道八
箇国岳阿南海道〈ミナミノミチ〉六箇国
一箇国
-R西海道〈ニシノミチ〉十
「源氏物語』にみる「受領」(「新潮日本古典集成」本による)
A
受領と言ひて、人の国のことにかかづらひいとなみて、
品定まりたるなかにも、またきざみきざみありて、中の品
のけしうはあらぬ、選り出でつべきころほひなり。〈帯木〉
B
「揚名の介なる人の家になむはべりける。男は田舎にま
かりで、妻なむ若くこと好みて、はらからなど宮仕え人に
て来通ふ、と申す。くはしきことは、下人のえ知りはべら
ぬにやあらむ」と聞こゆ〈夕顔〉
C
かの夕顔の宿りには、いづかたにと思ひまどへど、:
たしかならねど、けはひをさばかりにやと、ささめきしか
ば、惟光をかこちけれど、いとかけ離れ、けしきなく一言ひ
なして、なほ同じごと好きありきければ、いとど夢のここ
ちして、もし受領の子どもの好き好きしきが、頭の君に懐
ぢきこえて、やがて、率て下りにけるにやとぞ、思ひより
ける。この家あるじぞ、西の京の乳母の女なりける。〈夕
顔〉
D
何とも見入れたまふまじき、似而非受領の娘などさへ、
心の限り尽くしたる車どもに乗り、きまことさらび、心げ
さうしたるなむ、をかしき様々の見物なりける。〈葵〉
E
かの院のつくりざま、なかなか見どころ多く、今めいた
り。よしある受領などを選りて、あてあてにもよほしたま
ふ。〈湾標〉
:・:この、受領どもの、おもしろき家造りこのむが、こ
の宮の木立を心につけて、放ちたまはせてむやと、ほとり
につきて、案内し申さするを、さやうにせさせたまひて、
いとかうもの恐ろしからぬ御住ひに、おぼしうつろはなむ。
立ちとまりさぶらふ人も、いと堪へがたし」など聞こゆれ
ど・::・。〈蓬生〉
G
侍従などいひし御乳母子のみこそ、年ごろあくがれ果て
ぬ者にてさぶらひっれど、通ひ参りし斎院亡せたまひなど
して、いと堪へがたく心細きに、この姫君の母北の方のは
らから、世におちぶれて受領の北の方になりたまへるあり
けり。:::もとよりありつきたるさゃうの並々の人は、な
かなかよき人の真似に心をつくろひ、思ひ上がるも多かる
を、やむごとなき筋ながらも、かうまで落つべき宿世あり
ければにや、心すこしなほなほしき御叔母にぞありける。
〈蓬生〉
H
心ばへなど、はた、埋れいたきまでよくおはする御あり
さまに、心やすくならひて、異なることなきなま受領など
ゃうの家にある人はならはずはしたなきここちするもあり
て、うちつけの心みえに参り帰る。〈蓬生〉
I
世の中を捨てはじめしに、かかる人の固に思ひ下りはべ
りしことも、ただ君の御ためと、思ふやうに明け暮れの御
かしづきも心にかなふやうもやと、思ひたまへ立ちしかど、
身のったなかりける際の思ひ知らるること多かりしかば、
さらに都に帰りて、古受領の沈めるたぐひにて、貧しき家
の蓬葎、もとのありさまあらたむることもなきものから、
F
-5
公私にをこがましき名を広めて、親の御なき影をはづかし
めむことのいみじきになむ、やがて世を捨てつる門出なり
けりと人にも知られにしを:::〈松風〉
J
国々より、田舎人多くまうでたりけり。この国の守の北
の方も、まうでたりけり。いかめしく勢ひたるをうらやみ
て、この三条が言ふゃう、「大悲者には、異事も申さじ。
あが姫君、大弐の北の方ならずは、当国の受領の北の方に
なしたてまつらむ。二一条らも、随分にさかえてかへり申し
はつかうまつらむ」と、額に手をあてて念じ入りてをり。
右近、いとゆゆしくも言ふかなと聞きて、「いといたくこ
そ田舎びにけれな。中将殿は、昔の御おぼえだにいかがお
はしましし。まして今は、天の下を御心にかけたまへる大
臣にて、いかばかりいっかしき御なかに、御方しも、受領
の妻にて、品定まりておはしまさむよ」と言へば、:
〈玉重〉
K
女御のしおきたまへることをばさるものにて、作物所、
さるべき受領どもなど、とりどりにつかうまつることども、
いと限りなし。〈宿木〉
L
受領の御婿になりたまふかゃうの君たちは、ただ私の君
のごとく思ひかしづきたてまつり、手に捧げたるごと、思
ひあつかひ後見たてまつるにかかりでなむ、さるふるまひ
したまふ人々ものしたまへるを、:::〈東屋〉
M
「絵師どもなども、御随身どものなかにある、むつまし
き殿人などを選りて、さすがにわざとなむせさせたまふ」
と申すに、いとどおぼし騒ぎて、わが御乳母の、遠き受領
の妻にて下る家、下つ方にあるを、「いと忍びたる人、し
ばし隠いたらむ」と、かたらひたまひければ、いかなる人
にかは、と思へど、大事とおぼしたるに、かたじけなけれ
ば、「さらば」と聞こえけり。〈浮舟〉
資料2
「細部」
の力
聖心女子大学
原
子
岡
文
①惟光に夕顔の絡む家のことを探らせて、この腹心の影を
次第にくろぐろと浮き上がらせる。というより惟光もまた
山の気に立ちのぼる雲の姿なのであろう。
そういう合間に前段の空蝉のこと、雨夜の品定め以来の
品々の女への好奇心、空蝉と軒端荻を比べてのめりこむ心
の深さ、軽さ、さらに六条の女君をわがものにして以来の
冷ややかさ、その侍女にも気を散らして、さりげなくいな
されるくだりなど、まるでどうでもよいことのように挿入
されている。
この物語の命の長さは、もしかしたら、本筋よりはこう
したとりとめのないこぼれ話、何げない咳きのリアリティ
ーにあるかもしれないのだ。いやそうなのだ。主人公の男
君、女君の姿を刺すように見据えている物の怪ともいうべ
き作者の中に宿っている霊の力が、この名作を今に伝えて
-6-
いる。山
の気ともいうべき樹々のざわめきの中にこそ、しつら
えられたわざとらしい話の筋からはみ出た磐の細部にこそ、
この世のさまがまざまざと見える。そして山の気を集め寄
せて盛り上がる濃い灰色の雲が妖気漂う夕顔の話となる。
|||中略「!|
読者の夢をかきたてる華やかな女君や光り輝く恋の達人
光源氏は表向きの筋立てである。表向きの筋の合聞に作者
がしっかりとその眼で見届けたこの世のさまを、恐ろしい
までにまことのままに描きとどめた筆の力に誘われて、長
い年月を読者は読みついで来たものであろう。
このような立場の男が、このような立場の女が、このよ
うに立ち、このように目をそむけ、このように振舞い、こ
のように咳き、このように悲しみ、歓び、悔いるというよ
うなことが、そこに見えるように描かれているからだろう。
かき立てられた夢の漂って消えるさまが、消えてもまたほ
のぼのと夢の生まれるさまが初めもなく終りもないこの世
のさまとして、いつ果てるともなく打ち続く雲のようにひ
ろがってそこに在るので、読者はいくつかの人生を同時に
生きているような気分になる。
(大庭みな子「夕顔」新編日本古典文学全集
『源氏物語」②・月報)
②左衛門の督、「あなかしこ。このわたりに、わかむらさ
きやさぶらふ」とうかがひたまふ。源氏にかかるべき人も
見えたまはぬに、かの上はまいていかでものしたまはむと、
聞きゐたり。(『紫式部日記』日本古典集成五二頁)
③:::物語のことをのみ心にしめて、われはこのごろわろ
きぞかし、さかりにならば、かたちもかぎりなくよく、髪
もいみじく長くなりなむ、光の源氏の夕顔、宇治の大将の
浮舟の女君のやうにこそあらめと思ひける心、まづいとは
かなくあきまし。(『更級日記』日本古典集成三五
1六頁)
④
a
何事よりも何事よりも、大将の、帝になられたること。
返す返す見苦しく浅ましきことなり。めでたき才・才覚す
ぐれたる人、世にあれど、大地六反震動することやはある
べき。いと恐ろしくまことしからぬことどもなり。
源氏の、院になりたるだに、さらでもありぬべきことぞ
かし。されども、それは正しき皇子にておはするうへに、
冷泉院の位の御時、わが御身の有様を聞きあらはして所置
き奉り給ふにであれば、さまでの舎にはあるべきにもあら
ずOi---
物語といふもの、いづれもまことしからずとい
ふ中にも、これは殊の外なることどもにこそあんめれ。
[狭衣物語](『無名草子』日本古典集成六二
i三頁)
b
式部卿の宮、唐土の親王に生れ給へるを伝へ聞き、夢
にも見て、中納一言、唐へ渡るまではめでたし。その母、河
陽県の后さへ、この世の人の母にて、吉野の君の姉などに
て、余りに唐土と日本と一つに乱れ合ひたるほど、まこと
しからずOi--・「河陽県の后、切利天に生れたる』と空に
告げたるほどだにいとまことしからぬに、また、かの后、
吉野の君の腹に宿りぬ、と夢に見たるほどなど、乱りがは
しく、回利天の命はいと久しくあなるを、いつのほどにか
7-
またさることはあらむ、などおぽゆるこそ、口惜しけれ。
[
浜
松
中
納
言
物
語
]
(
七
八
1九頁)
c
女中納言の死に入り、延へるほどこそ、おびただしく
恐ろしけれ。鏡持て来て、万のこと、暗からず見たるほど、
まことしからぬことどもの、いと恐ろしきまでこそ侍れ。
[
古
本
と
り
か
へ
ば
や
]
(
八
二
頁
)
d
本のは、もとの人々皆失せて、いづこなりしともなく
て新しう出で来たるほど、いとまことしからず。
[
今
と
り
か
へ
ば
や
]
(
八
四
頁
)
e
中宮の御産の御祈りの仏の多さこそ、まことしからね。
[
海
人
の
刈
藻
]
(
九
一
頁
)
f
すべて今の世の物語は、古き帝にて、『狭衣』の天の
乙女、『寝覚』のうちしきなども、今少しことごとしくい
ちはやきさまにしなしたるほどに、いとまことしからずお
び
た
だ
し
き
ふ
し
ぶ
し
ぞ
侍
る
。
(
九
八
頁
)
「撞』、紫の上の物思へるがいとほしきなり。
g
(二六頁)
h
「めでたき女は誰々か侍る」と言へば、「桐査の更衣。
藤査の宮。葵の上の我から心を用ゐ。紫の上、さらなり。
明石も、心にくくいみじ」と言ふなり。(二七
i八頁)
i
いとほしき人、紫の上。
限りなくかたびかしくいとほしく、あたりの人の心ばへ
もいと憎き。父宮をはじめ、おほぢの僧に至るまで、思は
し
か
ら
ぬ
人
々
な
り
。
(
三
二
頁
)
また、須磨へおはするほど、さばかり心苦しげに思ひ
入り給へる紫の上も具し聞えず、せめて心澄まして一筋に
行ひつとめ給ふべきかと思ふほどに、明石の入道が婿にな
りて、ひぐらし琵琶の法師と向ひ居て、琴弾きすましてお
は
す
る
ほ
ど
、
む
げ
に
思
ひ
所
な
し
。
(
三
六
頁
)
k
紫の上はつかに見て、野分の朝ながめ入りけむまめ人
こ
そ
、
い
と
い
み
じ
け
れ
。
(
三
八
頁
)
l
紫の上のとりわき給へりしゅゑ、二条院に住み給ふこ
そいとあはれなれ。
薫大将、はじめより終りまで、さらでもと思ふふし一つ
見えず、返す返すめでたき人なんめり。
まことに光源氏の御子にてあらむだに、母宮のものはか
なきを思ふには、あるべくもあらず。紫の御腹などならば、
さ
も
あ
り
な
む
。
(
三
九
頁
)
m:::紫の上、涙を一目うけて見おこせて、
別るとも影だにとまるものならば
鏡を見てもなぐさみなまし
と
あ
る
所
。
(
四
四
頁
)
n
また、出で給ふあかっき、紫の上、
惜しからぬ命に換へて目の前の
別れをしばしとどめてしがな
と宣へるこそ、いと人わろけれ。(四五頁)
紫の上の失せのほどのことども、申すもおろかなり。
亡くなり果てて臥し給へるを、まめ人のほのかに見て、
いにしへの秋の夕の恋しきに
今はと見えしあけぐれの夢
-8-
O
野分のまぎれに見奉り給へりしことを、おぼし出でたるな
る
べ
し
。
(
四
八
頁
)
Pいとほしきこと。
「須磨」の御出立のほどの紫の上。・:
『若菜』にて、紫の上、片敷く袖もしみ氷り、臥しわづ
らひ給へる暁、おはして叩き給ふに、空寝して人開けぬ折
の
こ
と
。
(
五
四
頁
)
q
心やましきこと。
紫の上須磨へ具せられぬことだにあるに、明石の君まう
けて、問はず語りしおこすること。・:
女三の宮まうけて、紫の上に物思はせたること。
(五五
1六頁)
⑤a
きよげなる大人二人ばかり、さては童べぞ出で入り遊
ぶ。中に、十ばかりにやあらむと見えて、白き衣、山吹な
どのなえたる着て、走り来たる女子、あまた見えつる子ど
もに似るべうもあらず、いみじく生ひ先見えてうつくしげ
なる容貌なり。髪は一扇をひろげたるやうにゆらゆらとして、
顔はいと赤くすりなして立てり。
「何ごとぞや。童べと腹だちたまへるか」とて、尼君の
見上げたるに、すこしおぼえたるところあれば、子なめり
と見たまふ。「雀の子を犬君が逃がしつる。伏寵の中に舘
めたりつるものを」とて、いと口惜しと思へり
0
・
尼君、「いで、あな幼や。一言ふかひなうものしたまふか
な。おのがかく今日明日におぽゆる命をば、何とも思した
らで、雀慕ひたまふほどよ。罪得ることぞと常に聞こゆる
を、心憂く」とて、「こちゃ」と言へば、ついゐたり。
つらつきいとらうたげにて、眉のわたりうちけぶり、い
はけなくかいやりたる額っき、髪ざし、いみじううつくし。
ねびゆかむさまゆかしき人かな、と目とまりたまふ。
(日本古典文学全集『源氏物語』若紫什二八
Ol一一八一頁)
b
今日は、二条院に離れおはして、・::・姫君のいとうつ
くしげにつくろひたてておはするをうち笑みて見たてまつ
りたまふ。:::いとらうたげなる髪どもの末はなやかに削
ぎわたして、浮絞の表袴にかかれるほどけぎやかに見ゆ。
「君の御髪は我削がむ」とて、「うたて、ところせうもある
かな。いかに生ひやらむとすらむ」と削ぎわづらひたまふ。
(葵同二一l
上三頁)
-9-
C
姫君の何ごともあらまほしうととのひはてて、いとめで
たうのみ見えたまふを、似げなからぬほどにはた見なした
まへれば、けしきばみたることなど、をりをり聞こえ試み
たまへど、見も知りたまはぬ気色なり。
つれづれなるままに、ただこなたにて碁打ち、偏つぎな
どしつつ日を暮らしたまふに、心ばへのらうらうじく愛敬
づき、はかなき戯れごとの中にもうつくしき筋をし出でた
まへば、思し放ちたる年月こそ、たださる方のらうたきの
みはありつれ、忍びがたくなりて、心苦しけれど、いかが
ありけむ、人のけぢめ見たてまつり分くべき御仲にもあら
ぬに、男君はとく起きたまひて、女君はさらに起きたまは
ぬ
あ
し
た
あ
り
。
(
葵
六
二
|
六
三
頁
)
d
かかる御心おはすらむとはかけても思し寄らざりしか
ば、などてかう心うかりける御心をうらなく頼もしきもの
に思ひきこえけむ、とあきましう思さる。(六四頁)
か
み
⑥
a
解かば足にもと
rくべき毛髪を、根あがりに堅くつめ
て前髪大きく髭をもたげの、緒熊といふ名は恐ろしけれど、
れ
よ
き
し
ゅ
む
す
め
ご
此彰闘を此頃の流行とて良家の令嬢も遊ばさる〉ぞかし、色
白に鼻筋とほりて、口もとは小さからねど締りたれば醜く
からず、一つ一つに取立て〉は美人の鑑に遠けれど、物い
ふ撃の細く清しき、人を見る目の愛敬あふれで、身のこな
い
き
ノ
ー
、
こ
〉
ろ
よ
しの活々したるは快き物なり、:::子供中間の女王様:::
(「たけくらべ」『樋口一葉集」筑摩書房八九頁)
b
美登利くやしく止める人を掻きのけて、これお前方は
三ちゃんに何の答がある、正太さんと喧嘩がしたくば正太
さんとしたが宜い、逃げもせねば隠くしもしない、正太さ
んは居ぬでは無いか、此慮は私しが遊び慮、お前がたに指な
でもさ〉しはせぬ、ゑ〉憎くらしい長吉め、三ちゃんを何
ぜ
ぷ
故ぶつ、あれ又引たほした、意趣があらば私をお撃ち、相
手には私がなる、伯母さん止めずに下されと身もだへして
罵
れ
ば
、
:
:
:
(
同
九
二
頁
)
c
信如がいつも田町へ通ふ時、遁らでも事は済めども言
か
り
そ
め
く
ら
ま
はy近路の土手々前に、仮初の格子門、のぞけば鞍馬の石
ま
き
す
だ
れ
燈簡に萩の袖がきしをらしう見えて、縁先に巻たる簾のさ
な
か
あ
ぜ
ち
こ
う
まも懐かしう、中がらすの障子のうちには今様の按察の後
しつ
U・
ず
つ
ま
か
ぷ
た
ち
い
づ
室が珠教を爪ぐって、冠つ切りの若むらさきも立出るやと
思はる三其一ト構へが大黒屋の寮なり。(同九九頁)
見るに気の毒なるは雨の中の傘なし、途中に鼻緒を踏
み
ど
り
が
ら
す
きりたるばかりは無し、美登利は障子の中ながら硝子ごし
に遠く眺めて、あれ誰れか鼻緒を切った人がある、母さん
よ
切れを遣っても宣う御座んすかと尋ねて、:::
d
(同九九頁)
う
い
ノ
(
、
ゅ
ひ
わ
た
し
ぼ
は
な
e
初々しき大島田、結綿のやうに絞り放しふさ/¥と
ぺ
つ
こ
う
ふ
さ
懸けて、篭甲のさし込み、線つきの花かんざしひらめかし
つ
ど
く
さ
い
し
き
て、何時よりは極彩色の、唯京人形を見るやうに思はれて、
いつも
正太はあっとも言はず立止りしま〉例の知くは抱きつきも
う
ち
ま
も
せ
で
打
目
成
る
に
:
:
:
(
同
一
O一頁)
f
夫れなら何うしてと聞はるれば憂き事さま六¥是れは
何うでも話しのほかのつ〉ましさなれば、誰れに打明け言
ほ
う
な
ぜ
ふ筋ならず、物言はずして自づと頬の赤うなり、何故と言
きのふ
はれねども次第/¥に心ぽそき思ひ、すべて昨日の美登利
た
タ
が身に費えなかりし思ひをまうけて、唯々もの〉恥かしさ
言ふばかりなく、薄くらき部屋の中に誰れとて詞もかけも
せず我顔ながむるものなしに一人気ま〉の朝夕を経たや、
さらば此様の憂き事ありとも人目つ〉ましからずば斯くま
あ
ね
さ
ま
で物は思ふまじ、何時までも何時までも人形と紙雛様とを
ま
〉
ご
と
き
苧
相手にして飯事ばかりして居たらば撫かし嬉しき事ならん
い
お
と
な
を、ゑ〉嫌や/¥、大人に成るは嫌ゃな事、:(同一
O二頁)
おとな
g
美登利はかの日を始めにして生れ替りしゃうの柔順し
さ、用ある折は廓内の姉のもとまで遁へど懸けても町に遊
ぶ事をせず、友達淋しかりで誘ひに行けば、今にと空約束
-10-
なかよし
ばかり、さしもに仲善なりけれども正太と解けて物いふ事
も無く、何時も駈かしげに顔のみ赤めて筆やの庖に手をど
りの活濃さは薬にしたくも見る事ならず成けり、人は怪し
せい
がりて病ひの故かと危ぶむもあれども、母の親一人ほ〉笑
き
や
ん
わ
け
みては今にお侠の本性は現れまする、これは中休みと子細
ありげに言はれて知らぬ者には何の事とも思はれず、女ら
お
と
な
せ
っ
か
く
しく温順しく成ったと褒めるもあれば、折角の面白い子を
肇
な
し
に
爵
た
と
誹
る
も
あ
り
、
(
同
一
O三頁)
⑦
a
池はいと涼しげにて、蓮の花の咲きわたれるに、葉は
いと青やかにて、露きらきらと玉のやうに見えわたるを、
「かれ見たまへ。おのれ独りも涼しげなるかな」とのたま
ふに、起き上がりて見出だしたまへるもいとめづらしけれ
ば、「かくて見たてまつるこそ夢の心地すれ。いみじく、
わが身さへ限りとおぼゆるをりをりのありしはや」と、涙
を浮けてのたまへば、みづからもあはれに思して、
消えとまるほどやは経べきたまさかに蓮のつゅの
か
か
る
ば
か
り
を
(
若
菜
下
回
二
三
五
1六頁)
b
風すごく吹き出でたる夕暮に、前栽見たまふとて、脇
患によりゐたまへるを、院渡りて見たてまつりたまひて、
「今日は、いとよく起きゐたまふめるは。この御前にては、
こよなく御心もはればれしげなめりかし」と聞こえたまふ。
おくと見るほどぞはかなきともすれば風にみだるる
萩のうは露
げにぞ、折れかへりとまるべうもあらぬ、よそへられたる。
::・ややもせば消えをあらそふ露の世におくれ先立つ
ほど経ずもがな・・・...
秋風にしばしとまらぬつゅの世をたれか草葉の
う
へ
と
の
み
見
ん
(
幻
四
四
九
01一頁)
c:::宮は御手をとらへたてまつりて泣く泣く見たてま
つりたまふに、まことに消えゆく露の心地して限りに見え
たまへば、御諸経の使ども数も知らずたち騒ぎたり。
(同四九二頁)
⑧
a
おもふ事ありしころ、はぎを見て
おおきあかしみつつながむるはぎのうへの露吹きみだる
あ
き
の
よ
の
か
ぜ
(
『
伊
勢
大
輔
集
」
)
b
はぎ
判きゆるだにをしげにみゆる秋はぎのつゆふきおとす
こ
が
ら
し
の
か
ぜ
(
『
大
弐
三
位
集
』
)
c
萩にをける露と消えにし君が身を白玉とのみ
た
の
み
け
る
か
な
(
「
源
中
納
言
懐
旧
百
首
』
)
d
建保元年内裏詩歌合、野外秋望
2247むら雨の玉ぬきとめぬ秋風にいくのかみがく
萩
の
上
の
露
(
「
拾
遺
愚
草
』
)
e
題
し
ら
ず
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
332おく骨もしづ心なく制刷にみだれでさけるまのの
萩
原
(
『
新
古
今
和
歌
集
』
)
f
三十首歌人人によませさせ給ひし時、草花露を
院御製
499なびきかへる花のすゑより露ちりて萩の葉しろき
11-
庭の秋かぜ
g
(『玉葉和歌集』)
前中納言定家
479風ふけば枝もとををにおく露のちるさへをしき
秋
は
ぎ
の
は
な
(
『
風
雅
和
歌
集
』
)
乾元二年伏見院五十番歌合に、秋露を九条左大臣女
480しをれふす枝ふきかへす秋風にとまらずおつる
は
ぎ
の
う
は
露
(
同
)
h 資料3
中世文学の立場から
白
百
合
女
子
大
学
久
保
田
j享
源氏巻名和歌
清輔朝臣集恋
寄源氏恋
あふことはかたびさしなるまき柱ふす夜もしらぬ恋もするかな
長秋詠藻中恋
(おなじ人の十首の題のうち、恋一一首)寄源氏名恋
うらみてもなをたのむかな身をつくしふかきえにあるしるし
と思へば
源三位頼政集下
寄源氏恋を、歌林苑にて会に
人しれず物をぞおもふ野分してこす吹風にひまはみねども
近衛大納言集下恋
源じのまきにょする
むねにたくおもひぞたぐふかずり火のかけはなれたる人をこ
ふとて
小侍従集恋
源氏にょする恋
は〉きずのありしふせやをおもふにもうかりしとりのねこそ
わすれね
忠度朝臣集恋
寄源氏恋
あふと見るゆめさめぬればつらきかなたびねのとこにかよふ
まっかぜ
経正朝臣集恋
寄源氏恋
おもひかねこひなぐさめのゑあはせにきみがすがたをうつし
つるかな
千載和歌集巻第十四恋歌四
源氏物がたりにょするこひといへる心をよめる
(よみ人不知)
見せばゃな露のゆかりのたまかづら心にかけてしのぶけしき
をあふさかの名はわすれにし中なれどせきやられぬはなみだな
りけり
明日香井和歌集下
寄源氏恋
-12-
恋
もらすなよた立てならひとことよせてかきながしつる水ぐき
のあと
源氏供養の和歌
藤原隆信朝臣集下釈教
は〉の、紫式部がれうに一品経せられしに、
だらに口聞をとりて
夢のうちもまもるちかひのしるしあらばながきねぶりをさま
せとぞおもふ
新勅撰和歌集巻第十釈教歌
紫式部ためとて結縁経供養し侍ける所に、薬草聡品を
〉
く
り
侍
と
て
権
大
納
言
宗
家
のりのあめに我もやぬれんむつましきわかむらさきのくさの
ゆかりに
中御門大納言殿集
源氏の一品経くやうしけるところの供養に、
信解品止宿草蓄のこ〉ろを
かりそめのいほりむすびしことのはにけふよりのりのはなや
ひらけん
おなじき、薬草喰品のこ〉ろ、人にかはりて
のりのあめにわれもやぬれむ〉つましきわかむらさきのくさ
のゆかりに
藤原俊成の源氏物語についての発一一一一回
住吉社歌合嘉応二年十月九日
社頭月
四番
左
勝
散
位
従
四
位
上
藤
原
朝
臣
清
輔
月かげはさえにけらしなかみがきやよるべのみづにつら〉ゐ
るまで
右
参議従三位行左大弁兼勘解由長官阿波権守藤原朝臣実綱
っきかげにかなづるきねがころもではゆきをめぐらすこ〉ち
こそすれ
左歌、「よるべのみづにつら〉ゐるまで」などいへるも
じっ
rき、よろしくはみゆるを、おぼつかなきことyも
ぞ侍める。まづ「よるべのみづ」といふことは、源氏の
ものがたりにぞ、賀茂のまつりの日のうたに、「さもこ
そはよりべのみづもみくさゐめ」とよめる、みたまへし。
さらでは、ふるきうたにもみおよび侍らず。このみづ、
おろノ¥うけたまはるに、たとへばいづれのやしろにも
はべらめど、まづ当社のおまへの月には、うみのおもて
こほりをみがき、はまのまさごたまをしけらむをばおき
て、よりべのみづばかりにむかひて、月は「さえにけら
しな」とおもはむことやいか10
右歌、まひのすがたを
いふに、廻雪といふことのあるを、いま月のひかりによ
せて、「ゆきをめぐらす」とみゆらむこ〉ろ、いとをか
しくはみゆるを、「かなづるきねが」といへるわたりゃ、
よまぬことにはあらねど、ことに優にしもやきこえざら
む。左はおぼつかなきことまもぞ侍れど、うたのすがた
よろしくみゆ。なほかっとや申べからむ。
六百番歌合夏下
-13-
夕顔
十三番
左
女
房
かた山のかきねの日影ほのみえて露にぞうつる花のタがほ
右
勝
中
宮
権
大
夫
おりてこそみるべかりけれタ露にひもとく花の光ありとは
右方申云、「タがほ」とはをきたれど、題の心かすかに
や。左方申云、右歌、ひとへに源氏の物語ばかりを思へ
る、為ニ歌合之証一事、如何。
判云、左、題の心は幽にやは侍。只、「タがほの花」と
はいはで、など「花のタがほ」とはいへるにか。これも
題のま〉ならで、めづらしくいはんとにや。右、偏に源
氏物語には侍れど、又歌ざま優ならざるにはあらざるに
や。「花のタ良」には、右、まさり侍りなん。
十八番
左
持
有
家
朝
臣
むぐらはふしづがかきねも色はへて光ことなるゆふがほの花
右
隆
信
朝
臣
たそかれにまがひてさける花の名ををちかた人やとはずこたへ
む
右申云、「かきねの色はゆ」といはん事、いかま。左申
一五、「をちかた人に物申」といふ歌は、タがほの事とは
みえずや。
判云、左歌、「かきねの色」はいかにでも、「色はへて」
といへる調、不ユ庶幾一欺。右の歌、「遠かた人」の本歌
返しの歌に、「春されば」といへり。夕顔にはあらざる
べし。源氏には、たy当時しろくさける花をみて、「を
ち方人に」とはいはせたるを、随身聞知て、「かれをな
ん夕顔と申」といはせたる、又ひが事にはあらず。而、
今の歌は偏に源氏をおもひてよめる、しかるべからず。
源氏のためもあしくなりぬべし。但、左の「色はへて」、
猶、勝と定がたし。持などにや。
秋上
廿六番(野分)
左
兼
宗
朝
臣
百草の花もいかにかおもふらんあな情なの今朝の野分や
右
勝
中
宮
権
大
夫
吹みだる野分の風のあらければやすき空なき花の色/¥
左右共、無二指事-之由申ν之。
判云、「あななさけな」と、おかしきさまを庶幾せるに
や。右歌、「吹みだる」とをける、源氏の野分の玉かづ
らなど思出られて、えんなるさまには侍にや。但、左の
「花もいかに」といひ、右の「やすき空なき」などいへ
る、同ほどの事にやとは見え侍を、猶、左、「百草の」
なども、そのよせなくや。「吹みだる」に付て、右、す
こしまさるべくや侍らん。
冬上
十三番枯野
左
勝
女
房
見し秋をなに〉のこさん草の原ひとつにかはる野べのけしき
-14
隆信朝臣
霜枯の野べのあはれを見ぬ人や秋の色には心とめけむ
右方申云、「草のはら」、き〉よからず。左方申云、右歌、
ふるめかし。
判云、左、「なに〉残さん草の原」といへる、艶にこそ
侍めれ。右方人、「草のはら」、難申之条、尤、うた〉あ
るにや。紫式部、歌よみの程よりも物かくふでは殊勝也。
其上、花の宴のまきは、ことに艶なる物也。源氏見ざる
歌よみは遺恨事也。右、心詞、あしくはみえざるにや。
但、つねの体なるべし。左歌、宣、勝と申べし。
水無瀬殿恋十五首歌合建仁二年九月十三夜
三十三番(覇中恋)
左
勝
親
定
君ももしながめやすらん旅衣朝たつ月をそらにまがへて
右
左
大
臣
うつの山うつ〉かなしき道たえて夢に都の人はわすれず
左の豆町、「朝たつ月を空にまがへて」と侍る心すがた、
源氏物語の花のえんの一苛など思ひ出られて、いみじくえ
んにみえ侍り。右の歌は、「うつの山うつ〉悲しき」な
ど侍る、此ごろうつの山[越]、あまた聞え侍るにや。
左勝侍るべし。
正治二年俊成卿和字奏状
旦はのりながと申候しもの、わたくしのうちぎきに拾遺古今
と申名付候て、あつめせんじたる事候き。そのとき、清輔か
れにつきたるものにて、かたはらにそひ候て、もろともにつ
かまつりて候し、まことにみぐるしきことずも候き。まづは、
「てりもせずくもりもはてぬ春のよ」と申寄を、「夏の夜」と
しりて、夏の部にいれて候き。その寄は、源氏物語に、二月
の花のえんの巻に、内侍督に「おぼろ月よ」といはせて候を、
教長も清輔も、源氏を見候はず、まして文集と申文をも見候
はで、白楽天の詩に、「不ν明不ν暗躍々月、非ν暖非ν案、漫々
風」と申詩をこの寄にもよみて候を、いづれをもしり候はで、
「夏の夜」とかきて、夏の部に入て候。教長、清輔、ともに
うたてしき事候也。
林下集下雑
源氏集を皇大后宮大夫俊成卿にかりで、かへしおくると
て、かきはべりし
世中のいろなる水をいとへどもなをみなもとのうちにそみぬ
スV
-15
返事
いろをいとふのりのみなもとたづぬればそむるこ〉ろぞきと
りともなる
藤原定家の源氏物語についての発言
千五百番歌合秋四判者定家朝臣
七百九十八番
左
持
前
権
僧
正
秋はいぬと小倉の山に鳴鹿のこゑのうちにや時雨そむらん
右
通
具
朝
臣
ひるまなき袖をば露のやどりにて心の秋よいつかはるべき
この左歌の中の三旬、あまりや本歌にかはらず侍らん。
右歌の二句も、露のをきどころかはり侍らぬうへに、彼
源氏物語の歌には、上下をよびがたくや侍らん、いか
r。
八百番
左
公
経
卿
霜の下にかきこもりなば草の原秋のタもとはじとやさは
右
勝
雅
経
秋ふかき松のあらしのたった山よその梢をまづはらふ覧
左歌、これも源氏物語の心にかよへるにや。調づかひ、
えんには侍べし。右歌、「松に嵐の」といへる、「緑於太
山之阿、舞於松柏之下」などいふ心を思へるにや。いか
にも、「草の原」よりは、木だかき「松」に侍べし。
京極中納言相語
一近代の人源氏物語を見きたする様、又あらたまれり。或
は寄をとりて本歌として寄をよまんれう、或は識者をた
て〉、紫上はたが子にておはすなどいひあらそひ、系図
とかゃなづけてさたありと云々。ふるくはかくもなかり
き。身に恩給ふゃうは、紫の父祖の事をもさたせず、本
歌をもとめむとも思はず、調づかひのありさまのいふか
ぎりもなきものにて、紫式部の筆をみれば、心もすみて、
歌のすがたこと葉の優によまる〉なり。文集の[文]此
定なる物にて、文集にておほく寄をよむなり。筆のめで
たきが心はいかさまにもすむにや。
中世歌論における源氏物語
後鳥羽院御口伝
一、まだしきほどは、
万葉集見たるおりは、
百首の寄なかば
は万葉集のうたよまれ、源氏等物語みたる比は、又その
やうなるを、[よく/¥]心えて詠べき也。
て一骨合のうたをば、いたくおもふま〉にはよまずと、釈岡、
寂蓮などは申しが、別のやうにてはなし、題の心をよく
おもはへて、病なく、又、源氏等物語のうたの心をばと
らず、ことばをとるはくるしからずと申き。すべて物語
の奇の心をば、百首の寄にもとらぬ事なれども、近代は
そのきたにもをよばず。
歌苑連署事書
続古今の「せきふきこゆるすまのうらかぜ」は、光俊朝臣ゑ
らびいれて侍りける、行平中納言の集にもなきよし、沙汰あ
りけるに、かの朝臣は、源氏の物語を証拠にひきけれども、
それもさはやかに首尾かける事もなければ、光俊うたがひを
おひにけり。
愚問賢注
一、本説をとる事、詩の心をもよめり。又、漢家の本文勿論
欺。源氏狭衣の詞、又子細なきをや。六百番判詞に、俊
成卿の、「源氏見ざらむ歌よみは口惜事」と申されき。
しからば、源氏の詞など幽玄ならんをば、本歌にはとる
べきをや。続古今に、光俊朝臣、中河の心をよめるうた
入りたり。今も本歌にはとるべきにや。
本説、本文、詩の心、物語の心、さのみ一小ν可レ詠之由
申して侍れども、つねに見え侍るにや。よもぎふの
「本のこころ」、さごろもの「草の原」、目なれて侍る
敗。源氏は、歌よりは詞をとるなど申して侍る。須磨
-16-
に「あかつきかけて月いづる比なれば」といへるを取
りて、「春の色はかすむばかりの山のはにあかつきか
けて月いづるころ」、宇治に「御馬にめすほど、ひき
かへす心ちしてあさまし」といへるを、「面影のひか
ふるかたにかへり見る都の山は月ほそくして」と侍る、
艶におもしろく侍るにや。ともに京極入道中納言歌也。
現実の人物を源氏物語の人物によそえること
平家公達草紙
山のはちかき入日のかげに御前の庭のすなごどもしろくき
ょげなる上に、花の白雪そらにしられてちりまがふ程、物
のねもてはやされたるに、青海波の花やかにまひいでたる
さま、惟盛朝臣のあしふみ袖ふる程、世のけいき、入日の
かげにもてはやされたるかたち、にる物なくきよらなり。
おなじ舞なれどめなれぬきまなるを、内、院おはじめたて
まつり、いみじくめでさせ給。ち〉おと
rこといみえし給
はず、をしのごひ給、ことはりと見ゆ。みる人涙をながす。
かたては源氏の頭中将ばかりだになければ、中/¥にかた
はらいたくなん覚けるとぞ。舞おはりて、はじめのごとく
つらなりて楽屋へいる。た
rし輪台の舞人はたちくわ〉ら
ず。
資料4
「源氏物語」
の幕末
野
武
彦
神戸大学
口
発論大旨
(二江戸時代における「源氏物語』受容は、一つの完成し
た文化現象であった。それは、「湖月抄』をはじめとす
る注釈書を中心に、「修紫田舎源氏』をピ
1クとするパ
ロディ文学の成熟までの幅をそなえた『源氏物語』享
受のかたちを完結させていた。そのいわば〈源氏物語
文化》と呼べるものが、幕末の激動期にどのように変
容するのか。それが今回のテ1マである。
会己幕末期の『源氏物語』をめぐる話題は、けっきょくの
ところ、萩原広道の『源氏物語注釈』の問題に帰着す
る。たんなる研究史のビーカーの中だけで考えるので
はなく、文学史・思想史の領域すら越え出て、歴史の
撹持機にかけられた社会導体のうちに広道の源氏物語
語学が生まれ出てきた情景をスポットする。
(三)江戸時代の《源氏物語文化》の底流には、今更めくが、
「もののあはれ」と「もののまぎれ」との対立があった。
国学的主情主義と儒学的道徳主義、したがって菰戦論
との対抗H相互補完関係である。広道がこの二つを綜
-17-
合したことはよく知られている。その背後には、広く
国学世界全体で進んでいた「もののあはれ」「もののま
ぎれ」という対概念それぞれの自己変質があった。
(四)『源氏物語』論にこうした変化をもたらした幕末国学の
特色は、歌学派と古学派という対立する流派に大別さ
れていったことであった。前者は鈴屋門下、後者は平
田派であったと大雑把にいえる。その間にあって、物
語学派と呼べる人物は、ほとんど萩原広道ひとりしか
いなかったのである。押し迫る幕末状況と個人実存の
危機の中から《今なぜ物語か》の問題が切実に問われ
た事情をたどってみたい。
参考資料(言及する文献の抜粋)
平田篤胤「玉だすき』一之巻文化十年(一八一三)頃
O物語ぶみの中にも。光源氏の物語は。作り物語なれど。当
昔の淫乱なりし趣。この物語のいたく行なはれたるにでも
所知たり。(然れば古学せむ徒も、暇あらむ時に、一通り
は見るべし、然れど此を古学の要用なる書の如く云ひ、此
の物語なくては、物の哀れは知られざる如く云ひて、髭く
ひそらし男道なくも、読みふける人あるは、真のます荒男
読べきふみ、為すべきわざの、多かるべき事を得知らず、
鈴屋大人の玉の小櫛を、読みひがめる故なりかし、心をつ
けて見よ、此の物語を好み読む人、多くは容貌づくり艶ば
みて、鳴呼なるそぶり有る物なり、)
O是に就て思ふ由あり。そは伊勢物語に。むかし男有けり。
歌はえ詠ざりけれど。世中を思ひ知りたり。と有を按へば。
当時より。歌よむ人のみ。世の中の哀は知りて。歌よまぬ
人は。世の事情にうとき物のごと。言へること知らる。然
れど此は信られぬ事なり。
藤
井
高
尚
『
文
の
し
る
べ
』
文
政
九
年
(
一
八
二
六
)
Oげんじの物語は、湖月抄の本に、師のか〉れたる玉の小櫛
をくはへて見るべし。おのれも考おける事どもあまたあれ
ば、いかで小櫛のほとりばずかりのものは、かきて又そへ
んとぞ思ふ。
伴信友「表章伊勢日記附一二日』天保四年二八三二)序
Oさるたぐひの物語ぶみの趣をすべて論はず、其物語つくれ
る人の、世の中のさまのま〉に、おほかたのいろ/¥しき
すぢによりて、あはれふかきあらましごとなどを、そのか
みの平生詞に、俗言をさへに交へ、またをり/¥は、古言
のなよびたるかたにきこゆるをも、とりまじへなどして、
書と〉のへでもてあそびぐさとしたりしものなれど、真に
シゐノ
正しき古風を慕ぶとならば、その世々の風俗をわきまへ知
り、然る濫なるすぢの意にそむまじく、よく/¥其心しら
ひしてえらび見るべし、源氏物語は、殊にそのすぢをむね
と多くものして、あはれをつくしてうまく書と〉のへたる
書なれば、わきて心をつくべきなり、
堀内匡平『源氏紐鏡』天保十四年(一八四三)抜
Oむかしよりこれかれと、世に聞ゆる物語のなかに、ひかる
源氏の物語、ばかりすぐれて、おもしろさのかぎりしられぬ
はあらじ。さるからに、世にもてはやし来て、其註、さて
もさまざま多く、今は六十余部にもおよぶべし。されど、
-18-
猶もれたることおほかるなかに、物語のむねとあることさ
へかくろへて、いまだ世にあらはれたらぬぞくちをしきゃ。
いで其よしを、かつがついはむ。
中島広足『橿園文集拾遺』嘉永七年(一八五四)刊
O一八八源氏物語をとくこと
源氏物語をとくこと、近世まではおしなべて、儒仏のこ〉
ろによりて、をしへのかたにのみ、とりなし〉を、本居翁
はじめて、いにしへの心を得て、もの〉あはれを、しるべ
きために、書きたるもの也といはれたるは、誠に其世のさ
まをしり、つくりぬしの深き心を、あらはしつくされたり、
といふべし。さるはいにしへ学びせん人は、此心をもてみ
べきことは、今きらいふべくもあらねど、又大かたの世に
して、やむごとなき人などの、これまなばむとにもあらで
人によませて、心やりにきかん、とおもひ給ふもあり。わ
がつかふる君の、おほせごとあるは、姫君のあたりなどに
めしてよましめ給はんには、いなぴがたきわざなるを、さ
るをりは、またすこし心しらひして、其くだりによりては、
調輸のさまにて、書きたるもの也などやうに、ときなした
らんも、よろしかるべし。
近
藤
芳
樹
『
源
語
奥
旨
』
明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
O(紫式部が夢枕に立っていわく。)
予にいへらく、妾は一条のみかどのきさき上東門院に仕へ
し、式部といふ女なり。妾むかし源氏物語を著はしたるに、
よむ人妾が深意のある処をしらず、た立その文辞をのみ善
なかだち
して、徒らに好色の媒とせり。妾実に塊づ。抑此物語は、
もと権臣の政雇を憎み、皇族の衰微を憂へて著はせる書な
ηノ。
O其大旨は、はじめに源氏の君と、摂家の嫡子頭中将とを、
対偶にして、頭中将、この源氏の君に仕ふるに、全く主従
の如きさまにつくりなし、それより次第の昇進も、みな源
氏を頭中将よりも上等にす〉め、皇族はか〉るべき物ぞと
いふことを示し、云々。
Oされど実はかく、筆仇艇が}以てだに、摂篠の勢ひを挫ぎ、
皇族を尊くせんとし、その苦心、なかノt¥等閑のことなら
ざりしを、今や聖天子御位を継給ひて摂関将軍を廃せられ、
庶政を古へに復し給へるに妾が蓄懐もこ〉に晴て、泉下の
穆念も頓に散ぜり。
萩原広道『本教堤網』上
-19-
アハレ
一之巻「物の感」
弘化三年(一八四六)
エ
ス
キ
ゴ
ト
O源氏などに所見たるおもむきは、専ら好色のすぢに依たる
ことにて、ょのつね善悪邪正などいふとは甚異なるさまな
イ
ヒ
ナ
ジ
タ
マ
るを以て、其後の人どもさま戸¥に論詰り、平田氏の玉
タ
ス
キ
ウ
ケ
俸にさへいと/¥信ずけにいひたり。然れども、其は皆、
タハケゴト
好色の事によりて淫奔を勧むる媒ともならんかとてなん
ヒトムネ
めれども、また一概なる論なりと云べし。
カ
カ
ヒ
タ
ム
ネ
メ
さて好色に係るすぢもまた一偏には云べからず。人妻を
ヒトゾマ
想ひかけて身を亡し、人妻ながら想はれて節操を失ひなど
するが如き事は、誰も善からぬ事ぞとは思ひ知れども、其
ア
ハ
レ
ア
ザ
ケ
リ
ソ
シ
リ
想ふ心のいと/¥せちに感にて、人の噺弄世の誹誘を思ふ
タマノヲ
はものかは、二つなき魂緒の絶なん事をも先押出てものせ
アハレ
んに、しばく聞ては物の感の身に染て堪がたき事もあるは、
活たる人の情のうへには必あるべきおもむきなるを、物語
コ
マ
ヤ
カ
ア
ハ
レ
などはさる細密なる心のくま戸¥の感を見せ尽さんとて、
殊更に正なき好色のおもかげをも書たるにこそはあれ、此
マ
ト
モ
ノ
リ
セ
メ
ナ
ジ
を実に世の準則と思はんはいとあぢきなく、其を責詰りて
タ
ハ
ケ
ゴ
ト
ナ
カ
グ
チ
ア
ハ
レ
淫奔の媒と誹りたるも、又物の感のいみじきを得知らぬ
なり。
鈴
木
高
軒
宛
書
簡
嘉
永
田
年
二
八
五
二
O源氏物語宜敷注本無御座候に付、何卒こしらへ度兼々存居
候へども、兎角無隙候而もだし居申候。然る処、今般当表
書林之株と申もの、旧に復しかけ候処、ドサクサ致したる
訳合い御座候而、一向に規則相立不申候。夫に付、何事之
上木物も書林手へ受取候事。何方も一切見合居申候。さし
あたり大に困入申候事多く御座候。夫に付、先年少々こし
らへ懸置候源氏の注尺を蔵板に致候つもりにて、此節頻に
いとなみ居申候。注尺の例は契沖、為章、県居、鈴屋のも
のを拠として、愚案をまじへ、湖月抄巳前の注は無拠処計
に少々くはえて(何れも)頭書にし、本文は傍注にて漢字
と俗語とを訳注につけ、素人にもたやすくよめ候様にいた
し申候。外に評語の注をむねと、加へ申候これは先達未発
の説にて候へども、名文の名文たる故を評し著し候にて、
先は拙一家の論に候へども、不得止事しわざにて、文法の
則ともなかれしと思候迄に御座候。よしゃしゃは不知、上
木さへ致候はば、湖月抄は倒れ可申候。併、大部故、一度
にはとても出来不申候。先五六七巻ヅ、一軟として毎年嗣
出候つもりに御座候。然る処、肝腎此
O三文も無御座候。
大に閉口いたし候処、うれ口のよささうなる物に候故、彼
方の蔵板にすれば、金はいかほども出し候と申者、一両人
御座候へ共、それにては、此方之米橿之足しに成不申候。
夫故一案仕候而、万人講の如き事を企申候。大抵一朕金二
歩余に売せ候事故、右冊出来の上一部ヅ、返し候間(可申
見込にて)、二歩ヅ、三四ヶ月借用すると申仕法に御座候。
(下略)
O近藤(芳樹)氏帰郷のよし、留守なりと存候而たえて音信
も不仕候。よく/¥御通置可被下候。その内文通可仕候。
且彼人へは少し申にく〉て、源氏の企不申遣候問、老兄よ
り宣御唱し、ちとにでも世話してくれられ候様、御頼置可
被下候。奉頼上候。静間へもよろしく泰願候。
『
語
釈
』
第
二
巻
序
文
久
元
年
ご
八
六
二
九
月
この六年あまりかほと中風にて手をやみたりけれは板下を
かく事たにえせす源氏の評釈たえむとする事いとうれはしく
かなしかりけりこれによりてさきに彫らせつるちうさくをも
のしてまっかくなん五巻の草子とはなしたる語釈をも別にせ
んとおもひしかとはつかはりのほとなれはついでにこ〉にと
りそへつ次の巻々よりは人の手にか〉しめたれはいたうかは
りたるになん
文久はしめの年なか月
左なからに
20
広道しるす
進行ただいまよりシンポジウム「源氏物語はなぜ読まれるの
か」を開催いたします。
今回甲南女子大学で合同大会を開くにあたり、両学会事務局
で計画を練り、第一日目の行事として「源氏物語」を取り扱う
シンポジウムを開催することになりました。
つきましては、広く一般の方々にもご来場いただくことにな
り、本日を迎えた次第でございます。
まず最初に、司会の日本女子大学後藤祥子先生をご紹介いた
します。あとは後藤先生より講師の先生方をご紹介いたします。
では後藤先生、よろしくお願いいたします。
後藤いまご紹介いただきました日本女子大の後藤でございま
す。きょうはたいへん有意義なシンポジウムになるかと存じま
すけれども、たいへんふつつかでございますが、巡り合わせで
司会をさせていただくことになりました。どうぞパネリストの
先生方はじめ、フロアの先生方もよろしくお願い申し上げます。
それでは最初に講師の先生方のご紹介を簡単に申し上げます。
歴史学というお立場からまず最初にご発言いただきますのは、
膿谷寿先生でいらっしゃいます。同志社女子大学教授でいらっ
しゃいます。
非常にお若いころに「源頼光』(人物叢書)でデビューなさ
って、それ以来『清和源氏』とか、あるいは集英社の「王朝と
貴族」、それから講談社から先年出ました『藤原氏千年』、そう
いったもので、もう皆さんつとによくご存じでいらっしゃると
思います。平安建都千二百年の、これ平成六年でしたか、その
ときには、例の平安京の復元模型の企画にも参加なさいました
り、また平成十年の斎王群行の再現にも力をお尽くしになりま
したり、平安を現代によみがえらせる魔術師としてさまざまな
活躍をしていらっしゃいまして、おそらくお若い方々も、『藤
原氏千年』などで先生のお名前をよくご存じでいらっしゃると
思います。
きょうはその歴史学のお立場から、平安時代の「源氏物語』
を裏から支えた歴史学ということでお話をいただく予定でござ
います。
続きまして、聖心女子大学の原岡文子先生は、「源氏物語両
義の糸」という好著でご存じの方も多いかと思います。また有
精堂の校注叢書で「若紫」のたいへんきめ細やかな注釈でも、
わたしども禅益されるところがたいへん多く、非常に繊細で徽
密な論考に定評がおありになる方でいらっしゃいます。その他、
ポピュラーな源氏特集の監修や構成のお仕事も数多く、いちい
ちは申上げませんけれども、本質を衝いた作品の捉え方で、源
氏物語のみならず、枕草子、更級日記、婿鈴日記など非常に幅
広い活躍をしておいでになります。
続きまして、東大名誉教授・白百合女子大学教授の久保田淳
先生でいらっしゃいますが、もう中世和歌の泰斗としてご存じ
ない方はないかと思いますけれども、ご著書もたいへんに多く
て、何からご紹介したらいいかわかりません。『中世文学の世
界』、『新古今歌人の研究」、そしておそらく『新古今和歌集全
評釈」には、若い学生さんは四年間のあいだに必ず一年くらい
はご恩を被った方が多いんじゃないかと思います。そしてご大
著『中世和歌史の研究』「藤原定家とその時代』、また『中世文
-21-
学の時空』というたいへん幅広いご著書もおありでいらっしゃ
いますが、今回何よりも、先生が中世和歌を表看板に掲げなが
ら、裏側でたいへん恐るべき源氏読みでいらっしゃることから、
この企画にお願い致すことになったのだろうと存じます。先生
には、『花のもの言う』という、エッセイ集にしてはレベルが
高過ぎる新潮選書がございます、そうした中にさりげなく『源
氏』のくまぐまが読み込まれておりまして、わたしども改めて
源氏読みの威力をかいま見るわけでございます。
最後に近世・近現代文学というお立場から、神戸大学の野口
武彦先生にお出ましいただいております。ご著書のほうも近世
の秋成とか馬琴や荻生但係、それから宣長といったお仕事やら、
近代でも石川淳とか谷崎・大江・三島といった大物、さらにそ
のさきの超近代の作家群を縦横無尽に扱っていらっしゃるわけ
ですが、その先生が実は、むしろ三十数年も前から『源氏物
語』に関して、とりわけ萩原広道の源氏読みのすごさについて
わたしどもを稗益なさることたいへん多かった方でいらっしゃ
いまして、きょうもむしろ近世・近現代というお立場にとどま
らずに、いろいろなお話が伺えるのではないかと思っておりま
す。実はきょうの始まりが、十三時二十分からとなっておりまし
たものですから、まだ御到着でない方もいらして、たいへん申
しわけございませんが、いよいよ本番に入らせていただきたい
と存じます。
それではまず初めに膿谷先生から、資料の一ページ目、〈平
安朝の時空から〉と題しまして「『源氏物語』の時代と社会」
ということでお話をいただきたいと存じます。それでは先生、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
幽圃谷蜂谷でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
わたくしは実はここに座っているのは、先ほどからむず痔く
て、正直申しまして『源氏物語』の研究家でも何でもありませ
ん。『源氏物語』を通読したこともございません。ただ平安時
代を語るときに、夕顔の宿りの場所とか、そういう地理的な面
でむしろずるい利用の仕方しかしておりませんけれども、こう
いう席に来させていただいてたいへん光栄には思いますが、わ
たしはむしろここできようは勉強させていただきたいと思いま
して:::。今日の題が「源氏物語はなぜ読まれるのか」という
ことですけれど、わたしにとっては「源氏物語をなぜ読まない
のか」というような題に変えたほうが、むしろわたしにはぴっ
たりの題なんです。歴史のほうからどのようなアプローチがで
きるかということを考えてみますと、準拠論ということになろ
うかと思います。準拠論については、場所論とか人物論とか、
大きく分けてこの二つに多分限定されるのではないかと思いま
すが、もちろんわたくしはこの二つについて、「源氏物語』を
主にしてものを書いたことは全然ございませんけれども、一応
このこつとしていわれるのが皇族賜姓の問題と、それから諸国、
つまり受領の問題があると思います。
それで史料は、これについて全部説明をするということでは
ないんですけれども、一応あり得る史料として、一ページから
六ページまで挙げさせていただきました。それでまず史料の概
略だけ申しますと、一ページに皇族賜姓(賜姓源氏)の史料を
22-
挙げておきました。
それから二ページから四ページにかけては系図と諸国の実態
を知る史料を入れておきました。そして五、六ページには、
『源氏物語」の中に受領というものがどういう形で取り上げら
れているかという、主に中心になるものをいくつか挙げておき
ました。実はこれ、わたしが「源氏」を読んで探したわけでは
なくて、索引とかいろんな方に教えていただいたものを挙げて
みました。特に光源氏のモデルはだれかというときに、皇族賜
姓の問題が当然意識されてくるわけでありますけれど、その皇
族賜姓について、ここでは『源氏』からということではなくて、
当時の史実として一体どういうことがいわれているかというこ
とをご紹介させていただきたいと思います。
一ページのところに、「嵯峨源氏」と書いた、これはわたし
が昔『清和源氏』という本に挙げたその部分を、コピ
1いたし
ました。それからもう一点史料の説明を忘れましたが、きょう
慌てて一枚だけ手書きの含まれた系図をお入れしましたけれど、
(三ページ上段)これは後藤先生に教えていただいたんですが、
「今鏡』の中に『源氏』のことが非常に意識的に書かれている
ということを、初めてわたしは知りました。いままで院政期の
政治史を書くときに「今鏡』は大いに利用しましたけれども、
そういう見方をしたことはなかったものですから、よく読んで
みるとなるほど『源氏物語』を意識している書き方だと思いま
す。作者は『源氏』に非常なあこがれをもっていたのじゃない
かという意識をもちましたけれども、ここではそこまでの話に
は時間の関係で及びませんが、もし話がそこに及んだ場合には、
この系図があったほうが便利だろうということで、きょう慌て
て一枚入れさせていただきました。
皇族の賜姓について、一ページの史料に戻りまして、賜姓源
氏は、嵯峨源氏から始まります。その三行目のあたりに「信ら
八人、これ今上の親王なり。市して弘仁五年五月八日勅により
へぬし
姓を賜い、左京一条一坊に貫す。すなわち信をもって戸主とな
す」とあります。つまり平安京の左京の一条に宅地を与えられ
たわけです。これが賜姓皇族の最初であります。
信の父は嵯峨天皇で、時に天皇は三十歳です。この三十歳の
ときに十人余の皇子女がすでに生まれていますけれども、その
中で八人が源姓を賜って臣下に下った。その中心的な存在が信
ということになります。
これ以後、嵯峨天皇は四十人近く子どもをもうけます。嵯峨
天皇は日本の天皇でいちばん皇子女が多く、五十何人皇子女が
おりますけれども、このときに八人が賜姓源氏になり、このあ
と四十人近くの中から二十四人、臣下に下されております。つ
まり嵯峨源氏としては、一世源氏が三十四人ということですか
ら、五十人のうち、半分以上が賜姓されているということにな
ります。これは嵯峨源氏の一つの特色をあらわすわけです。
二ページの系図で嵯峨と書いたところに源融と書いてありま
すが、これは有名な、やはり嵯峨天皇の皇子で皇族賜姓された
方ですけれども、この融については『大鏡』に有名な話があり
まして:::。陽成天皇が九歳で即位しますが、彼は素行が悪く、
摂政藤原基経によって八年間で天皇の位を降ろされてしまいま
すが、その後、八十何歳まで長生きをするんです。陽成の後だ
-23-
れを天皇にするかというときに、この融が「ちかき皇胤をたづ
ぬれば、融らもはべる」と言った、そういう話が『大鏡」に出
てまいります。
それから特に皇族賜姓で問題になりますのは、「大鏡」に出
てまいります後三一条天皇の皇子に関してということになります。
それは、今日あとでお配りしました系図(三ページ上段)の中
に、ちょっとだけ触れておきますと、後三条天皇と源基子のあ
いだに生まれている実仁・輔仁という二人の親王がおります。
そして後三条天皇には、すでに入っていた藤原能信の養子の茂
子という女性とのあいだにのちの白河天皇が生まれています。
どうも後三条天皇という人は、自ら院政をおこなおうとした
意図が窺われます。自分は早くに位を子の白河天皇に譲ります。
そして皇太子には実仁親王をつけて、どうも後三条の意思では、
実仁のあと輔仁へと、こちらの方へつないでいこうとしたわけ
ですけれども、現実には後三条上皇が一年後に亡くなってしま
って、白河天皇は早くに上皇となって、輔仁親王の方へは譲ら
ずに自分の子どものほうにもっていったという、このへんが
『源氏物語』の真似をしているのではないかというのが、『今
鏡」の作者の書きぶりであります。
それからもう一つ場所論といいますか、諸国に関してですけ
れども、これは三ページ以降に史料を掲げておきました。日本
の国は六十八カ国、大・上・中・下というふうに分かれていて、
それぞれに国司が存在するわけであります。その前にこれら地
方に関する当時の人びとの思いというのを少し見てみますと、
やはり総体的に地方に対しては蔑視感がかなり伴っているとい
うことであります。
例えば例の菅原道真、彼は讃岐守になっていますけれども、
もちろん公卿になる前の話でありますが、讃岐に赴任したとき
に、かの地でつくった詩によりますと、やはり田舎はどうもあ
まり向かないというような口ぶりで歌っています。その中で、
讃岐国の人について彼はこういうことを言っています。この国
の人びとは組野卑賎で将来も暗い、と、ひとことでいうとそん
な言い方もしております。それから『伊勢物語」なんかで見ま
すと、陸奥田の女について作者は「歌さへぞひなびたりける」
という、こういう言い方。歌までが田舎臭いというような言い
方で、あまり好意的な見方をしておりません。
それから時代は降りますけれど、鴨長明は「都の手振りたち
まちに改まりて、ただひなびたる武士に異ならず」と言ってま
す。貴族が武家や庶民のような服装を身につけて、田舎の武士
にも異ならないような言い方、そういう状況を指してこういう
言い方をしているんです。貴族と武士を対照的に挙げ、貴族は
都の、まさに優雅なものであるけれども、武士は都びていてい
けないというような言い方をしております。
それから清少納言は『枕草子』の中で「受領」とか「都ぴ
た」ということばを何回か使っていますが、その中でも地方か
ら送ってきた贈り物の中には、物がなかったら意味がないんだ
と。しかし中央から行ったものは、手紙が添えられ都の情報が
入っているから、それだけでも大きなとりえであるというよう
なことで、おそらく清少納言も地方に対するそういう蔑視的な
意味が、多分盛り込まれているような気がいたします。
-24-
実は、紫式部にしても清少納言にしても、それからこれは一
般的によくいわれていることですけれども、王朝の女流文学の
書き手たちというのは、地方生活を体験している、つまり受領
の娘たちであるということが一つ大きな影響があると思います。
その地方に関しては、四ページの史料をご覧ください。地方
官を任命するのを、除目と雪国いました。そこにも書いておきま
あがためし
したように県召、これは国司を任命するものです。それに対
っかさめし
して司召というのは京官、つまり平安京における官人、律令
官人を選ぶものです。除目というのは、多くの方がおわかりだ
もうしぶみ
ろうと思いますが、申文という自己推薦を基本とする制度に
お
お
ま
が
き
なっています。そして大間書というのがありまして、それを三
ページに入れておきました。これは長徳二年の大間書で、たま
たま残っているわけでして、越前回を見ていただきますと、守
として従四位上源朝臣国盛という人が入っています。そして淡
路国を見ますと、従五位下藤原朝臣為時とあり、これが紫式部
のお父さんでありますが、つまりこれは当初の大間書です。
ところがご承知のように為時は当初、淡路守になったんです
が、これは説話集に出てくる話ですけれども、一条天皇に漢詩
で、淡路という下国の守にしかなれず非常に悲しい、と訴えた
ことで一条天皇そして道長のはからいで越前守になれたという
有名な話であります。
淡路国というのは下国です。それに対して越前固というのは
大国です。これは雲泥の差であります。ご承知のように、大国
から下固まで数もそこに書いておきましたけれども、熟園、つ
まり実入りのいい固からそうでない国とあるわけです。ですか
らみな大国の守になりたい。大国になりますとスタッフその他
を含めて全部ちがうわけですね。しかしだれでも大国の守にな
れるわけではなくて、やはり官位相当というのはそれなりに生
きておりますから、あまり身分が低いのに、大国をねらってい
くら申文を出してもそれは叶わない。だから身分相応のところ
をねらって申文を提出するわけです。為時は下固から大国の守
になったのですから願つでもない結果となったわけです。
いっぽうの源国盛という人はどうなったかといいますと、こ
の国盛は道長の乳母子であったわけですが、おそらく道長は国
盛を呼んで詰腹を切らせたということになろうかと思います。
国盛は実は次の年の春の除目で大国の播磨守になります。それ
はよかったのですが、国盛は播磨守に赴任する前に病死してし
まいます。つまり越前守に決まっていたのに辞めさせられたと
いうことでだいぶショックを受けたということが、どうやら原
因であったろうと考えられます。
たまたま長徳二年の大間書というのが残っていて、そのへん
の状況が非常によくわかるわけです。
それから申文についてですが、これを定められた期限までに
提出します。現在、四十通あまりの申文が残っています。それ
をみますと、それこそ涙ぐましい。自分を売り込むわけですか
らね。それで、中には泣くに泣けないような申文があります。
自分は過去においてこうこうこれだけのことをやってきた、ど
こどこの国司も歴任した、と自分の功績を称えながら肝心の自
分の名前を書き忘れているもの。これはもちろん不備な書類で
すから、はねられてしまいます。
-25-
これらの申文を除目のときまでにまず役人が調べて、不備な
ものは除外してしまいます。つまり今言ったような名前の書き
忘れとか、あるいはやってもいないのにどこどこの守をやった
とか、そういう類のものは外してしまいます。残ったものを公
卿会議にかけるわけです。
公卿会議によって決めるわけですが、そういうときに大きな
力をもつのが、つまり紫式部の時代だったら道長ということに
なります。道長の『御堂関白記』という日記を見てみますと、
「志:::」、つまり志すというのが盛んに書いてあります。いっ
てみれば、みな付け届けをするわけですね。道長に恩をうって
おけば次の除目のときにはお目こぼしがあるということで、み
な道長のところへいろんな物を、任国からもつできたりとか、
京にあってもいろんな物を付け届けしております。道長の土御
門殿という屋敷は、いまの京都御所の東、仙洞御所の北辺あた
りにあったわけですが、あのあたりでは、今流に申せば、朝か
ら晩までクロネコヤマトの宅急便が往来していたというような
現象だったと思うんですね。そういうことで、今よりも大っぴ
らにギプ・アンド・テイクの時代がこのときあったということ
なんです。
ところで、任国に入るのにどういう旋があるかということは、
四ページの上段「国務条々事」というのに記述があります。こ
れは実に四十二カ条にわたって、国司になったらこれこれこう
いうことをしなければならないという教訓めいたことを記して
います。そのうちの五ケ条だけを挙げておきましたが、もう時
聞がないので一つだけ読んでおきます。最初のところにありま
す「揮吉日時入境事(吉日時を択んで境に入る事こというと
ころですね。つまりいい日を選んで国境に入りなさいというこ
となんですが、「在京之問、未及吉日時者、逗留漫下(在京の
問、未だ吉日に及ばざる時は辺下に逗留)」。辺下というのは、
いい日までは国境で足踏みしておけということなんですね。そ
して「其間官人雑仕等、慮外来着(その問、官人雑仕ら慮外に
来着ごと。その聞にこんど赴任する国の官人たちがそこまで
出てくるということですね。で「令申事由者(事の由を申さし
むてへりごと、いろいろ事情を話させて、次に原文では「随
鋭(乱に随い)」といっているけど、「乱」では意味が通らない
ので、国史大系本の頭注にあるように「形」とすべき。「随形
召上(形に随って召し上ぐこと。形式どおりにそれを招けと
いうことですね。そしてまず「可同国風(国風を問うべしと
といっています。国風というのはその国はどういう状態か(人
口、特産等々)を国人から聞いて予備知識として仕入れておけ
ということなんですね。で「但可随形(但し形に随うべしご
と。それも形式どおりにやりなさいと。「専不可云無益事(も
っぱら無益のこと云うべからず)」、いらんことをべらべらしゃ
べってはいけない。「外国之者(げこくの者)」、つまり新しく
さかむか
赴任するそこの国の人びとは「境迎之日(境迎えの日こにそ
こへやってきて「必推量官長之賢愚(必ず官長の賢愚を推量す
べしごと。官長というのは国司のことです。つまりその境迎
えの場所に、こんど赴任する先の人たちがやってきて、こんど
の国司は利口か愚鈍か、そういうことを必ず見るから、無益な
ことはしゃべってはいけないんだと。必要なことだけを知識と
-26-
して得て、国に入りなさいといようなことをいっているわけで
す。こういう形で四十二カ条ずっとあるわけですね。
ですから、国司になってもなかなか大変なんですけれども、
一般に言われることは、もう地方に行くのは皆いやなんだけれ
ども、何が目的かというと蓄財です。実入りのよい国の受領を
何カ国かやると、大金持になります。受領たちは任国で得たも
のを京都の蔵に運ぶということがおこなわれます。大江匡房で
したか、九州の大宰府の役人をやったあと、「道理にてとりた
る物」と、「非道理にてとりたる物」を、それぞれ船に載せて
運んだら、後者の船だけが着いて、前者は沈んでしまったと。
世も末だという、これは説話集に出てくる話なんですけれど、
そういうことが当時おこなわれていたわけですね。
地方というのはこのような状況にあったということなんです
けれど、『源氏物語』に現われた受領については五ページから
六ページにかけて挙げておきました。物質的には豊かだけれど
品位がないとか、そういうことを盛んに言っております。もう
地方というのは全く、というような見方を、どうやら中央では
していたような形跡が、こういうところから窺えるようであり
ます。次
に、この「源氏物語』の中の受領関係の史料の中で、
Aか
らMまでございますけれども、例えばGなんかを見ますと、こ
れは「蓬生」の巻なんですけれども、やっぱり受領の北の方に
なるのは落ちぶれ者という言い方をしております。
それから「玉重」の巻で、玉重が九州で育って、京都に上が
ってくるときに、大夫監という人に求婚されるけれども、もう
なんとかぼうぼうの体で逃げてくるということなんですが、あ
の大夫監の書き方は、決していい書き方をしていません。非常
に組野だと。金はもっているけど粗野だという言い方をしてい
ますけども、中央から見たらそういう見方になるんでしょうね。
しかし彼は大宰監ですから、小弐の下、つまり大宰府の在地役
人としてはトップクラスに近いということです。上から三番目
ですからね。ですから彼が威張るのもわかるし、向こうにとっ
ては名門なんです。ただそういう人たちでも中央から見ると、
やはり下だという見方が「玉軍」の中にも出てまいります。そ
れで確か長谷寺に詣でたときに、大弐の北の方にならなくても、
大和守の北の方だったらいいというようなことを言っています。
大和国は大国で、しかも都から近いということが大きな条件で
すので、大和はそういう意味では畿内であって大国ですから、
だれもがねらうということになるわけですね。そういう話がや
はりこういうところにも初傍としてまいります。
それから『源氏物語』の中でちょっと地方のところを見てみ
ますと、紫式部なんかも「都ぴた」とか「田舎びた」とか、そ
ういう言い方をいろいろしていて、決してよい言い方をしてい
ません。ただしわたくしは、「源氏物語』の中にあらわれてい
る地方の描写というのは、ほとんど越前国で彼女が体験したも
のだろうと思うんですね。それから清少納言が『枕草子』の中
で地方のことを書いたりしていますけれど、彼女の知識は、お
父さんが周防守になったときに、確か彼女は十歳ぐらいだった
と思うんですが、そのときに実際に周防固で生活しています。
ですから、おそらく彼女の『枕草子』の中における地方という
-27-
のは、周防国だろうと思うんですね。
そういう意味では、準拠論の中でも場所論と人物論と二つあ
りますけども、場所論というのは紫式部が五条のあたりのこと
を夕顔の宿りの中で書いていますが、場所論としてかなり写実
的に書いているんじゃないかと思います。『源氏」をよく読み
込まないでこんなことをいうのは不謹慎かもしれませんが、そ
ういう気がいたします。
人物論はいろんな人をミックスして書いていると思うんです
ね。それで、なぜ『源氏物語』といって「藤氏物語」といわな
いのかとか、これは後でわたしはむしろ、この話が終わったら
そっちの席へ行ってここにおられる先生方にいろいろ聞いてみ
たいのです。ただ地方のことで最後にひとことだけ付け加えて
おきますと、中央から固に官符が出され、そして国から郡(国
符)、郡から村などへ(郡符)というのは『類取県三代格』など
から知られていましたが、これは形式だけであって、実際には
行われていたか否かはっきりしなかった。ところが先ごろ石川
ぼ
う
じ
さ
っ
せ
い
さ
つ
県の津幡町の加茂遺跡から勝示札(後世の制札)が発見され、
現実であることが証明されたのです。あれは九世紀中期の年紀
のある加賀国から加賀郡に宛てたのをうけ、郡から村へ宛てた
ものなのです。そこにはどういうことが書いてあるかというと、
朝から晩まで働けとか、お酒を飲んでも酔って過ちをおかすな
とか、いろんなことの禁止が書いてあるんです。
この発見により、今まで百姓たちは朝から晩まで働かされ、
あとは寝るだけといったイメージでとらえられていたけれど、
決してそうではなく、百姓たちもお酒を飲み騒ぎなどといった、
けつこう自由にふるまったことが知られるわけです。今後の古
代史に大きな影響を与える大発見と言えるでしょう。
最後は『源氏』から、最初からあまり『源氏』にかかわって
いませんけど、よけい離れてしまいましたけれど、最近の発掘
のニュースを取り混ぜてちょっと諸国の話と、それから最初に
皇族賜姓の話をさせていただきました。どうもありがとうござ
いました。
後藤膝谷先生、どうもありがとうございました。遅く見えた
方からはわたしども恨まれそうでございますけれども、きょう
の予定から申しますと、一時三十五分くらいから、ちょうどい
まぐらいから膿谷先生のお話が始まるはずだったんでございま
す。いろいろな関係で少し前のほうに押しておりまして、これ
はむしろ後半でフロアの先生方からのご質問をいただく時聞を
たっぷり取れると、一つは楽しみでもございますが、最初お聞
き落としになられました方々にはお詫び申し上げます。
牒谷先生からは、いまお聞き及びのように賜姓源氏の、賜姓
制度の出発点のお話、それから「源氏物語』の背景が非常にリ
アルであるというところから、除目や受領のお話、そして作者
の父親の為時の越前国赴任直前のドラマといったようなことに
ついてお話をいただきました。のちほどご質問いただきます。
それでは続きまして、原岡文子先生から「源氏物語はなぜ読
まれるのか」ということでございます。最初にちょっとお断り
申し上げておかなくてはいけませんでしたのは、「なぜ読まれ
るのか」というテ
1マが出されましたときに、わたしはたいへ
んうろたえまして、「なぜ読まれるのか」は、魅力があるから
-28-
だということで話は尽きてしまうのではないかという恐れがご
ざいましたものですから、先生方に自由にお考えいただいて、
「なぜ読まれるのか」と、あるいは「どう読まれてきたのか」
と、そこらへんは先生方にお任せ申し上げますので、ご自由に
なさってくださいというような余計なコメントを申し上げまし
たために、多少混乱を来したかもしれませんけども、その中で、
原岡先生は、できるだけこの所期のテ
lマ、「なぜ読まれるの
か」ということに沿ってお考えくださったようでございます。
それでは先生、よろしくお願い申し上げます。
原岡原岡でございます。
いま牒谷先生から、非常にリアルな、歴史的な背景、あるい
は場所に関してのお話で、||たとえば、五条の夕顔の宿のあ
たりについて、非常に写実的に記事が進められているというふ
うなお話がございましたけれども、私はそこに書きましたよう
に、『源氏物語』の中の「細部」の力||何かわけのわからな
いことが書いてあるなあとお思いかと思いますけれども、ーー
について少し考えてみたいと思います。
具体的に申しますと、「源氏物語」の中の細部の力というこ
とにつきまして、紫の上に関する叙述を中心に少し考えてみた
いと思っております。
これはさっき後藤先生がたいへんうまく説明してくださった
のですが、研究者であるよりも、むしろ愛読者として「源氏物
ヨ巴に関わってきた者として、一人の愛読者の立場からここで
は話をさせて頂く、というふうに考えていただければ幸いでご
ざいます。
『源氏物語』というのは、「主題」を考えてみますと王権の
物語、あるいは恋の物語、またそこから出てくる罪の問題に仏
教が関わってくるということで、王権とか恋とか仏教(仏道)
というふうに括ることができるのだと思いますけれども、そう
括ってしまいますと、そこからこぼれ落ちてくる細部の輝き、
あるいはその中に込められたリアリティというものがあるよう
に思うのです。
六頁の資料の①のところに新編日本古典文学全集『源氏物
語巴の月報の大庭みな子氏のエッセイをちょっと挙げておきま
したけれども、傍線のところに「この物語の命の長さは、もし
かしたら、本筋よりはこうしたとりとめのないこぼれ話、何げ
ない肱きのリアリティにあるかもしれないのだ」とあります。
「何げない咳きのリアリティ」、あるいは「わざとらしい話の筋
からはみ出た磐の細部」というふうなことばが使われています。
あるいは①の真ん中のあたりですけれども、「表向きの筋の
合聞に作者がしっかりとその目で見届けたこの世のさまを、恐
ろしいまでにまことのままに描きとどめた筆の力に誘われて、
長い年月を読者は読みついで来たものであろう」というふうな
ことが言われております。
私はこのエッセイを読みましたときに、たいへん共感してし
まい、愛読者の一人として「源氏物語』に心を惹かれてきたと
いうことについて、なぜなのだろうかと考えたときに、やっぱ
りこのことが一つ大きなこととして関わってくるというふうに
思わざるを得なかったのです。なお細部の力、魅力の問題につ
いては、既に三十年以上前に『源氏物語論」(筑摩書房一)の中
-29-
で、竹西寛子氏が関連する言及をされています。
いま申しました細部、あるいはリアリティということを頭に
置いたうえで、それではその「源氏物語』のほぼ同時代の資料
は、それをどんなふうに受け止めているのかということなので
すが、七頁の②、③に挙げましたのは『紫式部日記』と『更級
日記』で、これはもう挙げるまでもないような資料だと思うの
ですけれども、『紫式部日記』の中で公任が「このわたりに、
わかむらさきやさぶらふ」、||このあたりに若紫さんはいら
っしゃいませんかという形で紫式部に呼びかけている。公任が
少なくともあたかも現実に生きる一人の人間のように紫の上と
いう人を、非常に身近に現実的に、リアリティのあるものとし
て捉えていた。これは戯れの呼びかけということで考えますと、
やや割り引きしなければいけないということはもちろんあるの
だと思いますけれども、少なくともそういうことばが出てくる
のです。
あるいは『更級日記』の中で孝標女は、年頃になったら「光
の源氏の夕顔、宇治の大将の浮舟の女君のやうにこそあらめ」、
つまり浮舟とか夕顔のようになりたいわと、考えている。これ
もやはり非常にリアルな、現実のものとして物語の中の登場人
物を捉えている、ということなのではないだろうかと思います。
④のところに出しましたのは「無名草子』です。もちろん鎌
倉という少々時代の下る資料なのですけれども、この中に「ま
ことし」ということばが八例出てまいります。資料の④の
aか
らfのところまで八例挙げておきましたけれども、「無名草子』
の中では「まことし」という言葉が例えば「余りに唐土と日本
と一つに乱れ合ひたるほど、まことしからず」とあるように、
「まことしからず」とか「まことしからぬ」という形で使われ
ている。つまり『狭衣』であるとか「浜松』とか『とりかへば
や』、「海人の刈藻』、あるいは「狭衣』『寝覚』といった物語に
ついて、「まことしからず」というふうに批判しているのです。
逆にそれは、それらの物語が「まことしからぬ」物語であると
述べることで、『源氏物語』が非常にリアルな「まことし」と
いう物語であることを、証し立てるような仕掛けになっている
というふうに考えることができるのではないでしょうか。
例えば④の
a、源氏が准太上天皇になったということに関し
て、「源氏の、院になりたるだに、さらでもありぬべきことぞ
かし。されども、それは正しき皇子にておはするうへに、冷泉
院の位の御時、わが御身の有様を聞きあらはして所置き奉り給
ふにであれば」という形で、狭衣が即位したということに対置
させるとき、源氏が准太上天皇になったということについては、
非常に現実的な状況、現実的なリアルな書き込み方というのが
周到に用意されているという述べ方を、『無名草子」はしてい
ると思うのです。
ついでに「無名草子』の中で眺めわたしてみますと、今度は
同じ資料の
gから
qのところまで挙げましたけれども、紫の上
に関する叙述というのが十四例出てまいります。ちなみにほか
の女君をどのぐらい挙げているかということを見てみますと、
明石、夕顔、玉軍が各三例、葵の上が四例、あるいは浮舟や六
条御息所は一例で、女三の宮だけが七例なのですが、こういっ
た状況というのを考えてみますと、『無名草子』の中で紫の上
30-
という人物は、非常にある種のリアリティを持った、といいま
すか、感情移入することができるような人物としてとりわけ大
きく取り上げられているということが言えるのではないでしょ
うか。「いとほしき人」とか「めでたき人」とか、あるいは
「いとほしきこと」とか「心やましきこと」とか、さまざまな
トピックのもとにこの人物が、集中的に取り上げられていると
みることができそうです。
そんなふうに眺めわたしてみたところから、その物語の細部
のリアリティということ、それを紫の上をめぐって、少し考え
てみょうかと思うのです。「無名草子』の中の「まことし」に
ついては、最近島内景二氏が出された、『源氏物語の影響史」
(笠間書院)という大きなご本の中でも触れられていたことを
付け加えます。
そんなことを頭の隅に置きながら、具体的に、それではどん
な形でそれを跡付けるかということなんですけれども、九頁資
料⑤のところに出しましたのは、「源氏物語』の「若紫」「葵」
の用例です。十頁⑥は一葉の「たけくらべ』なのですが、今日
は「たけくらべ』の『源氏物語』受容というところから何か手
掛かりが出てこないだろうか、と、そんなことで少し話をさせ
ていただきたいと思います。
『たけくらべ』の源泉につきましては、これまでいろいろな
ことが言われています。まず幼なじみの恋という意味で、「伊
勢物語』の二十三段、筒井筒の章段というのが踏まえられてい
る。あるいはまた「若紫」の巻の叙述が踏まえられているとい
うことも指摘されています。⑥の
cの用例の中に、「今様の按
察の後室が数珠を爪ぐって、冠つ切りの若むらさきも立出るや
と思はる〉」とのことばが出てまいりますけれども、ここのと
ころにはっきりと「冠つ切りの若むらさき」と、「若紫」の姫
君に重なることばが出てくるわけです。
それからまたいわゆる美登利の変貌。たいへん元気のよかっ
た美登利が淑やかな女性に変貌していく、いわゆる美登利の変
貌といわれている部分、そこのところが「葵」の巻の紫の上の
新枕に重なってくるのではないだろうかということで、このこ
とは既に早く長谷川時雨などにより指摘されています。
そんなふうなさまざまなことが源泉として挙げられるわけで
すけれども、こうした事柄を踏まえながら、もう少し細かく見
ていくことができるのではないだろうかと思うのです。
まず第一に、『たけくらべ』の枠組みというものが、「若紫」
から「葵」の巻へという、その巻の流れの中に出てくる紫の上
が子どもから大人になっていく変化という、ここのところと対
照されるのではないだろうかと考えます。
「たけくらべ』に関しましては、前田愛氏が「子どもたちの
時間」(「樋口一葉の世界』前回愛著作集三、筑摩書房・平元)
という、非常に魅力的な捉え方をされています。『たりくらべ』
の登場人物たちは、「遊戯者としての子ども」と、名づけられ
るのですが、その子どもというのは、明るい未来を閉ざされて
いるからこそ大人の世界に繰り込まれる前に、つかの間の自由
を楽しむという、そういう子どもたちとして現われると述べら
れます。そして『たけくらべ』というのは、「子供中間の女王
様」として、大音寺前の子どもの遊びを主宰していた美登利が、
-31一
酉の市の祭り(マツリ)をきっかけに、もう一つの遊び(アソ
ビ)の空間に迎え取られる、そういう過程を描いた物語なのだ
と、そうした意味で子どもたちの時間というものが描かれてい
る。そのような読み取りがなされています。
『源氏物語』の「若紫」から「葵」の巻へというこの時間、
これは子どもたちというよりは、むしろ「子どもの時間」とい
うふうに申し上げたほうがよろしいのかもしれませんけれども、
非常に元気で、と申しますか、||以前に拙いもの(「紫の上
の登場」『日本文学』平成六・六月)をまとめたことがありま
すがーーに秩序に抗つてはばたく命の輝きにあふれる、反秩序
的な一つの力といいますか、パワーを持っていた小さな子ども
の、十歳ほどの紫の上が、やがて結婚という形で大人の秩序、
性をめぐる秩序の中に組み込まれていく。その時間というのが、
「若紫」から「葵」の中に織り込まれているというふうに考え
ることができるのではないだろうか。そうするとそれがすっぽ
り『たけくらべ』の枠組みの中に生かされているということが
考えられはしないだろうか、というわけです。
もう少し具体的に見てまいりますと、女主人公のキャラクタ
ーということなのですが、まず小さな紫の上、若紫のキャラク
ターに注目したいと思います。資料の⑤
aのところでご覧いた
だきますと「走り来たる女子」、走ってやってきた女の子とい
うわけです。そして「顔はいと赤くすりなして立てり」という
ふうに、泣いた跡が見えるような女の子、そしてそのことにつ
いて「童べと腹だちたまへるか」(けんかしたの?友達とて
という問いかけがなされていますけれども、けんかをして怒っ
て泣いている紫の上、そんなふうな形で出てくるのです。
あるいはまた「眉のわたりうちけぶり」、これは、「引き眉」
という大人の女性のお化粧をする以前の、生まれたままの眉の
紫の上、ということなのだと思いますけれども、そうしますと、
大人の秩序の世界の中に組み込まれていく以前の、まだ自在な
命の輝きを、子どもたちとの遊びの中に、||「あまた見えつ
る子ども」ということばも出てまいりますけれども||発揮し
ているような、そういう紫の上というのを見出すことができる。
決してお淑やかな、よそ行きのお洋服を着た「お嬢さまの紫の
上」ではないのだということを見ることができるかと思います。
美登利のほうを今度は跳めてみますと、さっきちょっと申し
ましたように、⑥
aに「子供中間の女王様」ということばが出
てまいります。あるいはその一行前のところに「身のこなしの
活々したるは快き物なり」とあって、非常に元気なキャラクタ
ーです。
それからまた⑥b、これはけんかの場面で、「意趣があれば
私をお撃ち、相手には私がなる」など、見栄を切るというふう
な美登利の姿が出てまいります。ここのところなどは、もしか
したら張りと意気地の、例の江戸の遊郭の遊女というふうなこ
とがむしろ反映しているのではないだろうか、とも思われ、ま
た『修紫田舎源氏』で紫という禿に紫の上が置き換えられてい
る、といったところとも関わるのだろうかという気もしますが、
ともかくここでもとても元気にけんかをして見栄を切る、そう
いう美登利が出てまいります。
そういう美登利に関しまして、例えば⑥の
gのところでは、
-32
きゃん
美登利のお母さんが「今にお侠の本性は」と、「お侠」という
ことばを
gの終わりから四行目のところで使っております。そ
んなふうにまず元気な美登利、元気な紫の上ということでキャ
ラクターが重なってくるということがあるのではないでしょう
.刀
それからもう一つ、その元気な子どもから大人へ、という変
化に関わって、髪の描写を顧みたいと思います。⑤の
a「髪は
扇を広げたるやうにゆらゆらとして」とあるのが紫の上の髪形
で、一方⑥の
aのところを見ますと、「解かば足にもとまくべ'ν
品目r
き毛髪を、根あがりに竪くつめて前髪大きく髭をもたげの、務
熊といふ名は恐ろしけれど」と、美登利の髪形がまず言及され
ているのです。そしてやがてその美登利が変貌していく。
eの
ところで「初々しき大島田、結綿のやうに絞り放しふさ/¥と
懸けて」という、ここで髪形が変わる、髪が変わるという形で、
その美登利の変貌というものが特徴づけられているというわけ
です。ま
た新枕の場面で、資料には、省略してしまいましたが、
「汗におしひたして、額髪もいたう濡れ給へり」と、ショック
のあまりに紫の上の額髪が濡れている、汗で濡れているという
描写が出てまいります。
それに対して『たけくらべ」ではこんな描写が出てまいりま
す。「まだ結ひこめぬ前髪の毛の濡れて見ゆるも子細ありとは
しるけれど」とあって、「前髪の毛の濡れて見ゆるも」という
形で、髪の毛が一つのショックの中で濡れているという描写が
出てまいります。そのあたりの対応というのも考えることがで
きるだろうというわけです。
さらに⑤のb、ここのところで光源氏が紫の上の髪を削ぐ、
髪を整えたという描写が出てくるのですけれども、これは、結
婚を前にして、いわば髪上げに当たるような一つの結婚への儀
式というのを、ここで光源氏が行ったというふうに考えること
ができるのではないだろうか、そんなことを柳井滋氏(「紫の
上の結婚」『平安時代の歴史と文学』吉川弘文館・昭同)が以
前に述べておられます。そうすると髪ということが、子どもか
ら大人へということに関わって「源氏物量巴の中では一つのポ
イントとなって出てくるのですが、それが「たけくらべ』の
「楯熊」から「大島田」へ、という描写に置き換えられている
というふうに考えることができるのではないだろうかというこ
とですね。
さっきのところでもちょっと申しましたけれども、集団の遊
びということを、次に考えてみたいと思います。「たげくらべ』
というのは、子どもたちの時間、子どもたちの遊びの時間とい
うことで、美登利とその仲間、正太郎であるとか信如であると
か長吉であるとか三五郎であるとか、こういった子どもたちが
たくさんの遊びをする。お神輿とか幻灯とか、知恵の板とか十
六武蔵とか細螺(きゃしゃご)はじきとか、それからけんかを
したりする、といった自在な遊びが、いろいろ出てくるのです
が、それに対しまして、「源氏物語』の中で、紫の上は「雛遊
び」をする女の子として出てくる。そしてまたその遊びは、
a
のところでも「あまた見えつる子ども」という、たくさんの子
どもたちの中で紫の上が一緒に遊んでいる、という形で出てく
-33-
るのです。
また「紅葉賀」の巻のところでは、ドールハウスを作って紫
の上が遊んでいるところが出てくるのですけれども、そこのと
ころでも犬君が、このドlルハウスを「傑やらひ」の真似をし
て壊してしまった、だからそれを一生懸命繕っているというふ
うな話が出てまいります。そうすると犬君などと一緒になって
元気に遊んでいる紫の上というのが紡御することになります。
ところがその合間合間に、今度はそういう遊びの中に、紫の
上が光源氏と一緒に遊ぶ、光源氏と碁打ちゃ偏継ぎをしたり、
あるいは雛遊びをする、そういう場面が紛れ込んでくるという
ふうな形になっております。
この紫の上の雛遊びの問題に関しましては、川名淳子氏、森
野正弘氏、中西紀子氏、そして田辺玲子氏などがいろいろなこ
とを既に述べられています。特に田辺氏の御論(「少女期の紫
の上」『窪麦』平十・九月)では、『たけくらべ』との関わりに
も言及されていますが、それらの諸論に導かれて、まとめてみ
ますと、紫の上をめぐる集団の遊び、そしてその中にだんだん
に源氏と遊ぶという場面が出てきて、それからやがて大人にな
っていくという、こんな形になっているのだと思います。
ともかく紫の上は、集団で遊ぶ女の子だったということ、そ
のことが「たけくらべ』の子どもたちの時間の中に、もう一つ
流れ込んでいっているのではないだろうか、と考えます。
ついでに申しますと、紫の上が「雛の棄てがたきさま」、つ
まり人形遊びがなかなか捨て難いものに思われる性分なんです
よというふうなことを、「若菜上」の巻で女三宮と初めて対面
したときに語るのですが、ここのところの「雛遊び」というの
は、たいへんアイロニカルな意味で使われているというふうに
多分考えられると思います。自在な、自由な輝かしい子どもの
時聞を担っていた「雛遊び」が、もはや、「結婚」の制度や秩
序の中で伸吟するしかない、紫の上のことばの中に現れること
で非常にアイロニカルな意味が漂い出す、ということだと思い
ます。『
たけくらべ」のほうで眺めてみますと、変貌した美登利が
「何時までも何時までも人形と紙雛様とを相手にして飯事ばか
りして居たらば撫かし嬉しき事ならんを」という形で、その子
どもの時間というのを、「人形と紙雛様とを相手にしてままご
とばかりしていたら、どんなにか:::」という、そういう時間
として述べているというふうに、押さえることができるかと思
います。そういう幾つもの対応・対照というのが、この作品の
聞には横たわっていると考えられます。
そして、そんなふうに『源氏物語』を受容しているというこ
とを『たけくらべ』がむしろ種明かししたのが、その「冠つ切
りの若むらさきも」という叙述なのだと、考えていいのではな
いでしょうか。ここのところの視線の構造は、ちょうど「若
紫」の垣間見と逆になっている、つまり美登利のほうが信如を
見ていて、という形で逆転しているのだということを、既に前
田愛氏が述べておられますけれども、こんな形で『たけくら
べ』は『源氏物語』受容を種明かししているとみることができ
るのではないだろうかということになります。
ここで話をちょっと元に戻してみますと、細部といったとき
-34-
に、いろんな細部があると思うのですけれども、主題、さっき
の王権とか、恋とか、そういうことにもろに結びついてくる細
部の輝きというのももちろん大きいのだと思います。ところが、
もう一っそこから逸脱してくる細部というのもやはりあるよう
な気がするのです。
紫の上がここでどうして登場してきたかと申しますと、藤査
に生き写しである、藤査への恋、その身代りということから掘
り起こされています。だとしたら、ここでは紫の上は淑やかな
美少女、藤査にそっくりの、美しい姫君、という形で出てくれ
ばべつに差し支えなかったのではないだろうか。ところがそこ
のところに、子どもから大人へという一つの時間というのが、
非常に詳細に織り込められている。藤査思慕ということとは直
接に関わらない、そこから逸脱してくる細部のカというふうに
私が思いますのは、そういう理由からなのですが:
『源氏物語』というのは、こういう細部を描くことによって、
私どもが持っている、すぐれて個別の体験といいますか、ーー
具体的に『たけくらべ』ということで申しますと、樋口一葉が
竜泉寺町で荒物とか駄菓子などを商った小さなお庖をした、そ
の時に実際に見聞した、非常に具体的なかけがえのない個別の
出来事というのがあるのだと思いますが||、そのかけがえの
ない個別の出来事に『源氏物語』がぶつかったときに、何かを
スパークさせる力をもっている、一つの物語というのを触発す
る力を持っている、ということが言えるのではないだろうかと
そんなことを、ちょっと考えてみたかったわけです。
もう時聞が残り少なくなりましたが、次の十一頁⑦のところ
では、歌の問題を少し考えてみました。『源氏物語』の細部と
いったときにはやはりことばの問題、||そしてそれは歌こと
ばということにつながってくる部分が大きいのだと思いますけ
れども||、そのカというのがやはり非常に大きな要素をもっ
ているということが言えるのではないでしょうか。今の『たけ
くらべ』のところでは主として髪ということを問題にいたしま
したけれども、もっと大きな部分で歌ことばの問題というのが
多分関わってくるだろうと思われます。ここではちょっとそれ
を考えてみたいということなのですが、⑦の
cの紫の上の亡く
なる場面で「まことに消えゆく露の心地して」と、露に喰えら
れているというところがございます。例の国宝「源氏物語絵
巻」の元になっているたいへん有名な場面ですが、その紫の上
の死は、「露が消えるように」という比喰によってかたどられ
ています。
その直前のところで、「おくと見るほどぞはかなきともすれ
ば風にみだるる萩のうは露」(⑦b)とあって、ここで萩の露
というふうなことばが使われています。この連想で、露の消え
るという、これはごく自然な、当たり前といえば、その通りの
ことだと思うんですけれども、実はその前にも一つ痕跡があり
まして、それを
aのところに挙げておきました。「若菜下」の
巻で、紫の上が大病の後危篤にまで陥って、そして蘇るという
場面、ここでも「消えとまるほどやは経べきたまさかに蓮のつ
ゅのかかるばかりを」と、実は露ということばが使われている
ということがあるのです。歌ことばの連鎖というものが非常に
周到に調えられている、と言えるのではないだろうかというこ
-35-
とです。もちろん露というのははかなさの象徴として歌の中で
の伝統をもっているわけで、当たり前といえば当たり前なんで
すけれども、こんなふうにちょっと直前に出てくるから「露の
心地して」ということではなくて、非常にその連鎖というもの
が周到に調えられているということが、この「若菜下」の巻の
用例を見ることによっても検証できるかと思います。
そして、また「萩の露」ということですが、これも歌の中で
一つの定型になっている萩、露、それからまた鹿、という組み
合わせを踏まえながら、紫の上の詠んだ歌が、「おくと見るほ
どぞはかなきともすれば風にみだるる萩のうは露」です。この
歌には、実は影響を与えた、それ以前の歌があったのではない
だろうかというふうなことを、寺本直彦氏が『源氏物語受容史
論考続編』(風間書一房・昭五九)の中で既に指摘しておられ
ます。「
拾遺集』に村上天皇が中宮を亡くされた時の歌というのが
出てくるのですけれども、詞書がついていまして、「中宮隠れ
給ひての年の秋、御前の前栽に露の置きたるを、風の吹きなび
かしけるを、御覧じて」とあります。その詞書に続くのが、
「秋風になびく草葉の露よりも消えにし人を何にたとへん」と
いう歌なのですけれども、これがこの紫の上の歌の中に流れ込
んでいったものだと寺本氏は捉えておられます。村上天皇の歌
を踏まえ、この印象深い紫の上の歌が出てくることになるとい
う展開です。
そして一方実はこの紫の上詠が同時代の和歌である、和泉式
部の歌の中に影を落としているのではないだろうか、とこれも
寺本氏が既に述べておられます。『和泉式部集』の歌なのです
が、小式部内侍が亡くなった後に「宮より、露おきたるからき
ぬまゐらせよ、経のへうしにせむ、とめしたるに、むすびつけ
たる」「おくとみしつゆもありけりはかなくてきえにし人をな
ににたとへむ」という、歌が残されています。上東門院から、
生前小式部の着ていた「露おきたる」唐衣を、供養のため経の
表紙にしようという、お召しがあった時、和泉式部は「おくと
みしつゆもありけりはかなくてきえにし人をなににたとへむ」
と詠んだのです。つまり娘を失ったあとの和泉式部の心情とい
うものが、この紫の上が詠んだ歌というものに触発される形で、
詠まれているということになるのでしょう。これは、ほぽ同時
代の二人の歌として、どちらが先なのかというのが多少問題が
残るところだと思いますけれども、寺本氏の論考の中では、紫
式部の歌が和泉式部の歌を掘り起こしているという見解が取ら
れています。
紫の上のこの歌をめぐって同じような現象をもう一つ挙げる
ことができそうです。「源中納言懐旧百首』という、源国信の、
堀河院追懐の歌を集めたものの中に「萩にをける露と消えにし
君が身を白玉とのみたのみけるかな」と、このような歌が出て
くるわけです。
そうしますと、久保田先生も「『源氏物語』と藤原定家、親
忠女及びその周辺」(『源氏物語と和歌』武蔵野書院・昭五七)
で述べておられることですが、当時の歌人たちというのは、お
めでたいこと、そしてまた悲しいことに出会ったときに、『源
氏物語』の中の歌であるとか場面であるとか、そういうものに
-36-
触発されて歌を詠むということがあったのではないだろうか。
こんなふうに跡付けることができるのではないかと思うわけで
す。そうしますと先ほどの話にちょっと戻りますが、『たけくら
べ』も、また歌についても、個別の状況の中に生きる私どもの
中で、その個別の体験が新たに一つの小さな物語として蘇るよ
うな、そういうものを触発するような、そうした力を『源氏物
韮巴は持っているというふうに考えることができるのではない
でしょうか。これが、長く広く『源氏物語』が読み継がれてき
たことの一つの理由として考えてもいいことなのではないだろ
うか、ということなんですね。
最後にひとことだけ付け加えさせていただきますと、
-11こ
れから先は私の本当のモノローグなんですが、ジェ
lムズ・ヒ
ルマンというユング派の心理学者が『原型的心理学』(河合俊
雄訳・青土社・平五)という本の中で、「魂ということでわた
しが意味しているのは実体よりもむしろ観点であり、物そのも
のよりもむしろ物に対する視点である」ということを述べられ
ました。魂に関わるイマジネーションというのは、事象を自分
自身の経験へと深化させるということなんですけれども、そう
しますと『源氏物語』の中のことばであるとか、書かれた細部
というものは、その意味で魂にかかわるイマジネーションを触
発するということになるかと思います。個別のかけがえのない
小さな物語、ー11それは、だれでも『たけくらべ」が書けると
か、すてきな歌が詠めるとかということでは決してないのです
けれどもーーでもかけがえのない一人ひとりの小さな物語を個
別の心の中に紡ぎ出す、あるいは喚起する、構築させる、そん
な力を『源氏物語』は持っているということを考えることがで
きるかと患います。
長くなって申しわけなかったんですけども、ありがとうござ
いました。
後藤原岡先生、どうもありがとうございました。非常に大き
な、しかも本質的な問題を提起されて、少し早く始まったもの
ですから、このへんも聞き落とされた方がもしいらしたらと思
ってくり返しますけど、王権や恋や仏教や罪といった大きいと
らえ方ではこぼれ落ちてしまいそうなところにこそ、細部の魅
力というものがあるのだということで、「源氏』以後の物語や
小説やさまざまな文芸が、「源氏物語』に触発されてつくり上
げられてきたそのカを、ジェ!ムズ・ヒルマンという人のこと
ばを引いて、魂にかかわるイマジネーションを喚起するものが
『源氏物語」の細部の描写の中に生きているのではないかとい
うお話をいただきました。このへん、またあとで先生方とのあ
いだにもご論議のある、たいへん興味深いところではないかと
思われますが。
それでは続きまして、久保田淳先生から中世文学のお立場で
お話をいただきます。よろしくお願いいたします。
久保田先ほどご紹介いただきました久保田でございます。
わたくしは、やはりこの表題を、「なぜ読まれるのか」とい
うよりもむしろ「いかに読まれてきたのか」というふうにあえ
て読み替えまして、中世文学における『源氏物語』の受容とい
うようなことできようはお話をさせていただきたいと思ってお
-37-
ります。
この問題は本当にたいへん大きなテlマで、また魅力的なテ
ーマであると思います。すでにいまも原岡さんのお話にもあり
ました亡き寺本直彦先生はじめ、多くの優れた方々の研究が試
みられ報告されております。ただ、それらは大体において「源
氏物語』研究の側からのアプローチであったり、中世文学の側
からの仕事である場合にも、そのうちのあるジャンル、あるい
は例えば『とはずがたり』というような一つの作品についての
ものであったりしたことが多いだろうと思います。
そうではなくて、中世文学研究者の立場として、中世文学の
総体を『源氏物語」の受容という切り口から見直したらどうな
るんだろうか。『源氏物語』受容を一つの軸として、新たな中
世文学史を構想し、叙述できないだろうか。実はそんな大それ
た望みをもってはいるのであります。もってはいるのでありま
すけれども、これは言うに易く行うにはたいへん難しい問題で
ありまして、きょうはとてもそういうことについてお話しする
力量も時間もございません。したがってきょうの話は、結局い
ままでわたしが主として考えてまいりました和歌の領域に限定
せざるを得ないのでありますが、ただこういう場所でそういう
望みがありますということを申しますと、引っ込みがつかなく
なりますので、自分自身をいわば追い込むような意味で、いつ
かそんなことをしてみたいと、まだそんな色気をもっておりま
す。和歌における『源氏物語』の受容がはっきりした形で認めら
れますのは、「寄源氏恋(源氏に寄する恋)」、あるいは「寄源
氏名恋(源氏の名に寄する恋)」というような題を詠んだ作品
の存在であります。こういう作品は、二百のうちに、場合によ
っては物名ふうに、隠し題ふうに必ず『源氏物語』の巻の名を
詠み入れております。それでこれを源氏巻名和歌というふうに
呼んでおきたいと思います。
平安の最末期のころからこの手の作品が目立ってまいります。
それを資料にちょっと掲げておきました。皆さんいずれもご存
じのものばかりですが、このうち例えば『長秋詠藻」に載って
おります藤原俊成の「寄源氏名恋」「うらみてもなをたのむか
な身をつくしふかきえにあるしるしと恩へば」。「湾標」の巻の
名を詠み入れておりますだけではありませんで、これはやはり
『源氏物語』「湾標」の巻での源氏の歌「みをつくし恋ふるしる
しにここまでもめぐり逢ひけるえには深しな」、これを踏まえ
た詠み方であることはすぐわかります。
それからその隣に、源三位頼政の「寄源氏恋を、歌林苑にて
会に」という詞書で、「人しれず物をぞおもふ野分してこす
(小簾)吹風にひまはみねども」。この歌、これもまた「野分」
の巻で、タ霧が紫の上の姿を見てその美しさに心を奪われると
いう、あの有名な場面を踏まえて、それを「こす吹風にひまは
みねども」と、いわば逆転させている詠み方であるということ
もすぐわかります。
和歌研究の側では、これらの作品の年代を特定したいのであ
りますけれども、ことはそう簡単ではありません。わたくしは
この俊成の歌と頼政の作とは、同じ機会に詠まれたものと考え
まして、それは俊恵の歌林苑での催しであっただろうと考え、
-38-
さらにその時期について一つの推定を以前試みたことがありま
すが、実はこれも確たることはいえないのであります。
ここに掲げた以外にも、この類の歌は中世にはたくさんあり
ます。有名なものといたしましては、藤原定家作と伝えられま
す源氏物語巻名和歌もありまして、これは冷泉為臣さんの「藤
原定家全歌集』に収められておりまして、わたしも先年『訳注
藤原定家全歌集』におきまして一応訳をしてみましたが、訳を
しながらこれはつくづく下手な歌だなと思いまして、これが定
家に仮託されているのは定家にとって迷惑なことじゃないかと
思いますが、そういうものも含めてこの類の歌はいろいろあり
ます。こ
れも資料に掲げましたが、平安最末期に源氏供養なる行事
がおこなわれておりますこともよくご承知のことと存じます。
これは俊成の妻、美福門院加賀を中心におこなわれております。
文学と信何の融合した行事ということになります。当然これは
法華経一日間経供養などの盛行と深くかかわっているわけであり
ます。そ
うなりますと、この源氏物語巻名和歌の流行というのも、
ちょうどこのころ盛んだったのでありますので、法華経二十八
品和歌を詠むという習慣が一方釈教歌のほうでありますが、そ
の二十八品和歌を詠むのとそれから巻名和歌を詠むというのは、
非常に共通するところがあるのではないか、そんなことを考え
ております。人間というものは何らかのよりどころを、どうし
てもほしがるものですね。拠点というもの、基準というものを
求めたがる動物だと思うんですが、この時代、平安の末ぐらい
から中世ごろの人びとにとって、仏教信何における『妙法蓮華
経』、これに匹敵するよりどころ、いわば基準、規範というも
のが、文学における「源氏物語』であったのではないか、いわ
ば仏教の『法華経」に匹敵するものが『源氏物語」であるとい
うふうにだんだん人びとは考えていったのではないか。わたく
しはきょうは本当に単純なことしか申し上げられませんで、そ
ういうことを申し上げたいのであります。
一種のそういう歌壇的流行として「寄源氏恋」というような
題を試みる前から、歌人たちの中の何人かの人は、こんな題を
設げる前からやはり『源氏』をよく読み、それを自分自身の作
品の中に取り込んでいこうと試みたのではないかと思います。
その代表的な一人が俊成であったと思います。
まだ顕広と申しておりましたころの俊成、この人は、非常に
若いときから『源氏』を読んでいて、それを作品に生かしてい
るのではないか。具体的に申しますと、『為忠家後度百首』と
いう百首歌は俊成が大体二十三、四ぐらいで、まだ顕広といっ
ていた頃に催されたものですが、それに参加しております。主
催者の藤原為忠はお奥さんでありましたので、その家の百首歌
に参加するのは当然のことなのでありますが、そこに「績見
恋」(わづかに見る恋)という題が出されております。その
「績見恋」という題で、彼はどう詠んだか。「のわきしてまよひ
しこすのかざまよりいりにしこころきみはしるかも」、こうい
うふうに詠んでおります。これなんかやっぱり先ほどの頼政の
歌でも、「こす吹風にひまはみねども」と否定形でありますけ
れど、扱われました「野分」のあの場面によっているわけです
39-
ね。こんなのを手初めといたしまして、彼の出世作ともいうべき
ものは崇徳院に詠進した「久安百首』。久安六年(一一五
O年)
の『久安百首』でありますが、そこでも俊成は「源氏物語』の
例えば「須磨」の巻あたりから表現を借りて、自分の新しい世
界をつくっている。こんなことをしているのですね。そういう
試みがいろいろなされたのちに「寄源氏恋」というような題が
歌壇的に流行してくるのではないかと思います。
そうなりますと、これは本当に平安文学、『源氏』の専門家
の方々にわたくしのほうからお伺いしたいんですが、一体顕広
はどんなきっかけで『源氏」に親しむようになったんでしょう
か。御子左の家に代々伝わる家の本の「源氏』というのがあっ
たのか。それともお男さんの丹後守為忠というのはたいへんな
富豪だったようでありますから、その周辺に「源氏』のいい本
があって、そのあたりから学んだのか。先ほど膝谷さんのお話
に『今鏡』のことが出てまいりましたが、「今鏡』はこの常盤
家の関係者、それも美福門院加賀の前の夫である藤原為経作と
いわれております。そんなことを考えますと、やっぱり具体的
にどういう形で平安末期の「源氏』が流伝していたのか。読ま
れていたのか。それを本当に教えていただきたいと思うのです。
ただ、ごく若いころの顕広は別といたしまして、後年、だん
だん宮廷和歌界において重きをなしたころの俊成の手元には、
『源氏物語」の歌を集めた本と想像されます「源氏集」なるも
のがあった。そのことは後徳大寺実定の家集『林下集』の記述
から知られます。これは資料に挙げてございますが、「源氏集
を皇太后宮大夫俊成卿にかりで、かへしおくるとて、かきはべ
りし」というので贈答があります。もういちいちお読みいたし
ませんが。
こういうものがあったとなりますと、俊成は、やはり歌人と
しての興味から、まず『源氏物語」の中の和歌を中心にこの物
語を読むといったような読み方をしていたのではないか。そん
なことが想像されます。こういうように、「源氏物語』の歌を
抜粋してそれを読む。こういう習慣というか、享受の仕方が、
のちに息子の定家の『物語二百番歌合』、それからこれは孫に
なる為家が撰したというのは樋口芳麻呂先生のご説であります
が、「風葉和歌集』の編纂なんていうことになっていくわけで
あります。
次に享受の問題で、わたくしがちょっと取り上げましたのは、
和歌批評の場、具体的な歌合の場で『源氏物語」がどのように
言及されているかということであります。ここにはスペースの
関係で、俊成と定家、御子左家における言及例しか挙げません
でした。六条家の場合もちょっと調べはしまして、それはそれ
でたいへんおもしろいことがいろいろ出てくるのですけれども、
このスペースでは挙げられませんでした。
このうちの俊成の『源氏物語」に関する発言例は、先ほど司
会の後藤さんからご紹介いただきました『新古今歌人の研究』
という旧著で大体取り上げているのでありますが、最初出てく
るところでいちばん早いのは、嘉応二年(一一七
O年)の『住
吉社歌合』。これはもう俊成は五十七歳になっております。そ
のときの判詞で、これは「よるべの水」という歌語、これが
-40-
『源氏』の「幻」の巻、中将の君ですね、召人の。「さもこそは
よるべの水に水草ゐめけふのかざしょ名さへ忘るる」という歌
を引いて述べております。実はこの歌合の判定に対しては、歌
の作者藤原清輔が陳状のようなことを書いたらしくて、むしろ
この場合は俊成はあとでギャフンと参っているのでありますが、
ともかくこれが、現在見られる範囲内では最初の発言例であり
ます。そ
れからあまりにも有名なのが『六百番歌合』における「源
氏』に関する言及。これが四カ所ぐらいあります。「夕顔」の
巻なんかは特に有名ですので申し上げません。「野分」の題で
は、中宮権大夫と申しますのは藤原家一房という人でありますが、
家房の歌についてやはり「源氏の野分の玉かづらなど思出られ
て、えんなるさまには侍にや」というふうにいっております。
これは玉賓の歌「吹き乱る風のけしきに女郎花しをれしぬべき
ここちこそすれ」という歌が連想されて、それで「えんなるさ
ま」といっているわけであります。
しかし何といっても有名なのは、次の「枯野」という題を詠
んだ主催者後京極良経、当時は左大将であった良経が詠みまし
た「見し秋をなににのこさん草の原ひとつにかはる野べのけし
きに」という歌に関連しての俊成の発言であります。
あまりにも有名なのでありますが、こういっているのですね。
「判云、左、「なにに残さん草の原』といへる、艶にこそ侍めれ。
右方人、『草のはら』、難申之条、尤、うたたあるにや」という
ふうに、右方の難に対してひどく反発いたしまして、「紫式部、
歌よみの程よりも物かくふでは殊勝也。其上、花の宴のまきは、
ことに艶なる物也。源氏見ざる歌よみは遺恨事也」と、こうい
っております。
もとよりこれは「花宴」の巻でのあの臨月夜の「うき身世に
やがて消えなば尋ねても草の原をば聞はじとや思ふ」というあ
の歌を思い起こしての発言なんですが、これも前にわたくしも
ちょっと書いたことですけれども、ここでこの良経の「見し秋
を」の歌の典拠として、直ちにこの膿月夜の歌を引き合いに出
すのは、実は問題ではないかと思うのです。良経の作の直接の
典拠としてはむしろ『狭衣物語』での狭衣の歌、『狭衣物韮巴
巻二の初めのところにあります、「尋ぬべき草の原さへ霜枯れ
て誰に聞はまし道芝の露」、これを引いたほうがずっとぴった
りするわけですね。
ところが俊成は、その『狭衣』を飛ばして、実はこの『狭
衣』の歌がすでに『源氏』の歌の影響下にあると思いますが、
いきなりその根源たる「草の原」という言葉の最初の出どころ
と思われます『源氏』の歌を連想して、『源氏』に話題をもっ
ていってしまっている。それだけ彼の『源氏』、特にこの「花
宴」の巻へのこだわりというものが、ここによく出ております。
この「六百番歌合』は、建久四年(一一九三年)に催されて
おります。この建久四年二月の十三日に、俊成は恋女房の美福
門院加賀を失いました。先ほど申しました源氏供養の中心的存
在であったあの美福門院加賀、これが亡くなっております。そ
して、『長秋草』の名で伝えられております俊成の家集には、
愛妻を失った彼の悲しみが側々と歌われております。
このことは「源氏物語研究集成』の第十四巻、「源氏物語享
-41一
受史」という論文集の中に、松村雄二氏が「源氏物語歌と源氏
取り」という、たいへん長編の論文をお書きですが、そこでも
言及されていることであります。この『長秋草』には愛妻追慕
の歌がたくさん続いておりますが、それを見ますと、本当に俊
成はまるで桐壷の更衣を失ったあとの桐壷帝のような歌、ある
いは夕顔に死別したあとの源氏のような歌、そんな歌を詠んで
いるのであります。
例えば「桐壷」の巻には桐壷帝の「尋ねゆく幻もがなってに
でも魂のありかをそこと知るべく」という歌がありますね。そ
れから「幻」の巻には、源氏の「大空をかよふまぼろし夢にだ
に見えこぬ魂の行方たづねよ」。まぼろしというのは、長恨歌
でいう道士でありますが、そういうことばを使って俊成は「や
まのすゑいかなるそらのはてぞともかよひてつぐるまぼろしも
がな」というふうに歌います。
それから「夕顔」の巻での源氏の「見し人のけぶりを雲とな
がむればゆふべの空もむつましきかな」。それから「葵」の巻
での、これは頭中将の歌「雨となりしぐるる空のうき雲をいづ
れの方とわきでながめむ」。それに似たような歌として「いつ
までかこのよのそらをながめつつゆふべのくもをあはれともみ
ん」なんていうふうに歌って、「ゆふべのくも」「ゆふべのそ
ら」「まぼろし」と来て、それでまた「くさのはら」というこ
とばを二度ぐらい使っているのです。「おもひかねくさのはら
とてわけきてもこころをくだくこけのしたかな」「くさのはら
わくるなみだはくだくれどこけのしたにはこたへぎりけり」、
こんなふうに歌っております。
だから俊成にとっては、松村氏もいっておられましたけれど、
「草の原」というのはこのように大事なことばなんですね。大
事なというか、自分自身の痛切な体験に直接響いてくることば。
これを右方が何か難じ申したというので、ちょっとアタマに来
ている。それでこんな判詞を書いているのじゃないかと思うわ
けです。
八十歳の老人俊成、しかもすでに出家して釈阿といっており
ますが、釈阿は『源氏物語』の桐壷の帝や源氏その人のように、
もう身も世もなく嘆き悲しんでいる。こういうような例がある
わけであります。
それから俊成の判のおしまいの例といたしましては、『水無
瀬殿恋十五首歌合』における判詞を挙げました。歌の作者に親
定とありますのは、これは後鳥羽院でして、左馬頭藤原親定と
いう人物の名前を借用しているのです。
後鳥羽院の歌「君ももしながめやすらん旅衣朝たつ月をそら
にまがへて」の歌について、「花のえんの寄など思ひ出られて、
いみじくえんにみえ侍り」と、こういうふうにいっております。
これは源氏の「世に知らぬ心地こそすれありあけの月のゆくへ
を空にまがへて」のあの歌を指すわけであります。
このように見てまいりますと、俊成は『源氏』の中でも特に
「花宴」の巻に深い思い入れがあったということが知られます。
これは歌合判詞ではありませんで、『俊成卿和字奏状』と申し
ますのは、正治二年(一二
OO年)、息子の定家が後鳥羽院に
詠進する百首歌のメンバーからはずされそうになっていたのを
憤慨したというか、憂えた俊成が、院に直訴した奏状でありま
42-
すが、その中で藤原清輔に対してほとんど暴言とも思われるよ
うなことをいっております。「源氏物語に、二月の花のえんの
巻に、内侍督に『おぽろ月よ」といはせて候を、教長も清輔も、
源氏を見候はず、まして文集と申文をも見候はで、白楽天の詩
に『不明不暗蝶々月(明らかならず暗からず騰々たる月)、非
暖非寒漫々風(暖かならず寒きにあらず漫々たる風)」と申詩
をこの寄にもよみて候を、いづれをもしり候はで、『夏の夜』
とかきて、夏の部に入て候。教長、清輔、ともにうたてしき事
候也」というのですね。
これは本当にそんなことがあったのかと不思議に思われるほ
どですが、まんざら嘘でもないのでしょう。なにしろこの『拾
遺古今』というのは残っていないから何ともいえないんですけ
どね。しかしこのような、ほとんど暴言とも思えるようなこと
を激しい物言いでいっているのは、いくら清輔が宏才博識を誇
っても、自他ともにそれを認めていても、こと『源氏』に関し
ては、自分こそは最もよく、深く読み込んでいるんだという、
こういう自負があったから、それがこんなことをいわせている
んじゃないかというふうに考えます。
続きまして、定家の、これは「千五百番歌合』における『源
氏』言及例というのを二つほど挙げました。もうあまりご説明
する時聞がないと思いますが、これがやはり「花宴」の巻に関
連して、二っともそうであります。特にあとの藤原公経の歌で
は、ここにまた「草の原」が出てまいりまして、そのことをや
はり息子の定家も、お父さん譲りで「えんには侍べし」という
ふうに批評しております。
実は六条家の歌人たちもこのころになりますと、非常によく
『源氏」を読んでいたと思いますね。これはあるいは俊成・定
家に対抗するという意識もあったかもしれませんですが、顕昭
なんかは非常によく読んでいたらしくて、『千五百番歌合」の
判調にやはり相当たくさんの言及例が出てまいります。それを
引けばよろしかったんですけれども、とてもそのスペースがあ
りませんので引けませんでした。ただその中には、無理やり
『源氏』に結びつけようとしているようなところもありまして、
やはり顕昭の読み方というのは、ちょっと俊成なんかとはちが
うのではないかなという気がいたします。
ただ、ちょっとこれは本当に資料として掲げなくて申しわけ
ないんですけれども、『千五百番歌合』の一二七六番右の歌に、
やはり「草の原」ということばが出てくる歌があります。この
歌の作者は俊成卿女の夫であった源通具なんですが、「草の原
とへば白玉とればけぬはかなの人の露のかごとや」という歌に
つきまして、顕昭は例の「うき身世に」の歌なんかを引きまし
て、しかしこの場合にはいかにも歌学者らしく、「うき身世に」
とそれから先ほど申しました『狭衣』の「尋ぬべき」の二つの
歌を引いて、この通具の歌を考えまして、そのあとこんなこと
をいっております。
「ふるき人は、歌合の歌には物語の歌をば、本歌にもいだし、
証歌にももちゐることなしと申しけれど、源氏、世継、伊勢、
大和とて、歌読の見るべきふみとうけたまはれば、狭衣も同事
欺」とありまして、ここでいわゆる作り物語と一緒に「世継」、
多分『大鏡』を指すんだろうと思いますけれども、「世継」の
-43-
ことばも歌詠みの見るべき文というふうに数えているのが、ち
ょっとおもしろいと思います。
それからやはり顕昭の判した例で、二二一
O番右の歌、これ
は通具の父であります内大臣源通親の歌で「しのぶとも軒の玉
水つぶつぶとありしあまよの物語せよ」という歌があります。
「ありしあまよの物語せよ」、これは「雨夜の品定め」をいって
いるわけですね。あしたのご発表にもあるようでありますが、
そういう「雨夜の品定め」を、このころからやっぱり『源氏」
の中でも一つの、たいへんおもしろい場面というふうにとらえ
ていたということが、この歌と判詞などから知られると思うの
であります。
こんな具合に、いろいろ具体的にこのころの歌人が『源氏物
語』の特にどういうところに心をひかれたかということを前々
から調べているのでありますが、これはなかなか果てしがあり
ません。やっている本人はけつこうおもしろがっているんです
けれども、問題はかなりこまごまとしたことになりますね。で
も原岡さんのお話にもありましたように、やっぱりわたくしは
物語、小説というものは細部にこだわるべきだと思って、自分
でもそんなことをやっているのでありますが。
ちょっと一つ、先年これは実は国語学会の大会のときに何か
話をせよといわれまして、歌ことばについてお話をしたときに
も取り上げたことですりれども、こんなに『源氏』に親しんで
いるはずの俊成が、『源氏物語』に基づくことが明らかである
息子の定家の歌を批判しているという例があります。
これもやはり『六百番歌合』なんですが、『六百番歌合』に
コ扇」という題が出されております。夏の題ですね。そのコ扇」
という題で定家は、「風かよふ扇に秋のさそはれてまづ手なれ
ぬるねやの月影」というふうに詠みました。ところが俊成は、
判の詞の中で、「左のねやは詩にも歌にもつくりよむ事に侍れ
ど、殊に庶幾すべからざるにや」として、これに否定的な評価
を下しております。勝ち負けは、これは相手の藤原家隆の作に
勝っているんですが。
ところがこの「ねやの月影」ということばは、ご承知のよう
に、『源氏物語』の「東屋」の巻の終わりで薫が歌っている歌
に見えるものであります。「里の名もむかしながらに見し人の
おもがはりせるねやの月かげ」。そしてその少し前には白い扇一
というのが出てまいりますね。ですから、定家は、この夏の題
の扇という、全く恋には関係のない題でありますが、そこから
直ちに、やはり「東屋」の巻のそのおしまいの叙述と、それか
らその物語歌を踏まえて、というか、それを利用して、自分の
歌を詠んだと思うんですね。
しかし俊成はそれに気がついたか気がつかないか、これを批
判しております。批判されたものですから、定家は自筆本の
『拾遺愚草』では「ねやの月かげ」を「とこの月かげ」という
ふうに、多分あとで直したんだと思いますけれども、そういう
形で書きとめております。書きとめてはおりますけれども、定
家は「ねやの月かげ」にはずっとこだわります。この少しあと
に定家は「さむしろにはつしもさそひふく風をいろにさえゆく
ねやの月かげ」と詠んでいるんです。
実は『六百番歌合』の前にすでにその「ねやの月かげ」とい
-44-
うことばを定家は使っておりました。「見るゆめはおぎのは風
にとだえして思もあへぬねやの月かげ」。ですから生涯に少な
くとも三度ぐらい「ねやの月かげ」をくり返して詠んでいます。
定家だけではありませんで、『六百番歌合』がおこなわれて
から数年のち、式子内親王が、これはもうなくなる前の年であ
りますが、「正治二年院初度百首』で「秋の色はまがきにうと
く成りゆけど枕になるるねやの月影」と詠み、それから藤原公
経が「こひわぶる涙や空にくもるらんひかりもかはるねやの月
かげ」、これは『千五百番歌合』で詠んでおります。それから
俊成が亡くなってとうの昔になった時点で、孫娘の俊成卿女が
「なれなれて秋にあふぎをおく露の色もうらめしねやの月か
げ」、こんなふうに詠みます。結局俊成の威令はおこなわれな
かったということになります。
このような例を含めまして、いろいろ考えているのでありま
すが、そんなことから、先ほど申しましたように、わたくしは
「源氏物語」は、この時代の人びとにとっては一つの規範とな
っていたのではないかと思うのです。大体政治のうえでは、中
世はよく延喜天暦の聖代ということを申しますね。本当に醍醐
天皇、村上天皇の時代がいい時代だったのかどうか知りません
ですけれども、中世の人は、延喜天暦の聖代というふうに、延
喜天暦を一つの政治上の規範と仰いでいたと思います。それか
ら仏教信仰においては、やっぱり『法華経』がいちばんのより
どころだったでしょう。
それと同じように『源氏物語』というのは、やはり彼らの、
文学という概念がちょっとわたしたちの文学とはちがうかもし
れませんが、何かそういうものを考えるときに『源氏物語』が
いちばんの規範だったのではないか。それ以外に、それ以上の
規範というものはなかったのではないか。だから原岡さんが最
後におっしゃったことと関連するんですが、現実のいろんな不
幸、あるいは喜びなんかに触れたとき、すぐ『源氏物語』では
どうだったろうということが反射的に来る。それで自らをいわ
ば『源氏』中の人物のように演じるといいますか、『源氏』を
現実に引きつけるというよりも、むしろ現実を『源氏』のほう
にもっていこうとする。現実を「源氏』を通して認識する。そ
ういうような思考の仕方というのが、この時代の人びとにあっ
たのではないか。そんな気がいたします。
ちょっと時間をオーバーいたしましたね。申しわけありませ
ん。後藤どうもありがとうございました。久保田先生にすればも
う年季の入ったテ
lマでいらしたのではないかと思うんですが、
それでも今日また新たないろいろなご指摘をいただきまして、
とりわけ原岡先生のお話との関連も最後のところでご自身がお
っしゃってくださいましたので、もうわたくしからお求めする
ということなしに次に移らせていただきたいと思います。
野口武彦先生、どうぞよろしくお願いします。
野口野口でございます。プログラムを拝見しましたら、近
世・近現代文学を担当しろと書いてありまして、これは外野を
一人で守れというようなご注文で、これはちょっと無理なので、
守備範囲を非常に狭く取らせていただきます。
長島という選手は、目の前に来たボ
lルしか取らないで、そ
45-
れを危うげに取ってファインプレーに見せたという、その手を
使おうと思います。ものすごい狭い、幕末の「源氏物語』とい
う、非常に限定された範囲でお話しします。
「源氏物語はなぜ読まれるのか」という問いかけには、もう
実はあらかじめ答えが用意されておりまして、それは、それぞ
れの時代に特有のコ
1ドで読者の心の琴線をかき鳴らすからで
あります。
では江戸時代にはどういうコ
lドであったのかということが
問題になります。たいへん江戸時代というのはハッピーだった
のです。源氏物語文化に関してはものすごいハッピーだったわ
けです。そのコ
iドは二つあります。一つは世俗化であります。
これには乱暴かもしれないけれども国学も入れます。注釈から
国学への流れがあります。作品としては「湖月抄』から『源氏
物語玉小櫛』に至るプロセスです。これを「みやびのまねび」
というふうに呼びます。こう申しますと国学は世俗か、『玉小
櫛』は世俗かいわれるかもしれませんが、源氏学というのは優
雅を民衆に分配することですので、世俗化、大衆化というふう
にいわせていただきます。
それから第二のコ
lドは俳諮化です。これは「みやびのもど
き」です。パロディですね。これは井原西鶴の『好色一代男』
から柳亭種彦の『修紫田舎源氏』の大ヒットにまでつながりま
す。この二つの読者層というのは、重なり合いません。しかしな
がら、その二つを足したところに、その和集合に源氏物語文化
があったといえます。わたくしの卑俗なことばで、これを源氏
物語カルチャーと呼んでいるんですが、そういうものがあった
と。しかし後者のほう、つまり俳諮化のほうは今日はいっさい
省略します。
きょうお話ししたいと思いますのは、幕末の『源氏物量巴で、
いま申しました世俗化、俳諮化というのが、共通の美意識がで
きあがっていた。何というか、美意識というのは、どういうも
のを美しいかと感じる共通の了解事項なんですね。それが崩れ
ると、パロディもへちまもなくなってしまうわけです。そうい
うものがなくなったのが幕末だろうと思います。
レジュメに書いておきましたが、幕末期の『源氏』の問題で
は、結局のところ、萩原広道の『源氏物語評釈』の問題に帰着
するわけです。結局というのは、なぜ結局かというと、この仕
事が、当時唯一無二の物語学だったということです。このこと
はもうちょっとあとで詳しくいいます。そういう意味で希少価
値に輝いております。
広道の位置づけというのは、近代的な源氏研究の先駆けだと
か何とかいろいろな評価があるようですけれども、ぼくはそれ
は一切目をっぷりまして、幕末国学がどうしょうもない混迷に
陥っていた、そこに一条の血路を切り開いた仕事というふうに
位置づけてみたいと思います。近代のことはもうどうでもよろ
しいのです。幕末のことで手一杯だと。
お手元の資料に柱を四つ書いておきました。その(一)はも
う済みました。(二)(三)(四)は必ずしも順序どおりにはい
きません。それから引用文献はいちいち読みませんので、必要
があれば何ページにこういう人の文章があるという格好で参考
-46-
にします。
江戸の源氏学では、この「源氏物語評釈』が出現するまで、
国学者のあいだでもずっとテキストおよび参考書は、『湖月抄』
と「源氏物語玉小櫛』だけだったようです。文政年間に書かれ
ました藤井高尚の「文のしるべ』という文章があって、これは
資料の十八ページにありますが、使っているのはこの『湖月
抄』と『玉小櫛』だといっているんですね。文政年間というの
は一八二
0年代ですから、ちょっと幕末には早いんですが、そ
れがいま話題にする一八五
0年代に至るまで三十年間ぐらい同
じだったようです。
というのは、広道自身が『源氏物語評釈』を刊行するときに、
これも広道書簡が二十ページにありますが、これを上木さえす
れば、つまり印制さえすれば、「湖月抄は倒れ可申候」と豪語
していることからわかります。それから『湖月抄」の版元から
苦情が出たという事実もありますので、依然『湖月抄」だった
ということがわかります。そして『源氏物語評釈』の刊行は、
「夕顔」の巻までの初映が嘉永七年(一八五四年)に出ました。
そして三帳目が「花宴」の巻で、また「花宴」なんですけども、
前の先生方もお話になったようにすべて「花宴」なんですけど
も、それで中絶したのが文久元年です。これはたいへん意欲的
であり、それ以上にものすごい山っ気のある出版だったことで
す。話が非常に俗っぽくなるんですが。
この評釈の特色は二つありまして、細かいことはまたあとで
いいますが、要点は、第一はアンチ国学的な、これは儒教的な、
ともいえるんだけれども、調喰説を取ったということです。典
拠説ともいえます。
それから第二点は、これは自分でも先達未発の説だといって
いて、私一家の説だといって独創性を強調する、大言社語して
いるんですが、文法、「のり」と読みますけども、文法の法則
があるということを主張して、それを注釈に取り入れた点です。
これは国学・儒学の対立さえ超えた新しい潮流の導入でありま
して、これは中国白話小説学です。当時としてピカピカの理論
だったわけです。ちょうど七
0年代における構造主義みたいな
ものです。たちまち廃れましたけれども。(笑)それは構造主
義の話で、こっちのことではありません。
江戸の源氏学に根本的に二つの流れがあったことはご存じの
とおりで、これも非常に大ざっぱにいいますが、一つは国学的
な「もののあはれ」の流れであり、もう一つは儒学的な「もの
のまぎれ」の説ですね。皆さんには説明の要はないと思います
が、一応いいますと、つまり「もののまぎれ」というのは、皇
胤の乱れにかかわる重大事があってそれを諭したんだという説
ですね。水戸の安藤為章の説です。つまりこれはモラリズムの
立場だといえると思います。
一方の「もののあはれ」は、これも言わでもがなですが、
「玉小櫛』で「もののあはれは恋こそまされ」で、これはわた
しの極端な理解かもしれませんが、「もののあはれ」がわかる
人だったら不義密通ぐらいは大目に見てやれという、これはも
のすごい、相当なアモラリズムです。国学の根本にはものすご
いアナーキーがありまして、その点を飲み込んでおかないとい
けないと思います。
-47
宣長の死後、国学は大きく二つに分裂いたします。これも皆
さんご案内のことですけども、一方は古学派ですね。平田篤胤
派です。これは『古事記』「日本書紀』の古道の基礎になる文
献ばっかりをやる。歌はからっきし下手くそです。歌に興味を
もちません。篤胤はどうも自分は「もののあはれ」がわからな
いというので相当ひがんでいたみたいなんですね。宣長には先
生だからさすがに悪口はいわないけれども、『源氏物語』は淫
乱だといっております。平田篤胤ならそうだろうと思いますけ
れども、その篤胤と喧嘩別れした伴信友という人物がありまし
て、これは資料の十八ページにあります。この人は史学派とい
う、珍しい歴史実証派なんですけども、この人も『源氏物語』
は気をつけて読めといっています。
それから鈴屋直系はこれは歌学派ですね。全部歌学びなんだ
けれども、この人びとは何かおずおずとしてしまいまして、ど
うも先生の宣長ほど大胆にいわないんですね。国学のアナーキ
ー性、がどんどん希薄になってしまいまして、中島広足などは、
これは嘉永ですが、「源氏』は「もののあはれ」のさまざまな
例を限りを尽くしているけれども、教えるときには適当に訊略
説を交えろといっているんですね。これは折衷論です。何かち
ょっとだらしないんですけども。根性がないんですね。
つまり、しだいに「もののあはれ」というのが、変質してい
くわけです。修正を被っていくわけですね。これは歌学派の随
一であり、それから物語派に行った萩原広道にもいえることで
して、広道には独特の「もののあはれ」論がありますが、要点
は何かというと、もののふにも「もののあはれ」があるという
んですよね。それは実は膿谷先生が引用されました「ただひな
びたる武士に異ならず」つであったでしょう。武士というのは
「もののあはれ」がないんだということになっているんですよ。
宣長もそういっていると。いや、そんなことはないだろうとい
うわけですよね。一寸の武士にも五分の魂で、武士にも「あは
れ」はあると。生死の境に身を置くのだから、ひとしお勝ると
いうふうに主張します。
どうしてそういうふうに「もののあはれ」が変質してくるか
というと、これは宣長の個性だと思うんですね。ものすごい冷
たいところがあります、宣長には。「もののあはれ」というの
は要するに人間の豊かな、鋭い感受性なんだけれども、それが
ない人間はもうだめなんですよ。突き放してしまうわけ。「も
ののあはれ」がわかる度合いというのがありまして、『玉小櫛』
もさまざまなケ
lスがありますけれども、もののふはそれにも
入らないわけです。だけれどもそうではなくて、もののふにも
あるんだというふうにいっております。
広道だけではなくて、歌学派の人びと、これはあまり名のあ
る人はいないんですけども、そういうことをいったら叱られま
すけれども、だんだん変わってきまして、「もののあはれ」と
いうのは人間の突き詰めた真心だというふうな言い方になって
まいります。これが幕末の政治運動と結びつくと、非常に危険
な、発火物質に変わっていくわけです。
おかち
さてその広道という人物の出自は、岡山藩の徒士です。徒士
というのは、笠をかぶって行列してあるく下級武士ですね。十
五俵二人扶持というから、ものすごい軽輩です。だからものの
48
ふだというんでしょうけれども、その武士もののあはれ論で発
奮しているにもかかわず、自分では武士らしい行動をしており
ません。時世を見ますと、これは嘉永、安政にかかりますので、
一八五
0年代ですよね。これはある意味では下級武士の時代な
んですね。いろいろ活躍の場をどんどん使ってきます。脱藩し
たり浪人したりなんかしてやっていきます。広道の周辺の国学
者仲間にも成功失敗を問わないというと飾った言い方でして、
実際には大部分が失敗しているんですけども、いちいち固有名
調は出しませんが、尊王摸夷論にアンガ
1ジュしまして、これ
懐かしいことばですね、アンガ
lジュというのは。(笑)アン
ガlジュするけど失敗するんです。本当は向かない人間ばかり
が飛び込むわけですから、非常に惨憶たることになります。
ところが広道自身は非常に冷ややかな距離を取っています。
浦賀に黒船が来たということを知らされても「ああ、そうです
か」という感じで、「それは下賎の身のかかはることにはござ
なく候」という感じの応対をするわりです。どうしてだろうか。
これは性格だといえばそれまでなんですけれども、どうもこれ
はおそらく岡山から出藩した、出てきた、何といいますか、無
断で出てきちゃったんだけども、逐電してきたわけだけれども、
その事情に理由があるみたいです。
萩原広道の伝記資料に関しては森川昭さんとか山崎勝昭さん
とか、非常に鰍密な研究がありまして、何といいますか、偏愛
的、全身没入的、まだいろいろ形容詞が浮かぶんですけれども、
ともかくそういう、全身をこめた伝記研究がありますが、この
出奪の事由についてはどうも口が重いので、ぽくの方からもい
いにくいんですけど、確かなうわさによりますと、広道は梅毒
にかかって鼻が落ちちゃったみたいなんですね。それでいづら
くなって出てくる。大阪に出てくる。大阪で国学者のグループ
を集めていろいろするんですが、どうも大阪というのは文人は
商売にならないみたいです。「源氏物語』の講義をやるといっ
たって人は来ないというんですよね。謝礼も入らない。
その中で救ってくれる人もいて、有名な医学の緒方洪庵、そ
の屋敷に行って「源氏物語』を講義するとか、そういう中から
「源氏物語評釈』の土台ができあがってくるわけです。そして
アルバイトに版下筆耕までやるわけですよね。版本にする原稿
を墨で書くわけです。筆跡がきれいなものですから。それまで
やる。それで体に悪いと知りながら酒をがぶがぶ飲むという。
そういう暮らしをやっていたということです。
そこでそういう土壌から出てくる『源氏物語評釈』というの
は、物語注釈という方法による『源氏物語』のリライトであっ
て、さらにいえば物語テキストを楽譜にして自分で音楽を演奏
しているという、そういう趣があります。そのことが、さっき
申しました物語調喰論ということと関係してまいります。「も
ののあはれ」論というのが変質したといいましたけども、それ
とほぼ並行して「もののまぎれ」のほうも意味内容が変わって
まいります。
天保年間に堀内匡平の「源氏紐鏡』というのがありますが、
資料の十八ページです。この「紐鏡』というのはいろんな意味
でおもしろいんですけども、「もののまぎれ」の一面である典
拠説を、例えば桐壷の帝と桐壷更衣は花山天皇と弘徽殿女御で
-49-
あるとか、臨月夜と源氏は二条后高子と業平だとか、いくらも
あるけれども、要するに歴史事実還元主義をとります。何でも
かんでも現実との照応を考えていくわけですね。こういうふう
に考えが行き着きますと、これはもう明治になってからですけ
れども、近藤芳樹の『源語奥旨』という、これは十九ページに
ありますが、非常に珍妙な主張になります。つまり紫式部は勤
王思想のさきがけだったというわけです。藤原というのは徳川
で、そういう寓意を、紫式部は徳川を知らないけれども、つま
り臣下が皇位をないがしろにすることを調している世界だと。
そういう勤王思想のさきがけだというわけですね。だけどこれ
は明治八年に書いているんだからちょっと迫力がありません。
ともかく、つまり極端な執筆意図を見る立場になっていきます。
この近藤芳樹という人は平田派なんだけれも、広道の交友範囲
内にいます。つまり広道の友達にいるのが全部そういうふうに
なっちゃうわけですよ。何らかの形で政治に破滅的に美しくコ
ミットするか、ちゃっかり便乗するかとか、そういうふうにな
っていくわけです。その中で物語学というのは孤塁を守るわけ
です。孤塁を守らざるを得ない事情があったのかもしれないわ
けです。
さて、広道の調喰説は、紫式部の身辺に何ごとか「もののま
ぎれ」の実事があったであろう、そしてそれが紫式部にとって、
「源氏物語』を執筆させる強烈な動機になったであろうという
ものです。決してそれ以上に、一つの作中、事件ごとにこれこ
れの実事が対応するというふうには考えておりません。モデル
とフィクションというのははっきり分けている。フィクション
だけが、それだけの論理で動いていくというふうに考えている
と思います。
『源氏紐鏡』にも「むかへ」という考え方がある。「むかへ」
というのは「対(ついこと書いて「むかへ」と読みます。つ
まり光源氏と頭中将、柏木とタ霧、紫の上と末摘花というふう
に必ず対があると、こういうわけですね。この対というのが、
建物で迫り持ちというのがありますね。両方からこう力がかか
る。それで支えあって維持するわけで、それが物語の構造軸に
なっているという、そういう考え方はすでにあるんです。
ところが広道はそうではなくて、何といいますか、迫り持ち
構造にはダイナミズムはないんですよ。動いてはいかないわけ
です。安定はするけれども。だけども広道はそうではなくて、
自分で文法、「のり」と呼ぶ物語の構造力学みたいなものを考
えるわけですね。主と客とか、正と副とか、伏線等々、いろい
ろ仕組みがあると。その構想自体の中にすべての物語のできご
とが配置されている。つまり一口にいいますと、物語中のあら
ゆる要素は、単独では存在しないと考えるわけです。何かある
事件があると、それは同時にどこかで、別のところで起きてい
る事件と呼応している。あるいは将来起こるであろう事件を想
定しているというふうに考えるわけですね。
そうすると、何か分子と分子のあいだに磁力が発生して、そ
して運動が起こるみたいに、物語がこうやって動いていくとい
うダイナモが仕掛けられる。そういうふうにぼくは理解してお
ります。
そのネタはこれは『水器伝」です。金聖嘆註の『水濡伝』で
-50-
す。詳しいことはいくらでもいえるんですけど、実例なしでい
いますと、広道には、小説学理論教条主義みたいなところがあ
ります。つまり最初から最後まですべてが完全に構想されてい
ると考えるわけですね。そうすると物語の進行にその作った理
論設計を当てはめなければいかんわけですよ。
それでぼくは、幸運にも広通は若死にしたと思います。つま
り、光源氏が死に、宇治十帖に行ったら、これはものすごい苦
闘を強いられるわけですよ。つじつまを合わせるために。諸先
生はご経験があると思うけれども、大体論文というのは、最初
に結論をつくるわけじゃないですか。ちがいます?そこに持
っていこうとするわけですよ。それで不利な資料は見ないんで
すね。でも良心がちくちくするから見る。すると収拾がつかな
くなるという。広道はそういう目に遭っただろうと思います。
どうもすみません、余計なところに行きましたが。
「田舎源氏』の種彦も幸いなことに天保の改革に引っ掛かる
んですよね。あれは「須磨」「明石」で終わっているんです。
つまり「田舎源氏』というのは、すべての方がご存じじゃない
と思うけども、足利将軍の世界にするわけです。お家騒動にす
るわけです。光源氏が足利光氏というので出てくるんです。う
れしいですね。夕顔の花はそのまま使えませんのでこれは烏瓜
に変える。すべてそういうふうに、俳句になるわけですわ。そ
れが「須磨」「明石」で終わっているんですよ。終わったんじ
ゃなくて、続けるはずだった。ベストセラーだから。ところが
天保の改革でストップして、当人も死んじゃったわけで、それ
から先書くのはものすごい苦しかったと思う。だから何か不思
議に、うまいときに死ぬことになっているんです、文学者とい
うのは。何かそういう運命を感じます。
その『評釈」は、これは実際に読んでいただくしかないんだ
けれども、最後が「花宴」で終わるんですね。これは何といい
ますか、おそらく偶然以上の何かがあると思いますけれども、
まず「紅葉賀」で光源氏との不義の子を藤査が、何というか
「庇なき玉」の場面ですよね。桐壷帝が一生懸命可愛がる。そ
れを見ている藤壷が、心でものすごい苦悩にさいなまれる。そ
れをものすごく見事に評釈を加えていきます。そしてそのあと
「紅葉賀」で、久保田先生のお話に出てきました中世の歌の
「艶のためし」になった源氏と膝月夜の君の応酬の歌が暗転し
し
ゅ
じ
た
ね
て、「須磨」「明石」の落塊に行くという、それを種子、種子と
書いて「くさはひ」と呼びますけれども、それがいかに巧みに
仕掛けてあるかということを分析したところで絶筆になるわけ
です。こ
の「源氏物語評釈」というのは、予約出版のようにして刊
行されました。お金を集めておいてできた物を渡すというやり
方。だんだんお金が集まらなくて、いつも金策に明け暮れてい
る。それでも好きな酒を飲む。中風が出る。とうとう右手が利
かなくなります。右手で書けなくなるわけです。その無念を語
った一文があります。これは読みます。資料の二十ページの最
後を見てください。
「この六年あまりかほと中風にて手をやみたりけれは板下を
かく事たにえせす源氏の評釈たえむとする事いとうれはしくか
なしかりけりこれによりてききに彫らせつるちうさく」、これ
-51-
は「注釈」ですね。「をものしてまっかくなん五巻の草子とは
なしたる語釈をもべつにせんとおもひしかとはつかはかりのほ
となれはついでにここにとりそへつ次の巻々よりは人の手にか
かしめたればいたうかはりたるになん/文久はしめの年なか
月左なからに」、左手で、ですね。「広道しるす」。
この次の巻々はついに世に出ませんでした。この一文は萩原
広道の白鳥の歌だろうと思います。ここで断絶する。その断絶
のさなかにこの仕事を置き去りにして話を閉じようと思います。
つまり萩原広道のみがただ一人そうであった幕末国学の物語
学派というのは、もしかしたら幕末国学を正気の側に、学問の
側につなぎ止める、最後の、唯一の思考装置だったのではない
かという気がいたします。それがぼくの最後の感想です。どう
もありがとうございました。
後藤ありがとうございました。売れっ子評論家らしく非常に
歯切れのいい分け方で、文化の中での『源氏』受容をご説明い
ただいたわけでございますけれども、ここでどういたしましょ
うか。所期の予定ですと、三時三十五分にこれが終わる予定で
ございましたので、ちょっと時聞を前半にいただいて講師の方
同士のディスカッション、あるいはいまのレポートでまだおっ
しゃり足りないところの追加、そういったことをちょっと順繰
りにお話しおきいただきたいと思いますけれども。
まず牒谷先生から追加のこと、あるいはお三方の先生方への
ご質問なりご意見なり、何かおありでいらっしゃいましょうか。
鵬谷「今鏡』に関わる、後でお配りした系図(三ページ上
段)をちょっと出していただきたいんですけれど。この説明を
しませんでしたが、もちろんわたくし自身がまだ結論があるわ
けでも何でもありませんけど、『今鏡』で言われているのは、
この後三条天皇とその皇子たちの関係と、白河天皇の関係で、
非常に微妙なところが確かにございます。先ほどちょっとだけ
触れましたが、後三条が位を譲るときにはもう遺言のように白
河を天皇に立て、実仁を皇太子に立てています。これは院政の
非常に複雑なこととも関連してくるんですが、白河という人の
個性もあるんでしょうけれども、後三条の方針をもちろん無視
したというふうに理解されていますが、当然、天皇になったら
無視するはずであります。弟に譲るはずはまずないんで、皇位
は自分の子供・孫へというのが天皇になったときの方針であり
ますから、これは「今鏡』の作者が言っているような形という
のは、美しい形ではありますけれど、実際には起こり難い。ま
して白河天皇は、当然のことながら弟に位を譲るようなことは
しないし、息子の堀河を立てて、しかもこれは異例な立て方な
んですね。
白河天皇は三十半ばぐらいで、一
O八六年に院政を始めます。
そのときに堀河天皇はまだ八歳になっていたかならないかなん
ですね。それなのに、堀河を皇太子にし、さらにその日に、自
分は位を下りて、堀河を立ててしまう。このように立太子と即
位の日が一緒というのは日本の天皇史上でもほかに例がないと
思います。これは白河がどうしても自分の直系に皇位を継がせ
たかったということのあらわれだと思いますね。
ですから『今鏡』の作者がそのへんをどう解釈したか。「源
氏』との関係がどういうふうにかかわってくるのかは、わたし
52-
もちょっとこれから勉強してみたいと思いますけれども。とこ
ろで白河上皇は、鳥羽天皇を早く辞めさせて代りに問題の「お
じ子」といわれた、実際には自分の胤だということになってい
る鳥羽の皇子の崇徳天皇を即位させてしまう。このへんの関係
も『今鏡』では非常に複雑な関係になっています。
また、輔仁親王の子どもの源有仁、この人は実は有仁親王だ
ったが皇族賜姓したわけで、その賜姓の仕方がまた異常であり
ます。どういうふうに異常かと言いますと、従三位という、今
まで皇族賜姓で従四位というのが一般的だということは『小右
記」でも言われていますが、従三位というのは:::。「今鏡』
の作者は罪滅ぼしのつもりであろうというようなことを言って
いますけれども、このへんのどろどろした感じというのが「源
氏』とどうかかわってくるかというのに興味をひかれますし、
少し調べてみたいところであります。
後線どうもありがとうございました。先生、いま後三条が白
河のあとはその弟たちへ次々と予定したのを白河が裏切ったの
は、白河にとっては当然のことなんだということをおっしゃっ
た。でも兄から弟へという譲位は歴史のうえではけつこうあり
ますね。
鵬谷あります。そういうことはあります。
後藤それは無視して、白河は我を通したというふうに。
鵬谷そうです。でも歴史のうえではありますけれど、しかし、
天皇になったときにはやっぱり自分の息子というのは、桓武天
皇の例でもそうですからね。ただ桓武天皇は即位したときに、
早良親王という人が親の意見、藤原百川の意見で皇太子に立て
られたのです。ですから早良皇太子をやめさせるというのは、
わたしは桓武天皇の陰謀だと思うんですけど。やっぱり天皇と
してみれば、自分の弟を皇太子にするというのは自分の意志で
はないはずなんです。それをこんどは、自分が天皇になったと
きになんとかして皇子を皇太子にと思うはずです。早良廃太子
は、例の種継暗殺事件に引っかけて桓武が仕組んだものと私は
考えます。それと同じような形なんです、ここは。
後藤はい、どうもありがとうございます。いま非常に『源
氏』離れ、物語離れをしているというふうに。
鵬谷わたしがしゃべると『源氏』から離れてしまうので、も
うあまり・:・。
後藤聞いている方もお感じになるかも知れないと思うので申
しますけれども。これは『源氏」は立太子もしない、即位もし
ないですけれども、父親桐壷の意志としては朱雀と同じように
源氏を考えているということは、「賢木」から「明石」あたり
で明らかで、皇位ということとは別に、二人の力でもって自分
の次の代を、というふうに考えていたという点でつながってく
るんだろうと思うんです。
それでは原岡先生、何かおありでしょうか。
原岡私はさっき時間もオーバーいたしましたので、別に補足
申し上げることはないんですけれども、一つ質問させていただ
いてもよろしいでしょうか。
それぞれのお話、たいへんおもしろく伺ったんですけれども、
野口先生が最後のところで、国学者の中で広道というのが、国
学を正気の側に止める唯一の人であったというふうなことをお
-53-
っしゃったと思うのですけども、そこのところ、もう少し具体
的にと申しますか、もう少し説明していただけたらと思うので
すけれども。
野口ポスト宣長というふうにまずくくりますね。そうすると、
これは文政ぐらいからですね。つまり江戸の十九世紀の最初ぐ
らいからになってしまいます。非常に長過ぎますので天保でま
た区切ります。天保の改革というよりも、むしろ天保の飢鍾に
どう対処するかということでふるいにかけられる時期があるわ
けです。これは儒学も同じことですけども。
それで、これはものすごい大きなテ
1マだから、ものすごく
粗雑にしかいえませんけれども、平田派というのは意外に実務
能力はあるんですよね。その天保のあと、こんどは嘉永に黒船
が来ますね。そうすると国学ですから、これは尊王撰夷になら
ざるを得ないんですよ。どうしても、立場上、建前上も。
そうするとどういうふうにするかというので、篤胤派は過激
派。平田激派というのが出るくらいですから。ですが、それ何
をやるかというと、文久三年に足利尊氏以下の首を斬るんです、
木造の。等持院から木像を持ち出してきて。これは狂信的で過
激な行為だと信じられ、ぼくもある時期まで、つい最近まで思
っていた。ところが考えてみたらこれはものすごい合理的なん
ですよ。なぜかというと、木像は斬り返してこないじゃないで
すか。だ
けど実際に同じころに新り合いをやっているのがいるんで
すよ。それで国学者というのは学問をしていれば安心だと思っ
ているととんでもないことで、学問したばっかりに暗殺された
国学者が少なくとも二人います。塙次郎と鈴木重胤。それは何
かというと、廃帝の例を研究していたと誤解されたからなんで
すね。鈴木重胤は、これは篤胤派なんだけれども、木像事件の
ときに噸笑したんですよ。木像を斬っても痛くないだろうとい
ってハハハと笑ったというんですね。それを聞きつけられて、
何者か知れない者に斬られて死んでいます。だけどそういう激
派のほかは、概して実務派なんです。農村救済とか何かやりま
す。明治維新になってもしっかりしていたのには、在地平田派
の力が大きいんです。
一方、歌学派のほうはまるっきりだめなんですよ。歌を歌う
か、歌を詠むかしていると思うと、いきなり行動に移ってしま
うんですよ、前後の見境なくという感じで。だから学問っぽい
学問をやらないんですよ。歌学派といっても要するに歌を詠む
のが真心だと。縦糸は万世一系の皇統であり、横糸は大和歌だ
というようなことをいって、いきなり現場に突入してしまうわ
けです。伴林光平なんていう人もその一人ですが。
広道はそういうふうにならないんですよ。極端にいえば「源
氏物語』を真面目に読んだのは、ほぽ広道一人ぐらいだったん
じゃないかということです。
後藤ありがとうございます。いまの野口先生の追加ご説明で
原岡先生のご質問がよくわかったのですが、わたしは単に平田
派の勤王的な熱気が上がったということだけかと理解しており
ましたが、そうではない、もっと実務的なものがあったという
ことですね。
野口はい。つまり歌学派というのは、何か内面的なんですね。
-54-
内面的というのは、こういう時代ではどうしょうもないんです。
後藤ありがとうございます。
久保田先生、何かおありでいらっしゃいましょうか。
久保田わたしも相当時間を超過したんじゃないかと思うんで
すが、ちょっと申し上げようと思いながら申し上げなかったこ
とは、「源氏集」なんかを持っていたということから、俊成は
やっぱり歌を中心に『源氏』を読んだのではないかということ
をさっき申し上げたんですけれども、しかしその俊成が、例の
「六百番歌合』の良経の歌に対する判調の中で「紫式部、歌よ
みの程よりも物かくふでは殊勝也」といっていることはやっぱ
り注目したいと思います。これは散文作家としての紫式部を評
価すべきだという提言とも受け取っていいんじゃないかと思う
んです。
そしてこれは全然触れませんでしたが、それに引き続きまし
て、定家の物語についての発言に続きまして、資料では『京極
中納言相語』の一説を引いておきました。これは定家の最晩年
における言談ですね。定家が弟子の藤原長綱に答えたものであ
りますが、その中でやはり定家が、『源氏物語』を自分はどう
読むのかということをいっている中で、「身に思給ふゃうは」、
これは「恩給ふる」とあるべきところですが「身に恩給ふゃう
は、紫の父祖の事をもさたせず、本歌をもとめむとも思はず、
詞づかひのありさまのいふかぎりもなきものにて、紫式部の筆
をみれば、心もすみて、歌のすがたこと葉の優によまるるな
り」というようなことをいっておりますね。これもやはり紫式
部の筆力を称賛したことばでありますから、歌人はすぐ歌に目
が行くでしょうけれども、それだけではない。やはり物語全体
の叙述ということを十分評価していたんだろうと思います。
ただ定家はこんなことはいっているんですけれども、自分で
はやっぱり実際にはいくらでも『源氏物語』の本歌取りをして
おります。それの一つの例として先ほど「ねやの月かげ」とい
うことばを問題にしたんですが、それ以外にも、ちょっと目立
って定家が使うことばに「聞きかなやまむ」という歌詞、歌句
があります。
これは壮年期というか、いちばん円熟したころの定家の歌に
二つぐらい出ているのですが、例えば「よそにのみききかなや
まむ郭公たかまの山のくものをちかた」とか「まだしらぬをか
べのやどの郭公よそのはつねにききかなやまむ」。いずれもほ
ととぎすの声について「聞きかなやまむ」といっているんです
が、これは『源氏」の読者ですと、すぐ「明石」の巻における
「いぶせくも心にものをなやむかなやよゃいかにと問ふ人もな
み」という源氏の歌に対する明石の君の返歌「思ふらむ心のほ
どややよいかにまだ見ぬ人の聞きかなやまむ」、あれを思い出
しますよね。そんなような使い方もしているので、特にどうい
うところから定家が『源氏』の句を取ってきているかなんてい
うことを探っていくと、定家の「源氏』読みの態度というのが
窺われるのではないかなということを考えております。
それから、平安最末期、中世初頭のころ『源氏物語』を、源
氏趣味といいますか、源氏文化を鼓吹した人として、わたくし
は土御門内大臣源通親の存在をやっぱりもっと見直すべきであ
ろうと考えております。これもすでに述べたことではあります
-55-
が、通親の二つの散文『高倉院厳島御幸記』、それから「高倉
院升還記」などを見ますと、非常に『源氏』の影響が細かいと
ころに見られます。「夢の浮橋」なんていうことばも、「夢のわ
たりの浮橋」、『源氏』の巻名であり、また引き歌に出てくるあ
の「夢の浮橋」ということばを広めたのは、あるいは通親では
ないかという気がするんです。その通親がやはり正治二年の
『百首』において、気がついただけでも三つぐらい源氏取りを
しております。
例えば「朝ごとに汀の氷ふみ分けて君につかふる道ぞかしこ
き」、これはのちに『新古今集』に採られましたけれども、こ
れは「浮舟」の巻での匂宮の歌「峰の雪みぎはのこほりふみわ
けで君にぞまどふ道はまどはず」、それの本歌取りであること
は明らかであります。
それから「なげきあまりあくがれいづる玉なりと君がつまに
しむすびとどめば」、これなんかは、本当に「葵」の巻での六
条御息所の生霊の歌「歎きわぴ空にみだるるわが魂を結びとど
めよしたがひのつま」、あれを直ちに連想させますし、それか
ら、これは恋の歌の中で「思ひくらすながめはうはの空なれば
ゆふべの雲のなつかしきかな」、これは先ほどもちょっと申し
ました、夕顔亡きあとに源氏が歌いました「見し人のけぶりを
雲とながむればゆふべの空もむつましきかな」、あれとそっく
りであります。
そしてこの通親も『正治百首』を詠む直前にやっぱり奥さん
を亡くしているんですね。先ほども申しました俊成と同じよう
なことを彼もやっている。あといちいち挙げませんですけれど
も、建礼門院右京大夫なんかを見ましでも、やっぱり右京大夫
は恋人の平資盛の追善をするときにすぐ『源氏』を思い出して、
源氏と自分をひき比べる。こんなことをやっています。このく
らいに現実が『源氏物語』の世界の中にずれ込んでいるという
ような、そういう生活というか、そういう感情を、このころの
歌に携わる人びとはもっていた。それほど『源氏』がらみにな
っていたという気がいたします。
後藤ありがとうございました。先生、とても資料をたくさん
出してくださった割には、時聞がちょっと、前半足りなかった
と存じますけれども、またのちほど。
では野口先生、こんどは。
野口こういうロスタイムのために用意しておいた話題なんで
すが。二つ追加というか、補足です。たんなるエピソードです
けども。
=一島由紀夫の「日本文学小史』というのがありまして、これ
は絶筆ですが、絶筆した時点がまたこれ『源氏物語』なんです。
それで大体三島由紀夫というのは『源氏物語』には驚くほど冷
淡なんですけれども、その中で何がいいかというと「花宴」だ
といっているんですね。ここに宮廷文化の、何といいますか、
いちばん完成があるといっている。以下引用ですが「源氏の罪
の意識を主軸にした源語観(源氏物語観)は、近代文学に毒さ
れた読み方の一つではないか」といっています。これはたんに
参考までに、です。何のコメントもないです。
それからもう一つは、つまり『源氏物語』調喰説というのは、
これはいろいろバリエーションがあるということの一つの証し
-56-
なんですけども、幕府側からも読めるんですよ。幕府に有利に
読めるんです。依田学海という人がいます。明治の文人として
皆さんご存じだと思いますけども、実はこの人物は、江戸時代
には佐倉藩の堀田家の留守居役です。江戸留守居役というのは、
つまり外交官ですね。だから情報収集を種々やっていて、それ
をその必要のためにというか、当人はそういうけども、それを
名目にして吉原へは行くわ、茶屋へは上がるわ、歌舞伎には行
くわという暮らしをずっとやっていた。官々接待のハシリです。
また勉強家であり、たいへんいろいろ読んでいるんですね。
この人物が、これは岩波から出ている『学海日録』でいつで
も見られますが、安政三年三月十四日の条にこういうことを書
いています。「座間に源氏物語湖月抄を見る。借りて之を読む。
云々」とあって、要するにこれはたいへんいいというわけです
ね。たいへんいいものだと。「予、是の書を読まんと欲して、
久しく果さず」。もってはいたけど読まなかったと。「今一たび
寓目するを得て、大いに素願に称ふ」。ょうやっと読めたとい
うわけですね。「予聞く、源語は大抵淫狼にして、君子の読む
べき者に非ず。蓋し西土の小説流のみと」、そういうふうにい
ったという。つまり『源氏物語」は淫狼な読物であって君子人
が読むものではないと。西土というのは中国という意味です。
大体これは『紅楼夢』『金瓶梅』の類いだというふうに思って
いたと。
そしたら傍らに栗原信允という人物がいて、この人は幕臣の
有職故実家なんですが、こういったというんですね。「源語は
是れ王室の類廃を慨きて志を寓する者なり。其の宮内の醜状を
審らかにし、貴戚の蚊屋を」、親戚ですね。藤原ですね。「蚊屋
を論ずるは最も作者苦心の処なり」と。つまりこれは寓意があ
ると。王室が衰えているのを歎くんだと。それは宮内の醜状と
いうのは、多分安政のころですから、尊王撰夷派の公家たちの
ことを意味している。だから全くさっきの近藤芳樹とは逆の角
度からいえるんですよ。
だから『源氏物語』というのは、ろくに読まないでもある意
図のもとにいくらでも活用できるという。調誠説というのは、
そういう面があるわけです。つまり広道はそれとはちがうとい
うことをいいたいわけです。
後藤近世から近代初期にかけての複雑な国学思想史の関係が
浮かび上がってきたように思います。
それでは四時ちょうどから後半の質疑応答のほうに入ってま
いりたいと存じます。先生方、どうもありがとうございました。
休
憩
!
後藤それでは、第二部の質疑応答に入らせていただきたいと
思います。
こういうシンポジウムにおいては、よく後半に質疑が集中し
まして、最後が不完全燃焼でちょっと物足りないという思いを
なさる方が多いかと思うんでございますけども、先ほどパネラ
lの先生方同士の質疑応答や追加は済んでおりまずから、どう
ぞ早速フロアのほうからの質疑をいただきたいと存じます。よ
ろしくお願いいたします。
いかがでいらっしゃいましょうか。パネラ!の順序というこ
とではなしに、どの先生へのご質問でも、順不同でお受げした
-57-
いと思います。どうぞ、よろしくお願いします。マイクが三本
ほど用意してあると思いますので、前のほうにマイクの方どう
ぞお願いいたします。いちばん前の先生です。
小林神奈川県立鶴見高校の小林と申します。先生方のお話を
伺いまして、非常にわたし自身いろいろためになった部分があ
りまして、本当に感謝したいと思います。
野口先生にちょっとお尋ねしたいんですが、わたしはたまた
まいま高校三年生に『源氏物語』「初音」、それから「野分」
「若菜」上下というふうに教えてきているんですが、わたしが
抱えている生徒は非常にこういう「源氏物語」をよく読んでい
る生徒なんですが、いまいろいろ社会問題化している、たとえ
ば青少年のいろいろ社会問題がありますね。低年齢の青少年の
犯罪とか。そういう中で、たまたま野口先生のお話を聞いて、
「もののあはれ」というのは人間のつきつめた真心であると。
やっぱりちょっと極論かもしれないんですが、そういう問題を
起こすような、例えばそういう青少年についても、やっぱりそ
ういう武士にもあるこういう「もののあはれ」がわからないの
はだめだというような、そういう発想の中で、例えば『源氏物
韮巴をいまの社会にどういうふうな形で還元できるか。わたし
はたまたま教育の場におるんですが、その中でどういうふうに
したらより効率的、ということばはよく合わないと思うんです
が、より深く、日本あるいは世界の文学の財産であるこの「源
氏物語』をよく理解してもらえるかというところをいま考えて
おるんですが、野口先生、そこらへんご意見がありましたらよ
ろしくお願いします。
野口ぽくがお答えするのに適当な人物かどうかわかりません
けれども、ぼく自身の経験からいいますと、高校のときにいい
国語の先生がいたんです。野本秀雄さんという方で、ご承知の
方もいると思いますが、その方にクラスで『源氏物語』の「夕
顔」の巻を習ったのでこういうことになったんです。何か恨み
をいうみたいですけども。そういうようなところがあります。
だからずいぶん大きいと思いますね、先生の影響というのは。
特に「夕顔」の巻だったのがいいと思います。つまり「桐壷」
からとかナントカそういうことでなしに、「夕顔」がいいんで
すよ、短編小説として。どういうところがいいかというと、や
っぱり、十七歳でしたつけね、あれは。
後藤源氏十七歳。
野口の少年なんです。問題の十七歳。そして何か怖いもの知
らずでできるわけでしょう。それが夕顔と呼ばれるなぞの女性
とデートして、二人っきりになろうとかいって、おばけが出ま
すよね。そのあと完全に少年に戻るでしょう。恐怖の。そうい
うところなんかもものすごくよくわかるんじゃないですか、い
まの高校生に。
そして、その広道の「評釈』はお読みでしょうか。そうです
か。その「夕顔」の巻のその段は抜群です。つまり広さがわか
るんですよ。寝殿ですね。広さというのが大体、ざっと計算し
たんだけど百六十平米ぐらいになるんです。
後藤百六十平米じゃきかない。一万平米ぐらい。
鵬谷平米ですか。平米だと一万四千。
野口邸の面積じゃなくて建物。
-58
鵬谷建物ですか。
野口源氏たちのいる寝殿の母屋です。とにかくものすごく広
いと思いますよね。その一角で燭台しかないわけでしょう。二
人のいる御帳台周り全部闇なんですよね。その閣の彼方からひ
たひたと迫ってくると。もちろん本文にそう書いてあるんだけ
ども。それはいい注釈があれば、本当に立体的に感じますね。
だからそういうのを読んで味わう少年であるかどうかというの
は、ものすごくちがうと思います。ぼくは多分そのせいでグレ
ずにここまで来たんだと思います。以上です。
後藤小林先生、よろしゅうございましょうか。それではどな
たか、どうぞお願いいたします。
田坂後ろのほうから申しわけございません。今日はおもしろ
いお話をありがとうございました。福岡女子大学の田坂と申し
ます。久
保田先生に教えていただきたいのですが、歌人たちが「源
氏物語巴の和歌を利用しているというお話を、たくさん用例を
挙げて教えていただいたんですけれども、最後に建礼門院右京
大夫のお話も出ましたので、世尊寺伊行の『源氏釈』ですけれ
ども、古い形とわたしは思っているんですけど、伝本には、注
釈の必要がないにもかかわらず、「源氏物語』の和歌をほぼ全
部引用しているのではないかと思われるような、そういう資料
もあるのですが、ひょっとすれば、お話に出ました「源氏集」
のような、そういう性格なども、まだ注釈として確立していな
いころの『源氏釈』なんかにはひょっとしたらあったのではな
いかなというふうに考えているんですけれども、そういうこと
は可能性として考えてもよろしいでしょうか。そういうことを
ちょっと教えていただきたいんですが。
久保田わたくしは「源氏集」という名前を『林下集』の調書
で見ているだけですので、本当にその実体はわからないんです
けれど、ただやっぱり「源氏集」というんですから、歌集のよ
うなものだろうと思って先ほどのようなことを申し上げたわけ
です。そ
れで右京大夫の問題ですけども、ご承知のように右京大夫
は俊成の家と非常にかかわりが深いわけですね。というか、世
尊寺伊行と俊成とが右京大夫の母である夕霧をともに愛したか
もしれないと。多分愛したのではないだろうかというふうに考
えられておりますよね。そんなことから考えますと、確かにそ
ういうものを右京大夫も見る機会があったでしょうし、あるい
は父の伊行も見る機会があり得ただろうと思うんですね。想像
するといろんなことが想像されます。
ですから、確かに伊行の講釈なんかの成立と、やはりそうい
うものとからめて考えるべきかなあと思つてはおります。ただ、
わたくしは『源氏』の古注なんていうのは、本当にこれから勉
強しないといけないので、そのへんはむしろ『源氏』のご専門
の方々にご意見を伺いたいと思っているわけです。ただそうい
うものがあったらきっと右京大夫も見ているのじゃないかなと
いう気は大いにしております。あまりお答えになりませんです
けど。
後藤ありがとうございました。田坂先生、よろしゅうござい
ますか。つい一日二目前に『源氏釈』の新しいテキストが出ま
-59-
したけれども、渋谷さんはおいででいらっしゃいましょうか。
何かご意見おありでいらっしゃいましたら。よろしいですか。
それでは、俊成の周辺に関しては、先ほど『今鏡」作者と美福
門院加賀のル
lトから俊成、御子左家というような、ある程度
の見通しのようなものが、膿谷先生から久保田先生にかけてや
や流れたかのように承りましたけれども、平安末期の和歌史な
どなさっていらっしゃる先生方から何かご意見なりご質問なり
ございましたでしょうか。
それではどうぞ、話題を変えまして、どなからでも、よろし
くお願いいたします。
鵬谷ではわたくしから原岡先生にちょっと教えていただきた
いんですけど、先ほど幼い紫の上の描写について、非常に詳し
くご説明いただいたんですが、『源氏』以外の平安の物語で、
子どもというのはどんなふうに描かれているんでしょうか。
原岡というのは、この小さな紫の上のような描写が出てくる
かどうかということですか。
腕谷ええ、そうです。
原岡子どもということになりますと、例えば『土佐日記』の
中で見えない子どもといいますか、亡くなってしまった子ども
というのが一つの隠れた重いポイントとして出てきて、ーーーと
いうのが非常にもう一つ印象的な子どものような気がします。
あと「宇津保』などですと、まだ全然調べていないのですが、
犬宮など大きくクローズアップされはしますが:::。全体とし
ては美しさ、愛らしきゃ、聡明さの型通りの強調が、目立つよ
うな気がしています。
鵬谷そうするとやっぱりあんなふうに幼い紫の上をよく見て
書けたというのは、やはり紫式部という女性の、いわば母親と
しての体験とかそういうものが生きているんですかね。どうな
んでしょう。
原岡あまりそういうことは、全然頭になかったんですけども、
「枕草子』の中で、小さい子どものとても生き生きとした記述
が出て来て、そこのところで清少納言がお母さんだったのかど
うかというようなことも問題になったりしますが、:::母親と
しての体験ということなのでもありましょうか。
私は、あまり紫式部自身の体験ということとは結びつけて考
えたことがなかったのですが、むしろ「若紫」のところで出て
くる子どもの描写に関しましては、例えば「顔はいと赤くすり
なして立てり」というので、泣いて、こすって赤くなった跡が
見えるという、この辺のところなど、むしろスサノヲがわんわ
ん泣いて、物が皆枯れてしまったという、そういったところと
結びつけて前に考えたことがあります。もちろん平安の『源氏
物語』は非常に洗練された優雅な物語ですから、わんわん泣い
て汚く演が出て、:::などといった、そういう話は出てこない
んですけれども、むしろあの須佐之男命のエネルギーみたいな
ものの痕跡がこういうところに止められているのではないか、
などと考えたことがあります。何かお答えになっていないかも
しれないんですけども。よろしいでしょうか。
後藤わたし先ほど原問先生のお話を伺っていて、紫が登場し
てきた源は、筋立てのうえからいうと、藤査への愛欲が導き出
したということになりますが、それにしては、藤壷そっくりの
60
大人子どもではなしに、子どもと等身大の、つまり藤壷への憧
僚とは異質の、逸脱、物語のうえでは逸脱というふうにおっし
ゃいましたけれども、そういう造形がなされているのだという
ことを、はっとさせられるような思いで伺っていたわけですけ
れども、例えば江戸時代の版本の挿絵などでは、子どもは大人
の小型という形で描かれますね。その割には、平安時代の、例
えば『寝覚』の絵巻の子どもでしょうか。比較的子どもを、江
戸時代の版本の挿絵よりは正確に子どもをとらえているという
ような気がするんですけれども、そういう意味では、比較的子
どもを見る日というのが、大人の小型化ではなしに、地盤とし
であったのかなと、いま原岡先生の『枕』などのお話を伺いな
がら思ったのです。
原岡大人とは別のものという形で見ていた、そういうまなざ
しがあったということですよね。
後藤子どもについては、先ほど原岡先生のほうからもご指摘
がありましたように、川名淳子さんとか森野さんとか中西さん
とか、いろいろご論文があるようですが、何か関連してご質問
なりご意見なりおありでいらっしゃいましょうか。よろしくお
願いいたします。
堀川池坊短大の堀川と申します。堀川善正です。いま子ども
が出ましたが、それと関連して、大人が、むしろ大人もお聞き
したい。質問なんです。
ことに女の場合は裳着、袴着。男子の場合は元服。元服すれ
ば当然、いわゆる添い伏しというように、いわば性的な何かも
出てくる。そうしますと、そういう大人、源氏も十何歳でもう
早々と元服して、そういうこともできて、いわゆる大人という
こと。そういういわゆる性的なことを含めて大人という。現在、
とにかく十七歳で少年法とかナントカとやっておりますが、や
はり何か法的な、儀式的なものとかかわっている、そのあたり
のことをお聞きしたいと思います。以上です。
後藤ありがとうございます。いまのは、特にどなたかにご質
問ということではなく伺っておいてよろしゅうございましょう
.刀堀川そうですね。結構です。
後藤どうもありがとうございました。まだほかにおいででし
たら。
神野藤跡見学園女子大学の神野藤昭夫でございますが、野口
先生と原岡先生にそれぞれ関連することがらについておうかが
いいたします。野口先生のお話で、ポスト宣長以降の『源氏物
語』研究の動向が、非常に明快にみえてまいりました。その限
りではよくわかったのですが、幕末からの『源氏物韮巴研究が、
明治に入って、どんなふうに継承されてゆくのか。断絶がある
のか、飛躍するのか。たとえば明治十年にできあがる東京大学
あたりでは、法制史を専門とする小中村清矩などが中心となる
わけですが、そういうアカデミズム内部ではどんなふうに受容
されているのか。それから、もう少し後になって帝国大学を出
た芳賀矢一や藤岡作太郎などの、近代国文学の成立を担う世代
の受容のしかた、それらとお話しになられた幕末までの「源
氏』研究との関連を、どんなふうに理解したらよいのか。先生
のご意見を承ることができればありがたいと思います。
-61-
原岡先生の『たけくらべ』と「源氏」との詳細な対比で、一
葉が『源氏』をずいぶん丹念に読んでいたということがよく理
解できました。お話から、一葉だけでなく、そういう『源氏』
を読む人たちの存在が、裾野のように広がっていたようにも思
われてくるわけですが、そうした実態と和学とか国学とかの研
究との関わりあいというか、重層性といいましょうか、そのへ
んのところはどんなふうになっているのだろうか。ただ発展的
興味だけからうかがうのですが、お教えいただけることがあり
ましたらお願いいたします。
後藤では野口先生からよろしくお願いします。
野口それ、ぽくの守備範囲からはずれるんですよ。宮沢大蔵
大臣みたいに、所轄範囲ではございませんといえば済むことな
んですけども。
ぼくはものごとを考えることと調べることの二つに分けるん
ですが、これは調べることに属すると思います。だから、確定
的なことはお答えできませんけども、一つメルクマールになり
ますのが、新しい『源氏研究資料集』が出ているみたいですけ
れども、古いものがありますね。三省堂の国語国文学研究資料
集成。近藤芳樹とか、堀内匡平とか、もってきたものと同じも
のですけれども。これ近藤芳樹のあとがすぐに坪内遁遥なんで
すよ。一度にがらっと変わります。
それで、あるいは間違いがあるかもしれませんけども、連続
していないと思います。いきなりこんど西洋文学のジャンル区
分がありますね。それに『源氏物語巴をはめ込もうという発想
になると思います。その聞の断絶がどのくらいのものであり、
何年ぐらい時差があるかということは、これは調べなければわ
かりません。
ただいえることは、明治になって国学というのは、ものすご
い貧乏くじ引きますね。例えば平田派は、島崎藤村の青木半蔵
ですね。初めは明治政府で一つできますでしょう。祭政一致で
すから。で、お祭りのほうはどんどん削り落とされていって、
「国学者は売られた」という有名な台詞を残して玉松操は消え
ていきます。そんな時代ですから、国学も国学の延長としては、
扱われていなかったと思います。
東大で文学部ができたとき、いちばんの人気は哲学ですよね。
哲学というのは、フィロソフィーと思うとそうじゃなくて、い
やフィロソフィーなんだけども、何か哲学というのは、キリシ
タンパテレンの秘法みたいに思われていたみたいです。それを
身につけると何でも問題が解決する、そういう学問だというん
で哲学をこしらえたと。これは三宅雪嶺がいっていることだか
ら本当だかどうか知りませんけれども、そんなありさまですか
ら、国文学科というのは、どころか国学というのはあとのほう
に拾い上げられてきたものだと思います。漢学も同様に惨憎た
るものだったと思います。
しかし一方、ここで原岡さんのほうに回すんですけども、中
島歌子でしたか、あの塾で『源氏』をやっているでしょう。あ
れは何でしょうか。「湖月抄』を使っているんですか。何かそ
のあたりを。そういうふうに振ります。
原岡私も守備範囲でなくて、とお答えしたいところなのです
が、萩の舎という歌の塾で何を使っていたかというのは、本当
-62
に申しわけないんですけど、調べておりません。ただ、樋口一
葉がこの『源氏物語』を講じていたといいますか、教えていた
というのが出てきまして、非常に粗末な身なりで、何か非常に
厳しい顔をして「源氏』を教えていたというふうなことを、思
い出としてそれを聞いた方が書いていらしたのを読んだことが
あります。
そういう形で樋口一葉は、自分で単に読んで楽しんでいたと
いうだけではなくて、解釈していたといいますか、講義をし、
教えていたというふうなことが一つはあったということだと思
います。
それでは、当時の、明治初期といいますか、一葉の時代にど
の程度『源氏」が読まれていて、そしてそれは『湖月抄』だっ
たのかどうかということについては、全然調べていないので、
よく分からないんですけれども、少なくてもそういう形で、今
のカルチャースクールではないのですが、萩の舎のようなとこ
ろで、||ここはかなり一葉とはちがって豊かな階層の女性た
ちも集っていたところだといわれていますけれども||そうい
う講義を聞いていたという形で、明治の女性たちが『源氏』に
親しんでいたということがある程度言えるだろうとは思います。
お答えになっていないかと思いますが。
神野藤要するに、階層の上の方でも下の方でも実態はよくわ
からないけれどもずいぶん分厚い層の中で読まれていた。そう
いう観点から捉えなおしてみなければいけないらしい。個人的
感想として受け止めました。ありがとうございました。
後藤神野藤先生、ありがとうございます。いま出てきた中島
歌子の『源氏講義録』が昨年発見されたのか、前々からわかっ
ていたのを昨年発表なさったのか、新聞にもちょっと話題にな
りましたけど、実践女子大学の野村先生か上野先生か、そこら
へんのこと、おわかりでいらっしゃいましたら、いまちょっと
コメントをしていただけましょうか。おいでじゃいらっしゃい
ませんか。
野村実践にこの三月までおりました野村でございます。です
からもう実践とは縁がないのでございますが、そういうような
ご指名がございましたので、ちょっとひとことだけ釈明させて
いただきます。
いまおっしゃった『源氏講義録」が発見され、あるいは発表
されたというのは、もしかしたら歌子ちがいで、下回歌子の講
義録ではないかと思うんでご、ざいますが。
後疎あっ、そうでしたか。失礼しました。
野村ちょっとそのへんが、萩の舎の名前が出てきではらはら
していたんですが。その件につきましては、ちょっと補足的に
申し上げさせていただきますと、それは実践の卒業生の方の縁
故の方が、中島門下でいらっしゃいまして、一葉なんかと非常
に親しくしていたので、そういう関係から、その一部でござい
ますが、いろんな文献が実践のほうに入ってまいりまして、そ
のことについてわたくしどものほうで調べたということがござ
います。ただいま『源氏』の話が出ていますが、残念ながらそ
れらの諸文献は実際「源氏』はほとんど関係ございません。
下回歌子の「源氏』の業績につきましては、別途にわたくし
も書いたことがあるものですから、それはそれで別の話にした
-63-
いと思いますが、ちょっと立ちましたついでにひとことだけ野
口先生に伺いたいんですが、よろしゅうございますか、そうい
う質問をして。
後藤はい、どうぞお願いします。
野村実は芳賀矢一が『国文学史十講』でもって、坪内迫遣の
『小説神髄』を引いて、そこに「もののあはれ」が出てくると
いうことを普通いわれていると思うんですが、そのへんの関連
はいまのお話の中ですとどういうつながりになりますでしょう
か。先ほど、つまり幕末国学から近代国文学へ、「源氏』のそ
ういう「もののあはれ」の理解みたいなもの、「もののあはれ」
といえば宣長もかかわるわけでしょうから、それが国文学にど
うつながっていくかという結節点にそれはなるのではないかと
いうのが、わたしの疑問で、これは全く中島、下回の歌子さん
たちの『源氏』とは関係ないんでございますけど、ちょっとお
伺いしたいと思いまして。
後藤とんだ無学をさらしまして、お恥ずかしゅうございます。
野口先生、ではお願いいたします。
野口ぽく本当にうろ覚えなんですけども、芳賀矢一さんて国
学ということばを使いますね。これが宣長・篤胤のいっている
国学と同じものかどうかということがございますね。ドイツ語
の訳ですよね。何というんですか、ドイツ語で国民文化の学み
たいなものがあるんですよ。何かそれが国学だと。ですから、
ぼくは継承というのは、非常にぼくは極端に図式的にいうほう
ですから、つまりあったかなかったかと考えた場合、ないと見
たほうがいいんじゃないかと思います。
それが野に下りますので、以後の近代日本文学では、ロマン
主義が間欺的に吹き上げてくるというような格好をとります。
国学というものは官のものになりにくいところがいまだにある
んじゃないかと思いますけど。これは本当にお答えではなくて、
逃げ口上なんですけども。そんなことで勘弁していただきます。
野村どうもありがとうございました。
野口ついでにいわせていただきますと、「もののあはれ」が
だんだん、要するに真心の、純粋度になってくると申し上げま
したけども、それも問歓的に出てきますね。与謝野鉄幹で出ま
すね。そのあと三島由紀夫に出ています。三島由紀夫の有名な
ことばなんだけども、これは『林房雄論』でしたか、つまり問
題はベクトルではなくてボルテージだという言い方をします。
つまり左を向こうが右を向こうがそれは問題ではない。何とい
いますか、エネルギーの、真心の量が問題だという言い方をす
るんですね。これは完全に右翼なんですよ。左翼はそういう考
え方は決してしないです。だから国学イコール右翼じゃありま
せんけれども、何か真心というのは絶対値みたいなもので、ど
んな符号でも取り得るという、そういうものが脈々とあるんじ
ゃないか。それが官のものにならないのは非常にいいことなん
じゃないかと。いよいよ脱線しましたけれども。
後藤どうもありがとうございます。何かほかに、いらっしゃ
いませんでしょうか。
堀川さきほどの子供の問題について、やはり久保田先生、野
口先生にお答え、あるいはご意見を伺いたいんですが、それは
江戸時代の好色物『一代男』の世之介ならば、子どもというこ
64
とを果たしてあるのかどうかもなんですし、やはり大人に対し
て子どもという概念があるんじゃないかと思いますので、その
あたり久保田先生、あるいは野口先生、両先生のお教えといい
ますか、ご意見を教えていただきたいと思います。
野口これいま衆議院で少年法を審議しているでしょう。これ
ものすごいホットな問題なんですよね。ですから、いまの少年
法の年齢がいくつかということは一切カッコに入れての話です
けども、何といいますか、法的に、何歳までが少年かというこ
とを決めることと、それから自然に性的に成熟して大人になる
年齢とのあいだには、相対的にずれがあると思いますね。
いまの少年法というのは、戦後日本のですよね。それ以前に
は徴兵年齢というのがありましたでしょう。それから元服年齢
というのがありますね。それでそれはどうも日本の社会に合致
していたと思うんですよ。現行の少年法がそれであるかどうか
ということは、非常にアクチュアルな問題ですから、明言は致
しませんが、どうなんでしょうか、実際以上に、現実の少年少
女というのは、われわれが法的に考えているよりもはるかに成
熟しているというふうに思いますね。ですから、たとえば少年
法といったものの基本は、実際の現実に、教育的とか懲罰的と
か、そういう問題ではなくて、その民族の成熟度に即したとい
うことを、根本的に考えてみる必要はあるんだろうと、そうい
うふうに思います。そういう趣旨のご質問だと思うんですが。
後藤堀川先生のご質問はそれでよろしいですか。
堀川それでは平安時代ならば、いわゆる男子なら元服と。
野口それは制度上の問題ですから、膿谷先生にお願いします。
つまり何歳で元服ということがあったかどうかということです
ね。堀川男子なら元服と。元服すれば添い伏しができると。性的
なものも経験すると。そういうものはもう大人になってしまっ
たと。子どもであっても。そのあたりも教えていただきたいと
思いますが。
後藤それじゃ膝谷先生から、平安時代の元服。
堀川久保田先生に。
鵬谷ではあとで久保田先生に振りますげども。もう平安時代
には元服ということは大人になる。女の人は裳着ですよね。た
だ年齢差はおそらく十歳から十五歳ぐらいまでで、人によって
幅がありますけれども、大体十二歳前後で一克服をするというこ
とは、もう大人の世界に入る。女性の場合は裳着を済ませれば
もう大人の女性になるということですから、そういうことが一
つのけじめになっていますね。ただ個人差がありますし、名前
だって頼通とか道長とか、ああいう名前は元服後につく名前で
あって幼名が必ずあるはずです。道長の場合はわかりませんが、
頼通は田鶴、このように名前も変わるということで、元服と裳
着は大人の世界に入る一つの境になっていると思いますね。
後藤それじゃ久保田先生、何か。
久保田本当にこれはわたくしが騰谷さんに教えていただきた
いことでして、いまお答えいただいたことでなるほどと思った
んですが。わたくしも平安の末から鎌倉にかけての、例えば歌
人なんかの、貴族としての歩みをよく日記記録から探ってみよ
うと思うんですけど、なかなかわかりませんですね。
-65-
ですが確かに元服は相当人によってちがうようなんで、大体
それから叙爵ですか、まず爵位を授けられる。貴族の場合だと
従五位下ぐらいからですか。その出発点というのは、本当に人
によってずいぶんちがうようですね。あれは当然親の関係その
他、いろんな縁故関係でそうなるんだろうと思うんですが、そ
ういう叙爵の年齢のちがいなんかが、その後のその人の成長に
どうかかわってくるのかなんてことは、非常におもしろい問題
だとは思つてはいるんですけど。全く、ただおもしろいなと思
うだけで、具体的にどう調べていいかもわかりません。
例えばわたくしにとっては比較的身近な存在、身近というの
はちょっと畏れ多いですが、関心をもっている存在ですと、や
っぱり定家の一族でして、定家はご承知のように『明月記』を
残しておりますから、子どもたちの成長過程なんかもある程度
推測できますね。そうしますと為家、あれは幼名が「みな」だ
ったと思いますけど、「みな」だった時代、それから為家とな
って、だんだん貴族社会に出ていく、そのあいだのことをずー
っと、日記が残っている範囲内ですけど、定家が見つめていろ
いろ書いている。大体子どもの愚痴ばっかりいっているわけで
すが、あんなことから昔の貴族の標準的な成長過程というもの
を考えていったらいいんじゃないかなということを思っており
ます。そ
れから、またそういうことと関連して、歌人が歌を読む年
齢というのはいつごろからかということも、非常に関心がある
んですが、これもあまり詳しい資料はわかっておりません。た
だ思いのほか遅いんじゃないかという気もするんですね。それ
は突き止められないだけかもしれないんですけれども。定家の
ような大歌人も伝説としては乳母に抱かれながら歌を詠んだな
んていうのがありますけれども、そういうものを除きますと、
やっぱり相当たってから公の歌会に出てくるような気がしてお
りまして、そんなこともちょっと人間の成長ということで考え
ております。これもあんまりお答えにならないと思いますけど
ふU
。堀川すみません。歌をいまいっていただきましたけれどもあ
りがとうございます。歌は、これは恋の心を知ったら歌が詠め
ると、何かありましたですね。だからいわゆる本当に歌が詠め
るということは、恋心との関連が非常に濃厚であると。すれば、
子どもでは詠めない。もし子どもが詠んだら、そのときは大人
になっており、歌の恋心がわかっており、歌も詠めたというふ
うになる。そういう考え方が一部あるんじゃないでしょうか。
そのあたりについて教えていただきたいと思います。
久保田先生か野口先生に伺いたいです。
久保田これ本当にわたしもただ感想ですけれども、確かに本
当の恋をしないでいい恋の歌はできないと思いますけど、ただ
やっぱり恋なんかほとんどわからないころから、練習というこ
とで恋の歌は詠んでいるとは思います。あの時代はみんな題詠
ですから、恋の題は当然出されるわけで、そうしましたら、幼
いとはいえ、歌会に出席したら恋の歌を詠まざるを得ないわけ
で、そういうことで詠んでいると思います。それで一応表現の
パターンみたいなものはそういう場で習得していく。
しかし、それが本当にいい恋の歌となるのは、やっぱりそれ
-66-
は実際に身を焦がすような恋を経験してからでないと詠めない
でしょう。「もののあはれ」の話がずいぶん出ましたけれども、
「もののあはれ」論で宣長が必ず引く俊成の歌がありますよね。
「もののあはれもこれよりぞしる」という、あれは何でしたつ
け。なにしろこれは恋をしろという歌ですよね。だから、それ
までの、いわば練習曲を弾くような形での恋の歌というのは、
ずっと子どものころから詠んでいるとは思うんです。ただ、そ
れだけじゃものにならないという気がするんですね。
堀川題詠で恋の歌を詠めるからもう大人であると。では子ど
もならば歌はもともとは詠めないということにいえるんでしょ
うか、どうでしょうか。ちょっとそのあたりをお願いします。
子どもならば、歌は、本当の歌は詠めないと。たんに手習いだ
けであるというようなことになって、ちょっとそのあたりそう
も思えてしまうんですけど、そのあたりについてお願いいたし
ます。
久保田ですから子どもの段階はやっぱりそれだと思います。
それで止まってしまう人もいるかもしれないとも思うんですよ
ね。ですけれど、歌人となるだけの人は、それで止まらないわ
けで、それは人によっていろいろだろうと思うんですが。
野口それに関連して申し上げますが、西鶴の世之介は、あれ
は源氏のパロディですから基準にはなりません。本来ならば、
西鶴は三つぐらいからやらせたかったと思います。しかし光源
氏のパロディだから、それから逆に制約されます。
それから、結局これ、いま話題にされていることというのは、
個人差の問題だと思うんですよね。それと一般的に年齢がいく
つぐらいかということは全く別問題だと思います。ですが、文
学というのは、優れた個人でやっていくものだから、だれかが、
何といいますか、標本というものになると思いますね。
それで今年三島由紀夫が三十周年で全集が出るんです。少年
時代のノ
lトが出てきたんですよね。それを見ると、全部でき
ていますね。死に方まで全部プログラムされているような感じ
です。だから生まれつきすべてを知っている少年というのもい
るんですよね。定家なんかもそういうところがあったんじゃな
いですかね。ですから、そういうのが引っ張っていくんじゃな
いですか。つまり少年の文学的成熟度というのは、そういうの
が引っ張っていくんですね。平均点を、こういう場合平均点と
いうのかどうか知りませんけども、上げていくんだと思います
30
E
,a司久保田さっきいいかけて度忘れしていたんですが、俊成の歌、
よくご承知だと思いますけど申し上げます。
「こひせずは人は心もなからましもののあはれもこれよりぞ
しる」ですね。あれは宣長が大好きな歌で、何度も引いており
ますが、あれは堀景山から習ったんじゃないでしょうか。宣長
自身の発見じゃないかもしれません。若いころの儒学の勉強の
たまものかもしれませんですが。あれは俊成の本音だろうとい
う気がいたします。それでやっぱりいい恋の歌というのはその
とおりで、「こひせずは人は心もなからましもののあはれもこ
れよりぞしる」だろうと思うんです。
これ、この機会にちょっと野口さんに伺いたんですけど、こ
こにいらっしゃいますか、百川さんの「もののあはれ」論につ
-67-
いて、野口さんはどうお考えですか。
野口(苦笑して)百川さんおいでになるんですか。実は敬遠
して読んでいないんです。どうもすみません。ここでそういう
ことを聞かれるとは思わなかった。
後藤それではあと十分ぐらいしか時聞が残っておりませんの
で、この機会にぜひ聞いておきたいことがございましたら。
久富木原共立女子短期大学の久富木原と申します。原岡先生
にお伺いしたいんですけれども、細部の力ということで。わた
しもちょっと細かいことが気になりまして、教えていただけれ
ばありがたいんですけれども。
『たけくらべ』のことなんですが、先ほど萩の舎の話なんか
も出ましたけれども、一葉は源氏取りの歌も何首も詠んでおり
ますし、非常に「源氏』には関心が深かったということがわか
るんですけれども、原岡先生のお話も、とてもそのとおりだと
思って感服して伺ったんですが、わたくしが気になっておりま
すところといいますのは、実は美登利が子どもから大人へと変
貌するところが、遊女になるところももちろんそうなんですけ
れども、酉の市で長吉に草履を投げつけられる。あそこはとて
も大きな山場だというふうに思うんです。あそこの場面は、祭
りの中で、しかもたくさん人がいるその面前で侮辱を受けると
いうことで、やはりすぐに連想されるのが車争いの場面だとい
うことだと思うんです。
ちょっと話は飛びますけれども、そうしますと、車争いの場
面には、紫の上は全く関与していないわけで、どうしてそれが
あそこの場面にいきなり出てくるのか。車争いを連想させる場
面が出てくるのかということは、とてもわたしは前から不思議
に思っていたんですけども。『たけくらべ』のいちばん最後の
場面で、信如が、造花の水仙を美登利の家に置いていくところ
がありますけれども、あそこはわたくしの解釈では、源氏が
「榊」の巻で六条御息所から菊の校に付けた歌を贈られる、そ
のパロディなのではないかというふうに思っているんです。
そうしますと、そういうとらえ方をしますと、美登利という
人物は、最初は若紫なんだけれども、大人の女性としての憂悶
というのを抱えるようになってからは、六条御息所のもつ憂悶
というか、そういう形に大きく転換していくのではないかとい
う、そういう感想をもっているものですから、そのところを、
何というんでしょうか、きょうの原岡先生のお話に関連させて、
わたくしなりに考えると、そういう大人の女性としての憂悶と
いうところで、原岡先生のおことばを使わせていただきますと、
何か全然別の女性なんだけれども、大人の女性の憂悶というと
ころで何か一葉の『たけくらべ』の中でスパークしたというん
でしょうか。その二人の女性がスパークしちゃったというんで
しょうか。そういう形で何か新しい物語の状況みたいなものが
生み出されていったのだろうかと。何かそんなふうな感想をも
ったんですけれども、原岡先生にぜひそこのところをお教えい
ただければと思います。
原岡今たいへんおもしろいことを教えていただいて、といい
ますか、私はそれは全然考えていなかったことなのですが、一
つ申しますと、祭りのところで草履をぶっつけられて、という
話が出てきまして、私も実はここはちょっと気になっておりま
-68-
した。祭りというのが確かにくっきりとした背景になっている
のです。さっき引きましたが、前田愛氏の論の中でも美登利が
西の市の祭りをきっかけに、もう一つの遊びの空間に迎え取ら
れていく、という読みが示されていて、つまり祭りというのが
大きなきっかけになってるということについて、注目されてい
るところがあると思います。
わたくしはこれは「源氏物語』の中の「葵祭」、車争いとい
うのと、ちょっと関連してくるのかしらと、実は少し思ったと
ころなんですけれども、ーーーその時に、久富木原さんは、六条
御息所の憂悶、紫の上が大人の女性になった時の問題、という、
そこのところに結びつけられるわけですけども、私自身として
は、そこまではちょっと今のところ、考えていなかった、私の
中ではむしろうまく整合しないというところがあります。
むしろ祭りがここのところに取り込まれるというのは、祭り
の高揚といいますか、祭りを背景にしたときに、祭りが登場人
物に乗り移る、といったことは、やっぱり古い時代の作品から
新しい作品まで、みんな言えるような気がするんですけれども。
祭りの高揚を背景にしたときに何かが起こる、といったことつ
であるような気がするんですけども。むしろその祭りのカみた
いなものがここにも働いていると考えて良いのではないかとい
うふうに、今は思っております。
後藤よろしゅうございましょうか。
久富木原ありがとうございました。祭りは確かにそういう高
揚があると思いますし、また一葉もこの酉の市のにぎわいとか、
祭り的なそういう空間というものは実際に体験しているでしょ
うから、そういうものは確かにあったと思います。ありがとう
ございました。
後藤それではもうあと五分くらいでございますが。
伊井大阪大学の伊井でございます。お二人、まず野口さんに
ちょっとお尋ねしたいんですけども、宣長から広道というふう
な、非常にダイナミックな当時の享受といいましょうか、お話
を聞いたのですが、「源氏物語」がなぜ読まれるのかというこ
とを考えますと、そのプロセスのあいだに出版という文化もあ
るんでしょうし、町人文化の発展もあったんでしょうが、地方
でずいぶんたくさん『源氏物音巴が読まれるんですよね。もう
書目もわからないような「源氏』の聞き書きみたいなものがわ
んさとあちこちでできるのですけども、なぜそれほどまでに
「源氏』に魅了されていくのかという、民衆の、人びとのそう
いう読まれる背景というようなものを、何かご存じであればお
教えいただきたいことと、もう一つ久保田さんにちょっとお尋
ねしたいんですが、中世の『源氏物語』の読まれていくやはり
大きな力というのは、俊成とか定家だろうとおっしゃるように
思うんですが、発表の中で和歌から『源氏物語』を読むという
ふうにおっしゃっておりましたけれども、『六百番歌合』でお
取り上げになったところで、紫式部というのが「歌よみの程よ
りも物かく筆は殊勝なり」ということで、物語性というものを
非常に重要視しているような気もするので、ここの「六百番歌
合』の判詞のことばの解釈というのは非常に難しいところもあ
ると思いますけれども、俊成とか定家がそういうふうに『源氏
物語』を評価していくという、それがその後の「源氏物語」が
-69-
読まれていく背景にも非常に大きな影響を与えていくんだろう
と思いますが、そのあたりをちょっとお教えいただければと思
います。以上一一点でございますけれども。
後藤では野口先生。
野口なぜ読まれたかですけれども、それはよかったからなん
ですけどね。ぽくもともと唯物論ですから、こういう用語法は
お気に入らないかもしれませんけども、知的欲求という、ある
いはみやびに参加したいという社会的ニ
lズが広範にあったと
思います。そして教えるほう、講釈するだけでも謝礼がもらえ
て食える一群の国学者がいるんですよね。そういう人たちが巡
業して食っていくというのがありますね。それから読んでい
るうちに、自分でも注釈をやってみたいという人が出てきます。
例えば広道なんかは自分の本の中で、本を読むときには必ず注
釈をつくろうと思って読めといっています。本当にそれをやっ
ているのがいると思います。それが手紙で交換しますよね。そ
ういうコミュニケーションができあがります。そのうちに財力
があると、あるいはパトロンを見つけて本を出そうという、そ
ういう何というか、端的に身も蓋もなくいってしまえば、マー
ケットができあがるわけですよね。そういうものが広範に、江
戸時代の後半にできていたんだろうと思います。だからさまざ
な関心、さまざまな趣味、さまざまな熱意があったというわけ
だと思います。
そして、広道の場合には、これはさっきいったような個人的
な事情も含めまして、ほとんど外界排除的にのめり込んでいた
面があると思いますよ。『源氏』の世界に。それは中世とも似
ていると思いますね。有名な紅旗征戎ですか。つまり黒船が来
ているけれども、それを聞き流して『源氏』の世界に本当にの
めり込むという。一つのことにはさまざまな動機が複合すると
思いますけれども、その一つの典型的なあらわれじゃないかと
いう気がします。
それで写本の往復とか、国学の、『源氏』の先生の巡業なん
ていうのは、これは資料から消えてしまいますよね。残るのも
あるけれども。そういう裾野というのはものすごく広かったん
じゃないかと思います。これは『源氏』だけではなくて、絵の
先生も巡業すれば食えたわけですよね。書の先生も食えたわけ
ですよ。広道なんかも、どうしても資金を調達したくて巡業に
出るんです。コ一十両稼ごうと思ったら二十両しか稼げなかった
とか。だけど本当はもっともうける人もいるとか、えらく生臭
いんだけれども、文学生産の現場というのはそういうものじゃ
ないかなと思います。どうもすみません、ロマンチックなお答
えでなくて。
久保田おっしゃるとおりだと思います。わたくしもさっきち
ょっと申し上げたと思うんですけれども、初めは歌中心に読ん
でいたかもしれない。しかしその読みは深まっていったと思い
ます。そしてそれが俊成だけではなくて、ほかの人びとの場合
もそうだろうと思うんですね。一つだけ具体的な例を挙げます
と、犬という素材が歌に盛んに歌われだすのは、この中世初頭
ぐらいでありまして、それは明らかに『源氏物語」「浮舟」の
巻に出てくる「里の犬」から犬が歌われるようになるんですよ
ね。犬を見ているだけでは絶対歌われないはずです。しかし定
70
家も寂蓮も「里の犬」を歌います。このことはそれだけ読みが
深まってきているということを意味しているわけで、やっぱり
俊成自身の読みもだんだん深まってきたんだろうと思います。
伊井どうもありがとうございました。
後藤たいへん魅力的な発見が、いま最後のところで出てまい
りましたけれども、たいへん司会が不手際でございまして、
『源氏物語』の非常に皆さんが肝心に思っていらっしゃる「も
ののまぎれ」の問題など、うまくふくらませきれないいたみが
ございました。それからっ一島が罪業意識を主軸とした近代的源
語観批判とか。時代的にも「源氏物語』の鍛誉褒庭というのは、
移り変わってきておりますが、最近二千円札でかなり市民権を
得たというような感じがいたしておりますけれど。逆に云えば、
一般にはどれだけ正統に受けとめられているのか、という疑問
でもございます。
そういう非常にアナーキーな、作品についての時代時代の受
容のあり方というものについて、きょうはたいへん分厚い論議
を交わしていただいたのではないかと思っております。
会場の皆様、ご協力をどうもありがとうございました。パネ
ラ!の先生方、どうもありがとうございます。
進行以上をもちまして、本日のシンポジウムを終了いたしま
す。講師の先生方、司会の労をお取りくださいました後藤先生、
ありがとうございました。これにて散会とさせていただきます。
(了)
71-