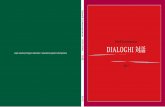リ仏教に おける相対的規準〔1〕 - ECHO-LAB
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of リ仏教に おける相対的規準〔1〕 - ECHO-LAB
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
駒澤大學佛教學部論集 第19號 昭和63年10月
パ ー リ仏教 に お け る相対的 規 準〔1〕一 kappiyaの 原義 一
片 山 一 良
1. 「仏教」 の 基本的枠組
ll. 「絶対的規準」 と 「相対的規準」
皿.kappiya の 語義
IV. kappiya の 類 語
1. 「仏教 」の 基本的枠組
今や 種 々 の 様相 を 呈 す る 仏教 に お い て , そ の 文 化が どの よ うに 変化 し た か を 見
る こ とは , た とえそ れを一
時代に 或い は一
社会に 限定 して み て も , 決 して 容易で
は な い。 しか しこ こ に 「仏教」が い わ ゆ る 「パ ー リ仏教」 また は 「南方上 座部
仏 教」を 指 し, 「伝統仏 教」 で あ る とす る な らば , そ うした 試み が 厳密 な意 味 で
の 文化変化の 研究 に は な らず とも, 伝統変化 の 考察 と して 我 々 に 可能な もの とな
る で あ ろ うと思わ れ る 。 なぜ な らば , 「伝統仏教」 とは , 出家を 中心 と し 在家 を
周 縁 とす る 仏教 に 外 な らず , 伝 統 の 中核 を なす い わ ば権威 として の テ キ ス トが 存
し, か つ そ の テ キ ス トをめ ぐる コ ン テ キ ス トと し て の 文化が 時間を 通 し て 連続す
る 「線 の 仏 教 」 だか らで あ る 。つ ま り伝統仏教は , 非連続 の 「点の 仏教 」 とも言
うべ き大乗仏教 と異 り, 出家/在 家 , テ キ ス ト/ コ ン テ キ ス トな どの 関 係が 対立
的で あ っ て, そ の 変 化や 特徴が よ り捉 え られ易い とい うこ とで ある 。
周 知の よ うに, 最初期 の 仏教で は , サ ン ガ の 確立 と共に 戒律が制せ られ , 随犯
随制を くり返 しつ つ, や が て 種 々 様 々 な規制が 固定 され て い っ た 。 しか し仏滅後
ま もな く, 王 舎城 の 第一 結集 (500人 阿羅漢結集)で , 次 の よ うな 決定が 下 された と
伝え られ て い る 。
「サ ン ガ は 未制を制せ ず , 所 制を 捨て ず , 所制の 学処 に 従 っ て 存する 」(Safigho apa ・
fifiatta血 na pafifiapeti pafifiattath na samucchindati yathapafifiattesu sikk 一
一 510一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
(2〕 パ ー一リ 仏 教に おけ る相対 的規準〔1〕 (片山)
hapadesu samadaya va 亡亡ati , Vin. II.288)
こ の 言 葉が そ の 後の 仏教 の 歴 史で い か に 重い 意味を 持 っ た か は , 現今 の 上 座部
仏教 僧か ら しば しば耳 に す る とこ ろ で あ り, 以下 に 始 ま る kappiya の 考察か ら
も次 第 に 明 らか とな るで あ ろ う。 少 く と もそ の 決定以来 , 文言 上 の 戒律は 当時の
ま ま保存 され て きた 筈で あ り, 今 日に 到 る まで そ の一
句 た りとも変 更 され た こ と
を 聞 か な い 。 だ が , 過 去2500年 もの 問 , 比 丘 の 生 活 規 定 た る律 に, 果 して 聊 か の
改変 もな か っ た の か ど うか , こ れ は 誰 もの 素朴な 疑問で あろ う。
もと よ り仏教 に は , 原始経 典 の 随所 (e .g. D .1.8 ; M . 1. 222 ;S.1.157 ;A . III.297 ;
Sn . p .102)で 知 られ る よ うに , 「法 (Dhamma ) と律 (Vinaya)」 とい う static な
教義 , テ キ ス ト と して の 二 面 が あ る 。 法 は 経 蔵 の , 律は 律蔵 の 内容 と し て 存す る
もの で あ り, 今 日 も上座部仏教国で は こ の 両 者を一
つ に し て“ Dhamma −Vinaya ”
(法 ・ 律) を‘ ‘Sasana”
(仏教) と呼ぶ こ とが あ る (e .9. Vajirafiarpavarorasa: En ・
trance to the vinaya, vol .1,
p. ix,1969)。 また 厂仏 を上 首 とす る 比丘 僧 に 」 〈Bud ・
dha −pamukharb bhikkhusahgha・h)な る表 現に 見 られ る (e . g. Vin.1.213;1λII.98;
M .1.236; Sn . p.111)通 り , 僧 は 仏 を 頂点 と して 律 に よ っ て そ の 形を 整 え , 各 メ ン
バ ー(比 丘) は 実践 法 と戒 律 の 実践を 通 し て 教法 の 理 解に 向か うもの で あ る が ,
仏 は 僧の メ ン バ ーで あ りな が ら弟子 とは 截然 と区別 され る 覚者 で あ っ て , 専 ら弟
子 の た め に 法 と律を説示 す る 存在 で あ る 。 か くし て 我 々 は 法 と律 と の テ キ ス トが ,
そ れ ぞれ 仏 (Buddha) と僧 (Safigha) とい う dynamic な 実践 者 , 即 ち コ ン テ キ
ス トに よ っ て 保持 され て い る こ とを ,つ ま り 「仏教」が 「法 ・律」 と 「仏 ・ 僧」
とい う枠組か ら成 る もの で あ る こ と を まず押 え る 必 要 が あ る 。
一
方で また , 仏 と法 (= 教法)が 仏教 の 内面を , 僧 と律が そ の 外面 を覆 っ て い る
と考えて よ い で あ ろ う。 上 座部仏教 国 で‘ ‘Sasana ”
(仏教) を‘ ‘Buddha −Dha ・
mma”
(仏 ・法) で も っ て 表わ す こ とは む しろ先 の 場合 よ り一
般 的で あ る と 言 っ
て よ い (Narada: The Buddha and his Teachings, p . vii , 1973)。 こ の 「仏 ・法」
に は 理 想的 , 普遍的 ,テ キ ス ト的な面が , 「僧 ・ 律」 に は 現実的 , 民族 的 ,
コ ソ
テ キ ス b 的な面 が 強 く打 出 され て い る こ とは ま た 明 白で あ る 。
こ の よ うに 見 る と , 「仏 教 」 の 基 本的枠組 に 二 重 の テ キ ス ト/ コ ン テ キ ス ト の
ク 卩 ス 関係が あ る こ とが 分か る 。 即 ち 内容 と し て , 教 義面 と実践面 〔保持者〕
か ら 厂法 ・律/仏 ・僧」な る枠組 が, 理 想面 と現実面 か ら 厂仏 ・法/僧 ・律」な
る 枠組 が成立 つ。 図 示 す れ ぽ 次 の 通 りで ある 。
一 509一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
パ ーリ仏教に お け る 相対的規 準〔1 〕(片 山) (3 )
[テ キ ス ト]
[Sasana ] [コ ソ テ キ ス ト]
Buddha ・一一1− ・・..1.._ISahgha
仏 僧
法
Dhamma
律
Vinaya [Sasana ]
(普遍性)
(単 一性)
(民族性)
(多様 性)
こ の 図 は また ,
一般 に 仏教 の 基本構造 と され 礼拝対 象 と され る い わ ゆ る 仏 ・
法 ・ 僧 の 三 宝 を 伝統仏教 の 立 場 か ら機能的 に 見 よ う と し た もの で もあ る 。こ れ に
基 づ い て 言 えば , 三 宝 は , 在 家に よ る 礼拝対象で あ っ て , 出家 と直接に は 関 係 し
難 い。 何 とな れ ば , 『律蔵』 の 説 明 に よ る 限 り,
「尊師 よ , こ の 我々 は 世尊 と法 とに 帰依 します」(ete mayarh bhante bhagavantaTh
sarapalh gacch 巨ma dhammafi ca , Vin.1.4)
とい うよ うに 仏教 最初 の 二 帰依 を 唱 え た 者 (dvevacika ) が 二 商人 Tapussa と
Bhallika ,つ ま り在 家者で あ る こ と , 同 じ く ,
「尊 師よ , こ の 私 は 世尊 と法 と比丘 衆 とに 帰依 し ま す」(es’ ahath bhante bhaga −
vanta 血 sara1 ,a血 gacchami dhammafi ca bhikkhusafighafi ca, Vin,1.16)
と仏教 で 初め て 三 帰 依を 唱 え た 者 (tevacika ) も長者 居士 (Yasa の 父) な る 在家で
あ っ た と す るか らで あ る 。 また 進具 (upasampada ) の 変遷 を 見て も , 仏弟子 に よ
る 三 帰依 進具 (tisaraUagamana −upasampada , Vin.1.22) は , 仏に よ る 善来比丘
進 具 (ehi ・bhikkhu ・up°
, Vin. L 12) とサ ン ガ に よ る 白四羯磨進具 (fiatticatuttha・
kamma ・up°
, Vin. L 56) との 間の し ば ら くの 期 間 に 行 なわ れ た も の で , 後に そ れ
が比丘 の upasarnpada に で は な く沙弥 の pabbajja の た め に の み 残 された に と
どま っ た こ と , 或 い は また具 足 戒を 受けた 比 丘 が三 帰依 を 唱 えた とい う記事が か
な り限定 さ れ る, な どの 理 由に よる 。 もち ろ ん比丘 ・比 丘 尼 が 仏 ・法 ・僧に 帰依 ,
もし くは 尊敬 の 念を表 明 した 言 葉は , 中村元博士 (rバ ウ ッ ダ ・仏 教』 p.15,1987)や
三 枝充悳 博士 (r仏教』No .1, p.59 ,
1987)の 指摘 もあ る通 り, あ ち こ ち (e . g, Thag .
一 508 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
(4 ) パ ー リ 仏教に おけ る相対的規準〔1〕 (片 山)
178;382; 589,Thig .53; 132;286) に 見 られ る 。 が ,註 釈に よ る と こ の 場合 の 「僧」
は , い ずれ も 「聖 な る 僧 」 (ariya −safigha, paramattha −sahgha ) と説 明 され て お り ,
い わ ゆ る 現前 サ ソ ガ で は な く三 宝 中 の 四 方サ ソ ガ と等質の もの で ある 。 とい うこ
とは , こ れ らの 告 白に 現わ れ る 「僧」 は , す で に 理 想的 な三 宝 の 概 念が 定着 して
か らの もの で , 決 し て 出家側 本来 の もの とは 言 えな い (Cf. Sn .569)。 礼拝 対 象 と
して の 「僧」が 出家 に 本来 的で ない とい うこ とは , 同 じ 『長 老偈』 (Thag .201)に,
また 『経集』 な ど (Sn.192, 1). II.208, S.1.30) に , 「仏」 と 「法」 に 対す る 尊崇
が 述べ られ 「僧」 は 欠如 し て い る と い うこ とか ら も指摘す る こ とが で きよ う。 具
足戒者 た る サ ン ガ (の メ ン バ ー)が 自己を 含む三 宝 に 礼拝す る こ とは ど う見て も
不 自然 と言 わ ね ぽ な らな い 。 理 念化 された 仏 ・法 ・僧 の 崇拝 は 『宝経 』 (Sn.222−
238)に も窺 え る 如 く, あ くま で も功 徳 (pufifia)志向 的 , 在家 的の もの で あ り, 出
家に 不 可欠な もの は 実践 的な 仏・法 ・律で あ る と考 え る 。 同 じ く「仏」に と っ て 不離
の もの は 「法 」の み とい うこ とに な ろ う。 した が っ て 仏教 の 基 本構造 を一
般 に 仏法
僧 の 三 宝 と して 強調す る の は , 専 ら在 家の 立 場か らで あ っ て 出家 の 側か らで は な
い, 三 宝 とは 律を 法に 吸収 した 在家的所産で あ る と言わ ね ば な らな い
。 我 々 は こ こ
で また , 仏教の 基本的枠組が , 出家 の 「仏 ・法 ・律」 (図の 実線方向), 及 び 在家 の 「仏 ・
法 ・僧」 (図の 点線方 向) とい う二 方 向か ら成 る もの で ある こ とを 確認 し て お きた い。
さて , 既 に 触れ た通 り, 図 の タ テ の 構成 (仏 ・法 と僧 ・律)か ら言 え ば, 仏 ・法
は 仏教 に お い て 決 して 変わ る こ と の な い 理 想面 , 普遍性/単一
性 に 貫 か れ , 僧 ・
律は 時 と場 とに 応 じて 変わ り うる 現実面 , 民族 性 / 多様性を 内包 し て い る こ とに
な る 。つ ま り仏教 は それ 自体 の 中に 明 らか に 不 変的 な 部 分 と可変的 な部 分 とを共
有 し て い るわ けで あ る 。 もち ろん それ は 世界宗教 とか 普遍宗教 とか 呼ばれ る キ リ
ス ト教や イ ス ラ ム 教 に お い て も異 る もの で は な い。 た だ 我 々 が 注意 し な けれ ば な
らぬ の は , 宗教の 世界性 とか 普遍性 とか を 口 に 出 して 言 う場 合 , そ こ に は 法 , も
し くは 教法の み が 意味 されて い る とい うこ とで あ る 。 仏 教が 普遍宗 教で あ る と言
わ れ る の もま さに その 点 ,つ ま り 「法」の 側 に しか な い
。
こ とに 我国に は , 仏教 の 現状を 嘆 きつ つ も, 法 の み を重視 し , 戒 律に 触れぬ ま
ま仏教 を理 解 し よ うとする向きもある 。しか しそ れ で は 十全 た りえ な い
。 戒律の
欠落 し た 「智慧 」 や 「慈悲」 が あ る の か ど うか 。コ ン テ ス トが脱 落 し た テ キ ス ト
に 意味がある の か ど うか 。 仏教 は 単 な る哲学的思弁で もなけれ ば , 倫理性を欠 く
知 的 パ ズ ル で もな い 。 「法」が 頭 とな り, 「律」が 手足 とな っ て 動か なければ 仏教
一 507 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
パ ー リ仏教に お ける相対的規準〔1〕(片山) (5 )
が 人間の 宗教 として 機能す る こ とは な い で あろ う。 原始経典 の 中で 法 と律が 区分
され並置 されて い る意味 もこ こ に ある筈だ 。
「こ れ は法で あ る , こ れは 律で あ る, これが 師の 教えで あ る」(ayalh Dhammo aya 血
Vinayo idalh Satthu Sasana血 , D .皿 .124)
と 。 そ し て ま た ,
「律は 仏教 の 命で ある 。 律が 存すれば仏教は 存す る」 (Vinayo nama Buddhassa
Sasanassa ayu, Vinaye thite S訌sana 血 thita血 hoti
, DA . L 11;S♪.1。13)
とは , eg−一結集以 来 の 伝統仏 教の 合言 葉で あ る 。 今 日なお 上 座 部仏教徒 は こ れを
信 じて 疑 うこ とが な い。 「法」の み で こ と足 れ りとす る 傾向は , 三 宝 の 理 念化 と
,
出家/在家 の 区別を 不 問 に 付 しが ちな大乗 的発 想に よ る と こ ろが 大 きい と思わ れ
る 。 そ こ で は 律 も法 の 中に 隠れ て し まい, 終 に は 頭 の み の 仏教が 金科玉 条 と して
謳歌 され る に 至 る とい うぺ ぎか 。 も し戒 律 , 実践 を欠 き歴 史 も文化 も無視 し て こ
れを “仏教モ と呼ぶ な らば , こ れ ほ ど都合 の よ い 平面 的な仏教は あ る ま い 。 こ の
ミ仏教 ミ は 自 ら欠落 した 深み に あ らゆ る もの を招 き寄せ , あ らゆ る もの と同化 し,
あ らゆ る もの に 帰 入 し て 様 々 な形 相を と り うる か らで あ る。
い わ ゆ る 学問仏教 ,
大乗的仏教 は こ の 類 に 属 し, 原始 仏教や 真 の 大乗 仏教 と大 き く隔た っ て い よ う。
法 と律 とは 不可分で あ るが 同一
で は ない 。 法は い わ ば積極的な理 念体系で あ り,
律 は 消極的 な 行動 体系 に 属 して い る 。 仏教 が 両者 に基 づ く宗教で あ る こ とを 我 々
は よ くよ く承知 し て お か ね ばな らぬ 。 即 ち , 律は 変 化 し うる も の だ が , 決 して 失
なわ れて は な らぬ の で ある 。
さて こ こ で 本 題 に 戻ろ う。 我 々 は 伝 統仏教が イ ン ド よ りス リ ラ ン カ,
ビル マ,
タ イな どに 伝播 し , 現在 も盛 ん に 信仰され , そ れ ぞ れ の 国独 自の 仏教 が 展開 して
い る事 実を知 っ て い る 。い か に 伝統仏教 と名づ け られ て も, そ れ らは 決 し て イ ン
ドの ま ま , 原始仏教 の ま まで は な い。 とすれ ば , 第一 結集時の 学処不 変の 原則 は
どの よ うに 生 きて い る の で あ ろ うか 。 これ に つ い て 我 々 は , 文字 の 建前を 保ち な
が ら, 現実の 問題を仏教内部で 巧み に 解決 した と考 え ざ る を えな い 。 な ぜ な らば ,
実際 に 地 理 や時 代 , 民族 を異 に して, 生活 の 規定が 変わ らぬ とい うこ とは 人間生
活 に は あ りえな い し , 律 とは そ の 社会 , 文化の一
面 で あ り, 環境に 応 じて 変わ り
うる性格を帯び て い るか らで あ る (D . R .154)。 それで は どの よ うな処 置 が 施 さ
れ , 何に よ っ て 律が 「不 変」か ら 「可 変」 とな り うる の で あろ うか 。 もし こ こ に
そ の 厂何」 の 整合性を 求め よ うとす る な らば , 我々 は ど うして も方便 的 と も 思
え る 厂相対的規準」 に 目を 向け る よ り術 は な い で あろ う。 そ の 第一 が 本稿主題の
一 506一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
(6) バ ー リ仏教に おけ る相対的規準〔1〕 (片 山)
kappiya,
よ り丁 寧に 言 えぽ kappiyakappiya に 外 な ら な い。 kappiya とは
,
長い 仏教 の 歴 史 の 中で , ほ ぼ 最初期 か ら培わ れ 保存 されて 来た 伝統 = 文化変化の
指針 と も看做 さ るべ き概念で あ る 。 その 語 自身は ヴ ェー ダに 現わ れ る kalpa (規
定 .法則) に 遡 り うる もの で , 仏教 の 初め に は 事柄 の 可か 否か を 判定 す る 「相応
しい 規準」 が意 味され た に 違 い な い が , そ れ が戒 律不 変 の 決定を 境に, 特殊 な意
味を帯び た術語 へ と発展 した の で あろ う。 そ して やがて 世俗の 詭弁に も似た もの
とな り, と くに 戒律保存の た め の 不 可欠 な手段 と も な っ た 。 確か }こ kappiya は ,
超俗 の 中に 世俗 を持込 ん だ 感を まぬ が れ な い が , それは 出家が 在家 に よ っ て 経済
的に 維持 され て きた とい う現実に 沿 っ て い る 。 出家 自らが こ の kappiyakappi・
ya ,つ ま り相応 , 不相応 の 方 法を心得,
一方, 在家 もこれ を よ く承知 し て
, 仏教
世界 に お ける 相互 の 理 解 と信頼関係 の 強化が 図 られ て きた の で あ る (Vin.皿.288)。
文化 が そ の 社会に お い て , 共 に 学 び , 学 ばれ , 伝 え られて ゆ くもの で あ る とす る
な らば,
こ の kappiya こ そ , ま さに 仏教 の 伝統 も し くは 文化を 保存す る た め の
正 当な方法 だ と言 え る で あろ う。
kappiyaは , 律を主 とす るい わ ぽ拡大 解釈で こ そあれ , それを 空洞化 させ る も
の で は な い 。 こ の 言葉が 存す る こ と自体 , 仏教 実践 と して の 法 ・ 律の 伝統が保存
され て い る こ とを物語 っ て お り,kappiya自身が 同時 に また 伝統 の 改革を示 して
い る と受け とめ られ るで あ ろ う。 以下 は こ の kappiya を 初期仏教 以来 の 伝統 ・
文 化変化 の 指標 (index) として 捉 え ,こ の 語 をめ ぐっ て 伝統仏教 の 特質を 明 らか
に し よ うとす る もの で ある 。 た だ し 本稿で は 第一
段階 と し て kappiya の 原義を
扱 うに とどま り , 典型的 な kappiya に は 言及 されな い 。
1 . 「絶対的規 準」と 「相対的規準」
仏教に お け る事柄 の 判定規準を ど こ に 求め る か とい う場合 , 我 々 に まず思 い 浮
か ぶ の は ,い わ ゆ る 「四 大教法」 (cattaro mahapadesa ) とい う言 葉 と そ の 内
容 で あろ うと思われ る。 しか し これ は , 時 間的に 限定された早 い 時 代 , 即 ち経 蔵 ,
律蔵が 成立 す る頃 ま で に, 遅 くと も書写 され る 頃 ま で に ま とめ られ た と推 定 され
る教法 の 四 種 の 出所 で あ るか ら , 別 に 扱わ れ ね ばな らな い。 今は こ れを も考慮に
入 れ て , 全体 的な 「規 準」 に 対す る 考 え方を こ こ に 提示 し て み よ う。
伝統仏教 に お け る規準に は , 絶対的 な規準 と相対 的な 規準 とい うもの が まず考
え られ る 。 そ して そ の 各 々 は 教義 と実践 に よ る規準に 分類 され るで あ ろ う。こ こ
一 505一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
パ ー リ仏教に お ける相対的規準〔1〕(片山) (7)
で 「絶対 的」 とい うの は , 経蔵, 律蔵の 中に 法 と律 とが 文字 と し て (「文字」 とは ,
仏語 , 結集時の 決定 , 書写時 の 文字を意味す る)固定 され た もの とい うこ と で , 仏教
に お い て は 絶対的 に 正 しい, また 字句 の 上 か らは 決 し て 改変の 認め られ ぬ 規準で
ある 。こ れ に 対 し て 厂相対的」 とい うの は 絶対 的で な い 規準 , 即 ち絶対的規準を
基 に 拡大解釈 して 認 め られ る よ うな 相応 しい もの で あ り, 先述 の 「四大教 法」の 第
二 部分に そ の 殆 ん どが 集約 され る で あ ろ う。 こ の 四大 教法に 経 と律の 二 種が ある
こ とは 既 に 他で 指 摘 した と こ ろで ある (第二 回 パ ー リ学仏教文化学会 , 1988年 5 月発
表 。 原稿は 学会誌第 二 号 に 掲載予定)。 また 「教義」 とは 「法」 も し くは 「教法」で
あ り, 「実践」 とは 積極 的に は 「教法」 な い し 「道」を 通 して, 消極 的に は 「戒」
な い し 「律」に よ っ て 行 なわれ る もの を い う。 た だ し こ の 法の 実践の 積極的, 消
極的 とい う分類 , そ の 言葉 の 使 い 方 に は 多少説 明を 要す る か と思わ れ る の で , 最
近話題 に な っ て い る 中村元博 士 の 『パ ウ ッ ダ』 (1節に 引用), 及 び 袴谷憲昭 教 授
に よ る批判 (「批判 として の 学 問」, 駒沢大学仏教学部論集第18号所収,1987年)を 紹 介
し て 補足 し よ う。 まず中村博士 は 三 宝 の 「法」を 次の よ うに 説 明 され る 。
「人間 に は , まず人間 として 守 らね ばな らない道筋 , 理法が ある 。 それ は 「人間を人
間 と して 保 つ 」 もの で ある 。 (中略)理 法は 普遍的な もの で あ り, 永遠に 通用 す る とい
っ て も, それは動か ない 固定 した もの で は ない 。 普遍的な もの は , 現実 の 場面に お い
て生 か され ね ばな らない。 根本の 理 法は 同 じで あ っ て も, それを具現す る 仕方は , 時
と と もに 異 り, また 所に よ っ て 異な る。 人間の 理 法とい うもの は , 具体的な 生 きた人
間に即 して 展闘す る 。 その こ とは , 思想 的に は 無限の 発展 の 可能性を もっ て い るわ け
で ある」 (前掲書 P.22)
こ の 見解に 対す る袴 谷 教授 の 批 判 は こ うで あ る 。 即 ち , 三 宝 中の 「法」が肥 大
し下落すれ ば 「普遍 的な理 法」 とな っ て 三 宝 の み な らずあ らゆ る もの を寛大に も
許容 して し ま うの で あ り,こ の 「普遍的な理法」を否 定 し なけれぽ 決 し て 仏 教
は 正 しい 仏教 とな る こ とは で きな い (前掲論 集 pp .424−425。 尚 , 同教授 に よ る精力的
な 同類の 批判は 「和の 反仏教性 と仏教の 反戦性」, 東洋学術研究第26号第 2 号 ,1987年11月,
「宝性論に お ける信の 構造批判」, 成田 山仏教研究所紀要第 11 号 ,1988 年 3 月参照) と。
本稿の 立 場 は , 両 見解を基 本的に は尊重す る 。 し か し 両者 に 「戒律」に 対す る認
識が 欠如 し て い る こ とは 否 め な い。 仏 教 に お け る
ミ理 法 ミ が 「縁起」に 代表 され
る こ とは 誰に も異論は な か ろ うが,
こ れを 拡大解釈 し て 行 け ぽ,
ミあ るが まま ミ
が ミわ が ま ま ミ とな り , あ らゆ る もの を生み 出す こ と とな っ て , ま さ に 袴谷教授
の 指摘 され る 通 りとな る 。 問題 は 「法」 に お け るミ理 法 ミ を 含む 「教 法」 とそ の
一 504 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
(8 ) バ ー リ仏教に おけ る相対的規 準〔1〕 (片 山)
「実践 法」 との 区別 , 「法」 と 「律」 との 区別 の 仕方 に あ る と考 え ら れ る 。 中村
博士 の 言われ るミ普遍的 な もの ミ,
ミ根本の 理法ミ とは 「教法」(ア ピ ダ ソ マ に い う
nippariyaya と pariyaya とを 一緒に ま とめ た 広義の“
pariyaya”
)を ,
ミ具 現す る 仕
方 ミ とは 「実践法 」を指 し , 前者 は 後者 , 即 ち 「道 」を通 して 積極的に 実践 され ,
倫理 性 を 帯び , 後 者は 前者 に よ っ て 理 論的 に 裏付 け られ る もの で ある こ と (金倉
圓照 「仏教に おけ る 法の 語の 原意 と変転」rイ ン ド哲学仏教研究 1』 p.104参照)を , そ し
て 何 よ りも 「戒」を 基盤 とす る 「律」 に よ っ て 止 悪の 側か ら消極 的で は あ るが 実
現 され ね ぽ な らぬ もの で あ る こ と (平 川彰 r原始仏教の 研究』 p,137 参照 ) を弁 え る
必 要 が あ ろ う。 こ こ に 消極 的 とい うの は 方 法 と して で あ っ て 内容を 指す もの で は
な い。 内容は む しろ 積極的 , 肯定的で あ り, 涅 槃な どに 見 られ る 否定 的表現 と同
一 カ テ ゴ リ ーに あ る と見て よ い (Cf. W . Rahula : What the Buddha tanght , p.42f.)。
戒律の 実践は , 積極的な 自己抑制 と限 りな く広が りゆ く放縦へ の 制御 とに 意義を
持つ。 「戒律」を 離れ , また こ れ を 「法」に
一括す る な らば ,
ミ普遍的な理 法を 否
定 しなげれ ば な らない ミ と言わ ね ば な らぬ は 自明の 理 で あ ろ う。
こ れ まで に 述 べ た と こ ろ を汲 み つ つ 全体的な 「規準」の 枠組を ま とめ れば , 大
概以下 の よ うに な ろ うか。
鵡欝 慧鞭:識
次 に 具体的な 「規準」に 移 る こ とに し よ う。 仏陀の 言葉 の 中 に は , 「規準」と
すべ き内容 の もの が い くつ か あ る が , そ の 代表 的な一
は , 晩年 の 旅 の 様子 を 描 い
た 『大 般涅 槃経 』 (1吻 侮ρσプ竰 ゐ6伽 召・suttanta ) に 見 られ る 。
「それ ゆ えアー
ナ ソ ダ よ 。 そな た らは 自己を洲 とし (attadipa ), 自己を 帰依所 と し
(attasarapa ), 他を帰依所 とせ ずに 住せ よ。 法を洲 とし (dhamma ・d!pa), 法を帰依
所 と し (dhamma ・sarapa ), 他を帰依所 とせ ずに 住せ よ」 (P . II.100−101)
こ こ に は 真 の 依 所 とす ぺ き 「法」 と , 規準 とすぺ き実践 主体た る 「自己 」 とが
強調 され て い る 。 それ らは い ずれ も絶対的 な規準で ある が , その 言葉は 抽象的で
何 ら具体性を持た ない (但 し S.V.・163等で は 「四念処法」を指す)。
一 503一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
パ ー リ仏教に おける相対的規 準〔1〕 (片山) (9 )
こ れ に 対 して 我 々 は , 仏教 の 実践 に 関す る具体的 な規準 と し て 「中道 」 (majj ・
hima・patipada) が 説か れて い る こ とを 承 知 して い る 。 釈尊最初 の 説法 と さ れ る
『転法輪経』 (1)hammacakleaPavattana ・sutta )で は , そ れ を次 の よ うに 言 う。
「比丘 らよ,
こ れ ら二 の 極端 (anta )を 出家者 (pabbajita) は 行な うべ きで ない。
二
とは何か , それは 諸欲に お け る卑俗 , 在俗 , 通俗的に して 非聖 (anariya )の, 無意義
(anattha ) な , 快楽に 耽る こ と (kamasukhallikanuyoga ), 及び 苦 し く, 非聖の ,
無意義な , 自虐 に 耽 る こ と (attakilamathanuyoga )で ある 。 比 丘 らよ, 如来は これ
ら二 の極端に 従わ ず , 中道 (majjhima patipada ) を よ く悟 っ た 。 〔これ は 〕眼 (ca −
kkhu )を生 じさせ , 智 (fiapa) を生 じさせ , 寂滅 , 勝智 , 正覚 , 涅 槃 (nibbana )に
導 く もの で ある 。 如来に よ っ て よ く悟 られ た 中道一 眼 を生 じさせ , 智を 生 じさせ ,
寂滅,正 覚 , 浬 槃 に 導くもの 一 とは何か 。 それ は 八 聖道 (ariya ・atthahgika −mag ・
ga )で ある 。 即 ち , 正 見 (samma ・ditthi), 正 思 (se・sahkapPa ), 正語 (s°
・vaca ),
正業 (s° −kammanta >, 正 命 (s
° ・ajiva), 正 精 進 (s° ・vayama ), 正 念 (s
° ・sati >,
正 定 (sa・samadhi ) で ある」 (Vin .1.10;S. V .420)
と 。こ の 趣 旨は , 極端 の 否定 で あ り , 仏教の 行動体系に お け る真正 の 規準を示 す
に あ る。 決 して 快楽 も苦行 も半ば に と い うよ うなミほ どほ どミ を 強調 して い るの
で は ない 。 こ こ に い う ミ真 正 ミ とは , 中道 の 「中」(majjhima ), 或 い は 八 聖道 の
「聖 」 (ariya ), また は そ の 各支 に 付 され た 「正」 (samma ) に 外 な らず , 仏教 の
「絶対的な正 し さ」 を い うもの で ある 。 中道 とは 真正 の 行道 (patipada ) で あ り,
正 しい 八 支か ら成 る 如来 の 完全 な道 (magga ) で あ る (S, V .435 , DA 。 II.354)。 こ
の 中道 , 即 ち八 聖道 に 関す る 教説 は , 釈尊に よ る 最初 の 説 法 と して 五 比丘 に , 最
後 の 説法 と し て Subhadda に (D .・II.151), また 45年間の 教化に お い て もしぼ し
ぽ示 された 仏教 の 最 も重要 な 実践 の 教 え とされ る 。 前掲 引用 の 外に 例 えぽ ,
「カ ッ サ パ 〔異学〕よ , 道 (magga )が あ り, 行道 (patipada )が ある。 その 道を行
く者は 自ら知 り (sama 血 fiassati), 自ら 見 るで あろ う (samalh dakkhiti),
ミ
沙門
ゴ ータ マ は 適時 (kala) を 語 り, 真実 (bh 且ta) を語 り, 意義 (attha ) を語 り, 法
(dham :na ) を語 り, 律 (vinaya )を 語 る ミ と 。 カ ヅ サ パ よ , 道 とは 何か , 行道 と は
何か 。
…… これは 八 聖道で ある」 (D .1.165)
とか , 或 い は ,
「友 よ , こ こ に 貪は 悪で あ り, 瞋 も悪で あ る 。 貪を 捨て , 瞋を 捨て るた め に 中道が あ
る 。 それ は眼を生 じさせ , 智を生 じさせ , 寂滅 , 勝智 , 正覚, 浬槃に 導 くもの で ある」
(1匠 1,15)
とか 様 々 に 中道 , 八聖道 の 教 え が説 か れ る が ,い ずれ もそ の 具体 的な 内容が 正見
一 502 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
(10) パ ー リ仏教に お ける相対的規準〔1〕(片山)
な い し正定 の 八 支で あ る こ とは 言 う迄 もな い。
こ の 「道 」は 「法」 の 積極的行動
面 で あ り, 仏教に お い て は , 何時 , 何処 に お い て も正 し く意義が ある ,つ ま り涅
槃に 導 く絶対 的な 規準 とな る もの で あ る 。 また 「八聖 道」の 各支は 戒 , 定 , 慧の
三 学に 配 され る が , こ の 場 合 の 厂戒」 も絶 対的 な規準 とな る 。 よ り充 分か つ 具体
的に 言 えぽ , 波羅提木叉 (patimokkha ) と し て 既に 制定 され 固定 さ れ た 150余条
(A .1.230f.) もし くは 227戒お よび 律の 諸規定が こ れ に 含 まれ る。
そ の 「戒 」は 条
文各 々 が 絶対 的に 正 しい 規準で あ る が ゆ え に , 「別解脱 」 (patimokkha 》 と も称 さ
れ る の で あろ う。
ミ別 ミ の 解脱 とは
ミ戒
一 一に よる別 々 ミ の 解脱を い うが ,
ミ法 と
は 別異 ミ の (つ ま り律に よ る)解脱を も含意 され て い る と思わ れ る 。 「戒律」が
「法」の 消極的 行動面 で ある こ とは 既 に 指摘 した通 りで あ る 。
以上 の よ うな 法 , また は 戒 律 に お い て 絶対的 に 正 し い とされ る絶対的規準に 対
して , 絶対的 で は な い が 絶対 的規準に 相応 しい と され る 規準が あ る 。 こ れ は ka−
ppiya と言わ れ , 我 々 が 相 対的規準 と呼ぶ もの で あ り, 次節 皿 以降 に 扱 わ れ る
こ とに な る 。
伝統 仏教に は か か る 絶対的規準 , 相対的規準 とい う規準の 大枠を 見 る こ とが で
きる が , 『指導論 』 (Netti・Pakaragea) に eよ こ れ が 端的に 示 され て い る よ うに 思 わ
れ る 。 そ の一
節を次 に 紹 介 して 本節を閉 じる こ とに し よ う。
厂認め られ た もの (anuftfiata )は , 世尊 の 認め られ た もの に よ っ て 説 明 され ね ぽ な
らない 。 それ は 五種で ある 。 即 ち防護 (sa1hvara ), 捨断 (pahana ), 修習(bhavana ),
作証 (sacchikiriya ), 相対的適正 (kappiyanuloma )で ある 。 それ ぞ れ の 地 (bhami)
に 見 られ る もの は ,相対的適正 に よ っ て 説 明されねぽな らない 。 世尊が捨て た (patikk・
hitta)もの は 捨て られ た 理 由に よ っ て説 明され る べ きで ある 。 認め られ た もの と捨 て
られた もの は , その 両者に よ っ て説 明され ねば な らな い 」 (1%鷭 192)
こ こ に お け る salhvara, pahana は 律 (SA . II.253f.), 即 ち 「戒 」 (Vism .7)
に ,bhavana は 「定」 に
, sacchikiriya は 「慧」 に
,つ ま り前 四種は 三 学 に 相
当す る絶対 的規準を表わ し , また 第五 の kapPiyanuloma は kapPiya,
つ ま り相
対的規準 を表 わ して い る と解せ られ る で あろ う。
皿 .kappiya の 語 義
こ れ よ りし ば らく相対的規準を 表わ す kappiya の 語義を 調べ る こ とに した い。
まず形式的 な語源的意味を 見 よ う。
一 501一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 University
パ ー リ仏教に お け る 相対的 規準 〔1〕 (片 山) (11)
kapPiya は ,パ ー リ語 の 動詞 kapPati(Skt. kalpateく VklP)=
‘
to be arra −
nged, to be fit’ (PTS ・D )に 由来 し , その 未来受動分 詞 と解され る (Childers・D 》
が , また パ ー リ語 の 名詞 kappa(Skt. kalpa < 、/klp)=
‘
rule’
か ら導か れた も の
(kapPiya く kapPa ・iya, Skt. kalpika< kalpa ・ika ・ =
‘
according to rule’
) で あ る
(PTS ・D ) と も見 られ る。い ずれ に し もて VklP に 由 来 し , 文 法的 に は Dative
case と結ばれ (Vdirttika ad Pdip.2,3
,13), 「相応 しい 」 (suitable ), 「許 され うる」
(allowable ), 「適切な」 (proper) の 意味を 持 つ。 なお 漢訳で は , 「聴」, 「浄」, 「如
法」, 「随順」 な ど (梵和大辞典), 或 い は 「可者」, 「中用」(MahdivsutPatti 9196,
9388) と示 され る 。
こ の一 般 的な 辞書の 意味に 対 して ,
パ ー リの 諸註釈 に 知 られ る と こ ろ は ど うで
あ ろ うか 。パ ー リ外律を 扱 っ た 後代の Pa”limuttakavinayavinicch¢ yasangaha
(:Sariputta, 12C )の 註釈 で ある y伽の 尸41σ褫 47 σ’魏δ (:Tipitakalahkara,15C; Be
,
vo1 .1, p.2 ,
1977)は , 「四浄地 j (catu ・kappiyabh6mi ) の kappiyaを 次 の よ うに 説
明 す る。
tattha kappanti ti kappiydi, kappa samatthiye ti dhatu .
こ こ で は kapPiya を語 根 kapP, 即 ち Skt.の VklP か ら作 られた もの と し ,
「適合す る 」, 「相応す る 」 の 意 に 解 して い る こ と が 分 か る 。 こ れ 以前 の 諸註釈
Atthakatha で は ど うか とい うと , そ こ に は 我 々 が 対象 として い る kapPiya に
直接言及す る もの は 殆 ん どな く,kappa の 解釈 に 終始 して い る と言 っ て よ い
。
直接的 な もの と し て は 次 の 『小誦経註』 (KhPA .208= PvA .26)の 解 釈を示 せ ば一一
応 こ と足 りるで あ ろ う。
kapPlyan ti anucchaviya 血 patirUparh ariyana 血 paribhogaraha 血 .
こ れ よ り kappiya が , 「適切 な」, 「適当な」, 「聖 者 の 受用 に 値 す る 」 を 意味
す る語で あ る こ とを知 る 。
こ の よ うな 次 第で , 以 下は kapPa を 通 し て kapPiya の 意味 を 窺 うこ と に し
た い。 まず 『長 部経典註』 (DA .1. 103) を 見 よ う 。
happa・saddo pi‘titthatu bhante Bhagava kappath’
(1). II.115),
tAtthi kappo
nipajjiturh’
(A . IV .333),
‘kappakatena akappakata 血 sa 庁1sibbita 血 hoti’ (Vin.
IV.121) ti eva 血 ayukappa ・lesakappa・vinayakappadisu sambahulesu atthesu
vattati .
こ れ に よれ ば , kappa の 意味が 具体 的に は 三 種掲げ られ て い る が , 他 に も多
一 500 一
N 工工一Eleotronio Library
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 University
(12) パ ー リ仏教に お け る相対的規準〔1〕 (片 山)
くの 意味が ある とい う。 そ の うち我 々 の 問題 とす る kappiya の 内容を 持つ の は
vinayakappa (律の 点浄)で あ る 。 例 え ば 「点浄 され た もの (kappakata ) で も っ
て 点浄 され て い な い もの (akappakata ) が 繕わ れ る」 と言 わ れ る 場 合 の もの で あ
る 。 因み に 『長部経典復註』 (DAT .1.182) で は 上 記 の 「多くの 意味」に つ い て
次が 補わ れ て い る 。
kappa・saddo mahakappa ・samantabhava −kilesakama ・vitakka −kala・pafifiatti.sa −
disabh訌v’・adisu vattati ti aha sambahulesu atthesu vattatl ti. tatha h ,
esa
‘
cattar’ imani bhikkhave kappassa asafikheyy2ni
,
(A . II.142)ti adisu ma ・
hakappe vattati .‘kevalakappath Veluvana 血 obhasetv 且
,
(S.1.52) ti adisu
samantabhave .‘
sahkappo kamo, rago kamo
, sahkapparago kamo ’
(Nd . II.
124) ti adisu kilesakame 。‘takko vitakko sa 血kappo ’
(1)hs.7)ti adisu vitakke ,
つ ま りこ こ に は 三 種の 外 に 七 種 の 意味が 説 明 され て い る が ,kappiya に 関す る
もの は 見当た らな い。
こ の よ うな 『長 部経 典註』 に 比 べ て , 他 の 主 た る註釈 書に は や や 詳し い kappa
の 内容が 知 られ る 。 即 ち 『中部経 典註』 (MA . II,125−126), r相応部経 典 註』 (SA .
1. 15), r増支部経典 註』 (AA . II. 377)及 び 『小 誦経註』 (KhA ・115−116)に は , 次 の
よ うなそ れぞれ に 全 く共通 の 説 明が 掲げ られ て い る 。
kapPa ・saddo panaya 血 abhisaddahana ・vohara 呷k訓 a ・pafi五atti ・chedana ・vikapPa ・
1esa−samantabhavadi anekattho . tatha hi ’
ssa‘
okappaniyam eta !血 bhoto Go −
tamassa yatha ta血 arahato sammasambuddhassa’
(M .1。249)ti evam 且disu
abhisaddahanam attho ,
‘
anuj 巨n 巨mi bhikkhave paficahi samapakappehi phalafU
paribhu丘jitun.
(Vin. II.109)ti evamadisu voharo,
‘
yena suda 血 niccakappa 血
viharanl’
(M .1、249) ti evamadisu kalo,
‘icc ayasma Kappo ,
(Sn.1092) ti
evamadisu pa鯔 atti,
‘
ala 血kata kappitakesamassu ’
(.r. Vl .268)ti evamadisu
chedanalh ,
‘kappati dvahgulakappo’ (Vin. II.294;300) ti evamadisu vikappo ,
‘
atthi kappo nipajjitun,
(∠4. IV .333)ti evamadisu IesQ,
‘keva !akappalh Ve・
luvanath obhasetva ’
(S.1.66)ti evamadisu sa !nantabhavo .
上 に 示 され た kapPa の 意味八 種 の うち ,二 種 が kapPiya の 内容を 持 つ
。
一
は vohara (慣習)の 意味で あ り, 例 えば 厂比 丘 ら よ,
五 種 の 沙門の 慣習 (sama ・
ηa・kappa) に よ っ て 果 実 を食 ぺ る こ とを 許す」 とい う場 合の も の で あ る 。 他は
vikappa (疇躇) の 意味で あ り, 例 えぽ 「二 指分 の 〔時間 の 〕躊躇 (kappa ) は 相
応 し い 」 とい う場 合 の もの で あ る 。 た だ しこ れ に つ い て は 問題が あ る 。つ ま りこ
一一499 一
N 工工一Eleotronio
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 University
パ ー リ仏教に おけ る相対的規準〔1〕(片山) (13)
の 場合 の kappa を , む し ろ常識 的に , 「時 間」 (time> と見てミニ 指分 の 時 間は
相応 しい ミ (Childers・D ) と か , 厂規定」(rule ) と見てミニ 指分の 〔時間の 〕規定
は 相応 しい モ (PTS ・D ) と解す る こ と も可能だ か らで あ る 。 もし そ の よ う に 読 む
な らば こ の kapPa は 我 々 の kapPiya の 意味に 属す る こ とに な ろ う。 し か し 後
述 の 通 り,time は kala と して ,
rule は vidhi (または (vidhana ) と して vi −
kappa と区別す る伝統的解釈が あ るか ら,こ こ で の kappa は 「躊 躇」 と解 すべ
きで あろ うと思わ れ る 。 なお また Subhttti の Abhidha’naPPadipika−・saci (ce ,
1893, p.76 脚註)に
‘
vikappo ti vividha kappana atthassa anekantikabhavo’
と述べ て い る こ と も考慮すべ きで あろ う。 した が っ て こ の kappa の’例文は 内容
と し て 直接 kapPiya と関係す る もの で あ るが, kapPa な る 語 自体 は kapPiya
と積極的 な関 連を 持た な い と見た 方が よい か も知れ ない。
以上 が い わ ゆ る Atthakatha に 知 られ る kapPa の 意味で ある が , そ の 他 に ,
12世紀 セ イ ロ ン の Moggallana に よる パ ー リ語最 古の 辞典 Abhidha’napPadipikd
(v .799) に 記載 され た 12義が あ る 。 即 ち 次 の 通 り。
kappo k巨1e y uge lese pafifiatti paramayusu ,
sadise tlsu samapavohara ・kappabindusu,
samantatte’
ntarakappadike takke vidhimhi ca .
さ らに こ れを含め て 最 も豊富な語 義18種を 紹介 して い る もの に 12世紀 ビ ル マ で
著わ され た パ ー リ語文法書 Saddaniti(:Aggavarhsa, ed . by H . Smith , 1928−1954)
が存す る 。 今こ こ で は Dhatumala §1525 (Sad 。 P.552) に 掲げ られ た 偈を 示 し ,
そ の 内容説明 を 整理 し,
また 各意味の 例を 付す こ とに し よ う。
vitakkei ca vidhane2 ca patibhage8 tath’
eva ca
pafifiattiyarb.4 tatha kales paramayumhie chedane7
samantabhave6 vohareg abhisaddahanei ° pi ca
viniyogeti ca vinayakiriyayarb :21esakei8 pi ca
− vikapp’u −ant :arakappesu !5
taOhaditthis}ユ16 ’
sahkhayei7
kappeis ca evamad1su kappa・saddo pavattati .
1・ vitakka 〔takka 〕(思惟) :‘
nekkhammasahkapPo _ ...avyapadasahkap ・
PO,
(S. II.152)
2. vidhana 〔vidhi 〕(規定):‘
civare vikapParb apajjeyya (Vin. III.216)
3. 、patibhaga 〔sadisa 〕(類似):‘
satthukapPena vata bho savakena sad 一
一 498 一
N 工工一Eleotronio Library
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
KomazawaUniversity
(14) .x' -- v caXac Sstrj'6NXI-blMmpCI) (lt pt)
dhim mantayamana na janimha' (M: I.1sc)
4. pafifiatti (gnt/i) : `icc
ayasma Kappo' (Sn. 10g2)
5. kala (eema):`yena sudath niccakappatn viharami' (M:I.24g)
6. paramayu (fimefifu) : `akahkhamano
Ananda tathagato kappaM tit-
theyya kappavasesarh va' (D.II. 103)
7. chedana (-bjwt) : `alafikato
kappitakesamassu' U.VI. 268)
8. samantabhava (samantatta) (seme) : `kevalakappaih
Veluvanaih obh-
asetva' (s. I. 66)
9. vohara Esamanavohara) (vawr) : `anujanami
bhikkhave paficahi sam-
anakappehi phalath paribhufijituth' (Vin. II. 109)
10. abhisaddahana (tsne) : `saddha
saddahana okappana abhippasado'
(Dhs. S12)
11. viniyoga (NM) : `evam
eva ito dinnatn petanath upakappati' (Pv. 20==
KhP. VII. 9)
12. vinayakiriya (kappabindu] (pmopfik) : `kappakatena
akappakatarb
sarhsibbitarii hoti' (Vin. IV. 121)
13. Iesa (ge0) : `atthi
kappo nipajjituM handahaM nipajjami'(D.III. 256)
14. vikappa (ecee):`kappati dvahgulakappo' (Iiin. II. 294)
15. antarakappa (*bl) : `apayiko
nerayiko kappattho safighabhedako......
kappaM nirayamhi paccati' (Vin. II. 205)
16. tarphaditthi (ptM : `na
kappayanti na purakkharonti dhamma pi
tesath na paticchitase, na brahmapo silavatena neyyo parafigato
ca pacceti tadi' (Sn. 803)
17. asahkheyyakappa (NIeeptsi) : `aneke
pi sarbvattakappe aneke pi viv-
attakappe' (Vin. III, 4)
18. mahakappa (Jkbl> : `cattar'
imani bhikkhave kappassa asankheyyani
(A. II. 142)
-t:al18fio kappa o!)fi.,muik, Subhttti trckD"cgh82tt: Abhidhanappa-
di]Pik a--saci (op. cit. , pp. 75-76) }C ig OX et ft V Pt{I ig '(i re tJ' 5 2"t < V N 6 .
*(, e oX 5 }i N"c gkstge Sc wt, sczaZee ?est op $iz6 kappa hs 6, R
-497-
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
パ ー リ仏教に おけ る相対的規準〔1〕(片 山) (15)
々 が 扱 う相対的規準 と して の kappiya の 意味が , 決 し て 尽 され て は い な い もの
の , あ る 程度 ま とめ られ る よ うに 思わ れ る 。 即 ち kappiya に 意味 され る もの は ,
「規定」 (vidhana , vidhi ), 「沙 門の 慣習」(samarpa −vohara ), 厂律の 行為」 (vinaya ・
kiriya・ kappabindu) な ど となろ う。 全体 と して は 「相応 し い 」 とい う意昧 を 持
つ。 た だ し こ の vidhi や vohara が ,
Vedahga の 一 た る Kalpa もし く は そ
れ が含む Dharma の 有す る意 味の一
面 で あ り,
ミ定 め られた もの ミ を 内容 と し
て い る こ とか ら言 えば,kapPiya は , 仏教以 前の kalpa な る語か ら採 用 され ,
仏教 の 中で‘‘dhamma ”
に 対する‘‘kappa ”
と して 定着 した もの と 考え られ る
で あろ う。 ち ょ うど形 と して samana ・dhamma が samapa −kapPa に 対応 する
よ うに。kappiya の 原義は お そ ら くこ こ に あ り, あ くま で も定 め られ た も の に
対 す る相応 し い 規準 と解すべ きで あろ うと思わ れ る 。 絶対的規準が 厂沙門の 正 し
い 規準」, 「如来 の 示す聖 な る規準」 で ある の に 対 し て , 相 対的規準 kappiya は
「沙門の 慣 習に 相応 しい 規準」, 「法 ・律に 相応 しい 規準」を 表わ す 。こ れ が 我 々
の 見方で あ る。
IV. 】cappiya の 類 語
前 節まで の 検討 に よ っ て , 規準 の 絶対性 が 「中」, 「聖1, 「正」に あ り, 具体的
に は , 法 で は 十二 縁起 ・ 四 諦 ・八 正 道 な どに , 律で は , 五戒 ・十 戒 , 或 い は 波羅
提木叉 な どの 規 定に 認め られ る こ と , こ れ に 対 して そ の 相対性 は kappiya に 求
め られ る こ とが ほ ぼ 明 らか で あ ろ う。 しか し なが ら kappiya に つ い て は まだ具
体的な 内容吟味 に 入 っ て は い な い。 そ の 前 に 我 々 は kappiya の 類語を 調べ る必
要が ある か らで あ る 。 kappiya の 語義 自体は 先 の 通 りで あ るが , そ の 持 つ 意味
の 相対性ゆ えに い くつ か の 語 源の 異 る 類語の 存在が 予 想 され る。 本節は 類語 の 検
討に よ っ て,kappiya の 語 の 特徴を よ り明 らか に するた め の もの で あ る 。
まず 『律蔵 』に お け る腱度部最初の 「大 品大腱 度」か ら見 よ う。 そ れ は 釈尊が
初 め て 行儀悪 しき比 丘 らを 叱責 した と伝 え られ る 文脈 に あ る も の で あ る 。
「比丘 ら よ , か の 愚人 らに 〔それ は 〕適切 で な く(ananucchaviya ), 適正 で な く(an ・
u !oma ), .適当蟹 (aPPatirttPa ), 沙 門 らし くな く (assam 恥 aka ), 相応 し くな く
(akappiya ), 僅すぺ か らざる (akaraPlya ) こ とで ある 。 比丘 ら よ, なぜ か の 愚人 ら
は上下 の衣 を整えず, 威儀を 正 さず托鉢に 回 っ た り, 人 々 が食べ て い るの に 軟食や硬
食, 味食 , 飲物の 上 に 鉢を出 した り, 自らX 一ブや ご飯を指 した りし て食べ, 食堂で
一 496一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
(16) パ ー リ仏教に お け る相対的規準〔1〕(片山)
も高い 声 とか 大 きな 声を 出して過 ごすの か。 比丘 ら よ
,こ れ は 未信の 者に 信を起 こ さ
せ , 既信の 者に い よ い よ 〔信を〕増大 させ る こ とに はな らな い。 比丘 らよ
, それ は か
え っ て 未信 の 者を不 信に させ , 既信者の一
部を離反 させ る もの で ある」 (VVin. L 45)
こ の 引用の 中に は ,akappiya な る語が 現わ れ て お り, また そ の 類語 を 数多 く
窺 い うる 。こ れ は , 『律蔵』 の 編集者 を 含め , 当時の 人 々 に よ っ て , kappiya な
る 言葉が 釈尊在世の 最初 か ら使用 され て い た と考 え られ た 結果で あ る と見 て よ い
で あ ろ う。つ ま りご く自然 の こ とを し て , もとも と 「規 則」を意 味す る kappa
(= kalpa, Skt.) の 派 生 語 kapPiya, も し くは akapPiya が , 沙 門の 具体的行動
の 適 , 不 適を 判断す る際に 用 い られ た とい うこ とで あ っ て , 戒律が 制定 され固定
され る 時に は こ の 語が 不 可 欠 で あ っ た とい うよ うに 解され る で あろ う。また これ
と殆 ん ど同 じ内容が , 経 分 別 最初 の 「波 羅夷」の 因縁話 の 中に も知 られ る こ とは
注 目され て よ い。 それ は 「律」 の 始 ま りが こ の 箇所あた りに あ る と考 え ら れ る
(宇井伯寿 r印度哲学研究第三 』 p.41参照)か らで もあ る 。 そ こ で は , 世尊は , か つ
て の 妻 と交 っ た Sudinna 長老 に 婬欲行 の 非 (Vin. III.20)を , 王 材を 取 っ た陶
工 子 Dhaniya 長老に 偸盗 の 非 (Vin. IV.44) を , 偽沙門 MigalapOikaに 頼ん
で 自分 た ち の 命を 断つ よ う指示 した 比丘 らに 殺生 の 非 (Vin. IV . 71) を , 超人法
(uttarimanussadhamma )が あ る と語 っ た 比 丘 らに 妄語 の 非 (Vin . IV .89) を説
い た とされ , そ の い ずれ の 話 に も次 の よ うな 言葉 が述 べ られ て あ る 。
「〔これは 〕適切で な く, 適正で な く, 適当で な く, 沙門 らし くな く, 相応 し くな く,
作す べ か らざる こ とで ある 。 愚人 よ, なぜ こ の よ うに よ く説か れた法 と律(Dhamma ・
Villaya)の も とで 出家 し なが ら , 終生 , 完全 無欠で 清浄無垢の 梵行を行 じる こ とが で
きな い の か 」
と。こ の 部 分は 『律蔵』の 随所 に 見 られ , 先 の もの よ り整 っ た い わ ぽ定型句 の 体裁
を なす。 「相応 し くな い 」 (akappiya ) とい うこ とは こ の 場 合 「法 ・律 に 違 背す る」
こ とで あ る。 即 ち ,
パ ー リ律 の 最初か ら , た だ し大鍵度 , 経 分別 の 因縁話に よる限
り, 「相応 しい 」 とは 「法 ・ 律に 相応 しい 」 とい うこ とで あ り , 前節 に 見た 解釈
と異 る と こ ろは な い 。 今 の 引用文 に つ い て 『律蔵註』 は 次 の よ うに 註釈 して い る。
「愚人 よ , お前の な した真実を欠 く者 の 行為は , 沙門の 因た る 諸法 , 或い は道 , 果 ,
浬 槃 , 教 の 皮膚に 逆 ら うもの (= 不 適 切 an ・anucchavika )で あ り, それ らの 皮膚,
影 , 好 ま しい 状態に 従わず ,つ い て 行 くこ と もな く, また それ らか ら遠 い 。 皮膚 に 逆
ら う (= 不適切で ある)か らこ そ, また 毛に 逆 らう (= 不 適正 で ある an ・anulomika )
の で あ り, それ らに と っ て不 適正 とな り, 〔行為は 〕また 逆, 反対の 状態に とどまる 。
一 495 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
パ ー リ仏教に お ける相対的規準〔1〕(片山) (17)
毛に 逆 ら うか らこ そ , また 姿が よ くない (= 不 適当 a ・p・patirapa)の で あ り, 姿 よ き,
等しい, 似合 うもの とな らず, 〔行為は 〕また 等 し くな く (a ・sadisa ), 不似合 い (a ・p−
patibhaga )で ある 。 姿が よ くない か らこ そ , また 沙門 らし くな く (assamapaka ),
沙 門の 行為 (sarnanakamrna ) とな らな い 。 沙 門 ら し くな い か ら相応 し くな い (= 不
相応 akappiya ) の で ある 。 ま こ と沙 門の 行為 とな らぬ もの は , それ ら に 相応 し くな
い。 相応 し くな い か ら作すべ か らざ る (akarapiya )こ とで ある 。 」 (SP.1.219−220)
と。 こ の 註釈か ら類 似的表現 の 相 異 が 多少 とも明 らか とな り , 我 々 は ,kappiya
とほ ぼ 同 じ内容 の 語 に,
anucchaviya (適切な ,
‘
皮膚に 順 ずる’
), anulomika (適
正 な,
‘
毛に 順 ずる}
), patirUpa (適当な,
‘
姿の よ い’
), samapaka (沙門ら しい ),
karap iya (作すべ き)が あ る こ とを 知 る 。 た だ し こ れ らの うち anucchaviya (ま
た は anucchavika )と , samapaka は 「律蔵』に 特有 の よ うで あ り, 四 ニ カ ー ヤ の 中
に は 見出 し 難 い。
anulomika は pabbajitanulomika (‘
出 家に 適正 の’ Sn .385)
とか ,samafifiassanulomika (
‘
沙門位に 適正 の’ Itiv.103) の よ うに 見 ら れ ,
pa・
tirUpaは また 種 々 の 類 語 と共 に 現お れ る 場 合 が 多 く, と く に 『律蔵』 に 頻 出す
る 。 例 え ぽ , 「波逸提 第55」 (与非親尼衣戒) に 関 して ,
「愚人 よ, 親族で な い 者は 親族で ない 比丘 尼に 対 し て 適 当 (patirttpa), 不 適当 (apa ・
tirapa)を , 或い は養 (santa ), 不 善 (asanta )を 知 らない 」 (Vin. IV.59)
とあ り, 続 く 「波逸提 第26」 (与非親尼作衣戒)に 関 して も,
「愚人 よ, 親族で ない 者は 親族で な経女性に 対 して 適 当, 不 適当を , 或い は 清浄 (pa ・
sadika ), 不 清浄 (apasadika ) を 知らな い」 (Vin . IV . 61)』
とあ る 。こ れ か ら santa (善い ), pasadika (清浄な) も同義語 と見 な し うる 。 ま
た 「不 定第 1」 に は ,
「尊者 よ, あなた が女性 と一緒に ひ と りで 秘密の 坐所に 坐 る の は 適 当 (patirapa)で
な く, 適宜 (channa )で は あ りませ ん 」 (Vin. III.187)
とあ り, 『ア ン バッ タ 経』 (1λ 1.91) に も下線 の 両語 が 認め られ る か ら , channa
(適宜 の )も同類 の 語 と考 え られ よ う。channa は chadeti < Vchad(
‘to seem
good’
,
‘to please’
)の p. p. に し て 「好 ま しい 」, 「喜ば しい 」 を 意味す る 。 さ ら
に また 敬虔 な女性 信者 Visakha が 釈尊に 八 願 (atthavara ) を乞 い,
「尊師 よ , 〔それ らは 〕相応 し い (kappiya )もの で あ ります し , 過誤の 無い (anava ・
jja) もの で もあ ります」 (Vin.1.292)
と説 明 した 言葉に 見 られ る anavajja (過誤 の 無い )も kapPiya と同内容 の 語 と
見な され うる 。 た だ し こ の anaVajja は , 本来 「禁 じられ な い 」 (くa− V’
vraj, Chi一
一 494一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Unlverslty
(18) パ ー リ仏教に お ける 相対的規準〔1〕(片山)
lders・1))もし くは 「非 難 され な い 」 (< an ・ava ・Vvad, PTS ・D ) の 意味を 持 ち , 罪
の 有無に つ い て, 対既念の Savajja と併用 (savajja va anavajja va
, A . ll.191),
また は 結合(savajjanavajja , D . ll, 223) して 使用 され る こ とは 注意 され て よ い
。
こ の 外に 我々 は 『律蔵』の 中で 次の よ うな定型 句に しば しば出会 う。
「こ れが そ の 場合 の 適法 (samici )で ある」 (Vin. III.186;222; 246, IV.80; 141;
163)
『律蔵』 自体が こ の 語 samici を そ の 直後で 説 明 して‘
anudhamma’
(随法)で
あ る とす る 。 律で は 上 記箇所 の 六 種が 数 え られ る (Vin. V .133, Sp.1339)が ,
ニ
カ ー ヤ で は 一 般 に 複合語 と し て 現わ れ る場 合が 多い。 因み に 一 例 を掲げて み よ う。
「い か な る家系 (kula) か らで あれ , 在家 よ り出家 へ と出家す るな らば , そ の 者は 如
来に よ っ て 説か れた 法 と律 (Dhamma ・Vinaya ) を信受 し , こ の よ うに 慈 , 悲 , 喜 ,
捨を 実践 し , 内に 寂静を得 , 内の 寂静 よ り沙 門に 適 う行道 (samarpa ・saml ¢ i・patipa ・
da) を 進む もの で ある , と私 は説 く 。」 (1匠 1.284)
上 記引用の sama ロa ・sam 正ci−patipada (沙尸『に 適 う行道)に 対応す る語句 と して
gihi−samici ・patipada (在家 eこ 適 う行道 , A . II.65), 或 い は gihi−samicikasikk ・
hapada (在家に 適 う学処 , S. V .387) な ども知 られ る 。 註釈 (AA . III.97; SA . IIL
289) に よれば , こ の 場合 の samici は anucchavika (適切 な) を意味す る か ら
kappiya の 同義語 と看做 され よ う。 し か しそ うす る と , samici は もと もと sa −
mma < samyac (Ved. f. pl. N . sam !cih ) と同 じ言葉で あ る (PTS −D )か ら, sa −
mma が 絶対性を示 す語で ある とした fi節の 解釈 に 矛盾す る こ とに な ろ う。 しか
も samici は‘‘
samici Bhagavato savakasahgho”
とい うよ うに , い わ ゆ る
僧 の 九徳の一 に 数 え られ る もの で あ る 。
つ ま り samici は kappiyaか , そ れ と
も samma 或い は majjhima か の 問題で あ るが , 今は 前者 と捉えて お く. しか
し samapa ・samici ・patipada の 場 合に し て も行道 の 手続 きは 異 ろ うと , そ の 結
果 は 前者 も後者 も等 し い 筈で あ る 。 相対 的な kapPiya は 常に 絶対的 な majjhi −
ma に 向か うもの で あ るか ら。
以上 の よ うに kappiya の 同義 語な い し類語 は 『律蔵』の 中 に 顕著 に 現わ れ る
が ,こ れ まで の 検討か ら主た る も の が anucchaviya
, anulomika
, pa‡irUpa で
示 され , そ れ に 続 く も の と し て samanaka , karapiya
, pasadika ,
channa ,
santa , anavajja が , さ らに は samid な ど種 々 様 々 に ある こ とを知 る 。 そ し て
また ,こ れ ら数多 くの 類語 の 中に あ っ て
,kappiya なる 語 が意味自体 に 個性 が
一 493 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary
Komazawa University
NII-Electronic Library Service
Kom 三1z 三1w 三1 Umversrty
パ ー り仏教に おけ る相対的規準〔1〕 (片山) (19)
乏 し く,い わ ば無表情 な言葉で あ る こ とに 気づ く。 そ こ か ら我 々 は ,
kappiya が
「相応」 とい う如 き漠 然 とし た 意味を持つ 語か ら後の 特殊 な 内容 の 語 へ と発展 し
て 今 日 まで 保存 され得 た の は , そ うした 言葉 自身 の 特 徴の 無 さか らで は なか ろ う
か , 加 えて それは こ の kappiyaが , た とえ ヴ ェー ダ の Kalpa か ら援用 された に
せ よ , 第一 義的 な majjhima に 対す る 第二 義的 な規準 と し て 使用 され位 置 づ け
られ た か らで は な い か と考 え る 。バ ラ モ ン の 用語 を 避 け る , も し採 用 した と し て
も第一
義的な扱い を 避 ける ,こ れ が 従来の 伝統的な仏教の 姿勢で あ る と言 っ て よ
い。
類語 に は こ の 他 に kappiya と語源 の 等 しい 派生語 と して vikappa とか vika ・
ppana もある が,
こ れ らに つ い て は , そ の 殆ん どの 用例が 『律蔵』 に 限定 され る
た め , 別 に 稿を 改め て 論 じる こ とに した い。
一 492 一
N 工工一Eleotronlo Llbrary