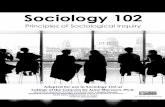The Sociology of the Pink-Collar Man
-
Upload
hirokoku-u -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of The Sociology of the Pink-Collar Man
男性ピンクカラーの社会学
一一ケア労働の男性化の諸相一一一
矢原隆行*
近年日本では,伝統的に女性的職業 (pink-collarjob) とみなされてきたい
くつかの職業において,いまだ少数ながら男性の参入が着実に生じている.と
りわけ,看護,介護,保育等のケア労働の領域で働く男性たちの姿は,それが
さまざまな男性優位の職業領域に進出して活躍する女性たちの姿と対照して観
察されるとき,今日の職業領域におけるジェンダ一体制の変容を体現するもの
として解されうる.しかじ,これまでジエンダーに関する大量の成果を生み出
している女性学のみならず, r男性性Jに焦点をあてる男性学の領域において
さえ,そうした「男性ピンクカラー」に焦点を当てた社会学的研究はきわめて
乏しい.本稿では,現代日本における男性ピンクカラーについて,とりわけ
「ケア労働の男性化」という視座から観察を試みる.当事者を含む多数の語り
から明らかなように,男性ピンクカラーは,ケア労働の領域における少数派で
あるがゆえ,時に「トークン」として位置づけられる.しかし,その位置づけ
は男性が多数派であるような職業領域における少数派としての女性と単純な
対称をなすものではない.そこに見出される振れは,ケア/労働およびそれを
取り巻く現代社会における普遍としての〈男〉というジエンダー秩序を映し込
み,かつ映し返すものである.
キーワード:男性ピンクカラー,ケア労働,ジエンダー
1 はじめに一一男性ピンクカラーの趨勢
本稿では,伝統的に女性向きの職業とされるさまざまなピンクカラー・ジョブの
なかでも,とりわけケア労働に焦点をあてる.看護,介護,保育といった他者のケ
アにかかわる労働は,家庭領域における女性役割の一見「自然」な延長として,現
在に至るまでその多くが女性によって担われてきた.そこには,一方で、,ケア労働
を女性がこれまで家庭内で果たしてきたさまざまな「女性らしさ」を必要とする職
業として位置づけると同時に,他方で,家庭における理想的な女性の役割とは優れ
た看護婦や保母のように家族をケア.することであるとするような,いわば家庭領域
と職業領域の双方におけるジェンダー・イメージの相互強化メカニズムが存在す
'広島国際大学医療福祉学部准教授 [email protected]
社会学評論 58 (3) 343
る1)
しかし,近年,いまだ少数とはいえ,そうしたピンクカラー・ジョブとしてのケ
ア労働の領域に着実な男性の参入が確認できる.たとえば,看護職について見ると,
2004年時点で約 129万人にのぼる看護師総数(准看護師を含む)に占める男性の
比率は約 4.5%と少数であるが,ここ 20年間ほどの推移を見ると, 1986年時点を
100として比較した場合, 2004年時点で女性看護師(准看護師を含む)が約 177で
あるのに対し,男性看護師(准看護師を含む)は約 278,さらに准看護師を除いた
場合, 2004年時点で女性看護師が約 220と,この 20年ほどでほぽ倍増しているの
に対し,男性看護師は約 479と5倍近い増加を示している2) また,保育職につい
て見ると, 2002年時点で約 32万人弱の保育所保育士に占める男性の比率は約1.3
%と看護職以上に少数派であるが, 1990年時点を 100として比較した場合, 2002
年時点で女性保育士が約 160であるのに対し,男性保育士は約 565と, 12年間ほ
どで5倍以上の急速な増加を示している3)
こうした男性ケア労働者の数的増加傾向のみならず,ケア労働の職業名称におげ
るジエン夕、一・イメージの変化も生じている.従来,ケア労働にかかわる職業は,
「看護婦さんJr保母さんJr寮母さん」等その公的名称あるいは一般的呼称におい
て,それを担う者が女性であることが明確に含意されていたが,それぞれの職業を
めぐる独自の歴史的・政治的文脈のなかで,いずれも特定の性を意味しない名称へ
の統ーが進展している.看護職については, 2001年の保健婦助産婦看護婦法改正
により,それまで「看護婦Jr保健婦」と同様の資格を有する男性に対して用いら
れてきた「看護土J(1968年よりそれ以前の「看護人」より名称改正)λ,r保健士」
(19伺93年より制度化)という名称が男女とも「看護師Jr保健師Jに統一された叫
また,保育職については, 1977年の児童福祉法施行令の改正により男性にも「保
母J資格の取得が認められたものの,その後も正式な資格名称が与えられないまま
でいた男性保育者について, 1999年より男女共通の名称として「保育士jが実現
した5) 介護職については,もともと必ずしも明確な資格が存在していなかったが,
1987年に制定された社会福祉士および介護福祉士法により,資格としては男女の
区別のない「介護福祉士」が誕生しており,介護職全般の呼称としても「ケアワー
カーJや「へJレバーJといった特定の性を合意しないものが普及しつつある.
こうしたケア労働の領域における男性ピンクカラーの数的増加や,当該職業名称
におげる男女の差異の消滅といった近年の趨勢を包括して,乙こでは「ケア労働の
男性化 (masculinizationof care work) Jと呼ぶへこの概念は,たんに当該職業
領域に参入する男性が(いまだせいぜいわずかな比率ながら)増えつつあることを
指すのみならず,諸々のケア労働における社会的ジェンダー・イメージの脱女性化
プロセスを含意する.ケア労働の男性化が社会にいかなる変化をもたらしうるか,
また,いかなる社会のあり様を反映していくのか,いまだその方向性が多様な可能
性をはらむ現時点においてその現状を観察しておくことは,ジェンダー研究のみな
らず,労働,ケア,感情といった社会学的研究の諸領域への展開の前提としても,
58 (3) 344
一定の意義を有するだろう.
しかし,これまでジエンダーに関する大量の成果を生み出している女性学のみな
らず,男性性に焦点をあてる男性学の領域においてさえ,そうした男性ピンクカラ
ーに焦点を当てた社会学的研究はきわめて乏しい.無論,当該領域について女性学
の立場からの研究成果を求めることは,いくぶん厚かましいかもしれない.日本に
おける女性労働研究を総括するなかで木本喜美子が論じているように, r従来の労
働研究は男性労働者を『労働者』として一般化して論ずることを当然のこととして
きたJ(木本 2003:4) のであり,労働研究の多くは民間大企業で働く男性に焦点
化してきた.そうした男性労働の「普遍性」に対して,女性労働は専ら家事・育児
役割との関わりから読み取られる,あくまで「特殊性」をはらんだものとして位置
づげられ,その実質はある意味で不可視化されてきたのである.したがって,労働
研究領域における女性学の目下の課題は,そうした「特殊J理論から脱したジエン
ダー視点の女性労働研究を着実に蓄積していくことに他ならない.
ならば, (民間大企業で働く男性に焦点化した)男性労働の普遍化を避けつつ,
ジエンダー視点、からの男性労働研究を展開する責務は,むしろ,圏内において近年
構築されつつある男性学の側にこそあるといえよう.だが,これまで圏内における
男性学研究や「男性解放」運動のおもな言説のなかで描写されてきたのは,えてし
て「仕事人間Jとして企業社会で苦闘する男性たちの抑圧された状況と,そこから
く降り〉て「主夫」として家事や育児等にかかわることで得られる豊かな人生観と
いった図式であった7) そこには家庭や地域におげる多様で充実した男性像に比べ,
職業領域における男性労働に対する比較的単純なイメージしか存在しない.たとえ
そのイメージが否定的なものであるにせよ,そうした単純な労働イメージは,従来
の男性労働の普遍的位置づけを暗黙裡に前提としてしまっているといえよう.伊藤
公雄に代表される圏内の男性学の議論が,社会において求められる「男らしさの
鎧J(伊藤 1996)からの解放をめざす男性運動との密接なかかわりのなかで進めら
れてきた以上,ある程度やむをえないとはいえ,日本の男性学および男性研究批判
を包括的におこなった渋谷知美が的確に指摘しているとおり,そこには, rその関
心を心理/個人レベルの問題に先鋭化させ,制度的/構造的な分析を等閑視J(渋
谷 2001:460) してきた嫌いがあり,そのことが男性学における労働概念の比較的
単純な把握にもつながっていると考えられる8)
こうした圏内の労働研究および女性学,男性学研究に対する現状認識を踏まえ,
本稿では,構造的にジエン夕、一化されたピンクカラー・ジョブ内部の男性労働者,
すなわち男性ピンクカラーの存在に焦点をあてる.その意義をあらためて述べるな
ら,それはいわば二重に不可視化されてきた領域を可視化する試みである.すなわ
ち,ひとつには,それは女性的職業という,労働研究における普遍的男性労働への
焦点化のなかで不可視化されてきた領域を観察する試みであり,もうひとつには,
それは男性労働者という, (女性労働者に焦点化する)女性学における女性労働研
究からも(仕事外での男の生き方に焦点化する)男性学研究からも不可視化されて
社会学評論 58 (3) 345
きた経験を観察する試みである.
2 変化において変化しないもの
2.1 少数派としての男性
R. M. Kanterは, 1970年代に実施された「インダスコ社Jと呼ばれる会社組織
の研究において男女の比率に着目し,集団類型として 85対 15の割合を上限として,
あるグループが多数派となり,他のクやループが少数派となる場合,その多数派を
「ドミナントJ,少数派を「トークン」と名づけた (Kanter1977 = 1995). トーク
ンの視覚的特徴は, r可視性Jr対照性Jr同化」の 3点.可視性とは, トークンが
注目の的になること,対照性とは, トークンのドミナントとの相違点が誇張される
こと,同化とは, トークンに社会一般のステレオタイプを当てはめることである.
Kanter自身の分析は, トークンとしてのインダスコ社の上級職女性の経験に着目
したものであるが,そこでは同時に,こうした問題が女性に限らずすべての少数派
に当てはまるものであることも強調されている.
個々の職種や職場環境により,当然一定の幅はあるものの,現在,圏内でケア労
働に従事する少数派男性の経験において,乙うしたトークンとしての視覚的特徴を
広く確認することができる9) 少ないところでは 1学年中男子学生 1名のみという
こともある看護系学校において男子学生は,授業時に教員から「今日は男はO匹お
るかな」と確認されたり,授業中何かと指名される 10},委員や係を頼まれるといっ
たことが多いばかりでなく, r校外での行動も端から見られてうわさになる」
(2002.12.20) といった可視性にさらされる.ある公立病院の女性看護部長は,最
初に採用した男性看護職者にミスが多かったため, r看護士=あんな人Jというイ
メージで職場の評価が決まってしまったと語る (1999.9.7). また,新生児にかか
わる職場で働く女性看護主任が,女性スタッフの間では患児に情がわき, rわー,可愛くなったね-Jといった会話が自然に起こるのに,男性スタッフにはそれが見
られない(1999.7.21),と男女の相違点を語るとき,そこではドミナントのカルチ
ャーが強調されている(対照性).さらに,精神科で暴れる患者の対応を頼まれた
男性看護職者は,自分が相手に話しかけて落ち着かせようと試みた際,女性スタッ
フから「そんなのは私たちができるんだJ,rそれ以外のものをして欲しくて呼んだ
のにJと,力で押さえつける役割を期待されたという (2002. 3 . 10) .そこには,
Kanterが「役割のカプセル化J(Kanter 1977 = 1995: 256) と指摘したのと同様の
同化の働きが見出せる.以上のごく限られた事例をなぞるだけでも,ケア労働に従
事する少数派男性もまた,たしかにトークンであることが確認できょう.
2.2 ケア労働固有の諸課題
2.1において確認された少数派としてのトークン性に加え,ケア労働に従事する
男性には,当該職業領域固有の諸課題が存在する.第 lに,ケア労働に従事する男
58 (3) 346
性は,多くの場合,ケア労働固有の身体接触にかかわるセクシュアリティの問題に
直面する.山田昌弘は,福祉ケアにおける男性のケアの可能性について論じるなか
で, r男性が行うケアは,特に女性にとって,構造上,①いやがられる(性的意味
が付与されてしまうため),もしくは,②好まれない(事務的,冷たい,情緒的意
味がこもっていなしコ)のどちらかに陥ってしまうJ(山田 1992:11) と結論づけて
いる.実際のケア現場の多面性からみれば,単純に過ぎる結論とはいえ,特に①に
ついては,女性看護職者の倍以上の比率にあたる 6割以上の男性看護職者が患者か
ら看護を拒否された経験11)を有するというデータも存在する (2003看護職・介護
職調査).多くの病院では,思春期の女性はもちろん,高齢女性にも「一応尋ねて,
嫌と言われたら女性に変わってもらうJ(2002.9.13) といった対応がとられている
が,夜間等で、人員が少ない場合や,学校における養護教諭の場合のように代わりと
なる女性が存在しない職場の難しさもある.
第2に,ケア労働は,いわゆる「感情労働」としての側面を強く有していること
が P.Smith (1992=2000)や圏内でも武井麻子 (2001)らによって指摘されている
が,実際にケアの場面で求められる感情労働の内容は, rこまやかな気づ、かいJや
「他者への共感Jといった母親や妻としての女性のイメージに結びついたものが多
い(武井 2001:76). その結果, 2.1で触れた対照性や同化の効果もあろうが,
r(女性の方が)思いやりの気持ちとか,やっぱり男性より持ちやすいというか,自
分も思いやりがないわけじゃないんですけどJ(2002.9.13) と感情労働における女
性の優位を語る男性看護職者の声もしばしば聞かれた.また,ケア労働者に感情労
働が課されるのは,患者等クライアントに対してのみではない.同じ職場で働く他
の職種との関係においても,女性のジエンダー・イメージに結びついた感情労働の
必要性が示唆される.ある大学病院の女性看護部長は, r職場ではもう全てを知り
尽くしていますよ,看護婦はね.そこに新しい人が3ヵ月交代でくるわけですから,
研修医が」と現場の知識についての看護職の優位を認めつつ,そうした場面でも
「医者は医者でやっぱり立てなさい」と指導していると語る (2001.1.20)問.
第3に,ケア労働が多くの場合,女性が多数を占めるピンクカラー・ジョブとし
て,他の職業に比べ社会的および経済的評価が低く抑えられてきたという問題が存
在する.無論,職種や勤務先によって一定の幅が存在するものの,一般に言われる
ように,日本の女性労働者の賃金カーブは,男性に比べ年功性が低く,女性労働者
が多数を占めるケア労働の領域では,他の職業に比べ賃金の上昇が低く抑えられて
いる.たとえば,人事院が実施した「平成 17年職種別民間給与実態調査」によれ
ば, r看護師」の平均給与月額は, 30歳代前半までは同じコメデイカルである「理
学療法士Jや「臨床検査技師」を上回るが,それ以降では逆転され,年齢が高まる
につれてその差は拡大している問.看護職と比較しでも平均給与が低い介護職や保
育職では状況はさらに厳しい.そうしたなか,男性介護職者の「最終的に自分とし
て,まあ男で,給料のこともあるし,先までこの仕事ができるのかなあって考えた
ら,たぶ、ん無理J(2002.3.2) といった見通しも生じる.また,経済的評価ばかり
社会学評論 58 (3) 347
でなく,職業にまつわる社会的イメージもひとつの課題である.ある男性看護職者
は, ["これまで仕事は楽しかったJとしながらも,結婚して自分の子どもができた
時期, ["自分はいくつまで,たとえば定年の 60まで患児のおむつ交換を本当にやっ
てるんだろうか.お父さんの仕事は何なのって言われたとき,誇らしげに言えるだ
ろうか」とあらためて自問したという (2002.3.4).こうした社会的評価の課題は,
既存の職業領域全体の権力関係上における男性優位の構造によって,男性が多数派
を占める職業領域に少数派として参入する女性たちが,ある穏「上昇」のイメージ
で捉えられがちであるのに対し,女性が多数派を占める職業領域に少数派として参
入する男性たちは,ときに「下降」のイメージで語られることにもよるだろう.
以上に見てきた課題の 3つの側面は,身体の次元,感情の次元,社会・経済の次
元と整理することもできょうが,現実の場面ではそれらが津然と折り重なりつつ男
性ケア労働者の困難さを形成している.
2.3 rそれでもやはり男の世界Jか
しかし,上述してきたような男性ケア労働者の少数派としての困難さ,および,
ケア労働固有の諸課題の存在にもかかわらず,米国における男性ピンクカラーの研
究で知られる c. L. Williamsは「それでもやはり男の世界だ (Still a Man's
World)Jと主張する (Williams1995). Williamsによれば, Kanterの議論は,
数における少数派/多数派の差異に着目して展開されており,大企業の女性労働者
が直面した諸問題が同じトークンとしての他のあらゆる少数派集団にもあてはまる
とする仮説には問題がある.すなわち, ["女性トークンと異なり,男性トークンは,
この特別扱いから明らかに利益を得ているJ(Williams 1995: 8)のである川.
Williamsが主張する男性トークンの利益の構造は次のようなものである.まず,
職場におけるトップの地位は,いわゆる「男性性」に関わっており,ピンクカラー
の職業領域においても管理職には出世に意欲的で,進取の気性に富み,決断力や理
性を持つといった男性において優勢と信じられている特性が期待される.また,上
司や同僚といった周囲は,女性よりも男性に対して意欲的で有能であることを期待
する.さらに,保育等子どもを相手にする仕事に就く男性が'性的に倒錯している疑
いをもたれる,といった男性への否定的ステレオタイプが問題になる場合でさえ,
そのことは男性の職場での地位を,より男性にふさわしいと考えられる管理的仕事
へと「上昇」させることにつながる.そして,その結果,女性が多数を占める職業
においても,男性は女性よりも高い地位と給与を得ることになる (Williams1995:
183). Williamsは,男性ピンクカラーに働くこうしたメカニズムを「ガラスの天
井」ならぬ「ガラスのエスカレーター (glassescalator)Jと名づけている.
Williamsの主張する男性ピンクカラーの優位性について圏内の統計資料から検
討してみよう. ["平成 17年賃金構造基本統計調査J(厚生労働省 2006)においてケ
ア労働にかかわるピンクカラー・ジョブのうち男女別の所定内給与額(きまって支
給する現金給与額のうち,超過労働給与額を差し引いた額)が比較可能な「看護
58 (3) 348
師J1准看護師J1福祉施設介護員」について年齢階級別にみると, 1看護師」では
ほとんど男女差が見出せないが, 1准看護師」では 30~34 歳までは男女にほとんど
差はないか,女性の所定内給与額の方がわず、かに上回っているものの, 35~39 歳
以降,男性の所定内給与額が女性を 1部から 2割ほど上回っている. 1福祉施設介
護員J では 30~34 歳以降で男女の差が聞き始め, 40歳代での男性の所定内給与額
は,女性の1.4倍ほどにもなる.
職務上の地位については,管見のかぎりこうした視点から分析可能である有用な
公式統計が得られないため, 12003看護職・介護職調査」のデータから看護職にお
ける経験年数区分 (10年単位)ごとの管理職者の比率を比較した.その結果,経
験年数 10~19 年の看護職者において,男性では 29.6 %が副師長以上の職位に就い
ているのに対し,女性でそうした職位にあるのは 11.2%と大きな差が確認された
(経験年数10年未満および20年以上では明確な男女差は確認できなかった).以上
の資料から判断するかぎり, Williamsが主張するピンクカラー・ジョブにおける
男性の優位性は,圏内においても(個々の職業聞に差異はあれ)一定程度存在する
といえよう.
では,ケア労働の領域への男性の参入という「変化Jは,結局,女性が多数派を
占める職業領域の内部において,その一部に男性がより高い地位と賃金を確保する
居場所を創出していくようなジェンダ一体制を構築すること,つまり「変化を生み
出さない変化Jにとどまるのだろうか.たしかにそうした側面は否定しがたいが,
そこにはなお変化につながる道筋も残されている.次節では,そうした可能性の糸
口を当事者である男性ピンクカラーの語りに焦点化するなかから導きたい.
3 男性ピンクカラーの戦略と戦術
3.1 男性ピンクカラーの戦略
矢原隆行は,男性看護職者が自分たちを当該職業領域に位置づけるうえで用いる
多様な語りについて検討するなかで,彼らが職業領域で直面する諸課題に対してと
り得る戦略として「戦略 1:男性性を不可視化するJ1戦略 2:男性性を可視化す
るJの大きく 2つに整理している(矢原 2002). これらの戦略は,さらにそれが職
業自体に向けられる場合と,個人としての男性看護職者に向けられる場合の 2つの
ベクトルを有する.戦略 1における男性性の不可視化とは,文字通り看護職につい
て男性性を無効化し,見えなくする戦略であるが,ひとつには,看護職自体の職務
内容を女性性や男性性に本来的に関係のない性中立的なものとみなすことにより,
職業としての看護職を性のカテゴリーの作用から引き離そうとする試みを,もうひ
とつには,個人としての男性看護職における男性性を不可視化する試み(同時に個
人としての女性看護職におげる女性性を不可視化する試み)を含む.具体的には,
前者は, 1専門職としての看護に性差は無関係J,後者は, 1男女差ではなく個人差
が問題」といったレトリックに集約できる 15)
社会学評論 58 (3) 349
戦略 2における男性性の可視化とは,不可視化の戦略とは反対に男性性を強調す
る戦略である.そこには,ひとつには,看護職の個々の職務内容として,男性向き
であるような仕事を指摘する試み,もうひとつには,個人としての男性看護職にお
ける男性性の意義を主張する試みを含む.具体的には,前者は, 1機械に強い男性
向きの仕事J1体力のある男性向きの仕事」等,後者は, 1男性ならではの看護の視
点」といったレトリックで表現される.男性性の可視化/不可視化というこうした
2つの戦略は,フェミニズ、ムにおいて論じられてきた,性差極大化/性差極小化と
いう区別にも準えることができるだろう.
矢原は,第 1の男性性の不可視化戦略が,看護業務特有の身体接触にともなうセ
クシュアリティの問題(女性患者からの拒否等)に直面する場合や,看護職という
職務遂行に要する技術的資源として女性性が埋め込まれている場面においては遂行
困難となるため,そうした状況では第2の男性性の可視化戦略の方が有効である,
としながらも,可視化戦略によってもたらされる看護職内部におけるく男性看護
職/女性看護職〉の差異的関係性の構築が,ジエン夕、ー・カテゴリー自体が現状に
おいてはらむ男女聞の傾斜的差異を看護職内部に導入するように作用する可能性に
ついて, 1980年時点で,看護職全体のおよそ 10%を占める男性が,管理職,教育
職,さまざまな職業組織,労働組合等の最高役職のほぼ半数を占めている英国の状
況をふまえつつ注意を促している(矢原 2002:1010).
以上の分析にさらに付け加えるならば,ここで述べられている可視化戦略が,直
接的に男性性の利点、を主張するものである点においてまさに「男性化」の戦略であ
ることは言うまでもないが,性差を不可視化するという第1の戦略もまた,そこで
性中立とされるものが,現実には(ピンクカラー・ジョブにおいても往々にして)
男性労働者を基準として構成された職業領域における「普遍的」労働者評価へとつ
ながっていくものであることを認識するならば同,それはやはりある種の「男性
化」の戦略であると言わざるをえないだろう.すなわち,いずれの戦略が用いられ
るにせよ,ケア労働領域への男性の参入は,当該職業内部における既存のジェン夕、
一体制の再生産にいたらざるをえない.
3.2 男性ピンクカラーの戦術
しかし,そもそもこうした見解にいたる前提としての 12つの戦略」という整理
は,果たして妥当なものか.男性性と職業が結びつけて語られる場面において,男
性ピンクカラーである彼らが,男性性の可視化あるいは不可視化とみなされる主張
をおこなうことは確かに観察できる.だが,そうした戦略は 2つのいずれを選択
したとしても,その貫徹を試みるならば,陸路に陥らざるをえないようなものでも
ある(当然のことながら,実際のケアの職場において完全に性差を無視することは
困難であるし,逆に,男性向きの仕事のみを選択して遂行することも困難である).
そして,それにもかかわらず,たいてい彼らは「なんとかやっていくJ.
乙の論理上の陸路と,実際上のパイアビリティ (viability) との隔たりについて
58 (3) 350
理解するために,あらためて男性ピンクカラーの語りに立ち返るならば,そこには
さまざまな水準において首尾一貫しない語りを見出すことができる.たとえば, 2.
1において紹介した,精神科で暴れる患者を言葉かけによってではなく,カで押さ
えつけることを期待された男性看護職者は,インタビューのなかでその経験に憤り,
そうした性差に基づく期待を誤ったものとして否定しつつ,同じインタビューの別
の箇所では, 1まあ仕事をしていく上では,男女関係ないと言いましでも,やはり
こう,力では女性は,男性の患者さんにかなうわけではありませんので」
(2002.3.10) と性差を肯定(男性性の可視化)する.また,別の男性看護職者は,
女性患者からの看護拒否について,その差恥心への配慮の必要'性を語りつつ, 1で
も,まあ男だろうが女だろうが,やっぱり信頼関係を築ければJ(2003.10.14) と
性差を超えた個人差の主張(男性性の不可視化)をおこなう.
主張の一貫性という観点から見るならば,彼らの主張は矛盾しており,その立場
は暖昧なものと感じられるだろう.しかし,実際のケア労働の場が,ジエンダー論
的に一貫した主張をおこなうことよりも,その場その場での臨機応変な対応、を求め
られる場であるという,ある意味でごく当たり前のことを想起するならば,そこで
試行錯誤的に「なんとかやっていく」ことこそ,男性ピンクカラーである彼らが実
践的に用いている「戦術Jであるととが理解される.先にふれた矢原 (2002)の言
う 12つの戦略Jと,ここで言う「戦術」との差異は, M. D. Certeauによる「戦
略と戦術の区別」に依拠したものである.Certeauは,その差異について, 1戦術
は,戦略が権力の公準によって編成されているのとおなじように,権力の不在によ
って規定されているJ(Certeau 1980 = 1987: 103) と述べているが,男性ピンクカ
ラーにおける一見すると唆昧で一貫しない主張は,それを「戦術Jとして捉えなお
すならば,そこに既存の「男性性Jの変容可能性を読み込むことができる.別言す
れば,そこで提示される「男性性jは,男性であるという強固なアイデンティティ
に基づくものというよりも,カテゴリーとしての性差の場当たり的な活用であると
もいえよう.
無論,彼らの性差をめぐる振る舞いが,局所における戦術的なものであるとして
も,そのことをもってケア労働の領域における既存のジェンダ一体制の再生産の可
能性が否定されるわけではない.同僚である多数派の女性たちゃ他の男性たちから
の期待,仕事を通して関わるさまざまな人々との聞で生じる諸々の機会に,彼らは
ときに男性であることの優位性を活用し, Williamsが述べるように男性トークン
としての特別扱いから利益を得ることもあるだろう.しかし,さらに問うならば,
そこで言われる「利益」とは,いかなる普遍的基準によって測定された利益である
のか.
4 変化において変化し得るもの一一普遍性の切り崩し
竹村和子は,普遍と個別という観点から性差別について論じるなかで, {男〉と
社会学評論 58 (3) 351
いう普遍が,個別的文脈によってつねに「汚染Jされており,それゆえ普遍が包含
する男は,すべて I~男〉ではない男J= I~男〉のような男J である,と指摘する
と同時に,他方で,普遍から排除された女は,男と交通するために I~男〉のよう
にJならざるをえない,としたうえで,つぎのように述べる.
個別性によってつねにすでに汚染されている男のなかの非整合性は, I~男〉
のような女」との対話によってさらに増幅され,また I~男〉のような女」の
〈男〉の起源性も, I~男〉のような男」によってさらに陵昧にされる.むろん
普遍化の過程でおこる普遍の指示対象のずれは,ずらされた意味がさらに占有
されて,普遍の再強化につながる場合がある.むしろ再強化の方が先行するほ
ど,普遍の形式力は強い.なぜなら個別はそれ自体では社会的に生存不可能で,
形式(名前)を与えられないかぎり,意味を獲得することができないからだ.
だが他方で, I~男〉のような男J と I~男〉のような女J のあいだでおこなわ
れる発話の入れ子構造のなかで, I非対称的で不可逆的Jに見えた男と女の関
係は流動化し, ~男〉という属性を確定化し絶対化していた普遍の指示対象は,
ひそかに,しかし確実に,切り崩されている. (竹村 2002:295)
社会において従来「女性向きJとされてきたケア労働に従事する男性ピンクカラ
ーは,まさに〈男〉の普遍的形式を裏切る I~男〉のような男」といえようし, I女性向き」とされてきたとはいえ,やはり普遍としての男性労働者を基準として構成
された「職業」の世界で労働に従事してきた女性ピンクカラーは, I~男〉のような
女Jだろう.そうした両者が向き合う場としてのケア労働の領域において展開され
るi性差をめぐる男性ピンクカラーの諸戦術は,竹村が指摘するように「普遍の再
強化」につながる可能性と同時に, ~男〉という普遍性を切り崩す可能性をもそこ
にはらんでいる.
2.1で紹介した,力で患者を押さえつけることへの周囲(女性たち)からの期待
に言葉かげで対応した男'性看護職者の振る舞い.男性看護職の採用に際して,男は
仕事を辞めないし,産休がないから都合が良いと考えたという注目の女性看護主
任は,その後の経験から「まあでも今は男も育休とるようになったからJ(1999.7.21) と,当初の期待が裏切られたことを語った.別の女性看護主任は,
「男性だからきっと,女性がまあ適当に抜げているところがあるんだけど,あの人
たちは,ぱあっとわかってくれるかなっていう期待があったJが,実際に男性看護
職者と仕事をするなかで「やっぱり女性も男性も一緒なんだJ(1999.7.28) と気付
いたという.また,男性看護職者や男性保育職者にその将来像を尋ねるなかで,
「お年寄りの世話をしたりするのが好きだからJI子どもと過ごせるのが一番なの
で」という理由で,管理的な仕事への「上昇」について思避する傾向を示す声が聞
かれることもしばしばあった17)
〈男》の普遍的形式が切り崩されるのは,職業領域においてばかりではない.自
58 (3) 352
分よりも多忙かつ高所得の職業に従事する女性と結婚しているある男性保育職者は,
家庭において家事の大半を担っていることについて, ["閉じように共働きしている
同僚の女の人たちゃ(園児の)保護者が,仕事しながら家事をやっているとこを見
てるんで,自分もやるのは当たり前のことJ(2004.10.28) と語った.無論,ケア
労働に従事する男性が,つねに家庭におけるジエン夕、一平等を実現しているなどと
は決して言えないが,彼らがその同僚の多くを占める女性たちから,日々職場およ
び家庭における「働きかた」を学ぶ機会に直面していることは確かだろう 18)
こうした男性ピンクカラーたちは,国内における男性学が提示する新たな男性像
のように「男らしさjからく降り〉ようとしているわけではなしかといって
Williamsら女性学の視座で描かれるように「男の世界」でその利益を享受するこ
とをつねに望んでいるわけでもない.ガラスのエスカレーターに乗るよりも,やり
がいを感じられるケアの場にとどまりたいという男性たちを,特権を有する側の賛
沢とみなしてしまうことも可能ではあろうが,そうした研究者側の枠組からは,
「普遍のダイナミックな変容の可能性J(竹村 2002:296) を窺うことは難しいだろ
う.変化において変化しうるものがあるとするならば,それは変化と見えるものを
構成している土台としての普遍自体をずらしていくような変化に他ならない.ケア
労働をめぐる社会的評価の変容可能性もそこに存する.
5 まとめ
以上,本稿において確認されたことは以下のとおり.ケア労働の領域において男
性ピンクカラーの増加,および,職業名称等における男性化(普遍化)が進展して
いる(1).そのなかで男性ピンクカラーは,少数派としての困難に直面しており
(2.1),そ乙にはケア労働固有の課題も存在する (2.2).ただし,男性ピンクカラー
の少数派としての困難は,企業における少数派女性とは異なり彼らにとって有利な
面を持つという主張も存在する (2.3).一方,男性ピンクカラーが用いる少数派と
しての 2つの戦略は,いずれもケア労働の男性化を帰結するが (3.1),しかし,そ
れが戦略ではなく戦術であることに,変化の可能性を読み込むことができる (3.
2).それは男性を基準とした普遍の変容可能性であり,それを観察する側の研究枠
組の変化を要請するものでもある (4)•
最後に,本稿の限界として,ここでは触れえなかったが,圏内におけるケア労働
領域のジエン夕、一体制の今後に大きな影響を及ぽす動きとして,すでに他の先進諸
国において見られるような「ケア労働の国際化J,すなわち,外国人(女性)によ
る圏内のケア労働力不足の埋め合わせという流れが,近年にわかに現実化しつつあ
る.ケア労働の領域が,男性に加え,外国人労働者を含みこんでいくなかで,どの
ようにその社会的位置づけと内部の構造化を進展させていくのか,そこで生み出さ
れる次なる普遍とはどのようなものか,事態は予断を許さない.
社会学評論 58 (3) 353
[付記] 本稿は,厚生労働科学研究費(医療技術評価総合研究事業「看護職におげる男女共同参
画の課題と可能性に関する研究」主任研究者:矢原隆行)および文部省科学研究費(若手研究
(B)課題番号 157101931"男性ピンクカラーの課題と可能性に関する社会学的研究」研究代表者:
矢原隆行)の一環として実施された研究成果の一部である.
[注]1) 看護職と女性をめぐる伝統的イメージについては, J anet Muff (1988 = 1997)を参照.
2) 日本看護協会出版会編『看護関係統計資料集』より算出.
3) 厚生労働省『社会福祉施設等調査報告』より算出.なお,この調査報告における 2003年の
該当データは従事者の算出方法が変更されているため,データの連続性を考え用いなかった.
さらに, 2004年以降は従事者の性別の数値が調査されていない.本稿におけるような研究関心
から見ると,国内におけるこうしたデータの整備状況はきわめて不十分といえる.
4) 1"助産師」については,名称は変更されたが,現時点で男性の受験資格は与えられていない.
本稿では,紙幅の都合上,助産師問題について詳述しないが,そこではジエンダー研究の観点
からも注目すべき議論がなされている.助産師問題論議の概要については山崎 (1996),1"名称
変更」改正法の経緯については大林 (2003a, 2003 b) を参照.
5) 統一名称を求めた保育者の活動,とりわけ正式名称を持たなかった男性保育者たちの活動に
ついて全国男性保育者連絡会事務局編(1997)を参照.
6)・同時に国内においては近年,急速な女性医師の増加,すなわち「医療の女性化 (feminaiza.
tion of medicine) Jが進展していることも,周知のとおりである.
7) 具体例としてメンズセンター編(1996)における諸議論を参照.
8) 渋谷による上記の批判を踏まえた最近の男性学研究として多賀 (2006)を参照.
9) 以下で用いるデータの調査は,主に厚生労働科学研究費医療技術評価総合研究事業
(2001~2002 年)および文部省科学研究費若手研究 (B) (2003~2004 年)による.面接調査
の対象は,看護職(学生を含む)男性48名,女性 17名,その他(介護職,保健師,養護教諭
等)男性23名,女性7名で,スノーボール・サンプリングにより全国の 10都府県より抽出し
た.一部を除き個別面接(アクティヴ・インタビュー法による)で,一人あたり 1時聞から 2
時間程度.内容はすべて録音し,後に文書化して整理した.以下で引用するさいには,インタ
ビュー実施日を, 2002年 1月2日の場合 (2002.1.2)と記す.また,これと並行して 2003年
1月に質問紙による自記式郵送調査を全国の病院(看護職調査)および高齢者施設(介護職調
査)からそれぞれランダム・サンプリングした 500ヵ所ずつに実施した(計 1000ヵ所に 4000
票配布).回収率は,看護職調査31.6%,介護職調査 27.9%であった.以下で結果の一部を
引用するさいには, (2003看護職・介護職調査)と記す.
10) そうした指名のなかには,衣服を脱ぐ必要のある清拭,聴診等の模擬患者役を多数の生徒の
前で代表してさせられた (2003.10.13) というものも含まれる.
11) ただし,セクシュアリティの問題ばかりでなく,特に高齢者(男女とも)から「もったいな
いJ1"男の人にそういうのは滅相もない,女の方を呼んでくださいJ(2000.8.2) と遠慮される
形での拒否の経験もしばしば聞かれた.
12) さらに,春日キスヨが調査した男性へルパーは, 1"私たちは看護婦さんの下で働くんだから,
男でもあなたその辺は心得ていた方がいいよ」と前任者から言われたという(春日 2001:67).
すなわち,ケア労働者は,他の職種との階層的関係において,男性に対しでも,女性に対して
も,ある種の感情労働が求められる.
13) 1"看護師長」になった場合,平均給与月額は上昇するが,それでも 40歳代後半以降, 1"臨床
検査技師」や「理学療法土Jを下回る(人事院 2006).
14) 同様の指摘は, ]. Acker (1990) らにおいてもなされている.
15) 調査を遂行する過程で,こうしたレトリックが本研究自体への批判として対象者から投げか
げられることもある.ある男性保健師は,仕事に男女差を持ち込むべきではないという語りの
58 (3) 354
後, rそもそもここ(筆者注男性ケア労働者)に問題意識を持ってくるのは何なのかっていう
ところが,ものすごしはっきり言って腹立たしいJ(2003.10.14) と憤りを示した.
16) ある女性看護主任は,男性看護職の採用について,新人の女性看護職者が突発的に妊娠して
産休,育休をとることでの職場への影響が大きいことを慨嘆した後, r男は産休がないからい
いって思いました.はっきり言ってJ(1999.7.21) と語った.
17) ただし,管理的な仕事への昇進を望まないからといって,彼らが現状のケア労働に対する報
酬に満足しているわけではない. r2003看護職・介護職調査」においても,同一職業で勤務先
を変更した理由にとして「収入」を挙げる率は,看護職,介護職ともに男性の方が多い.
18) 天童陵子らの調査によれば,すでに学生の時点で,ケア関連(介護,看護,福祉)の大学・
専門学校で学ぶ男子学生では,一般の男子学生に比べ性別役割分業にこだわらない比率が高く
なっている(天童 2006).
[文献]
Acker, ]., 1990,“Hierarchies, Jobs, Bodies: A theory of gendered organizations," Gender &
Society, 4(2): 139-58.
Certeau, M. D., 1980, Art de Faire, Paris: Union Generale d'Editions. (=1987,山田登世子訳
『日常実践のポイエティーク』国文社.l
伊藤公雄, 1996, r男性学入門』作品社.
人事院, 2006, r平成 17年職種別民間給与実態調査の結果J. (http://www.jinji.go.jp/kankoku/
minkan/ min_index.htm, 2006.9.27.l Kanter; R. M., 1977, Men and Women 01 the Coゆoration,New York: Basic Books. (= 1995,
高井葉子訳『企業のなかの男と女』生産性出版.l
春日キスヨ, 2001, r介護問題の社会学』岩波書底.
木本喜美子, 2003, r女性労働とマネジメント』勤草書房.
厚生労働省, 2006, r平成 17年賃金構造基本統計調査J. (http://wwwdbtk.mhlw.go必/toukei/
kouhyo/indexk-roudou.html#rou4, 2006.9.29.)
メンズセンター編, 1996, rr男らしさ」から「自分らしさ」へ』かもがわ出版.
Muff, J., 1988,“Of Images and Ideals: A look at socialization and sexism in nursing," A. H.
Jones巴ds.,lmages 01 Nurses: Per.ゆectivesIrom histoη" art and literature, Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 197-220. (=1997,中島憲子訳「イメージと理想一一看護
の社会化と性差別について」中島憲子監訳『看護婦はどう見られてきたか』時空出版, 230-
64. )
日本看護協会出版会, 1999, r平成 11年看護関係統計資料集.1.
一一一一, 2006, r平成 17年看護関係統計資料集J.
大林道子, 2003 a, rr名称変更』改正法の歴史的背景 1J r看護教育j44 (1): 37-43.
一一一一, 2003 b, rr名称変更』改正法の歴史的背景IIJr看護教育j44 (3): 224-9.
渋谷知美, 2001, rrフェミニスト男性研究』の視点と構想Jr社会学評論j41 (4): 447-63.
Smith, P., 1992, The Emotio加 1Labour 01 Nurs初'g,London: Macmillan Press Limited. (=2000,
武井麻子・前田泰樹監訳『感情労働としての看護』ゆるみ出版.)
多賀太, 2006, r男らしさの社会学一一揺らぐ男のライフコースJ世界思想社.
武井麻子, 2001, r感育と看護一一人とのかかわりを職業とすることの意味』医学書院.
竹村和子, 2002, r愛について一一ーアイデンティティと欲望の政治学』岩波書庖.
天堂陸子, 2006, rケアワーク志向の若者の仕事観,ケア経験とジェンダー意識一一2005年質問紙
調査に基づいて」第 79回日本社会学会大会ポスターセッション配布資料.
Williams, C. 1., 1995, Still a Man's World, Berkeley: University of California Press.
矢原隆行, 2002, r男性看護職をめぐる課題と戦略ーーその隆路と可能性についてJr看護学雑誌』
66 (11): 1006-11.
社会学評論 58 (3) 355
山田昌弘. 1992, r福祉とジェンダー-ーその構造と意味Jr家族研究年報j17: 2-14.
山崎裕二, 1996, r新しい思想としての『助産師jJr助産婦雑誌J50 (7): 18-24.
全国男性保育者連絡会事務局編, 1997, rr保父」と呼ばないで一一これからのゆたかな保育のため
に』かもがわ出版.
(原稿受付 2007.3.11 掲載決定 2007.9.14)
The Sociology of the Pink-Collar Man:
Aspects of the mascuIinization of care work
YAHARA, Takayuki
Hiroshima International Universiか[email protected]
In recent years, there has been an increase in men who compete for pink.collar .
jobs. In particular, there has been an increase in the number of males who
engage in care work such as nursing, caregiving, and child care. This phenome-
non can be interpreted as a change in the gender regime, especially when it is
observed in comparison to women who compete in occupations that are dominat-
ed by men. However, very few influential studies in the field of women's studies
have focused on pink-collar males. This is also the case in men's studies, which
have mostly focused on “masculinity." The purpose of this investigation was to
examine pink-collar men in ]apan, especially from the perspective of“masculin-
ization of care work." Many narratives demonstrate that pink-collar men are
sometimes considered as “tokens," because they are a minority. However, their
position is not simply symmetrical to that of women who are minorities in
male-dominated occupations. In a sort of irony, pink-collar men reflect the
gender order of modern society and care work, and vice versa.
Key words: pink-collar man, care work, gender
(Received March 11, 2007 / Accepted September 14, 2007)
58 (3) 356